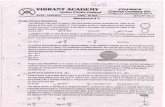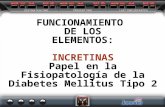DPP report Japan June 2014 Japanese pp01-36...DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 9...
Transcript of DPP report Japan June 2014 Japanese pp01-36...DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 9...
-
誤判の必然性死刑事件における司法
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 1 10/06/2014 09:34
-
謝辞 本報告書は英国外務省、Sigrid Rausing Trust、Oak Foundation、the Open Society Foundation、Simons Muirhead & Burton 国連拷問被害者支援基金による �e Death Penalty Project への助成により可能となった。
なお、本報告書の日本語への翻訳を担当していただいた千田瑛子氏に記して感謝を申し上げたい。
本翻訳は仮訳であり、かつ翻訳後の英語版が修正された箇所もあるため、引用あるいは参照する場合は、英語版をご利用ください。
© 2014 著者
本報告書の一部あるいは全部を無断で複写・転載・転訳載などをすること、また磁気媒体等に入力することは、法律で認められた場合を除き、著作者 の権利の侵害となりますので、これらの行為をする場合には、著者に承諾を求めてください。
�e Death Penalty Project8/9 Frith StreetSohoLondonW1D 3JBwww.deathpenaltyproject.org
ISBN: 978-0-9576785-2-1
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 2 12/06/2014 09:24
-
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 1 10/06/2014 09:34
-
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 2 10/06/2014 09:34
-
目次前書き 5
冤罪の事例 7(i) 日本 – 47年間死刑囚として過ごした袴田巌 8(ii) アメリカ – 虚偽の自白、不正な証拠、DNA 鑑定の始まり 13(iii) その他の国 – 手続きの不正、冤罪と不公正な裁判 19(iv)イギリス– 冤罪事件からの教訓 25
結論 28
付録: 自由権規約及びその他の国際基準の妥当性 29
著者 33
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 3 12/06/2014 11:32
-
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 4 10/06/2014 09:34
-
5
前書き 国際社会の死刑制度に対する態度は、どのような刑事司法においても人的ミスや、凶悪犯罪への感情的反応に影響される要素を伴うという事実をもとに発展してきた。冤罪は制度の成熟度合いに関わらず全ての司法制度において起きており、無実の人間が死刑になる危険性を孕んでいる。この危険性そのものが、世界各国がより積極的に死刑制度の廃止に向かうようになった理由でもある。
本報告書は日本、アメリカ、台湾、カリブ海諸国、シエラレオネ共和国及びイギリスにおける実例と調査結果から、世界的な動向を紹介するものである。国際人権法は、不当な有罪判決及び無実あるいは公正な裁判を受けていない人間への死刑執行の可能性を認めている。その結果、国際基準は死刑事件に厳格な基準を課すこと及びより高度な適正手続きを適用することを目指している。各国に対して死刑の適用において厳密な手続的規則の尊重を求める自由権規約及びその他の国際基準については、付録に記載した。
しかしながら本報告書に登場する実例からは、死刑存置国の司法制度が誤判の可能性のない信頼のおけるものであるとは言い難いことが浮き彫りにされている。いかなる刑事司法制度においても起こりうる最も重大な誤判は、無実の人間に死刑を適用することである。
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 5 10/06/2014 09:34
-
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 6 10/06/2014 09:34
-
冤罪の事例日本
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 7 12/06/2014 09:26
-
8
(i) 日本 – 47 年間死刑囚として過ごした袴田巌
日本人の男性 4 名が、 28 年から 33 年の独房監禁の後に無罪となった事件が 1980 年代に相次いだ。これらの冤罪事件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)は主に長く残酷な取り調べに原因があった.1 これらの事件は、無実のの者が有罪判決を受ける経緯だけでなく、上訴や再審請求はとても時間がかかり刑事司法制度は冤罪を認めたがらないことを浮き彫りにしている。
免田栄
免田栄は、 1983 年の再審によって釈放されるまでの 33 年間以上を死刑囚として過ごした。 1948 年のある夜中に侵入があり、老齢の祈祷師とその妻が手斧及びナイフで殺され、娘二人は重傷を追った。 農家の息子であった免田はその当時、この殺人事件を担当している警察官だと名乗っていた。このことがきっかけで、免田は、強盗、殺人、及び強盗殺人未遂の容疑よって逮捕され、一審の最初は罪を認めていた。しかし、第 3 回の公判 では自白は拷問により強要されたものとし、彼は一転して無罪を主張した。しかし、 1950 年に免田に死刑が言い渡された。
免田は無実である事を訴え、合計第 6 次まで再審請求を続けた。第 4 次請求の途中から日本弁護士連合会(日弁連)の支援が加わり、また第 6 次請求中に最高裁の再審開始基準が緩和されたこともあり(白鳥決定)、死刑判決を受けてから 29 年後の 1979 年に再審開始が決定された。再審では、免田は事件当夜は接客婦と過ごしたというアリバイが成立し無罪が言い渡された。当時18 歳であると偽っていた 16 歳の接客婦は、一審において免田と過ごした夜は事件の一日後であると供述していた。2 裁判官は、接客婦が未成年者であり、警察に対して弱い立場に置かれていたことを考慮した。 裁判所は主としてアリバイの成立に依拠して免田の無罪を言い渡したが、自白を得るための警察の取り調べの方法を批判した。免田は自白するまでの 3 日間、不眠状態で取り調べを受けさせられた。裁判官は一審の裁判官及び弁護
1 Kazuko Ito, Wrongful Convictions and Recent Criminal Justice Reform in Japan, University of Cincinnati Law Review (2013) Vol. 80 (4): 1245-75.
2 しかし、接客婦は公判中にこの供述を撤回した。
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 8 10/06/2014 09:34
-
9
人が自白の正統性に関して問わなかった事を批判したが、警察に関しては戦後に起きた事件当時は警察はそのような手続的保障に関して配慮が欠けていたと説明し、再審が行われた 1983 年では警察は戦後のような取り調べは行っていないことを暗示した。3
免田事件では自白を得るために代用監獄が利用された。代用監獄制度は、警察署の留置場に被疑者を勾留することによって、被疑者の勾留と取り調べの両者が同じ警察の下で行われる。 被疑者の逮捕から 3 日以内に検察官は勾留請求を裁判官に対して行う。勾留決定後、被疑者の身柄を釈放または起訴するまでに 10 日間取り調べを延長し、さらにもう 10 日延長し代用監獄を利用して取り調べすることが可能である。代用監獄制度は明治時代から始まり、上記の戦後の事例でも使われていたが、次項にみられるように 1960 年代にも頻繁に活用され、今日に至っても利用されている。
袴田巌
2014 年 3 月、袴田巌は 47 年間の独房監禁を経て、 死刑確定後に釈放となった日本で5人目の人物である。 1996 年 6 月、味噌工場の専務の自宅が強盗及び放火され、焼け跡から専務、妻と子供二人が死体で発見された。この強盗殺人放火事件から 3 ヶ月後に工場の従業員であった袴田が 4 名の殺人容疑で逮捕された。警察は、袴田の部屋から押収したパジャマに袴田のものではない微量の血痕及び放火に利用されたものと同じ油が付着していたとした。
袴田は無罪を主張したが、弁護士がいない環境下で 20 日間、一日最大 16 時間(平均 12 時間)の取り調べの後、殺人事件について「自白」した。4 公判では、自白は警察に強要されたものとし起訴事実を全面否認した。裁判では、検察が請求した 45 通の供述調書のうち 44 通は認められず、採用されたのは 1 通の供述調書だけだった。5
3 Foote, D., ‘From Japan’s death row to freedom,’ Pacic Rim Law & Policy Journal (1992), Vol. 1. No. 1 pp: 11-103.
4 日弁連「「袴田事件」再審開始決定に関する会長声明」 (2014) www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2014/140327.html
5 Amnesty UK, ‘Hakamada Iwao (2014) www.amnesty.org.uk/hakamada-iwao-death-penalty-row-japan#.U3uuAV7e5g1
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 9 10/06/2014 09:34
-
10
袴田事件の陪席裁判官だった熊本典道は、公判当時、袴田は無実だと思っていたが、二人の先輩裁判官を説得する事ができなかったことを認めた。熊本は、
「証拠をみると、厳しい取り調べによる自白以外、ほとんどなにもなかった」と語った。
1968 年に袴田に死刑を下してから 6 ヶ月後に熊本は判事を退官した。 2007 年にテレビの取材にて袴田に対して有罪判決を書くようにプレッシャーがあった事を語った。熊本の告白は裁判官の合議の秘密を破った上での発言であり、整然とした判決文の背後に存在する「人間関係の力学政治」が明らかになったまれな事例である。判決は厳密な法的議論及び公平な事実認定によって書かれ、年功序列等の要素に汚染されないことを人々は期待している。この事例は、裁判官たる者もこのようなプレッシャーから逃れられないことを示している。
一審公判中に血まみれの 5 点の衣類が、工場の味噌タンクの中から発見された。検察は主張を変更し、新しく発見されたこの 5 点の衣類を袴田が着て家族を殺害した後、パジャマに着替えて放火を行ったと説明した。自白及び衣類の発見が死刑判決の鍵となり、 1980 年に最高裁で死刑が確定した。
2014 年 3 月の袴田の死刑停止と即時釈放は、犯人が着ていたとされる 5 点の衣類の血痕のDNA鑑定から、それが袴田のものでも被害者のものでもないことが明らかにされたことによる。第二次再審請求審で、捜査機関が証拠をねつ造した疑いが指摘された。また、再審請求事件における 証拠開示の申請が袴田の弁護団によって 1981 年から行われていた事にもここでふれておきたい 。
再審の判決が出るまでは袴田の無罪は確定しないが、村山浩昭裁判長は、「拘置をこれ以上継続することは、耐え難いほど正義に反する状況にあると言わざるを得ない」とした。6 袴田事件は、第一次再審請求から日弁連の支援を受けたケースであったが,再審開始決定までに 33 年の年月がかかった。
6 Hiroko Tabuchi, ‘Soul-Searching as Japan Ends a Man’s Decades on Death Row,’ e New York Times, 27 March 2014, available at: www.nytimes.com/2014/03/28/world/asia/freed-after-decades-on-death-row-man-indicts-justice-in-japan.html
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 10 10/06/2014 09:34
-
11
過去の実例から学んだ教訓?
免田事件から 25 年経った今、袴田事件は何を意味するのか。唯一明確なのは、多くが変わっていないということである。袴田の事例は、 1980 年代に免田事件の冤罪究明につながった要因である警察の取り調べ、裁判、上訴に関する手続的保障の欠如である。 全ての取り調べが録音・録画されれば、強要による自白は難しくなる。一審また再審請求にて証拠の開示が全面的に行われていれば、袴田は約半世紀もの時を独房監禁で過ごさずにすんだであろう。7
7 日本に関するより詳しい手続的保障については「日本における死刑制度:日本の自由権規約の下
での法的遵守義務及び世論の死刑への態度についての報告書」を参照されたい。リンク:
www.deathpenaltyproject.org/wp-content/uploads/2013/03/DPP-Japan-report.pdf.
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 11 10/06/2014 09:34
-
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 12 10/06/2014 09:34
-
冤罪の事例アメリカ
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 13 12/06/2014 09:27
-
14
(ii) アメリカ-虚偽の自白、不正な証拠、DNA鑑定の始まり アメリカでは、最新のDNA鑑定が期せずして、死刑事件をも含めた冤罪事件がどのように生じるかを明らかにする新たな機会を提供することになった。今日に至るまでの間にDNA鑑定によって 18 件の死刑判決が冤罪であることがわかった。8 アメリカで死刑制度が復活した 1976 年以降、DNA鑑定以外の証拠による死刑判決の破棄は百件以上存在する。9 一体どれだけの無実の人間が有罪判決または死刑判決を受けたのか、我々には知る由もない。ほとんどの重犯罪には、かなりの年月が過ぎてしまっても鑑定可能な生物学的証拠は存在しないからだ。しかしながら一連の死刑事件の冤罪は、アメリカ国内の死刑制度を巡る議論に決定的な影響を与えた。
アメリカにおける一連の無罪となった死刑事件について、詳細な分析を行うことによって重要な教訓を得ることができる。 死刑判決の破棄とは、無実を証明する新たな証拠に基づいて、裁判所の判決あるいは恩赦によって以前の判決を 覆すことを指す。ブランドン・ガレット教授はDNA鑑定によって判決が破棄された事件の冤罪被害者たちを調査した。無罪となった死刑囚 18 人のうち 8 人は、虚偽の自白を行っていた。10 これらの事件はいずれも、冤罪被害者が自白したとされる「内部情報」や真犯人しか知り得ない詳細などに裏付けられて
8 Brandon L. Garrett, Convicting the Innocent (2011) (米国においてDNA鑑定によって明かになった、17件の死刑事件を含めた250件の冤罪事件についての分析); Brandon L. Garrett, e Banality of Wrongful Executions, Mich. L. Rev. (2014) (情報の更新及び米国の18件の死刑囚の冤罪事件についての研究)。9 e Death Penalty Information Centerによると死刑判決を受けた冤罪被害者は144人に上る。 e Innocence List, Death Penalty Info. Ctr., http://www.deathpenaltyinfo.org/innocence-list-those-freed-death-row (2013年 10 月 29 日のアクセスによる)。10 これらの自白の内容については下記の付録に詳細が記載されている。 Brandon L. Garrett, Characteristics of Exoneree False Confessions, Univ. of Va. Sch. of Law, www.law.virginia.edu/pdf/faculty/garrett/convicting_the_innocent/garrett_false_ confessions_appendix.pdfデモン・ティボドーの自白についての情報はKnow the Cases: Damon ibodeaux, Innocence Project参照。 www.innocenceproject.org/Content/Damon_ ibodeaux.php
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 14 10/06/2014 09:34
-
15
おり、一見説得力があるように見える。11 死刑判決を伴う事件においてさえ、無実の人間に対する判決は不思議なほど強固なものに見える。
例えばアール・ワシントン・ジュニアの事件を見てみよう。彼は 22 歳の知的障害を持った黒人の農場労働者だった。 1982 年、バージニア州カルペパーで若い母親が性的暴行を受け殺害されるという事件がおきた。ワシントンがDNA鑑定によって無罪となったのは、執行予定日の 9 日前、死刑囚として 18 年間過ごした後のことである。一体なぜこのようなことが起こったのか。ワシントンは警察の取り調べにおいて、 4 件の未解決事件について「はい、そうです」と答え自白している。いずれの事件も被害者がワシントンではないと宣言したか、その他の証拠によって彼の無実が証明された。この 4 件について彼は起訴されていない。しかし警察は、カルペパーの事件についても彼に尋ね、彼はそれも認めた。警察がワシントンに署名させた自白の口述記録の大部分で、ワシントンは警察の質問に「はい、そうです」と答えている。しかしながら自白の口述記録の要約部分には驚くほど詳細な情報が含まれていた。ワシントンは自ら被害者のアパートにシャツを残してきたと供述したとされる。これは警察が公にはしていない情報であった。そして彼はパッチワークが剥がされているというそのシャツの特徴を知っていたとされる。当然この取り調べの最中、警察がシャツを彼の前に見せていたはずである。口述記録によると、それだけにとどまらずワシントンは寝室の洋服ダンスの中にシャツがあったことを知っていたとされる。最後に、ワシントンはシャツに血液が付着していたため置いてきたと供述している。警察官がワシントンに見せたシャツには染みはなかった。法医学鑑定のため血液付着部分が切り取られていたからである。
この裁判において彼の自白は最も重要なものであった。検察官は陪審員に次のように述べた。「彼が現場にいて彼がやったのでないとしたら、一体誰がここまでの話を作り上げられるだろうか。この事件が起きたという事実、そしてアール・ワシントン・ジュニアがやったという事実に、なんら疑いの余地はない。」これは死刑事件であったが、裁判はたったの 5 時間で陪審員は早急にワシントンに死刑判決を下した。 1984 年から 1993 年の間、彼の上訴は棄却された。 1993 年になってDNA鑑定によってワシントンは死刑を免れた。しかし、自白の効力は強いものであり、バージニア州知事は一部の恩赦しか認めず、ワシントンは死刑囚ではなくなったが、終身刑を言い渡された 。 2000 年に新しい
11 これらの情報提供者が漏れ聞いたとされる証言については下記の付録に詳細が記載されている。
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 15 10/06/2014 09:34
-
16
DNA鑑定が行われ、再度ワシントンの無実が証明されただけでなく、真犯人のDNAがDNAデータベースの別の男性と一致したことにより、ようやく彼は恩赦を得た。釈放されたのは 2002 年のことである。
虚偽の自白についての研究は広く数多く行われているが、冤罪被害者の中で、専門家が彼らの自白の正統性について言及する機会があったのはわずかであった。 彼らのうちの多くは青少年か知的障害者で当局の暗示の影響を特に受けやすい者たちであったが、陪審員たちにそのことが説明されることはなかった。
これらの事件における様々な欠陥のある証拠は我々に懸念を与えるものである。 14 件の死刑事件において法医学的証拠が用いられ、かつその中には信頼性の低い証拠も含まれていた。毛髪の比較は 10 件、繊維の比較が 2 件、血清学または血液型が 9 件、歯痕の比較が 2 件で行われた。12 18 件中 10 件において刑務所内の人間を含めた情報提供者による証言が行われた。情報提供者はいずれも加害者だけが知りうる詳細な情報を漏れ聞いたと証言した。 9 件は目撃者による本人確認が行われた。13 例えばメリーランドで死刑判決を受けたカーク・ブラッズワースは、一人ではなく 5 人もの個別の目撃者によって犯行現場付近にいたことを確認された。目撃者の全員が間違っており、この事件の経験がある程度引き金となってメリーランドでは死刑が廃止された。
ブラッズワース事件は、 2011 年にジョージアで処刑されたトロイ・デイビスのような事件に懸念を与える。デイビスは、誘導的な方法を利用して本人確認をした大勢の目撃者証言によって有罪判決を受けた。しかしこの事件ではDNA鑑定を行える証拠は存在しなかった。
12 これらの事件及びその他のDNA鑑定によって明らかになった250の冤罪事件における法医学的証拠は下記の付録に詳細が記載されている。Brandon L. Garrett, Forensic Testimony, Univ. of Va. Law Sch.,www.law.virginia.edu/pdf/faculty/garrett/convicting_the_innocent/garrett_ forensics_appendix.pdf13 これらの事件及びその他のDNA鑑定によって明かになった冤罪事件における目撃証言は下記の付録に詳細が記載されている。Brandon L. Garrett, Characteristics of Eyewitness Misidentications in DNA Exonerees’ Trials, Univ. of Va. Law Sch., www.law.virginia.edu/pdf/faculty/garrett/convicting_the_ innocent/garrett_eyewitness_appendix.pdfデモン・ティボドーはさらに2人の目撃者によって誤った本人確認をされた。Innocence Project, supra参照
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 16 10/06/2014 09:34
-
17
これらの事件は通常、死刑判決が破棄されるまでに複雑な経緯をたどる。無罪となった 18 人中 4 人は 2 度の再審、 2 人は 3 度の再審を経ている。最終的にDNA鑑定によって無罪が確定するまでの間、彼らは再審の度に有罪判決を受ける。しかしレイ・クロンのようにDNA鑑定によって一度無実になっても、再度有罪判決を受けた者もいる。デイモン・ティボドーがミシシッピーで死刑判決を受けたときDNA鑑定はすでに可能であったが、警察は彼の自白に重点を置くあまり鑑定を行わなかった。クリス・オコアのように死刑判決を受けておらずとも、死刑になると脅迫され虚偽の自白をし、他の無実の男性に対する虚偽の証言をした事件も考慮されるべきである。いずれも何年もの後、DNA鑑定によって無罪となった。
アメリカ連邦最高裁判所は「穏やかならざる数の死刑囚が無罪となった 」14 と述べている。州単位では死刑事件の冤罪に対して、一部でモラトリアムあるいは死刑廃止が実施された。しかしながらこのような誤判を招く一因となった捜査手続きの多くは、現在も改善されていない。例えば連邦最高裁判所は、アメリカ憲法下において実際に無実であるという主張を認めることを否定した。15 最高裁はまた、憲法上の問題として自白証拠の信頼性を規制することを拒否した 。16 多くのアメリカの裁判所では虚偽の自白について専門家が証言することは認められない。しかしながらソール・カシン教授は次のように述べる。「虚偽の自白は、専門家でない者が良識で判断できるような現象ではない。」17 より多くのアメリカの裁判所が、特に殺人事件における警察の尋問を録画することを要求しているが、実際にはほとんどなされていない。
14 Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304, 320 n.25 (2002).15 Herrera v. Collins, 506 U.S. 390 (1993).16 Colorado v. Connolley, 479 U.S. 157, 161 (1986).17 Saul Kassin, Why Confessions Trump Innocence, 67 Am. Psychol 431–445 (Sept. 2012).
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 17 10/06/2014 09:34
-
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 18 10/06/2014 09:34
-
冤罪の事例その他の国々
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 19 12/06/2014 09:27
-
20
(iii) その他の国々-手続きの不正、冤罪と不公正な裁判
台湾
台湾では、不公正な裁判によって国家が誤って死刑を執行する危険性が実在するという事実によって国民の死刑制度に対する不安が広がっているにもかかわらず、 2013 年以降 11 件の死刑が執行されている。近年、深刻な人権問題として注目を集めた事件として江國慶事件、汐止三人事件、鄭性澤事件、邱和順事件の4件が挙げられる。18
台湾の法務省は 2011 年 1 月、 5 歳の少女が性的暴行を受け殺害された 15 年前の事件について 1997 年の江國慶の処刑が誤りであったことを認めた。江の両親による無罪キャンペーンを受けて軍事最高裁判所検察官室は、 2010 年に異例の審理再開の嘆願書を軍事最高裁判所に提出した。当局は、江の犯罪を自白する供述は 37 時間に及ぶ尋問、強い光への暴露、スタンガンによる脅迫及び激しい身体運動の強要を伴う睡眠の妨害を含む、軍の捜査官による拷問の結果であったことを認めた。19 裁判所が、江が拷問を受けたとする申し立て及び無罪の主張を無視し、かつ彼の有罪判決は軍事裁判所からの圧力によって性急に出されたものであることが認められたのである。20 江は、 2011 年 9 月に軍事裁判所から正式な無罪判決を受け、また同年 10 月に台湾の国防部長が江の親族に 340 万米ドル(約 3 億 5 千万円)賠償金を支払うことに合意した。 台湾総統馬英九が江の母親に公式に謝罪するとともに、この事件における検察の行いが「不正」であったことを認めた。21
18 より詳細な情報はe Death Penalty in Taiwan: A Report on Taiwan’s legal obligations under the International Covenant on Civil and Political Rightsを参照。 www.deathpenaltyproject.org19 Taiwan Alliance Against the Death Penalty, “Doubts raised over soldier’s execution”, 30 January 2011 www.taedp.org.tw/en/story/187520 Death Sentences and Executions 2013, Report by Amnesty International. China: Against the law: Crackdown on China’s human rights lawyers deepens, Report by Amnesty International (2011) 参照。www.amnesty.org/en/library/info/ASA17/018/2011/en21 e National, “Taiwan ‘child rapist’ cleared 14 years after his execution”, 2 February 2011www.thenational.ae/news/world/asia-pacic/taiwan-child-rapist-cleared-14-years-after-his-execution
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 20 10/06/2014 09:34
-
21
トリニダード・トバゴ
トリニダードのアンマリー・ボドラムは 1998 年 2 月 20 日に夫の殺人の罪で絶対的死刑の判決を受けた。控訴院への上訴が棄却されたため、彼女は英枢密院司法委員会へ上訴した。英枢密院は彼女の弁護人の著しい無能さが冤罪を招いたのではないかという点を考慮した。英枢密院の判決を述べるにあたってスタイン判事は次のように述べた。
「この事件における[弁護人]の度重なるミス、とりわけ 1998 年 2 月 17 日に最初の事実審理で何が起きたのか調査するための再審に従事していることに気づくという異常な失態は、彼に職務上必要な能力が欠如しているか、あるいは彼が最も根本的な職務上の義務をふざけて放棄したかのいずれであることを明かにしている。この事件は我々がこれまで関わってきた事件の中で、弁護人が刑事裁判における職務上の義務を遂行しなかった最悪の事件である。弁護人の職務不履行があまりにも根本的性質を有するため、我々は被告人が適正手続きを剥奪されたとみなさざるを得ない。この例外的な事件においては、被告人は公正な裁判を受けていないと結論づける必要がある。」22
セントクリストファー・ネイビス
セントクリストファー・ネイビスで死刑判決を受けた死刑囚人シェルドン・イサック23は、 2012 年に東カリブ諸国控訴院において上訴審の決定を受けた。セントクリストファー・ネイビスにおける最後の死刑執行は 2008 年であり、イサックとその他 3 人の共同被告人は死刑執行の危機にあった。英枢密院は彼ら 4 人死刑執行を上訴の判決がでるまで停止した。英枢密院に提示された精神分析の証拠によれば、イサックは重度の脳障害を抱えておりそもそも裁判にかけられるべき状態ではなかった。英枢密院は新たな証拠を考慮したうえで彼の有罪判決と死刑判決の確実性を再度審理するべきであるとして事件を東カリブ諸国控訴院に差し戻した。控訴院はイサックが重度(外見上明らかな)の精神障害を抱えているという新たな証拠を認め、彼は裁判を受けられる状態ではなくそれゆえ殺人の有罪判決及び死刑判決を受けるべきではなかったと結論
22 [2002] 1 Crim. App.R.12, [40]23 Sheldon Issac v Director of Public Prosecutions, Eastern Caribbean Court of Appeal, Criminal Appeal No. 19 of 2008
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 21 10/06/2014 09:34
-
22
付けた。また控訴院は、再審を「不適切かつ不必要である」とした。この死刑事件においてセントクリストファー・ネイビスの刑事司法制度は、誰一人イサックの精神状態を問わなかったという明らかな過ちを犯した。捜査機関、刑務所職員、弁護人そして判事までもが皆、イサックが重度の精神障害を抱えており裁判を受けられる状態ではなかったことを見過ごしていたのである。その結果、イサックは国際人権基準に反して裁判にかけられ、有罪判決及び死刑判決を受けかつ処刑される寸前だったのである。 カリブ海諸国やその他の国における多くの事件では、死刑判決後に精神疾患及びあるいは知的障害を患っていることが判明し、結果として彼らの有罪判決の確実性と死刑判決の正当性に大きな影響を与えている。 特に精神衛生管理レベルが低く、トレーニングや整備が十分でない国ではその傾向が強い。重度の精神疾患を患っている者に対しては、死刑事件に関する国際基準と各国が考慮するべき厳格な手続き上の要請に反して、現実には多くの死刑判決が下されている。
シエラレオネ共和国
「MK」は、シエラレオネ共和国で最長期間死刑囚として過ごした女性である。彼女は 2003 年に継娘を殺害したとして逮捕され、 2005 年当時シエラレオネ共和国にて存在した絶対的死刑判決を受けた。
MKの事件は本報告書で提起されている多くの深刻な人権問題に焦点を当てるものである。逮捕後から裁判の直前まで、彼女は法的援助を全く受けていなかった。読み書きのできないMKは、後に裁判で彼女に不利に働くことになる自白調書に拇印を捺印している。裁判の開始に伴って、はじめてMKに国選弁護人がつけられた。弁護人は裁判開始以前にMKと 3 度の面会を行ったが、いずれも 15 分以内の短いものであった。
裁判の後もMKには弁護人へのアクセス、また有罪判決に対する上訴は 21 日間以内に行わなければいけないという規程に関する知識や援助へのアクセスも与えられなかった。MKは判決の 10 ヶ月後に、刑務所の福祉担当官の援助を受けて控訴院に上訴した。その後控訴院は、死刑に直面している者であっても上訴の申請期限は厳守されなければならないという考えのもと、申請期限を越えた申請であったという理由で上訴を却下した。
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 22 10/06/2014 09:34
-
23
2010 年にMKはシエラレネオ共和国の非政府組織であるAdvocAidによる法的援助を受け、事件は再度控訴院に上訴された。死刑囚として 6 年間過ごした後の 2011 年 3 月、上訴院はMKの有罪判決を破棄する画期的な判決を下し、彼女はその直後に釈放された。裁判所は、法的助言及び援助の欠如と有罪判決に対する上訴援助の欠如という手続き上の不正は根本的なものであり、それゆえMKの裁判は無効であるとする判決を下した。国はMKがすでに死刑囚として過ごした年月を考慮し、再起訴を取り下げた。
上記の悲劇は、適正手続きと法の保護の適用が妥当でないと判断されたごく一部の事件である。これらからも明らかなように、信憑性の低い自白や犯人識別及び捜査上の不正を取り除くことができる十分な規制が行われていない。死刑に直面する者は、疑わしい自白の証拠に基づいて裁判にかけられ死刑判決を受けている。拘禁中に弁護人にアクセスできる権利は、ある国では実践的というよりも理論上の権利になってしまっている。裁判及び上訴を行う弁護人は、しばしば準備不足かつ、あるいは公正な裁判を確保するのに必要な経験に乏しく、また十分な擁護を準備するのに必要な専門家の助言(医学的あるいはその他)を得るだけの資金を持ち合わせていない。
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 23 10/06/2014 09:34
-
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 24 12/06/2014 09:27
-
冤罪の事例イギリス
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 25 12/06/2014 09:28
-
26
(iv) イギリス– 冤罪事件からの教訓
イギリスが死刑廃止に至るまでの経験から、我々は実に多くの教訓を学び取ることが出来る。特に重要なのは、死刑が廃止されたことによって数多くの冤罪事件の不公正が判決後に明らかになり、その是正が可能になったということである。
イギリスでは殺人事件に対する死刑適用は 1965 年に廃止されている。イギリス議会では死刑の適用を復活させようという試みもあったが、非常に悪質な事件における冤罪が続いたことによりそれは失敗に終わった。特に注目すべきなのは、いずれも無実の爆弾テロによる殺人罪で有罪となったバーミンガム・パブ爆破事件の 6 人とギルフォード・フォー事件の 4 人、そして 11 歳の子供に対する性的暴行と残忍な殺人を自白した後有罪判決を受けた知的障害を持つステファン・キスコである。彼は終身刑で 16 年間服役した後、身体上の問題で無精子であること及び彼の無実を証明する証拠を警察が握りつぶしたことが判明したため釈放された。24
死刑制度の廃止は、死刑を執行された被告人の事件を死後、裁判所が調べ直した一連の事件によってより強固なものになった。その一つが 1952 年 9 月 8 日にカーディフ刑務所で絞首刑を執行されたマハムド・フセイン・マテインである。 1998 年に控訴院は、彼の有罪判決が不確実であり破棄するべきであるとした。判決を下すにあたりローズ判事は、この事件が広く重要性をもつものであるとともに、「死刑は、人間が行いそれゆえ人的ミスを免れない刑事司法制度の頂点にあるべきものではない」ことを示していると述べ、冤罪の可能性及び無実の人間への死刑執行が避けられないものであることを痛烈に指摘した。バーミンガム・パブ爆破事件やギルフォード・フォー事件の捜査を行ったイギリスの警察官たちが特別に悪意を持っていたとか、あるいはその他の冤罪事件において職務上の義務を果たさなかったイギリスの検察官や科学者が、その他世界中の検察官や科学者と比べて能力を欠いていたなどということではない。
イギリスでは、これらの事件によって明かになった刑事犯罪制度の弱点を克服するために、 1997 年 6 月に刑事事件再審委員会(Criminal Cases Review
24 Roger Hood & Carolyn Hoyle, Chapter 2 Vanguard of Abolition, �e Death Penalty: A World-wide Perspective, (4th ed. 2008), Oxford: Oxford University Press, p. 42-47. 参照。
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 26 10/06/2014 09:34
-
27
Commission, CCRC)が設立された。同委員会はイギリス、ウェールズ及び北アイルランドの刑事裁判における冤罪の可能性のある事例を審査するための独立した公的機関である。25 設立以降 1 万 7 千件以上の申請があり、そのうち 500 件以上が控訴院に差し戻された。そのうちのおよそ 7 割の事件において有罪判決が破棄されている。26
委員会が誤判を明らかにするのに役立った一つの例は、 1979 年に起きた 22 歳の女性への性的暴行と殺人の罪で終身刑の判決を受けた知的障害を持つショーン・ホジソンの事件である。裁判において彼は自白(警察はこの自白に犯人のみが知りうる情報が含まれているとした)を撤回し無罪を主張した。刑務所でも彼は無実を主張し続けたため、「犯した罪と向き合う」ことが条件である仮釈放の可能性は完全に断たれた。 27 年に及ぶ服役の後、弁護士がDNA鑑定が可能な証拠を発見したことにより、彼は釈放された。犯行現場で採取された血液と精液の分析によって彼の容疑は完全に晴れた。
しかし委員会が設立されてもなお、司法行政における誤判の発見が全てのケースにおいて出来ている訳ではない。最近の例として、性的暴行の罪で有罪判決を受け 17 年間服役していたビクター・ニーロンの事件がある。ニーロンは終身刑の判決で服役中、彼の有罪を証明するために用いられた法医学的証拠を精査するよう委員会に申請した。しかしながら委員会は彼の有罪判決は確実なものであると判断し申請を 2 度にわたって却下した。 2013 年、 3 度目の申請でようやくニーロンの主張の正当性が認められ、彼の有罪判決はDNA鑑定を根拠に控訴院によって破棄された。委員長は、委員による適切な調査が行われなかったことに対して謝罪し、次のように述べた。「この事件について我々が重要な何かを見逃したという事実が悔やまれてならない。そしてその事実について、関係各者に謝罪する。」27
25 イギリス刑事事件再審委員会ホームページ: www.justice.gov.uk/about/criminal-cases-review-commission委員会が有罪判決が不確実なものである可能性が高いと判断した場合、委員会は事件を控訴院に差し戻すことができる。委員会の特徴は、その他の上訴方法を全て使い果たしてからでないと申請できないという点にある。審査を行うにあたっては、委員会は警察、法医学局、検察当局などの公的機関が保持している情報へのアクセス権限を持つ。また委員会は独自に巡査長や独立の法医学専門家を指定し、調査を行うことができる。26 イギリス刑事事件再審委員会は設立以降17708件の申請を受け、552件を控訴院に差し戻し、そのうち361件が控訴院で破棄の判決を受けている。27 BBCニュース, 2014年5月20日, 「誤判を受けた男、ビクター・ニーロンが謝罪を受ける」 www.bbc.co.uk/news/uk-england-27468183
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 27 10/06/2014 09:34
-
28
結論 手続的保障の改善、及び全ての事件の被疑者に対する法の保護の提供は不可欠である。しかしながらそれでも誤判や冤罪の可能性は、完全に消えるわけではない。本報告書で取り上げた日本やアメリカ(いずれも十分に発展した国であるが)の実例がその証拠である。そして死刑廃止後のイギリスおける事例は、どんなに整った刑事司法制度をもってしても、誤判をなくすことができない事を示している。
すべての国は、あらゆる死刑事件において適正手続きが曇りなく規程通りに行われているのかを問うべきである。極刑を科すにあたっては、捜査、起訴、裁判において冤罪の余地のない公正さと正当性をもって行われる、という前提が不可欠であることを認識しなければならない。理論的にはこの前提によって誤判の可能性は減少するが、しかしゼロになるわけではない。究極のところ、刑事裁判とは脆弱なものであり、たった一人の不誠実な警察官、たった一人の無能な弁護士、たった一人の熱心過ぎる検察官、あるいはたった一人の誤った目撃者がいれば制度が機能しなくなってしまうのである。
完璧な司法制度などというものは存在しない。すなわち誤判は避けられないものである。死刑が科される限り、そこには無実の人間が有罪判決を受け死刑に処される危険性が潜んでいるのである。
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 28 12/06/2014 09:28
-
付録自由権規約及びその他の国際基準の妥当性
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 29 10/06/2014 09:34
-
30
(i) 市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)
自由権規約の第 6 条第 2 項は下記のように定めている。
「死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。この刑罰は、権限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。」
死刑は、生命に対する権利の例外ではあるが、自由権規約第 6 条は死刑の適用及び執行について多くの保護条項を規定している。死刑は最も重大な犯罪についてのみ科すことができるが、厳密な手続的規則が尊重されねばならず、また 18 歳未満の者に科してはならず、妊娠中の女子に執行してはならない。
第 6 条第 6 項は、さらに死刑制度の現状を踏まえつつ、最終的な廃止を前提とする。
「この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用されてはならない。」
死刑存置が許容されている(第 6 条第 6 項にしたがって死刑廃止が保留されているというかなり特殊な)状況では、死刑の適用そのものが残酷あるいは異常な刑罰、拷問、又は非人道的な扱いや刑罰となるわけではない。しかしながら、自由権規約の他の条項に反する状況での死刑適用は、恣意的な生存権の侵害となりうる。さしあたって特に重要となるのは、公正な裁判を受ける権利と拷問の禁止である。
自由権規約第 14 条の包括的条項は、公正な裁判の最低保障を詳細に規定している。これらの条項はすべての死刑事件において守られなければならない。規約人権委員会は一貫して、死刑事件の審理過程で自由権規約第 14 条(公正な裁判)の違反があった場合、同時に自由権規約第6条(生命に対する権
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 30 10/06/2014 09:34
-
31
利)にも違反していることになるとしている。Carlton Reid 対 ジャマイカ事件において規約人権委員会は次のように判断した。
「自由権規約が尊重されない審理の結果として死刑判決を科すことは、規約第6条に違反する。委員会が一般的意見6(16)で述べたように、死刑は法律に従い、かつ、この規約の規程に反しない場合にのみ科することができるという規約は、すなわち独立の裁判所による公正な審理を受ける権利、無罪の推定、 防御権の最低限の保障及び上級裁判所による最審理を受ける権利を含め、規約で定められた手続上の保障が遵守されなければならない。ということを示している。」28
(ii) 死刑に直面する者の権利の保護を保証するセーフガード
自由権規約の第 6 条に示される死刑への制限は、死刑に直面する者の権利の保護の保障に関するセーフガード(以下「セーフガード」)に反映され、かつさらに発展して具体化されており、これに「いまだ死刑を科している国が適用するべき最低基準が列挙されている。」29 セーフガードは 1984 年、国連経済社会理事会決議 1984/50 により採択された。 1989 年に経済社会理事会は、これらの内容をさらに発展させ、とりわけ死刑の宣告及び執行に年齢の上限を設けることと、知的障害者を死刑から保護する対象に加えることを勧告した。国連経済社会理事決議1996/15 は、死刑制度を廃止していない加盟国に対し「死刑に直面する者の権利の保護を保障するセーフガードを効果的に適用すること」を要求している。このセーフガードの重要性は、 2005 年の国際連合人権委員会及び国連総会決議62/149及び 63/168 において、再確認されている。
すべての国は、死刑に適用される一般原則とみなされるべきセーフガードに定められた国際基準の制約を受けている。セーフガードの第5項は次のように述べる。
28 Communication No. 250/1987, U.N. Doc. CCPR/C/39/D/250/1987, (21 August 1990) at paragraph 11.5.29「死刑および死刑に直面する者の権利の保護を保証するセーフガードの実行-事務総長報告書」(U.N.Doc. E/2010/10, 33頁)
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 31 10/06/2014 09:34
-
32
「死刑は、公正な裁判を確保するためにあらゆる可能な保護措置を講じる法的手続きの後、権限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。この保護措置は、少なくとも自由権規約 14 条に含まれるものと同等であって、死刑の適用可能性のある犯罪につき嫌疑をかけられ、あるいは追訴を受けた者が、手続きのあらゆる段階で十分な法的援助を受ける権利を含む。」この条項は 1989 年の次の決議によりさらに強化されている。「死刑事件の被告に、それ以外の事件で与えられる保護に加えて、手続きのあらゆる段階で弁護人から十分な援助を受けられることを含め、防御の準備に時間と便益を与えることにより、特別な保護を与える。」
超法規的、即決あるいは恣意的処刑に関する国連特別報告者は、死刑事件における公正な裁判の保障は「どのような事件にも、例外も差別もなく実施されなければならない」と述べている。30 特別報告者はまた、「死刑の適用に至る手続きは、関連する国際法規に従って、裁判官及び陪審員の独立性、有能性、客観性、公平性につき最高レベルの基準に合致したものでなければならない」としている。31一般的な理解として、死刑に直面する者には、それ以外の事件で与えられるより保護の範囲を越えて、公正な裁判を確保するための特別な保護
(しばしば「超」適正手続きと言及されるもの)が与えられなければいけないと考えられている。
30 Extrajudicial, summary or arbitrary executions: Report of the Special Rapporteur…, UN Document E/CN.4/2001/9, (11 January 2001) paragraph 8631 Extrajudicial, summary or arbitrary executions: Report of the Special Rapporteur…, UN Document E/CN.4/1997/60, (24 December 1996) paragraph 81
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 32 10/06/2014 09:34
-
33
著者ロジャー・フッドオックスフォード大学犯罪学名誉教授、オールソールズカレッジ名誉フェロー。
ブランドン・ガレットバージニア大学法学院教授。
佐藤舞刑事政策研究所及びオックスフォード大学犯罪学研究所研究員。
田鎖麻衣子弁護士、NPO法人「監獄人権センター」事務局長。
ソール・レーフロインド & パヴェーイス・ジャバーe Death Penalty Projectの共同創設者及び共同常任理事。
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 33 10/06/2014 09:34
-
The Death Penalty Project 我々は、死刑に直面している者の人権を守る活動を行っている。我々は、死刑が法的強制力のある刑罰として定められている全領域を活動範囲とし、死刑囚及び死刑に直面している個人に対する無料で効果的な弁護の提供をする。
我々の活動は、 20 年以上にわたり、多数の冤罪の発見、公正な裁判の最低保証の推進、国内法及び国際法違反の確立にまでいたる欠かせないものとなっている。我々の法的活動によって、死刑の適応は国際人権法に基づき数多くの国で制限されるようになった。トーレニングプログラムや研究プロジェクトと通じて、死刑に関する意識を高め、 死刑制度に携わる主要関係者とのより深い熟議の推進を目的としている。
DPP report Japan June 2014 Japanese_pp01-36.indd 34 10/06/2014 09:34