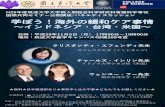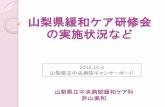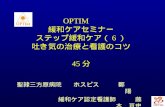在宅ターミナルがん患者支援のための モバイル版 Support Team … · ル1)(以下stas-j と略す)として施設に導入されている。緩和ケア領域では緩和ケア病棟、
緩和ケア地域連携クリニカルパス 運用の手引き「緩和ケア地域連携パス...
Transcript of 緩和ケア地域連携クリニカルパス 運用の手引き「緩和ケア地域連携パス...

2010年 7月
大垣市医師会
大垣市民病院がん診療委員会
緩和ケア地域連携クリニカルパス
運用の手引き
運用要綱
患者医療情報
わたしのカルテ
運用マニュアル
診療計画書
悲嘆ケアパンフレット


緩和ケア地域連携パス 運用要綱
【目的】
1)地域医療機関の機能分化と、連携を密にすることで患者家族の望む十分な医療を
提供しうる。
2)疾患の早期から、患者家族が持つ種々の苦痛を緩和するために、かかりつけ医と
病院の双方で連携して治療を行う。
【対象症例】
病院入院中あるいは通院中のがん患者で、今後の診療をかかりつけ医と病院医師が共同で、
あるいはかかりつけ医主体で診て行く必要があると考えられる症例を対象とする。
【基本原則】
1)パスへの登録症例は病院側で決定する。
2)パスの運用ツールは以下の5つからなる。
・「患者医療情報」
・「診療計画書」(急性期病院用・在宅ケア医用・患者用) ~
・「わたしのカルテ」 ~
・「悲嘆ケアパンフレット」
・「運用マニュアル」(急性期病院スタッフ用・在宅ケア医用) ~
3)「患者医療情報」についてはかかりつけ医と大垣市民病院との間で患者情報を共有するた
めのツールであり、それぞれの医療機関で複写を保存する。
4)「診療計画書」に沿って、それぞれの医療機関が診療計画を確認し、実施する。
5)患者家族には患者用の「診療計画書」を渡し予定された診療計画に関して理解を得る。
6)「わたしのカルテ」は患者が保管し、かかりつけ医・病院・訪問看護ステーションなどが
関わる時に共通の情報のもとで診療・処置が行えることを目的としたツールである。
7)「わたしのカルテ」の記載については、病院スタッフが「急性期病院スタッフ用マニュア
ル」を確認しつつ、患者家族に説明する。これまでの面談書・検査結果などの資料につい
ても「わたしのカルテ」内に挟み込めるよう準備をする。
8)退院時には可能な限り、退院時カンファレンスを行い、情報共有・連携を図る。
9)かかりつけ医は「かかりつけ医用マニュアル」を参考にしつつ、「わたしのカルテ」を用
いて患者管理を行う。
10)病状が変化した時、患者・家族は「わたしのカルテ」に記載された「緊急時の対応」に従
って連絡し、指示を仰ぐ。
11)かかりつけ医・病院スタッフ・訪問看護ステーションなどは連携を図りつつ、「わたしの
カルテ」に記載された患者・家族の希望をできるだけ実現できるよう努力する。
12)自宅での看取りを希望される場合は、かかりつけ医が家族と協力して対応する。
13)必要に応じて「悲嘆ケアパンフレット」を利用し、家族のサポートを行う。
14)各ツールに関する取り扱いの詳細については、「急性期スタッフ用マニュアル」・「在宅ケ
ア医用マニュアル」を参照すること。
15)不明な点は大垣市民病院よろず相談・地域連携課に照会すること。
3
15 30
34
3 14
31 33
それぞれの資料を載せてあるページを示した
簡単な紹介状も添付する
1


緩和ケア地域連携パス
患者医療情報
記載日:平成 年 月 日 登録番号:
患者氏名: 様 生年月日:大・昭・平 年 月 日
病院カルテ No. かかりつけ医カルテ No.
病院担当科 科 病院担当医師名 医師
かかりつけ医 ( )・病院・医院・クリニック 先生
がんの病名 血液型
手術日 □有□無:昭・平 年 月 日
手術術式
抗がん剤
放射線治療
□有□無:
現在の症状
(主病名) ① ② ③
患者への説明 例)余命半年と伝えた。
説明に対する
理解の印象 例)十分理解できていない様だが、さらに詳しく説明はしていない。
家族への説明 例)患者と同様、半年と伝えてあるが、状況によりさらに短くなる可能性、急変の
可能性を伝えてある。
説明に対する
理解の印象
例)充分理解されている。急変時は在宅での看取りも容認できそう。再確認をお
願いします。
キーパーソン 氏名:
関係:
連絡先:自宅:
携帯:
疼痛管理
(使用薬・投与法)
例)デュロテップ MTパッチ 12.6mgに加え、1日 3回程度オプソ 30mgでレスキ
ュー。ロキソニン 3錠、カロナール頓用 4錠、ガバペン 2錠(朝夕)
栄養管理
(点滴等あれば)
例)経口摂取可能。誤嚥の危険有り、入院中はミキサー食としていた。 経口摂取ができなくなる可能性有り、IVHポートを設置してあります。
その他治療内容 高血圧・狭心症があり、内服治療中。 ・・・・・・
社会資源
□ケアマネージャ:
□訪問看護ステーション:
□訪問リハビリ:
希望する
看取りの場所
□自宅 □病院 □その他:メモ
例)今のところ、できるだけ自宅で頑張りたいが、最期は病院でとの希望です。
その他
緩和パス 医療情報
2
病院主治医が記載し、準備する。 可能な限り記載するが、空欄があっても可
この部分は必ず記載すること。 特に、患者と家族への説明に違いがある時には詳細を記載 できれば、余命告知の有無と詳細を記載 (例:「余命何ヶ月ほどと伝えた」)
レ


「緩和ケア地域連携パス」
急性期病院 スタッフ用マニュアル 運用における各種注意事項
1.使用するツール
●「診療計画書」 ~
急性期病院用、在宅ケア医師用、患者様用、があります
●「緩和ケア地域連携パス 患者医療情報」
医師間で患者情報をやりとりするための共有ツールです。
実際に運用する時には紹介状(簡単なもので可)も添付します。
●「わたしのカルテ」 ~
緩和ケア地域連携パス運用において最も大事なものです。
患者の診療に対する希望、緊急時の対応、病状変化の記録、各種データの保存などほぼ全ての患者情
報をまとめたもので、患者、家族、診療機関、訪問看護ステーションなどの間で共有するためのもの
です。
●「地域連携クリニカルパスを利用される患者様へ」
緩和に限らず、西濃地域における各種地域連携クリニカルパスに関する患者説明用の文書です。
「わたしのカルテ」に「診療計画書(患者用)」「面談書」「検査データ」等とともに挟んで渡します。
●「悲嘆ケアパンフレット」
在宅ケア医に渡し、患者を喪った家族に対する悲嘆ケアの一助にして頂きます。
2.緩和ケアパス運用の実際
● 自宅近くの医師と連携協力して診療を行う方針が決定したら、「診療計画書」に沿って準備をします。
● それぞれの項目を満たしているかチェックをします
● 満たしていない項目は出来る限り条件を満たすよう努力します。
● 「わたしのカルテ」を患者、家族に渡し、記載方法の説明・希望の確認・データの添付・緊急時の対
応の確認と記入、利用可能な社会的医療資源の準備、などを行います。
● 退院前に合同カンファレンスを開き、再確認をします。
● ①患者医療情報・紹介状、②各医療機関用の診療計画書、③緊急時の対応、④説明書(・同意書)の
4つの書類をコピーし、各医療機関で保管します。
3.「わたしのカルテ」の運用方法
●「わたしのカルテ」は患者さん自身が所持します。
●「わたしのカルテ」を渡す時に、記入の仕方、使用方法を説明します。
●「わたしのプロフィール」、「わたしが大切にしていること」は患者さんかご家族に記載していただきま
す。
●「緊急時の対応」は主治医から指示を受け記載しますが、退院後に在宅ケア医からも指示があれば追加
記載するよう指導してください。
●「医療機関連絡先」についても漏れのないように記載しておくよう指導してください。
●「わたしの療養記録」について
・退院時に認められる痛みは「痛みの部位」に記載して評価方法・記載方法を説明してください。
NRSによる評価・最小/最大の痛みの点数・最大の痛みの回数(例:3点/7点/4回)など。
・退院後に新たに痛みが出てきた場合は追加記入して、評価するよう指導してください。
緩和パス急性期-1-
3
3
15 30
34
31 33
11 25
Faces Pain Scale でなく、Numerical Rating Scale

・「その他の症状」も同様に、入院中からある症状は前もって記載しておき、新たに出てきた症状につ
いては追加記載をするよう指導します。
・「日常生活」については、食欲、睡眠、排便、体重について記載方法を説明してください。
・無理に体重を量ったりしないよう、可能な範囲で記載するよう話して下さい。
・「薬の服用」について定期の鎮痛薬と屯用使用の鎮痛薬の服用状況について記載するよう指導してく
ださい。(医療用麻薬製剤の説明書は今後充実させてゆく予定です)
・他に治療中の病気があり、必要な薬があれば追加記入できることを説明してください。
・「その他」の欄には日常の気になることなどを記載してもらいます。
・在宅ケア医、専門病院医師受診時、訪問看護師訪問時にも見てもらい、アドバイスをもらう様指導
します。
・在宅ケア医、専門病院医師、訪問看護師に対しても、必要があれば空欄に生活指導・病状説明・アド
バイスなどを記入してもらうようお願いしてある旨説明します。
●資料の最後に、患者さん用の「わたしのカルテ」説明書を入れてあります。
参考にして下さい。
入入院院中中・・通通院院中中 医療チーム
○入院時・入院中に地域連携について
評価
主治医
○退院前に、医療連携を説明
○連携医療機関について相談
○地域連携パスの説明、提示
(○地域連携パスの同意書取得)
○わたしのカルテにアドバイス記入
よろず相談・地域連携課
○連携先医療機関調整、決定
○訪問看護ステーション決定
○連携医療機関に情報提供
○「わたしのカルテ」説明、提示
退退院院後後 地域連携拠点病院・専門病院
○定期の診察・精密検査
○緊急時の対応
地域連携病院・医院(在宅ケア医)
○日常診療、検査、治療、投薬
○わたしのカルテにアドバイス記入
○緊急時の対処指示
患者・家族
○医療機関受診(わたしのカルテ持参)
○診察・検査・治療・投薬内容の記載
○病状変化時、療養記録に追加記入
○患者さんの状態・思いに変化があれ
ば追加、変更記入
緩和パス急性期-2-
4

がん地域連携クリニカルパス
緩和ケア地域連携パス(緩和ケアパス)
「がん地域連携クリニカルパス(がんパス)」とは地域の在宅ケア医師と病院の専門医師とが、がん患者
の診療情報を共有できる診療計画書のことです。「がんパス」を上手く活用して、在宅ケア医師と専門医師
が協力してがん患者の診療を行います。
「がんパス」を利用することで、病院での治療内容・日常生活での各種問題などに関して医師の間で情報
をやりとりできるばかりでなく、患者さんご自身も病気の状態や診療計画を理解でき、病状に変化があった
時でも適切に対処ができるなど、安心して診療を受けることができるようになります。
現在稼働中の西濃地域における「がんパス」は、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、肝細胞がん、前立
腺がんの 6つのがんですが、今回、緩和ケアについても連携を図ることになります。
「緩和ケア地域連携パス」として、在宅ケア医師と病院医師との間で連携をして行きます。
1.在宅ケア医師の役割
●日頃の診療は、地域の在宅ケア医師が担当します。がんあるいはその他の持病の診療を担当します。
おもな診療内容を下に記します。
・定期的な診察、血液検査、画像検査など(結果は「がんパス」「わたしのカルテ」に記載します)
・定期的な薬の処方
・痛みや吐き気など各種症状の継続的な診療
・風邪をひいたり、熱が出たときなど、臨時の診療
・病状悪化などにより、病院での診察が必要と判断した時には病院に連絡し、紹介とします
2.病院専門医の役割
●必要に応じ、年に何回か病院に通院していただき、精密検査と診察を行います。
・精密検査としては、血液検査、超音波検査、CT検査、MRI検査などがあり、必要に応じて施行します。
・検査結果は「がんパス」あるいは「わたしのカルテ」内に記載して、在宅ケア医師に連絡します。
・病状が変化したときなどは在宅ケア医師の紹介により、臨時に病院で診察を行ったり、入院治療をしたり
することもあります。(経過を知る上で、紹介状を持参することをお勧めします)
・入院が必要な場合は開放病床(大垣市民病院の場合)を利用することも可能です。在宅ケア医師とよくご
相談ください。
患者
家族
訪問看護
ステーション
病院専門医
看護師
MSW
在宅ケア医
調剤薬局
わたしの
カルテ
がんパス
緩和パス急性期-3-
5
緩和ケア地域連携パスにお
ける在宅ケア医と病院医師
との機能分担に関する説明
です。
「わたしのカルテ」を用いて、情報共有を図り、患者家
族の望む緩和ケアを提供することをめざします。

連携中の日常生活について(参考)
1.安静と運動
●過度の運動により過労にならないように注意しましょう。
●しかし、過度の安静は必要ありません。
●毎日 30分ほどのマイペースでの散歩など、心地よい疲労感を感じられる適度な運動を続けて
ゆくことをお勧めします。
2.食事
●胃腸の手術後で特別な注意が必要な方は、医師の指示に従って下さい。
●病気だからといって、特定の食事だけを食べる、あるいは避けるようなかたよった食事は
良くありません。
●穀物を中心に、バランス良く食べるようにしましょう。
●脂肪を取りすぎないように注意してください。
●タンパク質は動物性よりも植物性の方が良いでしょう。
●香辛料や薬味など刺激物の取りすぎには注意してください。
3.アルコール
●アルコールは肝臓で分解されます。
●薬によっては、アルコールの分解に影響を及ぼすこともあり、注意が必要です。
●主治医の先生に飲酒が可能かどうか、確認をしてください。
●「飲んでも大丈夫」と言われても、ほろ酔い加減で済ませ、深酒は避けた方が良いでしょう。
4.入浴
●お風呂に入ることはそれだけで体力を要します。熱い風呂・長風呂は避けてください。
●負担が大きい時には浴室内に椅子を持ち込み、腰掛けてシャワーをかけてもらうなどの工夫も
必要です。
●食後 1時間は入浴を避けた方が良いでしょう。
5.旅行
●旅行が可能かどうか、また可能であっても注意しなければならない点については、主治医の
先生に確認をしてください。
●在宅酸素、在宅での点滴などをしている場合には準備や手続きが必要な場合があります。
●海外旅行をする時には、薬によっては事前に届け出が必要です。ご確認ください。
●無理のないスケジュールをたてることをお勧めします。
緩和パス急性期-4-
6
連携中の日常生活上の注意・アドバイスなどを記載してあります。疾患毎、患者毎に
状況が異なりますので、あくまで参考としてください。

「わたしのカルテ」 患者様用説明書
1.連携先の決定
●「わたしのカルテ」を使用したがん診療連携「緩和ケア地域連携パス」が始まります。
日頃かかりつけ医として受診される診療所や病院、医院、利用される調剤薬局、訪問看護ス
テ-ションなどを、主治医・看護師・医療ソーシャルワーカー(MSW)と話し合いながら決
めてゆきます。
2.患者さん・医療者が所有するもの
●患者さんには「診療計画書」と「わたしのカルテ」をお渡しします。
●「わたしのカルテ」は、連携している病院・医院などの医療機関だけでなく、その他の医療
機関(風邪でたまたま受診・歯医者・眼医者など)を利用される時にもご持参下さい。
また、訪問看護ステーションのスタッフとの連携にもご利用ください。
●「わたしのカルテ」の中のプロフィール、緊急時の連絡先、説明書・同意書、共同診療計画
書などの書類のコピ-を、連携している各医療機関で保管しています。
3.「わたしのカルテ」の目的
●「わたしのカルテ」は患者さんの「がん」という病気に対して、手術後の経過、その後の治
療経過(化学療法、放射線療法、内服薬など)、あるいはつらい症状の経過など、治療のす
べての場面で切れ目のない診療を安心して受けて頂くことを目的に作られています。
4.私のカルテの運用方法
●病院医師・看護師・MSWの指示に従って、必要な部分を埋めてください。
●「わたしのプロフィ-ル」に必要事項を記入して下さい。
●「わたしが大切にしていること」には医師や医療スタッフに伝えたいことを記載します。
●患者さんのがんに関する情報は、「患者医療情報」により医師間でやりとりしています。
●「緊急時の対応」には病状に変化があった場合の対応を病院医師・在宅ケア医の指示に従っ
て記載します。また、医療機関連絡先は各医療機関で記入してもらいます。
実際に病状に変化があった場合は、記載の指示に従って下さい。
●「診療計画書」に沿って診療が進められて行きます。指示に従って、各医療機関を受診して
下さい。
●「わたしの療養記録」は、毎日の患者さんの状態をご自身(ご家族)で記載する所です。わ
かる範囲で構いません。また、その他に気になることなどは「その他」の欄に記入して、医
師、看護師などにお伝えください。
・苦痛の強さは(最小の苦痛/最大の苦痛/最大の苦痛の回数)として記入して下さい。
例)痛み:3/7/4回、0/5/2回 など。呼吸困難:0/5/5回 など。
・体重などは毎日測定する必要はなく、無理に測定する必要もありません。できる範囲で。
●医師以外のスタッフからのアドバイスやお薬手帳にも目を通しましょう。
●検査データや画像所見、医師からの説明文書などもカルテ内に挟んでおくと便利です。
★「わたしのカルテ」は患者さんの大切な情報が詰まったカルテです。
紛失しないよう、十分に注意して下さい。
緩和パス急性期-5- 7
個人情報が入った書類であることを十分説明して下さい。
上手に活用して頂ければ幸いです。
「わたしのカルテ」患者用説明書ですが、病
院スタッフが説明します。「わたしのカルテ」
が有効利用できるように指導して下さい。

8

「緩和ケア地域連携パス」
在宅ケア医師用マニュアル 運用における各種注意事項
1.使用するツール
●「診療計画書」 ~
急性期病院用、在宅ケア医師用、患者様用、があります
●「緩和ケア地域連携パス 患者医療情報」
医師間で患者情報をやりとりするための共有ツールです。
実際に運用する時には紹介状(簡単なもので可)も添付します。
●「わたしのカルテ」 ~
緩和ケア地域連携パス運用において最も大事なものです。
患者の診療に対する希望、緊急時の対応、病状変化の記録、各種データの保存などほぼ全ての患者情
報をまとめたもので、患者、家族、診療機関、訪問看護ステーションなどの間で共有するためのもの
です。
●「地域連携クリニカルパスを利用される患者様へ」
緩和に限らず、西濃地域における各種地域連携クリニカルパスに関する患者説明用の文書です。
「わたしのカルテ」に「診療計画書(患者用)」「面談書」「検査データ」等とともに挟んで渡します。
●「悲嘆ケアパンフレット」
患者を喪った家族に対する悲嘆ケアの一助にして頂きます。ご利用下さい。
2.緩和ケアパス運用の実際
● 在宅ケア医師と連携協力して診療を行う方針が決定したら、急性期病院では「診療計画書」に沿って
準備をします。
● それぞれの項目を満たしているかチェックをし、準備を進めます。
● 満たしていない項目は出来る限り条件を満たすよう努力します。
● 「わたしのカルテ」を患者、家族に渡し、記載方法の説明・希望の確認・データの添付・緊急時の対
応の確認と記入、利用可能な社会的医療資源の準備、などを行います。
● 退院前に合同カンファレンスを開き、再確認をします。よろず相談センターから連絡をいたします。
● ①患者医療情報・紹介状、②各医療機関用の診療計画書、③緊急時の対応、④説明書(・同意書)の
4つの書類のコピーをお渡しします。お互いの医療機関で保管します。
3.「わたしのカルテ」の運用方法
●「わたしのカルテ」は患者さん自身が所持します。
●「わたしのカルテ」を渡す時に、記入の仕方、使用方法を説明してあります。
●「わたしのプロフィール」、「わたしが大切にしていること」の記載内容を確認して下さい。
●「緊急時の対応」を確認して下さい。追加があれば指導・話合いの後、記載してもらってください。
●「医療機関連絡先」についても漏れのないように記載しておくよう指導してください。
●「わたしの療養記録」について
・退院時に認められる痛みは「痛みの部位」に記載し、評価方法・記載方法は説明済みです。
NRSによる評価:最小/最大の痛みの点数・最大の痛みの回数(例:3点/7点/4回)で表現。
緩和パス在宅医-1-
9
3
15 30
34
31 33
11 25
Faces Pain Scale でなく、Numerical Rating Scale
病院スタッフ用と在宅ケア
医師用と別に準備しまし
た。同じようにみえますが、
若干表現が異なります。

・退院後に新たに痛みが出てきた場合は追加記入して、評価するよう指導してください。
・「その他の症状」も同様に、入院中からある症状は前もって記載しておき、新たに出てきた症状につ
いては追加記載をするよう指導してありますので、確認して下さい。
・「日常生活」については、食欲、睡眠、排便、体重について記載方法を説明してあります。
・可能な範囲で記載していただくよう指示してありますので、抜けもあるかもしれません。
・「薬の服用」について定期の鎮痛薬と屯用使用の鎮痛薬の服用状況について記載するよう指導してあ
ります。ご確認下さい。(医療用麻薬製剤の説明書は今後充実させてゆく予定です)
・他に治療中の病気があり、必要な薬があれば追加記入できることを説明してあります。
・「その他」の欄には日常の気になることなどを記載するよう説明してあります。
・在宅ケア医師、専門病院医師受診時、訪問看護師訪問時にも見てもらい、アドバイスをもらうよう指
導してあります。
・必要があれば空欄に生活指導・病状説明・アドバイスなどを記入してください。
●資料の最後に、患者さん用の「わたしのカルテ」説明書を入れてあります。
参考にして下さい。
入入院院中中・・通通院院中中 医療チーム
○入院時・入院中に地域連携について
評価
主治医
○退院前に、医療連携を説明
○連携医療機関について相談
○地域連携パスの説明、提示
(○地域連携パスの同意書取得)
○わたしのカルテにアドバイス記入
よろず相談・地域連携課
○連携先医療機関調整、決定
○訪問看護ステーション決定
○連携医療機関に情報提供
○「わたしのカルテ」説明、提示
退退院院後後 地域連携拠点病院・専門病院
○定期の診察・精密検査
○緊急時の対応
地域連携病院・医院(在宅ケア医)
○日常診療、検査、治療、投薬
○わたしのカルテにアドバイス記入
○緊急時の対処指示
患者・家族
○医療機関受診(わたしのカルテ持参)
○診察・検査・治療・投薬内容の記載
○病状変化時、療養記録に追加記入
○患者さんの状態・思いに変化があれ
ば追加、変更記入
緩和パス在宅医-2-
10

地域連携クリニカルパスを利用される患者様へ
『地域連携クリニカルパス』とは、その疾患に必要な検査や治療が盛り込まれ
ている「治療計画表」のことです。これを活用することで、在宅医と当院とが、
それぞれの役割に沿った、円滑な地域医療連携を目指しています。
《在宅医のメリット》
●特定の疾患だけでなく、患者様の全人的なサポートが受けられます。
●通院時間の短縮や、患者様やご家族のライフスタイルに合わせたスケジュール
の調整が可能です。
●専門的な医療が必要となった際に、当院医師への紹介状作成や検査・診察の
予約等、スムーズに受診できるよう、必要なサポートが得られます。
医療における『地域連携』とは、患者様を中心に地域のかかりつけ
医(在宅医)と当院との情報交換を行い、切れ目のない医療と安全
を提供する仕組みです。
在宅医は
あなたのもうひとりの主治医です
緩和パス在宅医-3-
11

がん地域連携クリニカルパス
緩和ケア地域連携パス(緩和ケアパス)
「がん地域連携クリニカルパス(がんパス)」とは地域の在宅ケア医師と病院の専門医師とが、がん患者
の診療情報を共有できる診療計画書のことです。「がんパス」を上手く活用して、在宅ケア医師と専門医師
が協力してがん患者の診療を行います。
「がんパス」を利用することで、病院での治療内容・日常生活での各種問題などに関して医師の間で情報
をやりとりできるばかりでなく、患者さんご自身も病気の状態や診療計画を理解でき、病状に変化があった
時でも適切に対処ができるなど、安心して診療を受けることができるようになります。
現在稼働中の西濃地域における「がんパス」は、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、肝細胞がん、前立
腺がんの 6つのがんですが、今回、緩和ケアについても連携を図ることになります。
「緩和ケア地域連携パス」として、在宅ケア医師と病院医師との間で連携をして行きます。
1.在宅ケア医師の役割
●日頃の診療は、地域の在宅ケア医師が担当します。がんあるいはその他の持病の診療を担当します。
おもな診療内容を下に記します。
・定期的な診察、血液検査、画像検査など(結果は「がんパス」「わたしのカルテ」に記載します)
・定期的な薬の処方
・痛みや吐き気など各種症状の継続的な診療
・風邪をひいたり、熱が出たときなど、臨時の診療
・病状悪化などにより、病院での診察が必要と判断した時には病院に連絡し、紹介とします
2.病院専門医の役割
●必要に応じ、年に何回か病院に通院していただき、精密検査と診察を行います。
・精密検査としては、血液検査、超音波検査、CT検査、MRI検査などがあり、必要に応じて施行します。
・検査結果は「がんパス」あるいは「わたしのカルテ」内に記載して、在宅ケア医師に連絡します。
・病状が変化したときなどは在宅ケア医師の紹介により、臨時に病院で診察を行ったり、入院治療をしたり
することもあります。(経過を知る上で、紹介状を持参することをお勧めします)
・入院が必要な場合は開放病床(大垣市民病院の場合)を利用することも可能です。在宅ケア医師とよくご
相談ください。
患者
家族
訪問看護
ステーション
病院専門医
看護師
MSW
在宅ケア医
調剤薬局
緩和パス在宅医-4-
わたしの
カルテ
がんパス
12
繰り返しになりますが、病院
スタッフ用と在宅ケア医用
と別に準備しました。

連携中の日常生活について(参考)
1.安静と運動
●過度の運動により過労にならないように注意しましょう。
●しかし、過度の安静は必要ありません。
●毎日 30分ほどのマイペースでの散歩など、心地よい疲労感を感じられる適度な運動を続けて
ゆくことをお勧めします。
2.食事
●胃腸の手術後で特別な注意が必要な方は、医師の指示に従って下さい。
●病気だからといって、特定の食事だけを食べる、あるいは避けるようなかたよった食事は
良くありません。
●穀物を中心に、バランス良く食べるようにしましょう。
●脂肪を取りすぎないように注意してください。
●タンパク質は動物性よりも植物性の方が良いでしょう。
●香辛料や薬味など刺激物の取りすぎには注意してください。
3.アルコール
●アルコールは肝臓で分解されます。
●薬によっては、アルコールの分解に影響を及ぼすこともあり、注意が必要です。
●主治医の先生に飲酒が可能かどうか、確認をしてください。
●「飲んでも大丈夫」と言われても、ほろ酔い加減で済ませ、深酒は避けた方が良いでしょう。
4.入浴
●お風呂に入ることはそれだけで体力を要します。熱い風呂・長風呂は避けてください。
●負担が大きい時には浴室内に椅子を持ち込み、腰掛けてシャワーをかけてもらうなどの工夫も
必要です。
●食後 1時間は入浴を避けた方が良いでしょう。
5.旅行
●旅行が可能かどうか、また可能であっても注意しなければならない点については、主治医の
先生に確認をしてください。
●在宅酸素、在宅での点滴などをしている場合には準備や手続きが必要な場合があります。
●海外旅行をする時には、薬によっては事前に届け出が必要です。ご確認ください。
●無理のないスケジュールをたてることをお勧めします。
緩和パス在宅医-5-
13

「わたしのカルテ」 患者様用説明書
1.連携先の決定
●「わたしのカルテ」を使用したがん診療連携「緩和ケア地域連携パス」が始まります。
日頃かかりつけ医として受診される診療所や病院、医院、利用される調剤薬局、訪問看護ス
テ-ションなどを、主治医・看護師・医療ソーシャルワーカー(MSW)と話し合いながら決
めてゆきます。
2.患者さん・医療者が所有するもの
●患者さんには「診療計画書」と「わたしのカルテ」をお渡しします。
●「わたしのカルテ」は、連携している病院・医院などの医療機関だけでなく、その他の医療
機関(風邪でたまたま受診・歯医者・眼医者など)を利用される時にもご持参下さい。
また、訪問看護ステーションのスタッフとの連携にもご利用ください。
●「わたしのカルテ」の中のプロフィール、緊急時の連絡先、説明書・同意書、共同診療計画
書などの書類のコピ-を、連携している各医療機関で保管しています。
3.「わたしのカルテ」の目的
●「わたしのカルテ」は患者さんの「がん」という病気に対して、手術後の経過、その後の治
療経過(化学療法、放射線療法、内服薬など)、あるいはつらい症状の経過など、治療のす
べての場面で切れ目のない診療を安心して受けて頂くことを目的に作られています。
4.私のカルテの運用方法
●病院医師・看護師・MSWの指示に従って、必要な部分を埋めてください。
●「わたしのプロフィ-ル」に必要事項を記入して下さい。
●「わたしが大切にしていること」には医師や医療スタッフに伝えたいことを記載します。
●患者さんのがんに関する情報は、「患者医療情報」により医師間でやりとりしています。
●「緊急時の対応」には病状に変化があった場合の対応を病院医師・在宅ケア医の指示に従っ
て記載します。また、医療機関連絡先は各医療機関で記入してもらいます。
実際に病状に変化があった場合は、記載の指示に従って下さい。
●「診療計画書」に沿って診療が進められて行きます。指示に従って、各医療機関を受診して
下さい。
●「わたしの療養記録」は、毎日の患者さんの状態をご自身(ご家族)で記載する所です。わ
かる範囲で構いません。また、その他に気になることなどは「その他」の欄に記入して、医
師、看護師などにお伝えください。
・苦痛の強さは(最小の苦痛/最大の苦痛/最大の苦痛の回数)として記入して下さい。
例)痛み:3/7/4回、0/5/2回 など。呼吸困難:0/5/5回 など。
・体重などは毎日測定する必要はなく、無理に測定する必要もありません。できる範囲で。
●医師以外のスタッフからのアドバイスやお薬手帳にも目を通しましょう。
●検査データや画像所見、医師からの説明文書などもカルテ内に挟んでおくと便利です。
★「わたしのカルテ」は患者さんの大切な情報が詰まったカルテです。
紛失しないよう、十分に注意して下さい。
緩和パス在宅医-6- 14
病院スタッフが使用法を説明します。
患者用説明書で、主旨を理解して頂け
れば幸いです。

わわたたししののカカルルテテ
●「わたしのカルテ」は、あなたの診療情報を管理する大切なノートです。
なくさず保管し、常に新しい情報が確認できるようにしておきましょう。
●「わたしのカルテ」は医療機関における診療記録の代わりをするものでは
ありません。また、個人情報が含まれていますので患者さんご自身で保管
して下さい。
15

わたしのプロフィール
(よみがな)
名 前
( )
住 所 (〒 - )
電話番号:( ) -
生 年 月 日 明・大・昭・平 年 月 日 血液型 ( )Rh(+・-)
病 名
これまでの
病気の経過
アレルギー
のある薬
かかっている
医 療 機 関
診療所: 医師氏名: ℡:
病院: 医師氏名: ℡:
病院: 看護師氏名: ℡:
訪問看護師: 氏名: ℡:
ケアマネージャー氏名: ℡:
[ ]: 氏名: ℡:
緊 急 時 の
連 絡 先
名前 (本人との関係)
℡(自宅) (携帯)
名前 (本人との関係)
℡(自宅) (携帯)
名前 (本人との関係)
℡(自宅) (携帯)
病気・治療の
説明を
して欲しい人
わたしのカルテ -1-
16
病院スタッフの指導で患者・
家族に記載してい頂きます。
それぞれの担当者に記載してもらうと間違いがありません。コミュ
ニケーションも図れます。

わたしが大切にしていること
●治療に関することでご希望やご意見があればお伝え下さい●
私は治療を受ける上で
ということを大切にしています
以下のようなこともご相談していただくことで、治療を進めて行く際に
とても参考になります
例)遠くても設備の整った病院に通う(5/7)
自宅で療養する(8/20) ↑お考えが変わったら二重線で消して下さい
例)仕事に支障がないよ
うに治療を受けたい
明るく楽しく過ごしたい
できるだけ自宅にいたい
●病名・病状・治療方針について、どのように説明してもらいたいですか?●
□具体的にはっきり説明して欲しい
□よくない情報はあまり詳しく知りたくない
□知りたくない
□今は決められない
□その他( )
●もし病状が悪化したら、どこで療養したいですか?●
□往診などで自宅で療養をしたい
□入院したい
□なるべく自宅で療養したいが必要があれば入院したい
□その他( )
●万が一、心肺停止が起こった場合、
心臓マッサージや人工呼吸を希望しますか?●
□希望する
□希望しない
□今は決められない
□その他( )
わたしのカルテ –2- 17

緊急時の対応
●緊急の時にどう対応したらよいか記入しておきましょう●
症状と対応
症状 対応
例)吐き気が強くなったら 在宅ケア医師に相談し、指示を受け病院を受診して下
さい
医療機関連絡先
病院・在宅ケア医師・訪看 連絡先(電話番号) □医院・□クリニック
□( ) ℡
□医院・□クリニック
□( ) ℡
□医院・□クリニック
□( ) ℡
□医院・□クリニック
□( ) ℡
□医院・□クリニック
□( ) ℡
訪問看護ステーション ℡
大垣市民病院 科 ℡ 0584-81-3341
担当科外来あるいは、救急外来へ連絡し相談を
わたしのカルテ –3- 18

わたしの療養記録
平成 22 年 7 月 No 1 .
症状 日 1~7 日 8日 日 日 日 日 日
痛みの部位 痛みの程強さ:痛み無しを 0、考えられる最高の痛みを 10 として 0~10 の数字で表現
(1日の最小/最大/最大の回数)で記載して下さい
■右肩 2/8/6回 4/9/10 回
■腰痛 3/7/6回 7/10/10 回
□
□
□
その他の症状 苦痛無しを 0、考えられる最悪の苦痛を 10 として 0~10 の数字で強さを表現
(1日の最小/最大/最大の回数)で記載して下さい
□呼吸困難
■嘔気・嘔吐 0/5/3回 頓服の痛 み止めで
□ 3/7/10 回
□
□
□
日常生活 食欲・睡眠は不:不良、中:まずまず、良にて表現:○を打つ・排便は回数で表現
食欲 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良
睡眠 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良
排便 0~2 回 0 回 回 回 回 回 回
体重 45Kg 45Kg Kg Kg Kg Kg Kg
薬の服用 特に医療用麻薬の服薬状況を記入して下さい。できていれば○、できなければ×で
■鎮痛剤 ○ △
■痛い時の薬 △ ○
□
□
□
□
その他
どんなことでも自由に記載してください。
痛み止めで嘔気が強く
食欲がない。時に吐く
こともある。辛い。
痛みひどく、痛み止めで
嘔気・嘔吐が強い。
□今ある症状にチェックをしてください。他に症状があればチェックをして症状を記入してください。
医師・看護師からのアドバイス:嘔気は 2週間ほどで落ち着いてくるはずです。吐き気止めを出しますので
1日 3回内服して経過を診て下さい。睡眠薬も出しておきます。7/8症状がひどいので一時点滴で経過観察
わたしのカルテ 療養
19
数日分を一枠に書いても良いで
すし、1 日分を 2 枠使って記載し
ても構いません。色々な使い方を
してみて下さい。
医師・看護師からアドバイスがあ
れば、記載してもらいます。

わたしの療養記録
平成 年 月 No .
症状 日 日 日 日 日 日 日 日
痛みの部位 痛みの程強さ:痛み無しを 0、考えられる最高の痛みを 10 として 0~10 の数字で表現
(1日の最小/最大/最大の回数)で記載して下さい
□
□
□
□
□
その他の症状 苦痛無しを 0、考えられる最悪の苦痛を 10 として 0~10 の数字で強さを表現
(1日の最小/最大/最大の回数)で記載して下さい
□呼吸困難
□嘔気・嘔吐
□
□
□
□
日常生活 食欲・睡眠は不:不良、中:まずまず、良にて表現:○を打つ・排便は回数で表現
食欲 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良
睡眠 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良
排便 回 回 回 回 回 回 回
体重 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
薬の服用 特に医療用麻薬の服薬状況を記入して下さい。できていれば○、できなければ×で
□鎮痛剤
□痛い時の薬
□
□
□
□
その他
どんなことでも自由に記載してください。
□今ある症状にチェックをしてください。他に症状があればチェックをして症状を記入してください。
医師・看護師からのアドバイス:
わたしのカルテ 療養 20

わたしの療養記録
平成 年 月 No .
症状 日 日 日 日 日 日 日 日
痛みの部位 痛みの程強さ:痛み無しを 0、考えられる最高の痛みを 10 として 0~10 の数字で表現
(1日の最小/最大/最大の回数)で記載して下さい
□
□
□
□
□
その他の症状 苦痛無しを 0、考えられる最悪の苦痛を 10 として 0~10 の数字で強さを表現
(1日の最小/最大/最大の回数)で記載して下さい
□呼吸困難
□嘔気・嘔吐
□
□
□
□
日常生活 食欲・睡眠は不:不良、中:まずまず、良にて表現:○を打つ・排便は回数で表現
食欲 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良
睡眠 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良
排便 回 回 回 回 回 回 回
体重 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
薬の服用 特に医療用麻薬の服薬状況を記入して下さい。できていれば○、できなければ×で
□鎮痛剤
□痛い時の薬
□
□
□
□
その他
どんなことでも自由に記載してください。
□今ある症状にチェックをしてください。他に症状があればチェックをして症状を記入してください。
医師・看護師からのアドバイス:
わたしのカルテ 療養
21

わたしの療養記録
平成 年 月 No .
症状 日 日 日 日 日 日 日 日
痛みの部位 痛みの程強さ:痛み無しを 0、考えられる最高の痛みを 10 として 0~10 の数字で表現
(1日の最小/最大/最大の回数)で記載して下さい
□
□
□
□
□
その他の症状 苦痛無しを 0、考えられる最悪の苦痛を 10 として 0~10 の数字で強さを表現
(1日の最小/最大/最大の回数)で記載して下さい
□呼吸困難
□嘔気・嘔吐
□
□
□
□
日常生活 食欲・睡眠は不:不良、中:まずまず、良にて表現:○を打つ・排便は回数で表現
食欲 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良
睡眠 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良 不・中・良
排便 回 回 回 回 回 回 回
体重 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
薬の服用 特に医療用麻薬の服薬状況を記入して下さい。できていれば○、できなければ×で
□鎮痛剤
□痛い時の薬
□
□
□
□
その他
どんなことでも自由に記載してください。
□今ある症状にチェックをしてください。他に症状があればチェックをして症状を記入してください。
医師・看護師からのアドバイス:
わたしのカルテ 療養 22

わたしの療養ファイル
●大切なデータ・面談書などはここに挟んでおきましょう●
●紹介状や医師から説明を受けた用紙・診療録のコピーなど
●血液検査の結果・レントゲン写真のコピーなど
●退院時の生活指導
●服用しているクスリのリスト など
わたしのカルテ ファイル 23
地域連携クリニカルパスの説明・緩和ケア地域
連携パス・連携中の日常生活について・わたしの
カルテの記載に関する患者説明書の 4 点を挟ん
であります。
必要があれば、面談書のコピー・検査データのコ
ピー、画像の説明書などを加えて挟んで下さい。

24

地域連携クリニカルパスを利用される患者様へ
『地域連携クリニカルパス』とは、その疾患に必要な検査や治療が盛り込まれて
いる「治療計画表」のことです。これを活用することで、在宅医と当院とが、そ
れぞれの役割に沿った、円滑な地域医療連携を目指しています。
《在宅医のメリット》
●特定の疾患だけでなく、患者様の全人的なサポートが受けられます。
●通院時間の短縮や、患者様やご家族のライフスタイルに合わせたスケジュール
の調整が可能です。
●専門的な医療が必要となった際に、当院医師への紹介状作成や検査・診察の
予約等、スムーズに受診できるよう、必要なサポートが得られます。
医療における『地域連携』とは、患者様を中心に地域のかかりつけ
医(在宅医)と当院との情報交換を行い、切れ目のない医療と安全
を提供する仕組みです。
在宅医は
あなたのもうひとりの主治医です
緩和パス患者-1-
25

がん地域連携クリニカルパス
緩和ケア地域連携パス(緩和ケアパス)
「がん地域連携クリニカルパス(がんパス)」とは地域の在宅ケア医師と病院の専門医師とが、がん患者の
診療情報を共有できる診療計画書のことです。「がんパス」を上手く活用して、在宅ケア医師と専門医師が
協力してがん患者の診療を行います。
「がんパス」を利用することで、病院での治療内容・日常生活での各種問題などに関して医師の間で情報
をやりとりできるばかりでなく、患者さんご自身も病気の状態や診療計画を理解でき、病状に変化があった
時でも適切に対処ができるなど、安心して診療を受けることができるようになります。
現在稼働中の西濃地域における「がんパス」は、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、肝細胞がん、前立
腺がんの 6つのがんですが、今回、緩和ケアについても連携を図ることになります。
「緩和ケア地域連携パス」として、在宅ケア医師と病院医師との間で連携をして行きます。
1.在宅ケア医師の役割
●日頃の診療は、地域の在宅ケア医師が担当します。がんあるいはその他の持病の診療を担当します。
おもな診療内容を下に記します。
・定期的な診察、血液検査、画像検査など(結果は「がんパス」「わたしのカルテ」に記載します)
・定期的な薬の処方
・痛みや吐き気など各種症状の継続的な診療
・風邪をひいたり、熱が出たときなど、臨時の診療
・病状悪化などにより、病院での診察が必要と判断した時には病院に連絡し、紹介とします
2.病院専門医の役割
●必要に応じ、年に何回か病院に通院していただき、精密検査と診察を行います。
・精密検査としては、血液検査、超音波検査、CT検査、MRI検査などがあり、必要に応じて施行します。
・検査結果は「がんパス」あるいは「わたしのカルテ」内に記載して、在宅ケア医師に連絡します。
・病状が変化したときなどは在宅ケア医師の紹介により、臨時に病院で診察を行ったり、入院治療をしたり
することもあります。(経過を知る上で、紹介状を持参することをお勧めします)
・入院が必要な場合は開放病床(大垣市民病院の場合)を利用することも可能です。在宅ケア医師とよくご
相談ください。
患者
家族
訪問看護
ステーション
病院専門医
看護師
MSW
在宅ケア医
調剤薬局
緩和パス患者-2-
わたしの
カルテ
がんパス
26

連携中の日常生活について(参考)
1.安静と運動
●過度の運動により過労にならないように注意しましょう。
●しかし、過度の安静は必要ありません。
●毎日 30分ほどのマイペースでの散歩など、心地よい疲労感を感じられる適度な運動を続けて
ゆくことをお勧めします。
2.食事
●胃腸の手術後で特別な注意が必要な方は、医師の指示に従って下さい。
●病気だからといって、特定の食事だけを食べる、あるいは避けるようなかたよった食事は
良くありません。
●穀物を中心に、バランス良く食べるようにしましょう。
●脂肪を取りすぎないように注意してください。
●タンパク質は動物性よりも植物性の方が良いでしょう。
●香辛料や薬味など刺激物の取りすぎには注意してください。
3.アルコール
●アルコールは肝臓で分解されます。
●薬によっては、アルコールの分解に影響を及ぼすこともあり、注意が必要です。
●主治医の先生に飲酒が可能かどうか、確認をしてください。
●「飲んでも大丈夫」と言われても、ほろ酔い加減で済ませ、深酒は避けた方が良いでしょう。
4.入浴
●お風呂に入ることはそれだけで体力を要します。熱い風呂・長風呂は避けてください。
●負担が大きい時には浴室内に椅子を持ち込み、腰掛けてシャワーをかけてもらうなどの工夫も
必要です。
●食後 1時間は入浴を避けた方が良いでしょう。
5.旅行
●旅行が可能かどうか、また可能であっても注意しなければならない点については、主治医の
先生に確認をしてください。
●在宅酸素、在宅での点滴などをしている場合には準備や手続きが必要な場合があります。
●海外旅行をする時には、薬によっては事前に届け出が必要です。ご確認ください。
●無理のないスケジュールをたてることをお勧めします。
緩和パス患者-3-
27

「わたしのカルテ」 患者様用説明書
1.連携先の決定
●「わたしのカルテ」を使用したがん診療連携「緩和ケア地域連携パス」が始まります。
日頃かかりつけ医として受診される診療所や病院、医院、利用される調剤薬局、訪問看護ス
テ-ションなどを、主治医・看護師・医療ソーシャルワーカー(MSW)と話し合いながら決
めてゆきます。
2.患者さん・医療者が所有するもの
●患者さんには「診療計画書」と「わたしのカルテ」をお渡しします。
●「わたしのカルテ」は、連携している病院・医院などの医療機関だけでなく、その他の医療
機関(風邪でたまたま受診・歯医者・眼医者など)を利用される時にもご持参下さい。
また、訪問看護ステーションのスタッフとの連携にもご利用ください。
●「わたしのカルテ」の中のプロフィール、緊急時の連絡先、説明書・同意書、共同診療計画
書などの書類のコピ-を、連携している各医療機関で保管しています。
3.「わたしのカルテ」の目的
●「わたしのカルテ」は患者さんの「がん」という病気に対して、手術後の経過、その後の治
療経過(化学療法、放射線療法、内服薬など)、あるいはつらい症状の経過など、治療のす
べての場面で切れ目のない診療を安心して受けて頂くことを目的に作られています。
4.私のカルテの運用方法
●病院医師・看護師・MSWの指示に従って、必要な部分を埋めてください。
●「わたしのプロフィ-ル」に必要事項を記入して下さい。
●「わたしが大切にしていること」には医師や医療スタッフに伝えたいことを記載します。
●患者さんのがんに関する情報は、「患者医療情報」により医師間でやりとりしています。
●「緊急時の対応」には病状に変化があった場合の対応を病院医師・在宅ケア医の指示に従っ
て記載します。また、医療機関連絡先は各医療機関で記入してもらいます。
実際に病状に変化があった場合は、記載の指示に従って下さい。
●「診療計画書」に沿って診療が進められて行きます。指示に従って、各医療機関を受診して
下さい。
●「わたしの療養記録」は、毎日の患者さんの状態をご自身(ご家族)で記載する所です。わ
かる範囲で構いません。また、その他に気になることなどは「その他」の欄に記入して、医
師、看護師などにお伝えください。
・苦痛の強さは(最小の苦痛/最大の苦痛/最大の苦痛の回数)として記入して下さい。
例)痛み:3/7/4回、0/5/2回 など。呼吸困難:0/5/5回 など。
・体重などは毎日測定する必要はなく、無理に測定する必要もありません。できる範囲で。
●医師以外のスタッフからのアドバイスやお薬手帳にも目を通しましょう。
●検査データや画像所見、医師からの説明文書などもカルテ内に挟んでおくと便利です。
★「わたしのカルテ」は患者さんの大切な情報が詰まったカルテです。
紛失しないよう、十分に注意して下さい。
緩和パス患者-4- 28

29

この地域は緩和ケアの普及に努めています
http://www.gankanwa.jp
大垣市民病院緩和ケアチーム
わたしのカルテ OPTIM
30