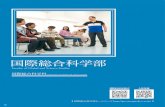理学部物理学物理学科科とはとは 員と学生とが研究及び勉学に励んでいます。首都大学東京の理学 …€¦ · 理学部物理学科は教員数が比較的多いことを生かして、
県立大、転換のときを振り返る - u-kochi.ac.jp ·...
Transcript of 県立大、転換のときを振り返る - u-kochi.ac.jp ·...


平成10年、池キャンパスの完成とともに、学部学科を大幅に改組。家政学部と文学部の2学部から、生活科学部、文化学部、看護学部、社会福祉学部に広がりました。また、大学院として看護学研究科を設置。さらに平成13年には大学院に人間生活学研究科と健康生活科学研究科が加わりました。この大きな転換期に、大学では何が起こり、何を目指したのか。当時の様子を2人の副学長に聞きました。
地域に開かれた大学として社会の評価を受ける覚悟
―平成10年の改組を新聞が「改学」と表現していたのが、生まれ変わった大学にぴったりだったと記憶しています。改学をどのように振り返りますか?
野嶋 池キャンパスには、家政学部看護学科から学部に昇格した看護学部と、新たに創設した社会福祉学部が入りました。また、永国寺キャンパスでも文学部は文化学部に、家政学部は生活科学部に改組しました。 看護学部の独立は、長年の悲願でも
ありました。高知県看護協会をはじめとする地域の医療職、看護職の人たちにバックアップしていただき、地域の方々にもご支援いただいたからこそ実現できました。社会福祉学部も同じで、新しい学部というのは、地域の課題に対応するものであるとともに、地域の方々の支援があって初めて誕生できるものです。2学部とも、地域に開かれた大学として、社会からきちんと評価をいただくという決意を強く打ち出していたと思います。荻沼 改学によって廃部になったのが、保育短期大学部(保短)です。当時、私は保短の教員をしていました。保短は高知県出身の学生が多く、県内高校生の進路の受け皿のひとつとして、幼児教育を目指す人たちが多く入ってきました。学生は1学年50名程
度、教員も13~14名で、アットホームな雰囲気でしたね。 改学では、保短の機能の一部である“福祉”を大学に移行しました。それを土台にでき上がったのが社会福祉学部です。高齢化社会を目前に、高知県の将来のことを考えて、社会福祉学部はつくられました。
教育環境が充実した反面2キャンパスゆえの不便も
―池キャンパスは新しい施設、新しい学部で、その運営にはいろいろと苦労があったのではないですか?野嶋 看護学科が永国寺にあった当時は、実習室が2つしかありませんでした。それが池では複数の実習室ができるなど、大きく教育環境が充実しました。池で校舎の建設が進められるときは、私たちも正式な図面とまではいきませんが、こういう教室にしてほしいと絵を描いたものです。でも素人ですから、入口のない部屋を描いてしまったり…(笑)。 ただ、良さがある一方、2キャ
ンパスに分かれての不便さもありました。当時の学生には不自由をかけたな、という思いがあります。荻沼 当時、教養課程は永国寺キャンパスで行っていましたから、社会福祉学部と看護学部の学生は教養課程の講義を受けるため永国寺まで通わなければいけませんでした。池と永国寺を結ぶバスを出したこともありましたよね。
変わり続けながら大切なものを受け継ぐ
―大学院設立も、同時期に行われましたね。野嶋 まず、修士課程として平成10年に看護学研究科が新設されました。さらに平成13年には人間生活学研究科と、複合領域型の博士後期課程として健康生活科学研究科が増設されました。当時、
看護学の教員不足が全国的に叫ばれていました。時代の要請に応えるためにも、一日も早く博士の学位を取得できる課程をつくりたかったんです。荻沼 健康生活科学研究科には、看護学領域、生活科学領域、社会福祉学領域があり、いろいろな分野の修士課程を修了した学生が入学してきました。複合領域型の学際的な博士後期課程をつくったという点で非常にユニークだったと思います。 ただ、たとえば看護の博士を目指す学
生に対して、専門が違う私が指導に入ることもあるわけで、最初は戸惑いもありました。
―常に新しいものに取り組もうという大学の姿勢が、過去の歴史から浮かび上がります。野嶋 新しいものをつくりだすだけでなく、高知女子大学時代からの伝統をどう踏襲していくのかということも大切です。それは、文化学部で言えば少人数制であり、看護学部で言えば学生の主体的に学ぶ教育環境を整えるということ。今後も本学が発展していくうえで改組や改革は行われると思いますが、変わりながらも大事なものは失わないようにしていかなければ、と思います。
野嶋 佐由美副学長
高知女子大学家政学部衛生看護学科卒業。明治学院大学大学院にて修士課程を、カリフォルニア大学サンフランシスコ校で博士課程を修了。医療法人精華園で臨床保健婦として勤務の後、昭和59年高知女子大学に着任。平成23年より副学長。看護研究、看護理論などが専門。看護学博士。
高知県立大学 創基70周年記念特集
県立大、転換のときを振り返る高知県立大学 副学長
野嶋 佐由美の じ ま さ ゆ み
池キャンパス

平成10年、池キャンパスの完成とともに、学部学科を大幅に改組。家政学部と文学部の2学部から、生活科学部、文化学部、看護学部、社会福祉学部に広がりました。また、大学院として看護学研究科を設置。さらに平成13年には大学院に人間生活学研究科と健康生活科学研究科が加わりました。この大きな転換期に、大学では何が起こり、何を目指したのか。当時の様子を2人の副学長に聞きました。
地域に開かれた大学として社会の評価を受ける覚悟
―平成10年の改組を新聞が「改学」と表現していたのが、生まれ変わった大学にぴったりだったと記憶しています。改学をどのように振り返りますか?
野嶋 池キャンパスには、家政学部看護学科から学部に昇格した看護学部と、新たに創設した社会福祉学部が入りました。また、永国寺キャンパスでも文学部は文化学部に、家政学部は生活科学部に改組しました。 看護学部の独立は、長年の悲願でも
ありました。高知県看護協会をはじめとする地域の医療職、看護職の人たちにバックアップしていただき、地域の方々にもご支援いただいたからこそ実現できました。社会福祉学部も同じで、新しい学部というのは、地域の課題に対応するものであるとともに、地域の方々の支援があって初めて誕生できるものです。2学部とも、地域に開かれた大学として、社会からきちんと評価をいただくという決意を強く打ち出していたと思います。荻沼 改学によって廃部になったのが、保育短期大学部(保短)です。当時、私は保短の教員をしていました。保短は高知県出身の学生が多く、県内高校生の進路の受け皿のひとつとして、幼児教育を目指す人たちが多く入ってきました。学生は1学年50名程
度、教員も13~14名で、アットホームな雰囲気でしたね。 改学では、保短の機能の一部である“福祉”を大学に移行しました。それを土台にでき上がったのが社会福祉学部です。高齢化社会を目前に、高知県の将来のことを考えて、社会福祉学部はつくられました。
教育環境が充実した反面2キャンパスゆえの不便も
―池キャンパスは新しい施設、新しい学部で、その運営にはいろいろと苦労があったのではないですか?野嶋 看護学科が永国寺にあった当時は、実習室が2つしかありませんでした。それが池では複数の実習室ができるなど、大きく教育環境が充実しました。池で校舎の建設が進められるときは、私たちも正式な図面とまではいきませんが、こういう教室にしてほしいと絵を描いたものです。でも素人ですから、入口のない部屋を描いてしまったり…(笑)。 ただ、良さがある一方、2キャ
ンパスに分かれての不便さもありました。当時の学生には不自由をかけたな、という思いがあります。荻沼 当時、教養課程は永国寺キャンパスで行っていましたから、社会福祉学部と看護学部の学生は教養課程の講義を受けるため永国寺まで通わなければいけませんでした。池と永国寺を結ぶバスを出したこともありましたよね。
変わり続けながら大切なものを受け継ぐ
―大学院設立も、同時期に行われましたね。野嶋 まず、修士課程として平成10年に看護学研究科が新設されました。さらに平成13年には人間生活学研究科と、複合領域型の博士後期課程として健康生活科学研究科が増設されました。当時、
看護学の教員不足が全国的に叫ばれていました。時代の要請に応えるためにも、一日も早く博士の学位を取得できる課程をつくりたかったんです。荻沼 健康生活科学研究科には、看護学領域、生活科学領域、社会福祉学領域があり、いろいろな分野の修士課程を修了した学生が入学してきました。複合領域型の学際的な博士後期課程をつくったという点で非常にユニークだったと思います。 ただ、たとえば看護の博士を目指す学
生に対して、専門が違う私が指導に入ることもあるわけで、最初は戸惑いもありました。
―常に新しいものに取り組もうという大学の姿勢が、過去の歴史から浮かび上がります。野嶋 新しいものをつくりだすだけでなく、高知女子大学時代からの伝統をどう踏襲していくのかということも大切です。それは、文化学部で言えば少人数制であり、看護学部で言えば学生の主体的に学ぶ教育環境を整えるということ。今後も本学が発展していくうえで改組や改革は行われると思いますが、変わりながらも大事なものは失わないようにしていかなければ、と思います。
荻沼 一男副学長
広島大学大学院理学研究科植物学専攻博士課程、退学。広島大学助手を経て、昭和60年より高知女子大学保育短期大学部に勤務。平成10年、高知女子大学に着任。平成23年より副学長。専門は植物細胞分類学。理学博士。
創基70周年記念特集
県立大、転換のときを振り返る高知県立大学 副学長
荻沼 一男か ず おお ぎ ぬ ま

社会福祉学部地域とつながる大学の先駆けとして
高知県立大学創基70周年「振り返り記」
平成10年、池キャンパスに誕生した社会福祉学部。高知県を取り巻く時代の要請によって生まれた学部として、今日までの歩みを振り返りました。
日本一小さい学部?だからこその機動力 長澤 社会福祉学部の歴史を振り返るうえで、創設期、確立期、拡充期の3期に分けることができると思いますが、まずは、開設準備から完成年度の平成13年度までの創設期を振り返りたいと思います。
川﨑 学部開設の3年ほど前から会議が何度も開かれ、夜遅くまで議論を重ねたものです。私はカリキュラムに応じた施設、障害のある人に対する配慮、地域への講座や地域の社会福祉従事者との共同研究などの充実を図るべく施設整備を担当しました。新しい学部を創設するのは非常に大変なことだという印象が強く残っています。 また、初年度で思い出すのは、リカレント教育講座です。これは高知県内で社会福祉に従事する方たちを対象にしたもので、平成10年9月にスタートしました。教員や学生も受講者と一緒に学ぶスタイルで、現場で仕事をしている人にとっては大学で普段とは違う雰囲気で学べ、われわれ教員や学生にとっては、現場からのさまざまな刺激を受けることができ、双方向で学べる非常に良い取り組みでした。
宮上 社会福祉学部では、当初から先駆けて「地域」というキーワードを掲げていろいろな取り組みを行いました。リカレント教育講座も地域の福祉職の方たちの専門性を高める学びの機会として設置しました。また、「池地域に祭りがあったらいいね」ということで、教員が高知県に事業提案をして、「三里まつり」が実現しました。平成11年から池キャンパスを会場にして始まり、学生が積極的に参加し、地域の方たちと大学がつながる良い機会になったのではないかと思います。これは形は変えつつも、今に引き継がれています。 社会福祉学部は、社会福祉という分野の教育に高知県内の大学で初めて取り組んだわけで、ゼロからのスタートでした。初年度の学生は30名、教員も13名という小さな学部で、日本で一番小さいのではないかとみんなで話したものです(笑)。しかし、小さいからこそ機動力があって、新たな事業にスピーディーに取り組むまとまりの良さがありました。さらに人手がないからこそ、学生の力を借りて一緒にやりましょう、という雰囲気が生まれました。長澤 面接を重視した入試というのも、初年度から始められたものですよね。宮上 そうでしたね。社会福祉を志向
する意識の高い学生を選抜するためには、面接をちゃんとしようという方針で、どのような方法で面接をするのか、何度も議論をしました。面接を重視するという方針は、当時としてはある意味冒険でしたが、受験生全員に面接をして合否を決めるという形を初年度から実施し、いまも続いています。川﨑 おかげで、1期生から社会福祉について感性の豊かな学生が集まりましたし、それは伝統的にいまも続いていると思います。他者に対する優しさや感受性を持った学生たちの力は、これからの社会で一層重要になってくるのではないでしょうか。
学生の主体性が活かされた学び 長澤 第1期生が卒業した次の年、平成14年度以降は、学部の体制が確立された時期だと考えますが、いかがですか?
宮上 創設当時から続けてきたものが充実し、確立してきた時期だと思います。たとえば実習のやり方、ゼミや卒論の指導、国家試験に対する取り組みなどがいい方向で固まってきた頃です。
長澤 国家試験対策といえば、「国試合宿」ですね。宮上 国試合宿は3期生が4年生のときにはじまりました。学生が企画し、場所を探し、仲間に呼び掛けて行う2泊3日の勉強合宿です。実は合宿以前の国家試験の合格率は他の大学と同じレベルだったのですが、合宿をした年に合格率が倍増しました。翌年には「国試合宿に参加すると合格するみたいだよ」と評判になって、いまも続いています。合宿だけで合格できるわけではありませんが、みんなで勉強する場を共有することで、国家試験に向けた心構えがより強くなる絶好の機会なんです。
長澤 ゼミや卒論の指導はどうですか?川﨑先生は、毎年ゼミ生が多かったですね。川﨑 ゼミで学び、卒論を書くときに、社会福祉学部では構想発表、中間発表、最終発表と3回行います。学生たちは本当にまじめに取り組んでいました。西内 卒論発表を3回するというルールによって、後輩も先輩の発表を見ることができ、「ゼミでの学び=卒論として、まとめなければならない」という意識が、学生たちに定着したように思います。宮上 卒論には文献研究や歴史研究もあるのですが、いまは現場に調査に行って聞き取り調査などを行うことにより、関心のある問題を一層深く研究することがゼミを通じてできているように感じています。西内 学生は1年生の頃から実習で地
域に出かけて活動していますし、ボランティアに参加する人も多く、地域活動に慣れていますよね。卒論も、文献を読んでまとめるだけでなく、調査に行くという学生が多いです。長澤 ボランティアの取りまとめサークルがあるほどで、窓口として様々な地域や施設から依頼を受けて学生につなげたり、他大学の学生と連携したりしています。学生が主体的にボランティア活動に取り組んでいるのも、社会福祉学部の特徴ですね。
地域社会の財産となる社会福祉専門職を養成 長澤 平成22年度から現在に至るまでを拡充期と位置付けました。この期間は、学部の定員の増員、介護福祉士養成課程の導入、男女共学化とさまざまな変化がありました。この時期をどのようにとらえていますか。
宮上 実は、基本的な雰囲気が大きく変わったとは思っていません。学生数が倍になって、にぎやかになったとは感じますが(笑)。「人に対してやさしく、主体性を持っている」といった学生の気質はあまり変わっていない気がします。良い伝統は残しつつ、パワーが増したと感じます。男子学生が増えたことで、それまでの女子大にはなかった多様なパワーが生まれたのでしょう。西内 カリキュラムは大きく変わりました。それまでは社会福祉士と精神保健福祉士、教職の3つの資格を軸にしていましたが、定員70名に増員の時に、高齢化の進む高知県の現状等を考え、介護福祉士の導入に踏み切りました。これによって、社会福祉士を目指す「社会福祉コース」と、精神保健福祉士を目指す「精神・社会福祉コース」、介護福祉士を目指す「介護・社会福祉コース」の3コースが整備され、より専門職として地域で活躍する人材育成の色合いが強くなったと思います。宮上 学部の基本は、社会福祉に置いていますから、介護福祉士や精神保健福祉士を目指す学生は、合わせて社会福祉士の資格取得も目指します。2つの資格取得を目指す学生は大変だと思うのですが、意欲の高い学生が多いですね。長澤 他の社会福祉系の大学は入学時から、社会福祉士、介護福祉士とコース
分けしているところが多いようですが、本学は社会福祉士をベースの資格にして、ゼミも3コースの学生が混在しています。おかげで学生の多様性が相互に作用して、良い学びの環境ができていると思います。
長澤 最後に宮上先生、今後のビジョンを教えてください。
宮上 定員が70名になって、卒業生もどんどん増えていきます。これら卒業生に対する支援や大学とのつながりを形にするため、卒業生が対象のリカレント研究会を組織したいと考えています。また県内高校生や地域の皆さんに、社会福祉の仕事や職種について、積極的に発信していきたいと思っています。 いま、大学全体が地域に出ようとしていますが、社会福祉学部は創設当時から地域と関わりを持ち続けてきました。その積み重ねを活かしながら、これからも社会福祉専門職の養成と地域とつながる研究を続けていきたいと思います。
Vol.2
西内 章社会福祉学部准教授専門分野・ソーシャルワーク、高齢者福祉平成15年着任
にしうち あきら
川﨑 育郎高知県立大学名誉教授 専門分野・臨床心理学平成10年着任
かわさき いくろう
宮上 多加子社会福祉学部長、教授専門分野・介護福祉学平成10年着任
みやうえ た か こ
西日本の公立大学で唯一、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の3福祉国家資格に対応。人々のより豊かな生活の実現に、主体的に対応できる質の高い社会福祉専門職を養成します。
社会福祉学部

日本一小さい学部?だからこその機動力 長澤 社会福祉学部の歴史を振り返るうえで、創設期、確立期、拡充期の3期に分けることができると思いますが、まずは、開設準備から完成年度の平成13年度までの創設期を振り返りたいと思います。
川﨑 学部開設の3年ほど前から会議が何度も開かれ、夜遅くまで議論を重ねたものです。私はカリキュラムに応じた施設、障害のある人に対する配慮、地域への講座や地域の社会福祉従事者との共同研究などの充実を図るべく施設整備を担当しました。新しい学部を創設するのは非常に大変なことだという印象が強く残っています。 また、初年度で思い出すのは、リカレント教育講座です。これは高知県内で社会福祉に従事する方たちを対象にしたもので、平成10年9月にスタートしました。教員や学生も受講者と一緒に学ぶスタイルで、現場で仕事をしている人にとっては大学で普段とは違う雰囲気で学べ、われわれ教員や学生にとっては、現場からのさまざまな刺激を受けることができ、双方向で学べる非常に良い取り組みでした。
宮上 社会福祉学部では、当初から先駆けて「地域」というキーワードを掲げていろいろな取り組みを行いました。リカレント教育講座も地域の福祉職の方たちの専門性を高める学びの機会として設置しました。また、「池地域に祭りがあったらいいね」ということで、教員が高知県に事業提案をして、「三里まつり」が実現しました。平成11年から池キャンパスを会場にして始まり、学生が積極的に参加し、地域の方たちと大学がつながる良い機会になったのではないかと思います。これは形は変えつつも、今に引き継がれています。 社会福祉学部は、社会福祉という分野の教育に高知県内の大学で初めて取り組んだわけで、ゼロからのスタートでした。初年度の学生は30名、教員も13名という小さな学部で、日本で一番小さいのではないかとみんなで話したものです(笑)。しかし、小さいからこそ機動力があって、新たな事業にスピーディーに取り組むまとまりの良さがありました。さらに人手がないからこそ、学生の力を借りて一緒にやりましょう、という雰囲気が生まれました。長澤 面接を重視した入試というのも、初年度から始められたものですよね。宮上 そうでしたね。社会福祉を志向
する意識の高い学生を選抜するためには、面接をちゃんとしようという方針で、どのような方法で面接をするのか、何度も議論をしました。面接を重視するという方針は、当時としてはある意味冒険でしたが、受験生全員に面接をして合否を決めるという形を初年度から実施し、いまも続いています。川﨑 おかげで、1期生から社会福祉について感性の豊かな学生が集まりましたし、それは伝統的にいまも続いていると思います。他者に対する優しさや感受性を持った学生たちの力は、これからの社会で一層重要になってくるのではないでしょうか。
学生の主体性が活かされた学び 長澤 第1期生が卒業した次の年、平成14年度以降は、学部の体制が確立された時期だと考えますが、いかがですか?
宮上 創設当時から続けてきたものが充実し、確立してきた時期だと思います。たとえば実習のやり方、ゼミや卒論の指導、国家試験に対する取り組みなどがいい方向で固まってきた頃です。
長澤 国家試験対策といえば、「国試合宿」ですね。宮上 国試合宿は3期生が4年生のときにはじまりました。学生が企画し、場所を探し、仲間に呼び掛けて行う2泊3日の勉強合宿です。実は合宿以前の国家試験の合格率は他の大学と同じレベルだったのですが、合宿をした年に合格率が倍増しました。翌年には「国試合宿に参加すると合格するみたいだよ」と評判になって、いまも続いています。合宿だけで合格できるわけではありませんが、みんなで勉強する場を共有することで、国家試験に向けた心構えがより強くなる絶好の機会なんです。
長澤 ゼミや卒論の指導はどうですか?川﨑先生は、毎年ゼミ生が多かったですね。川﨑 ゼミで学び、卒論を書くときに、社会福祉学部では構想発表、中間発表、最終発表と3回行います。学生たちは本当にまじめに取り組んでいました。西内 卒論発表を3回するというルールによって、後輩も先輩の発表を見ることができ、「ゼミでの学び=卒論として、まとめなければならない」という意識が、学生たちに定着したように思います。宮上 卒論には文献研究や歴史研究もあるのですが、いまは現場に調査に行って聞き取り調査などを行うことにより、関心のある問題を一層深く研究することがゼミを通じてできているように感じています。西内 学生は1年生の頃から実習で地
域に出かけて活動していますし、ボランティアに参加する人も多く、地域活動に慣れていますよね。卒論も、文献を読んでまとめるだけでなく、調査に行くという学生が多いです。長澤 ボランティアの取りまとめサークルがあるほどで、窓口として様々な地域や施設から依頼を受けて学生につなげたり、他大学の学生と連携したりしています。学生が主体的にボランティア活動に取り組んでいるのも、社会福祉学部の特徴ですね。
地域社会の財産となる社会福祉専門職を養成 長澤 平成22年度から現在に至るまでを拡充期と位置付けました。この期間は、学部の定員の増員、介護福祉士養成課程の導入、男女共学化とさまざまな変化がありました。この時期をどのようにとらえていますか。
宮上 実は、基本的な雰囲気が大きく変わったとは思っていません。学生数が倍になって、にぎやかになったとは感じますが(笑)。「人に対してやさしく、主体性を持っている」といった学生の気質はあまり変わっていない気がします。良い伝統は残しつつ、パワーが増したと感じます。男子学生が増えたことで、それまでの女子大にはなかった多様なパワーが生まれたのでしょう。西内 カリキュラムは大きく変わりました。それまでは社会福祉士と精神保健福祉士、教職の3つの資格を軸にしていましたが、定員70名に増員の時に、高齢化の進む高知県の現状等を考え、介護福祉士の導入に踏み切りました。これによって、社会福祉士を目指す「社会福祉コース」と、精神保健福祉士を目指す「精神・社会福祉コース」、介護福祉士を目指す「介護・社会福祉コース」の3コースが整備され、より専門職として地域で活躍する人材育成の色合いが強くなったと思います。宮上 学部の基本は、社会福祉に置いていますから、介護福祉士や精神保健福祉士を目指す学生は、合わせて社会福祉士の資格取得も目指します。2つの資格取得を目指す学生は大変だと思うのですが、意欲の高い学生が多いですね。長澤 他の社会福祉系の大学は入学時から、社会福祉士、介護福祉士とコース
分けしているところが多いようですが、本学は社会福祉士をベースの資格にして、ゼミも3コースの学生が混在しています。おかげで学生の多様性が相互に作用して、良い学びの環境ができていると思います。
長澤 最後に宮上先生、今後のビジョンを教えてください。
宮上 定員が70名になって、卒業生もどんどん増えていきます。これら卒業生に対する支援や大学とのつながりを形にするため、卒業生が対象のリカレント研究会を組織したいと考えています。また県内高校生や地域の皆さんに、社会福祉の仕事や職種について、積極的に発信していきたいと思っています。 いま、大学全体が地域に出ようとしていますが、社会福祉学部は創設当時から地域と関わりを持ち続けてきました。その積み重ねを活かしながら、これからも社会福祉専門職の養成と地域とつながる研究を続けていきたいと思います。
平成14年 4月精神保健福祉士受験資格に対応したカリキュラム導入
平成22年 4月定員70名に増員介護福祉士養成課程設置
平成23年 4月高知県公立大学法人に移行高知県立大学に校名変更男女共学
平成10年 4月社会福祉学部社会福祉学科開設 定員30名
社会福祉学部の
歩み hi s t o r y
司会・長澤 紀美子社会福祉学部教授専門分野・国際福祉、女性福祉平成15年着任
ながさわ き み こ









![建築都市工学部 履修ガイド - 九州産業大学 · 建築都市工学部専任教員紹介 [住居・インテリア学科] オフィスアワーとは… 入試部長](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5f72dd06e3015d41c53c92c4/cefef-f-c-cefefc.jpg)