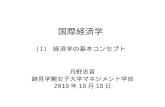SNA編 大阪府経済の概況 3 るところ:成 率(実質/名 )の推移 分かること:経済の足取り、方向感 【 阪府の経済成 率】 平成27年度の経済成
目指すべき経済社会と政策の基本的方向...28 第2章...
Transcript of 目指すべき経済社会と政策の基本的方向...28 第2章...

28
第2章 目指すべき経済社会と政策の基本的方向
前章で見てきたように、2000 年代の日本経済は、企業の生み出す付加価値の低迷、雇用
環境の悪化と労働所得の低下などにより、国内消費が低迷し、デフレが継続する「やせ我慢」
の縮小経済であった。また、円高を含め現状を放置した場合には、財政危機の発生にまで至
るリスクがあることも示された。
このような状況を抜本的に改善していくためには、我が国の経済産業構造全般に立ち返っ
て検討する必要がある。このため、我が国の成長を歴史的に振り返りながら、今後目指すべ
き方向性を検討していく。
1.戦後から現在に至るまでの我が国の成長モデル
まず、戦後復興から高度経済成長期、安定成長期においては、人口増加により国内市場が
拡大していたため、企業戦略としては、販売量、売上でシェアを拡大することにより付加価
値を上げることができた。このため、事業構造は、ピラミッド型(系列)の生産構造による
大量生産が主流となり、農村部から豊富な労働力も投入された。そして、製造業を中心に賃
金が上昇し、男性中心の就業構造の確立、専業主婦世帯の増加へとつながり、「一億総中流」
と呼ばれる分厚い中間層が形成されていった。
その後、バブルが崩壊し経済成長が低迷すると、市場拡大による販売量の増加が見込めな
くなり、90 年代の売上は低迷し、電機産業を中心に系列構造は崩壊していった。そして、
金融危機・銀行再編を通じて、ガバナンス機能も低下していった。こうした中で企業は、雇
用、設備、債務における3つの過剰を克服すべく、人員削減、設備投資抑制、資産売却と債
務返済(バランスシート調整)等を進め、企業体質の改善を図った。
しかし、実態は、賃下げ・値下げ競争への突入であり、非正規雇用と若年層失業が増加し
ていった。また、女性が働きやすい環境整備は進まず、女性就労は伸び悩んだ。この結果、
労働所得の低下、消費低迷は解消されず、デフレは継続し、これらのマイナス要因が負の循
環となり、やせ我慢・縮小経済へと陥ってしまった。
以上見てきたように、我が国は、企業戦略、産業構造、就業構造が相互に連関して、経済
産業構造全体が行き詰まりを迎えていることがわかる。

29
(出所)総務省「国勢調査」、「労働力調査」、「人口推計」、財務省「法人企業統計」、国立社会保障・人
口問題研究所「日本の将来推計人口」、延岡健太郎『価値づくり経営の論理』等を参考に作成
0
10
20
30
40
50
60
19
55
19
65
19
75
19
85
19
95
20
05
'女性就業率:%(
第3次産業
第2次産業
第1次産業
0
50
0
1,0
00
1,5
00
19
60
19
70
19
80
19
90
20
00
20
10
'売上高:兆円( 売上高
3.2
6.7
7.1
0
2
4
6
8 1
99
01
99
52
00
02
00
52
01
0
'1
5~
34歳失業率:%(
若年失業率
'暦年(
0
1
2
3
4
5
6 1
96
01
97
01
98
01
99
02
00
02
01
0
'営業利益率:%(
営業利益率
営業利益率の期間別平均
やせ我慢・縮小経済
バブル崩壊の調整期
人 口 企 業 戦 略 産 業 ・ 事 業 構 造 就 業 構 造
1950
2010
1980
1990
2000
1960
1970
石 油 シ ョ ッ ク
バ ブ ル 崩 壊
リ ー マ ン シ ョ ッ ク ・
金 融 危 機
東 日 本 大 震 災
安定成長
高度経済成長
戦後復興
プ ラ ザ 合 意
販売量
付 加 価 値 率付加価値
販売量を増やすことが付加価
値拡大に直結
•人口増
→市場拡大
•ピラミッド型'系列(の生産構造
による大量生産7.7%
10.4%
5.2%
3.8%
1.5%
0.6%
•売上の低迷→電機を中心に系
列構造の崩壊
•固定費負担→3過剰問題
•金融危機、銀行再編を通じて、
ガバナンス機能が低下
•賃下げ、値下げ競争
'実質円安による競争力の
維持(
↓
•労働所得の低下、消費低迷
↓
•デフレ継続
販売量
付加価値
コストカットによる値下げによって、
利益率を維持。
しかし販売量は伸び悩み。
経 済
金 融 危 機
•成長の限界
→所得の低迷
→パートタイム増加
•非正規雇用の拡大
→スキル蓄積不足
20
.2
26
.0
34
.4
15
20
25
30
35
19
90
19
95
20
00
20
05
20
10
'暦年(
'非正規比率:%(
非正規比率
年代平均
成長率
'実質(
•農村からの低廉な
労働力
•製造業を牽引力に
男性中心の担い手
→専業主婦の増加
不 良 債 権 処 理
付 加 価 値 率
I T 革 命
0 5 10
15
20
25
55
60
65
70
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
'生産年齢人口比率:%(
'高齢化率:%(
高齢化率'右軸(
生産年齢人口比率'左軸(

30
2.目指すべき経済社会ビジョン
これまでの成長戦略は、ともすれば、企業の競争力強化と生産性上昇を追求すれば足りる、
すなわち、企業が生産性の向上を通じ競争力を高め収益を上げれば、労働者にその果実が分
配され、国全体が豊かになるという「成長のトリックルダウン」を前提とした議論であった。
しかし、前項で見てきたように、生産性上昇が、ともすれば分子の付加価値の向上よりは、
分母のコストの削減によって達成された結果、この従来の成長モデル自体が限界を迎え、や
せ我慢・縮小経済を招くこととなってしまった。いわば「日本の成長」と「個人の豊かさ」
が乖離しつつあり、また、経済活動のグローバル化により、「企業の成長」と「日本の成長」
にもずれが生ずる場合がある。
もちろん、今後も、企業の競争力強化と生産性の向上を通じた経済成長は重要な課題であ
る。しかし、これまでの議論と歴史を振り返ると、今後これらは分母のコスト削減よりは分
子の価値創造によって達成されるべきであり、その質的違いを無視して生産性と成長率に係
る数字を伸ばすことだけを目的とした成長戦略、すなわち「成長のための成長戦略」では、
国民一人一人が豊かさを実感できる経済社会を作ることは難しい。
企業と国民が共有することができる新たな成長戦略を打ち出すためには、望ましい企業戦
略や産業構造のあり方、このための方策に加え、望ましい個人の働き方や就業構造のあり方、
このための方策についても一体的に考えることにより、「国家としての成長と個人の豊かさ
の再接合」を図る試みが不可欠である。
こうした「豊かさを実感できる成長」への転換を実現するために、今後目指すべき「経済
社会ビジョン」として、次の2点を掲げる。
<経済成長ビジョン>
・成熟に裏打ちされた日本人の感性や技術力を発揮することで、潜在内需を掘り起こし、
グローバル市場を獲得していく。いわば「成熟を力に」した価値創造経済社会を創出する。
<人を活かす社会ビジョン>
・女性、若者、高齢者、障害者等一人一人が、置かれた環境と能力に応じて、そうした価
値創造に参画し、成長を分配することで、活き活きと働く人々が増える経済を実現する。
すなわち「ワーカー」から「プレーヤー」へ向けた働き方の改革である。
・「ダブルインカム・ツーキッズ」を通じた、世帯所得の増加と尐子化の克服
・高齢者を含めた「全員参加」の推進により、「現役世代に依存する社会」から「全世代で支
え合う社会」へ転換

31
このようなビジョンの実現を通じて、人口減尐の中でも一人あたり国民所得(GNI)を
維持・増大し、成熟した豊かさを実感できる成長を実現する。そして、「全般的な貧困化」
を脱却し、全員参加で「厚みのある中間層」を形成していく。
後述する政策を通じて、新産業を創出し、アジアの市場を獲得するとともに、女性や高齢
者の就労促進を実現した場合(「政策実現ケース」)においては、一人当たりGNIは上昇し、
年収 300~700 万円の中間層が復活する方向に進んでいくことが見込まれる(試算の詳細は
後述)。
政策実現ケースにおける一人当たり実質GNI3・GDP
100
105
110
115
120
125
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
一人当たり実質GNI 一人当たり実質GDP'年度(
'2010年度=100(
政策実現ケースにおける所得(賃金・俸給)分布
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2010年
政策実現ケース
'年間収入階級:万円(
'就業者数:万人(
'注(産業別・性別・職業別の就業者数および一人当たり賃金・俸給より作成。賃金・俸給'雇い主の社会保険料負担等を除く(は雇用者報酬から算出したもの。一人当たり賃金・俸給は、産業別・性別・職業別の平均所得から算出したものであり、個々人の所得から作成したものではない点に留意が必要。また、賃金は雇用者のみのものであり、自営業者等は含まれない。政策実現ケースの実質平均所得は、2010年価格で評価したもの。
平均:388万円
'2010年(
平均:459万円'実質457万円('政策実現ケース(
3 実質GNI=実質GDP+交易利得+所得収支
交易利得=交易条件(輸出物価÷輸入物価)の変化に伴う所得の変化

32
3.政策の基本的方向
前章で見てきたような、貿易赤字から始まるリスクシナリオを回避するためには、現下の
急激な円高による急速な産業空洞化を防止しなければならず、適切なマクロ運営と緊急的な
円高・空洞化対策が不可欠である。
一方で、現在起きていることは空洞化ではなく産業構造の転換であるとの見方もできる。
1970 年代の石油ショック時は重厚長大から軽薄短小への転換に成功した。今回も過度に悲
観的にならず、日本の産業が更に強い国際競争力を持ち、新しい価値を創造していくことが
重要である。
行き詰まり、限界を迎えつつある企業戦略、産業構造、就業構造などの経済社会構造を転
換し、「価値創造経済社会」を実現するための経済産業政策として、次の3つの柱の下で新
たな政策を打ち出していく。
第一の柱
「価値創造」を通じた潜在内需の掘り起こしとグローバル市場獲得
第二の柱
「多様な人的資本」による「価値創造」の実現
第三の柱
急速な産業空洞化を回避し価値創造経済社会への転換を実現する間の時間軸調整
まず第一の柱として、国内に新産業分野を創出し、産業構造の転換を図っていく。具体的
には、国内の潜在需要を掘り起こし新たな内需型産業を拡大するとともに、国際分業の中で、
付加価値で競争できる新しい製品やサービスを生み出し、グローバル需要を取り込んでいく。
そして、グローバルに稼いだ収益を国内に還流する仕組みを整備することで、中小企業の活
性化や安定的な雇用の場の確保につなげていくことが重要である。

33
国内の潜在需要
①国内のイノベーションと需要の好循環
国内の潜在需要を掘り起こす
新たな内需型産業を拡大する
②アジア大のイノベーションと需要の好循環
グローバル需要を取り込む
先進国
新興国
アジア
収益を国内に還流する
中小企業の活性化安定的な雇用の場の確保
新産業分野
また、価値創造経済社会を構築していくためには、企業が「稼ぐビジネス」をしたたかに
行うだけでなく、一人一人が「稼ぐ人材」として、価値創造に参画する必要がある。
このため、第二の柱として、まず、多様性を高めイノベーションを創出すること、言い換
えれば、女性、若者、高齢者、障害者、外国人等一人一人が、置かれた環境と能力に応じて、
価値創造に参画できる環境を整備する「ダイバーシティ・マネジメント」が重要である。ま
た、価値創造をリードするイノベーション人材やグローバル人材が育つ環境を整備する。そ
して、各個人の産業間移動、職種転換を促し、各自の能力を最大限発揮して、価値創造に取
り組んでいくことが重要である。
「成熟を力に」• 多様な稼ぎ頭の産業構造• グローバル化• IT・ネットワーク化
産業構造の転換
「ワーカーからプレイヤーへ」• 画一(新卒採用、男性正社員、終身雇用)モデルの限界• ワークライフバランスの要請
(子育て・介護等と仕事の両立)
就業構造の転換
ダイバーシティ経営
多様な人材の能力を引き出し競争力を強化
異質同士の衝突・融合によるイノベーション
多様な人材を包容したグローバル展開
ワークライフバランスによる生産性向上
価値創造の実現へ
• 女性、若者、高齢者、障害者、外国人等一人一人の活躍• 円滑な労働移動の実現– スキル汎用化/学び直し– ITによる無形資産の蓄積
「人を活かす」産業の振興
多様で柔軟な働き方

34
このように、「攻め」の経済産業政策によって、産業構造と就業構造を転換することで、価
値創造経済社会への転換を図っていく。
他方で、行き過ぎた円高が急激に進行した場合には、これらの転換が実現される前に、我
が国経済は大きなダメージを受けてしまう恐れがある。前述した政策実現ケースと空洞化ケ
ースにおけるマクロ動向を比較すると、空洞化ケースでは、成長力の低下や雇用環境の悪化
が引き起こされることが見込まれる(試算の詳細は後述)。
成長3分野
(新たなエネルギー産業、ヘルスケア・子育て、クリエイティブ産業)
の潜在需要掘り起こしが実現した場合のマクロ動向予測
(2011 年度~2020 年度の平均値)
実質GDP成長率 +0.3%
+0.6%
+0.8%
6.1%
政策実現ケース
+1.2%
+1.6%
+1.9%
4.6%
空洞化ケース
1人当たり実質GDP成長率
1人当たり実質GNI成長率
失業率(2020年度)
'出所(三菱UFJリサーチ&コンサルティング試算'※1(空洞化ケースでもプラス成長となる理由は、足下の復興需要の拡大が主たる要因。
'※2(潜在需要が見込まれる3分野と外需の取り込みを考慮して試算したもの。他の政策効果とあわせて政府全体で新成長戦略の成長目標'2%(を目指す方針には変わりない。
'※3(政策実現ケースで失業率が4.6%となるのは、女性や高齢者等の労働参加が進むため。
'※1( '※2(
'※3(
ケース別の実質GDPの推移
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
政策実現 空洞化 '年度(
'兆円(

35
産業ごとの雇用誘発効果(生産が 10 億円増加した場合の雇用増加)を見ると、①潜在内
需の掘り起こしによる伸展が期待されるヘルスケア産業は、雇用吸収力は高いが生産性が低
く、②自動車、エレクトロニクス、機械産業は他産業への雇用誘発効果が非常に大きいこと
から、両者を共に伸ばしていくことが重要である。
自産業と他産業に対する雇用誘発効果
農林水産業
鉱業
飲食料品
繊維製品
パルプ・紙・木製品化学製品
石油・石炭製品
窯業・土石製品
鉄鋼
非鉄金属 金属製品
一般機械
電気機械
情報・通信機器
電子部品
輸送機械精密機械
その他の製造工業製品
建設
電力・ガス・熱供給業
水道・廃棄物処理
商業
金融・保険
不動産
運輸情報通信
公務 教育・研究
医療・保健・社会保障・介
護
その他の公共サービス
対事業所サービス
対個人サービス
0
10
20
30
40
50
60
70
0 20 40 60 80 100 120 140
'国内他産業への雇用誘発:人/10億人(
'国内自産業への雇用誘発:人/10億人(
70人/10億円 100人/10億円 130人/10億円
ヘルスケア産業
自動車、エレクトロニクス産業
'出所(総務省「平成17年産業連関表」より作成'注(各産業の生産額が10億円増加した場合の国内雇用誘発。
自動車、エレクトロニクス、機械産業
'国内他産業への雇用誘発:人/10億円(
'国内自産業への雇用誘発:人/10億円(
特に、価値創造経済への転換を実現するまでの間に、急速な円高等によって我が国の事業
環境が悪化し、自動車、電機、機械産業等を中心に産業空洞化が一気に進むことを防ぐこと
が不可欠である。ヘルスケア分野等の需要拡大によって雇用創出と生産性向上を図りつつ、
自動車・エレクトロニクス・機械産業の競争力を強化していくことが重要である。
このため、第三の柱として、緊急的な円高・空洞化対策を講じるとともに、世界水準の投
資、事業環境の整備に取り組む「守り」の対策が重要である。
具体的には、補正予算等を通じて、企業の国内投資に対する支援や国内市場の活性化に取
り組んでいく。さらに、我が国に立地する企業が国際競争で不利にならないよう、法人実効
税率引き下げや経済連携の推進など国内事業環境の国際的なイコールフッティングに取り
組み、世界水準の投資、事業環境を整備していく。

36
こうした取組を通じて短期的なリスクを回避しつつ、中長期的には、高付加価値型で差別
化された競争力を持つ製造業と、潜在内需を掘り起こしていくサービス産業を共に有する産
業集積国家としての日本経済を構築していく。
製造業については、独自の商品開発やブランド構築、あるいは顧客へのきめ細かい対応体
制強化等による「サービスとの融合」を進め、国際分業の中で価格交渉力の高いバリューチ
ェーン構造を強化していく。そして、「成熟」した国内市場の顧客ニーズを商品開発に活か
すことにより、新興国とは差別化された価値を創造していく。
サービス産業については、例えば、今後成長が見込まれるヘルスケア産業等において、も
のづくりのテクノロジーやITを導入し生産性向上を図るなど、一人当たり付加価値額を高
める取組を推進していく。
これにより、急速な産業空洞化を招くケースと比較して製造部門でも 100万人以上の雇用
を維持するとともに、サービス部門においても、BtoB、BtoC含め相当規模の雇用を
創出し、「人を活かす社会」構築を進めることとあわせ、経済全体の活性化を図っていく。
製造業とサービス産業の融合
製造業→「成熟」した顧客ニーズへの対応力を強化するため、きめ細かなアフターサービスやコンサルティング、システム構築など「サービスとの融合」
サービス産業→生産性向上等により一人当たり付加価値を高めるため、機械活用による高度化や省力化など「ものづくりテクノロジーやITの導入」
ものづくり サービスI T

37
製造業とサービス産業との融合事例
●社会インフラビジネスへの転換
日立 ・ 日立は、①モノの制御技術と、②データ処理のIT技術の両方に強み。(=世界でも数少ない企業)。・ この強みを活かし、スマートコミュニティや水道インフラ事業に、3年間で約1.7兆円を投資予定。
●システム・サービスと融合した5次産業化
コマツ ・ 建設機械に遠隔管理システム(KOMTRAX)を搭載。・ 2001年から70か国以上。→ 油圧機器(ハード)の高い技術力を持ちながら、位置情報と稼働情報で、ユーザ動向も把握。→ アフターサービスやソリューションの質を高めることで、「ハード+サービス」でのビジネスモデルへ。
・高齢者の自立支援と、介護実施者の負担軽減のため、2015年度を目途に、実践的介護ロボットの開発・導入を加速する。
●介護ロボットの導入による高齢者の自立支援と現場の負担軽減
167543
1239
4043
0
1000
2000
3000
4000
5000
2015 2020 2025 2035
介護ロボットの将来市場予測
(2010年経産省予測)
'億円(
●エネルギー関連ビジネスへの進出
トヨタ ・愛知県豊田市にてスマートコミュニティの実証実験。→全67世帯にPHV・EVを導入し、各家庭のモニターやスマートフォンにて
発電量、蓄電量、PHV・EVの充電残量、排出CO2量を管理する車載電池を核としたホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)を構築。
パナソニック
・ロボット技術を用いてベッドがそのまま車いすに変形することで、要介護者の移乗を支援し、自立した生活の促進と介護者の負担を軽減を実現。
●テクノロジーによるメディカル・ヘルスケア分野の高度化
ソニー ・テレビや業務用モニターの映像技術を活用し、3D表示モニターや有機ELモニターを医療用途で展開。
・ブルーレイディスク技術を細胞分析装置に応用。がん・再生医療の研究やiPS細胞研究などでの活用を見込む。
NEC ・NECが有する画像認識技術、情報処理技術を活かした病理診断支援システムを開発。