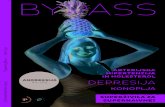排砂バイパストンネルの計画・設計手法の 体系化に向けた計 …bypass tunnel...
Transcript of 排砂バイパストンネルの計画・設計手法の 体系化に向けた計 …bypass tunnel...
-
24
1.はじめに
排砂バイパストンネル(以下「SBT」という。)は、貯水池堆砂対策として恒久的な効果が期待できる有力な工法である。しかし、SBTは世界的に見てもまだ施工事例数が少なく、個別ダムごとの状況に応じて施設計画・設計が進められているのが実情である。今後、より効率的、経済的なSBTを計画・設計する上では、SBTの計画・設計手法の体系化が不可欠である。
当財団では、平成20年度に発足した「ダム土砂マネジメント研究会」において堆砂対策の調査研究を行ってきたが、上記の状況を踏まえ、平成25年度からSBTに調査研究の軸足を置き、効率的、経済的なSBTの計画・設計手法の体系化の検討を進めている。
本報は、スイス・台湾・日本のSBTの事例分析について紹介した前報1)に引き続き、SBTの計画・設計手法の体系化に向けて作成したSBTの標準的な計画・設計検討フロー(以下「SBT標準検討フロー」という。)
の検証結果や課題等について考察を行ったものである。
2.構造諸元、排砂単価及び事業費の目安の設定
SBT標準検討フローの作成にあたり、制約条件となるSBTのトンネル径、縦断勾配、設計流速の目安を日本の4ダム、スイスの6ダムの事例を基に設定した。
また、トンネル延長については、縦断勾配の下限値が1/100程度であることを踏まえ、堤高を100mとした場合の10kmを上限値の目安として設定した。さらに、SBTの事業を具現化する上では、費用対効果や事業費も制約条件となり得る。このため、既設ダムの建設費より算定した有効容量1㎥当たりの単価4,000円/㎥を排砂単価の上限の目安とした。事業費については、新規ダム建設費よりも低く抑える必要があることから、既設ダムの平均建設費1,500億円の1/5程度(300億円)を上限値の目安とした。
以上をまとめた結果を表-1に示す。
調査研究 3-1
排砂バイパストンネルの計画・設計手法の 体系化に向けた計画・設計標準検討フローの検証
Verification of plan and design standard flowchart for systematization of planning and design method of sediment bypass tunnel
研究第二部 次長 小 野 雅 人研究第二部 上席主任研究員 北 村 永 晴
研究第二部長 奥 秋 芳 一
当財団では、堆砂対策の調査研究を目的として発足した「ダム土砂マネジメント研究会」において、効率的、経済的な排砂バイパストンネルの計画・設計手法について検討を進めている。本報は、計画・設計手法の体系化に向けて作成した排砂バイパストンネルの計画・設計標準検討フローの検証結果や課題等について考察したものである。
その結果、トンネル径が排砂バイパストンネルの適用性評価に影響を及ぼすこと、土砂濃度が新たな適用性評価指標になり得る可能性が示唆された。キーワード:排砂バイパストンネル(SBT)、計画・設計標準検討フロー、トンネル径、土砂濃度
At the dam sediment management study group that was established for the purpose of research and investigation of sedimentn measures, we are studying efficient and economical methods for planning and designing sediment bypass tunnels. This report considers the verification results and issues of the plan and design standard flowchart of the sediment bypass tunnel created for systematization of the planning and design method.As a result, it was found that the tunnel diameter affects the applicability evaluation of the sediment bypass tunnel. In addition, it was suggested that sediment concentration could be a new applicability evaluation index.Key words: Sediment bypass tunnel (SBT) , Planning and design standard flowchart, Tunnel diameter, Sediment
concentration
-
25
3.SBT 標準検討フロー
図-1にSBTの適用性を評価するSBT標準検討フローを示す。
当該フローは、SBTの適用性を体系的かつ標準的に評価することを目的として作成した。フローはSBTの標準的な検討を行う過程に、前記した構造諸元、排砂単価、事業費を制約条件として加えるとともに、対象流量がダムの計画最大放流量の内数であるかを確認する過程を加えて作成した。
なお、対象ダムの水位低下運用等に伴うトンネル延長の低減策については、SBTの適用性があると評価された段階において、ダムごとに詳細検討を行う手順とした。
4.SBT 標準検討フローの検証
(1)検討対象ダム検討対象ダムは、国土交通省及び水資源機構の管理
ダムから、幅広い流域面積を対象とする(流域面積が偏らない)ことを念頭に、各地方整備局管内ごとに3〜 6ダムを選定し、合計37ダムとした。
(2)土砂流入条件ダムへの流入土砂量の算出には、以下に示す簡易的
な統計手法である土砂量Lと流量Qの相関式より求めた。
L=αQβ
ここで、L:土砂量、Q:流量、α,β:係数である。各ダムの最適トンネル規模の設定においては、ダム
ごとの実績流量、流入土砂より個別にL-Q式を設定することが望ましい。しかし、ここでは日本全国の複数ダムに今回作成したSBT標準検討フローを適用し、その結果の妥当性や傾向を把握することが目的であるため、L-Q式は次の簡易な内容で設定した。
βについては、浮遊砂(2.0mm未満)のβを大きくするとSBTへの流入土砂量が増え、トンネル規模が大きくなる傾向が見られることから、一般的なβ=2で固定した。αは流量データが入手できた2002年〜 2017年の時間流量データから算出した年平均流入土砂量が各ダムの平均年堆砂量に一致するように設定した。
L-Q式に使用する粒度構成は、櫻井ら(2003)2)によって整理された日本の27ダムの貯水池内堆積土砂の粒度構成と流入土砂の粒度構成が把握できている日本の15ダムの平均値を基に、礫(2mm以上):15%、砂
(0.075 〜 2.0mm):35%、シルト・粘土(0.075mm以下):50%とした。
なお、接続支川が複数ある場合は、各支川からの流入量を個別に設定した上でL-Q式を設定する必要があるが、ここでは接続支川は1つと仮定して検討した。
(3)トンネル規模の検討条件表-2に最適トンネル規模の検討条件を示す。選定した検討対象ダムの最適トンネル規模は、前記
したL-Q式を実績流量に適用することにより、トンネル規模ごとに排砂単価を算出し、排砂単価が最小となる規模とした。
安目目項
トンネル径 D=3m~10m
縦断勾配 i=1/100~1/20
設計流速 V=10m/s~15m/s
トンネル延長 L<10km ダム高を100m程度として算出:Lmax
≒100/(1/100)=10,000m
排砂単価 4,000 円/m3(日本 49 ダムの有効容量 1m3当た
りの平均単価=3,992円/m3)
事業費 300億円(日本49ダムの新規建設費1,500億円
の 1/5を目安)
表-1 SBTの構造諸元、排砂単価、事業費の目安
件条討検目項
トンネル最大
流量
○パラメータ:各ダム 7ケース程度設定
※図-2 に示す SBT の既設事例より、比流量
0.1m3/s/km2~4.0m3/s/km2 程度の範囲を目
安として、検討ケースを設定
分派開始条件 ○流入量・貯水位とも制限を設けない
分派条件
○バイパス最大流量≧流入量
⇒ バイパス流量=流入量
○バイパス最大流量<流入量
⇒ バイパス流量=バイパス最大流量
土砂分派条件
掃流砂(D=2.0mm 以上と仮定):全量トンネルか
ら下流へ放流
浮遊砂(D=2.0mm 未満と仮定):トンネルへの分
派流量比率と同じ比率
土砂流入条件 ○「土砂流入条件」で設定したL-Q式を採用
トンネル諸元
○延長:貯水池平面から概略的に設定
○勾配:高低差=ダム高と仮定し、トンネル延
長と高低差からトンネル勾配を設定
計算期間 ○2002 年~2017 年までの 16 年間の実績流量
をそのまま使用
トンネル費用
○対象流量ごとの必要トンネル規模を基に初
期費用(トンネル工事費)、維持費用(摩耗補
修)を算出
排砂単価 ○排砂単価=トンネル費用(初期+維持)/100
年間の排砂量
最適規模の
評価
○上記で算出したトンネル規模毎の排砂単価
が最小となる規模を最適規模と評価
表-2 最適トンネル規模の検討条件
-
26
(1)トンネルの平面線形・縦断形の設定■トンネルのレイアウトを設定 ⇒ 概略的にはトンネル延長 L=貯水池延長 トンネル高低差H=ダム高 トンネル勾配 I =H/L
・トンネル縦断勾配は
1/100~1/20 程度か?
Yes
(2)トンネル対象流量の目安の設定 ■「地域別トンネル規模の目安」から対象ダムにおけるトンネル対象流量を概略的に設定
(3)トンネル断面形状の設定 ■上記の対象流量、縦断勾配からトンネル断面形状を設定
・トンネル径(D)は
3m~10m 程度か?
Yes
(4)排出可能土砂量の確認 ■上記のトンネル諸元で排出可能な土砂量を算定
No
(5)概算費用の算出 ■上記のトンネルの概算費用を算出
・排砂バイパス事業費・
排砂単価は目安以下か?
■排砂バイパストンネルの 適用性高い
■排砂バイパストンネルの適用性低い
Yes
No
【主な着目点等】
◯ トンネル事業費としては300 億円程度が上限の目安
◯ 排砂単価4,000 円/m3程度以下が目安 等
【主な着目点等】
◯ 貯水池形状・接続支川数・下流河川形状
◯ 地山の形状、地質状況
◯ 貯水池運用やバイパス呑口の標高の考慮
◯ 縦断形はレイアウトから決定 等
【主な着目点等】
◯ 排出土砂成分に対するトンネル内の掃流力が確保可能
か
◯ 過剰な摩耗が発生しないか 等
【主な着目点等】
◯ 対象ダムの所在地域の特性からトンネル対象土砂量の
目安を概略的に設定
◯ トンネル勾配毎の上限値も考慮
【主な着目点等】
◯ 水理計算の実施
◯ 馬蹄形(フラットインバート)、幌型、円形 等
【主な着目点等】
◯ 対象ダムの流入土砂L-Q式、実績流量を基に排出土砂
量検討
◯ 必要に応じて貯水池運用上の制約を考慮 等
No
・トンネル延長は
10km 程度以下か?
Yes
No
■排砂バイパストンネルの詳細検討ダムの抽出
【主な着目点等(別途検討)】
◯ ダムの堆砂状況
◯ 流域内でのダム機能の重要性 等
・トンネル対象流量は
計画最大放流量以下か?
【主な着目点等】
◯ ダムの洪水調節計画の内数かどうか確認
トンネル対象流量の
見直し
Yes
No
※必要に応じて水位低下運用によるコスト縮減について検討
【主な着目点等】
◯ 事業規模が大きくなりすぎないかの確認
【参 考】
◯ ダム接続河川数が2 本以下かどうか確認
【主な着目点等】
◯ 事業特性、新技術 等
排砂バイパス計画の検討スタート
図-1 SBTの計画・設計標準検討フロー
-
27
(4)SBT標準検討フローの適用結果SBT標準検討フローを適用した結果、37ダムのう
ち19ダムがSBTの適用性が高いと評価された(表-3)。一方、適用性が低いと評価された最多の要因はトンネル径であり、適用性が低いと評価された18ダムのうち11ダムがこの要因に該当した。これに次ぐ要因はトンネル勾配であり、6ダムが該当した。また、両者の要因を合わせると、適用性が低いと評価されたダムは15ダムとなった。
(5)SBT標準検討フローの適用結果の妥当性角(2005)3)が作成した貯水池特性(貯水池回転率・
貯水池寿命)と排砂工法の適用性の関係を示したグラフにSBT標準検討フローによる適用性の検討結果をプロットしたものを図-3に示す。このグラフでは、1/貯水池回転率(貯水池容量/平均年間流入水量)と貯
水池寿命(貯水池容量/平均年間流入土砂量)との関係より、貯水池寿命が短く、かつ貯水池回転率が高くなるにつれ、対策不要、貯砂ダム・土砂還元、排砂バイパス、フラッシング排砂(スルーシング)の順に排砂工法が分類されている。
SBT標準検討フローにより適用性が高いと評価されたダムは、このグラフにおいてSBTの適用性があると評価される範囲に集中しており、両者の調和性は非常に高い結果となった。
(6)適用性の評価に影響を及ぼした主な要因の分析適用性が低いと評価された最多の要因はトンネル径
であり、11ダムが該当した。この11ダムの内訳は、トンネル径D<3mが7ダム、トンネル径D>10mが4ダムであった。トンネル径D<3mの7ダムとトンネル径D>10mの4ダムのうち1ダムは、いずれも事業費と排砂単価は目安値を満足していることから、事業を実施する上では問題ないと判断できる。このため、トンネル径D=3 〜 10mの範囲を外れたダムの全てが、必ずしもSBTの適用性が低いという訳ではないと考えられる。
そこで、トンネル径D<3mのダムについては径を3m程度とし、トンネル径D>10mのダムのうちトンネル径以外の項目が目安値を満足しているダムは問題ないものとして再検討すると、図-4に示すように37ダムのうち27ダムについて適用性が高いとの評価になり、そのうちの16ダムがSBTの適用性があるとされる範囲に含まれた。
図-2 集水面積と既設トンネル対象流量(比流量)の関係
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
0 200 400 600 800 1000
トンネル
対象流
量(比
流量)
(m3 /
s/km
2 )
集水面積(km2)
凡例
◯:日本
△:スイス
□:台湾
特異値として棄却
0.1~4.0m3/s/km2
図-3 貯水池回転率・貯水池寿命と排砂工法
CAP:貯水容量(m3),MAR:平均年間流入水量(m3/年),MAS:平均年間流入土砂量(m3/年)
10
100
1000
10000
100000
0.001 0.010 0.100 1.000 10.000
貯水池
寿命
=CA
P/M
AS
1/貯水池回転率=CAP/MAR
: 貯砂ダム
: フラッシング排砂
: 排砂門
: 排砂管
: 排砂バイパス
: 陸上掘削
: 浚渫
適用性低い(検討対象ダム)
適用性高い(検討対象ダム)
貯砂ダム・土砂還元
対策不要(内的要因より)
フラッシング排砂(スルーシング)
排砂バイパス
-
28
注)表中の赤字は制約上限範囲外であることを示す。
適用
性判
断
1北
海道
299
92,7
00
325,9
30
74
0.0
14
7,4
00
120
30
0.1
04.1
06.2
91.6
1,7
70
80.2
-
2北
海道
292
66,0
00
442,1
04
59
0.0
08
4,8
00
60
40
0.1
43.3
07.3
50.0
1,1
60
86.2
○
3北
海道
1,6
62
108,0
00
1,8
86,5
19
369
0.0
12
12,1
00
250
100
0.0
69.3
09.7
336.6
1,3
70
80.8
-
4北
海道
1,2
15
31,5
00
1,4
61,4
00
710
0.0
29
14,5
00
460
150
0.1
214.7
013.3
631.3
1,7
00
76.5
-
5東
北583
114,1
60
1,4
07,8
69
194
0.0
08
11,0
00
130
150
0.2
67.8
09.3
255.0
1,9
40
78.2
-
6東
北635
65,0
00
1,2
78,2
85
217
0.0
10
9,9
00
190
100
0.1
68.1
08.9
239.0
2,0
30
66.6
-
7東
北231
109,0
00
900,8
60
153
0.0
10
5,4
00
50
60
0.2
63.5
08.6
58.2
550
73.0
○
8東
北225
53,1
00
401,8
31
92
0.0
14
6,1
00
70
40
0.1
83.5
07.1
65.1
940
84.0
○
9東
北205
50,0
00
490,2
85
79
0.0
10
5,9
00
90
60
0.2
94.6
07.9
82.7
1,4
30
83.9
○
10
関東
323
83,0
00
186,7
16
200
0.0
64
3,7
00
30
200
0.6
24.2
012.6
49.6
430
79.3
○
11
関東
170
26,9
00
133,1
54
89
0.0
40
4,0
00
50
80
0.4
73.9
09.2
48.8
1,0
10
75.4
○
12
関東
214
193,0
00
270,6
39
235
0.0
52
8,5
00
60
60
0.2
83.8
08.3
97.0
750
64.4
○
13
関東
167
204,3
00
546,9
45
117
0.0
13
8,9
00
70
40
0.2
43.5
07.1
92.8
1,3
20
72.0
○
14
北陸
618
24,7
00
1,6
15,3
08
546
0.0
20
2,4
00
30
90
0.1
53.1
010.5
27.0
90
67.5
○
15
北陸
826
57,5
00
1,0
60,0
27
161
0.0
09
4,1
00
60
90
0.1
13.1
06.9
27.7
300
69.3
○
16
北陸
193
33,9
00
567,1
83
35
0.0
04
2,5
00
30
45
0.2
32.4
08.5
20.6
770
85.9
-
17
北陸
428
231,0
00
1,1
75,0
76
232
0.0
12
12,0
00
80
40
0.0
93.8
07.2
136.1
4,5
80
51.1
-
18
北陸
76
27,5
00
193,3
88
77
0.0
24
2,3
00
20
30
0.3
91.7
07.3
13.5
390
76.0
-
19
中部
311
29,9
52
413,4
19
111
0.0
16
5,9
00
90
30
0.1
03.6
06.6
65.5
870
71.8
○
20
中部
471
40,0
00
988,7
09
164
0.0
10
7,0
00
90
100
0.2
15.6
08.9
118.9
1,1
50
74.6
○
21
中部
81
32,6
00
173,6
78
85
0.0
29
3,6
00
50
60
0.7
43.5
08.6
39.1
1,3
40
55.3
○
22
近畿
352
26,2
80
3,1
21,7
17
97
0.0
02
5,5
00
80
600
1.7
010.3
014.3
174.0
1,6
40
94.9
-
23
近畿
215
23,3
00
330,3
83
66
0.0
12
2,8
00
40
800
3.7
28.1
017.2
73.2
700
95.8
-
24
近畿
290
66,0
00
359,7
64
124
0.0
21
5,2
00
80
20
0.0
72.9
05.4
47.4
1,2
50
48.0
-
25
中国
308
47,3
00
373,7
95
59
0.0
09
5,0
00
100
30
0.1
03.8
06.3
59.3
1,0
10
61.2
○
26
中国
32
20,6
00
61,3
69
11
0.0
11
3,2
00
40
10
0.3
11.6
05.7
16.3
240
65.7
-
27
中国
301
112,0
00
281,8
85
162
0.0
35
5,9
00
50
90
0.3
04.0
09.4
72.1
990
76.1
○
28
中国
242
60,0
00
171,8
91
41
0.0
14
6,3
00
80
20
0.0
82.9
05.4
56.2
2,9
70
59.7
-
29
四国
73
12,8
00
31,1
78
24
0.0
45
2,7
00
40
10
0.1
41.6
05.7
14.5
780
55.8
-
30
四国
689
66,0
00
1,2
20,6
63
167
0.0
08
8,6
00
90
900
1.3
112.7
015.5
329.3
4,2
40
81.5
-
31
四国
168
16,0
00
201,1
97
32
0.0
09
6,0
00
100
100
0.6
05.9
08.8
107.1
5,3
10
77.1
-
32
九州
805
123,0
00
1,8
14,7
40
212
0.0
07
15,9
00
140
400
0.5
011.7
011.8
547.5
4,5
90
71.2
-
33
九州
89
23,3
00
104,8
15
24
0.0
14
3,8
00
70
80
0.9
04.6
08.8
54.1
3,8
60
77.9
○
34
九州
491
54,6
00
991,9
38
89
0.0
05
8,3
00
100
100
0.2
05.9
08.8
147.6
3,4
50
58.7
○
35
九州
185
59,3
00
424,2
01
99
0.0
14
5,6
00
60
150
0.8
15.3
010.6
90.5
1,5
90
70.3
○
36
九州
359
46,0
00
707,2
73
169
0.0
14
7,0
00
100
90
0.2
55.7
08.6
120.7
1,5
20
60.7
○
37
九州
34
13,6
00
23,0
91
13
0.0
33
2,0
00
20
20
0.5
91.5
06.6
10.1
1,4
00
73.1
-
適用性
高い
32
31
37
37
26
35
33
33
37
19
適用性
低い
56
00
11
24
40
18
初期
費用
(億
円)
排砂単
価
(円
/m
3)
排砂
効率
(%)
トンネル勾
配(1/N
)
対象
流量
(m3/s)
対象比
流量
(m
3/s/
km2)
トンネル
径(m
)管
内流
速(m
/s)
判定
適用
性高い:○
適用
性低い:-
No.
地方
土砂
バイパ
ストンネル
諸元
ダム
・貯水
池諸
元
流域面
積
(km
2)
総貯
水容量
(千
m3)
平均
年間
流入
水量
(千
m3)
平均
年間
流入
土砂
量
(千
m3/年
)
土砂濃
度(%)
トンネル
延長
(m)
表-3
SBT
の計
画・
設計
標準
検討
フロ
ーに
基づ
く適
用性
の評
価結
果
-
29
以上のことから、トンネル径については以下の方針で検討を進めていくこととする。・トンネル径は施工性や維持管理の観点から最低でも
3m程度は必要であることから、D<3mのダムについては径を3m程度に大きくした場合の事業費と排砂単価が目安値を満足しているかを確認する。
・トンネル径が10mを僅かに超える程度であれば、事業費や排砂単価が目安値を満足しているかを確認し、問題がなければ適用性が高いものと評価する。
・トンネル径が10mを大きく超過したことが要因で事業費や排砂単価が目安値を超過しているダムについては、事業費や排砂単価が目安値の範囲内に収まるまでトンネル径を小さくし、その場合の排砂効率が許容できるかを確認した上で適用性を評価する。
(7)新たな適用性判断指標の抽出図-4に示すSBTの適用性評価結果と土砂濃度との
関係に着目すると、土砂濃度が0.015%以上のダムついては、1ダムを除き適用性が高いとの評価結果になった。このことから、土砂濃度は適用性判断指標の一つになり得る可能性があると考えられる。
そこで、土砂濃度と他の項目との相関について感度分析を行った結果、排砂単価との相関が最も高いことが確認された。図-5に土砂濃度と排砂単価の関係を示す。土砂濃度が0.015%以上の範囲では、土砂濃度と排砂単価は負の相関関係にある。これは、SBTの規模が同等程度である場合、土砂濃度が上がると排砂量が増加し、排砂単価が下がることによる。
なお、土砂濃度が0.015%を下回ると排砂単価のばらつきが大きくなっている。これは、事業費に関係する他の要因が排砂単価に影響を及ぼすためであると考えられる。
5.まとめ
本報では、SBTの適用性を体系的かつ標準的に評価することを目的として作成したSBT標準検討フローより得られる結果や課題等について考察を行った。SBT標準検討フローにおいてSBTの適用性が高いと評価されたダムは、貯水池回転率と貯水池寿命の関係からSBTの適用性があると評価される範囲に集中しており、両者の調和性は非常に高い結果となった。しかし、トンネル径に目安値を設けたことで、経済的には問題ないものの適用性が低いと評価されるケースがあり、当該フローの見直すべき課題と考えられた。また、土砂濃度がSBTの新たな適用性判断指標になり得る可能性が示唆された。
今後、検討ダム数を増やしてフローの妥当性の検証を進めるとともに、SBTの適・不適の主要因の分析や適用性が低いと判断された場合の取り扱い、新たな判断指標の可能性等についても引き続き検討を行う予定である。
謝辞本稿は「ダム土砂マネジメント研究会(委員長 角哲
也 京都大学防災研究所教授)」の第15回研究会資料をもとに構成した。研究会において貴重なご助言・指導を頂いた委員の皆様方、また研究会資料作成にあたりデータの整理等にご尽力頂いた株式会社建設技術研究所の永谷言氏に紙面を借りて御礼申し上げる。
参考文献1) 大堀英良・小野雅人・工藤勝弘:排砂バイパストンネル事
例の分析(スイス、台湾、日本),水源地環境技術研究所所報,一般財団法人水源地環境センター,pp.29 〜 34,2017.12
2) 櫻井寿之・柏井条介・大黒真希:ダム貯水池の堆砂形態,土木技術資料 45(3),pp.56 〜 61,2003.3
3) 角哲也:土砂管理で「千年ダム」の実現を,季刊 河川レビュー,新公論社,2005
10
100
1000
10000
100000
0.001 0.010 0.100 1.000 10.000
貯水池
寿命
=C
AP
/M
AS
1/貯水池回転率=CAP/MAR
土砂濃度(%): 0.015
適用性高い(D=3.0m-10.0m)
適用性高い(D>10.0m)
適用性低い(D>10.0m)
適用性低い(トンネル径以外の要因)
排砂バイパス
図-4 貯水池回転率・貯水池寿命・土砂濃度と排砂バイパストンネルの適用性評価結果
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08
排砂単
価(円
/m3 )
土砂濃度
0.015
適用範囲
土砂濃度が高く
なると排砂単価
が下がる
(=平均年間流入土砂量×(1.0-0.4 (空隙率))/平均年間流入水量)
適用性高い(D=3.0m~10.0m)適用性高い(D>10.0m)適用性低い(D>10.0m)適用性低い(トンネル径以外の要因)
図-5 土砂濃度と排砂単価の関係










![Bypass gastri corregidoo[1]](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/55b800ffbb61ebe37c8b467d/bypass-gastri-corregidoo1-55bd331ceab27.jpg)