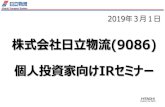特許権侵害訴訟における証拠収集手続の立法的課題 ·...
Transcript of 特許権侵害訴訟における証拠収集手続の立法的課題 ·...

論 文
特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3 15
1.はじめに
特許権侵害訴訟で も重要な問題は,特許権侵
害の成否である。特許権者1は,被疑侵害製品・方
法を特定し,侵害の事実を証明する。そのための
証拠は,原則として,特許権者自らが収集し,裁
判所に提出しなければならない。特許発明が物の
発明であり,被疑侵害物件が市販されている製品
である場合は,特許権者がその製品を購入し,調
査・分析することにより,特許権侵害の事実を容
易に確認し,証拠を提出することができる。しか
し,注文生産される特殊な工作機械など入手困難
な製品や,工場内部で実施される方法や製造方法
に関する発明のように,侵害行為の状況が外部か
らは不明であるような場合,あるいは,ソフトウ
エア関連発明のように,侵害行為の立証のために
被疑侵害者が有しているソースコードが必要な場
合には,特許権者がそれらの証拠を自ら収集し提
出することが極めて困難である。このような証拠
偏在のケースにおいて,証拠収集手続を拡充し,
特許権者の証拠収集・提出の負担を軽減すること
は,特許権の実質的な保護につながる点で,極め
て重要である。
2017 年 2 月 24 日,産業構造審議会知的財産分
科会特許制度小委員会(以下,「特許制度小委員会」
という。)で,「我が国の知財紛争処理システムの
強化について(案)」(以下,「紛争処理システム強
化案」という。)が公表され,特許権侵害訴訟にお
ける証拠収集制度の改善に向けた一定の方向性が
示された。本稿では,紛争処理システム強化案の
内容について紹介するとともに,そこで示されて
いる証拠収集手続改善の方向性について検討する
ことを目的とする。
なお,本稿のうち,意見にわたる部分について
は,著者の私見であり,著者所属の組織の見解と
は一切関係が無い。
* 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 准教授 Associate Professor, Graduate School of International
Corporate Strategy, Hitotsubashi University
特許権侵害訴訟における証拠収集手続の立法的課題
Legislative Issues of Evidence Collection Procedure in Patent Infringement Suits
東 松 修 太 郎*
Shutaro TOMATSU
抄録 2017年2月に,産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会で,「我が国の知財紛争処理シス
テムの強化について(案)」が公表され,特許権侵害訴訟における証拠収集手続の改善に向けた一定の
方向性が示された。本稿では,「我が国の知財紛争処理システムの強化について(案)」の内容について紹
介するとともに,そこで示されている証拠収集手続改善の方向性について検討することを目的とする。

論 文
16 特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3
2.政府における検討状況の概観
(1)政府における検討の経緯
ア.知的財産戦略本部での検討
政府では,知的財産戦略本部における「知的財
産戦略タスクフォース」2(2014 年~2015 年),「知
財紛争処理システム検討委員会」3(2015 年~2016
年)で証拠収集制度の在り方の検討が行われ,そ
れらを踏まえ,「知財推進計画 2016」において,
次のような提言が行われた。
まず,訴え提起後の証拠収集手続においては,
現行の書類提出命令を発令しやすくするために,
①具体的態様の明示義務が十分に履行されなかっ
た場合に書類提出命令が発令されやすくする方策,
②書類提出命令と秘密保持命令を組み合わせて発
令できるようにすること,及び,③中立的な第三
者が被疑侵害者に対して査察を行う制度(提訴後
査察)を導入すること,の 3 つについて,「産業界
を始めとした関係者の意見を踏まえつつ,具体的
に検討を進め,2016 年度中に法制度の在り方に関
する一定の結論を得る。」と提言された4。
一方,訴え提起前の証拠収集制度については,
「現行制度の利用例の共有等を進めるとともに,
現行制度が活用されていない要因の分析及びその
具体的改善策の可能性について検討する。」と提言
された。
イ.特許制度小委員会での検討
知財推進計画 2016 公表後, 2016 年 6 月より,
特許庁の特許制度小委員会において,証拠収集手
続の拡充を含めた特許制度の総合的な検討が行わ
れている。前述のように,2017 年 2 月 24 日,特
許制度小委員会において,紛争処理システム強化
案5が公表され,同日から,パブリックコメントが
募集された。紛争処理システム強化案では,証拠
収集手続について一定の制度改正の方向性が示さ
れている。そこで,まずは,紛争処理システム強
化案に示されている証拠収集手続の強化策につい
て紹介する。
(2)紛争処理システム強化案で示された証拠
収集手続の強化策
ア.中立の第三者が証拠収集に関与する制度
紛争処理システム強化案では,特許権侵害訴訟
の専門性,証拠の偏在や構造的な侵害立証が困難
性といった特殊性に鑑み,証拠収集手続を強化す
る措置を講ずる必要があるとする。一方で,強制
力を有する査察制度は,営業秘密の重要性や我が
国の法制度との整合性の疑問を考えると,強制力
のある中立の第三者が被疑侵害者に対して査察を
行う制度(提訴後査察)については,引き続き慎
重に検討することとし,まずは日本の民事訴訟制
度の枠組みに沿った形で中立的な第三者の技術専
門家が証拠収集手続に関与する制度を導入するこ
とで,手続の充実化を図り,その運用を注視する
ことが適切である,としている6。
また,その具体的方策として,①書類提出命令
及び検証物提示命令における書類及び検証物の提
出義務の有無を判断するための手続(インカメラ
手続)において,裁判官に技術的なサポートを行
うことを可能にすることや,②鑑定人に検証の際
の鑑定における秘密保持義務を課すことで,同手
続を秘密保護に配慮した形で行うことを可能とす
ることを例示しているものの,技術専門家の関与
の在り方については,今後,現行制度との関係,
新たに関与することとなる第三者の手続上の法的
位置付け,選任方法等に留意しつつ検討を進める
ことが適当である,としている。

論 文
特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3 17
イ.書類・検証物の提出必要性判断のためのイ
ンカメラ手続導入について
一方,紛争処理システム強化案では,書類提出
命令・検証物提示命令の制度において,書類・検
証物の提出の必要性の有無についての判断のため
に,裁判所がインカメラ手続により当該書類・検
証物を見ることを可能にする制度(以下,「提出必
要性判断のためのインカメラ手続」という。)を導
入することが提案されている7。本制度の導入によ
り,裁判所が書類・検証物提出の必要性を申立書
の主張のみから判断しづらい場合に,当事者に書
類・検証物をいったん提示させ,インカメラ手続
で実際に書類・検証物を見て必要性を判断できる
ようになる,としている。
ウ.具体的態様の明示義務不履行の場合に書類
提出命令を発令しやすくする方策について
知財推進計画 2016 では,具体的態様の明示義務
が十分に履行されなかった場合に書類提出命令が
発令されやすくする方策の導入が提言されていた
が,紛争処理システム強化案では,提出必要性の
判断のためのインカメラ手続(イ.参照)の制度
を導入した上で,その後の裁判所の運用を注視す
るとし,当該制度の導入によっても対応が困難な
課題が明らかになった場合に検討すべき課題であ
るとしている8。現行制度においても,裁判所は,
具体的態様の明示義務の履行状況や被疑侵害者と
権利者による攻撃防御の状況を踏まえて,訴訟指
揮により柔軟に書類提出命令を発令することは可
能であることや,インカメラ手続により証拠提出
の必要性を判断できるようにすることにより,具
体的態様の明示義務の履行にかかわらず,裁判所
が書類提出命令の要件を判断しやすい環境が整い
得ることが,その理由である。
エ.書類提出命令と秘密保持命令を組み合わせ
て発令できる方策について
同じく,知財推進計画 2016 で挙げられていた,
裁判所が書類提出命令の発令に併せて当事者の申
立てによらずに秘密保持命令を発令できるように
する方策も,提出必要性の判断のためのインカメ
ラ手続(イ.参照)の制度を導入した上で,その
後の裁判所の運用を注視するとし,対応が困難で
あることが明らかになった場合に検討すべき課題
であるとしている。秘密保持命令の範囲や名宛人
の特定については,事柄の性質上,当事者の協力
なしで裁判所が職権で判断することは難しいこと
や,裁判所は,書類提出命令の相手方から秘密保
持命令の申立てが無い場合には,訴訟指揮に基づ
き当事者に秘密保持命令の申立てを促し,あるい
は秘密保持契約等の締結を促すことも可能であり,
改正によらず運用で対応が可能であること,提出
必要性判断のためのインカメラ手続制度により,
秘密保持命令との発令の組合せによらず,裁判所
が書類提出命令の要件を判断しやすい環境が整い
得ること,がその理由である。
オ.訴え提起前の証拠収集処分
訴え提起前の証拠収集処分については,現行制
度の任意性は維持した上で,訴え提起後の証拠収
集手続の改善策と同様に,日本の民事訴訟制度の
枠組みに沿った形で中立的な第三者の技術専門家
が証拠収集手続に関与する制度を導入することで,
手続の更なる充実化を図ることが適切であるとし
ている9。このような方策として,例えば,秘密保
持の義務を課された第三者の技術専門家が執行官
に同行して技術的なサポートを行う仕組みを導入
することが考えられるが,技術専門家の関与の在
り方については,今後,現行制度との関係,新た
に関与することとなる第三者の手続上の法的位置

論 文
18 特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3
付け,選任方法等に留意しつつ検討を進めること
が適当である,としている。
カ.紛争処理システム強化案の分析
紛争処理システム強化案によれば,強制力を有
する欧州型の査察による証拠収集制度の導入につ
いては見送られる方向である。また,具体的明示
義務が果たされない場合に書類提出命令を出しや
すくすることや,書類提出命令と秘密保持命令と
を組み合わせて発令できるようにすることについ
ても,見送られる方向であるといえよう。一方で,
訴え提起後において,現行の民事訴訟制度の枠内
で,中立的な第三者の技術専門家が証拠収集手続
に関与する制度を導入すること,訴え提起前の証
拠収集処分の手続において,現行の民事訴訟の枠
内で,中立的な第三者の技術専門家が証拠収集手
続に関与する制度を導入すること,書類提出命
令・検証命令の際に,提出の必要性を判断するた
めのインカメラ手続を行うことができるようにす
ること,が提言されており,今後の特許制度小委
員会では,これらについて具体的な制度の検討が
行われるものと思われる。
以下の章では,紛争処理システムに示された二
つの立法的課題,すなわち,①書類提出命令にお
ける提出必要性判断のためのインカメラ手続の導
入と,②提訴前及び提訴後の中立的な第三者の技
術専門家が証拠収集手続に関与する制度の導入に
ついて,考察を行う。
3.特許権侵害を証明するための証拠
調べと証拠収集手続の概要
(1)特許権侵害を証明するための証拠調べ
本章では,前述の立法的課題の考察の前提とし
て,特許権侵害を証明するための証拠調べや,現
行の証拠収集手続について概観する。特許権侵害
の事実を証明するためには,対象製品・対象方法
を特定し,その技術的構成を明らかにする必要が
あるが,その際にしばしば用いられる証拠調べの
方法は,書証と検証である。例えば,対象製品に
ついての図面や写真,当事者による実験結果,プ
ログラムのソースコード等の文書・準文書が提出
された場合には書証に,また,権利者製品や被疑
侵害者製品そのものについては検証によって取り
調べられる。対象製品が工場の設備機械等である
場合や,対象方法が工場で実施される方法等であ
る場合については,裁判所及び当事者が,当該工
場に出向いて検証を行うことが考えられる10。し
かし,実務では,被疑侵害者の工場内での検証は
ほとんど行われていない11。多くの場合,それに
代えて,当該機械の写真や図面,被疑侵害者製品
の設計図,使用説明書,製造工程に関するマニュ
アル類,製造日誌等や当該方法を撮影した DVD
等が文書・準文書として提出され,書証として取
り調べられる。
ところで,特許権侵害を証明するための文書・
準文書(以下,「書類」ともいう。)や検証目的等,
多くの証拠は,被疑侵害者側に偏在している。し
かし,それらの証拠は,被疑侵害者にとって不利
になるものであり,被疑侵害者が積極的に提出・
提示することは期待できない。そこで,裁判所命
令等によって証拠収集を行う手続(証拠収集手続)
が必要となる。
(2)訴え提起後の証拠収集手続
ア.序論
特許権侵害訴訟提起後に利用できる情報・証拠
収集手続は,当事者照会(民事訴訟法 163 条),調
査嘱託(民事訴訟法 186 条),具体的態様の明示義
務(特許法 104 条の 2)等があるが,ここでは,
前述の立法的課題と関係の深い,書類提出命令・

論 文
特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3 19
検証命令について,説明する。
イ.書類提出命令・検証命令
特許権者は,本案の訴訟手続中で,文書提出命
令(民事訴訟法 221 条以下),書類提出命令(特許
法 105 条 1 項),検証物提示命令・検証受忍命令(特
許法 105 条 4 項。以下,併せて「検証命令」とい
う。)を通じて,被疑侵害者側に対して,書類や検
証目的の提出・提示を求めることができる12。文
書提出命令と書類提出命令とは,提出が命じられ
るための要件や,インカメラ手続の方式(当事者
の立会いを許すことができるかどうか等)に違い
があるが,一般に,書類提出命令のほうが,認容
されるための要件が緩やかであると考えられてい
る。そこで,以下では,書類提出命令と検証命令
に絞って説明する。
裁判所は,特許権者側から書類提出命令・検証
命令の申立てがあった場合,①侵害行為の立証に
必要であり(証拠調べの必要性),②被疑侵害者側
においてそれを拒むことができる「正当な理由」
がなければ(提出義務の存在),書類の提出や検証
物の提示,検証の受忍を命じることができる13(特
許法 105 条 1 項)。
「証拠調べの必要性」については,裁判所がそ
の裁量により判断する。すなわち,裁判所は,当
事者が申し出た証拠で必要ないと認めるものは,
取り調べることを要しない(民事訴訟法 181 条 1
項)とされており,書類提出命令の必要性の判断
も同条によって行われる。特許権侵害訴訟の場合,
一旦書類提出命令・検証命令が発令されると,被
疑侵害者の営業秘密を含む書類や検証目的が特許
権者に開示されてしまうため,書類提出命令等が
産業スパイ目的に濫用される可能性もある。その
ため,裁判所は,「証拠調べの必要性」について,
探索的な証拠調べ禁止の観点を加味して判断を行
っている。具体的には,一般的な証拠の必要性14を
満たすことに加えて,特許権者側で侵害であるこ
とを合理的に疑しめるだけの手がかりとなる疎明15を
尽くす必要があるとされている。
次に,「正当な理由」の有無は,書類や検証目的
が特許権者に開示されることにより被疑侵害者が
受ける不利益(主に営業秘密の漏洩)と,書類や
検証目的が訴訟に提出されないことにより特許権
者が受ける不利益(証拠の必要性の程度)とを比
較衡量して判断される16。当該書類や検証目的に
より,被疑侵害者が特許発明に属する構成や方法
を用いていることが明らかになる場合は開示の必
要性が高く,書類の提出や検証の目的の提示を拒
む「正当な理由」がないとの判断に傾く一方,非
侵害が明らかになる証拠であれば,被疑侵害者の
営業秘密の保護の程度は高いと考えられ,「正当な
理由」があるとの判断に傾く17。このような比較
衡量を行うためにインカメラ手続(特許法 105 条
3 項)を利用することもあり,同手続により非侵
害が明らかになった場合は書類の提出や検証目的
の提示を命じないこととなるため,被疑侵害者の
営業秘密の保護に役に立っている。
書類提出命令・検証命令が出されたにもかかわ
らず,被申立人(被疑侵害者)がそれに従わない
場合,裁判所は書類の記載や検証目的に関する申
立人(特許権者)の主張を真実と認めることがで
き(民事訴訟法 224 条 1 項,2 項),また,当該書
類の記載や検証目的に関して具体的な主張をする
こと及び当該書類や検証目的により証明すべき事
実(要証事実)を他の証拠により証明することが
著しく困難であるときは,裁判所は,その事実に
関する相手方の主張を真実と認めることができる
(同条 3 項)。したがって,書類提出命令・検証命
令が出されるかどうかは,特許権侵害訴訟の結果
に大きく影響を及ぼすものであるといえる。

論 文
20 特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3
(3)訴え提起前の証拠収集手続
ア.序論
訴え提起前については,本案がまだ裁判所に係
属していないため,書類提出命令等を用いること
はできない。訴え提起前に使われる証拠収集手続
は,証拠保全手続(民事訴訟法 234 条~242 条)
と,訴え提起前の証拠収集処分等(同法 132 条の
2~132 条の 5),弁護士法上の照会(弁護士法 23
条の 2)等がある。以下,前述の立法的課題と関
係の深い,証拠保全手続と,訴え提起前の証拠収
集処分における執行官に対する現況調査命令を概
観する。
イ.証拠保全
証拠保全手続(民事訴訟法 234 条~242 条)は,
訴訟における証拠調べの時期まで待つと,その証
拠調べが不能又は困難になる事情(保全事由)が
ある場合に,あらかじめ証拠調べを行い,その結
果を保存しておくための手続である18。例えば,
被疑侵害者の工場において特許装置(又は特許方
法)を用いて製造が行われており,その事実を明
らかにしておかないと被疑侵害者が製造方法や製
造装置を変更するおそれがある場合に,証拠保全
手続を行うことができる。証拠保全手続の本来の
機能は証拠の保全であり,また,訴訟提起前後の
どちらでも利用可能な手続であるが,証拠が被告
側に偏在している訴訟類型においては,訴訟提起
前に訴訟の相手方から事実・証拠を把握するため
の証拠開示のために使われることがある19。
証拠保全は,被疑侵害者に対する強制力は無い。
そのため,被疑侵害者の支配下にあるものを証拠
保全によって検証しようとしても,被疑侵害者が
営業秘密を理由に検証を拒んだ場合,検証は不能
となる20。
ウ.執行官に対する現況調査命令
特許権者が被疑侵害者等に訴えの提起を予告す
る通知(予告通知)をした場合には,特許権者は,
当該予告通知に係る訴えを提起した場合の立証に
必要であることが明らかな証拠となるべきものに
ついて,これを自ら収集することが困難であれば,
原則として予告通知をした日から 4 月の不変期間
に限り,執行官に対する現況調査命令を書面で申
し立てることができる。ただし,その収集に要す
べき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当
となる等の事情により,相当でないと認められる
ときは,申立てが棄却される。裁判所は,処分に
先立ち,予告通知の相手方(被疑侵害者)に対し
て意見を聴かなければならず,被疑侵害者からそ
の証拠に営業秘密が含まれるとの意見が述べられ
た場合は,嘱託を受けるべき者の負担が不相当に
なる等の理由により,申立てが認められない場合
が多いとされている21。また,被疑侵害者側が拒
否したときの制裁規定も無い。そのため,実務で
はほとんど利用されていない。
(4)中立の第三者が関与する証拠収集手段
ア.鑑定
鑑定は,特別の学識を有する第三者に,専門の
学識経験に基づいて,法規,慣習,経験法則など,
およびそれらを適用して得た判断の結果を裁判所
に報告させ,裁判官の知識を補充するための証拠
調べである(民事訴訟法 212 条~218 条)。鑑定人
は,裁判所等によって指名され,中立性の要請か
ら,欠格事由があり,忌避も可能である22。鑑定
人は,必要な調査と自己の知見とを総合して鑑定
意見を書面又は口頭で作成し,裁判所に提出する
(民事訴訟法 215 条)。当事者は,鑑定書を補充す
るために,期日において,口頭で鑑定人に質問す
ることができる。裁判所は鑑定意見に拘束されず,

論 文
特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3 21
その採否を自由に判断することができる(民事訴
訟法 186 条)。
特許権侵害訴訟では,損害論の審理において,
損害額を計算するために,計算鑑定(特許法 105
条の 2)が利用されている。計算鑑定は,裁判所
が指名する中立の計算鑑定人(公認会計士等)23が,
被疑侵害者の事務所等において,損害の計算をす
るために必要な会計書類等の資料を精査して鑑定
意見を作成し,裁判所に報告する制度である。計
算鑑定書を作成する際には,損害額の計算に不要
な営業秘密を書かない等の工夫が行われており24,
鑑定の基礎とした資料自体も訴訟の場に出されな
い。そのため,計算鑑定人が算定した損害額は計
算鑑定書によって訴訟の場に出される一方で,被
疑侵害者の営業秘密は一定程度保護される仕組み
になっている。
また,侵害論の審理においても,対象製品・対
象方法の構成を明らかにするために,鑑定の申請
がされることがある。しかし,適切な鑑定人の選
定が困難であり訴訟の遅延を招きかねないことや,
専門委員・調査官等の専門的知見を確保する制度
が別途あることから,専門技術に関する鑑定が実
施されることはほとんどないといわれている25。
イ.提出義務判断のためのインカメラ手続
特許権侵害を証明するための書類提出命令・検
証命令において,「正当な理由」,すなわち,書類・
検証目的の提出義務を判断するためのインカメラ
手続では,裁判所の命を受けて裁判所調査官が関
与することがある(民事訴訟法 92 条の 8 第 1 号ハ
参照)。裁判所調査官を中立の第三者と呼ぶことが
適切であるなら,これも中立の第三者が関与する
手続ということになる。
ウ.執行官に対する現況調査命令
これについては,3.(3)ウにて説明したとおり
である。
エ.事実実験公正証書
事実実験公正証書は,守秘義務を有する中立の
第三者である公証人が見聞した事実について作成
した報告書(公正証書)である(公証人法 1 条,
同 35 条)。裁判所が関与しないため,厳密には証
拠収集手続ではない。公証人が現場において,自
らの感覚作用によって,直接に,認識し体験した
事実を記載するため26,裁判所が行う検証に類似
し,当該公正証書は検証調書の性格を有するもの
であるとされている。事実実験公正証書では,物
件の形状,構造,動作説明,作用効果などについ
て事実実験をし,公正証書にすることができるた
め,大型装置や機械を使った生産方法の特許など
の侵害を証明するために極めて有効な立証手段に
なり得る27。一方で,公証人が直接見聞できない
化学物質の生産方法の特許やプログラムのソース
コード等については,そのままでは事実実験公正
証書が作成できない。
事実実験公正証書の作成は,裁判所が行う検証
に類似し,当該公正証書は検証調書の性格を有す
るものである28。また,公正証書は,日本や諸外
国での訴訟において高度の証明力を有しており29,
それを利用した証拠方法は極めて有効な手段にな
り得る。しかし,公証人が被疑侵害者の工場など
で事実実験を行う場合には,被疑侵害者の承諾が
必要となるので,現行制度下では事実実験公正証
書のみを利用して被疑侵害者の工場などで証拠収
集をすることは困難である30。

論 文
22 特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3
4.証拠提出の必要性を判断するため
のインカメラ手続の導入
(1)問題の所在
前述のように,裁判所は,特許権者側から書類
提出命令・検証命令の申立てがあった場合,①侵
害行為の立証に必要であり(証拠調べの必要性),
②被疑侵害者側においてそれを拒むことができる
「正当な理由」がなければ(提出義務の存在),書
類の提出や検証物の提示,検証の受忍を命じるこ
とができるとされている。そして,探索的申立て
排除の観点から,証拠提出の必要性(証拠調べの
必要性)があるといえるためには,特許権者側で
「侵害であることを合理的に疑しめるだけの手が
かりとなる疎明」をする必要がある。そして,特
許権者やその代理人は,直接対象書類や検証目的
を見ることはできないため,「侵害であることを合
理的に疑しめるだけの手がかりとなる疎明」は,
外部から入手可能な間接証拠(例えば,特許発明
が工場の中で行われる方法の発明であれば,製品
として売られている物に残されたその方法の痕跡
など)によって行っていく必要がある。しかし,
特許権者にとって間接証拠がどの程度入手可能か
は,事案によりまちまちであり,特許権者が 大
限度の努力を尽くしたとしても,「侵害であること
を合理的に疑しめるだけの手がかりとなる疎明」
をすることが困難な場合もある31。また,裁判所
自身も,当該書類・検証目的を直接見ることがで
きないため,上述の間接証拠から「侵害であるこ
とを合理的に疑しめる手がかりとなる疎明」がな
されているかを判断しなければならないという点
も問題であろう32。
(2)提出の必要性を判断するインカメラ手続
紛争処理システム強化案では,証拠提出の必要
性(証拠調べの必要性)を判断するインカメラ手
続の導入が提案されている。証拠提出の必要性の
判断にあたっては,当該証拠が侵害を証明するた
めにどの程度役に立つか(証拠価値)が極めて重
要である。しかし,現行制度では,インカメラ手
続は「正当な理由」の判断の目的でのみ許されて
おり(特許法 105 条 2 項),証拠提出の必要性(証
拠調べの必要性)の判断を目的としてインカメラ
手続を行うことは許されず,インカメラ手続によ
って証拠価値を確認することはできない。提出必
要性の判断のためのインカメラ手続を導入すれば,
外部から入手可能な間接証拠が乏しく「侵害であ
ることを合理的に疑しめるだけの手がかりとな
る」レベルの疎明が難しい事案についても,特許
権者が一定程度侵害の疑いを示せば,裁判所がイ
ンカメラ手続により直接当該書類や検証目的を検
分し,被疑侵害者が特許発明に属する構成や方法
を用いているか判断できるようになるのではない
だろうか。結果として,裁判所が証拠提出の必要
性(証拠調べの必要性)について,より正確に判
断できるようになり,侵害を証明するために真に
有用な書類や検証目的について,書類提出命令・
検証命令を出しやすくなることが期待される。
(3)民事訴訟法のインカメラ手続との関係
民事訴訟法の文書提出命令・検証命令における
インカメラ手続(民事訴訟法 223 条 3 項)はあく
までも民事訴訟法 220 条 4 号所定の除外事由認定
のための手続であり,「証拠調べの必要性」の判断
を目的としてインカメラ手続を行うことは明文の
規定に反し許されないと考えられている33。した
がって,特許法の書類提出命令・検証命令におけ
る証拠提出の必要性(証拠調べの必要性)の判断
のためのインカメラ手続を導入することは,民事
訴訟法のインカメラ手続との整合性の観点からの
検討が必要となるように思われる。通常の民事訴

論 文
特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3 23
訟における文書提出命令の判断における「証拠調
べの必要性」は,文書の表示・趣旨から形式的に
されれば足りる場合が多く,また疑わしい場合に
はその必要性を認めれば足りると考えられるため,
インカメラ手続を用いる必要はないとされている34。
それに対して,侵害の立証のための書類提出命
令・検証命令における「証拠調べの必要性」は,
文書の表示・趣旨から形式的に行えるようなもの
ではなく,当該書類や検証目的により,被疑侵害
者が特許発明に属する構成や方法を用いているこ
とが明らかになるかどうかの判断が必要になって
くるため,インカメラ手続を使う必要性は高いと
いえ,検討にあたってはこのような特殊事情も考
慮するべきであろう。
(4)特許権者への意見聴取のための開示
提出必要性判断のためのインカメラ手続を導入
する場合,現行の特許法 105 条 3 項と同様に,裁
判所の裁量により当事者,特に申立人(特許権者)
に書類や検証目的を開示して意見を聴くことがで
きるようにするべきだろうか。
インカメラ手続で提示された書類・検証目的を
裁判所が検討した結果,特許発明と明らかに異な
る構成を被疑侵害者が用いていると認められる場
合は,それによって侵害の証明を行うことはでき
ないから,証拠提出の必要性は無いと考えられる。
一方で,明らかに特許発明に属する構成を被疑侵
害者が用いていると認められる場合には,証拠提
出の必要性は有ると考えられる。これらの場合に
は,インカメラ手続において申立人(特許権者)
に書類・検証目的を開示して意見を聴く必要性は
無いといえよう。
他方,インカメラ手続で書類や検証目的を検討
しても,当該構成が特許発明の技術的範囲に属す
るかどうかが裁判所において一見して明らかでな
く,その点について双方当事者に主張立証を尽く
させることが必要な事案があるといわれている35。
このような場合は,裁判所は,特許権者の訴訟代
理人等に対して当該書類・検証目的を開示し,意
見を聴いた上で,証拠調べの必要性を判断する必
要があると考えられる。
したがって,提出必要性判断(証拠調べの必要
性の判断)のためのインカメラ手続を導入する際
には,現行の特許法 105 条 3 項と同様に,裁判所
の裁量により当事者に書類や検証目的を開示して
意見を聴くことができるようにするべきであると
考えられる。その場合,書類や検証目的に被疑侵
害者の営業秘密が含まれる場合も考えられ,特許
権者や代理人に対して秘密保持命令も発令できる
ようにすることも必要である。
(5)濫用防止
特許権侵害訴訟は,競業企業間で争いになるこ
とが多く,立証主題が営業秘密に直結することも
多い。そのため,当該営業秘密を知ること自体を
目的とする濫用的な,また,確たる証拠に基づか
ない探索的な,書類提出・検証目的提示の申立て
がされる可能性がある。そのような,濫用的・探
索的申立てに対し,応訴を強いられる被疑侵害者
の不利益は大きい36。
したがって,提出の必要性を判断するためのイ
ンカメラ手続が導入されたとしても,濫用的・探
索的申立ての場合での利用を許すべきではない。
濫用的・探索的な申立てが払拭される程度に,侵
害行為の存在を疑うことが合理的であることを裁
判所に示さなければインカメラ手続を行わないな
ど,濫用を防止する仕組みが必要になるものと思
われる。

論 文
24 特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3
(6)小括
以上のように,濫用防止措置等の検討は必要で
あるが,証拠提出の必要性の判断のためのインカ
メラ手続を行うことができるようにすることによ
り,侵害を証明するために真に有用な書類や検証
目的について,書類提出命令・検証命令を出しや
すくなることが期待される。
なお,この制度は,著作権侵害訴訟等,他の知
的財産権の侵害訴訟での導入の検討も必要である
ように思われる。現行著作権法における,著作権
侵害を証明するための書類提出命令(著作権法
114 条の 3 第 1 項)は,特許法と同様,「正当な理
由」判断のためのインカメラ手続は認められてい
るが(同条 2 項,3 項),証拠提出の必要性の判断
のためのインカメラ手続は認められていない。例
えば,プログラムは,特許権だけでなく,著作権
としても保護されており,著作権侵害訴訟で争わ
れることも多い。著作権侵害の証明のために,被
疑侵害者側ソフトウエアのソースコードが必要に
なることもあり,しばしばソースコードについて
書類提出命令がされる。このような場面では,証
拠提出必要性判断のためのインカメラ手続がある
ことにより,裁判所が証拠提出必要性についてよ
り正確に判断を行い,著作権の実質的保護につな
がるのではないだろうか。したがって,著作権侵
害訴訟についても,証拠提出必要性の判断のため
のインカメラ手続の整備を検討することが望まれ
る。
5.欧州における第三者証拠収集手続
(1)序論
次に,中立的な第三者が関与する証拠収集手続
(第三者証拠収集手続)を検討する。本章では,
その前提として,ドイツの査察制度と,フランス
のセジー・コントルファソン(saisie-contrefaçon)
を概観する。ドイツとフランスは,我が国と同じ
大陸法系に属し,また,訴訟の相手方に対して情
報や証拠を提供する義務は無いという原則(Nemo
contra se edere tenetur)を出発点としており,英米
法の国のような広範な証拠収集手続を有していな
い。また,ドイツの民事訴訟法は,我が国の民事
訴訟法の母法でもある。したがって,ドイツ及び
フランスの第三者証拠収集手続は,我が国での制
度検討の参考になり,有益な示唆を得ることがで
きると思われる。
(2)ドイツの査察手続
ア.制度の概要
ドイツにおける第三者証拠収集手続である査察
手続は,特許権者等が,侵害の主張・証明をする
ために,特許権者の申立てにより,裁判所が任命
する守秘義務を有する専門家(以下,「専門家」と
略す。)が,被疑侵害者側の有する証拠を査察し,
特許権侵害の有無についての専門家意見書を作成
する手続である37。
ドイツ特許法(以下,「PatG」と略す。)140c 条
は,特許権者は被疑侵害者に対して「書類の提供,
物品の検査,又は特許の対象である方法の検査を
請求することができる」権利(検査請求権,文書
提示請求権)を有することを定めており(同条 1
項),特許権者は検査請求権等に基づいて証拠を収
集することができる。この検査請求権等は,PatG
の他にも,ドイツ著作権法(以下,「UrhG」と略
す。)101a 条にも規定されている。また,ドイツ
意匠法,ドイツ商標法,ドイツ実用新案法,ドイ
ツ種苗法,ドイツ半導体保護法にも同様の規定が
あり38,これらの権利の侵害の訴訟においても,
検査請求権等によって証拠収集を行うことができ
る。ドイツの査察手続の利用率は,特許権侵害訴
訟全体の 5~10%程度であると言われており39,そ

論 文
特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3 25
れほど高くはない。
ドイツが 2008 年に PatG140c 条等を制定した契
機となったのは, 2004 年 4 月 29 日に「知的財産
権の行使を確保するための手段及び手続に関する
EC 指令」(2004/48/EC)(以下,「EC エンフォースメ
ント指令」と略す。)が出され,EU 加盟国に強力
な証拠収集手続の導入が求められることになった
ことである(同指令 6 条,7 条)。しかし,ドイツ
の知的財産権侵害訴訟では,PatG140c 条等の制定
以前から,ドイツ民法(BGB)809 条(検査請求
権),BGB810 条(文書提示請求権)の規定に基づ
く証拠開示の実務が行われてきた。かつて,ドイ
ツ連邦通常 高裁判所は,特許権侵害事件におけ
る BGB809 条の行使には,「権利侵害の高度の蓋
然性」が立証されなければならない旨判示した上
で,検査の方法として被疑侵害物件の分解までは
認めないとする決定を行った(Druckbalken 事件)40。
そのため,検査請求権の行使による証拠収集は,
実務上有用とはいえない状況にあった。しかし,
2002 年,ドイツ連邦通常 高裁判所は,Faxkarte
事件(ソフトウエア著作権の侵害においてソース
コードの開示が求められた事件)において,検査
請求権の行使の可否の判断は,「権利侵害の蓋然性
の程度」だけでなく,権利侵害を主張できる他の
可能性,被疑侵害者の正当な秘密保持の利益への
侵害や,かかる侵害が守秘義務を負った第三者の
介入によって除去されるかという点も考慮されな
ければならないとし,また,検査請求権の制限は,
特許権者と被疑侵害者との利益衡量によることを
示した41。この決定は,BGB809 条の検査が認めら
れる要件を事案に応じて緩和し,かつ,検査方法
として,被疑侵害物件の分解調査をすることを可
能としたものと解されている42。これをきっかけ
として,検査請求権等の行使による証拠収集が広
く行われるようになった。
検査請求権等は,仮処分でも本案訴訟のどちら
でも請求できる(PatG140c 条(3))が,実務では,
相手方無審尋でかつ迅速に手続を行うことのでき
る仮処分によることが一般的である。また,提訴
前だけでなく,提訴後においても行使することが
可能である。実務上,検査請求権等の行使(査察
手続)は,独立証拠調手続(本案訴訟提起前に行
う証拠調べ類似の手続)43(ドイツ民事訴訟法
(ZPO)485 条)の申立てと,検査請求権等を被
保全権利とする仮処分(ZPO935 条,同 940 条)
による受忍処分の申立てを同時に行う手続(デュ
ッセルドルフ手続)によって行われることが多く,
本稿でも,デュッセルドルフ手続について検討す
る。
イ.査察手続の申立て
査察の申立人は,特許権侵害訴訟を提起し得る
者であり,具体的には,登録のある特許権者,独
占的ライセンシー,非独占的ライセンシー等がそ
れに該当する44(以下,代表例として特許権者を
考える)。一方,被申立人は,被疑侵害者(直接侵
害者,間接侵害者,共同侵害者等)に限られてお
り(PatG140c 条(1)),第三者に対する査察は認
められない45。
査察の対象は,被疑侵害物件又は被疑侵害行為
に使われている物件である(以下,「査察対象物件」
という。)。裁判所は,査察の申立てに対して,査
察の対象(技術的特徴等)や方法(目視による検
査,機械の操作等)と,本案での訴額に応じた保
証金の金額等を決定し,査察命令を発する46, 47。
ウ.査察が認められるための要件
査察請求が認められるためには,申立人(特許
権者)は,①被疑侵害者が特許発明を実施してい
ることが十分疑われること(侵害の十分な可能性)

論 文
26 特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3
と,②特許権者等が訴訟上の請求を理由づけるた
めに必要であること(手続の必要性)の二点を疎
明すること,そして,③査察の請求が,当該事案
において均衡を失したものでないこと(比例性)
が必要である48。
「侵害の十分な可能性」は,一定程度の可能性
で特許権侵害が起こっている蓋然性があることを
指し示す明確な徴候があることであり,単に特許
権侵害に関して何らかの可能性があるだけでは足
りないとされている49。
次に,「手続の必要性」は,特許権者にとって,
証拠を入手するための,より簡易な他の方法が存
在しないことである50。例えば,市場で自由に入
手可能な被疑侵害品について査察を行うことは認
められない。
「比例性」は,申立人と被申立人(被疑侵害者)
との間の利益衡量によって判断される。具体的に
は,査察を実施することによる被疑侵害者の被害
の程度(被疑侵害者所有物の破壊や分解を伴うか
等),被疑侵害者が特許を侵害している可能性の高
さ,特許が無効になる可能性の高さ,適切な手段
によっても守ることのできない被疑侵害者の営業
秘密の価値などが考慮される51。
また,査察を仮処分で行う場合は緊急性の要件
が必要52であり,独立証拠調べ手続を同時に申し
立てる場合にはその要件も必要である53。
エ.査察の執行と結果の利用
査察は,裁判所によって選任された,弁理士や
大学教授等からなる,守秘義務を負った専門家(以
下,「技術専門家」という。)が執行する(ZPO404
条)。査察の執行は,①技術専門家が,被疑侵害物
件の所在場所に赴き,被疑侵害物件の調査を行っ
た上,その結果に基づいて,侵害がされているか
どうかについて専門家意見書を作成し,裁判所に
提出する手続,②提出された専門家意見書を申立
人である特許権者に交付するかどうかを裁判所が
決定する手続,の二段階で行われる54。仮処分の
場合,被申立人(被疑侵害者)は査察を行うこと
を事前に知らされていない55。被疑侵害者が査察
への協力を拒否する場合,専門家は,裁判所から
捜索令状を取得して,執行官や警察官の助力を得
て,査察の執行現場(被疑侵害者の敷地等)に立
入ることができる(ZPO892 条,同 758a 条)。
専門家は,被疑侵害物件の査察にあたり,観察
に加えて,侵害を確認するために必要なあらゆる
手段を用いることができる56。例えば,写真・ビ
デオの撮影57,対象物件の長さや重さ等の計測,
対象方法の実施や文書のコピー等ができ,事案に
よっては,パスワード入力を含む工場機械の操作,
機械の分解,対象物の破壊,分析のためのサンプ
ルの採取58やプログラムのソースコードの取得59
等が認められる。ただし,査察手続では,専門家
意見書作成の目的を超えて,証拠物の差押え等を
することはできず,その点で後述するフランスの
セジー・コントルファソンとは異なっている。ま
た,条文上は,商業的規模の侵害が行われた場合
には,銀行,財務又は営業関係資料も査察の対象
となることが規定されているが(PatG140c 条(1)
後段),実務上は,権利侵害が明白な事案で無い限
りこれらの書類については査察の対象とはならな
いと考えられている60。
被疑侵害者が査察を拒否したり,又は対象物件
を変更,隠匿,破棄したりした場合には,刑事罰
の対象となる(ZPO890 条)。また,裁判所は,証
明妨害として査察の申立人の主張する事実が証明
されたものと見なすことができる(同法 371 条 3
項)。
専門家から専門家意見書を受領した裁判所は,
被疑侵害者側の意見を聴取した上で,申立人であ

論 文
特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3 27
る特許権者やその代理人に専門家意見書を交付す
るか否かを決定する。
査察の結果申立人(特許権者)に交付された専
門家意見書は,本案訴訟における証拠として用い
ることができる(ZPO493 条,同 411 条)し,別
訴で利用することも可能である(同法 411a 条)。
オ.被疑侵害者の営業秘密の保護
被疑侵害者は,査察対象が自己の営業秘密を含
むことを理由に,査察手続を拒否することはでき
ないが,査察手続では,営業秘密保護のために以
下のような運用がされている。
まず,申立人(特許権者)は査察の執行現場に
立会うことができない。また,申立人(特許権者)
の代理人の立会いは,裁判所から守秘義務を課さ
れていることを条件に認められるが,そこで得た
事実の全てについては,守秘義務により,申立人
(特許権者)に開示することができない61。更に,
被申立人(被疑侵害者)の営業秘密への侵害が大
きく特許権侵害の蓋然性が低い場合には,申立人
の代理人の立会い自体が認められないこともある62。
次に,申立人(特許権者)への専門家意見書の
交付は,専門家意見書を得ることによる申立人(特
許権者)の利益と営業秘密を保持する被申立人(被
疑侵害者)の利益を比較衡量することで決せられ
る。専門家意見書に営業秘密が含まれていても,
裁判所が特許を侵害しているとの心証を持った場
合には,申立人(特許権者)の利益が優先され,
専門家意見が交付される。侵害事実とは無関係の
営業秘密は,黒塗りの上開示される等の方法によ
り守られる。一方で,裁判所が特許を侵害してい
ないとの心証を持った場合は,営業秘密保護の利
益が優先され,申立人(特許権者)に専門家意見
書は交付されない63。
他方,申立人(特許権者)の代理人である弁護
士・弁理士は,通常秘密遵守義務が課されている
ため,代理人への交付では,特段の事情の無い限
り直ちに認められる64。
このように,査察手続では,特許権者の査察へ
の立会いの制限と,専門家意見書の引き渡しの制
限という仕組みにより,被疑侵害者の営業秘密を
保護するとともに,特許権者の代理人には原則と
してアクセスを認めることにより,被疑侵害者側
の手続権とのバランスをはかっている。
カ.濫用防止措置
前述のように,裁判所が出す査察命令は,査察
の手段や対象の技術的特徴等,査察の範囲を様々
な面で制限するものとなっている65ため,探索的
な証拠収集を行うことはできない。また,査察命
令の発令には,侵害の十分な可能性の疎明が必要
であり,特許異議事件等が係属している場合は,
特許の有効性について主張・疎明することが必要
とされる66。さらに,査察の申し立てにあたって
は,保証金の供託が求められることがある。
提訴前に査察を行う場合であっても,申立人(特
許権者)は,査察後に,訴訟を提起することは義
務付けられていない。しかし,被申立人(被疑侵
害者)は,申立人(特許権者)側に対して,本案
訴訟提起の期限を設けることを請求することがで
きる(ZPO494a 条(1))。そして,その期限が守
られず,訴訟が提起されなかった場合,被申立人
(被疑侵害者)が手続で被った費用を申立人(特
許権者等)に負担させることができる67。
さらに,査察手続後に本案訴訟で被疑侵害者側
が勝訴した場合等には,被疑侵害者は特許権者に
対して査察手続によって被った損害の賠償を請求
することができる(PatG140c 条(5))。賠償を請
求できる損害は,査察手続と相当因果関係のある
ものに限られており,例えば,弁護士費用や,査

論 文
28 特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3
察により製品を生産することが妨げられたことに
より失った利益等の請求をすることができる68。
このように,査察手続は,命令発令における裁
判所の関与,発令の要件,保証金,訴訟提起期間
の制限や被疑侵害者の損害賠償請求権などがあり,
濫用防止のための機能を果たしているように思わ
れる。
キ.査察制度に対する評価
ドイツでは,査察手続は概ね高く評価されてい
る一方で,次のような批判もされている。まず,
査察結果を開示するかどうかの検討においては,
事実上特許権侵害が議論されるにもかかわらず,
申立人(特許権者)の代理人は査察の結果を申立
人(特許権者)に開示し,それに基づく申立人か
らの情報提供を受けられないという問題が指摘さ
れている69。また,別の観点として,査察につい
ては,本案訴訟とは別の手続で行われるため,特
に侵害訴訟係属後に査察が行われる場合に訴訟関
係が煩雑化するとの指摘がある70。
(3)フランスの第三者証拠収集制度
ア.制度の概要
フランスの特許権侵害訴訟では,セジー・コン
トルファソン(saisie-contrefaçon,以下,「セジー」
と略す。)と呼ばれる証拠収集手続を利用すること
ができる。特許権者等が,特許権の侵害事実を立
証するために,侵害物の調査,確認を行い,又は,
侵害物そのものや,侵害物や侵害方法に関する文
書を差し押さえる手続である71(フランス知的財
産法典 L615-5 条72)。特許権の他,商標権(同法
典 L716-7 条),著作権(同法典 L332-1~4)等に
関する訴訟でも,セジーによって証拠収集するこ
とができる。セジーの利用率は,大変高く,知的
財産権侵害訴訟の 80%にのぼるとされている73。
セジーによる証拠収集は,裁判所命令に基づき,
特許権者によって選任された執行士(huissier de
justice)74が主体となって執行する。執行士は,各
種の専門家(特許権者側の弁理士,写真家,鍵屋,
IT エンジニア,警察官等)を補佐として同行する
ことができるが,それらの専門家は執行士に代わ
って証拠を収集することはできない。
イ.セジーの申立手続と裁判所命令
セジーの申立ては,特許権者側が裁判所の命令
書の案文を作成し,弁護士を通じて裁判所に提出
することにより行われる。セジーを申し立てるこ
とができる者は,侵害訴訟を自ら提起できること
ができる者であり,具体的には,特許権者や独占
的ライセンシー75(以下,代表例として特許権者
を考える。)がそれに該当する。
一方,セジーの対象となる相手方は,被疑侵害
者(直接侵害者,間接侵害者)である76。また,
直接侵害や間接侵害にかかわっていない第三者で
あっても,侵害に係る証拠が発見されうる場合,
セジーの対象となる。例えば,薬やその製造方法
に関する特許の侵害で,薬の販売許可を出してい
るフランス医薬品安全庁(AFFSAPS)は,成分や
製造方法を証明するのに有効な審査書類を保管し
ていることもあるため,フランス医薬品安全庁が
セジーの対象になることもあり得る77。
セジーは,本案訴訟提起前に被疑侵害者無審尋
で行われる。また,本案訴訟中に,追加証拠提示
のために行うことができることも判例上認められ
ている78。
ウ.裁判所命令発令の要件
フランスで有効な特許権を有する特許権者であ
ればよく,ドイツのように,侵害の十分性や,手
続の必要性は,セジー発令の要件とはされていな

論 文
特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3 29
い79。そのため,侵害を疎明する必要も無いし,
市場で入手可能な製品に対してセジーを行うこと
も可能である。セジーの申立てが却下されること
はほとんどないが80,裁判所は,証拠収集の範囲
を超える申立てについて,差押えの範囲を限定す
ることがある81。
エ.セジーの執行と結果の利用
執行士は,現場に赴いて,セジーの命令書の記
載に基づき,証拠収集を行う。執行士は,セジー
を執行する前に,現場において,命令書を相手方
に提示し,相手方がセジーの目的と調査範囲を理
解できるようにしなければならない82。フランス
では,何人も, 真実の顕現のために, 司法に協力
しなければならない義務(司法協力義務)があり
(フランス民法典(C.Civ)10 条),被疑侵害者は
セジーの差押手続に協力する義務がある。被疑侵
害者が協力を拒んだ場合は,警察官に協力を要請
することができる83。また,証拠を隠蔽した場合
や,証拠収集を妨害した場合については,罰金や
懲役を命じられたりしたケースもあったようであ
る84。
執行士による証拠収集方法は,「詳細な記述」を
差し押さえるための「記述的差押え(saisie de-
scription)」及び「現物等」を差し押さえる「現実
の差押え(saisie réele)」である85。「記述的差押え」
は,執行士が,現場で目撃した侵害物,侵害方法
及び関連文書(発明に関する技術文書の他,カタ
ログ,広告,経理書類等の商業的文書や発送書類,
売り上げ伝票等の商業的文書)についての調書を
作成する手続である。方法の発明の場合は,執行
士の前で製造機械等を試験的に実施させることに
より,調書にする。また,同行した専門家(弁理
士)による「詳細な調書」(descriptive report)や,
関連文書の写しが添付されることもある。「現実の
差押え」は,侵害物そのもの,侵害された方法を
可能にする機械・器具そのもの,及び関連文書そ
れ自体の差押えである。ただし,侵害を証明する
の に 必 要 な 範 囲 , す な わ ち ,「 サ ン プ ル
(échantillon)」の差し押さえが認められるにすぎ
ず,実務ではあまり使われていないようである。
その代わりに,サンプルの購入などが行われるこ
とが多いといわれる86。
セジーによって特許権者に引き渡された証拠は,
本案訴訟の他,他国の特許権侵害訴訟においても
利用することができる87。フランスの実務では,
執行士による確認調書は,公正証書偽造の申立て
(フランス新民事訴訟法典(NCPC)306 条以下)
の手続によって,確認が誤りであったという立証
がなされるまでは真性なものとして扱われるため,
高い証明力を有する88。そのため,執行士による
確認調書の作成は,事実上,裁判官による検証を
代行している側面を有しているとされている89。
オ.被疑侵害者の営業秘密の保護
裁判長は,被差押人の請求に基づき,セジーに
おいて,秘密保持のためのあらゆる措置をとるこ
とができる(フランス知的財産法典 R615-4 条)。
セジーにおいては,侵害に関連する書類等であれ
ば,侵害と無関係な営業秘密が含まれていたとし
ても差押の対象となる。ただし,被疑侵害者から
営業秘密であるとの申し出があった場合,執行士
は,封筒(enveloppe scellée)に対象物を封印し,
執行後,執行士や書記官(greffier)が保管する。
その後,裁判所にて,裁判官の命令により,中立
の専門家が中身を確認し,侵害の立証に必要な書
類であるか,営業秘密が含まれているかなどを確
認・仕分けする。
申立人(特許権者)は,セジーの執行に立ち会
うことはできない。また,封印・保管されたもの

論 文
30 特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3
には専門家による確認・仕分けまでアクセスでき
ないし,確認・仕分け手続に立ち会うこともでき
ない。一方,侵害に関係あることがわかった場合
は,侵害に無関係な営業秘密は黒塗りの上,申立
人(特許権者)が当該情報を受け取ることができ
る。申立人(特許権者)の代理人は,秘密を遵守
するという条件の下で専門家による確認手続に立
ち会うことができる。
このように,フランスでは,証拠の収集に執行
士や専門家という中立の第三者が関与することが,
被疑侵害者の営業秘密の保護に一定の役割を果た
している。
カ.濫用防止措置
セジーは,要件が緩やかであるため,脅迫目的
や産業スパイ目的で利用(濫用)されるようにも
思われるが,現実に濫用されるケースは少ないと
されている90。それには,以下の制度が関係して
いるものと思われる。
まず,申立人(特許権者)は,セジー終了後,
所定期間内(20 営業日又は 31 暦日のいずれか長
いほう)に訴訟を提起することが義務付けられて
いる91。特許権者が期間内に訴訟を提起しないと,
差し押えが無効になり,収集した証拠は使用でき
なくなる他,被疑侵害者からセジーで被った損害
賠償を請求される。そのため,訴訟目的でなく被
疑侵害者の情報だけを入手するためだけにセジー
を利用することは難しくなっている。
次に,担当裁判官は,セジーが濫用されないよ
うに,セジーの範囲が限局されたものになってい
るか,常に注意を払っている92。セジーを実施す
る執行士や専門家は,自分たちの依頼者である申
立人(特許権者)が責任を問われないよう,裁判
所命令の範囲内でセジーを執行する93。このよう
に裁判官や執行士の第三者の関与があることが,
セジーにおいて濫用的な証拠収集を難しくしてい
るように思われる。また,被申立人(被疑侵害者)
は,裁判所命令の撤回や修正を求めて,不服申立
てすることもできる。
さらに,セジーが濫用された場合(例えば,営
業秘密の取得のみを目的として行われた場合等),
被申立人(被疑侵害者等)はセジーによって被っ
た損害についての損害賠償を請求することができ
る(C.Civ.1382 条)。また,裁判所は,証拠収集の
実行の際に,被申立人(被疑侵害者等)が被る損
害の賠償の担保のために,十分な保証金を供託す
るように申立人である特許権者に命じることがで
きる。このように,フランスでは,保証金や損害
賠償請求に加えて,裁判所の関与,中立の第三者
によって執行されることによって,セジーの濫用
を防止しているように思われる。
(4)ドイツ及びフランスの制度のまとめ
ドイツ及びフランスのいずれにおいても,特許
権侵害訴訟や著作権侵害訴訟等において,中立の
第三者による証拠収集手続が存在する。当該手続
では,被疑侵害者が協力を拒否する場合には,警
察による助力も含む直接強制が可能である。直接
強制の背景になる根拠としては,ドイツでは検査
請求権があるのに対して,フランスでは司法協力
義務がある。
両国における第三者証拠収集手続は,本案提訴
前・本案提訴後のどちらにおいても利用可能であ
り,提訴前の第三者証拠収集手続では,被疑侵害
者の審尋は行われない。フランスでは,ドイツと
比較して第三者証拠収集手続の許可要件が緩やか
であり,フランスでは多くの特許侵害訴訟でセジ
ーが使われていることにつながっているように思
われる。
証拠収集の主体となる中立の第三者については,

論 文
特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3 31
ドイツでは,裁判所任命の弁理士等の技術専門家
である。それに対して,フランスでは,当事者に
選任された執行士であり,弁理士等の技術専門家
が執行士を補佐する。証拠収集の対象物について
は,ドイツでは,調書(専門家意見書)に限られ
ている。これに対して,フランスでは,調書(執
行士報告書,専門家調書等)に加えて,関連文書
や被疑侵害品の差押えも可能である。
営業秘密の保護の点については,両国とも,中
立の第三者が証拠収集を行うことにより,特許権
者自身が被疑侵害者の営業秘密に直接アクセスす
ることを制限している。一方,特許権者の代理人
は,両国において,秘密保持を遵守する条件で営
業秘密を含む証拠へのアクセスが認められており,
営業秘密の保護と特許権者の手続保障とのバラン
スが図られていると評価できる。
査察(独) セジー(仏)
裁判所命令発令の要件
・侵害の十分性 ・手続の必要性 ・事案における均衡
・有効な特許権
市場で入手容易なものの
証拠収集 不可 可能
時期 本案提訴前・本案提訴後 本案提訴前・本案提訴後
被疑侵害者の審尋 提訴前は不要 提訴前は不要
執行者 裁判所任命の弁理士・大学教授等から
なる専門家 特許権者が選任した執行士
※専門家による補助有り
直接強制 有 有
証拠収集の内容 専門家意見書の作成
報告書の作成 被疑侵害品等の差押え 関連する書類(商業的文書を含む)の
差押え
特許権者の執行への
立会い 認められない 認められない
特許権者代理人の
執行への立会い 認められる(守秘義務付)
特許権者の弁理士が専門家として同行
可能。
特許権者の
営業秘密を含む文書への
アクセス
秘密保持の利益と証拠価値を衡量 現場で封緘の上,中立の専門家が侵害
と関連性があるかを確認。
特許権者代理人の
営業秘密を含む文書への
アクセス
認められる(守秘義務付) 秘密保持の遵守の下,裁判所の仕分け
手続に立ち会うことは可能。
濫用防止措置
・保証金の供託
・被疑侵害者に対する損害賠償
・被疑侵害者の申立てにより本案提訴
期間の制限
・認められるための要件で侵害の十分
性を考慮
・保証金の供託 ・被疑侵害者に対する損害賠償 ・一定期間内の本案提訴の義務付け ・裁判官が証拠収集範囲を制限

論 文
32 特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3
手続の濫用の防止については,両国のいずれに
おいても,申立における保証金の供託,被疑侵害
者側による損害賠償請求権等の規定,本案訴訟の
提訴期間の制限(フランスの場合は法令により,
ドイツの場合は被疑侵害者の申立てによる。)があ
る。また,査察やセジーの対象の特定,裁判所の
審査や,中立の第三者による命令の執行は,濫用
の防止に役に立っているものと考えられる。
6.中立の第三者が証拠収集に関与す
る制度の導入について
(1)査察制度導入の見送りについて
本章では,紛争処理システム強化案でで提案さ
れている,中立の第三者が証拠収集に関与する制
度について,ドイツやフランスの制度も踏まえつ
つ,若干の検討を行いたい。同強化案では,ドイ
ツの査察やフランスのセジーのような,強制力を
有する第三者証拠収集制度の導入については見送
られる方向である。そして,同強化案では,「日本
の民事訴訟制度の枠組みに沿った形で」第三者が
証拠収集手続に関与することを提案している。
ドイツやフランスの第三者証拠収集手続は,直
接的な強制力を有する点で,特許権者の証拠収集
をより容易にする点で魅力的であるが,一方で,
日本においてそのままの形で導入することには,
以下のような疑問がある。
まず,我が国において,直接強制により証拠収
集できるのは,真実発見の要請の強い刑事訴訟の
領域に限定されていることである。特許権侵害訴
訟の究極の目的は,当事者間の紛争の解決であり,
刑事訴訟と同程度の真実発見の客観的要請がある
とはいえない。次に,紛争処理システム案でも指
摘されていたように,ドイツ等で直接強制ができ
る根拠規定に対応する我が国の規定が無いことで
ある。前述のように,ドイツでは,検査請求権
(BGB809 条)を発展させる形で直接強制を伴う
査察手続が認められてきたが,日本の民法では,
BGB809 条に対応する検査請求権は規定されてい
ない。フランスでは,司法協力義務(C.Civ.10 条)
がセジーの直接強制を支える根拠になっているよ
うであるが,日本には,フランスのような司法協
力義務の規定は無い94。このような点を踏まえる
と,我が国において直接強制可能な第三者証拠収
集手続を導入することは,我が国における現行の
民事法の枠内では難しいように思われる。
(2)訴え提起後の証拠収集手続について
ア.紛争処理システム強化案の検討
紛争処理システム強化案では,訴え提起後の証
拠収集手続について,「日本の民事訴訟制度の枠組
みに沿った形で中立的な第三者の技術専門家が証
拠収集手続に関与する制度を導入すること」を提
案している。また,その具体的方策として,(Ⅰ)
書類提出命令及び検証物提示命令における書類及
び検証物の提出義務の有無を判断するための手続
(インカメラ手続)において,裁判官に技術的な
サポートを行うことを可能にすることや,(Ⅱ)鑑
定人に検証の際の鑑定における秘密保持義務を課
すことで,同手続を秘密保護に配慮した形で行う
ことを可能とすること,を例示している。
まず,(Ⅰ)については,現行制度でも裁判所調
査官による技術的サポートは行われているため
(民事訴訟法 92 条の 8 第 1 号),それに加えて別
の技術専門家によるサポートを可能にすることを
提案するものと思われる。例えば,特許権侵害訴
訟の争点整理や証拠調べでは,裁判所調査官では
まかないきれないような先端技術等の分野での知
見の提供や,当該技術分野の常識等の確認のため
に,専門委員が活用されている95が,専門委員を
インカメラ手続にも関与できるようにすることが

論 文
特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3 33
考えられる。
次に,(Ⅱ)については,侵害論の審理で,検証
や鑑定がほとんど使われていないことを踏まえ,
損害論で使われている計算鑑定のような制度を設
けたほうがよいように思われる。例えば,鑑定人
に守秘義務を課した上で,被疑侵害者の工場等で
侵害に関する状況について調査し,報告させる新
たな制度(侵害態様特定のための鑑定制度96)を
設ければ,より積極的な利用が期待できるのでは
ないだろうか。鑑定人は,裁判所に特段の制限を
課されない限り,あらゆる方法で鑑定のための必
要な資料を収集できるものとされている97。また,
鑑定の基礎資料を法廷に提出することは必ずしも
求められておらず,被疑侵害者も,対立当事者に
は開示できない資料であっても,第三者で守秘義
務を有する鑑定人へ資料を公開することは抵抗が
無い場合もあるものと思われ,被疑侵害者が書類
提出命令・検証命令を拒否している場合に代替措
置として使うことも考えられる。また,このよう
な制度は,資料として提出された書類が被疑侵害
者工場内で実施されている機械・方法に真に対応
したものであるか疑問がある場合(例えば,被疑
侵害者から提出された製造日誌等のねつ造が疑わ
れる場合98)に,鑑定人が被疑侵害者の工場等に
赴いて,工場内部での実施態様を確認することに
も使えるのではないだろうか。
なお,紛争処理システム強化案では検討対象と
なっていないが,事実実験公正証書を被疑侵害者
の工場等で作成することができるようにする案も
考えられるのではないだろうか。例えば,公証人
が技術専門家(弁理士等)を連れて被疑侵害者の
工場等に赴き,技術専門家の協力の下で事実実験
公正証書を作成できるようにすると,特許権者に
とって証拠収集の選択肢が広がるように思われる。
(3)訴え提起前の証拠収集処分について
紛争処理システム強化案では,訴え提起前の証
拠収集処分について,現行制度の任意性は維持し
た上で,日本の民事訴訟制度の枠組みに沿った形
で中立的な第三者の技術専門家が証拠収集手続に
関与する制度を導入することで,手続の更なる充
実化を図ることが適切である,とされている。ま
た,具体的な方策の例として,「秘密保持の義務を
課された第三者の技術専門家が執行官に同行して
技術的なサポートを行う仕組みを導入することが
考えられる」とされている。
フランスのセジーでは,執行士が証拠収集を行
うが,執行士は技術の専門家ではないため,専門
家である弁理士等を同行させ,その補佐を受ける。
日本の執行官も,フランスの執行士と同様,技術
の専門家ではない。そこで,フランスと同様に,
執行官が弁理士等の技術専門家の補佐を受けて証
拠収集する制度とすることが考えられる。また,
フランスにおいて執行士に同行する技術専門家が
「詳細な調書」(descriptive report)を作成し,報
告書に添付するのと同様に,日本でも,執行官が
作成する調査報告書に,技術専門家が作成する詳
細な技術説明書を添付するようにするのも一案で
はないかと思われる。
(4)著作権侵害訴訟等への導入の検討の必
要性
証拠調べに中立の第三者を関与させる制度は,
提出の必要性判断のためのインカメラ手続と同様
に,著作権侵害訴訟等,他の知的財産権の侵害訴
訟での導入の検討も必要であるように思われる。
ドイツで査察制度が本格的に始まるきっかけとな
った Faxkarte 事件がプログラムの著作権侵害事件
だったことを考えると,プログラム著作権侵害事
件の証拠袖手においても中立の第三者を関与させ

論 文
34 特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3
る制度の導入を検討することが望まれるのではな
いだろうか。
7.結びに代えて
本稿では,紛争処理システム強化案における証
拠収集手続の議論を紹介するとともに,改正の方
向が示された,①書類提出命令における提出必要
性判断のためのインカメラ手続の導入と,②提訴
前及び提訴後の中立的な第三者の技術専門家が証
拠収集手続に関与する制度の導入,について,雑
駁な検討を行った。今後,特許制度小委員会での
議論を通して,新しい制度の姿が明らかになって
いくと思われるが,制度改正により証拠収集手続
がより使いやすいものとなり,特許権侵害事件の
審理が一層充実することを期待したい。拙稿に対
して,法律家・実務家の方々からのご批判をいた
だければ幸甚である。
注)
1 特許権侵害訴訟は専用実施権者も提起できるが,ここ
では代表として特許権者が提起する場合を考えること
にする。 2 タスクフォース座長「知財紛争処理タスクフォース報
告書」(2015年5月28日),大野聖二「証拠収集手続の
強化・権利の安定性(無効の抗弁)に関する立法の動
向」ジュリスト1485号35頁(2015)。 3 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財紛争
処理システム検討委員会「知財紛争処理システムの機
能強化に向けた方向性について―知的財産を活用した
イノベーション創出の基盤の確立に向けて―」(2016年3月),横尾=八島=上山=吉井=相澤「座談会 知財
紛争(特許紛争)の課題」Law & Technology72号1頁以
下(2016),三村量一「知的財産紛争における証拠収
集手続について」ジュリスト1499号37頁(2016)。 4 知的財産戦略本部「知財推進計画2016」55頁(2016年5
月)。 5 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「我
が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて
(案)」(2017年2月)。 6 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会・前
掲注(5)3頁。 7 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会・前
掲注(5)3, 4頁。
8 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会・前
掲注(5)4, 5頁。 9 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会・前
掲注(5)5, 6頁。 10 田中成志「特許訴訟と証拠収集」自由と正義46巻9号60
頁(1995)。 11 飯村敏明=設樂隆一編著『リーガル・プログレッシ
ブ・シリーズ3 知的財産関係訴訟』32頁(青林書院,
2007)[吉川泉]。 12 制度の沿革や詳細は,中山信弘=小泉直樹『新・注解
特許法上巻』1845頁以下(有斐閣,2011)[相良由里
子]を参照。 13 中山=小泉・前掲注(12)1845頁以下。大渕哲也他編
『専門訴訟講座⑥特許訴訟下巻』1212頁[賴晋一]に
よると,実務では,通常,書類提出命令等の申立てが
された場合でも,裁判所と当事者双方で協議し,任意
に提出できるものを段階的に開示し,必要がなくなれ
ば申立てを取り下げ,なお必要な範囲についてのみ書
類提出命令の判断を行っており,さらに,裁判所が書
類提出命令等を認める場合も,その心証を開示しても
う一度任意に提出等をするように促すのが通常である
とのことである。そのため,実際に書類提出命令等が
出される件数は,少なくなっている。 14 例えば,沖中康人「書類提出命令」Law & Technology 71
号11頁,12頁(2016)で挙げられている,①裁判所が,
書類提出命令における要証事実の存在あるいは不存在
についてすでに十分な心証を得ている場合,②裁判所
が,構成要件のうちの一部について既に非充足の十分
な心証を得ている場合,③裁判所が,特許権者が主張
するクレーム解釈とは別のクレーム解釈を正しいと考
えているため,書類提出命令の要証事実では結論を左
右しない場合は,一般的に書類提出命令の必要性が無
いといえるだろう。 15 大阪地判昭和59年4月26日無体例集16巻1号248頁は,
「……右相手方に証拠の開示を強制し得るのも,結局
は右相手方がその開示(目的物の提示)に応じない場
合に,証拠申立者の該証拠に関する主張を真実と擬製
し得るだけの合理性の存する場合であるべく……その
ためには,少くとも証拠申立当事者によつて,自己の
証拠に関する主張が真実である可能性を合理的に予測
せしめ得るだけの手懸り(本件のような特許侵害訴訟
にあつては,目的物が侵害品であることを疑わしめる
だけの手懸り)となる疎明がなされなければならない
と思われるからである。」としており,髙部眞規子『実
務詳説特許関係訴訟第3版』84頁(きんざい,2016)は,
同判決を引用しつつ「相手方が提出に従わない場合に,
民事訴訟法224条1項により当該文書の記載を真実と認
めることができるだけの合理性が存することが必要で
ある。」とする。 16 沖中・前掲注(14)11頁以下。 17 沖中・前掲注(14)11頁以下。 18 特許訴訟における証拠保全手続については,田倉整=
内藤義三「特許侵害事件における証拠保全について」
自由と正義29巻4号74頁以下(1978),滝井朋子「特許
権侵害請求訴訟の対象の特定と情報請求権」日本工業
所有権学会年報20号55頁以下(1996),志賀勝「侵害

論 文
特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3 35
行為立証の容易化」牧野利秋他『知的財産訴訟実務大
系Ⅲ』435頁以下(2014)を参照。 19 秋山幹男他著『コンメンタール民事訴訟法Ⅳ』555頁(日
本評論社,2010)。 20 志賀・前掲注(18)437頁。 21 志賀・前掲注(18)436頁。 22 利害関係がある場合には鑑定人の欠格事由となり(民
事訴訟法212条2項),鑑定人が「誠実に鑑定すること
を妨げるべき事情」が存在する場合は,当事者は忌避
を申し立てることができる(同法214条)。 23 実務では,裁判所が,日本公認会計士協会の推薦名簿
に登載された候補者の中から適任者を選任し,指名す
ることが行われている。 24 座談会「知的財産訴訟の 新の実務の動向―東京地裁
知的財産部との意見交換会(平成13年度)―」判例タ
イムズ1095号4頁,14頁(2002年)[三村量一発言]。 25 飯村・設樂・前掲注(11)32頁。 26 森林稔「公証制度と知的財産」公証法学(26)1頁以下
(1997)。 27 岡口基一「論叢 知的財産権事件と公証実務」公証128
号8頁以下,9頁(2000)。知財高判平成23年6月23日判
例時報2131号109頁では,食品の包み込み成形方法の
特許の侵害が問題となった事案で,控訴審において原
告から提出された事実実験正証書に基づいて被告製品
の構成を認定し,特許権非侵害とした第一審判決を取
り消した。 28 棚町祥吉「工業所有権の証拠保全と公証制度」公証法
学22号47頁以下(1993),森林・前掲注(26)参照。 29 公正証書は,ハーグ条約(外国公文書の認証を不要と
する条約)における公文書として扱われる。 30 西田美昭他編『民事弁護と裁判実務⑧知的財産権』77
頁(1998)[島田康男]。 31 知財高判平成28年3月28日判例タイムズ1428号53頁
(2016)。 32 知財高判平成28年3月28日・前掲(31)(以下,「本件
判決」という。)は,書類提出命令の必要性判断にお
いて,原判決(東京地判平成26年12月25日裁判所HP参照(平成24年(ワ)第11459号))と結論が異なった事
例である。原判決は,特許権者の証拠提出の状況を含
む弁論活動から「探索的に本件申立てをしたものと推
認されてもやむを得ない」とし,証拠調べの必要性を
欠くものと判断したが,当該判決は,立証上の困難の
配慮等から,証拠調べを認めた。 33 秋山他・前掲注(19)464頁。 34 秋山他・前掲注(19)464頁。 35 髙部・前掲注(15)91頁は,このような事例について,
特許法105条1項の「正当な理由」の有無をインカメラ
手続で判断する場合,正当な理由があるかどうかにつ
いてインカメラに係る文書を開示して当事者の意見を
聴くことが必要であり,105条3項の場合にあたる,と
する。 36 知財高判平成28年3月28日・前掲(31)の解説参照。 37 ドイツの査察制度については,菊地浩明「欧州知的財
産訴訟の 新事情 ドイツ特許法改正とクロスボーダ
ー訴訟の現在(上)」判例タイムズ1310号23頁以下
(2010),春日偉知郎「インカメラ手続による秘密保
護の新たな展開」判例タイムズ1343号64頁以下(2011),
クラウス・グラビンスキー(三村量一=渡邉瑞訳)「ド
イツ特許訴訟における査察命令及び証拠収集手続の概
要」Law & Technology59号45頁以下(2013),設樂隆一
「知的財産高等裁判所の10年間の歩みと特許権侵害訴
訟の国際的比較を踏まえた今後の展望」判例タイムズ
1412号46頁以下(2015),特許第2委員会第5小委員会
「侵害の立証が困難な権利の活用を図る―『訴訟提起
前の証拠収集制度』に関する一考察」知財管理65巻11号1487頁以下(2015),三村量一「知的財産侵害訴訟
における証拠収集手続上の課題」自由と正義67巻2号24頁以下(2016),一般財団法人知的財産研究所『知財
紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に
関する調査研究報告書』166頁以下(2016),加藤朝道
「侵害訴訟改革の提言―ドイツを参考に―」パテント
70巻1号88頁以下(2017),の各々の文献で紹介されて
いる。 38 ドイツ意匠法46a条,ドイツ実用新案法24c条,ドイツ商
標法19a条,ドイツ種苗法37c条,ドイツ半導体保護法9条2項参照。
39 一般財団法人知的財産研究所・前掲注(37)176頁。 40 BGHZ 93,191=GRUR 1985,512. 41 BGHZ 150,377=GRUR 2002,1046.,服部誠「民事実体法
に基づく検査請求権の意義を拡大したドイツ連邦通常
高裁判所判決 Bundesgerichtshof 02.05.2002, I ZR 45/01-Faxkarte」Law & Technology 22号129頁以下(2004)。
42 菊地・前掲注(37)25頁。 43 独立証拠調手続については,ディーター・ライポルト
(本間靖典訳)「ドイツ民事訴訟における独立証拠調
べ手続の現況」判例タイムズ1080号52頁以下(2002)を参照。
44 Thomas Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7 Aufl, 2014, Rn.363.
45 Thomas Kühnen, a.a.O.(Anm.44), Rn.364. 46 Thomas Kühnen, a.a.O.(Anm.44), Rn.365-373, 376-382. 47 菊地・前掲注(37)26頁。 48 Thomas Kühnen, a.a.O.(Anm.44), Rn.438. 49 Thomas Kühnen, a.a.O.(Anm.44), Rn.367-371 によると,
例えば,クレームの構成が,外国で販売されている対
応製品の構成や通常従わなければならない技術標準と
一致することや,広告等によってクレームの構成の一
部が知られており,製品の有する効果が残りの発明特
定事項を示唆していること,などの事実が必要となる。 50 Thomas Kühnen, a.a.O.(Anm.44), Rn.376-381. 51 Thomas Kühnen, a.a.O.(Anm.44), Rn.385-396. 52 菊地・前掲注(37)26頁によれば,緊急性は,通常の
差止仮処分ほど厳格には要求されず,侵害事実を知っ
た後数ヶ月を経過したとしても問題にならない。 53 独立証拠手続が認められる要件は,訴え提起前と訴え
提起後で異なっている。訴え提起前は,訴訟を回避す
るのに役立つ可能性があることが必要である(ZPO485条2項)。訴え提起後は,相手方当事者が同意した場合
又は証拠が失われる若しくは証拠の利用が妨げられる
一定のリスクが存在する場合に認められる。一般財団
法人知的財産研究所・前掲注(37)166頁以下。 54 Thomas Kühnen, a.a.O.(Anm.44), Rn.418 55 そのため,被疑侵害者は,弁護士等に相談するために,

論 文
36 特許研究 PATENT STUDIES No.63 2017/3
長で2時間,査察の着手を遅らせることができる。 56 TOSHIKO TAKENAKA, et.al. PATENT ENFORCEMENT
IN THE US, GERMANY AND JAPAN margin no.11.57. 57 菊地・前掲注(37)27頁。 58 Thomas Kühnen, a.a.O.(Anm.44), Rn.404, 406. 59 Thomas Kühnen, a.a.O.(Anm.44), Rn.404. 60 Thomas Kühnen, a.a.O.(Anm.44), Rn.415,菊地・前掲注
(37)28頁。 61 ただし,守秘義務の対象は調査により判明した事実で
あり,調査の結果,専門家が侵害・非侵害のいずれと
判断したかは法的評価であるため,守秘義務の対象と
はならない。菊地・前掲注(37)27頁。 62 Thomas Kühnen, a.a.O.(Anm.44), Rn.454-457. 63 Thomas Kühnen, a.a.O.(Anm.44), Rn.458-474. 64 Thomas Kühnen, a.a.O.(Anm.44), Rn.454-457. 65 Thomas Kühnen, a.a.O.(Anm.44), Rn.365-373,376-382. 66 菊地・前掲注(37)26頁。 67 Thomas Kühnen, a.a.O.(Anm.44), Rn.480-481. 68 Thomas Kühnen, a.a.O.(Anm.44), Rn.454-457. 69 Dirk Schüssler-Langeheine Protection of Confidential
Information in Patent Litigation in Germany, in PATENT PRACTICE IN JAPAN AND EUROPE 377, 387 (Bernd Hansen & Dirk Schüssler-Langeheine, 2011).
70 春日・前掲注(37)75頁。 71 フランスにおけるセジー・コントルファソンについて
は,杉山悦子「フランス及びベルギーにおける情報収
集と秘密保護」知的財産訴訟外国法制研究会編『知的
財産訴訟制度の国際比較 制度と運用について』別冊
NBL81号140頁,145頁以下(2003),ウルラ・アルゲ
イヤ=ヤーゲン・シュミッチェン(山本宏訳)「ドイ
ツ,フランス及びイギリスの特許訴訟制度について」
国際商事法務34巻5号563頁以下(2006),今井弘晃「フ
ランスにおける特許権侵害訴訟の理論および実務につ
いて」牧野利明他編『知的財産法の理論と実務第1巻』
466頁以下(2007),竹下敦也「欧州での特許訴訟戦略
とフランス起源の証拠保全手段(Seizure)」AIPPI 55巻11号778頁以下(2010),カトリーヌ・トゥアティ他
(竹下敦也訳)「フランスにおける特許訴訟の概観」
パテント65巻1号35頁以下(2012),モンルワ幸希=駒
田泰土「フランスの特許訴訟における証拠収集制度」
Law & Technology 70号29頁以下(2016),一般財団法
人知的財産研究所・前掲注(37)189頁以下,の各々の
文献で報告されている。 72 フランス知的財産法典L615-5条の条文は以下のとおり
である。 L613-3条からL613-6条までに定められた特許所有者
の権利に反する如何なる行為も侵害を構成する。如
何なる侵害も,侵害者の民法上の責任を伴うものと
する。 ただし,侵害品に関し販売の申出をし,市販
に供し,使用し又は使用若しくは市販に供する 目的
で保有することは,当該行為が侵害品の製造者以外
によってなされている場合は,当該行為が事実を完
全に知った上でなされたときに限り,行為者の民事
責任を伴う。 73 モンルワ=駒田・前掲注(71)29頁。 74 山本和彦「フランス司法見聞録(4)―執行士」判例時
報1437号10頁以下(1993)によると,執行士とは,裁
判所付属吏(政府の承認の下に株を保有して一定の公
的な法律業務を独占して行うことが認められた自由専
門職であり,公務員ではない。)の一種であり,送
達・強制執行その他の職務を遂行する自由専門職であ
る。 75 独占的ライセンシーは,ライセンス契約中に別段の定
めがなく,かつ特許権者が特許侵害訴訟を提起しない
場合に限り,侵害訴訟を提起できる(フランス知的財
産法典L615-2条)。また,ライセンス契約は,第三者
に対抗できるよう,産業財産権庁(INPI)に登録され
ていなければならない(モンルワ=駒田・前掲注(71)32頁)。
76 Gérald Portal, The Seizure Infringement Procedure under French Patent Law, in PATENT PRACTICE IN JAPAN AND EUROPE, supra note 69, at 357, 362.
77 Portal, supra note 76. 78 一般財団法人知的財産研究所・前掲注(37)190頁。 79 モンルワ=駒田・前掲注(71)31頁。 80 今井・前掲注(71)474-475頁,竹下・前掲注(71)21
頁。 81 Portal, supra note 76. 82 Portalによれば,命令の提示からセジーの執行開始まで
は,実務上は少なくとも30分以上空けることが望まし
いとされている。Id.at 368. 83 杉山・前掲注(71)146頁。 84 モンルワ=駒田・前掲注(71)35頁。 85 今井・前掲注(71)475-476頁,モンルワ=駒田・前掲
注(71)30-31頁。 86 モンルワ=駒田・前掲注(71)31頁。 87 Portal, supra note 76 at 373. 88 杉山・前掲注(71)146頁,ウルラ・アルゲイヤ=ヤー
ゲン・シュミッチェン・前掲注(71)569頁。 89 杉山・前掲注(71)156頁の注(38)。 90 Bruno Boval, Bailiffs’ Reports, Seizure and Injunctions in
Patent Infringement Proceedings in France 24 (6) International Review of Industrial Property and Copyright Law 744,748 (1993). 今井・前掲注(71)476頁によると,
1990年から1996年までにパリ大審裁判所で,特許権侵
害訴訟注にセジーの濫用に基づく損害賠償請求が反訴
として提起された事件が119件あったところ,これが認
められたのは8件にすぎないようである。 91 モンルワ=駒田・前掲注(71)35頁。 92 Boval, supra note 90. 93 Boval, supra note 90. 94 日本の民事訴訟法においては,民事訴訟上の法におけ
る信義誠実義務則の規定(同法2条)があるが,司法協
力義務の規定は無い。 95 近藤昌昭=齋藤友嘉『知的財産関係二法/労働審判法』
25頁(商事法務,2004)。 96 杉山悦子「民事訴訟法から見た計算鑑定人の意義と機
能」一橋法学3(1)111頁,145頁。 97 二小判昭和31年12月28日民集10巻12号1639頁。 98 東京高判平成14年10月31日判例時報1823号109頁[トラ
ニスト事件]では,原審において訴訟用にねつ造され
た製造記録が提出されていたことが,控訴審において
明らかになった。