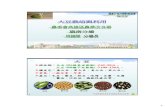令和元年産大豆の集荷・販売計画 · 2019-12-14 · 令和元年 11月 2 9 日 JA全農 麦類農産部 大豆・特産課 令和元年産大豆の集荷・販売計画(概要・速報)
愛知県稲・麦・大豆生産振興計画 - Aichi...
Transcript of 愛知県稲・麦・大豆生産振興計画 - Aichi...

策定年度 平成 22年度
目標年度 平成 27年度
愛知県稲・麦・大豆生産振興計画

○ 愛知県稲・麦・大豆生産振興計画目次
Ⅰ はじめに
1 策定の趣旨 ····························································1
2 振興計画の位置づけ ····················································1
3 目標年度 ······························································1
Ⅱ 本県の稲(米)、麦、大豆作の現状と課題
1 生産構造 ······························································2
(1) 生産農家の動向(担い手の姿) ·········································2
(2) 担い手の確保・育成 ··················································3
課 題
2 生産対策 ······························································4
(1) 水稲 ································································4
ア 需要見通し ························································4
イ 作付面積及び収穫量等の推移 ········································4
ウ 検査等級の推移 ····················································5
エ 生産コストの推移 ··················································6
オ 作付品種の推移 ····················································6
カ 生産技術 ··························································8
キ 新規需要米の動向 ··················································9
課 題
(2) 麦類 ································································ 10
ア 需要見通し ························································ 10
イ 作付面積及び収穫量等の推移 ········································ 10
ウ 検査等級の推移 ···················································· 11
エ 生産コストの推移 ·················································· 12
オ 作付品種の推移 ···················································· 14
カ 生産技術 ·························································· 14
課 題
(3) 大豆 ································································ 15
ア 需要見通し ························································ 15

イ 作付面積及び収穫量の推移 ········································· 15
ウ 検査等級の推移 ···················································· 16
エ 生産コストの推移 ·················································· 17
オ 作付品種の推移 ···················································· 18
カ 生産技術 ·························································· 18
課 題
3 出荷・流通対策 ························································ 20
(1) 米 ·································································· 20
(2) 麦類 ································································ 21
(3) 大豆 ································································ 21
課 題
4 環境対策 ······························································ 22
課 題
5 消費拡大対策 ·························································· 23
課 題
Ⅲ 品目別生産指標及び推進方策
1 水稲(主食用米) ······················································· 24
(1) 生産対策 ···························································· 24
ア 作付面積・単収・収穫量に関する目標 ·································· 24
イ 品質に関する目標 ·················································· 25
ウ 生産コストに関する目標 ············································ 25
(2) 目標達成に向けた取組 ················································ 26
ア 品種構成、導入・普及すべき技術 ····································· 26
イ 共同利用施設整備等 ················································ 27
ウ 安全・安心な米生産 ················································· 28
エ 出荷・流通対策 ···················································· 28
オ 消費拡大対策 ····················································· 28
2 水稲(米粉用米・飼料用米、WCS用稲) ································· 28
(1) 生産対策 ···························································· 28
ア 作付面積・単収・収穫量に関する目標 ·································· 28
イ 品質に関する目標 ·················································· 28
ウ 生産コストに関する目標 ············································ 28

(2) 目標達成に向けた取組 ················································ 29
ア 品種構成、導入・普及すべき技術 ····································· 29
イ 共同利用施設整備等 ················································ 29
ウ 安全・安心な米生産 ················································· 29
エ 出荷・流通対策 ···················································· 29
オ 消費拡大対策 ····················································· 29
3 麦類(小麦、六条大麦) ················································· 30
(1) 生産対策 ···························································· 30
ア 作付面積・単収・収穫量に関する目標 ·································· 30
イ 品質に関する目標 ·················································· 30
ウ 生産コストに関する目標 ············································ 30
(2) 目標達成に向けた取組 ················································ 31
ア 品種構成、導入・普及すべき技術 ····································· 31
イ 共同利用施設整備等 ················································ 31
ウ 安全・安心な麦生産 ················································· 32
エ 出荷・流通対策 ···················································· 32
オ 消費拡大対策 ····················································· 32
5 大豆 ·································································· 32
(1) 生産対策 ···························································· 32
ア 作付面積・単収・収穫量に関する目標 ·································· 32
イ 品質に関する目標 ·················································· 32
ウ 生産コストに関する目標 ············································ 33
(2) 目標達成に向けた取組 ················································ 33
ア 品種構成、導入・普及すべき技術 ····································· 33
イ 共同利用施設整備等 ················································ 34
ウ 安全・安心な大豆生産 ··············································· 34
エ 出荷・流通対策 ···················································· 34
オ 消費拡大対策 ······················································ 34
Ⅳ 地域別推進方策
1 地域別担い手の状況 ···················································· 35
2 地域別稲・麦・大豆生産状況 ············································ 37
3 尾張地域 ······························································ 38
4 西三河地域 ···························································· 38
5 東三河地域 ···························································· 39
6 中山間地域 ···························································· 40

- 1 -
Ⅰ はじめに
1 策定の趣旨
本県の稲、麦、大豆生産は、恵まれた自然条件や立地条件に加え、農業用水やほ場
整備等インフラ整備の充実や担い手への農地の利用集積による経営の大規模化などに
より発展してきた。その例として、集落ぐるみで、稲と麦・大豆を組み合わせたブロ
ックローテーションによる2年3作が広く定着するとともに、認定農業者や集落営農
組織など、水田経営所得安定対策加入経営体の平均経営面積は30.8haで全国一となっ
ている。
しかし、米の消費減退が続く中で、米価は下落を続け、麦、大豆は気象の影響など
により、収量、品質が低迷していることが、担い手の経営を不安定なものしている。
一方で、本県は、消費地に近い米、麦、大豆の産地であり、地産地消への関心の高
まりを受け、実需者からの期待も高いことから、今後、より実需者ニーズに応えられ
る産地育成をしていく必要がある。
このような中で、本県稲・麦・大豆の生産振興を図るとともに、食と緑の基本計画
に掲げた取組の目標を達成するため、愛知県水田農業基本方針(以下、「基本方針」
という。)に基づき、愛知県稲・麦・大豆生産振興計画(以下、「振興計画」という。)
を策定し、本県稲(米)、麦、大豆の生産振興に関する目標と目標達成の取組を具体
的に示すものである。
2 振興計画の位置づけ
この振興計画は、本県稲、麦、大豆の生産振興を図るための基本的な方向であり、
食と緑の基本計画に盛り込まれている目標及び基本方針で定めた本県水田農業のある
べき姿の実現に向けた取組の計画として位置づける。
3 目標年度
基本方針の目標年度と同じ平成27年度(2015年度)とする。

- 2 -
Ⅱ 本県の稲(米)、麦、大豆作の現状と課題
1 生産構造
(1) 生産農家の動向(担い手の姿)
本県においては、平坦地域を中心に、各地で集落を基盤とした水田農業が展開さ
れており、担い手への農地の利用集積や作付けの団地化が進んでいる。
生産農家の動向について、農林業センサスの「販売目的で作付けた水稲作付農家
数」は、2000年(平成12年)から2005年(平成17年)では42,612戸から31,168
戸と約27%減少し、作付面積は21,793haから 18,919haと約 13%減少している。
一方、このうち 10ha 以上水稲を作付けした農家数は 106 戸から 164 戸と約 55%
増加し、これら農家が作付けした水稲面積は1,595haから2,698haと約69%増加し、
販売目的で作付けされた水稲面積に占める割合は7.3%から14.3%と倍増しており、
稲作農家の作付規模が拡大している(表1)。
表1 販売目的で作付けた水稲作付農家数・面積
2000年(平成12年) 2005年(平成17年) 2005年/2000 年
水稲作付
農 家 数
水稲作付
面 積
構 成
比 率
水稲作付
農 家 数
水稲作付
面 積
構 成
比 率 農 家 数 作付面積項 目
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ④÷① ⑤÷②
戸 ha 戸 ha
1.0ha未満 39,497 14,629 67.1% 28,271 10,996 58.1% 71.6% 75.2%
1.0~5.0 2,822 4,295 19.7% 2,551 3,961 20.9% 90.4% 92.2%
5.0~10.0 187 1,275 5.9% 182 1,265 6.7% 97.3% 99.2%
10ha以上 106 1,595 7.3% 164 2,698 14.3% 154.7% 169.2%
計 42,612 21,793 100.0% 31,168 18,919 100.0% 73.1% 86.8%
出典:2000年、20005年農林業センサス
なお、水田作を中心とした集落営農組織は、22年度の水田経営所得安定対策への
加入は9組織、戸別所得補償モデル事業への加入は22組織となっている。
麦、大豆については、水田経営所得安定対策に加入している認定農業者等が、平
成21年産でそれぞれ、99.0%、96.4%を作付けしており、担い手が大部分を占めて
いる(表2)。
表2 水田経営所得安定対策加入農業者による品目別カバー率(22年度)
品 目 麦 大豆 米
加入面積 5,196ha 4,069ha 5,479ha
作付面積 5,250ha 4,220ha 31,000ha
カバー率 (対作付面積比) 99.0% 96.4% 17.7%
全国のカバー率 95.6% 82.3% 30.3%
出典:農林水産省公表資料から作成

- 3 -
(2) 担い手の確保・育成
水田作(水稲・麦・大豆作)に関わる認定農業者は平成22年3月末で478経営体
となっており、18年3月末の387経営体に比べ91経営体(24%)増加している(表
3)。
また、新規就農者数は、22年5月1日現在、農業全体で150人のうち、水田作部
門が32人で、21.3%を占めている。このうち、農業法人等への就業が13人(40.6%)
と多いことが特徴である。
表3 認定農業者の推移(水田作、法人を含む) (単位:経営体)
水田における利用権設定に所有権移転面積を加えた利用権設定等面積は、平成17
年度8,315haであったものが、22年度10,186haと 23%増加した(表4)。
表4 利用権設定等の推移(水田) (単位:ha)
課 題
• 基本方針で示した経営体モデルを基本に農地の利用集積を進めるとともに、多
様な経営体の戸別所得補償制度による経営安定を図ることが必要である。
• 「愛知県青年等就農促進方針」に基づく、技術指導や情報提供、円滑な就農と
経営の確立支援による次代を担う青年農業者等の育成を図る必要がある。
区 分 17年度 21年度
認定農業者 387 478
区 分 17年度 21年度
利用権設定等面積(田) 8,315 10,186
注 1)17年度は18年3月末、21年度は22年3月末実績
注 2)利用権設定等とは、利用権設定+所有権移転(累計)
注 1)17年度は18年3月末、21年度は22年3月末実績。
注 2) 水稲主体及び水稲+麦+大豆の経営体の実績。

- 4 -
2 生産対策
(1) 水稲
ア 需要見通し
食料需給表による国民1人当たり・1年当たり米の消費量は、漸減傾向であっ
たが、平成19年度は、穀物の国際価格高騰を受け、パン等小麦粉製品価格が上昇
したことから、米消費が伸び前年を上回った。20年度は、小麦製品価格の値下が
りにより、再び減少に転じた。21年度はさらに消費が減退し、58.5kgと前年から
0.5kg減少した(表5)。
表5 国民1人当たり・1年当たり米消費量の推移
(単位:精米kg/人・年)
年 度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
消 費 量 61.4 61.0 61.4 59.0 58.5
うち主食用 59.4 58.6 58.8 56.7 56.5
注)21年度は概数値 出典:食料需給表
また、全国の需要実績についても、漸減傾向の中、19年度は一時的に需要量を
回復したものの、その後再び減少に転じていている。
国は、22年(22年7月から23年6月)の需要見通しを805万tとしている(表
6)。
表6 全国の米の需要実績及び需要見通し (単位:万t)
年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
(見通し)
需要実績 852 838 855 824 810 805
出典:米穀の需要及び価格の安定に関する基本指針(平成22年7月)
注 1)平成17年は、17年7月から18年6月までの1年間。以下同様。
注 2)平成22年(見通し)は速報値で、8年から21年まで需要実績(19年を除く)を用いた
回帰式により算出された値。
イ 作付面積及び収穫量等の推移(表7)
本県の水稲作付面積は、平成21年産で31,100ha、うち主食用が30,800haとな
っている。水田面積の減少や米の生産調整の推進により水稲作付面積は漸減傾向
であるが、依然国が示す生産数量目標に比べて過剰作付状態となっている。
10a当たり収量は、直近5年では499kgから 516kgの間で変動しており、平均
は505kgで、全国の525kgと比べて低い。
収穫量は16万t前後で推移している。
また、本県の米の産出額は、17年の342億円以降、収穫量の減少、米価の下落
に伴い漸減傾向であったが、20年は前年より収穫量が増加したこと、販売価格が
上昇したことにより346億円と増加した。
なお、全国に占める本県のシェアは1.8%となっている。

- 5 -
表7 愛知県産水稲の生産状況の推移
項 目 17年産 18年産 19年産 20年産 21年産 平均
作付面積 (ha) 32,000 31,900 31,900 31,400 31,100 31,660
うち主食用 (ha) 31,110 30,800
10a当たり収量 (kg) 507 503 502 516 499 505
収穫量 (t) 162,200 160,500 160,100 162,000 155,200 160,000
うち主食用 (t) 160,500 153,700
平年収量 (kg/10a) 505 506 506 507 507 506
愛知県
産出額 (億円) 342 331 322 346 323 333
作付面積 (千 ha) 1,702 1,684 1,669 1,624 1,621 1,660
うち主食用 (千 ha) 1,596 1,592
10a当たり収量 (kg) 532 507 522 543 522 525
収穫量 (千 t) 9,062 8,546 8,705 8,815 8,466 8,718
うち主食用 (千 t) 8,658 8,309
平年収量 (kg/10a) 527 529 529 530 530 529
全
国
産出額 (億円) 20,234 18,894 18,058 19,312 18,044 18,1908
出典:作物統計、生産農業所得統計
注1)主食用作付面積及び収穫量の公表は平成20年産以降。
ウ 検査等級の推移(表8)
本県産米の1等比率は、常に全国を下回っている。年次による変動が全国に比
べ大きく、直近5年平均では全国が79.6%であるのに対して本県は62.7%とかな
り下回っている。
21年産は近年では も高い1等比率であったが、これは夏期の高温の影響によ
る白未熟粒の発生が比較的少なかったことによるものと考えられ、白未熟の発生
程度が検査等級を左右している。
また、近年では斑点米カメムシ類による斑点米も検査等級を落とす要因となっ
ている。

- 6 -
表8 愛知県産米の検査等級の推移
水稲うるち玄米 17年産 18年産 19年産 20年産 21年産(H22.10末) 平均
総数量(t) 52,537 51,654 56,797 56,218 58,053 55,052
1 等 55.4% 62.9% 61.7% 55.3% 78.4% 62.7%
2 等 41.7% 34.6% 35.3% 42.2% 19.4% 34.6%
3 等 2.5% 2.0% 2.5% 2.0% 1.7% 2.1%
愛知県
規格外 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.6% 0.5%
総数量(t) 5,047,547 4,776,481 4,805,870 5,093,440 4,818,566 4,908,381
1 等 75.1% 78.4% 79.6% 80.0% 85.1% 79.6%
2 等 19.8% 17.2% 16.6% 16.7% 12.1% 16.5%
3 等 3.3% 2.4% 2.0% 1.5% 1.0% 2.0%
全
国
規格外 1.8% 2.0% 1.8% 1.9% 1.8% 1.9%
出典:米の検査結果
注)平均値は各年の比率の単純平均のため、合計が100%にならないことがある。
エ 生産コストの推移(表9)
農業経営統計による資本利子・地代全額算入生産費(以下「全算入生産費」と
いう。)(東海3県5ha以上)は17年以降概ね漸減傾向で、20年では、10a当
たり92,415円で、全国の15ha以上の階層に比べ約8%低減している。
オ 作付品種の推移(表10)
主な作付品種は、「あいちのかおりSBL」(以下、「あいちのかおり」とい
う。)、「コシヒカリ」、「あさひの夢」、「ミネアサヒ」などである。
品種別では近年、極早生の「コシヒカリ」から中生の「あいちのかおり」への
転換がみられ、「あいちのかおり」の作付比率が4割を超えている。
なお、22年から「祭り晴」、「あさひの夢」に換わる早生新品種「ゆめまつり」
の作付けが始まった。

- 7 -
表9 水稲生産費の推移(東海3県5ha以上・全国水稲作付15ha以上) (10a当たり)
区 分 単位 17年 18年 19年 20年
物財費 円 65,183 61,568 56,770 59,780
種苗費 円 1,743 1,710 2,993 3,650
肥料費・農業薬剤費 円 12,545 10,857 10,307 13,115
光熱動力費 円 4,995 4,637 4,879 3,915
賃借料・料金 円 8,948 13,061 9,639 8,127
建物費 円 4,079 2,728 3,112 2,256
自動車・農機具費 円 24,477 21,055 19,116 22,956
その他の物財費 円 8,396 7,520 6,724 5,761
労働費 円 21,959 20,741 17,991 18,614
費用計 円 87,142 82,309 74,761 78,394
支払地代 円 13,857 12,188 13,917 12,396
その他の経費 円 3,943 3,314 2,483 1,625
支払利子・地代算入生産費 円 100,139 93,720 87,519 88,514
全算入生産費 円 104,942 97,811 91,161 92,415
投下労働時間 時間 12.05 12.77 10.15 11.39
玄米収量 kg 488 489 491 498
東
海
3
県
5
ha
以
上
60kg当たり全算入生産費 円 12,903 12,001 11,140 11,134
物財費 円 52,859 54,716 52,955 59,718
種苗費 円 1,630 1,600 1,736 1,923
肥料費・農業薬剤費 円 12,902 13,014 12,765 12,948
光熱動力費 円 3,608 3,844 3,877 4,261
賃借料・料金 円 5,192 5,973 4,975 5,352
建物費 円 3,694 4,203 3,549 4,062
自動車・農機具費 円 16,572 16,714 17,184 20,740
その他の物財費 円 9,261 9,368 8,869 10,432
労働費 円 25,087 23,951 24,402 21,123
費用計 円 77,946 78,667 77,357 80,841
支払地代 円 10,670 9,549 8,934 10,270
その他の経費 円 11,501 10,047 9,174 9,383
支払利子・地代算入生産費 円 87,565 86,366 84,478 88,545
全算入生産費 円 100,117 98,263 95,465 100,494
投下労働時間 時間 15.65 14.78 14.91 14.25
玄米収量 kg 531 537 523 524
全
国
15
ha
以
上
60kg当たり全算入生産費 円 11,313 10,979 10,952 11,507
出典:農業経営統計

- 8 -
表10 水稲品種別作付面積の推移
作付面積(ha) 比率(%) 品種名
17年産 21年産 17年産 21年産
あいちのかおりSBL 9,619 12,900 39.3 41.5
コシヒカリ 7,165 8,100 29.3 26.0
あさひの夢 1,610 2,300 6.6 7.4
ミネアサヒ 1,429 1,600 5.8 5.1
祭り晴 2,376 940 9.7 3.0
大地の風 651 880 2.7 2.8
その他 1,618 4,380 6.6 14.1
計 24,468 31,100 100.0 100.0
出典:17年は米穀の品種別作付状況調査(東海農政局食糧部資料)。
21年は水稲共済引受面積を基にした園芸農産課推計値。
カ 生産技術
本県の稲作の特徴的な技術として、全量基肥栽培と不耕起V溝直播栽培(以下、
「V直」という。)がある。
全量基肥栽培は、品種や熟期に合わせて配合した肥効調節型肥料を用いること
で、穂肥施用を省略する栽培法で、平成20年産では移植と直播を合わせて作付面
積の70%以上で実施されている。
V直は、育苗・移植期、収穫期の作業分散などを目的として稲作農家に受け入
れられ、栽培面積は徐々に拡大してきており、平成22年には1,687haとなった。
品種別では、導入初期はコシヒカリでの取組が中心であったが、近年はあいちの
かおりの栽培面積の伸びが大きい。また、整地法別では、代かきに対して、鎮圧
法での取組面積の伸びが大きい(表11)。
なお、水稲の種子更新率は徐々に高まってきているものの、平成 21 年度は
73.2%であった(表12)。また、種子の農産物検査合格率は17年産から21年産
平均で70.4%であった(表13)。
表11 水稲不耕起V溝直播栽培面積の推移 (単位:ha)
年 次 平成 18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成 22年
栽培面積 1,096 1,175 1,259 1,506 1,687
うち コシヒカリ 664 707 634 645 650 品種
別 うち あいちのかおり 331 369 477 663 764
うち 代かき 658 669 640 761 853 整地
法別 うち 鎮圧 438 505 619 745 834
出典:農業総合試験場、農業改良普及課調べ
注)「あいちのかおり」は「あいちのかおりSBL」を指す。

- 9 -
表12 種子更新率の推移 (単位:%)
品目 17年産 18年産 19年産 20年産 21年産 平均
水稲 68.5 65.1 72.5 73.8 73.2 70.6
小麦 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
大豆 36.4 43.6 47.7 47.0 50.2 45.0
注 1)種子更新率は更新した種子で栽培した面積÷全体栽培面積。
注 2)10a当たり種子使用量を、水稲移植3.5kg、V直7.5kg(19年産から)、小麦
は8.0kg、大豆4.0kgで計算
表13 種子合格率の推移 (単位:%)
品目 17年産 18年産 19年産 20年産 21年産 平均
水稲 65.6 70.1 61.0 70.9 84.2 70.4
小麦 98.1 30.0 57.0 76.6 49.7 62.3
大豆 46.0 11.5 51.7 60.4 19.1 37.7
出典:愛知県米麦振興協会資料
キ 新規需要米の動向
新たな生産調整の手法の一つとして、新規需要米(米粉用米、飼料用米、WC
S用稲)の取組が広がりつつあり、21年度は米粉用米22.4ha、飼料用米61.4ha、
WCS用稲34.3haの作付けがあった。
米粉については、近年、米も小麦粉並に微細な粉末加工が可能となり、小麦粉
の代わりにパンや麺に利用する新たな「ライススタイル」が作られつつある。地
産地消に対する消費者の関心の高まりも追い風となり、食品事業者による商品開
発が進んでいる。
なお、新たな食料・農業・農村基本計画では、32年度の生産数量目標を米粉用
米50万t、飼料用米70万tとして、現状(20年度)の 0.1万t、0.9万tから飛
躍的に拡大させることとしている。
課 題
• 過剰作付けを解消し、生産数量目標に即した生産を行うとともに、県産米の評
価向上のため、白未熟粒や斑点米の発生を低減させ、1等米比率の向上など品質
を向上させることが必要である。
• 県産米の評価向上を図るため、熟期別品種構成の再構築と早生品種は「ゆめま
つり」への作付誘導、種子の合格率、種子更新率の向上が必要である。
• 農業所得を確保するため、物財費、労働費の低減、単収の向上等により生産コ
ストを低減させることが必要である。
• 新規需要米の生産拡大に向けた、生産体制の確立が必要である。

- 10 -
(2) 麦類
ア 需要見通し
食料需給表による国民1人当たり・1年当たり食糧用小麦の消費量は、直近5
年では31~32kgで推移している。総需要量は550~600万tで推移しており、こ
れに対し国は、22年度の総需要見通しを569万tとしている(表13、14)。
総需要量に占める国内産供給量は、年度により大きく変動している。
表14 国民1人当たり・1年当たり食糧用小麦消費量の推移
(単位:kg/人・年)
年 度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
消費量 31.7 31.8 32.3 31.1 31.8
出典:麦の需要に関する見通し(平成22年3月)
注)平成21年度は概算値。
表15 食糧用小麦の総需要量及び国内産供給量 (単位:万t)
年 度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
(見込み)
22年度
(見通し)
総需要量 (a) 568 597 569 548 565 569
うち国内産 (b) 83 79 87 84 64 83
自給率 (c)=(b)/(a)
14.6% 13.2% 15.3% 15.3% 11.3% 14.6%
出典:麦の需要に関する見通し(平成22年3月)
注1)国内産の年度内供給比率は17年度から21年度平均で46.2%。
注 2)平成22年度(見通し)は、17年度から21年度までの平均需要量。
イ 作付面積及び収穫量等の推移(表16)
本県の小麦作付面積は、直近5年では減少傾向で、21年産は5,420ha、うち水
田作が5,310haであった。
10a 当たり収量は、直近5年では 278 から 359kg と年次変動が大きく、平均は
326kgで、全国の395kgと比べるとかなり低い。
直近5年の平均収穫量は18,000tであった。
六条大麦は、特定業者との契約により、尾張地域の一部で限定的に作付けされ
ており、作付面積はわずかに増加傾向である。
10a当たり収量は、直近5年では年次変動がきわめて大きく、平均が304kgで、
全国の309kgとほぼ同等である。
なお、本県の麦類の産出額は、20年で8億円で、ほとんどが小麦である。小麦
の全国産出額585億円に占める本県のシェアは1.4%となっている。
また、麦類の産出額については、19年度の水田経営所得安定対策導入以降、固
定払部分が算入されなくなったため、18年産から19年産で大きく減少している。

- 11 -
表16 愛知県産4麦の生産状況の推移
項 目 17年産 18年産 19年産 20年産 21年産 平均
作付面積 (ha) 5,730 5,640 5,600 5,440 5,490 5,580
うち田作 (ha) 5,560 5,470 5,440 5,320 5,390 5,436
収穫量 (t) 20,500 16,900 19,200 19,200 15,300 18,220
愛知県
産出額 (億円) 29 18 9 8 9 16
作付面積 (ha) 268,300 272,100 264,000 265,400 266,200 267,200
うち田作 (ha) 167,100 167,300 162,900 165,900 167,100 166,060
収穫量 (千t) 1,058 1,012 1,105 1,098 854 1,025
麦
類
全
国
産出額 (億円) 1,417 1,352 765 785 680 1,080
作付面積 (ha) 5,660 5,580 5,520 5,370 5,420 5,510
うち田作 (ha) 5,490 5,410 5,360 5,250 5,310 5,364
10a当たり収量 (kg) 359 301 342 352 278 326
収穫量 (t) 20,300 16,800 18,900 18,900 15,100 18,000
愛知県
産出額 (億円) 29 18 8 8 9 16
作付面積 (ha) 213,500 218,300 209,700 208,800 208,300 211,720
うち田作 (ha) 118,000 119,100 114,000 114,700 114,600 116,080
10a当たり収量 (kg) 410 384 434 422 324 395
収穫量 (t) 874,700 837,200 910,100 881,200 674,600 835,560
小麦
全
国
産出額 (億円) 1,187 1,152 610 585 477 884
作付面積 (ha) 71 65 73 73 77 72
うち田作 (ha) 71 65 73 73 77 72
10a当たり収量 (kg) 303 206 374 351 284 304
愛知県
収穫量 (t) 215 134 273 256 219 219
作付面積 (ha) 15,500 15,300 15,700 16,900 17,600 16,200
うち田作 (ha) 13,400 13,400 13,900 15,000 15,800 14,300
10a当たり収量 (kg) 303 278 332 331 301 309
六条大麦
全
国
収穫量 (t) 47,000 42,500 52,100 56,000 52,900 50,100
出典:作物統計、生産農業所得統計
注)19年産以降、水田経営所得安定対策の固定払部分が産出額に計上されなくなった。
ウ 検査等級の推移
本県産小麦の1等比率は18年産を除き、全国を上回っており、直近5年の平均
は76.5%である(表17)。
また、本県産小麦の品質評価区分のAランク率は低下傾向にあり、特に「農林
61号」のAランク率が低い(表18)。

- 12 -
エ 生産コストの推移
農業経営統計による全算入生産費(東海3県全階層)は、労働費が低下傾向で
あるものの、肥料費等が上がり、19年以降増加傾向にあるが、20年では、10a当
たり51,662円で、全国の10ha以上の階層の86%程度に抑えられている。しかし、
10a当たり収量が低いため、60kg当たり全算入生産費は8,907円で、全国を約16%
上回っている(表19)。
表17 愛知県産小麦の検査等級の推移
小 麦 17年産 18年産 19年産 20年産 21年産 平均
総数量(t) 19,621 16,585 18,593 18,493 14,791 17,617
1 等 94.0% 34.1% 87.4% 83.8% 83.2% 76.5%
2 等 2.2% 55.3% 8.6% 10.1% 9.6% 17.2%
愛知県
規格外 3.8% 10.6% 4.0% 6.1% 7.3% 6.4%
総数量(t) 946,474 870,333 961,274 956,624 812,143 909,370
1 等 71.1% 77.4% 86.6% 83.8% 63.0% 76.4%
2 等 17.7% 15.0% 4.9% 5.2% 17.3% 12.0%
全
国
規格外 11.2% 7.6% 8.5% 11.0% 19.7% 11.6%
出典:麦の検査結果
注)平均値は各年の比率の単純平均のため、合計が100%にならないことがある。
表18 愛知県産小麦の品種別ランク区分の推移
項 目 17年産 18年産 19年産 20年産 21年産 平均
出 荷 数 量 ( t )
① 16,781 11,172 11,612 10,067 7,007 11,328
Aランク数量(t)
② 11,716 5,914 4,590 0 0 4,444
A ラ ン ク 率
農
林
61
号 ③=②/①*100
69.8% 52.9% 39.5% 0.0% 0.0% 39.2%
出 荷 数 量 ( t )
④ 1,907 3,341 6,013 7,275 6,430 4,993
Aランク数量(t)
⑤ 487 3,341 4,009 3,613 4,940 3,278
A ラ ン ク 率
イワイノダイチ⑥=⑤/④*100
25.5% 100.0% 66.7% 49.7% 76.8% 65.6%
出 荷 数 量 ( t )
⑦=①+④ 18,689 14,512 17,625 17,342 13,437 16,321
Aランク数量(t)
⑧=②+⑤ 12,203 9,254 8,599 3,613 4,940 7,722
A ラ ン ク 率
計
⑨=⑧/⑦*100 65.3% 63.8% 48.8% 20.8% 36.8% 47.3%
出典:全国米麦改良協会等資料から作成

- 13 -
表 19 小麦生産費の推移(東海3県全階層・全国小麦作付10ha以上) (10a当たり)
区 分 単位 17年 18年 19年 20年
物財費 円 32,195 29,981 32,648 34,808
種苗費 円 3,461 2,921 3,008 2,942
肥料費・農業薬剤費 円 5,682 6,308 7,380 7,560
光熱動力費 円 1,286 1,281 1,382 1,741
賃借料・料金 円 9,314 9,011 9,367 9,150
建物費 円 926 1,012 659 973
自動車・農機具費 円 10,346 8,577 9,875 11,521
その他の物財費 円 1,180 871 977 921
労働費 円 7,942 7,787 7,067 7,188
費用計 円 40,137 37,768 39,715 41,996
支払地代 円 8,033 7,662 7,463 6,957
その他の経費 円 4,274 3,738 2,525 2,709
支払利子・地代算入生産費 円 48,324 45,515 47,347 49,118
全算入生産費 円 52,444 49,168 49,703 51,662
投下労働時間 時間 4.69 4.47 3.96 4.14
玄麦収量 kg 362 339 346 348
東
海
3
県
60kg当たり全算入生産費 円 8,692 8,702 8,619 8,907
物財費 円 42,370 40,219 42,916 45,793
種苗費 円 2,532 2,348 2,362 2,473
肥料費・農業薬剤費 円 12,358 12,004 12,680 14,076
光熱動力費 円 1,514 1,615 1,757 2,084
賃借料・料金 円 15,224 13,905 15,676 14,554
建物費 円 815 781 881 1,291
自動車・農機具費 円 7,018 6,890 7,251 9,236
その他の物財費 円 2,909 2,676 2,309 2,079
労働費 円 5,713 5,747 5,604 5,158
費用計 円 48,083 45,966 48,520 50,951
支払地代 円 3,340 3,305 3,829 3,243
その他の経費 円 5,839 6,540 5,395 5,633
支払利子・地代算入生産費 円 49,307 47,856 50,311 51,898
全算入生産費 円 57,262 55,811 57,744 59,827
投下労働時間 時間 3.50 3.56 3.59 3.26
玄麦収量 kg 467 440 475 467
全
国
10
ha
以
上
60kg当たり全算入生産費 円 7,357 7,611 7,294 7,687
出典:農業経営統計

- 14 -
オ 作付品種の推移(表20)
小麦は平成 16 年産から「イワイノダイチ」を導入し、21 年産の作付面積比率
は「農林61号」が約6割、「イワイノダイチ」が約4割である。
早生新系統「きぬあかり」を育成し、22 年度奨励品種化した。今後 23 年産(22
年秋播種)で種子生産を行い、24年産(23年秋播種)から一般栽培を開始すること
を決定している。
なお、「農林61号」、「イワイノダイチ」とも用途は、日本めん製造用に区分
され、パン・中華めん用小麦の作付けはほとんどない。
また、六条大麦は、「カシマムギ」を基幹に、18年産から収量性の高い「さや
がぜ」が導入されている。
表20 麦類品種別作付面積の推移
作付面積(ha) 比率(%) 品種名
17年産 21年産 17年産 21年産
農林61号 5,110 3,143 89.2 58.0
イワイノダイチ 549 2,089 9.6 38.5
その他 71 188 1.2 3.5
計 5,730 5,420 100.0 100.0
注 1)17年産は、園芸農産課調べ。21年産の品種別は、JAあいち経済連集計値。
注 2)21年産は、品種別作付面積の合計と統計値の県計の差を「その他」の品種とし
た。
カ 生産技術
単収とともに、タンパク質含量を向上させることが重要である。
タンパク質含量向上について、肥効調節型肥料を配合した追肥ワンタッチ肥料
を検討した結果、タンパク質含量が高まるなどの成果が得られている。
なお、小麦の種子更新率は、平成17年産から100%を達成している(表12)。
また、種子の農産物検査合格率は17年産から21年産平均で62.3%であった(表
13)。
課 題
• 食料自給率の向上に資するため、国の基本計画に即した数量目標の設定と生産
拡大が必要である。
• 本県産小麦の需要拡大を図るため、実需者の求める生産量、タンパク質含量の
確保など品質の向上と安定が必要である。
• 「きぬあかり」の生産拡大を図るため、実需者、生産者との協議、合意による
生産計画の策定が必要である。
• 農業所得を確保するため、物財費、労働費の低減、単収の向上等による生産コ
ストを低減が必要である。

- 15 -
(3) 大豆
ア 需要見通し
食料需給表による国民1人当たり・1年当たり大豆の消費量は、平成20年度以
降わずかに減少し、21 年度は 6.5kg であった。同様に 20 年の総需要量は 395 万
tで、前年から6.6%減少し、21年についても、前年より輸入量が減少し、国内
消費仕向量が減っていることから総需要量は前年に比べ減少していると推察され
る(表21、22)。
表21 国民1人当たり・1年当たり大豆消費量の推移
(単位:kg/人・年)
年 度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
消費量 6.8 6.8 6.8 6.7 6.5
出典:食料需給表
注)平成21年度は概算値。
表22 大豆の総需要量及び国内産供給量 (単位:万t)
年 17年 18年 19年 20年 21年
総需要量 426 415 423 395 未発表
うち国内産 16 23 23 26 23
出典:大豆に関する資料(平成22年3月)
注)21年のうち国内産は作物統計による。
イ 作付面積及び収穫量等の推移(表23)
本県の大豆は麦の後作としての作付けが大半であり、直近5年の作付面積は、
減少傾向にある。21年産では4,270ha、うち水田作が4,010haであった。
直近5年の 10a 当たり収量は、89~176kg と年次変動がきわめて大きく、平均
は144kgで全国平均と比べると低い。
なお、本県の大豆の産出額は 20 年で9億円となっている。大豆の全国産出額
423億円に占める本県のシェアは2.1%となっている。
また、大豆の産出額について、19年度の水田経営所得安定対策導入以降、固定
払部分が算入されなくなったため、18年産から19年産で大きく減少している。

- 16 -
ウ 検査等級の推移
愛知県の1等比率は、年次変動があるものの、21年産を除き全国を上回ってお
り、直近5年平均では約10ポイント高い37.2%である。また上位等級(1、2等)
比率も全国より約6ポイント高い72.4%である(表24)。
表24 愛知県産大豆の検査等級の推移
大 豆 17年産 18年産 19年産 20年産 21年産 平均
総数量(t) 5,189 5,128 6,202 5,385 2,738 4,928
1 等 28.6% 34.5% 41.9% 55.2% 25.6% 37.2%
2 等 39.3% 41.2% 32.9% 26.2% 36.4% 35.2% 72.4%
3 等 32.1% 24.3% 25.0% 18.5% 37.3% 27.4%
規格外 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.8% 0.2%
うち大粒 68.7% 79.9% 71.1% 78.1% 73.8% 74.3%
愛知県
うち中粒 29.9% 19.3% 27.6% 21.3% 25.6% 24.7%
総数量(t) 124,415 144,682 152,060 188,843 172,259 156,452
1 等 26.1% 19.1% 28.2% 32.0% 33.4% 27.8%
2 等 36.2% 46.1% 38.3% 34.2% 37.3% 38.4% 66.2%
3 等 36.8% 34.2% 32.7% 33.0% 28.6% 33.1%
全
国
規格外 0.9% 0.6% 0.9% 0.9% 0.6% 0.8%
うち大粒 63.0% 63.2% 62.0% 69.5% 67.2% 65.0%
うち中粒 27.7% 25.9% 29.2% 21.5% 22.7% 25.4%
出典:大豆の検査結果
注)平均値は各年の比率の単純平均のため、合計が100%にならないことがある。
表23 愛知県産大豆の生産状況の推移
項 目 17年産 18年産 19年産 20年産 21年産 平均
作付面積 (ha) 4,510 4,360 4,230 4,330 4,270 4,340
うち田作 (ha) 4,130 3,990 3,930 4,060 4,010 4,024
10a当たり収量 (kg) 158 148 176 147 89 144
収穫量 (t) 7,130 6,450 7,450 6,370 3,790 6,238
愛知県
産出額 (億円) 18 15 10 9 6 13
作付面積 (ha) 134,000 142,100 138,300 147,100 145,400 141,380
うち田作 (ha) 110,500 117,500 117,600 126,300 124,800 119,340
10a当たり収量 (kg) 168 161 164 178 158 166
収穫量 (t) 225,000 229,200 226,700 261,700 229,900 234,500
全
国
産出額 (億円) 583 547 361 423 364 479
出典:作物統計、生産農業所得統計
注)19年産以降、水田経営所得安定対策の固定払部分が産出額に計上されなくなった。

- 17 -
エ 生産コストの推移
農業経営統計による全算入生産費(都府県)は労働費が低下傾向であるものの、
肥料費等が上がり、20年では10a当たり57,864円で、前年に比べ上昇した。
全国との比較では 89%程度に抑えられているが、10a当たり収量が低いため、
60kg当たり全算入生産費は20,423円で、約3%上回っている(表25)。
表25 大豆生産費の推移(都府県・全国) (10a当たり)
区 分 単位 17年 18年 19年 20年
物財費 円 31,259 29,505 29,944 32,809
種苗費 円 2,300 2,203 2,182 2,312
肥料費・農業薬剤費 円 6,399 6,110 6,808 7,295
光熱動力費 円 1,378 1,377 1,392 1,649
賃借料・料金 円 10,949 10,330 9,310 9,546
建物費 円 911 781 781 1,215
自動車・農機具費 円 6,428 6,056 6,782 8,153
その他の物財費 円 2,894 2,648 2,689 2,639
労働費 円 16,931 14,761 11,689 11,482
費用計 円 48,190 44,266 41,633 44,291
支払地代 円 6,694 6,597 7,698 6,601
その他の経費 円 7,720 6,592 6,119 6,972
支払利子・地代算入生産費 円 54,879 50,748 49,296 50,801
全算入生産費 円 62,604 57,455 55,450 57,864
投下労働時間 時間 11.48 10.09 8.02 7.98
大豆収量 kg 165 152 156 170
都
府
県
60kg当たり全算入生産費 円 22,765 22,680 21,327 20,423
物財費 円 33,246 32,048 34,103 38,189
種苗費 円 2,526 2,420 2,578 2,622
肥料費・農業薬剤費 円 7,154 7,141 8,677 9,853
光熱動力費 円 1,507 1,566 1,745 2,101
賃借料・料金 円 10,700 10,138 9,153 9,672
建物費 円 975 895 861 1,368
自動車・農機具費 円 7,123 6,686 7,451 9,097
その他の物財費 円 3,261 3,202 3,638 3,476
労働費 円 17,110 14,782 13,233 13,031
費用計 円 50,356 46,830 47,336 51,220
支払地代 円 5,936 5,661 5,734 5,210
その他の経費 円 8,621 7,937 8,119 8,572
支払利子・地代算入生産費 円 56,422 52,582 53,275 56,457
全算入生産費 円 64,913 60,428 61,189 65,002
投下労働時間 時間 11.55 10.06 9.01 8.82
大豆収量 kg 177 171 188 197
全
国
60kg当たり全算入生産費 円 22,004 21,203 19,528 19,798
出典:農業経営統計

- 18 -
オ 作付品種の推移(表26)
作付品種は、「フクユタカ」がほとんどである。
「フクユタカ」は生育量が確保しやすく、播種適期が広いなど栽培適性に優れ
るとともに、タンパク質含量が高く、豆腐加工適性が高いことから、生産者、実
需者ともに評価が高い。
表26 大豆品種別作付面積の推移
作付面積(ha) 比率(%) 品種名
17年産 21年産 17年産 21年産
フクユタカ 4,510 4,239 100.0 99.3
その他 31 0.7
計 4,510 4,270 100.0 100.0
注 1)17年産は園芸農産課調べ。21年産フクユタカはJAあいち経済連集計値。
カ 生産技術
大豆に関する生産技術で特記的なものとしては「高能率摘心機によるダイズの
増収技術」がある。21年度までは、試作機による現地実証レベルの普及面積であ
ったが、22年度に市販化されたため、今後拡大が見込まれる。
なお、近年大豆栽培において も重要な課題であった帰化アサガオ類対策につ
いては、生産農家の認識が深まったことや農業総合試験場(以下、「農総試」と
いう。)から畦間除草を基軸とした体系処理技術が示されたことなどから、今後
発生状況に応じた対策の実施が見込まれる。
また、21年度に農総試と農林水産事務所農業改良普及課が行った広域重点調査
研究の調査結果によると、大豆作付面積の約半分で、帰化アサガオ類が発生して
いた。このうち発生程度別では、発生程度「多」は4.5%、「中」は7.4%であっ
た(表27)。
表27 県内大豆作付ほ場における帰化アサガオ類発生程度(平成21年度)
発生程度 比率(%) 発生状況 アサガオ
の被度
多 4.5 ほ場一面に発生。ほ場一面がアサガオに覆われている。 30%~
中 7.4 ほ場全面に散見、又は一部に密生。 ~30%
少 37.1 畦畔に発生、又はほ場の一部に散見。 ~10%
無 51.1 発生が見られない。 0%
出典:平成21年度広域重点調査研究事業成績書をもとに作成
また、大豆の生産安定においては、害虫対策も重要や要素である。近年では、
主要な害虫である「ハスモンヨトウ」の被害は以前に比べ少なく、「ミナミアオ
カメムシ」などカメムシ類による被害が顕在化し、問題となっている。

- 19 -
大豆の種子更新率は、平成21年産で50.2%であった(表12)。また、種子の
農産物検査合格率は17年産から21年産平均で37.7%と低い(表13)。
課 題
• 食料自給率向上に資するため、国の基本計画に即した数量目標の設定と生産拡
大が必要である。
• 本県産大豆の需要拡大を図るため、実需者の求める生産量の安定的な確保が必
要である。
• 大豆生産の安定を図るため、生産を不安定にしている要因の帰化アサガオ類、
カメムシ類対策の徹底が必要である。
• 所得を確保するため、物財費、労働費の低減、単収の向上等により生産コスト
を低減させることが必要である。

- 20 -
3 出荷・流通対策
(1) 米
米については、本県の米生産量のうち農協を通じて出荷されるものは約24%の約
4万tであり、残りの多くが自家消費や縁故米などとして流通、消費されている(表
28)。
表28 愛知県産米の流通比率(20年)
区 分 流通量(t) 比率(%)
出荷契約米 39,483 24.4
農家農協直売米 17,410 10.7
種子用 658 0.4
農家保有米等 104,449 64.5
計 162,000 100.0
注)東海農政局食糧部資料をもとに推計
農協を通じて出荷されたものの多くが業務用として消費されるほか、JAグルー
プ愛知の取組として、「あいちのかおり」を中心に毎年約 6,000tを学校給食に供
給している。
直近5年の全国の60kg 当たりの価格については、平成19年産で大きく下落し、
20 年産で回復。さらに 21 年産で下落した。本県産については経年変化を比較でき
るデータがないものの概ね全国と同様の傾向である。本県21年産コシヒカリの価格
は13,406円/60kg(相対価格公表値から算出)となっており、全国全銘柄平均の96%
である(表29)。
表29 米価格の推移(愛知県産コシヒカリ・全銘柄平均)
(単位:円/60kg)
項 目 17年産 18年産 19年産 20年産 21年産
愛知県産(a) 14,898 14,601 (13,214) (13,902) (13,406)
14,185 15,159 14,693 全国(b) 15,128 14,826
(13,336) (14,271) (13,895)
比率(a)/(b) 0.98 0.98 0.99 0.97 0.96
出典:(財)全国米穀取引・価格形成センター、農林水産省資料から算出
注1)18年産までは米価格センター価格(包装代、拠出金、消費税を含まない価格)。
注 2)19年以降愛知県産はセンターに上場していないため相対価格を( )書きで表示。
注 3)相対価格は公表値から消費税相当額、包装代を控除して算出。
注 4)比率は18年産までセンター価格、19年産以降相対価格で算出。
注 5)21年産のセンター価格は22年 7月まで、相対価格は22年3月までの価格。
また、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下、
「米トレーサビリティ法」という。)の制定に伴い、取引記録の作成・保存、産地

- 21 -
情報の伝達が義務づけられた。さらに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
(以下、「改正食糧法」という。)に基づき、加工用米、飼料用米、米粉用米等、
用途限定米穀の用途外使用が禁止された。
(2) 麦類
麦については、全量が民間流通麦として播種前契約により、農協系統を通じた出
荷となっている。小麦は大半が県内製粉業者に供給され、主に外国産麦との混合に
より日本めん用途に使われている。また、六条大麦は県内の食品事業者に供給され、
麦茶用として使われている。
価格については、民間流通に移行後、麦の価格形成は、一定の値幅制限をもった
入札によることが基本となっている。21年産では高騰する外国産麦との均衡を図る
ため、基準価格(前年の指標価格)が30%引き上げられた。
本県の 21 年産小麦指標価格は1t当たり 49,991 円と前年の 36,097 円から 38%
上昇した。その後、外国産麦の売渡価格の引き下げなどを受け、22年産では45,279
円と前年産から 9.4%下落したものの、依然高い水準にある。このため、国内産麦
価格が、外国産麦より高い状態となっている。
なお、本県産の価格は全国の9割程度で推移している(表30)。
表30 小麦落札価格の推移 (単位:円/t)
項 目 18年産 19年産 20年産 21年産 22年産
農林61号 33,482 34,674 36,889 51,312 46,645
イワイノダイチ 33,770 33,427 34,824 48,439 43,654 愛知県
加重平均(a) 33,526 34,171 36,097 49,991 45,279
全国(b) 37,194 38,694 41,170 57,033 52,610
比率(a)/(b) 0.90 0.88 0.88 0.88 0.86
出典:(社)全国米麦改良協会資料から算出
注1)消費税(地方消費税を含む)相当額を除いた額。
注 2)建値条件は、ばら、1等、産地倉庫在姿。
(3) 大豆
大豆については、自家用の生産を除きほぼ全量が、農協系統を通じた出荷となっ
ており、県内卸業者を通じて、同じく県内の豆腐を始めとする製造業者に供給され
ている。
大豆の価格形成は入札によることが基本となっている。
21年愛知県産大豆は、梅雨明けが遅く、播種が遅れたことや登熟期の台風の襲来
などにより収穫量が少なく、60kg当たり7,865円と前年産から13%上昇した。全国
との比較では17年産から20年産までは全国平均の94%から99%であったものが、
21年産では118%の価格となった(表31)。

- 22 -
表31 大豆落札価格の推移(普通・特定加工) (単位:円/60kg)
項 目 17年産 18年産 19年産 20年産 21年産
愛知県産(a) 6,765 6,523 6,947 6,989 7,865
全国(b) 6,931 6,835 7,364 7,079 6,692
比率(a)/(b) 0.98 0.95 0.94 0.99 1.18
出典:(財)日本特産農産物協会資料から算出
注1) 落札平均価格は、60kg当たりの包装代を含み、消費税及び地方消費税等は含まない価格。
注 2) 産地品種銘柄の粒別区分に該当しないものも含めて計算。
注3) 産地倉庫戸前渡し価格(倉庫からの引取運賃・ユーザーへの配送経費等は含まない価格)。
注 4) 平成 21年産は平成22年7月までの落札価格。
課 題
• 米については、「コシヒカリ」、「あいちのかおり」、「ミネアサヒ」を基幹
品種とした売れる米づくりの推進が必要である。
• 麦、大豆については、実需者の求める品質の確保と安定生産の推進が必要であ
る。
4 環境対策
水田作について、化学合成農薬や化学肥料の使用量低減などに取り組むエコファー
マーは、平成21年度末時点で868人、1,197件の計画が認定されており、「農地・水・
環境保全向上対策」により、これらエコファーマーが地域ぐるみで環境負荷の低減に
向けた水稲、麦・豆類の先進的な取組は92地域、1,580haで実施されている。
また、本県では農産物環境安全推進マニュアルを策定し、農業生産に伴う環境負荷
の低減と農産物の安全性の確保に取り組んでいる。麦、大豆に関してはJAあいち版
GAP等により、ほぼ全産地でGAP手法に取り組んでいる。
さらに、米については、JAグループ愛知は「安心あいち米」の推進に取り組み、
環境対策に寄与している。
注)安心あいち米:JA米でかつ①農薬使用 12 成分以下(慣行対比 20%減)、②環境
に優しい全量基肥使用のもの。
なお、JA米は①生産履歴がきちんと記録され、②銘柄が確認された種子(種子更
新)により生産し、③農産物検査を受検した米。
課 題
• 農業生産に伴う環境負荷の低減と農産物の安全性の確保のため、引き続き、こ
れらに配慮した稲・麦・大豆生産の推進が必要である。

- 23 -
5 消費拡大対策
本県は、名古屋市を始めとする大消費地を抱えた米、麦、大豆生産県であり、流通
コストが少なくてすむこと、農家と消費者・実需者の距離が近く連携がとりやすいこ
となどを活かして、地産地消の取組を推進している。
米については、「いいともあいち運動」を活用するなどして、JAグループ愛知と
市町村の連携により学校給食への県産米の供給を進めるとともに、公的施設や企業等
の社員食堂での利用促進を図っている。
また、米の消費拡大の一つとして、米粉の利用拡大を進めており、米粉の認知度を
高めるため、平成21、22年度に、「米粉・Rice Powderフェア」を開催し、消費者に
対して米粉利用食品の良さや特徴をPRした。
麦、大豆についても、学校給食に県産麦を使用したうどん、パンや県産大豆を使用
した豆腐等を供給するとともに、公的施設や企業等の社員食堂での利用促進を図って
いる。
特に近年では、地産地消に対する関心の高まりから、食品事業者には「愛知県産小
麦使用」や「愛知県産フクユタカ使用」などの強調表示をするなど地産地消に積極的
に取り組む動きがある。
課 題
• 実需者ニーズに応えるため、品質、量を安定的に供給するとともに、本県版地
産地消の取組である「いいともあいち運動」を活用して県産米、麦、大豆の消
費拡大を図る必要がある。

- 24 -
Ⅲ 品目別生産指標及び推進方策
1 水稲(主食用米)
(1) 生産対策
ア 作付面積・単収・収穫量に関する目標(表32)
主食用米に関しては、国の需給調整対策に即した生産を行う。
平成8年から22年までの需要実績(22年は需要見込み)から、27年の国全体
の需要量を 760万tと見込む。これに対し、18年産から22年産の愛知県産シェ
アから27年産のシェアを0.01806と見込む。これらから、平成27年産の主食用
米の生産量を137,300tとする。
単収については、栽培技術の改善、作付品種の転換などにより、10a当たり
508kgとする。
よって、平成27年度の主食用米作付面積は、27,000haとする。
需要量の推移
700
750
800
850
900
950
8年 9年 10年
11年
12年
13年
14年
15年
16年
17年
18年
19年
20年
21年
22年
23年
24年
25年
26年
27年
需要量
(万t)
759
0
愛知県シェアの推移
0.01776
0.017930.01787
0.01775
0.01749
0.01740
0.01750
0.01760
0.01770
0.01780
0.01790
0.01800
0.01810
0.01820
18年産 19年産 20年産 21年産 22年産 23年産 24年産 25年産 26年産 27年産
0.01806
0

- 25 -
表32 水稲(主食用、米粉・飼料用)の作付面積・単収・収穫量の目標
項 目 現 状 23年産 24年産 25年産 26年産 目標
(27年産)
作付面積 (ha) 31,660 30,590 30,340 30,090 29,840 29,800
うち主食用 (ha) 30,950 29,630 28,970 28,310 27,650 27,000
うち加工用 (ha) 250 270 280 290 300 300
うち米粉・飼料用 (ha) 84 600 970 1,340 1,710 2,300
うちWCS用稲 (ha) 34 90 120 150 180 200
10a当たり収量 (kg) 505 506 507 507 508 508
うち米粉・飼料用 (kg) - 531 532 532 533 533
収穫量 (t) 160,000 154,490 153,460 152,130 150,910 151,100
うち主食用 (t) 157,100 149,900 146,900 143,500 140,300 137,300
うち加工用 (t) - 1,400 1,400 1,500 1,500 1,500
うち米粉・飼料用 (t) - 3,190 5,160 7,130 9,110 12,300
注 1)現状は平成17~21年の5年平均 ただし、主食用作付面積、収穫量は20、21年の平均
(作物統計)。
注 2)加工用、新規需要米(米粉用、飼料用、WCS用稲の現状は21年産(園芸農産課調べ)。
イ 品質に関する目標(表33)
品質、特に農産物検査における1等比率を全国平均レベルまで引き上げること
とし、1等比率の目標を80%とする。
表33 品質(検査等級)に関する目標 (単位:%)
項 目 現状 目標
(27年産)
水稲うるち玄米 1等 62.6 80.0
小 麦 1等 76.5 90.0
1等 37.2 40.0 大 豆
1、2等 72.4 75.0
注)現状は平成17~21年産の単純平均。
ウ 生産コストに関する目標(表34)
生産コストは現状から10%以上低減することとし、60kg当たり全算入生産費の
目標を10,000円とする。

- 26 -
表34 生産コストに関する目標 (単位:円)
項 目 現状
(20年産)
目標
(27年産)
水 稲 11,134 10,000
小 麦 8,907 8,000 60kg当たり
全算入生産費 大 豆 20,423 19,500
(2) 目標達成に向けた取組
ア 品種構成、導入・普及すべき技術
作付品種については、平坦地においては、「あいちのかおり」と「コシヒカリ」、
中山間地においては「ミネアサヒ」を基幹品種として位置づける。
なお、平坦地については、「コシヒカリ」と「あいちのかおり」の間をうめる
補完品種として「ゆめまつり」を位置づけ、26年を目途に「あさひの夢」から全
面的に切り替え、「あきたこまち」、「大地の風」は需要に応じた、地域限定生
産とする(表31)。
近年問題となっている夏期の高温による品質低下に対しては、農総試において
高温等熟成に優れる品種を育成中であるが、完成の見込みは平成25年度である。
そこで、中山間地向け品種として育成した「みねはるか」は、高温登熟性が優れ
ることが認められたことから、実需者評価等を踏まえたうえで、「コシヒカリ」
の一部代替として平坦地での作付けを進める。
表35 水稲品種別作付面積の目標
作付面積(ha) 比率(%) 品種名
21年産 27年産 21年産 27年産
あいちのかおりSBL 12,900 13,000 41.5 44.8
コシヒカリ 8,100 7,300 26.0 25.2
ゆめまつり 0 3,500 0.0 12.1
あさひの夢 2,300 0 7.4 0.0
ミネアサヒ 1,600 1,500 5.1 5.2
祭り晴 940 0 3.0 0.0
大地の風 880 800 2.8 2.8
その他 4,380 2,900 14.1 10.0
計 31,100 29,000 100.0 100.0
注 1)21年実績は園芸農産課推計値。
注2)面積は米粉用・飼料用米等を含む。
栽培面では、各経営体の経営形態に合わせ、育苗が不要で大幅な労働時間の短

- 27 -
縮によるコスト低減等が可能なV直の導入拡大を進める。
なお、V直は、冬季代かきの実施が基本となっているが、用水を十分に確保で
きない地域においては、代かきに替わる技術として浅耕鎮圧等を導入推進すると
ともに、同栽培法は、3回の除草剤散布が基本となっていることから、この削減
に向けた技術開発を行う。
また、V直による深水無落水栽培は、品質の向上、施肥量の低減、雑草の抑制
等に効果があることが示唆されていることから、その効果を検証するとともに普
及を図る。
こうして、27年度のV直実施目標面積を2,000haとする(表36)。
表36 各作物の技術導入の目標
作 物 技術名 現状
(21年)
目標
(27年)
水 稲 不耕起V溝直播栽培 1,506ha 2,000ha
小 麦 新品種「きぬあかり」 12ha 1,500ha
大 豆 帰化アサガオ類防除対策
(発生レベル「多」、「中」の面積率) 11.9% 6.0%以下
注)帰化アサガオ類の発生レベル「多」は、ほ場一面に発生し、被度30%以上
の状態を、「中」はほ場全面に散見、又は一部に密生して、被度10%以上、
30%未満の状態を示す。
さらに、近年斑点米カメムシ類による
1等比率の低下や減収が問題となってい
るため、耕種的防除と組み合わせて、薬
剤防除の徹底を図る。
種子更新率の目標は80%とし、一方種
子の農産物検査合格率の本来 100%であ
るべきだが、段階的な目標として80%と
する(表37、38)
イ 共同利用施設整備等
共同乾燥調製施設においては、改正食
糧法に基づき、用途に応じた区分管理及
び農協系統の自主規格を踏まえた乾燥調
製により品質向上と均質化やトレーサビ
リティシステムを徹底する。
また、色彩選別機の導入を進めるとと
もに、品質低下を来さないような保管管
理を徹底する。
さらに、主食用米のほか新規需要米の拡大に備え、既存施設の再編整備を行う。
表37 種子更新率の目標
(単位:%)
品目 現状
(21年産)
目標
(27年産)
水稲 73.2 80.0
小麦 100.0 100.0
大豆 50.2 50.0
表38 種子合格率の目標
(単位:%)
品目 現状 目標
(27年産)
水稲 70.4 80.0
小麦 62.3 80.0
大豆 37.7 50.0
注)現状は17~21年産の平均。

- 28 -
ウ 安全・安心な米生産
安全・安心に対する消費者の関心の高まりに対応するため、種子更新の徹底や
生産者による生産工程管理、生産履歴の記帳の徹底を図る。
また、JAグループ愛知が進めている「JA米」、「安心あいち米」の取組や
「いきいき愛知認証米」の需要に応じた生産を支援する。
エ 出荷・流通対策
平成22年4月1日から施行された改正食糧法による米穀出荷・販売事業者の遵
守事項について周知、徹底を図るとともに、これまでの生産履歴の記帳と併せ、
米トレーサビリティ法による取引等の記録の作成・保存及び産地情報の伝達の徹
底を図る。
オ 消費拡大対策
児童、生徒に対しては、引き続き学校給食を通じた食育により、米を中心とし
た日本型食生活の良さを啓発するとともに、バケツ稲作や田植え・稲刈り体験な
どを通じて稲、米、ご飯に親しむ機会を提供することで農業への理解促進と米消
費拡大の意識付けを図る。
また、企業の社員食堂などへの利用促進を図ることで、本県産米の利用拡大を
図る。
2 水稲(米粉用米・飼料用米、WCS用稲)
(1) 生産対策
ア 作付面積・単収・収穫量に関する目標(表32)
米粉用米、飼料用米については、JAグループの取組を中心として、27年産作
付面積を2,300ha、10a当たり収量は、主食用米より5%多い533kgとする。
収穫量を12,300tとする。
WCS用稲については、27年産作付面積200haを目標とする。10a当たり収量
については、収穫時の水分含有率により大きく変動するため目標は定めないが、
平成21年度の調査では10a当たり3t近い収量(水分60%)を得た事例もあり、
一つの目安とする。
イ 品質に関する目標
米粉用米、飼料用米、WCS用稲については、当面は特に定めない。
ウ 生産コストに関する目標
当面は生産コストに関する目標値は特に定めないが、販売単価が極端に低いこ
とから、主食用米を基本にさらに低減させる必要がある。
このため、V直など低コスト技術や多収性品種の導入を含めた多収技術の開発、

- 29 -
普及に努める。
(2) 目標達成に向けた取組
ア 品種構成、導入・普及すべき技術
米粉用米、飼料用米、WCS用稲に使用する品種については、種子供給や交雑、
漏生もみなどの問題があることから、当面は主食用米品種を活用することとし、
作付拡大や作付けの団地化の状況を踏まえつつ、専用品種、多収性品種の導入も
視野に入れて推進する。
栽培技術については、V直など直播栽培により生産コスト低減に努める。特に
倒伏しにくく、地耐力の強いV直は、成熟期前に収穫するWCS用稲の多肥栽培
にも適応しやすい栽培法との知見があるため積極的に導入する。
なお、病害虫防除について、栽培コストの低減のために省略されがちであるが、
周辺の作物作付状況に留意し、特にカメムシ類等の防除を適正に実施する。
また、収穫に当たっては、用途に応じた適期収穫に努める。
イ 共同利用施設整備等
米粉用米、飼料用米については、改正食糧法に基づき主食用米と厳格に区別し
て保管、出荷する必要がある。このため、既存施設の補修、更新等を含めた再編
整備を推進する。
WCS用稲では、栽培面においては既存の水稲と共通して機械を利用できるが、
収穫・調製時に専用の機械が必要である。今後拡大するに当たっては、これら収
穫機、調製機の導入を支援する。
ウ 安全・安心な米生産
米粉用米に使用する農薬は、主食用米と同様、農薬取締法に基づく登録農薬で
あることが必要である。現状では、飼料用米については「飼料として使用する籾
米への農薬の使用について(平成21年 4月 20日付け21消安第658号、21生畜第
223号、農林水産省関係課長通知)」に、飼料用稲、WCS用稲については、「稲
発酵粗飼料用稲に係る農薬使用について(平成19年11月19日付け19生畜第1579
号畜産振興課長通知)」に基づく農薬使用を遵守する必要がある。
エ 出荷・流通対策
平成22年4月1日から施行された改正食糧法による米穀出荷・販売事業者の遵
守事項について周知、徹底を図るとともに、これまでの生産履歴の記帳と併せ、
米トレーサビリティ法による取引等の記録の作成・保存及び産地情報の伝達の徹
底を図る。
WCS用稲は、収穫・調製、運搬に多大な労力を要することから、耕畜連携に
よる生産と出荷・流通体制の確立が必要である。このため、地域の実情にあった
体制整備を推進する。
オ 消費拡大対策

- 30 -
米粉用米については、消費者に対して、米粉利用食品の認知度の向上を図ると
ともに、生産者と実需者(食品製造業者)の情報交換の場を設定するなどの連携
強化を図る。
飼料用米、WCS用稲については、 耕種農家と畜産農家の連携を促進する。
3 麦類(小麦、六条大麦)
(1) 生産対策
ア 作付面積・単収・収穫量に関する目標(表39)
小麦の作付面積については、現在の産地では今後拡大できる余地は少なく、減
少傾向にあることから、当面は現状維持を目標とし、作付面積 5,500ha、うち水
田作を5,400haとする。
単収については、排水対策の徹底などにより生産性の向上を図り、10a当たり
収量目標を360kgとし、収穫量目標は19,800tとする。
六条大麦については、実需者の希望する数量を確保するため作付面積を 90ha、
10a当たり収量を330kg、収穫量300tを目標とする。
表39 麦類の作付面積・単収・収穫量の目標
項 目 現 状 23年産 24年産 25年産 26年産 目標
(27年産)
作付面積 (ha) 5,580 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
うち田作 (ha) 5,436 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500麦
類
収穫量 (t) 18,220 18,700 19,100 19,600 20,100 20,100
作付面積 (ha) 5,510 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
うち田作 (ha) 5,364 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
10a当たり収量 (kg) 326 335 343 352 360 360
小
麦 収穫量 (t) 18,000 18,414 18,876 19,338 19,800 19,800
作付面積 (ha) 72 78 81 84 87 90
うち田作 (ha) 72 78 81 84 87 90
10a当たり収量 (kg) 304 312 317 321 326 330
六条大麦
収穫量 (t) 219 240 260 270 280 300
注 1)現状は平成17~21年の5年平均(作物統計)。 注 2)ラウンドの関係で、計が合わないことがある。
イ 品質に関する目標(表33)
小麦の品質については、直近5年のうち極端に1等比率が低かった平成18年産
を除けば、4年平均が87.1%であることから目標値を90%とする。
また、水田経営所得安定対策における品質評価区分のAランク比率目標値は
65%とする。
ウ 生産コストに関する目標(表34)
生産コストは現状から10%以上低減することとし、60kg当たり全算入生産費の
目標を8,000円とする。

- 31 -
(2) 目標達成に向けた取組
ア 品種構成、導入・普及すべき技術
小麦の作付品種については、「イワイノダイチ」の大部分と「農林61号」の一
部を、本県が育成し、22年度に奨励品種化した「きぬあかり」に置き換えること
とする。
「きぬあかり」の導入について、24年産から一般栽培を開始し、実需者の評価
に配慮しつつ順次拡大を図る一方で、種子供給の問題から「イワイノダイチ」の
取扱を早い段階に決定する。なお、27年産における「きぬあかり」の作付面積は
1,500haを目標とする(表36、40)。
なお、パン・中華めん用品種については、早急に本県に適応する品種を選定す
るとともに、導入方針を検討する必要がある。
六条大麦の作付品種については、実需者と生産者の協議により、「カシマムギ」
と「さやかぜ」の作付比率を7:3としており、これに即した作付けを行う。
麦類については、21、22年産と続けて不作に見舞われた。この主たる要因は播
種の遅れに伴う生育不良や湿害による登熟不良など、降水量が多かったことなど
気象によるところが大きいものの、栽培面の取組による地域差も見られた。
麦栽培において も重要なポイントである排水対策について、この2か年の結
果を踏まえ、改めて「弾丸暗きょの施工」等の実施率向上を図る。
また、小麦については実需者からタンパク質含量の向上・安定が求められてい
ることから、引き続き、肥効調節型肥料等を利用したタンパク質含量の向上に努
める。
表40 小麦品種別作付面積の目標
作付面積(ha) 比率(%) 品種名
21年産 27年産 21年産 27年産
農林61号 3,143 2,800 58.0 50.9
イワイノダイチ 2,089 1,200 38.5 21.8
きぬあかり 12 1,500 0.2 27.3
その他 176 0 3.2 0.0
計 5,420 5,500 100.0 100.0
注 1)21年品種別作付面積は、JAあいち経済連集計値、計は統計公表値。
注 2)21年産は、品種別作付面積の合計と統計値の差を「その他」の品種とした。
種子更新率の目標は引き続き 100%とし、一方種子の農産物検査合格率は、段
階的な目標として80%とする(表31、32)
イ 共同利用施設整備等
共同乾燥調製貯蔵施設については、麦や新規需要米の生産拡大の計画に合わせ、
既存施設の補修、更新等を含めた再編整備を推進する。

- 32 -
ウ 安全・安心な麦生産
消費者の安全・安心への関心の高まりに対応するため、種子更新の徹底や生産
者による生産工程管理、生産履歴の記帳の徹底を図る。
特に、例年発生しやすい赤かび病は、そのかび毒(DON(デオキシニバレノ
ール)等)が消費者の健康に影響を与える恐れがあるので、防除の徹底を指導す
る。防除に当たっては、農薬飛散防止等に配慮するなど、ポジティブリスト制度
に対応した麦づくりを推進する。
また、残留農薬分析やDON分析等を実施し、安全性を確保した上で実需者へ
出荷する。
エ 出荷・流通対策
引き続き、効率的なバラ流通を円滑に進めるために、産地ごとの品質格差をな
くすよう努める。
オ 消費拡大対策
小麦については、製粉業者と食品業製造業者のマッチングの機会を提供するな
どして、地産地消の取組を進める。
5 大豆
(1) 生産対策
ア 作付面積・単収・収穫量に関する目標(表41)
大豆は、播種時期が梅雨と重なり、生産が不安定であること、帰化アサガオ類、
カメムシ類の発生による減収、品質低下などにより、作付面積は漸減傾向である
が、麦後での作付けが主体であることから、単純な面積の比較では、今後やや拡
大できる余地はある。
麦後の不作付け地解消と併せ、作付面積の目標を 4,500ha、うち水田作を
4,200haとする。
単収については、適期播種の実施などにより生産性の向上を図り、10a当たり
収量の目標を180kgとし、収穫量目標は8,100tとする。
表41 大豆の作付面積・単収・収穫量の目標
項 目 現 状 23年産 24年産 25年産 26年産 目標
(27年産)
作付面積 (ha) 4,340 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
うち田作 (ha) 4,024 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
10a当たり収量 (kg) 144 156 162 168 174 180
収穫量 (t) 6,238 7,010 7,280 7,550 7,830 8,100
注)現状は平成17~21年の5年平均(作物統計)。
イ 品質に関する目標(表33)
農産物検査の1等比率、上位等級(1、2等比率)は全国平均を上回っている

- 33 -
が、引き続き、品質の向上に努める。
1等比率、上位等級比率をそれぞれ40%、75%を目標とする
ウ 生産コストに関する目標(表34)
生産コストは現状から5%程度低減することとし、60kg当たり全算入生産費の
目標を19,500円とする。
(2) 目標達成に向けた取組
ア 品種構成、導入・普及すべき技術
大豆品種については、豆腐用途として好まれる「フクユタカ」がほとんどであ
る。実需者からは、煮豆用、納豆用など他品種についての要望もあるが、現状「フ
クユタカ」を上回る品種が見あたらず、また、量的にも需要に応えられていない
ことから当面「フクユタカ」1品種を基幹品種として作付けする(表37)。
21 年産大豆は梅雨明けの遅れによる播種の遅れと梅雨明け後の干ばつによる
生育不良や登熟期の台風による倒伏などで、平年に比べ大幅に減収した。このこ
とを踏まえ、改めて麦作と併せた排水対策の徹底と図る必要がある。
表42 大豆品種別作付面積の目標
作付面積(ha) 比率(%) 品種名
21年 27年 21年 27年
フクユタカ 4,239 4,500 99.3 100.0
その他 31 0 0.7 0.0
計 4,270 4,500 100.0 100.0
また、収量、品質向上のための技術として、大豆 300A技術やその類似技術、
県が独自に開発した技術を地域の実情に合わせて普及させる。
具体的には、
① 畝立て播種技術:播種直後の降雨による発芽障害回避を目的として、10cm
前後の畝を立てて播種する技術。
② 高能率摘心機による大豆の増収技術:倒伏軽減、着莢数の増加による増収
を目的として、高能率摘心機を使用して摘心する技術。
③ 狭畦密植栽培技術:播種の遅れや土壌条件などにより、生育量不足が予想
される場合に、全体の生育量を確保することを目的として慣行栽培より
密植する技術。
を推進する。
そのほか、帰化アサガオ類やカメムシ類防除の徹底を図る。
帰化アサガオ類については、薬剤散布や中耕・培土等を組み合わせて、発生状
況に応じた適正な防除を実施することにより、発生程度「中」以上の面積割合を、
11.9%(21年度)から6.0%へ減少することを目標とする(表36)。
種子更新率の目標は50%とし、種子の農産物検査合格率は段階的な目標として
50%とする(表37、38)

- 34 -
イ 共同利用施設整備等
本県大豆の調製は、ほとんど生産者自身が、個人所有又は農協が設置した共同
調製施設を利用して行っている。大豆の均質化及び低コスト化を図るため、共同
調製施設の整備を行うとともに、品質低下の大きな原因となっている着色粒を除
去するため、色彩選別機の導入を進める。
ウ 安全・安心な大豆生産
安全・安心に対する消費者の関心の高まりに対応するため、種子更新の徹底や
生産者による生産工程管理、生産履歴の記帳の徹底を図る。
近年はフェロモントラップによるハスモンヨトウ防除の取組が行われ、一定の
効果を示している一方で、カメムシ類による被害が顕在化してきている。このた
め、カメムシ類防除を徹底するとともに、防除に当たっては、農薬飛散防止等に
配慮するなど、ポジティブリスト制度に対応した大豆づくりを推進する。
また、残留農薬分析等を実施し、安全性を確保した上で実需者へ出荷する。
エ 出荷・流通対策
生産者ごとの品質格差をなくすため、より選別の精度を上げるよう努める。
オ 消費拡大対策
いいともあいち運動を活用し、地産地消の取組を進めるとともに、実需者ニー
ズに即した安定供給に努める。

- 35 -
Ⅳ 地域別推進方策
1 地域別担い手の状況
本県の稲、麦、大豆を中心とした水田作の認定農業者は、平成21年度が478経営体
となっている。その地域別内訳は、尾張 188 経営体、西三河 250 経営体、東三河 40
経営体で、西三河地域が県全体の52.3%を、続いて、尾張地域が39.3%を占めている。
なお、地区別に見ても西三河地区が195経営体で県全体の40.8%を占めるに至ってい
る(表43)。
また、水田経営所得安定対策への加入者は、平成22年度県全体が379経営体、その
地域別内訳は、尾張70経営体、西三河275経営体、東三河34経営体で、西三河地域
が275経営体で72.6%を占めている。また、尾張地域の認定農業者は、水田経営所得
安定対策への加入率が低い(表43)。
表 43 地域別認定農業者数(水田作・21 年度)と水田経営所得安定対策加入者数(22 年度)
の状況
(単位:経営体)
構成比率 構成比率
地 域 地 区 認 定
農業者数 (%)
水田経営
所得安定対策
加入者数 (%)
認 定
農業者
集落営農
組 織
県 計 478 100.0 379 100.0 370 9
188 39.3 70 18.5 69 1
名古屋市 2 0.4 0 0.0 0 0
尾 張 77 16.1 13 3.4 13 0
海 部 70 14.6 46 12.1 45 1
尾 張
知 多 39 8.2 11 2.9 11 0
250 52.3 275 72.6 267 8
西 三 河 195 40.8 220 58.0 213 7 西三河
豊田加茂 55 11.5 55 14.5 54 1
40 8.4 34 9.0 34 0
新城設楽 21 4.4 18 4.7 18 0 東三河
東 三 河 19 4.0 16 4.2 16 0
出典:農業振興課資料、園芸農産課調べ
注1)認定農業者数は22年 3月末現在で水稲主体及び水稲+麦+大豆の経営体の実績。
注 2)水田経営所得安定対策加入者数は22年度実績。
注 3)時点等が異なるため認定農業者と水田経営所得安定対策の認定農業者は同一ではない。
平成 21 年度の県全体の水田の利用権設定等面積は、10,186ha で、田面積に占める
割合は22.7%となっている。このうち西三河地域は7,199haで、全体の70.6%を占め
ており、水田面積に対する設定率も40.7%と高い。一方、尾張地域は作業受託による
利用集積が多く、利用権等設定率は低い(表44)。

- 36 -
表 44 地域・地区別利用権設定等面積(平成22年3月末現在)
田面積
(H21.7.15)
利用権設定
面積(田)
所有権移転
面積(田・累計)
利用権設定等
面積(田) 利用権等設定率
地 域 地 区
① ② ③ ④=②+③ ⑤=④/①*100
(ha) (ha) (ha) (ha) (%)
県 計 44,900 9,926 260 10,186 22.7
19,500 1,870 82 1,952 10.0
名古屋市 553 3 0 3 0.5
尾 張 8,013 470 15 485 6.1
海 部 6,388 698 24 721 11.3
尾 張
知 多 4,577 700 43 743 16.2
17,700 7,161 37 7,199 40.7
西 三 河 11,949 5,491 23 5,514 46.1 西三河
豊田加茂 5,723 1,670 14 1,684 29.4
7,730 895 142 1,036 13.4
新城設楽 2,284 341 27 368 16.1 東三河
東 三 河 5,442 553 115 668 12.3
出典:農業振興課資料から作成
注)田面積の県計、地域計は公表値のため、地区の計と合わないことがある。
表 45 戸別所得補償モデル対策への加入申請状況(平成22年8月末) (単位:戸)
内 訳
構成地 域 地 区
加入者数 合 計
構成比率
(%)
うち 新規加入
新 規加入者率(%)
個人 法人 集落営農
戸数
県 計 20,304 100.0 5,869 28.9 20,215 67 22 611
6,831 33.6 3,446 50.4 6,796 24 11 452
名 古 屋 571 2.8 107 18.7 570 1 0 0
尾 張 1,757 8.7 1,149 65.4 1,745 10 2 18
海 部 3,765 18.5 1,646 43.7 3,745 11 9 434
尾 張
知 多 738 3.6 544 73.7 736 2 0 0
11,126 54.8 957 8.6 11,086 32 8 107
西 三 河 8,629 42.5 19 0.2 8,599 23 7 75西 三 河
豊田加茂 2,497 12.3 938 37.6 2,487 9 1 32
2,347 11.6 1,466 62.5 2,333 11 3 52
新城設楽 1,739 8.6 910 52.3 1,729 7 3 52東 三 河
東 三 河 608 3.0 556 91.4 604 4 0 0

- 37 -
平成22年度の戸別所得補償モデル対策への加入申請者数は、県全体で20,304 戸、
うち西三河地域が11,126戸で、54.8%を占めている。
また、20,304 戸のうち、5,869戸が前年まで生産調整に参加していなかった新規加
入農家で、尾張、東三河地域ではこの割合が、それぞれ50.4%、62.5%と、半数以上
を占めている(表45)。
2 地域別稲・麦・大豆生産状況(表46)
平成17年産から21年産の水稲、麦類、大豆の生産状況を表46に示した。
水稲について、作付面積では、尾張地域が県全体の50.2%を占めており、地区別で
は、西三河、尾張地区がそれぞれ約22%を占めている。10a当たり収量は、西三河地
域が515kgで他地域より高い。地区別では尾張地区が、唯一400kg台で、他地区と比
べやや低い。
麦類について、作付けの大半を占める小麦の作付面積は、西三河地域が、県全体の
88.5%と大半をこの地域が占めており、地区別に見ても西三河地区が71.3%を占めて
いる。小麦の10a当たり収量は、西三河地域が329kgで、他地域と比べやや高い。地
区別では海部地区が 340kg、西三河地区が 338kg となっている。また、尾張地区で六
条大麦が作付けされている。
大豆について、作付面積では、西三河地域が県全体の81.3%と大半をこの地域が占
めており、地区別に見ても西三河地区が72.9%を占めている。10a当たり収量は、尾
張地域と西三河地域がそれぞれ145kg、144kgと並んでいるが、地区別では海部地区の
173kgが突出して高い。
表46 地域・地区別収穫量(水稲・麦類・大豆 平成17~21年産平均)
水 稲 小 麦 六条大麦
作付面積
比率 収量 収穫量作付面積
比率 収量 収穫量作付面積
比率 収量収穫量
作付面積
比率 収量 収穫量
(ha) (%) (kg) (t) (ha) (%) (kg) (t) (ha) (%) (kg) (t) (ha) (%) (㎏) (t)
31,660 100.0 505 160,000 5,510 100.0 326 18,000 72 100.0 304 219 4,340 100.0 144 6,238
15,880 50.2 501 79,480 510 9.3 318 1,630 71 98.2 309 220 672 15.5 145 975
名古屋市 571 1.8 508 2,898 0 0.0 210 0 - -- - - 9 0.2 119 11
尾 張 6,971 22.0 485 33,784 21 0.4 200 42 70 97.5 306 214 100 2.3 99 101
海 部 4,862 15.4 509 24,742 437 7.9 340 1,487 - -- - - 444 10.2 173 766
知 多 3,461 10.9 521 18,021 52 0.9 192 100 - -- - - 118 2.7 77 98
9,978 31.5 515 51,420 4,874 88.5 329 16,040 - -- - - 3,528 81.3 144 5,096
西 三 河 7,019 22.2 521 36,585 3,926 71.3 338 13,264 - -- - - 3,165 72.9 147 4,667
豊田加茂 2,972 9.4 502 14,920 947 17.2 292 2,763 - -- - - 364 8.4 118 429
5,790 18.3 501 29,020 124 2.2 270 332 - -- - - 141 3.2 118 167
新城設楽 1,441 4.6 503 7,248 8 0.1 176 13 - -- - - 32 0.7 107 34
東 三 河 4,349 13.7 501 21,799 115 2.1 292 320 - -- - - 109 2.5 122 133
県 計
尾 張
西三河
東三河
水 稲 (子実用) 麦 類 (子実用)大 豆
地 域 地 区
出展:農林水産統計から作成
注1)ラウンドの関係で、地区の計と地域・県計が合わないことがある。
注2)収量は10a当たり
注2)市町村別の公表値を集計し、5か年単純平均したものであるため、作付面積、収量、収穫量の計算が合わないことがある。
注3)麦類については、農林水産統計に非公表値があるため、一部推計値を用いた。

- 38 -
3 尾張地域
(1) 地域の概要
尾張地域の水田作の担い手については、認定農業者数は、188 経営体であり、県
全体の39.3%を占める。主に作業受託を主体に、経営規模の拡大が図られている。
また、一部では、農協出資法人による営農が行われている。
尾張地域は、県内の水田面積の4割以上を占め、水稲作付面積の5割を占めてい
る。
水稲については、海部、知多地区の一部では有機栽培やレンゲ緑肥を利用した特
別栽培とこれよる地産地消の取組がされている。また、近年の夏季の高温による「コ
シヒカリ」の品質低下から、高温登熟性に優れる「みねはるか」の導入に向けた動
きがある。なお、海部地区の一部、知多地区では、WCS用稲の取組がある。
麦、大豆については、海部地区の一部で盛んに取り組まれており、麦については
肥効調節型肥料を利用したタンパク質含量の向上、大豆では、畦立て栽培や摘心技
術など新技術の導入にも積極的である。また、尾張地区の一部では、地元企業との
契約栽培による六条大麦の栽培が行われている。
(2) 推進方策
担い手については、引き続き経営安定のため、規模拡大及び戸別所得補償制度へ
の加入を推進する。なお、規模拡大に当たっては、作業効率を高め、低コスト化が
図れるよう配慮する。
現状、水稲の過剰作付けがあり、集団的な水田利用の取組が少なく、麦、大豆の
作付けが困難である地区には、今後、新規需要米の取組を積極的に進め、過剰作付
の解消に努める。
なお、水稲については、品質向上を進める一方、特徴ある栽培による高付加価値
化、地産地消の取組を進めるとともに、「みねはるか」の導入に当たっては、需要
に見合った計画的な生産を進める。
また、麦、大豆については、戸別所得補償制度において、収量、品質に従って交
付額が大きく増減する仕組みのため、取組がある地区においては、今後さらに収量、
品質の向上が図られるよう努める。
4 西三河地域
(1) 地域の概要
西三河地域の水田作の担い手について、認定農業者数は、250 経営体であり、県
全体の 52.3%を占める。また、平成 22 年度の水田経営所得安定対策への県全体の
加入経営体数379に対し、72.6%をこの地域が占めている。
なお、戸別所得補償モデル対策への加入者数は、県全体の 54.8%を占めており、
特に加入申請者数に対する新規加入者率が 8.6%と、他地域に比べ低く、従前から
生産調整に積極的に取り組んできた地域である。
また、担い手について、田面積に対する利用権等設定率が40.7%と、他地域に比
べ顕著に高いなど、主に経営受託を主体に、規模の拡大が図られており、中には経

- 39 -
営面積100ha規模の農事組合法人もある。
平坦部を中心に、ブロックローテーションによる稲-麦-大豆の2年3作体系が
広く実施され、県内水稲の3割以上、小麦、大豆の8割以上を作付けする本県水田
農業の中心地である。水稲については、近年の夏季の高温による「コシヒカリ」の
品質低下から、高温登熟性に優れる「みねはるか」の導入に向けた動きがある。
また、小麦、大豆については、気象の影響や雑草、害虫の発生などにより、近年
生産性が低下しているが、小麦については、弾丸暗きょの施工等、排水対策の徹底、
大豆については、帰化アサガオ類の防除対策等の重要性が改めて理解され積極的に
取り組む動きがある。さらに、小麦について、新品種「きぬあかり」をこの地域で
先駆的に拡大することとしている。
なお、県内向け水稲種子の大半と、小麦、大豆種子のすべての生産をこの地域で
担っている。
(2) 推進方策
西三河地域は、本県稲、麦、大豆作の中心的地域であり、今後とも、その地位を
維持、発展していく。
西三河地域の水田作の担い手については、引き続き経営安定のため、規模拡大を
進める。なお、規模拡大に当たっては、作業効率を高め、低コスト化が図れるよう
配慮する。
また、稲-麦-大豆の2年3作体系を中心とした、水田の有効利用を図るととも
に、収量、品質の向上を併せた水稲、小麦、大豆の生産性の向上を図る。
水稲について、「みねはるか」の導入に当たっては、需要に見合った計画的な生
産を進める。
麦、大豆については、戸別所得補償制度において、収量、品質に従って交付額が
大きく増減する仕組みのため、小麦では弾丸暗きょ施工等による排水対策の徹底、
大豆では、帰化アサガオ類やカメムシ類防除の徹底による単位面積当たりの生産量
の増加とともに、作付面積の維持、拡大による生産量の増加を図る。また、小麦「き
ぬあかり」については、今後の生産拡大に向け、タンパク質含量等、適正な品質の
確保に努める。
水稲、小麦、大豆の種子については、高品質な種子の安定生産、安定供給に努め
る。また水稲、小麦については、順調に品種転換が進むよう、採種農家、ほ場の選
定及び計画的生産に留意する。
5 東三河地域
(1) 地域の概要
園芸主体の地域で、集団的な水田利用の取組が少なく、水田作の担い手について、
認定農業者数は19経営体であり、県全体の4.0%、水稲作付面積は県全体の13.6%
と少ない。
水稲について、地域の一部で、個別許諾による独自の品種を採用し、化学合成農
薬使用量を低減した特徴ある栽培による地産地消の取組がある。また、近年の夏季

- 40 -
の高温による「コシヒカリ」の品質低下から、高温登熟性に優れる「みねはるか」
の導入に向けた動きや、WCS用稲の取組や今後積極的に推進する動きもある。
また、小麦、大豆については、一部で作付けがみられる。
(2) 推進方策
東三河地域においては、新規需要米の取組を積極的に進め、過剰作付の解消に努
める。特に、WCS用稲を推進する動きもあることから、地域の実情に合わせて推
進する。
水稲について、特徴ある栽培による高付加価値化、地産地消の取組を進めるとと
もに、「みねはるか」の導入に当たっては、需要に見合った計画的な生産を進める。
麦、大豆については、戸別所得補償制度において、収量、品質に従って交付額が
大きく増減する仕組みのため、取組がある地域においては、今後さらに収量、品質
の向上が図られるよう努める。
6 中山間地域
(1) 地域の概要
中山間地域の水田作の担い手について、認定農業者は、水稲主体で21経営体ある。
中山間地域は、作業効率が悪いため、経営規模の拡大が難しく、水稲、麦、大豆
を組み合わせた大規模水田作は困難であるため、麦、大豆の作付けはほとんどない。
水稲については、一部で、県との個別許諾により独自の品種を採用し、地域特産
物として加工、販売する取組が見られる。
新城地区では、水稲の種子生産やコントラクター方式によるWCS用稲生産や水
田放牧の取組がある。
(2) 推進方策
水田作の担い手については、集落営農組織や農協出資農業生産法人等の設立も含
めて進める。
中山間地域の水稲については、加工による地域特産物の開発など特色ある米づく
りを進めるとともに、WCS用稲や水田放牧の取組を進める。