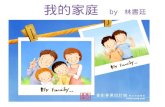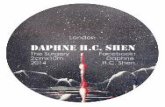工研院 可移轉技術統計 for 機械工會 - TAMI · 應用於機械加工估測刀具磨 耗狀態,取代過去傳統經驗 式換刀或固定切削里程換刀 ,減少因過早換刀造成刀具
村の統率者としての「刀自」 ――村と宮廷における …-・83・-...
Transcript of 村の統率者としての「刀自」 ――村と宮廷における …-・83・-...

-・83・-
「刀自」からみた日本古代社会のジェンダー
――村と宮廷における婚姻・経営・政治的地位――義
江
明
子
はじめに
一章
古代社会におけるジェンダーの特質――研究史より
一節
律令租税制と「編戸」
二節
夫婦単位の未確立
小結
二章
豪族層における「刀自」
一節
村の統率者としての「刀自」
二節 「家」の経営者としての「刀自」
三節 「男耕女織」言説への疑問
帝京史学26号.indb 83 2011/02/16 18:48:29

-・84・-
小結
三章
女性の政治的地位と婚姻・経営
一節
天皇のキサキ「夫人」=「大刀自」をめぐって
二節
古墳埋葬からみる女性首長
三節
伝承と征討記事にみる女性首長
小結
おわりに
はじめに
日本古代には、「刀自」(トジ)とよばれる女性たちがいて、村落における農業経営と村人の指揮に大きな役割
を果たしていた。また社会の上層をみると、天皇のキサキのランクの一つに「夫人」があるが、その和訓はオオ
トジ=「大刀自」である。彼女たちは元来、自分自身の宮で独立した経営を行っていた。
本稿では、古代女性史研究の主要な成果をふまえ、右の二つのレベルにおける「刀自」の社会的・政治的・経
済的働きを考察する。扱う時代は、おおよそ、三・四世紀から一二世紀、なかでもおもな分析対象とするのは八・
九世紀である。
帝京史学26号.indb 84 2011/02/16 18:48:29

-・85・-
日本の古代女性史研究は、すでに七〇年近い歴史をもつ。家族・婚姻史研究からはじまって、所有・政治・祭
祀等の各分野で、さまざまな女性の姿を明かにしてきた。近年では、性愛や子どもをめぐる議論も盛んである。
しかし、残念ながらその成果は、英語圏にはほとんど知られていない。特に、八・九世紀以前の日本女性の姿、
および彼女たちの〝発見〟が、これまでの日本古代史をどう具体的に書き換えつつあるのかについては、わずか
な例外〔Sekiguchi・2003
〕を除いて、全くといっていいほど伝わっていないといっても過言ではない。
本稿は本来、英語圏の日本前近代史研究者・女性史研究者に向けて、日本古代女性史研究の主要な成果を紹介
し、女性史研究の意義を明かにするために書いたものである(〔付記〕参照)。具体的には、古代女性史研究の成
果の中から、戸籍の父系擬制、家族・婚姻史、皇后をめぐる研究をとりあげ、それらを総合してあらたな展望を
示すことをめざした。これらはそれぞれ、一般古代史研究における戸籍論、古代社会論、王権論と多くの接点を
もち、女性史研究の成果は、その限りではこれまでも注目を集め、古代史学界全体に一定の影響を及ぼしてきた
といって良い。ただしそれは、それぞれの分野・テーマにおいて、女性史の成果を〝参照し付け加える〟ことに
とどまりがちであった。古代史の全体認識をゆるがすまでには至っていないのである。
そこで本稿では、これまで女性史研究の中でも具体的に解明されてきたとはいえない、地方村落において農業
経営と村人の指揮に大きな役割を果たした女性たち――「刀自」――に焦点をあて、彼女たちの具体的働きを解
明することを通じて、前記の三つの主要な研究成果が、実は大きな一つの枠組みで理解できることを示したい。
そのために以下、三つの異なる種類の史料を研究の素材としてとりあげる。①朝廷によって編纂された歴史書・
法令、②考古学資料および木簡、③説話である。①の公的記録から得られる女性関係の情報の欠如を補うものと
帝京史学26号.indb 85 2011/02/16 18:48:29

-・86・-
して、②の考古学資料および木簡はとりわけ重要である。③の説話は女性に関する豊富な情報を含むが、研究者
のジェンダー観と思い込みによって、しばしばその重要性は見逃され、誤って解釈されてきた。②の考古学情報
と照らしあわせつつ見ることで、説話をより深く再解釈していくことが可能になろう。
また本稿では、インセスト・タブーの分析、法制用語の日中比較、夫婦観念の長期にわたる変化などを、研究
史の重要な成果としてとりあげ、儀礼の分析を行った。これには理由がある。古代家族・婚姻史研究は多くの
成果をあげてきたが、主要な婚姻居住形態が何であったか、結婚・離婚をめぐる女性の主体性の有無といった基
本的論点をめぐっても、異なる見解が激しく対立し、いまだに決着をみていない〔義江二〇〇二b、三六九―
三七〇頁〕。それは、個々の史料をみていくだけでは、例えば、婚姻居住形態をめぐっては、通いもあり、妻方
居住もあり、夫方居住もあって、どれを主要とみるかは研究者の恣意的判断にゆだねられがちだからである。説
話にみえる婚姻居住例の統計的分析もなされているが、そもそも説話からこうした統計をすることにさほどの意
味があるとは思われない。婚姻・離婚をめぐっても、個々の史料には、夫の行動、妻の行動がさまざまに描かれ
ていて、多様な解釈の余地がある。
それに対して、儀礼や、インセスト・タブー、法制用語の特質、夫婦観念の長期的変化などには、家族・婚姻
形態の全体的特質、ジェンダーの全体構造が、いやおうなく投影されていると考えられる。こうしたものによっ
てまず古代のジェンダー構造の大きな枠組みをつかみ、それをふまえて個別の史料の分析にすすむ、という方法
を本稿では採用した。
まず第一章では、戸籍研究史と家族・婚姻史研究の成果から、八世紀においては夫婦単位は未確立で、夫を通
帝京史学26号.indb 86 2011/02/16 18:48:29

-・87・-
じての妻の労働成果の国家的徴収は実現していないことを確認し、「戸」や家族の枠組みを超えたところで、「妻」
の地位を前提としない〝独立した女〟の公的役割を解明する必要のあることを明らかにする。
次に第二章では、木簡と説話から、村人を率いる半公的地位にあった「里刀自」と、これまでは「家」内部を
統括すると考えられてきた「家刀自」とが、実は同じ実体をさすことを明かにし、正史に頻出する「男耕女織」
が実態の伴わない文飾にすぎないことを、「親耕親蚕」儀礼の再解釈と、「力田」表彰記事の分析から明確にする。
第三章では、天皇のキサキたち=「大刀自」の独立性を論じ、彼女たちと「里刀自」とに共通する歴史的前提
として、三・四世紀以来、日本列島上に広範に存在した女性首長を位置づける。
最後に結論として、「刀自」を軸として大きく古代社会のジェンダーの特質を見通した結果、今後の古代史研
究にどのような新たな展望が開けてくるのかを述べ、多様な史料を総合し分析する際の分析視点の重要性を確認
したい。
一章
古代社会におけるジェンダーの特質
一節
律令租税制と「編戸」
日本は、七世紀の後半ごろから、中国をモデルとした国家体制の整備を本格的にはじめた。国家支配の骨格と
なる律令法体系を中国から導入し、七世紀末にまず令(行政法)、八世紀初に律(刑法)と令の両方が揃った。
ここで完成した律令国家体制には、先進中国をモデルとする、上から枠づけられた国家理念の面が強い。この理
帝京史学26号.indb 87 2011/02/16 18:48:29

-・88・-
念と、日本の伝統社会の実態とはおおきなズレがあり、九世紀以降、平安時代に入るころから、ようやく律令国
家は日本の社会の実態にあう国制へと変容していった。同時に、社会の実態の方も、律令法によって新たに設定
された枠組みに規制されて、次第に伝統的な在り方を脱していったのである(吉田一九八三)。
勿論、日本の律令法は中国法そのままではなく、社会実態にあわせるための改変が随所で試みられている。ど
のような点で中国法からの改変がなされているのかを見ることによって、そこから逆に古代日本の社会実態を解
明する研究がさまざまに行われ、数々の成果を上げてきた。家族と親族のシステム、婚姻・相続をめぐる慣行な
どは、理念と実態のズレが大きく、改変箇所の分析による実態の解明が進展している分野である。
例えば、儀制令五等親条・喪葬令服忌条をみると、父系親族の側に極端に偏った構成をとる中国律令の親等規
定が、日本の律令では母方の親族をも広範囲に含むものに改変されている。これは、日本の基層の親族システム
を双系(双方)的なものとみなす、重要な根拠の一つである(明石一九九〇)。また、財産相続法である戸令応
分条についても、父の財産の息子達による分割を規定した中国法の規定に対し、日本法では、氏人が共有する一
族(氏)の財産を、族長(氏上)が管理分配するという要素が、中国的な法制用語の背後に見いだせる。特に八
世紀初の大宝令応分条では、女子の財産相続権が氏産の相続・分割に包摂される形で存在し、これは伝統的な相
続法の反映と考えられる(義江一九八六、第一編)。
その他にも、日中律令の比較による研究成果はさまざまな分野で蓄積され、『律令』〔日本思想大系〕の補注に
その集約を見ることができる。私は、その成果にジェンダーの観点からの分析を加えることによって、さらに新
たな展望が開けると思う。租税制と「戸」をめぐる問題は、その一つである。
帝京史学26号.indb 88 2011/02/16 18:48:29

-・89・-
律令国家の成立によって、それまでの村単位での生活・生産・貢納のシステム(部の制度)が廃止され、かわりに、
「戸」を単位として成人男性のみに賦課する全国一律の租税制度が実施された。ここで問題の焦点となるのは、「戸」
の性格である。
「戸」および戸籍の制度については、これまでにおびただしい研究がある。八世紀前半の奈良時代の戸籍が数
点まとまって現存し、古代社会史・家族史研究の格好の素材となってきた。かつては、戸籍に記載された「戸」(約
二〇~三〇人程度のメンバーを含む)と戸主を、実際にその通りの大家族と家長の存在を示すものとみて、家父
長制大家族説が盛んに説かれた(戸実態説。石母田一九四二、他)。しかし、一九五〇年代になると、戸籍の史
料批判がはじまり、「戸」は実際の家族とは大きなへだたりがあるとの指摘があいついだ(戸擬制説。岸一九五七a、
他)。さらに、一九六〇年代後半には、「戸」は国家が民衆支配のために人為的に編成した単位であり、戸籍は租
税と徴兵の台帳であるとの説(編戸説。安良城一九六七、義江〔浦田〕一九七二、他)がだされ、広く学界に受
けいれられ定着した。
編戸説は、女性史およびジェンダーの観点からみても、大きな意義をもつ。日中の律令法の比較を通じて積み
上げられてきた律令の理念と社会実態とのズレをめぐる研究成果と、編戸説の成果を総合することによって、国
家は、どのような家族実態をどのような理念で「戸」に編成しようとしたのか、という論点が明確に浮かび上がっ
てきたからである1。
この問題をめぐっては、一九七〇年代後半以降、女性史研究者である関口裕子氏が、先駆者高群逸枝氏の研究
成果を継承しつつ、精力的に解明をすすめてきた。これによって、国家は、「戸」を、(実態に反して)父系で編
帝京史学26号.indb 89 2011/02/16 18:48:29

-・90・-
成しようとしたことが明かにされた(父系編戸説)。戸籍に「嫡妻」と「妾」、「嫡子」と「庶子」が書き分けら
れていても、それは実際に妻と妾、嫡子と庶子の社会的区別が存在したことを意味せず、妻妾が実際に同居して
いたのでもない。また、戸籍に記された夫方同居や父系氏族の背後に、表面には顕れない妻方同居や別居訪問婚、
母系的な氏族のまとまりの実態があるとされた〔高群一九三八、関口二〇〇四〕。
現在の戸籍研究は、徴税の基礎単位設定、父系的原理の導入など、国家の政策方針による擬制を充分認識した
上で、現存戸籍の綿密な分析から、法的擬制の不徹底の陰にのぞく家族・婚姻の素顔を把握するという方向で行
われている。その代表的研究者である南部曻氏は、郡ごとの造籍方針の違いを押さえた上で、夫婦・親子の同籍・
別籍は同居・別居の実態を意味せず、国家の把握方針の違いに過ぎないことを明確にした。当時の通婚はほぼ里
(五〇戸からなる最末端の行政単位)の範囲で行なわれており、戸籍の擬制操作も里単位でなされた。戸籍には
片籍(片親と子ども)と独籍(独身者)が異常に多いが、里単位でみれば両者の男女数はほぼ釣り合っている(南
部一九九二)。「戸」はイヘ(家族)そのものでもなく、イヘの集合そのものでもない。そもそも律令国家はイヘ
そのものを戸籍上に登録することなどめざしてはおらず、「律令国家が知ろうとしたところの実態」は、夫婦関係・
子どもの人数・性別・年齢、その子(特に男子)の父姓継承といったことにすぎない(南部、二三七頁)。
それは、国家の把握力が弱体だったからではない。一般庶民においては、そもそも実態としてのイヘ自体が未
確立で、「籍帳上に明確な「家」の形をとって姿を現し得ない」ものだったからである(杉本一九八四)。戸主を
中心に、国家のめざす父系原理を基本としつつ、母系や姻戚関係をもまじえて、おおむね一定数の成人男性を含
むように編成された「戸」は、流動的なイヘの実態にみあった「擬制」の産物だったといえる。
帝京史学26号.indb 90 2011/02/16 18:48:29

-・91・-
このように、国家の造籍方針とその限界を明かにした現在の戸籍研究の成果の上に立って考えると、父系で編
成された「戸」は実態ではない、という関口氏の指摘だけでは、古代日本のジェンダー分析としては不充分であ
ることが見えてこよう。このことは、「戸」と租税制の問題を考えてみれば、はっきりする。
編戸された「戸」は、はたして律令的負担を担う単位としての現実的機能を持ったのだろうか。従来の戸籍分
析では、戸内に含まれる課丁の人数と戸主との続柄から、「戸」の均等的編成を指摘し、その目的・意義を論じ
てきた。そこでは、成人女性の数が正面から問題にされたことはなかったのである。現存の戸籍を分析すると、
たしかに「戸」はほぼ均等に三人から五人の成人男子を含み、兵士一~二名を出すように編成されている〔浦田
(義江)一九七二〕。しかし、成人女性は、成人男性の人数に見あうような均等な数で編成されてはいないのである。
例えば、大宝二年(七〇二)の御野国加毛郡半布里は、課丁の均等編成が現存戸籍中ではもっとも徹底し、一
戸三~四正丁、すなわち一戸一兵士の理念的戸がほぼ実現している戸籍として知られ、南部氏の調査でも、全体
的な男女比率、人口分布が自然で、婚姻関係・親子関係・人数などの把握がきわめて正確とされる。しかし、戸
内の課丁+兵士数、つまり成人男性数と、丁女(成人女性)数との差を調べてみると、男性より女性の数が三人
以上多かったり少なかったりという「戸」が、三九パーセントにのぼる。正丁三・次丁二・兵士一の計六人の成
人男性に対して成人女性は正女三人のみ(中政戸秦人部都弥戸)、正丁三・次丁一の計四人の成人男性に対して
正女は一人のみ(中政戸敢臣族岸臣目太戸)というように、丁女を均等に配分することには、まったく意が用い
られていないのである〔義江一九九五、二二六頁〕。
服藤早苗氏が明かにしたように、律令が規定する租税貢納品のうち、かなりのものが女性労働の生産物であり、
帝京史学26号.indb 91 2011/02/16 18:48:29

-・92・-
兵士役以外の力役は、実際には女性も担った〔服藤一九八二〕。八世紀末の史料からは、新たに支配領域に組入
れた東北地方に対して調庸を賦課するため、朝廷の命令で、本州中心部の五ヶ国(参河・相模・近江・丹波・但
馬)から一般の「婦女」が養蚕技術を教えるために陸奥国に派遣されたことがわかる(『日本後紀』延暦十五年
〔七九六〕十一月八日条)。調絹・也糸製作の多くが庶民女性の手になるものであったことが了解できよう。
したがって、成人女性(丁女)の労働に焦点をあてて考えてみると、成人男性のみに賦課する律令租税制度で
は、編成された「戸」は兵士徴発の基本単位ではあり得ても、租税貢納の単位としての機能を充分に果たすこと
はできないのである。そもそも、日本の調庸貢納制をめぐる令規定は、唐令のような戸内での調庸合成ではなく、
戸を超えた規模の合成を前提とする〔石上一九七三、大津一九九三〕。調絹・絁の「四丁成疋」規定や封戸の一
戸四丁基準が、一戸四丁の「標準戸」の設定と密接に関わることは間違いないが、そのために均等的戸の編成が
実際に必要だったわけではない。現実には、「里が少なくとも一戸平均四丁すなわち二〇〇人分の調庸を出し得
る規模に編成」されるという「里の均質化」によって、国家の必要な徴収は実現されていた〔佐々木一九八六〕。
これは、国家は「戸」とは別のしくみで人民の労働を把握していたこと、古代日本の労働・経営におけるジェ
ンダーの特質は、「戸」や家族を超えたレベルでの分析を必要とすることを示唆する。中国の租税制度は、夫と
妻を一組として「戸」に登録し、夫を通じて夫婦の労働の成果を徴収する、という理念でなりたっていた。つま
り、中国においては、〝成人男性への賦課〟は、妻に対する賦課をその内部に含んでいるのである。それに対して、
日本の律令は、〝成人男性への賦課〟を租税制度の原則として中国から取り入れ、戸籍制度も中国式に整えたが、
実質的には夫を通じての妻の労働成果の徴収はできていない。これは、基盤となる夫婦のありかたが、日本と中
帝京史学26号.indb 92 2011/02/16 18:48:29

-・93・-
国では根本的に異なっていたからである。
そこで次節では、八世紀(奈良時代)前後の夫婦関係の特色を、家族・婚姻史研究の成果から確認し、本稿の
考察課題を明確にしたい。
二節
夫婦単位の未確立
日本の古代女性史研究は、家族婚姻史研究から始まった。先駆的研究者高群逸枝氏は、奈良時代以前には夫婦
は通常は別居訪問婚の形態(当時の用語では「妻問」といわれる)をとっていたと論じた。高群氏によると、平
安時代には妻方居住(当時の用語では「婿取」。高群氏はこれを「招婿婚」と名づけた)が行われたが、室町時
代以降は嫁取婚、すなわち妻が夫方の家族に包摂される夫方居住が広まっていく〔高群一九五四〕。その後の研
究によって、個々の史料解釈や、母系制の主張、「招婿婚」概念、嫁取婚への移行時期など、高群説で否定・修
正された点は少なくない。しかし、父系制以前・嫁取婚以前の時代が過去にあったことを明かにし、いわゆる伝
統的な「家」社会は長期の歴史的変化を経て形成されてきたことを体系的に跡づけた点において、依然としてそ
の意義は大きい。
一九八〇年代以降、家族・親族研究の分野において、古代の日本は母系と父系の双方が重要な重みをもつ双系
(双方)的社会であるとの見解が、文化人類学の成果をも取り入れて提示された〔吉田一九八三、明石一九九〇。
双方社会の用語については、村武一九八一、二七三―二九一頁参照〕。ほぼ並行して、高群説の修正・継承をめざ
した関口裕子氏の非家父長制家族論も深められていった〔関口一九九三〕。これらは相互に密接に影響しあいな
帝京史学26号.indb 93 2011/02/16 18:48:29

-・94・-
がら学界に浸透していき、「氏」構造論〔義江一九八六〕・「家」成立論〔服藤一九九一〕などの個別成果が生み
出されるにいたる。
一九九〇年代以降、「家」成立の過程はさらに精密に探求された。高橋秀樹氏は、政治的地位の継承が「家」
形成の基盤であること、家業(公的職務)・政治的地位・家産を父子継承する「家」は、一一世紀から一四世紀
にかけて、貴族社会に次第に広まっていくことを、詳細に論証した〔高橋一九九六〕。また、後藤みち子氏は、「家」
形成の過程には、夫方同居による安定した夫婦関係の形成が伴っていること、同屋敷内別棟居住を経て、父夫婦
と嫡子夫婦の同棟での完全同居が実現するのは一五~一六世紀であること、同じ頃に、貴族の家の家業における
妻の公的役割がほぼ最終的に失われることを、具体的に跡づけた〔後藤二〇〇一、一五―九三頁〕。
以上の研究成果からわかることは、安定した夫婦関係の成立、政治的地位の父系継承、女性(とりわけ妻)の
公的役割の消失、の三者が密接な関係にあること、そして、一〇世紀以前には、この三者のどれもが未確立で、
形成の端緒段階にあったことである。政治的地位の父系継承と女性の公的役割消失の対応関係については、これ
までにあげた家族婚姻史研究・女性史研究の中で、すでに種々の指摘がなされてきた。本稿では、夫婦関係の不
安定性とそれが克服されていく過程に焦点をあてて、さらに詳しくみていきたい。
八世紀(奈良時代)前後における夫婦関係の不安定性をみる上では、明石一紀・梅村恵子両氏の研究が重要で
ある。
明石氏は、大祓の祝詞の中に「国津罪」として記された、「己が母犯せる罪、己が子犯せる罪、母と子と犯せる罪、
子と母と犯せる罪」(『延喜式』巻八)というインセスト・タブーのあり方に注目する。この四種の罪には、それ
帝京史学26号.indb 94 2011/02/16 18:48:29

-・95・-
ぞれ、1=息子が自分の母を犯す、2=父が自分の娘を犯す、3=(母の)夫が「母」(自分の妻)と「子」(妻
の娘、つまり自分の義理の娘)の両者を犯す、4=(娘の)夫が「子」(自分の妻)と「母」(妻の母、つまり自
分の姑)の両者を犯す、という四種の関係が、男性を主体として表現されている。ここからは、母と成人した息
子・娘が同居していて、そこに母の夫(息子・娘の父ではない)が通ってきて義理の娘を犯してしまう関係、あ
るいは娘の夫が通ってきて義母を犯してしまう関係、が日常的に起こり得たことがわかる。
明石氏は、インセスト・タブーにみられるこうした特色と、父系拡大家族が一般的存在ではなかったことを強
く示唆する親族名称体系の特色、および長期の通いを含む多様な婚姻居住形態等とを総合して、当時は母子集
団の結合がつよく、そこにルーズな夫婦結合で夫が結びつく形態の小家族が一般的だったと結論づけた〔明石
一九九〇、一六―一七頁〕。明石氏自身は、この家族形態を「妻と未婚の子供、そして夫」と定義した。しかし、
国津罪についての明石氏自身の前記の解釈を参照すればわかるように、「母と子と犯せる罪」「子と母と犯せる罪」
では、母と既婚の娘が同時に一人の男と性的関係を持つ事態が想定されており、母子集団に含まれる「子」は未
婚に限定されない。よって私は、「そして夫」という場合の「夫」が必ずしも「子供」の父ではないことを明示し、
女性を主体とした関係性の表現で統一するという意味で、古代の一般的家族形態を「母子+夫」と定義し直した
い。この「+」の部分の結合力は弱く、「夫」はしばしば入れ替わる。
ほぼ八世紀奈良時代ごろまでは、安定した一組の夫婦関係がつづくのではなく、男女どちらからでも離別が容
易な一時的対偶関係が基本だった。こうした婚姻関係は、当然、女性の法的地位にも顕著な特色をもたらすこと
となる。梅村恵子氏は、日本と中国の律令規定にみえる女性名称を綿密に比較分析し、次のような特質を明かに
帝京史学26号.indb 95 2011/02/16 18:48:29

-・96・-
した。
梅村氏によると、唐律令においては、1=女性名称「婦」(ヨメ)・「女」(ムスメ)・「婦女」(ツマとムスメ)・
「婦人」(ツマ)は、いずれも「家族内部における関係を表す語」である。2=生家に起居する女性「女」(ムスメ)
は法的未人格であり、生家より出て婚家に所属する女性「婦」「婦人」のみが法的人格として規定される。3=
女性は常に家族の中で父・夫・子との関係でのみ存在するものとみなされ、独立した女性として存在することは
法的には許されなかった。
それに対して日本の律令法では、1=家族関係から独立した女性をさす「女」(オンナ)が法的人格として登
場する。2=この「女」は、中国法にはみられない種々の公的権利を持つ。こうした特色は、婚姻が女性の社会
的地位の決定的変化要因とならず、未婚者と既婚者の区別があいまいな婚姻システムのもとでは、「家族という
単位を明確に枠組みできない」ことによる〔梅村一九七九〕。つまり、一組の夫婦という社会単位が確立してい
ないため、成人女性一般を「妻」として把握することが困難で、婚姻の有無に関わらない「女」(オンナ)とし
て法的に設定せざるを得なかったのである。
明石氏のインセスト・タブー分析と、梅村氏の法律用語の分析は、全く異なる角度からの研究である。しかし
両者の結論は、奈良時代前後の夫婦結合が安定した社会単位とはなり得ない流動的なものだったことを、一致し
て示している。
では、一組の男女が安定的な夫婦関係を形成し、それが社会の基本的単位となるのは、いつごろからなのだろ
うか。これについては、社会の変化を巨視的にとらえたものとして、貴族社会における正妻制の成立時期を考察
帝京史学26号.indb 96 2011/02/16 18:48:29

-・97・-
した梅村恵子氏・服藤早苗氏と、中下級官人・上層農民層の夫婦観に迫った勝浦令子氏の仕事が注目される。
平安貴族の婚姻は一夫多妻である。居住形態を全体的にみると別居/妻方居住/夫方居住が混在し、一組の男
女の間でも、婚姻関係の深化と変質に応じて、妻方での婿取儀式~数年間の妻方居住~新処居住/夫方居住と、
段階的に推移する。
梅村氏によれば、1=「多妻群中、他に隔絶した地位を有する妻」は、「男女両家の親の承認」と「あらかじ
め告知された儀式婚」によって社会的に認知され、「同居」で安定する。2=正妻の子と他妻の子は、男子は昇
進において、女子は婚姻相手の選定において、差がみられる。3=摂関家についてみると、正妻制は「遅くても
九世紀後半には成立」しているが、九世紀初にはまだ不明確である〔梅村一九八七〕。
つまり、少なくとも九世紀前半までは、最上級貴族においてすら、正妻の地位は未確立だったのだ。しかも、
儀式を経ない恋愛から始まって同居し正妻へという途もあり、別居のままでの正妻格扱いもあり、社会的慣行と
しての正妻制が貴族社会に定着するまでには、長い道のりを要した。服藤氏は梅村説の史料的根拠に疑問を呈
し、摂関家においても「同居の﹁正妻﹂が必要になり、緩やかにでも決まってくるのは、兼家の妻時姫ころから」、
すなわち一〇世紀後半とみている〔服藤二〇〇六、八九頁〕。
中級下級貴族においては、正妻の地位がはっきりして来るのは、平安後期のことである。一一世紀中頃に成立
した『新猿楽記』には、ある下級官人の理想の婚姻生活として、三人の妻と大勢の息子・娘にとりまかれた家族
の様子が描かれている。そのうちの本妻(もとつめ=正妻)は、老齢で、何のとりえもなく、性的魅力も感じら
れない。しかし、夫は、「諸の過失ありと雖も、既に数子の母となる、これを如何とするや」(いろいろ不満はあ
帝京史学26号.indb 97 2011/02/16 18:48:29

-・98・-
るが、数人の子供の母なのだから、いまさらどうにもできない)という。性愛関係の有無とはかかわりなく、最
初の妻であり、長年連れ添ってきたという実績と、夫との間に何人もの子供を生んだ功績が、安定した妻の座を
保証していることがわかる。もっぱら性愛関係でむすびつき、容易に離合をくりかえした奈良時代の夫婦関係と
は大きな違いである。
平安後期(院政期)に一組の夫妻の絆が強まることを、より下層の広範な階層について明かにしたのが勝浦令
子氏である。勝浦氏によれば、1=この時期には「夫妻を基礎単位とする宗教参加」が多くみられ、「所生愛子」「父
母供養」「二世円満」等の祈願を行っている。2=これは「母子+夫」という流動的な婚姻関係に基づく不安定
な奈良時代的小家族から、「夫妻+子」という安定した家族形態への過渡期に現れる、夫妻共同意識である。3
=平安後期から鎌倉期にかけて、夫妻が互いに相手を「縁友」と呼びあうようになるが、これは仏縁によって来
世にまで結びつく夫妻一体感が生まれてきたことの表れである〔勝浦一九八七.
〕。
以上、諸氏の研究成果によって、安定した夫婦関係の形成は平安時代を通じて貴族社会で次第にすすみ、鎌倉
時代前期の一三世紀頃までには、上層農民クラスでも実現したことを確認した。逆にいえば、九世紀頃までは、
社会の基礎単位となるような一組の夫婦関係は存在していなかったのである。「母子+夫」という、妻と夫の結
びつきが弱く流動的な家族形態は、律令制が導入された奈良時代においては、全階層にあてはまる特色だったと
みてよいだろう。
帝京史学26号.indb 98 2011/02/16 18:48:29

-・99・-
小結
ここで、①戸籍研究史の整理を通じて明かにした、日本の律令租税体系と「編戸」のシステムにおいては、中
国と異なり、夫を通じての妻の労働成果の徴収は実現していないということと、②家族婚姻史研究の成果によっ
て確認した、奈良時代における夫婦単位の未確立という特色とを、総合して考えてみたい。手がかりとなるのは、
婚姻形態の特色が日本の律令法にみられる〝独立した女〟の法的地位に反映しているという、先述した梅村氏の
研究成果である。「戸」や家族の枠組みでは把握できない〝独立した女〟は、現実の労働・経営の場でどのよう
な働きをしていたのだろうか。夫方同居による安定した夫婦関係の形成、父系の「家」の確立、妻の公的役割の
消失、の三者が互いに影響しあいつつ並行してすすむという、中世後期の貴族の「家」をめぐる後藤氏の研究を
参考にすると、奈良時代には、「妻」の地位を前提としない〝独立した女〟の公的役割が、社会の各階層におい
て存在したことが推定できよう。
上記の問題関心にもとづいて、以下、貴族・豪族層の〝独立した女〟の具体的存在形態を、「刀自」の語をキー
ワードとしてみて行く。
二章
経営者としての「刀自」
古代社会における「刀自」とは、そもそもは豪族層の女性に対する尊称であった。のちに「家刀自」という言
葉があらわれ、後世には次第に「家」の主婦をさすものとなっていく〔義江一九八九〕。しかし近代の民俗学に
帝京史学26号.indb 99 2011/02/16 18:48:30

-・100・-
おいては、しばしば両者は区別されず、「刀自」=「家刀自」=〝主婦〟とみなしがちであった。日本民俗学の
創始者とされる柳田国男は、古代以来の史料に見える「刀自」の語を検討して、「普通の用い方は家刀自、即ち
今いう主婦に限られていた」と、断言している〔柳田一九三九・一九四八〕2。
この解釈は歴史学においても広く受け入れられ、奈良~平安初期の史料にみえる「刀自」をも、「家」の内部
で夫を支える妻であったと単純に理解することにつながっていった。しかし実際には、古代の「刀自」は社会の
各レベルに存在し、独立した経済力を持ち、独自の経営を行っていた。前章で確認した夫婦の絆の弱さは、「刀自」
のこうした経済的独立性と密接に関わっている。
近年発見された木簡は、「刀自」が従来考えられていたよりもはるかに重要な存在であったことを、はっきり
と示している。公的記録や法令には全く見えない「刀自」が、日常的な記録である木簡には、説話と同様に、大
きく姿を現すのである。以下、一節では村の統率者としての「刀自」を木簡によって考察し、二節では家族の枠
を超えて大規模経営を行う「刀自」を、説話の再検討を通じて明かにする。
一節
村の統率者としての「刀自」
一九九三年に、福島県荒田目条里遺跡から九世紀半ばの木簡が発見された。幅四、五センチ、長さ六〇センチ
ほどの細長い薄板である。この木簡には、郡の長官である大領が、「里刀自」に対して、三四人の男女「田人」
を率いて大領の「職田」の田植え労働を行うよう命じる「郡符」が記されていた3。この木簡は多くの研究者の
注目を集めた。なぜなら、「郡符す」で始まる書式は郡の公式命令書であることを意味するにもかかわらず、そ
帝京史学26号.indb 100 2011/02/16 18:48:30

-・101・-
の宛先が「里刀自」という女性になっていたからである。
通常は、国―郡―里(郷)という律令国家の地方行政組織において、郡司の公式命令は里長(郷長)に対して
出される。国司・郡司・里長はいずれも男性である。「里刀自」という役職や地位は、公的には存在しない。本
来ならば、行政組織上のどこにも位置しない女性の「里刀自」は、宛先にはなり得ないはずである。にもかかわ
らずこの木簡において「郡符」が「里刀自」宛に出されていることは、「里刀自」と呼ばれる女性が、半公的地
位を占めていたことを示す。彼女はそうした地位に基づいて、村人の農耕労働の指揮・統率を行っていたと推定
されるのである。
この木簡の発見は、「刀自」=「家刀自」=〝主婦〟とする従来の刀自理解に再検討を迫るものといえる。し
かし多くの研究者は、「里刀自」を、里長の妻で臨時に夫の代理を務めたものとみなしがちだった。たとえば、
女性が農業労働力として大きな比重を占めたこと、農業経営・管理に従事していたことを認めながらも、「﹁家刀
自﹂が家を支配する主婦の尊称であったと同様に、里を統率する里長の妻は、﹁里刀自﹂と尊称された」とみる
のである。また、夫である里長は行政上の役割を負って郡衙に出向くことが多く、それに対して妻である里刀自
が「集落における構成員の動向を適確に把握し、農業経営に隠然たる力を発揮した」との推定もなされている〔平
川一九九六〕。しかし、こうした解釈の背後には、公的役割を果たすのは男(夫)で女(妻)が公的なことに携
わるのは夫の代理としてのみという、近代の公私分離のジェンダー観が無意識のうちに働いているのではないだ
ろうか。
もう一つ、別の木簡を例にあげよう。一九八三年に、藤原宮跡から長さ一メートル近い木簡が掘り出された。
帝京史学26号.indb 101 2011/02/16 18:48:30

-・102・-
そこには弘仁元年(八一一)から翌年にかけてのある荘園の収支決算が記され、領主から耕作を請け負った男
女の名前と請け負った内容が書き上げられていた4。それを見ると、「山田女」という女性が、自分自身の名で、
二町六段という、並んで記された他の男性請負人よりはるかに広大な面積の耕作を請け負っていたことがわかる5。
この帳簿には、山田女の夫についての言及はなにもない。服藤早苗氏は、山田女は独立した大農業経営主だとし
ている〔服藤一九九一、二四五―二四九頁〕。・
二つの木簡からは、九世紀において、東国のある村と都近くの荘園という異なった二つの地域で、農業経営を
行い、農耕労働を指揮する女性の存在を確認できたことになる。さらに、そうした女性が、あるいは村人を統率
する者として半公的地位にあり、あるいは荘園領主と請負契約をする経営主体としての立場にあったことも判明
した。女性のこうした公的地位・役割は、正史や法制からはわからない。日常生活の中で実際の必要に応じて書
かれた木簡によって、はじめて見えてきたことなのである。
二節 「家」の経営者としての「刀自」
次に、説話に表れる「家刀自」をみてみよう。彼女たちは「家」の「刀自」として、近代の〝主婦〟と同じよ
うにみなされがちであった。果たしてその解釈は正しいのだろうか。
九世紀初にまとめられた仏教説話集である『日本霊異記』には、大規模な農業経営を行う地方豪族や上層農民
の姿が多く描かれている。それらの説話にはしばしば、「家長」(男)と「家室」(女)が、夫婦のペアとして登
場する。漢語で表記された「家室」は、和訓では「いへとじ」とよばれている。すなわち「家刀自」である。旧
帝京史学26号.indb 102 2011/02/16 18:48:30

-・103・-
来の解釈では、「家長」(夫)が経営の責任者で、「家室」(妻)は夫を助けて家内の消費分配機能を掌る者、つまり、
家長の経営責任のもとでの任務分担とみてきた〔河音一九六三、鬼頭一九八六〕。だが、ここにもやはり、近代
の妻役割が無意識のうちに投影されているのではないだろうか。
こうした無意識の思い込みを離れて『日本霊異記』の説話を注意深く読んでいくと、「家室」は彼女たち自身
の経営を行っていることが見えてくる。よく知られた下巻二六話を例にとって見てみよう。この話の中で広虫女
は、「富貴にして宝多く、馬牛・奴婢・稲銭・田畠等有り」という富豪女性として描かれている。彼女は貪欲な
高利貸しで、村人から強欲に容赦なく取り立てたので、人々は家を棄て逃亡するありさまだった。ある日、広虫
女は病になり、夢の中で、地獄の閻魔大王の前に召されて、次のように三の罪を列挙して仏罰を宣告された。
一つは、三宝の物を多く用いて報いざる罪。二つは、酒を沽るに多の水を加えて多の直を取る罪。三つは、
斗升斤を両種用いて、他に与える時には七目を用い、乞い徴る時には十二目を用いて収る。この罪によりて
汝を召す。現報を得べし。今汝に示すなり。
閻魔大王の宣告の通り、広虫女は死後七日で、上半身牛の醜い姿で生き返った。さてこの話において注目すべ
きは、貪欲な経営を行って村人を苦しめたのも、仏罰を受けたのも、彼女一人の行動として描かれていることで
ある。広虫女は「讃岐国美貴郡大領外従六位上小屋県主宮手」という有力者の妻であるが、夫の経営の手助けで
はなく、彼女独自の経営であった故に、仏罰も彼女一人に下された、というのが話の基本的構成である。
帝京史学26号.indb 103 2011/02/16 18:48:30

-・104・-
一方、これも有名な中巻三二話の桜大娘は、村の福祉に貢献する経営活動を行った女性である。桜大娘の正式
の名前は、岡田村主姑女という。村の寺からの委託をうけて行われた彼女の経営活動は、次のように描かれている。
聖武天皇のみ世に、紀伊国名草郡の三上村の人、薬王寺のために知識を率引して、普く薬分を息す。その薬
料の物を、岡田村主姑女が家に寄せ、酒を作り利を息す。……
大娘は酒を作る家主、即ち石人が妹ぞ。(石人は)一人大きに怪しび、妹の家に往く。
薬王寺は、仏教による福祉活動の一環として、村人のための薬を備えることを計画した。そのために、三上村
の人々から知識(協力者)を募って稲をあつめ、それを元手に酒を作って利息つきで貸し出し、それで薬の費用
をまかなうこととしたのである。村人は、桜大娘に、造酒と貸し付け業務の一切を委託した。引用を省略した部
分では、大娘から酒を借りて返さないままに死んだ男が、牛に生まれ代わって寺で酷使され、その苦しさを夢の
中で石人に訴える、という筋書きになっている。
さて、上に引用した史料には、彼女の「家」に関する記載が三箇所にみえる。
1=村人が「岡田村主姑女の家」に造酒・貸し付けを委託した。
2=桜大娘は「酒を作る家主」である。
3=石人は(夢の中の男の話の真偽を確かめるために)「妹の家」に行った。
帝京史学26号.indb 104 2011/02/16 18:48:30

-・105・-
桜大娘の「家」は、造酒・貸し付け活動の経営拠点であり、彼女自身がその「家」の「家主」で、それは兄と
は別の「家」であることがわかる。大娘に夫がいたか否かは不明だが、いずれにしても、彼女の経営活動の描写
には、夫は一切登場しない。兄の石人も、「妹の家」にいってはじめて夢の中の男への貸し付けの事実を知るの
であるから、妹の経営には関わっていない。『日本霊異記』は、大娘の経営を彼女独自のものとして描いている
のである。
関口裕子氏は、説話に描かれた二人の女性――広虫女と桜大娘――を手がかりにして、「家刀自」を夫の経営
の補助者とする従来の解釈を批判した。関口氏は、当時の大経営においては、夫と妻がそれぞれ独立した財産所
有者・経営者だとしたのである〔関口一九七七〕。関口氏の主張は、当時の土地の売券に女性名が売り手・買い
手の双方にしばしば登場することからも裏付けられよう。
妻が夫の内助者ではなく夫と同様の経営者だった、という関口氏の主張は正しい。しかし私は、関口氏の理解
には不充分な点があると思う。それは、経営におけるジェンダー関係を、一つの「家」内部における夫と妻の権
限分割のありかたとしてしか見ていないことだ。広虫女と桜大娘の話が示していることは、妻は夫とは別の「家」
(経営拠点)の「家主」だったということである。これを理解するには、「家」という漢字が、古代日本において
何を意味したかを、深く知る必要がある。
古代の日本には、もともと固有の文字はなく、中国から学んだ漢字で日本語を表記した。「家」という漢字は、
吉田孝氏が解明したように、古代日本語の「イヘ」と「ヤケ」の双方を表記する文字として採用された。「イヘ」
は人間関係としての家族、「ヤケ」は経営拠点を意味する日本語である。「イヘ」という語で表された古代の家族
帝京史学26号.indb 105 2011/02/16 18:48:30

-・106・-
は、具体的には、本稿でここまでに繰り返し述べてきたように、「母子+夫」と表現できるような、不安定で外
延部の定まらない関係である。それに対して、「ヤケ」という語で表現されるものは、塀で囲まれた一区画の内
部に事務所・倉庫・厩・厨房などの複数の建物を含む、空間的広がりで捉えることのできる経営拠点である〔吉
田一九八三、Ⅱ章〕。
八世紀頃までは、「イヘ」と「ヤケ」は、実体としては一部で重なる(だからこそ、同じ「家」の字で表記さ
れたのだろう)が、本質的には別物であり、重ならないことが多い。つまり、豪族・貴族の男女は、それぞれ自
分の「ヤケ」(経営拠点)を持ち、婚姻によって夫婦が一つの「イヘ」を構成することもあるが、それぞれが自
分の「ヤケ」の経営をつづけ、離婚すれば別の相手との「イヘ」を作り直すことになる。一般庶民は、そもそも
流動的な「イヘ」だけで、経営拠点たる「ヤケ」などは持っていない。「イヘ」と「ヤケ」が広範な階層で重なっ
てくる、つまり、夫婦関係が安定して「夫婦+子」の家族単位を構成し経営単位としての機能を備えるに到るの
は、平安後期のことである。ここで名実ともに「家」が成立したことになる。
『日本霊異記』が編纂された九世紀初は、富豪層(豪族・上層農民)において「イヘ」と「ヤケ」が重なり始
めるごく端緒の時期である。『日本霊異記』にみえる男女ペアの家長と家刀自は、一つの「イヘ」を構成する夫
婦だが、それぞれが経営拠点としての「ヤケ」をもっている。桜大娘について、『日本霊異記』が「岡田村主姑
女の家」「酒を作る家主」「妹の家」と書く場合の「家」は、彼女の「ヤケ」をさしているのである。
これまでの「家」刀自をめぐる議論を振り返ってみると、多くの研究者は『日本霊異記』にみえる「家」と、
経営単位として確立した後世の「家」とを明確に区別せず、そこにさらに近代以降の主婦概念を投影してダブら
帝京史学26号.indb 106 2011/02/16 18:48:30

-・107・-
せ、家刀自を家長の補佐=〝主婦〟とみなしてきた。女性史研究者である関口裕子氏は、その解釈の誤りを鋭く
つき、妻は夫と対等の独立した経営者だったとした。しかし、その場合にも、一つの「家」内部でのジェンダー
関係、家長と家刀自の権限分割を論じる傾向が強く、「家」を超える広がりのなかに「家刀自」を位置づける視
点は弱かったのである。
関口氏の議論のもう一つの問題点は、妻が夫とは別に所有権・経営権をもっていたことの証明は行ったものの、
その経営の具体的内容の分析にまでは踏み込んでいないことである。私は、広虫女と桜大娘の経営内容の共通性
に注目したい。それによって、彼女たちの経営が、夫とともに構成する「家」(イヘ)を超えた広がりを持つこ
とが明らかになると考えるからである。
前述のように、広虫女の三つの罪の第一は「三宝の物を多く用いて報いざる罪」、第二は「酒を沽りて多の水
を加えて多の直を取る罪」だった。「三宝」とは、仏・法・僧、つまり、寺の物ということである。広虫女の経
営にも、桜大娘と同じく、寺から委託された稲の造酒・貸し付け活動が主要部分として含まれていたのだ。桜大
娘の話(中巻三二話)では、彼女を通じて寺の物を借りて返さなかった男が仏罰を受けて牛になり、広虫女の話(下
巻二六話)では、広虫女自身が寺から委託されたものを使い込んで返さなかったので、彼女自身が仏罰を受けて
牛の姿になったのである。
寺の物の運用が二人の経営の共通性の第一点だとすれば、もう一つの共通性は「酒」である。なぜ、酒作りと
その貸し付けが彼女たちの経営の主要部分をなすのか。また、そもそも、なぜ村人たちは、高利を承知で酒を借
りたのか。それは、古代社会において、酒が、単なる飲料ではなく、営農資本としての重要性をもっていたから
帝京史学26号.indb 107 2011/02/16 18:48:30

-・108・-
である。農繁期の雇傭労働は、酒と御馳走を提供して集めるというのが、当時の農業慣行だった。政府は貧富の
差の拡大を防止するために、その行き過ぎを禁ずる法令を、七世紀から九世紀にわたって度々出している(日本
書紀』大化二年三月甲申詔。『類聚三代格』巻十九、延暦九年四月一六日太政官符。『日本後紀』弘仁二年五月庚
寅勅)。
広虫女や桜大娘のような地方豪族層の女性は、村の農業経営の中心を担う有力者として、大量の酒を作り、そ
れを村人に営農資本として貸し付けるとともに、自身の大規模経営に駆使する労働力もその酒を使って集めたの
だろう6。そうした日常的な経営活動における力量を見込んで、村全体の福祉に関わる寺の資産の運用も任され
たのである〔義江一九九六、一九六―二〇八頁。脇田一九九二、一一二―一一七頁〕。ここまで述べてくれば明か
だろう。農業労働力を駆使する大規模経営主としての彼女たちの姿は、前章で荒田目条里遺跡発見の木簡から見
た「里刀自」と、少しも違いがない。私は、『日本霊異記』に描かれた「家刀自」たちと木簡にみえる「里刀自」
は、社会的には同じ位置にあると思う。
女性の経営主は、その経営の私的側面からは「家刀自」と呼ばれた。しかし彼女たちの労働指揮の権限や現実
の経営活動は、私的な「家」(イヘ)の範囲を超えて行われ、村人たちの生活に大きな関わりをもつものでもあった。
名称は異なるものの、「家刀自」の経営機能は、地方行政の上で半公的位置を占めていた「里刀自」と共通する。
村人の委託をうけて寺の物を運用した桜大娘は、村内部で半公的地位にあったといって良いだろう。・
もう一つ別の家刀自の話をみよう。『日本霊異記』上巻第二話に登場する美濃国のある富裕な「家」の「家室」
は、村の女性たちの精米労働を指揮している。
帝京史学26号.indb 108 2011/02/16 18:48:30

-・109・-
二月三月の頃に設けし年米を舂く時、その家室、稲舂女等に間食を宛てむとして碓屋に入る。
律令制下では、精米した米を都に運ぶ国が二二カ国指定されていた(『延喜式』巻第二十三、民部下)。美濃国
はその一つである。右の引用部分にいう「年米」は、美濃国から都に運ぶ白米のことで、そのための精米作業に
村の女たちが集められ、「家室」が彼女たちの労働を指揮しているのである。
精米作業は、古くから女性の集団労働として行われてきた。弥生時代の銅鐸絵画にも、女性二人が向き合って
杵で碓をつく様子が描かれている。ただし、律令制のもとでは、舂米の貢納責任者は男性とされていたので、女
性の舂米労働は〝隠れた労働〟となってしまい、公的な租税貢納のルートには表れない。平城宮跡からは、地方
から運ばれた舂米の荷札木簡が多数出土しているが、いずれも、「**国**郡**里戸主丹比連道万呂戸
白
米一俵」というように、男性の名前が書かれている。ところが、平城京の貴族邸宅跡から出土した舂米荷札木簡
には、「和銅三年四月十日
阿刀部志祗太女舂米」というように、「**国**郡**里」も「戸」もなしで、女
性名を記したものが見られる。
同じ舂米荷札木簡でありながら、両者の異なる記載形式は、律令制租税制度とジェンダーの関係をまことに鋭
く表象しているといえよう。国家租税としての舂米貢納では、男性だけが公的貢納責任者として名前を記し、女
性は〝隠れた〟存在となるのに対して、貴族の私的領地から、「国・郡・里」という地方行政組織と「戸主」の
手を経ることなく、個々の貴族に直接送られる舂米については、実際に舂米労働を行い・指揮した女性の名前が、
表面に姿を現すのである〔義江一九九〇、一四八頁〕。
帝京史学26号.indb 109 2011/02/16 18:48:30

-・110・-
ここからは、当然、正規ルートによって男性名で朝廷に納められた舂米も、実際には村の女性たちの精米労働
によるものであり、彼女たちの労働を組織したのは「家刀自」「里刀自」と呼ばれた女性たちだったろう、との
推定が成り立つ。村内部での彼女たちの半公的地位は、こうしたところに成立の根拠を持っていたのだ。
三節 「男耕女織」言説への疑問
では、夫婦単位が未成熟だったと考えられる奈良時代において、労働における夫婦分業観はどのようなものだっ
たのか。それを、宮廷で行われた「親耕親蚕」儀礼、次いで上層農民に対する「力田」表彰記事、という二つの
異なる面から見ていきたい。「親耕親蚕」儀礼は古代中国に由来し、「男耕女織(夫耕婦織)」の理念を皇帝・皇
后夫妻が自ら示したものとされる〔上田一九七九〕。この儀礼は奈良時代の宮廷に取り入れられ、実際に行われ
たことがわかっている。しかしそのことは果たして、中国と同様に〝男(夫)は耕し、女(妻)は織る〟という
家族内性別分業が、理念にもせよ古代の日本に存在したことを意味するのだろうか。
『万葉集』巻二〇に、大伴家持が詠んだ「初春の
初子の今日の
玉箒
手に執るからに
ゆらぐ玉の緒」
(四四九三番)という歌が載せられている。歌の詞書によると、これは、天平宝字二年(七五八)正月三日に、
内裏で王臣等に「玉箒を賜い」宴会をもよおした、その際に作られたものという。奈良の正倉院の宝庫には、「天
平宝字二年正月」と記した「子日手辛鋤」二口と「子日目利箒」二口が現存する。家持が歌を詠んだ、まさにそ
の儀式で使われたものと推定して間違いあるまい。通説では、この行事は中国の天子親耕・皇妃親蚕の儀式に倣っ
たもので、奈良時代半ばに唐風傾倒の一環として日本に移植されたものの、結局は根付くことなく短期間で姿を
帝京史学26号.indb 110 2011/02/16 18:48:30

-・111・-
消した、と理解されている〔井上一九七八・一九八八〕。
一方、「正月子の日」ということに注目すると、平安時代には正月子日の行事として「小松引と若菜を供する儀」
が行われた。正月年頭に春の野に出て小松を根引き、また野の若菜を摘んで食し、邪気を払う行事である。平安
中期には年中行事として成立しており、正月「上子日」には天皇に若菜が供された(『西宮記』恒例一)。『源氏物語』
若菜巻にも「正月廿三日、子の日なるに、左大将殿の北方、若菜まいり給う」とみえる。もっとも、これらの行
事は奈良時代の「親耕親蚕」儀礼とはつながらず、奈良時代に導入された外来思想は消え失せて「日本化」した
とみなされている〔山中一九七二、丸山一九九二〕。
八世紀半ばに中国風儀礼の導入が試みられたが結局は根付かなかった、というのはその通りだろう。しかし、
七五八年に実際にどうような行事が行われたのかをみていくと、そこにはある意味で平安時代の子日行事と通じ
る面がみてとれるように思う。つまり、導入された奈良時代天平宝字二年段階で、すでに「日本化」された行事
だったのではないだろうか。
中国の制は、天子が鋤を手にとって藉田を耕し、皇后が箒で蚕室を掃って蚕神を祭る儀式とされる。しかし、
七五八年に日本でもこれと同様の所作が実際に行われたことを示す痕跡はない。正倉院に鋤と箒の現物は残って
はいるが、家持の歌から推測すると、そこには〝鋤=天子(男・夫)、箒=皇后(女・妻)〟という、この行事の
本質に関わる性別分担はみられない。「玉箒手に執るからに
ゆらぐ玉の緒」とあるように、家持も含めて、男
である群臣が「玉箒」を賜り、彼らはそれを手にとってゆらゆらと揺すったのである。
この時の天皇は孝謙女帝である。そのため、寵臣である藤原仲麻呂がいわば〝皇帝〟に準じる立場で鋤を取り、
帝京史学26号.indb 111 2011/02/16 18:48:30

-・112・-
孝謙が玉箒を持った、という解釈もある〔井上一九八八、二〇〇頁〕。しかし、この推定に確たる根拠があるわけ
ではない。確かなことはただ、儀礼に使われた鋤と箒が正倉院に現存するということだけである。何よりもこの
解釈では、〝男の群臣たちが箒を揺らす〟という所作の意味は解けない。
正倉院に現在残る玉箒は、コウヤボウキの茎を束ねて作られ、その先端に色とりどりのガラス玉がくくりつけ
られている。そこで考えてみると、ゆらゆらと玉を揺すって身中の「魂・霊」(タマ)を奮い起こす儀礼は、古
くから行われてきた在来の呪法である。一方、平安時代の小松引・供若菜儀は、春の野で小松を引き若菜を摘ん
で邪気を払う。これは、大地の霊気、自然の生産力に対する呪的信仰という意味では、奈良時代の貴族が「玉
箒」に込めた思いとも共通するのではないか。そこに顕著にみられるのは、人間の生産活動そのもの(耕作・養
蚕)の奨励によってではなく、自然の威力への呪的依存によって豊饒を得んとする志向である。奈良時代の宮廷
では、農耕にかかわる豊饒儀礼として、中国から「親耕親蚕」儀礼にちなむ道具(鋤と箒)をとり入れ飾ったも
のの、実際の所作としては、〝男=鋤、女=箒〟の分担ではなく、光明皇太后も孝謙女帝も群臣たちも、皆が「玉
箒」を手にもってゆらゆらと揺すり、呪的に豊饒を願ったと推定されるのである7。
・
〝農耕=男、養蚕=女〟の社会的性別分業観を基礎に、君主夫妻(天皇・皇后)が儀礼によって生産労働の模
範を示すような社会的条件は、およそそこには存在しなかった。日本の古代は、こうした夫婦単位での生業分担
とは大きく異なる社会だったからである。
しかし、正史には「男耕女織」およびそれに類する、性別分業を奨励する文言が見える。次にはこれについて
検討しよう。『日本書紀』では、雄略天皇紀に「皇妃親桑」のことが記され(六年三月丁亥条)、継体天皇紀にも
帝京史学26号.indb 112 2011/02/16 18:48:30

-・113・-
「士耕・女績」「帝王躬耕・皇妃親蚕」の文字がみえる(元年三月戊申条)。これらが、実際に雄略~継体のころ(五
世紀後半から六世紀)に「親耕親蚕」儀礼や「男耕女織」通念が存在したことを意味せず、中国古典の文を借り
た潤色であることは、いうまでもない。しかし、奈良時代(八世紀)以降については、『続日本紀』に散見する「男
耕女織」文言を、ある程度、実際の社会通念や世帯内性別分業の存在を示すとする見方も有力である。
坂江渉氏は、日中の農民規範を比較考察した一連の論考において、「夫婦一対で農耕と養蚕を顕著に実践する
農民世帯」を「力田」として推挙・褒賞する中国の制度が、奈良時代の日本でも実現していたとして、『続日
本紀』以降の「力田」記事七例を検討し、中でも天平一九(七四七)年の夫婦一対の褒賞例に着目する(坂江
一九九二・一九九七・一九九八)。
しかし実は、この天平一九年五月辛卯条の「力田外正六位下前部宝公に外従五位下を授く。その妻久米舎人妹
女に外少初位上」との記事こそ、中国の「力田」と日本の「力田」の社会的基盤の違いを顕著に示すといえる。
坂江自身が整理して指摘するように、中国の「力田」は、「三老」「孝悌」「節婦」などとセットで褒賞されるこ
とが多い。つまり、夫婦一対の農耕養蚕活動は「力田」たる夫(男)によって代表され、妻(女)が単独で褒賞
されるのはあくまでも「貞婦」「節婦」等の婦徳によってなのである。それに対して奈良時代の日本では、夫で
ある前部宝公と妻である久米舎人妹女が、それぞれに褒賞され授位されている。これは、夫妻のそれぞれが農業
経営主であり、その活動を認められたことを意味すると見なければならない〔関口一九八二、一三七頁〕。
帝京史学26号.indb 113 2011/02/16 18:48:30

-・114・-
小結
さきに刀自に関連して述べたように、八~九世紀にかけては、女性(夫の有無をとわない)が単独で大規模に
土地を集積したり、男女の田人を駆使して農業経営活動を行っている事例が、土地売買文書・荘園経営帳簿木簡
や説話など、性格の異なる多様な史料によって確認されている〔関口一九八二、服藤一九九一、義江一九九六〕。
こうした全体的状況の中に久米妹女に対する「力田妻」褒賞記事を置いてみるならば、それが中国的な意味での
「夫婦一対」とはおよそ異質のものであることが、よく了解されよう。
荒田目条里木簡の「里刀自」、荘園の決算書木簡の「山田女」、『日本霊異記』の「田中広虫女」・「桜大娘」、そ
して力田として表象された「久米舎人妹売」。彼女たちはいずれも、階層としては上層農民~小豪族クラスに属し、
地方社会で大規模農業経営に力を発揮し、村の内外で半公的地位を占めていた。八世紀後半~九世紀前半は、旧
来の共同体的まとまりが崩壊し、村内部での階層分化が露わになりはじめる時期である。彼女たちは、同階層の
男性と同様に、この階層分化の過程に主体的に関わり、私経営を展開していったのだ。
彼女たちのこうした経済力・統率力は、歴史的には何に由来するのだろうか。次章では、もう一段上の階層で
ある中央貴族社会の「刀自」に焦点をあて、そこからさらに歴史をさかのぼって、「刀自」の淵源をどこにもと
めることができるのか、その前史を考えたい。
帝京史学26号.indb 114 2011/02/16 18:48:30

-・115・-
三章
女性の政治的地位と婚姻・経営
一節
キサキとしての「大刀自」
本節では、キサキとなった貴族層の「大刀自」を考察する。近年の古代宮跡の発掘からは、キサキと後宮の制
度について画期的な知見が得られた。これによって、これまで無前提に信じられていた、大王とキサキは宮殿内
で同居していたのだろうという推定は、完全にくつがえされることとなったのである。
本論に入る前に、まず、日本におけるキサキ制度の樹立過程を概観しておこう。七世紀末に中国にならった后
妃制度が律令規定として設けられるまで、キサキたちは明確にランクづけられてはいなかった。後宮職員令によ
れば、キサキたちは、妃・夫人・嬪の三ランクに分けられる。さらにその上の最高位に位置するのは皇后だが、
皇后は「職員」ではなく、後宮職員令には規定されない。皇后と妃は皇族出身女性、夫人と嬪は一般貴族出身で、「夫
人」の和訓は「おほとじ」すなわち「大刀自」である。ただし、律令の定める四ランクのキサキ制度は九世紀に
はほとんど形骸化し、皇族・貴族の出身区別もなくなる8。令制キサキのランク制度の外枠をとりはらってみれば、
いわば、キサキたちは、本質的にはみな「大刀自」だということもできよう。あとでもとりあげるが、弘仁八年
(八一七)勅には「妃某姓邑刀自」とあり(『類聚符宣抄』巻六)、「妃」も「邑(大)刀自」と称されたのである。
こうした観点から、政治権力を考察する本節では、平安時代の皇后たちまでを視野に入れて「大刀自」を考察する。
三崎裕子氏によれば、八世紀以前の「キサイノミヤ」は大王宮とは別のところに存在し、経営も「天皇の宮と
は別の基盤」を有していた。三崎氏は、中国流の用語と観念で書かれている『日本書紀』の「後宮」の事例を一
帝京史学26号.indb 115 2011/02/16 18:48:30

-・116・-
つ一つ検討し、六世紀の敏達の皇后、七世紀前半の「聖徳太子」(厩戸王)のキサキたち、七世紀後半の天武天
皇のキサキたち(皇后も含む)が、自分自身の宮に住んでいたこと、それらの宮は彼女たちがもともと出身氏族
の支配圏内にもっていた農業経営の拠点(ヤケ)であったことを明かにした。『日本書紀』が「後宮に納る」と
表記していても、それは大王宮内にキサキの身柄が実際に移動したことを意味するのではなく、「キサキの身分
になった」ということをいっているに過ぎない。また、そうした形態は令制下にも形を変えて引きつがれたこと
を推定したのである〔三崎一九八八〕。
三崎氏の研究は女性史研究者の間では注目されたが、一般の研究者は懐疑的だった。大勢のキサキたちが後宮
に集住して大王に奉仕するという通説のイメージは、『日本書紀』の「納後宮」という表記にも支えられて、当
然のように受入れられていたからである〔江守一九六〇、他〕9。ましてや、律令キサキ制度の整う八世紀以降
については、天皇とキサキたちの別居など考えられない、というのが一般的理解だったのである。聖武のキサキ
である光明が、父藤原不比等の邸宅に皇后宮をおいていたことはよく知られた事実だが、これは藤原氏の権勢の
大きさのしからしむるところであり、光明が父の邸宅を相続したことによる特殊事例とみなされてきたのである
〔林一九六一、七〇―七四頁〕。
だが、宮跡の発掘の進展は、こうした一般的理解を覆した。発掘によって,内裏内にはのちの平安宮のような
キサキたちの居住空間、いわゆる後宮殿舎の存在しないことが明かになったからである(橋本一九九五)。彼女
たちは内裏外に、独自の宮・宅(ヤケ)を営んでいたのである。このことは、当時の別居訪問婚の慣行、および
男女子による均分相続の伝統と深く関わるであろう。キサキの宮・宅は出身氏族に包摂された形で存在・維持さ
帝京史学26号.indb 116 2011/02/16 18:48:30

-・117・-
れ、所生皇子女は母の宮・宅で生育されたのである。それは、天皇―キサキ間においても同様であった。光明皇
后の事例は例外ではなく、他のランクのキサキたちにも当てはまることだったのである。
キサキたちの宮・宅は、たんなる居住空間ではない。都の郊外にある所領も含めて、大規模経営を行うための
経営拠点であり、物資の集積所であり、大勢の家政役人・従者・奴婢の働く場所であった。王族・貴族の女性は、
同階層の男性と同様に、相続や自分自身の宮廷における地位に応じて大規模所領を保有し、その経営にあたった
のである。貴族男性と結婚後も、あるいは天皇のキサキとなって後にも、彼女たちが独自の経営機能を保持する
ことに変わりはなく、その経営規模はさらに拡大・強化される。このように見てくると、里刀自や家刀自の経営
拠点であるヤケと、キサキ(大刀自)たちの宮は、女性による独自経営という意味では、基本的な共通性を持つ
ことが了解されよう。
もちろん、両者の経営規模には大きな違いがある。また後者の経営機能が氏族および国家機構によって大きく
支えられ、政治権力に関与したことは、決定的な違いといわねばならない。このことを、いわゆる「皇后権」に
ついて考えてみよう。古代王権史研究が明かにしてきたように、皇后は、大王・天皇の共治者としての大きな権
能を有していた(岸一九五七b)が、その背景には、こうしたキサキの宮の独立性の高さがあったのである。複
数のキサキたちの中での皇后の地位は、天皇の正妻という家族秩序によってきまるのでなく(すでに述べたよう
に、そのような家族秩序はまだこの段階では存在していない)、おもに出身氏族の政治力によって決まり、キサ
キ個人の資質・力量によって実現・維持された。
では、皇后の政治権力は、キサキが内裏内の後宮に住むようになった時、どのように変化したのだろうか。キ
帝京史学26号.indb 117 2011/02/16 18:48:30

-・118・-
サキたちの内裏内後宮集住が実現するのは、八世紀末以降であったらしい。橋本義則氏によれば、まず光仁天皇
の時(七七〇―)に皇后宮、ついで桓武天皇の時(七八一―)に皇后以外のキサキたちの後宮殿舎も内裏内に営
まれるようになり、「平安宮内裏の空間構造の原型、すなわち天皇とその皇妃達が内裏で同居する形態」が成立
する。これが内裏の構造として固定されるのは嵯峨朝(八〇九―)である(橋本一九九五、八八―九八頁)。
この観点からすると、次の弘仁八年(八一七)の勅はきわめて興味深い。
勅を奉るに、少納言奏するに、妃某姓邑刀自の辞を称するあり。自今以後、宜しく姓を除き、只、妃邑刀自
と称すべし。若し両妃有りて事、相疑うべくば、更に勅裁を聴け。……
(『類聚符宣抄』巻六、少納言職掌、弘仁八年六月二三日勅)
「某姓」、すなわち出身氏族名を付して「妃**邑刀自(大刀自)」と称されていた「妃」が、弘仁八年以後は
氏族名を除き、ただ「妃邑刀自」といわれることになったのである。キサキの大王・天皇に対する独立性は、出
身氏族の女性メンバーとして、氏族の経営拠点たるヤケを伝領し受け継ぎ経営するという点に支えられていた。
そのことを考えると、弘仁年間にはそうした古代的あり方が最終的に転換し、それが内裏内のキサキ集住空間(後
宮殿舎)の固定的確立の背景にあることをうかがわせるものといえよう。
さて、皇后・キサキたちの内裏内居住空間が固定確立したからといって、これをただちに天皇夫妻の同居の実
帝京史学26号.indb 118 2011/02/16 18:48:30

-・119・-
現とみるわけにはいかない。淳仁とその母の例にみるように、キサキの宮が内裏外にあった八世紀においても、
〝母〟であるキサキは、立后の有無にかかわらず「息子の天皇と共に」内裏内にあった〔西野一九九七、一六五頁〕。
キサキたちの内裏包摂が実現して後も、彼女たちの集住空間である後宮の統率権は、結局は天皇の〝母〟に握ら
れていく。皇后を「一夫一妻制における嫡后」と位置づける認識は、きわめて弱かったのである。実際、仁明―
朱雀間、すなわち九世紀半ばから十世紀半ばの約一世紀間は、皇后はたてられなかった。「母后の存在によって
妻后が生まれる意味も余地も希薄になった」からである〔東海林二〇〇四、七二頁〕。
この状況が、つぎの摂関政治につながる。平安中期、退位後の上皇は内裏を出るが、母后(上皇の妻)は「(息
子である)天皇とともに内裏にあり」天皇を後見した。「摂関(母后の父)の直盧が内裏内におかれ」、一〇世紀
末には、母后を支える政治機構として「上皇と同じような立場から政治に関与できるように」女院制がつくり出
された。「こうした母后、女院の政治的機能を利用して、摂関政治は成立した」のである〔古瀬二〇〇一、一五頁〕。「摂
政関白は『国母の代行』だった」〔服藤二〇〇三、七頁〕ともいえ、朱雀朝の初め、忠平の時に摂政の後宮直廬が
始まるのは、国母穏子の後宮支配確立と深く関わる〔東海林二〇〇四、六七頁〕。
さきに述べたように、古代の家族の結びつきは、〝母子+夫〟と表現できるようなものだった。母子の絆は強いが、
夫婦の絆は弱い。内裏におけるキサキの同居の本質も、天皇の〝妻〟としてではなく、〝母〟としての立場が優
越した、いいかえれば、夫妻同居ではなく母子同居だった。こうした関係にはっきりした変化が起こるのは、次
の院政期である。
栗山圭子氏は、後白河・高倉二代の女院(建春門院・建礼門院)を比較検討し、彼女たちが国母(天皇の母)
帝京史学26号.indb 119 2011/02/16 18:48:30

-・120・-
として政治的権限を行使するためには、「院(夫である上皇)との同居が不可欠」だったことを明らかにした(栗
山二〇〇二、二二九―二三〇頁)。摂関期の母子同居から、院政期の夫妻同居へと、キサキの政治権能の基礎条件
は大きく転換し、天皇家の家長としての地位を確立した院(上皇)の〝妻〟として、代行権限を果たすようにな
るのである。天皇家における一組の夫婦単位の成熟という婚姻関係の変化が、キサキの経営機能・政治権能の喪
失と密接に関わっていることが、長期にわたる歴史的変化から如実にみてとれよう。
よく知られているように、日本の古代には六世紀から八世紀後半まで、八代六人の女帝がいた(二人は重祚)。
最後の女帝称徳が死に、次に皇位についた光仁の時に、皇后の内裏居住がはじまり、さらに次の桓武の時に他の
ランクのキサキたちの後宮集住も実現する。女帝の終焉とキサキの独立性の消失は、ほぼ同時期なのである。こ
れは興味深い対応といって良いだろう。そしてその後、皇后不在の多かった平安前期を経て、平安中期には、母
子の絆の強さを政治形態に組み込んだ形で、国母となったキサキの権威がたかまり、それが摂関政治の土台とな
る。そして平安後期の院政期になると、キサキは家長の地位を確立した上皇の〝妻〟として、限定された政治権
限を持つにすぎなくなるのである。
では、八世紀までみられた女帝の政治権力や、独立した宮を保持したキサキたちの権力は、天皇の母であるこ
とにもとづいていたのだろうか?
従来の女帝論や皇后論は、彼女たちの「妻」「母」としての役割に焦点をあ
てる傾向が強かったが、私はそれには疑問を持つ。そこで次には、はるかに歴史を遡り、古墳時代の女性首長に
ついてみていきたい。
帝京史学26号.indb 120 2011/02/16 18:48:30

-・121・-
二節
古墳埋葬からみる女性首長
大王墓と考えられている全長四〇〇メートル以上の巨大な前方後円墳から、小集団の長を葬った小さな円墳・
方墳まで、日本列島上には一〇万基以上の古墳が存在する。かつては、政治的支配者=男性という前提からか、
古墳に葬られているのは男だろう、と漠然と考えられがちだった。立派な腕輪や首飾りをつけた女性埋葬例があ
ると、〝巫女〟の一言で片づけられてきた。だが、今井堯氏が、人骨資料を総合して古墳時代の女性の地位を考
察して以降、こうした見方は大きく変更を迫られている。四~五世紀を中心に、今井氏の分析結果をまとめると、
おおよそ次のようになる〔今井一九八二〕。
①五世紀半ば以前には、各地域の中心となる首長墳に単独あるいは中心人物として熟年女性が埋葬される例が、
九州から関東まで、広範な地域でみられる。
②副葬品から判断して、地域政治集団の女性首長は祭祀権だけではなく、軍事権・生産権をも掌握しており、
同時期の男性首長と同様の首長権を持つ。
③・
男性首長の単独中心埋葬は、女性首長例に比べてわずかに多い程度である。
性別の判定できる人骨例はそれほど多くはないのだが、そこから判断する限り、五世紀半ば以前には、日本の
各地に男女の首長がほぼ半々の割合で存在していたということになる。その後は、大規模墳・中規模墳での女性
首長埋葬例はみられなくなっていくが、小規模墳への女性埋葬はつづく。今井氏の分析対象には、大王墓は含ま
れていない。天皇の祖先の墓として宮内庁が管理していて、発掘調査をすることができないからである。
今井氏のあげる単独女性首長埋葬の代表例は、熊本県宇土市にある全長八七メートルの向野田古墳である。四
帝京史学26号.indb 121 2011/02/16 18:48:30

-・122・-
世紀末~五世紀初の前方後円墳で、三〇代後半の女性が単独で葬られていた。副葬品として、鏡三面、石製宝器、
勾玉などのほか、鉄の長剣・短剣、直刀、槍などの武具と、鉄斧・刀子などの工具が多数置かれていた。向野田
古墳は、同時期におけるこの地域最大規模の古墳である。つまり、彼女は、地域一帯の最高首長だったことにな
る。武器・工具の副葬品からみて、「軍事・生産を掌握した女性首長」というのが、今井氏の解釈である〔今井
一九八二、一三二頁〕。ただし、清家章氏の最近稿によれば、副葬される武器の種類と配置には男女で相違がみら
れ、首長層の軍事的紐帯への女性首長の関与は低かったとみられる〔清家一九九八〕
一方、森浩一氏は、古墳の立地から、女性首長が交通権を掌握していたと推定される例に注目している。一例
をあげると、丹後半島を貫流して日本海にそそぐ竹野川上流の丘の上(京都府大宮町)の大谷古墳には、熟年女
性が単独で葬られていた。鏡・玉類とともに鉄剣・鉄斧が副葬されていた。五世紀前半の前方後円墳で、全長
三二メートルと小型だが、周辺では傑出した規模の、最初に築かれた古墳である。当時、国内に鉄鋳造の技術は
なく、武器も農工具も、朝鮮半島からもたらされるものに依存していた。大谷古墳の主は、交通・交易権をにぎ
る大首長との連携により、鉄製品・技術を入手して、この地域で最初に支配権を確立した小首長だったことにな
る〔森一九八七、八五―八八頁〕。
以上、考古学の成果によって、日本列島の各地に女性首長がいたことを確認した。
三節
伝承と征討記事に描かれた女性首長
五世紀後半以降、ヤマト朝廷は各地の政治勢力を武力で統一し、支配組織を作りあげていった。この過程で、
帝京史学26号.indb 122 2011/02/16 18:48:31

-・123・-
制圧された土着勢力の姿は、八世紀前半にまとめられた『風土記』の伝承の中に見いだすことができる。
『風土記』は、朝廷に制圧された首長たちを、「国栖」・「佐伯」・「土蜘蛛」といった名称で、野蛮な異種族であ
るかのように描いている。一番よく使われている名称は「土蜘蛛」である。神話学者の溝口睦子氏によれば、「土
蜘蛛」伝承には、王権の論理とその土地固有の伝承が二重構造をなしていて、後者には、その土地の歴史に関す
る貴重な情報を含むという〔溝口一九九七〕。
北九州の豊後国風土記・肥前国風土記には、村を統括し、人々を率いて戦い、あるいは戦い敗れて降伏した男
女の「土蜘蛛」の話が、多数見られる。男女の「土蜘蛛」の人数はほぼ半々で、伝承から知られる活動内容にも
男女で大きな違いはない〔義江二〇〇三b〕。例をあげると、
1=豊後国速見郡条
昔、「処の長」だった速津媛は、征討にやってきた天皇を出迎えて、五人の土蜘蛛が立て籠もる場所を教え、
ことごとく滅ぼさせた。そこで(速津媛はこの土地の支配権を認められて)ここを速津媛の国といい、のち
速見郡と改めた。
2=肥前国杵島郡条
昔、「土蜘蛛八十女(大勢の女)」が山頂に立て籠もって、天皇の命令に従おうとしなかった。天皇は兵士を
派遣して全滅させた。そこでこの山を「嬢子山」というのである。
帝京史学26号.indb 123 2011/02/16 18:48:31

-・124・-
播磨国風土記の場合には、「土蜘蛛」は登場しない。その代わりに、男女の神々の物語が多数記されている。神々
とはいっても、神社に祭られる神ではない。人間と全く同じように、恋をし、農耕労働の指揮をし、支配領域を争う、
男神・女神たちの物語である。そこには、明らかに「村々の首長の面影」をみることができる〔倉塚一九六二〕。
在地勢力を「土蜘蛛」として描くか、「男神・女神」として描くかは、語り手の側の語り方の違いにすぎないの
である。
ここでも、男神と女神、すなわち男女首長の人数はほぼ半々であり、活動内容にもほとんど違いがない。一例
として、石龍比売の話を見てみよう。
3=・
揖保郡美奈志川条
イワ大神の子のイワタツヒメ(女神)とイワタツヒコ(男神)が水争いをした。男神は北の越部村に水を流
そうとし、女神は南の泉村に流そうとする。男神は頂上を低くして、北方に流したので、女神は櫛で流れを
せきとめ、溝を開き、泉村に流した。そこで男神は下流の水を西の桑原村に流そうとしたが、女神は地下に
樋を通して、泉村の田まで水を引いてくることに成功した。
4=・
同郡広山里条
イワタツヒメが泉村から放った矢が、この里まで飛んできて、矢の握りの部分しか見えないくらいしっかり
と地中にめりこんだ。
帝京史学26号.indb 124 2011/02/16 18:48:31

-・125・-
この二つの話で、女神の物語として描かれているのは、①男神との争いに勝つ機敏な判断力、②自分の村に農
業用水を引いてくる勝れた農業技術、③強い矢を放つ腕力・武力、の三者を兼ね備えた女性首長の姿である。矢
や石を投げて、その届く範囲を勢力圏と定めるというやり方は、男神どうしの縄張り争いの話としても、よくみ
られる話である。
女性首長の存在は、伝承の世界だけではない。八世紀前半に最後の大叛乱を起こして鎮圧された南九州の隼人
について、『続日本紀』は、「兵をもちて」(武器をとって)朝廷の使者を襲った隼人の首長たち数名の名を記録
している。その中でも筆頭に記載された、つまり、朝廷が乱の首謀者とみなしているのは、「薩摩比売・久米・
波豆」という三名の女性首長である〔『続日本紀』文武四年六月庚辰条。義江二〇〇四〕。
以上、古墳埋葬人骨の分析、風土記の説話、『続日本紀』の叛乱記録、を総合して考えると、三世紀から八世
紀初ごろまで、日本列島の各地に多数の女性首長がいて、男性首長とほぼ同様に、軍事・生産活動の指揮をし、
他の首長やヤマト朝廷との間で勢力争いを繰り広げていたことは、間違いないといって良い。
小結
ここで、女性首長を媒介に、二章一・二節で明かにした八~九世紀にみられる村の「里刀自」=「家刀自」の
半公的地位と、本章一節で述べた貴族女性(「大刀自」)の政治的地位の歴史的変化とを関連づけて考えてみよう。
そうすると、刀自たちは、古い時代の女性首長たちの末裔にほかならないことがみえてくる。
男女の首長たちは、ヤマト朝廷が統一権力を形成していく過程で、かつての独立した政治支配者、統率者とし
帝京史学26号.indb 125 2011/02/16 18:48:31

-・126・-
ての地位を失っていった。八世紀初の律令制の導入によって、男性首長の末裔は、朝廷の支配のもと、地方社会
における政治的リーダーとしての地位(郡司・里長)に組み込まれたが、女性首長は、公的地位から完全に排除
された。しかし、地方社会においては、彼女たちの村人に対する統率力は厳として存在し、その力に依存するこ
となくしては、国家の租税収取も、労働力の徴発も、現実には機能しなかった。これが、木簡と説話にみえる、「刀
自」たちの半公的地位の歴史的背景である。
里刀自は、階層としては里長と同階層であり、実際には里長の妻である場合も多かったろう。しかし、この時
代における夫婦の絆は安定したものではなかった。そのことを考えても、里刀自の半公的地位、経営主としての
力は、里長の「妻」であることに基づくのではない、ということを再度、強調しておきたい。
一方、政治権力を集中した朝廷内部においては、貴族女性が、後宮の女官として、九世紀初にいたるまで、男
性貴族と並ぶ大きな政治力を行使した
10
。また、貴族女性出身のキサキたち(大刀自)も、内裏に包摂される
ことなく、自分の宮・ヤケで独立した経営主でありつづけた。女官の政治的権限は、九世紀半ば以降、その多く
が男官にとってかわられ衰えていき〔吉川一九九〇〕、キサキの宮の独立性も八世紀末には失われる。しかし、
出身氏族の勢力を背景とするキサキの政治権力は、日常生活における母子結合の強さを背景に、平安中期以降、
国母の権力として姿を変えて再生し、摂関政治の土台となった。国母の権力が、上皇の「妻」であることに基づ
いて限定的に行使されるようになるのは、平安末期の院政期になってからである。
帝京史学26号.indb 126 2011/02/16 18:48:31

-・127・-
おわりに
以上、本稿で述べてきたことの意義を、①女性史研究の成果の総合、②古代史研究と女性史研究の総合、③異
なる性格の史料を分析する視点、の三点についてまとめ、結びとしたい。
まず、女性史研究の成果の総合について。戸主男性に率いられた父系大家族であるかのようにみえる古代の戸
籍が、実態ではなく、国家が父系原則を導入するに伴って机上で編成されたものであることを、古代女性史研究
はこれまでに明かにしてきた。長い歴史を持つ家族・婚姻史研究の分野では、別居婚や妻方居住婚の実態、母子
結合の強さと夫婦結合の弱さ、双系的な親族原理が、古代社会の特色として浮かび上がってきた。また、女帝や
皇后・女官が国政において果たした重要な役割には、近年、ますます焦点が当てられるようになってきている。
本稿では、これら三つの分野の成果を総合することをめざした。そのために、研究の手薄であった地方豪族層・
富豪層の女性=「刀自」の具体的働きに焦点をあてて、見てきた。その結果、1=独立した女性経営者としての
刀自が、「戸」の枠組みを超えたところで、村人を統率・指揮する半公的地位を占めていたこと、2=彼女たち
の遠い前身は、古い時代に日本列島上に広範に存在した女性首長たちであること、3=女性首長たちの持ってい
た政治権力は、八世紀以降は、国政レベルでのキサキ(大刀自)たちの政治的地位に顕著に集約されていくが、
その基礎にも、キサキの宮の独立性とそこでの彼女たち自身による経営があったこと、を明かにすることができ
た。
帝京史学26号.indb 127 2011/02/16 18:48:31

-・128・-
古代には八代六人の女帝がいた。彼女たちについては、皇位の父系継承を確保するための中継ぎ、あるいは、
巫女としての特殊能力によるとする議論が、通説的地位をしめてきた。こうした通説に対する批判は、近年の王
権論の中でようやく明確に示されるようになってきた〔荒木一九九九、義江明子二〇〇二a、仁藤二〇〇三〕が、
私はより根本的な問題として、女帝を日本古代王権の特殊事情や個別の政治過程からだけ説明するのではなく、
より広く、古代のジェンダー関係全体の中でとらえる視点が不可欠だと考えている
11。本稿で明かにしたように、
三・四世紀以来の女性首長の存在と、九世紀半ばまで確認できる村の刀自たちの半公的地位、一二世紀まで変質
しながら続くキサキたちの政治権力、の三者を、共通する一つの大きな枠組みの中でとらえ、こうした広い裾野
の上に出現したものとして、古代の女帝の意義を再検討すべきだと思う。王位継承の変化や王権構造の変化につ
いても、そこから新たにみえてくるものがあるはずである。
次に、古代史研究と女性史研究の総合について。石母田正氏の『日本の古代国家』〔石母田一九七一〕以来、
一九七〇年代以降の日本古代史研究は、石母田氏が提起した在地首長制論をめぐって展開してきた。そこでは、
中国から導入された律令制国家の支配組織のもとで、現実に生産活動の指揮と人民に対する直接の政治支配権を
にぎっていたのは、郡司から里長・村長にいたる在地首長層であることが、さまざまな角度から具体的に明かに
されてきた。しかし、夥しい数に上る在地首長制論の議論の中で、女性首長の存在が考慮されたことはない。ま
た、九世紀以降、そうした旧来の共同体の枠組みが壊れ、新たな村落秩序が形成されていく過程を究明しようと
する富豪論〔戸田一九六七他〕の中でも、女性の富豪=経営主の活動を組み込んだ分析は、ほとんどない
12
。本
稿では、地方豪族層・富豪層女性の村内部における役割と、それを掌握することが国家の租税徴収にも不可欠で
帝京史学26号.indb 128 2011/02/16 18:48:31

-・129・-
あったこと、彼女たちの前史がかつての女性首長にまで遡り得ることを示した。在地首長制論と富豪論の双方で、
女性を組み入れた議論が展開していくことを期待したい。
最後に、異なる性格の史料を分析する視点について。本稿では、最新の出土史料である木簡を活用して、〝隠れた〟
女性の姿を掘り起こすようにつとめた。木簡のもつ日常的生活記録という性格が、それを可能にしたのである。
木簡からは、〝隠れた〟女性の働きや半公的地位が明かになっただけではない。木簡からわかることと、律令を
はじめとする法制史料や『日本書紀』『続日本紀』といった朝廷の記録とのズレに注目することによって、なぜ、
彼女たちがこれまでは〝見えなかった〟のかも、明確にできたと思う。
重要なことは、それぞれの史料の本来持っている性格が異なる、ということだけではない。女性についての記
載が乏しく、また、国家の要請するジェンダー規範にそって叙述されている正史の記事であっても、注意深く読
んでいけば、〝隠れた〟女性の姿は見えてくる。平城宮址の発掘によってキサキの宮の内裏不在が確認される以
前に、『日本書紀』の批判的分析からキサキの宮の独立性を論証した三崎氏の仕事は、その良い例である。本稿
で行った力田褒賞記事の分析も、木簡にみえる「里刀自」、説話史料にみえる「家刀自」の再検討と総合することで、
「力田の妻」について、これまでとは異なる解釈を示すことができたと思う。
どちらの場合も、「後宮に納る」「家」など、史料上の用語を、その語のもつ中国語としての意味や、現代用語
としての意味に流されることなく、何を表現しているのかを厳密に考えていくことが、正史記事の批判的検討、
説話の読み直しにつながるのである。逆に、近代の「妻」役割や「家」概念を自明のものとしている限り、たと
え史料に貴重な記載が含まれていても、彼女たちの役割を真に把握することは難しい。史料にのぞむ私たち研究
帝京史学26号.indb 129 2011/02/16 18:48:31

-・130・-
者の視点を鍛えることで、〝隠れた〟女たちは語りだすのである。
注1・・
家族史研究の成果にもとづく戸籍研究史の整理は、杉本一九八六を参照。
2・・
近年、民俗学内部から提起された柳田主婦論への批判として、福田一九八九、倉石一九九五がある。柳田の主婦論が、
歴史の〝再解釈〟を通じて、近代の「家」を担う主婦像を創出しようとしたものであることは、義江一九九一、参照。
3
いわき市教育文化事業団『荒田目条里制遺跡
木簡は語る』一九九五、・
および木簡学会編『日本古代木簡集成』東京
大学出版会、二〇〇三、六四頁・図版四二。・
4・・
木簡から判明するこの荘園の経営方式全般については、村井一九八五、参照。
5・・
奈良国立文化財研究所『飛鳥藤原宮発掘調査出土木簡概報』七、一九八三。
6・・
酒部・酒戸等の官職・専業組織を除き、民間の酒造りは、古代にはもっぱら女性の仕事だった。中世になっても、「七十一
番職人歌合」には、酒作〔さかづくり〕・麹売〔こうじうり〕の女性の姿が描かれている(『七十一番職人歌合』六番・
三十八番)。それが近世に入るころから、女性不浄観の浸透とともに、醸造場は女人禁制の仕事場とされていくので
ある(脇田一九九二、第一章)。現在のところ、女性が酒作りの現場にいたことが確認できる最後の資料は、寛文九
(一六六九)年の絵馬である(井之本二〇〇〇)。この変化にともなって、古代には(造酒活動を担った)豪族層女性
の称であった「とじ」が、近世以降は、男性酒作り職人をさす「杜氏」(とうじ)になっていく。
7・
日本において、天皇・皇后夫妻による「親耕親蚕」〝風〟儀礼が定着したのはいつかといえば、それは明治以降のこ
帝京史学26号.indb 130 2011/02/16 18:48:31

-・131・-
とであった。ただし、あくまでも〝風〟であって、夫婦一対の儀式ではなく、中国古代の「親耕親蚕」とは似て非な
るものといわねばならない。養蚕の儀は明治八年(一八七五)、お田植え行事ははるかに遅れて昭和天皇の即位後に、
それぞれ別個の意図をもって時代の要請を担い創設されたのである。皇后の親蚕の儀は、当時の殖産興業の柱であっ
た女工による紡績奨励の意図を込めて、それを視覚化したものであった〔梅村一九九六、三二三―三二六頁〕。近代の
皇后、特に明治の昭憲皇后が国民統合に果たした「妻」表象の意義については、近年、大きく解明が進んでおり〔片
野一九九六・二〇〇二、若桑二〇〇一〕、親蚕の儀の創設も、その一環として位置づけることができよう。
・
一方、天皇のお田植え行事は、明治期に中国古代の藉田儀礼(皇帝による親耕)および近代欧州君主の勧農・勧業を
意識して建言されたが、その時には実現にいたらず、長期の検討を経たのち、一九二五年の昭和天皇即位後に最初の
行事が行われた。この時期における天皇儀礼としての大嘗祭の意義の浮上と関連するとみられ、収穫された新穀は新
嘗祭に供献された〔高木一九八九〕。新聞は天皇の〝お田植え〟を大きく報道し、国富の源泉たる農業生産の増進に
つとめる男性天皇の姿を、広く国民に印象づけたのである。
8・・
この過程を詳細に解明した最近稿として、遠藤みどり二〇一〇がある。
9・・・
家族・婚姻関係史料、なかでも『日本書紀』の史料批判の重要性については、義江二〇〇〇、参照。・
10・・
女官制度全般については、野村一九七八参照。・
奈良時代の女官の制度は、中国の制度をとりいれてはいるものの、
実質は全く異なる。これについては、本稿ではほとんど述べることができなかった。男官と女官の組織を通覧したジェ
ンダー分析は、古瀬一九八八、文殊一九九二、勝浦一九九五、吉川一九九〇、義江二〇〇三a等、参照。なお、采女
の叙位から女官の政治的地位全般を男官との共通性という観点から考察したものに、伊集院葉子二〇一〇a・bがあ
帝京史学26号.indb 131 2011/02/16 18:48:31

-・132・-
る。
11・・こうした視点は、すでに関口一九九一でも明確に指摘されている。
12・・
数少ないそうした仕事として、河音一九九〇、服藤一九九一がある。
引用参考文献
明石一紀
一九九〇 『日本古代の親族構造』吉川弘文館。
荒木敏夫
一九九九 『可能性としての女帝
女帝と王権・国家』青木書店。
安良城盛昭一九六七 「班田農民の存在形態と古代籍帳の分析方法」『日本封建社会成立史論』上、岩波書店、一九八四年
所収。
石上英一
一九七三 「日本古代における調庸制の特質」『歴史学研究別冊
歴史における民族と民主主義』青木書店。
石母田正
一九四二 「古代家族の形成過程」『石母田正著作集』二、岩波書店、一九八八年所収。
一九七一 『日本の古代国家』岩波書店。『同右』三、一九八九年、再録。
伊集院葉子二〇一〇a「采女の外五位昇叙」『古代文化』六二―一。
二〇一〇b「女官の五位昇叙と氏――内階・外階コースの検討を中心に――」『専修史学』四九。
井上
薫
一九七八 「子日目利箒小考」『龍谷史壇』七三―三。
一九八八 「子日親耕親蚕儀式と藤原仲麻呂」『橿原考古学研究所論集』一〇、吉川弘文館。
井之本泰
二〇〇〇 「智恩寺蔵『酒造り絵馬』と女性」『女性史学』一〇。
帝京史学26号.indb 132 2011/02/16 18:48:31

-・133・-
今井
尭
一九八二 「古墳時代前期における女性の地位」総合女性史研究会編『日本女性史論集』二、吉川弘文館、
一九九七、所収。
上田早苗
一九七九 「漢代の家族とその労働――夫耕婦績について――」『史林』六二―三。
梅村恵子
一九七九 「律令における女性名称」総合女性史研究会編『日本女性史論集』三、吉川弘文館、一九九七、所収。
一九八七 「摂関期の正妻」義江明子編『日本家族史論集』八、吉川弘文館、二〇〇二、所収。
一九九六 「天皇家における皇后の位置」『女と男の時空』二、藤原書店。
江守五夫
一九六〇 「母系制と妻訪婚」義江明子編『日本家族史論集』八、吉川弘文館、二〇〇二、所収。
遠藤みどり二〇一〇 「令制キサキ制度の展開」『続日本紀研究』三八七。
大津
透
一九九三 『律令国家支配制度の研究』岩波書店。
片野真佐子一九九六 「近代皇后像の形成」富坂キリスト教センター編『近代天皇制の形成とキリスト教』新教出版社。
二〇〇二 「近代皇后論」『岩波講座
天皇と王権を考える』七、岩波書店。
勝浦令子
一九八七 「院政期の宗教活動に見える夫と妻の共同祈願」『女の信心』平凡社、一九九五、所収。
一九九五 「古代宮廷女性組織と性別分業」『日本古代の僧尼と社会』吉川弘文館、二〇〇〇、所収。
河音能平
一九六三 「日本令における戸主と家長」『中世封建制成立史論』東京大学出版会、一九七一、所収。佐々木潤
之介編『日本家族史論集』三、吉川弘文館、再録。
一九九〇 「生活の変化と女性の社会的地位――首長制的秩序から家父長制的秩序へ――」女性史総合研究会
編『日本女性生活史2
中世』東京大学出版会。
帝京史学26号.indb 133 2011/02/16 18:48:31

-・134・-
岸
俊男
一九五七a「郷里制廃止の前後」『日本古代政治史研究』塙書房、一九六六年、所収。
一九五七b「光明立后の史的意義」『同右』、所収。
鬼頭清明
一九八六 「稲舂女考」『古代木簡の基礎的研究』塙書房、一九九三、所収。
倉石あつ子一九九五 『柳田国男と女性観』三一書房。
倉塚曄子
一九六二 「女神に関する覚書」『都大論究』二。
栗山圭子
二〇〇二 「二人の国母――建春門院滋子と建礼門院徳子――」『文学』三―四・五。
後藤みち子二〇〇一 『中世公家の家と女性』吉川弘文館。
坂江
渉
一九九二 「古代における力田者について」『ヒストリア』一三七。
一九九七 「古代国家と農民規範――日中比較研究アプローチ」『神戸大学史学年報』一二。
一九九八 「古代東アジアの王権と農耕儀礼――日中社会文化の差異――」鈴木正幸編『王と公――天皇の日
本史』柏書房。
佐々木恵介一九八六 「律令里制の特質について――日・唐の比較を中心として――」『史学雑誌』九五―二。
東海林亜矢子二〇〇四「母后の内裏居住と王権」『お茶の水史学』四八。
杉本一樹
一九八四 「編戸制再検討のための覚書」『日本古代文書の研究』吉川弘文館、二〇〇一、所収。
一九八六 「日本古代家族研究の現状と課題――関口裕子・吉田孝・明石一紀説を中心として」『同右』所収。
清家
章
一九九八 「女性首長と軍事権」『古墳時代の埋葬原理と親族構造』大阪大学出版会、二〇一〇、所収。
関口裕子
一九七七 「歴史学における女性史研究の意義――日本古代史を中心に――」総合女性史研究会編『日本女性
帝京史学26号.indb 134 2011/02/16 18:48:31

-・135・-
史論集』一、吉川弘文館、一九九七、所収。
一九九一 「古代女性の地位と相続法」武光誠編『古代女性のすべて』新人物往来社。
一九九三 『日本婚姻史の研究』上下、塙書房。
二〇〇四 『日本家族史の研究』上下、塙書房。
高木博志
一九八九 「日本の近代化と皇室儀礼――一八八〇年代の〈旧慣〉保存――」『近代天皇制の文化史的研究』校
倉書房、一九九七、所収。
高橋秀樹
一九九六 『日本中世の家と家族』吉川弘文館。
高群逸枝
一九三八 『母系制の研究』〔高群逸枝全集〕一、理論社、一九六六、所収。
一九五四 『招婿婚の研究』〔同右〕二・三所収。
戸田芳実
一九六七 『日本領主制成立史の研究』岩波書店。
南部
曻
一九九二 『日本古代戸籍の研究』吉川弘文館。
西野悠紀子一九九七 「中宮論」大山喬平教授退官記念会編『日本国家の史的特質
古代・中世』思文閣出版。
仁藤敦史
二〇〇三 「古代女帝論の現状と課題」『歴史評論』六四二。
野村忠夫
一九七八 『後宮と女官』教育社。
橋本義則
一九九五 「平安宮内裏の成立過程」『平安宮成立史の研究』塙書房。
林
陸朗
一九六一 『光明皇后』〔人物叢書〕吉川弘文館。
平川
南
一九九六 「里刀自小論――いわき市荒田目条里遺跡第二号木簡から――」『古代地方木簡の研究』二〇〇三、
帝京史学26号.indb 135 2011/02/16 18:48:31

-・136・-
所収。
福田アジオ一九八九 「柳田国男における歴史と女性」『柳田国男の民俗学』吉川弘文館、一九九二、所収。
服藤早苗
一九八二 「古代の女性労働」女性史総合研究会編『日本女性史1
原始・古代』東京大学出版会。
一九九一 『家成立史の研究』校倉書房。
二〇〇三 「九世紀の天皇と国母――女帝から国母へ――」『物語研究』三。
二〇〇六 「平安中期の婚姻と家・家族」加納重文編『源氏物語とその時代』〔講座源氏物語研究〕おうふう。
古瀬奈津子一九八八 「中国の『内廷』と『外廷』――日本古代史における『内廷』『外廷』概念再検討のために――」『日
本古代王権と儀式』吉川弘文館、一九八八、所収。
二〇〇一 「摂関政治成立の歴史的意義」『日本史研究』四六三。
丸山裕美子一九九二
・「唐と日本の年中行事」池田温編『古代を考える
唐と日本』吉川弘文館。
三崎裕子
一九八八 「キサキの宮の存在形態について」総合女性史研究会編『日本女性史論集』二、吉川弘文館、
一九九七、所収。
溝口睦子
一九九七 「『風土記』の女性首長伝承」前近代女性史研究会編『家・社会・女性
古代から中世へ』吉川弘文館。
村井康彦
一九八五 「宮所庄の構造」『国立歴史民俗博物館研究報告』八。
村武精一
一九八一 「社会人類学における家族・親族論の展開」村武精一編『家族と親族』未来社。
森
浩一
一九八七 「古墳にみる女性の社会的地位」森浩一編『女性の力』〔日本の古代〕一二、中央公論社。
文殊正子
一九九二 「令制宮人の一特質について」『仟陵』(関西大学博物館学課程創設三〇周年記念論集)。
帝京史学26号.indb 136 2011/02/16 18:48:31

-・137・-
柳田国男
一九三九 「女性史学」『定本柳田国男集』一四、筑摩書房、一九六二、所収。
一九四八 「主婦に就いての雑話」『同右』一五、一九六三、所収。
山中
裕
一九七二 『平安朝の年中行事』塙書房。
義江(浦田)明子一九七二 「編戸制の意義――軍事力編成との関わりにおいて――」『史学雑誌』八一―二。
義江明子
一九八六 『日本古代の氏の構造』吉川弘文館。
一九八九 「「刀自」考」『日本古代女性史論』吉川弘文館、二〇〇七、所収。
一九九〇 「古代の村の生活と女性」女性史総合研究会編『日本女性生活史1
原始・古代』東京大学出版会。
一九九一 「女性史と民俗学」『古代女性史への招待 〈妹の力〉を超えて』吉川弘文館、二〇〇四、所収。
一九九五 「古代の家族と女性」『岩波講座日本通史六
古代五』岩波書店。
一九九六 『日本古代の祭祀と女性』吉川弘文館。
二〇〇〇 「婚姻と氏族」『日本古代女性史論』吉川弘文館、二〇〇七、所収。
二〇〇二a「古代女帝論の過去と現在」網野善彦他編『ジェンダーと差別』〔岩波講座
天皇と王権を考える〕
七、岩波書店。
二〇〇二b・・
義江明子編『日本家族史論集』「解説」吉川弘文館。
二〇〇三a「女性史からみた日本古代の村と後宮――労働の国家的編成とジェンダー」『唐代史研究』六、
二〇〇三b「〝卑弥呼たち〟の物語――女と男/公と私――」赤坂憲雄他編『女の領域・男の領域』〔いくつも
の日本〕Ⅵ、岩波書店。
帝京史学26号.indb 137 2011/02/16 18:48:31

-・138・-
二〇〇四 「戦う女と兵士」西村汎子編『戦の中の女たち』〔戦争・暴力と女性〕一、吉川弘文館。
吉川真司
一九九〇 「律令国家と女官」『律令官僚制の研究』塙書房、一九九八、所収。
吉田
孝
一九八三 『律令国家と古代の社会』岩波書店。
若桑みどり二〇〇一 『皇后の肖像』筑摩書房。
脇田晴子
一九九二 『日本中世女性史の研究
性別役割分担と母性・家政・性愛』東京大学出版会。
Sekiguchi・2003・・The・Patriarchal・Fam
ily・Paradigm・in・Eighth-Century・Japan,・D
.Ko・et・al.,・eds.,・W
omen and Confucian
Culture in Premodern China, K
orea, and Japan.・University・of・California・Press.・
〔付記〕本稿は、・M
ON
UM
RN
TA
NIPPO
NICA
・60-4
(2005
)に掲載された拙稿Gender・in・Early・Classical・Japan:・M
arriage,・
Leadership,・and・Political・Status・in・Village・and・Palace・
の日本語原文を、若干の補足を加えてまとめ直したものであ
る。とはいっても、翻訳の過程で訳者とのやりとりを通じて大幅に手を加え組み替えたので、英訳された掲載版と原
文とは相当違っている。そもそもM
ON
UM
RN
TA
NIPPO
NICA
の日本語原稿は、唐代史研究会二〇〇二年夏季シン
ポジウムでの報告「女性史からみた日本古代の村と後宮――労働の国家的編成とジェンダー」の一部と、二〇〇三
年のInternational Federation for R
esearch in Wom
en’s History, B
elfast, Northern Ireland
での報告 “Public in Private Status in
Ancient Japan: The C
hange in Ideas Concerning the H
onorific Title of Wom
en Called ‘Toji’ : from
Housew
ife to Female C
hief”・・
をあわせたものを土台としている。唐代史研究会での報告は、『唐代史研究』六(二〇〇三年)に同題で掲載された
ので、本稿の一章と二章三節、三章一節とは、叙述が同論文と部分的に重なるところも少なくない。しかし、キサキ
帝京史学26号.indb 138 2011/02/16 18:48:31

-・139・-
まで含めて「刀自」という一貫した観点から考察したのは、日本文としては本稿がはじめてであり、こうした形で公
表することにもそれなりの意味はあろうかと思う。読者諸賢のご了解をお願いする次第である。・・
帝京史学26号.indb 139 2011/02/16 18:48:31

帝京史学26号.indb 140 2011/02/16 18:48:31