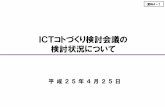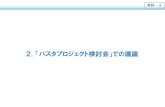2.5 災害対策検討支援ツールの開発 前節までの検討におい …- 214 - 2.5 災害対策検討支援ツールの開発 2.5.1 災害対策検討支援ツールの開発概要
大学における知的財産マネジメントの在り ...€¦ · 等 応 ※ ) ※ 検討...
Transcript of 大学における知的財産マネジメントの在り ...€¦ · 等 応 ※ ) ※ 検討...

大学における知的財産マネジメントの在り方について(報告書)
大学の成長とイノベーション創出に資する大学の知的財産マネジメントの
在り方について
大学等における職務発明等の取扱いについて
オープン&クローズ戦略時代の大学知財マネジメント検討会
大学等における産学官連携リスクマネジメント検討委員会


目 次
1.大学における知的財産マネジメントの在り方について ··················· 1
2.オープン&クローズ戦略時代の大学知財マネジメント検討会関連
大学の成長とイノベーション創出に資する大学の知的財産マネジメントの在り方に
ついて(概要) ································································ 3
大学の成長とイノベーション創出に資する大学の知的財産マネジメントの在り方に
ついて(本文) ································································ 5
参考資料 ····································································· 59
3.大学等における産学官連携リスクマネジメント検討委員会関連
大学等における職務発明等の取扱いについて(概要) ····························· 95
大学等における職務発明等の取扱いについて(本文) ····························· 97
参考資料 ···································································· 117


リスクマネジメント・コンプライアンス等
(特許法等の各種制度への対応※)
※職務発明制度等の特許法改正への対応について検討
各大学等が、戦略面・制度
面の両者に関して、総合的
な知的財産マネジメントを
適切に行うことで、
・イノベーション創出
・大学の成長
に結実させていくことが重要。
制度面
オープン&クローズ戦略時代の大学知財マネジメント検討会
「大学の成長とイノベーション創出に資する
大学の知的財産マネジメントの在り方について」
大学等における産学官連携リスクマネジメント検討委員会
「大学等における職務発明等の取扱いについて」
各研究開発
プロジェクトの
知財方針
大学の
知財戦略
戦略面
企業の
知財戦略
大学における知的財産マネジメントの在り方について
知的財産を適切に保護・活用する戦略的な知的財産マネジメントと制度改正等への対応を含めたリスクマネジメント
を適切に実行することで、大学が保有する研究経営資源を、イノベーション創出に結実させ、我が国の国際競争力強
化を図っていくとともに、大学に対する社会的な期待と信頼が高まり、大学がより一層成長していくことを目指すこ
とが重要。
各戦略に合わせた戦略的な
知的財産マネジメント
-1-

-2-

■大学の知的財産マネジメントの高度化
■イノベーション創出視点での大学の知的財産マネジメントの意義と基本的方向性
<大学知財マネジメントの戦略的方針>
各大学が、大学経営の観点から「知的財産戦略」を策定することが必要。
大学が、イノベーション創出に向けた知的財産活用の方向性に合わせて、大学が単独で保有する特許権を強化すると共に、
共有特許権も含めた知的財産権の活用方策を適切に選択する知的財産マネジメントを実行することが必要。
大学が、産学官連携活動や知的財産マネジメントの成果を、イノベーション創出や事業化の視点で評価することが必要。
知的財産は、技術シーズを実用化し、イノベーション創出を図るために必要不可欠なツール。
各大学は、イノベーション創出に結実していくために、知的財産の活用方策を意識して適切な形でマネジメントすることが必要。
各大学は、知的財産の大学経営上の取得・活用意義を明確にし、大学経営レベルで知的財産マネジメントを捉えることが必要。
「「大学の成長とイノベーション創出に資する大学の知的財産マネジメントの在り方について」(概要)
(文部科学省「オープン&クローズ戦略時代の大学知財マネジメント検討会」(平成28年3月16日)
企業の事業戦略が変容してきている中で、大学における知的財産マネジメントにおいても、
オープン&クローズ戦略等の企業の事業戦略に対応した高度なマネジメントが必要になってきている。
<大学知財マネジメントの体制・システム強化>
各大学は、産学官連携活動、知的財産活用に関するポリシーに即して、知的財産予算を適切に措置すると共に、間接経費を
知的財産マネジメント経費として適切に活用することが必要。
各大学が、概念実証(POC)を行うための仕組みを構築することが必要。
各大学が、企業のオープン&クローズ戦略に対応して、事業化視点での知的財産マネジメントを実現し得る体制を構築する
ことが必要。特に、一気通貫の知的財産マネジメント※1を展開し得る体制を構築することが必要。
「オープン&クローズ戦略」とは、ビジネス・エコシステム構造(企業等が互いに繫がって、自社も他社も共に付加価値を増やすモデル)を前提に、独占するコ
ア領域をクローズ領域として設定し、コア領域とパートナーとがつながる結合領域を知的財産等で保護した上で、パートナーに任せる領域であるオープン領域
を公開していくことで、市場コントロールのメカニズムを構築する戦略である。
※1事業化実現を目指してマーケティングモデル(発明創出時点等の早期のタイミングで、企業等に打診してニーズ把握するようなプレマーケティングを行い、企業ニーズに合
わせた強い知的財産権の取得・活用をすすめていくモデル)を実践し、研究開始・知的財産創出から、出願・権利化、技術移転までの一連の業務が適切に連動した一気通
貫の知的財産マネジメント
-3-

国に期待される取組の方向性
■研究開発プロジェクトの知財方針と大学の知的財産マネジメント
各研究開発プロジェクトにおいて、委託者側は、プロジェクト特性に合わせた知的財産の取扱いに関する方針・戦略を持つこ
とが必要。
大学側においても、プロジェクトの知的財産方針に即した知的財産マネジメントが求められることを理解し、プロジェクト初期
の時点から、知的財産方針の決定に積極的にコミットしていくことが重要。
■産業界側の知財戦略と大学の知的財産マネジメント
<産学のパートナーシップ強化と知財取扱い>
大学の研究成果(知的財産)が産業界側で適切に活用され、継続的にイノベーションを創出していくシステム構築実現のた
めには、産学の対話を通じて双方ビジョンの共有と意見対立緩和を図り、パートナーシップを強化することが重要。
共同研究の成果の取扱い(不実施補償等への対応)は、産学双方の共同研究の目的や状況等を考慮して、総合的な視点
で検討することが必要。
<大学が主導する非競争領域における知的財産マネジメント>
非競争領域※2においては、知的財産権を中核機関(大学等)が蓄積することと、蓄積された知的財産権を産業界側が利用
しやすくする戦略的知的財産マネジメントを行うことが必要。
新たな基幹産業の育成の核となる革新的技術の創出を目指した学問的挑戦性と産業的革新性を併せ持つ異分野融合の
研究の実現に向けて、世界的な技術・ビジネスの動向、関連業界の技術戦略の分析等と連動した知的財産マネジメントを
行える体制・仕組みを構築することが必要。※2「非競争領域」とは、競合関係にある複数の大学や企業間であっても、研究成果の共有・公開を可能にする
基礎的・基盤的研究領域であって、産業界のコミットが得られ、競争領域への移行も見込まれる領域を意味。
大学自身が知的財産戦略を策定し、それに応じた自律的な知的財産マネジメントを実行していくことの実現を目指して、国
は大学をサポートしていくことが重要。
国は、各大学の規模、特性等に応じた段階的なサポートの在り方を検討することが必要。
国は、産学官連携活動を促進し、大学の技術シーズをイノベーション創出に結実させていくための環境整備を進め、必要に
応じて制度の見直しを図っていくことが重要。
-4-

大学の成長とイノベーション創出に資する
大学の知的財産マネジメントの在り方について
平 成 2 8 年 3 月 1 6 日
オープン&クローズ戦略時代の大学知財マネジメント検討会
-5-

大学の成長とイノベーション創出に資する
大学の知的財産マネジメントの在り方について
目次
1.はじめに ······························································ 1
2.大学の知的財産マネジメントに関する現状と課題 ·························· 3
3.イノベーション創出視点での大学の知的財産マネジメントの意義と
基本的方向性 ························································ 10
4.大学の知的財産マネジメントの高度化 ·································· 18
4-1 大学知的財産マネジメントの戦略的方針 18
4-2 大学知的財産マネジメントの体制・システム強化 24
5.研究開発プロジェクトの知的財産方針と大学の知的財産マネジメント ······ 34
6.産業界側の知的財産戦略と大学の知的財産マネジメント ·················· 38
6-1 産学のパートナーシップ強化と知的財産取扱い 38
6-2 大学が主導する非競争領域における知的財産マネジメント 45
7.おわりに ···························································· 52
-6-

1
1.はじめに
科学技術・学術審議会 産業連携・地域支援部会 競争力強化に向けた大学知的資産マ
ネジメント検討委員会「イノベーション実現に向けた大学知的資産マネジメントの在り
方について ~大学における未来志向の研究経営システム確立に向けて~」(平成27
年8月)(以下、競争力強化に向けた大学知的資産マネジメント検討委員会報告書とい
う。)でも指摘されているように、現在我が国は、少子高齢化やテクノロジーの進化に
よる産業構造の変化、グローバル化や新興国の台頭による国際競争の激化、知のフロン
ティアの拡大による研究開発における不確実性の拡大等、急激な社会環境の変化に直面
している。こうした中で、我が国が持続的な発展を実現し、国際社会の中で存在感を示
していくためには、イノベーションを連続的に創出し、社会を変革する新たな価値や産
業を生み出していくことが不可欠である。そして、イノベーションの源泉である優良な
研究シーズや、それを支える卓越した研究人材を生み出す大学に対する社会からの期待
はますます大きくなってきている。
そしてよい技術を生み出せば事業化に成功するということが暗黙のうちに仮定され
ているリニアモデルでは、大規模なイノベーション創出を図ることが困難になってきて
いる。それは、基礎的・基盤的な研究を主とする大学と企業との連携においても例外で
はない。
したがって、日本にイノベーション連鎖をおこすためのエコシステムを確立すること
によって、イノベーションの生産性を高め、雇用創出がなされるメカニズムを作ること
が重要である。それによって我が国全体として研究開発投資を回収していくという視点
をもって、研究活動や産学官連携活動を推進していくことが非常に重要である。
そのためには、大学で生み出された先端的な技術を使った製品の実用化を単に目指す
だけではなく、例えばオープン&クローズ戦略等の企業が競争優位を実現できるビジネ
スモデルをあらかじめ設計し、多くの組織とともに企業の付加価値を長期に高める仕組
みを検討すること等を試み、これまでの産学連携のメカニズムを再構築しなければなら
ない。そして、国も、各プレイヤー(企業、大学等)と連携しながら、我が国のあるべ
き将来像をビジョンとして描き、技術領域を含めて基礎的・基盤的研究の方向付けを行
うとともに、期待される技術イノベーションの成果を、グローバル市場の競争優位性及
び雇用創出に結びつけていく仕組みを、研究開発投資を行う段階から構築することが求
められている。
本検討会においては、そのような環境の中で、大学の技術シーズをイノベーション
-7-

2
創出に結実させ、我が国の国際競争力強化を図っていくとともに、それによって大学に
対する社会的な期待と信頼が高まり、大学がより一層成長していくことを目指し、大学
における知的財産マネジメントの在り方を提案することとする1。
1 競争力強化に向けた大学知的資産マネジメント検討委員会報告書において、「本格的産学連携推進のため
のオープンプラットフォーム形成に求められる産学共創の場におけるオープン・アンド・クローズ戦略を
踏まえた知財マネジメントの在り方の検討も新たに進めていくこととしており、これは新たな組織対組織
の産学官連携の進化の一つのモデルとも考えられるものである。」という旨が提言されている。
-8-

3
2.大学の知的財産マネジメントに関する現状と課題
(1)大学の知的財産マネジメントに関するこれまでの取組経過等
我が国における産学官連携活動や、大学の知的財産活動は、1990年代後半から、
種々の推進施策が展開されてきたところである。教育による人材育成と研究による学理
の探究に重きを置き、公平で中立的な存在と捉えられてきた従来の大学が、産業との連
携を強化し、大学の「知」を社会に提供していくための取組が試みられてきた。
そして、それを更に加速させるべく、大学内の知的財産関係及び産学官連携関係の体
制強化を国が支援することで、特許等知的財産の出願・権利化の強化を図るとともに、
取得された知的財産権の活用が促進され、知的財産を活用してイノベーションを創出す
ることが図られてきた。
具体的には、以下のような取組を行ってきたところである。
○ 平成10年の「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進
に関する法律」(TLO法)が制定されて技術移転機関(TLO)が設けられるととも
に、平成11年に日本版バイ・ドール条項を含む「産業活力再生特別措置法」2、平成
14年に知的財産基本法3が制定されること等を通じて、大学の研究成果である知的財
産の取得・活用が促進されてきた。
○ また、教員個人での知的財産活動から、大学組織として知的財産活動に取り組むこ
とで、知的財産管理・活用の一元化を図ってきた。具体的には、科学技術・学術審議
会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会 知的財産ワーキング・グループにおけ
る提言も受けて(平成14年)、大学で生み出された知的財産等を原則大学帰属とし活
用する等、各大学が自らのポリシーの下で組織として一元的に管理・活用することが
促進されてきたところである。
○ さらに、大学内での組織体制の強化を図るべく、文部科学省において、平成15年
度より大学知的財産本部整備事業を通じた、大学の知的財産の創造・保護・活用を図
る体制整備の促進や、平成20年度より産学官連携戦略展開事業(平成22年度より
イノベーションシステム整備事業「大学等産学官連携自立化促進プログラム」に転換)
を通じた、大学の産学官連携機能の戦略的な強化等を図る取組を行ってきたところで
ある。
2 日本版バイ・ドール条項は平成19年に産業技術力強化法第19条に移行された。 3 知的財産基本法第7条において、大学等の責務として「大学等は、その活動が社会全体における知的財
産の創造に資するものであることにかんがみ、人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ積
極的に努めるものとする。」と規定された。
-9-

4
○ 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)における知財活用支援事業において、
大学における外国特許出願に対する出願費用、特許主任調査員による発明相談や特許
調査、研究成果の実用化促進に向けた大学の取組サポート等を継続的に実施している
ところである。
○ また、近年においては、知的財産の積極的活用に向けた取り組みを大学に促すこと
を目指して、科学技術・学術審議会 産業連携・地域支援部会 大学等知財検討作業部
会がとりまとめた「イノベーション創出に向けた大学等の知的財産の活用方策」(平成
26年3月5日)において、①大学等が保有する知的財産の集約・活用方策、②大学
等が保有する知的財産の活用方策と棚卸し、③大学等における知的財産に関わるリス
ク管理に関する取組の方向性について、提言がなされているところである。
(2)大学の知的財産マネジメントに関する現状
(大学知的財産マネジメントに関して、これまでの取組で実現したこと)
上記取組等を通じ、大学の産学官連携活動、知的財産活動に対する、否定的見解は縮
小し、社会的な受容性と期待感は高まったといえる。
また、我が国大学全体の特許出願件数が増加したこと、特許権実施等の対価やランニ
ングロイヤリティ収入が増加していること、各大学の知的財産関係規程やポリシーが整
備されたこと等を鑑みても、大学内での知的財産体制・システム構築が一定程度進展し
てきたと捉えられる。(参考資料 図表1~13:各種データ等)
(大学知的財産マネジメントに関して、これまでの取組で十分実現していないこと)
我が国大学の知的財産マネジメントについて、上記取組等を通じて、一定の成果があ
がってきているものの、イノベーション創出という視点でみた際、以下のような事項に
ついては十分に実現できておらず、更なる取組が必要である。
●産学官連携活動、知的財産マネジメント等に対する大学経営上の位置付けが高く
ない。
イノベーション創出に関する社会から大学への期待は非常に大きい一方で、各
大学の経営上の位置付けとして、産学官連携活動及び知的財産マネジメント活動等
は、教育及び研究等に比した優先順位が高められていない状況がある。そのため、
知的財産等への研究経営資源の配分(人材、予算等)は限定的になっており、大学
のイノベーション創出機能がポジティブなサイクルで廻っていない実情がある。
-10-

5
その点、イノベーション創出に向けた経営改革や財務基盤の強化を進め、我が
国の大学が世界に伍する大学へと変革していくために、長期的視野に立って、大学
全体の組織的な知的資産マネジメントの必要性が指摘されるところである4。
●大学発ベンチャー創出等を通じた大規模なイノベーション創出の成果は限定的で
ある。
これまでの産学官連携の取組について、本格的な連携や大規模なイノベーショ
ン創出に結実したものは決して多いとは言えない状況である(1件当たりの特許権
実施等収入や、1件あたりの共同研究金額は大きくないこと等からもそれがみてと
れる)。一方、大学が保有する基礎的・基盤的技術シーズを大規模なイノベーショ
ンに結実させていくためには、産学官連携活動が活発化した時期(1990年代後
半)からみても、さらに年月が必要であるとも指摘される。
これまで、我が国においては、共同研究の形態で、大学の技術シーズを社会に
価値提供することが試みられるケースが多く、大学発ベンチャーによるアプローチ
は限定的であり、大規模なイノベーションを実現している成果は限られている。そ
の点伸び代が十分あると見られることから、更なる可能性が見込まれる。この可能
性を後押しするに際して、大学発ベンチャーの起業と発展を目指すために必要不可
欠である単独特許の保有が、大学においては少数であることが課題であるとも考え
られている(我が国大学の単独特許の件数は大学出願件数全体の1/3程度と限ら
れており、共有特許が多くを占めている状況である。その点について、米国の状況
と比較すると顕著に異なり、米国では単独特許が多く、ベンチャー企業にも多く技
術移転が図られている状況である。)。
●事業化を意識した技術移転活動を実現している大学が限られている。
イノベーション創出に向けて、事業化を意識した積極的な技術移転活動が求め
られるが、マーケティングに基づいた技術移転活動を徹底している大学・TLOは
一部であり、大学の中に事業化視点での知的財産マネジメントが十分根差している
とはいえない。特に、発明創出の状況等に応じて、大学間での知的財産活動には種々
のレベル差がある。(参考資料 図表19:「大学特性を反映した一気通貫の知的財
産マネジメント」)
また、我が国においては、マネジメント人材が有期雇用であることが多いこと
にも起因し、技術移転に関するノウハウを、各大学が適切に保有、継承できていな
い可能性がある。
4 競争力強化に向けた大学知的資産マネジメント検討委員会報告書において、大学が有する研究経営資源
(知的資産)を、「人(研究人材等)」・「モノ(知的財産や研究インフラ等の固定資産等)」・「金(研究開発
投資の財源等)」としている。
-11-

6
●大学自身による自律的な知的財産マネジメントが実現できていない。
外国特許出願費用は、膨大なコストがかかるため、大学単独で出願する特許に
ついては、国の支援に依存している大学が多いのが実情である。予算面も含めた自
律的な知的財産マネジメントを実現している大学は限定的である。
また、会計検査院から、特許権の保有目的に留意しつつ、特許権の維持に要す
る費用の負担を軽減する観点から、保有する特許権の見直しを引き続き積極的に進
めていくことの必要性が指摘されているところである5。
●より一層強化した産学のパートナーシップが必要である。
イノベーション創出に向けた、産学のパートナーシップが十分でなく、依然と
して、共同研究締結時におけるいわゆる不実施補償6の問題等も指摘される。
(大学知的財産マネジメントに関する、最近の環境変化)
知的財産マネジメントは、企業活動の変化に伴い、特許出願による権利化を重視した
戦略から、最適な活用を図る戦略へと主流が変容してきており、以下に示すように環境
変化が生じてきている。
●ビジネスモデルの設計上、オープン&クローズ戦略が必要不可欠になってきてい
る。
オープン&クローズ戦略とは、ビジネス・エコシステム構造(企業等が互いに
繫がって、自社も他社も共に付加価値を増やすモデル)を前提に、独占するコア領
域をクローズ領域として設定し、コア領域とパートナーとがつながる結合領域を知
的財産等で保護した上で、パートナーに任せる領域であるオープン領域を公開して
いくことで、市場コントロールのメカニズムを構築する戦略である。我が国企業が
グローバル市場へ展開していくためには、ビジネス・エコシステムの中でビジネス
モデルを事前に設計していくことが必要不可欠であり、そのためにオープン&クロ 5 会計検査院「独立行政法人及び国立大学法人等の自己収入の確保等に向けた取組の状況についての報告
書」(平成27年12月)において、「特許権の保有目的に留意しつつ、特許権に係る事業化の拡大を図る
ことと併せて、取得した特許権について収入と比較して費用が多額であったり、事業化が見込めなかった
りする場合や、特許権の内容が陳腐化した場合等には、特許権の維持に要する費用の負担を軽減する観点
から、各法人において保有する特許権の見直しを引き続き積極的に進めていくことが必要である。」と指摘
されている。 6 不実施補償とは、「共同研究等により生ずる共有知財について大学等が知財を実施できない立場にある特
性に鑑み、企業が共有知財を実施することによって得た利益の一部を、大学等に対して支払う補償金」を
指す。「『日本再興戦略』改訂 2015-未来への投資・生産性革命-」(平成27年6月)において「大学と
企業間での共同研究契約について、共同研究の特許出願の形態・活用状況や、不実施補償を含めた契約の
実態を調査した上で、共同研究における特許出願と契約の在り方について検討し、その検討結果を踏まえ
て柔軟な契約締結を大学・企業に働きかける。」とされている。
-12-

7
ーズ戦略の思想が必要となる。(参考資料 図表14~17:「ビジネス・エコシス
テムの概念について」、「オープン&クローズ戦略について」、「オープン&クローズ
戦略と産学連携について」、「プログラム・マネジャー(PM)による産学官連携マ
ネジメント」)
その中で、大学の「知」を、企業の付加価値を長期に高めるメカニズムに位置
付けるという視点で、オープン&クローズ戦略に組み込んでいくことが必要不可欠
になってきている。
大学は、オープン&クローズ戦略といった、企業におけるビジネス戦略の高度
化に対応した知的財産マネジメントを十分に実行できていない可能性がある。
【産学官連携からみた企業側の知的財産マネジメント7】
●研究開発プロジェクトにおいて、オープン&クローズ戦略を意識した設計が必要
になってきている。
国は、各プレイヤー(企業、大学等)と連携しながら、我が国のあるべき将来
像をビジョンとして描き、技術領域を含めて基礎的・基盤的研究の方向付けを行う
とともに、期待される技術イノベーションの成果を、グローバル市場の競争優位性
7 産学官連携の成果をオープンにする態様は、様々な方法がある。例えば、複数者が関与したマルチラテ
ラルの連携のときは、第三者への利用も認めるケースがあるが、その中でも無償供与の場合は、参加して
共同研究開発に関与した企業にとって参加インセンティブが働きづらく、フリーライダーの競合を作り出
すことになるため、必ずしも望ましくない。また、当該ケースの中で、第三者にライセンスを行う場合、
例えば参加した企業の出口(ターゲット市場)と競合しない別の製品市場であるならば、企業側のインセ
ンティブも損なわれず、さらに、そのプロジェクトが構築するパテントプールの収入にもなるので、大学
が生み出す知がイノベーティブな産業創出に貢献し、更に参加するインセンティブを削ぐことも低くなる。
これらのことに留意は必要である。
-13-

8
及び雇用創出に結びつけていく仕組みを、研究開発投資を行う段階から構築しなけ
ればならない状況になってきている。
その中で、日本版バイ・ドール規定が適用される案件についても、国際競争力
という視点でオープン&クローズ戦略を意識して、各研究開発プロジェクトの知的
財産方針を策定することが求められる。
●大学の研究形態の発展を背景に、大学知的財産マネジメントの新しいフレームワ
ークを開発・運用する必要性が高くなってきている。
現在、複数機関が参画する組織的研究(コンソーシアム型の研究等)を実施
することが拡大しており、研究形態が多様化・高度化してきている中で、創出され
る知的財産の扱い等について、複数機関をまたぐ合意・運用等が必要となってきて
いる。また、そのようなコンソーシアム型研究を大学が主導して推進していくこと
が、より一層必要になってくるところであり、大学の研究形態の発展を背景に、大
学における知的財産マネジメントの新しいフレームワークを開発・運用する必要性
が高くなってきている。
(3)大学の知的財産マネジメントに関する主な課題
上記「(2)大学知的財産マネジメントに関する現状」に記載の「大学知的財産マネ
ジメントに関して、これまでの取組で十分実現していないこと」、「大学知的財産マネジ
メントに関する、最近の環境変化」等の状況を踏まえて、大学における知的財産マネジ
メントの具体的な課題を検討する。
○ 我が国の科学技術イノベーション政策の方向性について、第5期科学技術基本計画
(平成28年1月22日閣議決定)において、「企業や大学等が保有する知的財産の
価値を最大化するため、各主体の知的財産や標準化に対する意識を高めるとともに、
それぞれが連携して特許等を活用することで、新たなオープンイノベーションが創
出されるよう促す。」、「大学の知的財産の活用を促進するためには、大学自身が知的
財産戦略を策定しそれに応じて自律的な知的財産マネジメントを行うことが重要で
あり、国はそれを促す。このような取組を通じ、大学の特許権実施許諾件数が第5
期基本計画期間中に5割増加となることを目指す。」ということが示されている。
また、知的財産推進計画2015において、「大学自身の知財戦略策定及び自立的
な知財マネジメントの実行を各大学に促すため、知財戦略に沿って精選し絞り込ん
だ知財の権利化活動や知的財産の事業化プランに基づく技術移転活動の状況等を評
価して、外国出願等の大学の知財活動を支援する。」とされており、大学自身の知的
-14-

9
財産戦略策定及び知的財産マネジメントの実行の促進に向けた方向性が示されてい
る。
○ このような方向性や、大学の知的財産マネジメントに関する現状等も踏まえると、
大学における知的財産マネジメントの具体的な課題は、次のように捉えられる。
・大学経営レベルで、知的財産マネジメントの意義や必要性を捉えられていないこ
と。
・各大学に求められる知的財産マネジメントの高度化に対応する形で、学内の知的
財産予算の措置、知的財産関係人材の配置が十分になされていないこと。
・各大学の予算的な課題に起因して外国への出願件数・外国における権利化が十分
になされず、国内の権利だけが多く発生することになり、国内(企業)の実施の
みがその影響を受ける事態が生じること。
・大学発ベンチャー創出を促進するという観点等からみて、大学が単独で保有する
特許権の件数は限定的であること。
・我が国においては共有で保有する特許権が多い実態がある一方で、そのような共
有特許権を、効果的に活用する方策を十分に検討できていないこと。
・知的財産活用の促進に向けて、事業化視点での知的財産マネジメントの促進が必
要であること。また、企業におけるオープン&クローズ戦略への対応が十分にな
されていないこと。
・産業界側との対等なパートナーシップが構築できていないことにも起因し、共同
研究成果の取扱いにおいても、交渉が円滑に進まないケースもあること。
・我が国の国際競争力という視点でオープン&クローズ戦略を意識して、各研究開
発プロジェクトの知的財産方針を検討していくことが求められている一方で、国、
ファンディング・エージェンシーといったプロジェクト委託者側、及び企業・大
学等の受託者側の各機関に、その意識が希薄であること。
-15-

10
3.イノベーション創出視点での大学の知的財産マネジメントの意義と
基本的方向性
(全体的方向性)
・知的財産は、技術シーズを実用化し、イノベーション創出を図るために必要不可欠
なツールであるところ、各大学は、イノベーション創出に結実していくために、知
的財産の活用方策を意識して適切な形でマネジメントする必要。
・各大学は、知的財産の大学経営上の取得・活用意義を明確にし、大学経営レベルで
知的財産マネジメントを捉える必要。
「社会実装、雇用創出」といったイノベーション創出機能に関して、特定の技術課題
の解決だけでなく、新産業の創出も含めて、大学が保有する技術シーズの社会実装・事
業化等を実現し、革新的なイノベーションを連続的に起こしていくことが必要となって
きており、大学に対する期待は高くなってきている。
そのためには、大学で生み出された先端的な技術を使った製品を、単に実用化するだ
けでなく、企業の付加価値を長期に高める仕組みを検討する等して、これまでのメカニ
ズムを再構築しなければならない。大学においても、期待される技術イノベーションの
成果をグローバル市場の競争優位性、雇用創出に結びつけていく仕組みを考え、社会実
装を試みることが重要であり、オープン&クローズ戦略に対応したマネジメントの実行
が重要である。そして、企業がオープン&クローズ戦略を踏まえて事業展開していく際
に、知的財産は必要不可欠なツールである。
その一方で、知的財産権(特許権等の権利)を出願・登録することは、多大なコスト
を伴うことであるので、活用を十分に意識した戦略的な知的財産保護が、企業側では図
られている。大学についてみると、特許権保有件数が年々増加しており、特許権等に係
る収支(実施許諾等による収入と特許出願等に要する費用の差)の面からも、保有の在
り方に関する検討の必要性が提起されている8。
そのような中で、自身でビジネスを行わない大学が知的財産権を取得・活用していく
意義について改めて確認することは、大学経営として知的財産マネジメントの位置付け
を考えていく上でも非常に重要なことである。
(1)イノベーション創出視点で大学が知的財産権を保有する意義
○ イノベーション創出を目指して、大学が社会に価値を提供していくために取り得る
方策は多様なものがある(例えば、共同研究・受託研究、知的財産の譲渡、知的財産
8 会計検査院「独立行政法人及び国立大学法人等の自己収入の確保等に向けた取組の状況についての報告
書」(平成27年12月)を参照。
-16-

11
のライセンス、大学発ベンチャー創業等)。
産学官連携の形態として、我が国においては歴史的にも共同研究の形態が代表的に
取り組まれてきたところであるが、ベンチャー企業等を通じて社会実装を目指す方策
も、イノベーション創出効果が大きいことが指摘される。また、大学の技術シーズを
一企業で独占的に活用するという方策だけでなく、多様な企業と連携して社会実装を
試みる方策(非競争領域での共同研究等)も選択される。
各大学が保有する知的資産をどのように活かし、どのような方策によってイノベー
ション創出に結実していくかは、各大学が戦略性を持って選択・実行していく必要が
ある。その際に、大学は、オープン&クローズ戦略を意識し、どのように事業化して
いくかというビジネスモデルを検討することが期待されている。
【事業化視点での社会への価値提供方策】
○ 研究成果の取扱いが発明者個人の帰属であったとき、次のような懸念が考えられる
ところであった9。すなわち、①科学技術振興への国費の投入の成果としての特許が、
事実上研究者個人に帰属することが、納税者に対する説明責任上望ましくないと考え
られること、②国費投入の帰結である研究成果が、知的財産権化せずにパブリックド
メインに公表されるのみとなることが多くなり、外国への技術流出につながり得るこ
と、③国費投入の帰結である研究成果が、実用化に至らず追加の研究開発が必要とな
った場合、大学機関が適切に行う特許権等のライセンスを行うことが企業の追加投資
のインセンティブとなり、研究成果の社会還元が促進されるはずであるが、個人帰属
9 渡部俊也「イノベーターの知財マネジメント『技術の生まれる瞬間』から『オープンイノベーションの
収益化』まで」から引用。
-17-

12
とすることでそれが阻まれること等の懸念である。
そのような懸念に加え、教育・研究に続く第三の使命として社会貢献(教育・研究
成果の社会への提供)が大学に強く求められるようになってきた背景のもとで、我が
国においては、大学で創出された発明に関する権利帰属を、個人帰属から原則大学帰
属とすることが図られてきた経緯がある10。
○ 大学が産業界との連携を強化し、社会に価値を提供していく際に、特許権等の「知
的財産権」は、大学の技術シーズをイノベーション創出に結実させていくために必要
不可欠なツールであり、大学は活用方策に合わせて適切に保有すべきである。上述の
ような背景も含めて、大学が知的財産権を保有する意義は、以下のとおり多様な側面
から捉えられる11。
1つ目として、産業界での実用化を促すという意義がある。大学の技術シーズを社
会実装に結実していく方策には、大学発ベンチャーの創出や、知的財産のライセンス
といった種々の方策があるが、ビジネスを行う上で知的財産権による権利保護は必要
不可欠となる。
また、2つ目として、共同研究の実施といった産と学の連携を促進するという意義
がある。企業側にとって、技術シーズが知的財産権によって適切に保護されているこ
とが、事業化可能性に大きな影響を与えるところである。そのため、企業側が共同研
究の開始を検討する際にも、大学が保有する技術シーズが知的財産権によって適切に
保護されているか否かは、非常に重要視されることである。
3つ目として、研究成果を適切に保護するという意義がある。例えば、自機関の研
究を適切に実施する環境を整備する効果や、我が国の国費を投じた研究成果に対する
ただ乗り(フリーライド)を防止する効果等がある。(参考資料 図表26:「iPS
細胞技術に関する知的財産マネジメント」)
産学官連携活動における、知的財産権取得の副次的なものとして、実施許諾収入を
獲得することができるという意義・効果がある。
そのほかに、知的財産マネジメント活動を通じて、研究者に対する事業化関連の意
識向上が図られるといった、知的財産に関する普及啓発効果も、知的財産権の保有に
関連する効果として期待される。
大学によっては競争的資金の獲得を目的として特許出願するケースも存在すると
考えられる。しかし、イノベーション創出視点でみた知的財産権の本来の保有目的か
らとらえても、このような知的財産活動は必ずしも推奨されることではない。国の各
種評価において、特許出願を指標として用いる際には、知的財産権の件数のみに依存
10 科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会 知的財産ワーキング・グループ報
告書(平成14年11月)参照。 11 特許庁 平成20年度大学知財研究推進事業 「大学における研究成果と特許の質の関係に関する研究」
等も参考に、文部科学省で整理。
-18-

13
するような評価にならないよう、十分に配慮する必要がある。
【イノベーション創出視点で大学が知的財産権を保有する意義】
○ 大学が保有する知的財産権の活用効果を、特許権等に係る収支といった部分的な捉
え方で評価することは必ずしも適切ではなく、イノベーション創出効果や大学経営全
体への寄与度合い等で総合的に評価することが重要である。
特に、基礎的研究段階の技術シーズは、事業化までの不確実性が高く、出願・権利
化判断も非常に難しい側面がある。その中で、大学が特許権等に係る収支を短期的な
視点で追求する余り、本来保護すべき技術シーズの知的財産権化が適切になされず、
我が国全体のイノベーション創出が阻害されることは避けなければならない。
(2)大学経営視点からみた知的財産マネジメント
○ 現在、複数機関(複数の大学、企業等)が参画する組織的な共同研究(コンソーシ
アム型の共同研究等)を実施することが拡大しており、研究形態が多様化・高度化し
てきている(例えば、センター・オブ・イノベーション(COI)プログラムの実施
等)。そのような中で、創出される知的財産の扱い等について、複数機関をまたぐ合
意・運用等が必要となってきている。また、そのようなコンソーシアム型研究を大学
が主導して推進していくことも、より一層必要になってくるところであり、大学の研
究形態の発展を背景に、大学における知的財産マネジメントの新しいフレームワーク
を開発・運用する必要性が高くなってきている12。
コンソーシアム型共同研究を推進していくとき、機関毎に知的財産に対する方針や
必要な条件等が異なる。そのため、大学が知的財産フレームワークを適切に実行する
には、従来の大学知的財産マネジメントに求められる内容よりも大幅にレベルが高い、
専門的で柔軟性のある高度なレベルのマネジメントが求められる。具体的には、知的
財産と契約に関する専門性以外にも、研究成果の市場性や経済的価値といった事業理
12 フレームワークとして、例えば、①知的財産の帰属、②出願可否判断の手続、③知的財産権の取得手続、
④発明者ではない研究参画者の実施権、⑤実施許諾や譲渡等の権利活用等、⑥以上を運営する組織体制、
⑦研究開発プロジェクト終了後の権利維持管理等が挙げられる。これら事項に関する契約書締結、運用規
程の策定、発明委員会などの知的財産体制の運用が必要となる。
-19-

14
解、参画する企業・大学と折衝する調整・交渉機能(コミュニケーション力)等が必
要である。さらに大学側には利益相反や営業秘密管理等のリスクマネジメントも必要
になる。これらを実施する総合的なマネジメント力が大学に求められるようになって
きている。(参考資料 図表24:「プロジェクト形態別の契約事例」)
○ 産学官連携活動(共同研究・受託研究、ライセンス等の技術移転、ベンチャー創出
等の多様な連携を包含する)を、大学が行う目的には、
・「社会実装、雇用創出」
・「教育・研究の促進」
・「外部資金の獲得(ロイヤリティ収入、共同研究費等)」
といった点がある。これら目的の達成を通じて、社会・地域からの大学に対する評価
につながっていくことや、また、研究者の研究・発明創出モチベーションにつながっ
ていくことが期待されるところであり、少なくとも、企業等からの外部資金の獲得が
産学官連携の目的の全てではない。
○ 我が国の大学が、イノベーション創出に向けた経営改革や財務基盤の強化を進め、
世界に伍する大学へと変革してくためには、各大学保有の研究経営資源(知的資産)
を、いかに効果的にマネジメントしていくかが重要となってくる。そのような大学知
的資産マネジメントは、大学の価値を高め、大学自身の成長につながるものであるの
で、大学の研究経営上も重要な位置付けであることを、各大学が認識すべきである。
(参考資料 図表25:「近畿大学における産学官連携の広報・評価の取組事例」)
その中で、知的財産マネジメントは、産学官連携活動に関係する多様なマネジメン
ト要素と連動して総合的に判断すべきマネジメント要素である。大学は、知的財産マ
ネジメントを、部分的マネジメントとして実行するのではなく(例えば、特許権等の
実施許諾収入の向上のみを目指すべきではなく)、産学官連携活動や研究経営の強化
に向けて、総合的なマネジメントとして実行していく必要がある。
-20-

15
【産学官連携活動に関係する多様なマネジメント要素の例】
○ 各大学が、知的財産マジメントを大学経営レベルで捉えて、知的財産を保有する意
義・活用方策等の実効的なポリシーを明確にし、戦略的かつ総合的に知的財産マネジ
メントを実行していくことが重要である。
(3)大学の知的財産マネジメントに関する検討の方向
○ イノベーション・エコシステムの中で、各プレイヤーが最大限に活躍し、大学の技
術シーズが継続的なイノベーション創出に結実していくよう、社会全体の中で知と資
金がポジティブなサイクルで循環していくためのシステム構築がなされると同時に、
大学の成長が図られていくことが重要である。
○ それを具現化するためには、大学の知的財産マネジメントの高度化(戦略的方針の
設定と、体制・システムの強化等)を図ることが重要である。
また、我が国競争力強化に向けて、各研究開発プロジェクトにおける知的財産方針
を明確に定めることが重要であり、大学においてもそれを踏まえた知的財産マネジメ
ントを実行していくことが重要である。
-21-

16
さらに、企業の知的財産戦略を踏まえた大学知的財産マネジメントの実行が重要で
ある。産学双方のパートナーシップを強化するとともに、非競争領域における産学官
連携といった新たな枠組みの中でも実効的な知的財産マネジメントを進めていく必
要がある。
【大学の知的財産戦略と他の戦略との関係】
(4)国に期待される取組の方向性
○ 大学自身が知的財産戦略を策定し、それに応じた自律的な知的財産マネジメントを
実行していくことを目指して、国は大学をサポートしていくことが重要である。
ただし、大学内での知的財産マネジメントを改革していくことは、大学経営の一環
としての変革を伴うことであるので、一朝一夕に進展することではない。国は、それ
を十分に勘案し、大学自身の組織変革を前提にしつつも、イノベーション創出が阻害
されない形で、段階的に支援の在り方を変化させていく必要がある。
○ 各大学の規模、特性等によって、知的財産マネジメントを取り巻く状況・環境は大
きく異なる。国は、各大学の知的財産マネジメントレベルや状況に対応した段階的な
サポートの在り方を検討する必要がある。
イノベーション創出を通じた我が国の産業競争力強化
大学の知財戦略
大学経営層研究者学生
マネジメントスタッフ
各研究開発
プロジェクトの知財方針
(国の戦略等)
企業の知財戦略
大企業中小企業
ベンチャー企業
<主な関係プレイヤー>技術移転機関(TLO) 金融機関ベンチャー・キャピタル 地方自治体インキュベーター 公的研究機関
-22-

17
○ 産学官連携活動を促進し、大学の技術シーズをイノベーション創出に結実させてい
くことが重要である。国は、それを実現するための環境整備を進め、必要に応じて制
度の見直しを図っていくことが期待される。
-23-

18
4.大学の知的財産マネジメントの高度化
4-1 大学知的財産マネジメントの戦略的方針
(全体的方向性)
・各大学が、大学経営の観点から「知的財産戦略」を策定することが必要。
・大学が、イノベーション創出に向けた知的財産活用の方向性に合わせて、大学が単
独で保有する特許権を強化するとともに、共有特許権も含めた知的財産権の活用方
策を適切に選択する知的財産マネジメントを実行することが必要。
・大学が、産学官連携活動や知的財産マネジメントの成果を、イノベーション創出や
事業化の視点で評価することが必要。
知的財産マネジメントの強化は、大学が社会へ価値提供する機能の強化につながり、
イノベーション創出の実現可能性を強化することとともに、大学の価値向上につながっ
ていく。その意味で、知的財産マネジメントを、大学経営の一環として推進していくこ
とが必要不可欠である。
組織的な知的財産の新しいフレームワークの設計・運用を含め、事業化視点での知的
財産マネジメント(戦略性ある契約マネジメントや、徹底したマーケティングの実施、
事業プロデュース、リスクマネジメント等を含めた総合的なマネジメント)を実行する
ことが重要となってきており、求められるマネジメントは高度化してきている。
そのような状況を踏まえ、大学が目指していくべき知的財産マネジメントの戦略的方
針について、以下で検討する。
(1)社会への価値提供方策に合わせた大学知的財産マネジメントの必要性
○ 各大学は、大学経営の観点から「知的財産戦略」を策定すべきである。必要に応じ
て、知的財産権の取得を重点的に行う技術分野を設定することも有効である。
<大学が策定すべき知的財産戦略の項目例>
・大学経営としての知的財産の位置付け
・研究領域に応じた知的財産マネジメント予算の策定
・活用を意識した知的財産マネジメント体制の構築
・知的財産の取得を重点的に行う技術分野の設定
○ 大学においては、多様な技術分野、多様な研究フェーズで研究成果が生み出されて
いるが、その全てを知的財産権として権利化して保護することは現実的に困難である。
大学が組織として、活用可能性等を十分に勘案し、知的財産戦略を検討して、それに
-24-

19
沿って選択と集中を図る等、厳選した権利取得を行っていくことが重要である。特許
群として複数の権利で技術を保護すること等によって、事業化に資する権利保護を図
ることが望ましい。また、企業活動のグローバル化にも合わせて、取得する知的財産
権については、日本国内だけでなく外国での権利取得も検討することが重要である。
(参考資料 図表30:「岡山大学における少数精鋭の基本特許管理の事例」)
○ 技術シーズを社会に価値提供していく方策は、権利化等をしてから事後的に検討す
るのではなく、研究段階から早期に検討し、それに合わせた知的財産マネジメントを
実行し得る基本的方針が必要である。各技術シーズに対する企業のニーズや事業化ま
での見通し状況も含めて、特許権等の取得意義を明確化するとともに(例えば、大学
発ベンチャー創業を目指している場合、事業化実現までの年数はかかるものの、単独
特許権の取得が必要であること等)、特許権等を確実に実用化に発展させていくため
の活動を実行することが重要である。社会に価値提供していく種々の方策毎の知的財
産マネジメントについて、例えば、以下に記載するような事項に留意しつつ、活用方
策を検討していく必要があると考えられる。
<大学発ベンチャー>
○ 大学が主導してイノベーションを創出していくためには、事業化のコアとなり得
るような大学創出の研究成果を、大学単独の特許権として保有することが重要であ
る。特に、大学発ベンチャーを創出することを想定した場合は、独占的実施が重要
となるため、大学保有の単独特許が必要不可欠である13。しかし、大学組織が、技術
シーズの短期的な事業化(ライセンス等)の視点のみで評価する余り、ベンチャー
起業を志向する技術シーズの特許出願・登録が阻害されるというケース(すなわち、
大学として権利承継しないと判断されるケース)も生じているところである。各大
学は、大学発ベンチャーの創出も含めて、各研究シーズをどのように社会実装して
いくかといった方策・ビジョンを可能な限り明確にし、それに合わせて基礎的な段
階の研究シーズの特許権化を適切に行うことが重要である。(参考資料 図表27:
「ペプチドリームに関連する知的財産マネジメントの事例」)
その際に、ベンチャー・キャピタル(VC)等が研究開発の段階から関与し、事
業化視点で研究開発プロジェクトや知的財産マネジメントを推進し、適切な権利保
護を図っていくことが有効である。(参考資料 図表28:「大学発新産業創出プログ
13 東京大学政策ビジョン研究センター 大学と社会研究ユニット政策提言 「知的財産制度と産学連携に関
する論点」(平成27年3月)において、「ベンチャー創業に当たっては、基礎技術から単独特許出願がな
されて排他的な権利を獲得していることが重要であるが、現在の日本の大学の出願傾向からは、このよう
な状態を作り出すのが難しい可能性がある。ベンチャー企業によりインパクトのある特許を供給するため
には、少なくともベンチャー企業向けのパイオニア発明単独特許は、大企業との共有を避けるか、共有と
なった場合にもベンチャー企業へライセンスされることが可能な契約にするための施策が必要であるもの
と思われる。」と指摘されている。
-25-

20
ラム(START)の取組事例」)
<ライセンス>
○ 知的財産権をライセンス等によって社会実装に結びつけていくためには、マーケテ
ィングとセールス活動を適切に実行し、事業化視点で知的財産マネジメントを実践す
ることが必要である。また、大学独自の研究シーズ(基礎的研究、学術研究等の成果)
を、産業界に魅力的な形(事業化に資する権利範囲、出願国の選択等が適切な形)で
権利化していくことも重要であるが、その実現も徹底したマーケティングによって可
能となることである。それに関する具体的な体制・システム強化について、本報告書
4-2「大学知的財産マネジメントの体制・システム強化」で具体的に検討する。
<譲渡>
○ 我が国の大学が保有する共有特許権等が増加し、大学における管理負担も無視でき
ない状況であることを踏まえると、保有している共有特許権の大学側・企業側の活用
方針等を適切に判断し、一方の権利者に譲渡することも一選択肢として検討すべきで
ある。
ただし、譲渡を行う場合、我が国の公的資金を投入して得られた研究成果(知的財
産権)が譲渡されることが、プロジェクト全体の成果への悪影響につながらないこと
や、我が国の国際競争力強化の阻害につながらないことを十分に確認する必要がある。
大学自身が、我が国の経済成長を実現していくためのプレイヤーとして期待されてい
るという自覚を持って、知的財産マネジメントをすべきである。
なお、科学技術・学術審議会 産業連携・地域支援部会 大学等知財検討作業部会に
おいてとりまとめられた「イノベーション創出に向けた大学等の知的財産の活用方策」
(平成26年3月)14 において指摘されているように、知的財産権の譲渡(出願前譲
渡も含む)を行う際には、各大学の適切な判断が求められるところである。特に、大
学から創出された発明に関する特許権が、意図せずとも特許主張主体(Patent
Assertion Entity:PAE)に移転された場合、社会から大学に対する批判が生じる
おそれがあることを、大学は十分に理解する必要がある。
また、発明・権利の創出に関与する複数の要素のうち、人件費については公的資金
(特に、国立大学の場合は運営費交付金)が使用されることが多いことから、譲渡対
価や独占的ライセンスの対価においては、社会的説明等のリスクヘッジをはらうこと
も考慮しておく必要がある。さらに、譲渡することによって譲渡相手先以外との共同
研究が行えなくなる等、研究におけるリスクが将来的に発生することも研究者に対し
14 本報告書において、「大学等が知的財産権を、自ら事業をせず他の事業者に対し法外な対価を要求して
権利行使することを専ら業とする者等へ譲渡することは産業の正常な発展の阻害につながる恐れがあり、
大学等はそうした者等に知的財産権を譲渡することは原則避けるべきである。」として報告がとりまとめら
れている。
-26-

21
て周知徹底することも必要である。
<共同研究・受託研究>
○ 共同研究を行う際にも、1対1の個別共同研究(競争領域における共同研究)だ
けでなく、複数機関が関与した非競争領域における共同研究等、多様な連携の方策
が生まれてきている。今後、研究者個人にとどまらず、大学組織も一体となって取
り組むような大規模な共同研究等がますます重要になってくる。
また、いわゆる不実施補償の問題等による産業界側と大学側との摩擦を可能な限
り少なくすることで、社会実装の加速化や実施許諾収入の獲得にスムーズに結びつ
ける方策を検討し、大規模な共同研究を通じてイノベーション創出を図ることが重
要である。共同研究成果の取扱い等について、6章「産業界側の知的財産戦略と大
学の知的財産マネジメント」で検討する。(参考資料 図表29:「光触媒プロジェク
トに関連するマネジメント事例」)
(2)知的財産マネジメントに関連する多様な観点と方向性
○ 大学の知的財産(技術シーズも含む)の意義・効果を評価するためには、社会の中
で大学の知的財産がどのように活かされているかを見える化し、各大学が情報発信等
のアウトリーチ活動を行うことが重要である。また、産学官連携の成果は、製品化や
イノベーション実現に基づいて測られることが重要であり、そのため、特許権が実施
許諾収入に結びついているケースだけでなく、製品売上に基づく特許権の実施許諾料
支払を契約上企業に求めていないが製品化に成功しているケースや、特許権が共同研
究等(場合によっては、国の委託研究開発等)に活用されてイノベーション創出を目
指しているケース、企業のクロスライセンス等に活用されているケースについても、
各大学がその実態を定量的に捉えることが重要であると考えられる。大学が実態把握
をしていくことの実現方法を、大学側と産業界側の対話によって検討していく必要が
ある。(参考資料 図表25:「近畿大学における産学官連携の広報・評価の取組事例」)
○ 研究成果を論文という形態で迅速に公開していくことも、大学の役割として非常に
重要であるので、研究成果の論文公表を迅速かつ適切に行うことを可能とする知的財
産マネジメントシステム(迅速な出願判断を行えるシステム)を、各大学が構築する
必要がある15。また、論文公表を迅速に行うために、米国の仮出願制度を活用してい
る大学もある。(参考資料 図表31:「沖縄科学技術大学院大学の特許出願スキーム」)
15 これにも関連する点について、環太平洋パートナーシップ(TPP)協定の締結により、我が国の知的
財産制度において、グレースピリオドの期間(発明の新規性を喪失した場合でも、所定の条件において喪
失しなかったこととみなす新規性喪失の例外期間)を6か月から1年へ延長されることについて、必要な
措置を講ずるものとされている。なお、欧州の知的財産制度はこれと異なる点には留意が必要である。
-27-

22
各研究成果の知的財産の権利化要否を適切に判断した結果として、特許権等の取得
を行わずに、あえて論文公表化する戦略も時として有益である。論文公表をすること
で、長期的ビジョンで成長させていく必要がある技術シーズを、誰でも使い得る環境
とすることで、知的財産の実用化を早めていくという方針が取られることもある。
○ 企業の事業戦略として、オープン&クローズ戦略の一環で秘匿化を戦略的に行う必
要性が指摘されているところ、産学官連携の成果の取扱いとして秘匿化が企業側から
望まれるケースもより一層多くなっていくと考えられる。
大学の役割として、研究成果を広く公開していくことで、社会に価値を提供してい
くことが従来から大学に期待されているが、本格的な産学官連携を促進し、企業との
連携を強化していく中で、共同研究成果を大学が秘匿化していくといった、論文公表
等のオープンに開かれた形態以外での社会への価値提供態様の必要性も指摘される
ところである。形式知を秘匿化していく際には、論文公表すべき範囲と、敢えて論文
公表する必要がなく秘匿化が可能な範囲とを線引きして、大学の使命・役割と整合す
る研究成果の取扱いを検討していくことが重要である。また、秘密保持契約の遵守と
いう観点からも、大学は技術流出防止のためのリスクマネジメントを強化すべきであ
る16。さらに、大学における研究活動に関連した新たなフレームワーク等(例えば、
クロスアポイントメント制度、技術組合を利用した兼業等)を活用して、大学の研究
成果から発展した領域の一部を秘匿化してビジネスに活かすことも考えられる。
○ さらに、ビッグデータ等への注目から、データの活用が一層進展していく中で、大
学においても特許権以外の多様な知的財産(データ、著作権、ノウハウ等)を積極的
に活用しようとする動きもあるところ、これら多様な知的財産の活用方針とマネジメ
ントの在り方について、検討する必要性が指摘されている。(参考資料 図表32~3
4:「大阪大学における臨床試験データの移転スキーム」、「東京医科歯科大学におけ
る学術指導契約制度の導入」、「電気通信大学におけるソフトウェアライセンス実用化
事例」)
データの活用について、現時点では、産業界側のトレンドを中心に国において検討
が進められているところであるが、経済産業省「データに関する取引の推進を目的と
した契約ガイドライン」(平成27年10月)や、各種審議会等の検討結果、オープ
ンサイエンスの方向性等17も踏まえて、必要に応じて、大学に特有の課題等について、
16 大学における技術流出防止マネジメント(営業秘密管理等)の取組課題について、科学技術・学術審議
会 産業連携・地域支援部会 大学等における産学官連携リスクマネジメント検討委員会「大学等における
産学官連携活動の推進に伴うリスクマネジメントの在り方に関する検討の方向性について」(平成27年7
月)を参照のこと。 17 内閣府「国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会報告書」(平成27年3月)におい
て、オープンサイエンス推進に際し、「データへのアクセスやデータの利用には、個人のプライバシー保護、
財産的価値のある成果物の保護の観点から制限事項を設ける必要がある。」と言及されている。
-28-

23
国が検討していくことも必要であると考えられる。
○ 著作物については、文理を問わず日常的に創作されていること、多くの大学で個人
帰属として取り扱っていること、研究者にも個人でハンドリングする権利としての意
識が浸透していること、社会にも公的なものという意識・誤解が多いと考えられるこ
と等の理由から、特に産学官連携の経験が少ない研究者を中心に、著作物が無償また
は不十分な対価で学外へ提供され、産学官連携や知的財産にかかわる部署もそれを把
握できていないケースが少なくない。さらにプログラム著作権については、職務発明
と同じような取り扱いが必要なケースにも配慮する必要がある。産学官連携リスクマ
ネジメントの観点からも、大学の著作権に係る適切なマネジメントを検討していくこ
とは重要である。
○ なお、職務発明制度(特許法第35条)の改正に伴う、大学への影響等については、
科学技術・学術審議会 産業連携・地域支援部会 大学等における産学官連携リスク
マネジメント検討委員会において検討が進められているところである。
(3)国に期待される取組
○ 国は、大学に対して出願支援等を実施する際に、各大学自身が戦略立案・知的財産
活用方針を策定することや、技術移転活動を積極的に行うこと等を要件化していく
ことで、大学全体の知的財産マネジメントの高度化・自律化を促していくことが重
要である。
○ 国は、産学官連携活動の状況や知的財産マネジメントの状況を適切に評価すること
が重要である。例えば特許出願件数等の外形的評価ではなく、イノベーション創出や
事業化の視点での評価(例えば、製品化の状況等に基づく評価)が必要である。特に、
これまでに国が検討してきた評価指標18も活用しつつ、大学が創出したイノベーショ
ン創出効果の定量評価の必要性を産業界側から理解を得ながら、適切に評価し得る環
境の醸成を国がサポートすることが望まれる。なお、共有特許についても、その保有
意義と効果を検討・分析していくために、各大学は実施状況(実用化状況)を適切に
把握する必要がある。
18 平成24年度産業技術調査事業 産学連携機能の総合的評価に関する調査において、経済産業省・文部
科学省が共同で、イノベーションの促進に果たす役割やパフォーマンス評価を目的とした評価の枠組みを
検討してきたところである(ただし、データ取得が難しい観点も存在したところである)。また、経済産業
省において、平成25~26年度産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業(システム構築・運営実証事
業)等を通じて、各大学等の産学連携活動の状況を評価指標によって評価(可視化)した結果を大学等間
で比較可能とし、それを各大学等において産学連携活動のマネジメント改善を図ることを促進する取り組
みを行っている。
-29-

24
4-2 大学知的財産マネジメントの体制・システム強化
(全体的方向性)
・各大学は、産学官連携活動、知的財産活用に関するポリシーに即して、知的財産予
算を適切に措置するとともに、間接経費を知的財産マネジメント経費として適切に
活用することが必要。
・各大学が、概念実証(POC)を行うための仕組みを構築することが必要。
・各大学が、企業のオープン&クローズ戦略に対応して、事業化視点での一気通貫の
知的財産マネジメント19を実現し得る体制を構築することが必要。
【各研究に関する大学の研究マネジメントと知的財産マネジメントのフロー20】
知的財産権の取得及び維持にはコストを要するところ、支出抑制を含めたコスト意識
を持つことが必要不可欠である。
その一方で、イノベーション創出には、研究活動の実施に合わせて、知的財産の取得・
19 事業化実現を目指してマーケティングモデル(発明創出時点等の早期のタイミングで、企業等に打診し
てニーズ把握するようなプレマーケティングを行い、企業ニーズに合わせた強い知的財産権の取得・活用
をすすめていくモデル)を実践し、研究開始・知的財産の創出から技術移転までの一連の業務が適切に連
動した一気通貫の知的財産マネジメントのことを意味する。 20 知財マネジメント等のフローは、経済産業省「知財人材スキル標準」、文部科学省平成25年度科学技
術人材養成等委託事業「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備(スキル標準
の作成)」成果報告書、特許庁平成26年度産業財産権制度問題調査研究報告書「技術・知的財産を活用し
た事業化のための目利き機能に関する調査研究報告書」等を基に、文部科学省作成。
-30-

25
活用等の活動を積極的に行い、産業界で社会実装を図っていくことが必要となる。その
ため、大学経営上の投資的な視点で知的財産マネジメントへ戦略的資源配分(特に、予
算と人材の配分)を行うことも重要である。
知的財産権が社会実装に結実していくことは、実施許諾収入等の収入面だけでなく、
他の側面からも評価され、大学の成長に確実に結実していくことである。大学の成長の
原動力に資するか否かという中長期的な視点も持って、大学経営上の知的財産マネジメ
ントのポリシー・方針を定め、研究経営資源の適切な配分を決定する必要がある。
(1)知的財産予算に係る大学が目指すべき方向性
○ 産学官連携を加速し、研究成果をイノベーション創出に結実させていく上では、知
的財産権の取得・活用は必要不可欠であるところ、各大学における知的財産関連予算
の適切な確保は喫緊の課題である。財源が厳しい中で知的財産権の取得等に予算措置
するためには、各大学のポリシーに沿って知的財産権を取得する意義と効果を、各大
学自身が明確にし、学長・理事等を含めて学内での理解を得ることが重要である。ま
た、各大学の保有する知的資産や研究状況等(例えば、研究分野等)から創出が予想
される発明等の件数を予測し、必要な予算額をあらかじめ試算していくことが重要で
ある。そのためにも、各大学における研究状況等を把握した上での知的財産マネジメ
ントを実行していくことが望ましい。(参考資料 図表35、36:「知的財産関連の
財源確保の事例」)、「東京大学における知財戦略の策定、特許費用算出の基本的考え
方」)
○ 各大学の知的財産関連予算の財源として、運営費交付金等の機関運営経費からの支
出が多くを占めており、研究費の間接経費からの支出は限定的であるのが実情である。
しかし、各大学は公的な研究費の配分を受けて研究を実施しているところ、我が国研
究成果が適切に保護・活用されていくためには、各大学が間接経費を知的財産マネジ
メント経費として適切に活用していくことが重要である。間接経費の所定割合を、知
的財産関連経費として設定して運用することも効果的である。
また、公的な研究費の受託が終了した後に、適切に権利維持するための予算措置も
重要である。なお、直接経費での特許出願等が可能であるプロジェクトにおいては、
大学は、プロジェクト終了後の予算計画を、委託者側(国、ファンディング・エージ
ェンシー等)や、プログラムオフィサーといったプロジェクト推進主体等と一体とな
ってあらかじめ検討しておくことが特に重要である。
○ 短期的なライセンス可能性を重視する余り、中長期的視野でとらえるべき基礎的研
究の成果が保護されないことは、我が国全体のイノベーション創出効果でみたときに
-31-

26
必ずしも望ましい状況とは言えない。各大学においては、中長期的な視野で育成すべ
き技術シーズについてもイノベーション創出効果を十分に判断し、出願・権利化する
ための所定の予算措置を講ずることも重要である。
○ また、支出面から捉えると、大学保有の特許権等が増大している状況下において、
各大学は、技術移転の状況を踏まえた段階的な絞り込みを実施し、知的財産権に係る
支出費用の合理化を図ることは非常に重要である21。その際、事業化可能性や技術的
価値といった知的財産活用のための目利き機能を各大学が発揮すること、また、特許
主張主体(PAE)への移転され得る形での権利譲渡は原則として避けること等が重
要である。
ただし、支出費用の合理化を図ったとしても、真に必要な予算の確保は必要不可欠
である点は留意が必要である(現時点で知的財産予算が十分でない大学においては、
予算増額が必要である)。
○ 事業化が視野に入る段階にまで大学の研究成果が至っていないことに起因し、事業
化やベンチャー起業につながっていないという問題に対して、原石である基本技術を
もう少し磨くため、大学が概念実証(Proof of Concept(POC))を行える仕組みを、
大学内に構築している事例もある。各大学自身がギャップファンドの仕組みを構築す
ることで、技術移転を促進することは効果的である。ギャップファンドの運用におい
ては、事業化に向けた概念実証に適切に活用されるよう(すなわち、単なる研究費の
配分だけになってしまわないよう)、徹底したマーケティングを行う機能を有する技
術移転活動実施組織が、実効的に行うことが重要である。(参考資料 図表38:「沖
縄科学技術大学院大学におけるPOCプログラム」)
(2)知的財産人材・体制に係る大学が目指すべき方向性
○ アカデミアにおける資産の根源である研究者自身が、学理の追求や原理の解明を
通じて学術的な価値を追求するだけでなく、研究成果の社会への提供というイノベ
ーション創出活動の意義を理解し、知的財産マネジメントや事業化に向けた意識を
持つことが重要である。そのためには、例えば、産学官連携活動や知的財産活動に
関する事項を教員評価等に反映することも有効である。研究者への意識付けは、執
行部等によるトップダウンと、マネジメントスタッフによるボトムアップの双方向
21 科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会産学官連携推進委員会が取りまとめた「イノベーション促進
のための産学官連携基本戦略~イノベーション・エコシステムの確立に向けて~」(平成22年9月)にお
いて、「長期間活用されずに大学等が特許を長期間保有することは、研究成果の社会的活用を阻害するとと
もに、大学等の維持管理負担を増大させてしまうため、保有特許の棚卸しを行い、必要に応じて権利の放
棄を含めて整理していくことにより効率的に管理することも考えられる。」という方向性が示された。
-32-

27
から行うことが必要である。
また、知的財産の権利化業務、活用業務においても、研究者の意見を取り入れて、
マネジメントスタッフと意思疎通を図り、研究者に対して社会実装・事業化の実現
に向けたマインドを醸成することが重要である。効率的かつ効果的に、技術移転・
事業化につなげるためには、研究者と知的財産・技術移転等のマネジメント人材の
タッグでイノベーション創出を推進することが重要である。
特に、産学官連携や国家プロジェクトに関与する研究者に対して、プロジェクト
開始初期の時点で、知的財産マネジメントの必要性と具体的取組等について普及啓
発を図っていくことが重要である。
○ 産学官連携を通じて社会にイノベーションを起こしていくために、研究者個人とし
ての「個と個」の関係の重要性を認識しつつも、大学間・専門分野間・異分野間での
連携・連合も含め、大学組織と民間企業という「組織対組織」による共同研究の活性
化の重要性が、競争力強化に向けた大学知的資産マネジメント検討委員会報告書にお
いて指摘されている。各大学には、全学的な知的資産マネジメントを行える体制を強
化し、産業界との連携をより一層強化していくことが強く求められている。
○ 知的財産を効果的に取得・活用していくために、マーケティングとセールス活動を
適切に実行し、事業化視点で知的財産マネジメントを実践し得る体制を大学に構築す
る必要がある(学内の体制強化だけでなく、学外機関との連携スキームの確立を含め
た体制構築)。
その際、企業における、オープン&クローズ戦略に代表されるように、ビジネスモ
デルに合致した高度な知的財産マネジメントが求められるようになってきている。そ
れに対応したマネジメントの実現に向けて、各大学は、オープン&クローズ戦略等の
企業の戦略を理解した人材の育成を図るべきである。さらに、それを理解した上で、
大学の運用において求められるオープン&クローズ戦略等を実行できる人材の育成
を、産学官連携活動を実践していく中で行っていくことが望まれる。
○ 大学が有する基盤的技術シーズを大規模なイノベーションに結実していくために
は、技術シーズを基本特許として有効性ある適切な形で保護することが重要である。
特許性だけでなく、他者の知的財産権の状況に基づく権利の強さ、市場性、事業化可
能性等を初期段階から分析し、戦略性を持った知的財産マネジメントを実践すること
が重要であり、そのための人材確保・体制構築が必要である。そのためにも、発明創
出時点等の早期のタイミングで、企業等に打診してニーズ把握するようなプレマーケ
ティングを行い、企業ニーズに合わせた強い知的財産権の取得・活用をすすめていく
マーケティングモデルを実践していくことが重要である。
-33-

28
また、マーケティングとセールス活動を徹底し、外国特許出願の判断時点までに企
業の意向を把握し、それによって外国への出願要否の判断を行うことで、真に必要な
案件に特化して権利化を推進していくマネジメント事例も参考になる。(参考資料 図
表37:「東京大学における出願判断事例」)
○ また、研究マネジメント、共同研究等の契約マネジメント、知的財産権の取得・管
理活動、技術移転活動・コーディネート活動(ライセンス活動、共同研究のマッチ
ング活動等)を、別々の担当者が担当すると、初期の時点(研究段階・発明創出段
階等)からの事業化意識が希薄になるため、総合的なマネジメントになりづらいこ
とや、また、共同研究の契約時においてイノベーション創出に向けた総合的な契約
マネジメントが困難になることの可能性も指摘されるところである。
知的財産を含む大学の研究経営資源を最大限に活用していくためには、事業化実
現を目指してマーケティングモデル22を実践し、研究開始・知的財産創出から、出願・
権利化、技術移転までの一連の業務が適切に連動した一気通貫の知的財産マネジメ
ントを行える仕組みが必要となる23。(参考資料 図表19:「大学特性を反映した一
気通貫の知的財産マネジメント」)
例えば、一つの案件について、一人のマネジメント担当者が研究段階(発明創出
段階)から実用化段階(技術移転活動の段階)まで一貫してマネジメントを担う仕
組みとすることや、技術移転等に関係する各担当者(知的財産担当、URA、コー
ディネータ、ライセンス・アソシエイト、インキュベータ等)の連携が適切に図ら
れるとともに、適切な産学官連携リスクマネジメント(利益相反、営業秘密管理、
安全保障貿易管理等のマネジメント)、契約マネジメント等の基盤の上でそれらが推
進される仕組みとすること等の種々の工夫が想定される。(参考資料 図表39、4
0:「三重大学における社会連携と技術移転」、「関西TLOにおける営業活動の具体
事例」)
○ 出願・権利化業務において、企業等のニーズをタイムリーに取り入れて、早期段階
から産学共同で権利化を図ることも、大学の知的財産マネジメントの一手法として考
えられる。(参考資料 図表41:「企業と大学が早期パートナーシップ構築した企業
の戦略事例」)
ただし、そのために、大学は、発明創出段階から信頼ある連携パートナーを見いだ
22 (再掲)マーケティングモデルとは、発明創出時点等の早期のタイミングで、企業等に打診してニーズ
把握するようなプレマーケティングを行い、企業ニーズに合わせた強い知的財産権の取得・活用をすすめ
ていくモデルのこと。 23 マーケティングモデルを含む一気通貫の知的財産マネジメントの実践により、企業ニーズや実用化可能
性等を意識して出願・権利化(権利範囲の補正等)を行い、取得する権利の厳選、追加実験を含む権利の
強化・弱点克服等を早期段階で図ることが可能となる。また、オプション契約やマイルストーン契約等を
行い、企業における実用化を促進していくことも有効と考えられる。
-34-

29
すとともに、社会実装に向けた方針(公平・中立という大学の基本的立場を前提とし
た上で、一企業の独占的実施によって事業化を目指すのか、複数企業による非独占的
実施によって事業化を目指すのかといった大学側の方針等)を十分に検討することが
必要不可欠である。
○ 学内の体制を強化していくに際して、知的財産マネジメントには高度な専門性や所
定の経験等を要することを考慮して、担当者の処遇も含めた人事マネジメントを十
分検討すべきである。優秀な人材を長期的スパンで考えて登用することも効果的で
ある。
○ 各大学は、戦略性とスピード感を持った知的財産マネジメントを行うための体制構
築を検討すべきである。特に、特定技術分野に特化して組織的に編成された領域(部
局、研究所、センター等)を大学が有する場合には、当該領域に特化した知的財産
マネジメントチームを設けて、大学本部(学内全体の知的財産マネジメント組織)
から一定の権限委譲された自由度をもった知的財産マネジメントを行うことも有効
である。それにより、分野に特有の状況(技術動向、市場動向等)を踏まえて、専
門性を活かした高度な知的財産マネジメントの実現が期待される。(参考資料 図表
55:「東北大学CIESにおける知的財産マネジメントの体制」)
また、知的財産マネジメントチームの活動を支えるためには、大学特有の事情も
考慮して自身で知的財産情報を管理するための知的財産マネジメントシステムの構
築と、それを運用する知的財産管理のスペシャリストの存在が重要である。(参考資
料 図表42:「電気通信大学における知財業務管理」)
なお、特定分野に秀でた機関において、特許等の出願・権利化業務等を内製化す
ることで戦略性を強化するとともに、権利化関連コストの削減を図っている事例も
見られるところである(ただし、広範な技術分野を扱う大学において、特定分野に
特化せずに広い分野の出願・権利化業務を一担当者が担うことは、実効性、効率性
がむしろ低下する場合もあることには十分留意して、具体的方策を検討する必要が
ある)。
○ 事業化視点での知的財産マネジメントを行っていくためには、各大学の状況に合
わせて、学外の他のプレイヤーと連携することも重要である。地域の抱える課題解
決も含め、産学官連携を通じてイノベーション創出を図っていくために、イノベー
ション・エコシステムの中で、技術移転機関(TLO)やベンチャー・キャピタル
(VC)、金融機関、地方自治体や、他の大学・研究機関等と連携し、効率的かつ実
効的にマネジメントし得るシステムを、各大学が形成する必要がある。(参考資料 図
表43~45:「株式会社テクノネットワーク四国における金融機関との連携事例」、
-35-

30
「山形大学における金融機関との連携事例」、「九州地区における複数大学連携事例」)
○ 弁理士等には、外部からの権利化支援といった従来型支援業務の枠組みを越えて、
これら従来業務の運用柔軟化(例えば、特許出願することを前提とした定型的業務
の見直しや、大学と弁理士とで相互のパートナーシップ強化等)や、総合的支援(知
的財産戦略、研究企画、技術移転等へのサポート)、内部型支援(組織内部に入り込
んだ意思決定への参加等)が期待されるところである。大学側も、弁理士を業務の
一部又は全部の委託先として捉えるだけではなく、イノベーション創出上の知的財
産マネジメント面でのパートナーとして連携する可能性を検討することは効果的で
ある。
(3)大学知的財産マネジメント強化に向けたTLOとの連携方策
○ 技術移転機関(TLO)は、大学の研究者の研究成果を特許化し、それを企業へ技
術移転する組織である。我が国の産学官連携化活動、地域・社会連携の多様化に合わ
せて、産と学の仲介役の役割としてTLOが担う業務も多様化している実態がある。
そのような実態の中で、TLOについて、「統廃合して拠点化する等、求められる機
能を再整理して強化すべき」といった指摘もある24。
各TLOそれぞれの特徴を持った多様性のある活動は妨げられるべきところでは
ないが、マーケティングを重視した技術移転活動を行うTLOにおいては、各大学が
目指す方向性等に沿った価値提供が期待されるところである。すなわち、マーケティ
ングモデルの確立と普及、多数の中小規模の大学に対するサポート(広域的活躍)等
の機能強化を図り、大学の知的財産マネジメント活動・技術移転活動の高度化に向け
て、大学のサポートを実践していくことが期待される。(参考資料 図表46、47:
「TLOが目指す方向性の例」、「関西TLOにおける人材育成の取組事例」)
各大学においては、TLO等の外部機関と連携し、効率化を目指す際においても、
自身の保有する財産権を適切にマネジメントするために、対等なパートナーシップで
コミュニケーションを図れる体制(知的財産等に関する一定の知識を備える内部人材
の確保)を構築すべきである。
○ また、各TLO自身が、種々のデータ等を活用しながら、各機関のパフォーマンス
改善を図る努力をして、経営効率を高めていくことが重要である。技術移転機関の組織
間ネットワークを活かして、技術移転ノウハウの共有を図っていくことが重要である。
24 知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会の下に設置された地方における知財活用促進タスクフォース
がとりまとめた「地方における知財活用促進タスクフォース報告書」(平成27年5月)において、「TLO
を統廃合して拠点化するなど、求められる機能を再整理して強化すべきであるという意見があった一方で、
TLO の統廃合を施策で誘導的に促進すること自体は困難ではないかという指摘があった。」とされている。
-36-

31
(4)国に期待される取組
国は、大学の知的財産マネジメントレベルに対応した支援等を行う必要がある。
①大手・中堅の先進的大学に対しては、知的財産マネジメントの更なる高度化に
向けて、マーケティングモデルに基づく知的財産マネジメントの実現を促進し
ていく必要がある。
②断続的に事業化実現がなされるが、発明創出が限定的な中小規模大学について
は、外部連携機関を積極的に活用した知的財産マネジメントの仕組みづくりが
必要である。
③知的財産取得・活用が進展していない中小規模大学については、継続的な知財
意識の普及啓発が必要である。
知的財産マネジメント、技術移転活動の強化には、マネジメント組織が一定の規模で
ある必要はあるものの、大学組織全体の技術領域は広範囲で、創出される発明の件数が
限定的であるため、マネジメント組織が小規模となってしまうケースも多くある。これ
らを勘案し、国には以下のような取組等が期待される。国は、各大学のレベルに応じた
段階的な支援の在り方を検討すべきである。
(知的財産予算面に関する国の取組について)
○ 国が知的財産経費等の支援を行う際に、支援の在り方や範囲を十分に検討し、大学
自身による自律的運用(費用面も含む)を、将来的に実現化していくための支援の在
り方を検討すべきである。特に、国が行う外国特許出願支援の運用の在り方等を十分
に精査・最適化し、原則としては各大学自身による自律的な知的財産マネジメントの
実現を目指すべきである。
ただし、外国特許出願の費用負担は現在の大学財務上大きな負担であり、財務的な
裏付けを大学が整備する必要がある。国は、大学の負担の在り方について、大学の実
態を踏まえて、創出された発明の適切な知的財産権化やイノベーション創出が阻害さ
れないように配慮した上で、支援方法(大学の費用負担額、支援対象等)を段階的に
変更していく必要がある。
○ 基礎的研究等の研究成果について、一大学では負担しきれないが、我が国の国益の
観点から研究成果を特許権として保護する必要があると考えられるものを保護する
ためのスキームを構築することが重要である。例えば、複数企業等の経費分担の形で、
当該分野のパテントプール的に権利を維持していくこともあり得ると考えられる。
-37-

32
○ 知的財産権を中長期的な視野で維持・管理し、活用していくためには、産学官連携
の関連経費を基金化し、会計年度や中期目標期間にかかわらず、各大学が中長期的な
視点でマネジメントできることが可能となるような環境を整えることが、国に期待さ
れる。25
○ 研究開発によって生まれた発明は、当然求められる成果として予定されているもの
であることを鑑みれば、知的財産関連経費は、直接経費で措置されるべきとの意見も
ある。国及びファンディング・エージェンシーは、これまでの発明創出実績(例えば、
研究費規模別の発明創出数等の実績)を分析すること等によって、各大学や各プロジ
ェクト等が必要とする知的財産関連経費について検討し、知的財産関連経費の在り方
を分析・検討することが望ましい。
○ 大学自身で運用するギャップファンドの強化を促進するとともに、それを補完する
形の国のギャップファンドの仕組みを強化していくことが重要である。ただし、その
際においても、事業化構想等を適切に評価して採択し得る制度設計等が非常に重要で
ある。
(知的財産人材・体制面に関する国の取組について)
○ 知的財産マネジメントの自主運営が困難な大学に対して、マーケティングモデルを
実行している大学やTLO等によって、マーケティング支援や人材育成を図るスキー
ムを構築する必要がある。その際に、短期的な雇用ではない、大学に定着していく中
核的人材に対して人材育成施策を講じていくべきである。
○ 特に、中小規模大学等に対して、大学間が連携し、情報共有・意見交換を行い得る
「場」を構築する必要がある。大学横断的に協力して、知的財産マネジメントを行う
環境を醸成することが重要である。
○ 特に、中小規模大学等のように、発明創出が著しく限られている大学は、一機関で
知的財産体制強化や人材育成を図っていくことが現実的に困難である可能性がある
25 イノベーション実現のための財源多様化検討会「本格的な産学連携による共同研究の拡大に向けた費用
負担等の在り方について」(平成27年12月)において、民間企業との共同研究に関して、「こうした戦
略的産学連携経費(仮称)については、実質的な研究支援経費とは別途に基金化し、会計年度や中期目標
期間にかかわらず、各大学の中長期的な戦略の下で活用することが可能となるよう、国は必要な取組を行
うことが求められる。」という旨が指摘されている。なお、ここでの「戦略的産学連携経費(仮称)」は、
共同研究の大型化等を推進していくためには、実質的な研究支援経費以外にも、今後の産学連携活動の発
展に向けた将来への投資や、そうした活動に伴うリスクの補完のための経費(例えば、大学の産学連携機
能強化のための企画・提案関連経費や知財マネジメント関連経費、インフラ整備経費、広報機能関連経費
等が考えられる。)とされている。
-38-

33
ものの、国のサポートを永続的に受けることは厳しい状況である。そのため、発明一
件の案件毎に知的財産マネジメントを業務委託できる形態(従来多くの機関で採用し
ている年度毎の一括した業務契約ではない新たな形態)で、大学がTLO等の外部機
関を活用し得る環境を構築することを国が推進すべきである。
それに際して、各TLOの特徴や体制、これまでの取組等を比較し得る環境を国が
整備することで、各大学自身の知的財産活用方策等に合致したTLO等を選択できる
環境を構築することが重要である。
○ 特に、中小規模大学に対して、国が継続的な普及啓発を行うとともに、随時の相談
にも対応することで、知的財産マネジメントの裾野拡大を図っていくことが重要であ
る。
○ 企業におけるオープン&クローズ戦略といった高度な知的財産マネジメントの動
向を、大学側においても把握し得る環境を醸成するとともに(例えば、研修プログラ
ムの提供等)、秘匿化に対応し得る営業秘密管理のマネジメント手法を検討し、各大
学での取組を促進すべきである。
-39-

34
5.研究開発プロジェクトの知的財産方針と大学の知的財産マネジメント
(全体的方向性)
・各研究開発プロジェクトにおいて、委託者側は、プロジェクト特性に合わせた知的
財産の取扱いに関する方針・戦略を持つことが必要。
・大学側においても、プロジェクトの知的財産方針に即した知的財産マネジメントが
求められることを理解し、プロジェクト初期の時点から、知的財産方針の決定に積
極的にコミットしていくことが重要。
国の委託研究開発プロジェクトにおいて日本版バイ・ドール規定が適用され、知的財
産権が受託者に帰属することとなった結果、企業等が国の研究開発プロジェクトに参加
するインセンティブは明らかに向上した。その一方で、研究開発の成果の事業化が進ん
でいない場合も依然としてみられ、知的財産権を保有する者以外への研究開発成果の展
開が十分進まない可能性も懸念されるという指摘がある26。
国の研究開発プロジェクトに対する受託者側への参加インセンティブ向上と、国の戦
略としての研究開発成果の活用促進とのバランスの下で、日本版バイ・ドール規定が運
用されてきたところであり、これまでは、委託者側(国、ファンディング・エージェン
シー等)が、研究開発成果の活用を含めた知的財産マネジメントにコミットすることは
限定的であった。
しかし、オープン&クローズ戦略といった高度な知的財産マネジメントが求められて
いる中で、プロジェクトの成果を我が国の産業競争力の強化に結実させていくためには、
技術的なイノベーションが企業の付加価値生産性の向上につながるメカニズムを、プロ
ジェクト初期の時点から構想した上で、プロジェクトを推進していくことが必要となっ
てきている。
そのため、委託者側である国、ファンディング・エージェンシーが、研究開発投資を
イノベーションに結実させていくための戦略を持つ必要があり、知的財産マネジメント
にも必要に応じてコミットして、参画機関と一体となって、イノベーション創出を目指
していくことが求められるようになってきている。そのような環境下において、大学が
目指すべき方向性、国やファンディング・エージェンシー(特に、基礎研究、基盤的研
究開発、新技術の企業化開発等)が目指すべき方向性を以下で検討する。
26 経済産業省「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」(平成27年5
月)
-40-

35
(1)研究開発プロジェクトに関して、国、ファンディング・エージェンシーが目指す
べき方向性
○ 我が国のあるべき将来像をビジョンとして描き、技術領域を含めて基礎的研究の方
向付けを行うとともに、期待される技術イノベーションの成果をグローバル市場の
競争優位性、雇用創出に結びつけていく仕組みを、国、ファンディング・エージェ
ンシー等は、各プレイヤー(企業、大学等)と連携しながら、研究開発投資の初期
の段階から構築しなければならない。
そのために、国、ファンディング・エージェンシーは、オープン&クローズ戦略
の思想に基づいて、企業、大学等とともに、技術的な研究開発成果を社会的なイノ
ベーションに結実させていく戦略をあらかじめ構想しておかなければならない。
○ 研究開発成果をイノベーションに結実していくために、国の研究開発プロジェクト
における知的財産方針の策定強化が求められている27。
各研究開発プロジェクトの形態(一機関のみ、産学1対1、複数者のコンソーシ
アム等の形態)や、研究フェーズ(基礎的研究、応用研究等のフェーズ)に関わら
ず、委託者側(国、ファンディング・エージェンシー)はプロジェクト開始初期の
時点から、イノベーション創出に向けた知的財産方針を明確化する必要がある。そ
の際、そのプロジェクトの目的や位置付けを十分に踏まえて知的財産マネジメント
を行う必要がある。
また、プロジェクトを推進していく中で、実効的に知的財産マネジメントを行っ
ていくためには、プロジェクト推進主体(運営委員会、プログラムオフィサー(P
O)等)のリーダーシップが重要となる。
委託者側(国、ファンディング・エージェンシー)は、各プロジェクトにおいて
それを実行できるよう、知的財産マネジメント面でプロジェクトをサポートする体
制を強化すべきである。
○ 研究開発プロジェクトの特性を勘案した上で、採択要件に知的財産創出、技術移転
の計画等を入れることも考えられる(例えば、特許実施例まで実験するように研究計
画の範囲を拡張することや、技術移転の体制整備状況を考慮すること等)。
27 知的財産推進計画2015において、「国の研究開発の成果を最大限事業化に結び付け、国富を最大化
するため、日本版バイ・ドール制度の運用等について本年5月15日に策定された「委託研究開発におけ
る知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」(経済産業省)も参考にしつつ、国の研究開発プロジ
ェクトにおける知的財産マネジメントの在り方を検討し、必要な措置を講ずる。」と策定されている。
-41-

36
(2)大学が研究開発プロジェクトに関与していくときの方向性
○ 各大学は、研究開発プロジェクトに関与する際に、プロジェクトの知的財産方針と
各機関の知的財産マネジメントの関係性を考慮する必要がある28。コンソーシアム型
の複数企業が参加するプロジェクトに大学が参加するケースにおいて、大学の知的財
産ポリシーと研究開発プロジェクトの知的財産ポリシーが相反する場合(例えば、戦
略的な知的財産活用を大学が行っていきたいという意向と研究開発プロジェクトの
意向とが相違する場合)も想定される。
プロジェクト開始時点で、知的財産の取扱いについて、委託者側(国及びファンデ
ィング・エージェンシー等)と受託者側(企業、大学等)との間で十分に検討し、各
機関間で一定の合意を図ることが何よりも重要である。知的財産の創造と活用の最適
化に沿ったプロジェクトの方針(国等の方針)が的確に策定されているのであれば、
各機関(企業、大学等)はプロジェクトに参画する以上、我が国の国益を尊重する観
点から、原則としてプロジェクトの知的財産方針を尊重することが求められる。裏返
して言えば、各大学は、そのことを十分に理解し、プロジェクト初期の時点から、知
的財産方針の決定に積極的にコミットしていくことが重要である。
○ 各プロジェクトにおいて、具体的方針に沿って、論文公表に関する手続プロセス等
を明確化するとともに、研究者に対する意識向上を図り、プロジェクトの知的財産
マネジメントを適切に実行し得る体制を、各プロジェクトが構築することが重要で
ある。
○ 各大学が、特許権等に係る収支(実施許諾等による収入と特許出願等に要する費用
の差)のみの観点等から、研究成果を特許出願しないことを判断した場合や、登録し
た特許権等を権利放棄すると判断した場合において、国費を投じた我が国研究成果が
適切に保護できず、国益を損失する懸念もある。特に、国の研究開発プロジェクトの
研究成果であれば、我が国全体での利益に資するための知的財産保護が望まれるとこ
ろであり、プロジェクトの一環で研究成果を適切に取り扱うことが各機関に求められ
ていることは、各大学が十分に理解すべきである。大学においては、研究費の間接経
費等(場合によって直接経費)を適切に活用して、研究成果を特許権(外国における
権利も含む)として適切に保護することとともに、中長期的な視点での権利保有の計
画(権利放棄の判断タイミング等も含む)をあらかじめ検討しておくことの重要性を
理解すべきである。
28 大学組織と研究者の関係について、現状では、研究企画や、研究開発プロジェクトへの応募は研究者が
主導的に行っており、知的財産の取扱い等を含めた戦略に関して、大学が組織として研究開発プロジェク
トの初期段階で関与していることは限定的であることにも留意する必要がある。今後、大学がガバナンス
をより一層強化していく際の知的財産マネジメントについても、検討しておくことが重要である。
-42-

37
(3)国に期待される取組
○ 国及びファンディング・エージェンシーは、我が国の競争力強化に向けた各研究開
発プロジェクト(特に、基礎研究、基盤的研究開発、新技術の企業化開発等)の知
的財産ポリシーを策定するとともに、知的財産マネジメントが適切に実行されるよ
うプロジェクトを推進していくべきである。
○ 国及びファンディング・エージェンシー側においては、受託者である各機関が適切
に知的財産マネジメントを実践できるよう、各機関を継続的にフォロー・サポートし
ていくことも重要である。そのために、委託者側にも高度なマネジメント人材(事業
化を意識した出願・権利化、技術移転等のアドバイス機能をもつ人材)を配置するこ
とは重要である。
-43-

38
6.産業界側の知的財産戦略と大学の知的財産マネジメント
6-1 産学のパートナーシップ強化と知的財産取扱い
(全体的方向性)
・大学の研究成果(知的財産)が産業界側で適切に活用され、継続的にイノベーショ
ンを創出していくシステム構築実現のためには、産学の対話を通じて双方ビジョン
の共有と意見対立緩和を図り、パートナーシップを強化することが重要。
・共同研究の成果の取扱いは、産学双方の共同研究の目的や共同研究の状況等を考慮
して、総合的な視点で検討することが必要。
産学官連携について、米国においては、受託的な研究(いわゆる Sponsored Research)
や、リエゾン・プログラム、学生のインターンシップといった種々の形態での連携や、
大学発ベンチャー、特許ライセンスといった形態での技術移転を中心として産学官連携
が展開されてきた。その一方、我が国における産学官連携はそれとは異なり、歴史的に
も、共同研究を中心に推進されてきた。
共同研究等の産学官連携を通じて社会にイノベーションを起こしていくためには、研
究者個人にとどまらず、大学組織も一体となって取り組むような大規模な共同研究等が
今後ますます重要になってくる29。共同研究に限らず、産学協同でイノベーション創出
を目指していくためには、産学が一体となったパートナーとして、ビジョンを共有し、
同じ目標を目指していくことが重要である。
(1)産学のパートナーシップの強化に向けた方向性
○ 大学が創出した技術シーズが産業界でのイノベーション創出に結実し、それが大学
の成長を含めた我が国全体のイノベーション創出機能の強化につながっていくサイ
クルを確立することが重要である。そのために、継続的にイノベーションを創出し
ていくためのシステム構築(イノベーションを常に創出していくために、知と資金
が適切に流動し、今後のイノベーション創出機能が持続的に強化されていくような
システムの構築)を、産学が一体となって共通の目標として目指していくことが重
要である。
○ 産学官連携(特許ライセンス、共同研究等)に関して、大学側の意見として、大学
の「知的資産」の価値が企業側に適切に評価されていない可能性があること(例えば、
自社開発するよりも安価に技術獲得できているにも関わらず十分に尊重されていな
29 競争力強化に向けた大学知的資産マネジメント検討委員会報告書を参照。
-44-

39
いこと、お付き合い型の共同研究が多いこと等)、また、企業側の意見として、事業
化実現は企業努力によるところも大きい点や、研究段階では事業化成功リスクは非常
に高い点、製品売上げに占める特許の効果は限定的である点等が大学側に十分理解さ
れていない可能性があることといった、双方から意見が挙げられる状況である。
大学と企業とでは、双方の立場や社会的なミッションが異なるので、対立する事項
が生じることは当然であり、それ自体に問題があるわけではない。
しかし、大学側は、企業の事業戦略を尊重するとともに、イノベーションに結実す
る研究シーズの創出と適切なマネジメントを強化していくことに努めるべきであり、
また、企業側は、大学の「知」の価値を適切に評価してオープンイノベーションの効
果と効率性を尊重することに努めるべきである。そのような形で、産学双方の信頼関
係を醸成した中長期的なパートナーシップを強化すべきである。特に、企業側及び大
学側の経営レベルでの対話を通じて産学のビジョンの共有と意見対立緩和を図り、パ
ートナーシップを強化していくことが重要である。その際、産学の経営層(企業側役
員、大学側執行部等)だけでなく、知的財産マネジメント担当部署も交えて、知的財
産マネジメントに関する専門的な知見も経営レベルで捉えた上で、知的財産戦略を含
むイノベーション創出に向けたパートナーシップ強化策を一体的かつ総合的に議論
することが有効である。
○ 大学は、知的財産を実施(事業化)する術を持たないので知的財産収入を獲得する
必要があるといった主張のみをもって企業側に実施許諾収入(又は、いわゆる不実施
補償)を求めることは、企業側から理解を得られないことが少なくないことを十分理
解すべきである。もとより、大学における知的財産マネジメント・技術移転活動は、
実施許諾収入等の獲得が目的なのではなく、技術シーズをイノベーションに結実して
いくことが目的であるから、そのための条件は柔軟で多様に捉えるべきである。
○ 海外企業等へのライセンスや海外企業等との共同研究等の国際産学官連携を通じ
て、我が国大学の知的資産を最大限に活かしていくことを検討することも重要である。
その一方で、我が国研究成果が海外に流出するという観点から、国際産学官連携に
否定的な意見(例えば、我が国の研究成果であるにも関わらず国内企業に損失をもた
らす場合もあるという意見等)もあるところ、国は、国際産学官連携活動を促進する
上でのリスクマネジメントについて検討することで、国際産学官連携を推進していく
ための環境を整備する必要がある。
また、これまでと異なる連携パートナー(海外企業等)を開拓していく際に、各国
の知的財産取扱い慣行等の相違もあり、連携先から強い権利主張がなされるケース
(例えば、バックグラウンド特許の使用権利に関する強い主張、資金提供が少額のま
ま共同研究成果の知的財産の無償使用の主張等)も十分に想定されるところである。
-45-

40
大学においては、共同研究契約等の交渉力を強化し、共同研究の実施目的を勘案した
強い交渉を行うことが重要である。
(2)共同研究等の成果取扱い
○ 企業と大学の共同研究は、現在、少額の共同研究が大多数を占めており、共同研究
に対する大学の組織的関与は必ずしも強固なものではない。今後は、将来の産業構造
の変革を見越した革新的技術創出に向けて、研究者レベルの連携を越えて、連携をよ
り一層強化した「組織」対「組織」の共同研究を推進していくことが、大学には求め
られているところである。(参考資料 図表48:「企業における共同研究等のテーマ
と規模の例(一企業の事例))
また、研究対象の領域(例えば、競争領域、非競争領域等)や連携態様(例えば、
バイラテラル、マルチラテラル等)、研究場所(大学内外等)といった共同研究の連
携形態は多様なものがある。企業側の産業競争力に結実していくよう、オープン&ク
ローズ戦略に適切に活かせる形態で、産学の共同研究を推進していくことが重要であ
る。
【連携レベルの例】
連携態様 説明
組織的連携
「組織」対「組織」の共同研究。企業側役員、大学側執行部
(理事・副学長等)が関与する形で実施される多様で多面的
な組織連携。
研究者レベルの連携 研究者同士の信頼関係に基づく、いわゆるお付き合い型の共
同研究等も包含。
【共同研究の形態の例】
研究領域 参加機関数 説明
競争領域
バイ
ラテラル
大学と企業とが1対1で取り組むような研究。実用化
に近い応用フェーズの研究や、一製品少数特許の技術
分野における基礎的研究は、1対1のパートナーシッ
プを組むことが多いところ。
マルチ
ラテラル
複数の機関が参加するプロジェクト。競争領域である
ため、異業種連携、垂直連携の形態が想定されるとこ
ろ。
非競争領域 マルチ
ラテラル
競合企業を含めた複数機関が参加し得るプロジェク
ト。一製品多数特許の技術分野における基盤的技術の
研究、標準化関連技術の研究等が想定されるところ。
詳細については、6-2において検討。
-46-

41
【プロジェクトのタイプ】
【プロジェクト参加メンバー構成 (同業種、異業種、垂直連携等)】
【業種・業態・技術特性 (知的財産の意義)】
・フォーメーション形成タイプ(種々の国プロ)
・個別共同研究の集積タイプ ・会費制タイプ
ひとつのルール・規程等の下で各者が合意し、契約を締結するパターン。一体的チームを形成したフォーメーションを構築。
A大学
B社
C社D社
E社A大学
中核機関が、個別機関と個別共同研究契約を締結するパターン。
B社
C社
D社
E社
A大学
B社
C社
D社
会費制の仕組み等により、産業界が期待する研究テーマを設定し、大学等が中心となって研究を実施するような契約を締結するパターン。
・個別共同研究のタイプ
1対1での個別共同研究を行うパターン。
A大学
B社
2.異業種連携研究型
同種の製品・サービスを提供していない事業者同士が、それぞれの強みを活かしつつ、共同で研究開発を行っているもの
3.同業種連携研究型
同種の製品・サービスを提供している事業者(同業者)同士が、共同で研究開発を行っているもの (それぞれの強みを活かす場合や、共通基盤技術の開発を行う場合などがある)
1.垂直連携研究型
製品・サービスを直接に受発注する関係にある事業者同士が、共同で研究開発を行っているもの
●製薬・バイオ
●新素材
●エレクトロニクス・機械
基本特許の重要性 特許以外の要素の重要性
一製品少数特許:
基本特許の保有によってコア領域を保護することが重要。
一製品多数特許:
特許ポートフォリオの構築、ライセンス、標準化等の知財活用戦略が重要。
特許以外:
著作権や種々ビジネスモデル等の特許以外の要因も重要。
●IT
●インターネットビジネス・ソフトウェア
-47-

42
○ 共同研究の成果取扱いについて、産学双方の意思疎通・利害調整がうまくなされず、
一律かつ硬直的な契約内容・運用になっている可能性も指摘されるところである(例
えば、いわゆる不実施補償の問題等30)。産業界側・大学側の双方が、それぞれの共同
研究等の実施目的や、知的財産活用方策、意向等といった両者の立場を理解するとと
もに、共同研究等の状況を踏まえて、柔軟な交渉を行うことが重要である。31 (参
考資料 図表22、23、49:「共同研究等の成果の取扱に関する検討(調査結果)」、
「共同研究等の成果の取扱の柔軟化に向けた方策(調査結果)」、「共同研究等の柔軟
性のある共同研究契約の海外大学事例(調査結果)」)
○ また、研究成果の取扱い以外の各種共同研究契約事項も考慮して、共同研究の実施
目的を適切に達成し得るような総合的な共同研究契約を実現していく必要がある(例
えば、インターンシップの受入れ、学生の奨学金等の勘案)。知的財産マネジメント
を、産学官連携活動における多くのマネジメント要素のひとつであることを認識して
交渉を進めるべきある。
それを実現するためには、知的財産の側面だけで部分最適化した形での硬直的な交
渉(例えば、知的財産担当者や事務担当レベルで、大学側の実施許諾等収入の最大化
のみを目指した交渉や、企業側の費用負担の最小化のみを成果にする交渉が図られる
こと。)に陥らないように、共同研究の実施目的や連携のビジョンを共有する形で、
組織的な連携を強化し、双方 win-win な関係を目指していくことが重要である。(参
考資料 図表50:「柔軟性のある共同研究契約の事例」)
○ 基礎的・基盤的研究は単独で研究し、単独特許(基本特許)の出願を行ってから企
業との連携(共同研究)を行うとともに、共有特許(共同研究の成果)は非独占的通
常実施権(不実施補償は求めない)として、単独特許と共有特許を組み合わせて第三
者へライセンスを図る戦略をとる機関もある32。(参考資料 図表52:「物質・材料
研究機構におけるライセンス等の方針」)
また、共同研究成果の取扱いについて、発明の種類(装置の発明、材料の発明等)
30 一般社団法人 日本経済団体連合会「産学官連携による共同研究の強化に向けて ~イノベーションを
担う大学・研究開発法人への期待~」(2016年2月)において、不実施補償に関する大学等に対する期
待として、「硬直的な『知的財産管理(成果管理)』体制・ルールの改善。特に「不実施補償」に関し、非
独占的な自己実施において『不実施補償料を請求しない』ルール(産業技術総合研究所等が導入)をはじ
めとする、契約の柔軟化(各組織や分野の特性に応じた特許権取扱の類型化等)。」の必要性が説示されて
いる。また、同レポートで、政府に求められる対応として、「共同研究を通じ取得された知的財産の活用方
策についての類型化等を進め、『不実施補償』等の課題解決に向けたベストプラクティスの提示。」が提案
されている。 31 特許庁平成27年度産業財産権制度問題調査研究報告書「産学官連携から生じる研究成果活用促進のた
めの特許権の取扱に関する調査研究」の内容も参照のこと。例えば、「企業が非独占的実施権を選択した場
合、不実施補償を求めないが、大学等による第三者への実施許諾を自由とするといった契約例」等が紹介
されている。 32 例えば、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人物質・材料研究機構等が該当。
-48-

43
によって、単独保有(企業/大学)、共有保有とするかをあらかじめ定めて運用して
いる事例もある。(参考資料 図表51:「権利化対象案件の選択事例等」)
各大学においては、このような運用事例も参考にして、各機関で共同研究をどのよ
うに位置付けて、知的財産マネジメントをどのように行っていくかについて、運用方
針を検討することが重要である。その際には、イノベーション創出機能の強化(産学
の連携強化、社会実装の実現)と大学の成長の実現を目指すマネジメントが必要であ
る。
<特に、バイラテラルの共同研究>
○ 共同研究の成果の取扱いに関して、創出した研究成果の取扱いに関する権利帰属、
実施権の態様、同意規定、特許出願費用等の種々の要素が協議事項になる。
権利帰属、実施許諾については、以下のように、可能な限り単独保有の形態とする
等シンプルな保有形態を目指しつつ、共有保有の形態の場合は、企業側の独占意向と
大学側の活用意向等を勘案し、実施の独占性を判断することが重要である(例えば、
以下の成果の取り扱い態様がある)。また、オプション契約等を通じて、知的財産の
活用促進、社会実装の実現を図っていくことも効果的である。
【成果の取扱いバリエーションの例】
単/共 帰属・実施 条件の例
単独
企業単独保有 ランニングロイヤリティ相当の実施料が大学側に
還元する仕組みの可能性の検討が必要。
大学単独保有
(企業に実施許諾)
原則として、非独占的通常実施の形で、相手企業に
実施権付与。市場の切り分けを戦略的に行い、競合
企業以外に積極的に実施許諾する等。
共有
共有・独占実施
原則として、実施料ありとし、独占(優先交渉権)
の期間を一定程度定め、継続的な独占の是非を判断
する等。
共有・非独占実施 実施料(いわゆる不実施補償)有無については柔軟
な規定を設ける等。
<特に、マルチラテラルの共同研究(競争領域、非競争領域)>
○ コンソーシアム型プロジェクトにおける知的財産マネジメントにおいては、上記バ
イラテラルの共同研究の協議事項をベースにしつつ、各参加機関の意見調整を図るこ
とが求められる。詳細は、6-2「大学が主導する非競争領域における知的財産マネ
ジメント」において別途検討する。
-49-

44
<共有特許権の有効活用>
○ 共同研究等の成果である共有特許権が、企業側の事業戦略の変更等によって、権利
保有者である企業等において活用されずに死蔵するケースも多々あると考えられる。
企業側にとって防衛的な位置付けで用いられる側面もあるものの、新事業の創出等の
イノベーション実現に対する大学への期待が高い中で、一企業の防衛的な知的財産活
用方策が我が国イノベーション全体に寄与しているのか、また、公共的性格の大学の
立場と整合性が保たれるのかは十分に検討する必要がある。
その点について、例えば、権利保有企業において実用化されていない共有特許を第
三者に実施許諾可能とする等、保有する特許権を積極的な活用に結びつけていく方策
を検討することが重要である。その可能性について、各大学は産業界側と対話してい
くことが重要である。
(3)国に期待される取組
○ 共同研究契約において、柔軟性を持って研究成果の取扱いを決定していくための共
同研究契約の方向性を例示するとともに、各大学に対して普及啓発を図っていくべき
である。ただし、国の関与は、個別状況に応じた自由度をもった契約の実現を損なわ
ない範囲にとどめるべきである。
○ オープン&クローズ戦略の進展の中で、高度な契約マネジメントを大学が実現すべ
く、国は、戦略的な契約マネジメントを実行できる人材育成を図っていくべきである。
○ 産学双方のパートナーシップを強化していくために、経営レベルでの産と学の対話
の場を設けることが重要である。
-50-

45
6-2 大学が主導する非競争領域における知的財産マネジメント
(全体的方向性)
・非競争領域においては、知的財産権を中核機関(基幹大学等)に蓄積させることと、
蓄積された知的財産権を産業界側が利用しやすくする戦略的知的財産マネジメン
トを行うことが必要。
・新たな基幹産業の育成の核となる革新的技術の創出を目指した学問的挑戦性と産業
的革新性を併せ持つ異分野融合の研究の実現に向けて、世界的な技術・ビジネスの
動向、関連業界の技術戦略の分析等と連動した知的財産マネジメントを行える体
制・仕組みを構築することが必要。
我が国の大学には、世界トップレベルの研究能力によって大きなインパクトを持つイ
ノベーションを起こすポテンシャルが存在するにもかかわらず、その活用の可能性、価
値に関する企業への説明・提案は十分ではなく、特に基礎的研究については企業からの
資金導入がわずかにとどまっている。他方で、海外の大学では、基礎的研究から企業と
の共同研究に積極的に取り組み、その中で学生等の人材育成も行われている。
そのような中で、我が国の大学においても、基礎的研究からの産学官連携を促進し、
長期的視野を必要とするオープンイノベーションへの大学の貢献を拡大するとともに、
大学の教育研究の充実も同時に図るシステム作りが必要と考えられるところである33。
そこで、基礎的研究や人材育成に係る産学パートナーシップを拡大することに向けて、
求められるマネジメント要素を整理するとともに、マネジメント要素全体の中で知的財
産マネジメントを位置付けて、目指すべき知的財産マネジメントの在り方を検討する必
要がある。
(1)非競争領域における大学主導のコンソーシアム構築の必要性とマネジメント
○ 産業界との協力の下、大学が知的資産を総動員し、新たな基幹産業の育成に向けた
技術・システム革新シナリオの作成と、それに基づく非競争領域(すなわち、競合関
係にある複数の大学や企業間であっても、研究成果の共有・公開を可能にする基礎
的・基盤的研究領域であって、産業界のコミットが得られ、競争領域への移行も見込
まれる領域の意味。pre-competitive stage を意味し、競争前領域、協調領域等と同
33 産業界側から、日本経済団体連合会(2015年10月20日)「第5期科学技術基本計画の策定に向
けた緊急提言」において、「基礎研究から社会実装までのビジョンや経営課題の共有を通じた本格的な産学
連携や拠点形成、さらには産学連携での人材育成を進めるための有効な方策についても検討が必要であ
る。」、「次の時代を担う『新たな基幹産業の育成』に向けた本格的なオープンイノベーションを推進する。
具体的には、非競争領域を中心に複数の企業・大学・研究機関等のパートナーシップを拡大し、将来の産
業構造の変革を見通した革新的技術の創出に取り組む。」といった提言がまとめられているところである。
-51-

46
義としてここでは使用。)の共同研究の企画・提案等を行い、基礎的研究や人材育成
に係る産学パートナーシップを拡大することで、我が国のオープンイノベーションの
加速化が期待されるところである。
○ コンソーシアム34の形態でみたときに、出口志向のコンソーシアム(特に競争領域)
は、垂直連携又は異業種連携の方が、同業種連携よりも、成果が出やすいことが一般
的に知られている。市場の出口が異なるフォーメーションであれば、競合にならない
ため参加企業が協業を優先した研究環境を醸成しやすいこと、異なる発想のシナジー
効果が大きいこと、サプライチェーンの全体像・出口を見据えやすいこと等が理由と
してあげられる。
他方、非競争領域のコンソーシアムにおいては、同業種も含めた連携が望まれると
ころである。同業種連携であっても、非競争段階の基盤的技術を業界全体で連携して
底上げすることは、研究開発効率を高める効果や、研究開発のリスクを分散できる効
果が得られる。そのためには、各企業の特徴を発揮し得る競争領域につながるような
非競争領域の設計が重要となる。
○ 非競争領域における複数企業の連携を、大学が主導して実行していくような新たな
枠組みで産学パートナーシップの強化を図る際には、これまで以上に高度なマネジメ
ントが期待される。非競争領域を主導する大学においては、知的財産マネジメントだ
けでなく、研究マネジメント、大学組織マネジメント、産学官連携リスクマネジメン
ト、コーディネート業務、契約マネジメント等の各種マネジメントを、総合的かつ一
体的に推進し、産業界との連携を強化していくことが期待される。具体的なマネジメ
ント要素として、以下のような事項が想定される。
<知的財産マネジメント>
・コンソーシアムの発展を実現するための知的財産マネジメント(例えば、フ
ォアグランウドIPのコンソーシアム内での共有化等)
・シーズを社会実装する最適な方策(ベンチャー創出を含む)の戦略立案(研究
マネジメント、知的財産マネジメント、技術移転活動等が連動する一体的なマ
ネジメント体制の確立)
・競争領域・非競争領域を見据えた知的財産戦略、知的財産ポリシー、知的財産
マネジメント体制の構築
<研究マネジメント・組織マネジメント>
・企業群と協働で技術・システム革新シナリオの構想立案ができる研究者群の組
34 本報告書内において、コンソーシアムは、プロジェクト等の集合的な意味。以下、同様。
-52-

47
織化とそれを実現するためのガバナンス、推進体制の構築
・クロスアポイントメントの実施が可能となる仕組み(エフォート管理等)
・企業群との協働による、大きなイノベーション創出の核となる研究領域(競争
領域・非競争領域)の設定を実現し得る研究企画マネジメント(IRを活用し
た研究力分析、技術動向・業界動向・企業ニーズ等の把握)
・明確な研究計画(目的、目標、スケジュール、成果物、費用等)の提示
<産学官連携リスクマネジメント>
・競争領域・非競争領域の特性を踏まえ、企業間の公平性等の担保
・産学の連携強化を図っていく上での適切な利益相反マネジメント
・機密性の高い情報交換を通じた本格的な連携を実現可能とするための技術流出
防止マネジメント(特に、営業秘密管理)
<コーディネート(渉外)>
・定期的な産と学との意見交換の場の設定
・パートナー企業の獲得に向けた価値提案の渉外業務
・研究成果を広く社会にアピールするアウトリーチ活動
<契約マネジメント>
・積算に基づいた研究費(直接経費、間接経費)の算出を行うとともに、その根
拠の明確化・透明化の実現(そのための契約支援や経理・財務体制の構築を大
学本部が行うこと等)
・学生・ポスドクが活躍し得る環境を実現することも含め、産業界側と柔軟かつ
戦略的な契約を締結するための共同研究契約マネジメント(学生・ポスドクの
経済的報酬の位置付け、研究成果の発表等)
(2)非競争領域における知的財産の戦略的取扱い
○ マルチラテラル(コンソーシアム)型の共同研究において、協議すべき事項は多様
な要素がある。(参考資料 図表21:「プロジェクトの知財取扱いに関する合意書の
作成項目例・協議ポイント」)
非競争領域における知的財産マネジメントで特に重要な協議事項として、研究成
果(フォアグラウンドIP)の帰属、実施及び許諾に関する事項がある。これらを
決定していく際は、産業界側の視点、大学側の視点を考慮するとともに、知的財産
取扱い検討時の影響要素(プロジェクトのタイプ、参加企業の特性等)を考慮する
ことが重要である。
-53-

48
産業界側の視点
<発明創出機関として>
●知的財産の共有による不公平発生回避の必要性(研究貢献度・研究費支
出の考慮)
●成果が競争力確保に結実していく必要性
(ビジネスモデルに合わせた独占的実施、標準化等の実現可能性)
<コンソーシアム参画機関として>
●他者の研究成果(フォアグラウンドIP)が利用できることの有用性
●知的財産創出以外への期待(基幹大学のバックグラウンドIP利用、連
携先からのノウハウ獲得・ネットワーク構築、施設設備利用、技術領域
全体の発展等)
大学側の視点
<大学の財産保有・活用として>
●研究領域の発展に資する権利保有の実現
(次のプロジェクトのバックグラウンドIPに活用)
●社会実装によるイノベーション創出の実現
(特許死蔵化防止、VB創出実現化)
<プロジェクト管理として>
●知的財産取扱いの煩雑性・管理負担の抑制
(案件毎の価値判断、取引作業等)
知的財産取扱い検討時の影響要素
(1)プロジェクトのタイプ
(2)プロジェクト参加メンバー構成 ※原則として同業種
(3)業種・業態・技術特性 (知的財産の意義)
○ 非競争領域においては、「競合関係にある複数の大学等や企業間であっても、研究
成果の共有・公開を可能にする」ことを目指していることを踏まえると、コンソーシ
アム発展を通じたイノベーション促進のために、フォアグラウンドIPを、大学が積
極的に活用する知的財産マネジメントの実現が重要である。具体的には、プロジェク
-54-

49
トの研究成果を中核機関(基幹大学等)が蓄積すること(研究成果に係る知的財産権
の帰属を中核機関である基幹大学に集中させる一元的管理化)と、蓄積された知的財
産権を産業界側が利用しやすくする戦略的知的財産マネジメントを行うことの両者
の実現が必要である35。(参考資料 図表53~59:「物質・材料研究機構における
組織的連携のスキーム」、「東北大学CIESにおける知的財産マネジメントの事例」、
「TPECの知的財産マネジメントの事例)」、「IMECにおける知的財産取扱いパ
ターン」、「カーネギーメロン大学QoLT(ERC)における知財取扱い事例」、「T
IA-nanoにおける知的財産権の取扱いの例」)
○ 上記のように、コンソーシアムの発展のために、大学がフォアグラウンドIPを積
極的に活用していくマネジメントを、産業界側から理解を得て実行していくためには、
参画することへの価値を提供し、コンソーシアムに参加したくなる仕組みを大学が実
現していくことが前提である。大学は、例えば以下に示すような、コンソーシアム参
画に対する魅力提供と、必要な体制の構築を行うことが前提となる。
・大学に基盤的技術について強い技術力があること
・大学が魅力ある研究テーマを提案していること
・大学が一機関では所有できない設備を有していること
・大学が高度な知的財産マネジメント体制を有していること
・大学が強いリーダーシップを発揮すること(上記全項目と関係)
【プロジェクト・コンソーシアムの階層と知的財産帰属】
35 TIA-nano 運営最高会議「拠点活用プロジェクトにおける知的財産権の取扱いに関するガイドライン」
(平成25年3月)がとっている全体方針のひとつである。
-55-

50
【成果の取扱いバリエーション(例)】
領域 帰属・実施 条件等
非競争
領域
<共通的要素>
・プロジェクト内で創出されたフォアグラウンドIPは、プロジェク
ト内のメンバーは原則無償又は低廉で自由利用可(一般的に、コン
ソーシアム内は別途協議)。
・基幹大学が保有するフォアグラウンドIPは、次のプロジェクトの
バックグラウンドIPとしても活用可(単独・共有に関わらず)。
・第三者へ実施許諾する際は協議が必要36。
基幹大学単独保有
発明創出自体は、基幹大学の貢献が大きい案件で実現
しやすい(例えば、会費制等のタイプ)。
発明の特性等に応じて、大学側単独保有にする案件、
企業側単独保有にする案件、共有にする案件を切り分
ける方法もある。
基幹大学との共有
非独占実施
共有特許の扱いは、非独占で、コンソーシアム内では
同意規定なしとする。
個別共同研究の集積タイプで実現しやすい(IMEC
のようなモデル)。また、種々の国プロのようなフォ
ーメーション形成タイプにおいても、中核機関(基幹
大学)がリーダーシップを発揮することで、実現が可
能となる。
原則権利化しない
フォアグラウンドIPは基本的に権利化しない方針
とし、必要に応じて、ノウハウ(各種データ等)をプ
ロジェクトメンバーに無償で使用許諾を行う仕組み
をつくる。
技術組合等の
単独保有
事業化に向けて知的財産管理するために、技術組合を
設けて知的財産を一元的に管理する。
(参考)
競争
領域
―
参加企業のメンバー構成や技術領域、各社のビジネス
モデル等の種々の状況に合わせて、多様な運用が想定
される。状況に合わせた運用を柔軟に検討すべきであ
る。例えば、技術組合が一括管理するケース等もある。
36 参加企業の国際競争力を損なわないように第三者実施について判断する必要がある。また、コンソーシ
アム内メンバー(同一研究開発プロジェクトには直接参加していないが、他のプロジェクトに参加してい
るメンバー、該当プロジェクト後の後続プロジェクトに新たに参画してきたメンバー等)への実施許諾は、
原則として同意不要とする等、成果の利用が円滑に進むよう、あらかじめ協議しておくことが望ましい。
-56-

51
<その他事項>
・基幹大学に対する実施料(不実施補償等)の有無等の条件は柔軟に検討する。た
だし、実施料の要否については、発明への貢献度等も十分勘案する必要がある。
・基幹大学以外の大学に所属する研究者が参画するような場合においても、協議の
上、基幹大学側に権利を帰属させる等、可能な限り複雑ではない取扱いことが望
ましい。
(3)非競争領域において求められる知的財産マネジメント体制等
○ 新たな基幹産業の育成の核となる革新的技術の創出を目指した学問的挑戦性と産
業的革新性を併せ持つ異分野融合の研究の実現に向けて、世界的な技術・ビジネスの
動向、関連業界の技術戦略の分析等と連動した高度な知的財産マネジメントを行える
体制・仕組みが求められる。研究企画や共同研究契約等の各種マネジメントと一体的
な知的財産マネジメントを行うための仕組みが必要である。
○ 各大学は、特定技術分野に特化した知的財産マネジメントチームを設けて、大学本
部(学内全体の知的財産マネジメント組織)から一定の権限委譲された自由度をも
った知的財産マネジメントを行うことも有効である。それにより、分野に特有の状
況(技術動向、市場動向等)を踏まえて、専門性を活かした高度な知的財産マネジ
メントの実現が期待される。(参考資料 図表55:「東北大学CIESにおける知的
財産マネジメントの体制」)
(4)国に期待される取組
○ 国は、非競争領域のコンソーシアムを組成して研究開発プロジェクトを推進する中
で、非競争領域における戦略的な知的財産マネジメントの実現を促進するとともに、
多くの大学にとって参考となるような事例をできるだけ多く蓄積し、共有していくべ
きである。
-57-

52
7.おわりに
近年、企業の知的財産マネジメントがオープン&クローズ戦略として適切な活用を
図る戦略へと主流が変容している。その中で、大学の「知」を企業の付加価値を長期に
高めるメカニズムに位置付けるという視点で、大学における知的財産マネジメントにお
いても、オープン&クローズ戦略に対応したマネジメントの実行が必要不可欠になって
きている。
本検討会では、そのような環境変化の下で、イノベーション創出を実現するととも
に、それによって大学がより一層成長していくことを目指して、大学が知的財産マネジ
メントをどのように行っていくべきか、また、研究開発プロジェクト(国、ファンディ
ング・エージェンシー)や産業界との関係性で大学が知的財産マネジメントをどのよう
に行っていくべきか、といった点について検討を行ってきた。具体的には、以下のよう
に、大学の知的財産マネジメントの在り方が提起された。
○ 各大学は、知的財産を保有する意義を明確に意識し、イノベーション創出に結実さ
せることを目指し、大学経営レベルで知的財産マネジメントを捉える必要性がある
ことが提起された。
○ 各大学は、知的財産マネジメントの高度化に向けて、各大学の知的財産戦略を策定
し、それに即した体制・システムの強化(予算措置と間接経費の活用、事業化視点
でのマネジメント体制の強化等)を行うべきであることが提起された。
○ プロジェクト参加メンバー(企業、大学等)の各知的財産方針、知的財産ポリシー
の下で、各研究開発プロジェクトにおいて、委託者側(国、ファンディング・エー
ジェンシー)がプロジェクト特性に合わせた知的財産の取扱いに関する具体的方
針・戦略を明確に持つ必要があり、各大学は、その具体的方針に合わせた適切な知
的財産マネジメントを実行する必要があることが提起された。
○ 大学と産業界は、対話を通じて産学の意見対立を緩和し、パートナーシップを強化
していくことで、知的財産等の研究成果を継続的なイノベーションに結実していく
ためのシステムを構築する必要があることが提起された。また、大学が主導する非
競争領域における戦略的知的財産マネジメント実現に向けた方向性が提起された。
各大学は、知的財産マネジメントの意義を大学経営レベルで議論し、戦略を立案する
とともに、それに合わせた体制・システム強化を積極的に行うことが期待される。 国は、大学が目指すべき知的財産マネジメントを自律的に実現することに向けて、各
大学の取組をサポートしていくべきである。
-58-

参考資料
-59-

オープン&クローズ戦略時代の大学知財マネジメント検討会 設置要領
平成27年9月4日
文部科学省科学技術・学術政策局
1.設置趣旨
「競争力強化に向けた大学知的資産マネジメント検討委員会」における報告書(平成
27 年 8 月 5 日とりまとめ)を受け、オープン&クローズ戦略時代における大学の知的
財産マネジメントの在り方等について検討するために、本検討会を設置する。
2.検討事項
①オープン領域とクローズ領域の設定及びマネジメントの在り方 ②大学の知財戦略の確立と知財マネジメント向上の方策 ③その他必要な事項
3.委員の構成、任期及び運営
①検討会を構成する委員は、別紙のとおりとする。 ②委員の任期は、競争力強化に向けた大学知的資産マネジメント検討委員会委員の 任期満了日である、平成29年2月14日までとする。
③検討会には座長を置く。 ④座長は、検討会の事務を掌理する。 ⑤検討会は、個別利害に直結する事項についての検討も含まれる可能性があるため、 原則として会議及び議事は非公開で行う。
⑥このほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が検討会に諮って定める。 4.その他
この検討会に要する庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課
大学技術移転推進室が行う。
(参考資料1)
-60-

オープン&クローズ戦略時代の大学知財マネジメント検討会
委員名簿
井上 二三夫 シスメックス株式会社研究開発企画本部 副本部長兼知的財産部長
上野山 雄 パナソニック株式会社 フェロー
魚崎 浩平 国立研究開発法人物質・材料研究機構 フェロー
大嶋 洋一 国立大学法人東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター
戦略企画部門長
岡島 博司 トヨタ自動車株式会社技術統括部 担当部長
小川 紘一 国立大学法人東京大学政策ビジョン研究センター
シニアリサーチャー
小寺 秀俊 国立大学法人京都大学大学院工学研究科 教授
○後藤 吉正 国立研究開発法人科学技術振興機構 理事
進藤 秀夫 国立大学法人東北大学 理事(産学連携担当)
中島 淳 太陽国際特許事務所 所長
林 いづみ 桜坂法律事務所 弁護士
八島 英彦 三菱化学株式会社 執行役員 経営戦略部門 RD 戦略室長
◎渡部 俊也 国立大学法人東京大学政策ビジョン研究センター 教授
◎:座長、○:座長代理
(五十音順、敬称略)
(参考資料2)
-61-

オープン&クローズ戦略時代の大学知財マネジメント検討会
審議経過
※会議(資料・議事録含む)はすべて非公開
第1回 平成27年11月4日(水)
○ 非競争領域における知財マネジメントの方向性について
・「東北大学国際集積エレクトロニクスセンター(CIES)の知財マネジメン
ト事例」 大嶋洋一委員
第2回 平成27年12月11日(金)
○ 非競争領域における知財マネジメントの方向性について
・「COI等からみたマネジメントのポイント 共同契約時のポイント、留
意点や、マネジメント体制の在り方について」 小寺秀俊委員
・「NIMSの技術移転と知財戦略」 国立研究開発法人物質・材料研究機
構 青木芳夫外部連携部門長
第3回 平成27年12月24日(木)
○ 大学における知財戦略とマネジメントについて
・「産学連携によるイノベーションの創出」 株式会社東京大学TLO 山
本貴史代表取締役社長
・「沖縄科学技術大学院大学の取組に関して」 沖縄科学技術大学院大学 市
川尚斉 シニアマネージャー
第4回 平成28年1月19日(火)
○ 大学における知財戦略とマネジメントについて
・「大学の知財マネジメントの到達段階と今後の展開」、「ファンディングエ
ージェンシーの知財マネジメントの発展方向」 後藤吉正委員
○ 報告書(素案)について
第5回 平成28年 1月27日(水)
○ 報告書(案)について
(参考資料3)
-62-

オープン&クローズ戦略時代の大学知財マネジメント検討会
参考資料集
(参考資料4)
オープン&クローズ戦略時代の大学知財マネジメント検討会参考資料集
(各種データ等)
-63-

図表1 ポリシー・規程等の整備状況の推移
出典:文部科学省「平成26年度 大学等における産学連携等実施状況について」※大学等とは、国公私立大学(短期大学を含む)、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関法人を指す。
※平成21年度については調査していないため、線形補間して示している。※職務発明規程は、教職員のみのデータを示している。
・職務発明規程、知財ポリシー、産学連携ポリシー等を整備している機関は、増加している。
・「職務発明規程」を整備している機関数は、特許関係実績がある機関数を上回っている。
(参考)平成26年度特許関係実績がある機関は、275機関
※特許関係実績がある機関とは、当該年度に特許出願件数、特許権実施等件数、特許権実施等収入のいずれかがあった機関のこと。
236258
308325
344 353 357381
143171
207 218241 256 262 271
100120
158 168 184 199 203231
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
職務発明規程
知財ポリシー
産学連携ポリシー
2,313 2,563 2,755 3,256 4,225 5,197 6,570
9,396
14,016
19,825
25,945
31,002
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
国内単願 国内共有 外国単願 外国共有
図表2 特許出願・保有の状況
【大学等における特許出願件数の推移】
出典:文部科学省「平成26年度 大学等における産学連携等実施状況について」※大学等とは、国公私立大学(短期大学を含む)、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関法人を指す。
※平成15年度は、単独出願、共同出願の別がなく調査されている。
・特許出願件数はほぼ横ばいで推移しているが、特許権保有件数は増加している状況。
【大学等における特許保有件数の推移】
外国特許
国内特許
外国出願(共有、単願含む)国内出願(共有、単願含む)
2,462
5,994
8,527 9,090
9,869 9,435
8,801 8,675 9,124
9,104 9,303
9,157
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
国内単願 国内共有 外国単願 外国共有
-64-

2684
3901
579 884389 702164
336390
1091
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
国内単独 国内共有 PCT単独 PCT共有 各国単独 各国共有
図表3 特許出願・保有の状況
【大学等における平成26年度特許出願件数(件) 】 【大学等における平成26年度特許保有件数 (件) 】
・特許出願・保有について、大学単独のものが少ない状況。・また、特に単願について、外国特許出願・保有は、少ない状況。
米国
EPC
その他
外国出願(単願比率31%)
国内出願(単願比率41%)
PCT出願(単願比率40%)
外国出願(単願比率36%)
国内出願(単願比率47%)
出典:文部科学省「平成26年度 大学等における産学連携等実施状況について」※大学等とは、国公私立大学(短期大学を含む)、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関法人を指す。
10486
11972
3063
5481
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
国内単独 国内共有 各国単独 各国共有
図表4 実施許諾等の状況
※平成24年度本調査から、PCT出願を行い、各国移行する前後に実施許諾した場合
等における、実施等件数の集計方法を再整理した。
【大学等における特許権実施等件数及び収入額の推移】
出典:文部科学省「平成26年度 大学等における産学連携等実施状況について」※大学等とは、国公私立大学(短期大学を含む)、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関法人を指す。
・知的財産に関連する実施等件数・収入は増加傾向にある。・特許権の他に、マテリアル、著作権等の活用も進展してきている。
【大学等における知財実施等収入の内訳(平成26年度)】
543 543 639
801 774 986
891 1,446
1,092
1,558
2,212 1,992
185 477 1,103
2,409
3,532 4,234
4,527
4,968 5,645
8,808 9,856
10,802
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500特許権実施料収入
特許権実施等件数
百万円 件
-65-

図表5 実施許諾等の状況
【特許権実施等収入額の内訳(平成26年度)】【特許権におけるランニングロイヤリティの収入額の推移】
出典:文部科学省「平成26年度 大学等における産学連携等実施状況について」※大学等とは、国公私立大学(短期大学を含む)、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関法人を指す。
・特許権実施等収入の中で、ランニングロイヤリティは増加傾向にある。これまでの産学官連携の取組成果が、製品化に結実してきていると考えることができる。
256 305
378
274
458
541
648
1389
1738
2170
0
500
1000
1500
2000
2500
0
100
200
300
400
500
600
700
収入額
権利数
百万円 件
図表6 大学の知的財産・技術移転の状況の分類例
知財・技術移転の状況から、大学を3類型に分けて分析される。
「全大学の総合計」の増加は、「①増収傾向の大学」が牽引
「①増収傾向」+「②一時的増収」の大学で大半の収入を確保
全大学の総合計
①増収傾向(10大学)
②一時的増収(6大学)
③その他大学(百数十大学)
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
H21 H22 H23 H24 H25 H26
(千円)
-66-

図表7 実施許諾等の状況
【平成26年度実施許諾等の状況 (単願・共願の別) 】
件数【件】 収入【千円】
・実施許諾等収入に結びついている案件の多くは、単独出願のライセンス(実施許諾)である。単独の研究成果の知財に対する、産業界側からの期待が高いといえるのではないか。
出典:文部科学省「平成26年度 大学等における産学連携等実施状況について」※大学等とは、国公私立大学(短期大学を含む)、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関法人を指す。
47954540
248
1219
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
実施許諾
(単独)
実施許諾
(共有)
譲渡
(単独)
譲渡
(共有)
1,123,577
397,594
171,256
299,157
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
実施許諾
(単独)
実施許諾
(共有)
譲渡
(単独)
譲渡
(共有)
86
224 215
1,095
83 121
0
200
400
600
800
1,000
1,200
共有相手 国内
大企業
国内
中小企業
外国企業 その他 計
【千円】
共有相手以外
図表8 実施許諾等の状況
出典:文部科学省「平成26年度 大学等における産学連携等実施状況について」に基づく速報値
・特許権1件当たりの実施等収入は、平均18万円程度。1件当たりの実施等収入金額は、国内企業よりも、外国企業が高い。・共有特許について、共有相手以外への実施許諾は件数は限られているものの、所定金額で実施許諾されている。
相手先別特許権1件当たりの実施等収入金額(全案件)
相手先別特許権1件当たりの実施等収入金額(共有特許のみ)
共有相手以外
※ライセンス、譲渡の両者を含む
(左記全案件の内数)
全案件 件数(件) 金額(千円)1件当たりの金額(千円)
共有相手 4,389 375,510 86
国内大企業 1,593 322,323 202
国内中小企業 3,694 842,878 228
外国企業 448 319,767 714
その他 678 131,106 193
計 10,802 1,991,584 184
共有特許のみ 件数(件) 金額(千円)1件当たりの金額(千円)
共有相手 4,389 375,510 86
国内大企業 242 54,256 224
国内中小企業 646 138,839 215
外国企業 87 95,295 1,095
その他 395 32,851 83
計 5,759 696,751 121
※ライセンス、譲渡の両者を含む
-67-

図表9 知財関連経費の状況
支出内容内訳 【千円】 経費財源内訳 【千円】
【企業との共有特許の費用負担状況(件数)】
※補助金等: JST支援等を包含
出典:文部科学省「平成26年度 大学等における産学連携等実施状況について」※大学等とは、国公私立大学(短期大学を含む)、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関法人を指す。
※回答に誤答等があると考えられるところ、暫定値として把握しているため、概数として例示。
・特に、外国出願については、国の支援に依存する割合が大きい状況。・知財関連経費に対する間接経費からの支出が限定的である状況。
14
5453
1627
132
大学側が全額負担
企業側が全額負担
持分に応じて負担
持分と異なる割合で負担
【 特許関連経費の状況】
60%13%
2%
25% 出願
維持等
その他
※補助金等
47%
1%
19%
6%
2%
25%機関運営経費
直接経費
間接経費
ライセンス収入
その他
※補助金等
図表10 出願費用と実施許諾収入等の推移事例(特許群を創出した研究テーマ)
• 実用化に時間を要する先端技術分野のため、長期の特許維持が必要。出願等費用の財源として、全学経費から支出。⇒ 中長期的な視野での維持が必要。所定の出願等費用は必要不可欠。
• 厳格な維持放棄判断や共願先による費用負担により出願費用を抑制。⇒ 必要な権利の見直すは常に行う必要。
万円
件数
(累積)
(累積)
大学単願でも案件の位置付けにより、特許権の維持判断(維持期間等)は大きく変動する。- 基本発明を基にした受託研究等が継続する場合には、実用化可能性との関係で維持するケースがある。- 基本発明が共同研究に活用される場合には、費用負担がなくなれば維持される可能性が高い。- 単発の応用発明の場合には、ライセンス可能性に依存して維持する(プレマーケティングを踏まえて、総合的に判断)。
ある研究テーマにおける特許出願件数・費用と実施許諾収入等の推移
-68-

図表11 日米大学の特許の行方
日米大学の特許を比較すると、①米国は単願が多いのに対し、日本は共願が多い。②米国は中小企業・ベンチャーに委ねられることが多いのに対し、日本は大企業が多い。
日本の大学の特許の行方(2010年特許出願についての推定)
米国大学の特許の行方(2010年特許出願についての推定)
特許出願12,281
単願11,903
大企業4,159
中小企業5,921
ベンチャー1,823
共願368
国内特許出願6,490
単願2,596
共願3,894
大企業※
1,415
中小企業※
1,150
新規企業※
31
大企業※※
2,787
中小企業※※
1,106※ 最大値推計※※ 比率推計
我が国大学においては、全特許のおよそ65%が、何らかの形で大企業に委ねられ、およそ35%が中小企業に委ねられる。
東京大学政策ビジョン研究センター大学と社会研究ユニット政策提言 「知的財産制度と産学連携に関する論点」(平成27年3月)、及び知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会地方における知財活用促進タスクフォース(第1回)資料等から引用。
米国大学の特許の行方中小・ベンチャー等 63%程度大企業 37%程度
日本の大学の特許の行方中小・ベンチャー等 35%程度大企業 65%程度
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1991 1996 2001 2006 2011
米国 日本
(百万ドル)
(年度)
図表12 日米大学のライセンス状況の比較
大学技術移転サーベイ 大学知的財産年報2014年度版 より引用
【日米大学のライセンス収入の内訳】
【日本と米国におけるライセンス収入の推移】
・日本と米国では、技術移転活動が本格化したタイミングも異なるといった歴史的経緯や社会的背景もあり、現時点のライセンス収入額は日米大学間で差がある。
・米国においては、ライセンス収入に占めるランニング・ロイヤリティ収入の割合が大きくなっている。
・日本においても、産学官連携の成果の製品化実現がより一層進展していくことで、ランニング・ロイヤリティ収入が伸びていくことが期待される。 0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012
①ランニング・ロイヤリティ収入 ②株式関連での収入 ③その他のライセンス収入
日本 米国
(年度)
-69-

図表13 日米大学の産学連携活動の比較
分類公開特許件数
特許出願件数
ライセンス収入
ベンチャー起業数
特徴
カリフォルニア大学型 4.24 1.87 3.98 0.51 ライセンス収入が多い
スタンフォード大学型 4.58 3.42 2.43 1.20 特許出願等が多く、ライセンス収入が比較的多い。
MIT型 5.01 2.79 1.92 1.95 ベンチャー起業数が多い。
機関名特許出願1件当たりの研究費
(百万円/件)実施許諾等1件当たりの
ロイヤリティ収入 (万円/件)
カリフォルニア大学 233 2,721
スタンフォード大学 198 5,312
MIT 199 1,924
ハーバード大学 369 3,331
日本の大学A 48 18
日本の大学B 34 10
日本の大学C 47 15
・米国においては、産学連携活動の成果は、各大学の特色に合わせてライセンス収入、ベンチャー起業数と多様である。
・米国の大学においては、多額の研究費を費やして少数の特許出願がなされ、多額のロイヤリティー収入を生み出していると分析される。
株式会社旭リサーチセンター「日本及び米国の大学における産学連携活動に関する分析」(平成25年5月) より引用
【米国における産学連携活動の分析 (2004年データ)】
【日米の産学連携活動の比較 (研究費とロイヤリティ収入の状況)】
※ 公開特許件数、特許出願件数、ベンチャー起業数は、単位委託研究費当たりの件数(件/千万ドル)。ライセンス収入は、ライセンス1件当たりの金額(10万ドル/件)
(基礎的資料等)
オープン&クローズ戦略時代の大学知財マネジメント検討会参考資料集
-70-

21世紀のグローバル市場を特徴付ける社会経済思想としてのビジネス・エコシステム先進国と途上国を含む複数の企業が協調的に活動し 業界全体で収益構造を維持・発展させていく考え方。
*古典的なバリューチェーンでは、他社の影響力を減らして自社の付加価値を増やすモデル*ビジネス・エコシステムでは、自社も他社も共に付加価値を増やすモデル
*互いに繫がるエコシステムは、瞬時に巨大市場を創り、多くの企業にビジネスチャンスを与え、その波及効果がグローバル市場へ瞬時に伝播
*産学連携が生み出す技術を経済的価値に結びつけるにはダントツ技術を起点に、エコシステム構造を事前設計すべき
ビジネス・エコシステムの構造を事前設計するための経営ツールがオープン&クローズの戦略思想
●エコシステム:*本来は生物学における生態系を意味する単語
●ビジネスモデル:*1つの企業の収益構造を意味する表現
●ビジネス・エコシステム:*互いに繫がって付加価値を創り出す21世紀の経済環境を表現するために上記の2つを組み合わせたことば*2000年代から欧米で使われはじめた
図表14 ビジネス・エコシステムの概念について
小川紘一委員 講演資料より抜粋
図表15 オープン&クローズ戦略について
小川紘一委員 講演資料等を参考に文部科学省作成
自社のコア領域
オープン&クローズ戦略とは●オープンの例・論文等による公表・FRAND条件によるライセンス・標準化 等
●クローズの例・秘匿化・特許権等による独占 等
クローズ領域
自社と市場の境界
世界中のイノベーションをコア領域につなげる仕組み
境界を介してコア領域からオープン市場へ
オープン領域
・エコシステム構造を前提に、独占するコア領域(クローズ)を決め、・独占するコア領域パートナーとつながる結合領域に知財を刷り込ませた上で公開(オープン)、・コア領域からパートナーへ影響力を持たせる市場コントロールのメカニズムを、自社と市場の境界において、「伸びゆく手」として構築
パートナーに任せる領域(オープン)と自社のコア領域(クローズ)を事前設計するためには、オープン&クローズの戦略思想に基づいて、自社と市場の境界設計が必要。
独占と自由競争とを共存させるメカニズム構築がオープン&クローズの戦略思想
自由競争と独占が共存してはじめて・ 企業人のイノベーション投資に対してインセンティブが生まれる・ 研究開発に携わる人への自己実現や社会的栄誉に対するインセンティブが生まれる・ 技術イノベーションや製品イノベーションの連鎖が起こる
-71-

●開発される基盤技術をクローズ(開発者が独占)<リスク>1.研究戦略が特定企業の経営戦略や事業戦略に大きく影響される。*不実施リスクが高い、
2.市場の広がりが限定的、イノベイティブな産業に成り難い
3.研究者のイノベーション意識を削ぐ
<インセンティブ>1.企業側がビジネスチャンスと差異化を独占できる2.企業幹部を説得し易い
●開発される基盤技術をオープン(参加メンバー以外にも公開)<リスク>1.フリーライダーが多発、投資回収が困難、
2.技術が瞬時に国境を越え、生産性向上・雇用への貢献が限定的
3.企業研究者が企業幹部を説得できない(企業は本命の研究者を派遣しない)
<インセンティブ>1.研究成果を公表し易い、研究者のモチベーション向上2.世界中の国々の産業高度化に貢献(古典的イノベーション論)
図表16 オープン&クローズ戦略と産学連携について
小川紘一委員 講演資料より抜粋
産学連携が生み出す基盤技術
基盤技術との
結合技術
クローズ知財 オープン知財
競争領域非競争領域
独自のコア技術
オープン/クローズ知財
結合領域戦略1:ここを独占し、製品と市場を独占戦略2:この領域の知財を公開してパートナー
企業を増やしてオープンイノベーション、(結果的にオープン&クローズの構造が出来上がる)
クロスライセンス/調達等
図表17 プログラム・マネジャー(PM)による産学官連携マネジメント
小川紘一委員 講演資料より抜粋
■PMのミッション:お金を配分することではなく、いかにして①イノベイティブな製品を上市し、経済的価値を生み出すか②多くの収入をパテントプール / 大学へ還流させるかが期待されている。
■その為にやるべきことは、PM補佐を置き (超一流、非常勤)①創出する産業のエコシステム構造と競争ルールの事前設計②ビジネスモデル設計、事業化プロセスの概念設計③パテントプールへの資金還流の最大化, その為の知財マネジメント、契約マネジメント、広報マネジメント
④研究者・参加企業との信頼関係の醸成とメンテナンス⑤一連のマネジメントを通じてプロフェッショナル人財の育成を実践することである。
■研究開発の全てに責任と権限を持つPj-1, Pj-2, Pj-3,・・・・
PjL:プロジェクト・リーダー
PM:プログラム・マネージャー
-72-

図表18 ニーズブレークダウンの例(全固体電池)
出典:化学と工業① Vol.67-1 (2014年1月)射場英紀「サイエンスとイノベーションとのつながり」(p5-6)等関係資料等を基に作成
目標製品 出口課題 現象 基礎
全個体電池(LSB)
界面化学反応
不可逆Liがある
高出力(容量出力両立)
抵抗が高い
大容量
活物質が高抵抗活物質が絶縁性
活物質/電解質界面抵抗が高い
電解質・活物質界面の抵抗・・・
電解質が高抵抗Li拡散遅い・・・粒界抵抗
欠陥でのLiトラップ
副反応の進行(バルク)
界面での副反応
電子構造バンドキャップ異方性
界面イオン移動
界面電子移動
界面組成
個体内欠陥点欠陥、転移、置換…
・目標とする製品(例えば全固体電池)を実現するため、克服すべき課題、その出口課題を支配する自然現象がある。これは企業側にとって分析することが得意な領域である。基礎的な領域において、自然現象の解明、制御するための科学的アプローチがある。これは大学側が分析することが得意な領域である。
・大学側研究者も、企業側の出口課題や、対応する自然現象を一研究室で全てアプローチするのは限界があるところ、大学が組織的に研究者を動員し、組織対組織の連携を図ることが重要となる。
a.発明段階 :技術移転先・ビジネスモデルを想定した出願戦略b.プレマーケッテイング :候補企業に打診して出願可否判断c.出願の補強 : 企業意図を踏まえ追加実験などで出願を強化、外国出願の判断d.オプション ・マイルストーン契約 :事業化判断前でも、権利化等の各段階で支払いを受けるe.本契約 :マーケティングを継続、事業化判断を受けて本契約へ
a.発明時、教員に売り込先を聞く
b.出願前に企業に打診
一気通貫で担当
c.出願を補正して強い出願に仕上げる(1年以内)
d.マイルストーン契約‐優先的に特許を評価‐各段階で入金
e.事業化決定で本契約
図表19 大学特性を反映した一気通貫の知的財産マネジメント
マーケティングモデル(発明創出時点等の早期のタイミングで、企業等に打診してニーズ把握するようなプレマーケティングを行い、企業ニーズに合わせた強い知的財産権の取得・活用をすすめていくモデル)を実践し、研究開始・知的財産創出から、出願・権利化、技術移転までの一連の業務が適切に連動した一気通貫の知的財産マネジメントを行える仕組みが必要
一気通貫の知的財産マネジメントの具体的実践例
・発明時点から技術移転を目指して同じ担当者・組織が一気通貫で活動
・プレマーケッティングで出願要否判断・明細書強化・共同研究先探索
・オプション契約・マイルストン契約で特許登録前から収入を確保
-73-

※請求項数、中間処理手続の状況等に応じて、案件毎に費用は異なるため、一事例として示すものである。国内出願: 全140万円程度
PCT出願: 全50万円程度
米国出願: 全370万円程度
欧州出願: 全600万円程度
中国出願: 全400万円程度
各国移行1000万円以上
出願・権利化 約50万円・出願 約30万円・中間 約20万円
登録 約90万円 (約10年)
出願・権利化 約250万円・出願 約130万円・中間 約120万円※翻訳費用も含む
登録 約120万円 (約10年)
出願・権利化 約340万円・出願 約120万円(※)・中間 約220万円※翻訳費用はなし(米国で包含)
登録 約270万円 (約10年)
出願・権利化 約160万円・出願 約80万円・中間 約80万円※翻訳費用も含む
登録 約180万円 (約10年)
登録迄 数年
登録迄 数年
登録迄 数年
登録迄 数年
図表20 出願・権利化、登録費用の目安
図表21 プロジェクトの知財取扱いに関する合意書の作成項目例・協議ポイント
項 目 ※ 協議(合意)ポイント
目的等を協議。
定義 知財の取扱いに関する合意書の中のどの用語を定義するか協議。
知財運営委員会 ○
知財運営委員会を、他の委員会と独立して設置するかどうか。例えば、理事会や運営委員会等の他の委員会と兼用か、独立して設けるかどうか。可能であればその構成や権限を協議(プロジェクトに応じて最適なメンバー構成となるよう検討)。
委員会を具体的に開催するための手続きとして、その招集方法、議事運営方法、議決方法等を協議。
知財の専門家の専任
知財の専門家である知財コーディネータのような人材をコンソーシアム内に選任するかどうか。選任する場合は、その選任や解任方法。知財コーディネータの義務、業務範囲や権限等を協議。
秘密保持 ○
プロジェクト内での互いの情報流通等、プロジェクトの目的達成を推進すべく、情報管理の一貫として、どのような秘密保持義務を設けるか。秘密情報の大枠、秘密情報が使用できる範囲、その義務を担保するためにどうするかにつき協議。 秘密情報のランク等詳細の定義、誰に対して何を開示できるか等の詳細が必要であればその内容を協議。
技術開発協力者等の参加
○
プロジェクト外への秘密漏洩防止のため、どのような人材までを技術開発協力者として参加させてよいかを協議。
参加させる場合、技術開発協力者に義務づけるべき内容を協議(一例として他の技術開発従事者と同様の義務としている)。
成果の発表 ○
プロジェクトとして開示(発表)制限のルールを持つかどうかを協議。
外部への公表等の手順の詳細を協議。
知的財産権の帰属等 ○
○帰属を誰にするかを協議。 選択肢
① 知財の一元的管理をしない場合 ② 知財の一元的管理をする場合
a:特定主体(例えば、メンバー企業等により設立した株式会社、合同会社、技組等)に集中的に帰属、
b:特定主体と各メンバー企業等との共有、 c:各メンバー企業等に帰属しつつ、特定主体にサブライセンス
権付きライセンスを集約等。 ○その他:共有の場合の持ち分比率の決定方法を協議。
項 目 ※ 協議(合意)ポイント 知財の帰属を判断するための記録手段
○ 研究ノート、会議議事録等についての記録手段をどう確保するかを協議。
出願手続(発明等の届出) 発明等の届出を誰に届けるかを協議(たとえば、プロジェクトメンバ
ー、グループリーダー、プロジェクトリーダー、知財の担当者等) 知財運営委員会による発明等に関する審議等
○ 出願権利化・ノウハウ化、発明等の内容の確定等の重要な判断の主体を誰とするかを協議
決定の拘束力
審議の方法・ノウハウ秘匿の場合の運用、権利化・ノウハウ秘匿のともに不要とされた発明等の取扱いを協議。 知財運営委員会等の審議結果の拘束力の強さを協議。例えば、審議結果に対し一律従うか、決定後の状況変化等、やむを得ない事情等を考慮する程度とするかどうか等。
産業財産権等の実施、特に、不実施補償
○ 共有に係る知的財産の実施について協議。特に、不実施機関が含まれる場合についての補償料の取扱いを協議。
知的財産権(フォアグラウンドIP)の実施及び許諾
○ 本プロジェクトで生じた知的財産権(フォアグラウンドIP)の実施許諾をするか否か、有償又は無償を協議。シナジー効果の確保のために実施許諾が必要か、分野にもよるので協議が必要
知的財産権(バックグラウンドIP)の実施及び許諾
実施料等、実施権許諾の具体的内容を協議。 本プロジェクトの開始前からプロジェクトメンバーが有する知的財産権(バックグラウンドIP)の実施許諾をするか否か、有償又は無償を協議。
第三者実施 ○
バックグラウンドIPの特定方法、実施料等、実施権許諾の具体的内容を協議。 プロジェクト外の第三者の実施について協議。
知的財産権の移転等 フォアグラウンドIPのプロジェクト外の第三者に対する移転・専用
実施権や独占的通常実施権の設定可否。 脱退 ○ 本プロジェクト期間中に脱退したメンバーの取扱いを協議。 本プロジェクト終了後の取扱い等
秘密保持義務の有効期間の他、実施許諾等の終了後の延長期間、知財運営委員会機能をいつまでとするか、その他本合意書に定めた義務の延長等について協議。
本合意書の改訂 本合意書改訂の手続きについて協議。 損害賠償 本合意書内容に違反した場合の取扱いについて協議。
協議 本合意書に定めのない事項、解釈に関する事項や、本合意書の内容の疑義が生じた場合の取扱いについて協議。
紛争の解決 紛争が生じた場合の解決手法を協議。
※プロジェクト開始前に予め合意しておくべき事項に「○」を付記。
-74-

図表22 共同研究等の成果の取扱に関する検討(調査結果)
(1) 共同研究等の成果を単願あるいは持分譲渡するための課題我が国において、共同研究等の成果は大学等と企業の共有特許となる場合が多く、それに起因する問題が存在する。海外調査によると、米国、英国、ドイツ及びスイスでは、大学等と企業の共同研究等の成果が共有特許になる場合は稀である。また、共有特許の問題を避けるために、米国、英国やスイスでは大学等に権利を帰属させる、ドイツでは企業に権利を譲渡あるいは帰属させることが多いとの回答があった。
一方、国内の大学等及び企業の意識として、単願にするための交渉に時間を要するため、「共有特許のままとし、実施権等の交渉で詰めた方がよい」という意見が多い。契約交渉に時間や手間を要するより、研究を進めることが優先されている。共同研究等の成果を企業に帰属(持分譲渡も含む)させた場合に、大学等の研究への影響や成果が実施されない可能性があることが課題として挙げられている。
(2) 不実施補償について企業が非独占的実施権を得る契約をする場合でも不実施補償を求めている大学等では、企業との協議により、理解を得ている例がある。
企業が非独占的実施権を得る契約をした場合には不実施補償を求めない大学等もあり、その条件として大学等における第三者への実施許諾について事前の同意を契約に含めている(逐次同意を求めることは不要としている)例もある。この場合、不実施補償を請求しないことによる収入確保の代替手段としては、共同研究や受託研究の実施件数を増やすことや、第三者への実施許諾収入でまかなうなど、個々の共同研究等の契約に加えて大学等の組織全体での収益確保に向けた取組も見られる。
(3) 第三者への実施許諾に関する同意規定について大学等からの第三者への実施許諾については、企業が一定期間実施しなかった場合に、大学等が自由に実施許諾できることを認める場合が多い。企業が共同研究等の成果の周辺技術の特許を有しているため、第三者にとって、共同研究等の成果について大学等から実施許諾を得る価値が少ない場合もある。海外では、研究成果を活用促進するため、独占的実施権の期間やマイルストーンを定めることにより、企業によって実施されているかを判断、確認するための取決めを行っている場合があるとの回答があった。また、ドイツ、スイス及びフランスでは、共同研究等の成果を広く活用するため、企業に対して独占的実施権を与える分野・製品を限定し、それ以外の分野は他者に実施許諾できるように取決めを行っている場合があるとの回答があった。
(4) 共同研究等の契約雛型の運用について企業が大学等と研究を行う際、共同研究、受託研究に関わらず、大学の雛型を基本とする場合が多いとの回答であった。実際の契約交渉においては、雛型で対応できる項目と、個別に調整が必要な項目とが存在するため、研究契約雛形があることで交渉が効率的に進む面もある一方、契約雛形にとらわれすぎた調整は共同研究等の阻害要因となる可能性が指摘されている。
海外では、ガイドラインや契約雛形の例として、英国のランバードツールキット(下記調査研究報告書を参照のこと)、ドイツの連邦経済科学省が監修した契約雛形が存在する。契約雛形通りに契約が進まない場合があるので調整が必要となるが、これらのガイドラインや契約雛形は、契約の手続等に人員を割けない小さな大学や企業にとって各機関独自の契約雛形を作成する上で参考となっているほか、契約交渉が難航した場合の妥協点を探るため参照情報になっているとの回答があった。
平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「産学官連携から生じる研究成果活用促進のための特許権の取扱に関する調査研究」に関する特許庁提供資料に基づいて作成
図表23 共同研究等の成果の取扱の柔軟化に向けた方策(調査結果)
目的の組合せ
産学で関心の高い契約事項
共同出願す
るか否か
研究の公表
範囲
権利の帰属
海外出願の
対象国
実施権の種
類の選択
実施権の範
囲や期間
優先交渉権
の期間
実施料の設
定特許の費用
負担
第三者への
実施許諾の
同意の要否
第三者への
許諾条件等
イ 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇
ロ 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇
ハ 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇
ニ 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇
ホ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
へ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
凡例:「○」大学等と企業が関心の高い協議事項
共同研究の基本的な要件
研究対象分野(業種)研究段階(基礎・応用)バックグラウンドIP (大学側・企業側)研究予算規模当該企業と大学との共同研究等の実績発明の貢献度(持分比率)
大学等の判断要素
研究者の研究継続意向知財マネジメント(知財保有意向等)財政(特許関連収入)面財政(支出)面研究相手企業(大・中小・ベンチャー等)契約交渉対応企業における特許の社会実装状況
企業の判断要素
研究成果(特許)の活用意向 (独占の要否)特許の活用範囲や市場事業化までの見通し費用(支出)面契約交渉対応
●大学等と企業の共同研究等の主な目的と、関心の高い契約事項
●共同研究等の成果の取扱いに関する契約における判断要素
・大学等と企業における共同研究等を行う際に生じる懸念事項を解決するには、それぞれの立場や状況、研究成果の活用等の種々の条件を勘案する必要がある。
・そのため、共同研究等の契約を行う際に、大学等と企業の共同研究等に対する目的を双方が認識し、各種判断要素等を勘案して、契約事項等の内容(研究での公表、権利の帰属、実施許諾、費用負担など)を定めることが重要である。
※共同研究等の目的を果たすためには、前述のような共同研究等の成果の取扱に関する事項に限らず、幅広な視点をもって協議することも必要。
大学
企業教育研究 社会実装
自社での独占的実施
イ ロ
第三者も含めた非独占的実施
ハ ニ
技術シーズの探索・情報収集・ネットワーク形成
ホ ヘ
目指す方向性
平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「産学官連携から生じる研究成果活用促進のための特許権の取扱に関する調査研究」に関する特許庁提供資料に基づいて作成
-75-

(大学・公的研究機関等の取組事例)
オープン&クローズ戦略時代の大学知財マネジメント検討会参考資料集
図表24 プロジェクト形態別の契約事例
研究組織への参画連判状基本契約
機密保持契約書
中核機関等が中心になり,基本契約+弱い機密保持契約書を締結。その後、個々に共同研究・機密保持・知的財産契約書を締結
・契約書の内容の統一化が重要だが困難性を伴う
・個々の企業の知財と研究担当者の認識の差異もあり・契約に時間を要する(1年かかる場合も多い)
共同研究契約書
知財契約書
機密保持契約書
産
学
公的機関
1ST STEP
2ND STEP
共同研究契約書
知財契約書
機密保持契約書
大学等が中心になり,個々に契約基本契約書の統一化が重要
通常の2者による共同研究特定技術の移転や研究開発
1者からN者への技術移転1者の基礎研究等の研究成果を
N者が利用する場合
産 学
学
産
-76-

図表25 近畿大学における産学官連携の広報・評価の取組事例
産学官連携の成果の広報等
・産学連携の成果物である特許出願や新製品発売の際は、プレスリリースとしてマスコミに発表、場合によっては企業と共同会見をするなど、メディア露出・マスコミ報道を強く意識している。・マスコミ報道は大学の宣伝効果をもつものと考え、波及効果の大きい研究成果などを積極的にプレスリリースすることを推奨している。・広報部では、学部や研究所単位でどのような報道がどの程度あったかを調
査し、結果を部長会議等で報告、メディア露出度が高くイメージアップに貢献した教員を表彰する「KINDAI MEDIA AWARD」(特別研究費の交付)といった試みを行っている。こういった取組も近畿大学の独自のものといえる。
教員評価等
・教員の業績評価においても、評価項目には特許や研究成果の実用化といったように、産学官連携活動に関する項目が含まれている。特に社会活動との関係では、近畿大学の知名度や外部からの評価アップへの寄与との観点も大きく、そのような意味合いで産学官連携活動が取り上げられている。
・評価制度の実施とその結果の反映が、教員活動の一層のインセンティブとなるように試行錯誤が続けられている。
・近畿大学では、優れた成果を有する研究者でかつ必要と認められる場合に、講義や入試など学内業務の負担をなくして研究に専念することも配慮されている。
教員業績評価の指標において、顕著な業績評価の具体例の中で産学官連携に関する事項としては、「顕著な研究業績」のうち「特許等」で、「近畿大学での研究活動から生まれた新しい発明・発見が実用化され、社会から高く評価されて、大学に大きく貢献する特許、実用新案特許、ビジネスモデル特許等」とされている。また、他に、「社会活動における顕著な業績」で「産官学協同の研究開発等を通じて、産業界で成果をあげ、大学・学部等の評価を顕著に高めた業績」というように、産業界での成果と大学等の評価を高めることを関連づけて明示している。
文部科学省科学技術政策研究所Discussion Paper No.69「国立大学等における産学連携の目標設定とマネジメントの状況」(2010年10月)に基づいて作成
図表26 iPS細胞技術に関する知的財産マネジメント
自由競争
産業基盤として特許による独占を防ぎ、広く実施できるよう努める
●大学の研究成果の公共利用という使命と、独占的排他権である特許制度の思想とは対照的と捉えられるが、大学の研究成果をより広く利用を促進するために,特許制度を利用することも考える必要がある。
●研究開発を進めていくとiPS細胞に対する複数の特許が存在することになると予想され,大学が特許を保有しないと、結局他の特許権者によって独占されることになり得る。このような状況を考慮すると、大学も自ら特許を保有し、積極的に権利を制御し、開発を促進させることが必要である。※たとえば,保有している特許を利用してクロスライセンスにより他者の特許の実施許諾を受けることで,京都大学が作製したiPS細胞は自由に配布できる状況にしておくなどが考えられる。
●大学が特許を保有していることは、参入者にとって比較的安心感を生じさせる効果がある。
●iPS細胞そのものの作製にかかる技術は非独占として,iPS細胞を加工して最終製品とする技術は企業に独占実施させるという方法が考えられる。
「情報管理」Vol. 56(2013) No. 12「iPS細胞技術の普及における知的財産権の役割と挑戦」に基づいて、文部科学省作成
インフラストラクチャー
-77-

Cons 短期間(アップフロント)でライセンス収入はない(TLOは対価としてストックオプションで株として受け取る)Pros 技術の最大活用ができる(パッケージとしての特許価値を高める)
上場を果たした際にストックオプションを行使できる
図表27 ペプチドリーム起業に関連する知的財産マネジメント
☞創業者3人が初期投資、その後エンジェル(友人、肉親等)から資金を調達Pros 創業者・エンジェルの利益を最大にし、経営権を握るCons 経営は苦しい、基礎研究をする資金はない
☞第2次増資:キャピタルからの資金は1億円の投資で6%の株式シェアPros 経営権は握られないCons 継続的な資金調達はしてもらえない
☞運営資金は外部企業との契約による調達しか道がない☞TLOへのライセンス費用:ライセンス費用は低くセットしてもらうように交渉。最大の対価はストックオプション(新株予約券)で支払う。
☞大学研究者(菅教授)が、国内外の広告塔を担う。企業からの興味を惹き付け、契約のイニシャティブをとる。☞ペプチドリームと大学研究室(菅教授研究室)は共同研究契約を締結している。ただし、共同で公的研究費等の獲得は行わない。
☞ペプチドリームが進める事業には、教授及び大学研究室は直接関与しない(事業内容は、大学研究室でも全く知らない。)
菅裕明教授(東京大学大学院理学系研究科教授、ペプチドリーム株式会社Co-founder&社外取締役) 講演資料から引用
ベンチャー企業への技術ライセンスアウト (大学側からみたメリット・デメリット)
ペプチドリーム起業に関連する資金調達とライセンス費用
大学研究者(菅教授)とペプチドリームの関係(利益相反マネジメントの観点等)
空気圧駆動内視鏡ホルダー同社の最初の製品
図表28 大学発新産業創出プログラム(START)の取組事例
革新的技術による
メガベンチャーの創出
科学技術振興機構(JST)
研究者
事業プロモーター
ビジネスモデル
技術シーズ経営者候補
研究開発・事業育成
大学発新産業創出プログラムでは、ベンチャーキャピタル等の民間の事業化ノウハウを持った人材(以下、「事業プロモーター」という)ユニットを活用し、大学等発ベンチャーの起業前段階から、研究開発・事業育成のための公的資金と民間の事業化ノウハウ等を組み合わせることにより、リスクは高いがポテンシャルの高い技術シーズに関して、事業戦略・知財戦略を構築しつつ、市場や出口を見据えて事業化を目指す。これにより、大学等の研究成果の社会還元を実現しつつ、持続的な仕組みとしての日本型イノベーションモデルの構築を目指す。
東京工業大学での研究により得られた空気圧を用いて精密制御を実現する技術シーズを基に、執刀医の頭部動作により直感的に内視鏡を操作できる内視鏡操作システムおよび力覚定時機能を有する小型かつ高機能な次世代低侵襲手術支援ロボットシステムを開発
<期待される効果>
・事業プロモーターユニットと研究者が一体となり、専門人材(起業家、知財人材等)を含めたチームを形成しつつ、技術シーズの事業化に最適な研究開発・事業化計画を策定
・事業プロモーターユニットによるマネジメントの下、市場ニーズを踏まえ、マイルストン管理による研究開発・事業育成を実施
・企業価値の高い大学等発ベンチャーの創業とアーリー段階での民間資金の誘引
「気体の超精密制御技術を基盤とした低侵襲手術支援ロボットシステムの開発」開発期間:平成24年度~平成26年度研究代表者:只野 耕太郎(東京工業大学)事業プロモーターユニット:株式会社ジャフコ
<ベンチャー創出例>リバーフィールド株式会社・平成26年5月に設立・国産手術支援ロボットシステム等の先端的医療機器を事業化
研究開発支援
事業化支援
空気圧駆動内視鏡ホルダー同社の最初の製品
-78-

図表29 光触媒プロジェクトに関連するマネジメント事例
●2007年度~NEDO「循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト」がスタートした。プロジェクトの事前準備の段階で、開発目標を、①高感度光触媒材料の開発、②現場での効果検証と新しい機能の発現、③応用製品の開発に絞り込んだ。
●基礎研究を行う大学と、応用検討を行う企業の研究者が、当初から一緒に活動し、プロジェクトを支えたことが有効だった。光触媒材料を改良・量産化する企業、製品開発に携わる企業を一つのプロジェクトに共存させたことで、素材の開発・提供から部材への適用という流れがスムーズに行われた。
●最初から、プロジェクトに関わる全担当者たちに対して、2週間毎に東京大学に出向いてミーティングに出席するように、プロジェクトリーダー(PL)が要請した。それにより、企業間での重要な情報交換の場が構築された(人間関係の構築、企業間の信頼関係醸成等に成功)。
●厳格なルールを確立した上で、本音のディスカッションが行われるように配慮した。具体的には、定例ミーティングにて権利関係の問題が起こらないように、秘密保持と知的財産の取り扱いに関して各社契約を結んだ上で、さらに、議論の中で誰が真の発案者であったかがわかるように、ミーティングの内容をすべて録音するようにした。
NEDOホームページ「実用化ドキュメント」(室内でも使える可視光応答型光触媒を開発衛生的で快適な生活空間を提供 2014年2月取材)に基づいて、文部科学省作成http://www.nedo.go.jp/hyoukabu/articles/201318sdk/index.html
図表30 岡山大学における少数精鋭の基本特許管理の事例
共同研究領域
マグマ特許(構想)
コア特許 モジュール特許
システム特許制御技術特許
製造・製品特許
大学単独研究、知財形成
企業中心の作業、知財化
販売
マグマ特許(構想)の社会デビューイメージ
1.基本方針研究成果をもって、広く社会をはじめ産業界に貢献する。 大学が基本特許を確保し、これを多くの産業分野で活用いただく。
2.基本戦略①少数精鋭 ②マグマ特許 ③海外権利確保
3.大学が保有すべき特許について・大学における研究の成果は真理の発見であり、発明では無い。発明の目利きが携わったとしても、発見から導かれる発明
は、その時点で産業界が直面する課題解決に貢献できるものは僅かである。・しかしながら、発見から5~10年ほど経つと、その時の発明の真価が理解されることが多い。これはその間に研究が発展し、より身近な現象、応用として理解される為である。従って、身近な応用となった特許は産業界が個々の分野で活用するべきであるが、多分野にわたる基本特許は大学が管理し成果の貢献を最大化すべきである。この様な特許管理方法を岡山大学ではマグマ特許(構想)と呼ぶ。
4.マグマ特許(構想)のもたらすメリット等・マグマ特許は多くの場合コンセプト的である(新材
料の発見もその傾向がある)。そのため、マグマ特許は基本発明となるため、広範な応用分野を示唆する。
・産業界はマグマ特許を出発点として、各産業分野での自社製品の技術を開発し、得意分野での社会還元を果たすことになる。
・マグマ特許を大学が保有することは、基礎研究成果による社会貢献の最大化を果たすメリットに繋がる。・この様に、マグマ構想(特許)は広範囲な産業分野に強い影響を与えるため、大学が保有する単独特許の影響評価指標を高める事が可能となる。
-79-

図表31 沖縄科学技術大学院大学の特許出願スキーム
OISTの出願業務
仮出願スキーム導入以降、OISTの特許出願件数は増加
* 発明発掘活動: 様々な形の情報収集(PIインタビュー、広報の研究紹介アーカイブ、毎週木曜日に開催されるティータイムにおける情報交換、民間団体からのグラント応募補助)
* 発明の啓蒙活動と動機づけ: 学生向けの実務者セミナー以外に研究者や教員向けの知財セミナー、ギャップファンド、起業家育成プログラム、知財ポリシー
* 特許出願の流れ: 発明開示の後、評価会議(外部有識者、弁理士、分野毎の実業家等がボードに参加)を行い出願判断。出願には、米国仮出願制度を活用。
図表32 大阪大学における臨床試験データの移転スキーム
●治験を引き継ぐ製薬企業等から医師主導治験で得られた臨床試験データの移転を要請された場合、無償での移転では、大学等が企業に便宜を図ることになるため、大学等は製薬企業等に適切な対価の支払いを求めることが合理的である。
●ノウハウはノウハウ許諾契約、非臨床試験データはMTA(研究成果移転契約)で成果の移転を行っているが、臨床試験データの創出・作成には、多数の教職員等の関与があり、加えて創作の概念には馴染まないものである(成果有体物は、作製者の特定容易)。そのため、臨床試験データを現行の成果有体物規程で取り扱うのはその範疇を超えている。
●「臨床試験データ移転および使用許諾契約」を結ぶため、新たに臨床試験データ移転規程を定め、適正に運用する必要がある。医師主導治験で得られる臨床試験データ(いわゆる、治験データ) は、大学に帰属する(なお、発明規程の対象等は除外。) 。
●大学は、当該治験データの移転先に対して、日本及び外国における対象となる医薬品・医療機器の開発、製造、販売、輸入、輸出その他一切の行為に関わる再使用許諾権付き独占的使用権に関する第一選択権を許諾する。当該治験データを使用して、移転先が日本又は外国において医薬品及び医療機器の製造販売承認の取得を目的とした臨床試験を実施する場合、移転先は当該治験データの使用権行使の対価を大学に支払うものとする。
●当該治験データにより収入を得た場合は、研究室、治験の支援センター、部局、本部等に還元する運用としている。
医師主導治験に基づく臨床試験データ (いわゆる治験データ) の移転
医師主導治験で得られる治験データには、当該治験に基づき大学が取得した生データ、生データをもとに編集された治験申請用データ、及び大学が当該治験に基づき創作した全ての資料その他一切の学術・産業上、財産的価値のある成果が含まれる。ただし、当該成果には、発明規程等の対象は除外される。
-80-

図表33 東京医科歯科大学の学術指導契約制度の導入
≪学術指導開始までの流れ≫
●『学術指導契約』は、既存の共同研究・受託研究では困難であった技術指導、監修、コンサルティング等の産学連携案件について、従来の時間外兼業(大学の職務外)ではなく、本務(大学の職務)として対応する制度である。●従来から本学研究者は、企業等から各種相談等を受けて専門的な知見の提供を日常的に行っていた。その際、契
約・報酬なしに情報開示することが多く、知財にあたる情報を含む可能性もあった。本制度導入により適切な契約を締結することで、貴重な研究内容・知財を保護することを可能とした。
●これまで契約等で保護が困難であった、高度な知見、アイデア(医療現場のニーズ含)、ノウハウ等を、本学の知的財産として保護することが1つの目的である。また、新規の共同研究あるいは技術移転等を開始する前に、本制度を利用し、実施可能性を検討・確認することも可能にしている。●本制度が契機となって、共同研究契約等産学連携活動の件数・金額(大型・長期含む)の増加が期待される。
○従来より、個人兼業としてコンサルティング活動はなされているが、それを否定するものではなく、あくまでも業務としての行うコンサルティングと位置付け。
○共同研究等は一定の期間設定があるが、本取組では、時間単位の産学連携活動をも対象する他、報酬の額等にも上下限を設けず、柔軟な対応がとれる形。
○産学連携研究センターと機構事務部が、研究者と企業等との間を仲介する。候補となる研究者が不明の場合、産学連携研究センターが企業の要望を聞き、候補研究者の探索からサポートしている。
平成26年度 平成27年度(平成28年2月末時点)
契約件数 8件 24件
受入金額 196万円 472万円
図表34 電気通信大学におけるソフトウェアライセンス実用化事例
<育成>
●ニーズを満たさないソフトウェアは売れない。
・企業のニーズは、秘密保持条項のもとで共同研究を通して把握。
・サポート、メンテナンスも共同研究の範囲で対応。
・商業ステージでは、ベンチャー、ベンダーに技術移転し、これらの企業が対応。
・大学のツールレベルのソフトを、育成過程を経ずに、ベンダーが直接プロダクト開発してもうまくいかない(死の谷)。ベンダーも、エンドユーザの企業のニーズを把握して開発できないため。
エンドユーザーが企業の場合のソフトウェア育成モデル (適切なニーズ把握が重要)
●育成(実用化)段階でのソフトウェアの作成方針・育成段階では、共同研究先企業の課題解決にソフトを使用してもらい、そのフィードバックをもとに大学が企業のニーズに沿った研究開発を行う。
・育成によってソフトの中核部分(幹)が完成し、ユーザ企業がソフトの価値を認め自社用にソフトのカスタマイズ(改変)を希望する段階となったら、企業のカスタマイズ版(枝)を作成する。
●ソフトウェアのライセンスに向けて・特許権と著作権(ソフトウェア)をセットでライセンスすることにより、ソフトウェアの価値を高める。
・シミュレーションは、企業が抱える現実の課題に対応するためのモデル改良に長期間を要する。育成は、機能が未完成な大学のソフトに対応する余裕のあるパワーユーザの確保が不可欠になるので、デファクトになりそうな候補のみ対応するのが良い。・シミュレーションソフトウェア以外は、ポテンシャルユーザでも使用する可能性あり。
-81-

事例1: 産連部門が独自財源を持ち、その中から独自裁量で予算確保。
事例2: 共同研究の間接経費を、産連部門の活動予算に充当。知財・技術移転予算をその中から独自採用で確保。
事例3: 大学本部予算から知財・技術移転予算を確保。本部や役員の理解があり、予算を確保。
図表35 知的財産関連の財源確保の事例
事例4: 間接経費の所定割合(10%)を知財・技術移転予算として確保。
事例6: 潜在発明者(研究者、エンジニア職等) 1人あたり70万円規模(総予算の1%程度)と、所定規模の知財・技術移転予算を継続的に確保。合わせて経費削減策も講じ、実施料収入拡大も実現。
大学・研究機関において、知財・技術移転予算として、所定の規模を確保している事例として、以下のような取組がある。
事例7: 自学の技術分野別の出願件数、ライセンス件数等の実績を分析し、求められる特許ポートフォリオを検討し、必要予算を大学執行部と交渉。
事例5: 共同研究費の中で、特許経費を確保した契約を締結(パテントサーチャージ)。
図表36 東京大学における知財戦略の策定、特許費用算出の基本的考え方
STEP1. 基本的な考え方の確認知財戦略を検討する前提として、大学としての特許出願・技術移転活動の位置づけについて確認。
STEP2. 特許出願・技術移転活動実績の分析と強化策の検討
2.1 分野別出願・技術移転の分析、強化策の検討等①分野別出願・技術移転実績の分析
・分野別国内出願件数と外国出願率、分野別のライセンス成功率と契約成立時期、上記の年度別推移等により、これまでの分野別出願・技術移転実績の分析。上 記分析により、出願件数の多い分野、ライセンス成功率の高い分野、出願件数とライセンス成功率の関係、出願からライセンス契約成立までの期間等につき分析。
②上記分析から得られる技術移転実績の向上のための強化策検討、出願・権利化、権利維持要否の判断基準の設定
2.2 ライセンス先企業の分析、強化策の検討等①ライセンス先企業の企業規模によるライセンス実績分析②上記分析から得られる技術移転実績の向上のため強化策検討・上記分析結果を踏まえ、また大学の研究成果の性質、置かれた環境等を考慮して、今後更に注力すべき対象企業層を設定。
・上記企業向けの出願・保有特許ポートフォリオ、および技術移転活動を強化するにあたり、出願・権利化、権利維持要否の判断基準を設定。
2.3 分野別・ライセンス先企業別の分析以外の観点からの強化策を検討例えば、大学としての特許出願・技術移転活動の位置づけ、大学の特徴、あるいは技術動向や特許を取り巻く状況等から、考え得る強化策が無いか検討する。
2.4 その他検討が必要な事項今後の予算圧迫要因への対策等、その他に強化すべき必要事項が無いか検討する。
STEP3. 上記2で検討した強化施策による今後の単独特許ポートフォリオと活用の見込みこれまでの分野別出願、ライセンス実績、および2で検討した強化策により予想される出願等の増加件数、増加率を踏まえ、出願・保有特許件数、分野別保有特許ポートフォリオの構成、ライセンス件数等の今後の定量的予測を行う。
STEP4. 上記検討に基づく、必要な特許費用の検討
-82-

図表37 東京大学における出願判断事例
●外国出願の判断・実用化・事業化(活用)の観点からの外国出願の必要性(ライセンスの可能性、企業の実用化意欲の大きいこと)。・出願国として、通常はPCT出願を基本。・共同出願相手機関、ライセンシーの意向を尊重して決定。・「優先権主張出願報告書」の採用。
●各国への国内段階移行・基本的に、この時点までにライセンス契約、またはその合意ができていなければ移行しない。・審査請求の要否を合わせて「27ヶ月報告書」の採用。
●権利化・維持の要否の考え方(見極めのポイント)・出願後の市場・技術動向の変化、ライセンス活動の結果、および見極め以後のライセンス可能性を反映。・ライセンス済みのものはライセンシーの意向を尊重。
優先権主張報告書
・国内出願から10ヶ月を目処に、優先権主張出願、外国出願の要否に関する見解を、マーケティング状況、追加データの有無等を踏まえて、東京大学TLOより知財部に報告。発明者の同意の有無も確認。・企業との共同出願は、企業の意向を尊重。・知財部で、当該報告に基づき、優先権主張出願、外国出願の要否を決定。・基本は活用の可能性(権利として活用するため、何故外国出願が必要か)。
27ヶ月報告書
・PCT国内段階移行と審査請求の要否を同時に検討・判断
●予めマーケティングを実施し、ライセンス可能性等を踏まえて出願判断を行う運用。●基本的に、PCT出願のうち、各国の国内移行段階までにライセンスが契約成立又は合意形成できているものを、移行する運用としているところ。●なお、ライセンス成立案件について分析したところ、出願から1年以内(優先権主張出願期限)にライセンスが決まったものは、ライセンス成立案件のうち60~70%程度。外国出願したもので優先権主張出願期限以降にライセンスが決まったものは、ライセンス成立案件のうち10%程度。
出典:大学等産学官連携自立化促進プログラム 国際的な産学官連携活動の推進報告会(東京大学) (平成25年1月16日)「海外特許はどう取るべきか -海外特許の戦略的取得:考え方と実績-」 東京大学産学連携本部
図表38 沖縄科学技術大学院大学におけるPOCプログラム
POC (プルーフ・オブ・コンセプト)大学が所有する知財の価値を向上させるためのプログラム
資金支援に加え、以下サービス等を利用可。•メンターシップ採択者には外部のイノベーション専門家(EIE) がつき、技術指導およびプロジェクト全体の指導を提供。EIE は、技術開発と産業界での経験を有する世界的専門家。
•セミナー / ワークショップ起業、ビジネス、プロジェクト管理、知的財産に関するテーマのセミナーやワークショップに参加可。
•プロジェクト管理POC プログラムのスタッフは、プロジェクト期間中の計画、運営、問題解決において参加者をサポート。
•ビジネスおよび市場情報技術の利用分野をターゲットにした市場調査データを利用可。OISTプルーフ・オブ・コンセプトプログラム: 2015年度パイロット
資格要件:• 発明の開示
資金:• 500万円 – 1,000万円/プロジェクト• 外部の技術開発および産業界専門家によるレビュー
その他のサービス:• 外部のイノベーション専門家 による指導(1人/プロジェクト)• プロジェクトマネジメント• 起業家教育• ビジネスおよび市場動向に関する情報提供
-83-

■地域圏大学は「人」に依存■分野に応じて,1人で or チームで■出口・活用を見据えて
(ビジネスモデルを描きながら)
一気通貫型
■理想的なモデル・サイクル■地域圏大学には難しいモデル(人材)■ニーズとは?(入口の多様化)
ベルトコンベア型 7名
7名
4名
図表39 三重大学における社会連携と技術移転
三重大学の社会連携(産学官連携)の考え方1.三重大学には、三重地域圏の「知の拠点」として機能する使命がある。このため、「社会連携部門」を教育・研究部門と対等な学内組織とし、大学知財の社会還元推進の司令塔と位置付ける。
2.三重大学としての社会連携の目的を明確にし、地域社会と共有させる。3.地域で活動する人々が分け隔てなく集まり、協働作業ができる「地域のたまり場」として機能できる唯一の機関は「地方大学」である。
技術移転活動
「研究の活性化」、「社会貢献」のために、知財を活用。
図表40 関西TLOにおける営業活動の具体事例
☆特許出願~営業開始
事業化
基本特許(大学)
企業
①ライセンス
②共同研究スタート
F/S本格R&D
製品開発
連携する企業は、どぶ板の営業で見つける。
・100社程度、営業をかけて1,2社がライセンスに至る。・その後、事業化検討がスタートして、製品化・事業化に至る。
①基本特許②大学と企業の共同発明
経験年数により身に付くスキル・サイエンスの知識・マーケティング・知財・財務 など
採用時/育成時に重要なスキル・コンタクトスポーツ・累積経験・発明への思い
ライセンスアソシエイトには、以下のようなスキルが必要となる。
-84-

特許出願(単願)
図表41 企業と大学が早期パートナーシップ構築した企業の戦略事例
発明創出(単独発明)
技術移転・事業化
パートナー形成の早期化
大学 企業
企業としては、自社の競争力強化につながる技術シーズ・パートナー(研究者、大学等)を、グローバルに、日々探索している。
【企業と大学が早期パートナーシップ締結事例】
●大学が単独で創出した発明について、出願明細書を作るときから企業が積極的に参加する。それにより、グローバルに活用できる、強い権利を構築することができる(強い権利範囲の形成、グローバルな出願国選択等)。
●大学が知財マネジメントを強化し、積極的に実行していく際、企業と伍して競争できる知財組織、ビジネスセンスある人材が必要となる。しかし、民間企業の力を活用することで、効率的に、強く有用な権利化が実現できると考えられる(権利化段階から企業が関与することの効用)。
●権利者は大学としつつも、実質的には企業が出願手続きを実行する。企業にとって、単願・共願の別や権利帰属にこだわりはなく、事業の自由度・独占性が担保され、事業に資する形であることが重要である。事業化が成功し、イノベーション創出を実現した際には、適切な実施料を支払うことが可能になるので、企業・大学双方にとってwin-winの関係を構築できる。●大学が保有する知的財産権のライセンスは、競合他社を避けるように業種を分けて広くライセンスすることは可能である。
知財管理事務 (①期限管理、②費用管理、③契約管理、④各種調査対応等) の効率化
図表42 電気通信大学における知財業務管理
日本出願(原出願) 国内優先
PCT出願 PCT経由日本
日本分割1
日本分割2PCT経由
米国
PCT経由中国
PCT経由欧州
英国
仏国
台湾
P15-001 P15-001P
P15-001PCT P15-001R P15-001R-D1
P15-001R-D2
P15-001CN
P15-001US
P15-001EP
P15-001EP-GB
P15-001EP-FR
P15-001TW
(1)知財管理システムの導入・市販の知財管理システムは高額である。使用している場合においても、別途エクセルやアクセスで必要な情報を管理している状況(複数のソフトウェアを使用)。・特に、費用管理(出願費用、予算等)、JST外国特許出願支援関係(申請状況、請求情報)、ライセンス契約管理、補償金配分関係(実施料等)について、別途データを管理している状況。・国立大学の知財管理事務に適したシステムがない状況 (権利化の担当者と費用管理の担当者が違う部署、市販システムが大学特有の費用管理に対応していない、ユーザーライセンスの制限等の要因)。・電気通信大学においては、上述の問題を解決するような、知財管理システムを導入し、事務の効率化を実施している。
(2)情報の電子化・電子化を通じて、ペーパーレス化、情報のアクセス性向上、セキュリティ向上等が図られる。
・例えば、発明届出書、共同出願契約書、共同研究契約書、実施許諾契約書、譲渡契約書、譲渡証書、承継通知書、庁書類(明細書等)等が電子化されている。
(3)ファミリー管理番号の導入・ファミリー管理番号(一つの発明がある国へ出願された後に、その出願を基に優先権を主張して他の国へ出願された親子・兄弟関係のような出願のグループに付される共通の番号)を適切に管理。関連出願を可視化することで、以下を実現可能。権利化担当者 ⇒ 番号を見ただけで当該特許の状況を把握可財務関係者 ⇒ 資産計上の際、費用の計上漏れを防止可
上記取組を通じて、知財管理事務の効率化を図っている。
-85-

図表43 株式会社テクノネットワーク四国における金融機関との連携事例
●企業訪問(地銀ネットワークの活用)・「地域中小・中堅企業の課題解決型産学連携」を推進。新規事業に挑戦、今後ビジネス構築により事業化を目指す。・「徳島大学のターゲット企業」の明確化。
●ビジネスプランニング・「研究開発」と「ビジネス構築」の両面から地域中小・中堅企業をサポート。・地域の中小・中堅企業の弱みを解決。
●「企業訪問・課題抽出~事業化まで」、両機関の得意分野を活かし、補完関係を構築阿波銀行は、「企業ネットワーク、ビジネスプランニング、資金計画立案力など」を提供。テクノネットワーク四国・徳島大学は、「技術課題抽出・課題解決力、公的研究費獲得能力等」を提供。大学と地方銀行の補完関係が重要であり、大学主導や銀行に任せきりでは成功しない。
知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 地方における知財活用促進タスクフォース(第2回)平成27年3月4日 会議資料より抜粋
企業訪問 課題抽出研究者
とのマッチング
公的研究費獲得
ビジネスプランニング
事業化
阿波銀行企業紹介 認証支援機関確認
書作成、つなぎ融資ビジネス開発 新規事業への融資
TLO・大学企業同行 企業の技術課
題を抽出研究者探索マッチング
提案書作成ロビー活動
ビジネス開発会議出席
地域企業の意識変革と大学と企業を繋ぐシステム構築 「産学金連携人材育成モデル」
①山形大学「学金連携プラットフォーム」の構築・組織化・山形大学と12地域金融機関による学金連携プラットフォームの構築
・金融機関を対象としたコーディネータ研修の実施(事業・技術目利き研修を、山形大学が金融機関に対して実施)
②地域企業を対象とした高度人材育成講座の実施
図表44 山形大学における金融機関との連携事例
数値は26年度実績
地域企業
山形大学地域金融機関 12機関
山形大学認定産学金連携コーディネーター
国際事業化
研究センター
教員等
相談
技術等の高度な相談
調整
対応①
技術相談対応等
664社1,361件
10社22回
183名
学金連携プラットフォーム
経営系の相談
対応②
対応③
大学以外の専門家派遣 130社312回
対応③
-86-

一般財団法人工業所有権協力センター(IPCC) 「大学知財活動助成事業」の助成対象知財活動として、実施されている。
Kyushu Technology Collaboration(KTC)大学合同新技術説明会・技術相談会
【主催大学】九州工業大学、九州大学、熊本大学
【参加大学】
佐賀大学、大分大学、宮崎大学、鹿児島大学、北九州市立大学、福岡大学、九州産業大学、産業医科大学、久留米大学
・3大学(九州工業大学・九州大学・熊本大学)が連携して主催し、九州各県の大学も参加。
・九州エリアの多様な大学が連携して、「大学合同新技術説明会・技術相談会」を開催。今後も継続的に実施していく予定。
・企業の課題解決に向けた個別相談も同時開催。複数の大学が協力して課題解決を促進。地域活性化も目指す取組。
・従前、3大学で実施していた知財研究会を、各大学に参加を呼びかけ、今後、オール九州の知財研究会に拡大する予定。
図表45 九州地区における複数大学連携事例
●マーケティングモデルの確立技術移転を活発に行っているTLOが採用している、マーケティングを積極的に行って技術移転を行うモデルを早期に確立するべきである。
●共同研究の発掘や研究マネジメントにおけるURAとの連携一研究室⇔企業 から 大学(複数研究室)⇔企業 へ。大学は、学内の研究テーマの把握を行い、企業NEEDSとマッチングor提案する。URAと連動し、共同研究マネジメントも行う。マイルストーンの設定、経理処理、関連特許の把握や情報機密管理、報告書作成まで行う。
●GAPファンドの運営に対するコミットメント欧米の大学における、GAPファンド、POCファンドは、基礎研究の事業化に向けた研究を促進させるためのファンドである(いわゆるベンチャーファンドとは異なる) 。比較的アーリーステージの大学の技術をコマーシャライズの可能性が高いもの
を技術移転機関が選定し、発明者とアプライするものである。通常は、3段階程度にフェーズが分かれ、選定された研究は一定期間でのマイルストーンが設定され、それをクリアすれば次のステップに移行するスキームをとり、成果が出れば、ライセンスやベンチャー起業につながる。我が国の大学においても、これを全国で推進する必要があると考えられる。
●大学発ベンチャー創出に向けたベンチャー・キャピタル(VC)との連携大学発ベンチャー創出を加速していくために、イノベーション・エコシステムの中で、ベンチャー・キャピタルとの連携を強化していくことで、イノベーションを加速化していくことを考えていくべきである。
●自主運営が困難な大学知財本部に対するマーケティング支援や人材育成技術移転のプロとして世界基準になりつつあるRegistered Technology Transfer Professional(RTTP)を、我が国においても育成することが急務である。
また、TLOが大学を支援し、人材育成をサポートしていくことも重要ではないか。技術移転協議会(UNITT)等において、情報共有の場、人材育成の場として位置付けていくことも重要である。
図表46 TLOが目指す方向性の例
東京大学TLO 山本貴史社長 講演資料より抜粋
-87-

図表47 関西TLOにおける人材育成の取組事例
タイプ 形態
常駐 ・1担当者の週3~5日の各大学勤務※月2回の関西TLO本社勤務(進捗確認)
・他メンバーの適宜フォロー(同行、指導、情報共有)
常駐その他
・1担当者の週3日の各大学勤務・複数担当者のパートタイム担当
人材育成型
・週0.5~1の各大学対象者を関西TLO本社へ派遣-対象者の営業トレーニング-関西TLOリソースの活用
・トレーナーによる適宜フォロー(同行、指導)・社内勉強会(マーケ、契約、理念教育など)
●連携の具体的な業務形態
●人材育成型 技術移転の目標
①大学の産学連携人材の育成
②関西TLO他大学の営業先企業に、対象大学の案件を紹介する。
③関西TLOの他大学案件との連携可能性を探る。
タイプ 長所 留意点
従来型(常勤等)
TLOの人材を大学に派遣
・委託費のみで、基本的にはおまかせ対応ができる。
・委託費が高い。・TLOの人事異動があるため、担当者の定着は不透明である。
人材育成型
大学側の人材をTLOで受入
・自学の将来的なマーケティング人材を確保できる。・TLOの営業ノウハウの活用
・育成に2年程度かかる。・成果の成長カーブは緩やか。
●大学とTLOの連携モデル
図表48 企業における共同研究等のテーマと規模の例(一企業の事例)
技術
既存 新規
市場
新規マーケティング・
テーマ新規事業開拓テーマ
既存既存事業強化テーマ
新グレード・新製法開発テーマ
イノベーション・マトリックス
包括契約 個別契約
海外大学
50~300 10~20・担当研究者(ポスドク)が明確・スケジュール管理されている
国内大学
10~50 1・教育の一環として学生が研究実務を担う場合が多い・スケジュールと成果が不透明
・副学長や学部長が責任者・成果報告会(1回/年)を開催
・四半期毎に社内説明できるだけの研究の進捗を把握
・通常の競争意識に加えて、包括契約の範囲内でも競争意識が醸成されうる
・教授との信頼関係に基づく(国内は、いわゆるお付き合い型の共同研究も一部存在)
・国内大学との共同研究では、四半期毎の研究進捗を把握可の案件は一部
・研究者の競争意識は、同じ領域のアカデミアとの間で形成
大学との共同研究の規模とその差
●研究開発テーマは、対応部署に応じ3つに大別。基本的にはテーマの位置づけとステージによって判断。・事業部テーマ・本部テーマ・コーポレートテーマ(全社)
※1件あたりの契約額の概略イメージとその差の推定。国内大学(個別契約)の研究金額を基準にした場合の相対的な規模。
規模は、期待される成果の大きさと早さ、確度による
●海外大学と国内企業との共同研究成果取扱い事例・大学単独の権利帰属。a) 通常実施権の場合(サブライセンス権あり)特許出願・維持費の企業側負担。通常実施権が供与。
b)独占実施権の場合(サブライセンス権あり)希望する場合は独占可。追加の実施料が必要。ただし、不実施補償等はなし。
-88-

図表49 共同研究等の柔軟性のある共同研究契約の海外大学事例(調査結果)
●海外大学において、研究成果が企業により実施されないことを防ぐための対応としては、独占的実施権の有効期間を定める、あるいはマイルストーン(いつまでに特許出願、いつまでに商品化等)を定めるといった取決めを行っているケースがあった。
●研究成果を広く社会実装するための対応として、ドイツ、スイスやフランスでは大学等が企業に独占的実施権を与える分野・製品を限定し、それ以外の分野では他者に実施許諾できるように取決めを行っているとしたケースがあった。
●海外大学において、実施料の設定については、売上に対する実施料(ランニングロイヤリティ)に加えて最低補償料を設定することにより、企業への事業化を促すとともに、企業が事業化できない場合でも大学等が収益を確保しているケースがあった。
●米国、英国等においては、特許を大学に帰属させ、特許関連費用は企業が負担する形が多くみられた。
●英国においては、大学はランバートツールキットを参考にした独自雛形を持っているケースが多い。ランバートツールキットは、交渉が難航した際の妥協案として参照される場合もある。
●海外大学においては、共同研究等の成果の取扱に関する契約は、研究開始時(研究開始前)に実施料等も含めて定めておくことが多い。特許の実施料等の価値は研究開始前に不明瞭な場合もあるため、その場合にはある程度の幅を持って定め、契約を見直すことを条項に盛り込むこともある。
海外の大学等において、共同研究等の成果の取扱いを以下のように行っている事例が得られた。
平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「産学官連携から生じる研究成果活用促進のための特許権の取扱に関する調査研究」に関する特許庁提供資料に基づいて作成
図表50 柔軟性のある共同研究契約の事例
本格的な組織間連携の契約例総額数億円規模、複数年の共同研究契約において、以下のような多様な要素等(教育・研究活動等の研究成果以外の要素)を含む契約事例がある。・組織連携活動・共同研究費(複数部局で展開)・インターン費用(大学院生数名)・奨学金(大学院生数名)・企業幹部による出張講義(複数回)・大学が行うサービスに応じた研究経費(間接経費等)の交渉・大学内での企業側の種々の活動を許容
柔軟かつ多様性のある契約締結のために、大学に求められるスキルの例・企業側の目的・戦略を理解して、大学における戦略的な連携を企画できる力 (真の目的の把握)・雛形方式でない柔軟性ある知的財産契約の交渉力 (企業側の多様な観点からの要求に対する交渉)
・適切な利益相反マネジメントに基づいて、連携方式の多様性を許容するマネジメント力 (規則等による画一的な制限・禁止等の対応ではなく、柔軟性あるマネジメントを実行することで、大学側の契約の自由度を増すための方策)
企業側へのメリット提供の例 (共同研究契約の締結にも影響を与える得る要素)・よい研究成果の創出に対する期待度 (共同研究に従事する大学の人員、過去の実績等)・大学側の体制に対する信頼性 (例えば、技術情報管理に対する安全性)・企業側研究者受入れ時の待遇 (大学のインフラの利用、教育機会の提供等)・成果報告会等を通じた、他の研究成果を知る機会の提供
-89-

図表51 権利化対象案件の選択事例等
●発明のカテゴリーに応じた権利帰属先の切り分け (材料:大学側、装置:企業側)
共同研究契約においては、事前に共同成果物の帰属について各々が興味ある領域を提示し、原則論を定めておくことが有効である。
たとえば、新しい材料を用いた加工技術を大学と装置企業が共同研究テーマとする際に、研究対象として興味のある材料に関する成果は大学側、事業化に直結する装置に関する成果は企業側に帰属するといった例などが想定し得るケースである。
各々にとって興味のある領域を予め協議をし、相互に理解しておくことで相互に知財帰属の予見性が高まり、知財の帰属に関して不要なトラブルを避けることが可能となる。一度こじれると、共同研究契約の進捗にブレーキとなりかねない知財の帰属問題について、事前に判断基準を確立しておくことは、知財マネジメントにおける重要なスキルの一つである。
●発明の活用可能性を勘案し、製造方法は基本的に権利化しない方針
大学においては多様な発明が創出されるところ、これまで、製造方法の権利範囲のみの特許権も多く存在していた。 しかし、製造方法の権利だけでは、侵害立証可能性・排他性の観点からみても、権利としては非常に弱く、ライセンス可能性も低い。
それに鑑みて、製造方法の特許権については、出願せずに、ノウハウとして活用する方針に変更した。特許出願経費の削減にもつながった。
各機関にとって真に権利取得が必要な発明に整理し、戦略的に特許出願を行っている事例。
図表52 物質・材料研究機構(NIMS)におけるライセンス等の方針
論文・学会等での公表前にNIMS単独特許(基本特許)の出願を行う。NIMS単独特許(基本特許)の出願を行ってから企業連携を行う。企業との連携で創出された知的財産は企業とNIMSで共有し、原則、企業の自己実施は無償(非独占での自己実施に対する不実施補償は求めない)。
循環型基礎・基盤研究を目指す
必要に応じた企業連携
実用化研究周辺特許出願
基礎・基盤研究テーマ n
基礎・基盤研究テーマ n+1
基本特許出願
公表
企業への実施許諾
企業への実施許諾
基本特許出願公表
必要に応じた企業連携
n = 1,2,3…(新たなシーズ創製)
実用化研究周辺特許出願
特許ライセンスノウハウライセンス
特許ライセンスノウハウライセンス
NIMSの単独特許と第三者との共有特許をパッケージ化し、強固な特許ポートフォリオとしてライセンスする。ニッチマーケット等複数社購買が不要な場合を除き、原則ライセンスは非独占的通常実施権を複数社に付与する。物質・材料特許は国内材料メーカーに優先的にライセンスする(国内産業発展のため)。
*ライセンス先は2~3社が妥当、それ以上だと競争が激しく1社当たりの量産効果も出しにくい。
デバイス特許は国内外の技術力のある部品メーカーにライセンスする。*ライセンス先は応用分野ごとに数社ずつ必要。
大きな市場が見込まれる時は、デファクト・スタンダードを目指す。*その市場のトップシェアを持つセットメーカーの採用が必須。
共同出願時に企業が選択できるケース(原則はケース①)
①非独占的通常実施権(無償)、第三者実施は双方自由
②優先実施権(有償)を設定し、その後はケース1と同様
③優先交渉権(有償)を設定し、その後一時金を払い、独占的通常実施権(経常実施料※)。
※経常実施料は、共有者が独占実施権を有しながら事業を行わないケースを避けるため、 独占実施の場合の経常実施料は最低実施料を含むこととする。
基礎・基盤研究は単独で、実用化研究は企業と共同で
-90-

図表53 物質・材料研究機構(NIMS)における組織的連携のスキーム
NOIC(会員制連携センター) における知的財産の取扱い (具体例)
1.創出された知財はNIMSが一括して手続き・管理し、費用を負担する2.知財の取扱い・取決めは各オープンラボ(OL)単位で行う3.創出された特許の実施許諾は全て非独占的通常実施権4.NIMS-Aの研究者が創出した単独特許: A社・B社は他社より優位な条件で実施許諾を受けられる5.A社とNIMS-Aの共有特許: A社は無償実施権、B社は他社より優位な条件で実施許諾を受けられる
領域連携センター企業連携センター
NIMSと企業との間でセンター契約を締結して、両者の経営陣が参画して戦略的・継続的に連携する仕組み
特定領域の研究課題をNIMSと参加企業で共有する仕組み
会員制連携センター
共通の研究課題の下で会員制による共同研究を実施し、研究成果を共有する仕組み
■研究成果は原則共有しない ■研究成果を一部共有する
(磁性材料) (蛍光体材料)
(生体接着材料)
MSS Alliance(Core member + Application member) MSS Forum
その他連携の仕組み:アライアンス・フォーラム
研究成果を製品として業界標準にする為の新たな取り組み
クローズド・スキーム:規格書の作成 オープン・スキーム
例)嗅覚センサー:
<単粒子診断法>
オープンラボ
A社、B社、C大、NIMS-A
契約形態:
研究資金: 別途協議 別途協議 定額(会費)
知財帰属: 発明者主義 発明者主義 NIMS帰属
クローズド・スキーム
クローズドとオープンの ミックス・スキーム
オープン・スキーム
二者間契約 二者間契約 会則
共同研究活動の促進
先進的IPの発掘
IP価値の伸展
IPの適切な権利化
知財マネジメントを基礎とした共同研究による R&D 活動が新しい市場を創造するために貢献する
革新的な技術と新しいアプリケーションの創出
基本 IP
CIESのミッション
東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター(CIES)のミッションにおける知財マネジメントの役割
CIESにおいては、魅力ある基本IPをバックグランドIP(BIP)として共同研究契約においてパートナに提供する。BIPは、市場が存在することを前提にしたライセンス契約ではなく、これから市場が創設される近未来市場にチャレンジする企業と共同研究パートナとなるためのツールとして利用している。また、共同研究活動の成果として生み出されたフォアグランドIP(FIP)は、新たなパートナを引き込むための呼び水として利用している。
CIES
戦略企画部門
革新的な課題解決策の発案
IPの蓄積と運用
研究開発部門
コンソーシアム参加企業への魅力的なIPの
提供 新たな技術課題の提供
図表54 東北大学CIESにおける知的財産マネジメントの事例
-91-

東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター(CIES)の知財マネジメント機構
特許庁、INPIT
CIES
知的財産部
東北大学産学連携推進機構
CIESは、Chief Intellectual Property Officer(CIPO)を中心に知財マンジメントを企画・運用する独自の戦略企画部門を備えている。戦略企画部門には、知財情報管理する知財管理システム及び知財専門家が配備されている。戦略企画部門は、大学の知的財産部と連携をとりつつ、CIES固有の事情に反映した知財戦略の立案、戦略の運用を実行し、共同研究企業に対する満足度を高めるために時間軸に配慮した知財マネジメントを可能にしている。
共同研究企業
発明
戦略企画部門
知財専門家(知財PD,弁理士等)
知財管理システム
知財評価会議(出願前)
共同研究会議(発明者も参加)
特許
知財評価会議(権利化後)
CIPO(センター長)
報告・連絡
共同研究企業
共同研究企業
人材面の支援
図表55 東北大学CIESにおける知的財産マネジメントの体制
TPECのプロジェクトに参加
図表56 TPECの知的財産マネジメントの事例
●TPECのプロジェクトの特性・パワー・エレクトロニクス分野において、多様な製品への応用可能性があるが、実用化の道筋が見えていないものを対象とし、共同研究体「つくばパワーエレクトロニクスコンステレーションズ」(TPEC)で複数のプロジェクトが実施されている。事業化を目指すテーマを設定している。
・SiC製パワー半導体の基本構造や製造技術といった基盤技術や、試作ラインや研究設備を共有している。
・材料メーカー、製造装置・検査装置メーカー、パワー半導体メーカー、インバータなどモジュールを開発するメーカー、自動車やパワー・コンディショナーといった最終製品メーカーといった全ての階層のメンバー企業が参加。同業種から複数企業が参画することも制限せず。・契約内容は、企業と産総研とが 1 対 1で柔軟に契約する。
●TPECの研究成果(フォアグラウンドIP)の取扱い・フォアグラウンドIP自体は研究者の組織に帰属。
・TPEC内では研究成果がメンバーに公開されており、TPEC内の他プロジェクトでも、他者の成果(FIP)は自由に利用可。
・ただし、自社事業で知財を利用する場合に限って、独占を許可。一部の技術が重要な差異化要素となることがあるため。事業化まで時限的に独占を認め、成功したらその後も独占可(日本企業のニーズに合ったオープンさを担保)。・TPEC内オープンとは、秘密情報として開示を受けることができる情報であって、産総研つくばセンター内での研究開発において、無償で利用することが認められる技術情報の開示。外部に持ち出す場合等は、有償による技術移転を受けることが必要。
日経エレクトロニクス 2012年6月25日 掲載記事等を参考に文部科学省作成
TPEC内オープン
TPEC内クローズ
TPECの範囲
社内開発
企業
事業化SiC製パワー半導体の基本構造や製造技術等
研究プロジェクト
基盤技術
特定用途向けの電力変換器の開発等の応用を意識した複数プロジェクト
企業A 企業B 企業X・・・・企業C
-92-

図表57 IMECにおける知的財産取扱いパターン
IMECにおける知財管理の枠組みとなっているのは、産業提携プログラム(IMEC Industrial Affiliation Program: IIAP)。IIAPでは、知的財産権の所属、アクセス、保護に関して、IMECとIIAPに参加している研究パートナーとの間で、双務契約が結ばれる。契約の際に研究パートナーらは参加費用を支払い、IMECが保有している知的財産(バックグラウンドIP)へのアクセスを許される。また、IIAPを通して開発された知的財産(フォアグラウンドIP)は、研究パートナー間で共有されるが、非独占的であり、譲渡も認められていない。フォアグラウンドIPは、同じ研究分野の次の段階のIIAPが創設された時点で、IIAPのバックグラウンドIPになる。
IMECが目指すのは、R2以外のカテゴリーの財産権を吸収するだけ吸収し、自身のバックグラウンドIPを強化すると共に、IMECに所属しない外部組織のIIAPのフォアグラウンドIP、バックグラウンドIPへのアクセスを徹底的に遮断することである。こうすることでIMEC内のイノベーション・エコシステムが守られ、IMECのクラスターとしての機能や国際競争力が維持される。また、外部に知的財産が譲渡されないということは、研究パートナーやIMECが保有する知的財産の価値、今後のIMEC内部におけるR&D活動で、自分が所属する組織の重要性やプレゼンスを高めていくため、重要な知的財産を作り出す、もしくは知的財産にアクセスしていく必要がある。IMEC側にも研究メンバー側にもインセンティブがある体制である。
出典: 経済産業省 我が国イノベーション拠点のための海外拠点に関する基礎調査
フォアグラウンドIPの分類
R0: R0は、IIAPの途上でIMECの正規研究者ら(客員研究者ではない)の個別の研究によって生み出された知的財産の権利のカテゴリーであり、権利はIMECに帰属し、研究パートナーには帰属しない。研究パートナーらの権利へのアクセスは可能だが、独占・譲渡は認められていない。
R1: R1は、IMECの正規研究者らと、研究パートナーから派遣されてきた客員研究員の共同研究によって生み出された知的財産の権利のカテゴリーであり、権利はIMECと研究パートナーに帰属し、権利を持つ者のライセンス使用は認められている。開発に携わらなかったIMECの関係者には、権利(もしくは権利の一部)へのアクセスが認められている。
R1*: R1*は、R1の中でも、開発者本人(もしくは複数人)のアクセスのみが認められた知的財産のカテゴリーであり、同じIIAPに参加していた研究者であっても、アクセスは認められていない。
R2: R2は、IMECの主導するIIAP内で、研究パートナーから派遣されてきた客員研究員らが生みだした知的財産のカテゴリーであり、アクセスは研究パートナーには認められているが、IMEC側には一切のアクセスが認められていない。競争の概念を意識した権利のカテゴリーである。
R1 R2
R0
図表58 カーネギーメロン大学QoLT(ERC)における知財取扱い事例
・目的: ERC(Engineering Research Center)のプログラムであり、①産業界の競争力強化に向けた長期的なビジョンに焦点をあわせ、②伝統的な学問分野をインテグレートしてシステムレベル工学研究へ展開し、③研究と教育のための大学と産業界のパートナーシップを形成するためのもの。QoLTでは、高齢化社会における総合的生活支援技術を開発する目的のもと設立された。
・研究資金: NSF から毎年$4million の資金支援を受け、QoLT 参画企業から年間$1million の資金を獲得している。・研究体制: カーネギーメロン大学のロボティクスとピッツバーグ大学の医学を統合しており、研究者数十名と学生50名程が
参加している。・参加機関: カーネギーメロン大学、ピッツバーグ大学、企業10 社(インテル、日産、Bosch、三星、GMなど)・知的財産権: 大学の設備を使用した発明は、大学に単独帰属する。企業が使用を希望する知的財産権は、企業が出願を行い、権利は大学に帰属する。企業が知的財産権を使用する際は、原則実施料を有償で支払う。
・参加メリット: 右記のように、参加料別(アソシエイト、フル、マスター、プレミアムマスター)に種々の特典がある。
出典:
東京大学 中長期的な視点に立った多対多型産学官連携モデル
-93-

図表59 TIA-nanoにおける知的財産権の取扱いの例
1.基本的考え方(1)知的財産戦略と知財取扱規定等の関係知財取扱規程等を検討する際に、特許情報分析を活用しつつ利用可能なBIPを把握した上で、プロジェクトの知的財産戦略を明確にするとともに参加者と共有することが重要である。
(2)中核機関への知的財産権の蓄積と利用知的財産戦略を検討する際に、拠点活用プロジェクトの研究成果を中核機関に蓄積する戦略と、中核機関に蓄積された知的財産権を拠点活用プロジェクトの参加企業が利用する戦略の両面から考えることが重要である。
2.知財取扱規程等における検討事項 (一部抜粋)(1)知的財産権の帰属特に市場不確実性が高いプロジェクトの場合、参加企業の意見も踏まえつつ、研究成果に係る知的財産権の帰属を中核機関に集中させる一元的管理を検討する。
(2)知的財産権の組織的な管理と出願手続知的財産権の管理について、少なくとも研究成果をノウハウとして秘匿するか特許出願するかの選択を委員会等により組織的に管理することが適切である。
(3)参加企業への実施許諾(FIP)科学的・技術的難易度が高くかつ市場不確実性が高いプロジェクトにあっては、一括管理した知的財産権を一括(ワンストップ)ライセンスする方法を検討する。また、一括(ワンストップ)ライセンスが不適当な場合にあっても、市場不確実性が高い拠点活用プロ
ジェクトにあっては、権利者以外の参加企業からの実施許諾の申出に対して権利者による拒否を認めず、少なくとも適切かつ合理的な条件での実施許諾を義務づけることが適切である。
一方、市場不確実性が低い拠点活用プロジェクトや、科学的・技術的難易度が低く実用化に近いフェーズの拠点活用プロジェクトについては、参加企業の意向を十分に勘案して、権利者以外の参加企業からの実施許諾の申出に対して権利者による拒否権を認め、各参加企業の独自性の確保も配慮することが適切である。
(4)プロジェクト開始前の知的財産権(BIP)の取り扱いオープンイノベーションを促進する観点から、中核機関のBIPの取り扱いはもちろんのこと、参加企業のBIPの取り扱いについても、参加企業の同意が得られることを条件に検討を行い、FIPと同様にその取り扱いを規程に明記する。
出典: TIA-nano運営最高会議「拠点活用プロジェクトにおける知的財産権の取扱いに関するガイドライン」(平成25年3月)
-94-

■職務発明制度の改正と対応の必要性
職務発明制度の改正により、以下の事項について選択し得る制度となった。
①特許を受ける権利の原始的帰属先、②職務発明をした従業者等に与える相当の利益(金銭以外の経済上の利益)
「「大学等における職務発明等の取扱いについて」(概要)
科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会大学等における産学官連携リスクマネジメント検討委員会(平成28年3月31日)
(1)大学等における職務発明の範囲
大学等から、あるいは公的に支給された何らかの研究経費を使用して大学において行った研究又は大学等の施設を利用して行った研究の結
果生じた発明を職務発明の最大限としてとらえ、その範囲内で各大学等が自らのポリシーに基づいて取得・承継する権利を決定すべきである。
(2)大学等における特許を受ける権利の帰属
原始的な帰属先等を検討するに際して、重要なことは特許権等を適切に保護し活用することである。また、研究者の研究開発活動に対するイン
センティブを確保すること、権利帰属の安定性を担保すること、そして特許権等を活用しイノベーションに結び付けていくことが重要であり、それ
らに加えて制度運用手続の合理化という観点も勘案し、各機関で望ましい運用を決定すべきである。
各運用に関するメリット、留意点を把握した上で、適切な運用を選択することが重要である。
留意点として、例えば、特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性、二重譲渡による権利帰属の不安定性、日本版バイ・ドール対象案件の取扱い、機
関の権利取得の明確化プロセス、原始的機関帰属において出願しない案件の取扱い、職務発明の特定・該当判断、発明者の納得感等がある。
(3)大学等における相当の利益
特許法上の要件を満たすことを前提に、各機関での創意工夫を発揮して種々の相当の利益を設定することが可能である。各大学等においても、
相当の利益の内容を決定することが必要である。
①相当の利益は、経済的価値を有すると評価できること、②相当の利益の付与は、従業者等が職務発明をしたことを理由としていることが要件としてある。
各大学等は、相当の利益の付与に関する手続(協議、開示、意見聴取等)を、特許法に基づく指針(ガイドライン)に沿って行い、相当の利益を
与えることに係る不合理性が否定されるような運用に努めることで、訴訟等のリスクを低減することが重要である。
(4)学生発明等の取扱い等
学生発明等の取扱いは、事前に取決めをしておくことが望ましい。
所定の研究プロジェクトにおいて学生等がした発明を大学等機関側に承継することに関する同意を、大学等が学生等に対してあらかじめ求める
ことは、以下のことを満たしていれば、必ずしもアカデミックハラスメントに該当するわけではないと考えられる。
学生等が研究テーマを自由に選択して、教育の一環として研究が適切に行える環境であること、その研究に係る特定の目的達成のために合理的な範囲での適切
な譲渡契約内容となっていること、学生等に対して発明の取扱いについて十分に説明がされていることが必要である。
従前の運用を変更しないことも可能であるが、以下事項等を、
各大学等で検討、決定する必要
-95-

-96-

大学等における職務発明等の取扱いについて
平 成 2 8 年 3 月 3 1 日
科 学 技 術 ・ 学 術 審 議 会
産 業 連 携 ・地 域 支 援 部 会
大学等における産学官連携リスクマネジメント検討委員会
-97-

大学等における職務発明等の取扱いについて
目次
はじめに ·································································· 1
1.特許法第三十五条(職務発明制度)改正と対応の必要性について ············ 2
2.大学等における職務発明制度の現状経緯について ·························· 4
3.大学等における職務発明の範囲について ·································· 7
4.大学等における特許を受ける権利の帰属について ·························· 8
5.大学等における相当の利益について ···································· 12
6.学生発明等の取扱いについて ·········································· 15
7.その他の点について ·················································· 17
-98-

1
はじめに
知的財産を取り巻く環境は、経済のグローバル化やオープンイノベーションの進展な
どを背景にこの10年で大きく変化しており、平成14年に策定された知的財産戦略大
綱に基づく「知的財産立国」の実現がより重要となってきている。こうした状況を踏ま
えて、発明の奨励と併せて企業の知財戦略の変化に対応した環境整備により、我が国の
イノベーションを促進すること等を目的として、平成27年に特許法等について所要の
改正が行われたところである。
また、大学等が、イノベーション創出に向けた経営改革や財務基盤の強化を進め、世
界に伍する組織へと変革していくために、長期的な視野に立って、大学等が有する研究
経営資源をいかに効果的にマネジメントしていくかという視点が重要となってきてい
る。そのような中で、各大学等は、研究経営資源のひとつである知的財産を戦略的に取
得・活用するマネジメントを実行すると共に、アカデミアにおける資産の根源である研
究者自身の研究活動が促進されることを図るマネジメントを実行することが、より一層
強く求められてきている。
そのような中で、各大学等は、職務発明等の取扱いに関して、今後の運用を検討し、
決定する必要がある。
そこで、本検討委員会においては、大学等の知的財産マネジメントの強化と研究者の
発明創出インセンティブ向上を目指し、大学等における職務発明等の取扱いに関して、
各大学等が運用上留意すべき事項を中心に検討を行った。1
1 本検討委員会「大学等における産学官連携活動の推進に伴うリスクマネジメントの在り方に関する検討
の方向性について」(平成27年7月3日)においても、大学等における発明報奨に潜むリスクマネジメン
トに関して、さらなる検討事項とされている。
-99-

2
1.特許法第三十五条(職務発明制度)改正と対応の必要性について
(1)職務発明制度の趣旨について
職務発明制度(特許法第35条)は、「使用者、法人、国又は地方公共団体(使用者
等)」が組織として行う研究開発活動が我が国の知的創造において大きな役割を果たし
ていることにかんがみ、使用者等が研究開発投資を積極的に行い得るよう安定した環境
を提供するとともに、職務発明の直接的な担い手である個々の「従業者、法人の役員、
国家公務員又は地方公務員(従業者等)」が使用者等によって適切に評価され報いられ
ることを保障することによって、発明のインセンティブを喚起しようとするものである。
つまり、全体として我が国の研究開発活動の奨励、研究開発投資の増大を目指す産業政
策的側面を持つ制度であり、その手段として、従業者等と使用者等との間の利益調整を
図ることを制度趣旨としている。
(2)改正特許法の概要について
職務発明に関する現行制度は、近年の企業におけるイノベーションの変化の実態に必
ずしも対応していない側面があり、幾つかの問題が顕在化しつつあることが指摘されて
いるところ、知的財産の適切な保護及び活用により我が国のイノベーションを促進する
ため、発明の奨励に向けた職務発明制度の見直しが行われた2。具体的には、平成27
年改正の特許法第35条において、以下の事項が定められた。
① 権利帰属の不安定性を解消するために、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらか
じめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受け
る権利は、その発生した時から使用者等に帰属(原始的機関帰属)するものとする3。
② 従業者等は、特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の
経済上の利益(以下、「相当の利益」という。)を受ける権利を有するものとする。
③ 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、相当の
利益の内容を決定するための手続(相当の利益の内容を決定するための基準の策
定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基
準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見
の聴取の状況等)に関する指針を定めるものとする。
2 具体的な改正の必要性の背景として、①職務発明について特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の
不安定性、②職務発明について特許を受ける権利の二重譲渡が行われた場合の帰属の不安定性、③「相当
の対価」の在り方に対する多様なニーズの高まり、④「相当の対価」に関する法的予見可能性の低下及び
算定の複雑化に対する懸念が指摘されるところであった。3 改正前は、職務発明に該当する発明についても、その特許を受ける権利は発生した時点において発明者
に原始的に帰属し、あらかじめ定めたときに使用者等である機関は発明者から承継できる運用であった。
-100-

3
(3)特許法上の職務発明について
「職務発明」とは特許法第 35 条第1項において、従業者等がその性質上当該使用
者等の業務範囲に属し、かつその発明をするに至った行為がその使用者等における従業
者等の現在又は過去の職務に属する発明と規定されており、職務発明とそれ以外の発明
(自由発明、業務発明)との区分けは、使用者等の業務と従業者等の職務から客観的に
定まっているものである。大学等の教職員についても特則はなく、以下の原則が適用さ
れる。
(使用者等の業務範囲について)
企業においては、定款に定める「目的」に記載された事業(業務)を一応の基準と
し、又、現実に行われている業務及び近い将来具体的に計画されている事業(業務)
がこれに該当する。国、地方公共団体においては、当該公務員の属する機関の所掌
に属する事項の範囲がこれに該当する。
(職務について)
国公立や企業の研究所において、研究をすることを職務とする者が、テーマを与え
られ、又は研究を命ぜられた場合に生じた発明は明らかに職務上の発明となる。命
令又は指示がない場合であっても、結果からみて発明の過程となり、これを完成す
るに至った思索的活動が、使用者等との関係で従業者等の義務とされている行為の
中に予定され、期待されている場合をも含まれると考えられる。
(4)特許法改正への対応の必要性
特許法改正により、特許を受ける権利の原始的帰属先を各機関が選択し得る制度とな
り、また、職務発明をした従業者等に与える相当の利益は金銭以外の経済上の利益も選
択し得る制度となった。従前の運用を変更しないことも可能であるが、いずれにしても、
大学等においても、今後の具体的な運用を検討し、決定する必要がある。
そこで、本検討委員会において、大学等における職務発明等の取扱いに関して、各大
学等が運用上留意すべき事項等を中心に検討を行うこととした。4
4 実用新案権及び意匠権については、職務上創出された権利の扱いに関し、特許法第35条の準用規定が
設けられている。各大学等がこれら権利を管理する場合においては、職務発明に関する取扱いを準用する
ことが適当である。
-101-

4
2.大学等における職務発明制度の現状について
大学等における職務発明について、昭和52年学術審議会答申、昭和53年文部省通
知時は、個人帰属とすることを原則とし、一部を機関帰属とすることとしていた5。
しかし、知財立国の実現を目指す平成14年知的財産ワーキング・グループ報告書に
おいて、発明者個人から大学等機関に承継することを原則とすべきという方向性が示さ
れており、今日においても、この方向性に基づいて運用している大学等が多数である。
(1)平成14年知的財産ワーキング・グループ報告書
平成14年科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会 知的
財産ワーキング・グループ「知的財産ワーキング・グループ報告書」(以下、「平成14
年報告書」という)は、知的財産戦略大綱が策定され、国立大学の法人化前である状況
下において、以下に示すとおり、大学で生み出される知的財産等について、今後は、原
則大学帰属とし活用するなど、各大学が自らのポリシーの下で組織として一元的に管
理・活用を図ることが望ましい旨の方向性を示している。
・特許法上の職務発明規定における、大学の「業務範囲」や大学教員の「職務」の性
質に関する理解については、昭和 52 年学術審議会答申の当時と基本的に変化はな
い。
・大学の第三の使命としての社会への貢献、なかでも「知的財産立国」の実現に向け
て大学が自らの研究成果を主体的に育成し社会での活用を図ることが喫緊の課題
として重要であり、そのための環境整備も進められるといった状況の変化を勘案す
る必要性がある。
・このため、大学には、たとえ研究の企画・実施段階では必ずしも意図していなかっ
5 昭和52年学術審議会答申「大学教員等の発明に係る特許等の取扱いについて」では、大学における
研究に基づく発明に係る権利は、原則個人帰属とするが、特殊な発明(大学において特別な研究費等が投
入され計画的に推進されるプロジェクト研究の目的性に着目し、応用開発を目的とする特定の研究課題の
もとに当該発明に係る研究を行うために国が特別に措置した研究経費や特別に設置した大型研究設備によ
って行われた研究の結果生じた発明)に係る権利のみ、限定的に国に権利を承継させることとしていた。
同答申を受けて、文部省では昭和53年に学術国際局長・会計課長通知「国立大学等の教官等の発明に係
る特許等の取扱いについて」(文学術第 117 号)を発出し、国立大学等の教官等の発明に係る特許等につ
いて統一的な取扱いを定めた。 具体的には、教員等はその行った発明を(職務発明か自由発明かを問わず)
大学等の長へ届け出る義務があること、国は職務発明に係る権利のうち一定の範囲を承継すること、権利
の帰属については発明委員会の議に基づき大学等が決定すること等を定めるとともに、同答申の趣旨に従
い、次のいずれかに該当する場合は、原則として国が承継するものとするとした。
ア 応用開発を目的とする特定の研究課題の下に、当該発明に係る研究を行うためのものとして特別に国
が措置した研究経費(民間等との共同研究及び受託研究等経費のほか、科学研究費補助金を含み、教官当
積算校費、奨学寄附金等のような一般的研究経費は除く。)を受けて行った研究の結果生じた発明
イ 応用開発を目的とする特定の研究課題の下に、原子炉、核融合設備、加速器等のように国により特別
の研究目的のため設置された特殊な大型研究設備(電子計算機等のような汎用的なものは除く。)を使用し
て行った研究の結果生じた発明
-102-

5
たものであっても、研究から産み出され社会で活用可能な技術を社会に還元するこ
とが求められている。
・技術の社会への最適な移転を目指して、大学の研究から産み出された知的財産等を、
教育・研究機関としての大学の立場を堅持しつつ、産学官連携のもとで主体的・戦
略的に保護・育成しその活用を図ることは、大学にとって重要な役割である。
・施設設備や研究経費等、活動の基底部分を公的資金によって支えられている教員の
研究活動の成果について、国民(納税者)の理解が得られるよう配慮する必要があ
る。
以上の前提に立って、学術研究の発展や科学技術の方向性、また知的財産等のより効
果的な活用等の見地から、この時点の「最善の道」の選択として、以下の提言をしてい
る。
・大学が知的財産等を保護・管理し、有効な活用を企画・推進する能力を有すること
を前提に、教員が大学で行った職務発明に係る特許権等のうち、大学が承継するも
のの範囲について見直しを行い、機関帰属を原則とすることが適切である。
・具体的には、「大学から、あるいは公的に支給された何らかの研究経費6を使用して
大学において行った研究又は大学の施設を利用して行った研究の結果生じた発明」
を職務発明の最大限ととらえ、このうち、研究成果の効果的・効率的な育成と活用
推進の観点から各大学が承継するべきであると判断する範囲を、各大学がそれぞれ
自らのポリシーにおいて明らかにすることが必要である
・知的財産に係る権利等の帰属については機関帰属を原則としつつ、その範囲の広狭
等具体的な在り方については、大学ごとの合理的な判断に基づく多様性が尊重され
るべきである。
・各大学の発明規則等において、特許法第35条の「相当の対価」を規定し、教員に
対する補償やインセンティブの観点から、十分な対価の支払が必要であり、対価に
加えて、教員又は所属研究室等への研究奨励金としての還元もありうる。
(2)現在の状況(職務発明規程の整備状況等)
平成14年報告書及び平成16年特許法改正7を踏まえて、各大学等においては職務
6 「大学から、あるいは公的に支給された何らかの研究経費」としては、国や地方自治体等が大学に対し
特別に措置した研究経費、共同研究・受託研究に伴い大学が契約に基づき受け入れた研究経費、寄附金、
大学における経常的研究経費等、大学が何らかの形で教員に支給する経費及び科学研究費補助金等を指す。 7 平成16年特許法改正によって、「契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合
には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定
された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考
慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。」とい
う旨が規定された。
-103-

6
発明制度に対する対応は進展し、現在、380機関以上において職務発明規程が整備さ
れている状況である。また、職務発明を機関に承継することによって機関帰属を原則と
するような運用をほとんどの大学等が採用している状況である。8
ところで、特許法改正を見据えた職務発明の原始帰属先に関する検討に際しては、平
成26年7月日本学術会議 科学者委員会 知的財産検討分科会「科学者コミュニティか
ら見た職務発明制度のあり方と科学者に対する知財教育の必要性」において、「今後の
具体的なあり方としては、大学等の研究者にとっては、職務発明と見なされるものであ
っても、今後も発明者帰属が維持されることが望ましい。」という方向性が提案された。
また、平成27年1月産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会「我が国の
イノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」に
おいて、大学等は、「特許を受ける権利の従業者等帰属を希望する法人」として例示さ
れており、従業者等帰属を可能とするように制度設計すべき旨が言及された。
こうした検討経緯の結果、平成27年特許法改正により「あらかじめ使用者等に特許
を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生し
た時から使用者等に帰属する」と規定されたところである。改正特許法下において、大
学等を含む各機関は、改正法による原始的機関帰属とするか、従来どおり原始的発明者
帰属を前提とする機関(承継)帰属とするのか、を選択することが可能になった。
8 文部科学省「平成26年度 大学等における産学連携等実施状況について」より引用。
-104-

7
3.大学等における職務発明の範囲について
大学等における職務発明の範囲について、少なくとも現時点において、我が国で判
例・裁判例等の中での規範が示されたことはないが、平成14年報告書において示され
た方向性は現時点においても変更されることはなく、大学等から、あるいは公的に支給
された何らかの研究経費を使用して大学において行った研究又は大学等の施設を利用
して行った研究の結果生じた発明を職務発明の最大限としてとらえ、その範囲内で各大
学等が自らのポリシーに基づいて取得・承継する権利を決定すべきである。
大学等には組織的な知的資産マネジメントの実行が期待される中で9、大学等が保有
する知的財産権についても価値を最大化する形で大学組織が適切にマネジメントする
ことが重要であり、知的財産権を適切に保護・活用する方策を、各大学等は検討すべき
である。その結果として大学等に権利を帰属させる場合には、発明者に対して相当の利
益を適切に付与することが重要である。
他国の大学等においては、個々の特性に合わせた多様性のある知的財産ポリシーを
各々明確にした上で、大学等の機関側が取得・承継する権利の対象等を決定していると
解される。各国それぞれの法律の枠組みの中で運用されているため、他国の状況が我が
国において必ずしも全て参考になるわけではないものの、我が国の各大学等においても、
教職員の発明の取扱い(大学等の機関側が取得・承継する権利の対象、相当の利益等)
は、各機関の特性に合わせた独自性があるべきものであり、各機関の知的資産マネジメ
ント上の戦略的要素と捉えて、明確な知的財産ポリシー等を持つことが重要である。
なお、原始的機関帰属とする運用を選択する場合においては、各機関が定める職務発
明の範囲を明確にすることがより一層求められることには留意する必要がある。
9 科学技術・学術審議会 産業連携・地域支援部会 競争力強化に向けた大学知的資産マネジメント検討委
員会「イノベーション実現に向けた大学知的資産マネジメントの在り方について ~大学における未来志
向の研究経営システム確立に向けて~」(平成27年8月)(以下、競争力強化に向けた大学知的資産マネ
ジメント検討委員会報告書という。)を参照。
-105-

8
4.大学等における特許を受ける権利の帰属について
(1)権利帰属に関する現行の一般的な運用について
各大学等においては、例えば以下のように、発明の内容等に応じて承継の要否等を判
断して、大学等に帰属させるべきかを個々に判断している。
①発明者からの発明届出
②発明評価
③帰属判定(職務発明該当性、特許性・事業化可能性等に基づく承継要否)
④承継手続(譲渡証受領)
(2)権利帰属に関する改正特許法施行後の運用について
特許を受ける権利を大学等に帰属させる場合においても、原始的な帰属先(特許を受
ける権利が発生したとき、すなわち発明が生まれたときの帰属先)を、使用者等(機関)
と従業者等(発明者)のいずれにするかについて、①原始的には発明者帰属、②原始的
機関帰属、③特定の場合のみ原始的機関帰属(それ以外は原始的発明者帰属)といった
種々の運用があると解される。10
原始的な帰属先も含めた職務発明制度の運用を各大学等において検討するに際して、
重要なことは特許権等を適切に保護し活用することである。また、研究者の研究開発活
動に対するインセンティブを確保すること、権利帰属の安定性を担保すること、そして
特許権等を活用しイノベーションに結び付けていくことが重要であり、それらに加えて
制度運用手続の合理化という観点も勘案し、各機関で望ましい運用を決定すべきである。
その際に、各運用に関するメリット、留意点を把握した上で、適切な運用を選択するこ
とが重要である。
特許法第35条第3項に規定されているとおり、原始的に機関帰属とする運用とする
ときには、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権
利を取得させることを定める必要がある。例えば、職務発明規程等に「職務発明につい
ては、その発明が完成した時に、大学等が特許を受ける権利を取得する。」と規定した
場合には、原始的機関帰属となると解される11。また、原始的機関帰属を職務発明規程
等に定めた場合には、各大学等の機関としての方針として従業者等に対して開示してい
くことが重要である。
10 特許庁「大学等における特許法第 35 条第 3 項の適用について」も併せて参照のこと。 11 深津拓寛、松田誠司、杉村光嗣、谷口はるな「実務解説職務発明 平成27年特許法改正対応」(201
6年、商事法務)を参照のこと。
-106-

9
なお、職務発明規程等において、あらかじめ使用者等(機関)に職務発明に係る特許
を受ける権利を原始的に取得させることを定めなければ、法改正前と同様、原始的には
発明者帰属で大学等機関が承継取得すると定めことも可能である。
(原始的な帰属先の運用例と留意点)
①原始的には発明者帰属として大学等機関は承継取得する運用
権利を原始的には発明者帰属とし、権利ごとに帰属先を判断して、機関に帰
属させるときは承継する運用である(大学等における現行の一般的な運用)。こ
の場合、以下の事項等について留意する必要がある。
・特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性
共同研究などの場面において特許を受ける権利が共有に係るケースがあるが、
この場合、各共有者は、他の共有者の同意を得ない限り当該特許を受ける権
利の持分を譲渡することができない(特許法第33条第3項)。そのため、共
同研究によって特許を受ける権利が他社等の従業者等(発明者)との共有に
係る場合には、このあらかじめ定めた契約等だけでは足りず、当該他社等の
発明者たる従業者等の同意を別途得ない限り、自らの従業者等の特許を受け
る権利の持分すら自らに承継できないという問題が生じる。
・二重譲渡による権利帰属の不安定性
特許法第34条第1項の規定によれば、特許出願前における特許を受ける権
利の承継については特許出願が第三者対抗要件となるため、例えば、使用者
等(機関)が職務発明について特許を受ける権利を従業者等(発明者)から
予約承継していたとしても、当該従業者等が当該使用者等以外の第三者にも
当該特許を受ける権利を譲渡し、当該第三者が当該使用者等よりも先に特許
出願をした場合には、当該使用者等は当該第三者に原則として劣後する。こ
のように、使用者等が職務発明に係る特許権を自らが取得できない場合があ
り、使用者等の知的財産戦略に支障を生じ得る。
・日本版バイ・ドール規定12の適用対象案件の取扱い
12 日本版バイ・ドール規定(産業技術力強化法第19条第1項)として、以下の事項が定められている。 国は、技術に関する研究開発活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを
促進するため、国が委託した技術に関する研究開発の成果に係る知的財産権について、以下の4つの条件
を受託者が約する場合に、受託者から譲り受けないことができる。
①研究成果が得られた場合には遅滞なく国に報告すること、②国が公共の利益のために必要があるとして
求めた場合に、知的財産権を無償で国に実施許諾すること、③知的財産権を相当期間利用していない場合
に、国の要請に基づいて第三者に当該知的財産権を実施許諾すること、④知的財産権の移転等をするとき
は、合併等による移転の場合を除き、予め国の承認を受けること。
-107-

10
大学等機関に対する国の委託による研究開発の成果に係る知的財産権(特許
を受ける権利を含む)は、大学等機関の職務発明の典型例であるが、日本版
バイ・ドール規定適用により、所定の義務負担のもとで一律に、受託者(大
学等機関)が取得することとされている。したがって、大学等の機関は、当
該規定に則して運用できるよう留意する必要がある。
②原始的に大学等機関に帰属する運用
権利を原始的に機関帰属とする運用である。この場合、以下の事項等につい
て留意する必要がある。
・機関の権利取得の明確化プロセス
職務発明の該当性、権利帰属先等について適切な手続を踏み、各権利の帰属
先が、対外的・事後的に明確化にされるよう運用することが望ましい。例え
ば、職務発明に係る特許を受ける権利を大学等機関が取得・承継することを
証明するため、譲渡証・確認証等を徴する手続をとることが考えられる。
・原始的機関帰属において出願しない案件の取扱い
現在、多くの大学等においては、発明審査会等で発明評価を行い、機関に承
継帰属させることを前提として大学等機関側に帰属させるか否か(発明者等
個人側に帰属させるか)という帰属判断を行っている。このような大学等に
おいて、原始的機関帰属を選択した場合、大学等機関としての出願は不要と
判断した特許を受ける権利について発明者個人等に権利を譲渡することが必
要になることもある。
・職務発明の特定、該当判断
大学等においては、職務発明と自由発明等の判別が困難な場合があるが、そ
の場合、研究者が自己の判断でその属性を決定するのではなく、大学等の組
織に対して発明を開示した上で、職務発明と認めるべきか否かについて検討
する必要がある。特に、原始的機関帰属とする場合においては、職務発明の
該当性をあらかじめ明確にするよう留意する必要がある。
・発明者の納得感(原始的機関帰属とすることへの違和感)
自由闊達な発想を源泉とする学術研究においては、テーマの選定や研究方法
の選択等が研究者の自主性に委ねられており、企業等のような指揮命令のも
とで発明創出が図られるような研究の在り方とは異なるといった指摘もなさ
れることがある。そのような中で、創出された発明を原始的機関帰属とする
-108-

11
ことに対して違和感が呈されることもあるところ、大学等における研究者(発
明者)の納得感も考慮した職務発明の取扱いを検討することは必要である。
③特定の場合のみ原始的機関帰属(それ以外は原始的発明者帰属)とする運用
特定条件の特許を受ける権利(例えば、日本版バイ・ドール規定適用対象と
なる国の委託研究開発から生まれた発明、共同研究から生まれた発明に関する
特許を受ける権利等のような、外形標準的に識別可能な一部の職務発明の特許
を受ける権利)については、原始的に機関帰属とし、特定条件以外の特許を受
ける権利は、原始的に発明者帰属とする運用である。この場合、従業者等(発
明者)がその職務発明が原始的機関帰属なのか原始的発明者帰属なのか認識で
きるよう明確にし、使用者等である大学等は従業者等に対して丁寧に説明する
必要がある。13
外形標準的に識別可能な一部の職務発明については、上記②と同じく大学な
ど機関が原始的に一律に特許を受ける権利を取得することになり、権利帰属の
不安定性を解消し、知財管理事務の効率化を図ることが期待できる。この場合
の留意点は、上記②と同様である。
特定条件以外の特許を受ける権利は、上記①と同じく原始的に発明者に帰属
する。発明者帰属の特許を受ける権利について、必要に応じて個別に発明者か
ら機関に当該権利を選択的に承継することができることは、従来と同様である。
この場合の留意点は、上記の①と同様である。
13 仮に、原始的機関帰属を選択した場合、職務発明の特許を受ける権利が、一律に全て原始的に機関に帰
属することが原則であり、例外的に、外形標準的に識別可能な一部の職務発明の特許を受ける権利のみを
原始的に機関に帰属させ得るものと考えられる(特許庁「大学等における特許法第 35 条第 3 項の適用につ
いて」参照)。職務発明について発明審査会等において機関に帰属させるか否かを選択的に判断するスキー
ムでの特許を受ける権利の帰属先の選別は、外形標準的に識別可能なものと言えず、権利帰属の不安定化
を招く恐れがある点に留意する必要がある。
-109-

12
5.大学等における相当の利益について
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会において、特許法第35条第6項
で規定されている指針(ガイドライン)について議論され、とりまとめ案が公表された
ところであるが、大学等においても、当該指針が策定された後、当該指針に沿って適切
な運用が行えるようにすることが重要である。14
(1)相当の利益の内容について
大学等が特許を受ける権利を取得・承継する場合においては、研究テーマの設定や発
明創出の実現における発明者の貢献が大きいという大学等の実状も鑑みて、発明創出に
対する発明者の貢献は十分に評価して「相当の利益」を付与することが非常に重要であ
る。
職務発明をした従業者等に与えられる相当の利益には、金銭以外の経済上の利益も含
まれるが、①相当の利益は、経済的価値を有すると評価できること(例えば、表彰状等
のように相手方の名誉を表するだけのような、経済的価値を有すると評価できないもの
は含まれない)、②相当の利益の付与は、従業者等が職務発明をしたことを理由として
いること(例えば、従業者等が職務発明をしたことと関係なく従業者等に与えられた金
銭以外の経済上の利益をもって、相当の利益の付与とすることはできない)といった要
件を満たす必要がある。上記要件を満たした上で、各機関は、特許法第35条第5項に
おける適正な手続(協議、基準の開示、意見の聴取等の手続)を行う必要がある。
指針(ガイドライン)案においては、金銭以外の相当の利益の付与として、以下に掲
げるものが考えられると例示されている。
・使用者等負担による留学の機会の付与
・ストックオプションの付与
・金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格
・法令及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与
・職務発明に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾
上記例示以外にも、上記要件を満たすことを前提に、各機関での創意工夫を発揮して
種々の相当の利益を設定することが可能である。各大学等においても、相当の利益の内
14 指針(ガイドライン)案は、平成27年度改正法の平成28年4月1日施行後、経済産業省告示として
公表される予定。
-110-

13
容を決定する必要がある(ただし、必ずしも、金銭以外の経済上の利益を設定する必要
があるわけではない)。
大学等における金銭以外の経済上の利益として、例えば、研究費の増額、研究施設・
研究環境の整備等(以下、これらを総称して「研究費の増額等」という。)が検討対象
として挙げられるところではあるが、発明者個人にとって経済的価値を有すると評価で
きるかといった観点から、研究費の増額等が相当の利益に関する上記要件を満たすか否
かについて、肯定的見解と否定的見解が存在するところである。15
このような、上記要件を満たすか否か一義的判断に困難を伴う相当の利益(例えば、
上述の研究費の増額等。)を大学等において採用する場合、各大学等は、当該相当の利
益が上記要件を満たすかという一般的な評価や、各大学等の教職員の意向を、十分に勘
案して検討した上で、教職員個人にとって納得感が高まるようなインセンティブとなる
よう工夫することが重要であると考えられる。
その際に、企業等における研究者のインセンティブと、大学等における研究者のイン
センティブは異なる可能性がある点も留意する必要がある。
また、基準に定める相当の利益の内容が特定の方式で決定されなければならないとい
う制約はない。したがって、特許登録時や退職時に相当の利益を一括して与える方法を
各機関が採用することも可能であり、現在多くの大学等で行っている、いわゆる実績補
償方式(各機関に実施許諾収入があったときに所定の決まった割合を発明者に配分する
ような運用)は、選択肢の一つにすぎない16。退職者に対して相当の利益を退職後も与
え続けることの負担等を鑑みて、退職時に相当の利益を一括して与えるような方法を採
用することも可能である。
(2)相当の利益の付与に関する手続について
大学等と企業との間で異なる特有の事情も存在するが、特許法第35条第1項では
使用者等について大学等と企業を区別しておらず、大学等においても職務発明について
は同条の規定は当然適用されるため、各大学等は、相当の利益の付与に関する手続(協
議、開示、意見聴取等)を、同条第6項に基づく指針(ガイドライン)に沿って行い、
15 例えば、大学特有ではない一般的な議論として、研究費の増額等は、研究者の研究開発活動に対するイ
ンセンティブになり得るものである一方で、使用者等にも一定の利益がある性質のものであり、従業者等
個人の経済的価値を有すると評価できるものか否かといった判断について、種々の意見がある。その他、
使用者等と従業者等との協議段階や、意見の聴取段階(相当の利益を従業者等に付与する段階)において、
従業者等の同意をとる手続等が一例として考えられる。なお、大学等の研究者側が、敢えて研究費の増額
等を望むケースも存在する。16 例えば、所定のタイミングで、一括して相当の利益を与えた上で、その後、機関が得た実施料収入が大
規模であったときのみ、発明者に相当の利益として与えるような運用とすることも想定される。
-111-

14
相当の利益を与えることに係る不合理性が否定されるような運用に努めることで、訴訟
等のリスクを低減することが重要である。相当の利益について契約、勤務規則その他の
定めが整備されていない場合や、その定めたところにより相当の利益を与えることが不
合理であると認められる場合には、利益の相当性は、最終的には同条第7項の規定によ
り裁判所の司法判断により定められることについて留意する必要がある。
【相当の利益の付与手続の流れ】17
17 特許庁「特許法第 35 条第 6 項の指針(ガイドライン)案の位置づけと概要」より引用。
①基準案の協議
基準案の策定
基準の確定
①「協議」とは、基準の策定に関して、基準の適用対象となる職
務発明をする従業者等又は その代表者と使用者等との間で
行われる話合い(書面や電子メール等によるものを含む)全般
を意味する。
【例】従業者等が代表者を通じて話合いを行う場合の 適正な在り
方 <指針案第二 一 1(三)、第二 二>
②基準の開示
②「開示」とは、基準の適用対象となる職務発明をする従業者等
がその基準を見ようと思えば見られる状態にすることを意味す
る。
【例】イントラネットで基準を開示する場合に個人の専用 パソコン
を与えられていない従業者等がいる場合の適正な在り方
<指針案第二 一 1(四)、第二 三>
③「意見の聴取」とは、具体的に特定の職務発明に係る相当の利
益の内容を決定する場合に、 その決定に関して、当該職務発
明をした従業者等から、意見(質問や不服等を含む。)を聴くこと
を意味する。
【例】あらかじめ従業者等から意見を聴取した上で相当の利益の
内容を決定する方法の場合の適正な在り方 <指針案第二 一 1(五)、第二 四>
③意見の聴取
(異議申立手続含む)
相当の利益の決定
相当の利益の確定
-112-

15
6.学生発明等の取扱いについて
一般的には、大学等と雇用関係にない学生等(大学等の学生、大学院生及びポスドク
等を含む。以下、同じ。)は特許法第35条に定める「従業者等」に該当しないため、
学生等がした発明は職務発明には該当せず、当該発明に係る特許を受ける権利は、学生
等に帰属すると考えられる。
しかしながら、所定の研究プロジェクト(例えば、国の委託研究や企業との共同研究
等。以下、同じ。)で学生等がした発明について、各大学等はそのポリシーに従って特
許権等の活用の最大化が図られるよう、一元的に管理・活用することも含めて当該発明
の取扱いを検討する必要がある。
したがって、各大学等においては、当該発明の取扱いについて、発明が創出された後
に事後的に検討するよりも、事前に(例えば、研究プロジェクトに関与する前段階で)
取決めをしておくことが望ましい。この場合、特にアカデミックハラスメントに留意す
る必要があるが、所定の研究プロジェクトにおいて学生等がした発明を大学等機関側に承
継することに関する同意を、大学等が学生等に対してあらかじめ求めることは、学生等が
研究テーマを自由に選択して、教育の一環として研究が適切に行える環境であること、そ
の研究に係る特定の目的達成のために合理的な範囲での適切な譲渡契約内容となっている
こと、学生等に対して発明の取扱いについて十分に説明がされていることが満たされてい
れば、必ずしもアカデミックハラスメントに該当するわけではないと考えられる。18
なお、研究プロジェクトの参加に際して、学生等と取り決めるべき事項は、発明の取
扱いのみならず、秘密情報の取扱い等も含めて種々の事項があるので、それらを一体的
に取り決めることが望ましい。
他方、雇用関係にある学生等(所定の研究プロジェクトに参加し、大学等と契約を締
結して雇用関係が生じている学生等)が研究プロジェクトの中でした発明は、職務発明
として取り扱うことが可能であり、特許法第35条が適用される。この場合、教職員の
職務発明と同様に、雇用関係にある学生等との関係においても、特許法第35条第5項
の要件を満たす必要があることには留意が必要である。
なお、雇用関係の有無は、発明創出が期待される研究プロジェクトに対する給与支払
実態により評価される。研究プロジェクトと関係がない金銭付与(例えば、ティーチン
グ・アシスタント等の謝金といった、発明が創出された研究プロジェクトとは特段関係
がない謝金等)は、少なくとも職務発明制度上の雇用関係の根拠として認められないと
解されることに留意する必要がある。
18 例えば、その研究プロジェクトに参加せずとも、他の研究テーマを選択して研究を実施できる環境であ
ること、発明に対する学生等の寄与分・対価の額の決定方法・学生ベンチャーの起業時の扱い等が適切で
あること、学生発明に対して不当に広範に譲渡を求めるものではないこと等が挙げられる。
-113-

16
なお、産学官連携活動を教育の場として設定する際には、学生等という身分と矛盾が
起きないようなマネジメントが必要である。その一方で、学生等は、大学等の研究活動
や産学官連携活動を推進していく上で重要な存在であるところ、主体的な研究者として
育成・処遇される必要があることが指摘されている(例えば、経済的報酬を得られる形
での共同研究契約の締結等が考えられる)。19
19 競争力強化に向けた大学知的資産マネジメント検討委員会報告書から引用。
-114-

17
7.その他の点について
米国の大学等においては、外部からの訪問者等(例えば、客員研究員、ボランティア
等)を含めた、大学等と雇用関係にない者が発明に関与した際の取決め(例えば、visitor participation agreement)が整備されているケースもある。日本の大学等においても、
各大学等の状況等も勘案して、必要に応じて、雇用関係にない者の発明の取扱いについ
てもあらかじめ検討することは有用である。
なお、クロスアポイントメント制度20に伴う発明の取扱いについては、他の産学官連
携リスクマネジメント要素(例えば、営業秘密管理、利益相反マネジメント等)とも関
連し、総合的に検討する必要がある。
また、大学等が職務発明に関連する秘密情報(非公表情報等)を取り扱う際に、各大
学等の技術流出防止マネジメント体制を強化していくことも重要となる。
20 クロスアポイントメント制度とは、研究者等が大学、公的研究機関、企業の中で、二つ以上の機関に雇
用されつつ、一定のエフォート管理の下で、それぞれの機関における役割に応じて研究・開発及び教育に
従事することを可能にする制度のことである。
-115-

-98-

参考資料
-117-

科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会に置く委員会について
平成27年4月17日
科学技術・学術審議会
産業連携・地域支援部会
科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会運営規則第2条の規定に基
づき、科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会に以下の委員会を置く。
名 称 調査検討事項
地域科学技術イノ
ベーション推進委
員会
地域イノベーション・エコシステム(異なるプレーヤーが
生態系システムのように相互に関与してイノベーション創
出を加速するシステム)の創出・実現に向けた現状と課題の
把握とともに、その解決策及び取り組むべき方向性・戦略に
ついて検討を行う。
競争力強化に向け
た大学知的資産マ
ネジメント検討委
員会
大学が、学長のリーダーシップの下、外部機関との連携を
含めて、研究経営資源(研究開発投資の財源、知的財産等の
資産、研究人材等)を効果的に活用していくための戦略の在
り方について検討を行う。
大学等における産
学官連携リスクマ
ネジメント検討委
員会
大学自身が、産学官連携を推進する上で生じ得るリスク要
因のマネジメントを研究経営上の重要な課題として捉え、適
切に対応するための方策等について検討を行う。
(参考資料1)
-118-

科学技術・学術審議会 産業連携・地域支援部会
大学等における産学官連携リスクマネジメント検討委員会
委員名簿
(臨時委員)
◎渡部俊也 東京大学政策ビジョン研究センター教授
○馬場章夫 大阪大学特任教授
(専門委員)
足立和成 山形大学大学院理工学研究科教授
飯田香緒里 東京医科歯科大学研究産学連携推進機構教授、産学連携研
究センター長
伊藤伸 東京農工大学大学院工学府教授
伊藤正実 群馬大学産学連携・共同研究イノベーションセンター教授
苛原稔 徳島大学医学部長
植木俊哉 東北大学理事
江戸川泰路 新日本有限責任監査法人パートナー
新谷由紀子 筑波大学利益相反・輸出管理マネジメント室准教授
田仲信夫 一般財団法人安全保障貿易情報センター理事、総務企画
部長
西尾好司 株式会社富士通総研経済研究所主任研究員
野口義文 立命館大学研究部事務部長、産学官連携戦略本部副本部長
芳賀信彦 東京大学大学院医学系研究科教授
林いづみ 桜坂法律事務所弁護士
平井昭光 レックスウェル法律特許事務所長、弁護士、弁理士
三尾美枝子 キューブM総合法律事務所弁護士
峯木英治 株式会社ブリヂストン知的財産本部フェロー(本部長)
◎:主査、○:主査代理
(五十音順、敬称略)
(参考資料2)
-119-

関係条文等
知的財産基本法(平成 14 年法律第 122 号) -抄-
(目的)
第一条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強
化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及び
その効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現する
ため、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために
基本となる事項を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、
並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとと
もに、知的財産戦略本部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に
関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする。
(大学等の責務等)
第七条 大学等は、その活動が社会全体における知的財産の創造に資するものであるこ
とにかんがみ、人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努
めるものとする。
2 大学等は、研究者及び技術者の職務及び職場環境がその重要性にふさわしい魅力あ
るものとなるよう、研究者及び技術者の適切な処遇の確保並びに研究施設の整備及
び充実に努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策であって、大
学及び高等専門学校並びに大学共同利用機関に係るものを策定し、並びにこれを実
施するに当たっては、研究者の自主性の尊重その他大学及び高等専門学校並びに大
学共同利用機関における研究の特性に配慮しなければならない。
(事業者の責務)
第八条 事業者は、我が国産業の発展において知的財産が果たす役割の重要性にかんが
み、基本理念にのっとり、活力ある事業活動を通じた生産性の向上、事業基盤の強
化等を図ることができるよう、当該事業者若しくは他の事業者が創造した知的財産
又は大学等で創造された知的財産の積極的な活用を図るとともに、当該事業者が有
する知的財産の適切な管理に努めるものとする。
2 事業者は、発明者その他の創造的活動を行う者の職務がその重要性にふさわしい魅
力あるものとなるよう、発明者その他の創造的活動を行う者の適切な処遇の確保に
努めるものとする。
(連携の強化)
第九条 国は、国、地方公共団体、大学等及び事業者が相互に連携を図りながら協力す
ることにより、知的財産の創造、保護及び活用の効果的な実施が図られることにか
んがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
(参考資料3)
-120-

(研究開発の推進)
第十二条 国は、大学等における付加価値の高い知的財産の創造が我が国の経済社会の
持続的な発展の源泉であることにかんがみ、科学技術基本法(平成七年法律第百三
十号)第二条に規定する科学技術の振興に関する方針に配慮しつつ、創造力の豊か
な研究者の確保及び養成、研究施設等の整備並びに研究開発に係る資金の効果的な
使用その他研究開発の推進に必要な施策を講ずるものとする。
(研究成果の移転の促進等)
第十三条 国は、大学等における研究成果が新たな事業分野の開拓及び産業の技術の向
上等に有用であることにかんがみ、大学等において当該研究成果の適切な管理及び
事業者への円滑な移転が行われるよう、大学等における知的財産に関する専門的知
識を有する人材を活用した体制の整備、知的財産権に係る設定の登録その他の手続
の改善、市場等に関する調査研究及び情報提供その他必要な施策を講ずるものとす
る。
特許法(昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号)-抄-
(目的)
第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて
産業の発達に寄与することを目的とする。
(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、
その発明について特許を受けることができる。
一 ~ 三 (略)
2 (略)
(特許を受ける権利)
第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。
2 (略)
3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なけ
れば、その持分を譲渡することができない。
4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なけ
れば、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権
を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願
をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 ~ 7 (略)
-121-

(職務発明)
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従
業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその
性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその
使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」
という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承
継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権
を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじ
め、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は
使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤
務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらか
じめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受
ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許
を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため
専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明につ
いて使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項
の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他
の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を
有する。
5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の
利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行わ
れる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定につ
いて行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところに
より相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規
定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するもの
とする。
7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を
与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規
定により受けるべき相当の利益の内容は、 その発明により使用者等が受けるべき利
益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他
の事情を考慮して定めなければならない。
-122-

実用新案法(昭和三十四年四月十三日法律第百二十三号) -抄-
(目的)
第一条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図る
ことにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
(実用新案登録の要件)
第三条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係
るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受け
ることができる。
一 ~ 三 (略)
2 (略)
(特許法 の準用)
第十一条 (略)
2 (略)
3 特許法第三十五条 (仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従
業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。
意匠法(昭和三十四年四月十三日法律第百二十五号) -抄-
(目的)
第一条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、
もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
(意匠登録の要件)
第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、
その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 ~ 三 (略)
2 (略)
(特許法 の準用)
第十五条 (略)
2 (略)
3 特許法第三十五条 (仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従
業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。
-123-

著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号) -抄-
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者
の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意し
つつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とす
る。
(保護を受ける著作物)
第六条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護
を受ける。
一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を
有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、そ
の発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づ
きその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を
除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作
成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等 とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラ
ムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定め
がない限り、その法人等とする。
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年五月三十一日法律第四十三号)
-抄-
(目的)
第一条 この法律は、半導体集積回路の回路配置の適正な利用の確保を図るための制
度を創設することにより、半導体集積回路の開発を促進し、もつて国民経済の健全
な発展に寄与することを目的とする。
(回路配置利用権の設定の登録)
第三条 回路配置の創作をした者又はその承継人(以下「創作者等」という。)は、そ
の回路配置について回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を受
けることができる。この場合において、創作者等が二人以上あるときは、これらの
者が共同して設定登録を受けなければならない。
2~3 (略)
-124-

(職務上の回路配置の創作)
第五条 法人その他使用者の業務に従事する者が職務上創作をした回路配置について
は、その創作の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法
人その他使用者を当該回路配置の創作をした者とする。
種苗法(平成十年五月二十九日法律第八十三号) -抄-
(目的)
第一条 この法律は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示
に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正
化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。
(品種登録の要件)
第三条 次に掲げる要件を備えた品種の育成(人為的変異又は自然的変異に係る特性
を固定し又は検定することをいう。以下同じ。)をした者又はその承継人(以下「育
成者」という。)は、その品種についての登録(以下「品種登録」という。)を受け
ることができる。
一 ~ 三 (略)
2 (略)
(職務育成品種)
第八条 従業者、法人の業務を執行する役員又は国若しくは地方公共団体の公務員(以
下「従業者等」という。)が育成をした品種については、その育成がその性質上使用
者、法人又は国若しくは地方公共団体(以下「使用者等」という。)の業務の範囲に
属し、かつ、その育成をするに至った行為が従業者等の職務に属する品種(以下「職
務育成品種」という。)である場合を除き、あらかじめ使用者等が品種登録出願をす
ること、従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更すること又
は従業者等が品種登録を受けた場合には使用者等に育成者権を承継させ若しくは使
用者等のため専用利用権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条
項は、無効とする。
2 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務育成品種について、使用
者等が品種登録出願をしたとき、従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使
用者等に変更したとき、又は従業者等が品種登録を受けた場合において使用者等に
育成者権を承継させ若しくは使用者等のため専用利用権を設定したときは、使用者
等に対し、その職務育成品種により使用者等が受けるべき利益の額及びその職務育
成品種の育成がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定められる対価
の支払を請求することができる。
3 使用者等又はその一般承継人は、従業者等又はその承継人が職務育成品種につい
て品種登録を受けたときは、その育成者権について通常利用権を有する。
-125-

労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号) -抄-
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきも
のでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、
この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上
を図るように努めなければならない。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就
業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した
場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて
交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支
払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手
当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合において
は、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、こ
れに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関
する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めを
する場合においては、これに関する事項
(作成の手続)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過
半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組
織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かな
ければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添
付しなければならない。
-126-

(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その
減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における
賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
(法令及び労働協約との関係)
第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反して
はならない。
2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
(労働契約との関係)
第九十三条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法 (平成十九年法律
第百二十八号)第十二条 の定めるところによる。
労働組合法(昭和二十四年六月一日法律第百七十四号) -抄-
(目的)
第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進
することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交
渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労
働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係 を規
制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成すること
を目的とする。
2 (略)
労働契約法(平成十九年十二月五日法律第百二十八号) -抄-
(目的)
第一条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意によ
り成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を
定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにする
ことを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資すること を目
的とする。
(労働契約の成立)
第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃
金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
-127-

第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労
働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の
内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約にお
いて、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部 分に
ついては、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変
更することができる。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労
働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、
次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の
就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の 程
度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との
交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであ ると
きは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところに
よるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規 則の変更
によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に
該当する場合を除き、この限りでない。
(就業規則の変更に係る手続)
第十一条 就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十
九号)第八十九条 及び第九十条 の定めるところによる。
(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分
については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定
める基準による。
(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第十三条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分について
は、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働
者との間の労働契約については、適用しない。
-128-

教育基本法(平成十八年十二月二十二日法律第百二十号) -抄-
(教育の目的)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として
必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(大学)
第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真
理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、
社会の発展に寄与するものとする。
2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊
重されなければならない。
(教員)
第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と
修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 (略)
学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号) -抄-
第八十三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学
芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供
することにより、社会の発展に寄与するものとする。
第九十二条 大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければ
ならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教
授、助教又は助手を置かないことができる。
2 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置
くことができる。
3 ~ 5 (略)
6 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力
及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事
する。
7 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及
び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事す
る。
8 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する
者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
-129-

9 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事す
る。
10 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
第九十九条 大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は
高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文
化の進展に寄与することを目的とする。
国立大学法人法(平成十五年七月十六日法律第百十二号) -抄-
(目的)
第一条 この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が
国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設
置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置
して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定める
ことを目的とする。
(業務の範囲等)
第二十二条 国立大学法人は、次の業務を行う。
一 国立大学を設置し、これを運営すること。
二 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行
うこと。
三 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実
施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
四 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
五 当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
六 当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であっ
て政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を
行うこと。
七 産業競争力強化法 (平成二十五年法律第九十八号)第二十二条 の規定による
出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 ~ 3 (略)
-130-