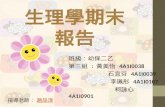特別支援学級における美術の造形活動を中心とした … › ~ckyk › kyoukakenkyu...
Transcript of 特別支援学級における美術の造形活動を中心とした … › ~ckyk › kyoukakenkyu...

特別支援学級における美術の造形活動を中心とした題材開発
- 感覚に直接働きかけ,内面表現を促す取組 -
柴田 緩子
美術科の授業において,発想を広げるために言葉が重要な役割を担うことが多い。しか
し,特別な支援を要する生徒たちは,言語を介した発想や,抽象的思考を苦手としている
ことがある。そこで,言語やイメージのみに頼るのではなく,具体物と直接かかわること
が重要だと考え,五感を駆使してモチーフとかかわり,そこから生じた思いを表現に活か
す題材開発を行った。実践を通して,生徒が自分の表現に自信を持つことができ,題材が
有効であるという結果が得られた。それらの実践をまとめ,『自分らしさに出会える造形活
動~感覚に働きかける題材・授業実践集』を作成した。
キーワード:感覚に働きかける,内面表現,自分らしさ,『造形題材・授業実践集』
Ⅰ 主題設定の理由
心の中にある漠然とした思いや感情を色や形として表現することは容易なことではない。通常学級
における授業では,キーワードによるウェビングなど,過去の自分の経験や記憶を言葉で再現するこ
とでイメージを明確にし,発想・構想を進めてきた。中学校学習指導要領解説美術編にも「抽象的な
言葉にも理解が深まる時期なので,対象から感じ取ったイメージや,自己を見つめて生じた感情など
を言葉にして書きとどめ,それを基に主題を考えさせる」ことが提示されている。
しかし特別支援学級の生徒たちにとっては,言葉や文章で表現すること,抽象的に思考することは
苦手なことである。そのため,誰かの模倣や,常に同じパターンで描くことで,とりあえず完成形に
たどり着くことが目標となってしまっており,「自分の思い」を表現するには至っていない。
そこで着目したのが「臨床美術」の考え方である。感覚を刺激して題材に迫り,工程を追って描き
進めることで個々の感性溢れる表現を引き出すことができるという。普段作品制作するときに使うの
は視覚が主であるが,五感を総動員して制作することで,表面的な形の写し取りが上手い下手ではな
く,モチーフの持つ本質的なものや,モチーフから感じたイメージそのものの表現に至ることができ
るのではないかと考えた。
また,五感を刺激して内面表現を促すことができる題材を開発し,題材集としてまとめることで,
特別支援学級担任が参考にして取り組みやすくなるのではないかと考えた。以上のことから本研究主
題を設定した。
Ⅱ 研究の目的
特別支援学級に在籍する生徒の美術の造形活動において,感覚(視・聴・味・触・嗅覚等)を刺激
することで,イメージを膨らませ,自分らしい内面表現ができる題材の開発を行う。
Ⅲ 題材開発の基本方針
通常の造形活動は,対象を目で見て,自分の表現している状態を目で見て,画材を手で持ち,作品
に触れながら表現している。つまり,視覚と触覚が主体となっている。
しかし目と手以外の感覚も大いに使って,体全体で感じながら表現することで,その表現の中には
「自分が感じたこと」が表れるのではないだろうか。対象とのかかわりを楽しみながら,そこに生じ
た自分の思いをそのまま素直に表現することで,他の誰のものでもない「自分」の作品をつくること
ができるのではないだろうかと考えた。以上のことから次のような基本方針で題材開発を行う。

【題材開発の基本方針】
・目と手以外の感覚を駆使する題材である。
・体全体で対象とかかわり,それを楽しめる活動である。
・制作において「感じる」ことが必要感のある活動になっている。
・自分の感じたこと,思ったことが表現に現れている。
・活動後の充実感が得られる題材である。
・美術専科ではない教師も取り組めるような内容である。
Ⅳ 研究の計画 自分らしい内面表現を引き出す
○基本方針に基づいた題材開発を行う。
○特別支援学校等を訪問し,題材や題材提示の仕方を収集 基本方針
する。
○特別支援学級生徒の実態に合わせて題材を再構成し,開
発した中から実践する。 題材開発
○生徒に対する事前事後の意識調査,行動観察と作品分析 +
により,題材が内面表現を促すことに有効であったかを (特別支援学校等から収集)
検証する。
○開発した題材を『自分らしさに出会える造形活動~感覚
に働きかける題材・授業実践集』にまとめる。 実 践
検証・考察
Ⅴ 研究の内容
1 題材構想 造形題材・授業実践集
基本方針に基づき,次のような題材を構想した。
■感じる × 描く
①感じたままに描こう(味・嗅)
②視点を変えて描こう(視・味・嗅・触) ■感じる × つくる
③育てながら描こう(視・味・嗅・触) ①手で感じてつくろう(触)
④気持ちのままに描こう(視・触) ②動きをつくろう(視・触)
⑤音楽を描こう(聴・触) ③気持ちの種をつくろう(触・嗅)
⑥小さなものを大きく描こう(視・触) ④音楽をつくろう(聴・触)
2 研究協力校での取組
(1) 実態を考慮した題材設定
研究協力校のK中学校特別支援学級は知的障害学級4名,情緒障害学級1名が在籍している。朝
の会や給食,技能教科等,多くの時間を交流学級で過ごし,大変意欲的に取り組んでいる。特別支
援学級での生徒たちは発言も多いが,交流学級では緊張のためか,自分を出せていないことを学級
担任から聞いた。
本研究の対象を第1学年2名とし,事前に個別のアンケートを実施した。それによると,美術は
比較的好きな教科であるが,授業の中で困ることもある。また,周囲を気にして集中できないこと
もあるようだ。困る内容としては「イメージがわかない」「イメージはあるが,どう表せばよいか分
からない」「自分の作品を友達に見られたくない」ということである。
写実的な作品がよい作品であるという捉えから,自身も写実的に描きたいという欲求も高いと思
われる。そこで,写実とは,対象の輪郭線を正確に描き出すことではなく,対象の本質を捉えて描く
ことであるということを感じさせたいと考えた。対象を視覚だけで捉えず,嗅覚,味覚,触覚をも使
ってしっかりとかかわることで,それが可能になるのではないかと考えて以下の題材に取り組んだ。
図1 研究の流れ

(2) 検証授業及び考察
○「感じる × 描く-果物や野菜を描こう-」
【題材の目標】
・対象とのかかわりを楽しみながら,自分の感じたことを表現しようとする。
・感じ取った自分のイメージをもとに色や形を生み出すことができる。
・オイルパステルの特徴を活かして生き生きと表すことができる。
・自他のよさや思いを感じながら作品を味わおうとしている。
【指導計画】
主な学習活動 時間 主な学習活動 時間
① 感じたままに描こう 1
② 視点を変えて描こう 1
③ 育てながら描こう
Ⅰ 根菜の育った土を意識し 1 Ⅱ 種から大きく育っていく 1
ながら下地を作る ように描く
①「感じたままに描こう」
モチーフの外観ではない部分に意識を向け,味覚を色と形だけで表現することにより,対象を深く
見つめた自分の思いを表現でき,表現の幅を広げることができるのではないか。その際,筆圧や手の
動きがそのまま画面に現れ,混色も容易なオイルパステルが適当であると考えた。
ねらい:味や香りから感じたことをもとに,色や形を見付けて表すことができる。
導入 オイルパステルに慣れ,画材の特徴を確認する。
中心活動 りんご酢・ワインビネガー・レモン汁のいずれかの香りと味を確かめ,感じたこと
を色と形で表す。
●思いを引き出せたか
「強い刺激」が表現を引き出すと考えたが,「表現したい」と思える刺激
でなければ,満足のいく表現には至らないと思われる。今回は「酸っぱい」
味覚を描いたが,「甘い」味覚や,様々な味覚の違いを表現するなど,取り
組み方を変えてみる必要がある。現段階ではこの題材で内面表現を引き出
せたという手応えはない。同じ「酸っぱい」でも表し方はそれぞれ異なる
んだという気付きは得られた。
②「視点を変えて描こう」
モチーフの周囲,つまり地の部分の形に着目することで,目の前にある形の微妙なフォルムに目を
向けられるようにする。そうすることで,既成のイメージではなく,モチーフとのかかわりを基に表
現することでき,対象の美しさの受け止め方,見方を広げることができるのではないかと考えた。
ねらい:図と地を反転させて見ることにより,ありのままの形に目を向け,個々のモチーフら
しさを表現することができる
パプリカ,ズッキーニ,紫タマネギ,マンゴー,キウイ,
桃を準備し,会話しながら自分で気に入ったモチーフを選
導入 ぶ。
黒い画用紙の上にモチーフを置き,描画する白画用紙に
墨でモチーフの外側の形から描き込んでいく。
墨を乾燥させている間に,モチーフを持って質感や重さ
中心活動 を確かめたり,割って香りや味を確かめたりする。
モチーフの味や香りを基にオイルパステルを選び,墨で
塗り残した部分を塗る。その上に皮を被せるように色を塗り重ねる。
図3 外側から描く
図2 導入の作品

●思いを引き出せたか
モチーフを自分で切って味わうことを楽しんでいた。「甘かったから」「思ったより酸っぱかっ
った」という自分の感じたことが,色や描き方に表れていたと感じる。
お互いの作品を鑑賞する際も,形の上手下手を見るのではなく,「酸っぱそう」「ずっしりして
いる」「ツヤツヤしてるみたい」という,描き表そうとした所を見いだすことができた。
③「育てながら描こう」
生命感を描くために,背景となる土にも意識を向ける。そこから育つ野菜は,最初とても小さな種
であることを確認することで,生命力を実感できると考えた。それにより,存在感のある野菜が描け
るのではないかと考えた。
ねらい:野菜の育つ過程に思いを馳せながら,対象の量感や生命感を描くことができる。
モデリングペーストが塗られた画面にアクリル絵の具で着彩
事前 し,土を描く。その際,茶色は使わず赤・黄・黄緑・橙・青・
紫の中から3色程度選んで混色する。
筆や刷毛で描くが,直接手で描いてもよい。
事前に描いた画面について,どんな土か,何が育つかなどを
話す。種を観察した後に,野菜(今回はかぶ)を観察して香り
中心活動 や味を確かめる。
最初に種を描き,その種をパステルでグルグル大きくしてい
きながら実を描く。その後葉や茎などを描いてから,和紙を水
ボンドで貼り付けながら細やかな表情をつけていく。
●思いを引き出せたか
小さな種と野菜を比べることで驚きと共に,
生命力を実感できた。味や香りから色を選び,
種から少しずつ大きく育てていくように描く
ことで,カブの輪郭線を追って描くことから
離れ,自分の表現意図を大切にした表現がで
きたと感じた。
特に生徒Aに関しては,頭の中にあるイメ
ージだけで描くことが苦手であることが分か
るが,モチーフとのかかわりの中で,表した
いことが生まれ,積極的に表現しようという
意識の高まりが感じられた。
図5 生徒Aの変容
○「感じる × つくる-手で感じてつくろう-」
【題材の目標】
・対象とのかかわりを楽しみながら,手で感じ取ったことを表現しようとする。
・対象から感じ取ったことを基にイメージを膨らませて,主題を生み出すことができる。
・全体と部分の形を意識しながら成形することができる。
・自他のよさや思いを感じながら作品を味わおうとしている。
モチーフを図6のような黒い箱に入れ,目には見えないようにした。手の感覚だけで表面の肌触
りや重さ,温度感,形の流れを感じ取る。見ることができない分,手に感覚を集中させることがで
きると考えた。また,普段生徒があまり馴染みがないであろうと思われるモチーフを準備すること
A「すきな野菜はない、描けない・・・」頭を伏せる
T「茶色を使わずに土の色をつくります。何色を選ぼうか?」
A「青と黄色と黄緑」「一気に垂らしていいですか?」
T「今日の土を描く活動はどうだったかな?楽しかった?」
A「わかんない」
T「どんな土を意識して描いたかな」
A「適当にやったらこうなった」
T「どんなカブを意識して描いたかな」
A「堂々としたカブ」
「葉っぱの大きさにこだわりました。」
図4 土を描く

で,物体が何であるという既成概念にとらわれずに自分の感覚を頼りに表現できるため,立体造形
表現に対する考え方,見方を広げることができると考えた。
ねらい:モチーフのフォルムや質感,量感を視覚ではなく,手で感じ取り,感じたことをもと
に主題を生み出し,形に表現することがきる。
中身の見えない黒い箱に手をいれ,モチーフ(カリフラワー,ハヤトウリ,ドラゴ
導入 ンフルーツ等,あまり馴染みのないもの)を手でしっかりと確認する。質感や重さな
ど,感じたことを自由に話す。
感じ取った触感や形の特徴,フォルムについて話しながら,何に焦点を当てて,ど
んなふうに表現してみたいのか見つける。表現には重量感のある紙粘土を使用する。
中心活動 時々モチーフを触って表現したいことを確かめながら制作する。
箱の中身とそっくり同じに作るのではなく,自分の手が感じ
たことをもとに,形を創り出す。
●思いを引き出せたか
複雑な形のモチーフの方が,形や触感等に変化があり,表現しやすかった。
一方,単純な形では,どこに面白さを見いだし表現につなげるか,苦労して
いた。同じモチーフで,それぞれ異なる表現の面白さを味わえるとよかった
のかもしれない。または,様々なモチーフを手で確かめ,自分で表現したい
ものを選ぶとよかったのではないか。
視覚に頼りがちな日常の中,何も視覚的情報がないところで,悩みながら
も自分の形を生み出した達成感があったようだ。「満足のいく作品ができた」
という発言があった。
(3)特別支援学校での実践
題材構想の中から描く題材一つを特別支援学校高等部で実
践する機会を得た。初対面の生徒たちであったので,「感じる
× 描く-音楽を描こう-」の前に,ウォーミングアップの題
材を組み込んで2時間題材として取り組んだ。
普段,造形的な活動にはあまり取り組むことがなかったと
いう生徒からも「またやってみたい」「楽しかった」という感
想が得られ,手応えを感じた。
参観した特別支援学校の先生からは「題材のアイディアが
新鮮だった。普段見られない豊かな表情が見られた。」等のプ
ラスの評価を得た。一方,時間設定や,活動スペース,説明
の仕方等における課題と改善点も得ることができた。
今後,地域の特別支援学校との交流の一助として題材を活
用していくことも可能であると感じた。 図7 特別支援学校での取組
3『自分らしさに出会える造形活動~感覚に働きかける題材・授業実践集』の作成
これまでの実践を『自分らしさに出会える造形活動~感覚に働きかける題材・授業実践集』にまと
めた。「Ⅰ章 はじめに」では美術科という教科についてや,題材・授業実践集のコンセプト,使い
方について説明し,「Ⅱ章 感覚に働きかけて造形する実践例」にこれまでの実践を図8のようなペ
ージ構成で掲載した。「Ⅲ章 感覚に働きかけて鑑賞する題材例」と「Ⅳ章 技法いろいろ」では,
その他,手軽に取り組める技法や鑑賞活動についての実践紹介,身近な材料を使った描画道具の紹介
をしている。
図6 教材と作品

Ⅵ まとめ
1 開発した題材について
抽象表現にあまり馴染みのない生徒の場合,導入で①「感じたままに描こう」に取り組むことが効
果的であった。“線と面と点”で美しい画面をつくることができること,形のないものの表現は多様
であることを実感し,モチーフの見方・捉え方を広げ,表現の幅を広げられる。また,各題材とも工
程を追って制作を進めていくので,生徒自身が題材に抵抗感なく,安心して取り組めたと振り返って
いる。授業参観した小学校教諭から「小学校でも参考にして取り組めそうだ」との感想を得た。工程
を追うことが,美術専科ではない教師にとっても,取り組みやすさにつながるのではないかと感じた。
2 自分らしい内面表現について
K中学校での授業実践後,生徒A「野菜は嫌いだけど,形を表現できた。もっとやりたいと思った。」
生徒B「野菜は色々な特徴があり,色々な角度から見ると世界が変わり楽しかった。またやりたい。」
という感想を得た。特に,制作においてイメージがわかずに困ることが多かった生徒Aは“視点を変
えて描く”活動を通して「自分の表現に自信が持てた」と振り返っている。描くことが苦手な生徒で
も,対象と楽しくかかわる中で新たな気付きが得られ,表現につながっていくことを実感できた。対
象への目の向け方,表現に対する考え方が広がり,自分の思いを作品に表すことができたと捉える。
3 今後に向けて
1単位時間完結型を目指して題材開発をしたが,活用に際しては,生徒の実態や時間割に合わせて
柔軟に取り組む必要がある。また 26 年度は,美術専科以外の教師に実際に『造形題材・授業実践集』
を活用してもらい,更に意見を取り入れながら改善していきたい。
〈参考文献〉
金子健二(2007)『改訂 臨床美術 認知症治療としてのアートセラピー』日本地域社会研究所
金子光史(2008)『アートびっくり箱 障害のある子どもの絵画指導』学研教育出版
芸術造形研究所(2008)『金子健二の言葉から学ぶ臨床美術の重要ポイント 触れる,聞く,ほめる。』
日本地域社会研究所
B.エドワーズ(2003)『脳の右側で描け【第3版】』エルテ出版
図8 造形題材・授業実践集ページ構成
準備するものを
写真で分かりやすく
生徒の作品掲載
生徒との実際の
やりとり
板書の仕方を
紹介する
実践してみての
改善点
流れとおよその時間
ねらい
題材観
画材
準備
題材名,働きかける感覚,時数