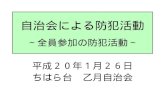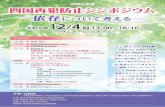「女性に対する暴力」を根絶するための課題と対策 ~性犯罪へ ... · 2018-12-10 · 成立した犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。資料6参照。)により、
犯罪収益移転防止法する法律が成立した。...
Transcript of 犯罪収益移転防止法する法律が成立した。...

11 ●2014年(平成26年)12 月 1 日発行 � 国際刑事立法対策ニュース(お問い合わせは各委員会へお願いいたします)
国際刑事立法対策 国際刑事立法対策 編集責任:国際刑事立法対策委員会 編集責任:国際刑事立法対策委員会
ニュース
2014.12.1No.22
本年11月19日、犯罪による収益の移転防止に関
する法律(以下「犯収法」という。)の一部を改正
する法律が成立した。
犯収法は、事業者による顧客管理措置を強化する
ため、平成23年に改正されたばかりである。平成
25年4月1日より改正法が施行され、わずか1年で再
度改正が必要となった。その背景には、国際的な規
制強化の動きがある。マネー・ローンダリング対策
を推進する FATF(Financial Action Task Force:金
融活動作業部会)は、日本のマネー・ローンダリン
グ対策の不備に懸念を表明し、本年6月、迅速な対
応を促す声明を公表した。これを受け、警察庁が設
置した「マネー・ローンダリング対策等に関する懇
談会」は、本年7月17日、顧客管理措置の再強化を
提言する報告書(以下「懇談会報告書」という。)
をとりまとめた。※1
今回の法改正により、国家公安委員会は、マネー・
ローンダリングの手口その他の状況に関して調査及
び分析を行い、事業者が行う取引の種別ごとにマ
ネー・ローンダリングのリスクを分析し、その結果
を犯罪収益移転危険度調査書としてまとめることに
なる。FATFが勧告するリスク・ベース・アプロー
チを採用する前提として、リスク分析に取り組むも
のと理解される。弁護士は、「依頼者の本人特定事
項の確認及び記録保存等に関する規程」(以下「本
規程」という。)第6条に基づき、法律事務の依頼を
受けるときは、依頼目的が犯罪収益の移転に関わる
ものか慎重に検討する義務があるが、その検討にあ
たってリスクを知る必要がある。もとよりマネー・
ローンダリングのリスクは、事業者によって差があ
ることから、事業者の特性を問わず横断的に一律に
規制するのではなく、事業者のリスクに応じた対応
が効果的になされるべきである(本年8月29日付け
警察庁「マネー・ローンダリング対策等に関する懇
談会」報告書に関する日本弁護士連合会会長声明)。
当連合会では、FATFが公表した法律専門家向けリ
スク・ベース・アプローチガイダンスや法律専門家
がマネー・ローンダリングに巻き込まれる危険指標
を明らかにした2013年6月「マネー・ローンダリン
グ及びテロ資金供与に対する法律専門家の脆弱性に
ついて」と題する報告書を翻訳し、会員の業務の参
考に供してきた。※2 今後はこれらの資料に加えて
国家公安委員会の分析結果を参考にして、我が国の
弁護士に関わるマネー・ローンダリングのリスクを
把握していくこととなる。
改正法案は、事業者に対して、体制整備の努力義
務を拡充することを求めている。懇談会報告書は顧
客管理措置の厳格化、継続的な顧客管理などの措置
を提言しているが、これらは改正法案に規定されて
いない。改正法案を施行する政省令レベルで義務付
けられると予想される。犯収法第11条によると、弁
護士による本人特定事項の確認、記録作成・保存並
びにこれらを的確に行うための措置について、他の
士業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定め
るところによるとされている。今般の犯収法改正及
びこれを施行する政省令によって、他の士業者に適
用される体制整備、顧客管理措置の義務が強化され
たときには、当連合会においても本規程の改正の要
否を再び検討する必要が生じる。
コラプション(汚職・腐敗)として国際的な取組が
進められているのは、自国民による自国内での賄賂
の規制ではなく、外国公務員に対する贈賄の規制で
ある。我が国でも、1998年に経済協力開発機構(以下
「OECD」という。)で採択された国際商取引における
外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約を批准
し、同年及びその後の不正競争防止法の改正によっ
て対応が図られている。しかし我が国は OECDから、
その法執行が不十分であるとの批判を浴びており、
弁護士会としてのこの問題に対する積極的な取組も
見られないとの指摘を受けているところである。
2014年6月23日に開催されたコラプション防止対
策に関する勉強会は、コラプションに関する理解を
深めること、そしてその上で、弁護士ないし弁護士
会としてこの問題にどう取り組むことができるかを
探るための良い機会となった。講師は梅田徹氏(麗
澤大学教授)で、同氏はコラプションに取り組んで
いる著名な国際的 NGOのトランスペアレンシー・
インターナショナル(TI)の日本支部である NPO
法人トランスペアレンシー・ジャパン理事長(当時)
であり、我が国におけるこの問題の第一人者である。
梅田氏からは、TIの活動の紹介、コラプション
規制をめぐる国際的動向、腐敗の防止に関する国際
連合条約(日本は未批准)などについての解説があっ
た後、コラプションに関する重要な論点であるファ
シリテーション・ペイメント(FP)についての話
題となった。この FPとは、「少額の円滑化のための
支払」(動きの遅い公務員の行為を促進するための
少額の支払)を指し、商取引やその他の不当な利益
を得るための支払ではないとして、米国、カナダそ
の他、いくつかの国で規制の対象から外れているが、
我が国では明確な除外規定はなく、処罰リスクが否
定できないという問題が存在している。
コラプションの問題は、近年ますます重要度が高
まり、海外進出企業はコンプライアンスの観点から
この問題に対する対応を迫られている。コンプライ
アンスに関する法的助言を求められることのある弁
護士として、この問題から無縁ではいられないこと
は明らかであろう。
2014年10月6日から5日間、ウィーン国連本部
の国連麻薬犯罪防止事務所において2年毎に開催
されている第7回国際的な組織犯罪の防止に関す
る国際連合条約締結国会議に当連合会から派遣さ
れて出席した。同条約には人身取引、移民、銃器
に関する3つの議定書も付いているが、国連総会
において同条約が採択されてから14年が経過し
た本年10月現在、主要国で条約本体を批准してい
ないのは日本、韓国及びイランであり、議定書を
含めすべて批准していないのは日本と韓国だけで
あるため、日本はオブザーバーの立場であった。
本会合では、条約等の履行状況に関する審査メ
カニズムにスポットが当てられたほか、サイバー
犯罪、森林伐採・木材違法取引・動物捕獲等の環
境犯罪、偽薬の取引、臓器売買、生殖器切断によ
る女性と子供に対する暴力なども新たな国際組織
犯罪としてその対策の必要性が強調された。また、
本条約は、イタリアのジョバンニ・ファルコーネ
判事らがマフィアにより爆殺されたことを契機に
締結されたことから、同判事の妹とイタリアの司
法大臣が出席して同判事らを偲ぶサイドイベント
も行われた。日本政府代表団は、2020年に開催
される東京オリンピックを前に安全、安心な国を
目指すため、同条約等の内容に沿って国際組織犯
罪防止対策を新たに講じ、特に、人身取引に関し
ては新たな政策を行っている旨のステートメント
をしていた。同条約等の履行と履行審査のために
は人身取引の被害者保護など NGOや市民社会の
協力が不可欠であることを米国等の主要国が提唱
していたことが印象深かった。
国際刑事立法対策委員会事務局長 片山 達(第二東京弁護士会)
犯罪収益移転防止法の改正と弁護士業務への影響
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約締結国会議
※2 http://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/ icc/mimoto_kakunin.html
※1 http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/ kondan kai/kondankai.htm
国際刑事立法対策委員会副委員長 村上 康聡(東京弁護士会)
コラプション(汚職・腐敗)防止対策に関する勉強会 報告
第7回
国際刑事立法対策委員会副委員長 山岸 和彦(第二東京弁護士会)