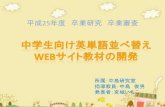建築工学科永井研究室 卒 業 研 究 ( 通年) 4’業... ·...
Transcript of 建築工学科永井研究室 卒 業 研 究 ( 通年) 4’業... ·...

建築工学科永井研究室
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
研究を遂行する上で、問題解決のための努力を厭わないこと、歴史的な建物調査や実測などの社会活動や研究室活動などに積極的に参加する意欲のある学生を望む。
下記内容について指導を実施する。・1か月に1度研究の進捗状況を把握し、実験の工程管理と研究の方向性を確認・研究を進める上での問題点・研究の纏め方・プレゼンテーションの纏め方と、プレゼンテーション能力
建築仕上材料は建物を守り、意匠性を付与する重要な素材である、材料の選定や施工方法によって、建物はテクスチャや印象が大きく変わる。さらに、材料の選定や納まりによって建物が長持ちしたり、早く劣化する。そのために、建築仕上材料は日々様々な開発がされている。人が一番近く接するのが仕上材料である。社会で求められている仕上材料やその施工方法の開発研究のためのテーマをみつけ実験・調査を通して以下の能力を身につける。・研究を纏める能力・問題解決能力・プレゼンテーション能力・コミュニケーション能力
下記の内容に従い評価する。・研究への取組みとコミュニケーション能力・実験・調査の工程管理・研究の纏める能力・プレゼンテーション能力
テーマにあわせて指導する
卒業研究を通して下記内容を履修する。・建築仕上材料の研究を通して、建設現場における問題点や課題を把握・研究の進め方や纏め方・グループで研究をすることでコミュニケーション能力を養う・プレゼンテーション能力を養う
過去の研究テーマ例①歴史的建造物の維持保全に関する研究②外壁よごれに関する研究③飯沼本家甲子蔵の実態調査④超高層建物の外壁材料・色彩調査・大規模修繕方法に関する研究⑤建築分野における光技術の開発研究⑥木材の有効利用に関する研究⑦新しい施工方法に関する研究
・建物における仕上材料の使われ方を日ごろから観察する・様々な仕上材料の特徴をよく理解する
卒 業 研 究
永井研究室(建築仕上材料研究室)TEL : 047-474-2508Email: [email protected]

建築工学科 塩川研究室
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
1.ダクト開口端反射減衰に関する研究 2.サウンドスケープに関する研究 3.室内音響設計
研究に関連する既往研究を調べて、専門的な知識を身につける。
卒 業 研 究
塩川研究室 津田沼5号館210号室 tel:047-474-2514 email:[email protected]
塩川 博義
定期的に研究内容について議論し、研究や設計の進め方、まとめ方を指導する。また、論文や図面のまとめ方、発表原稿の作成および発表方法について指導する。
建築音響および音環境に関するテーマを研究課題として、その目的に基づき、測定や調査あるいは設計をおこない、研究成果をまとめて、卒業論文・設計の審査会で発表を行う。
研究テーマに基づいた研究成果報告、論文や図面の提出内容および発表・質疑応答の状況等を含めて総合的に成績評価を行う。
研究テーマに応じて適宜選択する。

建築工学科 下村研究室
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
卒 業 研 究
津田沼校舎5号館303室(下村研究室:047-474-2523、[email protected])
①研究テーマ・研究の進め方の説明②研究テーマの選定後、以下の項目を実施・週1回 研究の進捗確認・議論・指導・月1回 卒研生全員による議論・指導・12~1月頃 論文作成・指導・卒業研究発表会
①実務における地盤工学の現状・課題の把握②研究課題の把握から成果報告までのプロセスの習得③調査能力・文章作成能力・コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力の向上
研究に取り組む態度70%、達成目標の到達度30%
随時提示する
主に以下の研究テーマを実施する①音による土質判別、②スウェーデン式サウンディング試験から直接液状化判定する方法の開発、③界面活性剤を活用した地盤改良体のばらつき低減、④山留め壁の鉛直支持力評価、⑤バイブロ工法により打設した杭の鉛直支持力評価および施工管理技術の開発
各研究テーマを実施に際して以下の項目を確実に遂行し、達成目標をクリアする①研究テーマの理解・選定、②研究工程の計画、③既往研究の調査・整理、④研究課題の把握、⑤実験・解析の実施、⑥研究成果のまとめ・公表(論文作成・プレゼンテーション)
地盤工学の復習

建築工学科 鎌田研究室
( 通年) 4 単位
木
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
卒 業 研 究
鎌田 研究室
実験を重視した研究を行うため、作業を厭わない学生を望む
前期で1、研究室での継続テーマの実施 データまとめ 報告会の実施を行い。2、単年度 研究テーマの選定 ・文献検索 ・卒業研究の着手を行い
後期では・データまとめ ・プレゼンテーションを実施し、最終的に卒業研究としてまとめあげる。
木質構造物の接合部や複合構造物に関する研究(実験)を行う中で、
1.実験の計画・実行・まとめを行い2.木質構造物の力学的な特徴を理解する。3. データまとめ・報告書等技術者として求められる最低限のスキルを身につける。
中間指導評価 50% 成果論文評価50%
木質構造設計基準・同解説 など
木質構造物の力学特性に関して、1)木質接合部の履歴特性に関する研究2)木質構造物の振動特性に関する研究など 構造物に限らず木材に関する多くのテーマを研究対象とします。
木質構造、木質材料について復習しておくこと。また、自分の行いたい研究テーマを見つけ、文献を読んでおくこと。

建築工学科 岩田研究室
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
興味を持った既往研究の資料収集
卒 業 研 究
岩田研究室 4号館306号室 tel:047-474-2492
社会の様々な出来事や問題に対して日頃から関心を持ち、建築に携わる立場として自分たちは「何ができるのか」,「何をすべきか」という意識を持って情報や知識を増やしておくこと。
・テーマ発見についての指導・調査手法や分析手法についての指導・文章の構成方法についての指導
目的と価値を定義し、適切な手段によって新しい知識を導く論理的思考のプロセスを習得する。
1.テーマ性(30%)2.調査・分析の手法の妥当性とその実践(30%)3.結果の論理性と文章の構成力(40%)
特になし
・最新既往研究についての学習(1-7週) 研究室で行った研究の紹介。 興味のある分野の既往研究を読み、研究の目的や方法について調べる。・研究テーマおよび研究・調査方法の検討(8-13週) 3-4名のグループで一つの研究テーマを決定。・研究・調査の実施(14−25週) 夏期休暇中明けに中間発表会を実施。・研究のまとめ(26-30週) 本文の執筆、学出講演会における発表、卒業論文審査会用パネルの作成

建築工学科
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
毎週1回のゼミで、その週に自分が行ったことをA4用紙1枚以上にまとめて発表する。自分の目で見て、頭で考え、分からないことは調べる、という作業を、とにかく毎週行うこと。
卒 業 研 究
亀井研究室4号館404室
毎週行うゼミで、その週に自分が行ったことをA4用紙1枚以上で報告する。自分の研究を第3者に分かるようにプレゼンテーションするだけでなく、友達の研究についても意見を出し一緒に考えることが求められる。研究の方法や分析については、内容ごとに異なるので、適宜研究に合わせた指導を行う。前期終了時(夏休み明け)に中間発表と中間概要提出を行う。
自分の興味・関心から、問題(事象)などを見つけ、解決の方向へとアプローチし、それを第3者に分かるように説明できるようになることを目標とする。その作業を行う中で、目的設定、調査手法・手段、結果の集計・分析、プレゼンテーション方法などを段階的に学んでいく。
毎週行う卒研ゼミでの成果物、中間発表、最終発表(概要・冊子含む)の総合評価
卒業論文の進め方 井上書院TEDトーク世界最高のプレゼン術 ジュレミー・ドノバン 新潮社すべてがわかる アンケートデータの分析 菅民郎 現代数学者
以下のテーマもしくは個人の興味のあるテーマについて研究を行う。平成27年度の具体的なテーマ例:a) 一般大衆誌における住宅・建築の取り上げられ方b) 黒沢隆研究(著作・作品等より)c) ドコモモジャパン選定建物等の一般公開についてd) 建築専門誌からよむ女性建築家「浜口ミホ」の思想その他、以下に関連するテーマでもよい。1) docomomo選定住宅の維持管理・評価2) 戦後戸建住宅の維持保存・継承3) 郊外戸建住宅団地の経年変化4) 近現代の住宅照明(岩井先生)について

建築工学科 廣田研究室
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
下記テーマは研究室の継続している研究テーマである。論文は下記より関連テーマを設定し,許可を得てからスタートする。設計は一定の規模以上とし,テーマは自由とする。
1.施設オープン化の方法論2.コミュニティ施設の計画論3.公共ストック空間の再活用方法4.建築の現代的クライテリア(評価軸・評価基準)と評価方法5.高齢者の住環境整備の方法6.習志野市の防災計画
・関連の既往研究をレビューしておくこと。・夏期休暇中に卒業設計で対象とする敷地調査を終えておくこと。
卒 業 研 究
廣田研究室:http://hirota-lab.arch.cit.nihon-u.ac.jp/TEL:047−474−2502mail:[email protected]
3月中にスプリングキャンプを行い,各自の研究テーマを決める。4月中は,過去の大会論文を用いて関連研究のレビューを行い,研究の枠組みを決める。5月から,本格的にスタート。まず,目的・方法・結論をつくる。レジュメ完成が目標。6月から,施設調査・アンケート調査開始。役所への調査依頼状を忘れずに。7月末で調査完了。8・9月で論文執筆。補足調査が必要になることもある。9月30日に論文提出。10月から卒業設計をスタートする。毎月中間報告会を行う。
1.公共建築における社会的な課題を設定し,解決方法を論理的に導く。2.現代の都市空間が有している建築的な課題に対して,解決のプログラムを組み立てて,図面や模 型で表現する。
前期:卒業論文後期:卒業設計
・卒業論文の書き方:井上書院・卒業設計の進め方:井上書院

建築工学科
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
深部体温、皮膚温、心拍数、血圧などの生体機能の測定方法、温度や湿度などの物理的温熱環境要素の測定方法を専門書などを通して予習しておくことが望ましい。
卒 業 研 究
三上研究室 津田沼校舎5号館209室Tel:047-474-2512E-mail:[email protected]
研究室の活動としてのボランティア活動に積極的に参加して欲しい。
定期的に卒業研究に関するミーティングを行い、その中で卒業研究に必要な基礎知識、調査及び実験の進め方、研究成果のまとめ方及びプレゼンテーション方法について指導する。
卒業研究における調査や実験を通して、①深部体温、皮膚温、温冷感、快適感などの温熱生理心理反応の測定及び評価方法を習得する。②温度、湿度、放射温度、気流速度などの温熱環境因子の測定及び評価方法を習得する。③新有効温度やPMVなどの温熱指標の使い方を習得する。④身体障がい者、高齢者の生理・心理・行動特性を理解する。⑤柔軟な思考能力、論文作成能力、プレゼンテーション能力を身に付ける。
普段の研究に取り組む姿勢と、2月上旬に開催される建築工学科卒業論文審査会でのプレゼンテーションにより評価を行う。
①空気調和・衛生工学会編:快適な温熱環境のメカニズム, 丸善, 1997②加藤象二郎他編:初学者のための生体機能の測り方, 日本出版サービス, 1999③日本建築学会編:室内温熱環境測定規準・同解説, 丸善, 2008④日本建築学会編:温熱心理・生理測定法規準・同解説, 丸善, 2014
平成27年度の卒業研究のテーマを以下に示す。①脊髄損傷者の温熱環境に関する研究②日本大学生産工学部の大学施設のエネルギー消費に関する実態調査と分析③バリアフリートイレ内のトイレカーテンのあり方に関する研究④ペルチェ素子を用いた接触式抜熱システムを搭載した車椅子の開発

建築工学科 師橋研究室
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
研究室で行われた既往の研究を卒業論文,学協会論文を通して学習する。また,学協会で発行している規準を調べ,現行の規準等との比較を行いながら研究の位置づけ理解しておく。
卒 業 研 究
師橋研究室 11号館101室 TEL:047-474-2534 [email protected]
実験作業を伴うことから,自主的かつ積極的な行動が取れる学生が望まれる。
通年という長い時間を掛けて研究指導が行われるので,受講する卒業研究生にも忍耐力が必要となる。研究は実験を行い現象を解明する手法を執っているので,実験計画,試験体の材料手配,試験体作成,載荷,データ整理,卒業論文の作成とボリュームがある。一つの研究テーマについて最後まで取り組み,その都度自分が直面する問題について解決する方法を教員の指導を受けながら進めることとなる。自分が進めている作業について,随時進捗状況を報告することで教員の指導を受ける機会を得て進展をはかり,研究資料をまとめる能力を養っていく。
卒業研究は,建築工学科の3年生までで学修した内容の総まとめとして位置づけられる科目である。従って,これまでの3年間で培った基礎学力や専門知識を基に応用力を養うことが達成目標のひとつとなる。それには,卒業研究生として所属した研究室が行って来た研究テーマを継承し,研究室に所属した仲間と共同で研究を遂行することにより,新しい知見を得ることが目標となる。特に,当研究室では建築構造設計系研究室として鉄筋コンクリート構造の構造特性を実験的研究により把握していく。
卒業研究の研究計画立案,実験参加状況および中間発表(20%),卒業論文審査会でのパネル発表および卒業研究概要(30%),卒業論文本論(50%)
再生骨材を用いるコンクリートの設計・製造・施工指針(案) 日本建築学会
繊維補強低品質再生骨材コンクリートの付着特性に関する研究:当研究室では,再生骨材コンクリートのより利用し易い環境を整えるため,最も品質が低い低品質再生骨材を用いた低品質再生骨材コンクリートを,乾燥収縮及び付着割裂強度の改善を目的としてビニロン繊維で補強し,梁部材の付着割裂強度を乾燥収縮ひび割れの影響を考慮して検討を進めている。低品質再生骨材コンクリートを対象としてた,乾燥収縮および乾燥収縮ひび割れについては材料学の観点から,梁部材の付着割裂強度については構造学の観点から解明を進める。また低品質再生骨材コンクリートは,地下構造部材や鋼管充填コンクリートなどに使用部位が限定されると想定されるため,構造モニタリングを長期的に行うことにより電気電子工学の観点からも視野に入れ,総合的に構造用コンクリートとしての有効利用の可能性を検討する。

建築工学科 篠崎健一研究室
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
卒 業 研 究
4号館2階 206号室 篠﨑健一研究室
特になし
卒業研究ゼミナールを定期的に行う。(原則毎週行う。)ここで研究の進捗状況を報告し、指導を受けなければならない。論文、設計とも、アプローチの方法は同じである。建築デザイン(意匠)、空間図式の探究、地域・ランドスケープデザインを基礎とし、研究および設計を行う。身近なことをテーマとし、ひとつひとつ作業や調査を重ね、それら基礎として論攷することで、高い次元へ到達するように求めたい。独創的な発想や新たな手法を構築し、説得力のある論理展開や計画とデザインを行うことを求めたい。常に、言葉を適切に使用することも、非常に大切であると考える。これもあわせて指導する。
テーマを発見する力、論理的に思考を重ねる力を養い、新たなものの見方を提示することを目標とする。設計においては、同様に論理的な思考のプロセスを求めるが、その上でそれを逸脱し、力強く説得力ある、豊かな空間を創造することが目標である。言葉や論理を弄するのではなく、空間に到達してほしい。これらのプロセスを通して、はっきりしたものの見方が示されなければならない。
卒業研究に取組む姿勢およびプロセス 50%, 卒業研究の結果 50%
その都度指示する。
基本的に卒業研究論文と卒業研究設計の両方をおこなうこととする。卒業研究論文は10月初旬までに完成する。上記研究テーマに基づいてグループで行うことを基本とするが、個人でおこなってもよい。その他のテーマについて探求したい場合は相談の上決定する。研究論文は、文献調査、フィールド調査(国内)を行い、ディスカッションを通してものの見方と得られる知見を整理し、論文としてまとめる。卒業研究設計は、原則、ひとり1テーマ(作品)とする。設計のテーマ、場所(敷地の選定)など設計の基礎となる事柄は、各自が発見し検討する必要がある。またその妥当性について、説得力のある説明をしなければならない。ひとつのプロジェクトを通して、密度濃く設計に勤しみ指導を受けることのできる機会である。これまで4年間に培った力を遺憾なく発揮されることを願う。
定期的に行うゼミナールにおいて、進捗状況を発表し指導を受けなければならない。発表に際しては、あらかじめレジュメ(論文・設計)やエスキース(設計)をまとめ、内容を全員が共有できるように準備しなければならない。これは、全員がすべての研究について、議論をし探究を深める機会であるからである。

建築工学科 小松研究室
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
授業科目として「鉄骨構造」,「鉄筋コンクリート構造」,「建築応用力学」,「建築構造力学」等の内容について十分に理解しておくこと。
卒 業 研 究
津田沼校舎6号館102室 小松研究室 047-474-2526
グループ研究が主体となるため,卒業研究生間の「和」をモットーとして,意欲的に研究室の活動に取り組む学生を期待しています。
第1段階では,研究テーマと直接関係した文献調査,研究テーマと関連する研究領域の動向・将来性などについての文献調査及び的確な研究計画の策定をさせる。第2段階では,研究計画に基づきデータの解析や収集を行わせる。さらに,研究の進捗状況を随時中間発表会等のプレゼンテーションにより発表を行うとともにグループ指導を行う。第3段階では,研究計画に基づいた実験あるいは解析手法によりえられた研究成果を,卒業論文としてまとめる。
設定した研究テーマについて,関連する既往の研究を文献等により調査を行い,その問題点を見いだす能力を身につける。そして,問題点の解決方法として実験および解析等による研究計画を行い,それに従って最終的に得られた成果を論文としてまとめ,同時に効果的にプレゼンテーションすることを到達目標とする。
研究への取り組み姿勢:50%達成目標への到達度 :50%
日本建築学会 構造関連規準書
鉄骨構造および合成構造について,次のようなテーマで卒業研究を行う。 ①組立補剛された山形鋼圧縮材の座屈耐力に関する研究 ②アルミニウムと木材による合成構造に関する研究 ③再生骨材コンクリートの合成構造への応用に関する研究 これらのテーマに関して実験および解析を行って行く。

建築工学科
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
卒 業 研 究
神田研究室
英語の能力が向上できる。
基礎学力を養うための勉強問題解決能力の育成論旨を有する文章の作成プレゼンテーション能力の育成
建築構造に関する基礎学力を養うとともに、実社会で建築物の構造設計を実施していけるような能力を養う。
週一回の打ち合わせ会、個別の打ち合わせ、学会などにおける論文発表、卒業論文かr総合的に評価する。
特になし
建築の構造全般多岐にわたる。
構造力学、応用力学の静力学のみならず振動工学のような動力学の基礎を学んでおく。

建築工学科 川島研究室
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室(連絡先)
備考(学生への連絡事項等)
以下の主テーマの中から一つを選び、各自提案書を作成し、プレゼンテーションを行う。次に、討議により主テーマごと1作品に絞り、グループワークにより研究計画書を作成し、役割分担を決めて研究を遂行する。1.フォルム構造システムのかたちと力の伝達機構に関する研究 -力の自然な流れを利用した構造の仕組みを考える-2. 曲げ構造システムのかたちと力の伝達機構に関する研究 -曲げモーメントに抵抗する合理的な構造の仕組みを考える-3.(中規模空間を対象とする)可動系構造システムに関する研究 -施工期間の短縮と解体・移築に相応しい構造の仕組みを考える-
建築構造力学Ⅰ~Ⅲ(外力と断面力の釣合、仮想仕事式による梁の変形、材端曲げとせん断力の基本式)および建築応用力学(断面力と応力度の関係、弾性曲線式、座屈)を復習しておくこと。
卒 業 研 究
川島研究室 津田沼校舎4号館103室TEL:047-474-2525 Email:[email protected]
川島 晃
卒業研究で大事なのは基礎的な知識を逐次積み重ねて専門の能力をスキルアップすることによりグループワークの中で能力を発揮しようとする(社会人基礎力を身に付ける)意欲です。研究室の諸活動に積極的に取り組む意欲のある学生を望む。
4月~6月:研究室における輪講と討議により研究テーマの理解を深める。7月:各自研究テーマを決めて、提案書を作成する。8月:第1週に提案書を発表し、グループ分けを行う。また研究計画書と役割分担を決める。9月~11月中旬:構造模型製作と予備実験(構造模型の精査期間)11月中旬~12月:本実験と構造解析および論文概要作成期間1月:本論作成
・グループワークによる研究計画に基づき、その役割分担を着実に達成できる。・建築構造力学に関する専門的思考力を高め、合わせて報告書を論理的にまとめ、かつ発表する 能力を身に付ける。
中間指導評価50%、成果論文評価50%
「空間デザインと構造フォルム」 Heino Engel著 培風館「自然な構造体」フライ・オットー著、岩村和夫訳 鹿島出版会「空間 構造 物語 ストラクチャーデザインのゆくえ」斎藤公男著 彰国社「力学と構造フォルム 建築構造入門」 望月洵著 (株)建築技術

建築工学科大内研究室
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
1.地域環境や歴史的文脈を認識し,設計内容に反映させる.2.複合的な設計条件を的確に把握し,合理的機能的に解決する.3.デザイン、構造計画・設計、環境・設備計画・設計に関する総合的に計画・設計する
卒 業 研 究
大内研究室 津田沼校舎4号館203号室Tel&Fax:047-474-2483(2538)Mail Adress:[email protected]
定期的に研究内容について議論し、研究の進め方、まとめ方を指導する。論文・設計を一体として、期間を設定して取り組み、最終成果を卒業作品として制作し学内外での発表会を行います。これまで、研究室にて学術雑誌や国際会議・国際コンペ等で成果を得てきた内容を下記にまとめる。■A分野:エコロジカルデザインKeyword :共生、レジリエンス、フラクタル、環境教育、環境心理、集落、ウォーターフロント、ICT、■B分野:サスティナブルデザインKeyword :景観、集住体、保存・再生、伝統技法や素材、コンパクトシティ、古代都市■C分野:ユニバーサルデザインKeyword:福祉、教育、医療、インテリア、GIS ・GPS、超高層、安心・安全、色彩と心理
現代社会の課題や文化・芸術における課題設定のもと、それらの解決策をまとめ卒業論文(前期提出)とします。さらに、社会に対する具体的な場所を各自設定し空間の提案として、企画、建築・都市計画・設計へと至る一連のプロセスから卒業制作としてまとめます。以上の成果品として、論文・設計を一体として、期間を設定して取り組み、最終成果を卒業作品(後期提出)としてまとめ上げます。
研究テーマに基づいた作品と研究成果の報告書、学内の学術講演会での発表の状況から成績評価を行う。
以下、国内外の学術雑誌や国際会議・国際コンペ等で成果を得てきたタイトルをまとめる。■A分野:エコロジカルデザイン1.日本太平洋の沿岸漁村地域の復興再生計画2.安全安心の地域社会に向けた持続可能な環境共生型街づくり3.GISによる景観認知の可視化モデルを用いた地域計画手法4.レジリエンスの向上に向けたコミュニティデザイン■B分野:サスティナブルデザイン1.集合住宅の集住体における児童をとりまく生命・成育環境の計画に関する研究2.フラクタル次元解析を用いた景観認知による可視化モデルの複雑性の定量化3.江戸東京の歴史的市街地における文化の継承4.歴史的都市鎌倉の景観デザイン■C分野:ユニバーサルデザイン1.救急医療システムによる生命環境モデルの構築2.古代ギリシャの都市・建築におけるアゴア(広場)の空間構造3.道路ネットワークと地域の狭域から広域にわたる防災・救急医療システム4..都市景観における街区の色彩構成と環境認知及び行動特性との相関

建築工学科 渡邉研究室
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
卒 業 研 究
4号館3階 渡邉研究室 tel:047-474-2488 [email protected]
場と場、人と人などの関係に対応する建築言語を見ていきながら、住宅・集合住宅・公共施設の魅力ある空間を各自の自由な視点(問題設定)で考察して卒業研究とし、特別設計や卒業設計つなげる指導をしていく。毎週の個人指導と月1回の合同発表。
物事の背後にある関係に気づく観察力と、論理的に言葉に表し、図やビジュアルに表現する力を身につける。
月1回の発表50%、最終発表50%
内容に合わせ選ぶ。
場所と場所の関係、人と人の関係、に対応する建築言語。魅力ある空間の関係性や空間構成。住宅の人の関係の研究。可動についての研究(ヒンジ、スライド、アジャスト、ガラリ、曲げる、空気、折れ戸)歩行空間の研究(曲がるタイミング・テンポ・角度、明暗、上る下る、幅狭く広く、水辺や植物)リフォーム、コンバージョン、住宅地、集合住宅、街並、玩具、遊具の研究。等、論文もしくは設計作品としてまとめる
自分の興味のあることがどういうことかを見つめ直すこと。

建築工学科 湯浅研究室
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
1.RC造の物性・劣化に関する研究2. RC造の非破壊試験方法の開発3.仕上塗材の劣化・RC 造保護機能に関する研究4.各種仕上材のコンクリート中の水分に起因した不具合に関する研究5.各種建築材料の劣化に関する研究6.RC造の解体に関する研究
随時、「建築構造材料」、「建築仕上材料」、「建築材料科学」、「建築保守管理」について復習すること。必要に応じて、高校の数学、物理、化学を復習すること。
卒 業 研 究
湯浅研究室 津田沼校舎5号館204号室Tel:047-474-2510Mail Adress:[email protected]
「建築構造材料」、「建築仕上材料」、「建築材料科学」、「建築保守管理」未修得者は、4年時に履修すること。
①研究目標を提示し、その目標を達成するための研究計画・実験計画を立てさせ、それをともに議論する。②実験遂行に責任を持たせ、随時その結果及び遂行上の問題点を報告してもらい、それをともに議論する。③結果を考察させ、その考察内容をともに議論する。④数回、その時点での研究の進捗状況、内容を発表させ、他の学生と議論させる。⑤卒業論文を作成させ、そのまとめ方について、ともに議論し、完成させる。⑥本人が担当した研究内容を、建築工学科主催の卒業論文審査会で報告させる。
1.担当した主題にそって実験計画をたて、実験日程がたてられること。2.実験を責任と誠意をもって実施できること。3.実験結果の整理を正確に行えること。4.論文を構成・作成できること。5.論文の概要を作成できること。6.研究内容を適切にパワーポイント等で説明できること。
成績評価は、研究室所属の卒業研究生、大学院生、教員が参加する数回の論文発表会と、提出された論文及びその概要を評価する。評価基準として重視するのは、論文・概要の内容、発表態度などが中心となるが、それらには研究活動全般に対する本人の意欲、積極性、努力などが自ずと反映されざるを得ないのが普通である。
随時提示する

建築工学科 藤本研究室
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
以下の主テーマについて、構造種別ごとにグループワークにより研究する。(1)各種合成構造に関する構造・耐震性能に関する研究(実験,解析,調査) 検討対象:①コンクリート充填鋼管(CFT)構造 ②鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)構造 ③繊維補強コンクリートを用いた鉄骨コンクリート(CES)構造(2)実建物の構造性能に関する研究(実測,解析,調査) 検討対象:①生産工学部キャンパス内建物 ②超高層建物(3)建築構造の歴史に関する研究(調査)研究領域:建築構造学、振動工学
建築構造力学,応用力学,建築実験,鉄筋コンクリート構造,鉄骨構造を復習しておくこと。
卒 業 研 究
Graduation research
藤本研究室 津田沼校舎11号館108室TEL:047-474-2530 Email:[email protected]
藤本 利昭
卒業研究で大事なのは基礎的な知識を積み重ねて専門の能力をスキルアップすることによりグループワークの中で能力を発揮しようとする意欲です(社会人基礎力を身に付ける)。研究室の諸活動に積極的に取り組む意欲のある学生を望む。
①研究室における輪講と討議により実践的な問題解決を図る。②また逐次中間発表会を行い,発表能力を身に付けさせる。③一定の成果の上がった研究については学内の学術講演会での論文発表なども実施する。
建築構造に関する実験・解析・調査を通して、①実際の建築物がどのように設計され,どの程度の構造安全性を有しているか理解を深める。②目的を達成するための手段(方法)を自ら計画(設計)し,実践(実験)することにより,問題解決能力を養う。③建築構造に関わる専門的思考力を高め,あわせて文章の書き方、発表の仕方などを身に付ける。
中間指導評価50%、成果論文評価50%
建築合成構造 松井千秋編著 オーム社コンクリート充填鋼管構造 松井千秋著 オーム社最新 耐震構造解析 柴田明徳 森北出版

建築工学科 北野研究室
( 通年) 4 単位
達成目標
研究指導の概要
学修の準備
履修内容
参 考 書
成績評価方法
研 究 室
備考(学生への連絡事項等)
卒 業 研 究
① 余暇活動(自由時間(余暇時間)に行う活動)と建築・都市空間(近隣空間を含み込んだ)の相補関係② 子供や高齢者を含み込んだ近隣空間における活動特性と連関する余暇空間・機能分布の最適化③ サスティナブルエリアデザイン(SAD)・コミュニティデザイン(CD)とコミュニティアーキテクト(CA)余暇活動(自由時間の活動)、余暇空間計画・デザイン、余暇環境、生活・居住環境づくり、サスティナブルエリアデザインに関連する上記の研究テーマの目的に基づき各種調査・分析等を行い、人・活動・空間・時間の相互浸透関係の視座から研究成果をまとめ、発表する。
定期的に研究内容について議論し、研究の進め方、まとめ方を指導する。併せて、発表原稿の作成及び発表方法について指導する。また、研究成果を基に設計競技・各種デザインに取り組み、創造力・構成力・デザイン力を養い、併せて社会活動(ワークショップ、ボランティア、イベント等)に積極的に参加し、社会性・協調性・コミュニケーション力を育む。〈条件〉卒業研究は論文と設計を行い、原則として論文は共同研究とし、設計は各自が設定したテーマとする。
① 資料等を参考にして研究テーマに関連する適切な情報を蓄積すると同時に、知識の習得の確認に努めること。② 研究課題に対する現況を良く認識し、問題点、改善すべき点を明確にすること。
①「余暇活動と建築・都市空間の相補関係」では、地域居住者の余暇活動と余暇空間の関係性について、時代背景と共に経年的な変容に着目し調査・分析を行い、特に生活活動に連関する近隣空間における余暇空間の時間・空間的計画方法論の観点から研究を進める。②「活動特性と連関する余暇空間・機能分布の最適化」では、余暇空間・施設計画の方向性として、特に近隣空間において、個別の空間・施設・機能の境界がなくなるような関係を有しながら、個々の活動者の主体的行動選択に対応した多様な余暇活動と空間が、時間を媒介として融合し得る情況づくりについて考える。③「サスティナブルエリアデザイン・コミュニティデザインとコミュニティアーキテクト」では、地域に持続・継承されてきた地域固有の活動・空間・時間を次世代に継承し、再生していくこと。継承されてきた生活・空間の秩序とそこで営まれてきた活動と調和するエリアの持続性。コンパクトであり、美しい持続可能な地域社会・環境の再生・創造に向けて、地域固有の自然・環境力、歴史・文化力、生活力、構想力、人間力そして再生力を紡ぎ出し、SADとCAの方策づくりへと展開する。(上記以外に個人的なテーマを希望する場合は、相談の上決定する。)
随時、関連情報を紹介すると共に、資料を配布する。 ・卒業論文の書き方(井上書院) ・卒業設計の進め方(井上書院)
研究テーマに基づいた研究成果、計画・設計提案作品の内容及び発表・質疑応答の状況から総合的に成績評価を行う。
北野研究室:4号館402室Phone:047-474-9697E-mail:[email protected]
共同研究(調査・研究論文)により協調性を養い、各自が設定するテーマに基づく計画・設計により創造性を育む。








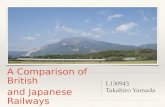



![第9回 麗澤大学国際経済学部国際産業情報学科 大塚研究室 卒論発表会 発表 … · 第9回麗澤大学大塚ゼミ卒論発表会 5 発表概要 [1] 渡部伸之(わたべ](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5ec8caa3cd03461bdb5f8514/c9-eecoeefecfc-cc-ece.jpg)