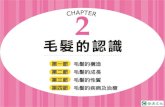.docx) - Wakkanai...1 第1章章章章 計画の策定にあたって計画の策定にあたって 第第第第1111節節節節 計画策定の趣旨計画策定の趣旨と目的
右枝節点繰上げ構文について€¦ ·...
Transcript of 右枝節点繰上げ構文について€¦ ·...

1.序
本稿では,次の(1)に示されているようないわゆる右枝節点繰上げ(Right Node
Raising : RNR)構文について考察する。
(1)a.I wrote and you sent the letter. ( = the letter) (Sanders 1977 :
247)
b.姉は犬を ,妹は猫を飼っている。( =飼っていて)
この構文が生成文法において,どのような構造からどのような過程を経て生成されるかという
問題は,未解決のままである。つまり,Ross(1967)以降この問題については異なるタイプ
の提案・仮説が示されてきたが,いずれのタイプのものについても不備があり,その不備はい
まだ解消されていない。
以下,第2節で英語の RNR構文の生成過程に関する先行研究を概観し,その問題点を紹介
する。次に第3節において,日本語の RNR構文の生成に関する先行研究の概観とその問題点
の紹介を行なう。続いて第4節において,RNR構文の生成過程に関する対案を生成文法の
「原理とパラミター理論(GB理論)」の枠組みに基づいて提示する。そして,その対案に基
づいて,第3節の日本語の RNR構文の生成に見られる先行研究の問題点がいかに解決される
かを考察する。最後に第5節において,第4節で仮説として提案された新たな分析の帰結の一
部として,第2節で示された英語の RNR構文に関する先行研究の問題点などもその分析によ
って解決されることを示す。
2.先行研究(一):英語のRNR構文の生成について
2.1.同一要素の移動を用いる分析
Ross(1967:97―98)によると,次の(2b)の RNR構文は,等位構造縮約(Conjunction
右枝節点繰上げ構文について
〔要 旨〕 本稿では,右枝節点繰上げ(Right Node Raising)構文について考察する。
生成文法において,この構文がどのような過程を経て生成されるかという問題は依然と
して解決されていない。本稿では,まず,英語と日本語のこの構文に関する先行研究を
概説し,その先行研究の問題点を示す。次に,生成文法の「原理とパラミター理論
(GB理論)」の枠組みに基づいて新たな仮説を提案する。そして,その提案によって,
先行研究に見られる問題点がいかに解決されるかを考察する。
〔キーワード〕 右枝節点繰上げ構文,同一要素の移動を用いる分析,同一要素の移動を
用いない分析,Saito(1987)の分析,三次元分析
岩 田 良 治
1

Reduction : CR)という(3)に示した規則の aによって(2a)から生成される。
(2)a.Sally might be pregnant, and everyone believes Sheila definitely is
pregnant.
b.Sally might be, and everyone believes Sheila definitely is, pregnant.
(3)Conjunction Reduction
a.[ and − [ X − A ]nB ]B
1 2 3OPT
[ 1 2 0]B#3
b.[ and − [ A − X ]nB ]B
1 2 3OPT
2#[ 1 0 3]B
Condition : all occurences of A are identical. (Ross 1967 : 220)
この(3a)の規則は,すべての被接続要素(conjunct)の右枝に生じている同一構成要素のコ
ピーを等位接続された節点(coordinate node)の右側にチョムスキー付加(Chomsky−
adjoin)し,元々の節点を削除する規則である。例えば,(2)を例にとると,規則(3a)は
基底構造(4)を(5)に変換する。
(4) S
and S S
NP VP NP VP
Sally might be V everyone V NP
pregnant believes it S
NP VP
Sheila definitely is V
pregnant
2 天理大学学報 第64巻第2号

(5) S
S V
and S S pregnant
NP VP NP VP
Sally might be everyone V NP
believes it S
NP VP
Sheila definitely is
問題点(�):Ross(1967:97)で指摘されているように,等位接続された節点にチョムスキ
ー付加される要素はすべての被接続要素に生じていなければならない。つまり CRは全域的
(across−the−board)に適用されなければならない。すると,Ross(1967:97)自身も述べ
ているように,CRは移動規則であるにもかかわらず,移動操作に課される普遍的制約である
(6)の等位構造制約(Coordinate Structure Constraint : CSC)に従わないということに
なる。(Ross 1967 : 96)
(6)Coordinate Structure Constraint
In a coordinate structure, no conjunct may be moved, nor may any element
contained in a conjunct be moved out of that conjunct. (Ross 1967 : 89)
問題点(�):CRの次の問題点は,Ross(1967:126―127)自身も指摘しているように,Ross
(1967)が普遍的な条件であるとしている次の随伴(pied−piping)という移動に関する
(7)の条件に関係している。
(7)No NP may be moved to the right out of the environment [ P ]NP. (Ross
1967 : 125)
この条件によって,例えば次の(8a)に見られるように,前置詞 ‘to’と後続する NP ‘my
friends’の随伴は義務的であり,NP ‘my friends’のみが移動した(8b)は非文となる。
(8)a.Mike talked about politics yesterday to my friends. (Ross 1967 : 125)
b.*Mike talked to about politics yesterday my friends. (ibid.)
しかし,次の(9)は CRがこの制約(7)の例外となることを示している。
右枝節点繰上げ構文について 3

(9)a.I am confident of, and my boss depends on, a successful outing at the
track. (Ross 1967 : 126)
b. S
and S S
NP VP NP VP
I am confident NP my boss V NP
P NP depends P NP
of a successful outing
at the track
on a successful outing
at the track
(Ross 1967 : 126)
(9b)のNP(= ‘a successful outing at the track’)のNPの右側の外部への移動は(7)の
条件によって禁じられるはずであるが,その移動の結果である(9a)は文法的である。以上
の例外性から考えて,RNR構文の生成に同一要素の移動を仮定する Ross(1967)の分析には
妥当性があるとは言い難い。
問題点(�):さらに,同一要素の移動を用いる分析に関する解釈上の問題点が木村(2005:41)によって指摘されている。次の(10)は動詞句削除(VP Deletion)が適用された文であ
る。
(10)Tom admires, and is sure that everyone else admires, Adolf Hitler, but of
course you and I don’t . ( = admire Adolf Hitler)(木村 2005:41)(ア
ンダーバーは筆者)
RNR構文の生成に関して移動を仮定する分析では,この例で ‘Adolf Hitler’は移動後は動詞句
内の要素ではない。一方,この例の ‘I don’t’以下の不在動詞句(missing VP)は ‘admire
Adolf Hitler’であり,この ‘Adolf Hitler’は動詞句内の要素である。(cf.McCawley 1982:
100)したがって,RNR構文に関して移動を仮定する分析では(10)のような動詞句削除が適
用された文で不在動詞句の解釈に関する現象を正しく捉えることができない。
問題点(�):RNR構文に関して移動を仮定する分析についての次の問題点は原口・鷲尾
(1988:155)で指摘されており,事例(11)に関係している。
(11)Smith loaned ― and his widow later donated ― a valuable collection of
manuscripts to the library. (Abbot 1976)
4 天理大学学報 第64巻第2号

この例の ‘a valuable collection of manuscripts to the library’は構成素(constituent)では
ない。移動規則は構成素のみに適用されるとすると,この事例は移動規則によって生成された
ものではないことを示している(1)。
2.2.同一要素の移動を用いない分析
Kimura(1986:123)は次の(12)の仮説に基づいて RNR構文の構造として,概略(13)
に示したものを提案している。
(12)a.The structure−preserving nature of RNRs
A “right−node−raised” element is located within the conjunct adjacent to it.
b.An interpretive analysis of RNRs
The rule involved in RNRs is an interpretive (or semantic interpretation)
rule.
(13) S’
S’ and S’
A B △i C D Xi
この分析では同一要素の上昇移動を伴わず,(13)の△iには解釈規則によって Xiの解釈が与
えられる。したがって,2.1節の Ross(1967)の CRと移動に課される普遍的制約との関係
に関して生じる問題は生じることはなく,また移動を仮定する分析に対して動詞句削除に係わ
る現象に関して指摘された問題(cf.(10))も生じることはない。
問題点(�):同一要素の移動を仮定しない上記の Kimura(1986)の分析の第1の問題点は,
空範疇(=(13)の△i)についてである。照応形(anaphor)である空範疇は岩田(1993;
1998:155)でも指摘されているように,NP痕跡でも PROでもありえず,また(14)に示し
た束縛理論(Binding Theory)の原理の(A)に違反もするので,そのような空範疇を持つ基
底構造を仮定することはできない。
(14)照応形は,その統率範疇内で束縛されていなければならない。(Chomsky 1981 :
188)
問題点(�):原口・鷲尾(1988:157)によると,上記の Kimura(1986:123)の分析には
次のような言語事実に関して問題が生じる。
(15)a.What did John argue, and Mary negotiate, with Fred about?(原口・鷲尾
(1988:157)
b.*John argued, and what did Mary negotiate with Fred about? (ibid.)
右枝節点繰上げ構文について 5

すなわち,上記(12),(13)のような分析では,(15a)に見られる wh移動は右側の等位項内
の wh要素をその外側に移動したものであるので,CSCに抵触し,非文法的になるはずであ
る。また(15b)は,適格であると予測されることになる。このように,Kimura(1986)の
分析はこのような事例に関して事実を正しく予測することができない。
以上のように,RNR構文が生成文法においてどのような構造からどのような派生過程で生
成されるかという問題,および RNR構文に関する言語事実がどのように説明されるかという
問題に対して,上記の移動を用いる分析と移動を用いない分析のいずれを仮定しても適切な説
明を与えることができない。
3.先行研究(二):日本語のRNR構文の生成について
まず,田川(2008:2)によると,日本語の RNR構文には次の特徴がある。
(i)RNR(=本節の(�)―(�)では,2.1.節や2.2.節の分析とは異なり,同一要素の削除)は等位構造の左側の等位項にのみ適用される。
(16)a.太郎はリンゴが好きで,花子はなしが好きだ。
b.*太郎はリンゴが好きで,花子はなしが好きだ。(田川 2008:2)
(�)RNRは等位接続の左側の等位項の右端にのみ適用される。(=中間位削除
(medial deletion)はできない。)
(17)*太郎は教科書を買い,花子は教科書を借りた。(田川 2008:1)
(cf.太郎は教科書を買い,花子は教科書を借りた。)
(�)端であれば構成素を成していなくても RNRを適用できる。
(18)太郎は次郎が花子を殺したと思い,次郎は太郎が花子を殺したと思った。
(cf.[VP[CP[TP次郎が[VP花子を殺し]た]と]思い])
次に,日本語の RNR構文に関する代表的な先行研究である Saito(1987)の分析を概観す
る。Saito(1987:321)は,いくつかの証拠に基づいて,RNRは,日本語では,かき混ぜ
(scrambling)と同じように,S構造レベルでの移動であると仮定する。しかしながら,
RNRという移動は,かき混ぜと違って,次の(19)の束縛理論の条件と(20)の適正束縛条
件(Proper Binding Condition)に従わない。
(19)A pronoun cannot c−command its antecedent.(Saito 1987 : 321)
(20)Traces must be bound.(ibid.)
次の例は RNRが(20)の適正束縛条件に従わないことを示している。
(21)John−ni hana−o, soshite Bill−ni tyokoreeto−o, Mary−ga okutta(koto)
6 天理大学学報 第64巻第2号

−to flower−acc and −to chocolate−acc −nom sent fact
(Saito 1987 : 322)
(21)では主語と動詞が RNRという移動を受けており,その構造は次のものであると仮定
されている。
(22) S
S Sk
S soshite S NP VP
PPi S PPi S Mary−ga ti tj V
John−ni NPj tk Bill−ni NPj tk okutta
hana−o tyokoreeto−o
(ibid.)
この構造から分かるように,まず,それぞれの等位項の間接目的語と直接目的語が Sに付加
され,次に最下位の Sが右枝節点繰上げとして移動されている。しかしながら,この構造の
痕跡である tiと tjは先行詞によって C統御(c−command)されていない。したがって,
(22)の分析では,(21)は事実に反して(20)の適正束縛条件によって非文法的であるとし
て排除されることになる。その結果,Saito(1987:323)は RNRという移動は適正束縛条件
(20)の制約を受けないという例外性を仮定している。
次に,(23)の例は(19)の束縛条件が RNRに適用されないということを示している。
(23)a.*Mary−ga ototoi, soshite karei−ga kinoo,
-nom the−day−before−yesterday and he−nom yesterday
[NP [S Johni−ni aitagatte ita ] hito ] −o tazuneta(koto)
-to wanted−to−see person −acc visited fact*‘Mary visited the person who wanted to see Johni the day before
yesterday, and hei visited the person who wanted to see Johni yesterday.’
(Saito 1987 : 324)
b.*Mary−ga Nancy−o, soshite Susan−ga karei−o
-nom −acc and −nom −acc
[NP [S Johni−ni aitagatte ita ] hito ] −ni syookaishita(koto)
−to wanted−to−see person −to intoduced fact*‘Mary introduced Nancy to the person who wanted to see Johni, and
Susan introduced himi to the person who wanted to see Johni.’ (ibid.)
右枝節点繰上げ構文について 7

RNRが(22)のような構造を導く移動であるという仮定のもとでは,(23a)と(23b)の
‘kare’が C統御する先行詞は存在しない。その結果,(19)の束縛理論の条件に従えば(23a)
と(23b)は文法的になるはずであるが,事実は逆である。したがって,Saito(1987)の分析
のもとでは,RNRという移動は束縛理論の条件に例外的に従わないと仮定しなければならな
くなる。
4.対案
RNRという操作が等位構造のみに適用できるもの,あるいは RNR構文は等位構文のみに
生じるものであるとすると(cf.岩田1998:67),RNR構文は生成文法の等位構造から生成さ
れることになる。では,その等位構造はどのような構造であるのか。等位構文の構造に対する
生成文法の従来の研究では,線状的構造に基づく分析と非線状的構造に基づく分析があるが,
本稿では,岩田(2012)に従って,等位構文は非線状な三次元構造を持つという分析を仮定す
る。その結果,RNR構文は非線状的三次元等位構造から生成されると仮定することになる。
それでは,上述の三次元分析に基づいて,第3節の日本語の RNR構文に関する先行研究で
ある Saito(1987)の分析の問題点がどのように解決されるかを考察する。第1に,適正束縛
条件に係わる事例(21)の基底構造は,三次元分析では次のものとなる。
(24) S
NP VP
S Mary−ga NP NP V
NP VP Bill−ni tyokoreeto−o okutta
Mary−ga NP NP V
John−ni hana−o okutta
この構造に「かき混ぜ」規則が適用されると,次の(25)が得られる。
8 天理大学学報 第64巻第2号

(25) S
PPi S
S Bill−ni NPj S
PPi S tyokoreeto−o NP VP
John−ni NPj S Mary−ga ti tj V
hana−o NP VP okutta
Mary−ga ti tj V
okutta
この構造の2つの等位項に共通の要素(=(25)の2つの[S [NP Mary−ga ] [VP ti tj [V okutta
]]])を単一の構成素として表示すると次の構造が得られる(cf.岩田 1998:17)(2)。
(26) S
PPi S
S Bill−ni NPj
PPi S tyokoreeto−o
John−ni NPj S
hana−o NP VP
Mary−ga ti tj V
okutta
この構造において,tiと tjという痕跡はそれぞれの先行詞によって C統御されるので,適正
束縛条件に関する上記の問題はこの分析では生じない。そして,この三次元構造を次の(27)
のように略記すると,文法の PF部門でこの構造に(28)に示した直線化規約(linearization
convention : LC)に従って音声解釈規則が適用されると(21)が生成される。
右枝節点繰上げ構文について 9

[ Johni−ni hanaj−o
(27) Mary−ga ti tj okutta ]
[ Billi −ni tyokoreetoj−o
(28)直線化規約(LC):次の構造において,
(a)X1と X2の右側に同一の要素がある場合は,その同一の要素より先に X1と X2を
解釈しなければならない。
(b)すべての X1と X2は同じ順序に解釈されなければならない。
(c)X1と X2の同じ左枝の位置に共通して含まれる要素の二度目およびそれ以降の
解釈に際しては,それ(ら)をゼロと解釈してもよい。
(d)X1と X2を解釈する際に,X1と X2の一方に等位接続要素(の音韻素性と形式素
性)を付加してもよい。
X1
X2(X(≠O)は要素の連鎖あるいはその一部である)
(岩田(2012:10))
次に,Saito(1987)の束縛条件に係わる例えば(23a)(の関係する部分)には,三次元分
析のもとでは,概略,次の構造が与えられる。
Mary−ga ototoi
(29) Johni −ni aitagatte ita
karei −ga kinoo
この構造において,代名詞である ‘kare’がその先行詞 ‘John’を C統御するので,この構造は
上記の束縛理論の条件に違反し,その結果,事例(23a)は非文法的となる。このように,本
稿の三次元分析のもとでは,上記の Saito(1987)の場合と違って,日本語のこの種の事例の
言語事実は正しく説明される。
5.三次元分析の帰結
ここでは,英語の RNR構文に関する先行研究の分析に関して第2節で指摘された問題点が
第4節の三次元分析に基づいてどのように解決されるかを考察することにする。
まず,Ross(1967)の問題点から考察する。(2a)の三次元構造は,概略,次のものである。
Sally might be
(30) pregnant
everyone believes Sheila definitely is
そして,この構造に LCに従って音声解釈規則が適用されて(2b)が生成される。この構造に
移動規則は適用されていないので,Ross(1967)のような同一要素の移動を仮定する分析の
場合と違って,等位構造制約が適用されないという例外性はこの三次元分析の場合には生じな
い。
10 天理大学学報 第64巻第2号

次に,(9a)は,概略,次の三次元構造を持つ。
I am confident of
(31) a successful outing at the track
my boss depends on
この構造に LCに従って音声解釈規則が適用されて(9a)が生成される。この構造では,‘a
successful outing at the track’は上記の Ross(1967)の分析のように移動の適用を受けた要
素ではないので,上記の移動を伴う分析が随伴という移動に関する(7)の条件に関して抱え
る問題は,本稿の三次元分析のもとでは存在しない。
さらに,2.1節での動詞句削除に関する言語現象についての問題を考えてみる。(10)に対
する三次元分析のもとでの構造は概略,次のものである。
[VP admires
(32) [IP1Tom Adolf Hitler ]]
is sure that everyone else [VP admires
[IP2 of course you and I don’t [VP admire Adolf Hitler ]]
この構造において,IP1の‘admires Adolf Hitler’の ‘Adolf Hitler’は IP2の動詞句の場合と同じ
ように動詞句内の要素であるので,2.1節で移動分析に関して指摘された問題は生じない。
そして,移動分析の4つ目の問題点に係わる事例(11)の三次元構造は次のものである。
Smith [VP loaned
(33) [NP a valuable collection of manuscripts] [to the
library]]
his widow later [VP donated
この構造の[NP a valuable collection of manuscripts][ to the library]は移動規則の適用によっ
て生じたものではないので,移動分析を仮定した場合に生じる上述の問題は生じない。
では,次に,同一要素の移動を伴わない分析として2.2節で紹介した Kimura(1986)の分
析に見られる問題点について考察する。まず,Kimura(1986)の分析で仮定される(13)の
構造にあるような照応形である空範疇は三次元分析のもとでは仮定されないので,Kimura
(1986)の分析に関して指摘された問題は三次元分析では生じることはない。
次に,上記(15)の三次元構造は次のものである。
(34) [COMP ] [ John argued with Fred about what ]
[COMP ] [ Mary negotiated with Fred about what ]
岩田(1998;etc.)の等位構造条件(Coordinate Structure Condition : CSC)(=「文法の規
則,条件および原理は,(三次元構造にある)すべての等位項に適用される。」)に従って,こ
の構造の両方の等位項に wh移動が適用される。その結果,概略,次の構造が得られる。
右枝節点繰上げ構文について 11

(35) [COMP what] [ did John argue with Fred about t]
[COMP what] [ did Mary negotiate with Fred about t ]
この構造の共通の要素が,上述のように,単一の要素として表示されると次の構造が得られる。
John argue
(36)what did with Fred about t
Mary negotiate
そして,この構造が PF部門で LCに従って音韻解釈規則の適用を受けると(15a)が生成さ
れる。したがって,三次元分析のもとでは上記2.2節で指摘された問題は生じない。
さらに,本稿の三次元分析によれば,本稿の2節と3節で示した問題点以外の問題点につい
ても解決策を示すことができる。例えば,Wexler and Culicover(1980:300)によると,次
の(37)の RNR構文は,共通要素の繰上げ(=移動)分析にしたがうと,その移動の結果,
(38)の構造となる。
(37)Mary buys, and Bill sells, pictures of Fred. (Wexler and Culicover 1980 : 299)
(38) S’
COMP S*
S NP
Mary buys and Bill sells pictures of Fred
この構造は基底部規則で生成されたものではなく変形が適用されて導かれた派生構造である。
変形が適用されて派生された構造にはさらなる変形の適用は許されないという凍結原理
(Freezing Principle)によって,この構造にさらに変形を適用することはできない。したが
って,次の(39)のように ‘picture of Fred’の ‘Fred’を wh要素として移動させることはでき
ないと予測される。しかし,事実は可能である。(cf.木村 2005:38―39)
(39)Who does Mary buy, and Bill sell, pictures of o?
このことは三次元分析では,概略,以下のように説明される。まず,この事例の三次元基底構
造は(40a)で,その構造に wh移動が岩田(1998;etc.)の CSCに従って適用されて(40
b)となる(3)。さらに,(40b)の同一要素が単一の要素として表示されると(40c)となる。
[COMP [ Mary buys pictures of who ]]
(40)a.
[COMP [ Bill sells pictures of who ]]
12 天理大学学報 第64巻第2号

whoi does Mary buy pictures of ti
b.
whoi does Bill sell pictures of ti
Mary buy
c.whoi does pictures of ti
Bill sell
そして,(40c)に音声解釈規則が LCに従って適用され最終的に(39)が生成される。このよ
うに,本稿の三次元分析のもとでは,(39)のような事例を凍結原理に違反することなく生成
することができる(4)。
6.結び
本稿では,英語と日本語の RNR構文について考察した。この構文がどのような構造からど
のような過程を経て生成されるかは,依然として解決されていない問題であり,この構文に係
わる言語事実がどのように説明されるかという問題には未解決の点が多く存在する。本稿では,
それらの問題点は,岩田(1998;他)で提案されている等位構文の三次元分析を採用すること
によって解決されるという提案を行なった。
註
(1) さらに,RNR構文が移動によって派生されるのではないことが Kitada(2012:92)によっ
ても指摘されている。また,RNR構文が(3)の CRによって派生されると仮定すると,英語
のいくつかの通時的言語事実を捉えることができないことが,岩田(1993;1998:155)によっ
て指摘されている。
(2) RNR構文に対して本稿の(26)と同類の構造が Citko(2011:3.6.3)によって提案されて
いる。つまり,Citkoによると例えば次の(�)にある RNR構文は1つの節点(node)が2
つの上位要素(mother)を持つ下記(�)の多節点支配構造(multidominant structure)を
持つ。
(�)John likes and Bill dislikes TV shows about vampires.
右枝節点繰上げ構文について 13

(�) &P
TP &’
John T’ & TP
T vP Bill T’
v VP T vP
likes v VP
dislikes DP
TV shows about vampires
この構造において,等位構文の左側の等位項は&を主要部(head)とする&Pの指定部
(specifier)として分析され,右側の等位項は主要部&の補部(complement)として分析され
ている。等位構文に対するこの分析は,岩田(2000;2012)で示されているように,不備なも
のである。したがって,Citkoの(�)は RNR構文の構造として採用しない。
(3) wh移動が(40a)の[ Bill sells pictures of who ]の方にも適用された証拠には,(39)の
‘Bill sell’の ‘sell’に3単現の ‘−s’が付いていないことがある。(cf. *Who does Mary buy, and
Bill sells, pictures of o ?)
(4) さらに,三次元分析のさらなる帰結として,岩田(1998)の第12章に述べられているように,
第4節の三次元分析に基づけば,日本語の RNR構文に関する言語類型論的特徴に対しても説
明を与えることができる。
参考文献
Abbot, B. (1976) “Right Node Raising as a Test for Constituenthood,” LI 7. 639−642.
Chomsky, N. (1981) Lectures on Government and Binding. Dordrecht : Foris Publications.
Citko, B. (2011) Symmetry in Syntax : Merge, Move, and Labels. Cambridge University Press.
原口庄輔・鷲尾龍一(1988)『変形』現代の英文法第11巻. 研究社出版株式会社.
岩田良治(1993)「等位構文に見られる省略現象の史的変化」.天理大学学報 第174輯,1―11.
.(1998)『三次元文法論』.英潮社.
.(2000)「生成文法における現代英語の等位構造について」.天理大学学報第195輯,39―61.
.(2012)「等位構文の形式と意味」.天理大学学報 第229輯,1―18.
Kimura, N. (1986) “Right Node Raising : A Null Anaphor Analysis,” English Linguistics 3,118−
133.
木村宣美(2005)「右枝節点繰上げの特異性」,弘前大学『人文社会論叢』人文科学篇14,31―46.
Kitada, S. (2012) “Linearization and Boundedness of Movement,” in JELS 29, 日本英語学会大会
運営委員会(編),86―92.
.(2005)「右枝節点繰上げの特異性」弘前大学『人文社会論叢』人文科学篇14,31―46.
McCawley J. (1982) “Parentheticals and Discontinuous Constituent Structure,” LI 13, 91−106.
14 天理大学学報 第64巻第2号

Ross, J.R. (1967) Constraints on Variables in Syntax. Ph.D. dissertation, MIT. Reproduced by the
Indiana University Linguistics Club, 1968.
Saito, M. (1987) “Three Notes on Syntactic Movement in Japanese,” In Issues in Japanese
Linguistics, ed. by T. Imai and M. Saito, 301−350. Dordrecht : Foris.
Sanders, G.A. (1977) “A Functional Typology of Elliptical Coordinations,” in Eckman, F.R.(ed.)
(1977) Current Themes in Linguistics : Bilingualism, Experimental Linguistics, and
Language Typologies. Hemisphere Publishing Corporation. 241−270.
田川拓海(2008)「形態統語理論における削除現象の取り扱いについて――日本語の右方節点繰上げ構
文を中心に――」第5回筑波応用言語学研究会(筑波大学)口頭発表.
Wexler, K. and P.W. Culicover (1980) Formal Principles of Language Acquisition. Cambridge,
Mass. : MIT Press.
右枝節点繰上げ構文について 15