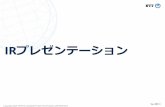第6回 税務収益会計のうち...
Transcript of 第6回 税務収益会計のうち...

税務会計論a 第6回
税務収益会計のうち 役務収益について
板橋雄大
1

Ⅰ.役務収益の意義と 原則的計上基準 1.役務収益の意義
役務収益とは、労働や技術などを提供する代わりに企業に入ってくる経済的な価値のことです。
不動産仲介斡旋業、技術役務提供業、運送業、倉庫業、各種サービス業などを営む企業の営業収益(営業収入)に該当するもののほか、役務の提供を内容とする付随的な経営活動から生じる営業外収益に属するものが含まれる。
また、こうした役務収益が、請負契約によるものである場合には、請負収益としての性格を持つことになる。請負収益の特徴としては「後払いが原則」という点である。
2

2.役務収益の原則的計上基準 役務収益の計上時期の決定については、税務上も、商品等の販売収益の場合と同様に実現主義を基調とした考え方に基づいています。 つまり、1会計期間において発生した費用および収益が、その期間において実現したものであるかどうかが重要になります。 実現主義は、一般的には、財貨の移転、役務の提供などによって債権が確定したときに収益が発生したとする考え方です。 前回紹介した最高裁判決(:船荷証券取組時点での収益計上を認めないとしたもの)によって、現在の税務における実現主義の採用と、一般的な取扱いの指針が明らかになりました。 もちろん、客観的にみてそこで収益が実現したといえる状態というのは個別的な取引ごとに本当は異なります。
3

役務収益の内容は、極めて多様なので、具体的計上基準に規定されていないような場合も多々あります。 そうした場合には原則的計上基準に基づいて具体的なケースへの適用を行うことになるのですが、その場合も、こうした役務収益の多様性を考えて、ある程度弾力的な運用が必要となるわけです。 たとえば、役務の提供が先週紹介した長期割賦販売等に該当するような場合には、その収益の計上には「延払い基準」を提供することが出来ます。 役務収益における原則的計上基準は
「役務提供完了基準」です。 これは、役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する方法です。
4

役務収益の取扱いについては、一つ有名な判例があります。実現主義等についても説明をしており、役務収益とその計上について非常にわかりやすい説明となっていますので、紹介します。 まず本件は、
仲介手数料請求権を仲介にかかる契約成立時において収益として計上すべきものとする課程処分は、請負報酬請求権を工事完成時に計上すれば足りるとする取扱いに比べて、課税上不当な差別をするものであつて、憲法一四条に反する旨の主張に基づいています。 これに対して、判決は、右両契約における取扱いは、いずれも権利確定主義によつて損益を計上すべきものとする点では何ら差別はなく、ただ仲介契約と請負契約との契約内容の相違に基づき事実上異なる結果となつているに過ぎないから、憲法一四条に反するものといえないと結論したものです。 Q-①課税上の不当な差別という主張、特に原告にとってなにが不利だと考えたのでしょうか?
5

原告の主張) 宅地建物取引業者の依頼者に対する義務の内容は、不動産取引の契約の締結にとどまらず、爾后(それ以降、という意味)の登記、引渡、代金決済等に関する役務も含まれるのであつて、 仲介手数料の支払いは、売買等の契約締結時ではなく、登記、引渡等が終了した後に行なわれるのである。 したがつて、被告主張のように、宅地建物取引業者の 仲介手数料を売買契約の成立時において収益に計上すれば、右契約が後に解除されると所定手数料の全部または一部が減額されることになつたり、右手数料の額自体が売買契約成立時には明確には取決めがないという極めて不確実な未実現収益を計上することとなつて、企業会計原則上のいわゆる「保守主義の原則」に反する結果となるうえ、契約媒介の外交員に対する支払手数料等の費用は、原告会社においては、原告が依頼者から現実に受領した仲介手数料の額によつて確定する定めであるため、会計原則上のいわゆる「費用収益対応の原則」にももとる結果となるのである。
6

それゆえ、このような宅地建物取引業の実態からすれば、仲介手数料については、いわゆる発生主義ないし権利確定主義によるよりもいわゆる現金主義によるのが相当である。 また、仲介手数料は、全役務の提供完了後にはじめて請求しうる点で、請負報酬に類似するものであるところ、請負報酬の収益計上時期については工事完成基準が採用されているのに、仲介手数料については仲介にかかる契約の成立時で収益に計上すべきものとして、本件のような更正をすることは、何らの合理的な理由なくして課税上の差別をすることに帰し、憲法一四条一項に違反する行政処分というべきである。 そして、本件においても本件の各売買の仲介については、右仲介受任の日から各売買契約成立の日までのいかなる段階においても、仲介手数料額についての約定がされておらず、いま売買契約が成立したからといつて報酬規定の最高限度額の報酬請求権が当然に発生し、もしくは確定するものとはいえないのであつて、右最高限度額の範囲内において契約成立に至る経緯、成立の難易等を考慮して約定しているのが実情である。 また、右仲介手数料収益に対応する費用としての支払手数料額は、契約成立時には全く未確定であつた。
7

判決内容:
法人税法上、課税の対象となる所得とは、当該事業年度の益金の額から同年度の損金の額を控除した金額とされ、右益金の額は、別段の定めがあるものを除き、資本等取引以外の取引にかかる当該事業年度の収益の額である旨定められている(同法二二条一、二項)。
そして、右の当該事業年度の収益および損金の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるべきものである(同条四項参照。なお、同項は本件には適用されないが、その趣旨は本件においても同様に解するのが相当である。)
8

したがつて、法人の所得の算定にあたり、当該収益がどの事業年度におけるものであるかを決定するについても、公正妥当な会計処理の基準に従うべきものと解するのが相当である。
ところで、近代企業にあつては、複雑な取引形態の下に多数の債権債務が同時に併存する実情にあるため、会計処理上いわゆる現金主義によつてはとうてい客観的かつ正確な損益を把握することができないから、これによることは適当でなく、いわゆる権利確定主義ないし発生主義によるのが公正妥当な会計処理の基準に従う所以であつて、この理は原告のような宅地建物取引業者の収益、損金についても妥当するものということができる。
9

したがつて、宅地建物取引業者の仲介手数料請求権は、仲介に必要な役務の提供があり、仲介にかかる契約が有効に成立し、かつ、仲介手数料の額が具体的に約 定されれば、特別な事由のない限り、その約定日の属する事業年度の収益としてこれを計上すべきものである。 すなわち、仲介人の役務の提供が完了し、これに 基づき仲介手数料の額が合意され具体的請求権が確定的に発生し、同額の積極財産が生じた以上、収益の実現があつたというべきである。 仲介手数料請求権の弁済期を基準として計上時期をきめることは、たな卸資産の割賦販売や延払条件付販売にかかる収入金等のように企業経理の健全性を特に考慮すべき要請から計上時期について特別の定めのある場合(法人税法六五条、六六条)に該当しないかぎり相当でなく、ましてや現金の支払いのあるまで収益に計上しないというのは合理性を欠くものである。
10

そこで、次に、原告のような宅地建物取引業者の仲介手数料ないし報酬(収益)および支払手数料(損金)がいかなる時点において確定するかについて検討する。 宅地建物取引業者は商人であるから、依頼者に対し報酬請求権を有する(商法五一二条)が、不動産取引の仲介は、民事契約の仲介ではあつても、これを商事仲立と区別すべき理由がないから、特別の事情のない限り、商事仲立に関する商法五五〇条一項を類推適用して、仲介が成功したとき、すなわち、当事者間の不動産取引の契約が有効に成立したときに、この報酬請求権が発生するものと解すべきである。そして、右報酬の額は、これについて約定があれば、宅地建物取引業法一七条に基づいて定められた報酬規定による最高報酬額の限度で約定に従うべきことは、いうまでもない。 商法第五百五十条
仲立人ハ第五百四十六条ノ手続ヲ終ハリタル後ニ非サレハ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス ② 仲立人ノ報酬ハ当事者双方平分シテ之ヲ負担ス (昭13法72・一部改正・旧第三一二条繰下)
11

したがつて、宅地建物取引業者の報酬請求権は、仲介にかかる契約が有効に成立し、かつ、報酬額が具体的に約定されて、これを行使しうる状態になつたとき、確定するものと解すべきである。 ところで、原告は、この点に関し、会計原則上の保守主義の原則を引用し、未収益についてはこれを益金に計上する必要がない旨主張する。なるほど、いわゆる 保守主義ないし安全性の原則は、企業財政の安全をはかるために尊重されるべきであるが、課税所得の計算は、負担の適正、公平を期するために、権利確定主義 の基準によるべきことは既述のとおりであつて、右保守主義の原則も、これによつて限定される範囲において認められるべきものと解するのが相当である。
⇒つまり、会計原則と、税法では目的が異なっているため、同じ扱いができない場合もあるのだ、と判決は言っています。
12

また、原告は、仲介手数料請求権を仲介にかかる契約成立時において収益として計上すべきものとする課程処分は、請負報酬請求権を工事完成時に計上すれば足りるとする取扱いに比べて、課税上不当な差別をするものであつて、憲法一四条に反する旨主張するが、右両契約における取扱いは、いずれも権利確定主義によつて損益を計上すべきものとする点では何ら差別はなく、ただ仲介契約と請負契約との契約内容の相違に基づき事実上異なる結果となつているに過ぎないから、憲法一四条に反するものといえないことは明らかである。る。
13

このように、収益の時点をどこにするのかというのは、きわめて大きな問題となり、税務当局と、納税者間でも裁判になることが多くあります。
収益の時点が異なると納税者にとってはどういう影響があるのでしょうか?
今期に計上すべきとされる収益を、来期に計上することが実現された場合に、どのような影響が出るのでしょうか?
14

さて、紹介した判例にも載っていますが、役務収益の計上時期の決定については、税務上も、商品等の販売収益の場合と同様に実現主義をベースとして、役務の全部の提供が完了した日が属する事業年度の益金の額に算入する方法、つまり、「役務提供完了基準」によることが原則とされています。しかし、役務収益は極めて内容が多様なので、具体的なケースへの適用に当たっては、弾力的な運用が必要となります。こうした具体的な計上基準のいくつかを紹介します。
15

Ⅱ 役務収益の具体的計上基準 1.不動産の仲介斡旋報酬。
先ほどの判例などの影響を受けた結果、現在では法人税基本通達という税務当局の解釈方針が定まっています。 土地、建物等の売買、交換、賃貸借の仲介または斡旋に伴う報酬は、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日に計上する(法人税基本通達2-1-11)。 ただし、売買または交換の仲介または斡旋による報酬について、継続してその契約にかかわる取引の完了した日(同日前に実際に受け取った金額があればそれについては、受け取った日)に計上しているときは、これが認められる。 この基準を「取引完了基準」という。
16

2.技術役務の提供報酬
設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供に係る報酬額は、原則として契約した役務の全部の提供が完了した日に計上される。
ただし、次の①②の事実がある場合には、その支払いを受けるべき報酬の額が確定する都度、その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の収益に計上することとなる(強制適用) 。
17

①報酬額が技術者などの人数や滞在日数などによって計算され、かつ一定の期間ごとに、その金額を確定して、支払いを受けることとなっている場合。
②たとえば、設計段階ごとに報酬額が区分されているように、作業段階ごとに報酬が区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度、その金額を確定させて支払いを受けることとなっている場合。
18

つまり、技術役務の提供も、「役務提供完了基準」に従うわけだが、上のようにいわば部分進行的にそのサービスの提供が完了し、報酬の授受もその部分については完結的に行われるのであるから、全体の役務提供の完了まで収益計上を留保し、いわば仮受金等として、繰り延べるような経理をすることは合理的でないことから、その都度収益計上すべきものとされる。
19

3.運送収入
陸運、海運、空運などの運送業における運送収入は、原則としてその運送に係る役務の提供を完了した日に計上します。
これも「役務提供完了基準」によることが、原則とされているわけです。
ただし、法人が、運送契約の種類、性質、内容等に応じて、たとえば、次の方法のうち合理的と認められるものを継続適用しているときは、これが認められます。
20

①乗車券、乗船券、搭乗券等を発売した日(自動販売機によるものは集金時)に計上する方法・・・・発券基準
②船舶、航空機等が積地をを出発した日に積載分について計上する方法・・・積地出発基準 ③一つの航海に通常要する期間がおおむね4か月以内である場合において、一つの航海を完了した日に計上する方法・・・航海完了基準
④一つの運送に通常要する期間または運送を約束した期間の経過に応じて、日割りまたは月割り等により計上する方法・・・運送期間経過基準
21

こうした例外的取扱いの存在がなぜ許されるのでしょうか?
実は、運送業というものの性格からすると、その多くは一般には、同質のサービスを反復継続的に、かつ大量に提供するものであります。仮にその収益計上について、厳格な完了基準の適用を要求したとしても、全体として企業の損益計算に与える影響は大きなものではないと考えられるのです。
むしろ、理論的な精緻さについては多少は犠牲にしても、実行可能な一定の基準を継続適用することにより、その損益計算の合理性を十分に担保することが可能であると考えられます。
22

そこで、収入に係る収益計上基準として、企業会計上も古くから一般に承認されていると認めらえるいくつかの基準を例示し、法人が、その運送契約の種類、性質、内容などに応じて、合理的と認められる基準を選択して、継続適用する場合には、税法上も幅広くこれを認めることが明らかにされています。
具体的な例示の第1は乗車券、乗船券、搭乗券等を発売した日にその発売金額を収益計上する方法で、一般には「発売日基準」といわれるものである。
しかし、切符が発売された時点では、当然旅客などへの役務の提供は終了していない。この方法では,実際に運送サービスを提供する前に収益が先行計上されることになるのであるが,会計実務上の簡便さという面からみてメリットがあるため,鉄道,バス会社等において広く採用されている基準である。
なお,発売日基準といっても,自動販売機によるものについては,その集金時点で発売があったものとして,その集金した金額を収益計上することになる。
23

第2が,いわゆる「積切り出帆基準」といわれるものであって,船舶や航空機による運送について,船舶,航空機等が積地を出発した時点でこれに積載した貨物又は乗客に係る運送収入を収益計上する方法である。 これも当然、役務の提供は終了していない時点で、収益が計上されることとなる。 この方法と3番目の方法のメリットは、同じものである。 第3番目は,いわゆる「航海完了基準」といわれるものである。すなわち,船舶による運送収入について,当該船舶が発港地を出発してから最終帰港地に帰着するまでの航海(一の航海)に係る全体の運送収入を一括してその一の航海の完了した時点で計上する方法である。
24

第2と、第3のメリットは、公開の途中の寄港地毎に会計処理を行う必要がないということである。たとえ航海途中で荷卸しを完了した貨物があったとしても,航海途中では収益計上せず,航海完了時点までその収益計上を繰り延べることになるのである。 ただし,これについては,航海期間が余りにも長期にわたるものに適用することは課税上も弊害があるし,企業会計上も妥当ではないと考えられるので,本通達においては,おおむね4月以内に完了する航海について,航海完了基準による収益計上を認めることとされている。 航海完了基準の適用のある一の航海に係る航海期間が「おおむね4月以内」とされているのは,実例に照らして,ほとんどの外航航路における一の航海が通常この程度の期間内に完了すると認められるからである。 ⇒4か月という制限がなく、非常に長期にわたる公開に適用すると課税上も弊害があるとしているが、どのような租税回避手法が考えられるか?
25

もちろん、同じく航海完了基準という名前になるのだが,個々の貨物の荷卸しを完了する都度当該貨物について運送収入を収益計上するという方法もある。このような意味における航海完了基準の採用も,法人が選択する限り,これが認められることとなる。これは、A港から出航し最終目的行がZ港だとした場合でも、A港からB港への航海を一つと数え、B港について荷を下ろした時点で、この一つの航海は完了したものと扱う方法である。
26

第4は,いわゆる「発生日割基準」又は「月割基準」等と呼ばれているもので,一種の進行基準的な収益計上方法である。すなわち,運送期間の経過に応じて,日割又は月割等によって運送収入を分割計上していく方法であって,海上運送業のほか,鉄道の定期乗車券などに係る収益計上にもこの方法が使われる例が多いようである。
以上が本通達において運送収入に係る収益計上基準として例示された四つの方法であり,運送業を営む法人は,これらの方法の中から,当該法人の営む運送の内容に応じて合理的基準を採用し,継続して適用すべきことになる。
27

ところで,以上のほか,これに関連して2つの補足的な規定が定められている。 一つは,運賃の交互計算又は共同計算を行っている場合の収益計上基準である。 例えば,鉄道の相互乗入れの場合や,海上運送業における運賃同盟などのように,2以上の運送業者が運賃の交互計算や共同計算を行っているケースは数多く存在する。 このような交互計算又は共同計算が行われる場合には,その計算期間が終了して計算が確定しない限り,それぞれの法人が配分を受けるべき金額が明らかにならないという事情がある。 そこで,このような場合には,その配分が確定した時点でその配分されるべき金額を収益計上すればよいことが明らかにされている。
28

次に,海上運送業を営む法人が船舶による運送に関連して受払いする滞船料又は早出料の計上時期についての定めがされている。
「滞船料」というのは,貨物の積卸期間が当初契約で予定した積卸期間を超過して運送期間がそれだけ長期にわたることになったため,割増しの運賃を徴収する場合のその割増運賃のことであり,「早出料」とは,逆に積卸期間が短縮されて,全体として航海日数が短縮されたために運賃の割戻しを行う場合のその割戻運賃のことである。
29

滞船料又は早出料は,運賃の加減算項目とされているのであるが,いずれも荷主その他運賃の支払者との間で協議をし,原因となる事実関係を相互に確認した上ではじめてその金額が確定するというのが普通である。したがって,現に貨物の積卸期間の延長又は短縮があったからといって,その時点で直ちにその受払金額を損益計上することができないという事情がある。そこで,このような事情を考慮して,滞船料又は早出料については,当事者間の協議が整い,その受払いすべき金額が確定した時点で損益として処理すれば足りることとされている。
30

前述の判決の「仲介人の役務の提供が完了し、これに 基づき仲介手数料の額が合意され具体的請求権が確定的に発生し、同額の積極財産が生じた以上、収益の実現があつたというべきである。」
、という表現から考えれば、これらの補足規定は、実際に収益の額が計算不可能であるために収益の実現とならないのだということが分かるはずです。
31




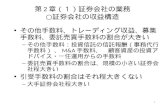




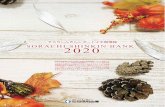

![· 2018年度の管理及び運用状況|2 運用実績 2 運用実績 [1]収益率・収益額等 ①収益率 2018年度の収益率は、](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5d6731ba88c99389108b6561/-20182-2-1.jpg)