異世界ファンタジーコミックスフェア ノベルティ配 …...書店都道府県 自治体名 書店名 宮城県 名取市 TSUTAYA 仙台南店 宮城県 名取市
第3章 岩手県の「第 2 クリーンセンター 仮称 建設計画」に伴...
Transcript of 第3章 岩手県の「第 2 クリーンセンター 仮称 建設計画」に伴...
-
第3章 岩手県の「第 2 クリーンセンター(仮称)建設計画」に伴う廃棄物処理システム整
備計画案についての対策案の環境影響評価と提案
3.1 岩手県の「第 2 クリーンセンター(仮称)建設計画」に伴う廃棄物処理システム
整備計画について
我が国において、廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分けられる。
岩手県では、産業廃棄物に関しては、排出量は近年横ばいの傾向を示しており(平成 14
年度には 218 万 t、ただし家畜糞尿を除く)、家畜糞尿、汚泥、がれき類、木くずが主な品
目となっている。不法投棄などの不適正処理が頻発していることが、産廃処理に関わる大
きな問題であり、住民は大きな不安感・不信感を持っている。また、岩手県では、廃棄物
を自県内で処理することを目標としているが、特定管理産業廃棄物に指定される品目の多
くは県外で処理されており、これも問題となっている。そのため、自県内で適正に廃棄物
を処理できる施設を用意することが必要とあるが、民間の処理施設は住民の反対運動によ
り設置が困難となっている。
一般廃棄物は平成 15 年度に 49 万 6 千 t に達しており、1 人あたりごみ排出量の増加と
ともに、排出総量も年々増加している。それに伴い、処理経費も増大しており、平成 15
年度では 1 人あたり約 9,500 円に上っている。ごみ処理の広域化をおこなうことで処理費
を削減できると考えられるが、広域化が完了しているのは県内 6 ブロック中 1 ブロックに
過ぎず、多くの市町村は、市町村単独あるいは 2-3 市町村で構成される一部事務組合にて
ごみを処理している。
現在、岩手県では、平成 7 年 9 月から県南に位置する江刺市に、大型産業廃棄物処理施
設「いわてクリーンセンター」が稼動している。平成 11 年度では、搬入された可燃ごみ
(13,033t)のうち中部ブロック、県南ブロック、沿岸南部ブロックからの搬入が 84%を占め
ている。搬入された不燃ごみ(28,387t)の 50%を県北ブロック、県央ブロック、沿岸中部ブ
ロックからの搬入が占めており、いわてクリーンセンターが県内の産業廃棄物受け入れ処
理施設として位置づけられていることがわかる。
しかし、既存施設には、中間処理施設における排出基準強化に伴う処理能力が減少して
いるものや、管理型最終処分場が不足している地域があるなどの問題がある。特に、県北
地区については、いわてクリーンセンターまでの運搬コストの問題もあることから、岩手
県としては、基幹施設としての焼却溶融施設、管理型最終処分場を新たに確保することが
203
-
求められている。
これに対して、岩手県では県北の九戸村江刺家に集中型廃棄物処理施設として「第 2 ク
リーンセンター(仮称)」の建設を計画している。第 2 クリーンセンター(仮称)建設計画は、
青森県境にて不法投棄された産業廃棄物を処理することを目的とするが、それだけではな
く、久慈地区、二戸地区から排出される一般廃棄物と各種産業廃棄物を合わせ、環境・経
済の両面から見てより効率的に処理することを目指している。さらに、それらの廃棄物を
処理する際、ガス化溶融システムの導入による高効率発電や金属系産業廃棄物の再生利用
など、廃棄物の再資源化による資源・エネルギーの再生利用をおこなうことにより、低環
境負荷型社会の形成を目指している。
第 2 クリーンセンター(仮称)の構想は、第 1 期事業として産業廃棄物焼却(溶融)施設の整
備が進められており、平成 18 年度に用地買収・着工、平成 21 年度から施設の稼動が予定
されている。また、第 2 期事業で一般廃棄物焼却(溶融)施設及び最終処分場の整備が平成
24 年度以降に予定されている。将来構想として整備時期は未定であるが、第 3 期事業の農
林水産系リサイクル施設整備が計画されている。(図3.1-1参照)
岩手県は、第 2 クリーンセンター(仮称)について、廃棄物の収集から処理・利用・処分
までの過程をライフサイクルでとらえ、総合的な環境負荷低減を考慮した新たな廃棄物処
理システムの構築を検討している。
このような、地域の廃棄物処理システムの構築に関する施策について、その環境負荷の
排出抑制と費用、便益を考慮した総合的な評価手法を開発することが本研究の目的である。
204
-
一般廃棄物処理部門
最終処分場
第2期事業
焼却(溶融)施設
産業廃棄物処理部門
最終処分場
焼却(溶融)施設
農林水産系リサイクル部門
第2クリーンセンター(仮称)構想
第3期事業
第1期事業H18 着工(予定)
H21 稼動(予定)
H24 以降
将来構想
(整備時期は未定)
整備スケジュール
図3.1-1 第 2 クリーンセンター(仮称)構想と整備スケジュール
205
-
3.2 平成 17 年度における研究開発内容
3.2.1 調査範囲
岩手県の第 2 クリーンセンター(仮称)建設計画では、廃棄物収集範囲を広域化し、集中
的な廃棄物処理をおこなうことによる処理効率の向上を目指している。したがって、第 2
クリーンセンター(仮称)を中心とした廃棄物処理システムに関して、岩手県内における廃
棄物の発生から処理、処分・再利用にわたる環境負荷の排出に加え、岩手県外からの廃棄
物やエネルギーの受け入れ・利用などを考慮した、ライフサイクル的な思考による環境影
響評価が必要である。
さらに、広域的な物質・エネルギーの流通を考慮する必要があることから、廃棄物処理
システムのライフサイクルにおけるデータは、量的データに加え、それらがどこに存在し
ているのかなどの空間的分布状況に関する情報の把握も必要である。
したがって、第 2 クリーンセンター(仮称)を中心とした廃棄物処理システムにおける、
廃棄物の発生から処理、処分・再利用に加え、地域外からの廃棄物やエネルギーの受け入
れ、および地域外への 2 次製品の輸送を対象範囲として設定し、インベントリデータを収
集する。これにより、当該地域の環境に著しい影響を与えることが予想される環境影響排
出物質の推定排出総量の 90%以上を把握する。
そこで、本研究開発では、岩手県環境生活部と協議の上、産業廃棄物(表3.2-1参照)
の中でも発生量が全排出量に対して圧倒的に多い家畜排せつ物(全排出量中 65.2%を占め
る)や、不適正処理の全量に対して 38%を占める木くず、加えて、産廃との同時処理によ
る効率化が検討されている一般廃棄物および廃プラスチック類を中心として環境影響評価
をおこなうこととする(図3.2-1、図3.2-2、図3.2-3参照)。なお、廃プラ
スチック類については排出割合が低い(0.7%)ものの、第 2 クリーンセンター(仮称)では大
型焼却(溶融)処理施設建設を計画しており、廃プラスチック類が高カロリーであることを
考慮し、検討対象とした。
206
-
表3.2-1 産業廃棄物の分類3-1)3-2)
分類(細分類) 内容 燃え殻 事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等 汚泥 無機性汚泥 有機性汚泥
工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程に
おいて生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの
廃油 一般廃油 廃溶剤 油泥
鉱物性及び動植物性油脂にかかるすべての廃油
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処
理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う
廃アルカリ 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理をした場
合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱う 廃プラスチック類 廃プラスチック 廃タイヤ
合成高分子化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類
紙くず
(1)建設業に係るもの (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) (2)パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの (3)出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの (4)製本業及び印刷物加工業に係るもの (5PCB が塗布され、又は染みこんだもの
木くず
(1)建設業に係るもの (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) (2)木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの (3)パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの (4)PCBが染み込んだもの
繊維くず
(1)建設業に係るもの (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) (2)繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック) (3)PCB が染み込んだもの
動植物性残渣
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用
した動物又は植物に係る固形状の不要物 (魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活
動に伴って生じた一般廃棄物) ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類) 金属くず ガラスおよび陶磁器くず 鉱滓
207
-
がれき類 コンクリート アスファルト その他建設廃材
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成
の目的となる土砂に準じたものを除く)
動物の死体 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 PM 煤煙発生施設・焼却施設の集塵施設で集められたもの
特別管理産業廃棄物 特管・廃油 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点 70[℃]未満のもの 特管・廃酸 pH が 2.0 以下の廃酸 特管・廃アルカリ pH が 12.5 以上の廃アルカリ
感染性廃棄物 感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃
アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず 、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第 2 条第 13 号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
廃石綿 特管・その他
家畜排せつ物 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の糞尿
家畜糞尿
汚泥
がれき類
金属くず
鉱滓
木くず
動植物性残渣
廃プラスチック類
煤塵
特別管理産業廃棄物
廃酸
ガラスおよび陶磁器くず
その他建設廃材
紙くず
廃油
廃アルカリ
燃え殻
動物の死体
ゴムくず
繊維くず
65.6%16.8%
6.9%
3.1%2.0%
図3.2-1 産業廃棄物排出割合(平成 11 年度 岩手県)3-2)
208
-
汚泥
がれき類
金属くず
鉱滓
木くず
動植物性残渣
廃プラスチック類
煤塵
特別管理産業廃棄物
廃酸
ガラスおよび陶磁器くず
その他建設廃材
紙くず
廃油
廃アルカリ
燃え殻
動物の死体
ゴムくず
繊維くず
48.7%
19.9%
8.9%
5.9%
3.7%
2.8%
図3.2-2 産業廃棄物排出割合(家畜糞尿を除く)(平成 11 年度 岩手県)3-2)
木くず
がれき類
ガラスおよび陶磁器くず
廃プラスチック類
汚泥
金属くず
廃油
鉱滓
動植物性残渣
38%
27%
7%
7%
8%
7%
図3.2-3 岩手県の不適正処理産業廃棄物内訳(平成 12 年度)3-3)
209
-
(1)、 プロセスフローの範囲(システム境界)
地域産業に対してライフサイクルアセスメントをおこなうにあたっては、従来の(製品に
対する)ライフサイクルアセスメント同様に、まず、データ収集の境界を設定する必要があ
る。すなわち、社会経済システムのどの部分を考慮しどの部分を考慮しないか、明確にす
る必要がある。あるシステムの境界内は評価し、境界外は評価しないことになる。システ
ム境界の設定は、評価対象とするサブシステムあるいはプロセスに対する物質・エネルギ
ーあるいは環境負荷物質などの流出入の大半を抑えられるように大きく設定することが望
ましいが、一方で、データ収集に要するコストの観点からは小さく設定した方が望ましい。
本研究開発では、システムの本質を捉えるとともに、データ収集に要するコストの抑制
を考慮してシステム境界を設定した。
(2)、 地理的範囲・分解能
地域産業に対してライフサイクルアセスメントを適用する場合の特徴は、地理的境界を
設定することである。地理的境界を明確に設定することによって初めてある地域における
地域産業の評価がおこなえる。
上記に基づき、本研究開発では地理的境界を設定した。
従来のライフサイクルアセスメントでもデータの精度は問題となったが、地域産業のラ
イフサイクルアセスメントでは、特に、地理的分解能の設定に結果が大きく左右される可
能性がある。システム境界や地理的境界と同じく、基本的には解像度が高いほど正確な評
価がおこなえる。しかし、高解像度のデータ収集にはコストを要すること、また既往デー
タを用いる場合、高解像度データが必ずしも用意されておらず、低解像度データを高解像
度化する際に精度が悪くなること、さらに高解像度データを用いた解析は計算コストが莫
大となる、といった問題点が存在する。
代表的な地理的分解能としては、表3.2-2に示すものがある。
210
-
表3.2-2 地理的分解能の一覧(2000 年度、境界部を含む)
名称 岩手県における例 岩手県におけるメッシュ数
2 次メッシュ 6041-54(新井田) など 192 3 次メッシュ 6041-5534, 6041-5535 など 15,964
広域 二戸地区, 盛岡地区など 9 市町村 03201(盛岡市), 03301(雫石町) など 59 集落 - -
2 次メッシュや 3 次メッシュ(基盤地域メッシュ)などは普遍的なメッシュ区分であり、
地図上の経緯度方眼を基準に定められている。また、自然情報を中心とした地域基盤デー
タは、3 次メッシュによって整備されていることが多い。一方、広域区分や市町村メッシ
ュといった行政区分は人為的に作成された区分である。人間の社会活動に伴うデータは、
一般に市町村単位で集計されている。このほかに、流域や地形地域区分のような自然地形
による単位も考えられる(県をまたぐため、ここではとりあげない)。
本研究開発は、岩手県における廃棄物の広域処理を評価対象としている。そのため、取
り扱うデータは、廃棄物の発生や処理といった社会活動に関するデータが中心であり、そ
の点では広域メッシュや市町村メッシュといった行政区分によるメッシュが望ましい。地
域メッシュ、特に 2 次メッシュのようなやや大きな区分の場合、市町村メッシュのデータ
を 3 次メッシュなどに細分化した後、統合して、データを作成するが、その際、統合する
メッシュが大きいほどデータの精度が落ちてしまう。また、広域処理を評価するため、全
県レベルで評価する必要があるが、メッシュ数からは 3 次メッシュの 15,964 個はあまり
にも過大であり、解析の際の計算コストが極めて高くなる。一方、広域メッシュの 9 個は
過少であり、精度上の問題が発生する。100 個前後となっている 2 次メッシュや市町村メ
ッシュが適正規模である。
よって、本研究開発は、基本的には市町村メッシュでデータを収集し、解析も市町村メ
ッシュでおこなった。ただし、一部、集落単位のデータを収集し 3 次メッシュ単位で解析
をおこなっている。
なお、社会活動データは市町村メッシュにより整備されていることがほとんどであるが、
近年の相次ぐ市町村合併(「平成の大合併」)により市町村数が減ってきており、本ケース
スタディの対象である岩手県でも 59 市町村(2000 年度)が、2005 年度末には 35 市町村に
まで減少する3-4)。面積や人口はそのままであるため、従来通りに市町村メッシュでデータ
211
-
を集計したとしても、その精度は 5 年前の 2/3 に落ちてしまう。今後も、本研究開発を始
めとする社会活動の地域的な解析・評価は、市町村単位で整備されたデータに基づいてお
こなわざるを得ないが、そのままでは精度が悪くなってしまうため、データの整備単位・
整備手法や整備されたデータの解析手法を検討する必要があると考えられる。
3.2.2 調査項目
(1)、 環境影響物質
廃棄物処理システムにおける共通的な環境影響排出物質は、輸送プロセスに要するエネ
ルギー、廃棄物処理施設の運用に要するエネルギー、廃棄物処理に伴う副産物(CO2、廃棄
物、CH4)の生成に起因するものが主であると想定した。
そこで、基本的に把握する環境影響排出物質を、「CO2、CH4、SOx、NOx、PM」とし
た。その選定理由は以下に示すとおりである。
• (CO2) 廃棄物処理システムのライフサイクルでは、ほぼすべてのプロセスでエネルギ
ーが使用されており、エネルギーとしての化石燃料の燃焼に伴いCO2が排出される。
CO2削減は我が国の国際的公約であり、地域住民の関心も高く、ライフサイクル的思
考に基づいた評価においてはCO2を対象とした評価が必須である。
• (CH4) 廃棄物システムでは、特に有機性廃棄物のメタン発酵処理がおこなわれること
もあり、それに伴うCH4の排出が予想される。温暖化に向けた温室効果ガスの低減も
世界的に関心が高まっていることから、CH4についても環境影響排出物質として評価
をおこなう。
• (SOx、NOx、PM) これら 3 種の環境影響排出物質は、廃棄物再資源化・処理プロセス
や廃棄物輸送プロセスにおける化石燃料の燃焼等に起因する排出物質であると予想さ
れる。これらの物質は、CO2と同様に重要な大気圏の環境影響排出物質と考えられる。
また、畜産業における家畜排せつ物の処理システムを考えた場合、上記に示した環境影
響排出物質のほかにも把握すべき環境影響排出物質が考えられる。処理によって家畜排せ
つ物に由来して発生する亜酸化窒素(N2O)、アンモニア(NH3)、また、浄化処理(排水処理)
後に河川放流される処理水の汚濁指標である生物化学的酸素要求量(BOD)、全窒素(T-N)、
全リン(T-P)が考えられる。また特に、家畜排せつ物処理システムでは生産された堆肥や液
肥を農地に散布し肥料として利用されるが、その時に施肥された窒素による環境影響が考
えられる。そこで、家畜排せつ物処理システムを検討する場合には、上記の環境影響排出
212
-
物質と「N2O、NH3、BOD、T-N、T-P」を把握すること、また施肥された窒素量(N)を調
査対象とした。
• (N2O) 家畜排せつ物に含まれる窒素化合物は、好気処理、嫌気処理の過程において亜
酸化窒素として発生する。この物質は、CO2と同様に重要な大気圏の環境影響排出物
質と考えられる。
• (NH3) 家畜排せつ物に含まれる窒素化合物は、好気処理過程(特に堆肥化処理)にお
いて発生する。この物質は、酸性化の原因となる環境影響排出物質と考えられる。
• (BOD、T-N、T-P)家畜排せつ物に含まれる有機物、窒素化合物、リンなどは、浄化処
理において浄化されてから河川放流されるが、それらが全て除去されたわけではなく、
河川放流基準以下までの浄化程度となり、少なからず環境への排出が考えられる。こ
れらの物質は、富栄養化に関連する環境影響排出物質と考えられる。
• (N) 堆肥や液肥といった形で農地に施用された N は、その施肥量が作物の N 需要に対
して適正な量であれば問題は無いが、過剰な施肥によって N の過剰な地下浸透が危惧
されている。これは、地下水における窒素汚染の原因の 1 つとして考えられている。
廃棄物処理システムのライフサイクルにおける環境影響物質の排出はエネルギー使用・
廃棄物処理に関わるCO2・SOx・NOx・PMであり、これらの排出量の網羅のためには、ま
ずエネルギー使用量と廃棄物発生量を網羅することが必要であり、これらは次項にて詳述
する実態調査、関連文献調査などにより把握した。実態調査では統計情報、事例情報を基
本とし、これにヒアリングやアンケート調査をおこなうことにより不足情報を補完し、廃
棄物処理に係る環境負荷排出量の 90%以上を網羅した。
(2)、 コスト
調査対象とした施策の現実的な実施可能性を検討するためには、物質収支や環境負荷量
に関するデータだけでなく経済面からの判断が必要であり、コストデータの整備が必要と
なる。
3.2.3 今年度の実施計画
平成 15 年度は、施策評価のための基礎データベースの作成をおこなった。具体的には、
廃棄物処理プロセス全体での環境負荷算定のために、廃棄物の発生分布を調査し、それに
加えて、現状の処理分布(処理施設の種類・立地)とそれに対応した処理プロセスのインベ
213
-
ントリを作成した。
平成 16 年度の研究開発は、平成 15 年度の研究開発で扱わなかった輸送に着目し、廃棄
物の流通実態および輸送経路、ならびに輸送プロセスのインベントリを作成した。地域産
業にライフサイクルアセスメント(LCA)を適用する場合、前述の通り、地域的な分布を取
り扱うため、従来の製品 LCA に増して輸送プロセスが重要となる。また、実際に地域施
策に研究開発成果を反映させるためには、コストデータが重要であることに着目し、各プ
ロセスのコストを調査、各プロセスのインベントリにコストデータを付加した。コストは
インベントリ以上に規模の経済性に左右されるため、一部のプロセスについては規模別の
データを作成した。また、廃棄物処理解析モデルを開発することによって、県北部の一般
廃棄物の処理に関して対策案を提案、現状および対策案での環境負荷を算出した。
平成 17 年度の研究開発は、平成 16 年度の環境影響評価を総合的な環境影響評価に拡張
した。具体的には、環境影響評価に時間変化の考慮と LIME に組み込まれていない局所的
な環境問題の考慮をおこなった。
時間変化を考慮した環境影響評価では、現在から将来にわたる人口の変化および排出抑
制・リサイクル施策の市民への浸透度の時間変化を考慮するために、市民・従業員 1 人あ
たりの品目別ごみ排出インベントリを作成し、旧盛岡市を対象に現在から 2030 年に至る
一般廃棄物処理計画の検討をおこなった。また、局所的な環境問題の環境影響評価では、
施肥からの余剰窒素と降水データ、地下水の環境基準から、地下浸透水の窒素許容量に対
する余剰窒素の割合を求めて汚染量を推定し、家畜排せつ物処理施設から生成した堆肥、
液肥の施肥による窒素の地下水への影響を考慮した評価をおこなった。
また、3 年間にわたる廃棄物処理計画に対するLCAの手順およびデータベースを、地域
LCA実務書のケーススタディとしてまとめることで、地方自治体が本研究開発成果を自ら
の施策に利用できるようにした。実施計画の全体像を表3.2-3に示す。
214
-
表3.2-3 平成 17 年度実施計画
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度
◆地域施策に関連するデータベースの作成
・地域環境 DB (GIS 上)
・現状の廃棄物発生量 ・処理施設の分布
・現状の輸送経路 ・DB の GIS 化 ・地域基盤データ
・現状の再利用分布 ・将来シナリオ検討
・インベントリデータ
(インベントリ・コスト) ・現状の処理技術
・現状の輸送技術 ・規模の経済性の考慮 ・データの付加
・データの修正・追加
◆地域施策の評価解析モデルの作成
・プロトタイプの作成 (処理・輸送の最適化)
・LIME (環境影響評価)の 組み込み
・アプリケーション ソフトウェア化
◆地域施策の環境影響評価・その他の成果
・現状の処理に伴う 環境影響評価
・現状の処理システムに
伴う環境影響 ・コスト評価
・現状および代替案の
処理システムに伴う
環境影響 ・コスト評価
・一部の代替案提案 ・複数シナリオの考慮 ・実務書の作成
(1)、 県北地区における一般廃棄物処理の地域内外を考慮した環境影響評価
平成 16 年度の研究内容の拡充として、県北地区における一般廃棄物処理システムの現
状と計画案についてそれぞれシミュレーションモデルを用いて評価し、計画案導入による
経済性・環境影響を定量化する。また、平成 15 年度および平成 16 年度作業で作成した廃
棄物の発生分布・現状処理拠点分布・再利用品需要分布(現状および将来)、輸送経路、処
理技術インベントリ・輸送技術インベントリの各種データを活用した。
(2)、 旧盛岡市における一般廃棄物処理の時間変化を考慮した環境影響評価
時間変化を考慮した環境影響評価では、市民・従業員 1 人あたりの品目別ごみ排出イン
ベントリを作成する。作成したインベントリを用いて、現在から将来にわたる人口変化お
よび排出抑制・リサイクル施策の市民への浸透度の時間変化から一般廃棄物の発生量、組
成の変化を考慮することで、旧盛岡市を対象に現在から 2030 年に至る一般廃棄物処理計
画を検討する。
215
-
(3)、 九戸村における家畜排せつ物処理の窒素を考慮した環境影響評価
家畜排せつ物処理システムの環境影響評価では、代表的な家畜排せつ物処理技術のイン
ベントリを作成し、環境影響の比較をおこなう。また、施肥窒素による地下水の窒素汚染
を評価するため、降水データ、地下水の環境基準値から、地下浸透水の窒素許容量を推定
する。処理技術の環境影響と施肥窒素による環境影響を組み合わせた評価をおこなうシミ
ュレーションモデルを作成し、九戸村の家畜(乳用牛)を対象に環境影響の少ない家畜排せ
つ物処理システムの検討をおこなう。
216
-
3.3 廃棄物処理システムの総合的な環境影響評価
3.3.1 概要
岩手県における廃棄物処理システムによる環境影響の低減に向けて、廃棄物処理計画に
関する提案をおこなうことを目標に、廃棄物処理システムの環境影響評価をおこなった。
地域施策は、事業の実施段階、事業の計画段階のほかに、その前段階として、基本計画
段階や構想段階が存在する。本ケーススタディは、第 2 クリーンセンター(仮称)事業3-5)の
ような具体的な事業の実施段階あるいは計画段階ではなく、岩手県あるいは各市町村でど
のような処理をおこなうのが望ましいか(廃棄物処理計画)という基本計画段階に対する提
案を研究開発の目的とした。
本年度おこなった岩手県におけるケーススタディを以下に示す。
(1)、 県北地区における一般廃棄物処理
久慈地区および二戸地区計 11 旧市町村(現 8 市町村)における可燃ごみ・不燃ごみの処理
を集約化した場合の環境負荷・コストの削減量を地域内外で評価した。なお、本ケースス
タディの計画案は、第 2 クリーンセンター(仮称)第 2 期事業と関連する。
[対象とする廃棄物]
• 一般廃棄物(可燃ごみ・不燃ごみのみ)
[対象とする地域施策(計画案)]
• 現状(旧二戸市・旧久慈市でそれぞれ広域処理)
• 第 2 クリーンセンター(仮)第 2 期事業(九戸村のみに集約広域処理)
[環境影響評価]
• CO2, SOx, NOx, PM, コスト
• 地域内外の環境負荷
217
-
一戸町
二戸市(旧浄法寺町)
洋野町(旧種市町)
二戸市(旧二戸市)
軽米町
洋野町(大野村)
久慈市(旧久慈市)
野田村
普代村
九戸村久慈市
(旧山形村)
図3.3-1 県北地区における一般廃棄物処理
(2)、 旧盛岡市における一般廃棄物処理
旧盛岡市(1992 年の都南村合併以前の盛岡市)における一般廃棄物(生活系ごみ・事業系ご
み)の処理に関して、排出抑制および分別収集・再資源化を強化する施策を導入した場合の
環境負荷削減量を現在から将来にわたって評価した。なお、本ケーススタディの計画案は、
旧盛岡市の一般廃棄物処理計画3-10)と関連する。
[対象とする廃棄物]
• 一般廃棄物
[対象とする地域施策(計画案)]
• 現状(廃棄物発生原単位を現状維持)
• 廃棄物排出抑制策(排出抑制およびリサイクルを推進)
いずれのシナリオに関しても将来にわたって人口は変化する
[環境影響評価]
• CO2, SOx, NOx, PM
• 現在~将来の環境負荷
218
-
岩手町
八幡平市(旧安代町)
葛巻町
紫波町 矢巾町
盛岡市(旧都南村)
八幡平市(旧西根町)
八幡平市(旧松尾村)
盛岡市(旧盛岡市)
盛岡市(旧玉山村)滝沢村
雫石町
図3.3-2 県央地区における一般廃棄物処理
(3)、 九戸村における家畜ふん尿処理
九戸村における家畜ふん尿(特に乳用牛ふん尿)の処理に関して、メタン発酵施設を導
入した場合の環境影響削減量を、LIME3-6)にて評価可能な地球温暖化や大気汚染など広範
に起こる環境問題だけではなく、局地的な環境問題である窒素による地下水汚染も考慮し
て評価した。なお、本ケーススタディの計画案は、第 2 クリーンセンター(仮称)第 3 期
事業3-5)と関連する。
[対象とする廃棄物]
• 家畜ふん尿(特に乳用牛ふん尿)
[対象とする地域施策(計画案)]
• 現状(堆肥化による分散処理)
• 第 2 クリーンセンター(仮)第 3 期事業(堆肥化+メタン発酵)
• すべてメタン発酵
[環境影響評価]
• LIME(CO2,CH4,NH3,SOx,etc.), コスト
• 局所的な環境影響も評価
219
-
九戸村
図3.3-3 九戸村における家畜ふん尿処理
3.3.2 県北地区における一般廃棄物処理の地域内外を考慮した環境影響評価
(1)、 背景
現在、岩手県では、県北地区の九戸村江刺家に集中型廃棄物処理施設として「第 2 クリ
ーンセンター(仮称)」の建設を計画している。
第 2 クリーンセンター(仮称)建設計画は、青森県境にて不法投棄された産業廃棄物を処
理することを目的とするが、それだけではなく、久慈地区、二戸地区から排出される一般
廃棄物と各種産業廃棄物を合わせ、環境・経済の両面から見てより効率的に処理すること
を目指している。さらに、それらの廃棄物を処理する際、ガス化溶融システムの導入によ
る高効率発電や金属系産業廃棄物の再生利用など、廃棄物の再資源化による資源・エネル
ギーの再生利用をおこなうことにより、低環境負荷型社会の形成を目指している。また、
建設に併せて、関連産業の整備・創出・活性化と新たな雇用の創出など地域経済へのてこ
入れも視野に入れた地域施策としている。
岩手県は、第 2 クリーンセンター(仮称)について、廃棄物の収集から処理・利用・処分
までの過程をライフサイクルでとらえており、総合的な環境負荷低減を考慮した新たな廃
220
-
棄物処理システムの構築を検討している。
上記の基本計画のもとに、第 2 クリーンセンターの事業計画は、具体的には、図3.3
-4のように考えられている。一般廃棄物処理について具体的な広域化計画(第 2 クリーン
センター第 2 期事業)が存在する県北地区における一般廃棄物処理システムの環境影響評
価を、ケーススタディとすることは、県北地区の広域化計画である第 2 期事業の立案の際
の参考になると考えられる。のみならず、今後、具現化していくであろう他の地区の広域
化計画の具体的な立案にも寄与するものと考えられる。
そこで、本ケーススタディでは、岩手県県北地区における一般廃棄物処理計画を対象と
して環境影響評価をおこなった。
221
-
第第33期事業期事業
第第11期事業期事業
第第22期事業期事業一般廃棄物処理部門
最終処分場
焼却または溶融施設
最終処分場
焼却または溶融施設
農林水産系リサイクル部門
産業廃棄物処理部門
第1期事業 [産業廃棄物処理施設(焼却または溶融)]H15 (2003FY) 施設建設用地の選定(→九戸村)
基本計画の策定
H16 (2004FY) 施設の規模および機能の精査整備手法の確定(→PFI)
H17 (2005FY) PFI事業者の募集および選定H18 (2006FY) 施設建設用地の買収(予定)
着工(予定)
H21 (2009FY) 稼働(予定)
第2期事業 [一般廃棄物処理施設(焼却または溶融),最終処分場]H24(2012FY)以降(予定)
第3期事業 [農林水産系リサイクル施設]時期未定(将来構想)
図3.3-4 第 2 クリーンセンター(仮称)構想
(2)、 本ケーススタディを扱うための環境影響評価手法
従来の LCA は、
• (企業は)
販売する製品から引き起こされる環境影響を低減したい。
LCA を通じて、製品のライフサイクルでどの段階/プロセスを改善すべきか?、知り
たい。
• (消費者は)
環境影響の削減に製品購入を通して貢献したい。
222
-
LCA を通じて、どの製品が環境に優しいのか、知りたい。
という目的のもとにおこなわれていた。そのため、LCA を通じて、評価対象とした製品が、
どれだけ(そして、どの段階/プロセスにおいて)環境影響を与えているかをわかることが重
要であった。
地域施策に LCA を適用する場合、
• (地方自治体は)
地域施策によって引き起こされる環境影響を削減したい。
LCA を通じて、いつ、どこで、どれだけ環境影響を発生するのか?、知りたい。
という目的の下におこなわれると考えられる。
製品の場合、広範に流通し、広く環境影響を及ぼすため、「いつ、どこで」ということは
問題視されない。しかし、地域施策の場合、特定の地域を対象とするため、特に、「どこで」
環境影響が発生するのか?ということが問題視される。「どこで」ということを従来問題視
していたため、環境アセスメントでは、地域施策を実施する地点の周辺に限って環境影響
を評価してきた。地域施策を評価対象として LCA を実施する際には、広範な(ライフサイ
クル、ライフチェーンにわたる)環境影響を評価する LCA の特徴を保持しつつ、施策対象
導入地域での環境影響も定量化できる LCA とすることが望ましい。
そこで、本ケーススタディでは、地域施策がもたらす環境影響を単に定量化するのでは
なく、地域施策がもたらす環境影響を地域内外で定量化できる環境影響評価手法を開発す
る。
(3)、 一般廃棄物処理に関わるデータベース整備
a、 地域環境データベース(地域基盤データ)
現実の地勢を考慮し、評価をおこなう際には、地勢上の制約条件を考慮する必要がある。
たとえば、施設立地に際しては行政上の各種土地規制や自然条件が、輸送に際しては実際
の道路網が、制約条件となる。本ケーススタディでは、市町村メッシュを評価解像度とし
たため、施設立地に関する制約は存在しないが、輸送に関する制約は考慮する必要があっ
た。
イ、 輸送網
数値地図3-7)より道路網データを作成し、作成した道路網データに基づいて、メッシュ代
表点間の最短距離をGISソフトを用いて算出した。作成した市町村間最短経路を図3.3
223
-
-5に示す。
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
浄法寺町
一戸町
二戸市
軽米町
九戸村
山形村 久慈市野田村
普代村
種市町
大野村
浄法寺町
一戸町
二戸市
軽米町
九戸村
山形村 久慈市野田村
普代村
種市町
大野村
メッシュ代表点各メッシュ間最短経路
図3.3-5 県北地区における輸送経路
b、 地域環境データベース(施策関連データ)
イ、 一般廃棄物発生分布
岩手県「一般廃棄物処理事業実態調査(平成 12 年度)」3-8)より、平成 12 年度(2000 年度)
における岩手県の一般廃棄物の発生分布を生活系ごみ・事業系ごみ別に作成した。分布図
を図3.3-6に示す。
224
-
生活系ごみ事業系ごみ生活系ごみ事業系ごみ
浄法寺町
一戸町
二戸市
軽米町
九戸村
山形村 久慈市野田村
種市町
大野村
浄法寺町
一戸町
二戸市
軽米町
九戸村
山形村 久慈市野田村
種市町
大野村
普代村普代村
図3.3-6 県北地区における一般廃棄物の発生分布
ロ、 一般廃棄物処理分布
岩手県「平成 13 年度 一般廃棄物処理事業の概況」3-9)より、平成 12 年度(2000 年度)に
おける岩手県の一般廃棄物の処理分布を作成した(図3.3-7参照)。
可燃ごみ不燃ごみ可燃ごみ不燃ごみ
可燃ごみ輸送量
浄法寺町
一戸町
二戸市
軽米町
九戸村
山形村 久慈市野田村
普代村
種市町
大野村
浄法寺町
一戸町
二戸市
軽米町
九戸村
山形村 久慈市野田村
普代村
種市町
大野村
図3.3-7 県北地区における一般廃棄物の処理分布(現状)
225
-
c、 プロセスインベントリデータベース
可燃ごみ・不燃ごみの処理プロセスフローを図3.3-8に示す.
活動
可燃ごみ
焼却[ストーカ式]
(准連続/バッチ)
焼却[ストーカ式](全連続)
焼却[固定床式]
(准連続/バッチ)
発電[系統]
電力(発電端)
処理主灰(発生端)
処理飛灰(発生端)
(各プロセスへ)
埋め立て[管理型]
A重油精製[製油所]
灯油精製[製油所]
都市ガス
灯油
軽油精製[製油所]
都市ガス[ガス基地]
A重油 軽油
焼却[流動床式](全連続)
直接溶融[シャフト式](全連続)
溶融スラグ(発生端)混合ごみ
不燃ごみ 圧縮・破砕
再資源化[スラグ利用業者]
発電[低温蒸気タービン]
低温蒸気(発生端)
固化灰(発生端)
不燃ごみ処理残渣(発生端)
分別収集
LPG[ガス基地]LPG
バックグラウンド
溶剤処理
セメント固化
飛灰(発生端)
温水利用(低温蒸気)
一般ごみ
発電[中温蒸気タービン]
温水利用(中温蒸気)
中温蒸気(発生端)
集約
集約
集約
集約
集約
処理残渣(発生端)
溶融スラグ
送電
電力
資源ごみ,集団回収物など 評価対象範囲(システム境界)
図3.3-8 可燃ごみ・不燃ごみの処理プロセスフロー
従来の LCA では、原料・製品・環境影響物質といった物質の入出力のみをプロセスの
インベントリとして整備していた。しかし、地域施策を検討する上で、コスト情報は必要
不可欠である。焼却など一部のプロセスでは規模の経済性が働くため、プロセス原単位が
施設規模によって変化する。そこで、本ケーススタディでは、プロセスの施設規模別にイ
ンベントリおよびコストデータを整備した。
イ、 分別収集(生活系・事業系)
本ケーススタディでは、広域化の効果が現れやすい、可燃ごみと不燃ごみを評価対象と
する。生活系ごみ・事業系ごみにしめる可燃ごみ・不燃ごみの割合は、それぞれ「盛岡市
一般廃棄物処理基本計画(案)(改訂版)」(平成 14 年 3 月)3-10)より作成した(図3.3-9参
照)。
226
-
84.80% 11.62%
0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
事業系
77.68% 7.33%生活系
10% 20% 30%
可燃ごみ不燃ごみ粗大ごみ等資源ごみ資源集団回収自己・民間リサイクル
図3.3-9 一般廃棄物の可燃ごみ・不燃ごみの割合
ロ、 焼却、直接溶融
岩手県内の各焼却施設および直接溶融施設の実際の操業状況をアンケート調査によって
把握し、燃料(灯油など)・薬剤(消石灰など)・環境影響物質(SOxなど)および固定費・変動
費についてデータを整備した。例として固定費を図3.3-10に示す。
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
200,000,000
0 20 40 60 80 100 120 140
処理規模 [t/d]
固定
費 [y
en/y
]
焼却[ストーカ式(バッチ)]
焼却[ストーカ式(連続)]
焼却[固定床式(バッチ)]
焼却[流動床式(連続)]
直接溶融[シャフト式(連続)]
図3.3-10 岩手県処理施設における処理規模と固定費の関係
整備したデータより規模別にインベントリを作成した結果は、本報告書付録のインベン
トリデータに示す。
ただし、プロセスに直接投入される薬剤などの物質は、波及がシステム広範に及ぶエネ
ルギーを除いて、NIRE-LCA ver.33-11)を用いて遡及計算をおこなって環境影響物質やコス
トを算出、プロセスから直接排出される環境影響物質やコストに予め加算しておいた。
227
-
ハ、 圧縮・破砕、埋め立て
焼却、直接溶融と同様の手法にてプロセスインベントリ・コストデータを作成した。埋
め立てに関しては実操業データが入手できなかったため、LCA日本フォーラムによるLCA
データベース3-12)を用いた。
ニ、 バックグラウンドプロセス
図3.3-8に示す発電や製油などバックグラウンドデータに関しては、産業技術総合研
究所によるNIRE-LCA ver.33-11)の値を用いた。発電についてのみ、地域ごとに環境影響物
質の値が大きく異なるため、東北電力の環境報告書3-13)よりインベントリを作成した。
(4)、 環境影響評価(県北地区における一般廃棄物処理システム)
a、 シナリオ設定
次の 2 シナリオの評価をおこなった。
• 現状シナリオ
• 共同処理シナリオ
イ、 現状シナリオ
現状の県北地区では、二戸地区 5 旧市町村(現 4 市町村)の一般廃棄物は二戸市の処理施
設にて、久慈地区 6 旧市町村(現 4 市町村)の一般廃棄物は久慈市の処理施設にて処理をお
こなっている。この 2 つの施設を所与として評価をおこなったのが、前者の現状シナリオ
である。
ロ、 共同処理シナリオ
集約処理の効果を見るため、九戸村のみに施設立地、中間処理施設は任意の焼却プロセ
スという制約条件のみ与え、コスト最小化のもとで計算をおこなったのが、後者の共同処
理シナリオ。直接溶融を対象外としたのは、直接溶融を選択した場合、集約案の利点が集
約処理の効果によるものなのかプロセス変更の効果によるものなのか不明になってしまう
ためである。
なお、いずれのシナリオにおいても、廃棄物の発生分布および処理施設の立地地点のみ
を所与の条件として、
• 発生した廃棄物がどの処理施設に運ばれるのか?
• 処理施設の立地地点にどのような廃棄物処理施設が建設されるのか?
228
-
については、廃棄物解析モデル(3.4節参照)を用いて求めた。
b、 施設立地・輸送経路解析ならびにインベントリ分析
イ、 現状シナリオ
廃棄物処理解析モデルを用いて、現状の発生分布(図3.3-6)と処理施設の立地分布
を条件とし、廃棄物処理解析モデルによるコスト最小をおこなった。
その結果、二戸地区 5 旧市町村はすべて二戸市に、久慈地区 6 旧市町村はすべて久慈市
に廃棄物を輸送する、という結果となった(図3.3-11参照)。このことは、廃棄物処
理において、輸送コストの全システムコストに占める割合が小さくないことを示している
といえる。また、現在の処理施設の立地条件下では、コスト最小化の面からは、現在の輸
送形態が望ましいことがわかった。同時に、現状では、コスト最適化による解と現状が一
致するため、現状の評価がおこなえた、といえる。
図3.3-11 現状シナリオでの一般廃棄物の輸送と処理
なお、環境負荷およびコストを算出した結果を図3.3-12に示す。廃棄物由来のCO2
を除くと、CO2とNOxは間接排出の寄与が大きいことが分かる。また、今回は評価対象外
としたが、CO2排出のうち、廃棄物由来のCO2の占める割合は大きいため、可燃ごみや不
燃ごみに含まれる資源化可能品目の資源化はCO2排出削減方策として検討の余地があると
いえる。
229
-
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
現状 共同処理
変動費
固定費
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
現状 共同処理
間接
直接
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
現状 共同処理
間接
直接
40000
41000
42000
43000
44000
45000
46000
47000
現状 共同処理
間接
直接
廃棄物由来
CO2[103kg-CO2/y]
SOx[kg/y]
NOx[kg/y]
コスト[106yen/y]
図3.3-12 現状シナリオと共同処理シナリオにおける環境負荷およびコストの比較
ロ、 共同処理シナリオ
集約処理の効果を見るため、九戸村のみに施設立地、中間処理施設は任意の焼却プロセ
スという制約条件のみ与え、コスト最小化のもとで計算をおこなった。直接溶融を対象外
としたのは、直接溶融を選択した場合、集約案の利点が集約処理の効果によるものなのか
プロセス変更の効果によるものなのか不明になってしまうためである。
計算した結果、図3.3-13に示すように、九戸村に
• ストーカ式連続焼却炉(可燃ごみ 75[t])1 基
• 流動床式連続焼却炉(可燃ごみ 25[t])2 基
• 圧縮・破砕処理施設(不燃ごみ 25[t])1 基
• 埋め立て処分場
がそれぞれ建設され、すべての市町村の廃棄物が輸送される結果となった。焼却炉に付随
して、飛灰の薬剤処理施設もそれぞれ建設された。
230
-
図3.3-13 共同処理シナリオでの一般廃棄物の輸送と処理
処理・輸送に伴う環境負荷およびコストは、図3.3-12に示す通りとなり、CO2、
SOx、NOx、コストいずれについても削減されると推定された。その削減幅はコストに関
しては 5%程度にとどまるものの、廃棄物由来CO2を除くCO2、SOx、NOxではいずれも 10%
前後に達しており、環境負荷を削減する観点からも集約処理は望ましいことが示唆された。
なお、SOxに関して地域外排出分が大きく削減されているが、これは集約によりバックグ
ラウンドで稼働する発電量が減少したためである。
(5)、 まとめ
a、 ケーススタディ
県北地区における一般廃棄物処理システムの環境影響に関する検討をおこなった。
従来の廃棄物処理システムの評価では扱われなかった地域内外の環境負荷を算出し、地
域外への環境負荷がCO2とSOxに関しては大きいことを示した。また、第 2 クリーンセン
ター(仮称)建設予定地となっている九戸村にて県北の一般廃棄物を集約処理した場合の評
価をおこなった。その結果、コストでは 5%減、環境負荷では廃棄物由来を除くCO2、SOx、
NOxで 10%減となり、九戸村での集約処理が財政面だけではなく、環境負荷の観点からも
望ましいことを示した。
231
-
b、 成果
本ケーススタディでは、地域施策に対してライフサイクルアセスメント手法を適用する
手順を開発し、同手法を適用することによって、環境影響評価を試みている。
まず、データベースの作成としては、分布データに関しては地域環境データベース
(REDB)として、GIS 上で包括的に扱うことを提唱し、その枠組みに基づいて、地域基盤
データならびに廃棄物分布データを整備した。整備した結果である地域別の新エネルギー
資源の需要や環境影響負荷量のデータベースは、GISデータの単位で集計することにより、
視覚的に高度な地図表現を可能にした。また、GISのネットワーク機能を利用することで、
処理施設等の拠点から地域への物流による環境負荷分析の着手を可能とした。このように
GIS は地域分析ツールとして適しており、その特性を生かし、地域の環境負荷量の偏りや
地域環境影響評価をわかりやすく示すことができたといえる。一方、GIS データの整備に
おいては、均質な情報、新鮮な情報の確保が課題であり、ここに労力の大半が費やされて
いるのが現状である。また、GIS データとして整備されていない自治体の保有する情報が
多々存在するため、これらも必要に応じて適宜入手し、データベースに加えていく必要が
ある。そうすることが、より多様な評価が可能になるデータベースの構築につながり、そ
れが今後目指すべき方向となる。
また、インベントリのデータ収集範囲を輸送プロセスに拡大、処理プロセスに関しては
規模の経済性を考慮、さらにコストをインベントリと同じ枠組みでプロセスデータとした。
コスト情報をプロセスデータとして持たせることにより、経済性評価をおこなえる準備が
整った。
3.3.3 旧盛岡市における一般廃棄物処理の時間変化を考慮した環境影響評価
(1)、 背景
本ケーススタディでは、当初、岩手県県央地区における一般廃棄物処理計画を対象とし
て環境影響評価をおこなう予定であったが、評価に用いるデータの入手の関係上、旧盛岡
市に限定して一般廃棄物処理計画を対象とした環境影響評価をおこなった。評価対象の変
更に関する経緯は(3)、b、イ、に述べる。
岩手県では、現在、一般廃棄物処理に関して、
• 処理(特に焼却処理)の広域化
• 分別収集の促進
232
-
を鋭意、進めている。
前者に関しては、岩手県では、主に「ごみ処理広域化計画」に規定されている。趣旨は、
焼却処理施設の連続運転が可能となる可燃ごみ量の規模を目指して、ごみ処理の広域化を
おこなうことである。
大量生産・大量消費・大量廃棄型生活様式の定着により、ごみ質が変化し、ごみ焼却に
伴うダイオキシン類による環境汚染が問題となってきた。そのため、連続焼却運転によっ
てダイオキシン類の発生を抑制する必要がある。また、焼却運転の連続化や処理施設の大
規模化は、焼却時の燃焼効率や廃熱の有効利用さらには再資源化の観点からも望ましいと
される。そこで、岩手県では平成 11 年に「ごみ処理広域化計画」3-14)を策定、全県を 6 つ
の広域ブロック(表3.3-1参照)に分割し、各ブロックにおける処理の広域化を推進し
ている。
233
-
表3.3-1 廃棄物処理広域ブロック3-14)
広域ブロック 現行ブロック 市町村(1991 年以前における市町村)
久慈地区広域行政事務組合 久慈市,普代村,種市町,野田村,山形村,大野村
県北地区 二戸地区広域行政事務組合
二戸市,浄法寺町,一戸町,九戸村,軽米町
葛巻町 葛巻町 岩手玉山環境組合 岩手町,玉山町 八幡平市 (西根地区衛生複合事務組合)
西根町,松尾村,安代町
滝沢村 滝沢村 旧盛岡市 盛岡市 雫石町 雫石町
県央地区
盛岡・紫波地区環境施設組合 都南村,紫波町,矢巾町 花巻地区広域行政組合 花巻市,大迫町,石鳥谷町,東和町 遠野地区厚生施設組合 遠野市,宮守村 北上市 北上市,和賀町,江釣子村 湯田町 湯田町
中部地区
沢内村 沢内村
胆江地区広域行政組合 水沢市,江刺市,前沢町,金ヶ崎町,胆沢町,衣川村
一関地方衛生組合 一関市,花泉町,平泉町 県南地区
東磐環境組合 大東町,藤沢町,千厩町,東山町,室根村,川崎村
沿岸中部地区 宮古地区広域行政組合 宮古市,田老町,山田町,岩泉町,田野畑村,新里村,川井村
陸前高田市 陸前高田市 釜石市 釜石市 大槌町 大槌町
沿岸南部地区
大船渡環境衛生組合 大船渡市,住田町,三陸町 *西根地区衛生複合事務組合は、2005 年、構成町村であった西根町・松尾村・安代町の合併により、八幡平市の行政組織に移行した。
後者に関しては、主に「分別収集促進計画」に規定されている。環境問題全体としては、
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムを見直し、持続可能な資源循環型の
地域社会を構築することを目的とする。
大量生産・大量消費・大量廃棄に支えられた社会経済の著しい発展により、一般廃棄物、
特に容器包装廃棄物は著しく増加し、廃棄物処理に伴う環境影響の増大をもたらした。こ
れに対して、平成 7 年に「容器包装に係わる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」
234
-
(容器包装リサイクル法)が制定され、消費者は分別排出・市町村は分別収集・事業者は再
商品化という役割分担が定められた。容リ法施行に対応し、岩手県では、平成 13 年に「い
わて資源循環型廃棄物処理構想」を策定するとともに、県内各市町村に対しては、平成 8
年に「第一期市町村分別収集計画」、平成 11 年に「第二期市町村分別収集計画」、そして
平成 15 年には「第三期市町村分別収集計画」3-15)を策定、容器包装廃棄物の分別収集およ
び分別基準適合物の再商品化を総合的かつ計画的に進めている。
県央地区は、岩手県内の 6 つの広域ブロックの内の 1 つであり、県都盛岡市を含むため、
6 ブロック中最大の人口を誇る。同時に一般廃棄物の発生量も最大である。県内最大のブ
ロックの一般廃棄物処理システムに関して
• 不要物(廃棄物)排出量・組成の時代的変化
• リサイクルの浸透
• 新しい焼却・溶融施設の導入、古い施設の劣化
を考慮して一般廃棄物処理に関する地域施策を評価し、またその代替案を提示することは、
他のブロックあるいは他の市町村の地域施策の立案にも寄与するものと考えられるため、
本ケーススタディでは、当初、県央地区の一般廃棄物処理を対象とした(後に対象地域を旧
盛岡市に限定)。
なお、県央地区は、図3.3-14に示すように 12 旧市町村(現 8 市町村)から構成され
ており、現在は、7 ブロック(2 つの一部事務組合と 5 市町村)にて処理をおこなっている。
235
-
八幡平市(旧安代町)
八幡平市(旧松尾村)
八幡平市(旧西根町)
葛巻町
岩手町
盛岡市(旧玉山村)
盛岡市(旧盛岡市)
滝沢村
雫石町
盛岡市(旧都南村)
紫波町
矢巾町
図3.3-14 県央地区における現行の一般廃棄物処理の枠組み
(2)、 本ケーススタディを扱うための環境影響評価手法
従来の環境アセスメントでは、廃棄物処理施設から直接排出される環境負荷(施設の煙突
より排出されるNOx排出など)しか評価されず、地球温暖化など地球環境問題への影響が評
価されなかった。一方、製品に適用されてきた従来のライフサイクルアセスメント(LCA)
では、環境排出をライフサイクルで評価するため、処理施設の運用段階における間接的な
影響(トラックによる廃棄物輸送に伴うCO2排出など)や処理施設の建設段階・廃棄段階で
の影響(処理施設建設時のセメント使用に伴う電力のCO2やSOxの排出)が考慮できた。しか
し、従来のLCAは、環境負荷の排出場所を考慮できず、また定常状態を仮定してライフサ
イクルを評価しているため、社会が変化したときの効果を考慮できなかった。
本ケーススタディ(県央地区における一般廃棄物処理に伴う環境影響の評価)を実施するに
は、上記の環境アセスメントやLCAでは不十分である。一般廃棄物処理計画を始めとする
地域施策に対する環境影響評価では、環境負荷あるいは環境影響の全体量だけではなく、
周辺住民にどれだけの被害(地域環境問題)がもたらされるのか、が求められる。この点で、
従来のLCAのみでは評価が不可能である。一方、近年、地球温暖化を始めとした地球環境
236
-
問題への関心も高まっており、この点で、従来の環境アセスメントのみでは評価ができな
い。地球温暖化に関しては、住民の関心だけではなく、「地球温暖化対策の推進に関する法
律」の第 4 条(地方公共団体の責務)において、「温室効果ガスの排出抑制のための施策を推
進する。自ら抑制のための措置をおこなうとともに、施策に関する情報提供をおこなう」
と明記されており、地方自治体は自らの温室効果ガスの排出量を定量的に把握する必要が
あるといえる。さらに、一般廃棄物処理計画の場合、施設の運用期間が長いため、その間
の社会の変化を考慮する必要がある。たとえば、人口が減少すれば、ごみの排出総量は減
少する。経済の進展に伴い、ひとりが排出するごみの量・組成が変化する。また、施策に
関しても、リサイクル施策への市民の理解度が深まれば、ごみの量は減少し、資源ごみの
割合が増加するであろう。このような社会の時間的変化は、これまでの環境アセスメント
やLCAでは扱ってこなかった事項である(図3.3-15参照)。
以上を踏まえ、本ケーススタディの実施にあたり、
• 地域内外の環境影響
• 時間変化(図3.3-16参照)
• ライフサイクル
を考慮できる環境影響評価手法を開発する。
地域内
地域施策によって引き起こされる
(住民への)環境影響を削減したい。
地方自治体
いつ、どこで、どれだけ環境影響が
発生するのか?
など
NOx
CO2 CH4CO2 SOx
CO2
SOx
地域外
図3.3-15 地域施策に対する LCA
237
-
既設
地区内他施設の利用 or簡易施設の利用?
(余剰)
処理システム設計案
環境排出評価(時間変化)
時間
排出量
期間内 期間外
時間間隔. . . . . .
直接対象期間 環境影響評価(時間変化)
不確実性を考慮するため、複数シナリオ下での個々の案を評価
評価期間内外のライフサイクル環境影響を算出(最も良い案を環境改善案として提案)
新設時間
処理量
新設(評価対象システム)
複数案を用意(もしくは評価後に案を見直し)
時間
影響量
. . . . . .
図3.3-16 時間軸を考慮したシステム案の評価・作成の例
(3)、 一般廃棄物処理に関わるデータベース整備
a、 地域環境データベース(地域基盤データ)
イ、 人口
廃棄物処理の環境影響の将来変化を評価するためには、廃棄物排出量を支配する人口の
将来変化データを作成する必要がある。
国立社会保障・人口問題研究所(社人研)では、市町村別の人口推計3-16)をおこなっており、
これと国勢調査を合わせることにより旧盛岡市の人口変化を予測できる。
しかし、社人研の市町村別人口推計は、全国人口の中位推計3-17)がベースとなっており、
この中位推計は、経済構造変化を加味した民間予測(たとえばアトラクターズ・ラボによる
予測3-18))と比較して楽観的な予測である(図3.3-17)。また、過去の社人研の人口予
測と実際の人口推移を比較すると、実態を表現しているのは、むしろ低位推計であった。
238
-
85,000,000
90,000,000
95,000,000
100,000,000
105,000,000
110,000,000
115,000,000
120,000,000
125,000,000
130,000,000
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050(年)
人口
[人
]
実績
社人研 中位推計
社人研 高位推計
社人研 低位推計
AL予測
図3.3-17 全国人口の変化
(社人研による予測とアトラクターズ・ラボ(AL)による予測との比較)
そこで、社人研の市町村別人口推計に全国の低位推計を加味して、将来人口データを作
成した。図3.3-18に示すように、旧盛岡市の人口は、2000 年の 240,000 人から 2030
年には 220,000 人に減少する見通しである。
(年)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
人口
[人]
葛巻町
岩手町
盛岡市(旧玉山村)
八幡平市(旧西根町)
八幡平市(旧松尾村)
八幡平市(旧安代町)
滝沢村
盛岡市(旧盛岡市)
盛岡市(旧都南村)
紫波町
矢巾町
雫石町
葛巻町
岩手町
盛岡市(旧玉山村)
八幡平市(旧西根町)
八幡平市(旧松尾村)
八幡平市(旧安代町)
滝沢村
盛岡市(旧盛岡市)
盛岡市(旧都南村)
紫波町
矢巾町
雫石町
旧盛岡市
図3.3-18 県央地区における人口の変化
239
-
ロ、 輸送網
廃棄物処理システムの環境影響を評価する際、輸送による影響を無視することはできな
い。特に、NOxやPM排出量に関しては輸送の影響は過半を占めると予想される。
輸送による影響は輸送距離に依存するため、輸送経路を正確に評価する必要がある。本
ケーススタディでは、メッシュ間の輸送距離を次のように求めた。
• 市町村間に関しては市町村代表点間距離
• 市町村内に関しては 3 次メッシュ代表点間距離
いずれも道路網マップ上で最短経路探索プログラムを用いることにより、算出している。
なお、市町村代表点は当該市役所・町村役場の座標、3 次メッシュ代表点は当該 3 次メッ
シュの重心とした。
解析結果を図3.3-19および図3.3-20に示す。
図3.3-19 県央地区における人口分布と市町村間輸送経路
240
-
図3.3-20 旧盛岡市における市町村内輸送経路
b、 地域環境データベース(施策関連データ)
イ、 県央地区における廃棄物排出実態
環境省統計資料3-19)より各市町村における排出ごみとして
• 収集ごみ(生活系+事業系)+直接搬入ごみ
混合ごみ
可燃ごみ
不燃ごみ
資源ごみ
その他
粗大ごみ
直接搬入ごみ
• 自家処理量
• 集団回収ごみ
を知ることができる。また、処理量として、
• 直接最終処分量
• 直接焼却量
• 焼却以外の中間施設
粗大ごみ処理施設
資源化等を行う施設
高速堆肥化施設
241
-
ごみ燃料化施設
その他施設
• 直接資源化量
• 集団回収ごみ
がわかる。
資源ごみのリサイクル・再資源化や排出総量の抑制に伴う焼却効率の変化を評価するに
は、廃棄物組成を把握する必要がある。上記の統計情報に基づいて
• 収集ごみ(生活系)+直接搬入ごみ+自家処理量+集団回収ごみ
を生活系ごみ排出量(不要物発生量)とすると、1 人あたりの生活系不要物発生量が市町村に
よってあまりにも大きく異なってしまう。一方、上記項目のうち、自家処理量は定量的に
把握するのが困難であるため、廃棄物組成データが存在する旧盛岡市の生活系不要物発生
量3-10)を各市町村一定として、逆に自家処理量を推定すると、図3.3-21に示す通り
となる。
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030(年)
推定
した
自家
処理
原単
位[g
/人
/d]
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030(年)
推定
した
自家
処理
原単
位[g
/人
/d]
旧玉山村
?
滝沢村
図3.3-21 県央地区における各市町村の自家処理原単位
図3.3-21に示した値を、旧盛岡市の調査結果や松藤らの組成データ3-20)を用いて、
組成配分をおこなうと、明らかに不合理な組成となる。これは旧盛岡市や松藤らのデータ
は都市域におけるごみ排出のみを分析・調査した事例であり、農村域の実態を反映してい
ないためと考えられる(松藤らのデータは人口 10 万人以上の都市を対象とする、と明記さ
242
-
れている)。図3.3-21に示した旧玉山村などを評価するためには、農村域におけるご
みの実態調査結果が必要であるが、現在の廃棄物研究は都市のみを対象としており、農村
域を対象とした事例が存在しないため、実態調査を新たにおこなう必要がある。
本ケーススタディでは、実態調査は今後の課題として、以下、データが存在する旧盛岡
市を対象に一般廃棄物処理に伴う環境影響評価をおこなった。
ロ、 旧盛岡市の廃棄物排出抑制策
盛岡市は、図3.3-14に示したように、
• 旧盛岡市(旧盛岡市域)
• 旧都南村(都南地区)
• 旧玉山村(玉山区)2006 年 1 月に編入合併
の 3 地域によって廃棄物処理の枠組みが異なるが、ここでは、旧盛岡市を対象とする。
盛岡市では、旧盛岡市を対象に、2002 年に「一般廃棄物処理基本計画(改訂版)案」3-10)を
まとめ、一般廃棄物(生活系・事業系)のリサイクルを中心とした排出抑制策を策定した。
本ケーススタディでは、旧盛岡市における同計画を定量化し、かつ人口変化も加味した場
合の環境影響の評価をおこなった。基本計画中の廃棄物排出策は表3.3-2および表3.
3-3に示す通りである。
243
-
表3.3-2 旧盛岡市における排出抑制策(生活系)
数値目標 分別排出率の向上(または減量効果)
施策 H12 現状
H23 推計
H23 目標
製品の長期利用,簡易包装の選択 - - 発生 抑制 食材の無駐・食べ残しの減量等 - -
再使用 使用後製品の再使用,交換等 (不明) 0%
全体で 10%の減量
家電リサイクル法 4 品目 粗大ごみ中
の 25% (推定)
なし なし
家庭での生ごみコンボスト化 4% 7% 8% 店頭回収 紙パック (不明) 0% 10%
排出 抑制 の
推進 再生 利用
白色トレイ (不明) 0% 5% 集団回収 新聞 39% 39% 40% 雑誌 21% 21% 25% 段ボール 20% 20% 25%
古紙
紙パック 2% 2% 10% 繊維 20% 20% 30% びん 14% 14% 15% 缶 9% 9% 15% 資源ごみ収集 <従来品目の分別率の向上> びん 62% 64% 70% 缶 63% 65% 70% ペットボトル 74% 75% 80% <新たな品目の回収> 新聞 - - 45% 雑誌 60%
古紙
段ボール - - 60% 白色トレイ - - 70%
プラ製 容器包装 白色トレイ以外 - - 70%
リサ イク ルの 推進
再生 利用
銀製容器包装 70%
244
-
表3.3-3 旧盛岡市における排出抑制策(事業系)
数値目標 分別排出率の向上(または減量効果)
施策 H12 現状
H23 推計
H23 目標
製品の長期利用,簡易包装等 産業廃棄物の搬入抑制 (不明) 0%
発生
抑制 経済的負担の適正化 H14,H15 手数料改定
全体で 10%の減量
再使用 使用後製品の再使用,交換等 (不明) 0%
家電リサイクル法 4 品目
不燃ごみ中
の 15% (推定)
なし なし
自主資源化ルート 新聞・雑誌 (不明) 0% 60%
古紙 段ボール (不明) 0% 60%
びん (不明) 0% 20% 缶 (不明) 0% 30%
排出
抑制
の
推進 再生
利用
食品廃棄物(生ごみ)の再生利用 (不明) 0% 30% 資源ごみ収集 <従来品目の分別率の向上> びん 33% 35% 40% 缶 21% 23% 40% ペットボトル 25% 26% 40% <新たな品目の回収> 古紙 (一部) 0% 10% プラ製容器包装 - - (今後,検討)
リサ
イク
ルの
推進
再生
利用
紙製容器包装 - - (今後,検討)
c、 プロセスインベントリデータ
一般廃棄物処理に関する各プロセスインベントリを整備した。本節では将来変化の評価
をおこなうことを目的としている。そこで、時間的に変化しうる項目である
• 不要物(廃棄物)排出量・組成の時代的変化
• リサイクルの浸透
• 新しい焼却・溶融施設の導入、古い施設の劣化
を考慮できるようにしなければならない。
そこで、プロセスインベントリデータの整備にあたって以下の点を考慮した。
• リサイクルパターンによって変化する収集プロセスを考慮するため、分別収集プロセ
245
-
スおよびリサイクルプロセスを処理フローに追加した。
• 不要物の時代的変化・リサイクルの浸透による可燃ごみの低位発熱量・含有 C 量の変
化に対応するため、分別~焼却の PIDB を再整備した。
• 施設の経年劣化については今後の課題とする。
特に焼却プロセスに関しては、投入燃料・CO2排出量を廃棄物組成に応じて変化可能なモ
デルとすると、不要物組成変化やリサイクルによる環境影響の変化を算出できるようにな
る。そこで、図3.3-22のような枠組みを考えた。ただし、この焼却プロセスを用い
るためには、組成を含んだ不要物データが必要となる。そこで、不要物(収集前の廃棄物)
の組成データを活動プロセスとして整備した。
プレリサイクル(事業系)
可燃ごみ焼却
[ストーカ式](全連続) 処理主灰
低温蒸気分別収集(事業系)
飛灰
一般ごみ(事業系)
活動(事業系)
不要物(事業系)
プレリサイクル(生活系)
分別収集(生活系)
活動(生活系)
不要物(生活系)
一般ごみ(生活系) [組成]
低位発熱量CN灰分
電力
都市ガス
灯油
A重油
軽油
LPG
低位発熱量C
CO2(燃焼起源)CO2(廃棄物由来)
NOxSOx
図3.3-22 焼却プロセスの考え方
焼却プロセスにおいて、Cの燃焼部分はCO2排出量となる。また、低位発熱量が不足す
る場合は、助燃剤が供給される。
イ、 旧盛岡市の活動プロセス(生活系・事業系)
廃棄物組成データを市民や事業所の活動プロセスのインベントリとして位置づけた。活
動プロセスは、市民 1 人あたり・事業所 1 従業員あたりの活動量(1 日単位)をインプット
データとして、1 人 1 日あたりの組成別不要物(集団回収や分別収集をおこなう前の廃棄物)
をアウトプットデータとするものである。つまり、廃棄物組成データをプロセスインベン
トリの形式に言い換えたものである。
旧盛岡市の基本計画中に、廃棄物組成の調査・推定結果が存在するため、これに松藤ら
246
-
の都市ごみの標準的な組成データ3-20)を加味することによって、旧盛岡市における活動プ
ロセスのインベントリデータを作成した。
不要物を計画収集廃棄物・集団回収物・自家処理物に分けるプレリサイクルプロセス、
計画収集廃棄物を可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ・粗大ごみに分ける分別収集プロセスも
整備した。同時に、インベントリではないが、品目(廃棄物組成)ごとの物性データも整備
したので、本項目で示す。
各プロセスのインプット・アウトプットと単位を整理すると表3.3-4となる。
表3.3-4 各プロセスインベントリの単位
プロセス 単位 インプット アウトプット
活動 [(g/d)/人] 市民(生活系)あるいは事業所
従業者(事業系) [人] 不要物(組成別) [g/d]
計画収集廃棄物(組成別) [g] 集団回収物 [g] プレリサイクル [%] 不要物(組成別) [g] 自家処理物 [g] 可燃ごみ(組成別) [g] 不燃ごみ(組成別) [g] 資源ごみ(組成別) [g]
分別収集 [%] 計画収集廃棄物(組成別) [g]
粗大ごみ(組成別) [g]
なお、現状の旧盛岡市のほか、廃棄物抑制シナリオ(生活系は表3.3-2、事業系は表
3.3-3を参照)が実施された場合の 2011 年における各プロセスのインベントリも整備
した。
i、 旧盛岡市の活動プロセスおよびプレリサイクル・分別収集プロセス(生活系)
生活系不要物の排出原単位は、市民 1 人ずつの活動原単位に居住人口を乗算した値とな
る。旧盛岡市実態調査に既往研究を加味して作成した。
247
-
表3.3-5 旧盛岡市の活動/プレリサイクル/分別収集の各インベントリ(生活系)
プロセス 活動 プレリサイクル 分別収集
不要物自家
処理
集団
回収
計画
収集
可燃
ごみ 不燃 ごみ
粗大 ごみ
資源
ごみ 廃棄物種類
([g/d)/人] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 厨芥 280.24 4.2% 0.0% 95.8% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%新聞紙 90.20 0.0% 38.7% 61.3% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%雑誌 49.56 0.0% 20.9% 79.1% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%段ボール 27.28 0.0% 19.9% 80.1% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%飲料用紙パック 2.86 0.0% 2.0% 98.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%紙箱・紙袋・包装紙 29.73 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%その他の紙(手紙・おむつ等) 108.54 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%布類 4.40 0.0% 20.0% 80.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%PET ボトル 8.41 0.0% 0.0% 100.0% 11.0% 15.0% 0.0% 74.0%PET 以外のボトル 6.31 0.0% 0.0% 100.0% 91.7% 8.3% 0.0% 0.0%パック・カップ・トレイ 10.75 0.0% 0.0% 100.0% 91.7% 8.3% 0.0% 0.0%プラ袋・シート・緩衝材・雑包装 40.80 0.0% 0.0% 100.0% 91.7% 8.3% 0.0% 0.0%その他のプラ(商品等) 16.68 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%スチール缶 15.84 0.0% 9.0% 91.0% 0.0% 30.2% 0.0% 69.8%アルミ缶 3.28 0.0% 9.0% 91.0% 0.0% 30.2% 0.0% 69.8%缶以外の鉄類 20.23 0.0% 7.7% 92.3% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%缶以外の非鉄金属類 4.36 0.0% 28.1% 71.9% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%リターナブルびん 9.22 0.0% 13.9% 86.1% 0.0% 27.4% 0.0% 72.6%ワンウェイびん・カレット 27.59 0.0% 13.9% 86.1% 0.0% 27.4% 0.0% 72.6%その他のガラス 8.73 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%陶磁器類 7.28 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%ゴム・皮革 4.34 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%草・木 21.02 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%繊維類(布団・カーペット) 0.88 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%木製家具(タンス・椅�











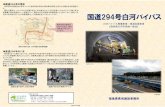




![愛知県庁業務継続計画 [南海トラフ地震想定]...愛知県庁業務継続計画 [南海トラフ地震想定] 平成21年11月 (平成28年3月改定) 愛 知 県](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5f07ad0b7e708231d41e2d3e/ccoeoeccec-fffoeeoef-ccoeoeccec.jpg)


