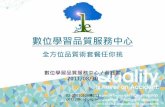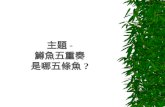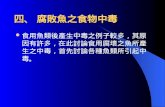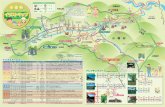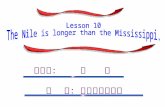觀賞水族生物郵票-金魚(第 輯) - post.gov.tw · 21 金魚原產於中國,是鯽魚的突變種,飼養金魚諧 音「金玉(魚)滿堂」,寓意吉祥、招財,是普遍且
第1章 水産資源及び漁場環境をめぐる動き - maff.go.jp...(2016) 年度 低中位...
Transcript of 第1章 水産資源及び漁場環境をめぐる動き - maff.go.jp...(2016) 年度 低中位...
-
11
○ 水産資源の管理には、資源評価により資源量や漁獲の強さの水準と動向を推定し、結果に基づいて適切な管理措置をとることが不可欠。
○ 令和元(2019)年度、資源評価対象種を50魚種から67魚種に拡大。
○ 令和元(2019)年度の我が国周辺水域の資源評価結果(80系群)では、資源水準の高位が19系群、中位が26系群、低位が35系群。
○ 国民生活の上で特に主要な13魚種33系群では、資源水準の高位が9系群、中位が14系群、低位が10系群。
○ 新たな資源管理の実施に向け、4魚種7系群については、MSYをベースとした資源評価が行われ、資源管理目標案と漁獲シナリオ案等が公表。
○ 資源管理の手法は、1)投入量規制、2)技術的規制、3)産出量規制の3つに大別。我が国では、漁業の特性や漁業者の数、対象となる資源の状況等により、これらの手法を使い分け、組み合わせながら資源管理を実施。
○ 採貝・採藻、定置網漁業、養殖業、内水面漁業等については漁業権制度で管理。沖合・遠洋漁業等については許可制度等で管理。
○ TAC制度はこれまで8魚種を対象に実施。現在、TAC魚種は漁獲量の6割を占める。
〇 今後、TACは、MSYを達成する資源水準の値などの資源管理目標に従い設定。TAC魚種を順次拡大し、漁獲量の8割がTAC魚種となることを目指す。
○ IQ方式は、大臣許可漁業から順次導入。沿岸漁業については、準備が整ったものから導入の可能性を検討。
(1)我が国周辺の水産資源
第1章 水産資源及び漁場環境をめぐる動き
(2)我が国の資源管理ア 我が国の資源管理制度
資料:水産庁・(研)水産研究・教育機構「我が国周辺水域の漁業資源評価」に基づき水産庁で作成
100
80
60
40
20
0平成8(1996)
10(1998)
12(2000)
14(2002)
16(2004)
18(2006)
20(2008)
22(2010)
24(2012)
26(2014)
令和元(2019)
28(2016)
年度
低中位
中高位
低位
中位
高位
令和元年度(2019)主要魚種13魚種33系群
低位10系群30%
高位9系群27%
中位14系群43%
%
我が国周辺の資源水準の状況と推移(主要魚種)
投入量規制(インプットコントロール)
技術的規制(テクニカルコントロール)
産出量規制(アウトプットコントロール)
例:漁船隻数・トン数の制限
例:若齢魚の漁獲制限
例:漁具の仕様の制限
例:禁漁区・禁漁期間の設定
例:漁獲可能量(TAC)の設定
例:漁獲努力可能量(TAE)の管理
資源管理手法の相関図
-
12
(3)実効ある資源管理のための取組ア 我が国の沿岸等における密漁防止・漁業取締り
○ 平成23(2011)年度より、国及び都道府県が「資源管理指針」を策定し、これに沿って関係する漁業者団体が「資源管理計画」を作成・実践する資源管理体制を実施。また、計画的な資源管理の取組を「漁業収入安定対策」により支援。
○ 漁業者自身による自主的な資源管理をより効果的なものとすることを目指して、これまで行われてきた「資源管理指針」に基づく「資源管理計画」は、新漁業法に基づく「資源管理協定」へと順次移行。
○ 平成30(2018)年における全国の漁業関係法令違反の検挙件数は、1,569件(うち海面1,484件、内水面85件)。漁業者以外による密漁が増加。特に、反社会的勢力が組織的に行う磯根資源の密漁は悪質化・巧妙化。
○ 漁業監督官等が、海上保安官及び警察官とともに取締任務に当たるとともに、各地の漁業者も、漁業協同組合を中心として、漁場の監視等の密漁防止活動を実施。
○ 新漁業法では、犯罪者に対して効果的に不利益を与え、密漁の抑止を図るため、大幅な罰則強化。
イ 資源管理計画に基づく共同管理の取組
操業(6月)イメージ
操業(12月)イメージ
共同漁業権(採貝・採藻)(3~ 6月)
共同漁業権(たこつぼ)(周年)
共同漁業権(たこつぼ)(周年)
共同漁業権(刺し網)(周年)
共同漁業権(刺し網)(周年)
定置漁業権(3~ 11月)
特定区画漁業権(ぶり)(通年)
特定区画漁業権(ぶり)(通年)
特定区画漁業権(のり)(10~ 3月)
漁業権漁業にかかる水面の立体的・重複的な利用のイメージ図
資料:水産庁調べ
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
件
昭和57(1982)
平成2(1990)
61(1986)
18(2006)
14(2002)
10(1998)
6(1994)
漁業者以外によるもの
漁業者によるもの
22(2010)
30(2018)
26(2014)
年
我が国の海面における漁業関係法令違反の検挙件数の推移
-
13
○ 一定の大きさまで育成してから放流して資源を増やす種苗放流の取組が、都道府県の栽培漁業センターを中心として各地で実施。
○ 国は、親魚の一部を獲り残して再生産を確保する「資源造成型栽培漁業」の取組等を推進。○ 国は、沖合域における水産資源の増大を目的として、ズワイガニ等の産卵・育成を図るための保護育成礁や、鉛直混合を発生させて海域の生産力を高めるマウンド礁の整備を実施。
○ 内水面では、内水面漁協が、アユやウナギ等の種苗放流や産卵場の整備を実施。
(4)資源を積極的に増やすための取組
○ 令和元(2019)年の水産庁による外国漁船の取締実績は、立入検査数8件、拿捕件数1件、違法設置漁具等の押収件数37件。
○ 日本海の大和堆周辺水域における北朝鮮籍漁船等による違法操業は、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなる問題。このため、漁業取締船を同水域に重点的に配備し、海上保安庁とも連携 し て 対 応。令 和 元(2019)年の水産庁による退去勧告隻数は延べ5,122件。
○ 周辺水域における外国漁船の違法操業に対応するため、令和元(2019)年度に、2隻の新型漁業取締船を新潟及び境港に配備するなど、漁業取締体制の強化を図っている。
イ 外国漁船の監視・取締り
稚魚等をお手渡しになる天皇皇后両陛下
(写真提供:秋田県)
日本海大和堆周辺水域において中国漁船に対し放水する漁業取締船
第39回 全国豊かな海づくり大会
令和元(2019)年9月に秋田県で開催された「天皇陛下御即位記念第39回全国豊かな海づくり大会・あきた大会」は、天皇陛下御即位記念の慶祝行事として、「海づくり つながる未来豊かな地域」を大会テーマに開催。天皇皇后両陛下によるハタハタ、サクラマス、エゾアワビ、ワカメの稚魚等のお手渡しが行われ、後日、秋田県内の各地で放流等を実施。
コラム
±0m
-50~-150m
-20~-40m
栄養塩の増 加
小型魚類
デトリタスの沈降(糞、死骸等有機物)
ベントス類の増加
魚介類の増加魚介類の蝟集
栄養塩濃度分布
マウンド礁造成後の
栄養塩濃度分布
マウンド礁マウンド礁
上層へ栄養塩を供給上層へ栄養塩を供給
付着生物の増加
有光層
流 れ
大型魚類植物プランクトンの増加
動物プランクトンの増加
資料:水産庁調べ
40
35
30
25
20
15
10
5
0
140
120
100
80
60
40
20
0
平成24(2012)
27(2015)
26(2014)
25(2013)
令和元(2019)
30(2018)
28(2016)
29(2017)
年
拿捕及び漁具押収件数
立入検査件数
拿捕件数(左目盛)
7
14
11
19
5
2
6
12
633
2
5
9
6
44 15
5
41
20 21
14
242680
111
86
2414
130
22 21
118
8
37
立入検査件数(右目盛)
件 件
漁具押収件数(左目盛)
ロシア漁船韓国漁船中国漁船台湾漁船
6
51
11
水産庁による外国漁船の拿捕・立入検査等の件数の推移
マウンド礁のメカニズム
-
14
○ 藻場・干潟の保全や機能の回復による生態系全体の生産力の底上げが重要。国は、地方公共団体による藻場・干潟の造成と、漁業者等による保全活動が一体となった、広域的な対策を推進。
○ 養殖漁場については、漁業協同組合等が水質に関する目標、適正養殖可能数量等をまとめた「漁場改善計画」を策定。これを、「漁業収入安定対策」により支援。○ 栄養塩類の減少、偏在等が海域の基礎生産力を低下させ、ノリの色落ちや魚介類の減少の要因となっている可能性。国は、影響の解明に関する調査・研究と栄養塩類の適切な管理の在り方の検討を推進。○ 内水面では、「内水面漁業の振興に関する基本方針」に基づき、関係府省庁、地方公共団体、内水面漁業協同組合等の連携の下、生息環境の再生・保全に向けた取組を推進。
○ 気候変動に対する「緩和策」として、ICTを活用した「スマート農林水産業」の実現や漁船の電化・水素燃料電池化の推進等により温室効果ガス排出削減を図り、「適応策」として、高水温耐性を有する養殖品種の開発等を推進。○ 海洋プラスチックごみは、環境や生態系のほか、漁獲物への混入等漁業にも影響。 水産庁は、1)漁具のリサイクル技術の開発・普及及び環境に配慮した素材を用いた漁具の開発、2)環境省と連携した、漁業者による海洋ごみの回収の促進、3)地域で行う海岸清掃の支援等を実施。
○ トド、ヨーロッパザラボヤ等の野生生物による漁業被害が発生。国では、都道府県の区域を越えて広く分布・回遊し、広域的な対策により被害の防止・軽減に効果が見通せるものについて、出現状況に関する調査と情報提供、被害軽減のための技術開発、駆除活動等への支援等を実施。
○ 内水面では、オオクチバスやカワウ等による資源の食害が問題。防除対策を推進。
(6) 野生生物による漁業被害と対策
(5)漁場環境をめぐる動き
〈オオクチバス〉外来魚による食害
〈トド〉
トドによる漁獲物の食害
気候変動による海洋生物の分布域の変化の把握及びそれに対応した漁場整備の推進
海洋環境の変化に対応しうるサケ稚魚等の放流手法等の開発
多くの漁獲対象種の分布域が北上
シロサケ・サンマの減少・小型化
将来予測 取 組
内水面漁業・養殖業
造成漁場
高水温耐性等を有する養殖品種の開発
養殖適地が北上し、養殖に不適になる海域が出ることが予測
河川湖沼の環境変化と重要資源の生息域や資源量に及ぼす影響評価
琵琶湖の貧酸素水の拡大による特産品(イサザ)の減少
防波堤、物揚場等の漁港施設の嵩上げや粘り強い構造を持つ海岸保全施設の整備を引き続き計画的に推進
波高や高潮偏差増大により、漁港施設等への被害が及ぶおそれ漁港・漁村
海面養殖業
海面漁業
農林水産省気候変動適応計画の概要(抜粋) 漂流ごみ等の回収・処理について(入網ごみ持ち帰り対策)
自治体、漁業関係団体等を通じて、協力依頼・助言
操業中に回収した海洋ごみを持ち帰り
持ち帰りされた海洋ごみを処分
自治体に協力依頼海岸漂着物等地域対策推進事業による支援
水産庁 環境省連 携
漁業者 自治体漁業者を含む関係者と具体的な実施方法について検討し、受入・処理体制を構築
受入・処理体制の例
(写真)香川県提供
資料:農林水産省「農林水産省気候変動適応計画概要」に基づき水産庁で作成
-
15
○ 平成30(2018)年の漁業・養殖業生産量は、前年から12万トン増の442万トン。うち海面漁業は前年から10万トン増の336万トン。ホタテガイ、サンマ及びカツオ類が増加し、カタクチイワシ及びアジ類が減少。海面養殖業は2万トン増の100万トン。内水面漁業・養殖業は5千トン減の5万7千トン。
○ 平成30(2018)年の漁業・養殖業の生産額は、前年から482億円減の1兆5,579億円。うち海面漁業は235億円減の9,379億円、海面養殖業は191億円減の5,060億円、内水面漁業・養殖業は56億円減の1,141億円。
○ 水産物価格は、資源の変動や気象状況等による各魚種の生産状況、国内外の需要の動向等、様々な要因の影響を複合的に受けて変動。
○ 漁業及び養殖業の平均産地価格は、近年、上昇傾向であったが、平成30(2018)年は、前年から19円/ kg低下し、347円/ kg。
(1)漁業・養殖業の国内生産の動向
第2章 我が国の水産業をめぐる動き
(2)漁業経営の動向ア 水産物の産地価格の推移
平成29年(2017)
平成30年(2018)
(千トン)
合 計 4,306 4,421 海 面 4,244 4,364 漁 業 3,258 3,359 遠洋漁業 314 349 沖合漁業 2,051 2,042 沿岸漁業 893 968 養 殖 業 986 1,005 内 水 面 62 57 漁 業 25 27 養 殖 業 37 30
生
産
量
資料:農林水産省「漁業・養殖業生産統計」
資料:農林水産省「漁業産出額」に基づき水産庁で作成
注:漁業生産額は、漁業産出額(漁業・養殖業の生産量に産地市場卸売価格等を乗じて推計したもの)に種苗の生産額を加算したもの。
漁業・養殖業の国内生産量・額の推移
〈生産量〉 〈生産額〉(億円)
平成29年(2017)
平成30年(2018)
合 計 16,061 15,579 海 面 14,864 14,438 漁 業 9,614 9,379 養 殖 業 5,250 5,060 内 水 面 1,197 1,141 漁 業 198 185 養 殖 業 998 956
生
産
額
サケ、サンマ、スルメイカの不漁について
令和元(2019)年のサケ、サンマ、スルメイカの漁獲量はいずれも過去最低レベル。不漁の原因として、海水温の影響のほか、魚種によっては外国漁船による漁獲が影響した可能性。原因を解明するためには複数年にわたる様々なデータに基づき資源状況や海洋環境の変化等の要因を科学的に分析する必要があり、データを継続的に収集する体制の構築が重要。
コラム
円/kg
平成19(2007)
20(2008)
21(2009)
24(2012)
25(2013)
22(2010)
23(2011)
30(2018)
29(2017)
28(2016)
27(2015)
26(2014)
年
400
350
300
250
200
0
資料:農林水産省「漁業・養殖業生産統計」及び「漁業産出額」に基づき水産庁で作成注:漁業・養殖業の産出額を生産量で除して求めた。
漁業・養殖業の平均産地価格
-
16
ウ 所得の向上を目指す「浜の活力再生プラン」
○ 平成30(2018)年の沿岸漁船漁業を営む個人経営体の平均漁労所得は、前年から32万円減少して186万円。漁労外事業所得を加えた事業所得は205万円。
○ 漁船漁業を営む会社経営体では、平成30(2018)年度は漁労利益の赤字が続いているものの、水産加工等による漁労外利益を加えた営業利益は282万円。
○ 燃油の価格は平成28(2016)年以来4年ぶりの低水準。
○ 平成30(2018)年の海面養殖業を営む個人経営体の漁労所得は、前年から402万円減少して763万円。
○ 魚粉の輸入価格は、平成27(2015)年4月には平成17(2005)年の約2.6倍まで上昇。その後はやや落ち着いて推移。
○ 燃油・配合飼料価格高騰時には、影響を緩和するため、国と漁業者による積立金から補てん金を交付。
○ 「浜の活力再生プラン」は、漁業所得を5年間で10%以上アップすることを目標とし、実現するための方策を地域自ら考え実施するもの。令和2(2020)年3月末までに647地区が実施段階に。○ 平成27(2015)年度からは、より広域的な競争力強化のための取組を行う「浜の活力再生広域プラン」もスタート。令和2(2020)年3月末までに154件が策定、実施。
イ 漁船漁業・養殖業の経営状況
1)兵庫県地域水産業再生委員会・但馬沖合底びき網 漁業部会平成26(2014)年度から「浜の活力再生プラン」の取組として、漁獲物の船内凍結や冷却海水水槽による鮮度保持対策、急速冷凍機器の導入による高鮮度で風味や食感を保った新商品の開発・販売を実施。生産から流通・消費に至る総合的な取組により、5年間で1割以上の漁業所得の向上を達成。
2)宮崎県串間市東地区地域水産業再生委員会
地域ごとの事情に即した「浜の活力再生プラン」
急速冷凍機器による鮮度を保ったホタルイカの新商品
「浜ほたる」(写真提供:兵庫県漁連)
平成26(2014)年度から「浜の活力再生プラン」に基づく取組として、定置網漁業を軸にしつつ、各漁業者が複合的に漁業等を実施することを可能とする体制作りや地域一体となったブランド化、消費拡大の取組を実践。地域が一体となって取り組むことで、5年間で1割以上の漁業所得の向上を達成。
事例
大型定置
個人で漁業 加工品製造・販売
当番制で大型定置網に従事し、基本的な所得を確保
当番以外の日・時間は、個人が主体的に漁や加工品販売等を実施することで、更なる所得を確保
たじま くしま
140120100806040200
円/L
平成19(2007)
20(2008)
21(2009)
22(2010)
23(2011)
24(2012)
25(2013)
26(2014)
27(2015)
令和元(2019)
2(2020)
30(2018)
29(2017)
28(2016)
年
A重油価格
原油価格
平成20(2008)年8月124.6円/L
平成20(2008)年7月88.7円/L
令和2(2020)年3月22.8円/L
令和2(2020)年4月63.1円/L
燃油価格の推移
25
20
15
10
5
020
(2008)19
(2007)18
(2006)平成17(2005)
21(2009)
22(2010)
23(2011)
24(2012)
25(2013)
26(2014)
2(2020)
令和元(2019)
30(2018)
29(2017)
28(2016)
27(2015)
年
万円/トン
配合飼料及び輸入魚粉価格の推移
資料:水産庁調べ
資料:財務省「貿易統計」、(一社)日本養魚飼料協会調べ、水産庁調べ
配合飼料
魚粉
令和2(2020)年2月188,492円/トン
令和2(2020)年1月138,921円/トン
-
17
○ 漁業就業者数は減少傾向で、平成30(2018)年は15万1,701人。○ 水産庁では、平成14(2002)年から、漁業経験ゼロからでも漁業に就業・定着できるよう、新規就業者の段階に応じた支援を実施。また、漁船乗組員不足に対応するため、水産高校生を対象とした漁業ガイダンスを支援。
○ 20トン以上の船舶の漁業では、海技士の高齢化と不足が深刻化。令和元(2019)年度より、水産高校卒業生が四級海技士試験を受験するのに必要な乗船履歴(1年9か月間)の短縮が可能となった。
○ 水揚げ後の陸上作業や水産加工業では、女性がより大きな役割。国は子供待機室や調理実習室等、女性の活動を支援する施設の整備を支援。また、女性が働きやすい漁業・水産業の現場改革や魅力向上を後押しする「海の宝!水産女子の元気プロジェクト」が平成30(2018)年11月に発足。
○ 特定技能制度により、漁業分野及び水産加工業においても、平成31(2019)年4月以降、一定の基準を満たした外国人の受入れを開始。
〇 外国人技能実習制度は、 漁業・養殖業における9種の作業及び水産加工業における8種の作業について技能実習を実施。
○ 令和元(2019)年の漁船の船舶海難隻数は510隻、漁船の船舶海難に伴う死者・行方不明者数は36人。○ 令和元(2019)年における漁船からの海中転落者(船舶事故以外の理由によるもの)は81人、うち死者・行方不明者は51人。
○ 海中転落時には、ライフジャケットの着用が生存に大きな役割(約2倍の生存率)。平成30(2018)年から、原則、全ての船舶において船室の外にいる全ての乗船者にライフジャケットの着用を義務付け。令和元(2019)年の海中転落時における着用率は約6割。
○ 小型漁船の安全性向上のため、スマートフォンを活用して、衝突、乗揚事故を回避するための実証試験を推進。
(3)水産業の就業者をめぐる動向
(4)漁業労働環境をめぐる動向
資料:海上保安庁「海難の現況と対策」
平成19(2007)
20(2008)
21(2009)
22(2010)
25(2013)
24(2012)
23(2011)
年
1,000
500
0
隻100
50
0
人
600 630543 510539
795732
812
707
880
651 646596
24
50
96
68
5764
55
39
65
26(2014)
令和元(2019)
30(2018)
29(2017)
28(2016)
27(2015)
3645
26
36
漁船船舶海難隻数(左目盛)死者・行方不明者数(右目盛)
漁船の事故隻数及び事故に伴う死者・行方不明者数の推移
資料:海上保安庁調べ
死亡・行方不明25%
死亡・行方不明60%生存
75%
生存40%
令和元(2019)年漁船ライフジャケット着用者 111人
令和元(2019)年漁船ライフジャケット非着用者 87人
ライフジャケットの着用・非着用別の漁船からの海中転落者の生存率
-
18
○ 水産業を成長産業に変えていくためには、ICT・AI等の技術を漁業・養殖業の現場に導入・普及させていくことが重要。○ 様々な分野で得られるデータの連携・共有・活用を可能とする「水産業データ連携基盤」の整備により効率的な経営等を支援。○ 水産庁では、令和元(2019)年5月から「水産業の明日を拓くスマート水産業研究会」を開催し、推進方策等について検討。
○ 漁業協同組合は、販売等の事業の実施などによる漁業経営の安定・発展への貢献、水産資源の適切な利用と管理等、漁村の地域経済や社会活動を支える中核的な組織。
○ 平成31(2019)年3月末現在の組合数(沿海地区)は945組合。○ 漁業者数の減少に伴って組合員数の減少が進行。依然、零細な組合が多い。合併等により組合の事業及び経営の基盤を強化するとともに、販売事業の一層の強化を図る必要。
(6)漁業協同組合の動向
(5)「スマート水産業」の推進等に向けた技術の開発・活用
7
4033
52
8070
52
132124
149
103
125
76 73
35
12
30
4 0 210 1610
7日先までの流速・塩分を予測海面から海底までの漁獲層ごとの水温、塩分、流速を動画表示
今までわからなかった海中での漁具の動きを可視化
魚群探知機の画面がスマートフォンで可視化
新規就業者にデータに基づき指導
資料:水産庁「水産業協同組合年次報告」(沿海地区漁協数)、「水産業協同組合統計表」(販売事業取扱高)及び全国漁業協同組合連合会調べ(合併参加漁協数)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0平成元(1989)
販売事業取扱高(百億円)
合併参加漁協数(組合)
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
沿海地区漁協数
12(2000)
10(1998)
5(1993)
14(2002)
16(2004)
18(2006)
20(2008)
22(2010)
24(2012)
30(2018)
28(2016)
26(2014)
年度
合併参加漁協数(左目盛)
販売事業取扱高(左目盛)
沿海地区漁業協同組合数、合併参加漁業協同組合数及び販売事業取扱高の推移
945組合
103百億円
2,134組合
165百億円
資料:水産庁「水産業協同組合統計表」
1009080706050403020100平成元(1989)
万人(全国計)
400
300
200
100
0
22(2010)
23(2011)
29(2017)
30(2018)
28(2016)
26(2014)
27(2015)
24(2012)
25(2013)
年度
人(1組合当たり)
51.8
17.1
34.7
87.1
176.2
263.3
173.3
183.1
356.4
172.8
177.2
349.9
172.3
175.4
347.7
177.2
342.0
164.7
176.0
335.1
159.1
173.4
327.9
154.5
171.5
322.0
150.5
167.5 166.3
312.6 308.3
145.2 142.0
35.1
17.1
18.1
34.4
17.0
17.4
33.7
16.7
17.0
32.8
17.0
15.8
31.7
16.7
15.1
31.1
16.4
14.6
30.2
16.1
14.1
29.5
15.8
13.7
28.6
15.4
13.2
漁業協同組合の組合員数の推移
沿海地区漁協数(右目盛)
准組合員数(左目盛)正組合員数(左目盛)正組合員数/組合(右目盛)准組合員数/組合(右目盛)計/組合(右目盛)
組合
スマートフォンで提供する漁場形成予測画面など
-
18
○ 水産業を成長産業に変えていくためには、ICT・AI等の技術を漁業・養殖業の現場に導入・普及させていくことが重要。○ 様々な分野で得られるデータの連携・共有・活用を可能とする「水産業データ連携基盤」の整備により効率的な経営等を支援。○ 水産庁では、令和元(2019)年5月から「水産業の明日を拓くスマート水産業研究会」を開催し、推進方策等について検討。
○ 漁業協同組合は、販売等の事業の実施などによる漁業経営の安定・発展への貢献、水産資源の適切な利用と管理等、漁村の地域経済や社会活動を支える中核的な組織。
○ 平成31(2019)年3月末現在の組合数(沿海地区)は945組合。○ 漁業者数の減少に伴って組合員数の減少が進行。依然、零細な組合が多い。合併等により組合の事業及び経営の基盤を強化するとともに、販売事業の一層の強化を図る必要。
(6)漁業協同組合の動向
(5)「スマート水産業」の推進等に向けた技術の開発・活用
7
4033
52
8070
52
132124
149
103
125
76 73
35
12
30
4 0 210 1610
7日先までの流速・塩分を予測海面から海底までの漁獲層ごとの水温、塩分、流速を動画表示
今までわからなかった海中での漁具の動きを可視化
魚群探知機の画面がスマートフォンで可視化
新規就業者にデータに基づき指導
資料:水産庁「水産業協同組合年次報告」(沿海地区漁協数)、「水産業協同組合統計表」(販売事業取扱高)及び全国漁業協同組合連合会調べ(合併参加漁協数)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0平成元(1989)
販売事業取扱高(百億円)
合併参加漁協数(組合)
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
沿海地区漁協数
12(2000)
10(1998)
5(1993)
14(2002)
16(2004)
18(2006)
20(2008)
22(2010)
24(2012)
30(2018)
28(2016)
26(2014)
年度
合併参加漁協数(左目盛)
販売事業取扱高(左目盛)
沿海地区漁業協同組合数、合併参加漁業協同組合数及び販売事業取扱高の推移
945組合
103百億円
2,134組合
165百億円
資料:水産庁「水産業協同組合統計表」
1009080706050403020100平成元(1989)
万人(全国計)
400
300
200
100
0
22(2010)
23(2011)
29(2017)
30(2018)
28(2016)
26(2014)
27(2015)
24(2012)
25(2013)
年度
人(1組合当たり)
51.8
17.1
34.7
87.1
176.2
263.3
173.3
183.1
356.4
172.8
177.2
349.9
172.3
175.4
347.7
177.2
342.0
164.7
176.0
335.1
159.1
173.4
327.9
154.5
171.5
322.0
150.5
167.5 166.3
312.6 308.3
145.2 142.0
35.1
17.1
18.1
34.4
17.0
17.4
33.7
16.7
17.0
32.8
17.0
15.8
31.7
16.7
15.1
31.1
16.4
14.6
30.2
16.1
14.1
29.5
15.8
13.7
28.6
15.4
13.2
漁業協同組合の組合員数の推移
沿海地区漁協数(右目盛)
准組合員数(左目盛)正組合員数(左目盛)正組合員数/組合(右目盛)准組合員数/組合(右目盛)計/組合(右目盛)
組合
スマートフォンで提供する漁場形成予測画面など
19
○ 近年の消費者の食の簡便化・外部化志向の高まりにより、水産物消費における加工の重要性が増大。多様化する消費者ニーズを捉えた商品開発が必要。
○ 経営の脆弱性、さらには、産地全体の機能強化等が多くの加工業者における課題。
○ 水産物卸売市場の数について、産地卸売市場は近年横ばい傾向、消費地卸売市場は減少。
○ 卸売市場は、水産物を効率的に流通させる上で重要な役割。一方、産地卸売市場の多くは規模が小さく価格形成力が弱いことが課題。市場統廃合等により維持・強化を図っていく必要。食品流通は多様化する実需者等のニーズに的確に応えていくことが重要。
(7)水産物の流通・加工の動向ア 水産物流通の動向
○ 米国やEU等に水産物を輸出する際には、水産加工施設等が、輸出先国・地域から求められているHACCP実施と施設基準への適合が必要。
○ このため、国では、一般衛生管理やHACCPに基づく衛生管理に関する講習会の開催等を支援するとともに、EUや米国への輸出に際して必要な施設認定を取得するための水産加工・流通施設の改修等を支援。
○ 令和2(2020)年3月末現在、水産加工業等における対EU輸出認定施設数は75施設、対米輸出認定施設数は454施設。
○ 水産加工業者を含む食品等事業者においては、令和2(2020)年6月から、HACCPに沿った衛生管理等の実施に取り組むことが必要(令和3(2021)年5月末までは経過措置として現行基準が適用)。
ウ HACCPへの対応
イ 水産加工業の役割と課題
市場数
平成20(2008)
21(2009)
22(2010)
23(2011)
24(2012)
29(2017)
30(2018)
年度27(2015)
28(2016)
26(2014)
25(2013)
350
300
250
200
150
100
50
0
地方卸売市場(消費地)
中央卸売市場
287 280 277 273 269 262 258 257 251 244
323333 332 331 329 318 317 317 312 313
地方卸売市場(産地)
資料:農林水産省「卸売市場データ集」注:中央卸売市場は年度末、地方卸売市場は平成23(2011)年度までは年度当初、24(2012)年度からは年度末のデータ。
水産物卸売市場数の推移
資料:水産庁調べ
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
施設数
26(2014)
28(2016)
29(2017)
27(2015)
25(2013)
24(2012)
23(2011)
20(2008)
21(2009)
平成17(2005)
18(2006)
19(2007)
22(2010)
30(2018)
令和元(2019)
年度
対EU(水産庁及び厚生労働省による認定施設数の合計)
対米((一社)大日本水産会及び厚生労働省による認定施設数の合計)
284317
363
411
454
192217 228
244260 268 253 254 252 262
45 51 5663 75
17 19 21 21 21 23 27 28 2936
水産加工業等における対EU・米国輸出認定施設数の推移
49 48 46 44 43 39 36 35 35 34 34
-
20
○ 平成30(2018)年の世界の漁業・養殖業生産量は前年から3%増の2億1,209万トン。このうち漁船漁業生産量は横ばい傾向、養殖生産量は急激に増加。
○ 漁船漁業生産量は、EU、米国、我が国等の先進国・地域ではおおむね横ばいから減少傾向。中国、インドネシア、ベトナム等の開発途上国で増加。
○ 養殖生産量は、中国及びインドネシアで増加が顕著。魚種別に見ると、コイ・フナ類や藻類の増加が顕著。
○ 生物学的に持続可能なレベルで漁獲されている世界の水産資源の割合は漸減傾向。平成27(2015)年には67%が生物学的に持続可能(うち生産量増大の余地のある資源は7%)、33%が過剰利用。
○ 世界の水産物輸出入量は総じて増加傾向。輸出量では、EU、中国、ノルウェーが上位。輸入量ではEU、中国、米国が上位。
○ 輸出入金額については、中国が世界最大の純輸出国。EU、米国、日本が主な純輸入国・地域。
(1)世界の漁業・養殖業生産
第3章 水産業をめぐる国際情勢
(2)世界の水産物貿易
資料:FAO「Fishstat」、農林水産省「漁業・養殖業生産統計」に基づき水産庁で作成
24,000
21,000
18,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
0
万トン
昭和35(1960)
55(1980)
45(1970)
平成2(1990)
12(2000)
30(2018)
22(2010)
年
世界の漁業・養殖業生産量の推移
資料:FAO「The State of World Fisheries and Aquaculture 2018」に基づき水産庁で作成
100
80
60
40
20
0
%
昭和49(1974)
53(1978)
57(1982)
61(1986)
平成2(1990)
6(1994)
10(1998)
14(2002)
18(2006)
27(2015)
年
生物学的に持続可能なレベル
にある資源の割合:67%
適正又は低・未利用状態の資源(適正レベルよりも資源量が多く、生産量増大の余地がある。)
適正利用状態の資源(資源量は適正レベルにあり、これ以上の生産量増大の余地がない。)
過剰利用状態の資源(適正レベルよりも資源量が少ない。)
世界の資源状況
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
万トン4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
万トン
昭和51(1976)
55(1980)
60(1985)
平成2(1990)
7(1995)
12(2000)
17(2005)
22(2010)
29(2017)
年 昭和51(1976)
55(1980)
60(1985)
平成2(1990)
7(1995)
12(2000)
17(2005)
22(2010)
29(2017)
年
その他日本タイインドペルー米国
ベトナムロシアノルウェー中国EU(28か国)
その他ベトナムノルウェーロシア韓国タイ日本米国中国EU(28か国)
資料:FAO「Fishstat (Commodities Production and Trade)」 資料:FAO「Fishstat (Commodities Production and Trade)」
世界の輸出量 世界の輸入量
内水面養殖業海面養殖業内水面漁船漁業海面漁船漁業
-
21
(4)国際的な資源管理
(3)水産物貿易をめぐる国際情勢
ア カツオ・マグロ類の地域漁業管理機関の動向
○ WTOルール交渉においては、漁業補助金に関する規律策定について議論。我が国は、禁止補助金は真に過剰漁獲能力・過剰漁獲につながるものに限定すべきとの立場。
○ 日米貿易協定は、令和2(2020)年1月1日に発効。本協定では、TPPで関税削減・撤廃した水産品全てを除外。
○ 世界のカツオ・マグロ類資源は、5つの地域漁業管理機関が全てカバーしており、我が国は全てに加盟。○ 中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)の令和元(2019)年の年次会合では、太平洋クロマグロに関し、令和2(2020)年の措置として、1)漁獲上限の未利用分に係る繰越率を、現状の5%から17%への増加すること、2)台湾からの通報により、大型魚の漁獲上限を台湾から日本へ300トン移譲することを可能とすることを採択。
○ 全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)については、令和元(2019)年9月開催のIATTCとWCPFC北小委員会の合同作業部会において、太平洋クロマグロの漁獲上限を議論。
○ 大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)の令和元(2019)年の年次会合では、メバチの令和2(2020)年の総漁獲可能量を62,500トン(うち我が国割当量13,980トン)に削減することを合意。○ インド洋まぐろ類委員会(IOTC)の令和元(2019)年の年次会合では、キハダの資源管理措置について、現行の漁獲量の削減措置を達成できない場合には超過分を翌年の漁獲上限から差し引くこと、小型魚が多く漁獲されるまき網漁のFADの使用可能数の制限を強化することを合意。
○ みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)の令和元(2019)年の年次会合では、ミナミマグロの資源状態に応じてTAC案を自動的に算出するための新たなプログラムを合意。
564
218154
36 51 30 37 4 4 1 18 12
110
359
6221 8 20 53 60 44 62 72 86 113
207
EU(28か国)
韓国
〈輸入額〉
〈輸出額〉
香港
日本
カナダ
タイ
インドネシア
米国
チリ
インド
ベトナム
ノルウェー
中国
600
400
200
0
200
400
億ドル
資料:FAO「Fishstat (Commodities Production and Trade)」(平成29(2017)年)に基づき水産庁で作成注:EUの輸出入額にはEU域内における貿易を含む。
純輸出入額
主要国・地域の水産物輸出入額及び純輸出入額
-
22
ウ IUU漁業の撲滅に向けた動き
○ 北太平洋の公海域では、北太平洋漁業委員会(NPFC)において、サンマ、マサバ、クサカリツボダイ等の資源を管理。
○ 令和元(2019)年7月には、サンマの公海の数量管理の議論が行われ、令和2(2020)年漁期における公海でのTACを33万トンとすること、令和2(2020)年の年次会合でTACの国別配分を検討すること、各国は令和2(2020)年の公海での漁獲量が平成30(2018)年の実績を超えないよう管理すること等を合意。
○ 規制措置を遵守せず無秩序な操業を行うIUU漁業は、水産資源に悪影響を与え、適切な資源管理を阻害するおそれ。
○ 地域漁業管理機関においては、正規の漁業許可を受けた漁船等のリスト化(ポジティブリスト)、IUU漁業への関与が確認された漁船や運搬船等のリスト化(ネガティブリスト)、漁獲証明制度によるIUU漁業由来の漁獲物の国際的な流通の防止等、IUU漁業の抑制・根絶に向けた取組を国際的に推進。
エ 二国間等の漁業関係
○ ロシアとの間では、相互入漁条件及び我が国漁業者の操業条件等を協議。このうち、令和2(2020)年の相互入漁の条件については協力費の支払いを中断。
○ 韓国との間では、相互入漁の操業条件等が合意に至っておらず、協議を継続中。○ 中国との間では、相互入漁の操業条件等が合意に至っておらず、協議を継続中。○ 台湾との間では、日台それぞれのルールで操業できる水域を分け、試行的に操業。○ 太平洋島しょ国のEEZは重要な漁場であるが、入漁料の引上げ、保護区の設定等により入漁環境の厳しさが増大。
イ サンマ・マサバ等の地域漁業管理機関の動向
カツオ・マグロ類以外の資源を管理する主な地域漁業管理機関
中西部太平洋まぐろ類委員会WCPFC
(平成16(2004)年)
大西洋まぐろ類保存国際委員会ICCAT
(昭和44(1969)年)
みなみまぐろ保存委員会CCSBT
(平成6(1994)年)
全米熱帯まぐろ類委員会IATTC
(昭和25(1950)年)
インド洋まぐろ類委員会IOTC
(平成8(1996)年)
注:( )は条約発効年
カツオ・マグロ類を管理する地域漁業管理機関
注:1) 我が国はSPRFMO及びNEAFCには未加盟。 2)( )は条約発効年
地中海漁業一般委員会GFCM(昭和27(1952)年)
北太平洋漁業委員会NPFC
(平成27(2015)年)
南インド洋漁業協定SIOFA
(平成24(2012)年)
南極の海洋生物資源の保存に関する委員会 CCAMLR(昭和57(1982)年)
南東大西洋漁業機関SEAFO(平成15(2003)年)
北西大西洋漁業機関NAFO(昭和54(1979)年)
北東大西洋漁業委員会NEAFC(昭和57(1982)年)
南太平洋漁業管理機関SPRFMO
(平成24(2012)年)
-
23
(6)海外漁業協力
(5)捕鯨をめぐる新たな動き
○ 我が国は、科学的根拠に基づいて水産資源を持続的に利用するとの基本方針の下、令和元(2019)年6月末をもって国際捕鯨取締条約から脱退し、同年7月から大型鯨類(ミンククジラ、イワシクジラ、ニタリクジラ)を対象とした捕鯨業を再開。
〇 再開した捕鯨業は、我が国の領海とEEZで、十分な資源が存在することが明らかになっている3種を対象とし、国際捕鯨委員会(IWC)で採択された方式(RMP(改訂管理方式))に沿って算出される捕獲可能量の範囲内で実施。
〇 鯨類科学調査については、国際捕鯨取締条約からの脱退後も引き続き実施し、IWC等の国際機関と連携しながら、科学的知見に基づく鯨類の資源管理に貢献。
○ 令和元(2019)年12月、「商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律」の改正法が成立。名称を「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律」に改めるとともに、鯨類科学調査を、捕鯨業の適切な実施等を確保するために引き続き重要な役割を担うものとして位置付ける等の改正を実施。
○ 我が国は、我が国漁船にとって重要な漁場を有する国や、海洋生物資源の持続的利用の立場を共有する国を対象に、水産業の振興や資源管理を目的として水産分野の無償資金協力(水産関連の施設整備等)や技術協力(専門家の派遣等)を実施。
○ 我が国漁船が入漁している太平洋島しょ国等の沿岸国に対しては、民間団体が行う水産関連施設の修繕等に対する協力や水産技術の移転・普及に関する協力を支援。
○ 東南アジア地域における持続的な漁業の実現のため、東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC)への財政的・技術的支援を実施。
「母船式捕鯨船団出港式」にて挨拶を行う𠮷川農林水産大臣(当時)
再開した捕鯨業で捕獲された鯨類のセリの様子
-
24
○ 平成30(2018)年度の魚介類の国内消費仕向量は716万トン(原魚換算ベース、概算値)。うち569万トン(80%)が食用、147万トン(20%)が非食用(飼肥料向け)。○ 平成30(2018)年度の食用魚介類の自給率(概算値)は、前年度から3ポイント増加して59%。
○ 食用魚介類の1人1年当たり消費量は、平成30(2018)年度は前年より0.5kg少ない23.9kg。
○ 生鮮魚介類の1世帯当たり年間支出額は、近年、横ばい傾向となっていたが、直近3年は減少傾向。
○ 消費者の食の志向に関する調査では、健康志向、簡便化志向の割合が増加。
○ 近年、消費仕向量全体に占める加工用の食用魚介類の割合が上昇。
(1)水産物需給の動向
第4章 我が国の水産物の需給・消費をめぐる動き
(2)水産物消費の状況ア 水産物消費の動向と消費者の意識
平成13(2001)年度ピーク:40.2kg/人年
食用国内消費仕向量569
生鮮・冷凍 209加 工 品 360
資料:農林水産省「食料需給表」
非食用国内消費仕向量
147
国内消費仕向量716
食用魚介類の国民1人1年当たり供給量【粗食料ベース】45.0kg【純食料ベース】23.9kg
国内生産量392
食 用 335非食用 57
輸入量405
食 用 312非食用 93
輸出量81
食 用 79非食用 2
在庫増加1
食 用 -1非食用 2
(単位:万トン)
〈平成30(2018)年度(概算値)〉
我が国の魚介類の生産・消費構造
資料:農林水産省「食料需給表」
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
万トン120
100
80
60
40
20
0
食用魚介類の消費仕向量
国民1人1年当たり食用魚介類供給量(粗食料、kg)
食用魚介類の自給率(%)
昭和35(1960)
45(1970)
55(1980)
平成2(1990)
12(2000)
22(2010)
30(2018)(概算値)
年度
国内生産量
輸入量
自給率(右目盛)
国民1人1年当たり食用魚介類供給量(粗食料、右目盛)
食用魚介類国内消費仕向量(左目盛)
昭和39(1964)年度自給率ピーク:113%
平成30(2018)年度(概算値)自給率:59%
食用魚介類の自給率の推移
資料:農林水産省「食料需給表」
50
40
30
20
10
0
kg/人年 g/人日
30(2018)
21(2009)
25(2013)
17(2005)
9(1997)
13(2001)
5(1993)
平成元(1989)
年度
平成30(2018)年度(概算値)33.5kg/人年
平成30(2018)年度(概算値)23.9kg/人年
平成30(2018)年度(概算値)79.1g/人日
平成元(1989)年度25.8kg/人年
90
60
30
0
食用魚介類及び肉類の1人1年当たり消費量(純食料)とたんぱく質の1人1日当たり消費量の推移
資料:(株)日本政策金融公庫「食の志向調査」に基づき水産庁で作成 注:破線は近似曲線または近似直線。
50454035302520151050
%
年
健康志向経済性志向簡便化志向
安全志向手作り志向
31(2019)
平成20(2008)
21(2009)
22(2010)
23(2011)
24(2012)
25(2013)
26(2014)
27(2015)
28(2016)
29(2017)
30(2018)
1月7月1月7月1月7月1月7月1月7月1月7月1月7月1月7月12月6月1月7月12月5月令和元(2019)
7月2
(2020)
1月
消費者の現在の食の志向(上位)の推移
魚介類(左目盛)
たんぱく質(右目盛)
肉類(左目盛)
-
25
○ 食品表示は、平成27(2015)年より、「食品表示法」の下で包括的・一元的に実施。
○ 平成29(2017)年9月に「食品表示基準」が改正され、輸入品以外の全ての加工食品について、製品に占める重量割合上位1位の原材料を対象(おにぎりののりについては重量割合に関わらず対象)に、その原産地の表示が義務化。
○ 水産エコラベル認証の活用の動きが世界的に拡大。我が国においては、マリン・エコラベル・ジャパン協議会(MEL協議会)によるMELの普及が進展。MELは、令和元(2019)年12月に世界水産物持続可能性イニシアチブ(GSSI:Global Sustainable Seafood Initiative)の承認を取得。○ 地理的表示(GI)保護制度については、令和2(2020)年3月末までに12件の水産物が登録。
○ 水産物の摂取が健康に良い効果を与えることが、様々な研究から明らかに。○ 魚の脂質に多く含まれているドコサヘキサエン酸(DHA)、エイコサペンタエン酸(EPA)といったn-3(オメガ3)系多価不飽和脂肪酸は、胎児や子供の脳の発育に重要な役割。
○ 魚肉たんぱく質は、人間が生きていく上で必要な9種類の必須アミノ酸をバランス良く含む良質のたんぱく質であるだけでなく、大豆たんぱく質や乳たんぱく質と比べて消化されやすく、体内に取り込まれやすいという特徴。
(3)消費者への情報提供や知的財産保護のための取組
イ 水産物の健康効果
筋トレのおともにお魚はいかが?
高齢化が進む日本社会において、日常生活に制限のない期間である「健康寿命」が注目されている。近年は幅広い層で健康を保つための要素の1つである筋肉への関心が高まり、筋力トレーニング(筋トレ)がブーム。筋肉づくりには、たんぱく質の補給が不可欠。魚は、アミノ酸スコアの高いたんぱく質が豊富。また、魚肉たんぱく質は大豆たんぱく質や乳たんぱく質と比べ、消化・吸収されやすい特性。近年では筋トレやダイエットをする人向けの魚商品も展開。魚を食べて運動をすることで、健康な身体を維持し、健康寿命が延びることが期待される。
コラム
0 20 40 60 80 100年
資料:厚生労働省「平成28年簡易生命表」及び「第11回健康日本21(第二次)推進専門委員会 資料」に基づき水産庁で作成
平均寿命 健康寿命
女性
男性
平均寿命と健康寿命の差(平成28(2016)年)
87.14
74.79
80.98
72.14
12.35年
8.84年
※認証数は令和2年3月31日時点(水産庁調べ)
〈日本〉【日本での認証数】48漁業、21養殖業•サケ(北海道)•カツオ(高知県他)•サンマ(岩手県)•サクラエビ(静岡県) 等58事業者(流通加工)
〈イギリス〉【日本での認証数】6漁業•ホタテガイ(北海道)•カツオ(宮城県、静岡県)•ビンナガ(宮城県、静岡県)•カキ(岡山県)273事業者(流通加工)
MEL認証MSC認証
〈オランダ〉【日本での認証数】9養殖業(64養殖場)•カキ(宮城県)•ブリ(宮崎県、鹿児島県、大分県)•カンパチ(鹿児島県) 等136事業者(流通加工)
ASC認証〈日本〉【日本での認証数】42養殖業•カンパチ(宮崎県)•ブリ(鹿児島県)•マダイ(愛媛県) 等24事業者(流通加工)
AEL認証
※今後、MELに統合
日本発の認証
海外発の認証
漁
業
養殖業
我が国で主に活用されている水産エコラベル認証
登録番号 名称 写真 特定農林水産物等の生産地
92 檜山海参
89 大野あさり
88 田浦銀太刀
84 豊島タチウオ
北海道久遠郡せたな町、二海郡八雲町、爾志郡乙部町、檜山郡江差町及び上ノ国町、奥尻郡奥尻町
広島県廿日市市
熊本県葦北郡芦北町田浦沖及びその周辺海域(八代海)
広島県呉市豊浜町豊島沖周辺海域
令和元(2019)年度におけるGI保護制度の登録産品(水産関係の例)
-
26
○ 令和元(2019)年の水産物輸入量(製品重量ベース)は前年比4%増の247万トン。輸入金額は前年比3%減の1兆7,404億円。
○ 品目別では、サケ・マス類、カツオ・マグロ類、エビ等が輸入金額の上位。
(4)水産物貿易の動向ア 水産物輸入の動向
○ 令和元(2019)年の水産物輸出量(製品重量ベース)は前年比15%減の64万トン。輸出金額は前年比5%減の2,873億円。
○ 主な輸出先国・地域は香港、中国、米国であり、これらの輸出金額は全体の約6割。○ 品目別では、ホタテガイ、真珠等が輸出金額の上位。○ 令和元(2019)年11月に「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」公布。「農林水産物・食品輸出本部」が農林水産省に創設。
○ 令和2(2020)年3月に、令和12(2030)年までに農林水産物・食品の輸出額を5兆円(うち水産物1.2兆円)とする新たな目標を設定。
イ 水産物輸出の動向
400
350
300
250
200
150
100
50
0
万トン18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
億円
資料:財務省「貿易統計」に基づき水産庁で作成
平成16(2004)
19(2007)
22(2010)
25(2013)
令和元(2019)
28(2016)
年
令和元(2019)年247万トン
輸入量(左目盛)
我が国の水産物輸入量・金額の推移
令和元年(2019)
1兆7,404億円
令和元年(2019)
1兆7,404億円 その他50.6%
エビ10.5%
エビ調製品4.3%
タラ類3.5%
イカ3.7%
カツオ・マグロ類11.0%
ベトナム6.8%
タイ6.5%
その他28.8%
韓国4.6%
米国7.7%
チリ9.4%
ロシア7.0%
ノルウェー6.2%
中国18.1%
カニ3.7%
インドネシア4.9%
〈輸入相手国・地域〉 〈輸入品目〉
農林水産物総輸入額に占める割合:18.3%
サケ・マス類12.7%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
万トン3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
億円
資料:財務省「貿易統計」に基づき水産庁で作成
輸出金額(右目盛)
平成16(2004)
19(2007)
22(2010)
25(2013)
令和元(2019)
28(2016)
年
輸出量(左目盛)
令和元(2019)年 2,873億円
令和元(2019)年 1兆7,404億円
我が国の水産物輸出量・金額の推移
その他45.3%
〈輸出相手国・地域〉 〈輸出品目〉
令和元年(2019)2,873億円
令和元年(2019)2,873億円
農林水産物総輸出額に占める割合:31.5%
ホタテガイ15.5%
真珠11.5%
サバ類7.2%
ブリ8.0%
ナマコ調製品7.2%
ベトナム6.0%
タイ7.2%
その他16.7%
韓国5.0%
米国11.9%
中国16.9%
香港29.8%
台湾6.4%
カツオ・マグロ類5.3%
令和元(2019)年64万トン
輸入金額(右目盛)
-
27
(1)漁村の現状と役割
(2)安心して暮らせる安全な漁村づくり
○ 漁港・漁村における防災機能の強化と減災対策の推進を図っていく必要。国は、防波堤と防潮堤による多重防護、粘り強い構造の防波堤、避難路の整備等を推進。
○ 台風19号等の自然災害による被害に対し、被害施設の復旧への支援等の各種支援対策を実施。○ 漁村では生活環境の整備が立ち後れ。集落道や漁業集落排水の整備等を推進。○ インフラの老朽化対策は政府全体の課題。予防保全のための対策を盛り込んだ計画に基づき、漁港・漁村インフラの維持管理と更新を推進。
○ 漁業集落の多くが、漁業生産には有利である反面、自然災害に対してぜい弱な立地(漁港背後集落のうち34%は半島、19%は離島地域)。高齢化、人口減少が進行(漁港背後集落の高齢化率は40%)。
○ 漁業及び漁村は、1)自然環境を保全する機能、2)国民の生命・財産を保全する機能、3)交流等の場を提供する機能、4)地域社会を形成し維持する機能等の多面的機能を発揮。広く国民一般も多面的機能の恩恵を享受。
○ 国では、藻場や干潟の保全、内水面生態系の維持・保全・改善、海難救助や国境・水域監視等の漁業者等が行う多面的機能の発揮に資する取組を支援。
第5章 安全で活力ある漁村づくり
漁港背後集落の人口(左目盛)漁港背後集落の高齢化率(右目盛)日本の高齢化率(右目盛)
19(2007)
22(2010)
25(2013)
令和元(2019)
28(2016)
平成16(2004)
245248250253
30.4
21.520.8
240
31.2
22.1
237
31.7
22.7
234
32.2
23.0
212
32.5
23.3
209
33.2
24.1
206
34.0
25.1
203 199
195 192192 184
35.1 36.3
37.2 38.138.9 39.7
26.0 26.6 27.327.7 28.1 28.4
年
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0
万人50
40
30
20
10
0
%
資料:総務省「人口推計」(国勢調査実施年は国勢調査人口による)、水産庁調べ注:平成23(2011)~ 31(2019)年の漁港背後集落の人口及び高齢化率は、岩手県、宮城県及び福島県の3県を除く。
29.428.928.3
20.219.5
漁港背後集落の人口
高齢化率
漁港背後集落の人口と高齢化率の推移
資料:日本学術会議答申を踏まえて農林水産省で作成(水産業・漁村関係のみ抜粋)
百余隻に及ぶ大漁旗で飾った奉迎船が織りなす、勇壮な入船・出船の海上神事[山口県祝島神舞]
キビナゴを使った伝統的鍋料理[長崎県五島地方]
干潟環境の悪化を防ぐため、貝類の突発的な大量斃死により発生した死骸を除去する取組[福島県]
流出油を回収する漁業者[神奈川県]カキ養殖
アマモの栄養株の移植や播種(はしゅ)により、アマモ場の維持・回復を図る取組[岡山県]
オニヒトデ等のサンゴを食害する生物を除去し、サンゴ礁を保全する取組[沖縄県]
自然環境を保全する機能
潮流
プランクトンによって濁っている海水(白っぽく見える)
カキによって浄化されたきれいな海水(濃く見える)
カキ養殖筏
交流等の場を提供する機能
川で魚とりを楽しむ人々[宮崎県]
干潟観察会[三重県]
体験乗船[北海道]
国民の生命・財産を保全する機能
転落者・漂流者の救助訓練の様子[青森県]
地域社会を形成し、維持する機能
漁業・漁村の多面的機能
-
28
(1)水産業における復旧・復興の状況
○ 漁村の活性化のためには、それぞれが有する地域資源を十分に把握し最大限に活用することで、来訪者を増やし、交流を促進することが重要。そのためには、漁村の特性に即した対策の実施、関係者と連携して地域一体となって取り組むことが重要。
○ 伝統的な生活体験や漁村地域の人々との交流を楽しむ「渚泊」について、国は、地域資源を魅力ある観光コンテンツとして磨き上げる取組等のソフト対策や、古民家等を活用した滞在施設等のハード対策を支援。
○ 「浜の活力再生プラン」及び「浜の活力再生広域プラン」の取組により、漁業振興を通じた漁村の活性化が期待。
○ 国は被災地の水産業の復旧・復興に引き続き取組。○ 水産業の拠点となる漁港には、高度衛生管理型荷さばき所や耐震強化岸壁等を整備。
(3)漁村の活性化
ビン玉縄編み体験 刺身づくり体験
海沿いに立ち並ぶ舟屋群 舟屋を活用した「舟屋の宿」
(写真提供:伊根町観光協会)
京都府伊根地区は、周囲の伊根湾に沿って約230軒の舟屋と呼ばれる1階が舟置き場、2階が二次的な居室となっている建物が建ち並ぶ。この風光明媚な町並みと自然が残る地域は、重要伝統的建造物群保存地区にも選定。近年、舟屋を宿泊施設に改修した
「舟屋の宿」が複数開業し、舟屋の宿泊を目的とした観光客が増加。平成28(2016)年から、アジア各国・地域などの外国人観光客も増加。また、舟屋に「泊まる」だけでなく、
伊根湾の新鮮な魚介類や、伊根名物の鯖のへしこ(ぬか漬)等を「味わう」ことや舟屋ガイドと廻れる体験ツアーや漁師に教わるロープワークとビン玉縄編み体験、刺身づくり体験などの「体験する」ことも合わせて、地域を満喫する渚泊の取組を実践。
京都府伊根町における渚泊の取組い ね
事例
第6章 東日本大震災からの復興
資料:(一財)漁港漁場漁村総合研究所「漁村活性化の実践に向けた取組のポイント」(水産業強化対策推進交付金産地協議会活動支援事業)に基づき水産庁で作成
水産物が主
地域の条件
集客しやすい
集客しにくい
地域資源
水産物以外が主(文化、自然環境等)
【取組】直接訪問してもらって、地元で水産物を食べてもらう
(具体例)直販店舗、定期市、飲食・レストラン、惣菜提供、イベント等
【取組】短期滞在型・長期滞在型を含めた総合的な都市漁村交流
(具体例)海レク、観光体験・交流、社会科見学・修学旅行、UIJターン移住、2地域居住、漁村留学等
【取組】水産物を地域外に販売していく
(具体例)新たな流通(実需者との直接取引)、加工、ブランド化、通信販売、移動販売、都市部での直売・飲食店等
【取組】長期滞在型の都市漁村交流
(具体例)修学旅行、UIJターン移住、2地域居住、漁村留学等
漁村の特性と取組例
-
29
(2)東京電力福島第一原子力発電所事故の影響への対応ア 水産物の放射性物質モニタリングと福島県沖での試験操業・販売
○ 国、関係都道県、漁業団体が連携し、水産物の放射性物質モニタリングを実施。その結果は公表。○ 令和元(2019)年度の基準値(100ベクレル/kg)超過検体の数は、福島県においては、海産種ではゼロ、淡水種では4検体。福島県外においては、平成26(2014)年以降、海産種では基準値超過検体は無いが、淡水種では2検体。
○ 放射性物質モニタリング結果が基準値を超える水産物は、国、関係都道県、漁業関係団体等の連携によって流通を防止。令和元(2019)年度には福島県沖の海産種の出荷制限が全て解除。
○ 福島県沖の沿岸漁業及び底びき網漁業は、モニタリングの結果を踏まえて試験操業・販売を実施。
陸揚げ岸壁について全延長の陸揚げ 172 208 248 273 284 291機能回復(漁港)部分的に陸揚げ 117 99 65 45 35 28機能回復(漁港)潮位によっては 23 9 5 1 0 0陸揚げ可能(漁港)復旧が完了した 974 1,417 1,903 2,324 2,514 2,602漁港施設(施設)
2 漁港•被災した漁港の全てで陸揚げ機能が回復。
被災319漁港の陸揚げ岸壁の機能回復状況(%):縦棒
被災2852漁港施設の復旧状況(%):折れ線
※各年の状況は3月末時点。※漁港施設とは、岸壁、防波堤、泊地、道路等をいう。※被災漁港数は7道県の合計。
R1H30H29H28H27H26
34
50
67
8188
91
54
37
7
65
31
3
78
20
2
86
14
0
89
11
0
91
90100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
漁港施設(折れ線)
陸揚げ岸壁(縦棒)
全延長の陸揚げ機能回復
部分的に陸揚げ機能回復
潮位によっては陸揚げ可能
水揚金額 801 375 560 649 695 743 722 741 719 606 (億 円)
水 揚 量 462 181 285 325 367 345 323 322 336 307 (千トン)
水揚金額 64% 81% 40% (123.6億円) (474.9億円) (7.1億円) 水 揚 量 61% 69% 54% (84.8千トン) (216.6千トン) (5.9千トン)
福島県(小名浜)
宮城県(気仙沼、女川、石巻、塩釜)
岩手県(久慈、宮古、釜石、大船渡)
R1の内訳
1 水揚げ
岩手・宮城・福島各県の主要な魚市場の水揚げの被災前年比(%)
※H22年は22年3月~23年2月、その他の年は2月~翌年1月。
R1H30H29H28H27H26H25H24H23H22
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
水揚量
水揚金額
47
70
8187
9390
9390
76
39
100
62
70
7975
70 7073
66
水産業復旧の進捗状況(令和(2020)年3月取りまとめ)
復旧隻数 9,195 15,308 17,065 17,947 18,257 18,486 18,651 18,679 18,694
うち岩手 4,217 7,768 8,542 8,805 8,852 8,852 8,852 8,852 8,852
宮城 3,186 5,358 6,293 6,861 7,106 7,310 7,465 7,465 7,565
福島 ― 256 289 340 358 383 393 421 436
•岩手県、宮城県においては、平成27年度末までに希望する漁業者に対する漁船の復旧は完了。•平成28年度以降は原発事故の影響で復旧が遅れている福島県について計画的に復旧を目指している。
※各年の隻数はH24年からH31年は3月末。R2年は1月末。※復旧隻数は21都道県の合計。
H30 R1 R2H29H28H27H26H25H24
復旧隻数
•今後再開を希望する福島県の漁船について計画的に復旧。
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
18,651
18,679
18,694
18,486
18,257
17,94717,065
15,308
9,195
3 漁船
418 645 672 705 729 749 754 754
22 23 23 23 23 23 26 27
(水産加工施設)•被災3県において、再開を希望する水産加工施設の9割以上が業務再開。
(産地市場)•岩手県及び宮城県は、22施設全てが再開。•福島県は、12施設のうち、5施設が再開。
業務再開した水産加工施設(施設)※1
業務再開した産地市場(施設)※2
産地市場
水産加工施設被災3県で被害があった産地市場(34施設)及び再開を
希望する水産加工施設(781施設)の業務再開状況(%)
※1 各年の数字は、H24年が3月末、H25年からH29年は12月末、H30年は9月末、R1年は12月末時点(R1年は再開を希望する水産加工施設数が減少(785→781)したため業務再開状況(%)が上昇した)。
※2 各年の数字は、H24年が4月末、H25年が12月末、H26年からH30年は2月末、 R1年はR2年1月末時点。
R1H30H29H28H27H26H25H24
•再開を希望する水産加工施設の9割以上が業務再開。
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
96 979591
8683
79
68 68 68 68 68
7679
55
65
5 加工流通施設
定置漁場 100% 100% 要望なし (138か所) (850か所) 養殖漁場 100% 99% 100% (165か所) (960か所) (11か所)
福島県宮城県岩手県R2内訳
がれきにより漁業
活動に支障のある
漁場(か所)
定置漁場 1,004 987 992 990 988 988 988 うち 976 980 988 988 988 988 988 処理済み 養殖漁場 1,101 1,100 1,129 1,131 1,135 1,135 1,136
うち 1,045 1,077 1,103 1,116 1,124 1,128 1,129 処理済み
定置漁場
養殖漁場
被災3県でがれきにより漁業活動に支障のある漁場のうち、
がれき処理済みの漁場(%)
※支障のある箇所数が増減するのは、気象海象によりがれきが当該漁場に流入したり、流出したりするためである。
※各年の数字は3月末時点(R2のみ1月末時点)。
R2R1H30H29H28H27H26
•がれきにより漁業活動に支障のあった定置及び養殖漁場 のほとんどで撤去が完了。
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
6 がれき
99999999989895
97 99100 100100100 100
ワカメ養殖※1 34,439 3,742 27,379 30,414 23,354 25,799 25,002 27,047 24,462 コンブ養殖※2 13,817 0 5,633 8,502 6,904 7,205 5,433 6,250 6,674 カキ養殖※3 4,031 354 719 1,476 2,207 2,386 2,316 2,503 2,423 ホタテ養殖※4 14,873 56 5,130 9,245 11,677 12,313 10,871 6,810 4,476 ギンザケ養殖※5 14,750 0 9,448 11,619 11,978 13,007 12,159 13,486 15,982
4 養殖•再開を希望する養殖施設はH29年6月末に全て整備完了。
岩手県・宮城県の主要な養殖品目の漁協共販数量の被災前年比(%)
※1 漁期は2月~ 5月。 ※3 漁期は9月~翌年5月。 ※5 漁期は3月~8月。※2 漁期は3月~ 8月。 ※4 漁期は4月~翌年3月。
H30漁期
H29漁期
H28漁期
H27漁期
H26漁期
H25漁期
H24漁期
H23漁期
H22漁期
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
11
80
88
68
75 73
79
71
91
108
8288
8179
64
00 09
18
37
5559 57
62 60
46 48
738379
62
34
41
62
50 52 3945
30
ギンザケ養殖
ワカメ養殖
コンブ養殖
カキ養殖
(単位:トン)
ホタテ養殖
※ コンブ養殖は、同一施設で生産できるワカメ養殖への転業や低気圧被害等により、生産が伸び悩んでいる。
※ カキ養殖は、むき身加工の人手不足等により、生産が伸び悩んでいる。
※ ホタテ養殖は、良質な種苗の不足等が原因と推測されるへい死の増加や貝毒による出荷自主規制の影響により、生産が減少している。
-
30
○ 依然として一部の消費者が福島県産の食品に対し懸念を抱いている。水産庁では、最新のモニタリング結果や水産物と放射性物質に関するQ&A等をWebサイトで公表する等、正確で分かりやすい情報提供に努力。
○ 海外に向けて、英語、中国語、韓国語でのモニタリング結果公表、各国政府や報道機関に対する調査結果や安全確保のための措置等の説明を行い、輸入規制の緩和・撤廃を働きかけ。水産物の輸入規制を講じていた53か国・地域のうち35か国が令和2(2020)年3月末までに輸入規制を完全撤廃。
○ 我が国が韓国に申し立てを行っていた「韓国による日本産水産物等の輸入規制」に関し、平成31(2019)年4月、WTOは上級委員会報告書を公表。上級委員会は、日本産水産物等を恣意的又は不当に差別していること、必要以上に貿易制限的なものであることを認定したパネル報告書の判断を取り消し。一方、日本産食品が韓国の定める安全性の数値基準(日本と同じ100ベクレル/kg)を十分クリアできるものとしたパネルの事実認定については上級委員会でも取り消されなかった。
○ 日本産農林水産物・食品に対して、輸入規制措置を継続している国・地域に対し、我が国の食品の安全性及び安全管理の取組を改めて説明しつつ、引き続き輸入規制の緩和・撤廃を求めている。
イ 風評被害の払拭と諸外国・地域による輸入規制への対応
福島県産のヒラメなどを使用した期間限定のオリジナルメニュー(写真提供:福島県)
福島県と福島県漁業協同組合連合会は、「常磐もの」(福島県沖で獲れる魚介類)を広くPRするため、株式会社フーディソン及び株式会社カカクコム(食べログ)とタイアップし、令和元(2019)年度に、首都圏の飲食店で福島県産水産物が食べられる「ふくしま常磐ものフェア」を開催。代表例であるヒラメやメヒカリ、マガレイなどが、各店舗により、期間限定のオリジナルメニューとして提供され、福島県産水産物の魅力とおいしさを広くPR。このフェアを通して、多くの人が福島県産水産物の魅力やおいしさを知り、消費の拡大、販路の拡大につながっていくことが期待される。
復活! 常磐もの! ~ふくしま常磐ものフェア~事例
「ふくしま常磐ものフェア」のロゴマーク(資料提供:福島県)
平成23(2011)
24(2012)
25(2013)
26(2014)
4ー
6月
7ー
9月
10ー
12月
4ー
6月
1ー
3月
7ー
9月
10ー
12月
4ー
6月
1ー
3月
7ー
9月
10ー
12月
4ー
6月
1ー
3月
7ー
9月
10ー
12月
4ー
6月
1ー
3月
7ー
9月
10ー
12月
4ー
6月
1ー
3月
7ー
9月
10ー
12月
4ー
6月
1ー
3月
7ー
9月
10ー
12月
4ー
6月
1ー
3月
7ー
9月
10ー
12月
1ー
3月
4ー
6月
7ー
9月
10ー
12月
1ー
3月
27(2015)
29(2017)
30(2018)
31年(2019)
28(2016)
平成23(2011)
24(2012)
25(2013)
26(2014)
4ー
6月
7ー
9月
10ー
12月
4ー
6月
1ー
3月
7ー9月
10ー12月
4ー
6月
1ー
3月
7ー
9月
10ー
12月
4ー
6月
1ー
3月
7ー
9月
10ー
12月
4ー
6月
1ー
3月
7ー
9月
10ー
12月
4ー
6月
1ー
3月
7ー
9月
10ー
12月
4ー
6月
1ー
3月
7ー
9月
10ー
12月
4ー
6月
1ー
3月
7ー
9月
10ー
12月
1ー
3月
4ー
6月
7ー
9月
10ー
12月
1ー
3月
27(2015)
29(2017)
30(2018)
31年(2019)
28(2016)
100
50
0
%3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
検体〈福島県で採取された海産種〉 〈福島県以外で採取された海産種〉
100
50
0
%3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
検体
100ベクレル/kg超(左目盛) 超過率(右目盛)100ベクレル/kg以下(左目盛)
120
90
57.1
299
430
380
649
278
828
300
1,092
202
1.302
154135
1,627
8430
1,921
34 33
1,987
25
10
2,153
94
2,031
0 0
2,211
00
2,044
0
0
1,937
0
1,458 1,753 2,005 2,370 2,151 2,239 2,139 2,316 2,418
0 00
0
0
00
0
00 0
0
1
2,171
2,232
2,064
2,298
1,965
1,567
1,407
1,590
1,665
1,354
1,476
1,490
1,134
36.9
41.0
21.625.1
9.613.4
4.67.7
1.7 1.61.5 1.0 0.4 0.20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22449
4.7 1.9
11
575
34
1,498
45
1,727
27
2,539
12
2,260
9
2,880
3
2,187
6
2,669
2
2,280
3
2,341
1
2,238
1
2,268
1
2,087
0
2,334
0
2,303
0
2,126
0
1,622
0
2,063
0
1,934
0
1,924
0
1,583
0
1,922
0 0
0
00
00
0
0 0 0
0
0
1,657
1,701
1,422
1,652
1,542
1,421
1,292
1,600
1,199
1,266 1,235
1,592
1,221
2.2 2.5 1.1 0.5 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
水産物の放射性物質モニタリング結果(令和2(2020)年3月末現在)
2020水産白書(概要版)1~2章2020水産白書(概要版)3~6章