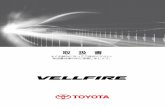イラン自動車・自動車部品産業 市場動向調査...イラン自動車製造社協会(Iran Vehicle Manufacturers Association : IVMA)によると、2017 年度の自
目 次(1) 1.法令等 (1)道路運送車両法(抜粋)...
Transcript of 目 次(1) 1.法令等 (1)道路運送車両法(抜粋)...


I
目 次
【地域教材編】Ⅰ 整備事業関係
1. 法令等
(1) 道路運送車両法(抜粋)……………………………………………………………………………… 1
(2) 道路運送車両法施行規則(抜粋)…………………………………………………………………… 4
(3) 自動車点検基準……………………………………………………………………………………… 7
(4) 自動車の点検及び整備に関する手引……………………………………………………………… 23
2. 通達等
(1) 道路運送車両法施行規則第3条「分解整備の定義」の解釈について(H8.8.20、自整第151号の2) 72
(2) 分解整備の定義に関する照会について(H7.10.25、自整第252号) …………………………… 75
(3) 分解整備の定義に関する照会について(H8.1.29、自整第24号) ……………………………… 76
(4) 分解整備の定義に関する照会について(H9.10.6、自整第172号)……………………………… 77
(5) 自動車分解整備事業関係業務処理要領 ………………………………………………………… 78
(6) 自動車分解整備事業(指定自動車整備事業を除く。)等の事業場における排出ガス測定器の
使用について ……………………………………………………………………………………… 90
(7) 「動力式トルク制御レンチの性能基準」及び「動力式トルク制御レンチの型式性能試験に
関する規定」について……………………………………………………………………………… 92
(8) 自動車整備士技能検定等にかかる適正な実務経験の証明について ………………………… 94
(9) 大型自動車等に関する不正改造(二次架装)の防止について ………………………………… 97
(10)大型自動車のホイール・ボルト折損による車輪の脱落事故防止について…………………… 98
(11)ターボチャージャーへの異物の混入防止について …………………………………………… 99
3.その他
(1) 認証の作業場の変遷 ……………………………………………………………………………… 100
(2) 認証の分類文字の変遷 …………………………………………………………………………… 104
(3) エンジンオイルフィルタ/エンジンオイル交換時の注意点 ………………………………… 105
Ⅱ 自動車検査関係
1. 事務関係
(1) 自動車検査証記載事項の変更に係る事務手続きの改善について …………………………… 107
(2) 自動車検査証備考欄の記載要領 ………………………………………………………………… 116
(3) 重量税等減免対象車の確認手順 ………………………………………………………………… 126
(4) 放置違反金滞納車に対する車検拒否制度について …………………………………………… 130
2. 検査関係
(1) 自動車の用途等の区分について ………………………………………………………………… 136
(2) 放送宣伝用自動車の構造要件について ………………………………………………………… 145
(3) キャンピング自動車の構造要件について ……………………………………………………… 149
(4) 車いす移動車の構造要件について ……………………………………………………………… 164
(5) 車両運搬車の構造要件について ………………………………………………………………… 169
(6) 構造等変更検査について ………………………………………………………………………… 175
(7) 自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時における取扱いについて(依命通達) …… 177

II
(8) 「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時における取扱いについて(依命通達)」の
細部取扱いについて ……………………………………………………………………………… 180
(9) 自動車NOx・PM法について…………………………………………………………………… 185
(10) 不正改造ダンプカーの排除について…………………………………………………………… 196
(11) 大型貨物自動車等の大型後部反射器、突入防止装置及び前部潜り込み防止装置について 201
(12) 側方灯及び側方反射器の取り付け位置について……………………………………………… 206
(13) 乗用車等の運転者の視界基準の概要…………………………………………………………… 208
(14) 前面ガラス等への装飾板の装着禁止について………………………………………………… 212
(15) 自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識等の貼付位置等…………… 213
(16) 速度計試験機の判定値について………………………………………………………………… 214
(17) ディーゼル黒煙検査のお知らせ………………………………………………………………… 215
(18) オパシメータを使用した粒子状物質(PM)の検査について………………………………… 217
(19) マフラー騒音規制適用車に係る消音器の基準適合性の確認等の取扱いについて………… 221
(20) 平成24年7月付近で施行された細目告示(抜粋)……………………………………………… 229
(21) 不適切な補修等について………………………………………………………………………… 231
(22) 受検者の皆様へ…………………………………………………………………………………… 232
(23) 自動車審査高度化施設の概要について………………………………………………………… 236
(24) タイヤ許容限度表………………………………………………………………………………… 240
(25) ハイブリッド車等の整備モードについて……………………………………………………… 246
(26) 保安基準適用時期等一覧表……………………………………………………………………… 252
Ⅲ 軽自動車検査関係
(1) 民間患者等輸送への軽自動車の導入についての一部改正について ………………………… 271
(2) 患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の許可等の取扱い
について……………………………………………………………………………………………… 271
(3) 軽自動車の改造について ………………………………………………………………………… 275
(4) 受検に関する注意事項について ………………………………………………………………… 276
(5) 不適切な補修等について ………………………………………………………………………… 279
【全国共通教材編】1. 法令等
(1) 追突事故時の被害軽減等のための道路運送車両の保安基準等の一部改正について
(平成24年7月26日) ……………………………………………………………………………… 281
(2) 自動車の低速走行時における側方の視認性向上等のための道路運送車両の保安基準等の
一部改正について(平成24年11月16日) ………………………………………………………… 286
(3) トレーラ・ハウスを一時的に運行できるようにするための制度改正等を行いました!!
(平成24年12月27日) ……………………………………………………………………………… 291
(4) バスに対する衝突被害軽減ブレーキの義務付け、二輪車騒音規制の協定規則の導入による
規制強化等に伴う道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について
(平成25年1月25日) ……………………………………………………………………………… 293

III
2. 通達等
(1) エンジンオイルの劣化による車両火災防止に向けた対策について
(平成24年7月13日 国自整第65号)……………………………………………………………… 300
(2) 「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定め
る告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改正について
(平成24年7月24日 国自技第66号の2)…………………………………………………………… 308
(3) チャイルドシートの肩ベルトによる子供の負傷を防止するための注意喚起について(協力
依頼)(平成24年8月31日 国自審第851号)……………………………………………………… 312
(4) 「非認証車に対する排出ガス試験等の取扱いについて」(平成3年6月28日付地技第168号)の
一部改正について(平成24年10月22日 国自環第144号の4)………………………………… 313
(5) 「道路運送車両法施行規則第36条第5項、第6項及び第7項の書面について」の一部改正について
(平成24年10月22日 国自環第142号の3)……………………………………………………… 318
(6) 「改造自動車に係る新規検査の際に提出する書面について」等の一部改正について
(平成24年10月22日 国自環第143号の3)………………………………………………………… 320
(7) 「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を
定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改正
について(平成24年11月15日 国自技第154号の2)……………………………………………… 331
(8) DPF(黒煙除去フィルタ)等の後処理装置付き車両の正しい使用方法について(周知依頼)
(平成24年12月26日 国自環第186号の2、国自審第1399号の2、国自整第174号の2) ………… 335
(9) 「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を
定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改
正について(平成25年1月25日 国自技第209号の2)…………………………………………… 339
(10) 受検代行業者及び自動車整備事業者の継続検査に係る広告等の適正化について
(平成25年3月25日 国自整第220号の2) ……………………………………………………… 343
3 その他
(1) 呼気吹込み式アルコール・インターロック装置の技術指針を策定しました。
(平成24年4月4日) ……………………………………………………………………………… 346
(2) 「自動車整備技術の高度化検討会」のとりまとめについて~汎用型スキャンツールの標準仕様等
がまとまり、新技術に対応した整備環境が整います~(平成24年7月3日) ……………… 361
(3) 軽自動車ユーザーの方々に定期点検整備を促す案内ハガキを初めて送付します。
(自動車点検整備推進運動の一環として、自動車を安全に使用いただく上で、軽自動車
ユーザーの方々にハガキを送付します。)(平成24年10月10日) ……………………………… 366
(4) 幼児専用車(園児バス)の車両安全対策をとりまとめたガイドラインが本日決定されました!!
(平成25年3月26日) ……………………………………………………………………………… 367
(5) 乗用車のアームレスト等の可動部にお子様が指等を挟み込まないよう注意しましょう
(平成25年3月28日) ……………………………………………………………………………… 386
(6) 我が国の自動車安全・環境基準の国際調和を積極的に進めていきます~国連欧州経済委員会
規則(UN/ECE規則)の採用に向けた行程表について~…………………………………… 387

IV
4.参考資料
(1) 国連の車両等の型式認定相互承認協定(1958年協定)の概要 …………………………… 389
(2) 国連の車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目 ……………………… 390
【資料編】Ⅰ 自動車検査関係
1.受検案内
(1) 自動車検査手引き ………………………………………………………………………………… 391
(2) 自動車の継続検査等の申請書の押印について ………………………………………………… 394
(3) 自動車検査証の有効期間の取扱いについて …………………………………………………… 396
(4) 管内運輸支局・事務所等連絡先及び付近案内図………………………………………………… 397
2.事務関係
(1) 車台番号等の打刻部分の修理について ………………………………………………………… 403
(2) 車台番号等の打刻部分の修理許可について …………………………………………………… 405
3.検査関係
(1) 検査機器による検査基準(抜粋) ………………………………………………………………… 406
Ⅱ 軽自動車検査関係
1.受検案内
(1) 軽自動車検査協会大阪主管事務所管内検査場の案内について ……………………………… 409
2.事務関係
(1) 車台番号打刻部分の修理について ……………………………………………………………… 414
(2) 検査対象軽自動車の自動車重量税額について ………………………………………………… 416
(3) 申請書類(OCRシート)について新規検査申請 ……………………………………………… 418
(4) 自動車検査証記入(構造等変更検査)申請 ……………………………………………………… 424
(5) 予備検査申請 ……………………………………………………………………………………… 424
(6) 自動車検査証記入申請 …………………………………………………………………………… 427
(7) 解体届出(自動車重量税還付申請) ……………………………………………………………… 429
(8) 一時使用中止(自動車検査証返納証明書交付)申請 …………………………………………… 432
(9) 各種申請依頼書 …………………………………………………………………………………… 434
Ⅲ その他
(1) 相談窓口について ………………………………………………………………………………… 439
(2) 自動車リサイクル法関係自治体お問合せ一覧(近畿管内抜粋) ……………………………… 441
(3) 自動車流入・運行規制関係相談窓口……………………………………………………………… 441
(4) 希望番号申込サービス …………………………………………………………………………… 442

【地 域 教 材 編】

Ⅰ.整 備 事 業 関 係

(1)
1.法令等 (1)道路運送車両法(抜粋)
(自動車分解整備事業の種類)
第77条 自動車分解整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の分解整備を行
う事業をいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 普通自動車分解整備事業(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車
分解整備事業)
(2) 小型自動車分解整備事業(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車分解整備事業)

(2)
(3) 軽自動車分解整備事業(検査対象軽自動車を対象とする自動車分解整備事業)
(認証)
第78条 自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事
業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
2 自動車分解整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行う
ことができる。
3 自動車分解整備事業の認証には、条件を附し、又はこれを変更することができる。
4 前項の条件は、自動車分解整備事業の認証を受けた者(以下「自動車分解整備事業者」という。)が行
う自動車の分解整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、且つ、当該自動車分解
整備事業者に不当な業務を課することとならないものでなければならない。
(申請)
第79条 自動車分解整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸
局長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その役員の氏名
(2) 自動車分解整備事業の種類
(3) 事業場の所在地
(4) 前条第2項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあっては、対象とする自
動車の種類その他業務の範囲 2 前項の申請書には、その申請が次条第1項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面
を添付しなければならない。
3 地方運輸局長は、自動車分解整備事業の認証を申請した者に対し、前2項に規定するもののほか、そ
の者の登記事項証明書とその他必要な書面の提出を求めることができる。
(認証基準)
第80条 地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車分解整備事
業の認証をしなければならない。
(1) 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
(2) 申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
イ 1年以上の懲役又は禁錮こ
の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ
た日から2年を経過しない者
ロ 第93条の規定による自動車分解整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過
しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日
及び場所に関する第103条第2項の公示の日前60日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるか
を問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であった者
で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代
理人がイ又はロのいずれかに該当するもの。
ニ 法人であって、その役員のうちイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの
2 前項第1号の規定による基準は、自動車分解整備事業の種類別に自動車の分解整備に必要な最低限度
のものでなければならない。
(変更届等)
第81条 自動車分解整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日か
ら30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所

(3)
(2) 法人にあっては、その役員の氏名
(3) 事業場の所在地
(4) 事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの
2 自動車分解整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を地方運輸局
長に届け出なければならない。
(標識)
第89条 自動車分解整備事業者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の
標識を掲げなければならない。
2 自動車分解整備事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。
(自動車分解整備事業者の義務)
第90条 自動車分解整備事業者は、分解整備を行う場合においては、当該自動車の分解整備に係る部分が
保安基準に適合するようにしなければならない。
(分解整備記録簿)
第91条 自動車分解整備事業者は、分解整備記録簿を備え、分解整備をしたときは、これに次に掲げる事
項を記載しなければならない。
(1) 登録自動車にあっては自動車登録番号、第60条第1項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあっ
ては車両番号、その他の自動車にあっては車台番号
(2) 分解整備の概要
(3) 分解整備を完了した年月日
(4) 依頼者の氏名又は名称及び住所
(5) その他国土交通省令で定める事項
2 自動車分解整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した分解整備記録簿の
写しを交付しなければならない。
3 分解整備記録簿は、その記載の日から2年間保存しなければならない。
(設備の維持等)
第91条の2 自動車分解整備事業者は、当該事業場に関し、第80条第1項第1号の規定による基準に適合
するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。
(遵守事項)
第91条の3 自動車分解整備事業者は、第89条から前条までに定めるもののほか、自動車の整備について
の技術の向上、適切な点検及び整備の励行の促進その他自動車分解整備事業の業務の適正な運営を確保
するために国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
(改善命令)
第92条 地方運輸局長は、自動車分解整備事業者の事業場の設備及び従業員が第80条第1項第1号の規定
による基準に適合せず、又はその業務の運営に関し前条の国土交通省令で定める事項を遵守していない
と認めるときは、当該自動車分解整備事業者に対し、その設備及び従業員を基準に適合させるため、ま
たはその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(事業の停止等)
第93条 地方運輸局長は、自動車分解整備事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内に
おいて期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。
(1) この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) 第78条第2項の規定による業務の範囲の限定又は同条第3項の規定により認証に付した条件に違
反したとき。
(3) 第80条第1項第2号イ、ハ又はニに掲げる者となったとき。

(4)
(2)道路運送車両法施行規則(抜粋)
第3条(分解整備の定義)法第49条第2項の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
(2) 動力伝達装置のクラッチ、(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)トランスミッション、プロペ
ラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
(3) 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリヤ・アクスルシ
ャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
(4) かじ取装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取ホークを取り外して行う自動車の整
備又は改造
(5) 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ、チャンバ、ブレ
ーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャ
リパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シュを
取り外して行う自動車の整備又は改造
(6) 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う
自動車の整備又は改造
(7) けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を
取り外して行う自動車の整備又は改造
(認証基準)
第57条 法第80条第1項第1号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。
(1) 事業場は、常時分解整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、且つ、
別表第4に掲げる規模の屋内作業場及び車両置場を有するものであること。
(2) 屋内作業場のうち、車両整備作業場及び点検作業場の天井の高さは、対象とする自動車について分
解整備又は点検を実施するのに十分であること。
(3) 屋内作業場の床面は、平滑に舗装されていること。
(4) 事業場は、別表第5に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交
通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。
(5) 事業場には、2人以上の分解整備に従事する従業員を有すること。
(6) 事業場において分解整備に従事する従業員のうち、少なくとも1人の自動車整備士技能検定規則の
規定による1級又は2級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行
う場合にあっては、2級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。第62条の2の2第1項第5号におい
て同じ。)に合格した者を有し、かつ、1級、2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者
の数が、従業員の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)
以上であること。
(変更届出事項)
第58条 法第81条第1項第4号に規定する事業場の設備は、屋内作業場の面積又は間口若しくは奥行の長
さとする。

(5)
(標識の様式)
第62条 法第89条の様式は、第20号様式による。
第20号様式(自動車分解整備事業者の標識)(第62条関係)
備考
(1) 自動車分解整備事業者の標識は、図示の例により、自動車分解整備事業者の標章、認証を行った
地方運輸局長名、自動車分解整備事業の種類及び対象とする自動車の種類をそれぞれ表示すること。
この場合において、対象とする自動車の種類は、次の区分により表示すること。
普通自動車(大型) (普通自動車のうち車両総重量が8トン以上のもの、最大積載量が5トン以
上のもの又は乗車定員が30人以上のものを対象とする場合に限る。)
普通自動車(中型) (普通自動車のうち最大積載量が2トンを超えるもの又は乗車定員が11人
以上のものであって、普通自動車(大型)以外のものを対象とする場合に
限る。)
普通自動車(小型) (普通自動車のうち貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、広告宣伝
用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するものであって、普通自
動車(大型)及び普通自動車(中型)以外のものを対象とする場合に限る。)
普通自動車(乗用) (普通自動車のうち普通自動車(大型)、普通自動車(中型)及び普通自動車
(小型)以外のものを対象とする場合に限る。)
小型四輪自動車
小型三輪自動車
小型二輪自動車
軽 自 動 車
大型特殊自動車
(2) 自動車分解整備事業の種類が二種類以上にわたるものにあっては、「 自動車分解整備事業」の
ように表示すること。この場合において、「普通」及び「小型」の文字は、図示の寸法にかかわらず、
縦25ミリメートルとする。
(3) 対象とする装置を限定する場合は、図示の例により、その旨を表示すること。
(4) 対象とする自動車の種類のうち、対象とする装置を限定しないものが4以上のときは、左右二列
に配置すること。
(5) 寸法の単位は、「ミリメートル」とする。
普通 小型

(6)
(6) 標識は、金属製又は合成樹脂製とすること。
(7) 標識の塗色は、橙黄色地に黒文字とし、標章は赤色とすること。
(分解整備記録簿の記載事項)
第62条の2 法第91条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 分解整備時の総走行距離
(2) 第62条の2の2第1項第5号に規定する整備主任者の氏名
(3) 自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号
(自動車分解整備事業者の遵守事項)
第62条の2の2 法第91条の3の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る料金を当該事業
場において依頼者に見やすいように掲示すること。
(2) 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業の依頼者に対し、必要
となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の概算見積もりを記載し
た書面を交付すること。
(3) 依頼者に対し、行っていない点検若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されない点検若しくは整
備を不当に行い、その料金を請求しないこと。
(4) 道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の改造を行わないこと。
(5) 事業場ごとに、当該事業場において分解整備に従事する従業員であって1級又は2級の自動車整備
士の技能検定に合格した者のうち少なくとも1人に分解整備及び法第91条の分解整備記録簿の記載
に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む。)。ただし、当該事項を統括管理
する者(以下「整備主任者」という。)は、他の事業場の整備主任者になることができない。
(6) 運輸監理部長又は運輸支局長から整備主任者に対し研修を行う旨の通知を受けたときは、整備主任
者に当該研修を受けさせること。
(7) エアコンディショナーが搭載されている自動車の点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、み
だりに当該エアコンディショナーに充てんされているフロン類(特定製品に係るフロン類の回収及び
破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に規定するフロン類をいう。)
を大気中に放出しないこと。
(8) 他人に対して法若しくは法に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反
行為」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助
けないこと。
2 自動車分解整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車分解整備事業の開始の日又
は次に掲げる事項に変更のあった日から15日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければな
らない。
(1) 届出者の氏名又は名称及び住所
(2) 整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地
(3) 整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務の開始の日
3 前項の届出書には、同項第3号の者が1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格したことを証す
る書面を添付しなければならない。

(7)
(3) 自動車点検基準
10
10
11
14
15
18
20

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)
(4) 自動車の点検及び整備に関する手引
平成19年 3 月14日
国土交通省告示第317号

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)
2.通達等
(1)道路運送車両法施行規則第 3条「分解整備の定義」の解釈について
自整第151号の2
平成8. 8. 20
平成7年8月に最終決着した自動車及び同部品分野に関する日米包括経済協議において分解整備の定義を
全般的に見直すこととされたことから、自動車技術、整備作業の実態等が変化したこと等を踏まえ、道路運
送車両法施行規則第 3 条の分解整備の定義を安全確保上及び公害防止上支障のない範囲で見直し、平成8年
8月 20 日以降は、スタビライザ、トルクロッド、トーションバー・スプリング、クラッチ(二輪の小型自
動車に限る)が分解整備の定義から除外されることとなったところであります。
今般、同協議の決着事項を踏まえ、この分解整備の定義の透明性の向上を図るため、標記について下記の
通りとすることとしましたので、これらについて了知するとともに、関係者に周知徹底を図り、今後はこれ
により遺漏なきよう取り扱われるようお願いします。
記
1.分解整備に該当する作業の範囲
自動車の構造及び装置は自動車によって異なることから、以下では、分解整備に該当する主要な作業を
例示します。
なお、ここでいう「取り外し」には、作業の過程における、自動車を保安基準に適合しない状態に至ら
しめる行為も含まれます。
また、「整備又は改造」とは、自動車について何らかの変化を施す作業全般をいいます。特に、整備とは、
給油脂、調整、部品交換、修理、その他の自動車の構造又は装置の機能を正常に保つ又は正常に復するた
めの作業(行為)をいいます。
(1)原動機
原動機について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① 原動機関係
シリンダブロック(ただし、二輪にあってはクランクケース。また、シリンダブロックの取り外し
を伴うフライホイールを含む。)
(2)動力伝達装置
動力伝達装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① クラッチ関係(二輪の小型自動車は除く。)
クラッチのレリーズフォーク、レリーズベアリング、ダイヤフラムスプリング、クラッチディスク、
クラッチカバー、プレッシャープレート及びプレッシャースプリング
② ギヤ関係
マニュアルトランスミッション、オートマチックトランスミッション、トルクコンバータ(CVT
を含む。)、トランスファ、トランスアクスル、デファレンシャル、差動制御装置、ファイナルギヤ

(73)
③ 推進軸・駆動軸関係
プロペラシャフト、ユニバーサルジョイント、センタベアリング、ドライブシャフト、等速ジョイ
ント
(3)走行装置(二輪の小型自動車を除く。)
走行装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① 懸架・回転関係
フロントアクスル、フロントナックルスピンドル、フロントホイールベアリング及びフロントキン
グピン並びに前輪独立懸架装置のサスペンションアーム、ナックルスピンドル、ホイールベアリング
及びキングピン並びにリヤアクスルシャフト
(4)かじ取り装置
かじ取り装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① ステアリング操作機構関係
かじ取りフォーク
② ステアリングギヤ機構関係
ギヤボックス
③ リンク機構関係
ドラッグリンク、ピットマンアーム、タイロッド、タイロッドエンド、リレーロッド、アイドラアー
ム、ナックルアーム、ベルクランク、セクタアーム、リンクロッド、フレーブレバー
(5)制動装置
制動装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① ドラムブレーキ関係
ブレーキドラム(二輪の小型自動車のブレーキドラムを除く。)、ブレーキシュー、ホイールシリンダ、
バックプレート、シューアジャスタ、ブレーキスプリング
② ディスクブレーキ関係
ブレーキキャリパ(ブレーキキャリパの取り外しを伴うブレーキパッドを含む。)、シリンダ、ピス
トン、ブレーキディスク
③ ホース、パイプ、バルブ関係
ホース、パイプ、リレーバルブ、チェックバルブ、ダブルチェックバルブ、プロポーショニングバルブ、
セーフティバルブ、セーフティシリンダ、メターリングバルブ、レギュレータバルブ、ABSアクチュ
エータ、ABSモジュレータ、ASRモジュレータ
④ 分配・倍力関係
マスタシリンダ、ブレーキチャンバ、倍力装置
(6)緩衝装置
緩衝装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。

(74)
① 緩衝関係
リーフスプリング、エアスプリング
(7)連結装置
連結装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① 連結装置関係
キングピン、カプラ、ルネットアイ、ピントルフック
(8) 付随作業が分解整備に該当するもの
① ストラットを取り外して自動車を整備又は改造する際にブレーキホースを取り外して自動車を整備
又は改造するもの。
② パワーステアリング装置を取り外して自動車を整備又は改造する際にギヤボックスを取り外して自
動車を整備又は改造するもの。
2.分解整備の定義に関する要望・苦情等処理窓口
この通達に示した作業は一般的な例であるため、全ての整備作業を網羅したものではありません。した
がって、この他不明な点については分解整備の定義に関する要望・苦情等処理窓口において対応すること
とします。
(窓口の連絡先)
国土交通省自動車交通局技術安全部整備課整備係
住 所:〒 100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
電話番号:03-5253-8111(内線 42415)
FAX番号:03-5253-1639

(75)
(2)分解整備の定義に関する照会について
自整第252号
平成7.10.25
標記について、下記1のとおり照会があり、下記2のとおり申立者に対し回答したので、通知します。
記
1.照会内容
(1)カムシャフトは形状によって、分解整備に該当するか。
(2)ターボチャージャーの追加又は交換は、分解整備に該当するか。
2.回答内容
(1)形状に係わらず、原動機の脱着を伴わない単なるカムシャフトの交換は、分解整備に該当しない。し
かしながら、交換の際、原動機の脱着を伴う場合は分解整備に該当する。
(2)原動機の脱着を伴わない単なるダーボチャージャーの追加又は交換は、分解整備に該当しない。しか
しながら、追加又は交換の際、原動機の脱着を伴う場合は分解整備に該当する。

(76)
(3)分解整備の定義に関する照会について
自 整 第 2 4 号
平成8.1.29
標記について、下記1のとおり照会があり、下記2のとおり申立者に対し回答したので、通知します。
記
1.照会内容
(1)重要保安部品4品目(ショック・アブソーバ(これに付随するコイルばねを含む。)、ストラット(こ
れに付随するコイルばねを含む。)、パワー・ステアリング及びトレーラ・ヒッチ)が分解整備の定義か
ら削除されたのはいつからか。
(2)重要保安部品4品目(ショック・アブソーバ(これに付随するコイルばねを含む。)、ストラット(こ
れに付随するコイルばねを含む。)、パワー・ステアリング及びトレーラ・ヒッチ)を取り外す際に、他
の分解整備の定義に該当する部位を取り外して行う作業は、分解整備に該当するか。
(3)ディスク・ブレーキのキャリパを取り外さずに、ブレーキパッドを交換する作業は、分解整備に該当
するか。
(4)リア・ブレーキ・ドラムを取り外し、再度組付けるという作業はそれだけで分解整備に該当するか。
2.回答内容
(1)平成7年 10 月 20 日
(2)該当する。
(3)該当しない。しかしながら、キャリパの一部を取り外して行う場合は、分解整備に該当する。
(4)該当する。

(77)
(4)分解整備の定義に関する照会について
自整第172号
平成9. 10. 6
標記について、平成8年1月から平成9年7月までの主な照会内容及び回答内容を別紙のとおりとりまとめ
ましたので通知します。
別紙
分解整備の定義に関す主な照会内容等一覧
照 会 事 項 回 答 内 容
1.シリンダヘッドの交換は分解整備に該当するか
2.タイミングベルトの交換は分解整備に該当するか
3.ストラットの交換は分解整備に該当するか
4.ギヤボックスの交換は分解整備に該当するか
5.パワーステアリングの交換は分解整備に該当するか
6.ストラットの交換の際、タイロットエンドを取り外して行う場合は分解整備に該当するか
7.ドラムブレーキを取り外して、再度組み付ける作業は分解整備に該当するか
8.ショックアブソーバを交換する際に、ブレーキキャリパを外さなければならないものは、
分解整備に該当するか
9.ブレーキキャリパの一方を持ち上げて、ブレーキパッドを交換することは分解整備に該当
するか
10.ブレーキキャリパを取り外さずに、ブレーキパッドを交換した場合は分解整備に該当するか
1.該当しない
2.該当しない
3.該当しない
4.該当する
5.該当しない
6.該当する
7.該当する
8.該当する
9.該当する
10.該当しない

(78)
(別 添)
(5)自動車分解整備事業関係業務処理要領
昭和59年7月1日 近畿運輸局長
改正 昭和62年9月1日 近運達甲第10号
〃 平成2年2月5日 近運達甲第3号
〃 平成7年5月8日 近運達甲第15号
〃 平成9年4月17日 近運達甲第43号
〃 平成10年3月3日 近運達甲第3号
〃 平成10年12月17日 近運達甲第34号
〃 平成14年12月25日 近運達甲第47号
〃 平成18年5月24日 近運達甲第2号
〃 平成19年3月28日 近運達甲第45号
〃 平成20年5月15日 近運達甲第2号
(規定する範囲)
第1条 自動車分解整備事業の認証(以下「認証」という。)関係の事務処理等については、道路運送車
両法(以下「法」という。)、道路運送車両法施行規則(以下「規則」という。)、自動車分解整備事業
の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について(依命通達)(平成14年7
月1日付け、国自整第63号)及び関係通達によるほか、この要領によるものとする。
(認証の分類区分)
第2条 認証は、対象とする自動車の種類により、次の16分類に区分して取り扱うこと。
分類 文字
自動車分解整備事 業 の 種 類 対 象 と す る 自 動 車 の 種 類
イ 普通・小型 大型 特殊
普通(大型)
普通(中型)
普通(小型)
普通(乗用)
小型四輪
小型 三輪
小型 二輪
軽
ロ 普通・小型 大型 特殊
普通
(中型)普通
(小型)普通
(乗用)小型四輪
小型 三輪
小型 二輪
軽
ハ 普通・小型 普通
(小型)普通
(乗用)小型四輪
小型 三輪
小型 二輪
軽
ワ 普通・小型 普通
(乗用)小型四輪
小型 三輪
小型 二輪
軽
ニ 普通 大型 特殊
普通(大型)
普通(中型)
普通(小型)
普通(乗用)
小型四輪
ホ 普通 大型 特殊
普通
(中型)普通
(小型)普通
(乗用)小型四輪
ヘ 普通 普通
(小型)普通
(乗用)小型四輪
カ 普通 普通
(乗用)小型四輪
ト 小型 小型四輪
小型 三輪
小型 二輪
軽
チ 小型 小型 二輪
軽
ヨ 小型 小型 二輪
リ 普通・軽 大型 特殊
普通(大型)
普通(中型)
普通(小型)
普通(乗用)
小型四輪
軽
ヌ 普通・軽 大型 特殊
普通
(中型)普通
(小型)普通
(乗用)小型四輪
軽
ル 普通・軽 普通
(小型)普通
(乗用)小型四輪
軽
タ 普通・軽 普通
(乗用)小型四輪
軽
オ 軽 軽

(79)
2 申請しようとする対象自動車の種類が前項のいずれにも該当しない場合は、直近にある区分に従う
こととし、分類文字を〇で囲むこと。
3 原動機、動力伝達装置、制動装置等の特定の装置を専門的に整備する自動車分解整備事業の認証(以
下「特定部品専門認証」という。)を行う場合においては、第1項の16分類に区分した分類文字は使用
しないこと。
(認証の申請)
第3条 法第79条第1項の規定による認証申請書は、第1号様式によること。
2 前項の申請書の記載項目及び法第79条第2項及び第3項に基づく書面は次のとおりとする。(法第79
条第1項、第2項及び第3項)
(1) 記載項目
① 申請者の氏名又は名称及び住所
② 申請者が法人の場合にあっては、役員の氏名及び役職名
③ 受けようとする自動車分解整備事業の種類
④ 事業場の名称及び所在地
⑤ 対象とする自動車の種類及び装置の種類
⑥ その他業務の範囲の限定
(2) 添付書面
① 申請者が法人の場合にあっては、商業登記簿謄本等申請者及び役員を特定できる書面
② 申請者が個人の場合にあっては、住民票等申請者を特定できる書面
③ 土地又は建物の登記簿謄本若しくは、建築物の確認済証(写し)等事業場の所在地を証する書面
④ 法第80条第1項第2号各号に該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等の書面(1号様式)
⑤ 法第80条第1項第1号の国土交通省令で定める設備及び従業員の基準に適合するものであるこ
とを証する次の事項を記載した書面
ア 設備の基準に係る事項(施行規則第57条第1項第1号、第2号、第3号及び第4号)
a.平面図
平面図に記載する事項は次のとおりとする。
・ 車両整備作業場の間口、奥行、面積、天井高さ、床面の状況
・ 点検作業場の間口、奥行、面積、天井高さ、床面の状況
・ 部品整備作業場の面積
・ 車両置場の間口、奥行
・ 作業場等平面図(作業場等名(優良自動車整備事業者の認定を受けている者であって、
自動車分解整備事業の屋内作業場と兼用している場合は、各々の事業場名)、レイアウト、
寸法、縮尺、方位等を記載したもの)
b.事業場機器一覧表

(80)
事業場機器一覧表に記載する事項は次のとおりとする。
・ 作業機械の種類毎の名称、能力、数
・ 作業計器の種類毎の名称、能力、数
・ 点検計器及び点検装置の種類毎の名称、形式(一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器
に限る。)、能力、数
・工具の種類毎の名称、能力、数
c.一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に係る国土交通大臣が定める技術上の基準に適合し
ていることを証する書面
上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検査用機械器具の審査基
準について」(平成7年6月14日付け自整第121号)により公正に試験を実施し、その結果
を記載した自動車検査用機械器具基準適合性試験成績書、自動車検査用機械器具校正結果
証明書等の書面であること。
イ 従業員に係る事項(施行規則第57条第1項第5号及び第6号)
技能検定規則の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格している者の
種類別の数及び分解整備に従事する従業員の数(1号様式)
(整備事業の追加等)
第4条 自動車分解整備事業者が、同一の事業場において、新たに法第77条の規定による他の種類の認
証を受けようとするときは、前条を準用する。
2 法第77条各号の規定による自動車分解整備事業の種類ごとに、対象とする自動車の種類又は装置そ
の他限定を受けた業務の範囲を拡大しようとするときは、前条を準用する。
3 前2項による申請を行う場合にあっては、第3条に係わらず別表の添付書面を提出すること。
(認証の変更届)
第5条 法第81条第1項、第82条、第83条の規定による変更の届出及び事業の一部の廃止、縮小(法第
77条の規定による自動車分解整備事業の認証の種類の一部の廃止及び第78条第2項の規定による対象
とする自動車の種類又は装置その他限定を受けた業務の範囲の縮小をいう。)の届出は第1号様式によ
るものとし、法第81条第2項の規定による事業の廃止の届出は第3号様式によることとする。
2 前項の届出書の記載項目は、次のとおりとし、別表に掲げる書類を添付すること。
① 届出者の氏名又は名称及び住所
② 事業場の名称及び所在地
③ 届出に係る事項
④ 認証番号
(整備主任者の選任届等)
第6条 規則第62条の2の2第2項に基づく整備主任者の選任等に係る届出は、第1号様式によること。

(81)
ただし、解任に係る届出の場合は第3号様式とする。
2 前記の記載項目は次の通りとし、別表に掲げる書類を添付するものとする。
① 届出者の氏名又は名称及び住所
② 統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地
③ 認証番号
④ 整備主任者の氏名及び生年月日
⑤ 統括管理業務の開始日
⑥ 整備主任者を解任する場合は、解任した整備主任者の氏名及び解任年月日
第7条 (削除)
第8条 (削除)
(申請等の提出)
第9条 申請書及び届出書を事業場の所在地を管轄する運輸支局長又は運輸監理部長(以下「運輸支局
長等」という)に提出すること。
(申請等の審査)
第10条 申請書及び届出書の審査は、提出された書面の記載内容、法第80条第1項の認証基準及び規則
第62条の2の2第5項に規定する整備主任者の資格等の確認により行うこと。
(申請書等の進達)
第11条 運輸支局長等は、申請書を受け付けたときは、前条の審査を行い、必要と認められるときは意
見を付して、次の各号に掲げる一覧表と申請書等(添付書面を含む。)を添えて運輸局長に進達すること。
(1) 自動車分解整備事業認証申請一覧表(第5号様式)
(2) 自動車分解整備事業変更届一覧表(第6号様式)
(3) 自動車分解整備事業廃止届一覧表(第7号様式)
(4) 整備主任者選任届一覧表(第5号様式)
(5) 整備主任者変更届一覧表(第6号様式)
(6) 整備主任者解任届一覧表(第7号様式)
(7) 認証書再交付申請一覧表(第5号様式)
(認証書の交付等)
第12条 運輸局長は自動車分解整備事業の認証をしたときは認証番号を定め、認証書(第8号様式)を
運輸支局長等を経由して申請者に交付する。
2 認証書の再交付は申請書(第4号様式)の提出があったときに行うこと。
3 第1項の認証番号は次の各号を順列させることにより行う。
(1) 近運整認
(2) 府県名頭文字
(3) 府県別一連番号

(82)
4 運輸局長は認証したとき及び変更届等の届出を受理したときは、第11条により提出された一覧表並
びに申請書等の添付書面を添え、運輸支局長等に通知する。
(監査等)
第13条 自動車分解整備事業者の監査は別に定める「自動車整備事業監査要領」により基づき実施する
こと。
2 自動車分解整備事業者には、法をはじめ、建築基準法、農地法及び公害防止法等関係法令について
も遵守するよう指導すること。
(附則)
1.この要領は、昭和59年7月1日から実施する。
2.この要領の制定にともない、昭和53年7月14付け大陸整第583号「自動車分解整備事業の認証関係業
務の取扱いについて」(以下「旧要領」という)は廃止する。
3.この要領の実施の際、旧要領により認証を受けた者は、この要領により認証を受けた者とみなす。
4.旧要領第5条第2項により定められた自動車分解整備事業の認証番号はこの要領の規定にかかわら
ず、なお従前の例とする。
5.改正前の要領による様式の申請書等用紙は、この要領のそれぞれの様式にかかわらず当分の間、こ
れを使用することができる。
附 則
1.この要領は、平成7年7月1日から実施する
附 則
1.この要領は、平成9年4月17日から実施する
附 則
1.この要領は、平成10年3月3日から実施する
附 則
1.この要領は、平成10年12月17日から実施する
附 則
1.この要領は、平成15年2月1日から実施する
附 則
1.この要領は、平成18年5月19日から実施する
附 則
1.この要領は、平成19年4月1日から実施する
附 則
1.この要領は、平成23年4月1日から実施する

(83)
別表 自動車分解整備事業に関する手続き一覧表
申請等の原因
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18
必要な書類等
申請者(届出者)
事業者
事業者
事業者
事業者
事業者
事業者
事業者
事業者
事業者
相続人
新法人
新法人
譲受人
事業者
事業者
事業者
事業者
事業者
事業者
提出期間 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 15 15 15
新規申請書(第1号様式) ○ ○ ○
変更届(第1号様式) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
整備主任者選任届(第1号様式) ○○※1
○※1
○
整備主任者変更届(第1号様式) ○
廃止届(第3号様式) ○
整備主任者解任届け(第3号様式)○※1
○※1
○ ○
認証書再交付申請書(第4号様式) ○
自動車整備士合格証書等の写し ○○※1
○※1
○
事業場機器一覧表(第2号様式) ○ ○ ○
一酸化炭素及び炭化水素測定器に係る技術上の基準に適合していることを証する書面
○※2
○※3
○※3
事業場平面図 ○○※4
○※4
○ ○
申請者が個人の場合、住民票等申請者を特定できる書面
○ ○ ○ ○
申請者が法人の場合商業登記簿謄本
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
事業場の建築確認、事業場の不動産登記簿謄本等所在を証する書面
○○※5
○※5
○
届出者が義務者であることが判る書面 ○ ○ ○
その他必要と認められる書面 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
認証書の返付 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
※1 特定部品専門認証(二級自動車シャシ整備士)から全部認証への追加・変更等に限る。 ※2 一酸化炭素及び炭化水素測定器が必要な事業場に限る。
※4 作業場等レイアウトの変更がある場合に限る。
※5 事業場の所在地に変更がある時に限る。
添付書面
※3 新規認証時と変更がなければ不要。
追加申請等
対象の自動車等の追加
認証の種類追加・変更
新規認証
事業の廃止
認証の種類・対象自動車等の縮小
法人役員の氏名
作業場の間口・奥行・面積
廃止等 整備主任者
解任
事業の相続
事業を合併
変 更
事業の譲渡
新規選任
氏名等の変更
14
車両法第80条第1項第2号の確認印・証明印
事業者の住所
事業場の所在地
事業場の名称
(選任届け記載事項
)
申請書等の種類
事業者の氏名・名称
事業譲渡印
認証書の再交付
事業の分割

(84)

(85)

(86)
参考資料
備 考 備 考原
動
機
動力伝達
走
行
操
縦
制
動
緩
衝
連
結
原
動
機
動力伝達
走
行
操
縦
制
動
緩
衝
連
結
※プレス
1 能力 15トン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○シックネス・ゲージ
10.04~1.0㎜11枚組
○ ○ ○ ○ ○ ○
エア・コンプレッサー
1動力 2.2kW
空気圧 8.4㎏/㎝2
タンク容量 105ℓ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ダイヤル・ゲージ
1
ゲージストローク 10㎜指針1回転 5㎜1目盛 0.1㎜
○ ○ ○ ○ ○ ○
※チェーン・ブロック
1つり上げ能力 1トン
○ ○ ◎△トーイン・ゲージ
1 スタンド式 ○ ○ ○
※ジャッキ
1押し上げ能力 3トン
○ ○ ○ ○ ○ ○
キャンバ・キャスタ・ゲージ ◎△
1 マグネット式 ○ ○ ○
バイス 1 口金の巾 150㎜
○ ○ ○ ○ ○ ○
ターニング・ラジアス・ゲージ ◎△
1 0~45° ○ ○ ○
充電器 1直流出力10~50A
○ △タイヤ・ゲージ
2 0~600kPa ○
ノギス 3 最大測定値 200㎜
○ ○ ○ ○ ○ ○ ※亀裂点検装置
1(品名)
カラーチェック○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
トルク・レンチ
2 1000㎝・㎏ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※検車装置
1 2柱リフト ○ ○ ○ ○ ○ ○
サーキット・テスタ
1DC 1200VAC 1200V500kΩ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ×一酸化炭素測定器
1
型式認定番号JATA-CO・HC-1銘柄・型式UREX-5000
○製造番号12345
比重計 1 スポイト式 ○ ×炭化水素測定器
1
型式認定番号JATA-CO・HC-1銘柄・型式UREX-5000
○製造番号12345
コンプレッション・ゲージ
2G 25㎏/㎝2
D 70㎏/㎝2 ○ ※ホイール・プーラ
1 万能型 ○ ○
ハンディ・バキューム・ポンプ
1 0~760mmHg ○ ○ ○ ○
※ベアリング・レース・プーラ
1 万能型 ○ ○ ○
エンジン・タコ・テスタ
1 0~7500rpm ○ ○ ○グリース・ガン
1 容量 200cc ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
×タイミング・ライト
1 筒型 12V ○部品洗浄槽
1縦 800㎜横 550㎜深さ 250㎜
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ノズル・テスタ
1 500㎏/㎝2 ○
(註) ※ 二輪自動車に不要
◎ 二輪自動車及び小型三輪自動車に不要
× ガソリン、LPGを燃料とする原動機を搭載した自動車の点検を行わない事業場に不要
軽油を燃料とする原動機を搭載した自動車の点検を行わない事業場に不要
△ カタピラを有する大型特殊自動車に不要
数 量
事業場名 ○○オートサービス
(日本工業規格A列3番)
品質・形状・機能(数量が2以上の場合は、最大性能のものを記入)
第2号様式 <記入例>
装 置 の 種 類機械計器工具
数 量
装 置 の 種 類品質・形状・機能(数量が2以上の場合は、最大性能のものを記入)
事 業 場 機 器 一 覧 表
機械計器工具
品質・形状・機能欄にも必ず記入してください

(87)

(88)

(89)

(90)
(6)自動車分解整備事業(指定自動車整備事業を除く。) 等の事業場におけ
る排出ガス測定器の使用について
各 陸 運 局 長 殿
沖縄総合事務局長 自 整 第 8 4 号 昭和 55.6.17
改正 国 自 整 第 48 号 平成 13.3.30
〃 国 自 整 第 95 号 平成 20.11.26 自動車局整備部長
自動車の排出ガス対策の進展に伴い、これに対応した整備体制の充実を図るため、ガソリン及び液化石
油ガスを燃料とする原動機の点検整備を行う事業場には、一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器(以下「排
出ガス測定器」という。)を保有することとされたが、その使用方については、下記事項に十分留意して適
正に行われるよう、関係者を指導されたい。
記
1 自動車の排出ガス装置に係る的確な整備
自動車の排出ガス測定器は、自動車の排出ガス対策に係る部分の点検整備を行うために必要な整備用
機器であるから、当該部分の点検整備を行う際には、これを適正に使用して、的確に整備を行うこと。
2 排出ガス測定器の取り扱い
排出ガス測定器の取り扱いについては、機械器具製作者が示す取り扱い方法等に基づいて適正な取り
扱いをしなければならないが、特に次の点に留意すること。
(1) 測定開始前
ア 排出ガス測定器が暖機されていること。
イ 清浄な空気を吸引して指針がゼロ点を指すことを確認すること。
ウ 簡易な校正装置を有する排出ガス測定器は、指針が所定の目盛りを指すことを確認すること。
(2) 測定時
ア 排出ガス濃度に見合ったレンジを測定すること。
イ プローブは、60 センチメートル以上そう入すること。
ウ メーターの読みは、指示値が安定したときに行うこと。
エ 測定ガスの吸引は、測定に必要な時間以上に長く行わないこと。
オ 引き続いて測定するときは、プローブを抜き、指針がゼロ点を指すのをまって、次の測定を行う
こと。
(3) 測定後
測定後、清浄な空気を吸引して内部を充分清掃した後、電源を切ること。
(4) 点検整備

(91)
プローブ、フィルタ類、ドレーン排出部等の水分の付着、汚損又は損傷、流量計の作動等、特に空
気やガスのフロー系統の異常の有無に注意して日常点検を行い、プローブ、ドレーン排出部の清掃、
フィルタ交換等必要な整備を行うこと。
3 排出ガス測定器の校正
排出ガス測定器の機能及び精度を維持するため、次のとおり校正を行うものとする。
(1) ゼロ校正
1日1回測定前に次のことを行うこと。
ア 指針が機械的にゼロ点を指すことを確認すること。
イ 暖機運転後、清浄な空気又はゼロガスを用いて、機械器具製作者が示す方法により指針がゼロ点
を指すよう調整すること。
(2) スパン校正
ア 簡易な校正装置を有する排出ガス測定器は、これを作用させて指針が所定の目盛りを指すことを
1日1回測定前に確認すること。
イ 校正用ガスを用いて行うスパン校正は、少なくとも2ヵ月に1回(接触燃焼方式のものにあって
は1日1回)機械器具製作者が示す方法により行うものとし、使用頻度に応じて適宜その回数を増
すこと。
(3) 定期校正
ア 定期校正は、ゼロ点、上記(2)イのスパン校正点及び中間点の3点について行うものとし、ゼロ点
と中間点は各レンジごとに行うこと。
また簡易な校正装置について、指針位置が目盛板にマークされているものは、指針が当該マーク
を指すことを確認すること。
イ 定期校正は、営利を目的としない法人であり、かつ、当該校正を遂行するに適切であると地方運
輸局長が認める者によって、少なくとも2年に1回行うこと。
(4) 臨時校正
排出ガス測定器の修理後は定期校正を行うこと。
(5) 備 考
ア 炭化水素測定器の場合、標準ガスは安定したプロパンガスが通常使用されているので、その濃度
値を機器ごとに示されている係数でノルマルヘキサン値に換算した値を標準ガスの濃度値として使
用すること。
イ 簡易な校正装置を有する排出ガス測定器については、スパンガスによる校正直後において当該装
置を作用させ、指針が指す目盛りを記録しておき、これを基準値として使用すること。
ウ 定期校正における排出ガス測定器の精度は、自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める
技術上の基準(平成7年運輸省告示第 375 号)第 52 条及び第 60 条に定めるとおりとする。
エ 校正の結果、不適合となったときは必要な調整修理を行うこと。

(92)
(7)「動力式トルク制御レンチの性能基準」及び「動力式トルク制御レンチ
の型式性能試験に関する規定」について
国 自 整 第 1 7 7 号
平成24年12月27日
大型車のホイール・ボルト折損による車輪脱落事故防止対策については、機会あるごとに注意を喚起して
きたところですが、依然として大型車のホイール・ボルト折損による車輪脱落事故が各地で発生しているこ
とから、平成 16 年 12 月に「大型車のホイール・ボルト折損による車輪脱落事故に係る調査検討会」の検討
結果に基づく事故防止対策について、大型車の使用者及び整備事業者等に周知徹底するとともに、中長期的
対策として、一般社団法人日本自動車機械工具協会等にインパクトレンチの改良等を依頼したところです。
この度、一般社団法人日本自動車機械工具協会(以下「協会」という。)より、動力式トルク制御レンチ
の性能基準及び規定を制定し、平成25年1月1日より、別添のとおり動力式トルク制御レンチの型式性能
試験を実施すること及びこれらに基づき協会が実施する型式性能試験に適合した動力式トルク制御レンチに
ついては、トルクレンチと同等以上の性能である旨の報告がありましたので、貴会傘下会員に対し周知方お
願いします。
なお、別添報告の概要については、別紙をご参照下さい。
別紙
動力式トルク制御レンチの性能基準等に関する概要
1.性能基準の制定
動力式トルク制御レンチ(通称:ナットランナ)の性能基準は、一般社団法人日本自動車機械工具協会
(以下、協会という。)技術委員会技術部会内に「インパクトレンチ検討WG」を設置して、ISO 5393(ね
じ付き締結具の回転バイト-性能試験方法)等を参考にして検討を行い作成したものです。
また、当協会では、動力式トルク制御レンチに関する以下の基準及び規程を制定し、これらに基づき型
式性能試験を実施します。
① 動力式トルク制御レンチの性能基準
② 動力式トルク制御レンチの型式性能試験に関する規程
2.性能基準の概要
(1) 性能基準の対象は、車両のホイールナット等を規定トルクで締め付けるときに使用する動力式トルク
制御レンチであり、動力源は、エア式、電動式及びその他の動力式制御レンチを対象とします。
(2) 性能基準の内容は、外観、耐久性、作動、構造及び機能等について、使用上問題がないかどうか、また、
機能等の取り扱いが容易であり、誤った操作をしたときは安全装置等が作動することなどを確認します。
(3) 性能精度は、動力式トルク制御レンチでハイトルクレートジョイント (スチール製ホイール相当 )及
びロートルクレートジョイント ( アルミ製ホイール相当 ) の各ジョイントを 25 回締め付けて得られた
測定値の平均値から統計的算術により求めた「ばらつき (% )」が 10%以内、及び各ジョイントの平均
値の差が締付トルク設定値に対して 10%以内であることを定めました。

(93)
3.型式性能試験の概要
当協会は、性能基準等に基づき型式性能試験を行い、これに合格した動力式トルク制御レンチの型式に
は「型式性能試験番号」を付与します。
また、合格した型式の動力式トルク制御レンチの筐体には、性能基準を満足していることの証として「型
式性能試験番号標」を貼付します。
4.動力式トルク制御レンチの性能維持
型式性能試験番号標が貼付された動力式トルク制御レンチの性能維持については、製作者等が購入先
(ユーザ )を管理し、定期的な動力式トルク制御レンチの点検整備等を行う仕組みとなっています。
また、製作メーカー側で実施する性能試験用検査装置の精度維持については、当協会で 1 回/年の校正
を実施することで精度を確保します。
5.トルクレンチと同等の取り扱い
型式性能試験番号標が貼付された動力式トルク制御レンチについては、トルクレンチと同等以上の性能
であり、この動力式トルク制御レンチで締め付けた車両のホイールナット等は、トルクレンチでの最終的
な確認は不要として取り扱いができます。

(94)
自動車整備士技能検定において、自動車整備事業場で受験資格を満足する実務経験があるかのごとく虚
偽申請を行い、検定試験に合格した者がいることが発覚し、検定合格を無効とする事例が発生しています。
また、自動車整備事業者の関わり合いを調査したところ、虚偽申請に関係していたことが判明しました。
自動車整備事業者によるかかる行為は、自動車整備士技能検定の厳正かつ公平な実施を阻害する行為で
あるとともに、自動車整備事業者の信頼を失墜させる行為であり、二度とこのようなことが行われないよ
う、下記の規定を参考にして自動車整備士技能検定申請書には、事実を記載していただくようお願いをし
ます。
特に、実務経験等の記載内容が正しくないことが判った場合は、受験者の検定合格の無効などの処分を
受ける(合格を無効とされた場合、最大3年の受験停止となります。)ことがありますので、注意してく
ださい。
実務経験に関する規定
自動車整備士技能検定の受験資格に係る自動車等の整備作業に関する実務経験の確認について
(自整第46号の2 平成12年 3月28日)(抜粋)
1.実務経験として認められる自動車等の整備作業
検定規則第2条中の二級ガソリン自動車整備士から三級二輪自動車整備士までに掲げる自動車整備
士の実務経験として認められる自動車の整備作業とは、次の(1)各号に掲げる事業場又は業務にお
いて行われている(2)ア.各号に掲げる分解、点検、調整等の整備作業をいう。
検定規則第2条中の自動車タイヤ整備士、自動車電気装置整備士及び自動車車体整備士の実務経験
として認められる自動車の装置の整備作業とは、次の(1)各号に掲げる事業場又は業務において行
われている(2)イ.中の該当する号において示すそれぞれの分解、点検、調整等の整備作業をいう。
ただし、これらの場合において、オイル、タイヤ、灯火装置、ワイパー・ブレード等の交換作業のみ
の整備作業及びアルバイト等臨時で勤務しているような作業経験は実務経験とは認められない。
(1)事業場又は業務
ア.道路運送車両法第78条の自動車分解整備事業の認証を受けた者の事業場
イ.道路運送車両法第94条の優良自動車整備事業者の認定を受けた者の事業場
ウ. 「自動車の定期点検整備促進対策に使用するステッカーに対する運輸省名義の使用について
(昭和48年8月17日付自整第176号・自公第40号)中の定期点検整備促進対策要綱5.
(2)に規定する特定給油所(特定給油所とは、自家用乗用自動車の、4輪主ブレーキ及び駐車
ブレーキがすべてディスク・ブレーキである自動車の1年ごとの定期点検整備(分解整備を除
(8)自動車整備士技能検定等にかかる適正な実務経験の証明について

(95)
く。)を確実に実施したとき、「定期点検整備促進運動」による点検整備済ステッカーを交付で
きる給油所をいう。)
エ.上記ア.又はイ.に掲げる事業場以外の自動車タイヤ整備作業工場、自動車電気装置整備作業
工場及び自動車車体整備作業工場並びに自動車整備用機械器具を備え付けた整備作業場を有す
るガソリン、自動車部品、自動車用品等の販売事業者の事業場
オ.(一社)日本自動車連盟(JAF)の路上故障自動車救援業務
カ.上記各号に掲げるものと同等の整備作業を行い得るその他の事業場又は業務
(2)分解、点検、調整等の整備作業
ア.自動車の整備作業
①道路運送車両法施行規則第3条に規定する分解整備に係る整備作業
②キャブレータ、インジェクション・ポンプ等の主要な装置の点検、調整等の整備作業
③自動車の装置、主要部品等の交換を行う整備作業
④自動車の装置、主要部品等に係る点検、調整等の整備作業
⑤上記各号に掲げるものと同等の自動車の点検、調整等の整備作業
イ.自動車の装置の整備作業
①自動車タイヤ整備士にあっては、ホイール・アライメント又はホイール・バランスの点検、
調整等のタイヤに係る整備作業
②自動車電気装置整備士にあっては、充電装置、始動装置、点火装置又は各種電子制御装置の
点検、調整等の電気装置に係る整備作業
③自動車車体整備士にあっては、フレーム又はボディーの点検、修正、改造等の車体に係る整
備作業

(96)

(97)
(9) 大型自動車等に関する不正改造(二次架装)の防止について
近運技管第 367号の2
近運技整第208号の2
近運技技第258号の2
平成 16 年 11 月 16 日
近 畿 運 輸 局 長
先般、当局管内において、大型自動車販売店4社と自動車架装会社3社が、新規検査又は予備検査を受
けた後、当該自動車に過積載等を目的とする改造を行い、不正改造、車検証不正取得を行ったとして、道
路運送車両法違反容疑で警察の捜索を受けた事実が判明した。
これらの行為は、道路運送車両法の違反であることを知りつくして販売並びに改造した悪質な行為であ
り、道路運送車両法の目的でもある「車両の安全性の確保」を阻害するのみならず、ひいては自動車関係
業界の社会的信用を失墜するものであり、極めて遺憾である。
なお、当局としては、不正改造を行った事業者が判明した場合には、これに対し厳しく対処する所存で
ある。
今後、かかる事態が再発することがないよう、自動車使用者からの要望による車両装備の受注から、架
装、納車までの流れ及び組織の体制を全面的に見直す等貴会傘下会員に対し、厳重に注意を喚起し、適切
な販売、整備及び使用の励行を周知徹底されたい。


(99)
(11) ターボチャージャーへの異物の混入防止について
国 自 整 第 3 6 号
平成 22年6月 30日
国土交通省自動車交通局
技術安全部整備課長
去る平成 21年3月 16日、静岡県の東名高速道路上り線牧之原サービスエリアにおいて、また同年9月
20日、同県の東名高速道路上り線196.7キロポスト付近においてバス火災が発生しました。
これらの事故については、自動車交通局の「自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会」の下に、
「バス火災事故に関する調査小委員会」を設置し、その原因究明と再発防止について検討が行われ、今般、
同小委員会においてバス火災事故調査報告書がとりまとめられ、同年9月20日の事故については、火災の
原因となったターボチャージャーの破損については、何らかの原因により液状シーリング材がエンジンオ
イルに混入したことによると推定され、ターボチャージャーへの異物の混入防止等について再発防止策が
提言されました。
これを踏まえ、ターボチャージャー潤滑系の配管部品類の整備を行う場合には、液状シーリング材を用
いないよう周知徹底をお願いいたします。
なお、ターボチャージャーが装備されたバスの火災事故を未然に防止するため、バス輸入・販売事業者
はバス製作者が定めたターボチャージャーの定期的な点検の励行をバス事業者に周知していますので、点
検整備を行う際にはその旨留意するよう併せて周知徹底をお願いいたします。

(100)
3.その他
(1)

(101)

(102)
(5)

(103)
(6)

(104)
(2)

(105)
= 正しく取付けられていない例 =
◆ カートリッジ型 1. 交換前のカートリッジのOリングが、エンジン側の座面に残ってないかを確認しましょう。
(二重パッキンの防止)
2. 新しいカートリッジのOリングにオイルを塗布し、規定のトルクで締付けてください。
◆ エレメント交換型 1. 新しいOリングにオイルを塗布し、Oリングを指定の位置に装着してください。
2. 新しいエレメントを取付け、キャップやドレンプラグを規定のトルクで締付けてください。
カートリッジ型、エレメント交換型ともに、
取付け後は、エンジンオイル漏れがないことを確認しましょう。
【 エンジンオイルフィルタ交換時の注意点 】
カートリッジ型 エレメント交換型
Oリングの取付け位置が
正しくなく、はみ出した状態
古いフィルタのOリングが
残ったままの状態
(3) エンジンオイルフィルタ/エンジンオイル交換時の注意点

(106)

Ⅱ.自 動 車 検 査 関 係

(107)
1.事 務 関 係
(1)
道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第67条第1項に基づく道路運送車両法施
行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)第35条の3第14号及び第15号に係る自動
車検査証記載事項の変更については、今後、一層の事務手続の改善を図る観点から、平成7年11月29日以
降は下記により取り扱うこととしたので了知されたい。
なお、これに伴い「被けん引自動車の自動車検査証記載事項の変更に係る行政事務手続の改善について」
(平成3年12月20日自技第90号)は、平成7年11月28日をもって廃止する。
記
1.施行規則第35条の3第14号関係(用途)
(1) 自家用乗用自動車等として登録又は車両番号の指定を受けている自動車を、道路運送法施行規則
(昭和26年運輸省令第75号)第52条により許可を受けた自家用貸渡乗用自動車等に変更する場合には、
法第67条第1項に基づく施行規則第35条の3第14号にいう「用途」の変更に該当するものとして取扱
うものとするが、この変更事由だけをもって法第67条第3項に定める「運輸省令で定める事由に該当
する場合において、「保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき」には該当しないものと
して取扱うものとする。
(2) 法第67条第1項に基づく自動車検査証の記載事項の変更申請においては、従前の自動車検査証の有
効期間の残存期間に応じ、以下により取扱うものとする。
① 有効期間の残存期間が1年を超えている場合
自動車検査証の記載事項の変更のあった日を起算日とし、その日から1年間の有効期間を付すも
のとする。
なお、この場合においては、新たに付される有効期間の満了日と同一の検査標章を交付するもの
とする。
② 有効期間の残存期間が1年以下の場合
従前の自動車検査証の有効期間満了日を付するものとする。
2.施行規則第35条の3第15号関係(被けん引自動車)
けん引自動車と被けん引自動車の組合せ(以下「連結組合せ」という。)を変更する場合にあって、
次の・又は・に該当する場合にあっては、法第67条第3項に定める「運輸省令で定める事由に該当する
場合」には該当しないものとして法第67条第1項に基づく自動車検査証記載事項の変更申請により取扱
うものとする。
(1) 連結組合せが「被けん引自動車をけん引することができるけん引自動車の車名及び型式の判定につ
いて」(昭和44年1月31日自車第80号)により道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
に適合すると認められる自動車又は「新型自動車等取扱い要領について(依命通達)」(昭和45年6月
12日自車第375号、自整86号)により新型自動車の審査を受け保安基準に適合すると認められた自動
車
(2) 上記・の連結組合せに係るけん引自動車の型式であって、排出ガス対策のみの改善により当該型式
が変更したと認められる自動車
(1)

(108)
登録自動車を貸渡(レンタカー)に変更する時の有効期間について
(1)初回有効期間の残存期間が2年をこえている場合
申請日を起算日とし、その日から2年間の有効期間となる。
(2)初回有効期間の残存期間が2年未満の場合
有効期間の変更は行わない。
(3)初回有効期間以外の場合
今まで通りとする。(平成7年11月29日付 自技第243号参照)
(例)初回有効期間が3年に自動車で初度登録年月日を平成23年4月2日として考える。
(つまり、有効期間が平成26年4月1日の車両を想定した場合)
1 初回検査前に変更した時
1-1 平成23年4月2日 ~ 平成24年4月2日の間に変更する時
上記(1)に該当する
→ 変更登録した日から2年間となる
1-2 平成24年4月3日 ~ 平成26年4月1日の間に変更する時
上記(2)に該当する
→ 平成26年4月1日となる
2 初回検査後の車を変更した時
(有効期間が平成28年4月1日の車両を想定した場合)
2-1 平成26年4月2日 ~ 平成27年4月2日の間に変更する時
上記(3)に該当する
→ 変更登録した日から1年間となる
2-2 平成27年4月3日 ~ 平成28年4月1日の間に変更する時
上記(3)に該当する
→ 平成28月4月1日となる

(109)

(110)

(111)

(112)
連結仕様検討書(ライト・トレーラ)
け ん 引 車 ト レ ー ラ 車 名 ・ 型 式 車 名 ・ 型 式
車両重量 w ㎏ 車両重量 w′ ㎏車両総重量 GVW ㎏ 車両総重量 gvw ㎏主制動力 Fm ㎏ 駐車ブレーキ力 Fs′ 0 ㎏駐車ブレーキ力 Fs ㎏ 被けん引車の主制動装置の省略
【車両総重量750㎏以下に限る】 最高出力 Ps Ps駆動軸重 WD ㎏ w + 55
2 ≧gvw 停止距離 S
m(諸元の値) Sa + 55
≧
1.主制動装置制動能力(※)
2.連結時駐車ブレ ーキ制動能力
B=(w+w′)× 0.2 ≦ Fs
B=( + )× 0.2 = ≦
( + )
けん引車が保安基準第12条第1項又は第2項を適合する車両
B=(GVW+gvw)×0.12 ≦ Fs
B=( + )× 0.12 = ≦
3.トレーラの駐車ブレーキ制動能力(※けん引車追加の場合は検討の必要なし。)
B′=w′× 0.2 ≦ Fs′
B′= × 0.2 = ≦
平成11年7月1日以降に製作された車両
B′=gvw× 0.18 ≦ Fs′
B′= × 0.18 = ≦
4.連結社利用走行性能
GCW= GVW+gvw = + =
(1)121 × Ps - 1900 ≧ GCW
121 × - 1,900 = ≧
(2)4 × WD ≧ GCW
4 × = ≧
平成6年4月以降に生産される乗用自動車の諸元表に100km/h走行時の停止距離(Sa)が記載されている
ため、次式により50km/h走行時の停止距離を求める。
S = 0.25 ×(Sa + 10)
S = 0.25 ×( + 10 )= m
貨物自動車等で諸元表に80km/hで制動停止距離が表示されている車両
S = 0.39 ×(Sa - 12)+ 7.5
S = 0.39 ×( - 12 )+ 7.5 = m
(※)については第1項又は第2項の車両にけん引される製作年月日、平成11年7月1日以降の慣性ブレ
ーキ付のトレーラについては適合することを要しない。
GVW+gvw + LT=S× = × GVW LT= m ≦ 22 m (けん引車の停止距離Sを計算で求める場合) ※諸元表に停止距離が記載されていない場合 GVW × 1.05 50 S= 9.8425× + Fm 36
× 1.05 50 S= 9.8425× + = m 36
2

(113)
ライト・トレーラ連結仕様検討書
車両総重量750㎏以下に限る
平成11年7月1日以降生産された被けん引車保安基準第12条第1項又は第2項のけん引車によりけん引す
る場合に適用する。
(高速ブレーキ対応車に限る)
け ん 引 車 ト レ ー ラ
車 名 車 名
型 式 型 式
登録番号又は車台番号 登録番号又は車台番号
車両重量 w ㎏ 車両重量 w′ ㎏
車両総重量 GVW ㎏ 車両総重量 gvw ㎏
駐車ブレーキ力 Fs ㎏ 駐車ブレーキ力 Fs′ 0 ㎏
最高出力 Ps Ps 車 体 の 形 状 トレーラ
駆動軸重 WD ㎏
諸元表上の制動停止距離 Sa m
1.被けん引車の主制動装置の省略
w / 2 ≧ gvw
/ 2 ≧
2.連結時駐車ブレーキ制動能力
B=(GVW+gvw)×0.12 ≦ Fs
B=( + )× 0.12 = ≦
3.トレーラの駐車ブレーキ制動能力(※けん引車追加の場合は検討の必要なし。)
B′=gvw× 0.18 ≦ Fs′
B′= × 0.18 = ≦
4.連結時走行性能
(1)GCW= GVW+gvw = + =
(2)121 × Ps - 1900 ≧ GCW
121 × - 1,900 = ≧
(2)4 × WD ≧ GCW
4 × = ≧
5.定員10人以下の乗用車であって、停止距離(S1)が次の式に適合する制動能力を有するものは1.が不
適合に係わらず制動装置を省略することができる。
S1 = Sa ×GCW / GVW ≦ 81m
S1 = × / ≦ 81m

(114)
牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書(乗用車用)
牽引車 車名: 型 式:
車台番号:
申請者名:
申請値: 主 ブ レ ー キ 有 り (㎏) 主 ブ レ ー キ 無 し (㎏) 牽引車の車検証より: 車 両 総 重 量 M: (㎏) 車 両 重 量 M': (㎏) 牽引車諸元表より: ★FS,F,操作力の単位が㎏の場合、 (㎏)×9.8= (N)積車時駆動軸重 Wd: (㎏) ★4WDなど、駆動軸が複数ある場合はその合計 原動機の最高出力 Kw: (KW) ★ (PS)×0.736= (kw) 駐 車 制 動 力 注 Fs: (N)
減 速 度 a: (m/s2) 若しくは、制動停止距離 Sv: (m) 制 動 初 速 度 V: (km/h) ★諸元表に主制動装置の制動力 Fのみの記載の場合は a=F/M として計算する。 F: (N) ★諸元表に a、Sv 及び V、Fの記載が無い場合は実測による。 (a= m/s2) 注 駐車ブレーキの操作力が以下の規定値に満たない場合、 制動停止距離の初速 50km/h の自動車 :手動式で 500(N)、足踏式で 900(N)
適用関係告示第9条第1項第4号が適用される自動車(同条第5項により適用される自動車を含む。)
制動停止距離の初速 50km/h 以外の乗用車 :手動式で 400(N)、足踏式で 500(N) 上記以外の自動車 :手動式で 600(N)、足踏式で 700(N) 次により換算してください。 諸元表の制動力×操作力の規定値 (N) × (N)
= = (N) 諸元表の操作力 (N)
(1) 駐車ブレーキ m1 = 0.85FS - M = 0.85× - = (㎏) (2) 連結状態での走行性能 m2 = 164.51 × KW - 1900 - M = 164.51 × - 1900 - = (㎏) m2′ = 4 × Wd - M = 4 × - = (kg) (3) 主ブレーキ無し 減速度 aを用いる場合 a m3 = - 1 M = -1 × = (㎏) 5.67 5.67
制動停止距離 Sv及び制動初速度 Vを用いる場合
V2 m3’ = - 1 M = -1 × = (㎏) 147(Sv-0.1V) 147×( -0.1× ) (4) 主ブレーキ有り 減速度 aを用いる場合 a m4 = 7.36 - 1 M = 7.36m3 = 7.36 × = (㎏) 5.67 制動停止距離 Sv及び制動初速度 Vを用いる場合
V2 m4′ = 7.36 - 1 M = 7.36 m3 = 7.36 × = (㎏) 147(Sv-0.1V (5) 牽引可能なキャンピングトレーラー等の車両総重量の決定 主ブレーキ無し m1,m2,m2′,m3(m3′),申請値の内、最軽量なものとする。 ただし、750kg を超えないこと、かつ M'/2 を越えないこと。 ≦ 750 ma = (㎏)≦ (M'/2)(10kg 未満は切り捨て) 主ブレーキ有り m1,m2,m2′,m4(m4′)申請値の内、最軽量なものとする。 ただし、1990kg を超えないこと。 mb = (㎏)≦ 1990(10kg 未満は切り捨て)
けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ KG及び KGとする。

(115)
(別 紙)
道路運送車両法施行規則の一部改正について
(自動車検査証への記載事項の改正によるトレーラ登録手続きの簡素化)
平 成15 年12 月
国 土 交 通 省
1.改正の背景
現行の制度では、被牽引自動車(以下「トレーラ」という。)の自動車検査証(以下「検査証」という。)
には牽引自動車(以下「牽引車」という。)の車名及び型式を記載する必要があり、トレーラの検査証に記
載されていない牽引車は当該トレーラを牽引して運行する事ができない。
このため、運送事業など多数のトレーラを運行している場合、牽引車を新しく導入する度に、当該牽引
車が牽引するトレーラの全ての検査証の記載事項を変更する必要がある。
また、トレーラのレンタル利用を行う場合、予め牽引車を特定することができないことから、そのレン
タルは事実上不可能となっており、特にレジャー等における利用が見込まれる2トン未満のトレーラを対
象に、平成12年に行われた検討会の結果(別添)に基づき制度の見直しを行う。
2.改正の概要
① 牽引車導入時にトレーラ検査証の記載事項変更を省略化とする。
牽引車の検査証にトレーラの車名及び型式を記載を可能とし、当該牽引車が牽引するトレーラについて
は、検査証への牽引車の車名及び型式の記載を省略できるようにする。
これにより、牽引車が導入する際のトレーラ検査証の記載事項変更を行う必要が無くなり、手続きが簡
素化される。
② キャンピングトレーラ等(※1)において、牽引車の記載を省略可とする。
「牽引可能なキャンピングトレーラ等の重量(※2)」を牽引車の検査証に記載可能とし、当該牽引車が
牽引するキャンピングトレーラ等については、検査証への牽引車の車名及び型式、牽引重量の記載を省略
できるようにする。
これにより、予め牽引車を特定しなくても能力の範囲内で様々なキャンピングトレーラ等を牽引するこ
とができるようになるため、レンタル利用等が可能となる。また、トレーラの減トンなど従前の取扱いと
の整合図るため、ユーザーの選択により牽引車の特定も可能とする。
(※1)キャンピングトレーラ等:セミトレーラを除く2トン未満のトレーラ
(なお、当該トレーラについては平成14年6月に限定牽引免許が新設されている。)
(※2)牽引可能なキャンピングトレーラ等の重量:
「原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能並びに牽引自動車及びキャンピングトレーラ等の制動
性能を基礎にして当該牽引自動車がキャンピングトレーラ等を牽引できるものとして算出された最大の車両
総重量」として新たに定義するもので、牽引重量(原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能を基礎にして
当該牽引自動車が最大限牽引することが出来るものとして算出された重量)とは異なる。

(116)
(2) 自動車検査証備考欄の記載事項
記載を要する自動車 記載事項 記載例
1.施行規則第52条各号の一に掲
げる処分を受ける自動車
処分年月日
処分の内容
附した制限
認定年月日
平成16年7月1日
近畿運輸局第123号
緩和事項「長さ」
緩和制限「自動車の後面及び運転者席
には、長さを表示するこ
と。」
2.4-57-2-1①(細目告示第42条
第1項、第2項、第120条第1
項)、4-57-2-1③(細目告示第
120条第2項)、4-58-2-1①(細
目告示第42条第5項、第120条
第5項)、4-58-3(細目告示第
120条第6項)、4-61-3(1)(細目
告示第121条第3項)、5-57-2-1
①(細目告示第198条第1項)、
5-57-2-1③(細目告示第198条
第2項)、5-58-2-1①(細目告
示第198条第5項)、5-58-3(1)
(細目告示第198条第6項)、
5-61-3(1)(細目告示第199条第
3項)の規定により、地方運輸
局長の指定を受けた自動車
指定内容
指定年月日
前照灯の取付位置
近運技技第123号
平成16年7月1日
3.保安基準第56条第4項の規定
により国土交通大臣の認定を
受けた自動車
認定内容
認定年月日
大臣認定
メタノール自動車
国自審第234号
平成16年1月15日
4.ワンマンバスの構造要件の適
用緩和を受けた自動車
緩和内容 ワンマンバス構造要件の適用緩和
近運事第345号
平成16年10月1日乗降口
5.タンク自動車 積載物品名
最大積載容積
比重又は定数
品名 第一石油類
容積 5000L
比重 0.75
5-1.荷台に危険物のタンクを
固定し、かつ、タンク以外に積
載量を有する自動車
タンクに積載する物品名
及び積載量の内訳
品名 灯油
容積 250L
比重 0.80
積載量内訳
タンク 200kg
荷 台 300kg

(117)
記載を要する自動車 記載事項 記載例
5-2.危険物運搬用タンク車で
あって、積載の組合せが多数あ
り、備考欄に記載することがで
きない自動車
積載の組合せが備考欄以外にあ
る旨
積載の組合せは、設置許可書等による
5-3.セメント、骨材及び水を
混ぜた生コンクリート以外の
ものを積載物品とするコンク
リートミキサー車
積載物品名
最大積載容積
比重
品名 流動化処理土
容積 5.78㎥
比重 1.65
6.被牽引自動車(牽引自動車の
車名及び型式について記載の
申し出があったものに限る。)
牽引自動車の車名及び型式
① ②以外の場合
② 型式が「不明」の場合
(型式にシリアル番号の一連番
号を除く部分を付記)
牽引車 日野P-AA
牽引車 フォード不明
(ABDE1234)
6-1.被牽引自動車であって、
次の各号に掲げるもの
(1) 第五輪荷重を有する牽引自
動車で牽引されるもの
(2) 基準緩和を受けている自動
車であって、速度制限装置が装
着されている牽引自動車で牽
引されるもの
第五輪荷重が分担する荷重
牽引自動車に速度制限装置が装
着されている旨
保安基準適合性の検討条件
① 運行時の最高速度50km/h超
60km/h以下の場合
② 運行時の最高速度50km/h以
下の場合
第五輪荷重 7690kg以上
牽引車の全型式に速度制限装置付又
は運輸W-AA、運輸W-ABには速
度制限装置付
運行時の最高速度は60km/h以下で検
討
運行時の最高速度は50km/h以下で検
討
7.牽引自動車(被牽引自動車の
車名及び型式について記載の
申し出があったものに限る。)
被牽引自動車の車名及び型式
① ②及び③以外の場合
② 型式が「不明」の場合(型
式にシリアル番号の一連番号
を除く部分を付記)
③ 型式が「組立」及び「試作」
の場合
(型式に車台番号を付記)
被牽引車 フルハーフ
ABCD
被牽引車 パーストナー不明
(ABDE1234)
被牽引車 組立
(東41567東)
7-1.基準緩和を受けている牽
引自動車
速度制限装置の装着の有無及び
その設定速度
速度制限装置付
最高速度60km/h以下
速度制限装置なし
8.4軸を超える自動車 軸重 第5軸重 8500kg

(118)
記載を要する自動車 記載事項 記載例
9.燃料の種類欄に「その他」と
記載した自動車
燃料の種類 燃料 水素
9-1.メタノールを燃料とする
自動車であって、次の各号に掲
げるもの
(1) メタノールとガソリン等
を混合したものを燃料とす
るもの
(2) 補助燃料としてガソリン
又は軽油を使用するもの
(3) ガソリン併用式のもの
(4) 通常はメタノールとガソ
リンの混合物を使用し、ガソ
リンのみも使用可能なもの
メタノールとガソリン等を85:
15の比率で混合したもの(M85)
を燃料とする旨
メタノール(M100又はM85)を
主燃料とし、補助燃料としてガ
ソリン又は軽油を使用する旨
ガソリンを併用することが可能
である旨
通常はメタノールとガソリンを
併用し、ガソリンのみも使用す
ることができる旨
燃料
メタノール(M85)
燃料
主 メタノール
(M100又はM85)
補助 ガソリン又は軽油
燃料
メタノール・ガソリン併用
燃料
メタノール・ガソリン混合物(混合率
可変)
9-2.CNGを燃料とする自動
車であって、次の各号に掲げる
もの
(1)ガソリン併用式のもの
(2)軽油を着火燃料とするもの
ガソリンを併用することが可能
である旨
CNGを燃料とし、軽油を着火
燃料とする旨
燃料
CNG・ガソリン併用
燃料
主 CNG
補助 軽 油
9-3.軽油を燃料とする自動車
であって、バイオディーゼル
100%燃料使用するもの
バイオディーゼル100%燃料を
併用使用している旨
燃料
バイオディーゼル100%燃料併用
9-4.ハイブリッド自動車であ
って、次の各号に掲げるもの
(1)電気式又は蓄圧式のもの
((2)を除く。)
(2)蓄電装置を充電するための
外部充電装置を備えるもの
ハイブリッド自動車である旨
プラグインハイブリッド自動車
である旨
ハイブリッド自動車
プラグインハイブリッド自動車
9-5.軽油を燃料とする自動車
であって、揮発油等の品質の確
保等に関する法律に基づく特
例措置による高濃度バイオデ
ィーゼル燃料を使用するもの
揮発油品確法の特例措置による
高濃度バイオディーゼル燃料を
併用使用している旨
燃料
品確法特例措置高濃度バイオディー
ゼル燃料併用
9-6.圧縮水素又は液体水素を
燃料とし、燃料電池スタック及
燃料電池自動車である旨 燃料電池自動車

(119)
記載を要する自動車 記載事項 記載例
び電動機を備えたもの
10.臨時乗車定員が定められた自
動車
臨時乗車定員 臨時乗車定員 108名
11.使用者の名義が複数の自動車 共同使用者の氏名又は名称及び
住所
共同使用者の氏名、住所
運輸太郎、東京都千代田区霞ヶ関2-1-3
12.緊急自動車であって、次の各
号に掲げるもの
(1)用途区分通達4-1-1以
外の自動車((2)を除く。)
(2)重度の傷病者でその居宅に
おいて療養しているものに
ついていつでも必要な往診
をすることができる体制を
確保している医療機関が当
該傷病者について必要な緊
急の往診を行う医師を当該
傷病者の居宅にまで輸送す
るために使用する自動車(以
下、「在宅傷病者緊急往診用
自動車」という。)
緊急自動車である旨
在宅傷病者緊急往診用自動車で
ある旨
緊急自動車
緊急自動車(在宅傷病者緊急往診用)
13.道路維持作業用自動車 道路維持作業用自動車である旨 道路維持作業用自動車
14.3-3-4④の適用を受ける
改造自動車
改造された装置名
改造通知書番号
改造通知年月日
改造内容 操縦装置
自近畿第123号
平成7年11月24日
14-1.走行装置としてゴム履帯
を有する自動車
ゴム履帯装着時の諸元を示す旨 括弧内はゴム履帯装着時を示す
15.並行輸入自動車 適用する保安基準の判定年月日
又は製作年月日
原動機型式打刻位置
原動機の最高出力時の回転数
保安基準適用年月日又は製作年月日
平成12年4月1日
原動機型式打刻位置
シリンダブロック上面左側前部
原動機最高出力時回転数
9,000rpm
15-1.並行輸入自動車であっ
て、次の各号に掲げるもの
(1) 専ら乗用の用に供する乗車
定員10人以下の自動車に適用
される排出ガス規制に適合し
たもの
(2) 二輪自動車又は側車付二輪
自動車に適用される排出ガス
規制に適合したもの
規制の対象となる排出ガス規制
の適合年
規制の対象となる排出ガス規制
の適合年
12年排出ガス規制適合
11年排ガス適合

(120)
記載を要する自動車 記載事項 記載例
(3) 別添1「改造自動車審査要
領」3.(1)から(10)までに該当
する改造により、装置が変更さ
れているもの
(4) 二輪自動車又は側車付二輪
自動車であって、後輪にばねそ
の他の緩衝装置を備えていな
いもの
(5) 初めて検査証を交付する検
査時に4-48-2-2(1)⑥の適
合性を4-48-2ー2-(3)②に
より確認したもの
変更された装置名
後輪にばねその他の緩衝装置を
備えていない旨
4-48-2-2(3)②ア又はイに規
定する書面又は表示
変更内容 緩衝装置
後輪 緩衝装置なし
初回検査時確認書面等
(騒音試験成績表)
(WVTA)
(車両データプレート)
(COC)
(外国登録証)
(認可書)
16.職権打刻をした自動車
車台番号打刻位置
(打刻届出に係る位置に打刻し
た場合を除く。)
シリアル番号を有する場合のシ
リアル番号
塗まつした車台番号(塗まつし
た車台番号が職権打刻である場
合を除く。)
原動機型式打刻位置
(打刻届出に係る位置に打刻し
た場合を除く。)
車台番号打刻位置
右側前輪ストラットハウジング上面
シリアル番号
ABCDEFGH123456789
シリアル番号
ABCDEFGH123456789
原動機型式打刻位置
シリンダブロック上面左側前部
17.「土砂等を運搬する大型自動
車による交通事故の防止等に
関する特別措置法
(昭和42年法律第131号)」に定
める土砂等以外の物品を専用
に運搬するダンプ自動車
土砂等を運搬しない旨 積載物品は土砂等以外のものとする。
18.熱害対策装置等を有する自動
車であって、次の各号に掲げる
もの(並行輸入自動車等、諸元
表等による識別が困難なもの
に限る。)
(1) 断続器の形式が接点式のた
め熱害対策装置等の装着が必
要なもの
(2) 断続器の形式が接点式であ
って、公的試験機関の試験結果
断続器の形式が接点式である旨
OBDⅡシステムを備えている
旨
接点式
接点式、OBDⅡ

(121)
記載を要する自動車 記載事項 記載例
によりOBDⅡシステムを備
えていることが確認されたも
の
(3) 断続器の形式が接点式であ
って、公的試験機関の試験結果
により失火検知システムを備
えていることが確認されたも
の
(4) 公的試験機関の試験結果に
より4-51-1-2(1)②又
は5-51-1(1)②ただし書
中「異常温度以上に上昇するこ
とを防止する装置」に該当する
ことが確認されたもの
失火検知システムを備えている
旨
燃料カット方式の異常温度上昇
防止装置を備えている旨
接点式、失火警報
接点式、異常温度上昇防止システム搭
載車( 燃料カット方式)
19.「窒素酸化物又は粒子状物質
を低減させる装置の性能評価
実施要領」(平成16年国土交通
省告示第814号。以下「低減装
置評価実施要領」という。)の
規定に基づき優良低減装置と
して評価・公表された装置(第
2種粒子状物質低減装置を除
く。)を装着することによりN
Ox・PM特例告示第4条(軽
油を燃料とする自動車にあっ
ては第4条及び第5条)の基準
(以下「NOx・PM法の基準」
という。)に適合することが確
認された自動車
優良低減装置が装着されている
旨
優良低減装置の優良評価番号
優良低減装置付
評価番号MLIT-NPR-1
19-1.原動機等の変更が行われ
た自動車であって、次の各号に
よりNOx・PM特例告示第4
条(軽油を燃料とする自動車に
あっては第4条及び第5条)の
基準に適合することが確認さ
れた自動車
(1) 公的試験機関の試験結果
(2) 諸元値を持つ原動機及び一
酸化炭素等発散防止装置に載
せ換えた場合であって、当該原
動機及び一酸化炭素等発散防
止装置が搭載されていた自動
原動機等の変更によりNOx・
PM法の基準に適合することを
確認した旨、平均値規制と基準
値(上限値)規制の別、試験モ
ード及びNOx・PM排出量
NOx・PM法対応変更有、平均値規
制、10/10・15モード、NOx0.48g/km、
PM0.055g/km

(122)
記載を要する自動車 記載事項 記載例
車の諸元値
19-2.原動機等の変更が行われ
た自動車であって、次の各号に
掲げるもの
(1) 公的試験機関の試験結果に
よりNOx・PM特例告示第2
条の基準に適合することが確
認された自動車であって第4
条の基準(軽油を燃料とする自
動車にあっては第4条又は第
5条)に適合していないもの
(2) 平成14年9月30日以前に公
的試験機関の試験結果により
「道路運送車両の保安基準及
び道路運送車両の保安基準の
一部を改正する省令の一部を
改正する省令」(平成14年国土
交通省令第24号)の施行前の保
安基準第31条の2の基準に適
合することが確認された自動
車であってNOx・PM特例告
示第4条(軽油を燃料とする自
動車にあっては第4条又は第
5条)の基準に適合していない
もの
NOx処理装置が装着されてい
る旨
NOx処理装置付
19-3.「道路運送車両の保安基
準第31条の2の規定に適合さ
せるために行う窒素酸化物又
は粒子状物質の排出を低減さ
せる改造の認定実施要領」(平
成17年国土交通省告示第894
号。以下「低減改造認定実施要
領」という。)の規定に基づき
優良低減改造として認定・公表
がされた改造を行うことによ
りNOx・PM法の基準に適合
することが確認された自動車
優良低減改造が行われている旨
優良低減改造の優良認定番号及
び交付番号
優良低減改造有
認定番号M L I T - R R - 1
交付番号A B C D 1 2 3 4
20.平成10年騒音規制適合自動車
及びそれ以降に規制強化がなさ
れた騒音規制適合自動車
騒音規制に適合している旨、近
接排気騒音規制値及び全輪駆動
の有無
平成10年騒音規制車、近接排気騒音規
制値99dB、全輪駆動
21.車いすを車体に固定すること 車いすを固定するための装置を 車いす固定装置付(1基)

(123)
記載を要する自動車 記載事項 記載例
ができる装置を有する自動車
(車いす専用のスペースを有
するものに限る。)
有する旨
22.用途区分通達4-1-1及び
4-1-2に掲げる自動車
使用者を変更した場合におい
て、変更後の使用者の事業等が
変更前の使用者の事業等と異な
る場合には、当該自動車の用途
及び車体の形状が変更となる場
合がある旨
この自動車は、使用者の事業により特
種用途に該当
23.用途区分通達4-1-3(3)
及び(4)に掲げる自動車(24.
に掲げる場合を除く。)
平成13年から施行される構造要
件が適用される旨
平成13年特種構造要件適用車
24.用途区分通達4-1-3(4)
に掲げる自動車のうちのキャ
ンピング車
平成15年から施行される構造要
件が適用される旨
平成15年特種構造要件適用車
25. 大型貨物自動車であって速
度抑制装置を装着した自動車
速度抑制装置を装着している旨 速度抑制装置付
26. 普通自動車であって、貨物の
運送の用に供する車両総重量
7t以上のもの
燃料タンクの個数及びそれぞれ
の容量
燃料タンク 2個 300L 300L
27. 自主防犯活動用自動車 自主防犯活動に使用する自動車
である旨
自主防犯活動用自動車
28. 専ら乗用の用に供する乗車
定員10人(平成24年6月30日以
前に製作される自動車にあっ
ては11人)以上の自動車であっ
て、高速道路等を運行しない自
動車( 昭和62年8月31日以前
に製作された自動車を除く。)
高速道路等を運行しない旨 高速道路等を運行しない自動車とし
て保安基準に適合
29. 「自動車の排出ガス低減性能
を向上させる改造の認定実施
要領」(平成19年国土交通省告
示第131号。以下「排ガス低減
性能向上改造認定実施要領」と
いう。)第3条の規定により、
認定を受けた改造を行った自
動車
排出ガス低減性能向上改造が行
われている旨
排出ガス低減性能向上改造の認
定番号
低減性能向上改造証明書〔「自
動車の排出ガス低減性能を向上
させる改造の認定実施細目」(平
成19年3月9日付け国自環第
249号)第4の低減性能向上改造
証明書をいう。以下同じ。〕の
交付番号
排ガス低減性能向上改造有
認定番号MLIT-RLEV-1
交付番号123

(124)
記載を要する自動車 記載事項 記載例
30. 平成17年規制適合のディー
ゼル車のうち、オパシメータを
使用して無負荷急加速時に排
出される排出ガスの光吸収係
数を測定するもの
オパシメータを使用して無負荷
急加速時に排出される光吸収係
数を測定する旨
オパシメータ測定
31. 1-3の2の規定により、二
輪自動車の保安基準を適用す
る自動車
二輪自動車の基準を適用する旨 二輪自動車の保安基準を適用
32. 「特定改造自動車のエネルギ
ー消費効率相当値の算定実施
要領」(平成21年国土交通省告
示第933号)第7条の規定により
有効な算定燃費値取得済証(以
下「算定済証」という。)の交
付を受けて、類型を特定した特
定改造自動車
燃費値の算定を受けた特定改造
自動車である旨及び算定済証記
載の改造車等燃費算定番号・区
分番号
90001・0001(算定燃費値取得済特定
改造自動車)
33. 排出ガス値及び燃費値に影
響を与える原動機、一酸化炭素
等発散防止装置、動力伝達装置
又は燃料の種類に変更が行わ
れたことを、新規検査若しくは
予備検査又は構造等変更検査
時に公的試験機関の試験結果
又は現車により確認した型式
指定自動車又は一酸化炭素等
発散防止装置指定自動車〔自動
車排出ガス規制の識別記号が3
桁以上の自動車〔大型特殊自動
車、二輪自動車及び側車付二輪
自動車を除く。〕に限る。〕
排ガス燃費影響装置等に変更が
ある旨
排ガス燃費影響装置等変更
34. 平成22年4月1日以降に製作
された自動車(乗車定員11人以
上の自動車、車両総重量3.5t
を超える自動車及び大型特殊
自動車を除く。)
消音器の加速走行騒音性能規制
(以下「マフラー加速騒音規制」
という。)が適用される旨
マフラー加速騒音規制適用車

(125)
○ 作業用附属装置、除雪装置、道路清掃装置等を随時取り外し、又は取り替えて使用できる自
動車については、次の例により記載するものとする。なお、軸重欄は、当該附属装置等を装着
した状態のうちの最も重い数値を記載するものとし、附属装置名についても記載するものとす
る。
(記載例)
車体の形状
ショベル・ローダ
乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量
1〔1〕人 - ㎏ 5700〔7460〕㎏ 5755〔7515〕㎏
長 さ 幅 高さ
〔590〕
518 ㎝
〔249〕
213 ㎝
〔315〕
274 ㎝
○ 立席を有する専ら乗用の用に供する乗車定員 11 人以上の自動車(立席に係る乗車定員の算出
について保安基準第 55 条に基づく基準緩和の認定を受けた自動車を除く。)にあっては、乗車
定員欄に立席を除いた乗車定員数を括弧書で付記するとともに、備考欄にその説明を、次の例
により記載する。
(記載例)
乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量
80〔40〕人 - ㎏ 4810 ㎏ 9210〔7010〕㎏
備考
乗車定員及び車両総重量欄の括弧外は高速道路等を運行しない際の立席を含めたすべての乗車
装置を最大に利用した状態を、括弧内は立席を除く乗車装置を最大に利用した状態を示す。

(126)
(3) 重量税等減免対象車の確認手順

(127)

(128)

(129)
「対象車種一覧詳細は 国土交通省HP
アドレス http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000007.html

(130)
(4) 放置違反金滞納車に対する車検拒否制度について

(131)

(132)

(133)
放置違反金等の滞納により検査証の有効期間を更新できなかった方は、
必ず①の「放置違反金督促状兼納付書」を指定金融機関で納付を行ない
領収証書(本通)を提示してください
①
下記②の納付書・領収証書では検査証の有効期間更新はできません
②

(134)
コード
10
11
12
13
14
20
21
22
23
24
25
30
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
60
61
62
63
64
65
70
71
72
73
74
80
81
82
83
90
91
92
93
94
95
96
97

(135)
検査証未交付警告文
本日検査の申請がありました「○○ △△△や××××」については、道路交通法第51条の6
の規定に基づく国家公安委員会からの通知 ( 駐車違反に関する違反金の滞納がある旨 ) を受けてい
るため、限定自動車検査証に示す保安基準不適合箇所について必要な整備を行い保安基準に適合す
ることになっても、道路交通法第51条の7の規定に基づき自動車検査証の有効期間の更新をする
ことはできません。
〔通知を受けている違反番号〕※
12345678901234501 12345678901234506
12345678901234502 12345678901234507
12345678901234503 12345678901234508
12345678901234504 12345678901234509
12345678901234505 12345678901234510
なお、当該通知に係る放置違反金等を滞納したこと又はこれを徴収されたことを証する書
面を限定自動車検査証の有効期間内に提示してください。提示されない場合は、再度、検査
が必要となります。
平成 ○○ 年 ○ 月 ○○ 日 ○○運輸支局長
※違反番号17桁、先頭の2数字で違反した県の番号
P 134 のコードを参照して下さい。

(136)
2.検 査 関 係
(1) 自動車の用途等の区分について
自 車 第 4 5 2 号
昭和35年9月6日
改正 国 自 技 第 202号
平成19年1月4日
道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第14号の自動車(軽自動車を除く。)の
用途及び軽自動車(二輪自動車を除く。)の分類は、次のとおり区分して取り扱うこととされたい。なお、
「貨物自動車と乗用自動車の区分に関する基準について」(昭和29年自車第366号)及び「貨物自動車と乗用
自動車の区別に関する基準の解釈について」(昭和29年自車第436号)は、廃止する。
1 乗用自動車等
1-1 乗用自動車等とは、乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外の
ものをいう。
1-2 乗用自動車等を次のように分類するものとする。
(1) 乗用自動車
(2)又は(3)以外の乗用自動車等をいう。
(2) 貸渡乗用自動車等
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「運送法施行規則」という。)第52条の規定に
より許可を受けた乗用自動車等をいう。
(3) 幼児専用乗用自動車
専ら幼児の運送を目的とする乗用自動車等をいう。
2 乗合自動車等
2-1 乗合自動車等とは、乗車定員11人以上の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外の
ものをいう。
2-2 乗合自動車等を次のように分類するものとする。
(1) 乗合自動車
(2)又は(3)以外の乗合自動車等をいう。
(2) 貸渡乗合自動車等
運送法施行規則第52条の規定により許可を受けた乗合自動車等をいう。
(3) 幼児専用乗合自動車
専ら幼児の運送を目的とする乗合自動車等をいう。
3 貨物自動車等
3-1 貨物自動車等とは、特種用途自動車等以外の自動車であって、次の(1)又は(2)のいずれかを満足する
ものをいう。
(1) (2)以外の自動車にあっては、次の①及び②を満足すること。

(137)
① 物品積載設備の床面積
自動車の物品積載設備(注1)を 大に利用した場合において物品積載設備の床面積(注2)が1
㎡(軽自動車にあっては、0.6㎡、二輪の自動車でけん引される被けん引自動車にあっては、0.2㎡)
以上あること。
② 構造及び装置
当該自動車の構造及び装置が3-1-1又は3-1-2に該当するものであること。
(2) 第五輪荷重を有するけん引自動車であって、セミトレーラ(前車軸を有しない被けん引自動車であっ
て、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分
がけん引自動車によってささえられる構造のものをいう。以下同じ。)をけん引するための連結装置を
有すること。
3-1-1 次の(1)から(4)までの基準に適合するものであること。
(1) 物品積載設備の床面積と乗車設備の床面積
自動車の乗車設備(注3)を 大に利用した場合において、残された物品積載設備の床面積が、この
場合の乗車設備の床面積(注4)より大きいこと。
(2) 積載貨物の重量と乗車人員の重量
自動車の乗車設備を 大に利用した場合において、残された物品積載設備に積載し得る貨物の重量(注
5)が、この場合の乗車設備に乗車し得る人員の重量より大きいこと。
(3) 物品の積卸口
物品積載設備が屋根及び側壁(簡易な幌によるものであって、その構造上屋根及び側壁と認められな
いものを除く。)によっておおわれている自動車にあってはその側面又は後面に開口部の縦及び横の有
効長さがそれぞれ800mm(軽自動車にあっては、縦600mm横800mm)以上で、かつ、鉛直面(後面の開口部
にあっては車両中心線に直角なもの、側面の開口部にあっては車両中心線に平行なものをいう。)への
投影面積が0.64㎡(軽自動車にあっては、0.48㎡)以上の大きさの物品積卸口を備えたものであること。
ただし、物品積載設備の上方が開放される構造の自動車で、開口部の床面への投影面積が1㎡(軽自動
車にあっては、0.6㎡)以上の物品積卸口を備えたものにあっては、この限りでない。
(4) 隔壁、保護仕切等
自動車の乗車設備と物品積載設備との間に適当な隔壁又は保護仕切等を備えたものであること。ただ
し、 大積載量500㎏以下の自動車で乗車人員が座席の背あてにより積載物品から保護される構造と認め
られるもの、及び折りたたみ式座席又は脱着式座席(注6)を有する自動車で乗車設備を 大に利用し
た場合には 大積載量を指定しないものにあってはこの限りでない。
3-1-2 次の(1)及び(2)の基準に適合するものであること。
(1) 隔壁等
自動車の運転者席(運転者席と並列の座席を含む。以下「運転者席」という。)の後方がすべて幌で
覆われた物品積載装置であって、運転者席と物品積載装置との間に乗車人員が移動できないような完全
な隔壁があること。

(138)
(2) 座席
物品積載装置内に設けられた座席は、そのすべてが折りたたみ式又は脱着式の構造のもので、折りた
たんだ場合又は取り外した場合に乗車設備が残らず貨物の積載に支障のない構造のものであること。
3-2 貨物自動車等を次のように分類するものとする。
(1) 貨物自動車
(2)以外の貨物自動車等をいう。
(2) 貸渡貨物自動車
運送法施行規則第52条の規定により許可を受けた貨物自動車等をいう。
4 特種用途自動車等
4-1 特種用途自動車等とは、主たる使用目的が特種である自動車であって、次の(1)から(3)のすべてを満
足するものをいう。
(1) 主たる使用目的遂行に必要な構造及び装置を有し(注7)、かつ、4-1-1、4-1-2又は4-
1-3のいずれか1つに該当するものであること。
(2) 大積載量を有する自動車にあっては、自動車の乗車設備と物品積載装置との間には、適当な隔壁又
は保護仕切等を備えたものであること。
ただし、 大積載量500㎏以下の自動車で乗車人員が座席の背あてにより積載物品から保護される構造
と認められるものにあっては、この限りでない。
(3) 次の①から③のいずれかに該当する自動車でないこと。
ただし、4-1-1の各車体の形状の自動車にあっては、この限りでない。
① 型式認証等を受けた自動車(注8)の用途が乗用自動車であって、車体の形状が箱型又は幌型のもの
であり、かつ、その車枠が改造されていないもの
② 型式認証等を受けた自動車の用途が貨物自動車であって、その物品積載設備の荷台部分の2分の1を
超える部位が平床荷台、バン型の荷台、ダンプ機能付き荷台、車両運搬用荷台又はコンテナ運搬用荷
台であるもの
③ 型式認証等を受けた自動車の用途が貨物自動車であって、セミトレーラをけん引するための連結装置
を有するもの
4-1-1 専ら緊急の用に供するための自動車
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条により指定又は届出された緊急自動車であって、かつ、
以下の車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を有するもの
救急車、消防車、警察車、臓器移植用緊急輸送車、保線作業車、検察庁車、緊急警備車、防衛省車、電
波監視車、公共応急作業車、護送車、血液輸送車、交通事故調査用緊急車
なお、被けん引車又は二輪車若しくは三輪車であることにより車体の形状の一部が異なる場合について
は、上記の車体の形状を以下の事例に示すように読み替えて適用する
(以下本項において同じ。)。
例:消防車→ 消防フルトレーラ

(139)
救急車→ 救急車二輪
警察車→ 警察車三輪
4-1-2 法令等で特定される事業を遂行するための自動車
使用者の事業が法令等(注9)の規定に基づき特定できるもので、その特定した事業を遂行するために
専ら使用する自動車であって、以下の車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を有するもの
給水車、医療防疫車、採血車、軌道兼用車、図書館車、郵便車、移動電話車、路上試験車、教習車、霊
柩車、広報車、放送中継車、理容・美容車
4-1-3 特種な目的に専ら使用するための自動車
特種な目的に専ら使用するため、次の①から③の全てを満足する自動車
① 次の(1)から(4)の区分に示す車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を運転者席以
外に有していること。
② 乗車設備及び物品積載設備を 大に利用した状態で、水平かつ平坦な面(以下「基準面」という。)
に特種な設備を投影した場合の面積(以下「特種な設備の占有する面積」(注10)という。)が1㎡
(軽自動車にあっては、0.6㎡)以上であること。
③ 特種な設備の占有する面積は、運転者席を除く客室の床面積(注11)及び物品積載設備の床面積並び
に特種な設備の占有する面積の合計面積の2分の1を超えること。
(1) 特種な物品を運搬するための特種な物品積載設備を有する自動車であって、車体の形状が次に掲げる
もの
粉粒体運搬車、タンク車、現金輸送車、アスファルト運搬車、コンクリートミキサー車、冷蔵冷凍車、
活魚運搬車、保温車、販売車、散水車、塵芥車、糞尿車、ボートトレーラ、オートバイトレーラ、ス
ノーモービルトレーラ
(2) 患者、車いす利用者等を輸送するための特種な乗車設備を有する自動車であって、車体の形状が次に
掲げるもの
患者輸送車、車いす移動車
(3) 特種な作業を行うための特種な設備を有する自動車であって、車体の形状が次に掲げるもの
消毒車、寝具乾燥車、入浴車、ボイラー車、検査測定車、穴堀建柱車、ウインチ車、クレーン車、く
い打車、コンクリート作業車、コンベア車、道路作業車、梯子車、ポンプ車、コンプレッサー車、農
業作業車、クレーン用台車、空港作業車、構内作業車、工作車、工業作業車、レッカー車、写真撮影
車、事務室車、加工車、食堂車、清掃車、電気作業車、電源車、照明車、架線修理車、高所作業車
(4) キャンプ又は宣伝活動を行うための特種な設備を有する自動車であって、車体の形状が次に掲げるもの
キャンピング車、放送宣伝車、キャンピングトレーラ
4-2 特種用途自動車等を次のように分類するものとする。
(1) 特種用途自動車
(2)以外の特種用途自動車等をいう。
(2) 貸渡特種用途自動車

(140)
運送法施行規則第52条の規定により許可を受けた特種用途自動車等をいう。
5 建設機械
建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に掲げる大型特殊自動車をいう。
6 自動車の用途等の区分に係る細部取扱い
(1) この通達に規定する自動車の用途等の区分を定量的に判断するに当たって必要な事項は、別途定める
(以下「細部取扱通達」という。)。
(2) 細部取扱通達において、本通達の規定を読み替えて適用する旨の規定がある場合にあっては、細部取
扱通達の規定により本通達の規定に適合するものと見なすものとする。
注1 物品積載設備
運転者席の後方にある物品積載装置(原則として、一般の貨物を積載することを目的としたものであ
って、物品の積卸しが容易にできる構造のもの。)をいう。
注2 物品積載設備の床面積
(1) 乗車人員の携帯品の積載場所と認められるもの、例えば後部トランク及び屋根上の物品積載装置の
床面積は、この場合の物品積載設備の床面積には含めないものとする。
(2) タイヤえぐり、蓄電池箱等の占める面積は、物品の積載に支障がない限り物品積載設備の床面積に
含めるものとする。
(3) 物品積載設備の上方開放部の面積が床面積より小さい構造の自動車にあっては、床面からの高さが
1m未満の箇所における 小開放部の水平面への投影面積をもって床面積とする。
(4) 物品積載設備が屋根及び側壁で覆われている自動車、例えばバン型の自動車の類にあっては、室内
高部と床面との中点を含む車室の断面積で大部分の床面に平行なものをもって床面積とする。
注3 乗車設備
運転者席の後方にある乗車設備をいう。
注4 乗車設備の床面積
(1) 運転者席の後方に設けられた座席の背あて後端から前方(前方を含む。)には物品が積載されない
構造の自動車にあっては、運転者席背あて後端(隔壁又は保護用の仕切のあるものにあってはその後
端。)から 後部座席の 後端までの大部分の床面に平行な距離に室内幅を乗じたものを床面積とす
る。
(2) 運転者席の後方に設けられた座席の前方又は側方に物品が積載される構造の自動車(この場合、積
載物品により安全な乗車が妨げられないよう、座席の前方又は側方に保護仕切等が必要である。)に
あっては、座席の床面への投影面積をもって床面積とする。ただし、次の床面は乗車設備の床面積に
含める。

(141)
(イ) 座席の前縁から250mmまでの床面(補助座席にあっては、座席を含む幅400mm、奥行650mmの床面)
(ロ) 乗車設備の一部として使用されることが明らかな床面。例えば保護仕切で囲まれた床面又は乗車
する人員の通路と認められる床面等。
注5 積載し得る貨物の重量
(1) 物品積載設備内に折りたたみ式又は脱着式の座席を備えた自動車にあっては、物品積載設備を 大
に利用した場合の 大積載量を指定する際に、 大積載量の基となる重量から乗車設備を 大に利用
した場合の乗車設備に乗車出来る人員の重量(脱着式の座席を備えた自動車にあっては、乗車設備を
大に利用した場合の乗車設備に乗車出来る人員の重量と脱着式の座席の重量との和)を減じた重量
をいう。
(2) 物品積載設備内に折りたたみ式及び脱着式の座席がなく、物品積載設備と乗車設備とが明確に区分
された自動車にあっては、 大積載量を指定する際に 大積載量の基となる重量をいう。
注6 脱着式座席
脱着して使用することを目的とした座席であり、工具等を用いることなく、容易に脱着ができ、かつ、
確実に装着ができる構造の座席をいう。
注7 主たる使用目的遂行に必要な構造及び装置を有し
車枠又は車体に、特種な目的遂行のための設備(「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等
における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け自技第234号、自整第262号)の指定部
品は、「特種な目的遂行のための設備」には該当しないものとする。)がボルト、リベット、接着剤又
は溶接により確実に固定されているものをいう。
なお、蝶ねじ類、テープ類、ロープ類、針金類、その他これらに類するもので取り付けられた設備は、
確実に固定されているものに該当しないものとする。
注8 型式認証等を受けた自動車
「型式認証等を受けた自動車」とは、次に掲げる各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の規定によりその型式について指定されたも
の
(2) 「自動車型式認証実施要領について(依命通達)」(平成10年11月12日付け自審第1252号)別添2
「新型自動車取扱要領」により新型自動車として届け出された型式のもの
(3) 「輸入自動車特別取扱制度について(依命通達)」(平成10年11月12日付け自審第1255号)別紙「輸
入自動車特別取扱要領」により輸入自動車特別取扱自動車として届け出された型式のもの
(4) 「並行輸入自動車取扱要領について」(平成9年3月31日付け自技第61号)別添「並行輸入自動車
取扱要領」(以下「並行輸入自動車取扱要領」という。)に基づく並行輸入自動車であって、並行輸

(142)
入自動車取扱要領により届出自動車との関連を判断するにあたり、上記(1)から(3)の型式と比較して
同一又は関連ありと判断したもの
注9 法令等
法律、政令、府令、省令及びこれらの規定に基づく告示並びに地方自治体が定める条例をいう。
注10 特種な設備の占有する面積
(1) 車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を基準面に投影した場合の面積をいう。
なお、車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備が格納式又は折りたたみ式の構造で
ある場合にあっては、これを格納又は折りたたんだ状態とする。
(2) 次の各号のいずれかに該当する部位及び当該部位に設けられた設備の基準面への投影面積は、特種
な設備の占有する面積には含めないものとする。
① 乗車人員の携帯品の積載箇所と認められるところ(トランク、ラゲッジスペース、インストルメン
ト・パネル、グローブボックス、トレイ、ルーフ・ラック等の各種ラック類等)
② 乗車装置の座席
③ 乗車装置の座席の上方又は下方(背あての角度が可変する座席にあっては、背あての角度は背あて
の支点をとおる垂直な面と背あてのなす角度は後方に30度(30度に保持できない場合は、30度に
も近い角度)とした場合の床面への投影面、座席が前後、左右に可変又は回転する場合は、可変又
は回転した状態で保持できるすべての位置における床面への投影面、折りたたみ式座席又は脱着式
座席にあっては、当該座席を乗車設備として利用したときの床面への投影面、これらの機能を併せ
持った座席にあっては、これらの要件のうち、該当するものすべてを組み合わせた状態における床
面への投影面とする。)
④ 乗車装置の座席の前縁から前方250mmまでの床面(座席が前後、左右に可変、回転、折りたたみ式
又は脱着式である場合にあっては、当該座席を利用できるすべての位置において、座席の前縁から
前方250mmまでの床面)
⑤ 特種な設備を基準面に投影した場合の部位と、物品積載設備を基準面に投影した場合の部位が重な
る部位
⑥ 当該自動車の修理等に使用する工具等を収納する荷箱
⑦ いかなる名称によるかを問わず、①から⑥と類似する部位
注11 運転者席を除く客室の床面積
(1) 運転者席の背あて後端(隔壁又は保護用の仕切のある場合にあっては、その後端)から乗車設備の
後部座席までを含む客室の後端(乗車設備の 後部座席より後方に物品積載設備又は特種な目的に専ら
使用するための設備を有する場合にあっては、乗車設備の 後部座席の背あて後端(隔壁又は保護用の
仕切がある場合には、その前端))までの車両中心線上における大部分の床面に平行な距離に室内幅を

(143)
乗じたものを客室の床面積とする。
この場合において、運転者席が前後に可変する座席にあっては、座席の位置は 後端とし、運転者席
の背あての角度が可変する座席にあっては、背あての角度は背あての支点をとおる垂直な面と背あてと
のなす角度は後方に30度(30度に保持できない場合は、30度に も近い角度)とする。
また、乗車設備の側方等に物品積載設備又は特種な目的に専ら使用するための設備を有する場合にあ
っては、上記にかかわらず、乗車設備の座席の床面への投影面積をもって客室の床面積とすることがで
きる。
この場合において、次の床面は客室の床面積に含むものとする。
(イ) 座席の前縁から250mmまでの床面(幅400mm、奥行400mm未満の補助座席にあっては、座席を含む幅
400mm、奥行650mmの床面)
(ロ) 乗車装置の一部として使用されることが明らかな床面。例えば保護仕切で囲まれた床面又は乗車
する人員の通路と認められる床面等。
(2) タイヤえぐり等の占める面積は、安全な乗車に支障がない限り、客室の床面積に含めるものとする。
(3) 客室の室内幅(乗車設備の側方等に物品積載設備又は特種な目的に専ら使用するための設備を有す
る場合を除く。)は、運転者席の背あて後端から客室の後端までの中間点における車両中心線に直交
する大部分の床面に平行な距離とする。

(144)
参考:平成13年改正(平成13年4月6日付け国自技第49号)の主文
現在、特種な用途に応じた設備を有する自動車を特種用途自動車として区分し、検査、登録において取り
扱っているところであるが、近年、検査時にはその設備を装備して登録し、その直後に当該設備を取り外し
て乗用自動車等と同じ仕様で不正に使用する事例が多発している。また、特種用途自動車として不正に検査、
登録を受けたとして、中古車販売業者が逮捕される事件も発生している。
このような不正使用の理由としては、①特種用途自動車は、乗用自動車等に比べ税、保険料が安いこと、
②現在規定されている特種用途自動車の構造要件が抽象的であること等があり、一方、これらを背景として、
検査時における自動車の用途の判定に当たって、申請者との間でトラブルが多発している状況にある。
こうした特種用途自動車の不正使用の防止及び検査時における自動車の用途の判定の適正化のため、特種
用途自動車の各車体形状毎に構造要件を具体的、かつ、詳細に定めるべく、パブリックコメントを募集した
ところ、多くの意見、要望があった。
これらの意見、要望も踏まえ、「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(昭和35年9月6日付
け自車第452号)(以下「用途区分通達」という。)の一部を別添新旧対照表のとおり改正することとし、
平成13年10月1日からこれにより実施することとしたので了知されるとともに、関係者を指導されたい。
ただし、改正後の用途区分通達4-1-3(4)のキャンピング車については、平成15年3月31日までは、
なお従前の例によることができることとする。
なお、平成13年9月30日(用途区分通達4-1-3(4)のキャンピング車については、平成15年3月
31日と読み替える。)において、特種用途自動車として既に登録を受けている自動車又は特種用途自動車
として車両番号の指定を受けている自動車にあっては、その自動車の構造・装置に変更がない限りにおいて
は、なお従前の例によることができることとする。

(145)
2

(146)

(147)
用途の判定用チェックシート(放送宣伝車 車体の形状コード:651)
(音声により放送宣伝を行う自動車)
年 月 日
車名 型式 車台番号
平床荷台が荷台部分の 1/2 を超えていないこと。(基本となった自動車の用途が「貨物」の場合に限る。裏面Ⅰ.参照)
構造要件及び現車の状態 構造要件への
適合性
放送設備
音声・音量等調整装置及びマイクロホンは、車室内に有しているか。 適・否
放送宣伝業務に従事する者の乗車設備の座席を有しているか。
この座席が固定された床面から上方には120㎝以上の有効高さを有しているか。
有効高さ( )cm≧120cm
適・否
車体の外側に、前後方向を指向した拡声器を有しているか。 適・否
ステージ又は資材置場
(どちらかの要件を満足すること)
ステージ
車体に設けられており、転落防止用の手すりを有しているか。 適・否
ステージの床面は連続した平面であり、かつ、滑り止めを施したものであるか。 適・否
ステージの床面から上方に有効高さ160㎝以上の空間を有するか。
有効高さ( )cm≧160cm 適・否
乗車設備からステージに至ることができる通路を有するか。 適・否
ステージが屋根部に設けられている場合にあっては、ステージに至るための安全に昇降で
きる階段、はしご等を有するか。 適・否
資材置場
車室内に設けられているか。 適・否
車室内の他の設備と隔壁、仕切棒等により明確に区分されているか。 適・否
物品積載設備を有していないか。 適・否
特種な設備の占有する面積は1㎡以上あるか。(裏面Ⅱ.参照) 適・否
特種な設備の占有する面積は1/2を超えているか。(裏面Ⅱ.参照) 適・否
終判定 放送宣伝車の構造要件
自動車検査証の有効期間
適 合 ・ 不適合
初回:2年・1年、2回目以降:2年・1年
終確認印
※ 終判定欄は、自動車検査官が総合判定で記入すること。

(148)
配置図等
Ⅰ.平床荷台に関する面積計算 ベース車の用途が「貨物」以外のときは計算不要
○ 荷台部分の面積
長さ(cm) 幅(cm) 面積(c㎡)
合 計(A)
○ 平床荷台の面積
項目 計算式等 面積(c㎡)
合 計(B)
・B / A =( )/( )=( )≦0.5 適・否
※ 平床荷台上方に、宙に浮いた状態で特種な設備を備えている場合、概ね0.5mを超えるもので有れば平床荷台に算定す
る。
Ⅱ.特種な設備に関する面積計算
○ 客室の床面積
客室内長(cm) 客室内幅(cm) 面積(c㎡)
合 計(A)
○ 特種な設備の占有する面積
項目 計算式等 面積(c㎡)
放送設備
放送宣伝業務に従事する者の乗車設
備の座席(1名分)
床面のステージ
屋根部のステージ
放送宣伝活動に必要な資材・機材を
収納する専用の置場
合 計(C)
・C-(屋根部のステージ)=( - ))= ≧ 10000 c ㎡ 適・否
・C/(A+B+C)=( /( + + )=( )> 0.5 適・否
※ 平床荷台上方に、宙に浮いた状態で特種な設備を備えている場合、概ね0.5mを目安に、以下であれば「特種な設備
の占有する面積」【C】、超えるものであれば「平床荷台の面積」として算定する。

(149)
3

(150)

(151)
(1) 車室内の他の設備と隔壁により区分された専用の場所に設けられた浴室設備及びトイレ設備の占める
面積は、「特種な設備の占有する面積」に加えることができる。
(2) 車室内が明らかに二重構造(注)である自動車(キャンプ時において屋根部を拡張させることにより
車室内が二重構造となる自動車を含む。)の上層部分に就寝設備を有する場合には、用途区分通達4-1
-3③の「運転者席を除く客室の床面積及び物品積載設備並びに特種な設備の占有する面積の合計面積」
に当該就寝設備の占める面積を加える場合に限り、「特種な設備の占有する面積」に当該就寝設備の占め
る面積を加えることができるものとする。
(3) 1(4)ただし書きの規定により、就寝設備と乗車装置の座席を兼用とする場合には、当該就寝設備のう
ちの乗車装置の座席と兼用される部分の2分の1は、「特種な設備の占有する面積」とみなすことができる。
(4) 1(5)に規定する格納式及び折りたたみ式の就寝設備であって、当該設備を展開又は拡張した部分の基
準面への投影面積が重複する場合は、その重複する面積の2分の1は、「特種な設備の占有する面積」と
みなすことができる。
5.構造要件に規定されていない任意の設備(乗車設備以外の座席(道路運送車両の保安基準の適用を受け
ない座席をいう。)及びテーブルに限る)は、その他の面積とし、その基準面への投影面積と1(5)に規定
する格納式及び折りたたみ式の就寝設備を展開又は拡張した部分の基準面への投影面積は、用途区分通達
4-1-3③の「運転者席を除く客室の床面積及び物品積載設備並びに特種な設備の占有する面積」に当
該就寝設備の重複する部分を加える場合に限り、「特種な設備の占有する面積」に当該就寝設備の重複する
2分の1を加えることができるものとする。
6.脱着式の設備は、走行中の振動等により移動することがないよう所定の場所に確実に収納又は固縛する
ことができるものであること。
7.物品積載設備を有していないこと。
(注)二重構造
ここでいう二重構造とは、上層部の 下部と上層部の投影面である床面との間のすべての位置において、
1,200mm以上の有効高さがあり、かつ、上層部の上面と屋根の内側との間のすべての位置において1,200mm
以上(上層部の上面が就寝設備である場合には500mm以上(就寝設備の一方の短辺から就寝設備の長手方
向に0.9mまでの範囲にあっては、0.3m以上))である構造のものをいう。
留意事項
・乗用自動車用又は貨物自動車用に製作された標準座席は、1(4)アに該当しないものとする。
・つなぎ目に穴・すき間があいているものは、1(4)イに該当しないものとする。
・脱着式の設備は、車両重量に含めるものとする。
・2(1)ウ及び2(2)キにおいて、「上方には有効高さ1,600mm以上の空間を有していること。」とあるのは、
キャンプ時において、車室を拡張させることができる構造のものであって、展開した状態において洗面
台等又は調理台等を利用するための床面から上方に有効高さ1,600mm以上の空間を有することとなる場
合を含むものとする。

(152)
用途の判定用チェックシート(キャンピング車 車体の形状コード:610)
年 月 日
検査日 年 月 日 車名 型式 車台番号
平床荷台が荷台部分の1/2を超えていないこと。(基本となった自動車の用途が「貨物」の場合に限る。裏面Ⅰ.参照)
構造要件及び現車の状態 構造要件へ
の適合性
就寝設備関係
構造
車室内に有しているか。
拡張式車室 : 有(屋根部・右側面・左側面・後面・その他( )) 適・否
乗車用座席と兼用の場合、座面及び背あて部が就寝設備になることを前提として製作された
ものか。 適・否
水平かつ平らであるか、連続した平面となっているか。 適・否
数
大人用就寝設備の数 = ( )人分 ≧ 乗車定員の1/3以上[端数は切り上げ]
[乗車定員3人以下の自動車は2人分][大人用が2人分以上ある場合に限り、子供用2人分で大人用1人分とみなす。]
適・否
寸法
大人用:長辺( )cm≧180cm 短辺( )cm≧50cm
上方の空間( )cm≧50cm[長手方向 90cm まで( )cm≧30cm]
小人用:長辺( )cm≧150cm 短辺( )cm≧40cm
上方の空間( )cm≧50cm[長手方向 90cm まで( )cm≧30cm]
適・否
格納式等
展開又は拡張した状態で就寝設備の構造要件を満足するか。
構造等 : 格納式 ・ 折りたたみ式 ・ 脱着式 適・否
格納式・折りたたみ式の就寝設備の端部は車体等に固定されているか。 適・否
格納式・折りたたみ式の就寝設備は、展開又は拡張するための専用のスペースがあるか。 適・否
脱着式の就寝設備は所定の場所に収納又は固縛できるか。
構造等 : 棚等に収納 ・ ベルト等で固定 ・ その他( )適・否
二層構造
上層部の 下部と床面との間隙は 120cm 以上あるか。( )cm 適・否
上層部の 下部と乗車装置の座面との間隙は 80cm 以上あるか。( )cm 適・否

(153)
水道設備
給水タンクの容量( )㍑≧10㍑ 排水タンクの容量( )㍑≧10 ㍑ 適・否
車室内において正対して容易に使用できる洗面台等を有しているか。 適・否
洗面台等に水を供給できる構造機能を有しているか。 (構造等: ) 適・否
洗面台等を利用するための場所は上方に有効高さ 160cm 以上の空間を有しているか。
( )cm≧160cm 適・否
炊事設備
調理台等は、30cm×20cm 以上の平面を有しているか。
長辺( )cm×短辺( )cm 適・否
コンロ等を有しているか。(設備名: ) 適・否
コンロ等の付近は耐熱性・耐火性であって、十分な換気が行えること。 適・否
常設のガスタンク等は車室内と隔壁で仕切られ、かつ、車外との通気が十分確保されており、損
傷を受ける恐れが少ない場所に取り付けられているか。 適・否
コンロ等の燃料配管は損傷を受けないよう確実に取り付けられているか、適当な覆いがあるか。 適・否
調理台等は正対して使用できるか。 適・否
調理台等を利用するための場所は 160cm 以上の有効高さであるか。
( )cm≧160cm 適・否
水道設備、炊事設備及びこれらの設備を利用するための場所の床面積は 0.5 ㎡以上あるか。
(裏面Ⅱ.③参照) 適・否
入浴設備及びトイレ設備は、車室内の他の設備と隔壁により区分された専用の場所に設けられているか。 適・否
物品積載設備を有していないか。 適・否
特種な設備の占有する面積は1㎡以上あるか。(裏面Ⅱ.参照) 適・否
特種な設備の占有する面積は1/2を超えているか。(裏面Ⅱ.参照) 適・否
終判定 キャンピング車の構造要件
自動車検査証の有効期間
適 合 ・ 不適合
初回:2年・1年、2回目以降:2年・1年
最終確認印
※最終判定欄は、自動車検査官が総合判定で記入すること。

(154)
配置図等
Ⅰ.平床荷台に関する面積計算 基本車の用途が「貨物」以外のときは計算不要
○ 荷台部分の面積
長さ(cm) 幅(cm) 面積(c㎡)
合 計(A)
○ 平床荷台の面積
項目 計算式等 面積(c㎡)
合 計(B)
・ B / A =( )/( )=( )≦ 0.5 適・否

(155)
Ⅱ.特種な設備に関する面積計算 ○ 客室の床面積
客室内長(cm) 客室内幅(cm) 面積(c㎡)
合 計(A)
○ 特種な設備の占有する面積
項目 計算式等 面積(c㎡)
就寝設備関係
専有部分 (固定式) (格納式) (二層構造)
座席と兼用部分 (×1/2)
小計(①)
ソファー、テーブルと重複する部分
(×1/2)
小計(②)
水道設備及び炊事設備
洗面台等
洗面台等を利用するための場所
調理台等
コンロ等
調理台等を利用するための場所
小計(③)
その他
浴室設備
トイレ設備
小計(④)
合 計(B)
・③( )c㎡≧5000c ㎡ 適・否
・B - ② = ( - )≧ 10000 c ㎡ 適・否
・B/(A+B)=( /( + ))=( )> 0.5 適・否
<参考>

(156)
用途の判定用チェックシート(キャンピング車 車体の形状コード:610)
平成25年 ○月 ×日
検査日 平成 25年○月×日 車名 ○○○○○ 型式△△△-
□□□□□車台番号 □□□□□-56789
平床荷台が荷台部分の1/2を超えていないこと。(基本となった自動車の用途が「貨物」の場合に限る。裏面Ⅰ.参照)
構造要件及び現車の状態 構造要件へ
の適合性
就寝設備関係
構造
車室内に有しているか。
拡張式車室 : 有(屋根部・右側面・左側面・後面・その他( )) 適・否
乗車用座席と兼用の場合、座面及び背あて部が就寝設備になることを前提として製作された
ものか。 適・否
水平かつ平らであるか、連続した平面となっているか。 適・否
数
大人用就寝設備の数 = ( 2 )人分
≧ 乗車定員の1/3以上[端数は切り上げ]
[乗車定員3人以下の自動車は2人分]
[大人用が2人分以上ある場合に限り、子供用2人分で大人用1人分とみなす。]
適・否
寸法
大人用:長辺( 185 )cm≧180cm 短辺( 50 )cm≧50cm
上方の空間( 120 )cm≧50cm[長手方向90cmまで( 120 )cm≧30cm]
小人用:長辺( )cm≧150cm 短辺( )cm≧40cm
上方の空間( )cm≧50cm[長手方向90cmまで( )cm≧30cm]
適・否
格納式等
展開又は拡張した状態で就寝設備の構造要件を満足するか。
構造等 : 格納式 ・ 折りたたみ式 ・ 脱着式 適・否
格納式・折りたたみ式の就寝設備の端部は車体等に固定されているか。 適・否
格納式・折りたたみ式の就寝設備は、展開又は拡張するための専用のスペースがあるか。 適・否
脱着式の就寝設備は所定の場所に収納又は固縛できるか。
構造等 : 棚等に収納 ・ ベルト等で固定 ・ その他( ) 適・否
二層構造
上層部の最下部と床面との間隙は120cm以上あるか。( )cm 適・否
上層部の最下部と乗車装置の座面との間隙は80cm以上あるか。( )cm 適・否
〔記載例〕

(157)
水道設備
給水タンクの容量( 10 )㍑≧10㍑ 排水タンクの容量( 10 )㍑≧10㍑ 適・否
車室内において正対して容易に使用できる洗面台等を有しているか。 適・否
洗面台等に水を供給できる構造機能を有しているか。 (構造等: 電動ポンプ ) 適・否
洗面台等を利用するための場所は上方に有効高さ160cm以上の空間を有しているか。
( 165 )cm≧160cm 適・否
炊事設備
調理台等は、30cm×20cm以上の平面を有しているか。
長辺( 35 )cm×短辺( 30 )cm 適・否
コンロ等を有しているか。(設備名: 電子レンジ ) 適・否
コンロ等の付近は耐熱性・耐火性であって、十分な換気が行えること。 適・否
常設のガスタンク等は車室内と隔壁で仕切られ、かつ、車外との通気が十分確保されており、損
傷を受ける恐れが少ない場所に取り付けられているか。 適・否
コンロ等の燃料配管は損傷を受けないよう確実に取り付けられているか、適当な覆いがあるか。 適・否
調理台等は正対して使用できるか。 適・否
調理台等を利用するための場所は160cm以上の有効高さであるか。
( 165 )cm≧160cm 適・否
水道設備、炊事設備及びこれらの設備を利用するための場所の床面積は0.5㎡以上あるか。
(裏面Ⅱ.②参照) 適・否
入浴設備及びトイレ設備は、車室内の他の設備と隔壁により区分された専用の場所に設けられているか。 適・否
物品積載設備を有していないか。 適・否
特種な設備の占有する面積は1㎡以上あるか。(裏面Ⅱ.参照) 適・否
特種な設備の占有する面積は1/2を超えているか。(裏面Ⅱ.参照) 適・否
最終判定 キャンピング車の構造要件
自動車検査証の有効期間
適 合 ・ 不適合
初回:2年・1年、2回目以降:2年・1年
最終確認印
※最終判定欄は、自動車検査官が総合判定で記入すること。

(158)
配置図等
Ⅰ.平床荷台に関する面積計算 基本車の用途が「貨物」以外のときは計算不要
○ 荷台部分の面積
長さ(cm) 幅(cm) 面積(c㎡)
315 165 51975
合 計(A) 51975
○ 平床荷台の面積
項目 計算式等 面積(c㎡)
設備以外 荷台部分 51975
乗車設備 160×100 -16000
浴室 120×90 -10800
洗面台、調理台及び電子レンジ 150×40 -6000
合 計(B) 19175
・ B / A =( 19175 )/( 51975 )=( 0.36 )≦ 0.5 適・否
浴室
洗面台、調理台及び電子レンジ
【就寝設備使用時】
160 155
165
150
185
100
就寝設備
90
40
120 100

(159)
Ⅱ.特種な設備に関する面積計算
○ 客室の床面積
客室内長(cm) 客室内幅(cm) 面積(c㎡)
160 165 26400
合 計(A) 26400
○ 特種な設備の占有する面積
項目 計算式等 面積(c㎡)
就寝設備関係
専有部分
(固定式)
(格納式)
(二層構造)
座席と兼用部分
(×1/2)
(185×100)×1/2 9250
小計(①) 9250
ソファー、テーブル
と重複する部分
(×1/2)
小計(②) 0
水道設備及び炊事設備
洗面台等 (調理台等及びコンロ等含む) 150×40 6000
洗面台等を利用する
ための場所 (調理台を利用するための場所を含む)150×35 5250
調理台等
コンロ等
調理台等を利用する
ための場所
小計(③) 11250
その他
浴室設備 120×90 10800
トイレ設備
小計(④) 10800
合 計(B) 31300
・③(11250)c㎡≧ 5000c㎡ 適・否
・B ≧ 10000 c㎡ 適・否
・B/(A+B)=(31300/(26400+31300))=(0.54)> 0.5 適・否

(160)
<参考>
キャンピング自動車の構造要件(旧基準) (平成8年4月1日~平成15年3月31日)
特種用途自動車等の車体形状であるキャンピング自動車は、次の各号に掲げる構造上の要件を満足する
ものであること。
1 車室(隔壁により外気と遮断された乗車空間をいい、車両の停止時に車体の一部を拡大することによ
って車室を拡張することができるものにあっては、車体を床面とするものに限り当該部分を含むものと
する。(※1)以下同じ。)内に居住することができるものであり、次の各号に掲げる要件を満足する就
寝設備を有すること。
(1) 就寝設備の構造及び寸法
① 就寝部位の上面部は水平かつ平ら(※2)である等、人が十分に就寝できる構造であること。
② 就寝部位の1人につき長さ1.8m、幅0.5m以上の連続した平面を有すること。
③ 1人当たりの就寝部位ごとに、就寝部位の上面部から上方に0.5m以上の空間を有すること。ただ
し、就寝部位の一方の短辺より就寝部位の長手方向に対し、0.9mの範囲までにあっては就寝する
ために必要な空間があればよい。
(2) 就寝設備の固定
① 就寝設備は走行中の振動等により移動することがないよう車体に確実に固定(※3)されている
こと。
② 就寝設備を格納できる構造のものは、格納した状態で走行中の振動等により移動することがない
よう確実に格納できること。
(3) 就寝設備の座席兼用
① 座席が就寝設備になることを前提に設計されている場合又は座席上にマットを載せる等により
平面を作り就寝設備とする場合に限り、就寝設備と座席を兼用することができる。ただし、運転
者席(運転者席と並列にある座席を含む。以下同じ。)は(3)②の場合を除き就寝設備と兼用する
ことはできない。
② 運転者席と就寝設備を兼用する場合は、運転者席と兼用する就寝設備を就寝設備にした状態で走
行することのできない構造の自転車でなければならない。
③ (3)①の場合を除き座席が平らになることをもって就寝設備としてはならない。
(4) 就寝設備の定員
乗車定員の3分の1以上(※4)の人が就寝することができる就寝設備を有すること(端数は切り
上げることとする。)ただし、乗車定員2人又は3人の自動車にあっては2人以上の就寝設備を有す
ること。
(5) 子供用就寝設備(※5)
(1)、(2)、(3)及び(4)の規定により就寝設備が2人分以上備えられている場合は、(1)、(2)及び(3)
の規定は子供用就寝設備について準用し、子供用就寝設備2人分をもって、就寝設備1人分とすること
ができる。(※6)この場合において、(1)②の規定中「1.8m」とあるのは「1.5m」と、「0.5m」とある
のは「0.4m」と、(1)③の規定中「0.5m」とあるのは「0.4m」と、「0.9m」とあるのは「0.8m」と読み

(161)
替える。
2 車室内に次の各号に掲げる要件を満足する水道設備及び炊事設備を有し、車室内において当該設備を
利用できるもの(※7)であること。
(1) 水道設備
水道設備とは、次の各号に掲げる要件を満足するものをいう。
① 10L以上の水を貯蔵できるタンク(※8)及び洗面台等(水を溜めることのできる設備をいう。
以下同じ。)を備え、洗面台等にタンクより水を供給できる構造機能を有していること。(※9)
② 10L以上の排水を貯蔵できるタンク(※10)を有していること。
③ 容易に使用することのできる位置にあること。
(2) 炊事設備
炊事設備とは、次の各号に掲げる要件を満足するものをいう。
① 調理台等調理に使用する場所(※11)で0.3m以上×0.2m以上の平面を有すること。
② コンロ等により炊事を行うために必要な熱量を得ることができること。
③ 火気等熱量を発生する付近は、発生した熱量により火災を生じない等十分な耐火性を有し、(※12)
窓、換気扇等により必要な換気が行えること。
④ LPガス等の燃料を使用し、LPガス容器等の常設の燃料タンク(※13)を備えるものにあって
は、燃料タンクの設置場所は室内と隔壁で仕切られ、かつ、車外との通気が十分に確保されてい
ること。
⑤ ④の燃料タンクについては、衝突等により衝撃を受けた場合に、損傷を受けるおそれの少ない場
所に取り付けられていること。
⑥ コンロ等に燃料を供給するための燃料配管は振動等により損傷を生じないよう確実に取り付けら
れ、損傷を受けるおそれのある部分は適当なおおいで保護されていること。
⑦ 容易に使用することのできる位置にあること。
(3) 水道設備及び炊事設備の固定
水道設備及び炊事設備は、走行中の振動等により移動することがないよう車体にボルト等により確
実に固定されていること。ただし、水道設備及び炊事設備の設置場所が他の部位と明確に区別できる
等専用の設置場所を有するものについては、取り外すことができる構造のものでもよい。
3 運転者席を 大限利用した状態で運転者席の背あての後縁(背あての角度は設計標準位置とする。)か
ら前方にある範囲を除く車室の面積のうち、就寝設備、水道設備及び炊事設備並びにそれらの施設を利
用するために必要な場所(※14)の占める面積(座席及び物品積載設備の占める面積を除く。ただし、
1.(3)の規定により座席と就寝設備を兼用するものにあっては、当該就寝設備の占める面積の半分を除く
ものとする。)の合計が2分の1以上あること。
【注釈】
(※1) 自動車の天井部を上方にせりあげて車室を拡大するもの(いわゆるポップアップルーフ)は車
室に含まれるが、トランクからテントを拡大する、自動車のバックドアを開放しテントを張るもの等は、
車体以外の部分を床面として利用するため車室には含まれない。
(※2) 就寝設備の上面の大部分が水平で平らであれば、凹凸をすべて否定するものでない。(ここで、

(162)
水平とは傾斜がないことをいい、平らとは平面度が高いことをいう。)
(※3) マジックテープにより確実に固定されるものは固定として認められるが、ひもによる固定方法
はひもをしめることから確実に固定される可能性は低く、固定方法として認めない。
なお、就寝設備と座席を兼用する場合に、マット等を座席の上面に敷く場合は固定する必要はない。
(※4) 乗車定員が10人のときは、10/3=3.3であることから、小数点以下を切上げて、4人の就寝設備が
必要。
(※5) キャンピング車の使用の一つとして家族で使われることを想定した場合、両親分の就寝部位が
備わっていれば、子供用として通常(大人分)の就寝設備を設ける必要がないため、一回り小さいもの
を設けることは合理的なことであり、これを通常の定員の算定とすることはできないことから、これが
2つあれば通常のものと同じく1人分として取り扱うこととしたものである。
(※6) 乗車定員が9人のときは、9/3=3であることから、3人の就寝設備が必要。このとき、通常の
就寝設備が2人分あり、かつ、子供用就寝設備が3つある場合は、2+3/2=3.5と就寝設備がトータル
で3つあることとなり、就寝定員を満たすこととなる。
(※7) 寝そべった状態でしか使用することのできないものは、水道設備又は炊事設備として認めない。
80㎝以上の高さが必要。
(※8) 水を貯蔵するタンクは、水道設備の一つであるものの直接的に利用するものでないことから、
天井又は床下等の場所に設置されていても差し支えないものとする。
(※9) 電動ポンプを有するものではなくともよいこととし、水のタンクを車両の上部に設置し重力を
利用して水を供給できるもの、手動のポンプ等により水を供給できるもの等も認める。
(※10) 排水を貯蔵するタンクを車両の外に設置するものは、そのまま排水口等に流すことと同じであ
り、タンクを設置する目的に反するものであることから、要件を満たすものとはいえない。
(※11) 調理に使用する場所を洗面台又はコンロの上部に板を敷くことにより確保するものは、調理に
使用する場所が固定的に備わっている場合に限り認める。
(※12) 炊事施設を利用した場合に、熱量により壁が溶ける等のおそれのないものをいう。炊事設備を
無理に設置した車両は、当該項目に注意する必要がある。
(※13) キャンプ用コンロ又はカセットコンロに使用されるカセット式ボンベは、常設の燃料タンクと
見なさない。
(※14) 就寝設備、水道設備及び炊事設備を利用するために立つ又は歩く場所並びに炊事を行うための
調理道具等を収納する棚、キャンプをする上で必要となる衣服を格納する家具類、シャワールーム等キ
ャンプを行うために必要な設備をいい、座席、物品積載設備等以外の場所を指す。

(163)
キャンピング自動車構造要件適合確認書
車名 型式 車台番号 作成者 電話 - -
1
就
寝
設
備
車室内で居住できる。(ボアアップ・ルーフは可、テント不可)
(1)
構造
・
寸法
① 上面 水平かつ平らである等、人が十分に就寝できる構造。
② 1人当たりの
連続した平面
長さ . m ≧1.8m(1.5m) ※ 括弧書きは子供の寸法
幅 . m ≧0.5m(0.4m)
③ 1人当たり上面部
からの上方空間
. m ≧0.5m(0.4m) ※ 括弧書きは子供の寸法
但し、長さ0.9m(0.8m)までの範囲は就寝するための必要な空間でよい。
(2)
固定
① 走行中、振動等により移動することがないよう車体に確実な固定。
② 格納構造は、格納した状態でも走行中の振動等により移動することがないよう車体に確実に格納できる。
(3)
座席
兼用
① 就寝設備になることを前提に設計した座席又はマットを載せ平面を作り就寝設備にできる。
ただし、運転車席と並列にある座席は(3)②の場合を除き兼用は不可。
② 運転者席と並列にある座席の兼用は就寝設備にした状態で走行できない。
③ (3)①の場合を除き、座席が平らになることをもって就寝設備にしていないか。
(4) 就寝設備の定員( )人≧乗車定員( )人÷3(端数は切下げ)但し、乗車定員2人、3人は2人以上
(5) 子供就寝設備(1)から(4)の規定により大人就寝設備が2人以上の場合、(1)、(2)、(3)を準用、子供就寝設備2人を1人
子供就寝設備定員( )人÷2 ((端数は切下げ)=大人就寝設備定員( )人)
2
水
道
設
備
・
炊
事
設
備
車室内で利用できる 水道設備及び炊飯設備を有する。
(1)
水道
設備
(3)
固定
①③ 容易に使用できる位置にある洗面台等(水の溜めることのできる設備。以下同じ。)への供給装置付
き水タンク( )L≧10L を有する。
②③ 容易に使用できる位置にある排水タンク( )L≧10Lを有する。
走行中に振動等により移動しないように車体にボルト等により確実に固定。(但し、他の部分と明確に区分
できる専用の設置箇所を有するものについては、取り外すことができる構造のものでもよい。)
(2)
炊事
設備
(3)
固定
① 調理台等調理場所の使用平面 ( . m)≧0.3m×( . m)≧0.2mを有する。
② 炊事を行うために必要な熱量を得ることができるコンロ等 (名称 )
③ 火気等熱量を発生する付近の、発生した
熱量により火災を生じない等の十分な構造
耐火構造( )
窓、換気扇等の換気構造装置等( )
④ ⑤
常設燃料
タンク
常設のLPガス容器等の燃料タンク(カセットボンベ、キャンプ用コンロ除く)を備え付けた場合
設置場所(位置) 各室の隔壁の仕切と車外との十分な通気の確保。
取付位置 衝突等により衝撃を受けた場合、損傷を受けるおそれが少ない。
⑥ コンロ等への
燃料供給配管
振動等により損傷を生じない確実な取付。
損傷を受けるおそれのある部分の適当な覆いによる保護。
⑦ 容易に使用することのできる位置にある。
走行中に振動等により移動しないように車体にボルト等により確実に固定。
但し、他の部分と明確に区分できる専用の設置箇所を有するものは、取り外し構造でもよい。
3
就
寝
面
積
〔車室の面積※1(①+②+③ . ㎡)〕×1/2≦ 〔キャンプ関係面積(①+② . ㎡)〕
① 水道・炊事設備の利用占有面積 ( ㎡)
② 就寝設備の面積(1(3)の兼用は1/2)( ㎡)
③ 座席・物品積載設備の占有面積 ( ㎡)
その他 製作平成6年4月1日以降の車の客室は、難燃材の使用が必要。 横向き、折り畳み以外は座席ベルトに注意。
① 就寝設備
② 水道設備 2-1 給水タンク
2-2 洗面台等
2-3 排水タンク
③ 炊事設備
・ 水道及び炊飯施設利用占有位置及び寸法(青色)
・ 就寝設備の位置及び寸法 (赤色)
・ 座席及び物品積載設備の位置及び寸法 (黄色)
※1 運転者席を 大限利用した状態で、運転者
席の背あての後縁(背あての角度は設計標準位置
とする。)から前方にある範囲を除く車室の面積
運 転
平面図

(164)
(4) 車いす移動車の構造要件について
車いすに着座した状態で乗降でき、かつ、車いすを固定することにより、専ら車いす利用者の移動の
用に供する自動車であって、次の各号に掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。
なお、特種な目的に使用するための床面積を算定するための設備には、車いすの利用者1人につき介
護人1人までの乗用設備を含めることができる。この場合における介護人の乗用設備は、車いすの近く
に設けられていること。
また、用途区分通達4-1(3)の規定は、本車体の形状には適用しないものとする。
1.車室には、車いすを確実に車体に固定することができる装置を有すること。
2.車いす利用者が容易に乗降できるスロープ又はリフトゲート等の装置を有すること。
3.車いすを固定する場所は、車いす利用者の安全な乗車を確保できるよう、必要な空間を有すること。
4.車いすに車いす利用者が着座した状態で、容易に乗降できる適当な寸法を有する乗降口を1ヶ所以
上設けられていること。
5.4の乗降口から1の車いす固定装置に至るための適当な寸法を有する通路を有すること。
6.車いす利用者の安全を確保するため、車いす利用者が装着することができる座席ベルト等の安全装
置を有すること。
7.物品積載装置を有していないこと。
留意事項
・車いすの利用者は乗車定員として算定するものとする。
・折りたたみ式座席等を設けている場所に設けられた車いす固定装置は、特種な目的に使用するため
の床面積を算定するための設備に含まないものとする。
審査事務規定(平成 14年 7月 1日 検査法人規定第 11 号)
第 55 次改正(平成 23 年 2月 23 日 改正)
施行 平成 23 年4月1日
第 2章 審査の実施方法
(略)
2-23 特種用途自動車の審査
(1) (略)
(2) 用途区分細部取扱い通達に規定する車いす移動車は、車いす利用者の安全な乗車を確保できる
ものとして乗降口及び車いす固定装置に至るまでの通路は、有効幅 440mm 以上、有効高さ 1130mm
以上、車いすを固定する場所は、有効長さ 700mm 以上、有効幅 440mm 以上、有効高さ 1130mm 以
上であること。ただし、新規検査又は構造等変更検査において、当該自動車の車いす利用者の安
全な乗車を確保することが確認できる写真の提出又は当該自動車による車いす利用者の乗車が確
認できる場合にあっては、この限りでない。

(165)

(166)

(167)
用途の判定用チェックシート(車いす移動車 車体の形状コード:531)
平成25年 ○月 ×日
車名 ○○○○○ 型式 △△△-□□□□□ 車台番号 □□□□□-12345
構造要件及び現車の状態 構造要件へ
の適合性
車いす固定装置を有しているか。 車いす固定装置( 1 )基 適・否
車いす利用者が、車いすに着座した状態で乗降することができるスロープ又はリフトゲート等を固定設
備として有するか。
装置名: スロープ ・ リフトゲート ・ その他( )
適・否
乗降口から車いす固定装置に至るための適当な寸法(有効幅44cm以上・有効高さ113cm以上)を有
する通路を有するか。 適・否
車いすを固定する場所は、車いす利用者の安全な乗車を確保できるよう、必要な空間を有するか。
有効長さ(110)cm≧70cm 有効幅( 80)cm≧44cm 有効高さ(130)≧113cm 適・否
車いす利用者が、車いすに着座した状態で容易に乗降できる適当な寸法を有する乗降口が1ヶ所以上あ
るか。 有効幅(100)cm≧44cm 有効高さ(120)cm≧113cm
乗降口の位置: 左側面 ・ 右側面 ・ 後面
適・否
車いす利用者のための安全装置(座席ベルト・ヘッドレスト等)を有するか。
座席ベルト:2点・3点・その他( )
ヘッドレスト:車両側 ・ 車いす側
適・否
物品積載設備を有していないか。 適・否
特種な設備の占有する面積は1㎡以上あるか。(裏面参照) 適・否
特種な設備の占有する面積は1/2を超えているか。(裏面参照) 適・否
最終判定 車いす移動車の構造要件
自動車検査証の有効期間
適 合 ・ 不適合
初回:2年・1年、2回目以降:2年・1年
最終確認印
※最終判定欄は、自動車検査官が総合判定で記入すること。
〔記載例〕

(168)
配置図等
特種な設備に関する面積計算
○ 客室の床面積
客室内長(cm) 客室内幅(cm) 面積(c㎡)
160 155 24800
(介護人席)80 45 -3600
合 計(A) 21200
○ 特種な設備の占有する面積
項目 計算式等 面積(c㎡)
車いすの占有する面積(注1)
スロープ又はリフトゲート等 150×125 18750
通路
介護人座席(注2) 80×45 3600
合 計(B)≧ 10000 c㎡ 22350
・B ≧ 10000c㎡ 適・否
・B/(A+B)=(22350)/(21200+22350)=(0.51)> 0.5 適・否
注1:折りたたみ式座席等を設けている場所に設けられた車いす固定装置は、特種な設備の占有する面積に当たらない。
注2:車いす利用者1人につき1座席に限る。
160 150
80
155
45
リフト、車いす固定装置
介護人座席
125

(169)
(5) 車両運搬車の構造要件について
自 技 第 1 5 4 号
自 技 第 2 5 0 号
平 成 10 年 12 月 9 日
車両運搬車構造要件
1.適用範囲
この構造要件は、専ら車両運搬用として使用する自動車に適用する。
2.全ての車両運搬車に適用される構造要件
2-1 荷台
荷台は、積載した車両の車輪を支持する床板、道板又は車輪支持枠等の床面を有し、確実に車
両を積載できるものであること。
2-2 輪止め
2階式荷台を有するものにあっては、2階の床面最前部付近に積載した車両を固定する輪止め
若しくはタイヤ落し(くぼみ)を設けるか、又は輪止めが取り付けられる構造であること。
2-3 後部扉
リヤオーバハングが最遠軸距の1/2を超える自動車にあっては、当該自動車の床面の後部に次
の構造を有する扉を設けること。ただし、床面が複数ある自動車にあっては、最後部の車軸中心
から床面の後端までの水平距離が最遠軸距の1/2以下の床面を除く。
(1) 後部扉は、積載した車両の一部が後方に突出しない構造であること。
(2) 後部扉の高さは、各階床面に車両を積載した状態において、当該床面より 450mm 以上である
こと。
(3) 道板として機能する後部扉にあっては、左右対称であり、かつ、荷台内幅寸法の 30%以上の
幅を有すること。
(4) 後部扉取付用の丁番は車体本体及び後部扉と溶接し、かつ、その丁番ピンも溶接する等によ
り取り外しできない構造であること。ただし、道板として機能する後部扉にあっては丁番ピン
の溶接は行わなくてもよい。
(5) 後部扉の後面に自動車登録番号標を取り付けること。ただし、車両運搬トラクタ(車両運搬
セミトレーラをけん引するトラクタであって、車両積載装置を有するものをいう。)及びセンタ
ーアクスル型車両運搬フルトレーラ(車両積載装置を有するトレーラであって、垂直方向に非
可動のけん引装置を有し、かつ、トレーラの車両総重量の 10%又は 10kN のいずれか小さい方
の値以下の垂直荷重しかトラクタに伝達されないように、均等に積荷された自動車の重心付近
に車両が配置されたものをいう。)をけん引するトラクタにあってはこの限りでない。

(170)
2-4 後部反射器
前項に規定する後部扉を有する自動車であって、道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」
という。)第 38 条第2項に規定する後部反射器を車体に取り付けることが困難な自動車にあって
は、当該反射器を後部扉に取り付けることができる。
なお、車両を積み卸しする際に支障をきたすため、当該反射器を回転する構造の自動車にあっ
ては、容易に保安基準第 38 条第2項の規定に適合する状態にすることができる構造であり、かつ、
走行中振動等により損傷しない構造であること。
2-5 後面に備える灯火器等の表示
自動車の後面に備える尾灯、非常点滅表示灯及び後部反射器のうち1組以上は、後部扉以外の
場所に取り付けられていること。
なお、駐車灯を備える場合にあっては、当該灯火は後部扉以外の場所に取り付けられているこ
と。
2-6 自動車登録番号標の表示
車両を積み卸しする際に支障をきたすため、自動車登録番号標を回転する構造のものにあって
は、走行状態においては、見易い位置に確実に固定できる構造であること。
2-7 緊締装置
積載した車両を確実に固定できる緊締装置が取り付けられる構造であること。
3.1階スライド荷台式車両運搬車の構造要件
1階スライド荷台式車両運搬車(1階式の車両運搬車であって、車両の積み卸しを容易にするため、
荷台を油圧等により後方へ傾斜スライドさせる機能を有したものをいう。)であってリヤオーバハングが
最遠軸距の1/2を超える自動車にあっては、前項の規定によるほか、次の要件に適合するものであるこ
と。
3-1 荷台あおり
荷台あおりの高さが 150mm であること。
3-2 床面
車両以外の物品が容易に積載できないよう開口部分を有するもの、又は孔明板等を使用するこ
と。
3-3 警報装置
荷台が所定の位置に格納されていない場合は、その旨を運転者席の運転者に警報するブザ、又
はパイロットランプ等の装置を備えていること。
3-4 「車載専用車」の表示
荷台両側面の見易い箇所にステッカー等により「車載専用車」の表示がされていること。
なお、1文字の大きさは幅 55mm 以上、高さ 55mm 以上とすること。
4.車両運搬トラクタ(通称、亀の子型トラクタ)の構造要件
車両運搬トラクタは、第2項の規定によるほか、次の要件に適合するものであること。

(171)
4-1 カプラオフセット
カプラオフセットは、原則として標準車と同一であること。
4-2 最大積載量及び第5輪荷重の表示
車体の後面には、最大積載量及び第5輪荷重を表示すること。
4-3 注意事項の表示
運転者席の見易い箇所にステッカー等により次の内容を表示すること。
(例)① このトラクタは、車両運搬専用であること。
② 単車で運行する場合は車両を積載しないこと。
③ 車両の前端より突出して車両を積載しないこと。
④ 積載時の高さが地上 3.8mを超えないこと。
⑤ 積載する車両の重量は〇〇〇〇kgを超えないこと。
5.車両運搬セミトレーラの構造要件
車両運搬トラクタによりけん引される自動車重量税課税対象車両運搬セミトレーラは、第2項の規定
によるほか、メーンフレーム左側前方の見易い箇所にコーションプレートにより次の内容を表示するこ
と。
(例) 「この車両運搬用セミトレーラは、自動車重量税課税対象車両です。」
6.センターアクスル型車両運搬フルトレーラをけん引するトラクタの構造要件
センターアクスル型車両運搬トレーラをけん引するトラクタであって、車両積載装置を有するものは、
第2項の規定によるほか、次の要件に適合するものであること。
6-1 警報装置
トラクタの単体走行時において、後部扉が有効に機能していない場合には、その旨を運転者席
の運転者に警報するブザー、又はパイロットランプ等の装置を備えていること。
6-2 注意事項の表示
運転者席の見易い箇所にステッカー等により次の内容を表示すること。
(例) ① このトラクタ及びセンターアクスル型車両運搬フルトレーラは、車両運搬専用であ
ること。
② 単車で運行する時は、自動車後面より突出して車両を積載しないこと。
③ センターアクスル型車両運搬フルトレーラは、荷台の前方又は後方に片寄って車両
を積載して走行しないこと。
④ センターアクスル型車両運搬フルトレーラのみに車両を積載して走行しないこと。
⑤ 積載時の高さが地上 3.8mを超えないこと。
以上

(172)
車両運搬車後部扉構造基準
1.後部扉はその間際より積載物の一部が後方に突出しない構造とする。
2.後部扉の高さは積載状態の上床々面の上限より 450mm 以上とする。
3.後部扉取付用の丁番は車体本体および後部扉と溶接し且つその丁番ピンも上下溶接する等により取外
しできない構造とする。
4.後部扉の下部後面に登録番号標を取付けることとし、後部扉を取外し、または全開放のまま運行でき
ない構造とする。
車両運搬車トラクタ及びトレーラ等構造要件の概要
車種別 車種ごとの構造要件 共通構造要件
1.1階スライド荷台式
(例図1)
対象1/2Wを超える車両に対する規
定
① 側面煽り高さは 150mm 以下
② 床面は次のいずれかの構造とす
る。
イ.開口部を有する。
ロ.積載車両の車輪を載せる道板等
により構成
ハ.車輪を載せる床面以外は網状又
は床面を有しない
③ 警報装置
運転者席にパイロットランプま
たはブザー等を備え、スライド荷台
が規定の位置に格納できていない
場合に警報を発するものであるこ
と。
④ 表示
荷台両側面の見易い箇所に「車載
専用車」と表示すること。(1文字
の大きさ 幅×高さ 55mm 以上)
1.荷台
積載車両を床板、道板又は車輪支
持枠等の床面に確実に積載できる
こと。
2.輪止め
2階式荷台の最前部に積載する
車両には、車両固定用の輪止め又は
タイヤ落としを設けること。なお、
輪止めは脱着式でもよい。
3.後部扉
リヤオーバーハングが1/2を超
えるものについては、次の後部扉を
設けること。
① 積載車両が後方に突出できな
い。
② 扉の高さは床面より 450mm 以
上
(各階の床面いずれも)
③ 道板と扉が共用のものは、左右
対称であり、かつ各道板の幅寸法
は、荷台内のり寸法の 15%以上
であること。(トラクタは除く)
④ 扉取付部丁番と本体とは溶接
構造であり、かつ、丁番のピンも
取外しのできない溶接加工であ
ること。
2.車両運搬トラクタ
(通称亀の子型トラ
クタ)
(例図3)
① 対象シャシの限定
カーメーカの標準トラクタを使
用するものであって、普通型トラッ
ク、タンプ車等の改造車でないこ
と。
② カプラのオフセット
標準車の数値を原則とする。

(173)
③ 積載量等の表示
最大積載量及び第5輪荷重を表
示すること。
④ コーションラベルの表示
運転者席の見易い箇所にトラク
タ使用上の注意事項を表示するこ
と。
ただし、道板と共用型の丁番ピ
ンは溶接不要。
⑤ 自動車登録番号表は扉に取付
けること。(トラクタを除く)
4.大型後部反射器
積載物の積卸しに支障があるた
め反射器が回転する構造のものは、
作業終了後走行状態において、保安
基準に適合する状態に容易に復す
る構造のものであること。
5.後面の灯火器等
次の灯火器それぞれ1組は、扉以
外の車体に取付けること。なお、駐
車灯を取付ける場合も同様とする。
尾灯、非常点滅表示灯、後部反射
器
6.自動車登録番号標の表示
番号標が積載物の積卸しに支障
があるため回転する構造のものは、
走行状態においても適法な位置等
に容易に復し、固定されるものであ
ること。
7.緊締装置
積載車両を確実に固定できる緊
締装置を有するものであること。
3.車両運搬セミトレー
ラ
(例図4)
車両運搬トラクタ(亀の子)によりけ
ん引されるセミトレーラには、メーン
フレーム左側面前方の見易い箇所に、
自動車重量税課税対象車両である旨
のコーションプレートを取付けるこ
と。
4.センターアクスル型
フルトレーラをけん
引するトラクタ
(例図5)
車両積載装置を有する本トラクタに
は、次の装置等を有すること。
① 警報装置
トラクタ単体で走行態勢に入る
際、後部扉装置が作動しないときは
その旨運転者席にパイロットラン
プまたはブザーにより警報するも
のであること。
② コーションラベルによる表示
突出して車載しないこと、けん引
時の車載条件、フルトレーラの車載
方法等トラクタ運転時の注意事項
等を運転者席に表示すること。
5.センターアクスル型
車両運搬フルトレー
ラ
(例図5)
① ドローバーの構造は、トレーラの
フレームと一体化された非可動の
ものであること。
なお、連結部に加わる垂直方向の
荷重は、10kN 又は当該トレーラの
総重量の 10%以下であること。
② 車軸(センターアクスル)の位置
は、積荷を均等に積載した状態にお
いて、その重心位置付近に配置され
たものであること。

(174)
(例図1) 1階スライド荷台式
(例図2) 単車(2階式)
(例図3) 亀の子型トラクタ+セミトレーラ
(例図4) トラクタ+セミトレーラ
(例図5) センターアクスル型フルトレーラ&トラクタ

(175)
(6)

(176)
教習車等の用途、車体の形状の変更に係る取扱い
(1) 用途区分通達4-1-2に掲げる自動車のうち車体の形状が教習車又は路上試験車であり、使用者の
みの変更に伴う用途、車体の形状の変更であって、次の各号のいずれかの変更に該当する場合においては、
法第67条第3項に定める「保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき」に該当しないものとし
て取り扱うものとする。
(ア) 使用者の変更前、変更後に係わらず、助手席に補助ブレーキを装備している場合(補助ブレーキに変更
がない場合)
この場合において、使用者の変更後における車体の形状を路上試験車又は教習車としようとする場合に
あっては、変更後の使用者が、それぞれの構造要件の留意事項で規定している使用者の事業等を特定する
ための書面の提出がある場合に限る
(基本車が乗用自動車である場合に限る) 路上試験車又は教習車⇔ 乗用自動車の各車体の形状
(基本車が乗合自動車である場合に限る) 路上試験車又は教習車⇔ 乗合自動車の各車体の形状
(基本車が貨物自動車である場合に限る) 路上試験車又は教習車⇔ 貨物自動車の各車体の形状
教習車⇔ 路上試験車
(イ) 使用者の変更後は、助手席に補助ブレーキを装備していない場合(補助ブレーキを取り外した場合)
(基本車が乗用自動車である場合に限る) 路上試験車又は教習車⇒ 乗用自動車の各車体の形状
(基本車が乗合自動車である場合に限る) 路上試験車又は教習車⇒ 乗合自動車の各車体の形状
(基本車が貨物自動車である場合に限る) 路上試験車又は教習車⇒ 貨物自動車の各車体の形状
注1 教習車又は路上試験車から変更した後の車体の形状は、基本車の用途及び車体の形
状とする。
注2 基本車とは、用途区分通達注8の型式認証等を受けた自動車をいう。
(2) 助手席に補助ブレーキを装備して、車体の形状を路上試験車又は教習車に変更する次の場合にあっては、
法第67条第3項に定める「保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき」に該当するものとして、
構造等変更検査を命ずるものとする。
乗用自動車(補助ブレーキ無)⇒ 路上試験車又は教習車
乗合自動車(補助ブレーキ無)⇒ 路上試験車又は教習車
貨物自動車(補助ブレーキ無)⇒ 路上試験車又は教習車

(177)
(7)

(178)

(179)

(180)
(8)
自 技 第 6 号
平成15年4月8日

(181)

(182)
自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時における取扱いの概要(参考)
部品区分
取付区分
長 さ 高 さ 幅 車 両 重 量
指定部品 指定外部品 指定部品 指定外部品 指定部品 指定外部品 指定部品 指定外部品
手による取付 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ボルト、ナッ
ト、接着剤等
による取付
○
±3cmまで
○
○
±4cmまで
○
○
±2cmまで
○
○
軽、小型にあっては±50㎏ま
で、普通、大型特殊にあって
は100㎏まで
○
溶接、リッベッ
トによる取付 ±3cmまで ○ ±4cmまで ○ ±2cmまで ○
軽、小型にあっては±50 ㎏まで、普通、
大型特殊にあっては100㎏まで ○
注)表中の「○」は、記載事項の変更又は構造等
変更検査の手続きが不要であることを示す。
【複数の自動車部品が装着されている場合の取扱い】
取付区分/部品区分 指定部品 指定外部品 通 用
手による取付 A B ケース1.A、B又はC若しくはその組合せ ケース2.D、E又はF若しくはその組合せ
ボルト、ナット、接着
剤等による取付 C D
○ 全ての部品の装着に伴う寸法、車両重量の
変化が通達で定める範囲内 ○ 溶接、リッベットによ
る取付 E F
注)表中の「○」は、記載事項の変更又は構造等変更検査の手続きが不要であることを示す。
(b-a)
(b-a)
(b-a)

(183)

(184)

(185)
(9) 自動車NOx・PM法について
大都市地域における窒素酸化物(NOx)による大気汚染は依然として深刻な状況が続いています。こ
れまでも、工場等に対する規制や自動車排出ガス規制の強化に加え、自動車NOx法(平成4年)に基づ
いて特別の排出基準を定めての規制(車種規制)をはじめとする対策を実施してきましたが、自動車の交
通量の増大等により、対策の目標とした二酸化窒素に係る大気環境基準をおおむね達成することは困難な
状況です。
一方、浮遊粒子状物質による大気汚染も大都市地域を中心に環境基準の達成状況が低いレベルが続くと
いう大変厳しい状況で、特に、近年、ディーゼル車から排出される粒子物質(PM)については、発がん
性のおそれを含む国民の健康への悪影響が懸念されています。このため、窒素酸化物に対する従来の対策
を更に強化するとともに、自動車交通から生ずる粒子状物質の削減を図るために新たな対策を早急に講ず
ることが強く求められています。
こうした背景を受けて、平成13年6月に自動車NOx法の改正法(自動車NOx・PM法)が成立しま
した。
この法律には、一定の自動車に関して、より窒素酸化物や粒子状物質の排出の少ない車を使っていただ
くよう、「車種規制」という規制が盛り込まれています。この規制によって、大都市地域で所有し、使用で
きる車が制限されています。
このような対策の実施には、皆様のご協力が不可欠です。大都市の大気汚染の改善のため、よろしくご
理解とご協力をお願いします。
二酸化窒素(NO2)
高濃度で呼吸器に悪い影響を与えるほか、酸性雨や光化学オキシダントの原因物質になると言われてい
ます。
浮遊粒子状物質(SPM)
大気中に長時間留まり、高濃度で肺や気管などに沈着して呼吸器に悪い影響を与えるほか、発がん性の
おそれが指摘されています。

(186)
車種別排出基準値一覧表
車種規制とは、自動車NOx・PM法の窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域(以下「対策地域」
といいます。)に指定された地域で、トラック・バス等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)及びディ
ーゼル乗用車に関して特別の窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準(以下「排出基準」といいます。)
を定め、これに適合する窒素酸化物及び粒子状物質の排出量がより少ない車を使っていただくための規制
です。この規制は対策地域内に使用の本拠の位置を有する新車と現在使用している車について適用されま
す。「使用の本拠の位置」については車検証をご参照ください。
<排出基準>
ディーゼル乗用車 NOx:0.48g/km(昭和53年規制ガソリン車並)
PM:0.055g/km(注)
バス・トラック等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)
車
両
総
重
量
区
分
1.7t以下 NOx:0.48g/km(昭和63年規制ガソリン車並)
PM:0.055g/km(注)
1.7t超2.5t以下 NOx:0.63g/km(平成6年規制ガソリン車並)
PM:0.06g/km(注)
2.5t超3.5t以下 NOx:5.9g/kWh(平成7年規制ガソリン車並)
PM:0.175g/kWh(注)
3.5t超 NOx:5.9g/kWh(平成10年、平成11年規制ディーゼル車並)
PM:0.49g/kWh(平成10年、平成11年規制ディーゼル車並)
(注)中央環境審議会第4次答申(平成12年)において、新長期規制(平成17年から実施)については、
新短期規制の2分の1程度より更に低減した規制値とすることが適当であるとされていることを踏ま
え、新短期規制(平成14年から実施)の2分の1の値としております。
この法律に基づく車種規制の他、自治体によっては独自の規制を行っている場合がありますので御注意下
さい。

(187)
「車種規制」が適用されている地域はどこですか?
車種規制が適用されるのは、自動車NOx・PM法の適用される対策地域です。対策地域は以下の要件を
同時に満たすことを指定の考え方の基本としています。
① 自動車交通が集中していること。
② 大気汚染防止法等による従来の措置(工場・事業場に対する排出規制及び自動車1台ごとに対する
排出ガス規制等)だけでは、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準の確保が困難であ
ること。
(注)窒素酸化物対策地域と粒子状物質対策地域とは同一のものとなっています。
対 策 地 域 < 首 都 圏 >
埼 玉 県
さいたま市、川越市、熊谷市(旧妻沼町、旧江南町を除く)、川口市、行田市、所沢市、
加須市、本庄市(旧児玉町を除く)、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、
深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、
和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、
幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、川島町、吉見町、
上里町、騎西町、宮代町、白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町、松伏町
千 葉 県
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、
八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、白井市
東 京 都
特別区(23区)、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市
町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、
東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、
西東京市、瑞穂町、日の出町
神奈川県
横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、
相模原市(旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町を除く)、三浦市、秦野市、厚木市、大和市
伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町
愛川町

(188)
対 策 地 域 < 愛 知 ・ 三 重 圏 >
愛 知 県
名古屋市、豊橋市、岡崎市(旧額田町を除く)、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、
豊川市(旧一宮町を除く)、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、
旧足助町、旧下山村、旧旭町及び旧稲武町を除く)、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、
常滑市、江南市、小牧市、稲沢市(旧祖父江町を除く)、東海市、大府市、知多市、知立市、
尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市(旧立田村及び旧八開村を除く)、
清須市、北名古屋市、弥富市、東郷町、長久手町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、
七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、武豊町、幸田町
三好町、音羽町、小坂井町、御津町
三 重 県 四日市市、桑名市(旧多度町を除く)、鈴鹿市、木曽岬町、朝日町、川越町
対 策 地 域 < 大 阪 ・ 兵 庫 圏 >
大 阪 府
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、
枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、
和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、
泉南市、四条畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、忠岡町、熊取町、田尻町
兵 庫 県
神戸市、姫路市(旧家島町、旧夢前町、旧香寺町、旧安富町を除く)、尼崎市、明石市、
西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、播磨町、太子町
※ 平成19年10月現在の行政区画により表示された区域です。
市町村合併があった場合でも区域に変更はありません。

(189)
これらの地図は、国土地理院長の
承認を得て、同院発行の数値地図
25000(行政界・海岸線)を複
製したものである。(承認番号
平13総複、第136号)

(190)
排出ガス規制区分別排出基準一覧表
排出基準に適合していない車は平成14年10月1日以降、対策地域内で登録できません。
すでに使用している車(使用過程車)については、その車種及び初度登録日(新車として登録された日)に
応じて定められる猶予期間を超えると車検に通らなくなります。
車 両 総 重 量
デ ィ ー ゼ ル 車
窒素酸化物等排出基準 〔測定モード〕
排出ガス規制区分(型式の識別記号) 適
否
ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス
1.7t以下 NOx:0.48(0.25)g/㎞
PM:0.055(0.026)g/㎞
〔10.15〕
平成14年規制適合車(KP-、HW-)
平成9年規制適合車(KE-、HA-)
平成5年規制適合車(KA-) 昭和63年規制適合車(S-) 昭和58年規制適合車(P-) 昭和57年規制適合車(N-) 昭和54年規制適合車(K-)
昭和52年度規制以前(記号なし)
×
×
×
×
×
×
×
1.7t超
2.5t以下
NOx:0.63(0.40)g/㎞
PM:0.06(0.03)g/㎞
〔10.15〕
平成15年規制適合車(KQ-、HX-)
平成10年規制適合車(KJ-、HE-)
平成9年規制適合車(KF-、HB-) 平成5年規制適合車(KB-) 昭和63年規制適合車(S-) 昭和58年規制適合車(P-) 昭和57年規制適合車(N-) 昭和54年規制適合車(K-)
昭和52年度規制以前(記号なし)
×
×
×
×
×
×
×
×
×
2.5t超
3.5t以下
NOx:5.9(4.50)g/kWh
PM:0.175(0.09)g/kWh
〔D13〕
平成15年規制適合車(KR-、HY-)
平成9年規制適合車(KG-、HC-) 平成6年規制適合車(KC-) 昭和63年規制適合車(S-) 昭和58年規制適合車(P-) 昭和57年規制適合車(N-) 昭和54年規制適合車(K-)
昭和52年度規制以前(記号なし)
×
×
×
×
×
×
×
×
3.5t超
NOx:5.9(4.50)g/kWh
PM:0.49(0.25)g/kWh
〔D13〕
平成16年規制適合車(KS-、HZ-)
平成15年規制適合車(KR-、HY-)
平成11年規制適合車(KL-、HM-) 平成10年規制適合車(KK-、HF-)
平成6年規制適合車(KC-)
平成2年規制適合車(W-)
平成元年規制適合車(U-)
昭和58年規制適合車(P-) 昭和57年規制適合車(N-) 昭和54年規制適合車(K-)
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
乗 用 車
NOx:0.48(0.25)g/km
PM:車両重量1265kg以下
0.055(0.026)g/km
車両重量1265kg超
0.055(0.028) g/km
〔10.15〕
平成14年規制適合車(KM-、KN-、HT-、HU-)
平成10年規制適合車(KH-、HD-)
平成9年規制適合車(KE-、HA-) 平成6年規制適合車(KD-)
平成4年規制適合車(Y-)
平成元年規制適合車(X-)
昭和61、62年規制適合車(Q-) 昭和57年規制適合車(N-) 昭和54年規制適合車(K-)
昭和52年規制以前(記号無し)
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

(191)
具体的には排出基準を満たしている車は次の通りです。
(注)トラック・バス等についてはガソリン車・LPG車でも、排出基準に適合しない場合がありますのでご注意下さい。
ガソリン・LPG車
窒素酸化物等排出基準 〔測定モード〕
排出ガス規制区分(型式の識別記号) 適否
NOx:0.48(0.25)g/km
〔10・15〕
平成12年規制適合車(GJ-、HP-)
10年アイドリング規制適合車(GG-、HL-)
昭和63年規制適合車(R-)
昭和56年規制適合車(L-)
昭和54年規制適合車(J-)
昭和50年規制適合車(H-)
昭和48年規制適合車(記号なし)
○
○
○
×
×
×
×
NOx:0.63(0.40)g/km
〔10・15〕
平成13年規制適合車(GK-、HQ-)
平成10年規制適合車(GC-、HG-)
平成6年規制適合車(GA-)
平成元年規制適合車(T-)
昭和56年規制適合車(L-)
昭和54年規制適合車(J-)
昭和50年規制適合車(H-)
昭和48年規制適合車(記号なし)
○
○
○
×
×
×
×
×
NOx:5.9(4.50)g/kwh
〔G13〕
平成13年規制適合車(GK-、HQ-)
平成10年規制適合車(GE-、HJ-)
平成7年規制適合車(GB-)
平成4年規制適合車(Z-)
平成元年規制適合車(T-)
昭和57年規制適合車(M-)
昭和54年規制適合車(J-)
昭和52年規制適合車(記号なし)
○
○
○
×
×
×
×
×
NOx:5.9(4.50)g/kwh
〔G13〕
平成13年規制適合車(GL-、HR-)
平成10年規制適合車(GE-、HJ-)
平成7年規制適合車(GB-)
平成4年規制適合車(Z-)
平成元年規制適合車(T-)
昭和57年規制適合車(M-)
昭和54年規制適合車(J-)
昭和52年規制適合車(記号なし)
○
○
○
×
×
×
×
×
(注)1「○」は適、「×」
は否を示す。ただ
し、「×」となっ
ている自動車で
あっても、型式に
よってはNOx
及びPMの排出
量が特に少なく
基準に適合とな
るものもある。
(注)2 窒素酸化物等の排
出基準欄の( )
内の数値は、平均
排出ガス基準値
を示す。また、1
0・15は10・
15モード、D1
3はディーゼル
自動車13モー
ド、G13はガソ
リン自動車13
モードを示す。

(192)
<新NOx・PM法記載例>
●「使用車種規制(NOx・PM)適合」と記載された自動車
この自動車は使用車種規制のNOx・PM排出基準に適合しています。対策地域内に使用の本拠を置いて
使用することができます。
●「この自動車はNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。」
この自動車は使用車種規制のNOx・PM排出基準に適合していません。このため、対策地域外に使用の
本拠を置いて使用することはできますが、対策地域内に使用の本拠を移すことはできません。
●「この自動車は平成○年○月○日以降の有効期間満了日を越えてNOx・PM対策地域内に使用の本拠を
置くことができません。」
この自動車は使用車種規制のNOx・PM排出基準に適合していません。このため、車検証の備考欄に記
載されている日付(平成○年○月○日)以降初めての有効期間満了日を超えて対策地域内に使用の本拠を
置いて使用することはできなくなります。ただし、備考欄に記載されている日付(平成○年○月○日)以
降初めての有効期間満了日までは、対策地域内に使用の本拠を置いて使用することができます。
●「この自動車は平成○年○月○日以降の有効期間満了日を越えてNOx特定地域内に使用の本拠を置くこ
とができません。また、平成○年○月○日以降の有効期間満了日を越えてNOx・PM対策地域内に使用
の本拠を置くことができません。」
この自動車は使用車種規制のNOx排出基準に適合していません。このため、車検証の備考欄に記載され
ている日付(平成○年○月○日)以降初めての有効期間満了日を超えて特定地域内に使用の本拠を置いて
使用することはできなくなります。ただし、備考欄に記載されている日付(平成○年○月○日)以降初め
ての有効期間満了日までは、特定地域内に使用の本拠を置いて使用することができます。
また、この自動車は使用車種規制のNOx・PM排出基準に適合していません。このため、車検証の備考
欄に記載されている日付(平成○年○月○日)以降初めての有効期間満了日を超えて対策地域内に使用の
本拠を置いて使用することはできなくなります。ただし、備考欄に記載されている日付(平成○年○月○
日)以降初めての有効期間満了日までは、対策地域内に使用の本拠を置いて使用することができます。
●「この自動車はNOx・特定地域内に使用の本拠を置くことができません。また、平成○年○月○日以降
の有効期間満了日を越えてNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。」
この自動車は使用車種規制のNOx・PM排出基準に適合していません。このため、特定地域以外に使用
の本拠を置いて使用することはできますが、特定地域内に使用の本拠を移すことはできません。
また、この自動車は使用車種規制NOx・PM排出基準に適合していません。このため、車検証の備考欄
この自動車は、対策及び特定地域内に使用の本拠を置いて使用することができない場合があります。次
の説明をよくお読み下さい。
なお、ご不明な点は最寄りの運輸支局等の窓口にご相談下さい。
自動車の備考欄に使用車種規制の基準の適否等について記載を受けた方へ

(193)
に記載されている日付(平成○年○月○日)以降初めての有効期間満了日を超えて対策地域内に使用の本
拠を置いて使用することはできなくなります。ただし、備考欄に記載されている日付(平成○年○月○日)
以降初めての有効期間満了日までは、対策地域内に使用の本拠を置いて使用することができます。
●「使用車種規制(NOx・PM)対象外特種自動車」と記載された自動車
この自動車は使用車種規制の対象外です。対策地域内においても使用の本拠を置いて使用することができ
ます。
<旧NOx法記載例>
●「使用車種規制(NOx)適合」と記載された自動車
この自動車は使用車種規制のNOx排出基準に適合しています。特定地域内に使用の本拠を置いて使用す
ることができます。
●「この自動車はNOx特定地域内に使用の本拠を置くことができません。」と記載された自動車
この自動車は使用車種規制のNOx排出基準に適合していません。このため、特定地域外に使用の本拠を
置いて使用することはできますが、特定地域内に使用の本拠を移すことはできません。
●「この自動車は平成○年○月○日以降の有効期間満了日を越えてNOx特定地域内に使用の本拠を置くこ
とができません。」
この自動車は使用車種規制のNOx排出基準に適合していません。このため、車検証の備考欄に記載され
ている日付(平成○年○月○日)以降初めての有効期間満了日を超えて特定地域内に使用の本拠を置いて
使用することはできなくなります。ただし、備考欄に記載されている日付(平成○年○月○日)以降初め
ての有効期間満了日までは、特定地域内に使用の本拠を置いて使用することができます。
●「使用車種規制(NOx)対象外特種自動車」と記載された自動車
この自動車は使用車種規制の対象外の自動車です。特定地域内においても使用の本拠を置いて使用するこ
とができます。
※ 本文中の「・・できません」を「・・できないおそれがあります」と記載されている自動車について
は、コンピュータシステムで判定できない自動車です。このため、この自動車の使用の本拠を対策地
域内で使用する場合は、運輸支局等の窓口にご相談下さい。
自動車NOx・PM法に基づく自動車検査証の有効期間の更新について
自動車NOx・PM法に基づき、使用の本拠が「対策地域」及び「特定地域」内にある場合は、自動車検
査証の備考欄に明記されている「特定期日」を越えた自動車検査証の「有効期間」が表示されている場合に
は、受検されても自動車検査証の有効期間の更新はできませんのでご注意下さい。
また、上記自動車を廃車し、特定期日以内に新規検査を受検されても、対策及び特定地域内での登録はで
きませんので、ご注意ください。
なお、自動車NOx・PM法関係に基づくお問い合わせについては、各運輸支局等にご相談下さい。

(194)
自動車NOx・PM法に関する自動車検査証備考欄打ち出し例
【有効期間の更新可能な場合の例1】
自動車の本拠の位置 神戸市○○区○○町○○
自動車の所在する位置
有効期間の満了する日
[神戸],継続検査,この自動車は平成25年9月30日以降
の有効期間満了日を超えてNOx・PM対策地域内に使
用の本拠を置くことができません。
この自動車の使用の本拠の位置は、NOx・PM対策地
域内です。
平成 25年6月11日
【理由】車検証の有効期間が特定期日を超えていない。
【有効期間の更新可能な場合の例2】
自動車の本拠の位置 大和郡山市○○町○○
自動車の所在する位置
有効期間の満了する日
[奈良],継続検査,
この自動車はNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置
くことができません。
この自動車の使用の本拠の位置は、NOx・PM対策地
域外です。
平成 25年10月12日
【理由】使用の本拠の位置が対策地域外にあるため。
【有効期間の更新出来ない場合の例1】
自動車の本拠の位置 姫路市○○区○○町○○
自動車の所在する位置
有効期間の満了する日
[姫路],継続検査,この自動車は平成25年9月30日以降
の有効期間満了日を超えてNOx・PM対策地域内に使
用の本拠を置くことができません。
この自動車の使用の本拠の位置は、NOx・PM対策地
域内です。
平成 25年10月11日
【理由】使用の本拠の位置が対策地域内にあり、車検証の有効期間が特定期日を超えている。
【有効期間の更新出来ない場合の例2】
自動車の本拠の位置 神戸市○○区○○町○○
自動車の所在する位置
有効期間の満了する日
[神戸],継続検査,この自動車は平成25年9月30日以降
の有効期間満了日を超えてNOx・PM対策地域内に使
用の本拠を置くことができません。
この自動車の使用の本拠の位置は、NOx・PM対策地
域内です。
平成 25年9月30日
【理由】使用の本拠の位置が対策地域内にあり、車検証の有効期間と特定期日が同一であるため。

(195)
N O x ・P M 低減装置性能評価制度の概要
我が国における窒素酸化物( N O x ) 及び粒子状物質( P M ) による大気汚染問題は、依然とし
て厳しい状況であり、これに対応するため、現在使用されている自動車に装着し、N O x 及びP M を低
減する低減装置の開発が望まれているところです。
このため、国土交通省は、「窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる装置の性能評価制度」( N O x ・
P M 低減装置性能評価制度) を平成1 4 年8 月に創設しております。
この制度は、平成1 4 年1 月に創設されていた「粒子状物質低減装置性能評価制度」を拡充し、P M を
低減する装置の他に新たにN O x 及びP M を低減する装置とN O x を低減する装置についても評価
し、公表するものです。
また、本評価制度において優良と評価された低減装置を装着している自動車については、自動車の検査に
おいて平成1 4 年1 0 月から施行される自動車N O x ・P M 法に基づく車種規制の基準に適合して
いると判定することとしております。
※装置と自動車の適合性や取り付け等に関しては、自動車販売店、修理店、装置製作者等へご相談下さい。

(196)
(10)

(197)

(198)
ートを張り、かつ、コボレーン等の本体が荷台の内側に傾く構造のものとする。
(2) ダンプカーの後部あおりに取り付けたコボレーン等であって、鉄板、ベニヤ板、硬質ゴム等を張り付
けたもの及び次の 4に示す後部あおりのCの高さ(ヒンジ部分を含む。)を超えるもので内側に傾かない
構造のものは、検査基準 4-18 の 3-2により、保安基準第 27 条第 2項に適合しないものとして、検査
に不合格とする。
なお、後部あおりに取り付けた基準に適合するコボレーン等とは、金属枠に布又はビニール製のシー
トを張ったものであり、かつ、Cの高さ(ヒンジ部分を含む。)を超えるものにあっては、コボレーン等
の本体が荷台の内部に傾く構造のものとする。
4.後部あおり
ダンプカーの後部あおりの一部又は全部が高い荷台(後部高あおり)は、検査基準 4-18 の 3-2 に
より、保安基準第 27 条第 2 項に適合しないものとして、検査に不合格とする。
ただし、後部あおり又は側部あおりの高い部分が下図の範囲内ある場合は、基準に適合するものと
して取り扱う。
なお、平成元年1月 31 日までに初めて登録された自動車については、下図のDの長さは(B-A)/
2以下とし、Cの高さは制限しない。
5.検査用あおり
保安基準第27条2項の規定に適合するダンプカーの後部あおりについて、スポット溶接(一部を残して線
状に溶接しているものを含む。)等により仮り止めした荷台又はアングル、ボルト、ナット等によりヒンジ
を仮に取り付けた荷台(検査用あおり)は、保安基準第27条第1項の「自動車の荷台その他の物品積載装
置は、堅ろうで、且つ、安全、確実に積載できる構造であること」の基準に適合しないものとして、検査
に不合格とする。
6.検査用荷台
未塗装の荷台等いわゆる検査用の荷台を昇降させる装置が確実に取り付けられていない荷台(検査用

(199)
ダンプ規制法による表示番号がダンプカー荷台の側面及び、後面に表示されていない荷台又はマジック

(200)
○ハイヒンジの場合はハイヒ
ンジの上端部までが 40cm
を超えている
後部あおり等

(201)
(11) 大型貨物自動車等の大型後部反射器、突入防止装置及び前部潜り込み防止装置に
ついて
1.大型後部反射器の備付けについて
貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が 7 トン以上のものの後面には、保安基準
第 38 条に規定する後部反射器に加え大型後部反射器の装備が義務付けられています。
○根拠規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・保安基準第 38 条の 2
項目
基準 平成 23 年 8 月 31 日以前
製作の自動車 平成 23 年 9 月 1 日以降製作の自動車
被牽引自動車以外 被牽引自動車
性能要件
① 反射部及び蛍光部か
ら成る一辺が 130mm以上の長方形
② 反射部・・・黄色 面積 800 c ㎡以上 (2 個以上の場合はそ
の和) ③ 蛍光部・・・赤色
面積 400 c ㎡以上 (2 個以上の場合はそ
の和)
① 反射部又は反射部及び蛍光部か
ら成る長さ 130mm 以上、幅
130mm 以上 150mm 以下の長方
形であり、かつ、長さの合計が
1,130mm 以上 2,300mm 以下 ② 黄色の反射部及び赤色の反射部
又は蛍光部からなる水平面と
45°±5°の角度をなす縞模様
であり、かつ、黄色の反射部及び
赤色の反射部又は蛍光部の幅が
100±2.5mm であること
① 反射部又は反射部及び蛍光部
から成る長さ 130mm 以上、幅
195mm 以上 230mm 以下の長
方形であり、かつ、長さの合計
が 1,130mm 以上 2,300mm 以
下 ② 黄色の反射部が赤色の反射部
又は蛍光部によって囲まれて
おり、かつ、黄色の反射部を囲
む赤色の反射部又は蛍光部の
幅が 40±1mm であること
取付位置
① 後面に備えなければ
ならない ② 上縁の高さが 1.5m 以
下 ③ 車両中心面に対して
対称 (後面が左右対称で
ない自動車は除く)
① 後面に備えなければならない ② 下縁の高さが地上 0.25m 以上
(セミトレーラで 0.25m 以上に取り付けることができない場合は地
上 0.25m より下でできるだけ高い位置) ③ 上縁の高さが地上 1.5m 以下であること
(自動車の構造上 1.5m 以下に取り付けることができない場合は地上
2.1m より下であり、かつ、地上 1.5m を超えるできるだけ低い位置)
④ 車両中心面に対して対称 (後面が左右対称でない自動車は除く)
⑤ 縞模様のものにあっては当該縞模様が車両中心線上の鉛直面に対し
て対称の位置となるように取り付けること 個
数 4 個以下 1 個、2 個又は 4 個であること
幾何学的視認性
なし 上方 15° 下方 15° (上縁の高さが地上 0.75m 未満に取り付けられている場合は下方 5°)
左方 30° 右方 30° (大型特殊自動車、小型特殊自動車、トラクタは除く)
[参考]平成 23 年 9 月 1 日以降 被牽引自動車以外
被牽引自動車
黄色の反射部 赤色の反射部
又は蛍光部
黄色の反射部 赤色の反射部
又は蛍光部

(202)
2.突入防止装置について
貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量3.5t以下の小型自動車、軽自動車及び牽引自動車を除く)
及びポール・トレーラの後面には、保安基準第18条の2に規定する大型の後部突入防止装置の装備が義務
付けられています。
○ 根拠規定 ……………………………………………………………… 保安基準第18条の2第3項
○ 適用時期
(1) 車両総重量8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの
平成4年6月1日以降製作車
(2) 車両総重量が7トン以上のもの
平成9年10月1日以降製作車
(3) 車両総重量が3.5トン超のもの
平成17年9月1日以降製作車
(4) 車両総重量が3.5トン超であって小型枠(長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)のもの
平成 19年9月1日以降製作車
(5) 協定規則第58号(第2改訂版)の適用
平成24年7月11日以降製作車
○ 取り付け例
①車両総重量 3.5t 超
②車両総重量 3.5t以下または適用時期以前の自動車
(小型車、軽自動車及びけん引自動車を除く)

(203)
ペ
後部突入防止装置の分類と車検等手続要領
(平成
24年7月
10日以前)

(204)
平成 24 年 7 月 11 日以降の突入防止装置 (標準以外 )について
203 ページの取り扱いは平成 24 年 7 月 10 日までであり、平成 24 年 7 月 11 日以降の取
り扱いは、以下のとおりです。
1.JABIA マークが廃止となり、協定規則認可プレート等になりました。(例:図 1)
2.取付規定も追加されています。(表1)
3.もし、認可プレート等が無い場合については、製造元に確認してください。
図1 認可プレート
表1 取付規定

(205)
○ 7.5 t超の自動車
① 細目告示別添 107「前部潜り込み防止装置の技術基準」に適合するもの
② 平面部の下縁高さが空車状態において地上 400mm 以下(コンクリート・ミキサー車及びダンプ車にあっ
ては地上 450mm 以下)であること
③ 平面部と空車状態における地上 1.8m 以下にある当該自動車の前端をそれぞれ車両中心線に平行な鉛
直面に投影したときの水平方向の距離は負荷後 400mm 以内であって取り付けることができる自動車の前
端に近い位置となるように取り付けられていること
○ 3.5 tを超え 7.5 t以下の自動車
① 堅ろうであり、かつ、板状その他他の自動車が衝突した場合に当該衝突した自動車の車体前部が潜り
込むことを有効に防止することができる形状であること。
② 平面部の下線の高さが空車状態において地上 400mm 以下であること
(152)
3.

(206)
(12)

(207)

(208)
(13) 乗用車等の運転者の視界基準の概要
Ⅰ 前方視界基準(新車及び使用過程車に適用する直接視界基準)
1.対象車種
① 普通自動車及び小型自動車で車両総重量3.5トン以下
(乗車定員11名以上・二輪自動車及び側車付二輪自動車等のものを除く。)
② 専ら乗用の用に供する自動車で、車両総重量が3.5トンを超えるもの及び軽自動車
(乗車定員11名以上・二輪自動車及び側車付二輪自動車等のものを除く。)(カタピラ及びそりを有する
軽自動車を除く)
※いずれも使用過程車を含む。 別添 審査事務規程(H16.12.2改正)
2.適用時期
平成17年1月1日
3.基準概要(別紙「前方視界基準」参照。)
(1) 要 件
自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児を模したもの)を鏡等を用いず直接視
認できること。
(2) 適用除外
Aピラー(窓枠のうち車両最前のあるもの)、ワイパー、室外後写鏡及びステアリングホイールに
より死角となる部分。
Ⅱ 直前側方視界基準(新車に適用する間接視界基準)
1.対象車種
軽自動車、小型自動車及び普通自動車(乗車定員11人以上のもの及び車両総重量8トン以上又は最大
積載量5トン以上のものを除く。)
2.適用時期
新型生産車:平成17年1月1日以降に製作された自動車
継続生産車:平成19年1月1日以降に製作された自動車
3.基準内容(別紙「直前側方運転視界基準」参照。)
(1) 要 件
自動車の前面及び左側面(左ハンドル車にあっては右側面)に接する高さ1m、直径0.3mの円柱(6
歳児を模したもの)を直接に又は鏡、画像等により間接に視認できること。
(2) 適用除外
① Aピラー(窓枠のうち車両最前にあるもの)及び室外後写鏡による一定の大きさ以下の死角
② ワイパー、ステアリングホイールにより死角となる部分

(209)
別 紙
直前側方運転視界基準 前方視界基準
:運転視界基準エリア
● :高さ1m、直径
0.3m
のポール
:適用除外エリア
(一定の大きさ以下)
注)いずれかの基準も左ハンドルの場合には
左右逆となる。

(210)
4-33 運転者席
4-33-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げ
られないものとして運転者の視野、物品積載装置等との隔壁の構造等に関し、視認等その他適切な方法
により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第21条関係、細目告
示第27条関係、細目告示第105条第1項関係)
① 普通自動車及び小型自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車、三輪
自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3.5t以下のもの、専ら乗用の用に供する自
動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車、三輪自動車並びに被牽引自動
車を除く。)であって車両総重量3.5tを超えるもの及び軽自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動
車を除く。)の運転者席は、運転者が運転者席において、次に掲げる鉛直面により囲まれる範囲内に
ある障害物(高さ1m直径30cmの円柱をいう。4-33-1(1)③において同じ。)の少なくとも一部を
鏡等を用いずに直接確認できるものであること。ただし、Aピラー、窓ふき器、後写鏡又はかじ取ハ
ンドルにより確認が妨げられる場合にあっては、この限りでない。
ア 当該自動車の前面から2mの距離にある鉛直面
イ 当該自動車の前面から2.3mの距離にある鉛直面
ウ 自動車の左側面(左ハンドル車にあっては「右側面」)から0.9mの距離にある鉛直面
エ 自動車の右側面(左ハンドル車にあっては「左側面」)から0.7mの距離にある鉛直面
(参考図)
② ①ア及びイにおける「当該自動車の前面」とは、当該自動車の車体(バンパ、フック、ヒンジ等( 指
定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものを除く。)の
附属物を除く。)の前面とする。

(211)
③ ①に規定する自動車の運転者席は、次に掲げる状態の自動車の運転者席に、自動車に備えられてい
る座席ベルトを装着し、かつ、かじ取ハンドルを握った標準的な運転姿勢をとった状態で着座した者
の視認により、①のアからエの鉛直面により囲まれるいずれかの位置に置かれた障害物の一部が直接
確認できない場合は、①の基準に適合しないものとする。ただし、Aピラー、窓ふき器、後写鏡又は
かじ取ハンドルにより確認が妨げられる場合にあっては、この限りでない。
(条件)
ア 自動車は、平坦な面上に置き、直進状態かつ検査時車両状態とする。
イ 自動車のタイヤの空気圧は、規定された値とする。
ウ 車高調整装置が装着されている自動車にあっては、標準(中立)の位置とする。ただし、車高を任
意の位置に保持することができる車高調整装置にあっては、車高が最高となる位置とする。
エ 運転者席の座席は、次のとおりに調節した位置とする。
(ア) 前後に調節できる場合には、中間位置とする。ただし、中間位置に調節できない場合には、中
間位置より後方であってこれに最も近い調節可能な位置とする。
(イ) 上下に調節できる場合には、中間位置とする。ただし、中間位置に調節できない場合には、中
間位置より下方であってこれに最も近い調節可能な位置とする。
(ウ) 座席の背もたれの角度が調節できる場合には、鉛直面から後方に25°の位置とする。ただし、
鉛直面から後方に2 5°の位置に調節できない場合には、鉛直面から後方に25°の位置より後方
であってこれに最も近い調節可能な位置とする。
オ 運転者席の座席に座布団又はクッション等を備えている場合には、これらのものを取り除いた状
態とする。
④ ① に規定する自動車以外の自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有するものであること。
⑤ 運転者席は、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものであること。この場合にお
いて、次に掲げる運転者席であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適
合するものとする。
ア 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の運転者席であって、保護棒又は隔壁を有するもの
イ 貨物自動車の運転者席であって、運転者席と物品積載装置との間に隔壁又は保護仕切を有するも
の。この場合において、最大積載量が500kg以下の貨物自動車であって、運転者席の背あてにより積載
物品等から保護されると認められるものは、運転者席の背あてを保護仕切りとみなす。
ウ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7 倍未満である三輪自動車の運転者の座
席の右側方に設けられた座席であって、その前縁が運転者の座席の前縁から20cm以上後方にあるも
の、又は左側方に設けられた座席であって、その前縁が運転者の座席の前縁より後方にあるもの
(2) 指定自動車等に備えられた運転者席と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた運転者席で
あってその機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細
目告示第105条第2項関係)

(212)
(14) 前面ガラス等への装飾板の装着禁止について
近年、大型トラック等において運転者の視界を妨げるいわゆる装飾板(別紙1参照)の装着が問題となって
いたところですが、国土交通省は本日、このような危険な装飾板の装着をなくすため、道路運送車両の保安
基準(昭和26年運輸省令第67号)を改正し、公布しました、概要等は次の通りです。
(規制の概要)
・ 対象自動車:被けん引自動車以外の全ての自動車
・ 規制の内容:前面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)に装飾板等を装着した状
態は、基準不適合とする(可視光線透過率が70%以上となるものは除く)。
・ 規制の開始:平成17年1月1日
(規制に至る背景)
平成15年11月26日、川崎市中原区において、装飾板を装着した大型トラックが道路を横断中のベビーカー
と母親を跳ね、ベビーカーの幼児が死亡し、母親が重傷を負うという事故が発生しました。この事故を受け、
国土交通省では、(社)全日本トラック協会等に対し、前面ガラス内側への装飾板等の装着の自粛について指
導してきました。また、並行して実態調査を実施し、その結果に基づき、法令改正による新たな規制を実施
することとしました。
別紙1
図 装飾板装着による影響

(213)
(15) 自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識等の貼付位置等
(審査事務規程5-47-1-1-(1)⑬)
自動車、自動車の装置等の盗難を防止するための装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の
盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識の上縁の高さ又
は刻印する文字及び記号の上縁の高さがその付近のガラスの開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と重な
る部分及びマスキングが施されている部分を除く。)の下縁から100㎜以下、かつ標識の前縁又は刻印の文
字及び記号の前縁がその付近のガラス開口部の後縁から125㎜以内となるように貼付又は刻印されたもの。
○自動車検査関係質疑応答Q&Aより抜粋
Q1 保安基準第29条第4項第7号に規定する運輸大臣が指定したものを定める告示(平成11年運輸省告
示第820号)で定める試験領域A及びBから外れた前面ガラス外周部にはアンテナを貼り付けてはなら
ないと解釈してよろしいか。
A1 「保安基準第29条第4項第7号に規定する運輸大臣が指定したものを定める告示」(平成11年運輸省
告示第820号)(以下「告示」という)第2号に規定するアンテナ(アンテナを接続するためのコネク
タ等アンテナを構成する付属品を含む。)は、試験領域A、B又はIの領域以外の領域に添付すること
ができる。この場合にあってアンテナの幅、本数の制限及びコネクタ等アンテナを構成する付属部品
の大きさに制限は設けていない。
Q2 告示で引用されている試験領域Bから除外する範囲の明確な寸法明示がないため、上下部分につい
て実際作業をする場合、どこまでがB領域で、どこからがB領域を外れるのか分からないと言う質問
があった。(付属書図より)
JIS R3212の試験領域Bを定める規定中但し書きでは、「前面ガラス周縁から25mm以内を除外す
る」となっており、上下部分についても単に周縁から25mmもB領域から外れると解釈してよろしいか。
A2 前面ガラス周縁から25mm以内、及び周辺部に不透明マスキングバンドがある場合において、そのバ
ンドの内側の線から25mm以内の部分は、JIS R3212付属書1.1.3(2.2)ただし書きにより試
験領域Bから除外されているため、貼り付ける機器の幅が1.0mm以下である必要はない。
Q3 アンテナとケーブルを繋ぐ部分(所謂コネクタ)もアンテナとして認めて良いか。
A3 告示第2号に規定するアンテナには、アンテナを接続するためのコネクタ等アンテナを構成する付
属部品も含まれる。
→ ABCD123456
→↑ ←

(214)
Q4 関連して前面ガラス周縁のマスキング部にステッカーを貼った場合不適合と判断すべきか。
A4 前面窓ガラスの周縁のマスキングが施されている部分は、取付枠、インストルメントパネルその他
車体と重なる部分の一部と解することができることから、保安基準第29条第3項及び第4項の規定の
適用を受けない部分と解することができる。
(16) 速度計試験機の判定値について
判定値
(1) 平成18年12月31日までに製作された自動車
① ②以外の自動車(四輪自動車)
31.0km/h≦V≦44.4km/h
② 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車
29.1km/h≦V≦44.4km/h
(2) 平成19年1月1日以降に製作された自動車
① ②以外の自動車(四輪自動車)
31.0km/h≦V≦42.5km/h
② 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車
29.1km/h≦V≦42.5km/h
平成18年12月31日までに製作された自動車
平成19年1月1日以降に製作された自動車
44.4 44.4
42.5 42.5

(215)
(17) ディーゼル黒煙検査のお知らせ
自動車検査独立行政法人
自動車検査法人は、「アクセル全開の空ぶかし」によるディーゼル黒煙検査を重点項目とすることとしてい
ます。
ディーゼル車を受検されます皆様には、ディーゼル黒煙の点検・整備に留意して検査を受けられますよう
お願いします。また、原動機を改造している場合は、検査により異常を生じることがありますので、適正な
状態で受検されるよう留意願います。
Q1:何故「アクセル全開の空ぶかし」を実施するのでしょうか?
A1:① 平成15年6月の「ディーゼル黒煙クリーンキャンペーン」から「アクセル全開の空ぶかし」を実
施しています。
② この取扱いについては、自動車検査法人の検査方法について規定している「審査事務規程」が改
正されており、6月1日から実施しています。
③ なお、保安基準(第31条第22項)では、「アクセル全開の空ぶかし」を行ったときに排出される黒
煙について規制されているため、これを目視で確認するときも同様な方法で行うことにしたもので
す。
(保安基準第31条第22項)
第十項から第十三項までの自動車は、原動機を無負荷運転した後、原動機を無負荷のままで急速に加速
ペダルを一杯に踏み込んだ場合において、加速ペダルを踏み込み始めた時から発生する排気管から大気
中に排出される排出物に含まれる黒煙について前項第二号に定める測定方法により三回測定し、その測
定した値の平均値が二十五パーセント以下でなければならない。
(審査事務規程3-21-6)
保安基準第31条第22項に規定する自動車にあっては、原動機を無負荷のままで加速ペダルを急速に一杯
踏み込み直ちに加速ペダルを放した場合において、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒
煙について目視により確認する。この場合において、黒煙が同項に規定された値を超えるおそれがある
と認められたときは、黒煙測定器を用いて以下により計測するものとする。

(216)
Q2:「アクセル全開の空ぶかし」でエンジンの調子が悪くなることがありますか。
A2:① エンジンが適正に整備されていれば不具合は起きないと考えています。
② また、一般的に異常摩耗や調整不良、ガバナーの細工などがなければ、エンジンの不具合は発生
しないとされています。
なお、自動車を適切に点検整備し、保安基準に適合するように維持することは使用者の義務とさ
れています。
(参考)ディーゼル黒煙に係る調査依頼への(社)日本自動車工業会からの回答(抜粋)
【照会事項】
原動機が無負荷運転されている状態からアクセルペダルを一杯に踏み込んだ場合、エンジン過回転(オ
ーバーラン)によるエンジン破損の可能性について
【(社)日本自動車工業会の見解】
フリー加速黒煙試験において、エンジンが適正な状態であれば(不正改造等がない状態)、エンジン回
転は定格回転に対し110%以上になることはありません。通常、110%回転程度は、メーカーで疲労保証
していますので、エンジンが破損することはないものと考えます。
Q3:「アクセル全開の空ぶかし」に加え、何故3回の機器測定まで行う必要があるのでしょうか?
A3:① 「アクセル全開の空ぶかし」は視認によって行っていますので、基準を超える黒煙を排出するお
それがあると判断された場合は、黒煙測定器を用いて3回測定することとされています。
② 3回の機器測定によることは、国土交通省令の保安基準に規定されています。
(保安基準第31条第22項)
第十項から第十三項までの自動車は、原動機を無負荷運転した後、原動機を無負荷のままで急速に加速
ペダルを一杯に踏み込んだ場合において、加速ペダルを踏み込み始めた時から発生する排気管から大気
中に排出される排出物に含まれる黒煙について前項第二号に定める測定方法により三回測定し、その測
定した値の平均値が二十五パーセント以下でなければならない。

(217)
(18)オパシメータを使用した粒子状物質(PM)の検査について

(218)

(219)

(220)

(221)
(19) マフラー騒音規制適用車に係る消音器の基準適合性の確認等の取扱いについて
国自環第247号
平成22年2月5日
改正 国自環第295号
平成22年3月31日
改正 国自環第205号
平成23年3月31日
改正 国自環第 70号
平成23年6月30日
今般、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示」(平成20年国土交通省告
示第1532号)等の制定に伴い、内燃機関を原動機とする自動車等が備える消音器は、加速走行騒音を有
効に防止するものでなければならないこと等とされたことを踏まえ、今後、道路運送車両の保安基準の細
目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号。以下「細目告示」という。)第40条第2項、第
118条第2項、第196条第2項、第252条第2項、第268条第2項及び第284条第2項並びに第
118条第3項、第196条第3項、第268条第3項及び第284条第3項に基づく消音器の基準適合性
の確認等に当たっては、下記のとおり取り扱うこととするので、了知されたい。
なお、別紙の関係自動車検査機関及び関係団体あて通知したので申し添える。
記
第1 消音器等の改造及び構造
1.消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造の例について
消音器本体の外部構造及び内部部品が恒久的方法(溶接、リベット等)により結合されていない(例:
ボルト止め、ナット止め、接着)消音器は、細目告示第40条第2項第2号、第118条第2項第5号及
び第196条第2項第5号の規定(以下「騒音低減機構の容易除去可能構造の禁止規定」という。)に適
合しない例とする。
2.消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造に該当しない例について
消音器本体に騒音低減目的以外の目的として装着されている外部構造部品(別紙1図1の網掛けの部
品)及び消音器本体以外に装着されている外部構造部品であって、それらを取り外しても騒音防止性能
に影響のないもの、並びに消音器本体に取り付けられた排気バルブを作動させるための制御機構装置(別
紙1図2の網掛けの部品)は、恒久的方法により結合されていなくても、騒音低減機構の容易除去可能
構造の禁止規定に適合する例とする。
3.加速走行騒音性能規制に影響しない消音器の改造の例について
「指定自動車等に備えられている消音器本体と同一であって、消音器本体と消音器出口側の排気管(テ
ールパイプをいう。以下同じ。)との接合部の内径が拡大されていないもの」又は「消音器出口側の排気
管に装着する意匠部品(騒音を増大等させるためのものを除く。)の取付け又は取外し」若しくは「予め
その基準適合性が確認されている消音器(指定自動車等に備えられている消音器を含む。)であって、排
気管部分へのDPF又は触媒の取付け」は、細目告示第118条第2項第6号及び第196条第2項第6

(222)
号の規定(以下「加速走行騒音性能規制」という。)に影響しない改造の例とする。
なお、この例は、「改造自動車に係る新規検査の際に提出する書面について」(平成23年6月30日
付け国自環第70号。以下「改造車の新規検査時提出書面通達」という。)記6.(2)の加速走行騒音値
に影響する消音器の改造を行う場合に該当しない例とする。
4.使用過程車における消音器以外の装置の改造により加速走行騒音性能規制に適合しなくなるおそれがあ
る改造について
異型式の原動機への換装(指定自動車等に備えられた消音器等であって、換装後の原動機用の加速走
行騒音性能規制に適合した消音器等とセットで換装した場合を除く。)は、加速走行騒音性能規制に適合
しなくなるおそれがある改造として取り扱うものとし、この場合における加速走行騒音性能規制への適合
性については、改造車の新規検査時提出書面通達別添9の加速走行騒音試験結果成績表により確認するも
のとする。なお、この場合の加速走行騒音試験結果成績表は、公的試験機関又は自動車製作者等(加速走
行騒音試験の実施について、自動車製作者と同等な能力を有すると認められる改造施工者を含む。)にお
いて実施されたものの写しで差し支えないものとする。
第2 公的試験機関による成績表の発行等
1.公的試験機関について
加速走行騒音試験結果成績表を発行する公的試験機関は、国若しくは地方公共団体の附属機関(国立
大学法人及び公立大学を含む。)若しくは公益法人又はこれに準ずるものであって、加速走行騒音につい
ての試験を行うのに必要な組織及び能力を有しているものと認められた機関とする。
2.騒音防止性能確認標章について
公的試験機関による騒音防止性能確認標章の発行等については、次のとおりとする。
(1)公的試験機関は、加速走行騒音試験の結果、消音器が加速走行騒音性能規制に適合している場合には、
申請者の求めに応じ、騒音防止性能確認標章(当該申請対象の自動車が備える消音器を特定すること
ができる確認番号等を記載した耐熱シールであって、車台番号ごとに発行されるものをいう。以下同
じ。)を発行することができる。この場合において、公的試験機関は、加速走行騒音試験結果成績表に、
当該確認番号を記載するものとする。
(2)(1)の規定により発行された騒音防止性能確認標章は、加速走行騒音試験結果成績表の「写真8
消音器表示」と同一位置に貼付するものとする。
(3)騒音防止性能確認標章の様式は、別添1によるものとする。
(4)騒音防止性能確認標章の紛失又は棄損による再発行の申請があった場合には、公的試験機関は、騒音
防止性能確認標章の再発行を行うことができる。
第3 協定規則及び欧州連合指令による取扱い
1.協定規則と同等な欧州連合指令について
(1)細目告示第118条第3項第1号ニ及び第196条第3項第1号ニの「協定規則第9号、第41号若
しくは第51号又はこれらと同等の欧州連合指令」とは、協定規則第9号 ※ 及び第41号 ※ にあっては、
78/1015/EEC※又は97/24/EEC※の指令とし、協定規則第51号※にあっては、70/157/EEC※の指令とする。
(2)細目告示第118条第3項第1号ホ及び第196条第3項第1号ホの「協定規則第59号若しくは第

(223)
92号又はこれらと同等の欧州連合指令」とは、協定規則59号 ※ にあっては、70/157/EEC※ の指令
とし 、協定規則92号※にあっては 、97/24/EEC※ の指令とする。
※協定規則及びこれと同等の欧州連合指令の概要は、それぞれ次のとおり。
(協定規則)
・協定規則第9号とは、側車付二輪自動車が発生する騒音に関する規定
・協定規則第41号とは、二輪自動車が発生する騒音に関する規定
・協定規則第51号とは、四輪以上の自動車が発生する騒音に関する規定
・協定規則第59号とは、乗車定員9人以下の乗用車及び車両総重量3.5トン以下の貨物車の交換
用消音器に関する規定
・協定規則第92号とは、二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)の交換用消音器に関する規定
(欧州連合指令)
・欧州連合指令 78/1015/EEC 及び 97/24/EEC とは、二輪自動車が発生する騒音に関する規定(97/24/
EEC には二輪自動車の交換用消音器に関する規定を含む。)
・欧州連合指令 70/157/EEC とは、四輪以上の自動車が発生する騒音及び交換用消音器に関する規定
2.協定規則又は欧州連合指令により消音器に表示される特別な表示について
(1)細目告示第118条第3項第1号ニ及び第196条第3項第1号ニの「協定規則第9号、第41号若
しくは第51号又はこれらと同等の欧州連合指令に適合する自動車が備える消音器に表示される特別
な表示」とは、次に掲げる表示をいう。
① 協定規則第9号又は第41号に基づくマーク
例:E4 41R-032439(協定規則第41号第3改訂版の認可をオランダで取得し、その認可番号が 2439
であることを示す。)
② 欧州連合指令 97/24/EEC に基づくマーク
例:e2(欧州連合指令 97/24/EEC の認可をフランスで取得したことを示す。)
(2)細目告示第118条第3項第1号ホ及び第196条第3項第1号ホの「協定規則第59号若しくは第
92号又はこれらと同等の欧州連合指令に適合する消音器に表示される特別な表示」とは、次の表示
をいう。
① 協定規則第59号又は第92号に基づくマーク
例:E1 59R-002439(協定規則第59号の認可をドイツで取得し、その認可番号が 002439 であるこ
とを示す。)
② 欧州連合指令 70/157/EEC 又は 97/24/EEC に基づくマーク
例:e9 030148(欧州連合指令 70/157/EEC の第3主要改訂版(92/97/EEC)の認可をスペインで取得
し、その認可番号が 0148 であることを示す。)
3.協定規則又は欧州連合指令への適合性を証する外国の法令に基づく書面等について
次に掲げる自動車は、細目告示第118条第3項第2号ロ及び第196条第3項第2号ロの「外国の
法令に基づく書面又は表示により、協定規則第9号、第41号若しくは第51号又はこれらと同等の欧州
連合指令に適合することが明らかである自動車」に該当するものとする。
(1)欧州連合指令 70/156/EEC 附則Ⅵ又は 2002/24/EEC 附則Ⅳ - Aに基づく自動車製作者が発行する完成
車の適合性証明書(COCペーパー)又はこれと同等のもの(WVTAラベル・プレート)を有する

(224)
自動車
ただし、欧州連合指令の規定に基づく少数生産車(年間生産台数が四輪車500台(一部250台)
未満、二輪・三輪車200台以下のものをいう。なお、車両識別番号(VIN)の3桁目の記号が「9」
である自動車はこれに該当する。以下(2)において同じ。)にあっては、この限りでない。
(2)欧州連合(EU)加盟国において生産された自動車(少数生産車を除く。)であって、EU加盟国の
政府が発行する自動車登録証を有する自動車
(3)協定規則第51号に基づくマークが、車両識別表示(車両データプレート)内か又はその近くに表示
されている自動車
(4)協定規則第51号又は欧州連合指令 70/157/EEC に適合する旨の認可書(協定規則第51号附則Ⅰの
車両型式認可書又は欧州連合指令 70/157/EEC 附則Ⅰ付録2の車両型式認可書をいう。)の写しを有し、
かつ、当該認可書に記載された車両型式の自動車と同一と認められる自動車
この場合において、当該認可の車両型式と同型の自動車であって、当該自動車に備える消音器が、
当該認可に係る消音器と同一の構造であり、かつ、同一の位置に備えられていることが明らかである
ものは、当該認可書に記載された車両型式の自動車と同一と認められるものとする。
第4 検査における加速走行騒音試験結果成績表等の取扱い
1.公的試験機関成績表の取扱いについて
公的試験機関が、指定自動車等以外の非認証車又は使用過程において消音器を改造した自動車に対し
て発行する加速走行騒音試験結果成績表については、本通の提示を求めるものとする。
この場合において、騒音防止性能確認標章が発行されている場合は、当該確認標章の発行を受けた自
動車の初めての新規検査(予備検査を含む。)の際に、加速走行騒音試験結果成績表の騒音防止性能確認
標章確認番号と検査申請車両の消音器に貼付されている騒音防止性能確認標章の確認番号が一致してい
ることを確認するものとする。
2.加速走行騒音試験結果成績表と検査申請車両の同一性の確認について
改造車の新規検査時提出書面通達に定める細目告示第40条第1項第3号の表の自動車の種別に応じ
た加速騒音値規制、又は、本通達に定める消音器の加速走行騒音性能規制のそれぞれへの基準適合性につ
いて、両通達の規定により、公的試験機関又は自動車製作者等が実施した加速走行騒音試験結果成績表又
はその写しにより判定する場合には、当該加速走行騒音試験結果成績表に係る試験自動車の構造・装置等
と検査申請車両の構造・装置等が同一であることを確認するものとする。
この場合において、「構造・装置等が同一である」とは、当該加速走行騒音試験結果成績表中の「試験
自動車」欄に記載される項目のうち、「車名」、「型式」(原動機等の改造により「改」を付した型式以外の
型式にあっては、「改」を除く型式)、「原動機型式」、「最高出力」(使用過程車の検査を除く。)、「変速機
の種類」(使用過程車の検査を除く。)、「車両総重量」(使用過程車の検査を除く。)、「消音器の個数」、「触
媒の有無」(使用過程車の検査を除く。)及び同成績表添付資料中の「消音器外観」に係る構造・装置等が
同一であることをいう。
なお、「車両総重量」にあっては、検査申請車両の車両総重量が同成績表の試験自動車の車両総重量よ
り重い場合、及び軽い場合であって、その差が試験自動車の車両総重量の-5%以内又は-20㎏以内の
場合は同一とみなすものとする。

(225)
3.騒音防止性能確認標章の取扱いについて
使用過程車の検査において、加速走行騒音性能規制への適合性を加速走行騒音試験結果成績表の提示
により確認する場合、騒音防止性能確認標章が貼付された消音器を備える自動車は、同規制に適合するも
のとして取り扱って差し支えない。
4.装置指定を受けた消音器の取扱いについて
装置指定を受けた消音器に係る取扱いは次のとおりとする。
(1)指定自動車等について消音器の改造を行う場合であって、改造後の消音器が道路運送車両法第75条
の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた騒音防止装置の消音器(以下「装置指定消音器」
という。)であり、かつ、同法施行規則第62条の4の騒音防止装置の型式指定番号標(以下「型式指
定番号標」という。)が当該消音器を備えた自動車に表示されているときは、当該表示は、改造車の新
規検査時提出書面通達記6.また書きの規定による「S」マークが付された性能等確認済表示と同等に
取り扱って差し支えない。
(2)装置指定消音器であって、型式指定番号標が当該消音器を備えた自動車に表示されている場合は、当
該型式指定番号標の表示は、加速走行騒音性能規制に適合する表示として取り扱って差し支えない。
第5 指定自動車等の製作者が行う表示
1.製作者表示を行うことができる場合について
指定自動車等の製作者は、当該指定自動車等に備える消音器に、製作者表示(細目告示第118条第
3項第1号イ及び第196条第3項第1号イの「指定自動車等の製作者が、当該指定自動車等に備える消
音器に行う表示」をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2.製作者表示の内容について
製作者表示は、当該指定自動車等の製作者の商号又は商標等とする。この場合において、部品番号等
の表示であっても、指定自動車等の製作者等の管理下にあることが別途証されたものは、製作者表示とし
て認めるものとする。
3.製作者表示の表示方法について
製作者表示の表示は、次により行うものとする。
(1)製作者表示は消音器毎に表示することとする。ただし、複数の消音器が一つの部品として一体となっ
ている場合は、当該部品として構成されているいずれかの消音器に行えばよい。
(2)製作者表示は、消音器を自動車に取り付けた状態で見えやすい位置に行うこと。ただし、自動車又は
消音器の構造上やむ得ない場合に限りピット及び手鏡等を使用して確認可能な位置とすることができ
るものとする。また、当該表示は容易に破損・滅失等しない方法(鋳出し、刻印又は金属プレートの
固着等)により表示しなければならない。
第6 原動機付自転車が備える消音器の取扱い
原動機付自転車が備える消音器の取扱いは、第1~第3及び第5の規定を準用する。
なお、第3の規定を準用する場合において、自動車に適用される協定規則及びこれと同等の欧州連合指令
は、それぞれ原動機付自転車に係る協定規則及び欧州連合指令に読み替えて適用するものとする。

(226)
別添1:騒音防止性能確認標章
ANT-○○○-△△△△
↑ ↑ ↑
① ② ③
①加速走行騒音試験を実施したことを示す記号
②公的試験機関の略称(アルファベット)
③確認番号(試験車両毎に公的試験機関が決定する番号))

(227)
9
別紙1:消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造に該当しない例
※二輪車について、消音器本体の後端に恒久的方法により結合されていない意匠カバーを装着す
る車両について、消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造であるかどうかを判別可能と
するため、申請書等の添付書面の構造・装置の概要説明書に、「意匠カバーを取り外しても、
消音器の騒音低減機構を容易に除去できない構造である」旨を記載するとともに、消音器概略
図を添付することとしている。
断熱パッド
断熱カバー
意匠カバー
バンド
消音器本体
接着
ボルト
ボルト
恒久的結合 図 1
プーリー ケーブル
ナット
排気バルブ
ケーブル 恒久的結合
図2
※二輪車について、消音器本体の後端に恒久的方法により結合されていない意匠カバーを装着す
る車両について、消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造であるかどうかを判別可能と
するため、申請書等の添付書面の構造・装置の概要説明書に、「意匠カバーを取り外しても、
消音器の騒音低減機構を容易に除去できない構造である」旨を記載するとともに、消音器概略
図を添付することとしている。

(228)

(229)
(20)平成 24 年7月付近で施行された細目告示(抜粋)
1.突入防止装置
【適用対象】
貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量3.5トン以下の小型自動車、軽自動車及び牽引自動車を
除く。)及びポール・トレーラ
【改正概要】
負荷倍数等の変更に伴い、JABIAリベットを廃止。協定規則認可品(Eマーク)となりました。
【適用時期】
平成 24年 7月以降に製作される自動車より適用します。
2.座席及び座席取付装置
【適用対象】
全ての自動車に適用。
【改正概要】
乗用車以外にも座席強度の基準の追加、全ての自動車に座席方向の規制をします。
【適用時期】
平成 24年 7月以降に製作される自動車より適用します。
3. 座席ベルト及び座席ベルト取付装置
【適用対象】
全ての自動車。
【改正概要】
三点式ベルトの適用範囲が拡大しました。横向き座席にニ点式ベルトが必要になりました。
【適用時期】
平成 24年 7月以降に製作される自動車より適用します。
4.乗降口
【適用対象】
バス型自動車以外の自動車。
【改正概要】
跳ね上げ式ドア、スライドドア及びバックドアも強度試験が必要になります。
【適用時期】
平成 24年 7月以降に製作される自動車より適用する。(一部 8月以降)
5.年少者用補助装置
【適用対象】
乗用車に適用されます。
【改正概要】
チャイルドシート固定装置の装着義務と固定装置について強度試験が必要になりました。
【適用時期】
平成 24年 7月以降に製作される自動車より適用する。

(230)
6.事業用自動車の構造基準
【適用対象】
乗車定員10人以下の乗用車(タクシー)に適用します。
【改正概要】
窓際座席すべてに、ヘッドレストが必要になりました。
【適用時期】
平成 24年 7月以降に製作される自動車より適用する。
7. ワンマンバスの構造要件
【適用対象】
乗車定員11人以下の乗用車(乗合バス)に適用します。
【改正概要】
前扉以外の乗降口を閉めない限り、走行装置に動力を伝達できない構造となりました。
【適用時期】
平成 24年 7月以降に製作される自動車より適用する。
8.電気自動車
【適用対象】
電気自動車等のうち、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽
自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、被牽引自動車並びに燃料電池自動車を除くもの。
【改正概要】
① 通常使用時の高電圧からの乗車人員の保護関係
○電気自動車等の通常時の感電保護に関し以下の要件を規定
・駆動系の高電圧からの感電保護に関する要件
・外部電源へ結合する装置からの保護に関する要件
・駆動用蓄電池の過電流に対する保護に関する要件
・水素ガスを発生する駆動用蓄電池を収納する場合の換気に関する要件
・走行可能状態の表示に関する要件
② 衝突後の高電圧からの乗車人員の保護関係
○電気自動車等の衝突後の感電保護に関し以下の要件を規定
・駆動系の高電圧からの感電保護に関する要件
・駆動用蓄電池からの電解液漏れに関する要件
・駆動用蓄電池の固定に関する要件
○上記要件が適用されない重量トラック、バス等に係る以下の要件を規定
・駆動用蓄電池及び電気回路の取付位置に関する要件
・駆動用蓄電池取付部の強度に関する要件
【適用時期】
平成 24年 7月以降に製作もしくは改造した自動車より適用する。

(231)
(21) 不適切な補修等について(自動車検査独立行政法人からのお知らせ)
これまで検査場において、灯火器の破損にセロハンテープを貼付したもの、灯火器等をガムテープで
取付けたもの、段ボール製のオーバーフェンダーを装着したもの等、耐久性が著しく劣る、又は、検査
後に取外されるような不適切な補修等を行った自動車を合格させるよう不当要求があり、トラブルとな
っていました。
このため、審査事務規程の一部を改正し、次の各号に掲げる補修等を行った自動車は、保安基準に適
合しないことを明確化しました。
① 灯火器の破損、亀裂等が粘着テープ類により補修されているもの
② 各種ダストブーツ類の破損、亀裂等が針金類又は粘着テープ類により補修されているもの
③ 灯光の色の基準に適合させるため、灯火器の表面に貼付したフィルム等がカラーマジック、スプレ
ー等で着色されているもの
④ 空き缶、金属箔、金属テープ又は非金属材料を用いて排気管の開口方向が変更されているもの
⑤ 排気管に空き缶、軍手、布類等の異物が詰められているもの
⑥ 走行装置の回転部分付近の車体(フェンダー等)にベルト類、ホース類、粘着テープ類、紙類、ス
ポンジ類又は発泡スチロールが取り付けられているもの
⑦ 緊急自動車の警光灯に形状が類似した灯火(赤色以外のものを含み、教習用二輪車に備える教習用
灯火を除く。)であって、当該灯火に係る電球、すべての配線及び灯火器本体(カバー類、粘着テープ
類その他の材料により覆われているものを含む。)が取り外されていないもの
⑧ 不点灯状態にある灯火(光源を取り付けていても点灯することができない灯火を備えた状態で指定
自動車等を受けている灯火、速度表示装置及び⑦の灯火を除く。)であって、当該灯火に係る電球及び
すべての配線が取り外されていないもの
⑨ 番号灯の一部が点灯しないもの
⑩ 灯火器、シートベルト、座席後面の緩衝材、後写鏡、窓ガラス、オーバーフェンダー、排気管、座
席、ブレーキホース、ブレーキパイプ、ショックアブソーバ、スプリング、タイロッド又は扉が粘着
テープ類、ロープ類又は針金類で取り付けられているもの(指定自動車等に備えられたものと同一の
方法で取り付けられたものを除く。)
⑪ 操縦装置の識別表示又は最大積載量の表示が貼り付けられた紙又は粘着テープ類(表示を目的とし
て製作されたものを除く。)に記入されているもの及び表示された内容が容易に消えるもの。
⑫タイヤの取り外しにより、軸数を減ずるもの又は複輪を単輪にするもの。

(232)
(22) 受検者の皆様へ
★★受検に当たって受検者の皆様にお守り頂くこと★★
自動車検査場において検査を受ける場合には、検査を安全かつ円滑に行うために、次の事項をお守り下さ
い。これらの事項が守られていない場合は、検査担当者から検査時において、指示が行われる場合がありま
す。また、この指示に従わないときは、受検車両の検査を行わないことがありますので、ご協力をお願いし
ます。
1.検査中は検査票を保持すること。
2.下回り部分は泥等の付着がなく装置等の確認ができる状態とすること。
3.車台番号及び原動機の型式の打刻は、汚れ等の付着がなく打刻文字等が確認できる状態とすること。
4.排気管は、排気ガス測定用プローブが挿入できる状態とすること。
5.荷台等は物品等が積載された状態でないこと。
6.座席、シートベルト、非常信号用具、消火器等は確認できる状態とすること。
7.窓ガラスは取り外された状態でないこと。
8.全ての車輪のホイールキャップ又はセンターキャップ、灯火器等に装着されているカバー等は取り外し
た状態とすること。
9.エンジンルーム内の検査を行う場合は、原動機を停止し、ボンネット(フード)を開け、支持棒等によ
り保持した状態とすること。
10.運転者席及び助手席の側面ガラスの検査を行う場合は、窓ガラスを閉じた状態とすること。
11.検査担当者からの指示により、警音器、方向指示器等灯火器又は窓拭器等を作動させること。また、指
示がある場合以外はこれら装置を作動させないこと。
12.検査機器の表示器による表示又は検査担当者からの指示により、原動機の始動及び停止を行うこと。
13.受検車両の構造・装置に応じ、検査機器の申告ボタンの操作を行うこと。
14.検査コース内において必要な受検車両の移動、停止位置での停車を行うこと。
15.検査機器の表示器による表示又は検査担当者の指示に応じテスタへの乗り入れ、脱出及び前照灯の点灯
操作等を行うこと。
16.記録器のあるコースにおいては記録器による検査結果の記録を行うこと。
17.検査が終了した場合(再検査の場合を含む)には、検査票に総合判定結果の記入を受けること。
18.走行距離計は総走行距離(オドメータ)を表示した状態とすること。
19.脱着式スタンション型のセミトレーラにあっては、必要本数のスタンションを装着した状態とすること。
20.軽油を燃料とする自動車はアクセルペダルのストッパボルト又はアクセルワイヤの改造等を行って当該
原動機の 高回転数を一時的に低下させた状態としないこと。
21.検査担当者がエア・クリーナのカバーの取り外しを指示した場合は、当該カバーを取り外すこと。
22.3次元測定・画像取得装置を使用して画像の撮影及び諸元測定を行っている場合は、受検車両以外の写
り込みを防ぐため受検車両の近傍に近寄らないこと。

(233)
特に、次の事項が守られていない場合は、検査を中止し、受検者に対する退去や自動車の撤去を命じるこ
とがあります。これに応じない場合は、コースの閉鎖や公務執行妨害行為等として警察への通報等厳正な措
置をとることがありますのでご承知下さい。
1.暴力、暴言等を行わないこと及び暴力、暴言等の威圧的行為により検査担当者にその場での再検査、合
格の判定等を強要しないこと。
2.検査を受ける自動車の運転者(1名に限る)以外の者が許可なく入場しないこと。
3.検査担当者が危険を感じる速度(歩行速度以上)で通行しないこと。
4.コース内で整備等をしないこと。
5.検査機器、検査設備等を損傷させ又は破壊しないこと。
6.座り込み、立ちふさがり又は自動車を放置しないこと。
7.旗、のぼり、プラカード類を検査コース内に持ち込まないこと。
8.拡声器等の放送設備を使用し、騒音を撒き散らさないこと。
9.凶器、爆発物等の危険物を持ち込まないこと。
10.その他検査業務上又は検査場管理上支障となる行為をしないこと。
○各検査コース共通の受検時の注意事項○
1.初めて受検する方はあらかじめ検査担当者に申し出て下さい。
2. 低地上高の低い車両、幅の広いタイヤ(偏平率50%以下)を装着した車両で受検する方は、検査担
当者に申し出て下さい。
3.トラクションコントロール装置装備車は、当該装置の作動を解除して受検して下さい。
4.車の中心をテスタの中心に合わせてまっすぐに進入して下さい。
5.テスタへの乗り入れ、脱出、その他の動作は表示器又は検査担当者の指示に従って下さい。
6.テスタ上では急停車、急発進をしないで下さい。
7.テスタ上ではハンドルを切らないで下さい。
8.ヘッドライト・テスタの動きに注意して進行して下さい。
9.ディーゼル車はCO・HCテスタを使用しないで下さい。
10.オートマチック車から離れるときは、サイドブレーキを掛け、シフトレバーを確実に「P」レンジの位
置にして下さい。
11.排気ガス・テスタのプローブを入れたままエンジンをスタートしたり、回転を上げたりしないで下さ
い。
12.検査コース内において車両を後退させる場合は表示器又は検査担当者の指示に従って下さい。
13.検査コース内は禁煙です。
受検に当たっての禁止事項

(234)
14.検査中の携帯電話の使用及びサンダル、スリッパ等運転装置の誤操作のおそれのある履物での受検は
ご遠慮下さい。
15.検査担当者の指示に従わずに受検車両を操作し、車両が損傷しても、当方は一切責任を負いませんの
で、検査担当者の指示に従って下さい。
16.必要な場合を除き、前後の受検車両との間に立たないで下さい。また、その間を通行しないで下さい。
検査は、自動車検査官の視認等や自動化された検査機器を用いて行います。
受検時の注意事項は次のとおりです。なお、検査コースにより検査機器の方式が異なる場合がありま
すので、詳しくは検査担当者にお尋ね下さい。
○自動方式総合検査機器(マルチ・テスタ)の受検時の注意事項○
1.軸重1,500kg(機器によっては2,000kg)以上の車両、二輪車及び三輪車はコースに乗り入れないで下
さい。
2.再入場車両、フラットロー車及び4WS車は該当する申告ボタンを押して下さい。
3.進入表示器の「進入」表示を確認したのち、ゆっくりとテスタへ乗り入れて下さい。
○自動方式検査機器の受検時の注意事項○
1.軸重1,500kg(機器によっては2,000kg、また、大小兼用コースにおいては10,000kg)以上の車両はコ
ースに乗り入れないで下さい。
2.前輪駆動車は、駐車ブレーキ選択ボタンを押して下さい。なお、大小兼用コースには、選択ボタンが
ない場合があります。
3.再入場する車両は該当する申告ボタンを押して下さい。なお、ヘッドライト、排気ガス及び下回りの
再入場の場合は、インターホン等で申告して下さい。
4.パートタイム4WD車は2輪駆動に切り替えて受検して下さい。
5.入場信号灯の「青色」を確認したのち、ゆっくりとテスタへ乗り入れて下さい。
6.ヘッドライト検査の際は車両の停止位置案内線に沿って正しくテスタに正対させて下さい。
7.フルタイム4WD車、二輪車及び三輪車は検査担当者に申し出て下さい。
8.2デフ車のスピード検査時はデフロックを入れて下さい。
○3次元測定・画像取得装置の使用時の注意事項○
1.停止位置案内線に沿って、コースの中央に直進姿勢で停止して下さい。
2.画像の撮影及び諸元測定の際は、受検車両以外の写り込みを防ぐため受検車両の近傍に近寄らないで
下さい。
◆◆◆◆ 検査機器の方式毎に次の事項にご注意下さい。◆◆◆◆

(235)

(236)
(23) 自動車審査高度化施設の概要について
自動車検査法人
平成 23 年6月

(237)

(238)

(239)

(240)
(24)
タイヤ許容限度表
〔タイヤ1本あたりの負荷能力(ロ
ードインデックス)〕

(241)

(242)

(243)

(244)

(245)

(246)
(25) ハイブリッド車等の整備モードについて
〔トヨタ車〕
◎ プリウス(GF-NHW10・ZA-NHW11に限る)
(1) 整備モードへの移行操作
① 次の②~⑤の操作を60秒以内に行う。
② IGスイッチをOFFからONにする。
③ シフトレバーPレンジで、アクセルベダルを2回全開にする。
④ シフトレバーNレンジで、アクセルベダルを2回全開にする。
⑤ シフトレバーPレンジで、アクセルベダルを2回全開にする。
⑥ 整備モードに移行し、マルチセンターディスプレイのハイブリッドシステム異常警告灯が点滅する。
⑦ IGスイッチをSTARTにすると、エンジンが連続運転となる。
注 意 ・整備モードでのアイドル回転数は1000rpm/minで、アクセルペダルを踏むと約1500rpm/min
までレーシングする。
・整備モード移行中にダイアグノーシスコードが記憶されると、マスターウォーニングは
点灯するが、マルチセンターディスプレイの警告灯の異常表示はされない。
・整備モードでの作業中にマスターウォーニングが点灯した場合は、整備モードを停止し
してダイアグノーシスコードの点検を行う。
<参考> 排気漏れ点検などでエンジンの連続運転を行う場合は、容易な方法としてエアコンの
FullスイッチをONしても良い。

(247)
プリウス(NHW20系、ZVW30系)に限る
整備モードへの移行操作
1.ブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを2回押す。(以下60秒以内に実施)
2.PポジショニングスイッチPレンジでアクセルペダルを2回全開にする。
3.ブレーキを踏みながらシフトスイッチNレンジに移行してアクセルペダルを2回全開にする。
4.Pポジショニングスイッチを押してPレンジに移行しアクセルペダルを2回全開にする。
5.整備モードに移行しマルチディスプレイ内のハイブリッドシステム灯が点滅する。(プリウス30
系は、整備モードに移行するとメンテナンスモードの表示が出る)
6.ブレーキを踏みながらプッシュスタートスイッチを1回押す。
(2) 車両検査時の留意事項
車両の状態
① 整備モードに移行する前にA/C OFF、Pレンジでエンジン始動後、数秒でエンジンが停止することを
確認する。(エンジン暖機状態の確認)
② 整備モードに移行し検査を行う。なお、検査時のシフト位置は次のとおりとする。
検 査 項 目 シ フ ト 位 置
1.自動車直進性試験(サイドスリップ) Dレンジ
2.制動力試験 Nレンジ
3.速度計試験 Dレンジ
4.排出ガス試験(アイドリング) Pレンジ
5.前照灯試験 Pレンジ
③ 検査終了後ただちに整備モード解除する。(IGスイッチをOFFにすると解除されます)
注 意 ・整備モードままで路上を走行すると、トランスアクセルを破壊する恐れがある。
(3) 速度計試験時の留意事項
注 意 ・負荷設定のないスピードメータテスタ上で急発進、急加速を行うとトランスアクセルを
破壊する恐れがある。
① 測定時はアクセルペダルをゆっくり踏み、緩やかに速度を上げる。
② 測定後はアクセルペダルをゆっくり減速し、停止する。

(248)
◎ エスティマ
整備モードについて
エスティマ・ハイブリッドは、エンジン暖機状態でバッテリの充電状態が良好、かつ、A/Cコンプレッサの
駆動要求がない場合には、停車中にエンジンを自動停止する。このため、点火時期の点検などで停車中でも
エンジンの連続運転が必要なときは4WD整備モードに移行する。
エスティマ・ハイブリッドは、後輪の駆動に電気モータを使用した電子コントロール4WD、トラクション・
コントロール(TRC)を採用しているため、スピードメータ・テスタなどで前輪のみ回転させる場合は、2
WD整備モードに移行して4WD制御及びトラクション・コントロールを解除する必要がある。
(1) (イ) 2WD整備モードへの移行操作(AHR10W)
① イグニッションスイッチをOFFからONにする。
② シフトレバーPレンジで、アクセルペダルを4回全開にする。
③ シフトレバーNレンジで、アクセルペダルを4回全開にする。
④ シフトレバーPレンジで、アクセルペダルを4回全開にする。
⑤ 整備モードに移行し、ハイブリッドシステムウォーニングおよびHVバッテリーウォーニングが点滅
する。
注 意 上記操作を90秒以内に行う。
⑥ イグニッションスイッチをSTARTにすると、エンジンが連続運転となる。
⑦ 整備モードの解除は、イグニッションスイッチをOFFにする。
(ロ) 4WD整備モードへの移行操作(AHR10W)
① イグニッションスイッチをOFFからONにする。
② シフトレバーPレンジで、アクセルペダルを2回全開にする。
③ シフトレバーNレンジで、アクセルペダルを2回全開にする。
④ シフトレバーPレンジで、アクセルペダルを2回全開にする。
⑤ 整備モードに移行し、ハイブリッドシステムウォーニングが点滅する。
注 意 上記操作を60秒以内に行う。
⑥ イグニッションスイッチをSTARTにすると、エンジンが連続運転となる。
⑦ 整備モードの解除は、イグニッションスイッチをOFFにする。
新型エスティマ(AHR20W)に限る
エスティマハイブリッドは、エンジン暖気状態でバッテリーの充電状態が良好かつA/Cコンプレッサ
ーの駆動要求がない場合には、停車中にエンジンを自動停止する。
このため、点火時期の点検など停車中でもエンジンの連続運転が必要な時は4WD整備モードに移行す
る。
エスティマハイブリッドは、後輪の駆動に電気モーターを使用した電子コントロール4WD、トラクシ
ョンコントロール(TRC)を採用しているため、スピードメーターテスタなどで前輪のみを回転させる場

(249)
合は、2WD整備モードに移行して4WD制御及びトラクションコントロールを解除する必要がある。
旧型(AHR10W)との違いは、2WD整備モード、4WD整備モードの移行操作時のアクセルペダ
ルの踏む回数が入れ違っています。
2WD整備モードの移行操作
1.IGスイッチをOFFからONにする。(以下60秒以内に実施)
2.シフトレバーPレンジでアクセルペダルを2回全開にする。
3.シフトレバーNレンジでアクセルペダルを2回全開にする。
4.シフトレバーPレンジでアクセルペダルを2回全開にする。
5.整備モードに移行し、マルチディスプレイに「2WD整備モード表示」が表示する。
「参考」整備モード中はマルチディスプレイに「2WD整備モード表示」と「VSCチェック表示」及びマ
スターウォーニング点灯が交互に繰り替えされる。
4WD整備モードへの移行操作
1.IGスイッチをOFFからONにする。(以下60秒以内に実施)
2.シフトレバーPレンジでアクセルペダルを4回全開にする。
3.シフトレバーNレンジでアクセルペダルを4回全開にする。
4.シフトレバーPレンジでアクセルペダルを4回全開にする。
5.整備モードに移行し、マルチディスプレイに「4WD整備モード表示」が表示する。
「参考」整備モード中はマルチディスプレイに「4WD整備モード表示」と「VSCチェック表示」及びマ
スターウォーニング点灯が交互に繰り替えされる。
(2) 車両検査時の留意事項
(イ) 車両の状態
① A/C OFF、Pレンジでエンジン始動後、数秒でエンジンが停止することを確認する。(エンジン暖機状
態の確認)
② 整備モードに移行して検査を行う。
③ 検査時の整備モード及びシフト位置は次のとおりとする。
検 査 項 目 整 備 モ ー ド シフト位置
1.自動車直進性試験(サイドスリップ) 4WD整備モード又は通常状態 Dレンジ
2.制動力試験 4WD整備モード又は通常状態 Nレンジ
3.速度計試験 2WD整備モード Dレンジ
4.排出ガス試験(アイドリング) 4WD整備モード Pレンジ
5.前照灯試験 4WD整備モード又は通常状態 Pレンジ
④ 検査終了後直ちに整備モード解除する。(IGスイッチをOFFにすると解除されます)
注 意 ・整備モード解除後、再度、イグニッション・スイッチをONし、インジケータ・ランプが
点灯していることを確認する。

(250)
(ロ) 速度計試験時の注意
注 意 ・2WD整備モードで行う
・負荷設定のないスピードメータ・テスタ上で急発進、急加減速を行うとトランスアクス
ルを破損する恐れがある。
① 測定時はアクセルペダルをゆっくり踏み、緩やかに速度を上げる。
② 測定後はアクセルペダルをゆっくり減速し、停止する。
(ハ) シャシ・ダイナモ・テスタ使用時の留意点
必ず適切な負荷設定後にテストを行う。
注 意 負荷が過小な状態で急発進、急加減速を行うとトランスアクスルを破壊する恐れがある。
◎ クラウン
車両検査時の留意事項
<参考>
マイルドハイブリッド車は、車両が停止すると、シストレバーがD、P、Nレンジ位置でエンジン停止条件が
成立すると自動的にエンジンを停止する。このため排出ガス測定、点火時期点検等でエンジンの連続運転が
必要となる場合にはO/DスイッチをOFFにしてエンジンを連続運転可能とする必要がある。
(a) 車両検査時のシフトレバー位置とO/Dスイッチ状態は次のとおりとする。
検 査 項 目 シフトレバー位置 O/Dスイッチの状態
1.自動車直進性試験(サイドスリップ) Dレンジ ONまたはOFF
2.制動力試験 Nレンジ ONまたはOFF
3.速度計試験 Dレンジ ONまたはOFF
4.アイドルCO/HC試験(アイドリング) PまたはNレンジ OFF
5.前照灯試験 Pレンジ ONまたはOFF
6.近接排気騒音試験 PまたはNレンジ OFF
〔ホンダ車〕
◎ インサイト・ハイブリッド車
車両時の対応
車検の検査工程でオート・アイドル・ストップ・システムが作動した場合、再始動して検査を受けること。
しかし、オート・アイドル・ストップ・システムが作動した場合でも、下記のものは性能を確保できる。
前照灯試験:12VバッテリにIMAバッテリから充電されるので性能は確保できる。
制動力試験:マスタ・パワーに専用の負圧センサがあり、負圧が低下すると自動的に再始動して負圧を確
保するので性能は確保できる。

(251)
【日産車】◎フーガハイブリット (Y51系)
・エンジン暖気状態でリチウムイオンバッテリの充電状態が十分な場合は、車両停止中にエンジンを自動 的に停止する。このため、エンジンの連続運転が必要な場合は整備モードを実施する必要がある。 ・シャシダイナモメータなどで車輪を回転させる場合は、整備モードを実施して車両を適切な状態にする必 要がある。
ハイブリットシステム警告灯
12V系充電警告灯
エンジン無負荷状態で実施する点検等
・クラッチ1を解放しエンジンを無負荷状態にする。(Pレンジのみ)・エンジンを連続運転する。
点滅 ー
2輪シャシダイナモメータで走行する場合等
前後輪の回生ブレーキのバランスを変更する。
ー 点滅
4輪シャシダイナモメータで走行する場合等
勾配推定を禁止する。 点滅 点滅
エンジンのみで走行する場合等
エンジンを連続運転する。 点滅 ー
[整備モードへの移行操作] 1.以下の操作を60秒以内に実施する。 (1)セレクトレバーをPレンジでキースイッチをONにする。 (2)アクセルペダル全開、全閉を2回繰り返す。 (3)ブレーキを踏みながらセレクトレバーをNレンジにする。 (4)アクセルペダル全開、全閉を2回繰り返す。 (5)ブレーキを踏みながらセレクトレバーをPレンジにする。 (6)アクセルペダル全開、全閉を2回繰り返す。 2.整備モード1に移行し、コンビネーションメータ内のハイブリッドシステム警告灯が点滅する。 3.車両をREADYにする。
※上記の方法は整備モード1の方法です。整備モード2へはアクセルペダルの操作回数を3回にする。整備モード3へはアクセルペダルの操作回数を4回にする。整備モード5へはアクセルペダルの操作回数を6回にする。
アクセルペダルの操作回数を変える(モードプラス1)ことで各整備モードへの移行が変わります。
整備モードの解除操作 1.キースイッチをOFFにすると整備モードは解除される。
15 ハイブリットシステム警告灯18 12V系充電警告灯
整備モード1
整備モード2
整備モード3
整備モード5
コンビネーションメータ
整備モード 主な使用目的 制御内容

(252)
(26)保安基準適用時期等一覧表
条 項 目 基 準 適 用 時 期
2 自動車の長さ、幅、高さ 長さ12、幅2.5、高さ3.8 m以下(セミトレーラー の全長にあっては連結中心より後端までの距離) 軽自動車 長さ3.0 幅1.3 高さ2.0 360㏄
長さ3.2 幅1.4 高さ2.0 550㏄ 長さ3.3 幅1.4 高さ2.0 660㏄ 長さ3.4 幅1.48 高さ2.0 660㏄
S50.12.31 以前S51. 1. 1 以降H 2. 1. 1 以降H10.10. 1 以降
4 車両総重量 自動車の種別 車 両 総 重 量
最遠軸距
セミトレーラー以外の自動車
5.5 m未満 20t以下
5.5 m以上7m未満
22t以下(長さが9m未満の自動車にあって は20t以下)
7m以上 25t以下(長さが9m未満の自動車にあって は20t以下、長さが9m以上11m未満の自動 車にあっては22t以下)
セミトレーラー 5m未満 20t以下
5m以上7m未満
22t以下
7m以上8m未満
24t以下
8m以上9.5 m未満
26t以下
9.5 m以上 28t以下
4 の2
軸 重 10t以下
隣接軸重 隣接軸距1.8m未満 18t以下(隣接軸重の和) H5.11.25 以降製作車(隣り合う車軸にかかる荷重の和が増加する改造を行う場合を除く)
隣接軸距1.3m以上1.8m未満で、1軸荷重9.5t以下
19t以下(隣接軸重の和)
隣接軸距1.8m以上 20t以下(隣接軸重の和)
輪荷重 5t以下
5 安定性 自動車の種別 最 大 安 定 傾 斜 角 度
側車付二輪 25°(空車状態)
車両総重量が車両重量の1.2倍以下の自動車
30°(空車状態)
二階建バス 28°(乗務員及び二階座席乗車状態)
上記以外 35°(空車状態)
6 最小回転半径 最外側のわだちについて12m以下
7 接地圧 ゴム製タイヤの接地圧は200㎏/cm以下

(253)
条 項 目 基 準 適 用 時 期
8
原動機及び動力伝達装置
二重アクセルリターンスプリング H6.4.1以降製作車(二輪自動車除く)
速度抑制装置の適用時期
車 種 適 用 時 期
新 型 車 継続生産車
平成6年度排出 ガス規制適合車
(KC-)
初年度登録 平成10年1月1日以降
平成15年9月1日以降の製作車
平成15年9月1日以降の最初の検査の日
初年度登録 平成9年1月1日~平成9年12月31日 平成16年9月1日以降の最初の検査の日
初年度登録 平成8年12月31日以前 平成17年9月1日以降の最初の検査の日
平成10、11年度排出ガス規制適合車 (KK-,KL-)
初年度登録 平成15年1月1日以降 平成15年9月1日以降の最初の検査の日
初年度登録 平成14年1月1日~平成14年12月31日 平成16年9月1日以降の最初の検査の日
初年度登録 平成13年12月31日以前 平成17年9月1日以降の最初の検査の日
上記以外の自動車 (輸入車など)
初年度登録 平成14年1月1日以降 平成15年9月1日以降の最初の検査の日
初年度登録 平成11年1月1日~平成13年12月31日 平成16年9月1日以降の最初の検査の日
初年度登録 平成10年12月31日以前 平成17年9月1日以降の最初の検査の日
9
走行装置等 空気入りゴムタイヤの滑り止めの溝深さ
二輪自動車 0.8mm以上その他の自動車 1.6mm以上
10
操縦装置
操縦装置の範囲(始動装置、前照灯、デフロスタの操作装置等)かじ取りハンドルの中心から左右500mm以内 操縦装置の識別表示
S50.12. 1 以 降(デフロスタに関する部分に限る) S48.12. 1 以降
11 かじ取り装置 衝撃吸収式かじ取り装置(乗用自動車) S48.10. 1 以降
11 の2
施錠装置
専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上のものを除く)
S48.12. 1 以降
12
制動装置
二重安全ブレーキ 液漏れ警報装置(二輪車除く) 圧力降下警報 ABS装置(12tを超える大型バス(一般路線バスを除く)及び7tを超えるトラクタ)
S46.12.31 以前の2t未満の自動車(10人以下の旅客運送事業用自動車除く)S50.12. 1 以降S45. 6. 1 以降H 3.10. 1 以降H 4. 4. 1 以降(12t超えバス)H 7. 9. 1 以降(13t以下トラクタ)

(254)
条 項 目 基 準 適 用 時 期
12
トラック・バス等
主
制
動
装
置
操作力 70㎏以下(700N)以下
総重量3.5t以下H11. 7. 1 以降(継続生産車) H 9.10. 1 以降
(新型車) 総重量3.5t超えH12. 7. 1 以降(継続生産車) H10.10. 1 以降
(新型車) H16. 1. 1 以降(製作車)
上記の車以外は4項適用(4項表参照)
制動能力 自動車の最高速度 75㎞/h超専ら専用(10人以上) 100㎞/h超総重量3.5t以下 75㎞/h超総重量3.5t超
停止距離S1 S2
イ.S1 ≦0.15V1+0.0077V1 2
制動初速度V1V2
最高速度V1 60㎞/h超専ら乗用(10人以上) :60㎞/h 80㎞/h超総重量3.5t超の自動車 :60㎞/h 80㎞/h超総重量3.5t以下の自動車 :80㎞/h ロ.S2 ≦0.15V2+0.0097V2
2 最高速度の80%の速度 V2 125㎞/h超専ら乗用 :100㎞/h (10人以上、総重量5t以下) 112.5㎞/h超専ら乗用 :90㎞/h (10人以上、総重量5t超) 150㎞/h総重量3.5t以下 :120㎞/h 125㎞/h総重量3.5t超12t以下 :100㎞/h 112.5㎞/h超総重量12t超 :90㎞/h けん引自動車セミトレーラをけん引するもの :80㎞/h
駐車ブレーキ
操作力 足動式70㎏(700N)以下 手動式60㎏(600N)以下
制動能力 けん引自動車(連結状態)
9/50のこう配で停止状態保持停止距離S ・S≦0.15V+0.0257V2
制動初速度 最高速度V(最高速度が30㎞/h超える自動車は
30㎞/h) 3/25のこう配で停止状態保持
専ら乗用(
乗車定員10人未満)
主
制
動 装
置
操作力 50㎏以下(500N)以下 ワンボックス車及び車枠有り4WD車除く H 8. 1. 1 以降(継続生産車)H 6. 4. 1 以降
(新型車) H11. 4. 1 以降
(輸入車) ワンボックス車及び車枠有り4WD車に限る H11. 7. 1 以降(継続生産車)H 9.10. 1 以降
(新型車) H14.10. 1 以降 H16. 1. 1 以降 上記の車以外は4項適用(4項表参照)
自動車の最高速度 125㎞/h超 125㎞/h以下
停止距離S1S2
イ.S1≦0.1V1+0.0060V12
制動初速度V1V2
最高速度V1 最高速度が100㎞/h超える自動車:100㎞/h ロ.S2≦0.1V2+0.0067V2
2 最高速度の80%の速度 V2 最高速度の80%が160㎞/h超自動車:160㎞/h すき間自動調整・磨耗確認・圧力蓄積(運転者の操作力で規定の制動力が得られるものを除く)の備付 イ.S1≦0.1V1+0.0060V1
2
制動初速度V1
最高速度V1 最高速度が100㎞/h超える自動車:100㎞/h
駐車ブレーキ
操作力 足動式50㎏(500N)以下 手動式40㎏(400N)以下
制動能力
1/5のこう配で停止状態保持停止距離S ・S≦0.1V+0.0257V2
制動初速度 最高速度V(最高速度が30㎞/h超える自動車は
30㎞/h)

(255)
条 項 目 基 準 適 用 時 期
12 (4項)抜枠
主制動装置制動能力
最高速度(㎞/h) 制動初速度(㎞/h) 停止距離(m)
80以上 50 22以下
35以上80未満 35 14以下
20以上35未満 20 5以下
20未満 その最高速度 5以下
駐車ブレーキ制動能力 1/5のこう配で停止状態保持
トレーラーの慣性ブレーキ 総重量3.5t以下のトレーラー(セミトレーラー除く) 最高速度20㎞/h未満のけん引自動車にけん引されるトレーラー 最高速度35㎞/h未満の大型特殊及び農耕小型特殊にけん引されるトレーラーで2t未満のもの
H11. 6.30 以前は下線を「総重量750㎏以下のトレーラー及び総重量750㎏を超3.5t以下のトレーラー」に読替
トレーラーの主制動装置の省略 総重量750㎏以下のトレーラーで車両総重量がトラクタの車両重量の1/2以下のもの けん引車が乗用車の場合 S1 ≦0.1V1+0.0071V1
2
H11. 7. 1 以降 H16. 1. 1 以降製作車
14 緩衝装置の備付 総重量2t未満のトレーラー以外(緩衝装置の改造を行ったものを除く。爆発性液体を運送するトレーラーは適用)
S58.12.31 以前は総重量2t未満の自動車
15 燃料タンク注入口及びガス抜口の距離 排気管の開口部から300ミリ以上露出電気端子及び電気開閉器から200ミリ以上
衝突時の燃料漏れ防止 もっぱら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上は除く)
S50.12. 1 以降
車両総重量2.8t以下の小型貨物車等 S62. 9. 1 以降S63. 4. 1 以降
(輸入車)
被追突時の燃料漏れ防止 もっぱら乗用の用に供する自動車 S62. 3. 1 以降S63. 4. 1 以降
(輸入車)
車両総重量2.8t以下の小型貨物車等 S62. 9. 1 以降S63. 4. 1 以降
(輸入車)
17 L.P.G容器の固定 全車 S47. 1. 1 以降
緊急遮断装置の備付 全車 H 1.10. 1 以降
18 回転部分突出禁止 全車 S49. 7. 1 以降
車体の衝撃吸収性能 もっぱら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上、二輪、側車付二輪、ワンボックス車、車枠を有する4WD車は除く)
H 8. 1. 1 以降H11. 4. 1 以降
(輸入車)
18 の2
巻込防止装置 普通貨物(大型貨物は全車適用) S48.12. 1 以降
突入防止装置 (けん引車除く) 大型貨物リヤバンパー(けん引車除く)
大型貨物普通貨物 総重量7t以上 積載量5t総重量8t以上の大型貨物 車両総重量3.5t超の貨物自動車 車両総重量3.5t超であって、小型枠(長さ4.7m、幅1.7m、高さ2m)の貨物自動車
S43. 8. 1 以降S48.12. 1 以降H 9.10. 1 以降H 4. 6. 1 以降H17. 9. 1 以降H19. 9. 1 以降
前部潜り込み防止装置 車両総重量3.5tを超える貨物自動車(三輪自動車、被牽引自動車及び全輪駆動車、並びに前部潜り込み防止装置を備えることにより本来の性能を損なうこととなる特殊な装備を有する自動車及び特殊な装備を装着するために前部潜り込み防止装置を装着することが困難な自動車を除く。)
H23.10. 1 以降

(256)
条 項 目 基 準 適 用 時 期
20
インストルメントパネルの衝撃吸収化 もっぱら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上、二輪、側車付二輪等を除く)
S50. 4. 1 以降
運転者室及び客室の内装材の難燃性 全車 H 6. 4. 1 以降H 7. 4. 1 以降
22 シートバック後面の衝撃吸収化 座席及び座席取付装置の取付強度の強化
もっぱら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上、二輪、側車付二輪等を除く)
S50.12. 1 以降
22 の3
座席ベルト及び座席ベルト取付装置の適用時期
対象車
対象 座席
専 ら 乗 用 専ら乗用以外 (50年3月31日以前の事業用乗用には運転者関及び旅客3人分の座席に第1種
ベルトを備える)
定員10人以下 定員11人以上 普 通 小 型
普通・小型 一般路線バス そ の 他
運転席及びこれと並列の座席
運 転 席
44. 4. 1 (1種)
50. 4. 1 (2種)
62. 3. 1 (2種ELR) 63. 4. 1
(輸入車)
62. 9. 1(1種ELR)63. 4. 1
(輸入車)
62. 9. 1(1種ELR)63. 4. 1
(輸入車)
50.12. 1(1種)
62. 9. 1 (1種ELR)63. 4. 1
(輸入車)
44.10. 1 (1種)
50. 4. 1 (2種)
62. 9. 1 (2種ELR) 63. 4. 1
(輸入車)
中 席
62. 3. 1 (1種ELR) 63. 4. 1
(輸入車)
62. 9. 1(1種ELR)63. 4. 1
(輸入車)
62. 9. 1(1種ELR)63. 4. 1
(輸入車)
62. 9. 1(1種ELR)63. 4. 1
(輸入車)
62. 9. 1 (1種ELR) 63. 4. 1
(輸入車)
助 手 席
48.12. 1 (1種)
50. 4. 1 (2種)
62. 3. 1 (2種ELR) 63. 4. 1
(輸入車)
62. 9. 1(1種ELR)63. 4. 1
(輸入車)
62. 9. 1(1種ELR)63. 4. 1
(輸入車)
50.12. 1(1種)
48.12. 1 (1種)
50. 4. 1 (2種)
62. 9. 1 (2種ELR) 63. 4. 1
(輸入車)
その他の座席
窓 側 席
50. 4. 1 (1種)
6. 4. 1 (2種ELR) 7. 4. 1
(輸入車)
62. 9. 1(1種)
63. 4. 1 (輸入車)
62. 9. 1(1種)
63. 4. 1 (輸入車)
50. 4. 1 (1種)
6. 4. 1 (2種ELR) 7. 4. 1
(輸入車)
中 席
62. 3. 1 (1種)
63. 4. 1 (輸入車)
62. 9. 1(1種)
63. 4. 1 (輸入車)
62. 9. 1(1種)
63. 4. 1 (輸入車)
62. 9. 1 (1種)
63. 4. 1 (輸入車)
座席ベルト非装着時警報装置 専ら乗用の用に供する普通自動車小型自動車若しくは軽自動車であって、乗車定員10人未満の自動車
H 6. 4. 1 以降H 7. 4. 1 以降 (輸入車)
22 の4
頭部後傾抑止装置の適用時期
対象車 対象 座席
乗 用 そ の 他 総重量3.5t以下 トラック・バス 自家用 事業用 小 型
運転者席 44. 4. 1 全 車 45. 4. 124. 7. 1
助手席 48.12. 1 48.12. 1
旅客3人分席 全 車
側面に隣接するすべての席 24. 7. 1
25 乗降口 ドアの開放防止装置
客室の乗降口を右側面以外に1箇所設ける 乗車定員11人以上の自動車は除く
S46. 1. 1 以降S50.12. 1 以降
29 窓ガラス
種 類区 分
安全ガラスの義務付け
強化ガラスの禁止 (部分強化ガラスは適合) H P R 合わせガラスの義務付け
前 面 ガ ラ ス
乗用車 33. 1. 1 45. 6. 1 62. 3. 1(輸入車63. 4. 1)
貨物等 33. 1. 1 45. 6. 1 62. 9. 1(輸入車63. 4. 1)
その他の ガ ラ ス
乗用車 48.12. 1
貨物等 48.12. 1

(257)
新型車 H12.10. 1 以降継続生産車 H14. 9. 1 以降
条 項 目 基 準 適 用 時 期
30 定常走行騒音(全車適用) 85デシベル 全ての種別について、 ア:S46.4.1以降イ:S47.1.1以降ウ:S51.1.1以降エ:S54.1.1以降
ただし 二輪の輸入車 H 1. 4. 1以降
また、試作車等はS61. 6. 1以降 普通・小型・軽の乗用以外と大特・小特の輸入車 H 4. 4. 1以降
また、試作車等はH 1. 6. 1以降 普通・小型・軽の乗用で輸入車 H 3. 4. 1以降
また、試作車等はS 61. 6. 1以降
近
接
排
気
騒
音(太線内は平成10~13年騒音規制)
二輪自動車(含・側車付) 99デシベル
大型特殊自動車、小型特殊自動車 110デシベル
普通自動車 小型自動車 軽自動車
定員10人 以下の 乗用以外
総重量 3.5t 超え
最高出力200PS 超 107デシベル
最高出力200PS 以下 105デシベル
総重量3.5t以下(定員10人以下の乗用含む) 103デシベル
ア:型式指定車 イ:S46.3.31以前の型式指定車 ウ:騒音認定車 エ:大臣認定車(少数台数、輸入車特別)
大型特殊自動車、小型特殊自動車 110デシベル
普通自動車 小型自動車 軽自動車 (定員10人以下の乗用除く)
総重量3.5t超
200HP 150KW※超
乗 用 99デシベル(10年規制)
乗用以外 99デシベル(13年規制)
総重量3.5t超
200HP 150KW※ 以下
全輪駆動車 98デシベル(13年規制)
全輪駆動車以外
乗 用 98デシベル(12年規制)
乗用以外 98デシベル(13年規制)
総重量3.5t以下 97デシベル(12年規制)
普通自動車 小型自動車 軽自動車 (定員10人以下)
定員7人以上 後部エンジン 100デシベル(11年規制)
新型車
10年規制H10.10.1以降
11年規制H11.10.1以降
12年規制H12.10.1以降
13年規制H13.10.1以降
後部エンジン以外 96デシベル(11年規制)
定員6人以下 後部エンジン 100デシベル(10年規制)
後部エンジン以外 96デシベル(10年規制)
二輪自動車 (側車付含む)
小型 94デシベル(13年規制)
軽 94デシベル(10年規制)
排気騒音 近接排気騒音が適用される製作年以前のもの 85デシベル
消音器の加速走行騒音性能規制 消音器が加速走行騒音を有効に防止す るものであること
新型車 H22.4.1以降
31
ブローバイガス還元装置の取付け
S46. 1.1 以降二輪車は 11.10.1 以降 軽油は 14年規制以降
燃料蒸発ガス抑止装置(ガソリン車のみ) S48. 4. 1以降
燃料蒸発ガス(HC)の排出基準 (ガソリン車のみ)
蒸発量2.0グラム
遅角調整(大臣の指示する遅角度に点火時期を調整する) S42.12.31 以前
排気管 の
向 き
左 右 向 開 口 不 可 S47. 1. 1 以降
左 向 開 口 不 可 S46.12.31 以前
熱害対策装置等(点火装置が接点式のものに限る)…遮熱板・温度センサー・燃料カットシステム・OBDⅡ以前

(258)
CO 全 車 4.5%
条 項 目 基 準 適 用 時 期
31 ア
イ
ド
リ
ン
グ
規
制
ガソリン・LPG車
10
年規制以前
(10年規制) 新型車
H.10.10. 1 以降
継続生産車 H.11. 9. 1 以降
輸入車
H.12. 4. 1 以降
H C
4 サ イ ク ル 車 1200ppm
特 殊 エ ン ジ ン 3300ppm
2 サ イ ク ル 車 7800ppm
ガソリン・LPG車・CNG車
10
年
規
制
以
降
C O 4 サ イ ク ル 車 1.0%
(排ガス記号) GC.GE.GF.GG.GH.GJ.GK.GL.GM等
(11年規制)
新型車
H.11.10. 1 以降継続生産車
H.12. 9. 1 以降
輸入車 H.13. 4. 1 以降
(12年規制)
新型車 H.12.10. 1 以降
継続生産車・輸入車
H.14. 9. 1 以降(13年規制)
新型車
H.13.10. 1 以降継続生産車・輸入車
H.15. 9. 1 以降
(14年規制) 新型車
H.14.10. 1 以降
継続生産車・輸入車 H.15. 9. 1 以降
(19年規制)
新型車 H.19.10. 1 以降
継続生産車・輸入車 H.20. 9. 1 以降
軽 自 動 車 2.0% GD.GF
H C
4 サ イ ク ル 車 300ppm GC.GE.GF.GG.GH.GJ.GK.GL.GM等
2 サ イ ク ル 車 7800ppm
軽 自 動 車 500ppm GD.GF
二
輪
車
(
側
車
付
含
む
)
10
年
規
制
C O 4 サ イ ク ル 車 ( 軽 ) 4.5% BA
2 サ イ ク ル 車 ( 軽 ) 4.5% BB
H C 4 サ イ ク ル 車 ( 軽 ) 2000ppm BA
2 サ イ ク ル 車 ( 軽 ) 7800ppm BB
11
年
規
制
C O 4サイクル車(小型) 4.5% BC
2サイクル車(小型) 4.5% BD
H C 4サイクル車(小型) 2000ppm BC
2サイクル車(小型) 7800ppm BD
19年規制
C O 小 型 二 輪
3.0% EAL.EBL
H C 1000ppm
黒
煙
規
制
ディーゼル乗用車
50%(4年規制以前) K.N.Q.X.Y
40%(6年規制) KD
25%(9、10、14年規制) KE.KH.KM.KN
総重量1.7t以下 総重量1.7t超え2.5t以下 (乗用車除く)
50%(63年規制以前) K.N.P.S
40%(5年規制) KA.KB
25%(9、10、14、15年規制)
KE.KF.KJ.KP.KQ
総重量2.5t以上 9年規制 総重量 3.5t以下 10年規制 総重量 12t以下 11年規制 総重量 12t超え
50%(2年規制以前) K.N.P.S.U.W
40%(6年規制) KC
25%(9、10、11、15、16年規制)
KG.KK.KL.KR.KS
(5年規制) 新型生産車 H 5.10. 1 継続生産車 H 6. 9. 1 輸入車 H 7. 4. 1
(6年規制) 新型生産車 H 6.10. 1 継続生産車 H 7. 9. 1 輸入車 H 8. 4. 1
(9年規制)新型生産車 H9.10. 1 継続生産車 H11. 7. 1 輸入車 H12. 4. 1
(10年規制) 新型生産車 H10.10 .1 継続生産車 H11 .9. 1 輸入車 H12. 4. 1
(11年規制)新型生産車 H11.10. 1 継続生産車 H12. 9. 1 輸入車 H13. 4. 1
(14年規制)新型車 H14.10. 1以降 継続生産車・輸入車 H16. 9. 1以降
(15年規制) 新型車 H15.10. 1以降 継続生産車・ 輸入車 H16. 9. 1以降
(16年規制)新型車 H16.10. 1以降 継続生産車・輸入車 H17. 9. 1以降
光吸収係数規制
17年規制適合車で、次の いずれかの条件を満たす自動車に限る ○備考に「オパシメータ測定」 ○型式指定番号「16000」以降 ○装置型式指定番号「G-2001」以降
0.80m-1 A※B、C※B、D※B
A※C、C※C、D※C A※E、C※E、D※E A※F、C※F、D※F A※G、B※G、C※G D※G、N※G、P※G (※はアルファベット)

(259)
条 項 目 基 準 適 用 時 期
31 光吸収係数規制
21年規制適合車 0.50m-1 L※A、F※A、M※A、R※A
L※E、M※E、R※E L※F、M※F、R※F L※G、M※G、R※G (※はアルファベット)
22年規制適合車 0.50m-1 S※F、Q※※
S※G、T※※ (※はアルファベット)
31 の2
指定自動車(NOx規制の適用車) ガソリン・ディーゼル・LPG車
普通貨物 小型貨物 大型バス 小型バス 特種自動車(トラック、バスがベースになったもの)
特定地域内に使用の本拠を有するものについて特定自動車排出基準によって判断する
型式指定車(輸入予定数2千台以上) ガス認定車(輸入予定数2千台以上) 窒
素酸化物諸元値
平均排出ガス基準値以下 新車 H 5.12.1 以降(総重量3.5t超5.0t以下は、H 8. 4. 1 以降) 使用過程車については個別猶予期間あり
型式指定車(輸入予定数2千台未満) ガス認定車(輸入予定数2千台未満) 輸入車特別、並行輸入車等 原動機の変更又はランクの変更を行ったもの及びNOx低減装置を装着したもの
31条の2の基準値以下
検査証の備考欄記載があればそれにより判定する
項 目 適用時期及び基準
32 前照灯等 H18. 1. 1 以降 H17.12.31以前
走行用
数 2個又は4個(二輪車等は1個又は2個)
色 白色 白色又は淡黄色(同一色)
電気結線 すべて同時又は左右それぞれ1個が同時点灯
取付位置 左右対称(二輪車にあっては走行用及びすれ違い用の中心が左右対称であればよい)
その他の要件 同時点灯時の最高光度の合計が430000cd以下
点灯操作状態表示装置 必要 (二輪車等は不要) 除外
すれ違い用 数 2個(二輪車等は1個又は2個)
色 白色 白色又は淡黄色(同一色)
電気結線
すれ違い操作時、走行用は消灯放電灯は走行用点灯時、消灯不可
放電灯点灯要件除外
二輪車等は原動機の作動中、走行用又はすれ違いのいずれか点灯
H10. 4. 1以降
取付位置
上縁 下縁 最外側 その他 照明部の中心が1.2m以下 下縁要件除外 1.2m以下 0.5m以上 0.4m以内
二輪車等は照明部の中心が1.2m以下左右対称(二輪車にあっては走行用及びすれ違い用の中心が左右対称であればよい)
33 前部霧灯 数 同時に3個以上点灯しない
色 白色又は淡黄色(同一色)
電気結線 走行用、すれ違い用の点灯状態にかかわらず点灯・消灯ができる
除外

(260)
条 項 目 適 用 時 期 及 び 基 準
33 前部霧灯 H18. 1. 1 以降 H17.12.31以前
取付位置
上縁 下縁 最外側 中心がすれ違い用の中心を含む水平面以下 0.8m以下 0.25m以上 0.4m以内
上縁はすれ違いの上縁を含む水平面以下
二輪車等は中心がすれ違い用の中心を含む水平面以下
見通し角度 上方 下方 内側方向 外側方向 除外
5° 5° 10° 45°
その他の要件 点灯操作状態表示装置 必要 除外
33 の2
側方照射灯 H21. 4. 1以降(乗用 9人以下/貨物 総重量3.5t以下) H27. 4. 1以降(乗用 10人以上/貨物 総重量3.5t超)
左欄以前
数 2個
色 白色 白色又は淡黄色(同一色)
電気結線 すれ違い用又は走行用が点灯している場合のみ点灯 方向指示器の作動又はかじ取り装置と連動 方向指示器の作動解除又はかじ取り装置が直進状態に戻った場合は自動停止
方向指示器と連動
取付位置
上縁 下縁 除外
0.9m以下 0.25m以上
すれ違い用の上縁を含む水平面以下
最後縁は自動車の前端から1m以内 最前縁は自動車の前端から2.5m以内
34 車幅灯 H18. 1. 1 以降 H17.12.31以前
数 2個又は4個 除外
色 白色(方向指示器等と構造上一体又は兼用及び二輪車等にあっては橙色可)
白色、淡黄色又は橙色(同一色)
電気結線 方向指示器と兼用の場合、方向指示器を作動させている側が消灯
取付位置
上縁 下縁 最外側 上縁が2.1m以下下縁要件除外
2.1m以下 0.35m以上 0.4m以内被牽引車は0.15m以内
左右対称 左右同じ高さ
二輪車等は中心が2m以下
見通し角度 上方 下方 内側方向 外側方向 除外
15° 15°5°(※1)
45°5°(※2)
80°
その他の要件 点灯操作状態表示装置 必要 除外
注※1:照明部の上縁高さが地上 0.75m未満である場合 ※2:被牽引車である場合

(261)
条 項 目 適 用 時 期 及 び 基 準
34 の2
前部上側端灯 H18. 1. 1 以降 H17.12.31以前
数 2個又は4個 除外
色 白色
取付位置 上側2個は上縁が前面ガラスの最上端以上(被牽引車は取り付けることができる最高の高さ) 4個備える場合は、上側2個と下側2個の距離は可能な限り離れており、下側2個の最前縁と自動車の後端との距離は0.4m以内で可能な限り自動車の後端に近付けて取り付けられていること
最外側から0.4m以内左右対称 車幅灯と0.2m以上離れていること
見通し角度 上方 下方 内側方向 外側方向
5° 20° 80°
35 前部反射器 色 白色 白色又は橙色
取付位置
上縁 下縁 最外側 反射部の中心が2m以下 下縁要件除外 1.5m以下 0.25m以上 0.4m以内
左右対称
見通し角度 上方 下方 内側方向 外側方向 除外
10° 10°5°(※1)
30°10°(※2)
30°
その他の要件 被牽引車の前面両側に必要
形は文字及び三角形以外 形は文字以外
35 の2
側方灯 側方反射器
色 橙色(尾灯等と構造上一体又は兼用にあっては赤色可) 前部又は中央部は橙色 後部は橙色又は赤色(同一色)
電気結線 方向指示器と兼用の側方灯は方向指示器の作動中に消灯すること 方向指示器と兼用でない側方灯は非常点滅表示灯と同時に点滅する構造可
取付位置 上縁 下縁 下縁要件除外
側方灯 2.1m以下 0.25m以上
側方反射器 1.5m以下 0.25m以上 中心が2m以下
二輪車等は中心が地上2m以下
長さ6mを超える普通自動車、ポール・トレーラ3mごとに必要 少なくとも1つは最前縁が自動車の前端から長さの1/3以上、かつ、最後縁が自動車の後端から長さの1/3以上 最前部の最前縁が自動車の前端から3m以内 最後部の最後縁が自動車の後端から1m以内
【乗用を除く】
長さ9m以上普通自動車
前部、中央部及び後部
長さ6m以上9m未満普
通自動車
前部及び後部
長さ6m未満普通自動車
である牽引自動車
前部
長さ6m未満の普通自動
車である被牽引自動車
後部
ポール・トレーラ
後部
前部の最前縁は自動車
の前端から長さの1/3以
内
後部の最後縁は自動車
の後端から1m以内
長さ6m以下の普通自動車である牽引自動車、被牽引車、及びポール・トレーラ 前部又は後部に必要 前部 最前縁と自動車の前端までの距離が長さの1/3以内 後部 最後縁と自動車の後端までの距離が長さの1/3以内
長さ6m超7m以下(乗用 10人未満)前部及び後部に必要 前部 最前縁と自動車の前端までの距離が3m以内 後部 最後縁と自動車の後端までの距離が長さの1/3以内
注※1:照明部の上縁高さが地上 0.75m未満である場合 ※2:被牽引車である場合

(262)
条 項 目 適 用 時 期 及 び 基 準
35 の2
側方灯 側方反射器 H18. 1. 1 以降 H17.12.31以前
長さ6m未満の後部の
側方反射器
最後縁は自動車の後端
から長さの1/3以内
見通し角度 上方 下方 前方向 後方向 除外
側方灯 長さ6m超 /側方反射器
10° 10° 5°(※1) 45° 45°
側方灯 長さ6m以下
10°
10°5°(※1)
30° 30°
その他の要件 形は文字及び三角形以外 形は三角形以外
36 番号灯 色 白色
37 尾灯 数 二輪車は後面に1個備えればよい
色 赤色
取付位置 上縁 下縁 最外側 下縁要件除外
2.1m以下 0.35m以上 0.4m以内
左右対称二輪車等にあっては中心が2m以下
見通し角度 上方 下方 内側方向 外側方向 除外
15°
15°5°(※1)
45° 80°
その他の要件 点灯操作状態表示装置 必要 除外
37 の2
後部霧灯 数 2個以下
色 赤色
電気結線 前照灯又は前部霧灯が点灯している場合のみ点灯できる構造、かつ、いずれかが点灯している場合においても消灯できる構造であること
次のいずれかの要件に適合する構造であること
ア 原動機を停止し、かつ、運転席の扉を開放した場合に後部霧灯の点灯操作装置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること
除外
イ 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点灯しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、点灯操作を行うまで消灯していること
取付位置 上縁 下縁 下縁要件除外
1m以下 0.25m以上
両側に備える場合は左右対称1個備える場合は中心が車両中心面上又はこれより右側
除外
二輪車等は中心が1m以下制動灯から0.1m以上離れていること
見通し角度 上方 下方 内側方向 外側方向 除外
5° 5° 25° 25°
その他の要件 光源は35W以下で照明部の大きさは140c㎡以下 尾灯の光度を超えること
点灯操作状態表示装置 必要
注※1:照明部の上縁高さが地上 0.75m未満である場合

(263)
条 項 目 適 用 時 期 及 び 基 準
37 の3
駐車灯 H18. 1. 1 以降 H17.12.31以前
色 前面は白色、後面は赤色両側面は進行方向が白色、後退方向が赤色 側方灯又は自動車の両側面に備える方向指示器と構造上一体の場合は橙色可
前面は白色、淡黄色又は橙色 後面は赤色
電気結線 前面に備えるものは後面に備えるものが点灯している場合のみ点灯すること 後面に備える駐車灯は、すべてが同時に点灯すること ただし、長さ6m以上又は幅2m以上の自動車以外は左側又は右側のみ点灯することができる 原動機が停止している状態において点灯すること
自動的に消灯しないこと 除外
取付位置 前面又は後面は最外側から0.4m以内(被牽引車は0.15m以内) 前面又は後面 左右対称
見通し角度 上方 下方 外側方向
前面又は後面 15° 15°5°(※1) 45°
両側面 15°
15°5°(※1) 45°
37 の4
後部上側端灯 数 2個又は4個 除外
色 赤色
取付位置 上側2個は取り付けることができる最高の高さ4個備える場合は、上側2個と下側2個は可能な限り離れた位置に取り付けられていること
除外
最外側から0.4m以内左右対称 尾灯と0.2m以上離れていること
見通し角度 上方 下方 外側方向 上方15°下方15°内側方向45° 外側方向80° 5° 20° 80°
38 後部反射器 色 赤色
取付位置 上縁 下縁 最外側 中心が1.5m以下下縁要件除外 1.5m以下 0.25m以上 0.4m以内
左右対称 除外
二輪車等は中心が1.5m以下二輪車は中心が車両中心面上 側車付二輪車の二輪車部分に備えるものにあっては中心が二輪車部分の中心面上でよい
見通し角度 上方 下方 内側方向 外側方向 除外
被牽引車以外
10°
10°5°(※1)
30°
30°
被牽引車 15° 15°5°(※1)
30° 30°
その他の要件 形は文字及び三角形以外被牽引車の形は正立正三角形又は帯状部の幅が一辺の1/5以上の中空の正立正三角形で一辺が0.15m以上0.2m以下
形は三角形以外被牽引車は正立正三角形又は帯状部の幅が30mm以上の中空の正立正三角形で一辺が0.15m以上
注※1:照明部の上縁高さが地上 0.75m未満である場合

(264)
条 項 目 適 用 時 期 及 び 基 準
38 の2
大型後部反射器 H23. 9. 1 以降 H23.8.31以前
数 1個、2個又は4個 4個以下
色 被牽引車以外黄色の反射部及び赤色の反射部は又は蛍光部からなる縞模様であること 被牽引車 黄色の反射部が赤色の反射部は又は蛍光部よって囲まれていること
反射部は黄色蛍光部は赤色
取付位置 上縁 下縁 下縁要件除外
1.5m以下 0.25m以上
左右対称
水平 除外
見通し角度 上方 下方 左方 右方 除外
15° 15° 5°(※1) 30° 30°
その他の要件 長さ130mm以上、幅130mm以上150mm以下の長方形被牽引車は長さ195mm以上230mm以下の長方形 長さの合計が1.13m以上2.3m以下
一辺が0.13m以上の長方形 反射部の面積 800c㎡以上 蛍光部の面積 400c㎡以上
39 制動灯 H18.1. 1以降 H17.12.31以前
数 二輪車は後面に1個備えればよい
色 赤色
取付位置 上縁 下縁 最外側 下縁要件除外
2.1m以下 0.35m以上 0.4m以内
二輪車等は中心が2m以下左右対称
見通し角度 上方 下方 内側方向 外側方向 後方10mの距離において地上2.5mまでのすべて位置から見通すことができる
15° 15°5°(※1)
45° 45°
その他の要件 尾灯と兼用の場合は尾灯のみ点灯時の5倍以上の光度であること
39 の2
補助制動灯 数 1個
色 赤色
取付位置 下縁が0.85m以上又は後面ガラスの最下端の下方0.15mより上方であって、制動灯の上縁を含む水平面以上
除外
中心は車両中心面上
見通し角度 上方 下方 内側方向 外側方向
10° 5° 10° 10°
その他の要件 尾灯と兼用でないこと
乗用 9人以下 装備義務付け貨物 バン型・総重量3.5t以下はH22.1.1以降装備義務
付け
除外
注※1:照明部の上縁高さが地上 0.75m未満である場合

(265)
条 項 目 適 用 時 期 及 び 基 準
40 後退灯 H18. 1. 1 以降 H17.12.31以前
数 2個以下
色 白色
電気結線 変速装置が後退の位置、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にある場合のみ点灯
変速装置が後退の位置のみ点灯
取付位置 上縁 下縁 H22.12.31以前は除外
1.2m以下 0.25m以上
両側に備える場合は左右対称 除外
見通し角度 上方 下方 内側方向 外側方向 除外
1個装備 15° 5° 45° 45°
2個装備 15° 5° 30° 45°
41 方向指示器 色 橙色
電気結線 毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅すること 両側面に備えるものは非常点滅表示灯と同時に点滅する構造可
取付位置
左右対称側面の最前縁は自動車の前端から2.5m(長さ6m以上の自動車は長さの60%)以内
大型貨物自動車等側面前部は自動車の前端から運転者室又は客室の外側後端まで 側面中央部の最前縁は運転者室又は客室の外側後端から2.5m(被牽引車は4.5m)以内
二輪車等以外 上縁 下縁 最外側 最内縁間隔 中心が2.3m以下 下縁要件除外 (前方・後方)
中心間隔が幅の50%以上でもよい
2.1m以下 0.35m以上 (前方・後方)
0.4m以内(前方・後方)
0.6m以上
二輪車等 中心が2.3m以下前方 中心間隔が0.3m(光源8W以上は0.25m)以上 後方 中心間隔が0.15m以上 前照灯又は尾灯が2個以上備えられている場合は中心が前照灯より外側に、尾灯より外側にあること
見通し角度 上方 下方 内側方向 外側方向 後面は後方10mの距離における地上2.5mまでのすべての位置から見通すことができること
前面 15° 15° 45° 80°
後面 15°
15°5°(※1) 45° 80°
側面 大型車等以外 15° 15°
5°(※1) -5°(後方) 60°(後方)
側面大型車等
30° 5° -5°(後方) 60°(後方)
側面中央部 大型貨物車等
自動車の最外側から外側方向1mで取付位置の前方1mから自動車後端までに相当する点における地上1mから1.6mまでのすべての位置から見通すことができること
その他の要件 点灯操作状態表示装置 必要
41 の2
補助方向指示器 装着可自動車の両側面に一個ずつまで 橙色 指示部上縁の高さ2.1m以下、下縁の高さ0.35m以上 車両中心面に対して対象
H17.12.31 以前は指示部中心高さ2.3m以下、下縁規定除外
41 の3
非常点滅表示灯 前条に準じて取り付け
注※1:照明部の上縁高さが地上 0.75m未満である場合

(266)
条 項 目 基 準 適 用 時 期
41 の4
緊急制動表示灯 緊急制動表示灯として制動灯及び補助制動灯を使用するもの 39条、39条の2に準じて取り付け 緊急制動表示灯として方向指示器及び補助方向指示器を使用するもの 41条、41条の2に準して取り付け
41 の5
後面衝突警告表示灯 後面衝突警告表示灯として方向指示器及び補助方向指示器を使用するもの 41条、41条の2に準して取り付け
42
灯光の色等の制限 赤色及び後方の地上2.5m以下の橙色の禁止(右記以外) 後方の白色灯火の禁止(右記以外)
① 側方灯② 尾灯 ③ 後部霧灯 ④ 駐車灯 ⑤ 後部上側端灯 ⑥ 制動灯 ⑦ 補助制動灯 ⑧ 方向指示器 ⑨ 補助方向指示器 ⑩ 非常点滅表示灯 ⑪ 緊急自動車の警光灯 ⑫ 火薬類又は放射性物質等の積載表示灯 ⑬ 事業用バスの地上2.5mを超える高さに備える後方表示灯
⑭ 路線バスの終車灯 ⑮ ハイヤー、タクシーの空車灯、料金灯、非常灯
⑯ 走行中に使用しない灯火 ⑰ 緊急制動表示灯 ⑱ 後面衝突警告表示灯 ⑲ 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示する電光表示器
① 番号灯 ② 後退灯 ③ 室内照明灯 ④ 路線バスの方向幕灯 ⑤ ハイヤー、タクシーの社名表示灯 ⑥ 走行中使用しない灯火
点滅及び光度の増減する灯火の禁止(右記以外)
① 側方灯② 方向指示器 ③ 補助方向指示器 ④ 非常点滅表示灯 ⑤ 緊急自動車の警光灯 ⑥ 道路維持作業用自動車の灯火 ⑦ ハイヤー、タクシーの非常灯 ⑧ 曲線道路用配光可変型前照灯 ⑨ 配光可変型前照灯 ⑩ 緊急制動表示灯 ⑪ 後面衝突警告表示灯 ⑫ 自主防犯活動用自動車の青色防犯灯 ⑬ 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の行先等を連続表示する電光表示器
⑭ 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える過負荷防止装置と連動する灯火
⑮ 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯
⑯ 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯
⑰ 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた灯火又はこれに準ずる性能を有する可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯
⑱ 路線を定めて定期に運行する一般乗用旅客自動車運送事業用自動車及び一般乗合旅客自動車運送事業用自動車に備える乗客が条項中であることを後方に表示する電光表示器
⑲ 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示する電光表示器

(267)
条 項 目 基 準 適 用 時 期
42
その他の禁止灯火等 ① 前面ガラス上方の青紫色の灯火(路線バスを除く)
② 前面ガラス上方の速度表示装置と紛らわしい灯火
③ 前方の赤色反射器又は後方の白色の反射器
④ 自車及び他の自動車の妨げとなる灯火 (走行用前照灯を除く)
43 警音器 警音器前方7mの位置の地上0.5mから1.5mの高
さで112db以下93db以上(動力が7kw以下の二輪車は112db以下83db以上)であること 警報音発生装置の備え付け 前方2mの位置で118db以下、周波数1800Hz~3550Hzまでの音の大きさは3550Hzを超える音の大きさを超えるものであり、かつ、車の前端から2mの位置で105db以上(動力が7kw以下の二輪車は95db以上)
H15.12.31以前製作車は前方2mの位置で115db以下90db以上、二輪車は115db以下の適当な大きさでもよい H16. 1. 1以降適用
44 後写鏡 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは、歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること ハンドルバー方式のかじ取り装置を備える二輪自動車等に備える後写鏡であって、次に掲げるものは基準に適合しない ・鏡面の面積が69cm2未満 ・その形状が円形の鏡面にあっては、鏡面の直径が94mm未満、又は150mm超 ・その形状が円形以外の鏡面にあっては、当該鏡面が直径78mmの円を内包しないもの、又は当該鏡面が120mm×200mmの長方形により内包されないもの 車室内後写鏡の衝撃吸収化(もっぱら乗用以外の普通車及び定員11人以上除く)
S48.12. 1 以降適用(普通貨物及び定員11人以上の車両はS49. 4. 1 以降適用) H19.1.1 以降 S50.12. 1 以降 H19. 1. 1 以降 細目告示別添80適用
直前直左鏡 ①小型自動車、軽自動車及び普通自動車(②の自動車を除く)には、前方0.3m、左側方0.3m(左ハンドル車は右側方0.3m)の距離にある障害物を確認できる直前直左鏡の備え付け ②車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上の普通自動車(乗車定員11人以上の自動車等を除く)には、前方2m、左側方3m(左ハンドル車は右側方3m)の距離にある障害物を確認できる直前直左鏡の備え付け
S50.11.30 以前 ①乗車定員11人以上の自動車及び総重量8t以上又は積載量5t以上の普通自動車(キャブオーバー等を除く)には、前方0.3mの距離にある障害物を確認できる直前直左鏡の備え付け ②総重量8t以上又は積載量5t以上の普通自動車(キャブオーバー等に限る)には、前方2m、左側方3mの距離にある障害物を確認できる直前直左鏡の備え付け H18.12.31 以前 ①乗車定員11人以上の自動車及び総重量8t以上又は積載量5t以上の普通自動車(キャブオーバー等を除く)には、前方0.3m、左側方0.3mの距離にある障害物を確認できる直前直左鏡の備え付け ②総重量8t以上又は積載量5t以上の普通自動車(キャブオーバー等に限る)には、前方2m、左側方3mの距離にある障害物を確認できる直前直左鏡の備え付け H19. 1. 1 以降

(268)
条 項 目 基 準 適 用 時 期
45 窓拭器等 自動式の窓拭器の備え付け
ウィンドウォッシャの取付
ウインドウォッシャの技術基準の適用
デフロスタの取付
デフロスタの取付(ワンマンバス)
デフロスタの技術基準の適用
サンバイザの衝撃吸収技術基準(定員11人以
上除く)
S35. 4. 1 以降適用(定員11
人以上除く)
S47. 1. 1 以降適用
S48.12. 1 以降適用
S50. 4. 1 以降適用
S47. 1. 1 以降適用
S48.12. 1 以降適用
S50. 4. 1 以降適用
46 速度計 ①四輪自動車(②以外)
31.0km/h≦V≦44.4km/h
②二輪・側車付二輪・三輪自動車等
29.1km/h≦V≦44.4km/h
※分解整備事業161ページ参照
47 消火器 乗車定員11人以上、幼児専用車、危険物等運
送する車両に備え付け
48 の2
運行記録計 貨物を運送する車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上の普通自動車及び前述のトレーラをけん引するトラクタに備え付け
48 の3
速度表示装置 貨物を運送する車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上の普通自動車及び前述のトレーラをけん引するトラクタに備え付ける事ができる 速度60km/h超えは3個、40km/h超えは2個40km/h以下は1個自動的に点灯する構造 誤差は、35km/h以上において速度計に準ずる 前方100mの距離から確認 黄緑色点灯順序は左、右、中央の順 前面ガラス上方で地上1.8m以上に取付
49 緊急自動車 警光灯及びサイレンの備え付け 警光灯は前方300mの距離から確認 赤色サイレンは前方20mの位置において90db以上120db以下 車体の塗色は、消防車は朱色、その他は原則白色
49 の2
道路維持作業用自動車 黄色で点滅式の灯火の備え付け150mの距離から確認
50 旅客運送事業用自動車 適当な採光、かつ、適当な室内照明灯の備え付け 運転者席の側面の窓は、有効幅及び有効高さ270mm以上開放できる構造
(乗降口の踏段) 乗降口の踏み段は、有効奥行き300mm以上。ただし、最下段以外の踏み段で扉等のためやむをえないものにあっては、有効幅350mm以上の部分について有効奥行き300mm(次の上段までの高さが250mm以下のものにあっては290mm)以上 〔乗車定員11人以上の自動車(幼児専用車を除く)に適用〕
(乗降口扉の手動開放等) 扉を開閉する装置が動力式である乗降口は、手動で扉を開閉する装置の備え、その位置及び開放方法を表示 〔乗車定員11人以上の自動車に適用〕

(269)
条 項 目 基 準 適 用 時 期
(ワンマンバスの構造要件) 車掌を乗務させないで運行することを目的とするものに適用 〔乗車定員11人以上の自動車に適用〕
H24.6.30以前 従前規定適用H24.7.1以降 別添10適用
(座席の間げき) 旅客の用に供する座席の前縁と、その前方座席、隔壁等との間げきは、200mm以上(当該座席が前方の座席と向かい合っているものにあっては400mm以上) 〔乗車定員10人以下の自動車に適用〕
(扉の開放方法の表示) 乗降口の扉を開放する操作装置又はその付近に表示 〔乗車定員10人以下の自動車に適用〕
50 の2
ガス運送容器を備える自動車等 バンパその他の緩衝装置の備え付け S51. 5.20以降適用
(注)この一覧は、保安基準の主な項目について規制値、適用時期等の概要をまとめたものです。この一覧の
内容の正確性については、万全を期していますが、検査の判定にあたっては、必ず、道路運送車両の保
安基準、自動車検査独立行政法人審査事務規程等の関係法令等の原文を確認してください。

Ⅲ.軽 自 動 車 検 査 関 係

(271)
(1) 民間患者等輸送への軽自動車の導入についての一部改正について
15軽検業第160号
平成15年9月30日
標記について、「民間患者等輸送への軽自動車の導入について」(平成13年6月29日付け、13軽検業第
89号)を下記のとおり改正したので、周知されたい。
記
1.軽福祉タクシーとして使用する車両は、運行時に寝台及び車椅子を固定することのできる設備を有す
る特種用途自動車とする。
2.業務の範囲は、「車椅子又は寝台を必要とする患者等及びその付き添い人の輸送に限ること」とする。
3.運賃設定については、軽福祉タクシーの車両価格は一般の小型タクシーとほぼ同一であるなど原価が
ほぼ同一であることに鑑み、一般小型タクシーと同様に取り扱うことが適当と考えられる。
なお、必要に応じ、割増、時間制運賃も弾カ的に認めることとする。
4.その他需要に対する審査、事業区域の範囲、運送の引受け等については、現在の民間患者等輸送事業
の取扱いと同様とする。
5.なお、軽福祉タクシーについては、自動車損害賠償責任保険の車種区分は特種用途自動車の軽自動車(自動車損害賠償保障法施行令第9条17号)を適用し、自動車検査証の有効期間は2年(道路運送車両法第61条)とする。また、車両番号標の自動車の用途による区分は特種用途自動車(道路運送車両法施行規則第36条2)とする。
(2) 患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の許可等の取扱いに
ついて
平成16年5月7日
16軽 検 業 第 74号
標記について、別添のとおり国土交通省自動車交通局旅客課新輸送サービス対策室長から、事業に使用す
る車両の範囲拡大に軽乗用自動車も含まれるので、「軽自動車検査ファイルに係る電子情報処理組織」のシ
ステム対応が可能となるよう依頼があり、検討した結果、平成16年6月1日(火)より一般乗用旅客自動車
運送事業用車両番号の払い出し業務を、電算システムにより行うこととしたので了解願います。(以下省略。)

(272)

(273)

(274)

(275)
(3)軽自動車の改造について
自 技 第159号
平成 8 年 9 月 30 日
軽自動車の衝突時の安全性向上への対応を目的として、今般、道路運送車両法施行規則(以下「施行規
則」という。)を改正し、改正後の軽自動車の規格を平成 10 年 10 月 1 日より適用することとした。
これに伴い、改正前の施行規則の規定(以下「旧規格」という。)に基づき製作された軽自動車につい
て、長さ又は幅を拡大することとなる改造が予想されるところであるが、軽自動車は、本来軽量、小出
力であり、改造の内容如何によっては、その走行安定性、制動特性、強度等に悪影響を及ぼす恐れが多
いと思料される。
このため、平成 10 年 10 月 1 日以降、旧規格に基づき製作された軽自動車の改造車については、下記
の点に配慮して検査を実施されたい。
記
1. 車両の長さ、幅、荷台の長さ及び幅は、道路運送車両法第 75 条の規定に基づく型式指定、「新型自
動車等取扱い要領」(昭和 45 年 6 月、自車第 375 号、自整第 86 号)に基づく届出等に係る同一型式の
自動車のそれらを上回っていないこと。
2. 通常予想される荷重条件において左右輪の輪荷重の差は、軸重の 12%以下であること。
(参考資料)
軽自動車の規格の変遷
~昭和 50 年 12 月 31 日 ~平成元年12月 31日 ~平成10年9月30日 ~ 現 在
長 さ 3.00m以下 3.20m以下 3.30m以下 3.40m以下
幅 1.30m以下 1.40m以下 1.40m以下 1.48m以下
高 さ 2.00m以下 2.00m以下 2.00m以下 2.00m以下
排気量 0.36リットル以下 0.55リットル以下 0.66リットル以下 0.66リットル以下

(276)
(4)受検に関する注意事項について
検査コース内における注意事項
(一般的注意事項)
1.初めて受検される方は、あらかじめ検査員に申し出て下さい。
2.検査コース内において携帯電話等を使用しないで下さい。
3.検査中はラジオ等を止め窓を開放して検査員等の指示が聞き取れるよう努めて下さい。
4.検査コース内は禁煙になっておりますので、おタバコはご遠慮下さい。
(受検前注意事項)
5.検査コースは、自動方式テスターとなっておりますので、あらかじめ検査コース入場前に検査コース
の検査状況を見学して下さい。この際、他の車両の検査の支障とならないように注意して下さい。
6.受付を終了した方は、受検要領等構内の掲示類を熟読の上、受検要領が確認できましたら、入場する
検査待機コース列の最後尾に車両を並べて下さい。
7.検査車両には運転者1名のみが乗車して積載物も降ろして受検して下さい。
8.ホイールキャップ等は受検前に取り外して下さい。
9.車体が低い車両(エア・スポイラー、泥除けの取付等により自動車の接地部以外の部分と地面との間
隔が少ない車両)又は、車体が著しく高い車両(荷台に幌等を取り付けている車両)は、検査に支障
をきたす恐れがあるか、又は検査コースに入場できませんので、あらかじめ検査員に申し出で下さい。
10.軸重1,000kg以上の車両、フルタイム4WD車及び三輪車は、あらかじめ検査員に申し出で下さい。
11.入口の信号灯が青(進入)になってから、誘導線に沿ってゆっくりと(5km/h以内)テスタへ乗り入
れて下さい。
12.各検査ブロックでは、検査判定後表示器の指示に従い、検査記録を検査票に記録して下さい。
13.検査中は危険ですので検査機器上に降車しないで下さい。排気ガス検査のため、又は、やむを得ず降車
する場合には足元に十分注意するとともに、ギアをニュートラル又はPレンジにし、サイドブレーキ
を確実に作動させて下さい。
14.再検査の場合は、検査コース入口部にある再検査該当ボタンを押してから入場して下さい。
(排気ガス検査関係)
15.降車する際は、必ず駐車ブレーキを引き、ギアをニュートラル又はPレンジにして下さい。
16.排気ガステスタのプローブを入れたまま車両を発進させたり、エンジンの回転を上げたりしないで下
さい。
17.排気ガステスタのプローブは検査終了後、元の場所に戻して下さい。
(サイドスリップ・ブレーキスピードメーター・ヘッドライト検査関係)
18.テスタへの乗り入れ、脱出、その他の動作は表示器又は検査員の指示に従って下さい。
19.テスタ上では、急停止、急発進をしないで下さい。
20.テスタ上では、ハンドルを切らないで下さい。
21.駆動軸とスピードメータ測定軸が異なる場合は、あらかじめ検査員に申し出て下さい。
22.ヘッドライト・テスタの動き、前方車両に注意して安全を確認してから進行して下さい。
(下回り検査関係)
23.下回り検査(ドライブオン・リフト)ではエンジンを停止させて、駐車ブレーキを引き、また検査員
の指示により駐車ブレーキの解除等を行って下さい。
(その他)
24.検査中は無理な運転等によって検査機器を損傷しないように注意して受検して下さい。
25.構内では不合格箇所の調整、修理等を行わないで下さい。
26.検査コース内において車両を後退させる場合は、検査員の指示に従って下さい。
27.その他不明な点がありましたら、あらかじめ検査員に申し出て下さい。
※以上は共通する注意事項ですが、検査場、検査コースによって、他に注意が必要となる場合があり
ます。

(277)
受検時の指示事項
受検者の皆様へ
自動車検査場において検査を受ける場合には、次の事項をお守り下さい。これらの事項が守られていな
い場合は、検査担当者から検査時において、受検者に対し指示が行われます。
なお、受検者がこの指示に従わなかった場合は、受検車両の検査を行えませんのでご承知下さい。
「受検に際して必要な指示事項」
①検査中は検査票を保持すること。
②下回り部分は泥等の付着がなく装着等の確認ができる状態とすること。
③車台番号及び原動機の型式の打刻は、汚れ等の付着がなく打刻文字等が確認できる状態とすること。
④排気管はプローブが挿入できる状態とすること。
⑤荷台等は物品等が積載された状態でないこと。
⑥座席、シートベルト、非常信号用具及び消火器等は確認できる状態とすること。
⑦窓ガラスは取り外された状態でないこと。
⑧全ての車輪のホイールキャツプ又はセンターキャップ、灯火器等に装着されているカバー等は取り外し
た状態とすること。
⑨エンジンルーム内の検査を行う場合は、原動機を停止し、ボンネット(フード)を開け、支持棒等によ
り保持した状態とすること。
⑩運転者席及び助手席の側面ガラスの検査を行う場合は、窓ガラスを閉じた状態とすること。
⑪検査担当者からの指示により、警音器、方向指示器等灯火器又は窓拭器等を作動させること。また、指
示がある場合以外はこれら装置を作動させないこと。
⑫検査機器の表示器により表示又は検査担当者からの指示により、原動機の始動及び停止を行うこと。
⑬受検車両の構造・装置に応じ検査機器の申告ボタンの操作を行うこと。
⑭検査コース内における受検車両の移動、停止位置での停車を行うこと。
⑮検査機器の表示器による表示又は検査担当者の指示に応じテスタへの乗り入れ、脱出及び前照灯の点灯
操作等を行うこと。
⑯記録器のあるコースにおいて記録器による検査結果の記録を行うこと。
⑰検査が終了した場合(再検査の場合を含む。)には、検査票に総合判定結果の記入を受けること。
⑱検査担当者がエア・クリーナのカバーの取り外しを指示した場合は、当該カバーを取り外すこと。
⑲走行距離計は総走行距離(オドメータ)を表示した状態とすること。

(278)
受検者の禁止事項
受検者の皆様へ
自動車検査場においては、次の事項をお守り下さい。これらの事項が守られていない場合は、検査を中
止し、受検者に対する退去や自動車の撤去を命じることがあります。
なお、これに応じない場合は、コースの閉鎖や公務執行妨害行為等として警察への通報等厳正な措置を
とりますのでご承知下さい。
「受検者の禁止事項」
①暴力、暴言等の行為を行うこと及び暴力、暴言等の威圧的行為により、検査職員にその場での再検査、
合格の判定等を強要しないこと。
②検査を受ける自動車の運転者(1名に限る)以外の者が許可なく入場しないこと。
③検査職員が危険を感じる速度(歩行速度以上)で通行しないこと。
④コース内で整備等をしないこと。
⑤検査機器、検査設備等を損傷させ又は破壊しないこと。
⑥座り込み、立ふさがり又は自動車を放置しないこと。
⑦旗、のぼり、プラカード類を検査コース内に持ち込まないこと。
⑧拡声器等の放送設備を使用し、騒音を撒き散らさないこと。
⑨凶器、爆発物等の危険物を持ち込まないこと。
⑩その他検査業務上又は検査場管理上支障となる行為をしないこと。

(279)
(5)不適切な補修等について
「軽自動車検査協会検査事務規定」(昭和48年協会規程第16号)
(平成15年7月15日付け、15軽検業第108号)
(不適切な補修等)
3-3-1 次の各号に掲げる補修等を行った自動車は、保安基準に適合しないものとする。
(1) 灯火器の破損、亀裂等が粘着テープ類により補修されているもの
(2) 各種ダストブーツ類の破損、亀裂等が針金類又は粘着テープ類により補修されているもの
(3) 灯火の色の基準に適合させるため、灯火器の表面に貼付したフィルム等がカラーマジック、
スプレー等で着色されているもの
(4) 空き缶、金属箔、金属テープ又は非金属材料を用いて排気管の開口方向が変更されているも
の
(5) 排気管に空き缶、軍手、布類等の異物が詰められているもの
(6) 走行装置の回転部分付近の車体(フェンダー類等)にベルト類、ホース類、粘着テープ類、
紙類、スポンジ類又は発砲スチロールが取り付けられているもの
(7) 緊急自動車の警光灯に形状が類似した灯火(赤色以外のものを含み、教習用二輪車に備える
教習用灯火を除く。)であって、当該灯火に係る電球、すべての配線及び灯火器本体(カバー類、
粘着テープ類その他の材料により覆われているものを含む。)が取り外されていないもの
(8) 不点灯状態にある灯火(速度表示装置及び(7)の灯火を除く。)であって、当該灯火に係る
電球及びすべての配線が取り外されていないもの
(9) 番号灯の一部が点灯しないもの
(10)灯火器、シートベルト、座席後面の緩衝材、後写鏡、窓ガラス、オーバーフェンダー、排気
管、座席、ブレーキホース、ブレーキパイプ、ショックアブソーバー、スプリング、タイロッ
ト又は扉が粘着テープ類、ロープ類又は針金類で取り付けられているもの(指定自動車等に備
えられたものと同一の方法で取り付けられたものを除く。)
(11)操縦装置の識別表示又は最大積載量の表示が貼り付けられた紙または粘着テープ類(表示を
目的として製作されたものを除く)に記載されているもの及び表示された内容が容易に消える
もの。

【全国共通教材編】

(281)

(282)

(283)

(284)

(285)

(286)

(287)

(288)

(289)

(290)

(291)

(292)

(293)

(294)

(295)

(296)

(297)

(298)

(299)

(300)

(301)

(302)

(303)

(304)

(305)

(306)

(307)

(308)

(309)

(310)

(311)

(312)

(313)

(314)

(315)

(316)

(317)

(318)

(319)

(320)

(321)

(322)

(323)

(324)

(325)

(326)

(327)

(328)

(329)

(330)

(331)

(332)

(333)

(334)

(335)

(336)

(337)

(338)

(339)

(340)

(341)

(342)

(343)

(344)

(345)

(346)

(347)

(348)

(349)

(350)

(351)

(352)

(353)

(354)

(355)

(356)

(357)

(358)

(359)

(360)

(361)

(362)

(363)

(364)

(365)

(366)

(367)

(368)

(369)

(370)

(371)

(372)

(373)

(374)

(375)

(376)

(377)

(378)

(379)

(380)

(381)

(382)

(383)

(384)

(385)

(386)

(387)

(388)

(389)

(390)

【資 料 編】

Ⅰ.自 動 車 検 査 関 係

(391)
1.受 検 案 内
自動車税等の滞納のないことを証するに足る書面(納税証明書)ただし、二輪自動車は除く
(8)
(9)
継続検査申請書(OCRシート第3号様式または専用第3号様式)

(392)
4.再検査の取扱い
(1)検査当日の取扱い(再入場)
① 概要
国から審査依頼があった日の審査時間内に限り、初回の入場を含めて3回まで(すなわち、再入場
は2回まで)に制限されます。
これにより、当日の審査時間内かつ制限回数内に合格しない場合には、限定自動車検査証の交付を
受ける等により、改めて検査申請を行うことが必要となります。
② カウント方法
継続検査の場合は、保安コースなどに入場した回数をカウントします。
新規検査・予備検査又は構造等変更検査で諸元測定を伴う場合は、計測コース及び保安検査コース
に入場した回数を計測コース又は保安コースの別毎にカウントします。(すなわち、計測コースに3回
まで、保安コースに3回までの入場が可能となります。)
(2)検査日の翌日以降の取扱い
① 有効な限定検査証の交付を受けている場合は、限定検査証に記載された不適合箇所を審査します。
② 新車、構造等変更検査など限定検査証の交付を受けられない場合は、初めての申請と同じ扱いにな
り、全ての審査項目を再度審査します。
*いずれの場合も必ず国の窓口で受付を済ませてから、検査コースに入場して下さい。

(393)
5.検査手数料(登録車)

(394)
(2) 自動車の継続検査等の申請書の押印について
自 技 第 4 8 号
平成8年3月26日
自動車の継続検査及び分解整備検査(以下「継続検査等」という。)の申請書については、申請を受け付
ける際に、継続検査等の申請を義務付けられている使用者(以下「申請義務者」という。)の押印がなされ
ているか否か確認しているところであるが今般、下記のとおり押印を省略できる場合及び印鑑の種類を明
確にしたので、平成8年4月1日からはこれにより取り扱われたい。
記
1 次の各号に掲げる場合は、継続検査等の申請書における申請義務者の押印を省略できることができる。
(1) 申請義務者が自動車の検査に係る申請手続きを委任する旨を記載した委任状の提出及び継続検査等
の申請書に当該委任状により委任を受けた代理人の押印がある場合
(2) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の規定に係る許可を受けた自動車であって、
当該自動車に係る使用者及び当該自動車の所有者である道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第
2項の規定より有償貸渡の許可を得た者(以下「リース会社」という。)において、道路運送車両法(昭
和26年法律第185号)第48条の規定による定期点検整備の実施及び同法第62条の規定による継続検査の
申請の手続きをリース会社が行うという内容を含む有償貸渡約款により有償貸渡の契約がなされ、か
つ、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和45年運輸省令第8号)第3
号様式又は専用第5号様式の余白部に別記様式による証明がある当該申請書により継続検査等の申請
があった場合
2 自動車の検査に係る申請書の押印には、市町村又は特別区の長の証明を受けた印鑑(申請者が法人で
あるときは、その代表者の印鑑であって法人の登記に関し印鑑を提出した登記所の証明を得たもの。)
のほか、次の印鑑を用いることができるものとする。
(1) 申請者が個人である場合は、申請者の氏名等を印章により確認することができる印鑑
(2 ) 申請者が法人である場合は、当該法人において当該自動車の管理を任されている者の印鑑(ただし、
次の記載例による場合に限る。また、1(2)別記様式の押印についても、これに準ずるものとする。)
〔記載例〕
申請人
(使用者)
氏名又は名称 ○○有限会社△△部□□課長▽▽ □印
別記
当社は、当該自動車について当該使用者との間で道路運送車両法第48条の規定による定期点検整
備の実施及び同法第62条の規定による継続検査の申請の手続きを当社が行うこととする契約を交わ
し、その旨当該有償貸渡約款に記載していることを証明する。
リース会社名 □印

(395)
3 自動車の継続検査等の申請書の押印について
別表の検査の申請等については、平成10年1月1日から、申請書に氏名を記載して押印する代わりに
署名※でもよいこととなりますので、申請書に記載する際には、以下の例により、楷書体等でていねい
に氏名を記載して下さい。
なお、新規登録、移転登録などは、従来どおり実印が必要です。
※ 署名は、申請者(使用者)本人が直筆でフルネームを記載して下さい。
○印は可、×印は不可とする。
○ (申請人) 運輸太郎 (ワープロ等+印鑑)→従来どおり
○ (申請人) (直筆)
○ (申請人) 運輸太郎 (ワープロ等+直筆)
(氏名が既にワープロ、ゴム印等で記載してある場合)
× (申請人) 運輸太郎 (ワープロ等)
× (申請人) 運輸太郎 (ワープロ等+サイン)
○ (申請人)運輸株式会社 (名称・代表者の役職・氏名
代表取締役 運輸太郎 +代表者印)→従来どおり
○ (申請人)運輸株式会社 (名称・代表者の役職
代表取締役 +代表者直筆の氏名)
○ (申請人)運輸株式会社 (名称・代表者の役職・氏名
代表取締役 運輸太郎 +代表者直筆の氏名)
(氏名が既にワープロ、ゴム印等で記載してある場合)
× (申請人) 運輸株式会社 (名称+代表者印)
(代表者の氏名の記載の方法は、個人の場合と同様です。)
※ なお、新規登録、移転登録などは、従来どおり実印が必要です。
※ 署名は、申請者(使用者)本人が直筆でフルネームを記載して下さい。
申請者が個人の場合の例
申請者が法人等の場合の例
運輸
代表
者印
代表
者印

(396)
(3) 自動車検査証の有効期間の取扱いについて
1.検査証の有効期間の満了する1カ月前の日
(例)
検査証の有効期間の満了する日 検査証の有効期間の満了する日の1カ月前の日
2月1日 1月1日
2月15日 1月15日
2月29日 1月29日
3月28日 2月28日
3月29日、30日及び31日 2月28日(閏年にあっては29日)
10月30日及び31日 9月30日
11月30日 10月30日
○注意事項
自動車検査証の有効期間は満了する日から1カ月を越えて残っている場合申請日当日から起算さ
れ、有効期間は短縮されますので、検査前に確認して下さい。

(397)
○大阪運輸支局
〒 572-0846
寝屋川市高宮栄町12-1
検査部門 TEL072(823)7945
FAX072(821)5507
登録部門 TEL050(5540)2058
振興会予約コーナー
TEL06(6613)1234
○自動車検査独立行政法人近畿検査部
(検査課)
TEL072(812)1818
FAX072(822)0110
※登録案内でオペレータにつなぎたい場合は音声ガイダン
スが流れた後に026とプッシュしてください。
※保安基準に係る適合性・並行輸入車・改造自動車等届出
書の取扱いについては、上記連絡先にお問い合わせくだ
さい。
大阪運輸支局付近案内図
(4) 管内運輸支局・事務所等連絡先及び付近案内図
○大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所
〒 594-0011
和泉市上代町官有地
検査部門 TEL0725(41)3981
FAX0725(43)6489
登録部門 TEL050(5540)2060
振興会予約コーナー
TEL06(6613)1234
○自動車検査独立行政法人和泉事務所
TEL0725(46)6969
FAX0725(43)6489
※登録案内でオペレータにつなぎたい場合は音声ガイダン
スが流れた後に026とプッシュしてください。
※保安基準に係る適合性・並行輸入車・改造自動車等届出
書の取扱いについては、上記連絡先にお問い合わせくだ
さい。
大阪運輸支局
和泉自動車検査登録事務所付近案内図

(398)
○大阪運輸支局 なにわ自動車検査登録事務所
〒 559-0031
大阪市住之江区南港東3-1-14
検査部門 TEL06(6612)6601
FAX06(6614)4596
登録部門 TEL050(5540)2059
振興会予約コーナー
TEL06(6613)1234
○自動車検査独立行政法人なにわ事務所
TEL 06(6612)8060
FAX06(6614)4596
※登録案内でオペレータにつなぎたい場合は音声ガイダン
スが流れた後に026とプッシュしてください。
※保安基準に係る適合性・並行輸入車・改造自動車等届出
書の取扱いについては、上記連絡先にお問い合わせくだ
さい。
大阪運輸支局
なにわ自動車検査登録事務所付近案内図

(399)
○京都運輸支局
〒 612-8418
京都市伏見区竹田向代町37
検査部門 TEL075( 681) 9763
FAX075( 681) 1795
登録部門 TEL050( 5540) 2061
振興会予約コーナー
TEL075(672)6381
○自動車検査独立行政法人京都事務所
TEL075(681)8595
FAX075(681)1795
※登録案内でオペレータにつなぎたい場合は音声ガイダン
スが流れた後に026とプッシュしてください。
※保安基準に係る適合性・並行輸入車・改造自動車等届出
書の取扱いについては、上記連絡先にお問い合わせくだ
さい。
京都運輸支局付近案内図
○京都運輸支局 京都南自動車検査場
〒 613-0036
京都府久世郡久御山町大字
田井小字東荒見27-2
検査部門 TEL0774(44)6591
FAX0774(44)6634
振興会予約コーナー
TEL075(672)6381
○自動車検査独立行政法人京都南事務所
TEL0774(44)7440
FAX0774(44)6634
※登録案内でオペレータにつなぎたい場合は音声ガイダン
スが流れた後に026とプッシュしてください。
※保安基準に係る適合性・並行輸入車・改造自動車等届出
書の取扱いについては、上記連絡先にお問い合わせくだ
さい。
京都運輸支局
京都南検査場付近案内図

(400)
○神戸運輸監理部 兵庫陸運部
〒 658-0024
神戸市東灘区魚崎浜町34
整備部門 TEL078( 453) 1103
FAX078( 431) 8761
登録部門 TEL050( 5540) 2066
振興会予約コーナー
TEL078(412)8030
○自動車検査独立行政法人兵庫事務所
TEL 078(453)1895
FAX078(453)5530
※登録案内でオペレータにつなぎたい場合は音声ガイダン
スが流れた後に026とプッシュしてください。
※保安基準に係る適合性・並行輸入車・改造自動車等届出
書の取扱いについては、上記連絡先にお問い合わせくだ
さい。
神戸運輸監理部
兵庫陸運部付近案内図
○神戸運輸監理部
姫路自動車検査登録事務所
〒 672-8588
姫路市飾磨区中島福路町3322
検査部門 TEL079(231)4801
FAX079(233)9511
登録部門 TEL050(5540)2067
振興会予約コーナー
TEL078(412)8030
○自動車検査独立行政法人姫路事務所
TEL 079(233)8266
FAX079(233)9511
※登録案内でオペレータにつなぎたい場合は音声ガイダン
スが流れた後に026とプッシュしてください。
※保安基準に係る適合性・並行輸入車・改造自動車等届出
書の取扱いについては、上記連絡先にお問い合わせくだ
さい。
神戸運輸監理部
姫路自動車検査登録事務所付近案内図

(401)
○滋賀運輸支局
〒 524-0104
守山市木浜町2298-5
整備部門 TEL077(585)7252
FAX077(584)2079
登録部門 TEL050(5540)2064
振興会予約コーナー
TEL077(585)7508
○自動車検査独立行政法人滋賀事務所
TEL077(585)7254
FAX077(584)2079
※登録案内でオペレータにつなぎたい場合は音声ガイダン
スが流れた後に026とプッシュしてください。
※保安基準に係る適合性・並行輸入車・改造自動車等届出
書の取扱いについては、上記連絡先にお問い合わせくだ
さい。
滋賀運輸支局付近案内図
○奈良運輸支局
〒 639-1037
大和郡山市額田部北町981-2
整備部門 TEL0743(59)2153
FAX0743(23)0023
登録部門 TEL050(5540)2063
振興会予約コーナー
TEL0743(57)6006
○自動車検査独立行政法人奈良事務所
TEL0743(59)2300
FAX0743(23)0023
※登録案内でオペレータにつなぎたい場合は音声ガイダン
スが流れた後に026とプッシュしてください。
※保安基準に係る適合性・並行輸入車・改造自動車等届出
書の取扱いについては、上記連絡先にお問い合わせくだ
さい。
奈良運輸支局付近案内図

(402)
○和歌山運輸支局
〒 640-8404
和歌山市湊1106-4
整備部門 TEL073(422)2153
FAX073(435)2099
登録部門 TEL050(5540)2065
振興会予約コーナー
TEL073(422)2466
○自動車検査独立行政法人和歌山事務所
TEL 073(422)2366
FAX073(435)2099
※登録案内でオペレータにつなぎたい場合は音声ガイダン
スが流れた後に026とプッシュしてください。
※保安基準に係る適合性・並行輸入車・改造自動車等届出
書の取扱いについては、上記連絡先にお問い合わせくだ
さい。
和歌山運輸支局付近案内図

(403)
2.事 務 関 係
(1) 車台番号等の打刻部分の修理について
最近、車台番号及び原動機型式の打刻部分を許可なく溶接したり、パッチ当てをしたり、或いは切断す
る向きが非常に多く、これらは車両法第31条によって何人といえども禁止されている。もし無断で違反し
たものには、車両法第107条によって30万円以下の罰金若しくは1年以下の懲役に処し、又は併科すること
になっているので、今後は斯の如き違反のないように関係者に周知徹底し、遺憾なきを期せられたい。
なお、許可を得る場合は下記により実施されたい。
記
1.車台番号(含原動機型式)打刻部分修理許可申請書2通(別紙)
2.許可申請書には打刻部分の拓本・写真(車台番号・登録番号、車輛の破損状況等が確認できるもの)
及びその他必要な書類を添付すること。
※許可申請は亀裂、その他修理を必要とする場合に限る。
《参考》道路運送車両法(抜粋)
(打刻の塗まつ等の禁止)
第31条 何人も自動車の車台番号又は原動機型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型
式の識別を困難にするような行為をしてはならない。
但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において国土交通大臣の許可を受け
たときはこの限りではない。
〈参考〉《職権打刻許可手続の例》
打刻部分、破損又は修理が必要
・ 事 業 者
打刻部分修理許可申請(2通) 現車提示(提示不可能な時は写真による)
・ 整 備 部 門
打刻部分修理許可書の交付
・ 事 業 者
修理、旧打刻部分切断後保存
・ 登 録 部 門
変更登録申請(打刻部分修理許可書及び旧打刻部分提出)
・ 整 備 部 門
現車提示、打刻
・ 登 録 部 門
変更手続完了
(注) ○後日、自動車損害賠償責任保険証明書の車台番号欄の訂正を必要とするときは、変更登録申請ま
でに旧車台番号の登録事項証明書を取っておくこと。

(404)
別紙様式
平成 年 月 日
近畿運輸局 運輸支局長 殿
神 戸 運 輸 監 理 部 長 殿
自動車検査登録事務所長 殿
所有者氏名 印
事業者氏名 印
認証番号
車台番号(含原動機型式)打刻部分修理許可申請書
1.車名
初度登録年 年 型式
2.登録番号
(車両番号)
3.車台番号
(原動機型式)
4.理由
5.拓本
本件について許可します。
第 号 平成 年 月 日
近畿運輸局 運輸支局長
神 戸 運 輸 監 理 部 長
自動車検査登録事務所長

(405)
(2) 車台番号等の打刻部分の修理許可について
車台番号及び原動機型式の打刻部分を修理する場合には、運輸支局長等の許可をうけた後、修理するよ
う「車台番号等の打刻部分の修理許可について」の通達により関係者に通知しているが、その手続を下記
のとおり改めたので貴傘下会員に周知方御願いする。
記
1.車台番号(含原動機型式)打刻部分修理許可申請書2通を整備課に提出する。
2.提出した許可申請書のうち1通を支局長(所長)決裁の後許可書として申請者に交付する。
3.修理が完了し、その車両の職権打刻をうけようとする場合には、前に交付した許可書を登録部門に提
出し職権打刻の決裁をうけ、次の書類を検査場に持参して職権打刻をうける。
この場合、原則として旧打刻部分は切り抜いて打刻担当検査官に提出するものとする。
(イ) 変更登録申請書
(ロ) 自動車検査証記入申請書
(ハ) 打刻部分修理許可書
(ニ) 職権打刻許可の決裁書
(ホ) 自動車検査証
(ヘ) 委任状
(ト) 部品販売証明書
4.職権打刻が完了した場合には上記書類を登録部門の受付窓口に提出し、自動車登録ファイルを変更し
た後登録部門で自動車検査証を訂正して申請者に返却する。(以下略)
〔参 考〕
職権打刻の取扱いについての業務連絡は次のとおりである。
(イ) 新規、継続検査の場合で職権打刻する必要があれば従来通り登録部門において立案し支局長(所
長)決裁をうけた後打刻する。
(ロ) ポールトレーラに変更するため職権打刻を要するものは打刻許可申請書2通を提出させその1通
に旧打刻を×印の刻印で抹消した拓本と、新たにポールトレーラとして使用するフレームに※「大
大」の刻印を打刻した拓本を貼付して担当検査官が割印した後返却する。ポールトレーラが完成し
たときは、その申請書を登録部門に提出させ、職権打刻許可の決裁をうけ、検査申請書を添付して
職権打刻するものとする。
(ハ) 車枠の変更によって職権打刻を必要とするものは、旧打刻を×印の刻印で抹消した後職権打刻す
る。この場合、職権打刻の立案について(イ)の例による。
※ 運輸支局名を示す符号であり、この場合は大阪運輸支局を示す。

(406)
3.検査関係 (1) 検査機器による検査基準(抜粋)
※最高光度の合計は 430,000cd 以下

(407)

Ⅱ.軽 自 動 車 検 査 関 係

(409)
大阪主管事務所
大阪市住之江区南港東3丁目4-62
TEL 06-6612-1565
車検予約自動化システム
TEL 06-6613-1234
1.受検案内(1) 軽自動車検査協会大阪主管事務所管内検査場の案内について
検査及び予約については、事務所、予約コーナーへ電話して下さい。
大阪主管事務所 高槻支所
高槻市大塚町4丁目20-1
TEL 072-661-5877
車検予約自動化システム
TEL 06-6613-1234

(410)
大阪主管事務所 和泉支所
堺市西区山田2丁190-3
TEL 072-273-1561
車検予約自動化システム
TEL 06-6613-1234
京都事務所
京都市伏見区竹田向代町51-12
TEL 075-671-0928
予約コーナー
TEL 075-672-6381

(411)
兵庫事務所
神戸市西区玉津町居住字孫田67-1
TEL 078-927-3648
予約センター(自動予約)
TEL 078-412-8030
兵庫事務所姫路支所
姫路市飾磨区中島3313
TEL 079-231-4101
予約センター(自動予約)
TEL 078-412-8030

(412)
奈良事務所
大和郡山市額田部北町980番地の3
TEL 0743-58-3018
予約センター(自動予約)
TEL 0743-57-6006
滋賀事務所
守山市木浜町2298-3
TEL 077-585-7103
予約コーナー
TEL 077-585-7516

(413)
和歌山事務所
和歌山市湊1106番地の25
TEL 073-433-4655
予約コーナー
TEL 073-431-9182

(414)
2.事務関係
(1)車台番号打刻部分の修理について
車両法31条ただし書による車台番号打刻部分の修理許可手続は次によること。
① 車台番号(含原動機型式)打刻部分修理許可申請書(別紙様式)2通を提出すること。
② 許可申請書には、打刻部分の拓本、写真及びその他必要な書類を添付すること。
(亀裂その他修理を必要とするようなものであること)
③ 取換部分の販売証明書(廃品業者のものでもよい)を添付すること。
④ 旧打刻部分は切り抜いて職権打刻時に提出する。
<参考>《職権打刻許可手続きの手順》
打刻部分、破損又は修理が必要
打刻部分修理許可申請書(2通)
現車提示(提示不可能な時は写真による)
打刻部分修理許可書の交付
修理、旧打刻部分切断後保存
記入申請(現車提示打刻部分修理許可書及び旧打刻部分提出)
打 刻
記 入 完 了
事 業 者
軽自動車検査協会
事 業 者
事 業 者
軽自動車検査協会

(415)
別紙様式
平成 年 月 日
軽自動車検査協会
大阪主管事務所長 殿
支 所 長
使用者氏名 (印)
事業者氏名 (印)
車台番号(含原動機型式)打刻部分修理許可申請書
1.車 名 初度検査年 型式
2.車 両 番 号
原動機型式
3.車 台 番 号
4.理 由
5.拓本及び写真貼付
備 考
職権打刻番号
本件について許可します。
平成 年 月 日
軽自動車検査協会
大阪主管事務所長
支 所 長

(416)
(2) 検査対象軽自動車の自動車重量税額について
平成 25 年5月1日より自動車重量税が以下のとおり変更になりました。

(417)

(418)
(3)申請書類(OCRシート)について新規検査申請
Ⅰ.新規検査を申請する場合、その自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会に自動車を持
込み、検査を受けてください。
なお、完成検査終了証若しくは保安基準適合証の提出がある場合は、自動車を持込む必要はありませ
ん。
Ⅱ.必要な書類等は次のとおりです。
1新車(新たに自動車を使用するときに車両番号の指定を受ける検査です。) <検査に必要な書類等>
1
新規検査申請書(OCRシート)第1号様式または専用1号様式(専用1号様式は型式車専用です。)
使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必要です。 使用者と所有者が異なる場合は、所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
2 完成検査終了証及び譲渡証明書 3 使用者の住所を証する書面 印鑑証明書、住民票抄本等で発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
4 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
5 自動車重量税納付書 416ページ参照 6 軽自動車税申告書
当協会または隣接する関係団体に用意してあります。 軽自動車検査票は持込検査を行う場合必要です。
7 自動車取得税申告書 8 軽自動車検査票
※型式指定車以外(一般車)は、第1号様式と第2号様式が必要になります。
2.中古車(自動車の使用を一時中止した自動車を再度使用するときに受ける検査です。) <検査に必要な書類等>
1
新規検査申請書(OCRシート)第1号様式または専用1号様式(専用1号様式は型式車専用です。)
使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必要です。 使用者と所有者が異なる場合は、所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
2 自動車検査証返納証明書等 所有者に変更のある場合は、譲渡人印が必要です。 3 使用者の住所を証する書面 印鑑証明書、住民票抄本等で発行日から3ヶ月以内のものが必要です。4 保安基準適合証 指定自動車整備事業者から交付を受けた場合必要です。
5 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
6 点検整備記録簿 車検時期に実施すべき定期点検の記録簿の提示が必要です。 5 自動車重量税納付書 416ページ参照 8 軽自動車税申告書
当協会または隣接する関係団体に用意してあります。 軽自動車検査票は持込検査を行う場合必要です。
9 自動車取得税申告書 10 軽自動車検査票
※型式指定車以外(一般車)は、第1号様式と第2号様式が必要になる場合があります。
Ⅲ.手数料
新規検査手数料
① 完成検査終了証の提出がある自動車、返納証明書とともに保安基準適合証の提出がある自動車並
びに限定自動車検査証とともに限定保安基準適合証の提出がある自動車
1両につき 1,100円
② 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車)
1両につき 1,200円
③ その他の自動車 1両につき 1,400円
なお、上記のほかに、ナンバープレート代、自動車重量税、自動車取得税が必要となります。(中
古車については、自動車取得税がかからない場合があります。)

(419)

(420)

(421)

(422)

(423)

(424)
(4)自動車検査証記入(構造等変更検査)申請
Ⅰ.自動車検査証の記載事項等の変更(構造等変更検査)を申請する場合は、その自動車の使用の本拠の
位置を管轄する軽自動車検査協会に自動車を持込み、検査を受けてください。
Ⅱ.必要な書類等は次のとおりです。
◎ 構造等変更検査(自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量、乗車定員、車体の形状等を変更した場合
受ける検査です。)
<申請に必要な書類等>
1 自動車検査証記入申請書 (OCRシート) 第2号様式
使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必要です。
2 自動車検査証(車検証)
3 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
更新された有効期間が満了するまでの期間の全部を重複するものが必要です。
4 点検整備記録簿 車検時期に実施すべき定期点検の記録簿の提示が必要です。
5 自動車重量税納付書 416ページ参照
6 軽自動車税申告書 当協会または隣接する関係団体に用意してあります。 軽自動車税申告書を行う場合必要です。 8 軽自動車検査票
※ 使用者等の変更が伴う場合は、第1号様式と第2号様式が必要になります。
Ⅲ.手数料
構造等変更検査手数料 1両につき 1,400円
なお、上記のほかに、車両番号の変更を伴う場合は、ナンバープレート代が必要となります。使用
者の変更の場合は自動車取得税が必要となる場合があります。
※ 詳しくは受検される事務所または支所にお問い合わせください。
(5)予備検査申請
・申請書1号
・自動車検査証返納証明書
・軽自動車検査票
・申請審査書
必要書類

(425)

(426)

(427)
(6)自動車検査証記入申請
Ⅰ.自動車の使用者の住所、氏名等自動車検査証の記載事項に変更があった場合は、その自動車の使用の
本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で、次の手続きをしてください。
Ⅱ.必要な書類等は、次のとおりです。
1.使用者または所有者が変わった場合
<申請に必要な書類等>
1
自動車検査証記入申請 (OCRシート) 第1号様式または専用2号様式 (専用2号様式は使用者、所有者、住所変更専用です。)
新しい使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必要です。 新・旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
2 自動車検査証(車検証)
3 使用者の住所を証する書面 印鑑証明書、住民票抄本等で発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
4 自動車損害賠償責任保険(共済)
証明書
5 車両番号票(ナンバープレート) 同じ管轄であれば変更する必要はありません。
6 軽自動車税申告書 当協会または隣接する関係団体に用意してあります。 軽自動車検査票は持込検査を行う場合必要です。 7 自動車取得税申告書
2.引っ越し等により使用者の住所(使用の本拠の位置)が変わった場合
<申請に必要な書類等>
1
自動車検査証記入申請 (OCRシート) 第1号様式または専用2号様式 (専用2号様式は使用者、所有者、住所変更専用です。)
使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必要です。 なお、使用者と所有者が異なる場合は、所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)も必要となります。
2 自動車検査証(車検証)
3 使用者の住所を証する書面 印鑑証明書、住民票抄本等で発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
4 車両番号票(ナンバープレート) 同じ管轄であれば変更する必要はありません。
5 軽自動車税申告書 隣接する関係団体に用意してあります。
※変更後の使用の本拠の位置を管轄する事務所または支所に申請してください。
Ⅲ.手数料
自動車検査証記入申請手数料 無 料
なお、車両番号の変更を伴う場合は、ナンバープレート代が必要となります。使用者の変更(売買
による名義変更)の場合は自動車取得税が必要となる場合があります。
※ 詳しくは申請される事務所または支所にお問い合わせください。

(428)

(429)
(7)解体届出(自動車重量税還付申請)
Ⅰ.使用済自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体された場合に、解体の届出が必要となります。
(被けん引車であるトレーラは除く。)
自動車をスクラップ(解体)にした場合は、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で、次の
手続きをしてください。
なお、既に一時使用停止の手続きを行い、その後、当該自動車を解体し、解体の届出をする場合は、
最寄りの軽自動車協会で手続きができます。
Ⅱ.必要な書類などは、次のとおりです。
1.解体届出(自動車検査証の返納を伴う場合)
1
解体届出書 (OCRシート) 軽第4号様式の3
使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必要です。 所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。 自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。
2 自動車検査証(車検証)
3 車両番号票(ナンバープレート)
4 軽自動車税申告書 隣接する関係団体に用意してあります。
※使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自
動車のみ手続きができます。
2.解体届出(既に一時使用中止の手続きを行い、その後、当該自動車を解体した場合)
1
解体届出書 (OCRシート)
軽第4号様式の3
所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要で
す。
自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取
証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入
が必要です。
※使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)移動報告番号の連絡
がなされた自動車のみ手続きができます。
3.自動車重量税廃車還付申請
自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に
還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
(車検残存期間が1カ月以上ある場合に限ります。)
なお、還付申請には振込先口座番号等が必要になります。
Ⅲ.手数料
解体届出(重量税還付申請)……………………………………………………無 料
※ 詳しくは申請される事務所または支所にお問い合わせください。

(430)

(431)

(432)
(8)一時使用中止(自動車検査証返納証明書交付)申請
Ⅰ.自動車の使用を一時中止する場合は、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で、次の手続き
をしてください。
Ⅱ.必要な書類等は、次のとおりです。
1
自動車検査証返納証明書交付 申請書・自動車検査証返納届出書(OCRシート)軽第4号様式
使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必要です。 なお、使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印も必要となります。
2 自動車検査証(車検証)
3 車両番号票(ナンバープレート)
4 軽自動車税申告書 隣接する関係団体に用意してあります。
Ⅲ.手数料
自動車検査証返納証明書交付申請手数料…………………………1両につき 350円
※ 詳しくは申請される事務所または支所にお問い合わせください。

(433)

(434)
(9)各種申請依頼書

(435)

(436)

(437)

(438)

Ⅲ.そ の 他

(439)
Ⅲ その他
(1)相談窓口について
(1) 公的相談窓口
クルマ購入時のトラブルなどについては、メーカーのお客様相談室の他、ここに挙げた公的な相談
窓口でも受け付けています。
・日本自動車販売協会連合会 03-5733-3105(法務部 消費者相談室)
新車の購入などについての消費者相談を受けてくれる。
・全国軽自動車協会連合会 03-5472-7861(代)
軽自動車の購入などについての消費者相談を受けてくれる。
・日本中古自動車販売協会連合会 03-5333-3328(JU中販連 自動音声相談サービス)
中古車の購入などについての消費者相談を受けてくれる。
・日本自動車輸入組合 03-5765-6811
輸入車全般について消費者相談を受けてくれる。
・自動車公正取引協議会 03-3556-9177(代)(消費者相談室)
消費者相談室で購入についての消費者相談を受けてくれる。
・自動車製造物責任相談センター 0120-028-222
・国民生活センター 03-3446-0999
(2) お客様相談窓口
国産車の場合は、すべてのメーカーがお客様相談室を設けており、購入の相談からクレームまで応え
てくれます。
外国車の場合は、日本法人や輸入元などがユーザーの問い合わせ窓口を設けている場合があります
が、クレームなどは直接受けていないところもあります。
【各メーカーお問い合わせ窓口】
スズキ㈱ お客様相談室 0120-40-2253
ダイハツ工業㈱ お客様相談室 0800-500-0182
トヨタ自動車㈱ お客様相談センター 0800-700-7700
日産自動車㈱ お客様相談室 0120-315-232
富士重工業㈱ お客様センター 0120-052-215
本田技研工業㈱ お客様相談センター 0120-112-010
マツダ㈱ コールセンター 0120-386-919
三菱自動車工業㈱ お客様相談センター 0120-324-860
いすゞ自動車㈱ お客様相談センター 0120-119-113
三菱ふそうトラック・バス㈱ お客様相談センター 0120-324-230
日野自動車㈱ お客様相談窓口 0120-106-558
日産ディーゼル工業㈱ お客様相談室 0120-67-2301
ヤマハ発動機㈱ お客様相談室 0120-090-819
川崎重工業(株) お客様相談室 0120-400-819

(440)
メ ー カ ー T E L
・BMW 0120-553578
・アウディ 0120-598106
・オペル 0120-711276
・クライスラージャパンセールス 0120-712812
・サーブ 0120-711276
・シトロエン 0120-554106
・シボレー 0120-402253
・ジャガージャパン 0120-050689
・フィアットアンドアルファロメオ モータース ジャパン 0120-779159
・フォード 0120-125175
・フォルクスワーゲン グループ ジャパン 0070-800-551133
・プジョージャポン 0120-840240
・ポルシェ 0120-846911
・ボルボカーズジャパン 0120-922662
・メルセデスベンツ日本 0120-190610
・ランドローバージャパン 0120-92-2992
・ルノー 0120-706365
(3) 【官庁等お問い合わせ窓口】
国土交通省:http://www.mlit.go.jp/jidosha/environment_measure/environment_measure.html
自動車検査独立行政法人:http://www.navi.go.jp/
環 境 省:http://www.env.go.jp/air/car/mado/index.html
経済産業省:http://www.meti.go.jp/policy/automobile/noxpmhouhp_zentai.htm
東 京 都:http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/
大 阪 府:http://www.pref.osaka.jp/
兵 庫 県:http://web.pref.hyogo.jp/
京 都 府:http://www.pref.kyoto.jp/
奈 良 県:http://www.pref.nara.jp/
滋 賀 県:http://www.pref.shiga.jp/
和 歌 山 県:http://www.pref.wakayama.jp/
自動車リサイクル法のお問い合わせ先
近畿経済産業局資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課
℡ 06-6966-6018
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
Japan Automobile Recycling Promotion Center
〒105-0012 東京都港区芝大門 1-1-30 日本自動車会館
http://www.jarc.or.jp
℡ 03-5733-8300・ 8301
有限責任中間法人 自動車再資源化協力機構
Japan Auto Recycling Partnership
〒105-0012 東京都港区芝大門 1-1-30 日本自動車会館
http://www.jarp.org
自動車リサイクルシステムに関するお問い合わせ先
自動車リサイクルシステムコンタクトセンター
(コールセンター):050-3786-7758

(441)
(2)自動車リサイクル法関係自治体問合せ窓口一覧 (近畿管内抜粋)
平成 24年 7月 4日現在
自治体名 自治体部局名 電話番号
滋賀県 琵琶湖環境部循環社会推進課 077-528-3474
京都府 文化環境部循環型社会推進課 075-414-4730
京都市 環境政策局事業系廃棄物対策室 075-366-1394
大阪府 環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課
自動車処理対策グループ 06-6210-9573
大阪市 環境局環境管理部産業廃棄物規制グループ 06-6630-3284
堺 市 環境局環境保全部産業廃棄物対策課 072-228-7476
東大阪市 環境部産業廃棄物対策課 06-4309-3207
高槻市 産業環境部資源循環推進課 072-675-5312
兵庫県 農政環境部環境管理局環境整備課 078-362-3281
神戸市 環境局事業系廃棄物対策室 078-322-5306
姫路市 環境局産業廃棄物対策室 079-221-2405
尼崎市 経済環境局環境部産業廃棄物対策担当 06-6489-6310
西宮市 環境局環境総括室産業廃棄物対策課 0798-35-3277
奈良県 くらし創造部景観・環境局廃棄物対策課産業廃棄物第二係 0742-27-8746
奈良市 環境部産業廃棄物対策課 0742-34-4592
和歌山県 環境生活部環境政策局循環型社会推進課廃棄物指導室 073-441-2681
和歌山市 生活環境部産業廃棄物課 073-435-1221
(3)自動車流入・運行規制関係相談窓口
自治体名 自治体部局名 電話番号
大阪府流入車規制
大阪府環境農林水産部環境管理室交通環
境課自動車排ガス規制・指導グループ
URL http://www.pref.osaka.jp/
06-6210-9587
兵庫県ディ―ゼル自動車等
運行規制
兵庫県農政環境部環境管理局水大気課
交通公害係
URL http://web.pref.hyougo.jp/
078-341-7711
(内線 3372)

(442)
(4)希望番号申込サービス 一般社団法人 全国自動車標板協議会
希望ナンバートップページ アドレス https://www.kibou-number.jp/html/CA0101.html
登録車 希望ナンバー予約センター
管轄 希望ナンバー予約センター 住所 TEL FAX
大阪 (一社)大阪府自家用自動車連合協会
寝屋川事業所 寝屋川市高宮栄町12番3号 072-825-4185 072-820-0691
なにわ (一社)大阪府自家用自動車連合協会
なにわ事業所
大阪市住之江区南港東3丁目
1番14号 06-6614-1185 06-6612-7279
和泉 (一社)大阪府自家用自動車連合協会
和泉事業所 和泉市上代町1078-2 0725-41-1200 0725-43-7285
堺
京都 (一社)京都府自動車整備振興会 京都市伏見区竹田向代町51
番地5 075-681-6200 075-661-2218
神戸 (一財)大阪陸運協会兵庫支部 神戸市東灘区魚崎浜町33番
地 078-453-3301 078-453-3302
姫路 (一財)大阪陸運協会姫路支部 姫路市飾磨区中島字福路町
3323 079-233-6131 079-233-6134
奈良 奈良県自動車整備工業協同組合 大和郡山市額田部北町981番
地4 0743-23-1166 0743-57-9111
滋賀 (一社)滋賀県自動車整備振興会 守山市木浜町2298番地1 077-585-5757 077-585-6055
和歌山 (一財)和歌山県自動車標板協会 和歌山市湊1106 073-422-2434 073-433-4025
軽自動車 希望ナンバー予約センター
管轄 希望ナンバー予約センター 住所 TEL FAX
大阪 (一社)大阪府自家用自動車連合協会
高槻事業所高槻市大塚町4丁目20番2号 072-662-5691 072-662-5601
なにわ (一社)大阪府自家用自動車連合協会
南港事業所
大阪市住之江区南港東3丁目
4番62号 06-6569-6287 06-6569-6286
和泉 (一社)大阪府自家用自動車連合協会
和泉軽事業所堺市山田2丁目190番地の3 072-260-1728 072-260-1738
堺
京都 (一社)京都府自動車整備振興会 京都市伏見区竹田向代町51
番地5 075-681-6200 075-661-2218
神戸 (一財)大阪陸運協会玉津支部 神戸市西区玉津町居住字孫
田67の4 078-927-7703 078-927-7739
姫路 (一財)大阪陸運協会姫路支部 姫路市飾磨区中島字福路町
3323 079-233-6131 079-233-6134
奈良 奈良県自動車整備工業協同組合 大和郡山市額田部北町981番
地4 0743-23-1166 0743-57-9111
滋賀 (一社)滋賀県自動車整備振興会 守山市木浜町2298番地1 077-585-5757 077-585-6055
和歌山 (一財)和歌山県自動車標板協会
軽自動車センター和歌山市湊1106-25 073-431-6134 073-431-6155

平成 25年度 自動車分解整備事業・業務資料
平成 25年9月 1日
監 修 近 畿 運 輸 局
発 行 近畿地区自動車整備連絡協議会
印 刷 メディアフタバ株式会社









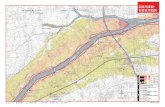







![ハイブリッド自動車49 ハイブリッド自動車 トヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車株式会社 C-HR[DAA-ZYX10] CT200h[DAA-ZWA10]](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5e6e0aa006c2a30f8d6cd183/ffffffee-49-ffffffee-ffeec.jpg)