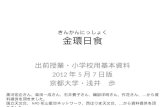知っておくべき インプラントオーバーデンチャー136 補綴臨床別冊/知っておくべきインプラントオーバーデンチャー はじめに インプラントを支台としたオーバーデンチャー
立夏 - satoyama.pref.fukui.lg.jp · 節伸びるといわれています。...
Transcript of 立夏 - satoyama.pref.fukui.lg.jp · 節伸びるといわれています。...


立夏(りっか)2017 5/5 夏が始まる日で、春分と夏至の中間にあたります。野山の木には、新しい葉が目立つようになります。
立夏から立秋の前日までが夏です。
七十二候
第十九候
蛙始鳴 かわずはじめてなく
5/5~5/9 カエル
第二十候
蚯蚓出 みみずいずる
5/10~5/15
ミミズ
第二十一候
竹笋生 たけのこしょうず
5/16~5/20
タケノコ
カエルが鳴き始めるころ。水田の中をスイスイ泳ぎ、活発に活動を始めます。「かわず」はカエルの歌語・雅語です。
冬眠していたミミズが地上にはい出てくるころ。畑の土をほぐしてくれるミミズは、動き始めるのが少し遅めのようです
タケノコが出てくるころ。このころ見られるのはマダケのタケノコでしょう。タケノコは成長が早く、一晩でひと節伸びるといわれています。
小満(しょうまん)2017 5/21 陽気が暖かくなり、畑の麦は大きく補を実らせ、草木の緑がくっきりと色濃くなってくる時期です。 あらゆる生命が天地に満ち始めるという意味の言葉です。
七十二候
第二十二候
蚕起食桑 かいこおきてくわをはむ
5/21~5/25
カイコ
第二十三候
紅花栄 べにばなさかう
5/26~5/30
ベニバナ
第二十四候
麦秋至 むぎのときいかる
5/31~6/4
ムギ
カイコが桑の葉を盛んに食べだすころ。蛾の一種である蚕蛾がつむいだまゆが美しい絹糸になります。
ベニバナの花が咲き誇るころ。ベニバナは紅色の染料や食用油をとるため古来から栽培されてきまし
た。
麦が実りたわわに黄金色の穂をつけるころ。ここでいう「秋」は穀物が成熟する実りの季節を表していま
す。
芒種(ぼうしゅ)2017 6/5 「芒(のぎ)」とは、イネ科の植物の穂の先で、針のようにとがっている部分のことです。
そうした穀物の種をまく時期とされています。
七十二候
第二十五候
蟷螂生 かまきりしょうず
6/5~6/10
カマキリの孵化
第二十六候
腐草為螢 くされたるくさほたるとなる
6/11~6/15
ホタル
第二十七候
梅子黄 うめのみきばむ
6/16~6/20
ウメの実
カマキリが卵からかえるころ。秋のうちに草むらなどに
生みつけられた卵から数百匹の子が誕生します。 草の中からホタルが舞い、光を放ち始めるころ。昔は
腐った草がホタルになると考えられていたようです。 ウメの実が黄ばんで熟すころ。青いウメが次第に、
赤く熟していきます。梅雨入りもこのころです。
夏至(げし)2017 6/21 冬至とは逆に、一年中で最も昼が長く、夜が短くなる日です。気温の面ではまだ真夏という感じはしませんが、日照時間はこれから冬に向かって少しずつ短くなっていきます。
七十二候
第二十八候
乃東枯 なつかれくさかるる
6/21~6/25
ウツボグサ
第二十九候
菖蒲華 あやめさく
6/26~7/1
ハナショウブ
第三十候
半夏生 はんげしょうず
7/2~7/6
カラスビシャク
乃東(だいとう)または夏枯草(かこそう)の異名を持つウツボグサが、黒ずみ枯れたように見えるころ。
アヤメの花が咲き始めるころ。端午の節句に用いる菖蒲(しょうぶ)ではなく、花菖蒲のことです。
半夏(はんげ)が生え始めるころ。田植えを終える目安とされました。半夏は烏柄杓(からすびしゃく)の異名です。
小暑(しょうしょ)2017 7/7 本格的な暑さが始まるころです。小暑と次の大暑の間を暑気と呼び、立秋の前日までに「暑中見舞い」を出します。
七十二候
第三十一候
温風至 あつかぜいたる
7/7~7/11
ツユクサ
第三十二候
蓮始開 はすはじめてひらく
7/12~7/16
ハスの花
第三十三候
鷹乃学習 たかすなわちわざをならう
7/17~7/22
タカ
暑い風が吹き始めるころ。温風は梅雨明けのころに吹く南風のこと。日に日に暑さが増して、本格的な
夏の訪れを感じます。
ハスの花が咲き始めるころ。優美なハスは天上の花にたとえられ、明け方に花を開き、昼過ぎには閉じて
しまいます。
鷹の子が飛ぶ技を覚え、巣立ちを迎えるころ。獲物を捕らえ一人前になっていきます。日本で鷹といえば
オオタカをさします。
大暑(たいしょ)2017 7/23 文字どおり、一年のうちで一番暑いころです。
ウナギで知られる「土用の丑」もこの期間中にあります。
七十二候
第三十四候
桐始結花 きりはじめてはなをむすぶ
7/23~7/27
キリの実
第三十五候
土潤溽暑 つちうるおうてむしあつし
7/28~8/1
アサガオ
第三十六候
大雨時行 たいうときどきおこなう
8/2~8/6
キキョウ
桐の花が実を結び始めるころ。桐はタンスや下駄などくらしの道具に欠かせません。五百円硬貨にも意匠化されています。
地面からは陽炎が立ち上がり、土がじっとりして蒸し暑くなるころ。木や草花の緑がますます濃くなってくる時期です。
この時期には、台風や集中豪雨、夕立などの大粒の雨が地面をたたきます。むくむくと湧き上がる入道雲は夏の原風景です。

◇初夏を過ぎると、昆虫や小動物など身近に見られる生きものの種類がさらに多くなります。◇
◇こんな生きものも見つけたら報告してください。◇
植物
ノアザミ
(科)
ホタルブクロ
(キク科)
オカトラノオ
(科)
里山で初夏から梅雨にかけて咲きます。近年は外来
種のアメリカオニアザミが造成地などで見られます。
里山の林縁や斜面でよく見られます。6~7 月頃にう
す紫色の釣鐘のような花を咲かせます。
里山の雑木林周辺に生え、白い花穂を虎のしっぽに
見立てて名づけられています。
ヤマユリ
(科)
ネムノキ
(マメ科)
サルスベリ
(ミソハギ科)
里山の雑木林周辺に生え、夏に大きな白い花を咲
かせます。とても強い芳香があります。
川岸や山野に生える落葉高木。6~7 月に花を咲か
せ、長く伸びた雄しべが房のように見えます。
庭や公園などによく植えられている落葉樹。漢名の百
日紅は花期が7~10月と長いためです。
昆虫
カブトムシ
(コガネムシ科)
ノコギリクワガタ
(コガネムシ科)
アブラゼミ
(セミ科)
クヌギなどの樹液や、熟した果実に集まる大型の甲虫類。オスには大きな角があります。
里山ではカブトムシと並んで最も人気がある甲虫の1つです。赤みがかった体色をしています。
ジージリジリジリと連続して鳴きます。体は胸部の赤褐色の2紋のほかはほぼ黒い色です。
オニヤンマ (オニヤンマ科)
シオカラトンボ (トンボ科)
トノサマバッタ (バッタ科)
里山の湧水周辺に見られ、縄張りを何度も往復してパトロールしている姿が見られます。
羽化したてのオスはメスと同じ色をしていますが、成熟するにつれて黒化し、白い粉でおおわれます。
川原などの草原にすみ、飛ぶ力がとても強いバッタです。幼虫も成虫も主に植物を食べます。
その他の生きもの
ホトトギス
(カッコウ科)
アオバズク
(フクロウ科)
アマサギ
(サギ科)
カッコウ類の中では遅く渡来し、5月中旬からその鳴き声を聞くことができます。
“青葉のころに渡来するミミズク”の意味どおり、福井県でも5月ごろから観察されます。
河川や水田とその周辺に生息し、中州や河川敷の林でコサギ、ゴイサギなどとコロニーを形成します。
シュレーゲルアオガエル
(アオガエル科)
ナマズ
(ナマズ科)
アマガエルによく間違えられますが、目の前後が黒くならないことや鼻先が尖っていることで見分けられま
す。。
4本の長いひげと大きな口を持つ肉食魚の一種。5月中旬から7月上旬に田んぼなどで産卵します。

見つけた生きもの
ホームページ掲載用のニックネーム
調べた(見た・聞いた)日 年 月 日
見つけた場所
(住所や目印など、できるだけ具体的に記入してください。)
一言コメント
プレゼントを希望される方は、以下も御記入ください。
住所 〒
氏名
連絡先
季節ごとの生きものの情報、画像を 投稿してください。
福井県里山里海湖研究所では、二十四節気や七十二候などの歳時記に見られる時節の生きものの情報や画像を募
集しています。
投稿いただいた情報は、専用のホームページ上で公開します。
情報をいただいた方の中から、毎月抽選でプレゼントを進呈します。
情報提供の仕方 ①生きものを見つける。
時節の生きものや植物などを探してみます。昨日までいなかった生きものや、
いつの間にか咲いていた花など、身のまわりの自然に目を向けてみましょう。
季節ごとの生きもの情報は、里山里海湖研究所のホームページでチェックしていただいてもOKです。
②-1里山里海湖研究所のHPから投稿する。
福井県里山里海湖研究所ホームページの投稿フォームから、氏名(ニックネーム)、見つけた生きもの、場所、コメン
トなどを記入して投稿してください。できるだけ、生きものを撮影した写真も添付してください。
HPアドレス:http://satoyama.pref.fukui.lg.jp
②-2郵送・FAX で報告する。
下記の報告シートに必要事項を記入の上、里山里海湖研究所まで送付してください。その際にも、できるだけ写真を
添えて送ってください。
郵送先:〒919-1331 三方上中郡若狭町鳥浜 122-31-1
FAX:0770-45-3680
③HPに生きものの写真や情報が表示されます。
福井県里山里海湖研究所のホームページ内に、生きものの写真や
情報などのほか、見つけた場所が福井県のマップ上に表示されます。