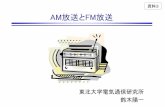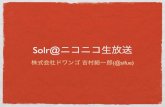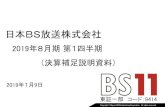朝日放送グループホールディングス株式会社 › ja › ir › library › presentation › main › ...朝日放送グループホールディングス株式会社
第 2 章 組織・運営 · 第 2 章 組織・運営 ... 半導体・デバイス事業本部長...
Transcript of 第 2 章 組織・運営 · 第 2 章 組織・運営 ... 半導体・デバイス事業本部長...
2.2 運営協議会委員名簿 運営協議会は、東北大学電気通信研究所長の諮問に応じ、共同利用・共同研究拠点とし
ての活動に関する重要事項、その他研究所長が必要と認める事項について協議する組織で
ある。
秋葉 重幸(委 員)株式会社KDDI研究所 主席特別研究員 荒川 泰彦( 〃 )東京大学 生産技術研究所 教授 一村 信吾( 〃 )独立行政法人 産業技術総合研究所 理事 上田 修功( 〃 )日本電信電話株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所長 潮田 資勝( 〃 )独立行政法人 物質・材料研究機構 理事長 江村 克己( 〃 )日本電気株式会社 執行役員 兼 中央研究所長 太田 賢司(委員長)シャープ株式会社 代表取締役 副社長執行役員
技術担当兼東京支社長 久間 和生(委 員)三菱電機株式会社 執行役副社長
半導体・デバイス事業本部長 久保田啓一( 〃 )日本放送協会 放送技術研究所長 坂内 正夫( 〃 )大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構
理事・国立情報学研究所長 富田 眞治( 〃 )京都大学 物質-細胞統合システム拠点 特定拠点教授 富永 昌彦( 〃 )独立行政法人 情報通信研究機構 理事 西尾章治郎( 〃 )大阪大学 大学院情報科学研究科 教授 丹羽 邦彦( 〃 )独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター
上席フェロー 吉田 博( 〃 )大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授 福村 裕史( 〃 )東北大学 大学院理学研究科長 内山 勝( 〃 )東北大学 大学院工学研究科長 亀山 充隆( 〃 )東北大学 大学院情報科学研究科長 新家 光雄( 〃 )東北大学 金属材料研究所長 河村 純一( 〃 )東北大学 多元物質科学研究所長 小林 広明( 〃 )東北大学 サイバーサイエンスセンター長 畠山 力三( 〃 )東北大学 大学院工学研究科 教授
2.3 共同研究組織 本研究所は平成6年に国立大学附属の共同利用研究所に改組され、全国唯一の情報通信に関する共同
利用研究所となった。本研究所はこれまで半導体材料、デバイス、磁気記録、光通信、電磁波技術、超
音波技術、音響通信、非線形物理工学、生体情報、情報システム、コンピュータソフトウェアなどの諸
領域において数々の世界的業績を上げてきた。また、「超微細電子回路実験施設」は改組を機として「超
高密度・高速知能システム実験施設」、さらに平成 16年の改組に伴い、「ナノ・スピン実験施設」と「ブレインウェア実験施設」の 2施設として設備を充実し発足した。実験施設ではこれらの技術を発展させると共にそれぞれの先導的研究開発を目指すことになった。 本研究所の各分野・実験施設の各部の充実により、情報通信に関する研究環境が一層整備されつつあ
る。これを背景として、本研究所の各研究分野・部の研究者は研究所の目的達成のための基礎研究に加
えて、全国の情報通信の科学技術の研究に携わる研究者と有機的な連携をとりながら、本研究所を中核
とする総合的な共同プロジェクト研究を行っている。 共同プロジェクト研究の研究組織は次のような手続きを経て構成される。まず毎年所内の研究組織が
研究者の英知を集めるためにユーザーの要望など所内外から広くご意見を戴き、それを基に「共同プロ
ジェクト研究」を立案する。それを「共同プロジェクト研究委員会」が審査し、課題を企画する。この
課題は「事務部研究協力係」より全国の国公私立大学及び研究機関に通知され、各共同プロジェクト研
究への参加者を公募する。なお、共同プロジェクト研究の採択に際し審査を厳格に行うため、平成19
年度に外部委員を含めたプロジェクト審査委員会を設置した。これにより応募研究者を含めた共同プロ
ジェクト研究組織が編成される。これを研究所内外の委員からなる「プロジェクト実施委員会」に諮問
し、その意見を尊重して「教授会」が最終的に共同プロジェクト研究実行案を承認し、実行に移される。 運営協議会は、本研究所の「共同プロジェクト研究」に関する運営の大綱について所長の諮問に応じ
て審議する。
組織・運営
4
電気通信-2章-二[9-12].indd 4 2012/08/23 14:21:20
2.2 運営協議会委員名簿 運営協議会は、東北大学電気通信研究所長の諮問に応じ、共同利用・共同研究拠点とし
ての活動に関する重要事項、その他研究所長が必要と認める事項について協議する組織で
ある。
秋葉 重幸(委 員)株式会社KDDI研究所 主席特別研究員 荒川 泰彦( 〃 )東京大学 生産技術研究所 教授 一村 信吾( 〃 )独立行政法人 産業技術総合研究所 理事 上田 修功( 〃 )日本電信電話株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所長 潮田 資勝( 〃 )独立行政法人 物質・材料研究機構 理事長 江村 克己( 〃 )日本電気株式会社 執行役員 兼 中央研究所長 太田 賢司(委員長)シャープ株式会社 代表取締役 副社長執行役員
技術担当兼東京支社長 久間 和生(委 員)三菱電機株式会社 執行役副社長
半導体・デバイス事業本部長 久保田啓一( 〃 )日本放送協会 放送技術研究所長 坂内 正夫( 〃 )大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構
理事・国立情報学研究所長 富田 眞治( 〃 )京都大学 物質-細胞統合システム拠点 特定拠点教授 富永 昌彦( 〃 )独立行政法人 情報通信研究機構 理事 西尾章治郎( 〃 )大阪大学 大学院情報科学研究科 教授 丹羽 邦彦( 〃 )独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター
上席フェロー 吉田 博( 〃 )大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授 福村 裕史( 〃 )東北大学 大学院理学研究科長 内山 勝( 〃 )東北大学 大学院工学研究科長 亀山 充隆( 〃 )東北大学 大学院情報科学研究科長 新家 光雄( 〃 )東北大学 金属材料研究所長 河村 純一( 〃 )東北大学 多元物質科学研究所長 小林 広明( 〃 )東北大学 サイバーサイエンスセンター長 畠山 力三( 〃 )東北大学 大学院工学研究科 教授
2.3 共同研究組織 本研究所は平成6年に国立大学附属の共同利用研究所に改組され、全国唯一の情報通信に関する共同
利用研究所となった。本研究所はこれまで半導体材料、デバイス、磁気記録、光通信、電磁波技術、超
音波技術、音響通信、非線形物理工学、生体情報、情報システム、コンピュータソフトウェアなどの諸
領域において数々の世界的業績を上げてきた。また、「超微細電子回路実験施設」は改組を機として「超
高密度・高速知能システム実験施設」、さらに平成 16年の改組に伴い、「ナノ・スピン実験施設」と「ブレインウェア実験施設」の 2施設として設備を充実し発足した。実験施設ではこれらの技術を発展させると共にそれぞれの先導的研究開発を目指すことになった。 本研究所の各分野・実験施設の各部の充実により、情報通信に関する研究環境が一層整備されつつあ
る。これを背景として、本研究所の各研究分野・部の研究者は研究所の目的達成のための基礎研究に加
えて、全国の情報通信の科学技術の研究に携わる研究者と有機的な連携をとりながら、本研究所を中核
とする総合的な共同プロジェクト研究を行っている。 共同プロジェクト研究の研究組織は次のような手続きを経て構成される。まず毎年所内の研究組織が
研究者の英知を集めるためにユーザーの要望など所内外から広くご意見を戴き、それを基に「共同プロ
ジェクト研究」を立案する。それを「共同プロジェクト研究委員会」が審査し、課題を企画する。この
課題は「事務部研究協力係」より全国の国公私立大学及び研究機関に通知され、各共同プロジェクト研
究への参加者を公募する。なお、共同プロジェクト研究の採択に際し審査を厳格に行うため、平成19
年度に外部委員を含めたプロジェクト審査委員会を設置した。これにより応募研究者を含めた共同プロ
ジェクト研究組織が編成される。これを研究所内外の委員からなる「プロジェクト実施委員会」に諮問
し、その意見を尊重して「教授会」が最終的に共同プロジェクト研究実行案を承認し、実行に移される。 運営協議会は、本研究所の「共同プロジェクト研究」に関する運営の大綱について所長の諮問に応じ
て審議する。
組織・運営
5
電気通信-2章-二[9-12].indd 5 2012/08/23 14:21:20
2.4 教育組織 東北大学電気通信研究所(以下、通研と省略)は、発足時から設立母体である電気工学科と協力体制を
とり、教育・研究の成果を挙げてきた。その後、通信工学科、電子工学科、情報工学科が順次設立され
るとともに、これらの電気・情報系 4学科との「一体運営」の協力関係が維持構築された。 現在、通研と電気・情報系との間には下図に示す相互教育関係が維持されている。2004 年、電気・
情報系 4 学科は応用物理学科と合同の大学科,電気情報・物理工学科となった。2007 年には情報知能システム総合学科と改称し,そのなかの 6コースが電気・情報系と位置づけられている。また、大学院重点化に伴い、通研教員と大学院の関係は兼担から兼務へ変わっている。2011年度は、通研の 27研究室・分野のうち 9研究部・分野が工学研究科電気・通信工学専攻に、11研究部・分野が電子工学専攻に、2 分野が情報科学研究科情報基礎科学専攻に、4 分野がシステム情報科学専攻に、1 研究部が応用情報科学専攻に、3 研究部・分野が医工学研究科医工学専攻に、それぞれ所属し、通研で研究指導を受けた大学院学生の総数は 196名、一研究室当たり平均 7名に達している。 通研と電気・情報系学科の関係で特徴的な点は、全教員が兼務として互いに協力し合っていることで
ある。通研の教授・准教授は全員、学部学生に対する講義を担当し、助教は実験を指導して教育に協力
している。一方、電気・情報系の教員も通研兼務であり、学部学生も通研の各研究室に配属されている。
これにより学生にとっても研究室選択の幅が広がり、世界最先端の研究指導が受けられるようになって
いる。一方、通研にとっても若い行動力は重要であり、研究活動が活性化される。通研が電気通信の分
野で多くの成果をあげてきた理由には、このような教育面での協力関係に因るところが大きい。 通研と電気・情報系の運営の中核には両組織の教授で構成される研究教授会がある。教授会通則に基
づく会議とは別の性格の、部局を横断して形成された会議であって、教育問題など相互に関連する重要
事項はここで審議される。教育上の具体的な事項の実行、運用に関しては、大学院に工学研究科電通・
電子専攻教員会議、電気・情報系 4コースに大学院教務委員会があり、通研からも委員が参加している。 通研は工学研究科、情報科学研究科、医工学研究科の関連研究分野と密接な協力体制をとり、研究の
みならず教育でも COEとしての重要な一翼を担っている。
研 究 教 授 会
電気通信研究所
大学院〈工学研究科〉
(1) 電気・通信工学専攻(2) 電子工学専攻
大学院〈情報科学研究科〉 (1) 情報基礎科学専攻 (2) システム情報科学 (3) 応用情報科学専攻
学部〈工学部 電気情報系〉 情報知能システム総合学科 (1) エネルギーインテリジェンスコース (2) コミュニケーションネットワークコース (3) 情報ナノエレクトロニクスコース (4) コンピューターサイエンスコース (5) 知能コンピューティングコース (6)メディカルバイオエレクトロニクスコース
兼務 会議構成員 学生の研究室配属
大学院〈医工学研究科〉
(1) 医工学専攻
組織・運営
6
電気通信-2章-二[9-12].indd 6 2012/08/23 14:21:20