2020年3月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) - …(IFRSの適用) 当社は、前連結会計年度末(2019年3月期)における連結財務諸表から国際財務報告基準(IFRS)を適
Applying IFRS - EY Japan · 2019-06-03 · ifrs 第16 号は、2019 年1 月1...
Transcript of Applying IFRS - EY Japan · 2019-06-03 · ifrs 第16 号は、2019 年1 月1...
1 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
目次
概要 ................................................................................................................................. 4
1. IFRS第16号の目的と適用範囲 ...................................................................................... 5
1.1 IFRS第 16号の目的 ....................................................................................... 5
1.2 IFRS第 16号の適用範囲 ................................................................................. 5
1.3 認識に関する免除規定 ..................................................................................... 5
2. リースとは何か ............................................................................................................ 6
2.1 契約にリースが含まれているか否かの判断 .......................................................... 6
2.2 契約におけるリース構成部分と非リース構成部分の識別及び区分、
ならびに契約対価の配分 ................................................................................ 20
2.3 契約の結合 .................................................................................................. 27
3. 主要な概念 ............................................................................................................... 28
3.1 契約の開始 .................................................................................................. 28
3.2 リースの開始日 ............................................................................................. 28
3.3 リースの開始日前における原資産への借手の関与 .............................................. 29
3.4 リース期間及び購入オプション ......................................................................... 29
3.5 リース料 ....................................................................................................... 35
3.6 割引率 ......................................................................................................... 40
3.7 当初直接コスト .............................................................................................. 41
3.8 経済的耐用年数 ............................................................................................ 42
3.9 公正価値...................................................................................................... 42
4. 借手の会計処理 ........................................................................................................ 43
4.1 当初認識...................................................................................................... 43
4.2 当初測定...................................................................................................... 46
4.3 事後測定...................................................................................................... 47
4.4 リース負債の再測定 ....................................................................................... 51
4.5 リースの条件変更 .......................................................................................... 52
4.6 借手に関するその他の事項 ............................................................................. 58
4.7 表示 ............................................................................................................ 60
4.8 開示 ............................................................................................................ 61
5. 貸手の会計処理 ........................................................................................................ 65
5.1 リースの分類 ................................................................................................ 65
5.2 貸手が適用する主要な概念 ............................................................................. 67
5.3 ファイナンス・リース ........................................................................................ 67
5.4 オペレーティング・リース .................................................................................. 71
5.5 リースの条件変更 .......................................................................................... 72
5.6 その他の貸手に関する事項 ............................................................................. 73
5.7 表示 ............................................................................................................ 74
5.8 開示 ............................................................................................................ 74
2 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
6. サブリース ................................................................................................................ 76
6.1 定義 ............................................................................................................ 76
6.2 中間の貸手の会計処理 .................................................................................. 76
6.3 転借人の会計処理 ......................................................................................... 78
6.4 表示 ............................................................................................................ 78
6.5 開示 ............................................................................................................ 78
7. セール・アンド・リースバック取引 .................................................................................. 79
7.1 資産の譲渡が売却であるかどうかの判断 ........................................................... 79
7.2 資産の譲渡が売却である取引 ......................................................................... 81
7.3 資産の譲渡が売却ではない取引 ...................................................................... 84
7.4 開示 ............................................................................................................ 84
8. 企業結合 .................................................................................................................. 85
8.1 企業結合における被取得企業が借手である場合 ................................................. 85
8.2 企業結合における被取得企業が貸手である場合 ................................................. 86
9. 発効日及び経過措置.................................................................................................. 87
9.1 発効日 ......................................................................................................... 87
9.2 経過措置...................................................................................................... 87
9.3 借手の経過措置 ............................................................................................ 88
9.4 貸手 ............................................................................................................ 96
9.5 その他の検討事項 ......................................................................................... 97
9.6 開示 ............................................................................................................ 98
付録A:IFRS第16号の用語の定義 .................................................................................... 100
付録B:IFRS第16号とIAS第17号との主要な差異 ............................................................... 103
付録C:IFRS第16号とASC第842号との主な差異 ................................................................ 109
付録D:リースの再評価及び再測定に関する要求事項の概要 .................................................. 115
3 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
重要ポイント
• IFRS第16号「リース」により、借手はほとんどのリースを貸借対照表に認識することになる。
• 借手は一部の例外を除いて、すべてのリースについて単一の会計処理モデルを適用する。
• 貸手の会計処理は、現行基準 IAS 第 17 号「リース」に定められる会計処理から基本的に
変更はない。
• IFRS第 16号は、2019年 1月 1日以降開始する事業年度から適用され、早期適用も認
められる。
4 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
概要
IFRS 第 16 号「リース」は借手に対して、大半のリースを貸借対照表に資産及び負債として認識す
ることを求めている。国際会計基準審議会(IASB/審議会)は米国財務会計基準審議会(FASB)と
共同して審議を重ねた結果として、新たなリース基準を公表した。一方の FASB も同様の基準を公
表したが、IASB と FASB の両基準には、重要な差異が生じることになった(例:FASB の基準では、
借手はリースをファイナンス・リース又はオペレーティング・リースに区分する)。このような違いによ
り、IASB の基準と FASB の基準では、一部の取引について会計処理に差異が生じる。本書の付録
Cに IFRS第 16号と ASC第 842号の主な相違点を要約しているため参照されたい。
従前の基準である IAS第 17号では、借手はオペレーティング・リースに関して、資産や負債を認識
することがないため、財務諸表利用者のニーズを満たしていないという批判があった。これに対して
IFRS第16号は、借手にほとんどのリースを貸借対照表に認識することを求めるとともに、開示を改
善することにより、従来の批判に対処している。これにより IASB は、借手の資産や負債がより忠実
に表現されることになり、借手の負債やリース活動の透明性が一層高まると考えている。
IFRS 第 16 号では、リースは「使用権モデル」により会計処理される。これは、借手はリースの開始
日時点で、リース期間にわたって原資産を使用する権利に関しリース料を貸手に支払う金融債務を
有することを反映している。貸手はリースの開始日に原資産を使用する権利を移転することになる。
リースの開始日とは、借手が原資産を利用できるようになる日をいう。
リースとサービス契約では会計処理に大きな違いが生じることから、契約がリースであるか、それと
もサービス契約であるかを見極める必要がある。IFRS 第 16 号ではリースの定義が変更されるが、
契約がリースを含むかどうかの評価は多くの場合には明白と考えられる。ただし、重要なサービス
が含まれる契約など、契約によっては、リースの定義の適用に関して判断が求められることがある。
借手における損益計算書の表示及び費用認識パターンは、IAS第 17号によるファイナンス・リース
と同様である(利息費用と減価償却費の合計であるリース費用が、契約期間の前半においてより多
く発生する)。
貸手の会計処理は、現行の会計処理から基本的には変わらない。貸手は IAS 第 17 号と同じ原則
を用いて、すべてのリースをオペレーティング・リース又はファイナンス・リースに分類する。
IFRS第 16号は、2019年 1月 1日以降開始する事業年度から適用される。
IFRS 第 16 号の経過措置によれば、借手は同基準の適用開始日(同基準を最初に適用する報告
期間の期首)に存在するリースに関して、完全遡及適用アプローチ又は修正遡及適用アプローチの
いずれかを用いることができ、一定の免除規定が設けられている。
本書は、IFRS第 16号の適用による影響を検討する際の一助となるように、その適用方法について
解説している。
また本書は、2018 年 12 月時点における EY の見解を示している。EY が新基準の分析や適用に
関する解釈をする過程において、新たな課題が識別され、それに応じて EY の見解が変わる可能性
がある点には留意されたい。
新たなリース基準では借手はほと
んどのリースを貸借対照表に認識
する。
5 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
1. IFRS第16号の目的と適用範囲
1.1 IFRS第16号の目的
IFRS 第 16 号は、リースの認識、測定、表示及び開示に関する原則を定めている。その目的は、
リース取引の借手及び貸手が、その取引を忠実に表現することにより、目的適合性のある情報を提
供することにある。これらの情報は、財務諸表の利用者が、リースによる財政状態、財務業績及び
キャッシュ・フローに及ぼす影響を評価するための基礎を提供することになる。
IFRS 第 16 号は、契約条件やすべての関連する事実と状況に照らして、同様の状況にある同様の
特徴を有する契約に整合的に適用することを求めている。
1.2 IFRS第16号の適用範囲
IFRS第 16号からの抜粋
3 企業は、本基準をすべてのリース(サブリースにおける使用権資産のリースを含む)に適用
しなければならない。ただし、下記のものは除く。
(a) 鉱物、石油、天然ガス及び類似の非再生資源の探査又は利用のためのリース
(b) 借手が保有している IAS第 41号「農業」の範囲に含まれる生物資産のリース
(c) IFRIC第 12号「サービス委譲契約」の範囲に含まれるサービス委譲契約
(d) IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」の範囲に含まれる貸手が供与する知的財産
のライセンス
(e) 映画フィルム、ビデオ録画、演劇脚本、原稿、特許権及び著作権などの項目について、借手
が IAS第 38号「無形資産」の範囲に含まれるライセンス契約に基づいて保有している権利
4 借手は、本基準を第 3 項(e)で記述したもの以外の無形資産のリースに適用することがで
きるが、要求はされない。
IFRS 第 16 号は下記を除く、すべてのリース(サブリースにおける使用権資産のリースを含む)に適
用する。
• 鉱物、石油、天然ガス及び類似の非再生資源の探査又は利用のためのリース
• 借手が保有するIAS第41号「農業」の範囲に含まれる生物資産のリース
• IFRIC第12号「サービス委譲契約」の範囲に含まれるサービス委譲契約。したがって、契約に
リースが含まれているかどうかを評価する前に、IFRIC第12号が適用されるかどうかを評価す
ることになる。
• IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の範囲に含まれる貸手が供与する知的財産のラ
イセンス
• 映画フィルム、ビデオ録画、演劇脚本、原稿、特許権及び著作権などの項目について、IAS第
38号「無形資産」の範囲に含まれるライセンス契約に基づいて借手が保有する権利
借手は、上記の項目に該当しない無形資産のリースに IFRS 第 16 号を適用することは求められて
ない。しかし、借手は、当該無形資産のリースを IFRS第 16号に従って会計処理することができる。
1.3 認識に関する免除規定
IFRS第 16号によると、借手は下記の取引に対しては認識の定めを適用する必要がない。
(a) 短期リース
(b) 原資産が少額のリース
これらの認識の免除規定は、セクション 4.1で説明している。
6 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
2. リースとは何か
リースとは、「特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契
約(強制可能な権利及び義務を創出する複数の当事者間の合意)又は契約の一部」である。
IFRS第 16号は、契約の開始時に、契約がリースであるか又はリースを含んでいるかどうかの判断
を求めている。契約がリースに該当するか、又はリースを含むかどうかの判断は、多くの契約では
明らかである。ただし、一部の契約では、リースの定義を適用する際に判断が求められる場合があ
る。たとえば、重要なサービス要素を含む契約では、当該契約により特定された資産の使用を指図
する権利が移転されるかどうかを判断することが困難になる場合がある。この点については下記で
説明する。
2.1 契約にリースが含まれているか否かの判断
IFRS第 16号からの抜粋
付録 A
用語の定義
リース(lease)
資産(原資産)を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分
契約(contract)
強制可能な権利及び義務を創出する複数の当事者間の合意
使用期間(period of use)
資産が顧客との契約を履行するために使用される期間(非連続の期間を含む)
9 契約時に、企業は、当該契約がリース又はリースを含んだものであるのかどうかを判定し
なければならない。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対
価と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるか又はリースを含んでいる。B9項
から B31 項は、契約がリース又はリースを含んだものであるかどうかの判定に関してのガ
イダンスを示している。
B9 契約が特定された資産(B13 項から B20 項参照)の使用を一定期間にわたり支配する権
利を移転するのかどうかを評価するため、企業は、使用期間全体を通じて、顧客が下記の
両方を有しているのかどうかを評価しなければならない。
(a) 特定された資産の使用からの経済的便益のほとんどすべてを得る権利(B21 項から B23
項に記述)
(b) 特定された資産の使用を指図する権利(B24項から B30項に記述)
B10 顧客が特定された資産の使用を契約期間の一部分についてのみ支配する権利を有してい
る場合には、契約は契約期間の当該部分についてのリースを含んでいる。
B11 財又はサービスを受け取る契約が、IFRS 第 11 号「共同支配の取決め」で定義されている
共同支配の取決めによって、又は共同支配の取決めのために締結される場合がある。この
場合、その共同支配の取決めは契約における顧客とみなされる。したがって、このような契
約がリースを含んでいるかどうかを評価する際に、企業は、共同支配の取決めが特定され
た資産の使用を使用期間全体を通じて支配する権利を有しているのかどうかを評価しなけ
ればならない。
B12 企業は、契約がリースを含んでいるかどうかを、独立したリース構成部分である可能性のあ
る構成部分のそれぞれについて評価しなければならない。独立したリース構成部分に関す
るガイダンスについては B32項参照。
リースとは、「特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり、対価と交換に移転する
契約(強制可能な権利及び義務を創出する複数の当事者間の合意)又は契約の一部」である。
7 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
2.1.1 共同支配の取決め
企業は、特定の事業活動(例:油田やガス田の探査、医薬品の開発)のために他の企業と共同支配
の取決めを締結することがある。
共同支配の取決めによる資産の使用に関する契約は、たとえば以下のようなさまざまな方法により
締結される。
1. 共同支配の取決めが法人格を有する場合には、共同支配の取決めにより契約が直接締結さ
れる。
2. 共同支配の取決めの当事者(すなわち、代表事業者と一般的に「その他事業者」と呼ばれるそ
の他の当事者)が、それぞれに同じ取決めに署名することで契約が締結される。
3. 共同支配の取決めを代表する1人又は複数の当事者により、契約が締結される。この点は通
常は契約において証拠付けられ、共同支配の当事者は、それぞれに当該契約に署名する場
合と同様の権利と義務を有する。このような状況では、事実と状況、及び各企業の法的なス
テータスを慎重に評価する必要がある。
4. 共同支配の取決めの代表事業者が自己の名義で、すなわち本人として契約が締結される。こ
れは、共同支配の取決めの代表事業者としての義務を履行するために使用する設備をリース
することもあれば、さまざまな関連性のない活動に係る設備をリースする場合に、このような契
約が締結されることもある(ジョイント・オペレーションのその他の当事者と締結される場合な
ど、関連性がない活動に関するその他の共同支配の取決めがこれに含まれる)。
財又はサービスを受け取る契約が、IFRS 第 11 号「共同支配の取決め」で定義される共同支配の
取決めにより、又は共同支配の取決めのために締結されることがある。その場合、その共同支配の
取決めは契約における顧客とみなされる。したがって、当該契約がリースを含むかどうかを評価す
る際には、いずれの当事者(例:共同支配の取決め又は代表事業者)が特定された資産の使用を
支配する権利を使用期間にわたって有しているのかを検討する。
共同支配の取決めの当事者が、営業活動を集合的に支配していることにより、その使用期間にわ
たって特定された資産の使用を支配する権利を当該取決めに対する共同支配を通じて集合的に有
している場合には、共同支配の取決めは、リースを含む契約の顧客になる。共同支配の取決めの
各当事者が、原資産の物理的に区別できない部分に対する権利を有しており、したがって、原資産
の使用から生じる経済的便益のほぼすべてに対する権利を有していない、又は一方的にその使用
を指図することができないという理由で、契約はリースを含んでいないと結論付けることは不適切で
ある。共同支配の取決めの当事者が、集合的に共同支配の取決めに対する共同支配を通じて、使
用期間全体にわたり特定された資産の使用を支配する権利を有しているか否かの判断にあたって
は、各当事者の権利と義務を慎重に分析する必要がある。
上記のシナリオのうちの最初の 3つについては、契約がリースである、又はリースを含んでいると判
断される場合には、共同支配の取決めの当事者(すなわち、代表事業者とその他事業者とで構成さ
れる共同支配事業者)それぞれが、IFRS 第 11 号第 22 項から第 23 項に従って共同支配の取決
め(リースを含む)に対する各持分を会計処理する。したがって、各当事者は使用権資産とリース負
債及び関連する減価償却費と利息費用に対するそれぞれの持分を会計処理する。
4 つ目のシナリオ(すなわち、代表事業者が自己の名義で契約を締結する)の場合、代表事業者は、
契約がリースであるか、又はリースを含んでいるかを評価する必要がある。代表事業者が特定された
資産の使用を支配する場合には、全体の使用権資産及びリース負債を自身の貸借対照表に認識す
る。たとえば、ジョイント・オペレーション契約(JOA)に従って、代表事業者がその他事業者に対して、
その持分に比例するコストを請求する権利を有している場合であっても、このケースに該当する。
また、代表事業者が借手であると判断される場合には、共同支配の取決めとサブリース契約を締結
しているかどうか(共同支配の取決めはサブリースの顧客かどうか)を評価する。たとえば、代表事
業者が供給業者と期間 5年の設備リース契約を締結し、その上で共同支配の取決めとも期間 2年
の取決めを締結する場合には、設備を 2 年間使用する権利の支配が当該共同支配の取決めに移
転する。しかし多くの場合には、契約により資産の使用を支配する権利を共同支配の取決めに移転
する法的に強制可能な権利と義務が生じず、代表事業者がサブリースを認識する要件を満たすこと
はないであろう。ただし、JOA に照らして共同支配の取決めが顧客であるか、すなわち代表事業者
との契約における借手になるかに関する結論は、個々の事実と状況による。
8 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
代表事業者とのサブリースが存在する場合、その他事業者は IFRS第 11号に従って、共同支配の
取決めの使用権資産及びリース負債に対するそれぞれの持分を認識し、代表事業者は共同支配
の取決めに対するサブリースを別途、会計処理する。一方でサブリースが存在しない場合には、そ
の他事業者は、代表事業者に生じるリース資産に関するコストに関して、自身の持分に対応する部
分が発生した時点で当該支払債務を認識する。
限られたケースではあるが、代表事業者とその他事業者が供給者と契約を直接締結することがあり、
その場合、代表事業者とその他事業者は、契約に対する持分に比例してその責任を負うことになる。
ジョイント・オペレーションに対する権利を有する当事者は、IFRS第11号に従ってリース資産、負債
及びリース費用をその持分に応じて認識する。
上記の「共同支配の取決めのために」という用語をどのように解釈し実務で適用すべきかに関して
は多くの議論がある。IFRS 解釈指針委員会(以下「委員会」)は 2018 年 9 月に、法人格を持たな
い共同支配の取決め(すなわちジョイント・オペレーション)における共同事業者のうちある事業者
(代表事業者)が、JOA の一環で共同で使用される有形固定資産に関するリース契約を、単独の署
名当事者として第三者である貸手と締結する事例について審議した。
さらに、この代表事業者は、ジョイント・オペレーションの契約上の取決めに従って、リース・コストの
うち他の共同支配事業者の持分に相当する金額を当該事業者から回収する権利を有している。質
問の提出者は、代表事業者のみが、貸手に支払いを行う一義的義務を有する場合に、リース契約
に係るリース負債の全額を認識すべきかを照会した。
IASB スタッフは、契約がリースを含むかどうかを評価するためだけに IASB は IFRS 第 16 号 B11
項を開発しており、同項はリース又は共同支配の取決めに関して求められる会計処理には影響を
与えないと述べた。この質問に関する暫定アジェンダ決定において委員会は、共同支配事業者は
IFRS第 11号 20項(b)に従って、(a) ジョイント・オペレーションに対する持分に関連して発生する
負債、及び(b)共同支配の取決めに対する他の当事者と共同で負担することになる負債の持分、
の両方を認識すべきことを指摘した。さらに、共同支配事業者が認識する負債には、一義的な責任
を負う負債も含まれるとされた。
その後、2019年 3月の IFRIC解釈指針委員会において当該論点が議論され、上記の考え方が再
確認された。また、ジョイント・オペレーションに関して、ジョイント・オペレーションの活動と当該事業
に対する共同支配事業者の持分を財務諸表利用者が理解するための十分な情報を開示すること
の重要さが強調された。すなわち、IFRS 第 12 号「他の企業への関与の開示」第 20 項(a)を適用
すれば、共同支配事業者は、ジョイント・オペレーションに対する持分の性質、範囲及び財務上の影
響(当該ジョイント・オペレーションに対する共同支配を有する他の投資家との契約上の関係の性質
及び影響を含む)を財務諸表利用者が把握できる情報の開示が求められることになる。
他方で委員会は、既存の基準が、代表事業者がジョイント・オペレーションに対する持分に係る負債
を識別し認識するための適切な基礎を提供しているという結論を出し、当該事項を基準設定アジェ
ンダに追加しないことを決定した。
代表事業者は委員会の結論を踏まえて、ヘッドリース・コスト(リース料が初期の段階でより多くなる
特性を有する)と、その他事業者への請求(サブリース又は共同持分に関する請求)により受け取る
収益の差額としての純損益の認識パターンを変更することが要求される可能性がある。
9 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
2.1.2 特定された資産
IFRS第 16号からの抜粋
B13 資産は、通常は契約に明記されることによって特定される。しかし、資産が顧客に利用可能
とされる時点で黙示的に定められることによって特定される場合もある。
B20 資産の稼働能力部分は、物理的に別個のもの(たとえば、建物のフロアー)である場合に
は、特定された資産である。資産の稼働能力又は他の部分のうち物理的に別個でないもの
(たとえば、光ファイバー・ケーブルの稼働能力部分)は、特定された資産ではない。ただし、
当該部分が資産の稼働能力のほとんどすべてを表しており、それにより資産の使用による
経済的便益のほとんどすべてを得る権利を顧客に与えている場合は除く。
契約は、特定された資産が存在する場合にのみリースを含むことになる。特定された資産が存在す
ることは、リースの定義における重要な要素である。特定された資産(identified asset)という概念
は、IFRIC 第 4 号「契約にリースが含まれているか否かの判断」における「特定の資産(specified
asset)」の概念と概ね整合している。IFRS 第 16 号では、特定された資産は契約において明示され
ている場合もあれば黙示的な場合もある。
設例 1 ―― 黙示的に特定された資産
顧客Xは供給者Yとの間で、5年間にわたり顧客X向けの特別仕様の鉄道車両を使用する契約を
締結する。当該鉄道車両は、顧客Xの製造工程で使用される材料を輸送するために設計されてお
り、他の顧客への使用には適していない。当該鉄道車両は、契約に明記されていないが、供給者
Yは顧客Xの使用に適した鉄道車両を1台しか所有していない。当該鉄道車両が適切に稼働しな
い場合、供給者Yは契約に基づいて、当該鉄道車両を修理又は交換しなければならない。供給者
Yは実質的な取替権を有しないと仮定する(セクション1.2.2.1「実質的な取替権」参照)。
分析:当該鉄道車両は、特定された資産である。当該鉄道車両は(シリアル番号などにより)契約
に明記されていないが、供給者Yは契約を履行するために、当該鉄道車両を使用しなければな
らず、当該鉄道車両は黙示的に特定されている。
設例 2 ―― 特定された資産 – 資産が顧客により使用可能となる時点で黙示
的に明示される場合
顧客Xは供給者Yとの間で、5年間にわたり車両を使用する契約を締結する。車両の仕様(ブラン
ド、車種、色、オプションなど)は契約に明記されている。契約開始時点において、当該車両は未
だ製造されていない。
分析:当該車両は特定された資産である。当該車両は契約開始時点において特定されていない
が、リースの開始日に特定されることが明らかである。当該車両は、顧客により使用可能となる
時点(例:開始日)で黙示的に特定される。
ある資産の稼働能力は、それが物理的に区分可能な場合には、特定された資産である(建物のフ
ロアー)。一方で、資産の稼働能力又は他の一部のうち物理的に区別できないもの(例:光ファイ
バー・ケーブルの稼働能力の一部)は特定された資産ではない。ただし、当該部分が資産全体の稼
働能力のほとんどすべてに相当し、それにより資産の使用から生じる経済的便益のほとんどすべて
を得る権利を顧客に与えている場合には、特定された資産である。
特定された資産は、より大きな資産
の物理的に区分可能な一部の場合
もある。
10 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
弊社のコメント
• 「ほとんどすべて」という用語は、IFRS 第 16 号において定義されていない。ただし、IAS 第
17号におけるリースの分類の際に使用されている用語と同様に捉えることが考えられる。
• 例えばある契約には、広域なネットワーク設備の一部を構成する特定目的の回線が含ま
れている場合がある(例:顧客の拠点までの「引込み回線」に関する通信要素と、2 拠点間
の専用回線に関する専用アクセスに分解される契約)。IFRS第 16号では、こうした契約が
特定された資産に該当するかどうかに関する明確な定めや設例は設けていない。ただし、
FASB の新基準では、特定目的の回線に類似する例が追加されている(ある顧客をより広
域のパイプラインに接続させるパイプラインの一部分)。この例では、広域のパイプライン
への接続部分は特定された資産に該当することが明確に示されている。IASB によれば、
IASB と FASB はリースの定義について同じ結論に至ったと述べている。したがって、単一
の顧客をより広域のネットワークに接続させるネットワークの引込み回線は、IFRS第 16号
において、特定された資産に該当する可能性がある。このような契約や類似する契約につ
いては、慎重な検討が必要になると考えられる。
設例 3 ―― 特定された資産 – より大きな資産の物理的に区分可能な一部
顧客Xは供給者Yとの間で、12年間にわたりニューヨークとロンドンを結ぶ光ファイバー・ケーブ
ルのうち3本を使用する権利に関する契約を締結する。当該契約により、顧客Xは、20本のファ
イバー・ケーブルのうち特定された3本を使用する。3本のファイバー・ケーブルには、契約期間
にわたり、顧客Xのデータのみが割り当てられる。供給者Yは実質的な取替権を有していないと
仮定する(セクション1.2.2.1「実質的な取替権」参照)。
分析: 3本のファイバー・ケーブルは、物理的に区分可能で、かつ契約で明記されているため、特
定された資産に該当する。
設例 4 ―― 特定された資産 – 資産の稼働能力の一部
シナリオ A
顧客Xは供給者Yとの間で、5年間にわたり、供給者Yのパイプラインを使用してA国からB国へ
石油を輸送する権利に関する契約を締結する。当該契約により、顧客Xは契約期間にわたりパ
イプラインの稼働能力の95%を使用する権利を有している。
分析:パイプラインの稼働能力の一部は特定された資産に該当する。パイプラインの稼働能力の
95%は、パイプラインの残りの稼働能力から物理的に区分可能ではないが、パイプライン全体の
稼働能力のほとんどすべてに相当し、パイプラインの使用から生じる経済的便益のほとんどす
べてを得る権利を顧客Xに与えている。
シナリオ B
事実関係はシナリオAと同じとする。ただし、顧客Xは契約期間にわたりパイプラインの稼働能力
の60%を使用する権利を有しているとする。
分析:パイプラインの稼働能力の60%は、その稼働能力のほとんどすべてとはいえないため、パ
イプラインの稼働能力の一部は特定された資産に該当しない。顧客Xは、パイプラインの使用か
ら生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利を有していない。
地役権や通行権は、特定の目的で他社の土地を利用、アクセス又は横切る権利を表す。たとえば、
地役権は既存の土地の区画又は水域の地上部分や地下部分を利用して配管その他の資産(例:
鉄道、電気・ガス・水道管又は電気通信線)を建設し運営する権利に向けて取得されるが、その一
方で、土地所有者は、地役権により移転される権利を妨げない限り、他の用途(たとえば農業)に土
地を継続的に使用することができる。地役権は期間の定めがなく永久になる場合もあれば、土地の
独占的又は非独占的使用の期間が定められ、地役権料を前払又は特定の期間にわたり支払われ
ることもある。
11 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
リースの定義は、契約は一定期間にわたるものでなければならないと定めており、永久的な地役権
は IFRS 第 16 号の適用範囲外になる。したがって、契約が永久的なものか、一定期間にわたるも
のかを判断するにあたって地役権に関する契約を慎重に検討する必要がある。以下のように契約
は永久的と思われても、実際には一定期間の契約であるということもある。
• 非常に長期の契約(例:FASBはその結論の根拠(BC113項)で土地の長期リース(例:999年
リース)には、ASC第842号が適用されると述べている)
• 借手が更新手数料を定期的に支払う限り「自動的に更新される」ため、解約不能リース期間を
有すると記載されている契約。これは実質的に任意の延長期間が付された固定期間の契約
である。
• ガス埋蔵量は最終的には枯渇することになり、使用期間を資産が使用される期間(例:回収
装置を通じて天然ガスが採取される期間)と定める契約は、永久ではなく、固定期間(すなわ
ち、生産が停止される時点で終了する)である。
地役権や通行権に関する契約がリースに該当するかどうかを判断するにあたって、特定された資産
が存在するか、顧客は特定資産の経済的便益のほとんどすべてを取得し、使用期間全体を通じて
資産の使用を指図する権利を有しているかどうかを検討する必要がある。
2.1.3 実質的な入替権
IFRS第 16号からの抜粋
B14 たとえ資産が特定されていても、供給者が使用期間全体を通じて資産を入れ替える実質的
な権利を有している場合には、顧客が特定された資産を使用する権利を有していない。資
産を入れ替える供給者の権利が実質的であるのは、下記の条件の両方が存在する場合の
みである。
(a) 供給者が使用期間全体を通じて代替資産に入れ替える実質上の能力を有している(たとえ
ば、顧客は供給者が資産を入れ替えることを妨げることができず、かつ、供給者が代替資
産を容易に利用可能であるか又は合理的な期間内に調達できる)。
(b) 供給者が資産を入れ替える権利の行使により経済的に便益を得ることとなる(すなわち、
資産の入替えに関連する経済的便益が、資産の入替えに関連するコストを上回ると見込
まれる)。
B15 供給者が、特定の日又は所定の事象の発生の後にしか代替資産に入れ替える権利又は
義務を有さない場合には、供給者の入替えの権利は実質的ではない。供給者は使用期間
全体を通じて代替資産を入れ替える実質上の能力を有していないからである。
B16 供給者の入替えの権利が実質的であるかどうかについての企業の評価は、契約開始時の
事実及び状況が基礎となり、契約時において、発生する可能性が高いとは考えられない将
来の事象の考慮は除外しなければならない。契約時において、発生する可能性が高いとは
考えられず、したがって評価から除外すべき将来の事象の例としては、次のものがある。
(a) 将来の顧客が資産の使用について市場よりも高いレートを支払うという合意
(b) 契約時にほとんど開発されていない新技術の導入
(c) 顧客による資産の使用又は資産の稼働と、契約時に可能性が高いと考えられた使用又は
稼働との間の著しい相違
(d) 使用期間中の資産の市場価格と、契約時に可能性が高いと考えられた市場価格との間の
著しい相違
B17 資産が顧客の敷地又は他の場所にある場合には、入替えに関連したコストは、一般的に、
供給者の敷地にある場合よりも高く、したがって、資産の入替えに関連した便益を上回る可
能性が高くなる。
B18 資産が適切に稼働しない場合又は技術的なアップグレードが利用可能になった場合に、供
給者が資産を修理及び維持管理のために入れ替える権利又は義務は、顧客が特定された
資産を使用する権利を有することを妨げるものではない。
B19 供給者が実質的な入替えの権利を有しているかどうかを顧客が容易に判定できない場合
には、顧客は、入替えの権利は実質的ではないと仮定しなければならない。
12 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
資産が特定されている場合であっても、供給者が使用期間(顧客との契約を履行するために資産が
使用される期間で継続していない期間を含む)にわたって資産を入れ替える実質的な権利を有して
いる場合には、顧客は特定された資産を使用する権利を有していないことになる。供給者の資産を
入れ替える権利は、以下の両方の条件が満たされる場合に実質的となる。
• 供給者は、使用期間にわたって代替資産に入れ替える実際の能力を有している(たとえば、
顧客は供給者による資産の入替えを禁止できず、かつ供給者は、代替資産を容易に利用可
能であるか、又は合理的な期間内に調達できる)。
• 供給者は、資産を入れ替える権利の行使により経済的便益を得る(資産の入替えに関連する
経済的便益は、資産の入替えに関連するコストを上回ることが見込まれる)
IASBは結論の根拠(BC第 113項)において、上記の条件により、顧客ではなく供給者が資産の使
用を支配することになる入替権と、契約の実態や特徴が変わることのない入替権を区別することを
意図したと述べている。
供給者が、特定の日又は所定の事象の発生の後にしか代替資産に入れ替える権利又は義務を有
さない場合には、供給者の入替えの権利は実質的ではない。これは供給者が、使用期間全体を通
じて代替資産を入れ替える実質的な権利を有していないためである。
供給者の入替権が実質的かどうかは、契約開始時における事実と状況に基づいて判断される。こ
の際には契約開始時点において、発生する可能性が高いとは考えられない将来の事象を考慮する
ことはできない。IFRS第 16号では、供給者の入替権が使用期間にわたり実質的かどうかを評価す
る際に、契約開始時点で発生する可能性が高いとは考えられないため、考慮してはならない状況の
例として以下を挙げている。
• 将来の顧客が資産の使用について市場よりも高いレートを支払うという合意
• 契約時にほとんど開発されていない新技術の導入
• 顧客による資産の使用又は資産の稼働と、契約時に可能性が高いと考えられた使用又は稼
働との間の著しい相違
• 使用期間中の資産の市場価格と、契約時に可能性が高いと考えられた市場価格との間の著
しい相違
入替権が実質的であるためには、当該権利により供給者が経済的便益を得ることが求められること
は新たな概念である。IASB は結論の根拠(BC 第 113 項)において、多くの場合、資産の入替えに
はコストが生じるため、供給者は入替権の行使により便益を得ないことが明らかであろうと述べてい
る。また、資産の物理的な所在地が、資産の入替えに伴うコストに影響を及ぼす可能性がある。た
とえば、顧客の敷地に設置されている資産の入替えに関連するコストは、通常は、供給者の敷地に
設置されている類似資産の入替えに関連するコストより高くなる。なお、供給者が入替えに関連する
コストは重要ではないと判断した場合であっても、それが直ちに供給者が入替権から経済的便益を
得ることにはならない。
さらに IFRS 第 16 号は、供給者が実質的な入替権を有しているかどうかを顧客が容易に判断でき
ない場合には、顧客は供給者の入替権を実質的なものではないと推定すべきことを明確にしている。
この規定は、入替権が実質的なものではないことを証明するために、顧客が過度な労力を費やすこ
とまで求められないことを明確化する意図がある。一方、供給者は、入替権が実質的であるかどう
かを判断するための十分な情報を有しているため、IASB は供給者に対しては同様の推定規定を定
めていないと EYは考えている。
原資産が適切に稼働しない場合(例:通常の保証条項)や、技術的な改良が利用可能になった場合
に供給者が代替資産に入れ替えることを容認又は要求するような契約条件は、実質的な入替権と
はみなされない。
同様に、特定の日又は一定事象の発生時以降に限り、供給者が代替資産に入替えを行う権利又
は義務を有している場合においても、供給者は使用期間にわたり代替資産に入れ替える実際の能
力を有していないため、実質的な入替権とはみなされない。
13 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
設例 5 ―― 入替権
シナリオ A
ある電子データ保存業者(以下、供給者)は、特定のサーバー(No. 9)を利用し、集中管理デー
タ・センターを通じて、データ保管サービスを提供している。供給者は、アクセス可能な単一のロ
ケーションに同種のサーバーを多数保有しており、契約開始時において、顧客の同意なく、使用
期間にわたりデータを別のサーバーに入れ替えることが認められており、データの入替えは容易
である。また、供給者は、データを別のサーバーに入れ替えることによって、わずかな費用でネッ
トワークのパフォーマンスを最適化することができるため、経済的便益を得ることになる。さらに、
供給者は当該入替権を契約における重要な権利として交渉しており、当該入替権が契約の価格
設定に影響を与えていることを明らかにしている。
分析:顧客は特定された資産を使用する権利を有していない。なぜなら、契約開始時において、
供給者はサーバーを入れ替える実際の能力を有しており、かつその入替えにより経済的便益を
得ると考えられるためである。ただし、顧客は、供給者が実質的な入替権を有しているかどうか
容易に判断できない場合(例:供給者の管理状況が不明確な場合)には、入替権は実質的でな
いと推定し、特定された資産があると判断する。
シナリオ B
事実関係はシナリオAと同じとする。ただし、No. 9のサーバーはカスタマイズされており、供給者
は使用期間にわたり当該サーバーを他のサーバーに入れ替える実際の能力を有していない。さら
に、供給者が類似したサーバーを調達することにより経済的便益を得るかどうかは不明である。
分析:供給者は資産を入れ替える実際の能力を有しておらず、かつ資産の入れ替えにより供給
者が経済的便益を得る証拠は存在しないため、当該入替権は実質的ではない。したがって、
サーバーNo. 9は特定された資産に該当すると考えられる。このシナリオでは、実質的な入替権
の条件が両方とも満たされていない。供給者が実質的な入替権を有しているためには、両方の
条件を満たす必要があることに留意されたい。
14 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
2.1.4 特定された資産の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利
IFRS第 16号からの抜粋
B21 特定された資産の使用を支配するためには、顧客は使用期間全体にわたり資産の使用か
らの経済的便益のほとんどすべてを得る権利を有している(たとえば、期間全体にわたり資
産の独占的使用を有していることによって)ことが必要となる。顧客は、資産の使用からの
経済的便益を多くの方法(資産の使用、保有又はサブリースなどによる)で直接又は間接に
得ることができる。資産の使用から得られる経済的便益には、主要なアウトプット及び副産
物(これらの項目から生じる潜在的なキャッシュ・フローを含む)や、資産の使用から得られ
る他の経済的便益のうち第三者との商取引から実現することのできるものが含まれる。
B22 資産の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利を評価する際に、企業は、
資産の使用から生じる経済的便益を、顧客が資産を使用する権利の定められた範囲の中
で考慮しなければならない(B30項参照)。たとえば、
(a) 契約が自動車の使用を使用期間中に特定の地域のみに限定している場合は、企業は当該
地域内での自動車の使用から生じる経済的便益のみを考慮しなければならず、それ以上
は考慮してはならない。
(b) 契約が顧客は自動車を使用期間中に特定のマイル数までしか運転できないと定めている
場合には、企業は認められたマイル数の自動車の使用から生じる経済的便益のみを考慮
しなければならず、それ以上は考慮してはならない。
B23. 契約で、顧客が資産の使用から得られたキャッシュ・フローの一部分を対価として供給者又
は他の当事者に支払うことが要求されている場合には、対価として支払われるキャッシュ・
フローは、顧客が資産の使用から得る経済的便益の一部とみなさなければならない。たと
えば、顧客が小売スペースの使用から生じる売上高の一定割合を当該使用の対価として
供給者に支払うことを要求されている場合、その要求は顧客が小売スペースの使用からの
経済的便益のほとんどすべてを得る権利を有することを妨げるものではない。これは、当該
売上高から生じるキャッシュ・フローは、顧客が小売スペースの使用から得る経済的便益と
みなされ、その一部分を供給者に当該スペースを使用する権利の対価として支払うもので
あるからである。
特定された資産の使用を支配する権利を有するためには、顧客は、使用期間にわたり(例:当該使
用期間を通じて資産を独占的に使用することで)特定された資産の使用から生じる経済的便益のほ
とんどすべてを得る権利を有していなければならない。「ほとんどすべて」という用語は、IFRS 第 16
号では定義されていない。ただし、リースの分類に関する IAS 第 17号と同様の用語として捉えるこ
とができると考えられる。
顧客は、資産を使用、保有又はサブリースなどすることにより、直接的又は間接的に経済的便益を
得ることができる。経済的便益には、資産の主要なアウトプット(例:財又はサービス)及び副産物
(例:資産の使用により生じた再生可能エネルギー枠)、及びこれらの項目から生じる可能性のある
キャッシュ・フローが含まれる。さらに経済的便益には、資産の使用により第三者との商取引(例:資
産のサブリース)から実現する可能性のある便益も含まれる。しかし、特定された資産の建設又は
所有から生じる経済的便益(例:税務上の加速償却及び投資税額控除による税務上の便益)は、資
産の使用から生じる経済的便益ではないと考えられる。したがって、顧客が経済的便益のほとんど
すべてを得る権利を有しているかどうかを評価する際には、このような経済的便益は考慮されない。
顧客が資産の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利を有しているかどうかを評
価する際、契約により定められた顧客としての使用権の範囲内における資産の使用から生じる経済
的便益を考慮することになる。単に供給者の原資産に対する利益を保護するためだけの権利(例:
顧客が供給者の車両を運転できる走行距離に課せられた制限)は、それ自体のみでは、顧客が資
産の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得ることを妨げるものではないため、このような
権利は、顧客が経済的便益のほとんどすべてを得る権利を有しているかどうかを評価する際に考
慮しない。
顧客が契約に基づき、資産の使用から生じるキャッシュ・フローの一部(例:小売店舗の使用から生
じた売上高の一定割合)を供給者又は他の当事者に対価として支払う必要がある場合には、当該
キャッシュ・フローは資産の使用から生じた顧客の経済的便益と考える。
リースは、特定された資産の使用を
支配する権利を一定期間にわたり
対価と交換に移転する
15 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号からの抜粋
B24 顧客は、下記のいずれかの場合にのみ、使用期間全体にわたり特定された資産の使用を
指図する権利を有する。
(a) 顧客が使用期間全体にわたり資産の使用方法及び使用目的を指図する権利を有している
場合(B25項から B30項に記述)
(b) 資産の使用方法及び使用目的についての関連性のある決定が事前に決定されており、か
つ、下記のいずれかである場合
(i) 顧客が使用期間全体を通じて資産を稼働させる権利(又は自らの決定する方法で他
者に資産を稼働させるよう指図する権利)を有していて、供給者にはそれらの稼働指
示を変更する権利がない。
(ii) 顧客が、使用期間全体にわたる資産の使用方法及び使用目的を事前に決定するよう
に、資産(又は資産の特定の側面)を設計した。
IFRS 第 16 号では IFRIC 第 4 号と異なり、顧客が特定された資産の使用を指図する権利を有して
いることが求められる。IFRIC 第 4 号では、IFRS 第 16 号で求められている顧客が特定された資産
の使用を指図する権利を有していない場合であっても、たとえば、顧客が原資産から生じるアウト
プットのほとんどすべてを得ており、アウトプット単位当たりの価格要件を満たしていれば、当該契約
は支配の要件を満たす可能性があった。一方、IFRS 第 16 号では、このような契約はリースに該当
しない。
次のいずれかに該当する場合には、顧客が使用期間にわたり特定された資産の使用を指図する権
利を有していることになる。
• 顧客は使用期間にわたり資産の使用方法及び使用目的を指図する権利を有している。
• 資産の使用方法及び使用目的に関連する事項が事前に決定されており、かつ次のいずれか
に該当する。
(1) 顧客が使用期間にわたり資産を稼働させる(又は顧客が決定する方法で他社に資産を
稼働させるように指図する)権利を有しており、供給者には当該稼働の指示を変更する
権利がない。
(2) 顧客が使用期間にわたる資産の使用方法及び使用目的を事前に決定するように資産
(又は資産の特定の側面)を設計した。
2.1.5.1 使用期間にわたり資産の使用方法及び使用目的を指図する権利
IFRS第 16号からの抜粋
B25 顧客は、契約に定められた使用権の範囲内で、使用期間全体にわたり資産の使用方法及
び使用目的を変更できる場合には、資産の使用方法及び使用目的を指図する権利を有し
ている。この評価を行う際に、企業は使用期間全体にわたる資産の使用方法及び使用目
的の変更に最も関連性のある意思決定権を考慮する。意思決定権は、使用から得られる
経済的便益に影響を与える場合には、関連性がある。最も関連性のある意思決定権は、資
産の性質及び契約の条件に応じて、契約によって異なる可能性が高い。
B26 状況に応じて、定められた顧客の使用権の範囲内で資産の使用方法及び使用目的を変更
する権利を与える意思決定権の例として、下記のものがある。
(a) 当該資産によって産出されるアウトプットの種類を変更する権利(たとえば、船積用コンテナ
を物品の輸送に使用するのか保管に使用するのかを決定する権利や、小売スペースで販
売する製品の構成を決定する権利)
(b) アウトプットが産出される時期を変更する権利(たとえば、機械や発電所をいつ使用するの
かを決定する権利)
(c) アウトプットが産出される場所を変更する権利(たとえば、トラック又は船の目的地を決定す
る権利や、設備をどこで使用するのかを決定する権利)
(d) アウトプットを産出するかどうか及び当該アウトプットの数量を変更する権利(たとえば、発
電所からエネルギーを産出するかどうかや、当該発電所からどれだけのエネルギーを産出
するのかを決定する権利)
契約に重要なサービス要素が含ま
れている場合には、顧客が特定さ
れた資産の使用を指図する権利を
有しているかどうかの判断が、より
複雑になる可能性がある。
16 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号からの抜粋
B27 資産の使用方法及び使用目的を変更する権利を与えない意思決定権の例として、資産の
稼働又は維持管理に限定されている権利がある。このような権利を保有しているのが顧客
である場合も供給者である場合もある。資産を稼働させるか又は維持管理するような権利
は、資産の効率的使用に不可欠であることが多いが、資産の使用方法及び使用目的を指
図する権利ではなく、資産の使用方法及び使用目的に関する決定に左右されることが多
い。しかし、資産を稼働させる権利は、資産の使用方法及び使用目的について関連性のあ
る決定が事前に決定されている場合には、資産の使用を指図する権利を顧客に与える場
合がある(B24項(b)(i)参照)。
顧客が使用期間全体を通じて、資産の使用方法及び使用目的を指図する権利を有している場合に
は、顧客は常に特定された資産の使用を指図する権利を有している(顧客は使用期間全体を通じて
使用方法及び使用目的を変更することができる)。資産の使用方法及び使用目的は、単一の概念
である(資産の「使用方法」と資産の「使用目的」を別個に評価しない)。
顧客が使用期間全体を通じて資産の使用方法及び使用目的を変更する権利を有しているかどうか
を評価する際には、顧客が、資産の使用から見込まれる経済的便益に最も影響を及ぼす意思決定
権を有しているかどうかに着目することになる。最も重要となる意思決定権は、資産の性質及び契
約条件に応じて異なる可能性が高い。
IASB は、結論の根拠(BC 第 120 項)において、資産の使用方法及び使用目的に関する決定は、
企業の取締役会による決定と同様とみなせると述べている。企業の営業活動及び財務活動に関す
る取締役会の決定は、当該決定に基づく個人の行動よりも、通常は最も重要な決定である。
IFRS 第 16 号は、資産の使用方法及び使用目的を変更する権利をもたらす意思決定権の例として、
以下を挙げている。
• 資産によって産出されるアウトプットの種類を変更する権利(例:船積用コンテナを物品の輸
送に使用するのか保管に使用するのかを決定する権利、小売スペースで販売する製品の構
成を決定する権利)
• アウトプットが産出される時期を変更する権利(例:機械や発電所をいつ使用するのかを決定
する権利)
• アウトプットが産出される場所を変更する権利(例:トラックや船の目的地を決定する権利、設
備の使用場所や設置場所を決定する権利)
• アウトプットを産出するかどうか、及び当該アウトプットの数量を変更する権利(例:発電所か
らエネルギーを産出するかどうかや、当該発電所からどれだけのエネルギーを産出するのか
を決定する権利)
一方、IFRS第 16号では、資産の使用方法及び使用目的を変更する権利に該当しない意思決定権
の例として、以下を挙げている。
• 資産の維持管理に関する意思決定権
• 資産の稼働に関する意思決定権
資産の維持管理及び稼働に関する決定は、当該資産を効率的に使用するためには不可欠である
ことが多いが、これらを決定する権利は、それ自体のみでは、使用期間全体を通じて資産の使用方
法及び使用目的を変更する権利にはならない。
顧客が資産の使用を指図する権利を有するために、原資産を稼働させる権利を有している必要は
ない。たとえば、顧客の指図により、供給者の従業員が資産を稼働させる場合も考えられる。ただし、
下記で説明しているように、資産の使用方法及び使用目的に関連する事項が事前に決定されてい
る場合には、資産を稼働させる権利は、資産の使用を指図する権利を顧客に与える可能性がある。
17 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
弊社のコメント
契約がリースに該当するか、又はリースを含むかの評価は、多くの契約では、単純であると EY
は考えている。ただし、一部の契約では、リースの定義を適用する際に、判断が求められる場合
がある。たとえば、重要なサービス要素を含む契約では、当該契約により特定された資産の使
用を指図する権利が移転されるかどうかを判断することは、困難な可能性があると我々は考え
ている。
2.1.5.2 資産の使用方法及び使用目的に関連する事項が事前決定されている
契約には、顧客が特定された資産の使用を指図する権利を有しているかどうかが不明瞭な場合が
ある。これは、資産の使用方法及び使用目的に最も関連性のある決定が、資産の使用に関する契
約上の制約により事前に定められている場合(例:資産の使用に関する決定が契約交渉時に顧客
と供給者により合意されており、当該決定を変更することができない場合)に生じることが考えられ
る。また、資産の使用方法及び使用目的に最も関連性のある決定が、実質的に資産の設計によっ
て事前に決められている場合にも生じる可能性がある。
IASB は、結論の根拠(BC 第 121 項)において、資産の使用方法及び使用目的が事前に決定され
るケースは、比較的少ないと予想していると述べている。このようなケースでは、次のいずれかに該
当する場合、顧客は使用期間にわたり特定された資産の使用を指図する権利を有することになる。
• 顧客が使用期間全体を通じて資産を稼働させる又は自らの決定する方法で、他者に資産を
稼働させるよう指図する権利を有しており、供給者はそれらの稼働指示を変更する権利がな
い。
• 顧客が使用期間全体にわたる資産の使用方法及び使用目的を事前に決定する方法で、資産
(又は資産の特定の側面)を設計した。
顧客が、使用期間全体にわたる資産の使用方法及び使用目的を事前に決定する方法で資産(又
は資産の特定の側面)を設計しかたどうかを評価するには、重要な判断が求められる可能性がある。
顧客が、使用期間全体にわたる資産の使用方法及び使用目的を事前に決定する方法で資産を設
計したかどうかの評価に関する例については、IFRS第 16号の設例 9を参照されたい。
2.1.5.3 使用期間より前における資産のアウトプットの指定
IFRS第 16号からの抜粋
B28 資産の使用方法及び使用目的についての関連性のある決定は、いくつかの方法で事前に
決定される場合がある。たとえば、関連性のある決定が、資産の設計によって又は資産の
使用に関しての契約上の制限によって事前に決定される場合がある。
B29 顧客が資産の使用を指図する権利を有しているかどうかを評価する際に、企業は、使用期
間中に資産の使用に関する決定を行う権利のみを考慮しなければならない。ただし、顧客
が B24 項(b)(ii)で記述したように資産(又は資産の特定の側面)を設計した場合は除く。
したがって、B24 項(b)(ii)の条件が存在する場合を除き、企業は使用期間前に事前決定
される決定を考慮しない。たとえば、顧客が使用期間前にアウトプットを指定できるだけであ
る場合には、顧客は当該資産の使用を指図する権利を有していない。使用期間前に契約
においてアウトプットを指定できる能力は、資産の使用に関する他の意思決定権がない場
合には、財又はサービスを購入する顧客と同じ権利を顧客に与えるだけである。
顧客が使用期間の開始日より前に、資産から生じるアウトプットを指定することだけはできるが、当
該アウトプットを使用期間にわたって変更できない場合には、顧客は当該資産の使用を指図する権
利を有していない。ただし、顧客が IFRS 第 16 号 B24 項(b)(ii)で定められている、資産又は資産
の特定の側面を設計した場合にはこの限りではない。顧客が資産又は資産の特定の側面を設計し
ていない場合に、顧客が資産の使用に関する他の関連性のある意思決定権(例:アウトプットを産
出するかどうか、アウトプットの産出時期、及び何を産出するかを変更する能力)を有していないの
であれば、契約においてアウトプットを指定できる顧客の能力は、リースを含まない契約において財
又はサービスを購入する顧客と同じ権利を顧客に与えているにすぎない。
18 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
2.1.5.4 防御的な権利
IFRS第 16号からの抜粋
B30 契約に、資産又は他の資産に対する供給者の利益を保護したり、供給者の職員を保護した
り、供給者の法律又は規則への準拠を確保したりするために設計された条件が記載される
場合がある。これらは防御的な権利の例である。たとえば、契約が、(i) 資産の使用の最
大量を指定するか又は顧客が資産を使用できる場所若しくは時期を限定したり、(ii) 顧客
に特定の運用上の慣行に従うことを要求したり、(iii) 顧客に資産の使用方法の変更を供
給者に伝えることを要求したりする場合がある。防御的な権利は、通常、顧客の使用権の
範囲を定めるものであるが、単独では、顧客が資産の使用を指図する権利を妨げるもので
はない。
供給者の防御的な権利は、それ単独では顧客が特定された資産の使用を指図する権利を妨げるも
のではない。防御的な権利は、通常、資産の使用を指図する顧客の権利を排除することなく、顧客
の使用権の範囲を定めるものである。防御的な権利は、供給者の利益(資産に対する利益、供給
者の従業員、法規制の遵守)を保護することが意図されており、たとえば、資産の最大使用量や資
産の使用場所に関する制限、特定の稼働方法に従う義務などが挙げられる。
設例 6 ―― 資産の使用を指図する権利
顧客Xは供給者Yとの間で、3年間にわたり車両を使用する契約を締結する。当該車両は契約で
特定されている。供給者Yは、特定された車両が稼働しない場合(例:故障)を除き、当該車両を
別の車両に入れ替えることはできない。
契約に関するその他の事項
• 顧客Xは、車両を稼働する(自身で運転する)か、又は当該車両の稼働を他者に指図する
(例:運転手を雇う)。
• 顧客Xは、(下記で説明する契約の制限の範囲内で)車両の使用方法を決定する。たとえ
ば、顧客Xは使用期間全体にわたり、車両をいつ、どこで、どのように、何の目的で使用す
るのかを決定し、また当該決定を使用期間全体にわたり変更することができる。
• 供給者Yは、資産に対する自身の利益を保護するために、車両の特定の使用方法(例:車
両を海外に移すこと)や車両の改造を禁止している。
分析: 顧客Xは、使用期間全体にわたり特定された車両の使用を指図する権利を有している。
顧客Xは、車両をいつ、どこで、どのように、何の目的で使用するのかを変更できる権利を有して
いるため、当該車両の使用を指図する権利を有している。
車両の特定の使用方法及び車両の改造を禁止する供給者Yによる制限は、顧客Xが資産を使
用できる範囲を定める防御的な権利であると考えられるが、顧客Xが資産の使用を指図するか
どうかの評価に影響を及ぼすものではない。
19 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
2.1.6 フローチャート
下記のフローチャートは、契約がリースであるか、又はリースを含んでいるかどうかを決定する際の
意思決定プロセスを示しており、IFRS第 16号の適用指針で記述されているものである。
2.1.7 契約の再評価
IFRS第 16号からの抜粋
11 企業は、契約の条件が変更された場合にのみ、契約がリース又はリースを含んだものであ
るのかどうかを再判定しなければならない。
IFRS 第 16 号では、契約条件が変更された場合にのみ、契約がリースであるか又はリースを含ん
でいるかどうかの再評価を行う。契約条件の変更には、契約に定められているオプション(例:更新
オプション)の行使又は失効は含まれない。
借手及び貸手の再評価と再測定に関する概要については、付録 Dを参照されたい。
Yes
No
Yes
顧客 使用期間全体を通じて資産の使用方法及び
使用目的を指図する権利は、顧客、又は供給者の
いずれが有しているか? B25項から B30項を
検討する。(セクション1.2.3.2「特定された資産の
使用を指図する権利」参照)
供給者
契約はリースを 含んでいる
契約はリースを 含んでいない
顧客は使用期間全体を通じて資産の使用から
生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利を
有しているか?B21項から B23項を検討する。
(セクション 1.2.3.1「特定された資産の使用から生じる
経済的便益のほとんどすべてを得る権利」参照))
No
Yes
No
いずれも有していない:資産の使用方法
及び使用目的が事前に決定されている
(セクション 1.2.3.2「特定された資産の
使用を指図する権利」参照)
顧客は、供給者により稼働指示を変更されることなく、
使用期間全体を通じて資産を稼働させる権利を
有しているか?(セクション 1.2.3.2「特定された
資産の使用を指図する権利」参照)
開始
資産は特定されているか? B13項から B20項を検討する。
(セクション 1.2.2「特定された資産」参照)
No
Yes
顧客は、使用期間全体にわたる資産の使用方法
及び使用目的を事前に決定する方法で資産
(又は資産の特定の側面)を設計したか?
(セクション 1.2.3.2「特定された資産の使用を
指図する権利」参照)
契約条件が変更された場合には、
契約にリースが含まれているかどう
かの再評価を行う。
20 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
2.2 契約におけるリース構成部分と非リース構成部分の識別及び区分、
ならびに契約対価の配分
2.2.1 契約におけるリース構成部分の識別及び区分
IFRS第 16号からの抜粋
12 リース又はリースを含んだものである契約について、企業は、契約の中のリース構成部分
のそれぞれを契約の非リース構成部分と区分して会計処理しなければならない。ただし、企
業が第 15 項の実務上の便法を適用する場合は除く。B32 項から B33 項は、契約の構成
部分の分離に関してのガイダンスを示している。
B32 原資産を使用する権利は、下記の両方に該当する場合には、独立したリース構成部分である。
(a) 借手が、原資産の使用から、それ単独で又は借手が容易に利用可能な他の資源と組み合
わせることで便益を得ることができる。容易に利用可能な資源とは、別個に(貸手又は他の
供給者によって)販売又はリースされている財又はサービス、あるいは借手がすでに(貸手
から又は他の取引若しくは事象により)入手している資源である。
(b) 原資産が、契約の中の他の原資産への依存性が高くなく、相互関連性も高くない。たとえ
ば、借手が原資産をリースしないことを契約の中の他の原資産を使用する権利に著しく影
響を与えずに決定できるという事実は、当該原資産が当該他の原資産への依存性が高くな
く相互関連性も高くないことを示唆するかもしれない。
B33 契約に、借手に財又はサービスを移転しない活動及びコストについて借手が支払う金額が
含まれている場合がある。たとえば、貸手が支払額の合計に管理業務に係る料金やリース
に関連して生じた他のコストで、借手に財又はサービスを移転しないものを含める場合があ
る。このような支払額は、契約の独立した構成部分を生じさせないが、契約の中の個々に
識別された構成部分に配分される合計対価の一部とみなされる。
16 第 15項の実務上の便法が適用される場合を除き、借手は非リース構成部分を他の適用さ
れる基準を適用して会計処理しなければならない。
B55 リースが土地と建物の両方の要素を含んでいる場合には、貸手はそれぞれの要素の分類
がファイナンス・リースなのかオペレーティング・リースなのかを第 62 項から第 66 項及び
B53 項から B54 項を適用して個々に評価する。土地要素がオペレーティング・リースなの
かファイナンス・リースなのかを判定する際に重要な考慮事項の 1 つは、土地の経済的耐
用年数が通常は確定できないことである。
B56 土地と建物のリースの分類及び会計処理のために必要となる場合には常に、貸手は、リー
ス料(一括前払を含む)を、契約日におけるリースの土地要素と建物要素の賃借権の公正
価値の比率により、土地要素と建物要素に配分する。リース料をこれらの 2 つの要素に信
頼性をもって配分できない場合には、リース全体をファイナンス・リースに分類する。ただ
し、両方の要素がオペレーティング・リースであることが明らかである場合はこの限りではな
く、その場合には、リース全体をオペレーティング・リースに分類する。
B57 土地と建物のリースで、土地要素に係る金額が当該リースに対して重要性がないものにつ
いて、貸手は、当該土地と建物を、リース分類の目的上、単一の単位として扱い、第 62 項
から第 66 項及び B53 項から B54 項に従ってファイナンス・リース又はオペレーティング・
リースに分類することができる。こうした場合、貸手は、建物の経済的耐用年数を原資産全
体の経済的耐用年数とみなさなければならない。
21 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
ある契約が複数の資産(例:建物及び設備、複数の設備)を使用する権利を含んでいる場合、以下
の両方の要件を満たすのであれば、各資産を使用する権利は別個のリース構成部分として識別さ
れる。
• 借手が、当該資産を単独で、又は借手が容易に利用可能な他の資源との組合せにより、当
該資産の使用から生じる便益を得ることができる(容易に利用可能な他の資源とは、貸手又
は他の供給者が個別に販売もしくはリースしている財又はサービス、あるいは借手が貸手や
他の取引又は事象を通じて既に入手している財又はサービスをいう)。
• 原資産が、当該契約における他の原資産に大きく依存しておらず、高い関連性も有していない。
上記の要件のどちらか一方が満たされない場合には、複数の資産を使用する権利は単一のリース
構成部分とみなされる。
設例 7 ―― リース構成部分の識別及び区別
シナリオ A
借手は、掘削目的で使用する掘削機と関連する付属品(例:掘削機用部品)のリースに関する契
約を締結する。借手は地元の採掘企業であり、掘削機を銅鉱山で使用する予定である。
分析:借手の観点からは、契約に含まれるリース構成部分は1つである。借手は、付属品を利用
せずに、掘削機の使用から生じる便益を得ることができないため、掘削機の使用は付属品の利
用に依存していると考えられる。
シナリオ B
事実関係はシナリオAと同じとする。ただし、契約には運搬トラックを使用する権利も含まれてい
る。借手は運搬トラックを他の用途(例:他の鉱山の鉄鋼石の輸送)に使用することができる。
分析: 借手の観点からは、契約には、付属品と一体になる掘削機のリースと、運搬トラックの
リースという2つのリース構成部分が含まれる。運搬トラックは、掘削機とは関係なく他の用途で
使用することができるため、借手は、運搬トラックを単独で、又は容易に利用可能な他の資源と
組み合わせることにより便益を得ることができる。また借手は、掘削機を単独で、又は容易に利
用可能な他の資源と組み合わせて利用することにより便益を得ることもできる。
IFRS 第 16 号では、土地と土地の改良部分(例:建物)を使用する権利が含まれる契約の場合、貸
手に対して土地を使用する権利を別個のリース構成部分として分類し(セクション 5.1「リースの分
類」参照)、会計処理することを求めている。ただし、別個のリース構成部分として会計処理すること
による影響がリースにとって重要でない場合にはこの限りではない。たとえば、土地のリース構成部
分として認識される金額に重要性がない場合、土地を区別して会計処理する必要がないことが考え
られる。なお、リース料を土地と建物に信頼性をもって配分できない場合には、リース全体をファイ
ナンス・リースに分類する。ただし、両方の構成部分がオペレーティング・リースであることが明らか
である場合には、リース全体をオペレーティング・リースに分類する。
弊社のコメント
建物全体(建物のすべて)をリースしている場合には、実質的には建物が建つ土地もリースして
いることになるため、土地と建物を別個のリース構成部分として会計処理する可能性がある。一
方で、建物の一部(例:高層ビルの 1 フロア)のみリースしている場合には、必ずしも土地と建物
を別個に会計処理する必要はないと考えられる。
22 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
2.2.2 契約におけるリース構成部分と非リース構成部分の識別及び区別
リース契約には、リースに加えて、リース以外の財又はサービスを購入又は売却する合意(非リー
ス構成部分)が含まれる契約が多く存在する。非リース構成部分は他の基準に従って、リース構成
部分と区別して識別し、会計処理される(ただし、借手がセクション 2.2.2.2「実務上の簡便法-借
手」で解説している実務上の簡便法を適用する場合を除く)。たとえば、借手(顧客)は、非リース構
成部分を未履行契約として会計処理し、貸手(供給者)は、IFRS第 15号の適用対象となる契約とし
て会計処理することが考えられる。
契約には、貸手から借手に移転する財又はサービスに関連しない項目(例:貸手が借手に請求する
手数料やその他の管理費)が含まれる場合がある。このような項目は、別個のリース構成部分や非
リース構成部分に該当しないため、借手及び貸手は、契約対価を当該項目に配分することはない
(借手による契約対価の配分についてはセクション 2.2.3.2「契約対価の配分-借手」、貸手による
契約対価の配分についてはセクション 2.2.4.2「契約対価の配分-貸手」を参照)。
ただし、貸手がサービス(例:メンテナンスや電気・ガス・水道の供給)を提供したり、原資産を稼働す
る(例:傭船や航空機のウェットリース(機材、乗務員、メンテナンスなどを包括したリース))場合、当
該契約は、通常、非リース構成部分を含んでいると考えられる。
弊社のコメント
借手は、契約における非リース構成部分を識別することにより、実務を変更することが必要にな
る可能性がある。IAS 第 17 号では、リース構成部分と非リース構成部分の会計処理(たとえ
ば、オペレーティング・リースとサービス契約の会計処理)は、多くの場合には同じであることか
ら、これらを識別することについてあまり重視されていなかった可能性がある。しかし、IFRS 第
16 号では、ほとんどのリースが貸借対照表に認識されることから、借手は契約におけるリース
構成部分と非リース構成部分を識別するために適切なプロセスを整備することが必要になる場
合がある。
2.2.2.1 借手による補填
IFRS第 16号では、共用部分のメンテナンス(例:建物の共有部分の清掃、従業員及び顧客のため
の駐車場の除雪)、及びテナントに提供されるその他の財又はサービス(例:電気・ガス・水道の供
給、ゴミの撤去)などのメンテナンス活動に対する支払いは、借手がサービスの提供を受けているた
め非リース構成部分に該当すると考えられる。
一部のリースでは、リースの対象となる資産に関連しているが、借手に移転しない財又はサービスに
係る活動及びコストに関して、借手が貸手に対して補填(又は貸手に代わり一定の支払い)する場合
がある(例:建物がリースされているかどうかや、借手が誰であるかに関係なく、貸手が負担する固定
資産税の支払い。資産に対する貸手の投資額を保障する保険料の支払いで、保険請求時において
地主が保険金を受領するもの)。IFRS第 16号では、このような支払いは財又はサービスに対する支
払いではないため、契約における別個の構成部分には該当しない。したがって、当該支払いを、対価
合計の一部として、契約において別個に識別された構成部分(リース構成部分及び非リース構成部分)
に配分する。また、このような支払いが固定(又は実質的に固定された)リース料もしくは変動リース
料のいずれに該当するのかを評価する必要がある(セクション 3.5「リース料」参照)。
23 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
設例 8 ―― リース契約の構成部分に該当しない活動
シナリオA
借手は、3年間にわたり、年間固定料金が12,000千円である設備のリース契約を締結する。契
約における年間固定リース料の内訳は、以下のとおりである。
賃料9,000千円、メンテナンス料2,500千円、及び管理費500千円
分析: 契約には、リース構成部分(設備のリース)と、非リース構成部分(メンテナンス)の2つの
構成部分が含まれている。一方、管理費は、借手に移転される財又はサービスに対する支払い
ではない。したがって、契約の対価合計である36,000千円をリース構成部分(設備のリース)と
非リース構成部分(メンテナンス)に配分する。
シナリオ B
事実関係はシナリオAと同じである。ただし、契約では、追加で借手に対して設備の原状回復費
用の負担を求めることが明記されている。
分析: 契約には、リース構成部分(設備のリース)と非リース構成部分(メンテナンス)の2つの
構成部分が含まれている。原状回復費用は、管理費と同様に、リース契約期間の終了時点で実
施されることから、借手に財又はサービスを移転するものではない。したがって、契約の対価合
計を、リース構成部分(設備のリース)と非リース構成部分(メンテナンス)に配分する。
なお、使用権資産の当初測定に含まれる原状回復費用の取扱いについては、下記4.2.1を参照
されたい。
2.2.2.2 実務上の簡便法 — 借手
IFRS第 16号からの抜粋
15 実務上の便法として、借手は、原資産のクラスごとに、非リース構成部分をリース構成部分
と区別せずに、各リース構成部分及び関連する非リース構成部分を単一のリース構成部分
として会計処理することを選択することができる。借手は、この実務上の便法を IFRS 第 9
号「金融商品」の 4.3.3項の要件を満たす組込デリバティブに適用してはならない。
IFRS第16号では、実務上の簡便法として、借手は原資産の種類ごとに会計方針の選択により、契
約における別個のリース構成部分と非リース構成部分を、単一のリース構成部分として会計処理す
ることを認めている。この簡便法は、対価を別個のリース構成部分と非リース構成部分に配分する
ために生じるコスト及び管理上の負担が、使用権資産及びリース負債をより正確に表示するという
便益を上回る可能性があるとの懸念に対処するために設けられたものである。IASB は、契約にお
ける非リース構成部分がリース構成部分と比べて重要性がない場合に、この簡便法が使用される
ことを想定している。ただし、借手は、当該簡便法を使用する場合でも、契約における複数のリース
構成部分(セクション 2.2.1「契約におけるリース構成部分の識別及び区別」参照)を単一のリース
構成部分として会計処理することはできない。使用権資産及びリース負債の測定に関する解説は、
セクション 4「借手の会計処理」を参照されたい。
明確には示されていないが、非リース構成部分は、リース契約に含まれるサービスに関係すると考
えられる。IFRS第 16号の結論の根拠の BC133項及び BC135項は、サービス構成部分である非
リース構成部分に言及している。したがって、リースが棚卸資産の購入、あるいは有形固定資産や
無形資産など他の資産の購入に係る構成部分を含む場合には、当該リースに係る原資産の種類
に実務上の便法を適用するとしても、棚卸資産の購入等に係る構成部分は、他のリース及び非リー
ス構成部分から区別しなければならないと考えられる。たとえば、契約に、リース構成部分のみなら
ず、サービス及び棚卸資産の建設に使用される板金の購入に係る非リース構成部分も含まれる場
合、物理的な財の購入は、「リース構成部分に関連する非リース構成部分」にはならないので、板金
の購入は、リース構成部分と合わせて会計処理するのではなく、棚卸資産の構成部分として会計処
理すべきであると考えられる。
なお、借手は、会計方針として、契約における別個のリース構成部分と非リース構成部分を、単一
のリース構成部分として会計処理することを選択した場合、契約対価全額をリース構成部分に配分
する。この結果、リース負債及び使用権資産の当初測定及び事後測定の金額は、当該会計方針を
選択しなかった場合と比較して大きくなる。
借手は、会計方針の選択により、非
リース構成部分をリース構成部分
から区分せずに会計処理すること
ができる。
24 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
2.2.3 契約対価の算定及び配分 – 借手
2.2.3.1 契約対価の算定
IFRS第 16号は、リース契約における「対価(consideration)」を定義しておらず、IFRS用語集にお
いても「対価」は定義されていない。しかし、リース契約における借手にとっての対価とは、固定支払
い(例:月次のサービス費用)又は実質的に固定された支払い、指数又はレートに応じて決まる変動
リース料(開始日の指数又はレートを用いて当初測定される)などのセクション 3.5「リース料」で解
説しているすべての支払いから、借手に支払った又は支払うべきインセンティブ(リース料に含まれ
ているインセンティブを除く)を控除したものと考えられる。
2.2.3.2 契約対価の配分 – 借手
IFRS第 16号からの抜粋
13 リース構成部分と 1 つ又は複数の追加的なリース構成部分又は非リース構成部分とを含
んだ契約について、借手は、契約における対価を、リース構成部分の独立価格と非リース
構成部分の独立価格の総額との比率に基づいて各リース構成部分に配分しなければなら
ない。
14 リース構成部分と非リース構成部分の独立価格の比率は、貸手又は類似の供給業者が当
該構成部分又は類似の構成部分について個々に企業に請求するであろう価格に基づいて
算定しなければならない。観察可能な独立価格が容易に利用可能でない場合には、借手
は、観察可能な情報の利用を最大限にして、独立価格を見積もらなければならない。
借手は、(原資産の種類ごとに)実務上の簡便法(セクション 2.2.2.2「実務上の簡便法-借手」参
照)を適用せず、契約における各リース構成部分と非リース構成部分を区別して会計処理する場合
には、契約対価を独立価格の比率に基づいて、リース構成部分と非リース構成部分に配分すること
が求められる。借手は、観察可能な独立価格(顧客が契約の構成部分を別個に購入する価格)が
利用可能な場合には当該価格を使用しなければならない。観察可能な独立価格が容易に利用可
能でない場合には、借手は、観察可能な情報を最大限に利用して、独立価格を見積もる。契約で明
記された価格は、財又はサービスの独立価格を示している可能性はあるが、会計処理の目的上そ
のような推定は置かれていない。
設例 9 ―― リース構成部分と非リース構成部分への契約対価の配分 – 借手
借手は設備のリース契約を締結する。当該契約では、貸手がリースの対象となる設備のメンテ
ナンスを実施し、当該メンテナンス・サービスに関する対価を受領することを定めている。当該契
約におけるリース構成部分及び非リース構成部分の固定価格は、以下のとおりである。
リース 80,000千円
メンテナンス 10,000千円
合計 90,000千円
独立価格は容易に観察可能ではないため、借手は観察可能な情報を最大限に利用して、リース
構成部分と非リース構成部分の独立価格を次のように見積もる。
リース 85,000千円
メンテナンス 15,000千円
合計 100,000千円
分析:リース構成部分の独立価格は、独立価格の見積額合計の85%を占める。借手は契約対価
(90,000千円)を以下のように配分する。
リース 76,500千円(1)
メンテナンス 13,500千円(2)
合計 90,000千円
(1) 85% x 90,000千円
(2) 15% x 90,000千円
25 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
2.2.4 契約対価の算定及び配分 – 貸手
2.2.4.1 契約対価の算定 – 貸手
セクション 2.2.3.1「契約対価の算定」で解説したとおり、IFRS 第 16 号は、リース契約における「対
価(consideration)」を定義しておらず、IFRS 用語集においても「対価」は定義されていない。しかし、
貸手にとってのリース契約における対価には次のものが含まれると考えられる。
• セクション3.5「リース料」で解説しているリース料の支払い
• リース期間におけるその他の固定支払い(例:月次のサービス費用、メンテナンスなどの非
リース構成部分)又は実質的に固定された支払いから、借手に支払った又は支払うべきイン
センティブを控除したもの
• リース期間におけるその他の変動支払いのうち指数又はレートに応じて決まり、開始日(セク
ション3.2「リースの開始日」参照)の指数又はレートを用いて当初測定されるもの
• IFRS第15号の変動対価に関する要求事項に従い取引価格に含まれるその他の変動支払い。
なお、当該変動支払いの条件は、次のいずれかに個別に関連している。
• リースではない1つ以上の財又はサービスを移転するための貸手の努力
• リースではない1つ以上の財又はサービスの移転から生じる結果
変動対価は、IFRS第 15号において幅広く定義されており、さまざまな形態をとる可能性がある。対
価の変動は、値引き、リベート、返金、クレジット、価格譲歩、インセンティブ、業績ボーナス、ペナル
ティ、又はその他の類似の項目によって生じる場合がある。貸手は、変動対価を見積もる際に、変
動対価の種類毎に見積りの制限が適用されるため、契約に含まれているさまざまな種類の変動対
価を適切に識別できることが重要になる。
変動対価の形態、変動対価の見積り、変動対価の見積りに係る制限に関する詳細な解説について
は、弊法人の刊行物「Applying IFRS: IFRS 第 15 号 顧客との契約から生じる収益(2018 年 10
月)」1を参照されたい。
2.2.4.2 契約対価の配分 – 貸手
IFRS第 16号からの抜粋
17 リース構成部分と 1 つ又は複数の追加的なリース構成部分又は非リース構成部分とを含
んだ契約について、貸手は、契約における対価を IFRS第 15号の第 73項から第 90項を
適用して配分しなければならない。
IFRS第 16号では、貸手は IFRS第 15号第 73項から第 86項を適用して、契約対価を独立販売
価格の比率に基づいてリース構成部分と非リース構成部分に配分することが求められる。さらに、
貸手は IFRS第 15 号第 87 項から第 90 項を適用して、契約対価の事後的な変動をリース構成部
分と非リース構成部分に配分する必要がある。独立販売価格とは、企業が約束した財又はサービ
スを顧客に販売するであろう独立した価格をいう。独立販売価格が直接的に観察可能ではない場
合、貸手は独立販売価格を見積もらなければならない。IFRS第 15号第 79項には、独立販売価格
を見積もるための適切な方法が定められている。
独立販売価格の見積りや見積方法に関する詳細な解説については、弊法人の刊行物「Applying
IFRS: IFRS第 15号 顧客との契約から生じる収益(2018年 10月)」1を参照されたい。
弊社のコメント
収益認識に関する会計方針(リースを含む契約に係る収益認識に関する会計方針を含む)を策
定する場合には、独立販売価格の見積りに際して、経理部や財務部のみでなく、他の部署から
も情報を入手する必要がある。特に観察可能なインプットが限られている、又は存在しない場合
には、見積独立販売価格を算定するために必要な情報を入手し、その内容を理解する必要が
あると考えられる。現行基準において、独立販売価格を見積もっていない場合には、実務の変
更が生じる可能性がある。
1 当該刊行物は https://www.shinnihon.or.jp/ifrsから入手可能。
貸手は、契約対価を独立販売価格
の比率に基づいてリース構成部分
と非リース構成部分に配分する。
26 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
2.2.5 設例 ― 契約における構成部分の識別及び区別ならびに契約対価の算定及び配分
IFRS第 16号における以下の設例では、借手がどのように契約におけるリース構成部分と非リース
構成部分を識別及び区別し、契約対価を算定及び配分するかについて解説している。
IFRS第 16号からの抜粋
設例 12 ―― 借手による契約のリース構成部分と非リース構成部分への対価の配分
貸手が、ブルドーザー、トラック及びパワーショベルを、借手の鉱山事業で 4 年間使用するため
に借手にリースする。貸手は、設備の各項目をリース期間全体にわたりメンテナンスすることに
も合意する。契約の合計対価は CU600,000(a)であり、年 CU150,000の延払とパワーショベル
のメンテナンスを実施した作業時間数に応じて決まる変動金額で支払われる。変動支払いは、
パワーショベルの再調達原価の 2%を上限とする。対価には、設備の各項目のメンテナンス・
サービスのコストが含まれる。
借手は、非リース構成部分(メンテナンス・サービス)を IFRS第 16号の第 12項を適用して設備
のリースのそれぞれと区分して会計処理する。借手は IFRS第 16号の第 15項における実務上
の便法を選択しない。借手は、IFRS 第 16 号の B32 項における要求事項を考慮し、ブルドー
ザーのリース、トラックのリース、パワーショベルのリースはそれぞれ独立したリース構成部分で
あると結論を下す。これは以下の理由による。
(a) 借手は、この 3 つの設備項目をそれぞれ単独で又は他の容易に利用可能な資源との組合
せでの使用から便益を得ることができる(たとえば、借手は、事業で使用するための代替的
なトラック又はパワーショベルを容易にリース又は購入することができる)。
(b) 借手は 3つの設備項目のすべてを 1つの目的(すなわち、鉱山事業を営むこと)でリースし
ているが、機械は互いに依存性が高くはなく、相互関連性も高くない。借手が各設備項目の
リースから便益を引き出す能力は、他の設備を貸手からリースするのかリースしないのか
の決定に大きな影響を受けない。
したがって、借手は、契約の中に 3 つのリース構成部分と 3 つの非リース構成部分(メンテナン
ス・サービス)があると結論を下す。借手は、IFRS第 16号の第 13項から第 14項のガイダンス
を適用して、契約の対価を 3つのリース構成部分と非リース構成部分に配分する。
いくつかの供給者が類似のブルドーザー及びトラックについてメンテナンス・サービスを提供して
いる。したがって、それら 2つのリース設備の項目についてメンテナンス・サービスの観察可能な
独立価格がある。借手は、貸手との契約と同様の支払条件を仮定して、ブルドーザーとトラック
のメンテナンスの観察可能な独立価格をそれぞれCU32,000とCU16,000に設定することがで
きる。パワーショベルは高度に特殊化されたものであるため、他の供給者は類似のパワーショベ
ルのリースをしておらず、メンテナンス・サービスも提供していない。それでも、貸手は、類似のパ
ワーショベルを貸手から購入する顧客に 4 年間のメンテナンス・サービス契約を提供している。
それらの 4年間のメンテナンス・サービス契約の観察可能な対価は、4年間にわたり支払われる
固定対価の CU56,000と、パワーショベルのメンテナンスを実施した作業時間数に応じて決まる
変動金額である。変動支払いは、パワーショベルの再調達原価の 2%を上限とする。したがっ
て、借手は、パワーショベルのメンテナンス・サービスの独立価格を CU56,000 に変動金額を加
算したものと見積もる。借手は、ブルドーザー、トラック、パワーショベルのリースの観察可能な独
立価格を、それぞれ CU170,000、CU102,000、CU224,000 と設定することができる。
借手は、契約における固定対価(CU600,000)をリース構成部分と非リース構成部分にそれぞ
れ次のように配分する。
CU ブルドーザー トラック パワーショベル 合計
リース 170,000 102,000 224,000 496,000
非リース 104,000
固定対価合計 600,000
借手は、変動対価のすべてをパワーショベルのメンテナンス(したがって、契約の非リース構成
部分)に配分する。借手は各リース構成部分を IFRS第 16号におけるガイダンスを適用して、配
分された対価を各リース構成部分に係るリース料として扱って、会計処理する。
(a) 設例において、貨幣金額は「通貨単位」(CU)で表示している。
27 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
2.3 契約の結合
IFRS第 16号からの抜粋
B2 本基準を適用するにあたり、企業は、下記の要件のいずれかに該当する場合には、同一の
相手方(又は相手方の関連当事者)と同時又はほぼ同時に締結した複数の契約を結合し
て、単一の契約として会計処理しなければならない。
(a) 当該諸契約が、当該諸契約を一体として考慮しないと理解できない全体的な商業上の目的
でパッケージとして交渉されている。
(b) ある契約で支払われる対価の金額が、他の契約の価格又は履行に左右される。
(c) 当該諸契約で移転される原資産の使用権(又は契約のそれぞれで移転される原資産の各
使用権)が、B32項に記述する単一のリース構成部分を構成する。
IFRS第 16号は、下記の要件のいずれかに該当する場合には、同一の相手方(又は相手方の関連
当事者)と同時又はほぼ同時に締結した複数の契約を単一の契約として取り扱うことを求めている。
• 契約が全体的な商業上の目的で一括して交渉されており、契約を一体で考慮することが前提
となっている
• ある契約で支払われる対価の金額が、他の契約の価格又は履行に左右される
• 契約における移転される原資産を使用する権利(又は各契約における移転される原資産を使
用する各権利)は、単一のリース構成部分を構成する(セクション2.2.1「契約におけるリース
構成部分の識別及び区分」参照)
IASB は、結論の根拠(BC 第 130 項から第 132 項)において、複数の契約を別個に会計処理した
場合に、取引の全体が忠実に表現されないことへの懸念に対処するために、これらの要件を開発し
たと述べている。
28 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
3. 主要な概念
借手及び貸手は、リース契約を識別、認識及び測定するにあたり、全般にわたり同一の主要な概念
を適用する。
3.1 契約の開始
IFRS第 16号からの抜粋
9 契約時に、企業は、当該契約がリース又はリースを含んだものであるのかどうかを判定しな
ければならない。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と
交換に移転する場合には、当該契約はリースであるか又はリースを含んでいる。B9 項から
B31 項は、契約がリース又はリースを含んだものであるのかどうかの判定に関してのガイ
ダンスを示している。
付録 A
用語の定義
リースの契約日(契約日)(inception date of the lease (inception date))
リース契約の日又は当事者がリースの主要な契約条件について確約した日のいずれか早い日
IFRS第 16号では、顧客及び供給者は、契約の開始時に、契約がリースであるか、又はリースを含
んでいるかどうかを判定することが求められる。リースの契約日とは、リース契約を締結した日又は
当事者がリースの主要な契約条件について確約した日のいずれか早い日である。
結論の根拠(BC 第 72 項)では、リース契約日からリース開始日(セクション 3.2「リースの開始日」
参照)までの期間においては、リース契約には IAS第 37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」で定
められている不利な契約が適用されると述べられている。
3.2 リースの開始日
IFRS第 16号からの抜粋
付録 A
用語の定義
リースの開始日(開始日)(commencement date of the lease (commencement
date))
貸手が借手による原資産の使用を可能にする日
原資産(underlying asset)
リースの対象である資産で、貸手によって借手に当該資産を使用する権利が移転されているもの。
リースの開始日とは、貸手が借手による原資産(リースの対象となる資産)の使用を可能にする日
である。リースの開始日は、リース契約に明記された日(例:賃貸料の支払期日)より前の場合があ
る。たとえば、資産の稼働を開始する前に、借手がリースした場所の改良を行う場合(例:借手が賃
借設備に独自の改良を加えるためにリースした場所を使用する期間)などに生じるケースが多い。
借手が、資産の使用開始前又はリース条件に基づくリース料の支払前に、原資産の使用に対する
占有又は支配を獲得する場合には、リース料の支払いが開始されていない、もしくはリース開始日
が後日付けとなることがリース契約で定められている場合であっても、リース期間は開始しているこ
とになる。したがって、契約に基づくリース料の支払開始時期は、リースの開始日に影響を与えるも
のではない。借手は、リースの開始日においてリース負債及び関連する使用権資産を認識する(た
だし、短期リース又は少額資産に関する免除規定を適用する場合を除く。セクション 4.1.1「短期
リース」及び 4.1.2「少額資産のリース」参照)。また、ファイナンス・リースを行う貸手は、リースの開
始日において正味リース投資未回収額を認識する。
契約の開始時に、契約がリースであ
るか、又はリースを含んでいるかど
うかを判定する。
29 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
3.3 リースの開始日前における原資産への借手の関与
一部のリースでは、借手による原資産の利用が可能となる前にリースの交渉が行われる場合があ
り、これは借手が原資産を使用するために建設又は再設計することが必要となる場合があるためで
ある。このような場合、借手は、契約の条件に応じて、資産の建設又は設計に関する支払いが求め
られることがある。
原資産の建設又は設計に関するコストが借手に生じる場合には、借手は当該コストを適用可能な
他の基準(IAS 第 16 号「有形固定資産」など)を適用して会計処理することになる。原資産の建設
又は設計に関するコストには、原資産を使用する権利に係る借手の支払いは含まれない。原資産
を使用する権利に係る支払いは、当該支払いの時期に関係なく、リースに対する支払いである。
原資産に対する法的所有権が貸手に移転され、さらに当該資産が借手にリースされる前に、借手
が原資産に対する法的所有権を保持する場合がある。しかし法的所有権を保持すること自体が取
引の会計処理方法を決定するものではない。
原資産が貸手に移転される前に借手が当該原資産を支配している(又は原資産に対する支配を獲
得する)場合には、当該取引は、下記セクション 7 に記載される方法で会計処理されるセール・アン
ド・リースバック取引となる。
しかし、原資産が貸手に移転される前に借手が原資産に対する支配を獲得していない場合には、
当該取引はセール・アンド・リースバック取引ではない。たとえば、貸手が原資産を製造業者から購
入し、それを借手にリースすることを目的として、製造業者、貸手及び借手との間で取引の交渉が
行われる場合には、これに該当する可能性がある。このような場合、貸手に法的所有権が移転され
る前に、借手が原資産に対する法的所有権を取得することがある。ただし、借手が原資産に対する
法的所有権を保持していたとしても、原資産が貸手に移転される前に原資産に対する支配を獲得し
ていない場合には、当該取引はセール・アンド・リースバックではなく、リースとして会計処理されるこ
とになる。
3.4 リース期間及び購入オプション
3.4.1 リース期間
IFRS第 16号からの抜粋
18 企業は、リース期間を、リースの解約不能期間に下記の両方を加えたものとして決定しなけ
ればならない。
(a) リースを延長するオプションの対象期間(借手が当該オプションを行使することが合理的に
確実である場合)
(b) リースを解約するオプションの対象期間(借手が当該オプションを行使しないことが合理的
に確実である場合)
19 借手がリースを延長するオプションを行使すること又はリースを解約するオプションを行使し
ないことが合理的に確実であるかどうかを評価する際に、企業は、B37 項から B40 項に記
述しているように、借手がリースを延長するオプションを行使すること又はリースを解約する
オプションを行使しないことへの経済的インセンティブを生じさせるすべての関連性のある
事実及び状況を考慮しなければならない。
B36 リース期間は開始日に開始し、貸手が借手に提供した無料賃貸期間があればそれを含める。
30 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号からの抜粋
B37 開始日において、企業は、借手がリースの延長又は原資産の購入を行うオプションを行使
すること、あるいはリースを解約するオプションを行使しないことが、合理的に確実であるか
どうかを評価する。企業は、借手がオプションを行使すること又は行使しないことへの経済
的インセンティブを創出するすべての関連性のある事実及び状況を考慮する。これには、
開始日からオプションの行使日までに予想される事実及び状況の変化が含まれる。考慮す
べき要因の例として、下記のものがあるが、これらに限定されない。
(a) オプション期間に係る契約条件(市場のレートとの比較で)、たとえば、
(i) オプション期間におけるリースに係る支払金額
(ii) リースに係る変動支払い又は他の条件付支払いに係る金額(解約ペナルティや残価
保証から生じる支払いなど)
(iii) 当初のオプション期間後に行使可能なオプションの契約条件(たとえば、現時点で市
場のレートよりも低いレートで延長期間の終了時に行使可能な購入オプション)
(b) 契約期間にわたり実施された(又は実施予定の)大幅な賃借設備改良で、リースの延長又
は解約のオプション、あるいは原資産を購入するオプションが行使可能となる時点で借手に
とって重大な経済的便益を有すると見込まれるもの
(c) リースの解約に係るコスト(交渉コスト、再設置コスト、借手のニーズに適合する他の原資産
を特定することのコスト、新たな資産を借手の業務に組み込むコスト、解約ペナルティ及び
類似のコストなど)。これには、原資産を契約に定められた状態で又は契約に定められた場
所に返還することに関連するコストが含まれる。
(d) 借手の業務に対しての当該原資産の重要度(たとえば、原資産が特殊仕様の資産かどう
か、原資産の所在地、適合する代替品の利用可能性を考慮)
(e) オプションの行使に関連した条件設定(すなわち、1 つ又は複数の条件が満たされた場合
にのみオプションが行使できる場合)及び当該条件が存在することとなる確率
B38 リースを延長又は解約するオプションが 1 つ又は複数の他の契約上の要素(たとえば、残
価保証)と組み合わされて、当該オプションの行使の有無に関係なく、借手が貸手にほぼ同
じ最低限又は固定キャッシュ・リターンを保証する結果となる場合がある。このような場合、
B42 項の実質上の固定リース料に関するガイダンスにかかわらず、企業は、借手がリース
を延長するオプションを行使すること又はリースを解約するオプションを行使しないことが合
理的に確実であると仮定しなければならない。
B39 リースの解約不能期間が短いほど、借手がリースを延長するオプションを行使するか又は
リースを解約するオプションを行使しない可能性が高くなる。これは、代替資産の入手に関
連したコストが、解約不能期間が短いほど比率的に高くなる可能性が高いからである。
B40 借手が特定の種類の資産(リースであれ所有であれ)を通常使用してきた期間に関しての
過去の慣行及びその経済的理由は、借手がオプションを行使すること又は行使しないこと
が合理的に確実であるかどうかを評価する上で有用な情報を提供する場合がある。たとえ
ば、借手が通常は特定の種類の資産を特定の期間にわたり使用してきた場合、又は借手
が特定の種類の原資産のリースについてオプションを頻繁に行使する慣行を有している場
合には、借手は当該資産のリースに係るオプションを行使することが合理的に確実である
かどうかを評価する際に、その過去の慣行の経済的理由を考慮しなければならない。
31 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
リース期間は、リースの開始日に開始し、リースの解約不能期間に下記の両方を加味することによ
り決定される。
• リースを延長するオプションの対象期間(借手が当該オプションを行使することが合理的に確
実である場合)
• リースを解約するオプションの対象期間(借手が当該オプションを行使しないことが合理的に
確実である場合)
「合理的に確実」という表現は、現行の IAS第17号でも使用されており、通常、高い蓋然性として解
釈される。したがって、IASBは現行の実務が変わることは想定していないと考えられる。
購入オプションは、リースの延長オプションやリースの解約オプションと同じ方法で評価することにな
る。IASB は、結論の根拠(BC 第 173 項)において、原資産の購入オプションは、原資産の残存す
る経済的耐用年数にわたりリース期間を延長するオプションと経済的に同様であると述べている。
3.4.1.1 リース期間及び購入オプションの評価
借手がリースの延長オプションもしくは原資産の購入オプションを行使すること、又はリースの解約
オプションを行使しないことが合理的に確実であるかどうかを評価する際、借手及び貸手は、借手
がリースの延長、解約又は購入オプションを行使することに伴い生じる経済的インセンティブに関連
性のあるすべての要因を評価する必要がある。
一定のケースでは、リースの開始日(セクション 3.1「契約の開始」参照)からオプションの行使日ま
での期間が長くなるにつれて、オプションの行使が合理的に確実かどうかの判断が、さまざまな要
因に起因して困難になる。たとえば、予測期間が長くなれば、リースの対象となる資産に対する将来
のニーズに関する借手の見積りは、不正確になる。また、新技術が含まれているような特定の資産
は、主要エリアに位置する商業用オフィスビル全体のリースなど比較的安定した資産と比較すると、
将来の公正価値を予測することが難しい。
借手によるオプションの行使が合理的に確実であると判断するためには、オプションの行使日まで
の期間が長いほど、将来の公正価値の見積額と比較して、オプション価格が相対的に低くなければ
ならない。オプション価格と資産の将来の公正価値の見積額との差異は、著しく価値が変動する資
産の方が、比較的安定した価値の資産よりも大きくなる。
人為的に短いリース期間(例:リース期間が 4年間である本社、流通施設、製造プラント又はその他
の主要不動産のリース)は、借手に対して購入又は延長オプションを行使するための重要な経済的
インセンティブを実質的に生じさせる可能性がある。これは、借手が事業を継続する上での原資産
の重要性や、オプションが存在しない場合において借手がリース契約を締結していたかどうかを評
価することによって裏付けられる場合がある。
同様に、借手の事業における原資産の重要性は、購入オプション又は延長オプションを行使するこ
とが合理的に確実であるかどうかに関する借手の決定に影響を及ぼす可能性がある。
たとえば、特殊仕様の設備(例:製造プラント、流通施設、本社)をリースしている企業が、購入オプ
ション又は延長オプションを行使しなかった場合、代替施設が容易に利用可能でないのであれば重
要な経済的損失を被ることが考えられる。つまり、オプションを行使せずに代替資産を検討する場合
に、企業に不利な影響が生じさせる可能性がある。
借手は、連続していない期間のリース契約を締結する場合がある。このようなリース契約は小売業
界で見られることがあり、小売業者は 1 年のうち一定の連続していない期間(例:連休期間)に同一
の小売スペースを賃借する契約をショッピング・センターと締結することがある。スポーツ・チームが、
1 年のうち連続しない特定の日にスポーツ・スタジアムを借りる場合にも、同様の契約が存在する。
合意した使用期間中、顧客は原資産を使用する権利を支配することから、これらの契約は通常、
リースの定義を満たすことになる。このような契約のリース期間は、設例 10 のシナリオ C に示され
るように、非連続の期間を合算した期間となる。
32 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
設例 10 ―― リース期間の決定
シナリオ A
P社は、解約不能期間が4年間で、2年間の延長オプション(固定価格)が付された機械装置の
リース契約を締結した。将来のリース料はリース契約日における市場相場に近似するように設
定されている。解約に係るペナルティや、P社が延長オプションを行使することが合理的に確実で
あることを示唆するその他の要因は存在しない。
分析:リース開始日において、リース期間は4年となる。
シナリオ B
Q社は、解約不能期間が4年間で、2年間の延長オプションが付された建物のリース契約を締結
した。当該延長オプションの価格は市場価格に基づいており、Q社は建物の入居前に、賃借物件
に係る設備造作に対する支払いを行う。なお、設備造作の価値は、4年間経過後においても重
要であることが見込まれており、当該建物を引き続き占有することによってのみその価値が実現
する。
分析: Q社は、当初の解約不能期間が経過した時点で設備造作を放棄した場合には、重大な経
済的損失が生じるため、リース開始日において、延長オプションを行使することが合理的に確実
であると判断する。したがって、リース開始日において、Q社はリース期間が6年となると結論付
ける。
シナリオC
R社は、ショッピング・センターにおける特定の小売スペースを賃借する契約を締結した。R社は、
5年間の解約不能な期間中、10月、11月及び12月のみ、当該小売スペースを利用することが
できる。貸手は、5年間毎年、同じスペースを提供することに合意している。
分析:リース開始日時点で、リース期間は15ヵ月となる(契約に定められる5年の期間中、毎年
3ヵ月)。
3.4.1.2 解約可能リース
IFRS第 16号からの抜粋
B34 リース期間の決定及びリースの解約不能期間の長さの評価にあたり、企業は、契約の定義
を適用して、契約に強制力がある期間を決定しなければならない。借手と貸手のそれぞれ
がリースを他方の承諾なしに多額ではないペナルティで解約する権利を有している場合に
は、リースにはもはや強制力がない。
B35 借手のみがリースを解約する権利を有している場合には、当該権利は借手が利用可能な
リース解約オプションと考えられ、企業はリース期間を決定する際にこれを考慮する。貸手
のみがリースを解約する権利を有している場合には、リースの解約不能期間には、リース
解約オプションの対象となっている期間が含まれる。
貸手と借手の双方が、他方の承諾なく、多額ではないペナルティによりリースを解約する権利を有し
ている場合、契約は強制可能ではない。ペナルティには、解約オプションが行使された場合におい
て、一方の当事者が他方の当事者に支払うことになる契約上の金額のみが含まれると解釈すべき
か(狭義の解釈)、それとも重要な経済的不利益もペナルティとみなすべきか(広義の解釈)という論
点が存在する。リース期間の決定に関して、IFRS 第 16 号は、借手がオプションを行使すること、又
は行使しないことへの経済的インセンティブを生じさせるすべての関連性のある事実と状況を考慮
することを求めている。したがって、契約上の文言や財務上の性質にとらわれることなく、解約に係
るペナルティのすべての側面を考慮しなければならないと思われる。借手が貸手の承諾なしには
リース契約の更新オプションを行使することができない状況では、このガイダンスは直接適用されな
いが、この規定を類推適用して、すべての事実と状況を考慮に入れ、重要な経済的不利益の有無
を評価することが適切であると考えられる。
契約がリースの定義を満たす場合、借手及び貸手にとっての解約不能期間は、リース期間の一部
とみなされる。貸手のみがリースを解約する権利を有している場合には、当該リースの解約オプショ
ンの対象期間もリースの解約不能期間に含まれる。一方、借手のみがリースを解約する権利を有し
ている場合には、当該権利はリース期間を決定する際に考慮される解約オプションである。3.4.1.1
リース期間及び購入オプションの評価を参照。
33 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
不動産リースについては、多くの国や地域で、リース契約の契約条件に加えて、現地の不動産に関
する法律の影響を受ける。すなわち借手は、リース契約に定められていなくても、現地の法規制に
より、法律上の更新オプションを与えられる場合がある。借手が現地の法律によりそのような権利を
与えられる例としては、空港ターミナルや小売向けショッピング・スペースが挙げられる。企業はリー
ス期間を算定するにあたって、現地の法規制により、リース期間の評価に織り込む必要のある強制
可能な権利及び義務が創出されるかを検討する必要がある。
IFRS 第 16 号は、「解約可能」、「月極」、「任意解約」、「自動継続」、「永久」、「無期限」などと呼ば
れる契約であっても、強制可能な権利及び義務が創出される場合には適用される。それらの種類の
リースでは一般的に、一方の当事者が契約の解約通知を出すまで、契約は解約不能期間を超えて
継続することになる(例:借手又は貸手が契約の解約を選択しない限り契約が月次で更新される)。
なお、借手及び貸手の両者が、解約不能期間終了時以降いつでもリースを解約する権利を有して
おり、当該解約に係るペナルティが重要ではない場合、解約不能期間を超える強制可能な権利及
び義務は存在しない(すなわち、リース期間は解約不能期間に限定される)。ただし、借手のみが更
新オプションを有している場合には、上記の経済的不利益を含め、借手がリースの延長を合理的確
実に行うかを判断する際に考慮すべき他の要因が存在することがある。
設例 11 ―― 解約可能リース
あるリース契約は、最初の1年間は解約不能であり、借手及び貸手の両方が合意した場合に
は、1年延長することができる。延長に合意しない場合であっても、いずれの当事者にもペナル
ティが発生することはない。最初の1年間の解約不能期間は、強制可能な権利及び義務が創出
されるためリース契約の定義を満たす。しかし、1年の延長期間においては、いずれの当事者も
重要なペナルティが課されることなく、リース契約を延長しないことを一方的に選択することがで
きるため、契約の定義に該当しない。すなわち、リースの開始日時点で、いずれの当事者も当初
の解約不能期間を超える強制可能な権利及び義務を有しない。
3.4.2 リース期間及び購入オプションの再評価
IFRS第 16号からの抜粋
20 借手は、延長オプションを行使すること又は解約オプションを行使しないことが合理的に確
実であるかどうかを、下記に該当する重大な事象又は状況の重大な変化の発生時に、見
直さなければならない。
(a) 借手の統制の及ぶ範囲内にあり、かつ、
(b) 借手が過去にリース期間の決定に含めていなかったオプションを行使すること又は過去に
リース期間の決定に含めていたオプションを行使しないことが合理的に確実であるかどうか
に影響を与える(B41項に記述)。
21 企業は、リースの解約不能期間に変化があった場合には、リース期間を改訂しなければな
らない。たとえば、リースの解約不能期間は下記の場合に変化する。
(a) 過去に企業のリース期間の決定に含めていなかったオプションを借手が行使する場合
(b) 過去に企業のリース期間の決定に含めていたオプションを借手が行使しない場合
(c) 過去に企業のリース期間の決定に含めていなかったオプションを借手が行使することを契
約上強制する事象が発生した場合
(d) 過去に企業のリース期間の決定に含めていたオプションを借手が行使することを契約上禁
止する事象が発生した場合
34 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号からの抜粋
B41 第 20 項では、開始日後に、借手は次のような重大な事象又は状況の重大な変化の発生
時にリース期間を見直すと定めている。その事象又は状況変化とは、借手の統制の及ぶ範
囲内にあり、借手が過去にリース期間の算定に含めていないオプションを行使すること又は
過去にリース期間の算定に含めていたオプションを行使しないことが合理的に確実である
のかどうかに影響を与えるものである。重大な事象又は状況変化の例として、下記のもの
がある。
(a) 開始日には予想されていなかった大幅な賃借設備改良で、リースの延長又は解約のオプ
ション、あるいは原資産を購入するオプションが行使可能となる時点で借手にとって重大な
経済的便益を有すると見込まれるもの
(b) 開始日には予想されていなかった原資産の大幅な改変又はカスタマイズ
(c) 過去に決定したリース期間の終了後の期間に係る原資産のサブリースの契約締結
(d) オプションの行使又は不行使に直接に関連性のある借手の事業上の決定(たとえば、補完
的な資産のリースを延長したり、代替的な資産を処分したり、使用権資産を利用している事
業単位を処分したりする決定)
3.4.2.1 リース期間及び購入オプションの再評価 - 借手
IFRS 第 16 号では、リースの開始後(セクション 3.2「リースの開始日」参照)において、リース期間
の変更につながる重大な変化が生じていないかどうかを確かめるために、借手に対してリースの状
況をモニタリングすることを求めている。以下の両方に該当する重大な事象又は状況の変化が生じ
た場合には、借手はリース期間の再評価が求められる。
• 借手のコントロールの範囲内にある場合
• 借手がリース期間の算定に含めていなかったオプションを行使すること、又はリース期間の算
定に含めていたオプションを行使しないことに関して、合理的に確実かどうかの評価に影響す
る場合
下記は、借手のコントロールの範囲内にある重大な事象又は状況の変化の例である。
• オプションの行使が可能となる時点において、借手による重要な経済的価値を有すると見込
まれる大幅な賃借設備の改良の実施
• 原資産の大幅な改良又はカスタマイズの実施
• 借手のオプションを行使する又は行使しないことに直接関連する事業上の決定(例:補完的な
資産のリースの延長、代替資産の処分)
• オプション行使日を上回る期間にわたる原資産のサブリース
市場要因による変動(例:類似資産のリース又は購入に関する市場相場の変動)は、借手のコント
ロールの範囲外であるため、借手は当該要因による再評価は行わない。IFRS 第 16 号では、借手
が過去において行使することが合理的に確実ではないと判断していたオプションを行使する場合、
あるいは過去において行使することが合理的に確実であると判断していたオプションを行使しない
場合には、借手はリース期間を再評価することが求められる。さらに、過去において、リース期間の
算定に含めていないオプションに関して、当該オプションの行使が契約上強制される事象が発生し
た場合、又はリース期間の算定に含めていたオプションに関して、当該オプションの行使が契約上
禁止される事象が発生した場合においても、リース期間の再評価が行われる。
借手は、自身のコントロールの範囲内にある重大な事象又は状況の変化が発生した場合に、リー
ス期間の再評価が求められるため、通常は、実際にオプションが行使される前に、リース期間の再
評価が行われることになる。なお、リース期間の再評価の結果により、リース期間又は購入オプショ
ンの行使に関して変更がある場合には、借手は、再評価日時点における修正後のインプット(例:割
引率)を使用してリース負債を再測定し、再測定により生じた差額を使用権資産で調整する。ただし、
使用権資産をゼロにまで減額した場合には、借手は残りの金額を純損益で認識する(セクション
3.5.9「リース負債の再評価」参照)。
借手の再評価及び再測定に関する要求事項の概要については付録 Dを参照されたい。
35 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
3.4.2.2 リース期間及び購入オプションの再評価 – 貸手
IFRS 第 16 号では、貸手は、オプションの行使がリース期間の算定に含まれていない場合には、借
手がリースの延長オプション、解約オプション又は原資産の購入オプションを行使した際に、リース
期間の再評価を行うことが求められる。
貸手の再評価及び再測定に関する要求事項の概要については付録 Dを参照されたい。
3.5 リース料
IFRS第 16号からの抜粋
付録 A
用語の定義
リース料(lease payments)
借手が貸手にリース期間中に原資産を使用する権利に関して行う支払いであり、次のもので構
成される。
(a) 固定リース料(実質上の固定リース料を含む)からリース・インセンティブを控除したもの
(b) 変動リース料のうち指数又はレートに応じて決まるもの
(c) 購入オプションの行使価格(借手が当該オプションを行使することが合理的に確実である
場合)
(d) リースの解約のためのペナルティの支払い(リース期間が、借手がリースを解約するオプ
ションを行使することを反映している場合)
借手については、リース料には、借手が残価保証に基づいて支払うと見込まれる金額も含まれ
る。リース料には、契約の非リース構成部分に配分された支払いは含めない。ただし、借手が非
リース構成部分とリース構成部分を合算して単一のリース構成部分として会計処理することを選
択する場合は除く。
貸手については、リース料には、貸手に提供された残価保証(借手、借手と関連のある当事者、
又は貸手と関連のない第三者で保証に基づく義務を弁済する財務上の能力のある者が行うも
の)も含まれる。リース料には、非リース構成部分に配分された支払いは含めない。
リース料とは、リース期間中に原資産を使用する権利に関して行う貸手に対する借手の支払いであ
り、次のもので構成される
• 貸手から受領するリース・インセンティブを控除した後の固定支払い(実質的な固定支払いを
含む。セクション3.5.1「実質的に固定されたリース料」及びセクション3.5.2「リース・インセン
ティブ」参照)
• 指数又はレートに応じて決まる変動リース料(セクション3.5.3「指数又はレートに応じて決まる
変動リース料」参照)
• 購入オプションの行使価格(借手が当該オプションを行使することが合理的に確実である場合。
セクション3.5.4「購入オプションの行使価格」参照)
• リースの解約に係るペナルティの支払い(借手によるリースの解約オプションの行使がリース
期間に反映されている場合。セクション3.5.5「解約ペナルティ」参照)
• 残価保証に基づき借手により支払いが見込まれる金額(借手のみ。セクション3.5.6「残価保
証により支払いが見込まれる金額―借手のみ」参照)
• 借手、借手と関連のある当事者、又は貸手と関連のない第三者(保証に基づく債務を弁済す
る財務上の能力のある者)が、貸手に対して提供する残価保証(貸手のみ。セクション3.5.7
「残価保証―貸手のみ」参照)
リース料には、契約における非リース構成部分に配分された支払いは含まれない。ただし、借手が
非リース構成部分とリース構成部分を合わせて単一のリース構成部分として会計処理することを選
択する場合にはこの限りではない。
指数又はレートに応じて決まる変動
リース料は、リース料に含まれる。
その他の変動リース料はリース料
に含まれない。
36 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
3.5.1 実質的に固定されたリース料
IFRS第 16号からの抜粋
B42 リース料には、実質上の固定リース料が含まれる。実質上の固定リース料とは、形式上は
変動可能性を含んでいるが、実質上は不可避である支払いである。実質上の固定リース料
は、たとえば、下記の場合に存在する。
(a) 支払いが変動リース料として構成されているが、当該支払いに真正の変動可能性がない。
そうした支払いは、実際の経済的実質のない変動条項を含んでいる。そうした種類の支払
いの例として、次のものがある。
(i) 資産がリース期間中に稼働が可能であると判明した場合にのみ、又は発生しない可
能性が本当はない事象が発生した場合にのみ行わなければならない支払い。
(ii) 当初は原資産の使用に連動した変動リース料として構成されているが、開始日後のあ
る時点で変動可能性が解消されて残りのリース期間については支払いが固定となるも
の。そのような支払いは、変動可能性が解消された時点で実質上の固定リース料とな
る。
(b) 借手が行うことのできる複数の支払セットがあるが、それらの支払セットのうち1つだけが現
実的である。この場合、企業は現実的な支払いのセットをリース料と考えなければならない。
(c) 借手が行うことのできる複数の現実的な支払セットがあるが、それらの支払セットのうち少
なくとも 1つを実行しなければならない。この場合、企業は合計金額が(割引後のベースで)
最低となる支払セットをリース料と考えなければならない。
リース契約の中には、支払いが変動するように定められている場合や、変動要素を含んでいるよう
な場合があるが、契約条件により固定された金額の支払いが回避できない場合には、実質的に固
定された金額の支払いを含んでいる。このような支払いは、リース開始時点でリース料総額に含ま
れ、リース資産及びリース負債を測定する際に考慮される。
3.5.2 リース・インセンティブ
IFRS第 16号からの抜粋
付録 A
用語の定義
リース・インセンティブ(lease incentives)
貸手が借手にリースに関連して行う支払い、又は貸手による借手のコストの弁済若しくは引受け
貸手とのリース契約の中には、借手がリースを締結するためのインセンティブを含んでいる場合が
ある。このようなインセンティブには、借手に対する現金の支払い、借手の費用(例:移転費用)の補
填、又は借手が第三者と締結している既存のリースの貸手による引受けなどが挙げられる。
借手の場合、リースの開始日以前に借手が受け取るリース・インセンティブは、借手の使用権資産
の当初測定の金額から減額される。リース開始日時点で借手が受け取ることになるリース・インセン
ティブは、借手のリース負債から減額される(したがって、使用権資産も同じく減額される)。
貸手の場合、借手と同様に、借手に対して支払われた、又は支払いが予定されているリース・イン
センティブはリース料総額から控除されるため、リースの分類判定に影響する。ファイナンス・リース
の場合、借手に対して支払いが予定されているリース・インセンティブは、開始日時点のリース債権
見積額から減額されるため、貸手の正味リース投資未回収額の当初測定の金額が減額される。オ
ペレーティング・リースの場合、貸手は、借手に対して支払いが予定されているリース・インセンティ
ブに関する費用を繰り延べて、当該費用をリース期間にわたってリース収益から減額しなければな
らない(セクション 4「借手の会計処理」及びセクション 5「貸手の会計処理」参照)。
IFRS第16号の設例13では、賃借設備改良に係る貸手からの補償は、他の基準を適用すべきで、
それはリース・インセンティブにはならないとしている。しかし、貸手からの賃借設備改良の補償は
リース・インセンティブであり、IFRS 第 16 号に従ってそのように会計処理しなければならないと EY
は考えている。IASBは 2018年 5月の会議で、この設例は IFRS第 16号のリース・インセンティブ
の会計処理に混乱を生じさせる可能性があると結論付けた。したがって、IASBは次回の IFRS年次
改善で設例 13の修正を提案することを暫定決定した。改訂案では、貸手からの賃借設備改良の補
償に関する説明が削除されることが提案されている。
37 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
3.5.3 指数又はレートに応じて決まる変動リース料
IFRS第 16号からの抜粋
42 借手は、次のいずれかの場合には、改訂後のリース料を割り引くことによってリース負債を
再測定しなければならない。
(a) 残価保証に基づいて支払われると見込まれる金額の変動がある場合。借手は、改訂後の
リース料を残価保証に基づいて支払うと見込まれる金額の変動を反映するように算定しな
ければならない。
(b) 将来のリース料の算定に使用される指数又はレートの変動(たとえば、市場賃料の調査後
に市場賃料率の変動を反映するための変更)による将来のリース料の変動がある場合。借
手は、キャッシュ・フローの変動があった場合(すなわち、リース料の修正が生じた場合)に
のみ、リース負債を改訂後のリース料を反映するように再測定しなければならない。借手
は、リース期間の残り期間についての改訂後のリース料を、改訂後の契約上の支払いに基
づいて算定しなければならない。
43 第 42 項を適用するにあたり、借手は割引率を変更せずに使用しなければならない。ただ
し、リース料の変動が変動金利の変動から生じている場合は除く。その場合には、借手は
金利の変動を反映した改訂後の割引率を使用しなければならない。
指数又はレートに応じて決まる変動リース料には、たとえば、消費者物価指数やベンチマーク金利
(LIBOR など)に連動した支払い、市場の賃貸料率の変動を反映するように変動する支払いが含ま
れる。このような支払いは、リース料総額に含まれ、測定日時点(例:当初測定の場合はリース開始
日時点)の指数又はレートを使用して測定される。IASB は、結論の根拠(BC 第 165 項)において、
指数又はレートに応じて変動するリース料の測定に関して不確実性があることを認めているが、変
動リース料の支払いは回避することができず、借手の将来の活動に依存するものではないことから、
資産(貸手の場合)及び負債(借手の場合)の定義を満たすと考えている。リース料を決定するため
に使用された指数又はレートの変動に伴い、将来の支払いに関するキャッシュ・フローが変更される
場合(リース料総額が修正される場合)には、借手は事後的にリース負債の再測定を行う(セクショ
ン 4.4「リース負債の再評価」参照)。
設例 12 ―― 指数又はレートに応じて決まる変動リース料
A社は10年間にわたる不動産のリース契約を締結した。1年目のリース料は1,000千円である。
リース料は、変動利子率ではなく、消費者物価指数(CPI)に連動している。第1年度の期首時点
のCPIは100である。リース料総額は2年毎に期末時点で見直される。第1年度の期末時点にお
けるCPIは105、第2年度の期末時点におけるCPIは108であった。
分析:リース開始日時点では、10年間のリース契約の年間リース料は1,000千円である。 A社
は、将来において指数が変動する可能性を考慮しない。第1年度の末日時点では、リース料は
変更されないため、リース負債は見直されない。第2年度の末日時点では、リース料が変更され
るため、A社は残りの8年間の年間リース料を1,080千円 (1,000千円/100×108)に見直す
が、割引率は変更せずにリース負債(及び使用権資産)を再測定する。
3.5.4 購入オプションの行使価格
借手が購入オプションを行使することが合理的に確実な場合には、当該行使価格をリース料に含め
る。つまり、リース契約に含まれる資産の購入オプションの行使価格を、リースの更新オプション及び
解約オプションの評価と同じように考慮する(セクション 3.4「リース期間及び購入オプション」を参照)。
3.5.5 解約ペナルティ
借手がリースを解約しないことが合理的に確実な場合には、リース期間は当該解約オプションが行
使されないことを前提に決定されるため、解約ペナルティはリース料に含めない。一方で、借手が
リースを解約しないことが合理的に確実でない場合には、解約ペナルティをリース料に含める。リー
スの解約ペナルティをリース料に含めるかどうかの判断は、リースの更新オプションの評価と同様で
ある。
38 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
3.5.6 残価保証により支払いが見込まれる金額 – 借手のみ
IFRS 第 16 号では、借手は、残価保証に基づき貸手に対する支払いが見込まれる金額をリース料
総額に含めことが求められる。
借手は貸手に対して、リースの終了時に貸手に返還する原資産の価値が、少なくとも一定の金額に
なることを保証する場合がある。このような保証は、リース契約を締結することにより借手に強制可
能な義務を生じさせる。借手が保証する貸手の残存価値に関して不確実性がある場合には、債務
の存在ではなく、債務の測定においてその不確実性を考慮する。
残価保証に基づき支払いが見込まれる金額に変更が生じた場合、借手はリース負債の再測定が求
められる(セクション 3.5.9「リース負債の再評価」参照)。
設例 13 ―― リース料に含まれる残価保証
R社(借手)は、リース契約を締結し、リースの終了時において、貸手が他の当事者に資産を売
却する際に15,000千円を得ることを保証する。リースの開始時点において、R社は、原資産の
見積残存価値に基づき、リースの終了時点で6,000千円を負担することを見込んでいる。
分析: R社は、残価保証に基づいて、貸手に対して6,000千円を支払うことを見込んでいるため、
当該金額をリース料に含める。
弊社のコメント
IFRS 第 16 号は、残価保証に基づいて見込まれる変動に関して、どの程度の頻度で再評価す
べきかを明確にしていない。我々は、再評価の頻度を決定するために、関連する事実及び状況
に基づく判断が求められると考えている。
3.5.7 残価保証 – 貸手のみ
IFRS 第 16 号は、借手、借手と関連のある当事者、又は貸手と関連のない第三者(保証に基づく債
務を弁済する財務上の能力のある者)が、貸手に対して提供する残価保証をリース料に含めること
を求めている。借手の場合は、支払いが見込まれる金額のみをリース料に含めるため、貸手の場
合とは異なる(セクション 3.5.6「残価保証により支払いが見込まれる金額 – 借手のみ」参照)。
3.5.8 リース料総額に含まれない金額
指数又はレートに応じて決まるものではなく、実質的な固定支払い(セクション 3.5.1「実質的に固定
されたリース料」)にも該当しない変動リース料は、リース料総額に含まれない。これらに該当する支
払いの例として、業績(例:売上高に対する割合)や原資産の使用状況(例:飛行時間や生産数量)
に基づく変動リース料などが挙げられる。このような変動リース料はリース料総額に含まれず、支払
いを生じさせる事象が発生した期間において、純損益で認識する(他の IFRS に従ってその他の資
産の帳簿価額に含まれる場合を除く)。
場合によっては、リース期間中に変動性が解消され、残りのリース期間においてリース料が固定額
となる場合がある。この場合、リース負債を新たに固定額となったリース料を用いて再測定(相手勘
定は使用権資産)する。また、契約に偶発性の解消時点が明記されており、借手がリース料の
キャッチアップの支払いを即時に行うことが要求される場合がある。こうしたキャッチアップの支払い
は、借手による以前の期間における資産の使用に厳密に関係する。このような場合、偶発性が解消
した時点で、リース負債の一部としてキャッチアップ債務を認識し、(相手勘定として使用権資産を調
整するのではなく)即時に費用化すべきであると我々は考えている。
39 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
設例 14 ―― 指数や利率に応じて決まるものではない変動リース料
医療機器製造企業であるA社は、医療機器に関連する消耗品の供給を行っている。A社の顧客
であるB社は、医療センターを運営している。A社とB社との間で締結された契約によれば、A社
は、医療研究施設の機械装置を使用する権利を無償でB社に付与する。B社は、当該機械装置
に使用される消耗品を1単位あたり100千円でA社から購入する。この消耗品は当該機械装置
のみでしか使用することができず、B社は他の消耗品をこの代替物として使用することはできな
い。契約では、最低購入数量は定められていない。B社は、過去の実績から、当該消耗品を年間
8,000単位購入する可能性が非常に高いと見込んでいる。B社は、この契約には医療機器装置
のリースが含まれると判断している。契約には残価保証やその他の形式の対価についても定め
られていない。
分析:この契約には医療機器のリースと消耗品の購入(非リース構成部分)の2つの構成要素が
含まれている。
B社は、消耗品の年間購入数量が8000単位より少なくなる可能性は非常に少ないと考えている
が、この契約では、当初測定(A社及びB社)及びリースの分類(A社)を目的として用いられる
リース料は存在しない。
A社及びB社は、将来の支払いに関連する対価を、契約のリース構成部分と非リース構成部分
(消耗品)とに配分することになる。
リース料総額には、契約の非リース構成部分に配分された金額は含まれない。ただし、会計方針の
選択により、借手がリース構成部分と非リース構成部分を単一のリースとして会計処理を行う場合
には、非リース構成部分に配分されるべき金額もリース料総額に含まれる(セクション 2.2.2「契約
におけるリース構成部分と非リース構成部分の識別及び区別」参照)。
借手がリース契約を締結する場合、貸手は各国の税法に従って付加価値税(VAT)を借手に請求す
る場合がある。多くの国や地域で貸手が税務当局に代わり VAT を徴収し、税務当局にそれを納付
している。VAT が借手の義務である(すなわち貸手の義務ではない)場合、貸手において VAT が
リース料に含まれることはない。借手においては、貸手がリース料を請求した時点で VAT に係る負
債が発生することになる。ただし、VAT が全額回収されない場合もある。たとえば、借手のビジネス
において、VAT の回収が禁止されている場合やリース資産の性質上回収が禁止されている場合が
挙げられる。通常こういった状況では、借手は VAT をリース料に含めず、負債が発生した時点で純
損益に認識する(他の基準の資産要件を満たす場合を除く)と我々は考えている。なお、当該論点
についての実務慣行は定まっていない。
3.5.9 リース負債の再評価
IFRS 第 16 号は、リース料の変動を反映するために、リース負債をどのように再測定すべきかにつ
いて具体的な規定を設けている(セクション 4.4 参照)。借手はリース負債の再測定に係る金額を
使用権資産の修正として認識する。ただし、使用権資産の帳簿価額がゼロまで減額されていて、さ
らにリース負債の測定において減額部分がある場合には、借手は再測定の残額を純損益に認識す
る(「付録 D:リースの再評価及び再測定に関する要求事項の概要」参照)。
3.5.10 貸手による再測定
貸手は別個のリースとして会計処理されないリースの条件変更(リース範囲の変更、又はリースの
当初の契約条件には含まれていなかった対価の変更)が生じた場合に、リース料総額の再測定を
行う(セクション 5.5「リースの条件変更」参照)。
40 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
3.6 割引率
IFRS第 16号からの抜粋
付録 A
用語の定義
リースの計算利子率(interest rate implicit in the lease)
(a)リース料と(b)無保証残存価値の現在価値を、(i)原資産の公正価値と(ii)貸手の当初直接
コストとの合計額と等しくする利子率
借手の追加借入利子率(lessee’s incremental borrowing rate)
借手が、同様の期間にわたり、同様の保証を付けて、使用権資産と同様の価値を有する資産を
同様の経済環境において獲得するのに必要な資金を借り入れるために支払わなければならな
いであろう利率
割引率は、リース料総額の現在価値を算定するために使用される。リース料総額の現在価値は、
リースの分類を判定する場合や(セクション 5.1「リースの分類」参照)、貸手の正味リース投資未回
収額及び借手のリース負債を測定するために使用される。
貸手は割引率としてリースの計算利子率を用いるが、リースの計算利子率は、以下の算式を成立さ
せる利子率である。
当初直接コストは、貸手が製造業者又は販売業者である場合を除き、正味リース投資未回収額の
当初測定に含め、リース期間にわたって認識される収益から減額する(セクション 5「貸手の会計処
理」及びセクション 3.7「当初直接コスト」参照)。
借手は、リースの計算利子率を容易に算定できる場合には、当該計算利子率を使用してリース料
総額を割り引く。ただし、当該計算利子率を容易に算定できない場合には、追加借入利子率を使用
する。
なお、「容易に算定できる」とは、「見積り可能」と同義語ではない。したがって、リースの計算利子率
が見積り及び(又は)仮定を使用してのみ算定可能となる場合は、リースの計算利子率は容易に算
定できないことになる。
借手の追加借入利子率とは、借手が、同様の期間(リース期間)にわたり、同様の保証を付けて、使
用権資産と同等の価値を有する資産を同様の経済環境において獲得するための資金を借りるとし
た場合に、支払わなければならないであろう利率である。
追加の借入利子率を算定する場合、借手は、原資産ではなく、使用権資産を担保とした同様の条
件における借入を考慮する。たとえば、5 年の不動産リースでは、借手は使用権資産と同様の 5 年
を基礎とした条件の借入を考慮し、使用期間が長期に及ぶ不動産そのものと同様の条件の借入を
考慮するわけではない。不動産利回りなどの観察可能な利子率を、追加借入利子率の算定の出発
点とすることはできるが、使用権資産と同様の価値を有する資産を考慮するために、一定の調整を
検討する必要がある。借手の与信状況、借入通貨、リース期間の長さによっても一定の調整を検討
する必要がある。また、追加借入利子率を算定するために重要な判断が必要になる場合もある。
上述のとおり、借手の追加借入利子率は、同様の経済環境などを考慮して、借手が支払わなけれ
ばならないであろう利子率を反映したものである。契約上、借手が自身の機能通貨以外の通貨で
リース料の支払いを行うことが定められている場合には、借手の追加借入利子率は、当該外国通
貨で同様の金額を借り入れた場合の利子率を基礎として算定する。外貨建てリースについては下
記 4.6.2で説明している。
借手が原資産を
使用する権利に
対して支払う リース料総額の
現在価値
+ 無保証残存価値
の現在価値 原資産の
公正価値
貸手の 当初直接 コスト
= +
41 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
弊社のコメント
リースの計算利子率は、契約に記載されている利子率と一致するとは限らず、貸手の当初直接
コストや残存価値の見積額を反映させる必要がある。そのため、借手はリースの計算利子率を
算定することが困難な場合があり、その際には追加借り入れ利子率を算定する必要がある。
3.6.1 子会社の追加借り入れ利子率の算定-財務機能が一元化されている場合
企業グループによっては、財務機能を一元化し、親会社が企業グループにおけるすべての必要な
資金を管理している場合がある。IFRS 第 16 号では、このような財務機能が一元化されている場合
における子会社の追加借入利子率を、一律に親会社の追加借入利子率とすることはできない。子
会社である借手の追加借入利子率を算定するにあたり、すべての事実及び状況を検討しなければ
ならない。一方、子会社の債務が明示的又は黙示的に保証されている場合には、親会社の利子率
と同様の利子率となる場合がある。
3.6.2 割引率の再評価
セクション 3.5.9「リース負債の再評価」及び 4.5「リースの条件変更」を参照されたい。
3.7 当初直接コスト
IFRS第 16号からの抜粋
69 当初直接コストは、製造業者又は販売業者である貸手に生じたものを除いて、正味リース
投資未回収額の当初測定に含められ、リース期間にわたり認識される収益の金額の減額
となる。リースの計算利子率は、当初直接コストが正味リース投資未回収額に自動的に含
まれるような方法で定義されており、それらを別個に加算する必要はない。
付録 A
用語の定義
当初直接コスト(initial direct costs)
リースの取得の増分コストのうち、当該リースを取得しなければ発生しなかったであろうコスト
(ファイナンス・リースに関して製造業者又は販売業者である貸手に生じたコストを除く)
IFRS第 16号では、当初直接コストを、リースを取得しなければ発生しなかったであろう増分コストと
定義している(例:手数料、既存の借手にリースを解約してもらうインセンティブとして当該借手に支
払う金額)。借手及び貸手にとって、当初直接コストの定義は同じである。IFRS 第 16 号における当
初直接コストに関する規定は、IFRS 第 15 号の増分コストの概念と同じである。IAS 第 17 号では、
当初直接コストを、リース契約の交渉及び締結に直接起因する増分コストと定義しており、製造業者
又は販売業者である貸手に発生するコストは除かれる。
弊社のコメント
当初直接コストの定義の改訂に伴い、貸手の実務が変わる可能性がある。IAS第 17号で除外
されていた一般管理費の配賦額(例:給与)に加えて、リースの取得にかかわらず発生するコス
ト(例:特定の弁護士報酬)も貸手の当初直接コストの範囲から除かれる。
当初直接コストとは、リースを取得し
なければ発生しなかったであろう増
分コストである。
42 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
3.7.1 当初直接コストに関する貸手の会計処理
IFRS 第 16 号では、貸手が製造業者又は販売業者である場合を除き、貸手は、当初直接コストを
ファイナンス・リースにおける正味リース投資未回収額の当初測定に含め、リース期間にわたり認識
される収益から減額することが求められる。リースの計算利子率の定義では、当初直接コストは自
動的に正味リース投資未回収額に含まれるため、当該コストを別個に加算する必要はない。
貸手が製造業者又は販売業者である場合には、ファイナンス・リースに関連して発生した当初直接
コストは、リース開始時に費用で認識する。
IFRS第 16号では、オペレーティング・リースの場合、貸手は、当初直接コストを原資産の帳簿価額
に含める。したがって、当初直接コストは、リース収益と同じく、リース期間にわたり費用として認識さ
れる。
3.7.2 当初直接コストに関する借手の会計処理
IFRS第 16号では、借手は、当初直接コストを使用権資産の当初測定に含めることが求められる。
弊社のコメント
IAS 第 16 号が適用される資産の取得に関連して生じる一定のコストは、当初認識時点で資産
化する必要がある。しかし、IFRS第 16号は、使用権資産を経営者が意図した方法で稼働可能
にするために必要な場所及び状態に置くことに直接起因する借手のコストの会計処理について
は取り扱っていない。したがって、使用権資産の取得に関連するコストが他の IFRS(例えば IAS
第 16 号)の資産化の対象にならない場合、実務において、発生した時点で純損益に計上する
場合と IAS第 16号を類推適用して資産化する場合が見られる。
3.8 経済的耐用年数
IFRS第 16号からの抜粋
IFRS第 16号からの抜粋
付録 A
用語の定義
経済的耐用年数(economic life)
資産が1名又は複数の利用者により経済的に使用可能と見込まれる期間、あるいは資産から 1
名又は複数の利用者が得ると見込まれる生産物の数又は類似の単位
3.9 公正価値
IFRS第 16号からの抜粋
付録 A
用語の定義
公正価値(fair value)
本基準における貸手の会計処理の目的上、独立第三者間取引において、取引の知識がある自
発的な当事者の間で、資産が交換され得るか又は負債が決済され得る金額
貸手における公正価値の定義は、IAS第 17号の定義と同じである。これは、IAS第 17号における
貸手の会計処理モデルを実質的に引き継ぐとした IASBの決定によるものである。
43 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
4. 借手の会計処理
4.1 当初認識
IFRS第 16号からの抜粋
付録 A
用語の定義
短期リース (short-term lease)
開始日において、リース期間が 12 ヵ月以内であるリース。購入オプションを含んだリースは、短
期リースではない。
5 借手は、下記のものには第 22項から第 49項の要求事項を適用しないことを選択できる。
(a) 短期リース
(b) 原資産が少額であるリース(B3項から B8項に記述)
6 借手が、短期リース又は原資産が少額であるリースのいずれかに第 22 項から第 49 項の
要求事項を適用しないことを選択する場合には、借手は当該リースに関連したリース料を、
リース期間にわたり定額法又は他の規則的な基礎のいずれかにより費用として認識しなけ
ればならない。借手は、他の規則的な基礎の方が借手の便益のパターンをより適切に表す
場合には、当該基礎を適用しなければならない。
7 借手が短期リースを第 6 項を適用して会計処理する場合、借手は、次のいずれかであると
きは、本基準の目的上、当該リースを新たなリースとみなさなければならない。
(a) リースの条件変更がある場合
(b) リース期間に変更があった場合(たとえば、借手が過去にはリース期間の決定に含めてい
なかったオプションを行使した場合)
8 短期リースについての選択は、使用権が関連する原資産の種類ごとに行わなければならな
い。原資産の種類とは、性質及び企業の営業における用途が類似した原資産のグルーピ
ングである。原資産が少額であるリースについての選択は、リース 1 件ごとに行うことがで
きる。
22 開始日において、借手は使用権資産及びリース負債を認識しなければならない。
IFRS 第 16 号では、借手は、短期リース(セクション「4.1.1 短期リース 」参照)及び少額資産リー
ス(「4.1.2 少額資産リース」参照)の免除規定を適用する場合を除き、すべてのリースについて、
リース料総額を表す負債、及びリースの期間にわたり原資産を使用する権利(使用権資産)を表す
資産を認識する。
短期リース及び少額資産リースに関する会計方針の選択は、IFRS 第 16 号の適用に係るコスト及
び煩雑さを低減することが意図されている。ただし、借手は当該会計方針を選択する場合、短期
リース及び少額資産リースについて一定の定量的及び定性的開示を行う必要がある(セクション
「4.8 開示」(借手)参照)。
44 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
4.1.1 短期リース
借手は、IFRS第 16号の短期リースの定義を満たすリースについて、会計方針として IAS第 17号
のオペレーティング・リースと同様の会計処理(短期リース免除規定)を行うことができる。短期リー
スは、「開始日において、リース期間が 12 ヵ月以内であり、原資産を購入するオプションを含まない
リース」と定義される。
短期リースに係る免除規定は、使用権に関連する原資産の種類ごとに適用することができる。原
資産の種類とは、企業の営業活動における同様の性質及び使用方法に基づく原資産のグループ
である。
当該会計方針を選択した場合、借手は、リース負債及び使用権資産を貸借対照表で認識せずに、
リースに関連するリース料総額を、リース期間にわたり定額法又は他の規則的な方法で費用として
認識する。なお、他の規則的な方法は、借手の便益のパターンをより適切に表す場合に適用するこ
とが求められる。
リースが短期リースの定義を満たすかどうかを判断する際、借手は、他のすべてのリースと同じ方
法でリース期間を評価する(セクション「3.4 リース期間及び購入オプション」参照)。リース期間に
は、リースの解約不能期間に加えて、借手がリース期間の延長オプションを行使することが合理的
に確実である場合の延長オプションの対象期間、及び借手がリース期間の解約オプションを行使し
ないことが合理的に確実である場合の解約オプションの対象期間が含まれる。この判断はリースの
開始日時点で行うことになるので、リース期間が後に 12 ヵ月未満に短縮された場合でも、当該リー
スを短期リースに分類することはできない。なお、短期リースの定義を満たすためには、リースに原
資産の購入オプションが含まれていないことが要件となる。
リースの条件変更、又はリース期間に関する借手の評価の変更(例:借手がリース期間の算定に含
めていなかったオプションを行使する場合)が生じた場合、開始時点で短期リースの定義を満たして
いるリースは、新たなリースとして取り扱われる。当該新たなリースは、他の新たに契約したリースと
同様に、短期リースに係る免除規定の適用要件が満たされるどうかを判断する。
短期リースに係る会計方針の選択は、IFRS 第 16 号の適用に係るコスト及び複雑さを低減すること
が意図されている。ただし、借手は、当該会計方針を選択する場合、一定の定量的及び定性的開
示を行う必要がある(セクション「4.8 開示」参照)。
借手は、原資産の種類ごとに会計方針を定めた場合には、その後、当該種類に係るすべての短期
リースを、選択した会計方針に従って会計処理することになる。会計方針の変更の可能性がある場
合には、IAS第 8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従って評価する。
設例 15: 短期リース
シナリオA
借手は、解約不能期間が9ヵ月であり、さらに4ヵ月間リースを延長できるオプションが付された
リース契約を締結する。リースには購入オプションは含まれない。延長期間における月額リース
料は市場相場よりも著しく低いため、借手は、リース開始日時点で、リース期間の延長オプション
を行使することが合理的に確実であると判断している。
分析:リース期間(13ヵ月)は12ヵ月よりも長い。したがって、借手は、当該リースを短期リースと
して会計処理することはできない。
シナリオB
事実関係はシナリオAと同じとする。ただし、延長期間における月額リース料は市場相場と同じで
あり、また延長オプションの行使が合理的に確実となるその他の要因が存在しないことから、借手
は、リース開始時点で延長オプションを行使することが合理的に確実でないと判断している。
分析: リース期間は12ヵ月以下(9ヵ月)である。したがって、借手は、原資産の種類ごとに会計
方針の選択により、短期リースに係る免除規定に従って当該リースを会計処理することができ
る。当該会計方針を選択した場合、借手は、IAS第17号のオペレーティング・リースと同様に、
リース負債及び使用権資産を貸借対照表で認識せず、リース期間にわたり定額法又は別の規
則的な方法でリース料総額を費用として認識する。
借手は、会計方針の選択により、原
資産の種類ごとに、短期リースに関
する使用権資産及びリース負債を
認識しないことができる。
45 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
4.1.2 少額資産のリース
IFRS第 16号からの抜粋
B3 B7 項に定める場合を除き、本基準は、借手が原資産が少額であるリースの会計処理に第 6
項を適用することを認めている。借手は、リースされている資産の経過年数に関係なく、原資
産の価値を当該資産が新品である時点での価値に基づいて評価しなければならない。
B4 原資産が少額であるのかどうかの評価は、絶対値ベースで行われる。少額資産のリース
は、それらのリースが借手にとって重要性があるかどうかに関係なく、第 6 項における会計
処理の要件を満たす。その評価は、借手の規模、性質又は状況の影響を受けない。した
がって、異なる借手でも、特定の原資産が少額であるかどうかに関して同じ結論に至ると見
込まれる。
B5 原資産は、下記の場合にのみ、少額である可能性がある。
(a) 借手が原資産を単独で又は借手が容易に利用可能な他の資源と組み合わせて使用するこ
とから便益を得ることができ、かつ、
(b) 原資産の他の資産への依存性や相互関連性が高くない。
B6 資産が新品時に通常は少額ではない性質のものである場合には、原資産のリースは少額
資産のリースに該当しない。たとえば、自動車のリースは、新車は通常は少額ではないの
で、少額資産のリースに該当しないであろう。
B7 借手が資産を転貸しているか又は資産を転貸することを見込んでいる場合には、ヘッドリー
スは少額資産のリースに該当しない。
B8 少額の原資産の例としては、タブレット及びパーソナル・コンピュータ、小型の事務所備品、
電話などがある。
借手は、原資産の価値が少額である(少額資産)リースに関して、免除規定を選択することができ、
当該選択はリースごとにできる。この会計方針を選択した場合、借手は、リース負債及び使用権資
産を貸借対照表に認識せずに、リースに関連するリース料総額を、リース期間にわたり定額法又は
他の規則的な方法で費用として認識する。
借手は、リースの対象となる資産の経過年数に関係なく、当該資産の新品の価値に基づき原資産
の価値を評価する。原資産が少額であるか否かの評価は、絶対的な金額を基準に行う。つまり、少
額資産のリースに係る免除規定は、借手にとってそのリースが重要であるかどうかに関係なく要件
が満たされるものであり、この評価は、借手の規模、性質又は状況に左右されるものではない。した
がって、特定の原資産が少額資産に該当するかどうかの評価は、借手が異なる場合でも、同じ結論
に至ることが想定されている。IASB は、当該免除規定の導入に至る過程において、新品の価値が
5,000 米ドル以下の原資産を念頭に置いている。少額資産の例として、デスクトップ・パソコンや
ノート・パソコン、事務用小型備品、電話、ならびにその他の少額設備などが挙げられるが、新車は
通常少額ではないため、少額資産には該当しないと考えられる。
原資産が少額となり得るのは、以下の両方の要件を満たす場合のみである
• 借手は資産を単独で、又は借手が容易に入手できる他の資源と組み合わせて使用すること
で便益を得ることができる
• 原資産は他の資産に依存しない、又は密接に関連しない
たとえば、事業で使用するためにトラックをリースする場合、リースにはトラックのタイヤの使用も含
まれる。タイヤを意図した目的で使用するためには、トラックと合わせて使用するしかないため、この
タイヤはトラックに依存している、又は密接に関連していることになる。したがって、このタイヤは少
額資産の免除規定の要件を満たさないと考えられる。
なお、サブリース又はサブリースを予定している中間の貸手は、ヘッドリースを少額資産のリースと
して会計処理することはできない(セクション「5.2 中間の貸手の会計処理」参照)。
46 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
4.2 当初測定
4.2.1 使用権資産
IFRS第 16号からの抜粋
当初測定
使用権資産の当初測定
23 開始日において、借手は使用権資産を取得原価で測定しなければならない。
24 使用権資産の取得原価は、次のもので構成されなければならない。
(a) リース負債の当初測定の金額(第 26項に記述)
(b) 開始日以前に支払ったリース料から、受け取ったリース・インセンティブを控除したもの
(c) 借手に発生した当初直接コスト
(d) リースの契約条件で要求されている原資産の解体及び除去、原資産の敷地の原状回復又
は原資産の原状回復の際に借手に生じるコストの見積り。ただし、それらのコストが棚卸資
産の製造のために生じる場合は除く。借手は、開始日に又は原資産を特定の期間中に使
用した結果として、それらのコストに係る義務が生じる。
25 借手は、第 24 項(d)に記述したコストに対する義務が生じた時点で、当該コストを使用権
資産の取得原価の一部として認識しなければならない。借手は、棚卸資産を製造するため
に特定の期間中に使用権資産を使用した結果として当該期間中に生じたコストに IAS 第 2
号「棚卸資産」を適用する。本基準又は IAS 第 2 号を適用して会計処理したこうしたコスト
に係る義務の認識及び測定は、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」を適用して
行われる。
借手は使用権資産を取得原価で当初測定する。取得原価は以下のすべての項目により構成される。
• リース負債の当初測定額(セクション「4.2.2 リース負債」参照)
• リース開始日以前に支払われたリース料から、貸手より受領したリース・インセンティブを控除
した後の、開始日時点もしくはそれ以前に借手に支払ったリース料(セクション「3.5.2 リー
ス・インセンティブ」参照)
• 借手が負担する当初直接コスト(セクション「3.7 当初直接コスト」参照)
• 原資産の解体及び除去、原資産の設置場所の原状回復、又はリースの契約条件で定められ
ている状態に原資産を回復させるために借手に発生するコストの見積額(ただし、棚卸資産を
生産するために発生するコストを除く)
借手は当初測定時点で、解体、除去及び原状回復コストを使用権資産に含めなければならない。
当該コストは、リース開始時点で発生する場合もあれば、原資産を使用した結果として特定の期間
に発生する場合もある。棚卸資産を生産するために使用権資産を使用した結果として特定の期間
に生じるコストは、IAS第2号「棚卸資産」に従って会計処理する。解体、除去及び原状回復コストに
関連する負債は、IAS第 37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」に従って認識及び測定する。
47 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
4.2.2 リース負債
IFRS第 16号からの抜粋
リース負債の当初測定
26 開始日において、借手は、リース負債を同日現在で支払われていないリース料の現在価値
で測定しなければならない。当該リース料は、リースの計算利子率が容易に算定できる場
合には、当該利子率を用いて割り引かなければならない。当該利子率が容易に算定できな
い場合には、借手は借手の追加借入利子率を使用しなければならない。
27 開始日において、リース負債の測定に含められるリース料は、リース期間中に原資産を使
用する権利に対する下記の支払いのうち開始日に支払われていない金額で構成される。
(a) 固定リース料(B42項に記述している実質上の固定リース料を含む)から、受け取るリース・
インセンティブを控除した金額
(b) 変動リース料のうち、指数又はレートに応じて決まる金額。当初測定には開始日現在の指
数又はレートを用いる(第 28項に記述)
(c) 残価保証に基づいて借手が支払うと見込まれる金額
(d) 購入オプションを借手が行使することが合理的に確実である場合の、当該オプションの行
使価格(B37項から B40項に記述した要因を考慮して評価)
(e) リースの解約に対するペナルティの支払額(リース期間が借手によるリース解約オプション
の行使を反映している場合)
借手は、リース開始日時点で、リース期間にわたり支払うリース総額の現在価値でリース負債を当
初測定する。借手は、リース開始日時点で、上記セクション 2 及び 3 で解説した概念を適用して、
リースの構成部分を識別し、リース期間、リース料総額及び割引率を決定する。
4.3 事後測定
4.3.1 使用権資産
IFRS第 16号からの抜粋
使用権資産の事後測定
29 開始日後において、借手は、使用権資産に原価モデルを適用して測定しなければならな
い。ただし、第 34 項及び第 35 項に記述している測定モデルのいずれかを適用する場合
は除く。
原価モデル
30 原価モデルを適用するためには、借手は、使用権資産を取得原価に下記を加減した金額
で測定しなければならない。
(a) 減価償却累計額及び減損損失累計額を控除
(b) 第 36項(c)に定めているリース負債の再測定について調整
31 借手は、使用権資産を減価償却する際に IAS第 16号「有形固定資産」の減価償却の要求
事項を適用しなければならない。ただし、第 32項の要求事項の適用がある。
32 リースが原資産の所有権をリース期間の終了時までに借手に移転する場合、又は使用権
資産の取得原価が購入オプションを借手が行使するであろうことを反映している場合には、
借手は、使用権資産を開始日から原資産の耐用年数の終了時まで減価償却しなければな
らない。それ以外の場合には、借手は、使用権資産を開始日から使用権資産の耐用年数
の終了時又はリース期間の終了時のいずれか早い方まで減価償却しなければならない。
33 借手は、IAS 第 36 号「資産の減損」を適用して、使用権資産が減損しているかどうかを判
定し、識別された減損損失を会計処理しなければならない。
48 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号からの抜粋
他の測定モデル
34 借手が IAS第 40号「投資不動産」の公正価値モデルを投資不動産に適用する場合には、
借手はその公正価値モデルを IAS第 40号の投資不動産の定義を満たす使用権資産にも
適用しなければならない。
35 借手の使用権資産が、IAS 第 16 号の再評価モデルを適用する有形固定資産の種類に関
するものである場合には、借手はその再評価モデルを当該種類の有形固定資産に関連す
る使用権資産のすべてに適用することを選択できる。
借手は、原価モデルを適用して使用権資産の事後測定を行う(ただし、下記で説明する他の測定モ
デルを適用する場合を除く)。
原価モデル
借手は、原価モデルを適用する場合、取得原価から減価償却費累計額及び減損損失累計額を控
除して使用権資産の事後測定を行う。
借手は以下の規定に従って、IAS第16号の減価償却規定を適用して使用権資産の減価償却を行う。
リースが原資産の所有をリース期間が終了するまでに借手に移転する、又は使用権資産の取得原
価が、借手が購入オプションを行使することを反映している場合、借手は、リース開始日から原資産
の耐用年数が終了するまでの期間にわたり使用権資産を減価償却する。それ以外の場合には、借
手は、リース開始日から使用権資産の耐用年数が到来するまで、又はリース期間が終了するまで
のいずれか早い時点までの期間にわたり使用権資産を減価償却する。
使用権資産は、有形固定資産に関する現行基準の会計処理と整合する方法により減価償却を行う。
IAS 第 16 号は、減価償却の方法に関して、定額法、定率法及び生産高比例法などを挙げている。
IAS 第 16 号の要求事項では、減価償却が耐用年数にわたり資産から生じる便益の費消パターン
を表しており、各期間を通じて一貫して適用されることを重視している。
IAS 第 16 号はまた、取得原価に占める割合が重要な有形固定資産項目のそれぞれの構成部分
は別個に減価償却すると定めている。企業は、有形固定資産項目に関して当初認識した金額を重
要な構成部分に配分し、構成部分ごとに別個に減価償却する。たとえば、IAS 第 16 号に述べられ
るように、飛行機の胴体とエンジンを別個に減価償却することは適切である。多くの場合は、使用権
資産は、1 つの原資産又は重要な構成部分に関連し、よってコンポーネント・アプローチは必要にな
らない。しかし、耐用年数が異なる重要な構成部分からなる使用権資産については、コンポーネン
ト・アプローチの適用が必要かどうかを評価する必要がある。
借手は IAS第 36号「資産の減損」を適用して使用権資産が減損しているかどうかを判断し、識別し
た減損損失を会計処理する。
その他の測定モデル
借手は、投資不動産に関して IAS 第 40 号「投資不動産」の公正価値モデルを適用している場合、
当該モデルを IAS第 40号の投資不動産の定義を満たす使用権資産にも適用する。
使用権資産が、借手が IAS 第 16 号の再評価モデルを適用する種類の有形固定資産項目に関係
する場合、借手は、当該種類の有形固定資産に関連するすべての使用権資産に再評価モデルを
適用することができる。
49 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
4.3.2 リース負債
IFRS第 16号からの抜粋
リース負債の事後測定
36 借手は、開始日後において、リース負債を次のようにして測定しなければならない。
(a) リース負債に係る金利を反映するように帳簿価額を増額
(b) 支払われたリース料を反映するように帳簿価額を減額
(c) 第 39 項から第 46 項で定めている見直し又はリースの条件変更を反映するか、又は改訂
後の実質上の固定リース料(B42項参照)を反映するように帳簿価額を再測定
37 リース期間中の各期間におけるリース負債に係る金利は、リース負債の残高に対して毎期
一定の率の金利を生じさせる金額としなければならない。毎期の利率は、第 26項に記述し
た割引率、又は該当がある場合には、第 41 項、第 43 項若しくは第 45 項(c)に記述して
いる改訂後の割引率である。
38 開始日後において、借手は下記の両方を純損益に認識しなければならない。ただし、当該
コストが他の適用可能な基準を適用して他の資産の帳簿価額に算入される場合を除く。
(a) リース負債に係る金利
(b) リース負債の測定に含めなかった変動リース料(当該変動リース料が発生する契機となっ
た事象又は状況が生じた期間において)
IASB は結論の根拠(BC182 項)において、リース負債は、その他の金融負債と同様の方法(償却
原価法)で会計処理すべきと述べている。したがって、リース負債は、負債の残高に対して毎期一定
となる割引率を用いて増加させ(割引率の変更が求められる再評価が行われない限り、リース開始
時点で決められた割引率を使用する)、リース料の支払額はリース負債から減額する(セクション
「3.5.9 リース負債の再測定」及びセクション「4.5 リースの条件変更」参照)。
4.3.3 費用認識
借手は、リースに関して以下の項目を費用で認識する。
• 使用権資産の減価償却費
• リース負債に係る利息費用
• リース負債に含まれない変動リース料(例:指数又はレートに応じて決まるものではない変動
リース料)
• 使用権資産の減損損失
使用権資産の減価償却費及びリース負債に係る利息費用
借手は、リース開始日後に、使用権資産の減価償却費及びリース負債に係る利息費用を別個に認
識する。借手が定額法により使用権資産の減価償却を行う場合、各期間の費用合計(減価償却費
及び利息費用の合計)は、一般的に、リース期間の初期においてより多くなり、時の経過に伴い少
なくなる。これは、毎期一定の利子率がリース負債に適用されるため、リース期間中における現金
の支払いに伴いリース負債が減少し、それに応じて利息費用が減少するためである。したがって、
利息費用はリース期間の初期により多く発生し、時の経過に伴い少なくなる。利息費用がこのように
認識されることにより、使用権資産の減価償却を定額法で行う場合には、リース期間の初期により
多くの費用が認識される。この費用認識パターンは、IAS第 17号におけるファイナンス・リースの事
後測定と同じである。
変動リース料
借手は、開始日後において、リース負債の測定に含めていない変動リース料を、変動リース料の支
払いの原因となる事象又は状況が発生した期間に純損益で認識する。
借手は、一般的に、リース期間の
初期においてより多くの費用を認
識する。
50 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
使用権資産の減損
借手の使用権資産には、現行の減損に関する規定である IAS第 36号「資産の減損」が適用される。
借手は、使用権資産が減損していると判断した場合、減損損失を認識し、減損損失控除後の帳簿
価額で使用権資産を測定する。借手はその後、減損した時点から、使用権資産の耐用年数到来時
点、又はリース期間の終了時点までのいずれか短い期間にわたり、一般的には定額法により使用
権資産の減価償却を行う。ただし、借手が原資産の購入オプションを行使することが合理的に確実
である場合、又はリース期間の終了時までに原資産の所有権が借手に移転される場合には、減価
償却期間は原資産の残存耐用年数となる(セクション「4.6.1 使用権資産の減損」において、使用
権資産の減損に関して追加で解説している)。
4.3.4 設例 ― 借手の会計処理
設例 16 ―― 借手の会計処理
H社(借手)は、3年間にわたる機器のリース契約を締結する。H社は、各年度末において、第 1
年度 10,000 千円、第 2 年度 12,000 千円、第 3 年度 14,000 千円の支払いを行う。当該設
例では、単純化のために、リース料総額に関する他の項目は考慮しない(例:購入オプション、
リース開始日以前の貸手に対する支払い、貸手から受領するリース・インセンティブ、当初直接
コスト)。使用権資産及びリース負債の当初測定値は、33,000 千円である(約 4.235%の割引
率を使用して算定されるリース料総額の現在価値)。
H社は、リースの計算利子率を容易に算定することができないため、追加借入利子率を使用して
いる。H社は、使用権資産をリース期間にわたり定額法で減価償却する。
分析: H社はリース開始日に使用権資産及びリース負債を認識する。
使用権資産 33,000千円
リース負債 33,000千円
使用権資産及びリース負債を当初認識する。
第 1年度の仕訳は以下のとおりである。
利息費用 1,398千円
リース負債 1,398千円
実効金利法により、利息費用を計上し、リース負債を増加させる (33,000千円 x 4.235%)
減価償却費 11,000千円
使用権資産 11,000千円
使用権資産の減価償却費を計上する (33,000千円 ÷ 3年)
リース負債 10,000千円
現金 10,000千円
リース料を支払う
下記は、当該リース契約の会計処理をまとめたものである(再評価による変更が生じないことを
前提とする)(単位:千円)。
当初 1年目 2年目 3年目
現金によるリース料の支払い 10,000 12,000 14,000
認識されるリース費用
利息費用 1,398 1,033 569
減価償却費 11,000 11,000 11,000
期間費用合計 12,398 12,033 11,569
貸借対照表
使用権資産 33,000 22,000 11,000 —
リース負債 (33,000) (24,398) (13,431) —
51 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
4.4 リース負債の再測定
IFRS第 16号からの抜粋
39 開始日後において、借手は第 40項から第 43項を適用して、リース料の変動を反映するよ
うにリース負債を再測定しなければならない。借手はリース負債の再測定の金額を使用権
資産の修正として認識しなければならない。しかし、使用権資産の帳簿価額がゼロまで減
額されていて、さらにリース負債の測定の減額がある場合は、借手は再測定の残額を純損
益に認識しなければならない。
40 借手は、次のいずれかの場合には、改訂後のリース料を改訂後の割引率で割り引くことに
よって、リース負債を再測定しなければならない。
(a) リース期間の変化(第 20 項から第 21 項に記述)があった場合。借手は、改訂後のリース
料を改訂後のリース期間に基づいて算定しなければならない。
(b) 原資産を購入するオプションについての判定(第 20項から第 21項に記述した事象及び状
況を購入オプションの文脈で考慮して判定)に変化があった場合。借手は、改訂後のリース
料を購入オプションに基づいて支払われる金額の変動を反映するように算定しなければな
らない。
41 第 40項を適用するにあたり、借手は、改訂後の割引率を、リース期間の残り期間について
のリースの計算利子率(当該利子率が容易に算定できる場合)又は見直し日現在の借手
の追加借入利子率(リースの計算利子率が容易に算定できない場合)として決定しなけれ
ばならない。
42 借手は、次のいずれかの場合には、改訂後のリース料を割り引くことによってリース負債を
再測定しなければならない。
(a) 残価保証に基づいて支払われると見込まれる金額の変動がある場合。借手は、改訂後の
リース料を残価保証に基づいて支払うと見込まれる金額の変動を反映するように算定しな
ければならない。
(b) 将来のリース料の算定に使用される指数又はレートの変動(たとえば、市場賃料の調査後
に市場賃料率の変動を反映するための変更)による将来のリース料の変動がある場合。借
手は、キャッシュ・フローの変動があった場合(すなわち、リース料の修正が生じた場合)に
のみ、リース負債を改訂後のリース料を反映するように再測定しなければならない。借手
は、リース期間の残り期間についての改訂後のリース料を、改訂後の契約上の支払いに基
づいて算定しなければならない。
43 第 42 項を適用するにあたり、借手は割引率を変更せずに使用しなければならない。ただ
し、リース料の変動が変動金利の変動から生じている場合は除く。その場合には、借手は
金利の変動を反映した改訂後の割引率を使用しなければならない。
リースの条件が変更(当初のリースの契約条件に含まれていないリースの範囲又はリースの対価
の変更)され、当該変更が別個の契約として会計処理されない場合、借手は IFRS 第 16 号に従っ
てリース負債を再測定することが求められる。この点はセクション「4.5 リース負債の再測定」を参
照されたい。借手はまた、以下のどれか 1 つでも変更された場合には、リース料総額を再測定しな
ければならない。
• リース期間(セクション3.4.1 リース期間を参照)
• 借手が原資産を購入するオプションを行使することが合理的に確実かどうかの評価(セクショ
ン3.4.1.1 リース期間及び購入オプションの評価を参照)
• 残価保証により支払いが見込まれる金額(セクション3.5.6 残価保証により支払いが見込ま
れる金額 – 借手のみを参照)
• 指数又はレートの変動から生じる将来のリース料(セクション3.5.3 指数又はレートに応じて
決まる変動リース料を参照)
• 実質的に固定されたリース料(セクション3.5.1 実質的に固定されたリース料を参照)
52 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
借手は、リース期間の変更又は原資産の購入オプションに係る評価の変更によりリース料を変更す
る場合、変更後の割引率を用いる。割引率の変更は、リース期間の残存期間のリースの計算利子
率を基に行う。当該利子率を容易に算定できない場合、借手は、追加借入利子率を用いる。また、
リース料が、残余価値保証に関する予想金額及び指数又はレートに応じて変更される場合には、指
数もしくはレートが変動金利でない限り、当初の割引率を用いる。
リース契約に市場金利の調整(市場賃料の見直し)が含まれる場合、借手と貸手の交渉が決着する
までに一定の時間(交渉期間)を要する場合がある。たとえば、5 年経過時点で適用市場金利を調
整することを定めた、期間 10 年のリースを考える。市場賃料の見直しは、5 年目に開始されること
になるが、6年目以降にならないとその交渉は完了しない。6年目において、依然として交渉が続け
られるものの、借手は当初の契約に基づいたリース料を支払うことになる。交渉期間が終了した時
点(すなわち 6年目から 10年目までのリース料総額が最終的に決着した時点)で、新しいリース料
が 6年目のはじめに遡及的に適用される。
この設例では、借手は、賃料の予想される増加について6年目の期首時点でリース料を調整してい
ない。つまり、借手は、市場賃料の見直しが完了し、契約上のキャッシュ・フローが確定した段階で、
リース料を調整している。
4.5 リースの条件変更
IFRS第 16号からの抜粋
付録 A
用語の定義
リースの条件変更(lease modification)
リースの当初の契約条件の一部ではなかったリースの範囲又はリースの対価の変更(たとえ
ば、1つ若しくは複数の原資産を使用する権利の追加若しくは解約、又は契約上のリース期間の
延長又は短縮)
リース契約に条件変更が生じた場合(当初のリースの契約条件に含まれていないリースの範囲又
はリースの対価の変更が生じた場合)、条件変更後の契約がリースに該当するか、又はリースが含
まれているかどうかを評価する(セクション「2.1.7 契約の再評価」参照)。引き続きリースが存在す
る場合には、リースの条件変更に伴い以下のいずれかが生じる。
• 別個のリース(セクション「4.5.1 リースの条件変更により別個のリースが生じるかどうかの判
断」参照)
• 既存のリースの会計処理の変更(セクション「4.5.2 別個のリースが生じない条件変更に関
する借手の会計処理」参照)
既存の購入オプション又は延長オプションの行使、もしくはこれらのオプションの行使が合理的に確
実かどうかの評価の変更は、リースの条件変更に該当しないが、リース負債及び使用権資産の再
評価が求められる(セクション「3.5.9 リース負債の再測定」参照)。
4.5.1 リースの条件変更により別個のリースが生じるかどうかの判断
IFRS第 16号からの抜粋
44 借手は、下記の場合には、リースの条件変更を独立したリースとして会計処理しなければ
ならない。
(a) その条件変更が、1 つ又は複数の原資産を使用する権利を追加することによって、リース
の範囲を増大させており、かつ、
(b) 当該リースの対価が、範囲の増大分に対する独立価格及びその特定の契約の状況を反映
するための当該独立価格の適切な修正に見合った金額だけ増加している。
リースの条件変更とは、当初のリー
スの契約条件に含まれていない
リースの範囲又はリースの対価の
変更をいう。
53 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
借手は、以下の両方の要件に該当する場合、リースの条件変更(当初のリースの契約条件に含ま
れていないリースの範囲又はリースの対価の変更)を別個のリースとして会計処理する。
• 条件変更に伴い原資産を1つ以上使用する権利が追加され、リースの範囲が増大する場合
• リースの対価が、リースの範囲の増大に係る独立販売価格に相当する金額だけ増加し、特定
の契約状況を反映した調整が当該独立販売価格に行われている場合
リースの条件変更が上記の両要件に該当する場合、条件変更前の当初のリースと条件変更による
別個の新規リースの 2 つのリースが生じことになる。借手は、リースを含む別個の契約を、他の新
たに契約したリースと同じ方法で会計処理する(セクション「4.5.3 設例-リースの条件変更に関す
る借手の会計処理」における IFRS第 16号設例 15参照)。
リースの条件変更が上記のいずれかの要件に該当しない場合には、条件変更後のリースを別個の
リースとして会計処理してはならない(セクション「3.5.9 リース負債の再測定」参照)。
4.5.2 別個のリースが生じない条件変更に関する借手の会計処理
IFRS第 16号からの抜粋
45 リースの条件変更のうち独立したリースとして会計処理されないものについては、リースの
条件変更の発効日において、借手は次のことを行わなければならない。
(a) 条件変更後の契約における対価を第 13項から第 16項を適用して配分する。
(b) 条件変更後のリースのリース期間を第 18項から第 19項を適用して決定する。
(c) 改訂後のリース料を改訂後の割引率で割り引くことによって、リース負債を再測定する。改
訂後の割引率は、リース期間の残り期間についてのリースの計算利子率(当該利子率が容
易に算定できる場合)又は条件変更の発効日現在の借手の追加借入利子率(リースの計
算利子率が容易に算定できない場合)として決定される。
46 リースの条件変更のうち独立したリースとして会計処理されないものについては、借手は次
のことを行うことによってリース負債の再測定を会計処理しなければならない。
(a) リースの条件変更のうちリースの範囲を減少させるものについては、使用権資産の帳簿価
額をリースの部分的又は全面的な解約を反映するように減額する。借手は、リースの部分
的又は全面的な解約に係る利得又は損失を純損益に認識しなければならない。
(b) 他のすべてのリースの条件変更については、使用権資産に対して対応する修正を行う。
別個のリースが生じないリースの条件変更の場合、借手は契約対価を配分し(セクション「2.2.3.2
契約対価の配分-借手」参照)、リース負債を再測定する(条件変更後のリース期間及び条件変更
の効力発生日時点の割引率(原則として、リースの計算利子率。ただし、リースの残存期間に係る
リースの計算利子率を容易に算定できない場合には、追加借入利子率)を使用する)。
リースの条件変更により、リースの範囲の全部又は一部が減少する場合(例:リース対象の面積が
減少する場合)、IFRS第 16号では、借手は、リースの全部又は一部の解約として使用権資産の帳
簿価額を減額しなければならない。リース負債の減少額と使用権資産の減少額との差額は、条件
変更の効力発生日時点で純損益において認識する(セクション「4.5.3 設例-リースの条件変更に
関する借手の会計処理」における IFRS第 16号設例 17及び 18参照)。
一方、それ以外の別個のリースが生じないリースの条件変更の場合、IFRS第 16号では、借手は、
リース負債の再測定による差額を対応する使用権資産で調整するため、純損益が生じることはない
(セクション「4.5.3 設例-リースの条件変更に関する借手の会計処理」における IFRS 第 16 号設
例 16, 18及び 19参照)。
IASBは、結論の根拠(BC204項)において、当該アプローチによりリースの条件変更の実態を忠実
に表現し、リースに関する借手の権利及び義務の変更に対応するように利得又は損失を認識する
ことができると述べている。リースは、使用権資産とリース負債の両方を生じさせるため、リースの
条件変更に伴い借手の権利(使用権資産)、リース負債又はその両方が変更される。
54 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
場合によっては、借手と貸手が、後日開始するリース契約の条件変更に合意することがある(すな
わち、両当事者が合意する日付より後の日付で変更後の条件が有効になる)。たとえば、借手が資
産を 10 年間リースするリース契約を貸手と締結する。両者は、8 年目の期首時点で、9 年目の期
首時点から有効となる契約の条件変更に合意する。
• 条件変更により、別個のリースが生じることはないが、契約の範囲が増大する場合、借手は
条件変更後の契約に定められる対価を既存のリース構成部分と非リース構成部分に再配分
し、両当事者が条件変更に合意した日時点(8年目の期首時点)でリース負債を再測定する。
• 条件変更により別個のリース構成部分が生じるとしたら、借手は条件変更後の契約に定めら
れる対価を、両当事者の条件変更合意時点(8年目の期首時点)で、既存及び新規のリース
構成部分と非リース構成部分のそれぞれに配分する。借手はまた、同日に既存のリース構成
部分に係るリース負債を再測定する。ただし、新しいリースの構成部分に係るリース負債及び
使用権資産の認識は、新しいリース構成部分の開始日時点(9年目の期首時点)で行う。
• 条件変更により範囲が減少する場合、借手は条件変更後の契約に定められる対価を、それ
ぞれの既存のリース構成部分と非リース構成部分に再配分し、条件変更の発効日時点(8年
目の期首時点)でリース負債及び使用権資産を再測定する。
「付録 D:リースの再評価及び再測定に関する要求事項の概要」を参照されたい。
4.5.3 設例 ― リースの条件変更に関する借手の会計処理
IFRS第 16号からの抜粋 設例
例 15 — 独立したリースである条件変更
借手は、10年間にわたる 2,000平方メートルの事務所スペースのリース契約を締結する。第 6
年度の期首において、借手及び貸手は、残りの5年間について、当初のリース契約を変更し、同
じ建物の3,000平方メートルの事務所スペースを追加で借りることに合意する。追加した事務所
スペースは、第 6 年度の第 2 四半期末に借手が利用できるようになる。リースに係る合計対価
の増額は、新たな 3,000平方メートルの事務所スペースに対する現在の市場賃料に見合うもの
である。なお、貸手が同一のスペースを新たなテナントにリースする場合に生じたであろうコスト
(たとえば、マーケティング・コスト)が発生していないことから、借手は割引きを受けており、当該
金額を調整している。
借手は、当該条件変更を、当初の 10 年間のリースとは区分して、独立したリースとして会計処
理する。なぜならば、当該条件変更は、借手に原資産を使用する追加の権利を与えており、リー
スに係る対価の増加が、追加された使用権の独立価格(契約の状況を反映した調整後の独立
価格)に見合うためである。この例における追加の原資産は、新たな 3,000平方メートルの事務
所スペースである。したがって、新たなリースの開始日(第 6 年度の第 2 四半期末)に、借手は
追加した 3,000 平方メートルの事務所スペースのリースに係る使用権資産とリース負債を認識
する。借手は、当該条件変更により、当初の2,000平方メートルの事務所スペースに関するリー
スの会計処理を修正しない。
55 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号からの抜粋 設例
例 16 — 契約上のリース期間の延長によりリースの範囲が増加する条件変更
借手は、10年間にわたる 5,000平方メートルの事務所スペースのリース契約を締結する。年間
リース料は CU100,000 であり、各年度末に支払われる。リースの計算利子率を容易に算定す
ることはできない。開始日現在の借手の追加借入利子率は年 6%である。第 7 年度の期首に、
借手及び貸手は、当初のリース契約を変更し、契約上のリース期間を 4 年間延長することに合
意する。年間リース料の変更はない(第 7 年度から第 14 年度までの各年度末に CU100,000
が支払われる)。第 7年度の期首現在の借手の追加借入利子率は年 7%である。
条件変更の発効日(第7年度の期首)において、借手はリース負債を以下に基づいて再測定する。
(a) 残存リース期間 8年
(b) 年間支払額 CU100,000
(c) 借手の追加借入利子率 年 7%
条件変更後のリース負債は、CU597,130 となる。条件変更直前のリース負債は、CU346,511
である(第 6 年度末時点までの金利費用の認識を含む)。借手は、条件変更後のリース負債の
帳簿価額と条件変更直前のリース負債の帳簿価額との差額(CU250,619)を、使用権資産の調
整として認識する。
例 17—リースの範囲が減少する条件変更
借手は、10年間にわたる 5,000平方メートルの事務所スペースのリースを締結する。年間リース
料は CU50,0000 であり、各年度末に支払われる。リースの計算利子率を容易に算定することは
できない。開始日現在の追加借入利子率は、年 6%である。第 6 年度の期首に、借手及び貸手
は、当初のリースを変更して、第 6年度の第 1四半期末から事務所スペースを 2,500平方メート
ルまで減少させることに合意する。第 6 年度から第 10 年度までにおける年間の固定リース料は
CU30,000である。第 6年度の期首現在の借手の追加借入利子率は年 5%である。
条件変更の発効日(第6年度の期首)において、借手はリース負債を以下に基づいて再測定する。
(a) 残存リース期間 5年
(b) 年間支払額 CU30,000
(c) 借手の追加借入利子率年 5%
条件変更後のリース負債は CU129,884 となる。借手は、残りの使用権資産に基づいて(当初
の使用権資産の 50%に相当する 2,500 平方メートル)、比例的に減額させる使用権資産の帳
簿価額を算定する。
条件変更前の使用権資産(CU184,002)の 50%は CU92,001である。条件変更前のリース負
債(CU210,618)の 50%は CU105,309 である。したがって、借手は、使用権資産の帳簿価額
を CU92,001、リース負債の帳簿価額を CU105,309 だけ減額する。借手は、リース負債の減
額と使用権資産の減額との差額(CU105,309-CU92,001=CU13,308)を、条件変更の発効
日(第 6年度の期首)に利得として純損益で認識する。
借手は、残りのリース負債 CU105,309 と条件変更後のリース負債 CU129,884 との差額
(CU24,575)を、リースに係る支払対価の変動と修正後の割引率を反映した使用権資産の調整
として認識する。
56 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号からの抜粋 設例
例 18 — リースの範囲の増加及び減少を伴う条件変更
借手は、10年間にわたる 2,000平方メートルの事務所スペースのリース契約を締結する。年間
リース料は CU100,000 であり、各年度末に支払われる。リースの計算利子率を容易に算定す
ることはできない。開始日現在の借手の追加借入利子率は、年6%である。第6年度の期首に、
借手及び貸手は、当初のリースを次のように変更することに同意する。(a) 第 6 年度の期首か
ら、追加で同じ建物の 1,500 平方メートルの事務所スペースを含める、また、(b) リース期間を
10年から 8年に短縮する
3,500 平方メートルに係る年間の固定支払額は CU150,000 であり、各年度末に支払われる
(第 6年度から第 8年度)。第 6年度の期首現在の借手の追加借入利子率は、年 7%である。
範囲の増加を伴う 1,500 平方メートルのスペースに係る対価は、当該増加に係る独立価格(契
約の状況を反映した調整後の独立価格)に見合うものではない。したがって、借手は、範囲の増
加に伴う追加の 1,500平方メートルの使用権を、独立したリースとして会計処理しない。
当該リースに係る条件変更前の使用権資産とリース負債の額は、次のとおりである。
リース負債 使用権資産
期首残高 6%
支払利息
リース料
期末残高
期首残高
減価償却費
期末残高
年度 CU CU CU CU CU CU CU
1 736,009 44,160 (100,000) 680,169 736,009 (73,601) 662,408
2 680,169 40,810 (100,000) 620,979 662,408 (73,601) 588,807
3 620,979 37,259 (100,000) 558,238 588,807 (73,601) 515,206
4 558,238 33,494 (100,000) 491,732 515,206 (73,601) 441,605
5 491,732 29,504 (100,000) 421,236 441,605 (73,601) 368,004
6 421,236 368,004
条件変更の発効日(第6年度の期首)において、借手はリース負債を以下に基づいて再測定する。
(a) 残存リース期間 3年
(b) 年間支払額 CU150,000
(c) 借手の追加借入利子率 年 7%
条件変更後のリース負債は CU393,647 となる。この内、 (a) CU131,216 は、第 6 年度から
第 8年度の年間リース料の増加 CU50,000に関するものであり、(b) CU262,431は、第 6年
度から第 8年度までの残りの 3年間の年間リース料 CU100,000に関するものである。
57 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号からの抜粋 設例
リース期間の短縮
条件変更の発効日(第 6年度の期首)において、条件変更前の使用権資産は CU368,004であ
る。借手は、当初の 2,000 平方メートルの事務所スペースに係る残りの使用権資産(当初の 5
年間のリース期間ではなく、残りの 3 年間のリース期間)に基づいて、比例的に減額させる使用
権資産の帳簿価額を算定する。当初の 2,000 平方メートルの事務所スペースに係る残りの使
用権資産は、CU220,802(CU368,004÷5×3年)である。
条件変更の発効日(第 6 年度の期首)において、条件変更前のリース負債は CU421,236 であ
る。当初の 2,000 平方メートルの事務所スペースに係る残りのリース負債は、CU267,301(3
年間分のリース料 CU100,000を当初の割引率年 6%で割り引いた現在価値)である。
したがって、借手は、使用権資産の帳簿価額を CU147,202(CU368,004-CU220,802)、
リース負債の帳簿価額を CU153,935(CU421,236-CU267,301)だけ減額する。借手は、
リース負債の減額と使用権資産の減額の差額(CU153,935-CU147,202=CU6,733)を、条
件変更の発効日(第 6年度の期首)に利得として純損益で認識する。
リース負債 CU153,935
使用権資産 CU147,202
利得 CU6,733
条件変更の発効日(第 6 年度の期首)において、借手は、残りのリース負債を変更後の割引率年
7%で再測定した影響額 CU4,870(CU267,301-CU262,431)を、使用権資産で調整する。
リース負債 CU4,870
使用権資産 CU4,870
リース・スペースの増加
追加の 1,500 平方メートルの事務所スペースに係るリースの開始日(第 6 年度の期首)に、借
手は、範囲の増加に伴うリース負債の増加 CU131,216(3 年間分のリース料 CU50,000 を変
更後の割引率年 7%で割り引いた現在価値)を、使用権資産で調整する。
リース負債 CU131,216
使用権資産 CU131,216
条件変更後の使用権資産及びリース負債の額は、以下のとおりである。
リース負債 使用権資産
期首残高
7%
支払利息
リース料
期末残高
期首残高
減価償却費
期末残高
年 CU CU CU CU CU CU CU
6 393,647 27,556 (150,000) 271,203 347,148 (115,716) 231,432
7 271,203 18,984 (150,000) 140,187 231,432 (115,716) 115,716
8 140,187 9,813 (150,000) - 115,716 (115,716) -
58 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号からの抜粋 設例
例 19 — 対価のみを変更する条件変更
借手は、10年間にわたる5,000平方メートルの事務所スペースに係るリース契約を締結する。第
6年度の期首に、借手及び貸手は、残りの 5年間について、当初のリースを変更して、リース料を
年CU100,000から年CU95,000に減額することに合意する。リースの計算利子率を容易に算定
することはできない。開始日現在の借手の追加借入利子率は、年 6%である。第 6年度の期首現
在の借手の追加借入利子率は、年 7%である。年間リース料は各年度末に支払われる。
条件変更の発効日(第6年度の期首)において、借手はリース負債を以下に基づいて再測定する。
(a) 残存リース期間 5年
(b) 年間支払額 CU95,000
(c) 借手の追加借入利子率 年 7%
借手は、条件変更後のリース負債の帳簿価額(CU389,519)と条件変更直前のリース負債の帳
簿価額(CU421,236)の差額 CU31,717を、使用権資産で調整する。
4.6 借手に関するその他の事項
4.6.1 使用権資産の減損
IFRS第 16号からの抜粋
33 借手は、IAS 第 36 号「資産の減損」を適用して、使用権資産が減損しているかどうかを判
定し、識別された減損損失を会計処理しなければならない。
借手の使用権資産には、現行の減損に関する基準である IAS第 36号「資産の減損」が適用される。
IAS 第 36 号は、各報告期間において、減損の兆候の有無を識別することを求めている。減損の兆
候が存在する場合、資産(又は資産が含まれる資金生成単位(CGU))の回収可能価額を見積もる
ことになる。CGUの回収可能価額が CGUの帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識する。減
損損失を認識した場合、減損損失控除後の使用権資産の帳簿価額が減価償却の新たな基礎とな
る金額になる。
過去に認識された減損損失がもはや存在しないか、又は減少している可能性を示す兆候が存在す
る場合には、過去に認識された減損損失を事後的に戻入れるかどうかを評価する必要がある。減
損の戻入れによって増加した資産の帳簿価額は、減損がなかったとした場合の減価償却控除後の
帳簿価額を超えてはならない。
借手は、IAS 第 17 号においてファイナンス・リースにより保有される資産にも同じ減損の規定を適用
する。IAS第 17号においてオペレーティング・リースとして会計処理されているリースの場合、新たに
減損の規定が適用されることになるため、費用の認識時期に重要な影響を与える可能性がある。
弊社のコメント
IAS 第 17 号において貸借対照表に認識されていないリース(オペレーティング・リース)に関し
て、使用権資産の減損テストの実施により減損損失が発生する場合には、費用が認識される可
能性がある。
59 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
4.6.2 外貨建てのリース
借手は、外貨建てのリースに IAS第 21号「外国為替レートの変動の影響」を適用する。借手は、他
の貨幣性負債と同様に、外貨建てリース負債を各報告日時点の為替レートを使用して再測定する。
為替レートの変動によるリース負債の変動は純損益で認識する。使用権資産は取得原価で測定さ
れる非貨幣性資産に該当するため、為替レートの変動の影響は受けない。IASB は、結論の根拠
(BC199 項)において、当該アプローチにより、外国為替変動による利得又は損失の認識により純
損益が変動することを認識しているが、当該純損益が為替レートの変動からのみ生じていることは、
財務諸表の利用者にとって明らかであると述べている。
4.6.3 ポートフォリオの適用
IFRS第 16号からの抜粋
B1 本基準は、個々のリースの会計処理を定めている。しかし、実務上の便法として、企業は本
基準を特性の類似したリースのポートフォリオに適用することができる。そのための条件
は、本基準をポートフォリオに適用することが財務諸表に与える影響が本基準を当該ポート
フォリオの中の個々のリースに適用した場合と重要な相違がないと企業が合理的に見込ん
でいることである。ポートフォリオを会計処理する場合には、企業はポートフォリオの規模及
び構成を反映した見積り及び仮定を使用しなければならない。
IFRS 第 16 号は、原則として個々のリース毎に適用されるが、同種資産のリース(例:複数の同種
車両のリース)を多く有している場合には、個々のリース毎に会計処理を行うことが困難になる場合
がある。IASB は、結論の根拠(BC83 項)において、このような懸念に対処するために、ポートフォリ
オにおける個々のリースに IFRS 第 16 号を適用した場合でも財務諸表に重要な影響はないと合理
的に見込んでいる場合には、実務上の簡便法として、同様の特徴を有するリースにポートフォリオ・
アプローチを認めたと述べている。
弊社のコメント
IASBは、IFRS 第 16 号において、IFRS 第 15 号と同じポートフォリオ・アプローチを適用するこ
とを認めた。ポートフォリオ・アプローチは、財務諸表における重要な会計上の相違が見込まれ
ていない場合において、一定のリースを資産として認識することなく、費用計上する現行の実務
に類似している。
4.6.4 法人所得税の会計処理
IFRS 第 16 号は、借手の法人所得税の会計処理に影響を与える可能性がある。借手は、IFRS 第
16号において、IAS第17号では貸借対照表に認識されることのないリース(オペレーティング・リー
ス)に関して資産及び負債を認識することが求められており、当該リースに関連する資産及び負債
の測定が変更される可能性がある。当該変更が法人所得税の会計処理に与える影響は、以下が
挙げられる。
• 繰延税金資産及び負債の認識及び測定
• 繰延税金資産の回収可能性の評価
60 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
4.7 表示
IFRS第 16号からの抜粋
47 借手は、下記の内容を貸借対照表に表示するか、又は注記で開示しなければならない。
(a) 使用権資産(他の資産と区分して)。借手が使用権資産を貸借対照表において区分表示し
ない場合には、借手は次のことを行わなければならない。
(i) 使用権資産を、対応する原資産が自社所有であったとした場合に表示されるであろう
表示項目に含める。
(ii) 貸借対照表のどの表示項目が当該使用権を含んでいるのかを開示する。
(b) リース負債(他の負債と区分して)。借手がリース負債を貸借対照表において区分表示しな
い場合には、借手は貸借対照表のどの表示項目が当該負債を含んでいるのかを開示しな
ければならない。
48 第 47項(a)の要求は、投資不動産の定義を満たす使用権資産には適用されず、当該資産
は貸借対照表において投資不動産として表示しなければならない。
49 純損益及びその他の包括利益の計算書において、借手は、リース負債に係る金利費用を
使用権資産に係る減価償却費と区分して表示しなければならない。リース負債に係る金利
費用は、財務コストの内訳項目であり、IAS 第 1 号「財務諸表の表示」の第 82 項(b)で純
損益及びその他の包括利益の計算書において区分表示することが要求されている。
50 借手は、キャッシュ・フロー計算書において、次のような分類をしなければならない。
(a) リース負債の元本部分に対する現金支払いを財務活動に含める。
(b) リース負債の金利部分に対する現金支払いに、IAS第 7号「キャッシュ・フロー計算書」にお
ける支払利息に関する要求事項を適用する。
(c) 短期リース料、少額資産のリース料及びリース負債の測定に含めなかった変動リース料
を、営業活動に含める。
使用権資産及びリース負債は、他の資産及び負債と同じ検討を踏まえて、貸借対照表において流
動又は非流動の区分に分類する。
以下の表では、リース取引に関連する金額に係る借手の財務諸表の表示方法を示している。
財務諸表 借手の表示
貸借対照表 • 使用権資産は以下のいずれかの方法で表示する。
• 他の原資産(例:自己所有資産)と区分して表示する。
• 原資産として所有していた場合と同じ表示科目に含めて表示
し、使用権資産が含まれる貸借対照表の表示科目及びその金
額を注記で開示する。
• 投資不動産の定義を満たす使用権資産は投資不動産として表示
する。
• リース負債は以下のいずれかの方法で表示する。
• 他の負債と区分して表示する。
• 他の負債に含めて表示し、リース負債が含まれる貸借対照表
の表示科目及びその金額を注記で開示する。
損益計算書 リースに関連する減価償却費及び金利費用を区別して表示する(リース
に関連する減価償却費と金利費用を合算してはならない)。リース負債に
係る金利費用は金融費用の一部となる。
キャッシュ・フロー
計算書 • リース負債の元本の返済は財務活動に表示する。
• リース負債に係る金利の支払いは、IAS 第 7 号「キャッシュ・フロー
計算書」における会計方針に従って表示する。
• 貸借対照表に認識されない少額資産のリース及び短期リースに係
るリース料、ならびにリース負債に含まれていない変動リース料の支
払いは営業活動に表示する。
• 非資金取引(例:リース開始時の当初認識)は、非資金取引に関す
る情報を注記で開示する。
61 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
4.8 開示
4.8.1 開示の目的
IFRS第 16号からの抜粋
開示
51 開示の目的は、借手が注記において、貸借対照表、純損益計算書及びキャッシュ・フロー計算
書で提供される情報と合わせて、リースが借手の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フロー
に与えている影響を財務諸表利用者が評価するための基礎を与える情報を開示することであ
る。第 52項から第 60項は、当該目的を満たす方法に関する要求事項を定めている。
借手の開示の目的は、リースが借手の財務諸表に与える影響(例:リースから生じるキャッシュ・フ
ローの金額、時期及び不確実性)を財務諸表の利用者が理解できるようにすることである。IASB は、
結論の根拠(BC215 項)において、借手がリースに関する開示全体の質及び情報価値が IFRS 第
16 号の目的を十分に満たしているかどうかを評価することにより、借手の開示に関する規定の解
釈及び適用が改善すると述べている。
IFRS 第 16号によると、借手はすべての注記をひとまとめにして、又は関連する注記に含めて開示
することになる。IASBは、結論の根拠(BC228項)において、IAS第 1号「財務諸表の表示」第 113
項で規定されている方法でリースに関する情報を提供することが、最も効果的であることが多いと
述べている。
4.8.2 資産、負債、費用及びキャッシュ・フローの開示
IFRS第 16号における借手の開示に関する要求事項は、以下のとおりである。
IFRS第 16号からの抜粋
53 借手は、報告期間についての下記の金額を開示しなければならない。
(a) 使用権資産の減価償却費(原資産のクラス別に)
(b) リース負債に係る金利費用
(c) 第 6 項を適用して会計処理した短期リースに係る費用。この費用にはリース期間が1ヵ月
以下のリースに係る費用を含める必要はない。
(d) 第 6 項を適用して会計処理した少額資産のリースに係る費用。この費用には第 53 項(c)
に含まれている少額資産の短期リースに係る費用を含めてはならない。
(e) リース負債の測定に含めていない変動リース料に係る費用
(f) 使用権資産のサブリースによる収益
(g) リースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額
(h) 使用権資産の増加
(i) セール・アンド・リースバック取引から生じた利得又は損失
(j) 報告期間の末日現在の使用権資産の帳簿価額(原資産のクラス別に)
54 借手は、第 53項で定めている開示を表形式で提供しなければならない。ただし、別の様式
が適切である場合は除く。開示する金額には、借手が当報告期間中に他の資産の帳簿価
額に含めたコストを含めなければならない。
55 借手は、報告期間末で契約済みの短期リースのポートフォリオが、第 53 項(c)を適用して
開示した短期リース費用が関連している短期リースのポートフォリオと異質である場合に
は、第 6 項を適用して会計処理した短期リースに係るリース約定の金額を開示しなければ
ならない。
56 使用権資産が投資不動産の定義を満たしている場合には、借手は IAS 第 40 号の開示要
求を適用しなければならない。その場合、借手は当該使用権資産について第 53項の(a)、
(f)、(h)又は(j)の開示を提供することを要求されない。
62 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号からの抜粋
57 借手が使用権資産を IAS第 16号を適用して再評価額で測定している場合には、借手は、
当該使用権資産について IAS第 16号の第 77項で要求している情報を開示しなければな
らない。
58 借手は、リース負債の満期分析を、他の金融負債の満期分析とは区分して、IFRS 第 7 号
「金融商品:開示」の第 39項及び B11項を適用して開示しなければならない。
借手は、以下の情報を開示する。当該情報は、財務諸表の利用者にとって最も有用であると考えら
れる。
• 原資産の種類ごとに区分した使用権資産の帳簿価額及び減価償却費
• リース負債に係る金利費用
• リース期間が1ヵ月以上の短期リースに係るリース費用
• 少額資産のリースに係るリース費用(短期リースに該当する場合を除く)
• 変動リースに係るリース費用(リース負債に含まれていない変動リース料)
• 使用権資産のサブリースから生じる収益
• リースのキャッシュ・アウトフロー合計額
• 使用権資産の増加額
• セール・アンド・リースバック取引から生じる利得及び損失
• 原資産の種類ごとに区分した使用権資産の期末帳簿価額
上記の開示は、他の形式の方が適切である場合を除き、表形式で表示することが求められる。開示
される金額には、借手が報告期間に他の資産の帳簿価額に含めたコストも含まれる。
さらに借手は、IFRS 第 7 号「金融商品」第 39 項及び B11 項に従い、リース負債の満期分析を他
の金融負債と区別して開示する。IASB は、結論の根拠(BC222 項)において、借手の会計モデル
が、リース負債は金融商品であるという前提に立っており、他の金融負債に適用される満期分析の
開示規定をリース負債に適用することが適切であると述べている。
借手は、報告期間の末日において、短期リースに関するコミットメントが同一期間の短期リースと異
なる性質を有している場合には、当該短期リースのコミットメントの金額を開示する。
投資不動産の定義を満たす使用権資産に関しては、IFRS 第 16 号第 53 項(a)、(f)、(h)及び(j)
を開示する必要はない。ただし、借手は IAS第 40号の開示規定を適用することが求められる。
借手は、IAS第 16号を適用して使用権資産を再測定する場合、使用権資産に関して IAS第 16号
第 77項で規定されている情報を開示しなければならない。
弊社のコメント
IFRS第16号は、リースのキャッシュ・アウトフロー合計額の開示を求めている。なお、少額資産
のリース及び短期リースは当該開示の範囲から明確に除外されていないため、これらのリース
もキャッシュ・アウトフローの開示の範囲に含まれると EYは考えている。
63 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
4.8.3 追加の開示
IFRS第 16号からの抜粋
59 第 53項から第 58項で要求している開示に加えて、借手は、自らのリース活動について第
51 項の開示目的を満たすために必要な追加の定性的情報及び定量的情報(B48 項に記
述)を開示しなければならない。この追加的な情報には、財務諸表利用者が下記のことを評
価するのに役立つ情報が含まれる場合があるが、これらに限らない。
(a) 借手のリース活動の性質
(b) 借手が潜在的に晒されている将来キャッシュ・アウトフローのうちリース負債の測定に反映
されていないもの。これには、下記から生じるエクスポージャーが含まれる。
(i) 変動リース料(B49項に記述)
(ii) 延長オプション及び解約オプション(B50項に記述)
(iii) 残価保証(B51項に記述)
(iv) 借手が契約しているがまだ開始していないリース
(c) リースにより課されている制限又は特約
(d) セール・アンド・リースバック取引(B52項に記述)
60 短期リース又は少額資産のリースを第 6 項を適用して会計処理している借手は、その旨を
開示しなければならない。
借手は追加的な情報を提供するにあたって以下を検討する。
(a) 当該情報が財務諸表の利用者にとって目的適合性があるかどうか。上記に定められる情報
は、財務諸表の利用者にとって目的適合性があると予想される場合にのみ含める。利用者が
以下を理解するのに役立つ場合には、追加的な情報は目的適合性がある。
(i) リースが提供している柔軟性。たとえば、借手が解約オプションを行使する、又は有利
な条件でリースを更新することでエクスポージャーを減少させることができる場合には、
リースは借手に柔軟性を提供している可能性が高い。
(ii) リースにより課される制限。リース契約の内容によっては、たとえば、特定の財務比率
を維持することを借手に要求することにより、借手に一定の制限を課す場合がある。
(iii) 報告される情報の主要な変数に対する感応度。報告される情報が、たとえば、将来の
変動リース料に対して重要な影響を与える可能性がある場合がある。
(iv) リースから生じる他のリスクに対するエクスポージャー
(v) 業界慣行からの逸脱。逸脱の例としては、借手のリース・ポートフォリオに影響を及ぼ
す通例でないもしくは独特のリース条件が挙げられる。
(b) 当該情報が基本財務諸表に表示されている情報又は注記で開示されている情報で明らかに
なっているかどうか。借手は、財務諸表のいずれかの箇所ですでに表示している情報を繰り
返す必要はない。
変動リース料に関する追加的な情報のうち、状況に応じて、開示目的を満たすために必要となる可
能性のある情報には、財務諸表利用者が、たとえば以下を評価する際に役立つ情報が含まれる場
合がある。
(a) 借手が変動リース料を使用する理由及びそのような支払いが一般的かどうか
(b) 変動リース料の固定リース料に対する相対的な大きさ
(c) 変動リース料が依存する主要な変数及び当該主要な変数の変動に対応してどのように変動
するのか
(d) 変動リース料が他の業務及び財務に及ぼす影響
64 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
延長オプション又は解約オプションに関する追加的な情報のうち、状況に応じて、開示目的を満たす
ために必要となる可能性のある情報には、財務諸表利用者が、たとえば以下を評価する際に役立
つ情報が含まれる場合がある。
(a) 借手が延長オプション又は解約オプションを使用する理由及びそれらのオプションが一般的
かどうか
(b) オプション・リース料のリース料総額に対する相対的な大きさ
(c) リース負債の測定に含まれていなかったオプションの行使が一般的かどうか
(d) 当該オプションが他の業務及び財務に及ぼす影響
オプション・リース料とは、リースを延長又は解約するオプションの対象期間のうち、リース期間に含
まれていない期間において原資産を使用する権利に対して借手が貸手に行う支払いをいう。
残価保証に関する追加的な情報のうち、状況に応じて、開示目的を満たすために必要となる可能性
のある情報には、財務諸表利用者が、たとえば、以下を評価する際に役立つ情報が含まれる場合
がある。
(a) 借手が残価保証を提供する理由及び当該保証が一般的かどうか
(b) 残存価値リスクに対する借手のエクスポージャーの大きさ
(c) 当該保証が提供される原資産の性質
(d) 当該保証が他の業務及び財務に及ぼす影響
65 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
5. 貸手の会計処理
IFRS 第 16 号は、IAS 第 17 号の貸手の会計処理モデルを実質的に引き継いでいるが、IFRS 第
16 号における借手の会計モデルの決定が、貸手の会計処理に影響を与えている。その結果として、
IFRS第 16号と IAS第 17号の貸手の会計処理規定に差異を生じている。IFRS第 16号の適用に
より、サブリース、当初直接コストの会計処理や、開示において、貸手の会計モデルが変更される可
能性がある。
5.1 リースの分類
IFRS第 16号からの抜粋
61 貸手は、それぞれのリースをオペレーティング・リース又はファイナンス・リースのいずれか
に分類しなければならない。
62 リースが、原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合には、
ファイナンス・リースに分類される。原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべ
てを移転するものではない場合には、リースはオペレーティング・リースに分類される。
B53 本基準における貸手についてのリースの分類は、リースが原資産の所有に伴うリスクと経
済価値をどの程度移転するのかを基礎としている。リスクには、操業休止又は技術的陳腐
化による損失や経済状況の変化によるリターンの変動の可能性が含まれる。経済価値は、
原資産の経済的耐用年数にわたる収益性の高い営業の期待及び価値の増価又は残存価
値の実現から生じる利得で表される場合がある。
B54 リース契約には、契約日と開始日との間に生じる特定の変化(貸手の原資産の取得原価の
変化又は貸手のリース融資コストの変化)についてリース料を調整するための契約条件が
記載される場合がある。その場合、リースの分類の目的上、このような変化の影響は契約
日に生じたものとみなさなければならない。
貸手は、リースの契約日にすべてのリースをファイナンス・リース又はオペレーティング・リースに分
類する。リースの分類により、貸手のリース収益の認識方法及び認識時期、ならびに計上すべき資
産の内容が決まる。以下で示しているリースの分類要件は、IAS第 17号と同じである。
5.1.1 リースの分類要件
IFRS 第 16 号におけるリースの分類は、IAS 第 17 号から変更されていない。リースの分類は、原
資産の所有に伴うリスクと経済価値を貸手又は借手がどの程度有しているかにより決定される。こ
の分類は、契約の形式ではなく、取引の実質に応じて決まる。
IFRS 第 16 号で示されている、単独で又は組み合わせにより、通常はファイナンス・リースに分類さ
れる状況の例は、以下のとおりである。
• 当該リースにより、リース期間の終了までに借手に資産の所有権が移転される
• 借手が、オプションが行使可能となる日の公正価値よりも十分に低いと予想される価格で原
資産を購入するオプションを有していることにより、当該オプションが行使されることは契約日
において合理的に確実である
• 所有権が移転しない場合でもリース期間が原資産の経済的耐用年数の大部分を占める
• 契約日において、リース料の現在価値が、少なくとも原資産の公正価値のほとんどすべてと
なる
• 原資産が特殊な性質のものであり、借手のみが重要な改変なく使用できる
IFRS第16号は、IAS第17号におけ
る貸手の会計処理モデルを実質的
に引き継いでいる。
66 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号で示されている、単独で又は組み合わせにより、リースがファイナンス・リースとして分
類される可能性のある指標は、以下のとおりである。
• 借手がリース契約を解約できる場合に、当該解約に関連する貸手の損失を借手が負担する
• 残存資産の公正価値の変動による利得又は損失が、借手に帰属する(例:リースの終了時に
おいて売却収入とほぼ同額の賃借料の割戻しを受ける)
• 借手が、市場相場よりも著しく低い賃借料で次期のリース契約を継続できる
上記に加えて、下記事項の検討により、リース契約の経済的実態を判断することもできると、EY は
考えている。
• 賃借料は、資産の市場相場における使用料(オペレーティング・リースであることを示す指標)
に基づいているか、又は資金の調達利子率(ファイナンス・リースであることを示す指標)に基
づいているか
• リース契約にプット・オプション及びコール・オプションが含まれているか。オプションが含まれ
ている場合、事前に定められた価格又は算定方法によりオプションの行使が可能か(フィナン
ス・リースであることを示す指標)、又はオプションの行使時における市場価格でオプションの
行使が可能か(オペレーティング・リースであることを示す指標)
5.1.2 土地及び建物のリースの分類判定
土地と建物の両方の要素を含むリースについては、貸手は、土地の経済的耐用年数は通常は確定
できないということに留意した上で、それぞれの要素をファイナンス・リース又はオペレーティング・
リースのいずれかに分類する。貸手は、契約締結日における、リースの土地要素と建物要素の公
正価値の比率により、対価を土地要素と建物要素に配分する。リース料を、これらの 2 つの要素に
信頼性をもって配分できない場合には、両方の要素がオペレーティング・リースであることが明らか
である場合を除き、リース全体をファイナンス・リースに分類する。オペレーティング・リースであるこ
とが明らかである場合は、リース全体をオペレーティング・リースに分類する。
土地要素に係る金額が当該リースに対して重要性がないものについては、貸手は、土地と建物を
リースの分類上、単一の単位として扱い、ファイナンス・リースもしくはオペレーティング・リースのい
ずれかに分類する。その場合、貸手は、建物の経済的耐用年数を、原資産全体の経済的耐用年数
とみなす。
5.1.3 リースの分類判定で考慮される残価保証
貸手は、IFRS 第 16 号におけるリースの分類要件を評価する際に、貸手とは関係のない第三者に
よって提供される残価保証がある場合、「ほとんどすべて」の判定に当該金額(債務の最大金額)を
考慮することが求められる。
5.1.4 リースの分類の再評価
IFRS第 16号からの抜粋
66 リースの分類は契約日に行われ、リースの条件変更があった場合にのみ見直しが行われ
る。見積りの変更(たとえば、原資産の経済的耐用年数若しくは残存価値の見積りの変更)
又は状況の変化(たとえば、借手の契約不履行)は、会計処理の目的上、リースの分類の
変更を生じない。
貸手は、リースの条件変更(当初のリースの契約条件に含まれていないリースの範囲又はリースの
対価の変更)があった場合にのみ、リースの分類を見直すことになる。
貸手は、リースの条件変更の効力発生日において、条件変更の内容を踏まえてリースの分類を再
検討する。リースの条件変更に伴い別個の新たなリースが識別された場合には、他の新たに契約し
たリースと同じ方法でリースの分類を行う(セクション「5.5 リースの条件変更」参照。貸手の再評価
及び再測定に関する要求事項の概要は付録 D を参照)。
67 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
5.2 貸手が適用する主要な概念
IFRS第 16号からの抜粋
付録 A
用語の定義
リース投資未回収総額
次の合計額
(a) ファイナンス・リースにおいて貸手が受け取るべきリース料
(b) 貸手に発生している無保証残存価値
正味リース投資未回収額
リース投資未回収総額をリースの計算利子率で割り引いた額
無保証残存価値
原資産の残存価値のうち、貸手による実現が確実でないか、又は貸手と関連のある者のみが保
証している部分
貸手は、リース開始時点において、原資産の当初直接コスト、リース期間、リース料総額、公正価値
及びリースの計算利子率の決定など、セクション 3 で解説した主要な概念を適用する。また、貸手
はリースを認識及び測定するために、以下で示す会計処理の概念を適用する。
リース投資未回収総額
貸手のリース投資未回収総額は、下記の割引前の金額で構成される。
• ファイナンス・リースにおいて貸手が受領するリース料総額(セクション「3.5 リース料総額」
参照)
• 貸手に発生する無保証残存価値(無保証残存価値とは、原資産の残存価値のうち、貸手によ
る実現が確実でない、又は貸手と関連のある者のみが保証している部分をいう)
正味リース投資未回収額
貸手のファイナンス・リースの正味リース投資未回収額は、リース投資未回収総額をリースの計算
利子率で割り引くことにより算定される。
5.3 ファイナンス・リース
5.3.1 当初認識及び測定
IFRS第 16号からの抜粋
認識及び測定
67 開始日において、貸手は、ファイナンス・リースに基づいて保有している資産を貸借対照表
に認識し、それらを正味リース投資未回収額に等しい金額で債権として表示しなければな
らない。
当初測定
68 貸手は、正味リース投資未回収額を測定するためにリースの計算利子率を使用しなければ
ならない。サブリースの場合に、サブリースの計算利子率を容易に算定できないときには、
中間の貸手は、サブリースの正味リース投資未回収額を測定するために、ヘッドリースに使
用した割引率(サブリースに関連する当初直接コストについて調整後)を使用することがで
きる。
69 当初直接コストは、製造業者又は販売業者である貸手に生じたものを除いて、正味リース
投資未回収額の当初測定に含められ、リース期間にわたり認識される収益の金額の減額
となる。リースの計算利子率は、当初直接コストが正味リース投資未回収額に自動的に含
まれるような方法で定義されており、それらを別個に加算する必要はない。
68 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号からの抜粋
正味リース投資未回収額に含まれるリース料の当初測定
70 開始日において、正味リース投資未回収額の測定に含められるリース料は、リース期間中
に原資産を使用する権利に対する下記の支払いのうち開始日に受け取っていない金額で
構成される。
(a) 固定リース料(B42 項に記述している実質上の固定リース料を含む)から、支払うリース・イ
ンセンティブを控除した金額
(b) 変動リース料のうち、指数又はレートに応じて決まる金額(当初測定には、開始日現在の指
数又はレートを用いる)
(c) 貸手に提供される残価保証(借手、借手と関連のある当事者、又は貸手と関連ない第三者
で保証に基づく債務を弁済する財務上の能力のある者によるもの)
(d) 購入オプションを借手が行使することが合理的に確実である場合の、当該オプションの行
使価格(B37項に記述した要因を考慮して評価)
(e) リースの解約に対するペナルティの支払額(リース期間が借手のリース解約オプションの行
使を反映している場合)
貸手は、リース開始日にファイナンス・リースを以下のように会計処理する。
• 原資産の帳簿価額の認識を中止する
• 正味リース投資未回収額を認識する
• 販売利益又は販売損失を純損益で認識する
ファイナンス・リース(貸手が製造業者又は販売業者である場合を除く)の場合、当初直接コストは
ファイナンス・リース債権の当初測定額に含まれる。当初直接コストはリースの計算利子率の算定
において考慮されるため、別個に加算する必要はない。
正味リース投資未回収額は、リースの計算利子率で割り引かれた(1)リース料総額の現在価値(セ
クション「3.5 リース料」参照)及び(2)無保証残存価値の現在価値(セクション「3.6 割引率」参照)
の合計額で当初測定される。販売利益又は損失は、原資産又はリース債権の公正価値のいずれ
か低い金額と無保証残存価値控除後の原資産の帳簿価額との差額として測定される。
5.3.2 製造業者又は販売業者である貸手
IFRS第 16号からの抜粋
71 開始日において、製造業者又は販売業者である貸手は、ファイナンス・リースのそれぞれに
ついて下記を認識しなければならない。
(a) 収益(原資産の公正価値、又は、それよりも低い場合には、貸手に対して発生するリース料
を市場金利で割り引いた現在価値)
(b) 売上原価(原資産の取得原価、又はそれと異なる場合は帳簿価額から、無保証残存価値
の現在価値を控除)
(c) IFRS第15号が適用される売切り販売についての方針に従った販売損益(収益と売上原価
の差額)。製造業者又は販売業者である貸手は、貸手が原資産を IFRS 第 15 号に記述さ
れているように移転するのかどうかに関係なく、開始日にファイナンス・リースに係る販売損
益を認識しなければならない。
72 製造業者又は販売業者は、資産を購入するのかリースするのかのいずれかの選択を顧客
に提供することが多い。製造業者又は販売業者による資産のファイナンス・リースは、原資
産の通常の販売価格(適用される数量割引又は値引きを反映)での売切り販売から生じる
損益に相当する損益を生じさせる。
73 製造業者又は販売業者である貸手が、顧客を引き寄せるために人為的に低い利子率を付
すことがある。そのような利子率を使用すると、当該取引による合計収益のうち貸手が開始
時に認識する部分が過大となる。人為的に低い利子率が付された場合、製造業者又は販
売業者である貸手は、販売利益を市場利子率が課されたと仮定した場合に適用される利
益に限定しなければならない。
69 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号からの抜粋
74 製造業者又は販売業者である貸手は、ファイナンス・リースの獲得に関連して発生したコス
トを開始時に費用として認識しなければならない。それらは主として製造業者又は販売業者
の販売利益の稼得に関連したものであるからである。ファイナンス・リースの獲得に関連し
て製造業者又は販売業者である貸手に発生したコストは、当初直接コストの定義から除外
されており、したがって、正味リース投資未回収額から除外される。
製造業者や販売業者である貸手は、開始日において、IFRS第 15号が適用される通常の販売に関
する方針に従って販売利益又は販売損失を認識する。
したがって、製造業者又は販売業者である貸手は、リース開始日において、以下を認識する。
• 原資産の公正価値を収益として認識する(市場利子率を使用して割り引いたリース料総額の
現在価値の方が低い場合には、当該金額)
• 無保証残存価値の現在価値控除後の原資産の取得原価(又は帳簿価額)を売上原価として
認識する
• 通常の販売に関する方針に従って認識される販売利益又は販売損失。IFRS第15号に基づき、
製造業者又は販売業者である貸手は、開始日において、貸手が原資産を移転しているかどう
かにかかわらず、ファイナンス・リースに係る販売利益又は販売損失を認識する
ファイナンス・リース契約の締結に関連して発生する製造業者又は販売業者である貸手のコストは、
主に当該貸手が販売利益を獲得するために発生するものであるため、開始日において費用として
認識し、正味リース投資未回収額には含めない。
5.3.3 事後測定
IFRS第 16号からの抜粋
事後測定
75 貸手は、貸手の正味リース投資未回収額に対する一定の期間リターン率を反映するパ
ターンに基づいて、リース期間にわたり金融収益を認識しなければならない。
76 貸手は、金融収益をリース期間にわたり規則的かつ合理的な基礎で配分しようとする。貸
手は、当期に係るリース料をリース投資未回収総額に充当して元本と未稼得金融収益の
両方を減額する。
貸手はリース開始後にファイナンス・リースを以下のように会計処理する。
• 正味リース投資未回収額の残高に対して毎期一定の利益率(リースの計算利子率)を適用す
ることにより、リース期間にわたり純損益で金融収益を認識する。正味リース投資未回収額に
関して認識される収益は、以下により構成される。
• リース債権に係る利息収益
• 無保証残存資産に係る利息収益(リース終了時点の予想価値まで増加させることによ
り生じる)
• 受領したリース料を正味リース投資未回収額(上記で算定される金融収益控除後の金額)か
ら減額する
• 正味リース投資未回収額に含まれない変動リース料(例:業績又は使用に応じて変動する支
払い)から生じる収益を、当該収益が発生する期間において別個に認識する
• 正味リース投資未回収額の減損があれば認識する
製造業者又は販売業者である貸手
が意図的に低い利子率を提示する
場合であっても、販売利益は、市場
利子率に基づいて算定する。
70 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
5.3.4 正味リース投資未回収額の再測定
正味リース投資未回収額は、リース開始後において以下のいずれかの状況が発生する場合を除き、
再測定されない。
• リースの条件変更(当初のリースの契約条件に含まれてないリースの範囲又はリースの対価
の変更)が生じた場合に、条件変更後のリース契約が別個の契約として会計処理されない場
合(セクション「5.5 リースの条件変更」を参照)
• リース契約の解約不能期間の変更に伴いリース期間が変更される場合(セクション「3.4.2.2
リース期間及び購入オプションの再評価- 貸手」参照)
5.3.5 貸手のファイナンス・リースの会計処理
以下の設例では、販売利益が発生する場合におけるファイナンス・リースの貸手の会計処理につい
て解説している。
設例 17 ―― 販売業者である貸手のファイナンス・リースの会計処理
貸手は借手との間で 10 年間にわたる設備に関するリース契約を締結する。設備は特殊な仕様
ではなく、10 年後のリース期間の終了時点において、貸手は他の用途に使用することができる
と見込んでいる。また、リース契約により、以下の事項が示されている。
(単位:千円)
• 貸手は、年間リース料 15,000を年度末に受領する。
• 貸手は、10年後のリース期間の終了時点における設備の残存価値を 50,000 と見込んで
いる。
• 販売価格がリース期間の終了時点の見積残存価値(50,000)を下回ることにより貸手に損
失が生じる場合には、借手は貸手に対して 30,000までの残価保証を提供する。
• 設備の見積耐用年数は 15年、帳簿価額は 100,000、公正価値は 111,000である。
• 借手は、原資産の購入オプションを有しておらず、リース期間の終了時点において原資産
の所有権が借手に移転されることはない。
• リース計算利子率は 10.078%である。
リース料総額の現在価値合計は、原資産の公正価値のほとんどすべてであるため、貸手はリー
スをファイナンス・リースに分類する。
リース開始時点で貸手はファイナンス・リースを以下のように会計処理する。
正味ファイナンス・リース投資未回収額を計上し、原資産の認識を中止する
正味リース投資未回収額 111,000(a)
売上原価 92,344(b)
収益
103,344(c)
リース目的で保有する不動産
100,000(d)
(a) 正味リース投資未回収額は、(1)年間リース料 15,000の 10年間分に残価保証 30,000
を加算し、それをリース計算利子率で割り引いた 103,344(リース料総額)、及び(2)無保
証残存価値20,000の現在価値(7,656)により構成される。なお、正味リース投資未回収
額は、その他の資産と同様に貸借対照表における流動と非流動への分類を検討する(セ
クション「5.7 表示」参照)。
(b) 設備の売上原価は、設備の帳簿価額 10,000から無保証残存価値 7,656の現在価値を
控除した金額である。
(c) 収益はリース債権と同額である。
(d) 原資産の帳簿価額
貸手は、リース開始時点で、リース料総額 103,344 から、資産の帳簿価額(100,000)と無保
証残存価値(7,656)の差額 92,344を控除した 11,000を販売利益として認識する。
第 1年度のファイナンス・リースの仕訳:
現金 15,000(e)
正味リース投資未回収額 investment in the lease
3,813(f)
利息収益
11,187(g)
71 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
設例 17 ―― 販売業者である貸手のファイナンス・リースの会計処理
(e) 各年度末時点で年間リース料を受領
(f) 受領した年間リース料(15,000)から利息収益 11,187 を控除した金額を正味リース投資
未回収額とする。
(g) 利息収益は、正味リース投資未回収額の残高に毎期一定となる割引率を使用して算定さ
れる(算定方法は下記参照)。
以下の表では、リースから生じる利息収益及びリース期間にわたる正味リース投資未回収残高
の推移を示している。
年度
年間賃借料
年間利息収益(h)
正味リース投資
未回収額の年度末残高
当初正味投資未回収額
Initial net investment
千円 — 千円 — 111,000千円
1 15,000 11,187 107,187
2 15,000 10,803 102,990
3 15,000 10,380 98,370
4 15,000 9,914 93,284
5 15,000 9,401 87,685
6 15,000 8,837 81,522
7 15,000 8,216 74,738
8 15,000 7,532 67,270
9 15,000 6,780 59,050
10 15,000 5,950 50,000(i)
(h) 利息収益は、各年度の期首時点の正味未回収投資額に 10.078%を乗じて算定される。た
とえば、第 1年度の利息収益は、111,000(当初正味未回収投資額)x10.078%となる。
(i) リース期間の終了時点における設備の見積残存価値
5.4 オペレーティング・リース
IFRS第 16号からの抜粋
認識及び測定
81 貸手は、オペレーティング・リースによるリース料を、定額法又は他の規則的な基礎のいず
れかで収益として認識しなければならない。貸手は、他の規則的な基礎の方が原資産の使
用により便益が減少するパターンをより適切に表す場合には、当該基礎を適用しなければ
ならない。
82 貸手は、リース収益を稼得する際に生じるコスト(減価償却を含む)を費用として認識しなけ
ればならない。
83 貸手は、オペレーティング・リースの取得の際に発生した当初直接コストを原資産の帳簿価
額に加算し、当該コストをリース期間にわたりリース収益と同じ基礎によって費用として認識
しなければならない。
IFRS第 16号では、貸手はオペレーティング・リースを IAS第 17号と同様の方法で会計処理する。
すなわち、貸手は原資産を継続して認識し、正味リース投資未回収額を貸借対照表に認識はせず、
販売利益を損益計算書で認識することもない。原資産は、継続して適用される会計基準(例:IAS 第
16号)に従って会計処理される。
その後、貸手は、定額法又は原資産の使用から生じる便益の費消パターンをより適切に表すその
他の規則的な方法のいずれかを使用して、リース料総額をリース期間にわたり均等に認識する。
リース開始後は、貸手は指数又はレートを基礎としない変動リース料(例:業績や使用状況に応じて
決まる変動リース料)を獲得した時点で認識する。
また、オペレーティング・リースの貸手は IFRS 第 16 号に従って、リース開始時点の当初直接コスト
を繰り延べ、リース収益と同じ基準でリース期間にわたり認識する。
セクション「3.4.2.2 リース期間及び購入オプションの再評価-貸手」も参照されたい。
72 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
5.5 リースの条件変更
IFRS第 16号からの抜粋
付録 A
用語の定義
リースの条件変更
リースの当初の契約条件の一部ではなかったリースの範囲又はリースの対価の変更(たとえ
ば、1つ若しくは複数の原資産を使用する権利の追加若しくは解約、又は契約上のリース期間の
延長又は短縮)
ファイナンス・リースの条件変更が生じた場合(当初のリースの契約条件に含まれていないリースの
範囲又はリースの対価の変更が生じた場合)、条件変更後のリースを再評価し、リースに該当する
か、リースが含まれているかどうかを評価する必要がある(セクション「2.1 契約にリースが含まれ
ているか否かの判断」参照)。リースが継続して存在する場合には、ファイナンス・リースの条件変更
に伴い以下のいずれかが生じる。
• 別個のリース(セクション「5.5.1.1 リースの条件変更に伴い別個のリースが生じるかどうか
の判断」参照)
• 既存のリースの会計処理の変更(セクション「5.5.1.2 別個のリースが生じない条件変更に
関する貸手の会計処理」参照)
オペレーティング・リースの条件変更が生じた場合、条件変更の発効日から新たなリースとして取り
扱う(セクション「5.5.2 オペレーティング・リースの条件変更」参照)
5.5.1 ファイナンス・リースの条件変更
5.5.1.1 リースの条件変更に伴い別個のリースが生じるかどうかの判断
IFRS第 16号からの抜粋
79 貸手は、下記の場合には、ファイナンス・リースの条件変更を独立したリースとして会計処
理しなければならない。
(a) その条件変更が、1 つ又は複数の原資産を使用する権利を追加することによって、リース
の範囲を増大させており、かつ、
(b) 当該リースの対価が、範囲の増大分に対する独立価格及びその特定の契約の状況を反映
するための当該独立価格の適切な修正に見合った金額だけ増加している。
以下の両方の要件に該当する場合、貸手はファイナンス・リースの条件変更を別個のリース(当初
のリースと区分されるリース)として会計処理する。
• 条件変更に伴い原資産を1つ以上使用する権利が追加され、リースの範囲が増加する場合
• リースの対価が、リースの範囲の増加に係る独立販売価格に相当する金額だけ増加し、当該
価格に対し、特定の契約状況を反映した調整が行われている場合
リースの条件変更が上記の両要件に該当する場合、条件変更前の当初のファイナンス・リースと条
件変更による別個のリースの 2 つのリースが生じることになる。貸手は、別個のリースを、他の新た
に契約したリースと同じ方法で会計処理する。リースの条件変更がいずれかの要件に該当しない場
合、リースの条件変更により別個のリースが生じることはない。リースの条件変更により別個のリー
スが生じない場合の会計処理は、セクション「5.5.1.2 別個のリースが生じない条件変更に関する
貸手の会計処理」を参照されたい。
73 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
5.5.1.2 別個のリースが生じない条件変更に関する貸手の会計処理
IFRS第 16号からの抜粋
80 ファイナンス・リースの条件変更のうち独立したリースとして会計処理されないものについて
は、貸手は当該条件変更を次のように会計処理しなければならない。
(a) 条件変更が契約日に有効であったとしたならばリースがオペレーティング・リースに分類さ
れていたであろう場合には、貸手は次のことを行わなければならない。
(i) リースの条件変更を条件変更の発効日から新たなリースとして会計処理する。
(ii) 原資産の帳簿価額をリースの条件変更の発効日直前の正味リース投資未回収額とし
て測定する。
(b) 上記以外の場合には、IFRS第 9号の要求事項を適用しなければならない。
ファイナンス・リースの条件変更が、別個のリースを生じさせない場合には、貸手は、条件変更後の
リースの分類に従い条件変更の会計処理を行う。条件変更が開始日において有効であったならば、
リースがオペレーティング・リースに分類されていた場合には、貸手は、当該条件変更を、効力発生
日時点から新たなリースとして会計処理する。原資産の帳簿価額は、条件変更の効力発生日直前
の正味当初リース投資未回収額として測定する。それ以外の場合は、正味リース投資未回収額は、
IFRS第 9号「金融商品」に従って会計処理する。
付録 D「貸手の再評価及び再測定に関する要求事項の要約」を参照されたい。
5.5.2 オペレーティング・リースの条件変更
IFRS第 16号からの抜粋
87 貸手は、オペレーティング・リースの条件変更を当該条件変更の発効日から新たなリースと
して会計処理しなければならない。当初のリースに係る前払リース料又は未払リース料は
新たなリースに係るリース料の一部とみなす。
オペレーティング・リースの条件変更に伴い、条件変更後の契約が引き続きリースとなる、又はリー
スが含まれる場合、当該条件変更を効力発生日から新たなリースとして取り扱い、条件変更時点で
リースの分類を見直す(「5.1 リースの分類」参照)。その結果、新たなリースはオペレーティング・
リース又はファイナンス・リースのいずれかに分類される。当初のリースに係る前払リース料又は未
払リース料は、新たなリースに係るリース料の一部に含める。
5.6 その他の貸手に関する事項
5.6.1 正味リース投資未回収額の減損
IFRS第 16号からの抜粋
77 貸手は、IFRS 第 9 号における認識の中止及び減損の要求事項を正味リース投資未回収
額に適用しなければならない。貸手は、リース投資未回収総額の計算に使用する無保証残
存価値の見積りを定期的に見直さなければならない。無保証残存価値の見積りの減額が
あった場合には、貸手は、リース期間にわたる収益の配分を改訂し、発生した金額に関して
の減額を直ちに認識しなければならない。
貸手は、IFRS第 9号「金融商品」の認識の中止及び減損に関する規定を適用することで、正味リー
ス投資未回収額の減損を評価する。
貸手は、ファイナンス・リースの条件
変更が別個の契約として会計処理さ
れない場合、効力発生日時点におい
てリースの分類の再評価を行う。
74 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
5.6.2 ポートフォリオの適用
IFRS第 16号からの抜粋
B1 本基準は、個々のリースの会計処理を定めている。しかし、実務上の便法として、企業は本
基準を特性の類似したリースのポートフォリオに適用することができる。そのための条件
は、本基準をポートフォリオに適用することが財務諸表に与える影響が本基準を当該ポート
フォリオの中の個々のリースに適用した場合と重要な相違がないと企業が合理的に見込ん
でいることである。ポートフォリオを会計処理する場合には、企業はポートフォリオの規模及
び構成を反映した見積り及び仮定を使用しなければならない。
IFRS第 16号は、個々のリースに適用されるが、同種資産のリース(例:複数の同種車両のリース)
を多く有している場合には、個々のリースに会計処理を行うことが実務上困難になる場合がある。
IASBは、結論の根拠(BC83項)において、このような懸念に対処するために、ポートフォリオにおけ
る個々のリースに IFRS第 16号を適用した場合でも財務諸表に重要な影響はないと合理的に見込
んでいる場合には、実務上の簡便法として、同様の特徴を有するリースにポートフォリオ・アプロー
チを認めたことを述べている。
5.7 表示
IFRS第 16号からの抜粋
67 開始日において、貸手は、ファイナンス・リースに基づいて保有している資産を貸借対照表
に認識し、それらを正味リース投資未回収額に等しい金額で債権として表示しなければな
らない。
88 貸手は、オペレーティング・リースの対象となっている原資産を、原資産の性質に応じて貸
借対照表に表示しなければならない。
貸手は、IAS 第 17 号と同様に、ファイナンス・リースで保有している資産を貸借対照表で認識し、
IFRS 第 16 号の正味リース投資未回収額に等しくなる金額でリース債権として表示する。また、貸
手は IFRS 第 16 号に従って、オペレーティング・リースの対象になる原資産を資産の性質に基づい
て貸借対照表に表示しなければならない。
さらに、正味リース投資未回収額は、その他の資産と同様に、貸借対照表において流動と非流動に
分類する。
5.8 開示
IFRS第 16号からの抜粋
開 示
89 開示の目的は、貸手が注記において、貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計
算書で提供される情報と合わせて、リースが貸手の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フ
ローに与えている影響を財務諸表利用者が評価するための基礎を与える情報を開示する
ことである。第 90 項から第 97 項は、当該目的を満たす方法に関する要求事項を定めて
いる。
90 貸手は、報告期間に係る下記の金額を開示しなければならない。
(a) ファイナンス・リースについて
(i) 販売損益
(ii) 正味リース投資未回収額に対する金融収益
(iii) 正味リース投資未回収額の測定に含めていない変動リース料に係る収益
(b) オペレーティング・リースについて、リース収益(指数又はレートに応じて決まるものではな
い変動リース料に係る収益を区分して開示)
91 貸手は、第 90項で定めている開示を表形式で提供しなければならない。ただし、別の様式
の方が適切である場合は除く。
75 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号からの抜粋
92 貸手は、自らのリース活動について第89項の開示目的を満たすために必要な追加の定性
的情報及び定量的情報を開示しなければならない。この追加的な情報には、財務諸表利
用者が下記のことを評価するのに役立つ情報が含まれる場合があるが、これらに限らな
い。
(a) 貸手のリース活動の性質
(b) 貸手が原資産に対して保持している権利に関連したリスクをどのように管理しているのか。
特に、貸手は、原資産に対して保持している権利についてのリスク管理戦略を開示しなけ
ればならない。これには、貸手が当該リスクを低減している手段が含まれる。そのような手
段には、たとえば、買戻し契約、残価保証、所定の限度を超える使用に対する変動リース
料などがある。
ファイナンス・リース
93 貸手は、正味リース投資未回収額の帳簿価額の著しい変動についての定性的説明及び定
量的説明を提供しなければならない。
94 貸手は、リース料債権の満期分析を開示しなければならない。この満期分析は、割引前の
受取リース料を、少なくとも今後 5年間については各年度の金額、残りの年数に関してはそ
の合計金額で示さなければならない。貸手は、割引前のリース料を正味リース投資未回収
額と調整しなければならない。この調整は、リース料債権に係る未稼得金融収益と割引後
の無保証残存価値を識別しなければならない。
オペレーティング・リース
95 オペレーティング・リースの対象となっている有形固定資産について、貸手は IAS 第 16 号
の要求事項を適用しなければならない。IAS第16号の要求事項を適用するにあたり、貸手
は、有形固定資産の各クラスをオペレーティング・リースの対象となっている資産とオペレー
ティング・リースの対象となっていない資産に分解しなければならない。したがって、貸手
は、オペレーティング・リースの対象となっている資産(原資産のクラスごと)について、IAS
第 16号で要求している開示を、貸手が保有し使用している所有資産と区分して提供しなけ
ればならない。
96 貸手は、オペレーティング・リースの対象となっている資産について、IAS 第 36 号、IAS 第
38号、IAS第 40号及び IAS第 41号の開示要求を適用しなければならない。
97 貸手は、リース料の満期分析を開示しなければならない。この満期分析は、割引前の受取
リース料を、少なくとも今後 5年間については各年度の金額、残りの年数に関してはその合
計金額で示さなければならない。
貸手における開示の目的は、リースが貸手の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに与える
影響に関して、財務諸表利用者が評価するための基礎となる情報を開示することである。
IFRS 第 16 号では、貸手は、リースに関する定量的及び定性的情報、IFRS 第 16 号の適用におけ
る重要な判断、ならびにリースに関する財務諸表で認識される金額を開示する。
貸手は、重要でない情報を詳細に開示することや、異なる特徴を有する項目をまとめて開示するこ
とによって、有用な情報が不明瞭になることを避けるために、開示の集約又は分解に関する適切な
レベルの決定に際して判断が求められる。
貸手は、リースの対象となる資産の
残存価値に関連するリスクの管理
方法について、より多くの情報の開
示が求められる。
76 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
6. サブリース
6.1 定義
IFRS第 16号からの抜粋
付録 A
用語の定義
サブリース(sublease)
原資産が借手(「中間的な貸手」)から第三者にさらにリースされ、当初の貸手と借手との間の
リース(「ヘッドリース」)が依然として有効である取引
借手は、当初のリース契約が有効である期間において、リース資産をさらにリースする契約を締結
することがある。このような契約では、ある当事者が同一の原資産の借手及び貸手として行動する。
当初のリースはヘッドリース、当初の借手は中間の貸手又は転貸人、最終的な借手は転借人と呼
ばれることがある。
サブリースは、別個のリース契約となる場合もあれば、第三者が当初のリースを引き受けるが、当
初の借手が当初のリースの主たる債務者である場合もある。
6.2 中間の貸手の会計処理
IFRS第 16号からの抜粋
B7 借手が資産を転貸しているか又は資産を転貸することを見込んでいる場合には、ヘッドリー
スは少額資産のリースに該当しない。
B58 サブリースを分類する際に、中間の貸手は、サブリースを次のようにしてファイナンス・リー
ス又はオペレーティング・リースに分類しなければならない。
(a) ヘッドリースが、企業が借手として第 6 項を適用して会計処理した短期リースである場合に
は、サブリースはオペレーティング・リースに分類しなければならない。
(b) それ以外の場合には、サブリースは、原資産(たとえば、リースの対象となっている有形固定
資産項目)ではなくヘッドリースから生じる使用権資産を参照して分類しなければならない。
借手が第三者に対して原資産の再リースを行い、当初の借手が当初のリースの主たる義務を保持
する場合、取引はサブリースとなる。通常、当初の借手は、当初のリース(ヘッドリース)について借
手の会計処理を継続し、サブリースを貸手(中間の貸手)として会計処理する。
ヘッドリースが短期リースに該当する場合、サブリースはオペレーティング・リースに分類される。そ
れ以外の場合には、サブリースは、ヘッドリースの使用権資産(ヘッドリースの原資産とは異なる資
産)を参照して、セクション「5 貸手の会計処理」の分類要件に従って分類される。
貸手
当初の借手(中間の貸手/転貸人)
サブリース
借手(転借人)
ヘッド・リース
77 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
設例 18 ―― サブリースの分類
F社(当初の借手/中間の貸手)は、5年間にわたり建物をリースする。建物の経済的耐用年数は
30年である。さらに、F社は4年間にわたり建物をサブリースする。サブリースは、(原資産である
建物ではなく)ヘッドリースの使用権資産を参照して分類される。たとえば、耐用年数に関する要
件を評価する場合には、4年間のサブリース期間と使用権資産に関する5年間のヘッドリース期
間(建物の耐用年数30年ではなく)を比較する。その結果、サブリースはファイナンス・リースに
分類される場合がある。
中間の貸手は、サブリースを以下のように会計処理する。
• サブリースがオペレーティング・リースに分類される場合、当初の借手は、他のリース同様に、
ヘッドリースに係るリース負債と使用権資産に関する会計処理を継続する(セクション「4 借
手の会計処理」参照)。ヘッドリースに係る使用権資産の帳簿価額残高がサブリース収益の
見込額を上回る場合には、ヘッドリースに係る使用権資産が減損している可能性がある。使
用権資産は、IAS第36号に従って減損の判定が行われる。
• サブリースがファイナンス・リースに分類される場合、当初の借手は、サブリースの開始日時
点でヘッドリースに係る使用権資産の認識を中止し、借手の会計モデルに従って当初のリー
ス負債の会計処理を継続する(セクション「4 借手の会計処理」参照)。当初の借手は転貸人
として、正味サブリース投資未回収額を認識し、減損の判定を行う(セクション「5.6.1 正味
リース投資未回収額の減損」参照)。
サブリースにおいて計算利子率を容易に算定することができない場合、中間の貸手は、ヘッドリース
の割引率を使用する(サブリースに関連する当初直接コストについて調整)。
複数の契約が同時又はほぼ同時に締結される場合、中間の貸手は、契約の結合に関する要件を
検討する必要がある(例:複数の契約が単一の商業上の目的で一括して交渉される場合、ある契約
で支払われる対価の金額が他の契約の対価又は履行に左右される場合)。契約の結合が求められ
る場合、中間の貸手は、ヘッドリースとサブリースを結合された単一の取引として会計処理する(セ
クション「2.3 契約の結合」参照)。
貸手は、資産を転貸する、又は転貸を予定している場合には、セクション「4.1.2 少額資産のリース」
の要件が満たされる場合でも、ヘッドリースを少額資産のリースとして会計処理することはできない。
以下で掲載している IFRS第 16号の設例では、同一の原資産のヘッドリース及びサブリースを締結
する中間の貸手が新基準の要求事項を適用する場合について解説している。
IFRS第 16号からの抜粋 設例
設例 20 ―― ファイナンス・リースに分類されるサブリース
ヘッドリース:中間の貸手は、5 年間にわたる 5,000 平方メートルの事務所スペースに係るリー
ス契約(ヘッドリース)を企業 A(ヘッドリースの貸手)と締結する。
サブリース:第 3 年度の期首に、中間の貸手は、ヘッドリースの残りの 3 年間にわたり、5,000
平方メートルの事務所スペースを借手(サブリースの借手)にサブリースする。
中間の貸手は、ヘッドリースから生じた使用権資産を参照して、サブリースの分類を行う。中間
の貸手は、IFRS第 16号の第 61項から第 66項の要求事項を考慮して、当該サブリースをファ
イナンス・リースに分類する。中間の貸手は、サブリースの締結時に、以下のとおり会計処理を
行う。
(a) サブリースの借手に移転するヘッドリースに係る使用権資産の認識を中止し、サブリースに
対する投資を認識する。
(b) 使用権資産とサブリースに対する投資に差額がある場合には、純損益を認識する。
(c) ヘッドリースに係るリース負債を引き続き貸借対照表で認識する。当該負債は、ヘッドリー
スの貸手に対する支払リース料を表している。
中間の貸手は、サブリース期間において、サブリースに係る金融収益及びヘッドリース係る利息
費用の両方を認識する。
78 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号からの抜粋 設例
設例 21 ―― オペレーティング・リースに分類されるサブリース
ヘッドリース:中間の貸手は、5 年間にわたる 5,000 平方メートルの事務所スペースに係るの
リース契約(ヘッドリース)を企業 A(ヘッドリースの貸手)と締結する。
サブリース:ヘッドリースの開始時に、中間の貸手は、2 年間にわたり、5,000 平方メートルの事
務所スペースを借手(サブリースの借手)にサブリースする。
中間の貸手は、ヘッドリースから生じた使用権資産を参照してサブリースの分類を行う。中間の
貸手は、IFRS 第 16 号の第 61 項から第 66 項の要求事項を考慮して、当該サブリースをオペ
レーティング・リースに分類する。
中間の貸手は、サブリースの締結時において、ヘッドリースに係るリース負債及び使用権資産を
引き続き貸借対照表で認識する。また、サブリース期間において、以下を認識する。
(a) 使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息費用
(b) サブリースに係るリース収益
6.3 転借人の会計処理
転借人は、リースを他のリースと同じ方法で、(IFRS 第 16 号の認識及び測定の規定に従って新た
なリースとして)会計処理する(セクション「4 借手の会計処理」参照)。
6.4 表示
他の IFRS で義務付けられていない又は容認されない限り、IAS 第 1 号第 32 項により資産と負債
及び収益と費用を相殺することはできない。したがって、中間の貸手は、ヘッドリース及びサブリー
スから生じるリース負債とリース資産を、IAS第 1号における相殺に係る要件を満たす場合を除き、
相殺できない。同様に中間の貸手は、IAS第 1号における相殺に係る要件を満たす場合を除き、減
価償却費と利息費用は、それぞれ原資産を同じくするヘッドリースとサブリースから生じるリース収
益(ヘッドリースからのリース収益は使用権資産を認識中止する場合に発生する利得部分)と相殺
することができない。
6.5 開示
IFRS 第 16 号では、リースが貸手の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに与える影響に関
して、財務諸表利用者が理解するための基礎となる定性的及び定量的情報を開示しなければなら
ない。これには、中間の貸手に該当する場合も含む。借手の開示はセクション「4.8 開示」、貸手の
開示はセクション「5.7 開示」を参照されたい。
79 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
7. セール・アンド・リースバック取引
IFRS第 16号からの抜粋
セール・アンド・リースバック取引
98 企業(売手である借手)が資産を他の企業(買手である貸手)に売却して当該資産を買手で
ある貸手からリースバックする場合には、売手である借手と買手である貸手の両方は、そ
の譲渡取引とリースを第 99項から第 103項を適用して会計処理しなければならない。
セール・アンド・リースバック取引では、ある企業(売手である借手)から他の企業(買手である貸手)
に資産が譲渡され、当該資産が売手である借手にリースバックされる。IFRS 第 16 号では、借手は
ほとんどのリース(借手の会計方針の選択によるが、少額資産のリース及び短期リースを除くすべ
てのリース)を貸借対照表に計上することが求められるため、セール・アンド・リースバック取引はオ
フバランスでの資金調達の手段ではなくなる。売り手である借手と買手である貸手の双方は、IFRS
第 15 号を適用してセール・アンド・リースバック取引を資産の売却及び購入として会計処理すべき
かを判断しなければならない。
7.1 資産の譲渡が売却であるかどうかの判断
IFRS第 16号からの抜粋
資産の譲渡が売却であるかどうかの判断
99 企業は、資産の譲渡を当該資産の売却として会計処理すべきかどうかを決定するために、
履行義務がいつ充足されるのかの決定に関する IFRS第 15号の要求事項を適用しなけれ
ばならない。
資産の譲渡を売却及び購入として会計処理すべきかどうかの判断にあたり、売手である借手と買手
である貸手の両者は、資産に対する支配を移転させることにより、どの時点で履行義務を充足した
のかに関して IFRS 第 15 号の要求事項を適用する。原資産に対する支配が買手である貸手に移
転している場合には、当該取引は資産の売却・購入とリースとして会計処理され、移転していない場
合には、売手である借手と買手である貸手の両者は当該取引を金融取引として会計処理する。
IFRS 第 15 号では、資産の支配が移転しているかどうかの判断にあたり、以下のように定めている。
IFRS第 15号からの抜粋
31 企業は、約束した財又はサービス(すなわち、資産)を顧客に移転することによって企業が
履行義務を充足した時に(又は充足するにつれて)、収益を認識しなければならない。資産
が移転するのは、顧客が当該資産に対する支配を獲得した時(又は獲得するにつれて)で
ある。
32 第 22項から第 30項に従って識別された履行義務のそれぞれについて、企業は契約開始
時に、企業が履行義務を一定の期間にわたり充足する(第 35項から第 37項に従って)の
か、それとも一時点で充足する(第 38項に従って)のかを決定しなければならない。企業が
履行義務を一定の期間にわたり充足するものではない場合には、当該履行義務は一時点
で充足される。
セール・アンド・リースバック取引
は、借手にとってオフバランスでの
資金調達の手段ではなくなる。
80 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 15号からの抜粋
33 財及びサービスは、たとえ一瞬だけであっても、受け取って使用する時点では(多くのサー
ビスの場合)資産である。資産に対する支配とは、当該資産の使用を指図し、当該資産か
らの残りの便益のほとんどすべてを獲得する能力を指す。支配には、他の企業が資産の使
用を指図して資産から便益を得ることを妨げる能力が含まれる。資産の便益とは、次のよう
な多くの方法で直接又は間接に獲得できる潜在的なキャッシュ・フロー(インフロー又はアウ
トフローの節減)である。
(a) 財の製造又はサービス(公共サービスを含む)の提供のための当該資産の使用
(b) 他の資産の価値を増大させるための当該資産の使用
(c) 負債の決済又は費用の低減のための当該資産の使用
(d) 当該資産の売却又は交換
(e) 借入金の担保とするための当該資産の担保差入れ
(f) 当該資産の保有
34 顧客が資産に対する支配を獲得しているかどうかを評価する際に、企業は、当該資産を買
い戻す契約を考慮しなければならない(B64項から B76項参照)。
38 履行義務が第 35 項から第 37 項に従って一定の期間にわたり充足されるものではない場
合には、企業は当該履行義務を一時点で充足する。顧客が約束された資産に対する支配
を獲得し、企業が履行義務を充足する時点を決定するために、企業は第 31 項から第 34
項の支配に関する要求事項を考慮しなければならない。さらに、企業は支配の移転の指標
を考慮しなければならない。これには次のものが含まれるが、これらに限定されない。
(a) 企業が資産に対する支払いを受ける現在の権利を有している―顧客が資産に対して支払
う義務を現時点で負っている場合、そのことは、顧客がそれと交換に、当該資産の使用を
指図して当該資産からの残りの便益のほとんどすべてを獲得する能力を得ていることを示
す可能性がある。
(b) 顧客が資産に対する法的所有権を有している―法的所有権は、どの契約当事者が、資産
の使用を指図して資産からの残りの便益のほとんどすべてを獲得する能力又は当該便益
への他の企業のアクセスを制限する能力を有しているのかを示す可能性がある。したがっ
て、資産の法的所有権の移転は、顧客が資産に対する支配を獲得していることを示す可能
性がある。企業が法的所有権を顧客の支払不履行に対する保護としてのみ保持している
場合には、企業の当該権利は、顧客が資産に対する支配を獲得することを妨げるものでは
ない。
(c) 企業が資産の物理的占有を移転した―顧客による資産の物理的占有は、当該資産の使用
を指図し、当該資産からの残りの便益のほとんどすべてを獲得する能力又は当該便益へ
の他の企業のアクセスを制限する能力を顧客が有していることを示す可能性がある。しか
し、物理的な占有は資産に対する支配と一致しない場合がある。たとえば、買戻し契約や
委託販売契約の中には、顧客又は受託者が、企業が支配している資産の物理的占有を有
するものがある。逆に、請求済未出荷契約の中には、企業が、顧客が支配している財を物
理的に占有するものがある。B64項からB76項、B77項からB78項及びB79項からB82
項は、買戻し契約、委託販売契約及び請求済未出荷契約の会計処理に関するガイダンス
をそれぞれ示している。
(d) 顧客が資産の所有に伴う重大なリスクと経済価値を有している―資産の所有に伴う重大な
リスクと経済価値の顧客への移転は、顧客が当該資産の使用を指図して当該資産からの
残りの便益のほとんどすべてを獲得する能力を獲得したことを示す可能性がある。しかし、
約束した資産の所有に伴うリスクと経済価値を評価する際に、企業は当該資産を移転する
履行義務に加えて独立した履行義務を生じさせるリスクを除外しなければならない。たとえ
ば、企業が資産に対する支配を顧客に移転しているが、移転した資産に関連した維持管理
サービスを提供する追加的な履行義務をまだ充足していない場合がある。
(e) 顧客が資産を検収した―顧客による資産の検収は、顧客が当該資産の使用を指図して当
該資産からの残りの便益のほとんどすべてを獲得する能力を獲得したことを示す可能性が
ある。契約による顧客の検収の条項が、資産に対する支配が移転する時期に与える影響
を評価するために、企業は B83項から B86項のガイダンスを考慮しなければならない。
81 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
上記の指標は、買手である貸手が原資産の支配を獲得したかどうかに関して、いずれも単独で決
定されるものではない。売手である借手及び買手である貸手は、支配が移転しているかどうかを判
断するにあたり、すべての関連する事実及び状況を考慮しなければならない。また、買手である貸
手が支配を獲得したと判断するためには、すべての指標が存在している必要はない。これらの指標
は、顧客が資産の支配を獲得している場合に存在することが多い要因であり、支配の原則を適用す
る際の一助として示されている。なお、弊法人の刊行物「Applying IFRS: IFRS 第 15 号 顧客との
契約から生じる収益」1 では、資産の支配が移転しているかどうかの判断に関して詳細に解説して
いる。
IASBは、結論の根拠(BC262 項)において、リースバックが存在していることのみで、売却が生じた
ことが否定されることはないと述べている。これはリースは、原資産の支配を移転するものではなく、
原資産の売却と購入とは異なるためである。リースでは、リース期間にわたり原資産の使用を支配
する権利が移転される。ただし、売手である借手が実質的に原資産を買い戻すオプション(資産を
買い戻す権利)を有している場合には、買手である貸手は資産の支配を獲得していないため、売却
には該当しないことになる。
弊社のコメント
• 新基準における要求事項は、売手である借手の現行実務を大幅に変更させる。IFRS 第
16号では、売却に該当するかどうかの判断にあたり、売手である借手は IFRS第 15号の
要求事項を適用する。また、売却の要件に該当する場合であっても、通常は、セール・アン
ド・リースバック取引はオフバランスでの資金調達の手段とはならない。
• IFRS第16号では、売手である借手が原資産の残りの経済的耐用年数の実質的にすべて
の期間にわたりリースを延長できる借手の更新オプション(例:固定価格、行使日時点の公
正価値)によって、売却の処理が否定されるかどうかについては取り上げられていない。
我々は、原資産の残りの経済的耐用年数の実質的にすべての期間にわたりリースを延長
できるオプションを有する借手は、経済的に、原資産を購入するオプションを有する借手と
同じような立場にあると考えている。したがって、更新価格が更新オプションの行使日時点
の公正価値でない場合には、当該更新オプションの存在により、IFRS 第 15 号及び第 16
号に基づく売却として処理されることはない。
7.2 資産の譲渡が売却である取引
IFRS第 16号からの抜粋
資産の譲渡が売却である場合
100 売手である借手による資産の譲渡が、資産の売却として会計処理するための IFRS 第 15
号の要求事項を満たす場合には、
(a) 売手である借手は、リースバックから生じた使用権資産を、資産の従前の帳簿価額のうち
売手である借手が保持した使用権に係る部分で測定しなければならない。したがって、売
手である借手は、買手である貸手に移転された権利に係る利得又は損失の金額のみを認
識しなければならない。
(b) 買手である貸手は、資産の購入を該当する基準を適用して会計処理し、リースを本基準に
おける貸手の会計処理の要求事項を適用して会計処理しなければならない。
101 資産の売却の対価の公正価値が資産の公正価値と等しくない場合、又はリース料が市場
のレートで行われていない場合には、企業は売却収入を公正価値で測定するために下記
の修正を行わなければならない。
(a) 市場を下回る条件は、リース料の前払として会計処理しなければならない。
(b) 市場を上回る条件は、買手である貸手が売手である借手に提供した追加の融資として会計
処理しなければならない。
102 企業は、第 101 項で要求している潜在的な修正を、下記のうち容易に算定可能な方に基
づいて測定しなければならない。
(a) 売却の対価の公正価値と資産の公正価値との差額
(b) リースに係る契約上の支払いの現在価値と市場のレートでのリースに係る支払いの現在価
値との差額
セール・アンド・リースバック取引の
買手は、他の資産の買手とは異な
り、新たな収益基準を適用して資産
を購入したかどうかを判断する。
82 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
7.2.1 売却の会計処理
資産の譲渡が売却に該当する場合、売手である借手は以下を行う。
• 原資産の認識を中止する。
• 買手である貸手に移転された権利に関連する利得又は損失を認識し、オフマーケット条件に
関して調整する。
買手である貸手は、資産の購入を、資産の性質に基づいて他の基準に従って会計処理する(例:有
形固定資産であれば IAS第 16号)。
弊社のコメント
IFRS第 16号では明示されていないが、セール・アンド・リースバック取引において、売手である
借手は、損失の発生を見込んでいる場合であっても、当該損失を繰り延べることはできないと
我々は考えている。さらに、売手である借手はまた、IFRS 第 5 号に従って資産を売却目的保有
に分類すべきかどうか検討し、また、取引前に減損が発生していた可能性がないかを検討する
必要がある。
7.2.2 リースバック取引の会計処理
売手である借手及び買手である貸手の両者は、売却が生じた場合、他のリースと同様に(セクショ
ン 4「借手の会計処理」、セクション 5「貸手の会計処理」参照)、オフマーケット条件に関して調整
を行い、リースバック取引を会計処理する。具体的には、売手である借手は、リースバック取引に
係るリース負債と使用権資産を認識する(短期リース及び少額資産のリースに係る免除規定を適
用できる)。
7.2.3 オフマーケット条件に関する調整
セール・アンド・リースバック取引における売却とその後のリースバックは、通常、相互に関連してお
り、一括して交渉される。そのため、取引は、売却価格が公正価値より高く又は低く、リース料が市
場相場よりも高く又は低くなるように組成される場合がある。このようなオフマーケット条件により、
売却に係る利得又は損失とリースに係るリース費用及びリース収益の認識が歪められる可能性が
ある。セール・アンド・リースバック取引の売却に係る利得又は損失とリースに関連する資産及び負
債が過小又は過大計上されないようにするために、IFRS 第 16 号では、セール・アンド・リースバッ
ク取引のオフマーケット条件について、売却に係る対価の公正価値と資産の公正価値の差額と、契
約上のリース料支払総額の現在価値と市場相場によるリース料支払総額の現在価値の差額につ
いて、より容易に算定可能な方法により調整を行うことが求められる。
売却価格が原資産の公正価値を下回る場合、あるいはリース料総額の現在価値が市場相場によ
るリース料総額の現在価値を下回る場合には、より容易に算定可能な方法を使用して、売手である
借手は、当該差額だけ売却価格を増加させるとともに、リース料の前払いとして使用権資産の当初
測定に含める。売却価格が原資産の公正価値を上回る場合、あるいはリース料総額の現在価値が
市場相場によるリース料総額の現在価値を上回る場合には、より容易に算定可能な方法を使用し
て、売手である借手は、当該差額だけ売却価格を減少させるとともに、買手である貸手からの追加
の融資として認識する。
買手である貸手も、オフマーケット条件に関して原資産の購入価格を調整することが求められる。こ
のような調整は、売手である借手からのリース料の前払い、あるいは売手である借手に対する追加
の融資として認識される。
83 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
7.2.4 設例
以下の IFRS第16号の設例では、セール・アンド・リースバック取引の会計処理について示している。
IFRS第 16号設例の抜粋
設例 24 ―― セール・アンド・リースバック取引
企業(売手である借手)は、建物を他の企業(買手である貸手)に現金 2,000,000 千円で売却す
る。当該取引の直前における当該建物の取得原価は 1,000,000 千円である。当該取引と同時
に、売手である借手は、買手である貸手との間で、当該建物を 18 年間にわたり使用する権利に
関する契約を締結する。当該取引の契約条件は、売手である借手による建物の譲渡に関して、
IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」における、履行義務がいつ充足されるのかの判定
に関する要求事項を充足している。したがって、売手である借手及び買手である貸手は、当該取
引をセール・アンド・リースバックとして会計処理する。この設例では、初期直接コストを無視する。
売却日現在の建物の公正価値は 1,800,000 千円である。建物の売却価格は公正価値と異な
るため、売手である借手及び買手である貸手は、売却代金を公正価値で測定されるように調整
する。つまり、売却価格の超過額200,000千円(2,000,000千円-1,800,000千円)を、買手
である貸手が売手である借手に対して行う追加の融資として認識する。
リースの計算利子率は年 4.5%であり、売手である借手は容易に算定することができる。年間支
払額の現在価値(18 回分の年間支払額 120,000 千円を年 4.5%で割り引いた額)は
1,459,200千円となり、このうち 200,000千円は追加の融資に関するものであり、1,259,200
千円はリースに関するものである。18回分の年間支払額に対応する額は、それぞれ16,447千
円と 103,553千円である。
買手である貸手は、当該建物のリースをオペレーティング・リースに分類する。
売手である借手
売手である借手は、開始日に、建物のリースバックから生じた使用権資産を、借手が保持する使
用権資産と建物の従前の帳簿価額の割合から測定する。当該金額は、699,555 千円であり、
1,000,000 千円(建物の帳簿価額)÷1,800,000 千円(建物の公正価値)×1,259,200 千円
(18年分の使用権資産に係る割引後のリース料)で計算される。
売手である借手は、買手である貸手に移転された権利に関する範囲のみで、利得 240,355 千
円を認識する。建物の売却に係る利得は 800,000千円(1,800,000千円-1,000,000千円)
であり、この内訳は以下のとおりである。
(a) 559,645 千円(800,000 千円÷1,800,000 千円×1,259,200 千円)は、売手である借
手が保持している建物の使用権に関する部分である
(b) 240,355 千円(800,000 千円÷1,800,000 千円×(1,800,000 千円-1,259,200 千
円))は、買手である貸手に移転された権利に関する部分である
売手である借手は、開始日に、この取引を以下のように会計処理する。
(単位:千円)
現金 2,000,000
使用権資産 699,555
建物 1,000,000
金融負債 1,459,200
移転された権利に係る利得 240,355
84 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号設例の抜粋
買手である貸手
買手である貸手は、開始日に、この取引を次のように会計処理する。
建物 1,800,000
金融資産 200,000 (18回分の支払額
16,447を年率 4.5%
で割り引いた金額)
現金 2,000,000
買手である貸手は、開始日に、年間支払額 120,000 千円のうち 103,553 千円をリース料とし
て処理することによって、当該リースを会計処理する。売手である借手から受領する年間支払額
のうち残りの 16,447 千円は、(a) 金融資産 200,000 千円の回収として受領した金額と、(b)
利息収益として会計処理される。
7.3 資産の譲渡が売却ではない取引
IFRS第 16号からの抜粋
資産の譲渡が売却ではない場合
103 売手である借手による資産の譲渡が、資産の売却として会計処理するための IFRS 第 15
号の要求事項を満たさない場合には、
(a) 売手である借手は、譲渡した資産を引き続き認識し、譲渡収入と同額の金融負債を認識し
なければならない。売手である借手は、金融負債を IFRS第 9号を適用して会計処理しなけ
ればならない。
(b) 買手である貸手は、譲渡された資産を認識してはならず、譲渡収入と同額の金融資産を認
識しなければならない。買手である貸手は、金融資産を IFRS第 9号を適用して会計処理し
なければならない。
資産の譲渡が売却ではない場合、売手である借手は当該取引を融資として会計処理する。売手で
ある借手は、セール・アンド・リースバック取引の対象である譲渡された資産を引き続き認識し、受領
した金額を IFRS 第 9 号に従って金融負債として会計処理する。また、支払金額から利息費用に相
当する部分を控除した金額は、金融負債から減額される。
資産の譲渡が売却ではない場合、買手である貸手は譲渡された資産を認識せず、支払金額を金融
資産として認識し、IFRS第 9号に従って会計処理する。
7.4 開示
IFRS第 16号からの抜粋
B52 セール・アンド・リースバック取引に関する追加的な情報のうち、状況に応じて、第 51 項の
開示目的を満たすために必要とされる可能性のある情報には、たとえば、下記のことを財
務諸表利用者が評価するのに役立つ情報が含まれる場合がある。
(a) 借手がセール・アンド・リースバック取引をする理由及び当該取引の一般性
(b) 個々のセール・アンド・リースバック取引の主要な契約条件
(c) リース負債の測定に含まれていない支払い
(d) 当該報告期間におけるセール・アンド・リースバック取引のキャッシュ・フロー上の影響
売手である借手は、IFRS 第 16 号の開示の目的を満たすために必要となるリース活動に関する定
性的及び定量的情報を追加で開示することが求められる場合がある。借手の開示の要求要事につ
いては、セクション 4.8「開示」を参照されたい。
売手である借手は、IFRS 第 16 号第 53 項(i)に基づき、セール・アンド・リースバック取引から生じ
た利得及び損失を、他の資産の処分から生じた利得及び損失とは区別して開示することが求めら
れる。
85 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
8. 企業結合
8.1 企業結合における被取得企業が借手である場合
IFRS第 3号からの抜粋
被取得企業が借手のリース
28A 取得企業は、IFRS 第 16 号に従って識別された、被取得企業が借手のリースであるものに
ついて、使用権資産とリース負債を認識しなければならない。ただし、取得企業は、下記の
リースについては、使用権資産及びリース負債を認識することを要求されない。
(a) リース期間(IFRS第 16号で定義)が取得日から 12 ヵ月以内に終了するリース
(b) 原資産が少額であるリース(IFRS第 16号 B3項から B8項に記述)
28B 取得企業は、リース負債を、取得したリースが取得日時点で新規のリースであったかのよう
にして、残りのリース料(IFRS 第 16 号で定義)の現在価値で測定しなければならない。取
得企業は、使用権資産を、リース負債(市場の条件と比較した場合の当該リースの有利又
は不利な条件について調整後)と同額で測定しなければならない。
8.1.1 リースの当初測定
IFRS 第 16 号の公表に伴う IFRS 第 3 号の改訂では、企業結合で取得したリースの当初測定に関
する要求事項を定めている。
取得企業は、取得したリース負債を、リース契約が取得日時点における新たなリースであるかのよ
うに測定する。つまり、取得企業は、取得日時点における残存リース料総額の現在価値を使用して、
IFRS第 16号の当初測定に係る規定を適用する。取得企業は、セクション 3「主要な概念」で解説し
た、リース期間、リース料及び割引率の決定に関する要求事項に従う。
使用権資産は、認識された負債と等しい金額で測定され、市場条件と比較して有利又は不利なリー
ス条件がある場合には、調整を行う。リースのオフマーケット条件の性質は、使用権資産として表わ
されるため、取得企業は市場条件と比較して有利又は不利なリース条件に関して、別個に無形資
産又は負債を認識することはない。
取得企業は、取得日から 12 ヵ月以内にリース期間が終了するリース及び少額資産のリースに関し
て使用権資産及びリース負債を認識することは求められない。IASBは、結論の根拠(BC298項)に
おいて、短期リース及び少額資産のリースにおけるオフマーケット条件に関して、資産及び負債の
認識を取得企業に求めるかどうかを検討したと述べている。短期リース及び少額資産のリースにお
けるオフマーケット条件は、重要な影響を有していることは稀であるため、資産及び負債の認識を求
めないことが決定されている。
8.1.2 リースの事後測定
取得したリース負債及び使用権資産の事後測定に係る要求事項は、他の既存のリース契約に係る
要求事項と同じである。
86 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
8.2 企業結合における被取得企業が貸手である場合
IFRS第 3号からの抜粋
17 本基準は、第 15号の原則に関して、次の 2つの例外を設けている。
(a) 被取得企業が貸手であるリース契約を、IFRS第16号「リース」に従って、オペレーティ
ング・リースかファイナンス・リースのどちらかに分類する
(b) 契約を、IFRS 第 4 号「保険契約」に従って保険契約として分類する(ただし、IFRS 第
17 号「保険契約」では、同基準を適用する企業の場合は、この例外規定の適用対象
から除かれる)
取得企業はそれらの契約を、契約開始時(又は分類が変更となるような方法で契約条件が変更
された場合には、その条件変更の日(これは取得日であるかもしれない))における契約条件及
びその他の要素に基づいて分類しなければならない。
B42 被取得企業が貸手となるオペレーティング・リースの対象となる建物又は特許などの資産
の取得日公正価値を測定するにあたり、取得企業はリースの契約条件を考慮に入れなけ
ればならない。取得企業は、オペレーティング・リースの条件が市場の条件と比べて有利又
は不利であるとしても、個別の資産又は負債を認識しない。
IFRS 第 16号では、取得企業は、リースの開始日、又はリースの分類が変更されるような契約条件
の変更が行われている場合には当該条件変更の日における契約条件に基づいて、取得した貸手
のリースをファイナンス・リース又はオペレーティング・リースに分類することが求められる。したがっ
て、リースの条件変更が行われていない場合には、企業結合の結果によりリースの分類が変更さ
れることはない(セクション 5.5「リースの条件変更」参照)。
87 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
9. 発効日及び経過措置
9.1 発効日
IFRS第 16号からの抜粋
発効日
C1 企業は、本基準を2019年1月1日以後に開始する事業年度に適用しなければならない。
早期適用は、IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」を本基準の適用開始日以前に
適用している企業について認められる。企業が本基準を早期適用する場合には、その旨を
開示しなければならない。
IFRS第 16号は、2019年 1月 1日以後開始する事業年度から適用される。IFRS第 15号を既に
適用している場合、又は IFRS第 16号と同じ日から IFRS第 15号を適用する場合には、早期適用
が認められる。IFRS第 16号の早期適用を選択した企業は、その旨を開示しなければならない。
弊社のコメント
IFRS 第 15 号の適用日は、2018 年 1 月 1 日以後開始する事業年度である。IASB は、IFRS
第 16号における一部の概念について IFRS第 15号の概念と整合させている(例:セール・アン
ド・リースバック取引における資産の譲渡が売却であるかどうかの判断)。したがって、特に貸手
である一部の企業は、両基準の適用日を同じ日にするために、1年早く IFRS第 16号の適用を
検討することが考えられる。
9.2 経過措置
IFRS第 16号からの抜粋
経過措置
C2 C1 項から C19 項の要求事項の目的上、適用開始日は、企業が本基準を最初に適用する
事業年度の期首である。
IFRS第 16号の経過措置は、IFRS第 16号を最初に適用する事業年度の期首(適用開始日)に適
用される。たとえば、報告日が 2019 年 12 月 31 日の企業は、経過措置を 2019 年 1 月 1 日に
適用する。
9.2.1 リースの定義
IFRS第 16号からの抜粋
リースの定義
C3 実務上の便法として、企業は契約がリース又はリースを含んだものであるかどうかを適用
開始日現在で見直すことを要求されない。その代わりに、企業には次のことが認められる。
(a) 過去に IAS第 17号「リース」及び IFRIC第 4号「契約にリースが含まれているか否か
の判断」を適用してリースとして識別された契約に本基準を適用すること。企業は C5
項から C18項の経過措置をそれらのリースに適用しなければならない。
(b) 過去に IAS 第 17 号及び IFRIC第 4 号を適用してリースを含んでいるものとして識別
されなかった契約に本基準を適用しないこと。
C4 企業がC3項の実務上の便法を選択する場合には、その旨を開示し、実務上の便法をすべ
ての契約に適用しなければならない。その結果、企業は第 9 項から第 11 項の要求事項
を、適用開始日以後に締結(又は変更)された契約のみに適用しなければならない。
IFRS第16号は、2019年1月1日
以後開始する事業年度から適用さ
れる。
88 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
借手及び貸手は、既存の契約に IFRS 第 16 号で定義されるリースが含まれているかどうかを再評
価しないことを選択することができる。この実務上の簡便法を選択する場合には、IAS 第 17 号及び
IFRIC第 4号においてリースを含んでいない契約(例:サービス契約)も再評価する必要はない。
IFRS 第 16 号におけるリースの定義のガイダンスを適用して、既存の契約を再評価することを求め
た場合には、企業に対して過度なコストを負担させることになると IASB は考えたため、この実務上
の簡便法が設けられている。
実務上の簡便法を適用することを選択する場合には、その旨を開示し、適用開始日時点で存在して
いるすべての契約に適用する。したがって、リースごとに当該オプションを適用することはできない。
弊社のコメント
IAS 第 17 号に定められるオペレーティング・リースの会計処理はサービス契約の会計処理に
類似していることから、契約がリースであるか、サービス契約であるか、必ずしも検討する必要
がなかったと考えられる。企業によっては IAS 第 17 号及び IFRIC 第 4 号による評価を見直す
必要が出てくる。なぜなら、IFRS 第 16 号では大半のリースが借手の貸借対照表に計上される
ことになり、契約を、リースを含む契約としてではなくサービス契約として処理するとしたらその
影響が大きいためである。IFRS第 16号の実務上の簡便法では、契約にリースが含まれている
かどうかを再評価しないことを容認しているが、これは、IAS 第 17号及び IFRIC 第 4 号に基づ
き適切に評価された契約についてのみ適用できると考えられる。
9.3 借手の経過措置
IFRS第 16号からの抜粋
借手
C5 借手は、本基準をリースに次のいずれかにより適用しなければならない。
(a) IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」を適用して、表示する過去
の報告期間のそれぞれに遡及適用
(b) 遡及適用し、本基準の適用開始の累積的影響を C7項から C13項に従って適用開始
日に認識
C6 借手は、C5 項に記述した選択を、自らが借手であるリースのすべてに首尾一貫して適用し
なければならない。
C7 借手が本基準を C5 項(b)に従って適用することを選択する場合には、借手は比較情報を
修正再表示してはならない。その代わりに、借手は本基準の適用開始の累積的影響を、適
用開始日現在の利益剰余金(又は、適切な場合には、資本の他の内訳項目)の期首残高
の修正として認識しなければならない。
借手は、以下のいずれかにより、リースに対して IFRS第 16号を適用する。
• IAS第8号を適用して、表示する過去の報告期間すべてに遡及適用する(完全遡及適用アプ
ローチ)
• IFRS第16号の適用開始に伴う累積的影響を、適用開始日の利益剰余金(又は適切な場合に
は、その他の資本の内訳項目)の期首残高を修正して認識する(修正遡及適用アプローチ)
借手は、選択した移行アプローチを、すべての借手のリースについて首尾一貫して適用する。
89 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
9.3.1 完全遡及適用アプローチ
IAS第 8号からの抜粋
遡及適用
22 第23項に従い、会計方針の変更を第 19項(a)又は(b)に従って遡及適用する場合には、
企業は、表示する最も古い過去の期間について影響を受ける資本の各内訳項目の期首残
高及び表示する過去の各期間について開示するその他の比較対象金額を、新たな会計方
針を以前から適用していたかのように修正しなければならない。
遡及適用に対する制限
23 遡及適用が第 19 項(a)又は(b)により必要とされる場合には、会計方針の変更を遡及適
用しなければならない。ただし、当該変更の期間固有の影響又は累積的影響を測定するこ
とが実務上不可能である範囲は除く。
24 表示する 1 期又は複数の過去の期間に関する比較情報について会計方針を変更する場
合の期間固有の影響を測定することが実務上不可能である場合には、企業は、遡及適用
が実務上可能である最も古い期間の期首(当期である場合もある)の資産や負債の帳簿
価額に対し新たな会計方針を適用し、そして当該期間について影響を受ける資本の各内
訳項目の期首残高に対しそれに対応する修正をしなければならない。
25 当期の期首において、過去のすべての期間に新たな会計方針を適用することの累積的影
響を算定することが実務上不可能な場合には、企業は実務上可能な最も古い日付から将
来に向かって新たな会計方針を適用するために比較情報を修正しなければならない。
26 企業が新たな会計方針を遡及適用する場合には、企業は実務上可能である期間まで遡っ
て過去の期間の比較情報に新たな会計方針を適用する。過去の期間に対する遡及適用
は、当該期間について貸借対照表の期首と期末の残高に対する累積的影響を算定するこ
とが実務上可能である場合を除き、実務上可能ではない。財務諸表に表示する期間よりも
前の期間についての遡及適用により生じる修正金額は、表示する最も古い過去の期間に
ついて影響を受ける資本の各内訳項目の期首残高に計上する。通常、修正は利益剰余金
に対して行われる。しかし、修正が資本の他の内訳項目に対しても行われることがある(た
とえば、ある IFRS に準拠するために)。財務データの過年度要約など、過去の期間に関す
るその他の情報についても実務上可能な期間まで遡って修正される。
27 企業が、過去のすべての期間に対し新たな会計方針を適用することの累積的影響を測定
することができないため、新たな会計方針を遡及適用することが実務上不可能である場合
には、企業は第 25 項に従って、実務上可能な最も古い期間の期首から将来に向かって、
新たな方針を適用する。したがって、当該日付以前に発生した資産、負債及び資本に対す
る累積的修正分については考慮しない。会計方針の変更は、過去のいずれかの期間につ
いて将来に向かって当該方針を適用することが実務上不可能であっても、認められる。第
50項から第 53項は、新たな会計方針を 1期又は複数の過去の期間に適用することが実
務上不可能である場合の指針を示している。
完全遡及適用アプローチを選択した場合には、IAS第 8号に従って、財務諸表に表示されるすべて
の期間について IFRS第 16号の規定を適用する。
90 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IAS第 1号からの抜粋
会計方針の変更、遡及的修正再表示又は組替え
40A 企業は、次に該当する場合には、第 38A項で要求している最低限の比較財務諸表に加え
て、前期の期首現在の第 3の貸借対照表を表示しなければならない。
(a) 会計方針の遡及適用、財務諸表上の項目の遡及的修正再表示、又は財務諸表上の
項目の組替えを行い、かつ、
(b) その遡及適用、遡及的修正再表示又は組替えが、前期の期首現在の貸借対照表上
の情報に重要性のある影響を与える。
完全遡及適用アプローチでは、IFRS第16号を、財務諸表に表示されるすべてのリース契約につい
て、開始時から適用されていたかのように適用する。たとえば、2019 年 1 月 1 日から IFRS 第 16
号を適用する場合、比較期間が 1 期のみ表示されることを仮定すると、2019 年 12 月 31 日時点
における財務諸表において、2018年 12月 31日までの比較期間について修正再表示を行わなけ
ればならない。この場合、IAS 第 1 号に従って、2018 年 1 月 1 日時点の開始貸借対照表の修正
再表示が求められる。
9.3.2 借手の修正遡及適用アプローチ
9.3.2.1 過去にオペレーティング・リースに分類していたリース
IFRS第 16号からの抜粋
過去にオペレーティング・リースに分類していたリース
C8 借手が本基準を C5 項(b)に従って適用することを選択する場合には、借手は次のようにし
なければならない。
(a) 過去に IAS第 17号を適用してオペレーティング・リースに分類したリースについて、適
用開始日にリース負債を認識する。借手は、当該リース負債を、残りのリース料を適
用開始日現在の借手の追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値で測定しなけ
ればならない。
(b) 過去に IAS第 17号を適用してオペレーティング・リースに分類したリースについて、適
用開始日に使用権資産を認識する。借手は、リース 1 件ごとに、使用権資産を次のい
ずれで測定するのかを選択しなければならない。
(i) 本基準が開始日から適用されていたかのように帳簿価額で。ただし、適用開始日
現在の借手の追加借入利子率を用いて割り引く。
(ii) リース負債と同額で。ただし、適用開始日の直前に貸借対照表に認識した当該
リースに係る前払リース料又は未払リース料の金額の分だけ修正する。
(c) 適用開始日現在の使用権資産に IAS 第 36 号「資産の減損」を適用する。ただし、借
手が C10項(b)の実務上の便法を適用する場合を除く。
C9 C8 項の要求事項にかかわらず、過去に IAS 第 17 号を適用してオペレーティング・リース
に分類したリースについて、借手は、
(a) 原資産が少額であるリース(B3 項から B8 項に記述)のうち第 6 項を適用して会計処
理されるものについては、移行時に修正を行うことを要求されない。借手は、それらの
リースを適用開始日から本基準を適用して会計処理しなければならない。
(b) 過去に IAS 第 40 号「投資不動産」における公正価値モデルを用いて投資不動産とし
て会計処理したリースについては、移行時に修正を行うことを要求されない。借手は、
適用開始日から IAS第 40号及び本基準を適用して、当該リースから生じた使用権資
産及びリース負債を会計処理しなければならない。
(c) 過去に IAS 第 17 号を適用してオペレーティング・リースに分類し、適用開始日から
IAS 第 40 号における公正価値モデルを用いて投資不動産として会計処理するリース
については、使用権資産を適用開始日現在の公正価値で測定しなければならない。
借手は、適用開始日から IAS 第 40 号及び本基準を適用して、当該リースから生じた
使用権資産及びリース負債を会計処理しなければならない。
91 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
修正遡及適用アプローチでは、借手は比較年度の修正再表示を行わずに、IFRS 第 16 号の適用
開始に伴う累積的影響を、適用開始日の利益剰余金(又は、適切な場合には、その他の資本の内
訳項目)の期首残高を修正して認識する(セクション 9.2「経過措置」参照)。借手は、過去に IAS 第
17号に基づきオペレーティング・リースに分類していたリースに関して、リース負債を認識する。リー
ス負債は、残存リース料総額の適用開始日の借手の追加借入利子率を使用した割引現在価値で
測定される。借手は、個々のリースに関する使用権資産を以下のいずれかにより測定する。
• 開始日からIFRS第16号の適用を仮定した場合の帳簿価額(適用開始日の借手の追加借入
利率を使用する)
• リース負債と同額(既に認識した前払リース料又は未払リース料は調整する)
借手は、適用開始日において、使用権資産に IAS 第 36 号を適用する。ただし、借手が、セクション
「9.3.2.2 過去にオペレーティング・リースに分類していたリースに関する実務上の簡便法」で解説
する不利なリースに関する実務上の簡便法を適用している場合を除く。
借手は、新基準への移行時において、少額資産のリースを調整することは求められない(セクション
「4.1 当初認識」(借手)参照)。
借手は、過去に IAS第 40号における公正価値モデルを使用して投資不動産として会計処理してい
たリースについても、移行時の調整は求められていない。ただし、過去に IAS 第 17 号でオペレー
ティング・リースとして会計処理し、適用開始日から IAS 第 40 号における公正価値モデルを使用し
て投資不動産として会計処理するリースについては、使用権資産を適用開始日の公正価値で測定
しなければならない。
9.3.2.2 過去にオペレーティング・リースに分類していたリースに関する実務上の簡便法
IFRS第 16号からの抜粋
C10 借手は、過去に IAS第 17号を適用してオペレーティング・リースに分類していたリースに本
基準を C5 項(b)に従って遡及適用する際に、下記の実務上の便法のうち 1 つ又は複数を
使用することができる。借手はこれらの実務上の便法をリース 1 件ごとに適用することが認
められる。
(a) 借手は、特性が合理的に類似したリース(類似した経済環境における類似したクラス
の原資産についての、残存リース期間が類似したリースなど)のポートフォリオに単一
の割引率を適用することができる。
(b) 借手は、減損レビューを実施することの代替として、リースが適用開始日直前におい
て IAS 第 37 号「引当金、偶発負債及び偶発資産」を適用して不利であるかどうかの
評価に依拠することができる。借手がこの実務上の便法を選択する場合には、借手
は、適用開始日現在の使用権資産を、適用開始日の直前に貸借対照表に認識した不
利なリースに係る引当金の金額の分だけ修正しなければならない。
(c) 借手は、適用開始日から 12 ヵ月以内にリース期間が終了するリースについて、C8項
の要求事項を適用しないことを選択できる。この場合、借手は次のようにしなければな
らない。
(i) 当該リースを第 6項に記述している短期リースと同じ方法で会計処理する。
(ii) 当該リースに関連するコストを、適用開始日を含む事業年度における短期リース
費用の開示の中に含める。
(d) 借手は、当初直接コストを適用開始日現在の使用権資産の測定から除外することが
できる。
(e) 借手は、契約にリースを延長又は解約するオプションが含まれている場合にリース期
間を算定する際などに、事後的判断を使用することができる。
92 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
借手は、過去にオペレーティング・リースに分類していたリースに関して、個々のリースに以下の実
務上の便法を使用することができる。
• 類似した特徴を有するリースのポートフォリオに単一の割引率を適用する(同様の経済環境
における同様の種類の原資産について、同様の残存リース期間を有するリース等)
• 減損レビューを実施する代わりに、不利なリース契約に係る引当金に関して使用権資産を調
整する。借手がこの実務上の便法を選択する場合、借手は、適用開始日直前の貸借対照表
に計上されている不利な契約に関する引当金の額だけ使用権資産を適用開始日時点で調整
する。IASBは結論の根拠BC287項で、IFRS第16号に移行する時点でそれぞれの使用権資
産に関し減損判定を行うことは、多大なコストが発生すると説明している。さらに、IAS第37号
を適用して識別される不利なオペレーティング・リース負債は、使用権資産の減損を表す可能
性が高い。仮に適用開始日直前の不利な契約に関する引当金がゼロであるとしても、借手は
実務上の便法を適用して適用開始日時点の減損判定を行う必要がないと考えている。
• リース期間が適用開始日から12ヵ月以内に終了するリースに関して、認識の免除規定を適
用する
• 当初直接コストを使用権資産の測定から除外する
• リースを延長又は解約するオプションを含んでいる契約におけるリース期間の算定などに、事
後的な判断を使用する。IFRS第16号は、事後的な判断の使用に関する詳細なガイダンスを
定めていない。しかし、IAS第8号第53項の規定同様、判断と見積りを要する事項にのみ事後
的な判断を用いることができ、したがって、指数や料率の変更などの事実に関係する項目に
事後的な判断を用いることはできないと考えている。
IFRS 第 16 号は、移行時に修正遡及適用法を採用する場合、契約のうちリース構成要素と非リー
ス構成要素をどのように区分し配分すべきかを定めていない。我々は、借手は IFRS第 16号 13項
から 16 項を適用して、リース開始日に算定される契約における対価を、同日のリース構成要素の
相対的独立販売価格を基にそれぞれのリース構成要素と非リース構成要素に配分すると考えてい
る。ただし、借手が各リース構成要素と関連する非リース構成要素を単一のリース構成要素として
会計処理する実務上の便法を用いる場合を除く。上記 3.2を参照。同様の結果になる他のアプロー
チも許容される。
9.3.3 過去にファイナンス・リースに分類していたリース
IFRS第 16号からの抜粋
過去にファイナンス・リースに分類していたリース
C11 借手が本基準を C5項(b)に従って適用することを選択する場合は、IAS第 17号を適用して
ファイナンス・リースに分類されていたリースについて、適用開始日現在の使用権資産及び
リース負債の帳簿価額は、IAS 第 17 号を適用して測定した同日直前におけるリース資産及
びリース負債の帳簿価額としなければならない。それらのリースについて、借手は適用開始
日からは本基準を適用して使用権資産及びリース負債を会計処理しなければならない。
借手は、IFRS 第 16 号の適用開始日に存在するファイナンス・リースに係る資産及び負債に関して、
従来の帳簿価額を変更することなく使用することになる。
93 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
設例 19 ―― 完全遡及適用法及び修正遡及適用法を用いたリース契約の
移行時の会計処理
小売業者(借手)は、2017 年 1 月 1 日に小売スペースに係るリース契約(契約期間は 3 年)を
締結した。年間のリース料は 1,000 百万円であり、2017 年、2018 年、2019 年の 12 月 31
日にそれぞれリース料が支払われる。当該リース契約は、IAS 第 17 号に従ってオペレーティン
グ・リースに分類されていた。同小売業者は、2019 年 1 月 1 日に開始する事業年度から IFRS
第 16号を適用する。
IFRS 第 16 号の適用開始日時点の追加借入利子率は年率 3%であり、リース開始日時点の追
加借入利子率は年率 6%であった。使用権資産はリース期間にわたり定額法で減価償却され
る。年率 6%を用いて算定した 2017年 1月 1日時点の残存リース料の現在価値は 2,673百
万円である。また、年率 3%を用いて算定した 2018年 1月 1日時点の残存リース料の現在価
値は 2,829百万円、2019年 1月 1日時点の残存リース料の現在価値は 971百万円である。
実務上の便法は適用しない。
単純化のため、この設例では以下の仮定を置く。
• 借手には当初直接コストは発生しない
• リース・インセンティブはない
• 原資産を解体及び除去し、原資産の敷地を原状回復する、又はリースの条件に定められる
状態に原資産を戻す取決めはない
以下の例は、完全遡及適用アプローチと修正遡及適用アプローチを用いた場合の適用開始日
のリース負債及び使用権資産並びにリースに係る費用の算定方法を示している。
完全遡及適用アプローチ
分析: 完全遡及適用アプローチでは、リース負債及び使用権資産を開始日の追加借入利子率
を用いて測定する。その後、リース負債は利息法を用いて測定し、使用権資産はリース期間であ
る 3 年にわたり定額法で減価償却する。以下の表は、リース開始日から完全遡及アプローチを
採用した場合の勘定残高を示している。
使用権
資産
リース
負債
利息費用 償却費用 利益
剰余金
2017年 1月 1日 2,6731 2,6731 – – –
2017年 12月 31日 1,7822 1,8333 1604 8915 (51)
2018年 12月 31日 8916 9437 1108 891 –
2019年 1月 1日 891 943 – – –
2019年 12月 31日 – – 579 891 – 1 リース料(1,000百万円)の現在価値(割引率は 6%)
2 2,673百万円 – (2,673百万円/ 3 年) = 1,782百万円
3 2,673百万円(前年末のリース負債) – 1,000百万円(現金支払い) + 160百万円(当期利息費用) =
1,833百万円
4 2,673百万円× 6% = 160百万円
5 2,673百万円/ 3 年 = 891百万円
6 1,782百万円– (2,673百万円/ 3 年) = 891百万円
7 1,833百万円(前年末のリース負債) – 1,000百万円(現金支払い) + 110百万円(当期利息費用) =
943百万円
8 1,833百万円× 6% = 110百万円
9 943百万円× 6% = 57百万円
94 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
設例 19 ―― 完全遡及適用法及び修正遡及適用法を用いたリース契約の
移行時の会計処理
IFRS第 16号の適用時点で、借手は上記表の 2017年 12月 31日時点の帳簿価額で使用権
資産とリース負債を計上するとともに、使用権資産とリース負債の差額を 2018 年 1 月 1 日時
点の利益剰余金に計上する(2018年財務情報のみが比較情報として含まれると仮定する)。
(単位:百万円)
使用権資産 1,782
利益剰余金 51
リース負債 1,833
2018年 1月 1日現在のリース関連資産及び負債を当初認識する
以下の仕訳が 2018年に行われる:
利息費用 110
リース負債 110
利息法を用いて利息費用を計上し、リース負債を増加させる
減価償却費 891
使用権資産 891
使用権資産の減価償却費を計上する
リース負債 1,000
現金 1,000
リース料の支払いに伴いリース負債の認識を中止する
以下の仕訳が 2019年に行われる:
利息費用 57
リース負債 57
利息法を用いて利息費用を計上し、リース負債を増加させる
減価償却費 891
使用権資産 891
使用権資産の減価償却費を計上する
リース負債 1,000
現金 1,000
リース料の支払いに伴いリース負債の認識を中止する
95 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
設例 19 ―― 完全遡及適用法及び修正遡及適用法を用いたリース契約の
移行時の会計処理
修正遡及適用アプローチ(代替 1)
分析: 修正遡及適用アプローチ(代替 1)では、残存リース料を適用開始日時点の借手の追加
借入利子率(年率 3%)を用いて割り引くことにより、リース負債の金額を測定する。 使用権資
産は、IFRS 第 16 号が開始日から適用されていたと仮定した場合の帳簿価額とする。使用権資
産は、リース期間である 3年間にわたり定額法で減価償却する。
(単位:百万円)
使用権資産 94310
利益剰余金 2811
リース負債 97112
2019年 1月 1日現在のリース関連資産と負債を当初認識する
以下の仕訳が 2019年に行われる:
(単位:百万円)
利息費用 2913
リース負債 29
利息法を用いて利息費用を計上し、リース負債を増加させる
減価償却費 943
使用権資産 943
使用権資産の減価償却費を計上する
リース負債 1,000
現金 1,000
リース料の支払いに伴いリース負債の認識を中止する
修正遡及適用アプローチ(代替 2)
分析: 修正遡及適用アプローチ(代替 2)でも、上記の代替 1 と同様に、適用開始日時点の追加
借入利子率を用いて、残存リース料総額を割り引くことによりリース負債の金額を測定する。こ
の例では、前払リース料及び未払リース料が存在していないため、使用権資産の帳簿価額は適
用開始日時点のリース負債の金額に等しくなる。
使用権資産 97112
リース負債 97112
2019年 1月 1日現在のリース関連の資産及び負債を当初認識する
以下の仕訳が 2019年に行われる:
(単位:百万円)
利息費用 2913
リース負債 29
利息法を用いて利息費用を計上し、リース負債を増加させる
減価償却費 97112
使用権資産 971
使用権資産の減価償却費を計上する
リース負債 1,000
現金 1,000
リース料の支払いに伴いリース負債の認識を中止する
10 2,829百万円 (開始日時点のリース料(1,000百万円)の現在価値(割引率は 3%) )–
(2,829百万円/ 3 年) × 2 = 943百万円
11 971百万円– 943百万円= 28百万円
12 適用開始日時点のリース料(1,000百万円)の現在価値(割引率は 3%)
13 971百万円× 3% = 29百万円
96 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
設例 19 ―― 完全遡及適用法及び修正遡及適用法を用いたリース契約の
移行時の会計処理
リース契約の会計処理のまとめると、以下のとおりとなる(再評価による変更はないと仮定)。
完全遡及適用
アプローチ
修正遡及適用
アプローチ
(代替 1)
修正遡及適用
アプローチ
(代替 2)
2019年 1月 1日現在の期首貸借対照表への影響
使用権資産 891百万円 943百万円 971百万円
リース負債 943百万円 971百万円 971百万円
2019年 12月 31日に終了する期間の活動
リース料の支払い 1,000百万円 1,000百万円 1,000百万円
リース費用の認識額
利息費用 57百万円 29百万円 29百万円
減価償却費 891百万円 943百万円 971百万円
合計 期間費用 948百万円 972百万円 1,000百万円
上記の例では計算上四捨五入しているため、計算結果に軽微な差が生じている。
9.4 貸手
IFRS第 16号からの抜粋
貸手
C14 C15 項に記述する場合を除いて、貸手は、自らが貸手であるリースについて移行時に修正
を行うことを要求されず、当該リースを適用開始日から本基準を適用して会計処理しなけれ
ばならない。
貸手は、下記で解説するサブリースを除き、貸手のリースに関して、移行時に修正を行うことは求め
られない。すなわち、貸手は、適用開始日から IFRS第 16号を適用してリースの会計処理を行う。
9.4.1 サブリース
IFRS第 16号からの抜粋
貸手
C15 中間の貸手は、次のようにしなければならない。
(a) IAS第 17号を適用してオペレーティング・リースに分類され適用開始日現在で継続中
のサブリースを見直して、それぞれのサブリースを本基準を適用してオペレーティン
グ・リース又はファイナンス・リースのいずれに分類すべきかを決定する。中間の貸手
は、この評価を適用開始日において同日現在のヘッドリース及びサブリースの残りの
契約条件に基づいて行わなければならない。
(b) IAS 第 17 号を適用してオペレーティング・リースに分類されたが本基準を適用すると
ファイナンス・リースであるサブリースについては、当該サブリースを適用開始日に締
結された新たなファイナンス・リースとして会計処理する。
中間の貸手(同一の原資産の借手及び貸手となる企業)は、適用開始日に存在するオペレーティン
グ・リースに分類されるサブリースが、IFRS 第 16 号においてオペレーティング・リース又はファイナ
ンス・リースのいずれに分類されるのかを判断するために再評価を行う。この再評価は、原資産で
はなく、ヘッドリースに関連する使用権資産を参照して、ヘッドリースとサブリースの残りの契約条件
に基づいて行われる。
IAS 第 17 号においてオペレーティング・リースに分類されていたサブリースが、IFRS 第 16 号では
ファイナンス・リースに分類される場合には、中間の貸手は当該サブリースを適用開始日に締結さ
れた新たなファイナンス・リースとして会計処理する。サブリースから生じる利得又は損失は、適用
開始日の利益剰余金(又はその他の資本の内訳項目)の累積的なキャッチアップ修正に含める。
97 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
9.5 その他の検討事項
9.5.1 セール・アンド・リースバック取引
IFRS第 16号からの抜粋
適用開始日より前のセール・アンド・リースバック取引
C16 企業は、適用開始日前に締結されたセール・アンド・リースバック取引を、原資産の譲渡が
売却として会計処理されるための IFRS第 15号の要求事項を満たしているかどうかを決定
するために見直してはならない。
C17 セール・アンド・リースバック取引が IAS 第 17 号を適用して売却とファイナンス・リースとし
て会計処理されていた場合には、売手である借手は次のようにしなければならない。
(a) リースバックを、適用開始日現在で存在している他のファイナンス・リースを会計処理
するのと同じ方法で会計処理する。
(b) 引き続き、売却に係る利得をリース期間にわたり償却する。
C18 セール・アンド・リースバック取引が IAS 第 17 号を適用して売却とオペレーティング・リース
として会計処理されていた場合には、売手である借手は次のようにしなければならない。
(a) リースバックを、適用開始日現在で存在している他のオペレーティング・リースを会計
処理するのと同じ方法で会計処理する。
(b) リースバックによる使用権資産を、適用開始日の直前の貸借対照表において認識した
市場の条件と異なる部分に関して繰り述べた利得又は損失について修正する。
売手である借手は、IFRS第 15号に従い売却が生じているかどうかを判断するために、過去のセー
ル・アンド・リースバック取引を見直すことは認められない。
売手である借手は、IFRS 第 16 号への移行日において、セール・アンド・リースバック取引を遡及修
正しない代わりに、リースバック取引を、下記の事項に従い、適用開始日において存在する他の
リースと同じ方法により会計処理する。
• 過去にファイナンス・リースに分類していたセール・アンド・リースバック取引の場合には、売却
に係る利得を、IAS第17号と同じ方法で継続して償却する
• 過去にオペレーティング・リースに分類していたセール・アンド・リースバック取引の場合には、
適用開始日におけるオフマーケット条件に関して繰り延べられた利得又は損失を使用権資産
で調整する
9.5.2 過去に企業結合で認識した金額
IFRS第 16号からの抜粋
過去に企業結合に関して認識した金額
C19 借手が、企業結合の一部として取得したオペレーティング・リースの有利又は不利な条件に
関して、IFRS 第 3 号「企業結合」を適用して過去に資産又は負債を認識した場合には、借
手は、適用開始日において、当該資産及び負債の認識の中止を行うとともに、使用権資産
の帳簿価額を対応する金額の分だけ修正しなければならない。
借手が、企業結合の一部として取得したオペレーティング・リースの有利又は不利な条件に関して、
過去に資産又は負債を認識していた場合には、借手は当該資産及び負債の認識の中止を行うとと
もに、対応する金額について使用権資産の調整を行う。
98 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
9.6 開示
9.6.1 適用開始時における開示規定
IFRSの基準を遡及適用する場合には、IAS第 8号で求められる開示を行う。
IAS第 8号からの抜粋
開示
28 ある IFRS の適用開始が、当期又は過去の期間に影響を与える場合、そのような影響があ
るが修正額の算定が実務上不可能である場合、又は将来の期間に影響を与えるかもしれ
ない場合には、企業は次の事項を開示しなければならない。
(a) 当該 IFRSの名称
(b) 該当する場合には、会計方針の変更が経過措置に従って行われた旨
(c) 会計方針変更の内容
(d) 該当する場合には、経過措置の概要
(e) 該当する場合には、将来の期間に影響を与えるかもしれない経過措置
(f) 当期及び表示する過去の各期間について、実務上可能な範囲で、次の事項に関する
修正額
(i) 影響を受ける財務諸表の各表示項目
(ii) IAS 第 33 号「1 株当たり利益」が企業に適用される場合、基本的及び希薄化後
1株当たり利益
(g) 表示している期間よりも前の期間に関する修正額(実務上可能な範囲で)
(h) 第 19項(a)又は(b)で求められる遡及適用が、特定の過去の期間について又は表示
する期間よりも前の期間について、実務上不可能である場合には、その状態が存在
するに至った状況、及び会計方針の変更がどのように、そしていつから適用されてい
るかの概要の記載
その後の期間の財務諸表でこれらの開示を繰り返す必要はない。
9.6.2 修正遡及適用アプローチを選択する借手の追加の開示
IFRS第 16号からの抜粋
開示
C12 借手が本基準を C5 項(b)に従って適用することを選択する場合には、借手は IAS 第 8 号
の第 28 項で要求されている適用開始に関する情報を開示しなければならない。ただし、
IAS 第 8 号の第 28 項(f)で定めている情報は除く。IAS 第 8 号の第 28 項(f)で定めてい
る情報の代わりに、借手は下記を開示しなければならない。
(a) 適用開始日現在の貸借対照表に認識されているリース負債に適用している借手の追
加借入利子率の加重平均
(b) 次の両者の差額の説明
(i) 適用開始日の直前の事業年度の末日現在で IAS第 17号を適用して開示したオ
ペレーティング・リース約定(C8 項(a)に記述した適用開始日現在の追加借入利
子率で割引後)
(ii) 適用開始日現在の貸借対照表に認識したリース負債
C13 借手が C10 項に示した実務上の便法のうち1つ又は複数を使用する場合には、その旨を
開示しなければならない。
99 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
借手は、IAS第 17号と比較した新基準の適用による影響を、財務諸表利用者が理解するために役
立つような特定の開示が求められる。借手は、IAS 第 8 号第 28 項(f)の規定の代わりに、以下を
開示する。
• 適用開始日における追加借入利子率の加重平均
• 下記の差額に関する説明
• 適用開始日直前の年次報告期間の末日において、IAS第17号で報告されていたオペ
レーティング・リースに関するコミットメントの割引額
• 適用開始日に累積的なキャッチアップ調整を行うことで貸借対照表に計上されるリース
負債の金額。短期リース及び少額資産のリースに関する認識の免除規定を適用した場
合において、差額が生じる可能性がある。
100 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
付録A:IFRS第16号の用語の定義
以下の表は、IFRS第 16号の付録 Aに定義される用語を要約している。
用語 定義
リースの開始日(開始日) 貸手が借手による原資産の使用を可能にする日
経済的耐用年数 資産が 1 名又は複数の利用者により経済的に使用可能と見込ま
れる期間、あるいは資産から 1 名又は複数の利用者が得ると見
込まれる生産物の数又は類似の単位
条件変更の発効日 両方の当事者がリースの条件変更に合意した日
公正価値 本基準における貸手の会計処理の目的上、独立第三者間取引に
おいて、取引の知識がある自発的な当事者の間で、資産が交換さ
れ得るか又は負債が決済され得る金額
ファイナンス・リース 原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転す
るリース
固定リース料 リース期間中に原資産を使用する権利に対して借手が貸手に行う
支払い(変動リース料を除く)
リース投資未回収総額 次の合計額
(a) ファイナンス・リースにおいて貸手が受け取るべきリース料
(b) 貸手に発生している無保証残存価値
リースの契約日(契約日) リース契約の日又は当事者がリースの主要な契約条件について
確約した日のいずれか早い日
当初直接コスト リースの取得の増分コストのうち、当該リースを取得しなければ発
生しなかったであろうコスト(フ ァイナンス・リースに関して製造業
者又は販売業者である貸手に生じたコストを除く)
リースの計算利子率 (a)リース料と(b)無保証残存価値の現在価値を、(i)原資産の公
正価値と(ii)貸手の当初直接コストとの合計額と等しくする利子率
リース 資産(原資産)を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に
移転する契約又は契約の一部分
リース・インセンティブ 貸手が借手にリースに関連して行う支払い、又は貸手による借手
のコストの弁済若しくは引受け
リースの条件変更 リースの当初の契約条件の一部ではなかったリースの範囲又は
リースの対価の変更(たとえば、1 つ若しくは複数の原資産を使用
する権利の追加若しくは解約、又は契約上のリース期間の延長又
は短縮)
101 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
用語 定義
リース料 借手が貸手にリース期間中に原資産を使用する権利に関して行う
支払いであり、次のもので構成される。
(a) 固定リース料(実質上の固定リース料を含む)からリース・イ
ンセンティブを控除したもの
(b) 変動リース料のうち指数又はレートに応じて決まるもの
(c) 購入オプションの行使価格(借手が当該オプションを行使す
ることが合理的に確実である場合)
(d) リースの解約のためのペナルティの支払い(リース期間が借
手がリースを解約するオプションを行使することを反映してい
る場合) 借手については、リース料には、借手が残価保証に
基づいて支払うと見込まれる金額も含まれる。
借手については、リース料には、契約の非リース構成部分に配分
された支払いは含めない。ただし、借手が非リース構成部分とリー
ス構成部分を合算して単一のリース構成部分として会計処理する
ことを選択する場合は除く。
貸手については、リース料には、貸手に提供された残価保証(借
手、借手と関連のある当事者、又は貸手と関連のない第三者で保
証に基づく義務を弁済する財務上の能力のある者が行うもの)も
含まれる。リース料には、非リース構成部分に配分された支払い
は含めない。
リース期間 借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、次の両
方を加えた期間
(a) リースを延長するオプションの対象期間(借手が当該オプショ
ンを行使することが合理的に確実である場合)
(b) リースを解約するオプションの対象期間(借手が当該オプショ
ンを行使しないことが合理的に確実である場合)
借手 原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得す
る企業
借手の追加借入利子率 借手が、同様の期間にわたり、同様の保証を付けて、使用権資産
と同様の価値を有する資産を同様の経済環境において獲得する
のに必要な資金を借り入れるために支払わなければならないであ
ろう利率
貸手 原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に提供す
る企業
正味リース投資未回収額 リース投資未回収総額をリースの計算利子率で割り引いた額
オペレーティング・リース 原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転す
るものではないリース
オプション・リース料 リースを延長又は解約するオプションの対象期間のうちリース期
間に含まれていない期間において原資産を使用する権利に対して
借手が貸手に行う支払い
使用期間 資産が顧客との契約を履行するために使用される期間(非連続の
期間を含む)
残価保証 貸手と関連のない者が貸手に対して行う、リースの終了時の原資
産の価値(又は価値の一部)が少なくとも所定の金額となるという
保証
使用権資産 借手が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産
102 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
用語 定義
短期リース 開始日において、リース期間が 12 ヵ月以内であるリース。購入オ
プションを含んだリースは、短期リースではない。
サブリース 原資産が借手(「中間的な貸手」)から第三者にさらにリースされ、
当初の貸手と借手との間のリース (「ヘッドリース」)が依然として
有効である取引
原資産 リースの対象である資産で、貸手によって借手に当該資産を使用
する権利が移転されているもの。
未稼得金融収益 次の両者の差額
(a) リース投資未回収総額
(b) 正味リース投資未回収額
無保証残存価値 原資産の残存価値のうち、貸手による実現が確実でないか、又は
貸手と関連のある者のみが保証している部分
変動リース料 リース期間中に原資産を使用する権利に対して借手が貸手に行う
支払いのうち、開始日後に発生する事実又は状況の変化(時の経
過を除く)により変動する部分
他の基準で定義され、本基準において同じ意味で使用されている用語
契約 強制可能な権利及び義務を創出する複数の当事者間の合意
耐用年数 資産が企業によって利用可能であると見込まれている期間、又は企
業が当該資産から得ると見込まれる生産物の数又は類似の単位
103 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
付録B:IFRS第16号とIAS第17号との主要な差異
下記の表では、IFRS第 16号と IAS第 17号との主要な差異をまとめている。IAS第 17号に基づ
くリースの会計処理の詳細については、弊法人出版の IFRS国際会計の実務 International GAAP
2019第 22章「リース」2を参照されたい。
IFRS第 16号 IAS第 17号
リースの定義 IFRS 第 16 号では、リースとは、
資産(原資産)を使用する権利を
一定期間にわたり対価と交換に
移転する契約又は契約の一部を
いう。
支配する権利が顧客に移転して
いるかどうかを判断するために
は、顧客が使用期間全体を通じ
て、特定された資産の使用から生
じる経済的便益のほとんどすべて
を得る権利及び特定された資産
の使用を指図する権利を有してい
るかどうかを評価する(セクション
2.1「契約にリースが含まれている
か否かの判断」)。
IAS 第 17 号では、リースとは、貸
手が一括又は複数回の支払いを
得て、契約期間中、資産の使用権
を借手に移転する契約をいう。
IFRIC 第 4 号「契約にリースが含
まれているか否かの判断」の下で
は、IAS 第 17 号の適用範囲に含
まれるために、契約による資産の
使用を支配する権利の移転は求
められていない。
認識の免除規定
短期リース―借手 借手は、リース期間が 12 ヵ月以
内であり、購入オプションを有して
いないリースに関して、使用権に
関連する原資産の種類ごとに、
IAS 第 17 号のオペレーティング・
リースと同様の会計処理の適用を
選択できる(セクション 4.1.1「短
期リース」)。
該当なし
少額資産のリース―
借手
借手は、少額資産のリースに関し
て、個々のリースごとに IAS第 17
号のオペレーティング・リースと同
様の会計処理の適用を選択でき
る(例:タブレットやパソコン、オ
フィス用小型家具、電話。セクショ
ン 4.1.2「少額資産リース」)。
該当なし
分類
リースの分類―
借手
借手は、すべてのリースに単一の
認識及び測定アプローチを適用
する。
ただし、借手は、短期リース及び
少額資産のリースについて、使用
権資産及びリース負債を認識しな
いことを選択できる(セクション
4.1「当初認識」)。
借手は、すべてのリースに 2種類
の認識及び測定アプローチを適
用する。
借手は、所有に伴うリスクと経済
価値のほとんどすべてを移転する
リースをファイナンス・リースに分
類し、それ以外のリースをオペ
レーティング・リースに分類する。
2 IFRS国際会計の実務 International GAAP 2019
104 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号 IAS第 17号
測定
当初測定に
含められる
リース料―借手
借手は、開始日において、リース
負債を、リース期間にわたり支払
われるリース料総額の現在価値
で測定する(短期リース及び少額
資産のリースを除く)。
リース料には、以下が含まれる
(セクション 4.2.2「リース負債」)。
(a) 固定支払い(実質的に固定さ
れた支払いを含む)から、受
領したリース・インセンティブ
を控除した額
(b) 指数又はレートに応じて決ま
る変動リース料(開始日の指
数又はレートを使用して当初
測定する)
(c) 残価保証に基づいて借手に
よる支払いが見込まれる
金額
(d) 購入オプションの行使価格
(借手による購入オプション
の行使が合理的に確実な
場合)
(e) リースの解約ペナルティに係
る支払い(借手によるリース
の解約オプションの行使が、
リース期間に反映されている
場合)
使用権資産の取得原価は、以下
により構成される(セクション
4.2.1「使用権資産」)。
(a) リース負債
(b) 開始日前に支払われたリー
ス料から、受領したリース・イ
ンセンティブを控除した額
(c) 当初直接コスト
(d) 資産除去債務(棚卸資産の
製造のために生じるコストは
除く)
借手は、リース期間の起算日にお
いて、ファイナンス・リースを、リー
ス開始日に算定したリース物件の
公正価値又は最低リース料総額
の現在価値のいずれか低い金額
で、資産及び負債として貸借対照
表に認識する。
最低リース料総額とは、借手が
リース期間にわたって支払う、又
は支払うことになる金額(変動リー
ス料、サービスに対するコスト及
び貸手が立替払いした諸税金の
支払いを除く)であり、借手の場合
には、借手又は借手と関連のある
者が支払いを保証している額を加
算する。
オペレーティング・リースでは、当
初測定において資産及び負債は
認識されない。
105 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号 IAS第 17号
リース負債の
再評価―借手
開始日後において、別個の契約と
して会計処理されないリースの条
件変更が生じた場合(リース範囲
の変更や、リースの当初の契約条
件には含まれていなかった対価の
変更)、借手はリース負債を再測
定することが求められる(セクショ
ン 4.5「リース契約の条件変更」)。
以下のいずれかが変更された場
合には、借手は、リース料を再測
定することが求められる。
• リ ー ス期 間 ( セ ク シ ョ ン
3.4.1)
• 借手が原資産の購入オプ
ションを行使することが合理
的に確実かどうかの評価(セ
クション 3.4.1.1)
• 残価保証に基づいて支払い
が見込まれる金額(セクショ
ン 3.5.6)
• 指数又はレートの変動に伴う
将来のリース料(セクション
3.5.3)
現行の IFRS では取り扱われてい
ない。
原価モデル以外の
使用権資産の
測定基礎―借手
借手が投資不動産について IAS
第 40号における公正価値モデル
を適用している場合には、投資不
動産の定義を満たす使用権資産
についても公正価値モデルが適
用される(セクション 4.3.1「使用
権資産」)。
借手が保有する不動産の持分
が、投資不動産として会計処理さ
れる場合には、IAS 第 40 号によ
り測定されるため、IAS第17号の
適用範囲には含まれない。
106 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号 IAS第 17号
リース契約の
条件変更
オペレーティング・
リースの条件変更―
貸手
貸手は、オペレーティング・リース
の条件変更を当該条件変更の発
効日から新たなリースとして会計
処理しなければならない。
当初のリースに係る前払リース料
又は未払リース料は、新たなリー
スに係るリース料の一部として取
り扱う(セクション 5.5.2「オペレー
ティング・リースの条件変更」)
現行の IFRS では取り扱われてい
ない。
別個の新たな
リースが生じない
リース契約の条件
変更―借手及び貸手
借手:
(a) 条件変更後の契約における
対価を配分する
(b) 条件変更後のリースのリー
ス期間を決定する
(c) 条件変更後のリース料を条
件変更後の割引率で割り引
くことにより、リース負債を再
測定し、対応する金額を使用
権資産で調整する
さらに借手は、リースの全部又は
一部の解約に係る利得又は損失
を純損益で認識する。
ファイナンス・リースの貸手:(条件
変更が開始日において有効であ
ることを仮定した際に、リースがオ
ペレーティング・リースに分類され
る場合)
(i) 当該条件変更を新たなリー
スとして会計処理する
(ii) 原資産の帳簿価額を条件変
更の発効日直前の正味リー
ス投資未回収額で測定する
上記以外の場合、条件変更は
IFRS 第 9 号「金融商品」に従って
会計処理される(借手の場合はセ
クション 4.5.2「別個のリースが生
じないリース契約の条件変更に係
る借手の会計処理」、貸手の場合
は 5.5.1.2「別個のリースが生じ
ないリース契約の条件変更に係
る貸手の会計処理」)。
現行の IFRS では取り扱われてい
ない。
107 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号 IAS第 17号
表示及び開示
表示―借手 貸借対照表―使用権資産(投資
不動産の定義を満たす場合を除
く)を他の資産と区分して表示す
る。貸借対照表において使用権
資産を区分して表示しない場合に
は、借手は使用権資産を、原資産
として所有していた場合と同じ表
示科目に含めて表示し、使用権
資産が含まれる貸借対照表の表
示科目を開示する。
リース負債は、他の負債と区分し
て表示する。貸借対照表において
リース負債を区分して表示しない
場合には、借手はリース負債が含
まれる貸借対照表の表示科目を
開示する。
損益計算書―リース負債に係る
利息費用と使用権資産に係る減
価償却費を区分して表示する。
リース負債に係る利息費用は、財
務費用を構成するため、IAS 第 1
号「財務諸表の表示」第 82項(b)
により、損益計算書において区分
して表示することが求められる。
キャッシュ・フロー計算書―リース
負債の元本部分に対する現金の
支払いは財務活動に分類し、金
利部分に対する現金の支払い
は、支払利息に関する IAS第7号
に従って分類する。
短期リース及び少額資産のリース
に係るリース料ならびにリース負
債の測定に含めなかった変動
リース料は、営業活動に分類する
(セクション 4.7「表示」)。
貸借対照表における表示―取り
扱われていない
損益計算書―オペレーティング・
リースに関する費用は、単一の項
目で表示する。
キャッシュ・フロー計算書―オペ
レーティング・リースに関する現金
の支払いは、営業活動として表示
する。
開示―借手及び貸手 開示の形式を含む詳細な開示が
求められる。
また、開示の目的を満たすために
リース活動に関する定性的情報
及び定量的情報が求められる(セ
クション 4.8「開示」及び 5.8「借手
及び貸手による開示」)。
定量的及び定性的開示は求めら
れているが、通常、IFRS 第 16 号
で求められる開示より少ない。
108 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号 IAS第 17号
セール・アンド・
リースバック取引
セール・アンド・
リースバック取引―
売却が生じているか
どうかの判断
売手 /借手及び買手 /貸手は、
IFRS 第 15 号の要求事項を適用
し、セール・アンド・リースバック取
引において売却が生じているかど
うかを判断する(セクション 7.1「資
産の譲渡が売却であるか否かの
判断」)。
リースバックがオペレーティング・
リース又はファイナンス・リースの
いずれに該当するかに焦点を当
てており、売手/借手及び買手/貸
手は、資産の譲渡が IAS第 18号
の売却の要件を満たすことは明
示的に求められていない。
セール・アンド・
リースバック取引―
売手/借手の
会計処理
売手/借手は、従前の資産の帳簿
価額のうち売手/借手が保持した
使用権に係る部分により、リース
バックから生じた使用権資産を測
定し、買手/貸手に移転された権
利に関してのみ利得又は損失を
認識する(セクション 7.2.1「売却
の会計処理」)。
セール・アンド・リースバック取引
によりファイナンス・リースが生じ
る場合には、売却代金のうち帳簿
価額を上回る額を繰り延べ、リー
ス期間にわたって償却する。
セール・アンド・リースバック取引
によりオペレーティング・リースが
生じ、かつ当該取引が公正価値
に基づいていることが明らかな場
合には、直ちに損益を認識する。
セール・アンド・
リースバック取引―
公正価値で行われて
いない取引に係る
売手/借手の
会計処理
資産の売却に係る対価の公正価
値が資産の公正価値と等しくない
場合、又はリース料が市場相場と
異なる場合には、売却収入を公正
価値で測定し、リース料の前払
(市場条件を下回る場合)、又は
追加の融資(市場条件を上回る場
合)として、適切な方法で調整を
行う。
(セクション 7.2.3「オフマーケット
条件に関する修正」)。
セール・アンド・リースバック取引
により生じるオペレーティング・
リース:
売却価格が公正価値を下回る場
合―直ちに損益を認識する。
ただし、売却損が発生し、当該損
失がその後のリース料を市場価
格よりも低くすることにより補填さ
れる場合には、以下を行う。
• 当該損失を繰り延べ、資産
の使用が見込まれる期間に
わたって、リース料に比例し
て償却する。
• 売却価格が公正価値を上回
る場合―公正価値を上回る
金額を繰り延べ、資産の使
用が見込まれる期間にわた
り償却する。
企業結合
企業結合―被取得
企業が借手の場合―
当初測定
取得企業は、リース期間が取得日
から 12 ヵ月以内に終了するリー
ス、及び少額資産のリースに関し
て、使用権資産及びリース負債を
認識することは求められない。
取得企業は、使用権資産を、市場
条件と比較して有利又は不利な
リース条件を反映するように調整
し、リース負債と同じ金額で測定
する(セクション 8.1.1「リースの当
初測定」)。
残存リース期間が取得日から
12ヵ月以下となるリース及び原資
産が少額のリースに関して免除規
定は設けられていない。
オペレーティング・リースの条件が
市場条件と比較して有利な場合
には無形資産が認識され、不利
な場合には負債が認識される。
リースが市場条件に基づく場合で
あっても、市場参加者が当該リー
スの価格を支払う意思を有してい
る場合には、無形資産が、オペ
レーティング・リースに関連してい
る場合がある。
109 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
付録C:IFRS第16号とASC第842号との主な差異
IASBは、IFRS第 16号と同様の基準書である ASC第 842号「リース」を公表した米国の FASB と
共同で審議を行った上で、IFRS第 16号を公表した。IFRS第 16号と ASC第 842号は、借手に大
半のリースをオンバランスすることを求めている。ただし、両基準書の間には、かなり多くの差異が
存在する。以下の表はそのうちの主な差異を示しており、IASB と FASB がそれぞれの基準書(すな
わち IFRS 第 16 号及び ASU2016-2)の結論の根拠で示されている差異に関する説明を要約して
いる。
IFRS第 16号 US GAAP ASC第 842号
範囲及び測定に関する例外規定
少額資産に関する
免除措置3
原資産の価値が少額な場合に
(たとえば、新品時に 5,000 米ド
ル以下)、借手はリースごとに、
リースを認識しないという選択が
できる。
原資産の価値を基にしたリースの
認識免除措置はない。
無形資産に関する
範囲に関する
免除措置4
映画フィルム、ビデオ、演劇、脚
本、特許や著作権など、IAS第38
号「無形資産」の適用範囲に含ま
れるライセンス契約に基づいて借
手が保有する権利以外の無形資
産については、借手は IFRS第16
号を適用できる。
貸手は、IFRS 第 15 号「顧客との
契約から生じる収益」の範囲に含
まれる知的財産のライセンスを除
き、無形資産のリースに IFRS 第
16号を適用する。
無形資産に関するすべてのリース
が、ASC第 842号の適用範囲か
ら除外される。
主要な概念
リース負債 –
変動リース料の
見直し5
あらかじめ設定された指数又は
レートに応じて決定されるリース
料の変動により契約上のキャッ
シュ・フローに変動が生じる場合
には(すなわち、リース料に変動
が生じる場合には)、リース負債を
見直す。
あらかじめ設定された指数又は
レートに応じて決定されるリース
料の変動については、リース負債
が他の理由により再測定される場
合に限り(例:リース期間の変
更)、リース負債の再測定を行う。
貸手は条件変更の場合にのみ再
測定を行う。
公開企業
(PBEs)以外の
すべての企業の
会計処理 – 割引率
IFRS 第 16 号は非公開企業に対
して、代替的な会計処理を定めて
いない。
非公開企業は、リース負債の当
初及び事後測定に関して、リスク・
フリー・レートを使用できる。
割引率の決定 借手はリース開始日時点で割引
率を決定するが、貸手は契約日
時点でリース計算利子率を算定
する。
借手と貸手双方ともに、リース開
始日時点で割引率を算定する。
3 IFRS第 16号 BC308項 及び ASC第 842号 BC421項 4 ASC第 842号 BC431項 5 IFRS第 16号 BC309項 及び ASC 第 842号 BC425項
110 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号 US GAAP ASC第 842号
借手の追加借入
利子率の算定
IFRS第 16号は、リース期間の決
定に際して考慮されていないオプ
ション(例:購入及び延長オプショ
ン)による影響を、借手は考慮す
ることができるかについて定めて
いない。
借手はリース期間の決定に際して
考慮されていないオプション(購入
及び延長オプション)による影響を
考慮することができる。
当初直接コスト
(IDCs)の定義
IDCs は、リースを取得しなければ
発生しなかったであろうリースの
取得に係る増分コストである。
ただし、ファイナンス・リースに関し
て、製造業者又は販売業者である
貸手に生じたコストは除外される。
IDCs は、リースを取得しなければ
発生しなかったであろうリースの
取得に係る増分コストである。
原資産の公正価値と帳簿価額と
が異なる場合、貸手は販売型リー
スの IDCsを費用処理する。
リースの分類
借手のリースの
分類6
すべてのリースを使用権モデル
に基づいて会計処理する(ASC
第 842 号のファイナンス・リース
に類似)。
ただし、認識に関する免除規定が
適用される場合を除く。
認識するリースは、ファイナンス・
リース又はオペレーティング・リー
スのいずれかに分類する。借手
はリース開始日時点でリースを分
類する。
貸手のリースの
分類
リースの契約日にファイナンス・
リース又はオペレーティング・リー
スのいずれかに分類する。
リースの開始日時点でオペレー
ティング・リース、直接ファイナン
ス・リース又は販売型リースのい
ずれかに分類する。
貸手 – リースの
分類要件
すべての分類要件は個々に、又
は全体として検討される。
IFRS 第 16 号では要件を、個々
に、又は全体として考慮すること
になり、ファイナンス・リースとして
の分類になる状況の例と状況を
載せている。
ある要件を満たすとしても、それ
が必ずしもフィナンス・リースとし
ての分類になる訳ではない。
分類要件のいずれもが、決定要
因になりうる。
すなわち、いずれか一つの要件
が満たされる場合、リースは販売
型リースになる。
回収可能性 IFRS第 16号には、リース料の回
収可能性を検討する際の明確な
ガイダンスはない。
リース料の回収可能性を、リース
が直接ファイナンス・リース又はオ
ペレーティング・リースに分類すべ
かを検討する際に考慮する。
サブリース サブリースを分類する際に、中間
の貸手は、ヘッドリースに係る使
用権資産を参照してサブリースを
分類する。
サブリースを分類する際に、中間
の貸手は、ヘッドリースに係る使
用権資産ではなく、原資産を参照
してサブリースを分類する。
6 IFRS第 16号 BC304項及び ASC第 842号 BC420項
111 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号 US GAAP ASC第 842号
借手の会計処理
短期リース –
購入オプションの
有無
リース契約に購入オプションが含
まれる場合、借手がオプションを行
使することが合理的に確実かどう
かに関係なく、当該リースが短期
リースの要件を満たすことはない。
リース契約に行使することが合理
的に確実な購入オプションが含ま
れる場合、当該リースは短期リー
スの要件を満たさない。
短期リース –
リース期間の変更
短期リースに条件変更が生じた場
合、新たなリースとして取り扱わ
れる。
その新しいリースの期間が 12 ヵ
月超になる場合、短期リースの要
件を満たさない。
以下のいずれかに関して借手の
評価に変更が生じた場合、その
リースは短期リースの要件を満た
さなくなる。
• 変更後に残余リース期間
が、従前に決定していたリー
ス期間の終了時点から 12 ヵ
月以上延長された場合
• 購入オプションを行使するこ
とが合理的に確実になった
場合
指数又はレートに
応じて決まるもので
はない変動対価の
リース構成分部分と
非リース構成部分へ
の配分
IFRS 第 16 号では、借手は変動
対価全体を契約の非リース構成
部分に配分することができる。
借手は、指数又はレートに応じて
決まるものではない変動対価につ
いては、契約のリース構成部分と
非リース構成部分とに配分する。
コンポーネント化 借手は、使用権資産を減価償却
するにあたって IAS 第 16 号「有
形固定資産」の定めを適用する。
当該定めは、ある有形固定資産
の取得原価総額と比較して重要
なコンポーネントは、それぞれ別
個に減価償却すると定めている
(すなわちコンポーネント・アプ
ローチ)。
コンポーネント別の減価償却は、
容認されているが一般的ではな
い。
貸手の会計処理
リース構成部分と
非リース構成部分を
区別しない実務上の
便法
IFRS 第 16 号では、貸手の実務
上の便法はない。
貸手は、一定の要件を満たす場
合、原資産の種類ごとに、リース
構成部分と非リース構成部分を区
別しないことが認められる。
さらに、非リース構成部分が契約
の支配的な要素である場合には、
当該契約を ASC第 606号に従っ
て会計処理する。
直接金融リースの
販売利益の認識7
フィナンス・リースの販売利益は、
リースの開始日時点で認識する。
IFRSは、販売型リースと直接金融
リースを区別していない。
直接金融リースの販売利益は、
リース開始日時点から繰り延べた
うえで、リース期間にわたり収益
に認識する。
7 ASC第 842号 BC427項
112 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号 US GAAP ASC第 842号
回収可能性 IFRS第 16号は、リース料の回収
可能性の検討に関する明確なガ
イダンスを定めていない。
リース料の回収可能性は、販売
型リースの当初認識及び測定の
際に考慮する。
また、回収可能性は、オペレー
ティング・リースの収益認識パター
ンを決定する際にも考慮する。
さらに、リースを直接金融リースに
分類すべきか、又はオペレーティ
ング・リースに分類すべきかを判
断する際にも回収可能性を考慮
する。
販売型リース又は
直接金融リース8の
条件変更
(US GAAPに従っ
て、別個の契約を
生じさせることなく、
オペレーティング・
リースに分類される
ことのないもの)
貸手は、別個のリースが生じるこ
とのない、引き続きファイナンス・
リースに分類されるリースの条件
変更については、IFRS 第 9 号を
適用して会計処理する。
条件変更が契約日に有効であっ
たとすれば当該リースがオペレー
ティング・リースに分類されていた
であろう場合には、当該条件変更
は、条件変更の発効日から新た
なリースとして会計処理する。
ASC 第 842 号は、別個の契約を
生じさせることのない販売型リース
及び直接金融リースの条件変更に
関するガイダンスを定めている。
指数又はレートに
応じて決まるもので
はない変動対価の
リース構成部分と
非リース構成部分へ
の配分
IFRS第 16号は、リース構成部分
の変動対価に関するガイダンスを
設けていない。
貸手は、IFRS第 15号第 73項か
ら第 90 項のガイダンスを基に契
約上の対価を配分する。
指数又はレートに応じて決まるも
のではない変動リース料の条件
が、部分的であってもリース構成
部分に関係する場合、貸手は当
該変動リース料を、変動リース料
の基礎となる事実と状況の変化
が発生する(たとえば、変動対価
の金額の基礎になる借手の販売
の発生)前には認識しない。
変動対価の基礎となる事実と状況
の変化が生じた場合に、貸手はそ
れらの変動リース料をリース構成
部分と非構成要素に配分する。
リース構成部分にのみ配分する
606-10-32-40 の要件を満たす
場合を除き、契約の対価の配分
又は別個の契約として会計処理さ
れることのない直近の契約条件と
同じ基準で変動リース料の配分を
行う。
8 IFRS第 16号第 80項及び ASCd第 842項 BC429項
113 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号 US GAAP ASC第 842号
セール・アンド・リースバック取引
セール/パーチェス・
アンド・リースバック
取引における
資産の譲渡が売却で
あるかどうかの判断
資産の譲渡を売却として会計処
理すべきかどうかを判断するため
に、売手/借手と買手/貸手は、
IFRS 第 15 号における履行義務
の充足時期の決定に関する定め
を適用する。
資産の譲渡が売却及び購入であ
るかどうかを判断するために、売
手/借手と買手/貸手は以下を検
討する。
• 譲渡が ASC 第 606 号の売
却に関する要件を満たすか
どうか(ただし、公正価値で
の買戻オプションがあっても
売却の要件が満たされない
とは限らない)
• リースバックを買手である貸
手が販売型リースに分類し
ている又は売手/借手がフィ
ナンス・リースに分類してい
る場合、売却及び購入には
該当しない
セール・アンド・リース
バックにおける利得と
損失の認識9
売手/借手は、買手/貸手に移転さ
れた権利に係る利得及び損失の
額のみ(オフマーケット条件であ
れば調整する)を認識する。
売手/借手は、利得及び損失を即
時認識する(オフマーケット条件で
あれば調整する)。
売却の要件を
満たさない場合 –
売手/借手
売却の要件を満たさない資産の
譲渡について、貸手及び借手は
IFRS 第 9 号「金融商品」に従って
金融取引として会計処理する。
IFRS第 16号は金利に関する追加
的なガイダンスを設けていない。
売却の要件を満たさない資産の
譲渡について、貸手及び借手は
金融取引として会計処理する。
ASC 第842号は、(例:損失が予
め組み込まれないようにする)一
定の状況における金利の調整に
関する追加的なガイダンスを設け
ている。
その他の検討事項
関連当事者間の取引 IFRS第16号は、関連当事者間の
リース取引を取り扱っていない。
IAS 第 24 号「関連当事者につい
ての開示」に関連当事者について
の開示に関するガイダンスが設け
られている。
リースの法的に強制可能な条件
を基に、セール・アンド・リースバッ
ク取引を含む関連当事者間の
リースを分類し、会計処理する。
関連当事者間の取引は開示しな
ければならない。
9 IFRS第 16号 BC306項及び ASC第 842号 BC430項
114 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
IFRS第 16号 US GAAP ASC第 842号
発効日及び経過措置
発効日 すべての企業は、IFRS第16号を
2019 年 1 月 1 日以降開始する
事業年度から適用する。
上場企業及びその他の一定の企
業は、ASC 第 842 号を 2018 年
12 月 15 日以降開始する事業年
度から適用する。
その他の企業は、2019 年 12 月
15 日以降開始する事業年度から
適用する。
早期適用 早期適用も認められるが、 IFRS
第 15 号を既に適用している、又
は IFRS 第 16 号と同時に適用す
る必要がある。
すべてのケースで早期適用は容
認される。
修正遡及アプローチ
による移行 –
比較年度への適用
比較年度は修正しない。 ASC 第 842 号は、財務諸表に表
示される最も古い比較年度の期
首時点もしくは発効日時点のいず
れかで経過措置を適用するオプ
ションを定めている。
財務諸表における最も古い比較
年度の期首時点で経過措置を適
用する場合には、比較年度を修
正する。
発効日時点で経過措置を適用する
場合には比較年度を修正しない。
修正遡及アプローチ
による移行 –
具体的な経過措置
経過措置は主に、IAS 第 17 号に
おいてオペレーティング・リースに
分類されていた借手のリースを取
り扱っている。
すべてのリースに関し、ASC 第
842 号を適用する前及び適用した
後のリースの分類に応じて、具体
的な経過措置が定められている。
完全遡及適用
アプローチによる
移行
IFRSでは容認されている。 US GAAPでは禁止されている。
レバレッジド・リース レバレッジド・リース会計は、IFRS
第 16号では容認されていない。
レバレッジド・リース会計は、ASC
第 842 号の発効日以降に開始
するリースについては廃止され
ている。
ただし、発効日より前に開始して
いるレバレッジド・リースは例外と
なる。
既存のレバレッジド・リースが発効
日以降に条件変更される場合、
リースは ASC 第 842 号に従って
会計処理され、もはやレバレッジ
ド・リースとして会計処理すること
はできない。
115 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
付録D:リースの再評価及び再測定に関する要求事項の概要
下記の表では、IFRS第 16号において借手及び貸手に求められるリースの再評価及び再測定に関
する要求事項をまとめている。IFRS第 16号の発効日より前に開始したリースに関する要求事項に
ついては、セクション 9「発効日及び経過措置」を参照されたい。
借手 貸手
契約がリースである
又はリースを含んで
いるかどうかの
再評価
契約の条件が変更された場合にの
み、契約がリースであるか又はリー
スを含んでいるかどうかを再判定
する(2.1.7「契約の再評価」)。
契約の条件が変更された場合にの
み、契約がリースであるか又はリー
スを含んでいるかどうかを再判定
する(2.1.7「契約の再評価」)。
リース構成部分と
非リース構成部分へ
の契約対価の配分
別個のリースとして会計処理され
ない条件変更時に配分する(セク
ション 4.5.2「別個のリースが生じ
ないリース契約の条件変更に係
る借手の会計処理」)。
特に取り扱われていない。
リース期間及び
購入オプションの
再評価
以下の両方に該当する重大な事
象又は状況の変化が生じた場合
には、リース期間及び購入オプ
ションを再評価する。
• 借手のコントロールの範囲内
にある場合
• 借手がリース期間の算定に
含めていないオプションを行
使すること、又はリース期間
の算定に含めているオプショ
ンを行使しないことに関し
て、合理的に確実かどうかの
評価に影響する場合
リースの解約不能期間に変更が
あった場合には、リース期間を見
直す(セクション3.4.2.1「リース期
間及び購入オプションの見直し―
借手」)。
リースの解約不能期間に変更が
あった場合には、リース期間を見
直す(セクション3.4.2.2「リース期
間及び購入オプションの見直し―
貸手」)。
リース料の再測定
(指数又はレートに応
じて決まる変動リー
ス料、購入オプション
の行使価格、及び残
価保証に基づいて支
払いが見込まれる金
額(借手の場合のみ)
が含まれる)
以下のいずれかが生じた場合に
再測定を行う(セクション 3.5.9
「リース負債の再評価」、及びセク
ション 4.5.2「別個のリースが生じ
ないリース契約の条件変更に係
る借手の会計処理」)。
• 別個のリースとして会計処理
されないリースの条件変更
以下のいずれかが変更された
場合
• リース期間
• 原資産の購入オプションに
関する評価
• 残価保証に基づいて支払い
が見込まれる金額
• リース料の算定に使用され
た指数又はレートの変動か
ら生じる将来のリース料
• 実質的に固定されたリース
料の変動
リースの解約不能期間に変更が
あった場合、再測定を行う(セク
ション 3.4.2.2「リース期間及び購
入オプションの再評価―貸手」)。
116 Applying IFRS 新たなリース基準 2018年12月
借手 貸手
リースの分類の
再評価
該当なし リースの条件変更があった場合に
見直す(5.1.2「リースの分類の見
直し」)。
割引率の再評価 以下のいずれかが生じた場合に
再評価する。
• リース期間の変更
• 原資産の購入オプションに
関する評価の変更
• 別個のリースとして会計処理
されないリースの条件変更
• 変動金利の変動に伴うリー
ス料の変動
セクション 3.5.9「リース負債の再
評価」及びセクション 4.5.2「別個
のリースが生じないリース契約の
条件変更に係る借手の会計処理」
割引率の評価に関し、具体的な
要求事項は定められていない。
注: 借手及び貸手によるリースの条件変更の会計処理の詳細については、セクション 4.5「リース契約の条件変更」(借
手)及びセクション 5.5「リースの条件変更」(貸手)を参照されたい。
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
EYについて
EY は、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの
分野における世界的なリーダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービ
スは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらします。私たちはさま
ざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出
していきます。そうすることで、構成員、クライアント、そして地域社会のた
めに、より良い社会の構築に貢献します。
EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークで
あり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立
した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限
責任会社であり、顧客サービスは提供していません。詳しくは、ey.com をご覧
ください。
EY新日本有限責任監査法人について
EY新日本有限責任監査法人は、EYの日本におけるメンバーファームであ
り、監査および保証業務を中心に、アドバイザリーサービスなどを提供して
います。詳しくは、www.shinnihon.or.jp をご覧ください。
© 2019 Ernst & Young ShinNihon LLC.
All Rights Reserved.
ED None
本書は EYG No. 012807-18Gblの翻訳版です。
本書は一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されており、会計、税務およびその他の専門的な
アドバイスを行うものではありません。EY 新日本有限責任監査法人および他の EY メンバーファーム
は、皆様が本書を利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。具体
的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。

























































































































![[ 第1条(約款の適用) ]](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/568130ef550346895d97137c/-568130ef550346895d97137c.jpg)
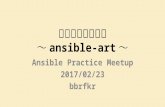











![分項名稱Section Name: 接納註冊 (全文本) Acceptance for … · Limitation: 不適用 [527] 條件: Condition: 不適用 其他: Others 不適用 ... use in the metal](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5ebbe78a29bb472e7e7a6fee/ecsection-name-ce-oe-acceptance-for-limitation-ec.jpg)


