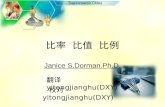ICT 関連動向の国際比較及び国内外の ICT 利活用先 …...ICT 関連動向の国際比較及び国内外のICT 利活用先進事例調査 報告書 平成21 年3 月
―比例のグラフを題材として―...キーワード:ICT活用 ICT practical use, GRAPES,...
Transcript of ―比例のグラフを題材として―...キーワード:ICT活用 ICT practical use, GRAPES,...

中学校数学におけるICT利用による授業実践―比例のグラフを題材として―
大室敦志・西仲則博・竹村景生(附属中学校)
Mathematics class practice by the ICT use in the junior high school―A graph of the proportion as a subject―
Atsushi OMURO・Norihiro NISHINAKA・Kageki TAKEMURA(Nara University of Education Junior High School)
要旨:平成20年に告示された新学習指導要領において、中学校数学では、ICT機器を適切に活用し、学習の効果を高めるようにしていくことが、より一層求められている。ところが、普段の授業においては、それほどICT活用は進んでいないように思われる。その理由として、準備時間がかかることが挙げられている。そこで、準備時間を多く必要としない方法で、ICT機器を活用した授業を、「比例のグラフ」の単元で計画し、実践を行った。既存のプレゼンテーションソフトと関数グラフソフト「GRAPES」を組み合わせることで、短時間で教材を作成することができ、また、生徒にとっても、視覚的にわかりやすい授業を行うことができた。
キーワード:ICT活用 ICT practical use, GRAPES, 比例のグラフ A graph of proportion
1 .はじめに
平成20年に告示された新学習指導要領において、中学校数学では、「コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用し、学習の効果を高めるよう配慮するものとする」と明記されているように、学校現場では、コンピュータ等のICT機器を活用した授業を行っていくことが求められている。また、教具としての活用の形態については、「普通教室にノートパソコンと液晶プロジェクタを持ち込んで提示器具として用いるなど、指導内容との関係で柔軟に対応できるようにすることも考えられる」と明記されている(文部科学省[ 1 ])。コンピュータ等によって画像や動画を提示することにより、生徒の学習効果を高めることが期待できるからである。 一方で、普段の授業では、ICTを活用することが難しいと感じている教師も少なくはない。ICT活用が進まないのは、「準備に時間がかかりすぎる」ことが理由だと、 8 割以上の教員が答えたアンケート結果も公表されている(日本教育工学振興会[ 2 ])。 そこで、中学校第 1 学年「比例のグラフ」の単元において、教材作成の準備に時間を多く必要としない方法でICTを活用する授業を計画し、実践を行った。
2 .既存のソフトウェアを使う
今回の実践では、プレゼンテーションソフトと、インターネットから無料で自由にダウンロード可能な関数グラフソフト「GRAPES」の 2 種類のソフトウェアを使用した。
2 . 1 .プレゼンテーションソフト PowerPointなどに代表されるプレゼンテーションソフトは、容易な操作で文字やイラスト、写真などを取り込んだスライドを作成することができる。アニメーション機能などを使用すれば、文字やイラストなどに動きを付けることができ、強調するなどの効果を容易に加えることができる。このようにして作成したスライドは、プロジェクタ等を使用して大きく映すことで、生徒にとってわかりやすい説明をすることが可能となる。また、生徒に提示する時間の短縮も可能である。たとえば、水槽に水を入れる様子を実験するのであれば、水槽や蛇口から水が出る環境が必要であるが、プレゼンテーションソフトを使えば、水槽に水が入る様子のシミュレーションを提示することができる。さらに、画面を 1 つ戻すだけで繰り返し提示することが可能となるのも、プレゼンテーションソフトの長所の
301

1 つである。 一方で、黒板での板書であれば授業の記録が残っていくが、スライドでは、次のスライドへ行くと前のスライドの画面を見ることができなくなる。そのため、たとえば、授業のタイトルや目標など、常に意識して欲しいことや残しておきたいことは、黒板と併用するなどの工夫をしていくことが求められる。 また、アニメーションによって「動き」をつけることができるのは、プレゼンテーションソフトの大きな特長であるが、今回のような関数のグラフの表示を行うのには、作成時間等が掛かることから、他のソフトとの併用を考えた。 そこで、まず、黒板の右側でプロジェクタを投影し、左側で板書を行える形をとった。プロジェクタによる黒板への投影は、さらに、その投影画像上にチョークで自由に書き込みができ、また簡単に消すことができるため、指導者と学習者が共通のイメージを持つことが可能となるといった報告がされている(たとえば、神奈川県立総合教育センター[ 3 ])。 本実践では、プレゼンテーションソフトと関数グラフソフトのGRAPESを使用した。GRAPESとプレゼンテーションソフトを併用した実践例として友田勝久氏の実践[ 4 ]がある。友田氏の報告では、GRAPESを補完するためにプレゼンテーションソフトが使用されていた。本実践では、プレゼンテーションソフトの機能を補うためにGRAPESを用いた。
2 . 2 .GRAPESの特徴 GRAPESは、友田勝久氏(大阪教育大学附属高等学校池田校舎)が作成したフリーの関数グラフソフトで、インターネット上で無料で自由にダウンロードすることが可能である。(http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~tomodak/grapes/)このソフトでは、式を入力するだけで、コンピュータの画面上にさまざまな関数のグラフを描画することができる。 今回の比例のグラフの単元では、y=axのグラフを描写することだけでなく、y=axについて、対応する変数x,yの値の組を座標とする点(x,ax)をとり、xの値を変化させていったときの点の残像を記録していくことも可能である。たとえば、y= 5 xについて、xの値を0.1ずつ増やしていくときにとる点の残像は、図 1 のようにGRAPESの画面上に表示される。 このように、GRAPESを使用すれば、使用する教材に合うような式を入力するだけでグラフを生徒に提示することができる。また、プレゼンテーションソフトでは、動きをつけたり数値を変えたりする際には、 1つ 1 つの動作を設定する必要があるが、GRAPESにおいては、その操作が、式を書き換えたり変数を動かしたりするだけで容易にできる。このようなGRAPESの特徴を組み合わせることによって、プレゼンテーショ
ンソフトのみで教材を作成するときと比較すると、授業の準備に要する時間の短縮を図ることが可能となる。
3 .授業までの準備
比例のグラフの指導にあたり、まず、教科書分析を実施し、比例の定義とそのグラフの扱い方の小中比較を行った。その結果、比例の定義の違いとグラフをかくときの変数の扱いの違いに着目し、グラフを「点の集合」と意識できるようにプレゼンテーションソフトとGRAPESを併用して教材を作成した。
3 . 1 .「比例のグラフ」の小中比較 中学校第 1 学年で学習する「比例のグラフ」は、小学校第 6 学年でも扱われている単元である。その扱い方の違いから、次の 2 つに着目した。 1 つ目は、比例の定義に違いである。小学校第 6 学年の教科書では、
「 2 つの量があって、 1 つの量が 2 倍、 3 倍、…になると、それに対応するもう 1 つの量も 2 倍、 3倍、…になるとき、 2 つの量は比例する」[ 5 ]
と表での見方をもとに定義されている。これに対し、中学校第 1 学年の教科書では、以下のような定義となっている。
「xにともなってyが変化し、その関係が次のような式で表されるとき、yはxに比例するという。
y=ax」[ 6 ] 小学校では、比例の関係を、具体的な数量で 2 倍、3 倍、…と捉えていたが、中学校では、文字を使った式で表すことによって、変域を、分数、小数や負の数といった実数全体に拡張していくことが可能となる。 2 つ目は、比例のグラフが直線になることの扱い方である。小学校第 6 学年では、水槽に水を入れる事象を扱うなかで、( 1 )水を入れる時間と水の深さの関係を表に整理
し、その点をグラフにかき入れる。( 2 )水を入れた時間と水の深さの関係を表すグラフ
は、下のような直線になる。(教科書では、グラフを図示している)
と、比例のグラフが直線になることを扱っている。ここでは、「比例する 2 つの数量について、そのグラフ
図 1 GRAPESの画面
大室 敦志・西仲 則博・竹村 景生 中学校数学におけるICT利用による授業実践
302 303

が直線になることを、具体的な数量に即して理解できるように指導することが必要である」[ 7 ]とされている。具体的に数値を何点かとり、その点を結んだ原点を通る直線が、比例のグラフであると指導されている。 一方、中学校第 1 学年では、y= 2 xを成り立たせるx、yの値の組を座標とする点を多くとっていくと、これらの点の集まりは一直線上に並び、さらに、xの変域がすべての数であるとき、原点を通る直線になる、と説明されている。 中学校第 1 学年では、座標を用いることによって、グラフを点の集合として表すことができるようにすることが求められている。そこで、ICTを活用した比例のグラフの指導を行うとき、グラフが「点の集合」だということを意識できるような指導の流れとして、次の(場面 1 )~(場面 4 )を計画した。(場面 1 )水槽に水が入っていく様子を観察し、時間
と水が入った高さを秒ごとに記録し、座標平面上に点で表す。
(場面 2 )時間を細かく見ていくと、そのときの水の高さはどうなっているのか、0.1秒刻みで観察していき、座標平面上に点で表す。
(場面 3 )さらに時間を細かくしていくと、点の集まりはどうなるかを考える。
(場面 4 )点の集まりが直線になることを、水槽に水が入っていく様子と並べて確認する。
3 . 2 .ICT機器の利用 今回の授業実践では、(場面 1 )~(場面 4 )においてICT機器の利用を計画した。(場面 1 )、(場面 2 )、(場面 4 )では、水が入る様子のシミュレーションと座標平面を提示するために、プレゼンテーションソフトを使用し、(場面 3 )では、点を多くとっていく様子を示すためにGRAPESを使用した。 (場面 1 )水槽に水が入る様子と、座標平面上に点をとる様子を結びつけるために、プレゼンテーションソフトでスライドを作成した。アニメーションをつけることで、時間の経過と水が増えていく様子を提示することができる。また、座標平面と水槽を 1 枚のスライドに並べることで、水槽に水が入る事象と座標を結びつけて考える事が可能となっている。(図 2 )
図 2 は、 1 分ずつ時間を止めていき、 5 分になったときの様子である。座標平面は、GRAPESの画面をコピーしたものを使用した。
(場面 2 ) 1 分と 2 分の間に着目し(図 3 )、グラフを拡大したものと水槽を拡大したものを同時に示し、0.1分刻みで点をとっていくスライドを作成した。(図4 )
(場面 3 )さらに時間を細かく見ていくときには、GRAPESの画面を生徒に提示する。GRAPESで点の残像を表示することで、y=axを満たす点の集合が、どのような形になっていくかを見ることができる。たとえば、xの値を0.01ずつ大きくした点をとっていくと、図 5 のように点の集まりが描かれる。
図 5 では、点が重なりあって直線を描いているように見えるが、GRAPESでは、図 6 のように座標の一部分を拡大表示することが可能である。
図 2 (横軸が時間、縦軸が水の高さ)
図 3
図 4
図 5
大室 敦志・西仲 則博・竹村 景生 中学校数学におけるICT利用による授業実践
302 303

さらに細かく値をとっていくと、この隙間に点が並んでいく様子を見ることができる。比例のグラフで描く直線が、「点の集合」だということを意識することができる。
(場面 4 )もう一度スライドに戻り、図 7 のように水が連続的に入っていくのに合わせてグラフを描いていく。そうすると、描かれるグラフが直線になることをより意識することができる。
また、図 8 のようなワークシートを作成し、グラフの作成や気付いたことをメモできるようにした。
4 .実践報告
ICTを使った授業の実践として、「比例のグラフ」の単元で授業を行った。その概要と、授業を行った際
の生徒の反応を記載する。
4 . 1 .実践授業「比例のグラフ」実施月:2010年10月対 象:国立大学法人附属中学校 1 年 4 学級場 所:数学教室準備物:ノートパソコン、プロジェクタ本時の目標:・比例を動的なイメージとしてとらえることができ
るようになる。・比例のグラフを点の集まりとしてとらえることが
できるようになる。
図 9 のように、黒板の右側にプロジェクタでパソコンの画面を投影し、左側で、板書を行えるように設定した。
4 . 2 .授業の展開 次の①~⑥の流れで授業を行った。それぞれの場面で用いたICT機器や問いかけや生徒の反応などについても記す。① 課題を提示する。
・プレゼンテーションソフトで作成したアニメーションを見ながら、水が入る様子を観察する。
② 「時間をx分、高さをycmとして、xとyの値の組を表にまとめましょう。」・ワークシートへ記入していく。
③ 表でまとめたx、yの組を座標平面上に点をとる。・生徒が、ワークシートの座標平面に点をとってい
った後、(場面 1 )のスライドを見せながら確認する。
・この時点で、小学校で習ってきたように定規を使って点と点を直線で結んでいる生徒が数名いた。
④ 「この間はどうなっているのだろう」
図 6
図 7
図 8
図 9 教室の配置
高さ50cmの水槽に水を入れていくとき、時間と高さの関係を調べよう。
大室 敦志・西仲 則博・竹村 景生 中学校数学におけるICT利用による授業実践
304 305

・ 1 分の点と 2 分の点の間に着目させ、その間を「直線で結んでいいのだろうか?」問いかけた。
・生徒が考える時間をとった後、(場面 2 )のスライドで0.1分刻みに点をとった結果を確認する。
⑤ 「さらに細かく点をとるとどうなるのだろう」・生徒からは、「0.01分刻みやもっと細かく点をと
る」といった反応があり、それを確認するために(場面 3 )のようにGRAPESを用いた。授業開始までに、プレゼンテーションソフトとGRAPESを同時に起動しておき、すぐにGRAPESを使えるようにしておいた。
・細かく点をとっていくと線になっていく様子を観察し、だんだん「直線で結ぶ」理由が見えてきたようである。
⑥ 「比例のグラフを点で結ぶのは、細かく点をとっていった集合であるグラフが直線になるからです」・(場面 4 )のスライドを提示し、水の高さとグラ
フとの関係を確認する。
4 . 3 .授業の感想 4 .2 .で示した展開で授業を行い、授業終了後にワ
ークシートを回収した。そこに書かれた生徒の授業の反応の一部を、表 1 と図10に示した。
5 .まとめと今後の課題
今回の授業実践では、中学校第 1 学年「比例のグラフ」の単元において、教材作成の準備に時間を多く必要としない方法でICTを活用する授業を計画し、実践を行った。教材作成の方法として、既存のICT機器を組み合わせることで、準備時間の短縮を図ることができた。 最後に、この教材を使用した授業実践を生徒の授業の反応から考察を行う。まず、スライドでのアニメーションを用いた説明では、黒板では表現することが難しい比例の動的なイメージを想像しやすく理解しやすいものとなったようである。また、GRAPESを用いることで、点と点をとるその間の点やさらにその間の点の存在に生徒が気づくことができる授業となったことが伺える反応もあった。このように、ICTを活用した授業によって、通常の黒板での授業よりも緻密でかつ簡単に生徒に提示することができたのではないだろうか。 今後の課題として、「比例のグラフ」の単元においてのICTのよりよい活用法を探っていくとともに、この単元以外の授業においても、効果的でかつ準備が容易なICTの活用法を考えていくことが必要である。
6 .参考文献
[ 1 ].文部科学省,『中学校学習指導要領解説 数学編』,教育出版,2008年.
[ 2 ].日本教育工学振興会,「地域・学校の特色等を活かしたICT環境 活用先進事例に関する調査研究 報告書」,2009年.
[ 3 ].神奈川県立総合教育センター ,「ITを活用した授業づくりハンドブック」,2007年.
[ 4 ].友田勝久,「 2 次関数の係数とグラフ」,2004年.http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~tomodak/grapes/resource/quad/quad01.html
[ 5 ].中原忠男ほか,『小学算数 6 年下』,日本文教出版,2009年.
[ 6 ].重松敬一ほか,『中学数学 1 』,日本文教出版,2009年.
[ 7 ].文部科学省,『小学校学習指導要領解説 算数編』,東洋館出版社,2008年.
図10 生徒が記入したワークシート
・比例のグラフでなぜ直線を引くのかがわかった。・点と点の間に何があるのかがわかった。・今まで比例のグラフをかく時は深く考えずにか
いていたけれど、今回の授業で意味が分かりました。定数が分数になってもグラフの点をとればちゃんとかけるんだなと思いました。
・私は小学校のグラフとまったく一緒だと思っていたけど、違うということがわかった。小学校のときは、ひとつひとつの数字をつなげたもの。中学校はすべての数字をならべたもの。
・動画だったので想像しやすく、理解しやすかった。・パワーポイントの説明だったので、イメージし
やすかった。
表 1 生徒の授業の反応(下線は筆者)
大室 敦志・西仲 則博・竹村 景生 中学校数学におけるICT利用による授業実践
304 305