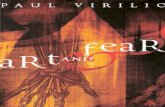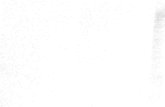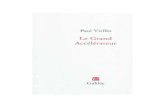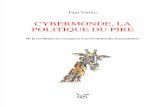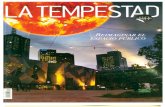Abstract - Tokyo University of Foreign...
Transcript of Abstract - Tokyo University of Foreign...
折り重なる空間 ポール・ヴィリリオの思想についての一試論 203
折り重なる空間 ポール・ヴィリリオの思想についての一試論
平田 周
Les espaces reptie’s: un essai sur la pense’e de Paul Virilio
Shu Hirata
Abstract
Cette these est un essai sur la pens6e de Paul Virilio, En me focalisant sur deux
rapPorts h l’espace-temps, c’est-a-dire sur l’opPosition entre esl)αceγ6θZ/temps
durable et espace virtue1〃θγ理)s re-eL telle qu’elle se dessine dans la pens6e de Virilio
sur la vitesse, j’essaie de d6crire globalement sa pens6e.
Virilio d6finit la fonction de la technique en tant que vitesse. Certes, on peut
consid6rer que cette d6finition n’est pas originale, car notre environnement est empli
de multiples vitesses engendr6es par la t616Vision, rinternet, le t616phone portable_
Mais, le concept de Vitesse chez Virilio concerne avant tout le rapport entre 1’espace et
le temps. En effet, il signifie la r6duction de la distance entre rici et l’ailleurs en un
instant. Sur le temps r6el, compression de distance entre rici et 1’ailleurs par la vitesse,
se replient les horizons des espaces r6els,1’ici et l’aileurs oU les corps vivants se
situent.
De cette superposition des horizons des espaces r6els au temps r6e1 procede une
s6rie de problemes. Cette these examine ces problemes:tout d’abord, le probleme de
l’espace mlitaire dans la seconde guerre mondiale qui tourne autour de deux
principes: 1’organisation de 1’espace par rarchitectonique d’une part et par la
t616technologie irnrnat6rielle d’autre part(chapitre 1,2);ensuite, le probleme est celui
de la perception spatiale et de la r6alit6 urbaine par rapPort b la technologie
61ectronique(chapitre 3);enfin, Virilio pose le probleme de la guerre vue en temps
r6el b travers un 6cran, et non plus, depuis la guerre froide, faite dans un espace r6el
(chapitre 4).
Le temps r6el qui est un el6ment constitutif du temps de la mondialisation agit sur
l’espace r6el du monde. Virilio nous donne les comaissances indispensables pour
204 平田 周
r(≦且6chir sur notre situation.
序 技術と空間、そして、戦争を横断する思想
第一章 戦争の風景
第一節 攻撃と防御の弁証法
第二節 空間の組織化の二つの原理
第二章 空間の秩序
第三節 囲い:領土化
第四節 非物質的な囲い
第三章乗り物としてのメディア
第五節 地平なき知覚
第六節 否定的地平のなかの都市
第四章 グローバルな囲い
第七節 冷戦以後のヴィリリオの戦争論におけ
る環境の問題
第入節 リアル・タイムの専制、あるいは単一
のパースペクティブの支配
第九節 グローバルな空間秩序としての人道の
名の下の戦争とテロリズムとの戦争
結論
序技術と空間、そして、戦争を横断
する思想
本稿は、フランスの思想家ポール・ヴィリリオ
の思想についての一試論である。この試論の主題
は、彼の思想のなかでとりわけ主要な問題となっ
ている〈現実の空間(respace r6el)〉と〈リァ
ル・タイム(le temps r6el)〉の対立軸を中心に据
えて、彼の思想を考察することにある。ヴィリリ
オは、1970年代後半から都市計画、技術哲学、軍
事史の領域をまたぐ著作を発表しながら、いくつ
かの展示会のキュレーターも務めてきた。彼の著
作は、ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリ
によって書かれた『ミル・プラトー』で取りあげ
られ、それ以後、日本でも紹介されるようになり、
国際関係論、都市社会学、メディア論、といった
様々な領域で参照されている。英米では、まず、
ジェームズ・ダー・デリアンがヴィリリオの思想
を国際関係論の領域で精力的に紹介し、近年では、
現象学・存在論的な技術論の観点から彼の思想に
アプローチする研究も現われてきている1。本稿
はヴィリリオを論じるにあたって、彼についての
先行研究から多くの示唆を得ている。しかし、そ
の参照先となるヴィリリオの思想の多様な側面は、
どの学問領野に彼の思想を位置づけるべきなのか、
という問いを生じさせる。
何が、都市や技術や戦争といった様々な主題の
横断を可能にしているのか、と問うならば、それ
はヴィリリオが自らの思想のキーワードとして用
いる〈速度〉という概念ではないだろうか。ヴィ
リリオは、技術の機能を〈速度〉に見てとる。技
術が生み出す速度が、空間に及ぼす影響について
いえば、日々、われわれがテレビやインターネッ
ト、携帯電話といった端末に囲まれ、そのなかで
目まぐるしく移り変わる情報を浴びていることか
らも理解できる。これら遠隔技術に支えられた情
報システムは、コミュニケーション活動や物流、
金融システムといったわれわれの社会・経済活動
全般に及んでいる。ヴィリリオが概念として用い
る速度は、ある瞬間のうちにこことよそとを隔て
る距離の縮減を意味する。ヴィリリオは、この速
度による空間の圧縮を「リアル・タイム」とよび、
このリアル・タイムにおける活動が現実の空間に
おける活動に優位にあると述べている。このリア
ル・タイムと現実の空間という時間と空間の対比
は、「空間の絶滅」や「空間の終わり」といった
ヴィリリオが時折みせる極端な言い回しとあいま
って、われわれに混乱を生じさせる。むしろ、わ
れわれは、この二つの対立を、時間と空間(res-
pace-temps)の二つの関係として捉えることに
よって、この対立を鮮明にすることができる。す
なわち〈現実の空間一持続的な時間〉と〈仮想=
潜在的な(virtuel)空間一リアル・タイム(le
temps r6el)〉という対立である2。様・々なテクノ
ロジーが氾濫する現代において、身体を基底とし
た活動の場である現実の空間の諸地平は、まるで
折り重なる空間 ポール・ヴィリリオの思想についての一試論 205
ある映画のなかのディゾルヴされた二つの場面の
ように、ヴァーチャルな空間に折り重ねられてい
る。
ヴィリリオは、哲学の教育課程を経たのでもな
く、その文体も哲学的ではない。しかし、もし、
彼の著作に「哲学」があるとするならば、技術に
よる空間と時間の経験の変容を問い直したところ
にある。この問いかけこそが、都市や技術、戦争
といった主題の横断を可能にしたものであり、そ
れ故、本稿が以下で検討していくものである。
本論に入る前に、なるべくヴィリリオの思想に
関わる限りで彼の生い立ちを見ていくことにした
い。
ポール・ヴィリリオは、1932年、第三共和制下
のフランス、パリで、イタリア人コミュニストの
父親とフランス人の母親の間に生まれた。第二次
世界大戦における戦争体験、とりわけ1942年のナ
ントでの空爆の体験によって、彼はトラウマとも
言えるような記憶を抱えることになる。その体験
は、第二次大戦中にナチスが連合軍の上陸を阻む
ために、ヨーロッパ沿岸に築いた数多くのトーチ
カの調査へと、彼を向かわせることになる。18才
の時にカトリックへの信仰を持つようになり、技
術職業学校で訓練を受けた彼はステンドグラス職
人として身を立てる。この時にジョルジュ・ブラ
ックやアンリ・マティスと教会のステンドグラス
制作を行っている。そして、この時期、コレージ
ュ・ドゥ・フランスのメルロ=ポンティの講義に
自由聴講生として参加している。1963年、建築家
クロード・パランと「アルシテクチュール・プラ
ンシプ」という建築運動(以下、「建築原理」と
略記)を組織し、その理論を1966年の間に出版さ
れた9冊のマニフェストのなかで展開する。ヴィ
リリオがステンドグラス職人だった頃の縁で、ヴ
ィリリオとパランは、ネヴェルにサン・ベルナデ
ットゥ・デュ・バンレー教会を建設したが、しか
し、他の多くの建築計画は実現されないまま、
1968年の五月「革命」を巡るヴィリリオとパラン
の意見の決裂によって、このグループは解散する。
この時の二人の決裂は二人の五月革命に対する正
反対な態度によるものだとされている。パランは、
建築原理の運動は政治的なものとは無関係だとし
ていたのに対し、ヴィリリオは、シチュアシオニ
スト・アンテルナショナルに強い影響を受け、68
年の運動に熱狂的に参加した。その後、「建築原
理」の活動が認められ、ヴィリリオは1969年から
パリの建築大学(Ecole sp6ciale d’architecture in
Paris)で教えることになる3。
学者の歩む道筋というよりも職人のそれを思わ
せるヴィリリオの歩みは、もちろん彼の思想と無
関係ではない。手を用いるステンドグラスの職人
やマティエールを扱う建築家の仕事の経験が、ヴ
ィリリオが現実の空間と呼ぶものと結びついてい
ることは容易に想像できる。われわれが第一章で
みるように、ヴィリリオの幼少期の戦争体験は、
「第二次世界大戦は私の母であり、父であった」
と書き記すほど、彼の思想形成に大きな影響を与
えている(Viriho 1976/1993,15)。この主題は、
シルヴィエール・ロトランジェがいうように、ヴ
ィリリオの思想の「原光景」をなしている。そし
て、この原光景は、主に、第二次世界大戦におけ
る二つの風景、すなわち「ヨーロッパ要塞」と
「ナントの爆撃」によって形作られているように
思われる。われわれは、この二つの戦争の風景の
うちに、二つの空間の組織化の原理を見出すこと
ができる。そして、われわれは、第二章において、
それぞれの原理が持つ空間の秩序について検討す
る。ヴィリリオの初期の著作における空間の組織
化とその秩序の問題を明らかにすることによって、
われわれは、戦争の問題から離れて技術の問題に
専心していく彼の著作を理解することができる。
第三章で検討するように、ここにおいて、空間の
組織化の二つの原理は、「現実の空間」と「ヴァ
ーチャルな空間」あるいは「リアル・タイム」の
対立と結びついていることが明らかになるであろ
う。以上のような検討を踏まえて、われわれは、
第四章で検討する時事論的な色彩の強いヴィリリ
オの著作、とりわけ、第一次湾岸戦争から第二次
湾岸戦争についての彼の戦争論を理解することが
できるのである。以下で見るように、ヴィリリオ
206 平田 周
の著作において様々な概念や造語が現われるが、
それらの概念で問題になっている現実の空間とリ
アル・タイムの対立を把握することによって、わ
れわれは、現代の世界における技術と空間、そし
て戦争の関係について理解することができるであ
ろう。
第一章 戦争の風景
第一節 攻撃と防御の弁証法
第一次世界大戦と同様、第二次世界大戦は、敵
の粉砕のために、あらゆる人員・資源が動員され
る総力戦であった。戦場の後背地である都市も、
食料や武器・弾薬を前線に送るための重要な拠点
となったため、戦場は、前線と銃後の区別なく、
あらゆる領域に及ぶ。飛行機による爆撃は、第一
次世界大戦やスペイン内戦のときから行われてい
たが、第二次世界大戦になると全面的に行われる
ようになる。
このような戦争のなかに、ヨーロッパ要塞とい
う軍事的建造物とナントの爆撃という出来事が存
在する。ヨーロッパ要塞は、ナチスが連合軍の上
陸を阻止するために、ノルウェー北部の海岸から
南フランスの海岸にわたって作られた巨大な軍事
建造物群である。他方で、ヴィリリオが体験した
「ナントの空爆」は、それが味方である連合軍に
よってなされたという点で、第二次世界大戦にお
ける特異な場面を映し出すものである。1940年6
月14日にパリが陥落し、ドイツの占領から逃れる
ため、多くの人々が南に向かう。ヴィリリオは、
彼の母親の実家があるナントをその疎開先とする
が、そのナントもやがて、ドイツ軍によって占領
される。連合軍は、ドイッによる占領からの「解
放」の名の下に、逆説的にも友軍の都市であるナ
ントを空爆する。
この軍事的空間に至るまでの歴史を、ヴィリリ
オは攻撃と防御の弁証法として次のように定式化
している。「戦争術は人間に、まさに自然な生息
地が見出されていたところに、人間に適さない場
を構築することを目的とする。〈中略〉[そして、]
諸々の新しい兵器から作られる人工気候二人工環
境(climat artificiel)は、軍事的な建造物がもっ
ぱらその人工性に応えることを要求する」
(Virilio 1975/1991,37-38)。兵器が作り出す人工
気候に、自然環境の上に築き上げられる人工的な
軍事的空間が対応する。敵に「降りかかる」矢の
「雨」や岩を投げつける岩石機、「降り注がれる」
燃焼物の「滝」といった表現が指し示しているよ
うに、戦争は、防衛的な建造物や前線の組織化に
よって風景を紡ぎだすだけでなく、「自然の諸力
とも競合する」。つまり、生身の身体、あるいは
それを防護する鎧で存続することができた環境を
解体し、新たな「気候=風土(cl㎞at)」を作り
出す。このように作り出された人工気候に対して、
要塞化された都市の城砦を強化する砦や稜墨が応
える。さらに、それに対して、最初の「空間の飽
和」の始まりを告げる大砲が新たな気候を作り出
し、稜墨はその新たな気候に適応する形態を取る
ことになる。この攻撃と防御の弁証法は、ヴィリ
リオが「空の到来」と呼ぶ、新たな環境変化によ
って、一つの終着点を迎える。つまり、絨毯爆撃
による「空間の飽和」である。「空間の飽和」と
いう用語は、一般的に20世紀初頭の地理学におい
て、二次元の地図上に探査すべき空白地がないこ
とを示す言葉であるが、ヴィリリオはこの用語で
空という垂直的な三次元の領域も軍事的活動の場
となったことを指し示す。そして、この垂直性の
次元は、それまでの都市のパースペクティブを変
えると、ヴィリリオは主張する。都市は、壁、つ
まり面(face)によって作り出される内と外、前
と後といった水平的次元によって規定されてきた
が、空という垂直的な次元から見れば、もはや全
ては表面(surface)でしかない。対立は、内と
外や近さと遠さではなく、上と下や高さと低さに
変わる。それ故、ヴィリリオが「垂直的沿岸(le
littoral vertica1)」と呼ぶ、都市への新たな通路は、
前線と銃後の区別なく、都市がたとえどれだけ前
線から離れていようが、軍人と民間人の、占領者
と被占領者の、そして、友と敵の区別さえなく、
「上から」の無差別爆撃を可能にしたのである。
折り重なる空間 ポール・ヴィリリオの思想についての一試論 207
理性の狡知か、狂気のそれか。いずれにしても、
この攻撃と防御の弁証法が孕む否定的な契機、す
なわち暴力は、ヴィリリオにとって、いかなる目
的の成就も、「綜合」も意味しない。垂直的沿岸
によって、都市を織り成す建物(=不動なもの)
(㎞meuble)が持っている堅固な安定性は、「ト
ランプカードで作られた城」みたいなものになっ
たと、ヴィリリオは言う。先までの町の平穏な賑
わいは掻き消され、都市の配置は全く別様のもの
となる。「ひっくり返る(Chavirer)というこの
言葉は正確な状況を復元する。付け加えれば、ル
ソー橋の車庫からそう遠くないところにあった機
関車が車庫の天辺に納まり、七階立ての建物の屋
根にはプラタナスの木が一本そのままあった……
超現実的である」(Virilio 1976/1993,19)。ヴィリ
リオのナントの空爆の体験とは、その体験が綴ら
れた「都市的なあまりにも都市的な」というテク
ストの表題がニーチェの著作の表題のパラフレー
ズであることにならって、ニーチェの言葉をパラ
フレーズするならば、「都市の死」の体験なので
ある。たとえ、戦争の後に、都市が復興されたと
しても、この否定性は、ヴィリリオのなかで、止
揚されずに残り続けている。なぜならば、幼年期
のヴィリリオにとって「永遠のもの」であった都
市は消失し(Virilio+Ewald 1995,96)、それを可
能にした「人工気候=環境」は存続しているから
である。
第二節 空間の組織化の二つの原理
われわれは、この攻撃と防御の弁証法の空間へ
の広がりとそれがもたらした空間の飽和において、
空間の組織化の二つの原理を見てとることができ
る。
第二次世界大戦において現われたこの軍事的建
造物の建築的特徴の新しさについてのヴィリリオ
の記述は、もちろん重要なものである4。しかし
だからといって、この「要塞」という軍事的建造
物が、ヴィリリオを、ヨーロッパの歴史における
都市と軍事的なものとの結びつきについての探求
へと向かわせているという点を見過ごすことはで
きない。ヨーロッパの歴史において存在してきた
都市国家の城塞を思い起こすならば、人はこのこ
とを容易に確認できるだろう。都市はある空間を
囲い込み、そこに城塞を打ち立てることによって、
自らの領土を形成する。言いi換えれば、都市は、
囲いを設けることによって、任意の空間を領有す
る。ヨーロッパ要塞とこの「囲い」の政治的役割
との結びつきについて、ヴィリリオは次のように
述べている。
1940年と1945年の間に、旧大陸[ヨーロッ
パ]は多くの点で現在の時代を思い起こす
諸々の状況を体験した。この時代に、より正
確には1943年と1944年との間に、各人は、自
らの家族を避難させることができるように、
自らの庭や中庭に溝を掘るように奨められた。
ナチスは、占領した国々の住民たちに彼らの
解放を期待させるよりも、恐れさせるように
導くために、新聞の中で、仮定の上での諸々
の廃塘の合成写真を流布していた。総力戦の
苦悶は先取りされていたのである……。あま
りにも有名なヨーロッパ要塞の閉じられた領
野は、当時、心理学的であると同時に社会学
的な重要な効果を持っていた。この領野は、
未来への同じ恐怖のうちに占領者と被占領民
を結びつけようとし、要塞化された囲い
(renceinte)は統一と帰属意識を同時に、そ
れらを持たぬものに与えていた。共同体的、
あるいは国民的な感情の構築におけるこの囲
い(enclos)の役割はあまりにも忘れられて
いるが、政治は(古代の)都市攻略術(po-
liorc6tique)や攻囲術、包囲術、隔離の学と
の関係なくしては、存在しない(Virilio
1976/1993,213)。
ここに見られるように、ヨーロッパ要塞は、都
市と軍事的なものの結びつきの歴史のなかに置か
れ、その空間の組織化は建築によって担われてい
る。しかし、第二次世界大戦の軍事的空間には、
もう一つの空間の組織化の原理が働いている。空
208 平田 周
間に存在するあらゆる建物(「障害物」)が解体・
崩壊する混沌とした戦争の風景のなかに、別の空
間の組織化が追求される。この原理は、ナントの
空爆に結びついているというよりも、より正確に
は空襲に対する防衛体制と結びついている。ヴィ
リリオは、上の引用のすぐ後で、次のように述べ
ている。
ての「速度」の違いにある。空間の組織化は、上
で述べたように社会の組織化と切り離せない。言
い換えれば、空間の組織化は常に空間の秩序を持
っている。だとすれば、われわれはこの速度の差
異を念頭に置きながら、二つの原理における空間
の秩序の差異を見ていかなければならないであろ
う。
ドイッの領土では、警報システムは戦争の
心理学において重要な役割を果たしている。
爆撃機の編隊がヨーロッパ要塞の沿岸の境界
を越えるやいなや、その侵入が、警報によっ
て人々に知らされ、編隊の侵入やその行先の
変更に応じて、その変更が、目標となった都
市に伝えられる。戦争の空間と時間は圧縮さ
れ、危険は何百万もの聴衆者によって同時的
に体験される。保護してくれるものとは、情
報であるかのように思われ、もはや空間がな
いのであれば、時間を確保する必要がある
・… キなわち、反応の時間を。自らを効果的
に守るためには、何にかえても、不意打ちの
効果をそがなければならない。このことは
〈後からみれば(αposteγiori)〉、『わが闘争』
の著者が正しかったことを明らかにしている。
彼は獄中で、「防衛という考えが生にとり葱
き、生を満たしている」と述べていた(ibid.,214)(引用した原文におけるイタリ
ック体は〈〉に入れてある。以下の引用も
同様である)。
軍事的空間における「攻撃と防御の弁証法」は、
マテリアルな建築による防御物から非物質的な遠
隔技術に依拠した防衛体制を優位に置く。第二次
世界大戦では、空間を組織する二つの原理が共存
している。一方では、ヨーロッパ要塞に見られる
ように、建築術によって担われている空間の組織
化の原理が存在し、他方では、ラジオや警報シス
テムといった技術によって組織される空間がある。
この二つの原理は、共に防衛という観点では共通
するが、大きな違いは、空間を組織するにあたっ
第二章 空間の秩序
第三節 囲い:領土化
ヴィリリオが1970年代に出版した著作、具体的
に言えば、『バンカー・アルケオロジー』(1975)、
『領土の不安定性』(1976)、『速度と政治』(1977)、
『民衆的防衛とエコロジー闘争』(1978)では、こ
れらの著作が出された当時の戦争を取り巻く時代
状況についての分析と戦争と都市との関係の歴史
についての考察とが重なり合っている。
これらの著作の論点を振り返ると同時に新たに
展開する対談集、『純粋戦争』の中で、ヴィリリ
オは、次のように自己規定している。「私は第一
に都市計画家です。しかし、都市との関係は、私
には真っ先に、政治との関係なのです。そして、
語源的には、都市計画家と政治家は同じなのです。
政治的イデオロギーにからめとられて、政治とは、
何よりも「ポリス」だということが隠蔽されてき
ました」。ヴィリリオにとって、都市計画家は、
ポリスを空間化する役割を担うが故に、政治家と
同じ位置に立つものとされる。そして、都市の起
源を問うロトランジェに対して、ヴィリリオは、
次のように答えている。
都市計画の思想には、二つの大きな流派があ
ります。そのうちの一つによれば、まず商業
主義があって、それから都市の結晶化、都市
的定住性が生まれます。もう一方は少数派で
すが、フィリップ・トインビーなどが言うよ
うに戦争が先で、商業は後からやってくると
考えています。もちろん、私は後者の立場で、
都市は戦争の結果、少なくとも戦争への備え
折り重なる空間 ポール・ヴィリリオの思想についての一試論 209
(preparation for war)の結果だと主張する側
にいます(Virilio+Rotoringer.1983/1997
[1987],9,11 [8,101)。
戦争に都市の起源を見ることは、空間の組織化
を通じた戦争の組織化の始まりを考えることであ
る。続けて、ヴィリリオは、部族たちの戦争と国
家によって組織される戦争との違いを説明してい
る。ピエール・クラストルは、未開社会ないしは
部族社会において、戦争は国家に抗するために行
われるものだとしたが、ヴィリリオは、クラスト
ルが論じた部族社会の戦争をローマ人が言う「騒
乱(t㎜ulus)」っまり、現代的に言えば、ほぼ
内戦に近いものとして位置づけている。もちろん、
部族社会において、空間の組織化が存在しないと
いうことは不当なことである。部族社会の村落は、
一定の秩序をもって形成されている。しかし、少
なくとも、部族社会は、多くの労働力を必要とす
る防塞を持たない、あるいは持つ必要を感じない。
ヴィリリオにとって、〈いつ〉空間の組織化を伴
った国家が現われたのかが問題なのではない。あ
くまでも、問題なのは、二つの社会での戦争の組
織化の違いであり、「囲い」の果たす役割である。
実際、別のところで、ヴィリリオは、城塞という
囲いをもった都市の「定住者」と「遊牧民」とを
対立させている。ジャン・デュビノー(Duvignaud 1977)は、遊牧民を「都市であらざ
るもの(non-ville)」に依拠した民族として定義
しているが、ヴィリリオの議論は、5世紀に西ロ
ーマ帝国を滅ぼした遊牧騎馬民族が、いかに定住
者になるのかということを問題にしている。
それまで、定住することなく、移動することに
専心してきたこの遊牧民族は、自らの空間と時間
を移動し続ける持続の中に引き伸ばし、全ての空
間が直接的で、従って、近接的であるような(移
動の)空間の中に充足していたと、ヴィリリオは
述べている。言い換えれば、遊牧民の主体にとっ
て、意志することと動くこととの間に大した距離
はほとんど存在していなかった(というより、む
しろ、意志、つまり計画するより先に動くと言っ
たほうがいいかもしれない)。このような遊牧民
の性質は、「主体が領土によって自らを立ち上げ
るようになる時に」、言い換えれば、古代ローマ
にあったような要塞が、「戦略的な建設によって、
継続的な障害というその最初の定義のもとで再び
現われる」時に、消滅する。なぜならば、騎馬民
族が以前には走破していたような「領野は以後、
制限され、走破されなくなり、支配され、見られ
る」ようになり、空間の直接性は消滅し、「法を
遵守する原理(16galisme)」を媒介とした空間秩
序が課されるようになるからだと、ヴィリリオは
述べている。
ヴィリリオは、「「防御を〈戦闘の最も強力な形
式〉にしているもの」(クラウゼヴィッッ)から
結論を引き出すときだ」と主張する。すなわち、
防御の概念からそれに一般的に結びつけられ
ている〈不可侵(non-agression)〉という考
えを取りあげれば、いかにあらゆる防御物
(protection)の構築が、それ自体で社会的な
暴力の行為であるかを理解できる(Virilio
1976/1993,75-77)○
この文章の註で、ヴィリリオは、ロムルスによ
るレムスの殺害に触れている。すなわち、領土を
区切る単純な線を侵犯することが、兄弟殺しとな
る逸話である。この逸話が伝えているのは、空間
の境界線が、生死を分かつ境界線へと変化すると
いうことである。空間を区切ることが同時に、生
死の境界をも区切る。この生死を司る原初的な法
が、防衛のために空間を区切ることの根拠を裏打
ちし、時にその「社会的な暴力」を表出させる。
それゆえ、ヴィリリオは次のように国家を定義す
る。
従って正確には、国家の誕生は、社会性の領
野のただ中に、その存在者(6tant)を据え
ること、言い換えれば、自らの領野の人工性
を築き上げることなのである。その起源から
して、社会の人工性と自然性を作り出し、対
210 平田 周
立させるのは、国家なのであり、それゆえ、
国家は、常に法廷であり、都市(原国家(1’UγstCtαt))なのである(Zbid.,80)。
もちろん、都市の「内壁(intramuros)」にそ
の領土を制限された都市国家と内壁に制限される
ことなく「国土」を領土とする国民国家とは異な
る。しかし、ここではあくまでも、「原型」とし
ての国家が語られている。言い換えれば、国家は、
空間を領土化し、その領土に自らの秩序を課すも
のとして規定される。そして、空間の組織化と法
の制定の結びつきこそが、部族社会や遊牧民社会
とは異なる特定の社会の組織化を可能にする。こ
のような秩序が、第一節で見た建築あるいは領土
による空間の組織化のなかにある。では、第二の
空間を組織する原理において、いかなる空間の秩
序が伴っているのであろうか。この点についても、
先の対談に耳を傾けてみよう。
第四節 非物質的な囲い
19世紀までは、社会はブレーキの上に成り立
っていました。速度を高める手段にとても乏
しく、〈中略〉大まかに言って、19世紀まで
は速度の生産がありませんでした。城壁、法、
規則、禁止事項などを通じて、ブレーキを作
ったのです。〈中略〉それから突然、大革命
が起こるのです。これは産業革命、交通革命
などとも呼ばれていますが、私は速度[走
行]体制の革命(dromocratic revolution)と
呼びたい。なぜなら、発明されたものは単に
よく言われるように似たものを複製化する可
能性ではなく、〈中略〉まず蒸気機関によっ
て、そして内燃機関によって速度を作り出す
手段だったからです。ブレーキの時代から、
アクセルの時代へ移ったのです。つまり、権
力は加速することそれ自体に投資し始めたの
です(Virilio+Rotoringer.1983/1997[19871,
50-51{64])○
ブレーキからアクセルレーターへの都市の機能
転換は、都市の下部構造(infrastructure)の整
備を通じて、空間の上に物質的に築き上げられる
囲い=城塞(1’einceinte)から速度を「支え」と
した空間の組織原理への移行を物語っている。こ
の移行に伴って、権力は、空間を走破する時間
[速度]を通じて、空間をコントロールするよう
になる。
このような都市の運搬・輸送機能を支えるイン
フラストラクチャーの役割の重要性を戦争との関
係において強調するために、ヴィリリオは、クラ
ウゼヴィッッの理論的な敵対者であるアンリ・ジ
ョミニが展開した「兵姑術(10gistique)」という
議論を取りあげている。ロジスティックスは、現
在では、原材料の調達から完成した製品の配送に
まで至る物流の仕組み全体を指すが、もともとは
進軍する軍隊への武器や食料、衣服の輸送を確保
するための技術を指していた。モスクワ遠征後の
1814年にフランス軍を離れるまで、ナポレオンの
参謀として名を馳せたジョミニが兵姑術の議論を
展開させたのは、ナポレオン戦争時に何十万もの
兵士に食料を補給する必要性があったからだと、
ヴィリリオは言う。つまり、兵砧術とは、戦線の
拡大に伴って、いかに人と物を効率良く動かす流
れを作ることができるかという要求から生まれた
ものであり、現代風に、「ネットワーク」の構築
と言い換えることができるものである。この兵姑
術の議論は、第一次世界大戦と第二次世界大戦を
頂点とする総力戦において展開された「戦争経
済」の原型であるとも、ヴィリリオは指摘してい
る(Virilio+Rotoringer.1983/1997[1987],23-24
[25])。
以上のことを踏まえると、『速度と政治』は、
まさにこの都市の機能変換と戦争との関係を、最
初から最後まで叙述していることが理解できる。
この著作は、「あらゆる革命には交通が逆説的に
現前する」という一文で始まり、エンゲルスが生
きた時代において、プロレタリアートが革命的な
諸力となるのは生産現場ではなく、生産の歯車か
ら離れ群衆となる街路においてであると言う。そ
して、ヴィリリオは、街路、あるいは「アスファ
折り重なる空間 ポール・ヴィリリオの思想についての一試論 211
ルトは政治的領土なのか」と奇妙な問いかけをし
ている。この問いから出発して、「不動の機械」
である要塞から「動的機械」である「道路と鉄道
のインターチェンジ」への移行の歴史が様々なエ
ピソードを連ねながら語られていく。その叙述か
ら理解できるのは、ヴィリリオにとって、(産業
革命によって成立した)近代の都市とは、都市と
農村という固定された対立を指すのではなく、停
止と交通という動的な対立を示唆する場なのであ
る。言い換えれば、ヴィリリオにとって、(近代
の)都市とは、「高速交通路(河川、道路、沿岸
航路、鉄道など)に貫かれた人間の居住地」であ
り、諸々の技術的運搬手段が織り成す「軌道の織
物」に他ならない(Virilio 1977[2001],13,15,17
[10,13,15】)o
ここで、当然の疑問が浮かび上がる。ブレーキ
としての都市において、権力は、空間を仕切るこ
とによって、その空間を動くものに秩序を課して
いたとするならば、加速する交通の場となったア
クセルレーターとしての都市において、権力はど
のように機能するのであろうか。「アスファルト
は政治的領土なのか」という奇妙な問いかけがこ
の問いと通底しているように思われる。移動と運
動の場は、どのように区切られるのか。アクセル
レーターとしての都市において、権力は、空間の
仕切りによって運[移]動を制限するだけでなく、
運動そのものに対して介入する。ヴィリリオは、
移動と運動に対する「速度規制」に触れた後で次
のように述べている。
したがって国家の政治権力は二次的な意味に
おいてのみ「他階級の抑圧のために組織され
た一階級の権力」であり、より物質的なレベ
ルでは、〈治安警察にほかならない〉。〈治安
警察とは、すなわち交通管理(voirie)であ
り〉、それこそが国家の政治権力であるのは
次の点に関わっている。ブルジョワ革命の黎
明期以来、政治的言説は、社会秩序を(人々
の、あるいは商品の)交通に、そして、革命
や暴動を交通渋滞、違法駐車、玉突き衝突、
事故に混ぜ合わせながら、古い自由都市的な
攻囲術を多かれ少なかれ意識的に取り込んで
ゆく一連の過程にほかならなかったのである
(Virilio 1977[2001],23-24[24])。
ヴィリリオにとって、権力とは、自らが支配す
る領土的秩序に従って、人や物の運動の流れをコ
ントロールするものである。かつての城塞都市は、
門によって人や物の流れをコントロールしていた。
都市の門や港の出入り口における人や物の流れの
コントロールに加えて、近代の都市において、人
や物の流れそのものの中で、社会秩序と秩序壊乱
的なものを区別する。街路の革命的運動は、権力
にとって、交通規制の対象でしかない。つまり、
近代の権力は、ある空間の出入りをコントロール
するだけでなく、街路の運動をコントロールする5。
しかし、この街路の運動への介入も、「攻囲術」
という言葉で語られていることに注意する必要が
ある。この「囲い」は、空間において物質的なも
のとして築き上げられるのではなく、運動の軌道
上に築き上げられている。この囲いの「非物質
性」は、航空機の利用が一般的なものになり、よ
り都市が加速する1970年代において顕著になる。
ヴィリリオは、1970年代の脱産業化社会におけ
る経済体制の変換の相反する影響を語っている。
一方では、多国籍業の活動による最初の影響が、
工業生産地帯において生じる。つまり、海外に低
賃金労働者を求める企業が工場を移転させ、それ
までの工業都市の産業を廃棄する(d6sindustr-
iser)。ヴィリリオが、念頭に置いているのは、
イギリスのリヴァプールやシェフィールド、アメ
リカのセント・ルイスやデトロイト、西ドイツの
ドルトムントといった都市である。他方で、かつ
ての港や駅のように、国家の新たな玄関となった
空港を中心に巨大な集住地域が出現する。しかし、
「これらの空港の建設は、「ハイジャック」に対す
る防衛という至上命令に従わされることになる」。
したがって、この新たな都市は、同時に交換やコ
ミュニケーションの場だけではなく、「「航空警察
212 平田 周
や国境警察」にとっての管理と高度監視によって
推進される実験場」となる。この新たな実験場に
おいて、管理されるのは、主体(sujet)という
よりも正確には、その行程(trajet)だとヴィリ
リオは主張する。
従って、もはやかつてのように、監禁によっ
て伝染病患者や容疑者を分離することが問題
なのではなく、とりわけ、その行程において
容疑者を捕捉すること(intercepter)が問題
となったのである。つまり、容疑者の衣服や
荷物を検査する時間が問題なのである。そこ
から、やむを得ない場におけるカメラや電波
探知機、発見器の急激な増殖が生じるのであ
る (Virilio 1984b,10-11)。
この移動の自由の場であるはずの空港に設置さ
れた監視技術は奇妙なことに監獄にも適用され、
銀行やスーパーマーケット、ハイウェイといった
より日常的な場所にも設置されるようになる。監
視技術は、それを内面化するかどうかに関係なく、
リアル・タイムで、主体の行程の傍らに存在する。
この囲いの非物質化は、明らかに、鉄道や自動車
といった様々な「投射物」が都市を貫き、領土の
流動性が増大すること対応している。この囲いは、
物質的なものではなく、不可視で、「動的」なも
のとして現われている。先に我々は、運動の軌道
に介入する権力を見たが、ここでは、運動の軌
[弾]道が囲いを打建てている。いわば、かつて
の要塞を象徴とする囲いが建築術によって築き上
げられていたとするならば、加速した都市におい
て、囲いは、技術が産み出す運動や速度によって、
「非物質的な囲い」として、構築される。
しかし、速度は、国(内の領)土の管理に役立
つだけなのだろうか。『領土の不安定性』という
タイトルが暗示しているように、速度と領土の関
係は、不吉な側面を持つ。実際、ヴィリリオは次
のように述べている。
もし、人工的な社会的領野の創造に必要な
城壁=囲い(1’enceinte)が物理的なもので
あるならば、その領野の内容は心理的なもの
である。困苦を味わうこの内的な全体性が到
達した諸次元は、18世紀の終わりから20世紀
までのヨーロッパにおける民族主義的な諸々
の戦争(guerres natiomalistes)を説明する。
その歴史は、まず、〈壁一前線〉という観念
の、言い換えれば、国民=国家の囲い(en-
Ceinte natiOnal)という観念の延長のために
生じるものであり〈中略〉、次に大陸の囲い
の観念(第三帝国の「ヨーロッパ要塞」)に
よって生じる。そして最終的には、[核によ
る]現状維持と、根本的に大陸的な大がかり
な閉鎖の〈心理的な囲い〉を破壊するであろ
う衛星中継による諸々の番組の放送のような
新たな問題(人はこの点に関するソヴィエト
の気のない態度がアメリカの新たな戦略的な
実現の惑星的な特徴の前での諸々のイデオロ
ギーの乱暴な衰退の徴であることに気づくで
あろう)とともに、地球規模の囲いが生じる
(Vir且io 1976/1993,83)。
冷戦期の中で書かれたものであるが、この文章
は、当時、ヴィリリオが何によって地政学的な空
間が支配されていると考えていたのかを明らかに
してくれる。核戦略とコミュニケーション・メデ
ィアが、地球規模の囲いを築き上げる。囲いが地
球規模に至るとき、その空間の秩序は、かつての
領土的境界の原則にしたがった国家間の政治的秩
序を不安定なものにする。実際、当時、主権国家
間の秩序を規定し、東西を分割していたのは、ア
メリカとソヴィエトの核の傘だったのではないだ
ろうか。互いがつかず離れず、破壊し合うことが
できるという「相互確証破壊」、あるいは恐怖の
均衡と呼ばれていた奇妙な「抑止」の論理こそが
空間の秩序を担っていたのである。
空間を組織する原理は、繰り返しになるかもし
れないが、建築術よりも速度を産み出す技術に優
位が置かれることになる。ここで、われわれが区
別した「囲い」と「非物質的な囲い」の区別は、
折り重なる空間 ポール・ヴィリリオの思想についての一試論 213
時期区分はだいぶ異なるものの、ドゥルーズの
「規律訓練社会」と「管理社会」の区別と重なる。
ドゥルーズは、管理社会の分析の先駆者として、
ウィリアム・バロウズ、ミッシェル・フーコー、
ヴィリリオの三人の名を挙げ、「閉じられたシス
テムの持続」において作用する「規律訓練社会」
から「超高速(ultra-rapides)的な管理形態」へ
の移行の分析者としてヴィリリオに言及している
(Deleuze 1990/2003[1992],241[293])6。この二つ
の空間の組織化の形態を踏まえることによって、
なぜ、ヴィリリオのテクストが、とりわけ、1980
年に出版された『消滅の美学』以降、視聴覚メデ
ィアの分析に重点を置くようになるのかを、我々
は理解できる。実際、1990年に出版される『不動
の極[邦題:瞬間の君臨]』の副題に、ヴィリリ
オは、「環境コントロールについての試論」とい
う副題を付している。
第三章乗り物としてのメディア
第五節 地平なき知覚
ヴィリリオの技術についての分析の特徴は、技
術、あるいはメディアを「乗り物=媒体(v6i-
cule)」として考えることにある。この考えにつ
いて、ヴィリリオは、次のように述べている。
速度は一つの環境(milieu)なのであり、環
境そのものなのです。われわれは大地の表面
に住んでいるだけでなく、速度に住んでいる
のです。速度は環境であり、様々な乗り物=
媒介(v6hicules)は、それらが環境を解釈
するという意味で、その環境の理論なのです。
例えば、車は、超音速の飛行機や歩行や自転
車と異なる速度の環境を解釈します。速度は
一つの環境であり、自転車や馬、車といった
新たなメディアのそれぞれの発明は、環境を
解釈する方法なのです(Virilio+Ewald1995,102)。
この考えが最初に示されたのは、1976年に出版
された『領土の不安定性』の末尾に置かれた、
「媒介するもの(v6iculaire)」という論考におい
てである。この論考は、タクシーの乗客の身体に
おける「厳密には決して横切られた環境と混同さ
れない「速度の国」とは何か」という奇妙な問い
かけから始まる。通過している場所とは異なる
「速度の国」という言い方に現われているように、
乗り物の乗客が置かれた場所ならざる場所性が問
題となっている。言い換えれば、問題となってい
るのは、知覚の場である。
この乗り物としてのメディアという考えは次の
二つの観点から興味深いように思われる。その観
点とは、一つは、現象学的観点であり、もう一つ
は、もちろん第一の観点と密接な結びつきを持っ
ているのだけれども、ヴィリリオが導入した「動
く乗り物」と「動かない乗り物」という区分であ
る。
ヴィリリオは、第一の乗り物として、歩行者
(pi6ton)の身体を取りあげている。ヴィリリオ
は、歩くという運動において、その身体と身体の
速度は一致し、この「動物的身体」は、植物の発
育の時間とは異なる生物学的かつ生理学的な時間
の中に暮らし、自らの運動能力において、身の回
りの現象を知覚すると述べている。このような見
方は、明らかに次のようなメルロ=ポンティの見
方を踏まえている。「身体とは世界内存在の媒質
(v6hicule)であり、身体を持つとは、ある生物
体にとって、特定の環境(milieu)に適合し、い
くつかの企て=投企(projets)と一体となり、
そこに絶えず自己を参加させてゆくことである」
(Merleau-Ponty 1945[1967],97[(1)147-1481)7。
メルロ=ポンティの認識に加えて、ヴィリリオ
がメディアを「乗り物」、あるいは「世界内存在
の媒質」として考えるとき、メディア利用者は
「乗客」として考えられ、彼が用いる「乗り物」
とカップリング(couplage)しているものとして
考えられる。たとえば、馬に乗る者は、馬の速度
において、環境を観察するわけだが、彼の世界の
見え方は、歩行者や自動車とカップリングされて
いるものと異なる見え方なのである。
214 平田 周
メディアを乗り物として考えるというヴィリリ
オの考えが独特なのは、この見方を馬や自動車と
いった「動く乗り物」だけでなく、「動かない乗
り物」と呼びながら、視聴覚メディアにも適用す
るからである8。ヴィリリオのテクストにおいて、
運搬手段としての「動く乗り物」よりも伝達手段
としての「動かない乗り物」についての分析に重
点が置かれるのは、後者が圧倒的に「速い」とい
う理由もあるのだが、何よりも、まさに後者にお
いて、現象学的な知覚の場が問題になるからであ
る。
ここで、ゲシュタルト心理学および現象学とヴ
ィリリオの関係についてうまく整理している、イ
アン・ジェームズの議論を参照しよう。彼によれ
ば、ゲシュタルト心理学(この心理学自体、現象
学の影響を受けているのであるが)は、知覚は、
旧来の連合主義者が考えるように、原子的な知覚
の集まりとして形成されるのではなく、「地」と
「図」の関係によって、言い換えれば、形態とそ
の形態が置かれた背景によって決定されると主張
する。他方で、現象学は、空間が実体的な物それ
自体なのか、あるいは単に物と物との間の関係を
指すのかについては関心を持っていない。むしろ、
現象学は、空間をまず何よりも知覚されるものと
して経験する。そして、この空間的な知覚は、そ
の身体が位置する空間と切り離せないものと考え
られ、これを現象学は「空間性」と定義する。言
い換えれば、高さと幅と奥行きを持った三次元の
空間として理解される空間は、「位置づけられ、
生き生きとした空間性」なくしては理解できない。
それゆえ、身体が環境に埋め込まれていること、
あるいは環境との関わりの中での身体の位置取り
と運動が重視されなければならないと現象学は考
える (James 2007,12-24)。
ジェームズが整理したように、まさにメルロー
ポンティは、『知覚の現象学』の「序論」におい
て、ロックやヒュームなどイギリス経験論が仮定
したような経験の最小単位としての「感覚(sen-
sation)」に代えて、知覚を経験の条件に据えよ
うと試みた時、ゲシュタルト心理学の議論を活用
している。知覚は、(空間の)状況を「一挙に
(per-)把握する(cept)」。メルロ=ポンティは、
映画の観客と歩行者との対比を通して、知覚によ
る対象の空間把握を考察している。
映画を見ていて、カメラが急にある対象に向
けられ、それからそれに接近してそれをわれ
われに大写しにして見せる場合、われわれは
それが灰皿だとかある人物の手なのだという
ことを想起することならたしかにできるけれ
ども、はじめて見てそれがそういうものだと
実際に認知することはできるものではない。
というのも、そもそもスクリーンは地平をも
たないからである。これに反して実際に物を
見る場合には、私が自分のまなざしを風景の
一部のうえに据えると、その部分は自己を活
発化し、自己を展開して、一方、他の諸対象
の方は周縁へと退き、眠り込むけれども、し
かしそれらとても、けっしてそこに在ること
をやめることはないのである。ところが、こ
れらの諸対象とともに、これらの諸対象の地
平をも、私は新たに自分の意のままにし得る
のであり、現在私が凝視している対象も、視
界の周縁に移されて見られることによって、
これらの地平のなかに含まれてくるようにな
る。〈中略〉対象一地平という構造、つまり
パースペクティブというものは、したがって、
私が対象を見ようとする場合に私の妨げとな
るものではない。〈中略〉ある対象を見ると
いうことは、その対象のなかに住まいに来る
ことであり、そこから他の一切の事物をそれ
らがその対象の方に向けている面にしたがっ
て捉えることである。〈中略〉それらの事物
をもまた私が見ているそのかぎりでは〈中
略〉私は潜在的にはそれらの事物のなかに位
置づけられながら、私の現在の視覚の中心と
なっている対象を、すでに様々な角度から統
覚している(apergois)わけである(Merleau-Ponty 1945 [1967】,82-83 [(1)
126-128])o
折り重なる空間 ポール・ヴィリリオの思想についての一試論 215
「対象一地平」という構造において、われわれ
は、事物を様々なパースペクティブから統覚する
ことによって、事物の多様な現われを見る。セザ
ンヌの絵において表現されたように(ヴィリリオ
は、メルロ=ポンティと同様、しばしばセザンヌ
の絵画への愛好を口にする)。しかし、スクリー
ンにおいて、パースペクティブは閉じられている。
というのも、それは「地平を持たないからであ
る」。まさに、視聴覚メディアにおけるこのよう
な知覚の場こそが、ヴィリリオが「否定的地平」、
あるいは「非一場(non-lieu)」と呼ぶものであ
る。現実空間に存在していた起伏(relief)も奥
行き(profondeur)も存在しない否定的地平にお
いて、事物は、厚み(epaisseur)や立体感(vol-
ume)を持たない、ただの外観(apparence)と
なる。当然のことだが、スクリーンに映る灰皿の
背後には、スクリーンの裏側しか見えないのだが、
それは、灰皿を眺めるパースペクティブが画一化
されているためである。このような歩行者と映画
の対比は、「知覚の体制」の差異を明確にするた
めのものであって、もちろんその優劣を決めるも
のではない。メルロ=ポンティが「想起」という
言葉で示しているように、映画のイメージはモン
タージュを通じた時間において組織されているか
らである。空間を造型する建築に携わってきたヴ
ィリリオにとって、建築と時間芸術である映画と
の対比は重要なものである。しかし、ヴィリリオ
が問題とする「経験の地平」の喪失は、電子メデ
ィアが広まっていく時代において、より露わにな
っていく。「ポスト・モダン」とも呼ばれるこの
時代において、イメージの「浮遊感」や「無重力
感」がリアリティとして知覚されることになるだ
ろう。
メディアを「乗り物」として考えること、それ
は、様々な速度が生み出す「知覚の経路(tra-
jet)」において、主体[人間]と客体[世界]と
のつながりを考察することである。我々は様々な
「乗り物」・機械(自転車や自動車、バイク、鉄道、
映画)を通じて、自らを取り巻く環境を知覚す
る9。このような様々な知覚の経路を通じた、人
間という生き物と環境との生態的な関係を指して、
ヴィリリオは、「知覚のエコロジー」とよぶ。し
かし、このような「知覚のエコロジー」は、電子
メディアが支配的な「知覚の経路」として選択さ
れていくような時代になると汚染されていくと、
ヴィリリオは述べている(Virilio 1995,75-87)1°。
というのも、電子メディアという「動かない乗り
物」は、「距離」や「広がり」、「自然な大きさの
知覚」を汚染するからである。このような電子メ
ディアにおいて、もはや、現実の空間におけるパ
ースペクティブよりも、「リアル・タイム」のパ
ースペクティブが問題となる。言い換えれば、問
題なのは、いま一ここにおける知覚ではなく、よ
そにあるものがここにおいて現われること、すな
わち「遠隔現前」とは、いま一ここという現実の
空間において何を意味するのかということである。
都市計画家を自認するヴィリリオにとって、この
問題は、都市の問題でもある。それこそが『危機
の空間』と題された著作の問題である。
第六節 否定的地平のなかの都市
ヴィリリオは、遠隔技術が作り出す界面(in-
terface)は、それまでの空間的な境界概念を一
変させるものだという。つまり、かつては家に入
ることと同じように、都市を訪れることは身体を
持った人間が物理的に境界をまたぐことを意味し
ていたが、遠隔技術の利用者たちにとって、家も
都市も共に扉=門(porte)を唯一の境界とはし
なくなった。凱旋門のような都市の入り口は、価
値を減じられ、無数のスクリーンによって機能す
るインターフェイスが、知覚することのできない
非物質的な電波を通じて、インタラクティブな網
目を形成する。そして、遠隔技術を通じたインタ
ラクティヴィティは、都市を境界づけていたここ
とよその分割ではなく、こことよそを「分離不可
能(non-s6parbilit6)」にすることによって機能
する。このことは、具体的に知覚可能な空間の境
界が絶対的な客観性を持たなくなったことを意味
する。「コントロール・モニターやスクリーンの
面の間(inter-facade)を通じて、よそはここで
216 平田 周
始まる。またその反対も同様である……」(Virilio 1984b,13)。
ヴィリリオは、あたかも、インタラクティブな
網の目において、ベルグソンが意識の内的持続を
描き出すために用いた「相互浸透」が生じている
ように描いている。「〈もし、空間が、すべてが同
じ場所(place)〉にあることを妨げるものである
とするならば、この急激な封じ込め(confine-
ment)はすべてを、絶対的にすべてを特殊な場
所(emplacement)なき場所に運ぶ……。自然な
起伏と時間の距離の全ての局所化を、すべての位
置を衝突させる」。つまり、相互外在性において、
人や物は、その身体や物体が占めている位置を譲
り渡すことはできないのであるが(それは、身体
にとって死を、物体にとって破壊を意味する)、
インタラクティブな網の目において、少なくとも、
人や物、場の「外観」の交換は、いくらでも可能
になる。しかし、相互浸透性といっても、ベルグ
ソンは、この特徴を「持続」に与えたのに対し、
ヴィリリオは、この特徴をベルグソンの持続と対
立するような「遍在性(ubiquit6,0mnipr6-
sence)」に与える(ibid.,19,155)。ベルグソン
の持続の定義をパラフレーズするならば、「遍在
性とは、ここ[よそ]がよそ[ここ]を謡ってす
すみながら膨らんでゆく終わりなき現在という囲
いである」11。
こことよそを分離不可能なものにし、絶えず膨
張していくこの〈いま〉とは、都市という現実の
空間にどのような影響を及ぼすのであろうか。
「家にいる遠隔的な聴衆が、劇場や都市の聴衆や
俳優たちの定住性を引き継ぐのは、発信と受信の
リアル・タイムにおける集中が、共に人々が暮ら
す(cohabitation)現実空間の旧来の集中を、つ
まり、それまで都市建築が占有していた隣…人性の
単位を更新するからである」と、ヴィリリオは述
べている(ibid.,96)。つまり、ここに「住まっ
ていない」12といわれる遠く離れたものの知覚は、
現実の空間の上に反映されるのだ。ヴィリリオは、
このような「定住性」の相違を、現実の空間にお
ける「公共空間」とリアル・タイムにおける「公
共イメージ」の違いとしても説明している。つま
り、遠隔的技術を介した知覚の現実とは、身体的
な知覚の直接的な現実との知覚の経路の違いにと
どまらず、現実の空間の組織化にも関わるものな
のである。ヴァーチャルな空間が現実の空間に折
り重ねられる。公共イメージが公共空間に取って
代わることは、空間の危機である。そして、この
空間の危機は、もちろん、多国籍企業による都市
空間の再編と無関係ではない13。ヴィリリオは、
この都市の再編の背後に1980年代のネオリベラリ
ズム的な経済政策をも見てとっているが(ibid.,
160)、こうした遠隔技術を通じたインタラクテ
ィブな活動は、情報革命を経た90年代以降、さら
に激化する。そして、ヴィリリオは、「フーコー
の言う大監禁は、18世紀に始まるのではなく、21
世紀に始まるのです」とまで、主張する(Virilio
+Petit 1996[19971,48[53])。一見、アナクロニ
ックな印象を与えるこの発言は、瞬間的に行われ
るヴァーチャルな投機や株の取引が、会社が積み
上げてきた価値のみならず、実物経済を支配して
いくような社会の一側面を言い当てているように
思われる。ついでに触れておけば、ヴィリリオは、
『危機の空間』が出版された同じ1984年に、ウィ
リアム・ギブソンの『ニューロマンサー』におい
て、「ヴァーチャル・スペース」や「サイバー・
スペース」という言葉が使われていたことを、自
ら指摘している(Virilio+Rotoringer 2002,80)。
われわれは、以上のような視聴覚メディアにお
ける遠隔現前についてのヴィリリオの現象学的技
術論を通して、空間の組織化の二つの原理を新た
に定義することができる。すなわち、建築による
空間の組織化は、現実の空間〈における〉分離を
行うのに対し、遠隔技術の速度による空間の組織
化は、こことよそを分離不可能にすることによっ
て、現実のいま一ここという空間〈と〉の分離を
行う。
このような現実的な空間とヴァーチャルな空間
との分離という主題は、ヴィリリオが建築原理の
運動をしていたときに影響を受けていたギー・ド
ゥボールのスペクタクルの概念にも見られる。実
折り重なる空間 ポール・ヴィリリオの思想についての一試論 217
際、ドゥボールが指導的に率いたシチュアシオニ
スト・アンテルナショナルは、映画と都市という
ヴィリリオと親しい主題に取り組んでいた。1967
年に出版され、68年の五月革命において多大な影
響を及ぼしたとされるスペクタクルの概念は、現
実の空間における大道芸などの見世物や、フーコ
ーが『監獄の誕生』のなかで古典主義時代の「死
の権力」(それが用いる見せしめの刑)を特徴づ
けるものとして用いたそれを意味しない。ドゥボ
ールは、「分離こそがスペクタクルのアルファで
あり、オメガであ」り、「スペクタクルはさまざ
まなイメージの総体ではなく、イメージによって
媒介された、諸個人の社会的関係である」と述べ
ている(Debord 1967/1992[2003],16,27[15,25])。
つまり、ドゥボールが用いるスペクタクルとは、
現実とイメージあるいは外観とが分離するような
社会状況において機能している。このような社会
は、現実において孤立しアトム化した諸個人が、
擬似的な社会的全体性のイメージを与えられるな
かで、「分離されたまま」社会に統合されるよう
な社会である(例えば、諸個人の各々が壁に囲わ
れた家でテレビを見る時、自らの意志でそれをす
ると同時に、その諸個人が同じイメージを共有し
ているように)。つまり、スペクタクルは、個人
と同時に社会全体を支配する。
ドゥボールのスペクタクルの概念は、ヴィリリ
オにも影響を与えているように思われる。しかし、
もし、ヴィリリオにおいて、このようなスペクタ
クルの起源が問われるとするならば、その起源は
消費社会においてではなく、戦場の歴史において
である。『危機の空間』と同年1984年に出版され
た『戦争と映画』において、ヴィリリオは次のよ
うに書いている。
〈戦場の歴史とは、まず何よりもその知覚の
場の変貌の歴史に他ならない〉。言い方を換
えれば、戦争とは「物質的」勝利(領土獲得、
経済支配)を収めることよりも、知覚の領野
(champs de perception)の「非物質性」を支
配するところに成立している(Virilio 1984a/
1991[1999],10[28-29])。
われわれは、この戦場の歴史を通じて、90年代
以降の戦争の問題へと向かい、再び第二章で触れ
た、核と情報コミュニケーションによる地球規模
の囲いに戻るであろう。ただし、米ソの対立が終
わった冷戦以後の時代において、地政学的な勢力
図は姿を変える。ポスト冷戦の時代の戦争は情報
の時代と時を同じくしている。「生中継」の放送
(CNNは、1980年に開設された)も活発に行われ
るようになる。ここでよく知られた軍事技術史的
事実に触れておくならば、ポケベルやインターネ
ットなど「情報革命」の象徴である通信技術は、
核戦争のような「非常事態」に備えて、アメリカ
の国防費によって開発された。つまり、冷戦以後
の社会のインフラストラクチャーは、冷戦の軍拡
競争の賜物なのである。
第四章 グローバルな囲い
第七節 冷戦以後のヴィリリオの戦争論に
おける環境の問題
見世物(spectacle)としての戦争。リアル・
タイムで世界中にテレビ中継された湾岸戦争は、
そのように形容することができるだろう。人類の
歴史において、戦争〈する〉という営みは絶えな
いと言われるが、遠隔コミュニケーションが可能
にした、この戦争を〈見る〉という営みは、もし
後の歴史がこの時期を振り返るならば、人類学的
に「風変わり」なものとして記録されるのではな
いだろうか。
このように「自然化された」戦争を〈見る〉と
いう習慣の始まりと同時に、湾岸戦争は、アメリ
カ軍の兵器と戦術の革命、RMA(revolution in
military affairs)が初めて実際の戦場で試された
戦いでもある。巡航ミサイルや精密誘導ミサイル
に典型的に見られるような間接照準火器(それに
対して戦車砲や小銃のように裸眼で標的を狙う兵
器を直接照準火器とよばれる)や偵察衛星やドロ
ーン(遠隔操縦の無人飛行機)が多用されたこの
218 平田 周
戦争において、従来の戦争にあったような圧倒的
な破壊力よりもいかに迅速に敵を見つけ、捕足す
るかが問題になる。言い換えれば、防御構造とし
ての「障害物」や攻撃としての「破壊兵器」より
も、C31(co㎜and, co㎜unication, control, in-
formation)として象徴されるコミュニケーショ
ン技術が、戦場において優位になる。
以上の二つの点を踏まえれば、第一次湾岸戦争
を分析したヴィリリオの『砂漠のスクリーン』と
いう表題には、二重の意味が込められていること
が容易に理解できるだろう。クウェートとイラク
の砂漠の戦場において多国籍軍が用いるスクリー
ンと、地球規模で視聴者に見つめられるテレビの
それである。1990年代以降に、この著作とは別に、
ヴィリリオは、コソヴォ紛争、そして、第二次湾
岸戦争についての著作を発表している。
これら三つの戦争が行われる時代は、東西の壁
が崩れ、以後いかなるオルタナティブな政治体制
もあり得ず、自由主義市場と民主主義化の「輸
出」が、「歴史の終焉」の名の下に唱えられる時
代である。それら三つの戦争は、巨大なアメリカ
の軍事力の影響力なしには考えられない。しかし、
その影響力はどのような論理と環境において、行
使されるのであろうか。三つの戦争をそれぞれ分
析するヴィリリオの三冊の著作は、「電子的な環
境」による現実の「地理物理的」環境のコントロ
ールを分析している点で、結びついている。確か
に、ここで問題になっているのも、ある瞬間のな
かで空間を縮減する速度や現実の空間とヴァーチ
ャルな空間の折り重なりあい、遠さと近さの混合
といった主題である。しかし、これら三冊の著作
では、その環境における戦争と見ること[視覚]
の関係、あるいはより抽象的に、力とイメージの
結びつきを可能にするものが問題となっている。
戦争と視覚の問題は、『戦争と映画』のなかで探
求されたものである。この著作は、90年代以降の
時事的色彩の強いヴィリリオの戦争論に歴史的な
パースペクティブを与えている。
戦争と見ることの関係は、戦場における、そし
て、戦場を越えた空間の重なり合いの歴史のなか
で結ばれていく。この主題に焦点を絞りながら、
以下では、ヴィリリオの四つの著作を概観し、冷
戦以後の戦争をとりまく問題を検討してみたい。
第八節 リアル・タイムの専制、あるいは
単一のパースペクティブの支配
戦場の歴史において、破壊兵器の絶えざる進歩
はその射程に見合うだけの目標補足技術、すなわ
ち「視覚の分離」の発展を伴っている。ヴィリリ
オは、この分離の発展の歴史を次のように要約し
ている。
事実、遠い過去の時代、高く葺えていた城塞
に始まり、「望楼」の考案という建築学的革
新、係留気球の利用、さらには空軍の創設と
写真による戦場復元技術の出現(一九一四
年)を経て、レーガン大統領提案の「早期警
戒衛星」に至るまで、私たちは休むことなく
戦争における知覚の領域の拡大に立ち会って
きた。肉眼が捉える視覚世界や直接的な視像
は次第に消失し、「眼」に代わって、光学的、
光電子的手段や最高度に精密な「コリメータ
ー(照準器)」が出現したのだ(ibid.,122
[227])。
第一次世界大戦の戦場において、兵士たちは、
暫壕の中に這いつくばって、敵の姿も眼にするこ
とができないし、誰を撃っているのかさえも正確
に確認することができない。裸眼で見ることが限
定されているために、非現実感が強められること
になる。なぜならば、「砲撃がすでに人間よりも
空間に向けられていた」戦争において、身体的な
知覚は、極めて不確実で、危険なものとなったか
らである。「ここでは、もはや自らの視線を信じ
得ない、ものうげな見張り兵の「眼」にではなく、
むしろリュミエール兄弟が発明したシネマトグラ
フにより多くの信頼が置けるといった事態が生じ
ているのである」(Zbid.,126-127[235-237])。
もはや生身の身体のリアリティを信ずることは
できない。それゆえ、「監視装置と近代的戦争機
折り重なる空間 ポール・ヴィリリオの思想についての一試論 219
械の錯綜ないしは結合」が、現実の空間とヴァー
チャルな空間の接合が要請されていく14。しかし、
この知覚の領野は、戦場を越えて公共空間へと拡
がっていく。メディアによる国民の動員は、我々
が先に見た、現実的な公共空間から公共イメージ
への移行を記しづけている。ヴィリリオがその移
行を説明するにあたって取り上げるのは、毎年50
万人もの人を動員した「第三帝国党大会」である。
この大会に集まった多くの群衆は、各人の意思に
関わらず、ヒトラーの演出のエキストラでしかな
かったと、ヴィリリオは言う。1934年の党大会を
『意志の勝利』に仕上げたレニ・リーヒェンシュ
タールの言葉を、ヴィリリオは引用している。
「「大会の準備は映画の準備と並行して進められた。
つまりこの出来事は、ただ単なる人民集会として
ではなく、プロパガンダ映画の材料を提供する形
で組織されたのだ。……〈すべてはカメラとの関
係において決定された〉……」」(ibid.,101
[186-187])。公共空間を形作るスタジアムの熱狂
的な聴衆は、もはやプロパガンダ映画を作るため
の材料、つまり「さくら」でしかない。ヒトラー
が公共空間に集まる人々と公共イメージを見る
人々とのどちらに重きを置いていたかは明らかで
ある。このことは、ヒトラー、あるいはナチズム
の公共空間に対するシニシズムをも示している。
というのも、ヒトラーは、自らの演説の宛先を彼
が演説しているスタジアムという空間よりも、そ
こに不在の(映画館に来る)聴衆に向けているか
らである。
これらの公共イメージの創出や情報操作、情報
歪曲は、視聴覚メディアや情報通信技術が作り出
す知覚の領域が「行動の場」となったことの当然
の帰結であるように思われる。そして、この「知
覚の領野」は昔話ではなく、イデオロギーは違え
ども、その環境をより高度に発展させて現代に現
われている。そのような環境が『戦争と映画』の
出版の7年後にヴィリリオが向き合うことになる
ものなのである。
ヴィリリオは、『砂漠のスクリーン』において
次のように述べている。
各々の観客の注意を焦点化し、一極化させる
ことは住民の意見より住民の時間性のあり方
や時間の用法を漸次的に再組織化することで
ある。直接的イメージは、空間やスクリーン
に映ずる画面構成によってではなく、まず、
時間性によるフィルターなのである(Virilio
1991,38)。
ヴィリリオは、ベトナム戦争における報道は、
「遅れた時間」であったと言う。つまり、ここと
よそは、厳然と分かたれ、反省も可能であった。
しかし、テレビの「否定的地平」において、我々
の現実感を構成する知覚は、いま一ここに「住ま
わず」、こことよそは融合する。現実の空間のパ
ースペクティブがその多様性に対して特徴づけら
れていたのに対して、リアル・タイムのパースペ
クティブは、そのパースペクティブの一様性によ
って、つまり、視点の調整によって、特徴づけら
れる。リアル・タイムにおいて、無限に切り取ら
れる砂漠の戦場の視点は、客観的な情報を与える
というより、視覚の調整を通じて、リアリティを
課すのである。
現実の空間に覆いかぶさるリアル・タイムとは、
「グローバルなものとローカルなものとの融合」
に他ならない。こことよそを結びつける「グロー
バルな時間」、すなわち「遍在性」は、ローカル
な時間、すなわち、「持続」を支配する。この
「偏在性」による「持続」の支配は、イラク兵に
とっては、文字通り「身にしみる」ことであり、
都市、あるいは国家にとっては、その自律性に関
わる。ヴィリリオは、この自律性の危機をより具
体的に、民主主義の危機だと見なしている。つま
り、グローバルなものとローカルなものとの相互
的フィードバックの加速が、境界づけられた領土
のうちでの自律的決定を危機に陥れる。ヴィリリ
オは、この危険性を「リアル・タイムの専制」と
呼び、その危険について警鐘を鳴らす(ibid.,
177,191)。リアル・タイムは、現実の空間の異
なる諸地平を折り重ねながら、単一のパースペク
ティブを課す。われわれはこの単一のパースペク
220 平田 周
ティブのもとで、何を見て、何を見ないのであろ
うか。言い換えれば、何が見えるものとなり、何
が見られないものとなるのであろうか。ドゥボー
ルのスペクタクルの概念以上に、ヴィリリオの速
度の概念が明らかにしているように思われるのは、
速度が抑圧する他(者)の場とそこから生じる他
(者)のパースペクティブである。リアル・タイ
ムの単一のパースペクティブは、複数のパースペ
クティブを自らに従わせることによって現われる。
続く、ヴィリリオの二つの戦争論の問題も、グロ
ーバルな囲いとなったメディア環境における他者
のパースペクティブの圧砕に他ならない。
第九節 グローバルな空間秩序としての人
道の名の下の戦争とテロリズムと
の戦争
リアル・タイムの専制、あるいはリアル・タイ
ムの囲いが、地球規模で構築される。しかし、こ
のグローバルな囲いにおいて、いかなる空間の秩
序が働いているのであろうか。言い換えれば、グ
ローバルな囲いという環境と対になる言説とは何
であろうか。
湾岸戦争は、1990年イラクのクウェート侵攻に
対して行われた国連決議がイラクによって無視さ
れたため1991年多国籍軍のイラク空爆をもって開
始された。つまり、湾岸戦争は、まがりなりにも、
国連の決議を通して実行されたが、『ペテンの戦
略』で問題になるコソヴォ紛争においてはそうで
はない。この「人道的」と称された戦争は、事実
上、国連の安保理決議を無視して行われた。この
ヴィリリオのNATOのコソヴォへの介入に対す
る批判は、人道と軍事活動との結びつきに対して
向けられる15。ヴィリリオは、この介入を正当化
する言説として、「コソヴォで起こっているのは、
領土よりも価値が問題となるような、新たな種類
の戦争なのだ」というトニー・ブレアの言葉を引
いている(Virilio 1999[2000],13[12])。戦争は、
人道、あるいは「人権」の名の下で、脱領土化さ
れることになる。このような言説に対して、ヴィ
リリオは三つの観点から批判している。
まず、人道的戦争は、多くの国々に自国の主権
の行方を懸念させ、諸国間での大量破壊兵器開発
競争を促進させる危険を引き起こすのではないか
というものである。この点を象徴する例として、
ヴィリリオは、核兵器保有とミサイル保有に関す
るインドや北朝鮮のミサイル防衛のために観測衛
星の打ち上げたばかりの日本を挙げている。この
点に加えて、人道的戦争は、核ミサイルや宇宙空
間に展開する兵器を開発する力のない「弱小国」
においては、化学兵器や細菌兵器が広まる危険を
増大させる。そして、第二に、人権という普遍的
な価値を政治的領土に優i先させることは、戦争を
「世俗的な正戦」とし、政治的な調整が困難にな
るまで、戦争を絶対化するという点である。
そして、第三に、この人道の名の下でのコソヴ
ォへの介入を広めるために、使われたメディアで
ある。この人道を広めるために、様々なチャリテ
ィーやメディア・キャンペーンが行われた。その
一方で、ヴィリリオは、「郊外」という「無権利
地帯」が地球に広がっていると言う。この「郊
外」は、先進国のそれだけを指しているのではな
い。ラテン・アメリカやアフリカの国々おいて、
政府軍やパラミリタリーが市民に向けて行う戦争
とそれによって荒廃した都市をも指している。
「郊外の収容施設の被収容者たちは、この国の大
臣たちが好んで繰り返すような「野生人」でも
「新たなる未開人」でもない。実際には、彼らは、
人間としてほとんど前代未聞の窮乏と悲惨が抑え
がたく噴出していることを知らせる警鐘に他なら
ない」(ibid.,68[791)。「野蛮人」や「未開人」
と罵られる移民や難民は、ほとんどメディアによ
って伝えられることもなく、誰の関心も引かない
ような紛争や貧困から逃れ、自らを保護する「法
治国家」を夢見ながら、やって来た人々に他なら
ないと、ヴィリリオは主張する。一方では、人道
の名の下での介入が存在し、他方では、人々の権
利が消滅していく地帯が存在する。このような対
比を示すことによって、ヴィリリオは、誰にとっ
ての人道が、誰にとっての「普遍的価値」がこの
コソボへの介入において、問題になったのかを問
折り重なる空間 ポール・ヴィリリオの思想についての一試論 221
いかけている16。
そして、この戦場の活発な舞台となったのは、
地球外(extraterrestre)の宇宙空間である。バ
ルカン上空には、およそ50基の様々な種類の人工
衛星が周回していたという。そして、コソヴォへ
の介入は、空爆という遠隔戦争の手段が取られた。
さながら、米軍の兵器の「見本市」と化したこの
戦争は、絨毯爆撃という「古典的な」戦略ではな
く、「全方位的な監視」から得られる情報を通じ
た「ピンポイント」爆撃を採用した。しかし、
「ピンポイント」といっても、この爆撃は、ベオ
グラードの中国大使館への誤爆を象徴するような、
事故なのか意図的なのかわからない、「付随被害」
を多発的に引き起こすことになる。そして、この
「人道的」戦争は、戦況がはかばかしくなくなる
とともに、民間人の住む居住区域の組織的破壊を
実行するようになる。
結局、NATOは東ヨーロッパでの最初の軍事的
介入を統御することができなかった。しかし、こ
のことは、アメリカにとっては何の痛手にもなら
なかったと、ヴィリリオは言う。なぜならば、ア
メリカは、この人道、あるいは人権と軍事活動と
が初めて結びつけられた戦争において、自らの軍
事力を実験し、見せつけ、自らの軍事的ヘゲモニ
ーを確立したからである。ヴィリリオは、この戦
争が、広島と長崎の原爆投下からソ連が核を開発
するまでの間の「抑止の独占」に匹敵する「第二
の抑止の独占」の時代の始まりなのだと主張する。
ヴィリリオは、この「第二の抑止の独占」を情報
技術に依拠した「グローバル情報支配」と呼び、
コソヴォは、「第一の抑止の独占」の時代の広島
と長崎と同様、この戦略の「実験地」となったと、
主張している17。
「人道」の名のもとの空間の秩序とグローバル
情報支配という囲い。ヴィリリオは、コソヴォ紛
争の分析において、世界は、「四方形のスクリー
ン」に制御されたと述べていたわけであるが、で
はその後の世界の空間秩序はどうなったのであろ
うか。9・11以降、グローバルな囲いのなかで、
「テロリズムとの戦争」が人道の名のもとの戦争
に付け加わる18。
「9・11」に続く、アメリカへのアフガニスタン
への侵略(2001年)と第二次湾岸戦争(2003年)
について、ヴィリリオは、『パニック都市』の中
で分析を行っている。ここでも戦争とメディアに
よる囲いが問題になっているのだが、その空間の
秩序を担うのは、恐怖ないしは「パニック」であ
る。
ヴィリリオは、この「テロリズムと反テロリズ
ムの戦争」を、その「強迫観念」によって特徴づ
けている(Viriho.2004[2007],45-46[47])19。こ
の強迫観念によって、「テロリズム」の性質が変
化すると、ヴィリリオは言う。「実際、大量テロ
リズムの〈個人主義的な〉性質は、戦争の政治的
形態に対してふたたび問いを投げかける。そこに
は公的な性質と、限界、そしてなにより〈戦争目
的〉があった」。しかし、「テロリズム」は、戦争
目的を失い、「匿名」なものとなる。つまり、テ
ロリズムは、範例、あるいはモデルとなり、国民
的な規模で動員されていくことになる。
こうした(ヴィリリオが「ハイパーテロリズ
ム」と呼ぶ)「テロリズム」のモデル化は、「パニ
ックを払いのけるという口実のもとにパニックを
増殖させる」心理操作を行うアメリカと共犯的な
関係を持つ。人々は、リアル・タイムでスクリー
ンに映し出される単一の恐怖のイメージのループ
化によって閉じ込められ、「意見のモデル化」と
も呼ぶべき「感情の同期化」や「世論の規格化」
を作り上げていく。「実体としての戦争という政
治的技術はふたたび恐怖の技術と化する」(ibid.,
46,68[48,74])○
国民の不安感や恐怖心を煽ることによって、法
をなし崩し的なものにしていくことに対する批判
は、アメリカ国内における法律に携わる専門家に
よって行われている2°。ヴィリリオは、このよう
な不安や恐怖心の増大は、「テロリズムとの戦争」
を超えて、「ゲイテッド・コミュニティー」のよ
うな都市を監視カメラや壁で囲いながら、「内部
的安心感」を享受し、異邦者を締め出す都市の形
態にも現われていることを指摘している。そして、
222 平田 周
ヴィリリオは、国の内外において、「包囲神経症
(psychose obsidionale)」が増大し、都市の「要
塞化」、あるいは「攻囲戦」が再び回帰してきて
いると主張する。あたかも、21世紀の最初の戦争
とその環境の秩序が再び、「防衛という観念が生
にとり懸き、生を満たしている」という言葉で占
められたかのように。それゆえ、ヴィリリオは、
この環境を次のように名づける。「感情民主主義」
の下での「ヒステリー[強迫神経症]的グローバ
リゼーション」と(ibid.,66[72])21。
そして、この感情民主主義に支えられた戦争は、
都市へと向かう。20世紀、そして、今世紀の戦争
は、国際的な戦争や内戦というよりも、絶えず、
都市へ、そして、市民へと向けられていた[る]。
「ゲルニカとコヴェントリー、ハンブルクやドレ
スデン、そしていうまでもなくヒロシマとナガサ
キ」、レバノンやパレスチナ人居住区に対して繰
り返される空爆、コソヴォ、アフガニスタン、イ
ラク、戦場となった都市のリストは無限に延びる
だろう。「どこまでなのか。いつまでなのか。〈都
市という拷問部屋〉を前にした、これだけの軽視
は。これだけの臨床的無関心は」(ibid.,103
[115])。このようなヴィリリオの怒りに、ナント
の空爆の響きを聞き取らずにはいられない。ナン
トの空爆という、決して普遍的ではないが、その
特異な体験は、それぞれの都市とそこに住む人間
が被った災厄の体験と分かち合うものがある。こ
の人間と都市が被った災厄の、その目を覆わんば
かりの惨憺たる光景は、20世紀と今世紀の国際的
な政治的調整の明白な「失敗」を指し示す。それ
と同時に、この光景は、その歴史が克服できず繰
り返されたという意味において、運命的なものを
感じさせる。
この運命は抗い得ないものなのであろうか、ヴ
ィリリオは何かオルタナティブを呈示していない
のであろうか。ヴィリリオは、ただ、現実の空間
への回帰を述べるだけに留まっている。このよう
なヴィリリオの議論は、技術文明によって荒廃さ
せられた〈自然〉に対するノスタルジーだとして
片づけられるものであろうか。しかし、ここで自
然とされている「現実の空間」は何も楽園という
わけではない。なぜならば、われわれは第二章で
見たように、現実の空間においても空間の秩序が
存在する以上、法とそれを支える暴力は存在する
からである。現実空間に対するヴァーチャルな空
間、あるいはリアル・タイムの専制を告発するこ
とは、何がわれわれの存在の基底をなしているか
について反省を迫る。
身体を持つ存在である限り、人間存在は、空間
を占めることなしに存在することはできない。こ
の関係は、個人的な次元に留まらず、都市に関係
する以上、集合的な次元にまで関わるものである。
現実の空間一持続的な時間に、いま一ここに存在
することは、〈時間のパースペクティブ〉の形成
と切り離すことができない。時間のパースペクテ
ィブはもちろん、パースペクティブを一様なもの
にするリアル・タイムのパースペクティブとは異
なる。時間のパースペクティブにおいて、〈どこ
にいるか〉という位置をめぐる問いが、空間のパ
ースペクティブと同様に重要であり、この位置づ
けが過去・現在・未来を持った歴史を構成する。
それ故、ノスタルジーとしてではなく、この〈ど
こにいるか〉を問う限りにおいて、現実の空間へ
の参照は意味を持つ。それは、未来へのパースペ
クティブを切り開くための一つの条件である。し
かし、それは困難なしにというわけではない。運
命のように抗い得ない戦争と技術を前にして、人
間存在と空間との関係の未来が問われなければな
らない。それ故、求められているのは、何か奇抜
なオルタナティブというよりも、状況を反省する
距離を作り出し、その反省を根拠に行動するとい
う極めて日常的な所作である22。いかに、われわ
れの時代が方向づけを失ったかを描き出しながら、
それでもヴィリリオの理論は、「どこにいるか」
を問うという日常的な実践の必要性を絶えず呼び
かけているように思える。どこか祈りにも似た呼
びかけを。
折り重なる空間 ポール・ヴィリリオの思想についての一試論 223
結論
われわれがこれまで辿ってきたヴィリリオの思
想の道筋を概観してみよう。
第二次世界大戦を基点とする西洋の軍事的空間
についてのヴィリリオの探求は、戦争が展開する
空間とそれが用いる技術の歴史と切り離すことが
できない。第二次世界大戦の戦争の風景を構成し
ていたヨーロッパ要塞と空爆による都市の瓦礫は、
ヴィリリオに二つの空間の組織化の原理の探求へ
と向かわせる。そして、その二つの原理は、現実
の空間と技術の速度が生み出すリアル・タイムの
対立へと帰着する。このヴィリリオの思索の手引
きとなったのはメルロ=ポンティであった。現実
の空間における事物は、それを知覚する身体の位
置・運動を通じて多様な現われを見せる。それに
対して、こことよそ、近さと遠さ、ローカルなも
のとグローバルなものとを同一時間上に結ぶ、あ
るいは衝突させるリアル・タイムのテレビ視聴に
おいて、外観は、「対象一地平」という構造を持た
ず、「否定的地平」、あるいは「非一場」のなかで、
一様なパースペクティブのもとに現われる。この
知覚における次元の差異は、都市という空間の危
機として現われる。ヴァーチャルな空間一リア
ル・タイムによる現実の空間一持続的な空間の支
配は、都市を形作る隣人性を破壊するという形で
都市に反映され、(ドゥボールのスペクタクルの
概念と似た)「公共イメージ」が、政治的なもの
を担っていた公共空間よりも優勢になることを意
味している。ヴァーチャルな空間一リアル・タイ
ムのパースペクティブはまた、人類が戦争を〈見
る〉ようになった湾岸戦争以降の時代の環境でも
ある。そこでは、単一のパースペクティブが、テ
レビ視聴者のそれのみならず、それが映さない現
実空間の他のあらゆるパースペクティブをも支配
する。冷戦以後のアメリカの軍事力の行使は、こ
のパースペクティブの「専制」と切り離すことが
できない。単一のパースペクティブは見えるもの
と見えないものを自動的に選別する。現実の空間
へのヴィリリオの絶えざる参照は、失われた過去
への郷愁ではなく、まさにこのような現状を告発
するための批判的な距離を確保する試みなのであ
る。そして、このような距離の創出こそが他のパ
ースペクティブを生み出し、別の未来のパースペ
クティブを切り開くための条件なのである。
冒頭で述べたように、ヴィリリオの思想の位置
づけは難しい。しかし、メルロ=ポンティの現象
学を彼固有の仕方で継承・発展させ、速度の概念
をキーワードに、技術や空間、戦争といった主題
を横断していくヴィリリオの思索には、社会的な
領野に開かれた〈哲学する〉という営みが見出し
得るのではないだろうか。それこそが、「折り重
なる空間」と題した本論文が示したかったことの
一つである。もちろん、この論文は一つの試論で
あって、彼の思想の全てを描き出したわけではな
い。ヴィリリオの思想と結びつく多くの思想的影
響関係も手つかずのまま残されている。「建築原
理」を組織していたヴィリリオの都市・空間論と、
彼とほぼ同時期に都市・空間の哲学を開始したア
ンリ・ルフェーヴルとの関係。冷戦下に、ヴィリ
リオが展開した戦争論とクラウゼヴィッツの戦争
論や、ヴィリリオの盟友でもあったドゥルーズと
ガタリとの理論的関係。そして、ヴィリリオとキ
リスト教、あるいはキリスト教左派との関係、こ
こでは最も彼に親しい技術の主題に取り組んでい
たジャック・エリュールの思想との関係が考察さ
れなければならないだろう。そのような関係の網
の目を解きほぐすことによって、フランス思想史
のまだ明かされていない一側面が浮かび上がって
くるように思われる。
注
1 日本で、ヴィリリオの思想を研究した単独の著作として、和田(2004)がある。英語圏では、Redhead, S.
(2004)及び、James,1.(2007)がある。前者は、カルチュラル・スタディーズの観点から、後者は現象学の観
224 平田 周
2
3
4
5
6
7
80∂
10
11
12
13
14
点から、それぞれアプローチしている。2002年の1月の『現代思想』では「ヴィリリオ 戦争の変容と政治」
と題された特集が組まれた。その他のヴィリリオについての論文は、参照文献(4)を参照。
ベルナール・スティグレールは、ジャック・デリダとの対談のなかで、ヴィリリオの技術論が、「スクリーンと
活字の間の対立」に沿って展開していると述べている。しかし、このような現前と表象の対立において、ヴィリ
リオの思想を捉えるならば、後に本論が論じる、「知覚の場」とそこから生じる「パL-一・iスペクティブ」の問題が
抜け落ちでしまうだろう。ヴィリリオの思想の軸となっているのは、現実の空間とリアル・タイムという空間の
差異・対立であり、このように捉えるならば、彼の思想は、スティグレールとデリダの二人が「記憶の証書
地政とテレテクノロジー」と題された対話のパートで語っている事柄と、共通する部分があるのではないだろう
か (Derrida+Stiegler 1996【2005])。
以上のヴィリリオの伝記的情報は、参照文献で挙げた対談集やVirilio(1975/1991,213)所収の「バイオグラフ
ィー」などを主に参照して作成した。ヴィリリオの著作自体には、副題が付されていないものが多く存在するが、
『バンカー・アルケオロジー』に収められているこのバイオグラフィーには、1991年までに出版されたヴィリリ
オの著作に副題が付けられている(この副題は、ヴィリリオの著作のタイトルよりも、内容を明らかにしてくれ
ているように思われるので、文献一覧において、副題が原著作に付されていない著作にも副題を書き加えておく)。
田中純は、ドイッ表現主義建築の代表的な作品であるエーリッヒ・メンデルスゾーンのアインシュタイン塔を取
り巻く様々な歴史を記述する際に、ヴィリリオの『バンカー・アルケオロジー』に触れている。その中で、田中
(1995、136)は、バンカーの「大地の非物質化」という特徴と絶対戦争の現実化の重なり合いについてのヴィリ
リオの叙述が、カールシュミットの戦争論における、大地のノモスの死と繊滅戦争の出現を念頭に置いたもので
はないかと示唆している。
フィリップ・プティとの対談の中で次のようにヴィリリオは述べている。「権力とはいつも、伝令者や輸送手段
や通信手段によって、領土を管理する力のことなのです」(Virilio+Petit 1996[1997],15[7】)。
ヴィリリオ自身の二つの空間の組織化の原理をより厳密に検討するためには、法の形成や経済的なプロセスを吟
味しなければならないが、ここでは、その余裕はない。その作業の前提としてBensald(1997)を挙げておきた
い。実際彼は、自らの著作でヴィリリオの著作を参照している。
プチ・ロベールによれば、v6hiculeは、運搬する(transporter)を意味するラテン語vehereの名詞形、 vehicu-
1umを語源として持ち、16世紀頃から用いられるようになった。この言葉は、「ある場所から他の場所へと、伝
達すること(transmettre)や通過させるのに役立つもの」、あるいは「運ぶ=担うこと(porter)やコミュニケ
ートすることに役立つもの」と定義されている。用例としては、当時、「光を媒介=運搬するもの(v6hicUle)
として考えられていたエーテル」といったようなものがある。このような原義から、メルロ=ポンティの「媒
質」やヴィリリオの「乗り物」とった言葉の用法は生じる。
「動かない乗り物」についての議i論は、Virilio(1990【2003])の第二章を参照。
乗り物と知覚の関係を扱った著作として、Schivelbusch(1977[1982])がある。彼は、この著作で、鉄道の速度
が生み出す「パノラマ的眺望」を記述している。
自然のエコロジーに留まらず、複数のエコロジーを思考する著作として、Guattari(1989[2008])を参照。この
著作は、ヴィリリオが編纂する叢書「危機=批判の空間(respace critique)」に収められている。
「持続とは過去が未来を蕃ってすすみながらふくらんでゆく連続的な進展である」(Bergson 1907/1941[1979】,4
[25])。
「遠隔現前の問題は、身体の配置、位置づけを限定できないものにします。ヴァーチャル・リアリティーの問題
のすべては、本質的に言って、ここで、今を否定すること、「今」のために「ここ」を否定することにあります。
すでに言いましたが、「ここ」はもはやありません。すべてが「今」なのです」(Vir且io+Petit 1996[1997】,44
[47])。
「本国の集住地の脱産業化やオートメーションの進歩、労働力の衰退、そして、テクノロジーによる瞬間的でイ
ンタラクティブな処理能力は、いまや、国民資本主義の〈外延性〉を顧みずに多国籍的な独占の〈内包性[強
度]〉を特権化する」(Virilio 1984b,157-158)。
この近接した空間(現実の空間)と遠く離れた空間(ヴァーチャルな空間)との共存は、いまだ「遅れた時間」
である飛行機による空からの平面的な偵察から、「リアル・タイム」でのレーダーを通じたインターフェイスの
知覚への移行によって実現する。この移行は、1940年の英国空軍が使用した電磁波利用のレーダーを搭載した飛
行機において、極めて象徴的な形で生じていると、ヴィリリオは述べている。つまり、「ヘッドを挙げたポジシ
ョンでは、透明な大気と肉眼による視界が、ヘッドを下げたポジションでは、透明なエーテルとテレビが、パイ
ロットの視線を捉えるというわけだ」(Virilio 1984a/1991[1999],131-132[245-246】)。
折り重なる空間 ポール・ヴィリリオの思想についての一試論 225
15 この二つの結びつきについて、ヴィリリオは、1996年の対談のなかで、次のような発言をしている。「ソマリア
と旧ユーゴスラビア以来、私たちは、人道主義的なものと言えども軍事的なものに結びついているということを
知りました。〈中略〉世界化された社会においては、世界戦争はなんらかの世界警察を生み出します。軍事力は
警察力になります。今後は、あらゆる軍隊が世界の憲兵になるでしょう」(Virilio+Petit 1996[1997],97-98
[120P。
16人道の名の下で行われる戦争を問題にするならば、その準拠となる人権の概念を巡る言説が検討されなければな
らない。人権を道具としてではなく、政治的な緊張関係を孕んだものとして考える議論として、Lefort(1981/
1994,45-83.)及びBalibar(1992,238-266)を参照。
17 ヴィリリオは、この論点を、『ペテンの戦略』の出版直後にジョン・アーミテージと行われた「コソヴォ戦争は
起きた」という対談でも強調している(Virilio 2001,167-197)。
18 ヴィリリオは、なぜ、「テロリズム」を巡る言説が、グローバルな「知覚の領野」と結びつくことになったかの
分析を行っていない。9・11以後の世界の現象を切り取る「テロリズム」という言葉の〈世界化〉と世界秩序へ
のその効果についての検討がなされなければならない。この問題を検討したものとして、西谷(2002/2006)を
参照。
19 ヴィリリオは、最近の紛争が、かつての戦争と異なり、死傷者の80パーセントが一般市民に達しているというこ
とを指摘しながら、この「強迫観念」を示すものとして、イスラエルとパレスチナ双方の主張を取り上げている。
「〈われわれが戦っているのは無実の一般市民ではなくテロリストであるということを忘れてはならない〉。」(イ
スラエルのヨセブ・パリツキー国家基盤大臣の言葉)。このテロリストに一般市民が含まれていることは、容易
に想像がつくことである。そして、「彼らはわれわれの子供たちを殺す。彼らの子供たちが殺される。もはや被
害の及ばぬ場所はない。もはや一般市民も個人も被害をまぬがれない。〈これは開かれた戦争であり、限界はな
く、タブーはない〉」(パレスチナのイスラム原理主義知識人ガジ・アハメッドの言葉)。これらの強迫観念を指
して、ヴィリリオは、「テロリズムと反テロリズムの戦争」を「目的なき戦争」だと述べている。
20 この点については、以下のドキュメンタリーを参照。アレックス・ギブニー監督「民主主義「米国・闇へ」」
(NHK、2008年1月2日放送)。おりしも、『パニック都市』の出版された2004年に、イラクのアブクレイブ収容
所での抑留者に対する拷問の実態が明るみに出された。このドキュメンタリーでは、アブクレイブ収容所事件の
発覚後においても、アメリカの民意の35パーセントがアメリカ軍の拷問を用いた「テロリズムとの戦い」を支持
したことを伝えている。
21「事実として、格言の言うとおり、「ヒステリー[強迫神経症]とは〈時間〉の敵である」のだとすれば、ループ
化された恐怖のリアル・タイムはまさしく「ヒステリー」的なものである。またそれは経済的、政治的、そして、
戦略的なグローバリゼーションの時間である。反省の時間は乗り越えられ、条件反射の時間こそが巨大なテロリ
ズムの今日的問題になっているのだ」(ibid.,60[65])。
22 この点に関して付け加えておくならば、「9・11」の被害者の遺族たちが、この悲惨を直接的に体験した人々こそ
が、アメリカが行う戦争の口実や「人質」になることを拒むことによって、「感情民主主義」と戦争との結びつ
きとその現実に対して、最も根本的な反省と異議申し立てを行ってきた人々だったことを忘れるべきではないだ
ろう。2001年と2003年の反戦運動もまた同様に。
参照文献一覧
※ 本稿における外国語文献の引用文は原則的に訳書がある場合にはそれを参照した上で訳出している。先学の蓄積
に感謝したい。
一、ポール・ヴィリリオの著作
(1)単行本
(1975/1991)Bzenんer arche’otogie:窃μ(》θszeγ膓εsPαcθmieitαireθτ↓γo]ρ6θηde tα Secon(ZθGzeθTTe mon(Ziαle, Paris:CCI.
[原著副題:第二次世界大戦のヨーロッパの軍事的空間についての研究]
(1976/1993)L抗s6cμ勿Zε伽僻権oτγθ:θ85α乞sμγ1αg60poZ仇4μθcoMθ卿oγα碗θ, Paris:Galil6e.[原著副題:現代の
地政学についての試論]
(1977)vitesse et poLitaqzee : essai dθ dromologie, Paris:Galil6e. ==(2001)市田良彦訳『速度と政治 地政学から
時政学へ[原著副題:走行学試論]』平凡社
226 平田 周
(1978)Defenoe popzelaire et tzLttes e’cologieqzLes, Paris:Galil6e.=(2007)河村一郎・澤里岳史訳『民衆防衛とエコロ
ジー闘争』月曜社
(1980/1989)Esthe’thiqzee de 1α dispαrition : essαi szer le ci7zgnzαtisme, Paris:Galil6e.[原著副題:運動学試論]
(1984a/1991)G2Lθrre et cinema: logistiqzee de 1αpθrcθption, Paris:Edition de 1’Etoile.=(1999)石井直志+千葉文夫
訳『戦争と映画 知覚の兵砧術』平凡社(1984b)L ’espαse critiqzLe :esscti szer 1 ’zeTbαniswze et les nozLvetLes technologies, Paris:Christian Bourgois.[原著副
題:都市計画とニュー・テクノロジー]
(1984c)L ’hort20n negαtzf・essai de dromoscopte, Paris:Galil6e.=(2003)丸岡高広訳『ネガティブ・ホライズン
速度と知覚の変容』[原著副題:走行光学試論]産業図書
(1988)Lα mαchine de vision: essai szLr tθs nozevellθs techniqzLes de repre’sentation, Paris:Gali16e.[原著副題:表象
の新しい技法についての試論]
(1990)L’i物ertie polαire: essαi szer tθ contoγ6tθ d ’environnement, Paris:Christian Bourgois.=(2003)土屋進訳『瞬
間の君臨 リアルタイム世界の構造と人間社会の行方[原著副題:環境コントロール]』新評論
(1991)L ’e’crctn du desθrt: chγoniqzees de gzeerre, Paris:Gali16e.[原著副題:戦争のクロニクル]
(1993)L ’art dzL motezer, Paris:Gali16e.==(2003)土屋進訳『情報エネルギー化社会 現実空間の解体と速度が作
り出す空間』新評論
(1995)Lαvitθssθde tαtiberαtion, Paris:Gali16e.
(1996)Un 1)αysαge d’e’venements, Paris:Galil6e.
(1998)Lα bombe infomaαtipzee, Paris:Galil6e.=(1999)丸岡高広訳『情報化爆弾』産業図書
(1999)Strategte de 1α dθception, Paris:Galil6e.=(2000)河村一郎訳『幻滅への戦略』青土社
(2002)Ce qzei arrive, Paris:Gali16e.=(2003)青山勝・多賀健太郎訳『自殺へ向かう世界』NTT出版
(2004)Lα ville pαniqzLe : AittezeTs commenoe ici, Paris:Gali16e.=(2007)竹内孝宏訳『パニック都市 メトロポ
リティックスとテロリズム[原著副題:よそはここで始まる]』平凡社
(2005a)LhcoZdθ励o吻τηθZ, Paris:Galil6e.(2006)小林正巳訳『アクシデント 事故と文明』青土社
(2005b)L ’Artδぽ)eγ■te de v2Le, Paris:Gali16e.
(2007)Z/〔功初θγrsτ絃dze ddsαstTe, Paris:Gali16e.
(2)シルヴェール・ロトランジェとの対談集
Virilio, P.+Rotoringer, S.(1983/1997)PzcrθWar, New York:Semiotext(e).=
ピー・ユー
+ (2002)Crel)zLsczetαrdα?vn, New York:Semiotext(e).
+ (2005)Theαcci(Zθnt()f art, New York:Semiotext(e).
(1987)細川周平訳『純粋戦争』ユー・
(3)その他の共著、対談集
Virilio, P+石田和男(1993)「現代戦争論序説 カンボジア、湾岸、旧ユーゴ」『現代思想』:20-29
+Ewald, F.(1995)“Paul Virilio, Vitesse, guerre et Vid60”吻α⑭θ励θγατγθn㎜6ro 337, Novembre 1995:
96-103.
+Petit, F.(1996)Cybemaondθ, tα politiquθ du ptrθ, Paris:Textuel.ニ(1998)本間邦雄訳『電脳世界』産業
図書 +Parent, C.(1996)A7℃hitectzeγe princi oθ1966 und 1996, Les E ditions de L’㎞pr㎞eur.
+Brausch, M.(1997)V()yαge el ’h乞ver, Paris:Parentheses.
(2001) ViTilio live, edited by Jhon Armitage, London:Sage pubUcations.
(2002)「予測が的中して残念だ」中山元訳『発言 米同時多発テロと23人の思想家たち』朝日出版社:
26-33
+Baj, E.(2003)Discozeγs szLr l ’ho7・γezer dθ1 ’αrt, Lyon:AteHer de creation hbertaire.
(4)ヴィリリオに関する論文・著作
Der Derian, J.(1992)Antidmplomctcg : Spiθs, TerroT, Speed,αnel War, Oxford:Blackwell.(この著作でとりわけ、ヴ
ィリリオが論じられた第六章「国際関係の(時)空間」は、邦訳されている。『現代思想』第30巻第1号:
156-166)
Luke, T.+OTuathai1,G.(2000)“Thinking Geopolitical Space The spatiality of war, speed and vision in the work of
折り重なる空間 ポール・ヴィリリオの思想についての一試論 227
Paul Virilio”Thinんing Spαcθ, edit by Crang, M.+Thrift, N., London and New York:Routledge:360-379.
Arrnitage, J., ed.(2000)Pαul砺γ祝乞o:From moder z乞sime to hyX)θmaodθwaismαnd Bθyond, London:Sage.
Redhead, S.(2004)Pαzet協γ仇o:Thθo r乞st foT Accθlerαted CzelzLtzere, Tronto:University of Toronto Press.
James,1.(2007)PαzLl Virilio, London and New York:Routledge.
田中純(1995)「血のデュナーミク」『残像のなかの建築:モダニズムの〈終わり〉に』未来社:122-143
土佐弘之(2003)「まなざし(視覚/身体)のグローバル・ポリティックス 圧縮された時空間の歪みとバロック的
戦争機i械」『安全保障という逆説』青土社:179-215
松葉祥一(2002)「戦争・速度・民主主義」『現代思想』第30巻第1号:212-221
和田伸一郎(2004)『存在論的メディア論 ハイデガーとヴィリリオ』新曜社
二、その他参照文献
Balibar, E.(1992)“Qu’est-ce qu’une politique des droits”Les fTontiθres de eαd6ηzocγ⑳α庇θ, Paris:La D6couverte:
238-266.
Bensaid, D.(1997)Lθ pαri meZαncotiqzee, Paris:Fayard.
Bergson, H.(1907/1941)L’吻o励乞oηcMα励cθ, Paris:Presses Universitaires de France.=(1979)真方敬道訳『創造的
進化』岩波書店
Clastre, P.(1997/2005)Arche’ologiθ dθ eα viotθnce, Paris:Editions de raube.=(2003)毬藻充訳『暴力の考古学』現
代企画室
Deleuze, G.(1990/2003)PozerpαTlers, Paris:Minuit.=(1992)宮林寛訳『記号と事件』河出書房新社
Derrida, J.+Stiegler, B(1996)君仇ogγ仰れθs dθ1α協吻旭oη, Paris:Gali16e-INA.=(2005)原宏之『テレビのエコー
グラフィー デリダ〈哲学〉を語る』NTT出版株式会社
Debord, G.(1967/1992)LαSoc協6 dμ3pθ伽dθ, Paris:Gallimard.=(2003)木下誠訳『スペクタクルの社会』筑摩書
房
Duvignaud, J.(1977)L乞ezea;θt non liθur, Paris:Gali16e.
Foucault, M(1975)Suweilter et punir, Paris:Gallimard.=(1977)田村傲訳『監獄の誕生』新潮社
Guattari, F.(1989)Lθ8励08θco/og乞θs, Paris:Galil6e.=(2008)杉村昌昭訳『三つのエコロジー』平凡社ライブラリー
Lefort, C.(1981/1994)“Droits de 1’horrume et politique”Lηηuθ吻η』oc卿μθ, Paris:Fayard:45-83.
Merleau-Ponty, M.(1945)Phe’nomelogie dθ tα pθrception, Paris:Gallimard.=(1967)竹内芳郎・小木貞孝訳『知覚
の現象学1』みすず書房
Schivelbusch, W(1977)Geschichte deγEisenbαhnrei8θ, ZzeT lndzestTictlis乞eTzLng von Rαμ祝und 2eZt伽19.
JahrhzeneleTt, Hanser Verlag.=(1982)加藤二郎訳『鉄道旅行の歴史 19世紀における空間と時間の工業化』法
政大学出版局
小崎哲哉「コソボ戦争で引き裂かれた欧米の知識人たち」『論座』1999年9月号、p158-167
金森修(2003)『ベルクソン』NHK出版
高木徹(2002/2005)『戦争広告代理店 情報操作とボスニア紛争』講談社
西谷修(2002/2006)『〈テロル〉との戦争』以文社