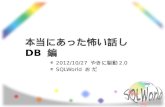Ⅲ 中1ギャップ - tym.ed.jp · - 102 -...
Transcript of Ⅲ 中1ギャップ - tym.ed.jp · - 102 -...
- 101 -
Ⅲ 中1ギャップ
中1ギャップとは...
○ 小学生から中学 1年生になったことがきっかけとなり、学習や生活の変化になじ
めずに不登校となったり、いじめが増加するという現象。ギャップの典型例として、
コミュニケーションの苦手な生徒が小学校時の友人や教師の支えを失う「喪失不安
増大型」、小学校でリーダーとして活躍していた生徒が中学校で自己有用感を感じ
られなくなってしまう「自己発揮機会喪失ストレス蓄積型」があるといわれている。
1 現場から見た最近の気になる傾向と問題点
(1) 子供の様子から
○ 小学校の時に不登校傾向やいじめがあったから、中学校でもそうなるとは限らな
い。また、中学校という環境の変化によって、小学校時に不登校だった児童の状況
が一変するということを期待するのも難しい。
中学校での状況を考えてみると
・ 学習面 ・・・・・・・教科担任制、学習でのつまずき等
・ 人間関係面・・・・・・・友達・親・教師等、人間関係の複雑化
・ 発達段階として・・・・・心身の発達、思春期
・ 取り巻く環境の変化・・・携帯電話・インターネット・メディアの影響
などの状況があり、中1ギャップは、様々なことが複雑に絡み合って起こっている
ように考えられる。
(2) 保護者の様子から
○ 母親自身が家庭での居場所を見失っている場合がある。
・ 不登校等の問題が発生する以前から、家族同士の関係がぎくしゃくしている。
(祖父母とうまくいっていない、父親の協力を得られないなど)
・ 子供に近い存在である母親のコミュニケーション不足。
・ 家族と問題を共有できない、協力してもらえないことへの不満。
・ 母親が自分一人で抱え込んでしまう。母親自身が情緒不安定である。
○ 父親が子育てを放棄している場合がある。
・ 母親は学校や相談機関へ出かけて行くが、父親は仕事が忙しいことを理由に、
子供が抱える問題に向き合わない。(向き合えない)
○ 祖父母が保護者以上に子供の問題に口出しする場合がある。
・ 子供が板挟みになる。保護者の不満のはけ口になり子供の対応への配慮がない。
・ 家庭において、子供の居場所がなくなる。
○ 不登校に関する知識が不足している保護者がいる。
・ 不登校状態の子供に対しては、個に応じた支援が必要であるが、どこかで得た
- 102 -
文面上の知識に頼って、同一の対応に陥ってしまう場合がある。
・ 以前のように、不登校になった原因ばかりを追及し、犯人捜しをする保護者は
少なくなり、無理に登校刺激を与えずにゆっくりと構えて、子供の今を受け入れ
るというかかわり方をする保護者が増えた。
2 中1ギャップに関連する事例
(1) 小学生の児童の様子から
<事例6 特別支援を必要とする児童> (小学6年 女子)
○ 本人の状況
E児は入学当初、よく泣いていた。他の人と交わろうとせず、一人で過ごすこ
とが多かった。人前で話すときの声が小さく、周りから「もっと大きな声で言っ
て」と言われ泣き出すことがあった。
健康診断の結果、難聴の疑いがあることが分かる。その後検査を受けるために
病院へ行くが、CTスキャンの中に入ることを嫌がり、詳しい検査はできなかっ
た。生活の中で聞き取りにくい音があることは事実であった。
5年生になり、ほとんど話すことはないが、人の話は目を見てしっかりと聞こ
うとしている。聞き取りにくいため、相手の表情や口の動きを見ているのかもし
れない。 聞いたことはきちんと実行することができる。朝のスピーチでは、な
かなか最初の言葉が出てこない。その後たどたどしく小さな声で話した。その間
も泣いていた。他の子供たちはE児のそんな様子をよく理解しているのか、黙っ
て聞いていた。
体育の時間に100m走をした。スタートしてからしばらくすると泣き出して
しまい、顔をくしゃくしゃにしながら走っていた。タイムは28秒。最後まで止
まらずに走り続けたことをほめた。また、運動機能の未発達が目立つ。片足けん
けんやスキップ、平均台の上で立つといった動きができなかった。その他にもあ
るのではないかと思われる。
休み時間には、特定の子供と遊ぶということはなく、一人でいたり、グループ
の周辺にいたりする。他の子供が楽しく遊んでいる様子を見て、本人も楽しそう
な笑顔を浮かべることもある。
○ 担任の支援・援助
左耳が難聴ということを考慮して、座席を教室の左側にした。このような座席
の配慮をするとともに話をするときも、できるだけ目を見て反応を確かめながら
話すようにした。話の内容を理解しているか、ある程度分かるようになってきた。
町別児童会の話をしているときも「どの教室に行けばよいか分かりますか」とい
う問いかけに表情が一瞬曇ったように思え、後で確かめたところ分からなかった
とのことである。
○ 友達とのかかわり
5年生の3学期から何人かの女子のグループで一緒に行動することが多くなっ
- 103 -
た。「E(名前)」と呼ばれ楽しそうに話をしたり、遊んだりする姿が見られた。
放課後も一緒に遊ぶことがある。しかし、自分が相手の家に行くことよりも、誰
かが本人の家に来るということが多い。
友達の蛍光ペンを勝手に持っていき、自分のものとして使っていたことが分か
る。どうして、そんなことをしたのか問いただしたところ、見ているうちに欲し
くなったと言う。自分の気持ちを抑えることができなかったようだ。人のものに
手を出すのはよくないと言って聞かせた。
6年生ではクラス替えもなく、5年生のときに仲良くなった友達と一緒にいる
ことが多い。仲良しグループ4人で交換ノートを始める。最初は前向きな内容の
ものであったが、だんだんと友達や級友の悪口を書くようになる。(本人だけで
はない)そのことがクラスの中でも噂になる。本人たちを呼んで話を聞いてみる
と、噂の内容は本当のことであると認める。悪口を書かれた方の気持ちを考えた
り、交換ノートをする意味について考えたりすることで再発しないように指導し
たが、こちらが話をしている最中もどこか焦点の定まらない様子であった。本当
に心に響いたのか心配である。
《考察》
コミュニケーションをうまくとることができない要因として、難聴であること
が大きいように思われる。そのため、本人が話している内容を聞き取りやすいよ
うに教室の座席を工夫することが必要である。また、大事な事柄はしっかりと目
を見て理解の状況をつぶさにとらえることが大事であると感じる。さらには、そ
のようなE児を取り巻く環境として、友達の存在が大きく影響するものと考える。
ただ、これまであまり他と関係を築くことができなかったE児が他の意見に流さ
れてしまい、自分を見失ってしまうことも懸念される。
このように、支援の必要な児童にとって環境は非常に大切であるといえる。
中学校入学という大きな環境の変化に適切に対応するためにも、小中の連絡を密
にし、子供を取り巻く環境や周囲の理解を求めていかなければならない。
<事例7 メタ認知力特別支援を必要とする児童> (小学6年 女子)
○ 本人の状況
F児は幼少期から家庭的に不安定なこともあり、人とのコミュニケーションを
うまく図れない。学年が上がるにつれ、少しずつかかわりが上手になってきてい
るが、同学年の児童から見ると、なぜそのような行動をするのか理解できない面
がある。例えば、F児はよく友達に嫌な思いをさせているのだが、自分では気づ
いていない。
そんな時には、個別に話をし、どうすればよかったのか振り返らせるようにし
ている。
- 104 -
○ 指導の実際
<例1> ろうかですれ違うとき大きくよけるF児 T:教師、C:児童
T::○○ちゃんが、嫌な思いをしているのは知ってる?
C:(首を横にふる)
T:○○ちゃんがEちゃんに無視されたっていってるよ。
C:無視してない。
T:先生も見てたんだけど、さっき廊下ですれ違ったとき、よけたでしょう。
どうして?
C:・・・・・
T:まず、自分が相手をよけたかどうかは分かる。
C:よけてない。
T:Fさんはよけてないんだね。でも、この前、先生が歩いてきたときにもあ
ったんだけど、廊下で会ったら大きくよけることがあるよね。自分のやっ
てること分かる?
C:(首を横に振る)
T:そうか、よけているかどうかわからないんだね。じゃあ先生がやってみる
ね。
<演じてみる>こんな感じだよ。どう?分かった?
T:これだと相手はよけられているって感じるんだよ。どうしてよけたの?
C:ぶつかるのいやだから。
T:お友達は、そのFちゃんの態度を無視されたって受け止めているんだよ。
大きくよけると避けられているような気がするんだよ。分かる?
C:(うなずく)じゃあ、あやまってくる。
<例2> 親切に鉛筆をひろってくれた子に「ありがとう」も言わず、さ
っと取り上げたり、今開かなければいけない教科書のページを教
えてもらったのに冷たい態度をとったりしたF児
T:友達はFさんに親切にしてくれたんだよ。なのに、その態度はひどいよ
ね。わかる?
C:(うんうんとうなずきながら聞く)
T:どうしてそういう態度をとったの。
C:どうしたらいいかわからんもん。
T:わからんかったのね。じゃみんなに聞いてみようよ。
<クラスのみんなにこの問題を投げかけてみた。>
T:Fさんは、人に親切にしてもらったのに、ひどい態度をとってしまったの。
でも、どうしていいか分からんかったんだって。みんなどうしたらいいか
教えてあげて。
- 105 -
c:「ふん」っていう態度とるのはだめだと思う。
c:拾ってもらったら、「拾ってくれてありがとう。」って言えばいい。
c:どうすればいいかわからんかったら、相手の言うこと聞いて、なんか言わ
れたら、逆に「じゃあ、どうすればいいが。」って聞き返せばいい。
T:じゃあみんな、変だな、嫌だなと思う態度があったら教えてあげてね。
《考察》
F児は、本当に自分のしたことが相手に嫌な思いをさせているとは思っていな
いようである。しかし、教師の話は素直に聞き、話せば理解し、行動に表そうと
して努力している。クラスの児童は、F児とは長いつき合いだということもあり
F児の言動をそのまま受け止めていて疎外することはない。そういう土壌があれ
ば、クラス全体に問題を投げかけることで解決を図ることも考えられる。
しかし、中学校に入学すれば、様々な小学校から児童が入学してくるので、簡
単には理解してもらえない環境になると考えられる。そのためにも小学校ではF
児の言動を見守り、集団生活をする上で不適切であると感じたときには、適切に
丁寧に具体的に指導していくことを積み重ねていくことで、社会性が身に付きコ
ミニュケーション能力が高まっていくのではないかと考えている。
(2) 保護者への支援と関係機関との連携
<事例8 親の愛情を十分に受けずに育った生徒> (中学1年 女子)
○ 幼少期の影響
幼少期に親の愛情を十分に受けずに育つと、発達課題を十分にクリアできてい
ないことが考えられる。こうした場合、小学校高学年になってから親(または身
近な人)の関心を得るために不適応行動を起こすことがある。その際、親(保護
者)は目の前の現象だけをみて子供を否定的にとらえがちである。そのため、子
供に対して支配的な言動が増え、子供は表面上は従っているようにみえて、見え
ないところで反社会的な行動をとるケースがある。行動を起こす子供に対する指
導とあわせて保護者に対するケアが必要となる。
○ 保護者への支援
中学校へ進んで反社会的な行動を示したケースでは、幼少時に両親がいなくな
るという特殊性はあるものの、保護者への支援が必要なケースである。この場合、
自分自身が子育てに失敗したと感じている祖母が、今度は 孫のことで悩んでい
た。孫のちょっとした行動や言動にあれこれと指示を与えることが多く、子供の
自己決定の場を少なくしていたと考えられる。高学年になって反抗的な態度や生
活習慣の乱れ、不登校傾向が出てきた時に初めてこれまでの子育てについて考え
ることができた。
- 106 -
○ 家庭内での関係の確立
幼少時に足りなかったものを今改めて求めていることを受け止めてやることの
大切さを話すとともに、これまでがんばってきた祖父母の姿を認め、励ますこと
に力を入れた。こうしたことによって家庭内では少しずつ落ち着きを取り戻しな
がら小学校を卒業したが、中学校で新しい環境になったことや自分自身の体と心
の成長のアンバランスから不安定になっていったのではないか。中学校では保護
者である祖父母と緊密に連絡を取っていたが、小学校のときのように素直に自分
の行動を振り返ることができなくなっていた。そのため、祖母にはかぜ気味で休
むと言っておきながら、実際には住居侵入を繰り返すといった行動に走っていた。
《考察》
今回のケースでは5年生の段階で不登校傾向が見られたときに巡回カウンセラ
ーに本人に対する面接を行ってもらった。その結果、「ボーダー」ではないかと
の所見を受けた。更に6年生の3学期にも不登校に陥り、総合教育センターや心
療内科を紹介したが、アドバイスを祖母自身がすんなりと受け止めることができ
なかった。発達課題を十分にクリアできないまま思春期を迎えてしまったために
起きたともいえる今回のケースでは、学校として担える部分よりも保護者へのサ
ポートを十分に行い、家庭内での関係を確立することが重要であった。また、こ
のケースでは、機関への情報提供が不十分であったことも原因の一つでなかった
かと考えられる。ただ、情報提供に関しては個人の問題としての兼ね合いもあり、
判断が難しいところである。
中学校での問題行動の際は、即座に警察や児童相談所との連携がとられ、スピ
ーディーに対応がなされた。そのため、1学期の早い段階で問題の発見と対応が
なされ、夏休みを迎えることができた。日頃からこうした関係機関と連携がとら
れていることが重要である。
(3) 中学校での不登校傾向の生徒の例
<事例9 相談室登校できない生徒への援助> (中学1年 女子)
○ 相談室の実態
学校内にある相談室は、「教室に戻るための準備の部屋」として位置づけられ
ている。生徒が登校することを促す余り「何をしてもいい部屋」ということにな
らないように、相談室での過ごし方の最低限の約束は必要になる。そもそも、相
談室は、不登校生徒のためだけに設置された部屋ではなく、全校生徒が利用でき
る部屋であり、学校の中にある学習室なので、生徒指導上、相談室の活用につい
てはいろいろな規制が生じるのはやむを得ない。
- 107 -
○ 個に応じた支援
相談室で過ごす他の生徒が学習をしているときに騒いだり、学習はやらず自分
の好きなこと(やれること)だけをしたりして過ごすといった、相談室での約束
を守ることができない生徒はもとより、相談室で過ごす一人一人の生徒の状況に
応じて対応するには、担任や学年担当者、相談室担当者、スクールカウンセラー、
養護教諭などいろいろな立場の多くの教師がかかわることが必要である。また、
教師間の協力のみならず、地域の方や元教育関係者にボランティアとして、相談
室の手伝いをしていただくことも関係生徒とともに担任においても心強い支援と
なっている。生徒に成果を求めない、時間にあわただしく振り回されないボラン
ティアの方々の姿勢や話の内容に、子供たちの心は随分と癒されていると思う。
<事例 10 他者と話をつなげて会話できない生徒>
○ 最近の一般的な中学生の状況
大きな問題を抱えている生徒だけでなく、一般的な中学生に言えることだが、
一対一の会話しかできない。ある生徒が、担任などの教師に自分のことを話す場
合、教師の周りに一緒に集まっているにもかかわらず、相づちを打ったり、話題
に話をつなげる生徒はほとんどいない。最初の生徒とほぼ同じような方向性の話
が続く場合でも、次の生徒はまた一人称の話題を一から始める。その次も同じで
ある。「私も同じようなことがあって、あのね~」といったような仲間意識で話
の輪を広げることがない。小さな話の波紋がたくさんできるだけで、波紋と波紋
が重なり合って大きな波紋へと成長することはまずないようである。
不登校生徒のうち、宿泊や体育大会といった行事に参加できる生徒は、自分と
他者との関係に興味がない生徒であることが多い。その行事の内容にどれだけ自
分が興味があるか、かかわれるのかということのみに関心が向き、参加すること
で周りはどう思うか、事前学習などで参加していないとき、周りの生徒がどれだ
けフォローしてくれているかということには意識が向きにくいようである。
《考察》
中学校では、入学直後、新しい集団における人間関係づくりを目的として構成
的グループ・エンカウンター等のグループワークを4~5時間取り入れている。
また、学級満足度調査(Q-U調査)を年に2度程度実施し、学校生活不満足群
だと考えられる生徒個々への支援方法を対策委員会を開いて検討している。
このように、効果的な実践手法を用いて、生徒の社会性を高め、集団づくりが
よりスムーズに行えるように支援したり、客観的な分析ツールを生かした個に応
じた的確な援助の観点を明確にしたりすることが、小学校から中学校への大きな
環境の変化に対する阻害要因を取り除くことにつながり、少しでも「中1ギャッ
プ」を解消することに役立つものと考えられる。
- 108 -
3 中1ギャップとの関連における考察
(1) 小学校と中学校との連携
① 学校説明会
・ 中学校から前年度の卒業生が小学校に来校し、次年度入学生となる6年生と交
流する会がある。中学校の学習や活動について中学校の生徒自身が説明してくれ
る。小グループに分かれて話をする場もあり、直接気軽に質問に答えてもらえる
雰囲気で、しかも身近な先輩から生の声を聞けるということで、進学への不安が
期待に変わる絶好の機会であると考えられる。
・ 中学校では、体験入学として、校舎見学や模擬授業(主に英語など)体験を行
っている。中学校の学習スタイルや授業のテンポなどが体験でき、入学への不安
が、新たな環境でがんばろうという希望に少し変わったのではないかと考えられ
る。
② 小中連絡会
・ 定期的に小中連携推進会議を実施し、各校の現状や課題について共通理解を図
っている。3月には、小中連絡会を実施し、入学後に必要な支援の方法等につい
て具体的な情報交換を行っている。
この連絡会は、特別支援を要する児童への理解が高まってきたこともあり、最
近は以前より重要に受け止められるようになったと思う。入学後しばらく経って
も、児童を理解する上で分からない点があれば連絡を取り合うことが、以前より
多くなってきている。生活や学習の仕方、大きく言えば校種間の文化の違いによ
るギャップにすぐに適応できない児童にとって、急に中学校で大人扱いされるこ
とは相当なプレッシャーになっているのではないかと考えられる。中学校の生活
を急いで身に付けさせるのではなく、慣らしながら馴染んでいけばよいといった、
小学校とのなめらかな連続が生活面や学習態度面においては必要ではないかと考
える。そのためには、小中の教師間がお互いの現状や児童の様子について情報交
換し、理解しようとする努力が行われることはよいことだと思う。
③ 学校間の差をなくすために
学校間の差とは
中学校は、いろいろな小学校の児童が集まってくる上に、本人の発達課題の達
成度も様々であるし、小学校とは授業の受け方や指導法についても異なっている。
「教科担任制で専門性をより意識した教科内容を行っている中学校」と「学級
担任制で子供の活動の様子に合わせた指導を行っている小学校」というように体
制や指導観にも違いがある。
児童の側においても、中学校生活が始まってしばらく経って、どのように授業
を受け、どのように学習していけばよいのかというようなことが分かってくる児
童と分からない児童の差は大きい。
・ 中学校と小学校の教師は、子供の成長・発達をもっと長い目で見通し、生活の
- 109 -
力をどのような段階でどの程度身に付けていくのか、それが中学校にどのように
つながるのかなど、児童の実態、教師の仕事、教育活動の実際について理解し合
っている必要があると思う。小・中の差異をなくせばよいのではなく、児童が、
中学校進学を節目として受け止め、今までと違う環境へ主体的に対応していこう
とする気持ちをもてるように、教師側が児童の発達を意識し、実際の様子から判
断して、実態に合わせた指導をしていけばよいのではないか。
・ 不登校傾向のある生徒(理想と現実とのギャップがある子供の場合)について、
小学校から連絡された内容と照らし合わせて、入学当初の学級の仕事分担や班編
成を考えることは大切である。
しかし、それでも目立つ仕事や役割をやりたいと自分から進んで挙手し立候補
したがる。しかし、最後までできなかったり、止めたいといって泣いたりして、
周りの生徒との関係が崩れることがある。登校できている生徒だと、時間と共に、
自分の力量や周りの生徒との関係がだんだんとわかりはじめ、トラブルも減るが、
不登校生徒の場合、その経験が少ないため、不成功経験だけが残ることが多い。
中学校では、自治性を養うために委員などの選出には時間をかける。
「どういう学年(学級、学校)にしたいか」を年度当初だけでなく、頻繁に生徒
自身が考える場を設ける。「どういった人物に委員会などでがんばってほしいか」
というリーダーの人物像をイメージさせる。その後推薦や立候補で具体的な人物
を考えていく、という手順である。その都度、学年生徒会だよりや学年生徒会掲
示板を用いて生徒の思いを伝えていく。自分の適性を見つめる場になるし、リー
ダーをみんなで支えていこうという雰囲気にもなる。
ただし、リーダーとフォロアーは場合によって適材適所で入れ替わっていくこ
とも生徒には知らせる(納得させる)必要はある。
このシステムの移行が漸次行われていくことによって、小学校の時はリーダー
として活躍していたのに中学校では認められないといったことへの不満や自信喪
失が減っていくものと考える。
(2) 地域、関係機関等との連携
① 地域における交流活動
・ 前述の学校説明会以外にも、部活動体験や授業体験等を通して中学校の生活を
体験することによって入学前の不安の軽減に努めている。また、小学校の住民運
動会や地域の文化祭に中学生ボランティアが参加して、小学生との交流を深めて
いる。夏季休業中には、小中合同のクリーン活動を行ったりしている。
・ 子育てが母親だけの負担にならないよう、学校から父親や祖父母へ直接のメッ
セージを送る。学校のこと、子供の学校生活のことを理解してもらい、協力を仰
ぐために、父親や祖父母対象を明記した学校公開、授業参観を開く。
② 関係機関との連携
・ 日常的にカウンセリング指導員が各小学校を巡回し、小学校の現状を把握する
- 110 -
とともに、問題解決に協力している。特に、小中連絡会等で話題に挙がった児童
に対して、カウンセリング指導員が直接小学校へ出向き、本人の様子を見ていく
ことで、その後の指導に生かしている。
・ 教育機関(市教育センター、県総合教育センター教育相談部、教育事務所、生
涯学習室等)や児童相談所、一般の相談機関(心の健康センター、子育てほっと
ライン等)、医療機関を紹介(年度当初に保護者宛のプリント配布)して、相談
機関との協働支援等を実施する。また、民生児童委員や補導委員との協議連絡会
を定期的に実施し、地域の力を借りて問題解決にあたっていく。
(3) 個人の能力として ~スムーズな移行に向けて身に付けておきたい能力~
生活面では
① 主体的に学習に取り組む態度を養う。
・ 家庭学習等の習慣を身に付け、学力の落ち込みを防ぐ。
② 規則正しい生活リズムを確立する。
・ 食事や睡眠時間の乱れを解消し、基本的生活習慣を身に付ける。
③ 家族の一員としての自覚を高める。
・ 家庭内での自分の立場を考え、役割を果たす。
情緒面では
① 困難を乗り越えていこうとする心の強さをもつ。
・ 逃避しない。他に打ち込めるものを見つける。
・ ストレスを溜め込まずに発散する方法を知る。
② 自立した思考をもつ。
・ 的確な自己判断がくだせる。保護者への依存からの脱却を図る。
③ 自己肯定感を高める。
・ 自分を大切にし、周りも大切にしようとする心を育てる。
認知面では
① 悩みを抱えたままにせず、相談する勇気をもつ。
・ 自分の思いを正しく他者に伝える力を培う。
② フォーマルな集団になった場合でも、協力しあう力をもつ。
・ 仲良し集団ではなくても、仲間を尊重し、助け合う。
環境面では
① 悩みや困りごとを打ち明けやすい環境を整備する。
・ 信頼関係の構築及び定期的な教育相談や悩みアンケートの実施等
② 学校組織を生かしたチーム援助の体制を強化する。
・ さまざまな活動場面における情報収集に努め、援助の方策を共通理解する。
- 111 -
☆ 研究員からの提言及び課題~協議からの話題より
話題1: 中1ギャップをどうとらえたらいいのかな
中学校では、遅刻、孤立傾向と同時に、体調不調を訴えるなどして、
不登校傾向に陥ることがあるんじゃないかと思ってます。そのような
場合は、まず家庭と連携を取り、本人のいないところで連絡を取り合
って、状況を共有することが大切だと思いますね。
不登校傾向の情報は小学校へも連絡を取り、情報を
もらいますが、教師が子供を見る目にも小学校と中学
校の教師にはギャップがあるのではないでしょうか。
どのくらいかかわったら、教師が生徒の心のよりどころになれるの
でしょうか。教師の見る目がちがうのではなく、担任の裁量で上手に
子供の実態に合わせて指導していたのを、小学校を離れて入学すると
一人状態になるのが生徒にとってギャップなのではないでしょうか。
不登校の要因を把握するのは難しいですね。友達とう
まくいかない。勉強、部活の人間関係、環境への不適応
・・・。いずれにしても学校では、壁を取り除くように
動いています。
中学校と小学校の文化の違いのようなカルチャーショッ
クは前からあって、そこに現代のいじめや不登校といった
問題が結び付くことで、さらに中1ギャップの問題が複雑
化しているのではないでしょうか。
小学校での不登校は、親の養育態度や基本的な生活習慣の問題
を要因として考えられる場合がありますが、中学校では、担任と
本人のかかわり、体制の違いもあって違う要因も考えられます。
学力の問題はシビアで、自信がなくなる場合が多いんじゃ
ないかな。最近、学習から逃げ出し、自分を認めてくれる先
輩について行く遊び型不登校が増えたとも感じますね。
ただでさえ不安なのに、安心できる友がいないし、親のバック
アップがないとなると、勉強も大きなマイナス要因となってきま
すね。逆に、親のフォローで自信をもたせられる場合もあると思
いますよ。
- 112 -
話題2: 何かいい対策はないかな
中1ギャップだと気づいてから生徒を理解するのではなく、
個人のカルテを作ってそれを幼保・小・中と引き継いでいけば、
何かあったときに対応がしやすいのではないでしょうか。
カルテは個人の情報だから、保護者の承諾もないのに小
学校から中学校へと引き継ぐわけにはいかないという問題
点もあるため、実施は難しいと思います。
誰が中学校でギャップを感じるか分からないので、個人カルテ
といっても全員について記載しなければならないこととなり、特
別支援の個別支援計画のようなわけにはいかないと思いますよ。
中学校入学後に、子供自身が中学校の生活に対し不安に思
っていることをアンケートのような形でとって、生徒指導に
活用したことがあります。それまでは、小中の連絡会で教師
同士が情報交換を行い、教師同士がつながることばかり考え
ていました。
カルテを作ろうと思うと、個人の情報なので慎重な取り扱
いや保護者の理解が必要です。しかし、アンケートなら子供
の生の声が聞けるし、子供も本音が言えます。子供の直接の
声を聞く方法としていいですね。しかも、それなら中学校へ
と引き継ぐことも可能なのではないでしょうか。
6年生の3学期の時期に、アンケートとして書いてもらい、
中学校入学後しばらくたった時期にも書いてもらう。そして、
子供自身の生の声を、中学校の入学期の不安解消に生かしてい
くのはよい方法ではないでしょうか。
中学校に入学すれば、学習形態や生活の違いなどで、誰で
もギャップは感じているはずです。ただつまずくかどうかの
違いだと思います。アンケートは、そのつまずきを早期に発
見し、子供の思いをつかんで指導できる一つのよい方法だと
考えられます。
もちろん、日頃から早期発見・早期支援に全力を尽くすことや
決して見捨てることなく、愛情をもって根気強く生徒にかかわる
ことは大切にしていきたいですね。