7.細胞の情報伝達と物質輸送 - MBL...7.細胞の情報伝達と物質輸送...
Transcript of 7.細胞の情報伝達と物質輸送 - MBL...7.細胞の情報伝達と物質輸送...
7. 細胞の情報伝達と物質輸送生物が個体として存在するために
7-1. 細胞はたがいに影響しあい、さまざまな情報や物質をやりとりする
「細胞間の情報伝達」生物は、光、熱、音、化学物質、磁気など外部環境からの多種多様なシグ
ナルに応答・適応する仕組みを備えています。多細胞生物の体内の細胞は周
りの細胞と細胞外液という環境からのシグナルを受け、それに応答します。
細胞間で情報を交換する方法として下記の 3 種類の方法があります。
1)シグナル伝達物質を受容体で受け取る。
2)お互いの細胞表面分子が結合して細胞を刺激する※ 1。
3) 隣接する細胞を結合させるギャップという構造を利用して物質を伝達す
る※ 2。
シグナル伝達物質
シグナル伝達物質には、ホルモン、局所的化学伝達物質(サイトカイン)、
そして神経伝達物質などがあります。これらは情報を伝える距離に違いがあ
ります。
① ホルモン
内分泌細胞によって、合成・分泌され、血流に乗って全身をめぐり、その
ホルモン受容体を発現する標的細胞に作用します。
② 局所的化学伝達物質
近くの細胞に情報を渡します※ 3。白血球細胞が出すサイトカインなどはす
ぐに分解されたり、細胞に取り込まれるので、1 mm 以下の範囲の細胞にし
か作用できません。
※ 1 上 皮 細胞から神経に分化する細胞は
Delta(デルタ)という膜貫通タンパク質
を表面上に発現し、周りの細胞が神経細
胞に分化するのを妨害します。一方、周
りの細胞は Notch(ノッチ)と呼ばれる
受容体を細胞表面に発現しており、Delta
からのシグナルを受け取ると、神経細胞
にならずに上皮細胞として維持されます。
※ 2 2 つの細胞が十分に接近すると細胞膜を
横断するギャップ結合と呼ばれる細胞間
チャネルができます。タンパク質のような
大きな物質は移動できませんが、分子量
1,000 以下の低分子、たとえば ATP、ア
ミノ酸、あるいは中間代謝物を細胞間で
共有できるようになります。
※ 3 局所的化学伝達物質(サイトカイン)を
分泌した細胞自身が受け取って反応する
場合は、オートクラインと呼び、近傍の
細胞に化学物質が作用する場合は、パラ
クラインと呼びます。がん細胞はオートク
ライン作用によって自身の生存や増殖を
促進することがあります。
77
③ 神経伝達物質
神経の軸索末端から放出されます。神経軸索末端と神経伝達物質の受容体を
持った神経細胞とはシナプス(シナプス間の距離は 20 − 30 nm) という構造
を形成しています。刺激をうけた神経細胞は軸索に沿って電気的刺激を高速で
伝えます。軸索末端に達した電気シグナルは化学シグナルに変換され、細胞外
に放出された神経伝達物質はシナプスを拡散し、次の神経細胞の受容体に結合
します。
また、シグナル伝達物質は、大きさと親水性で二つのグループに分類できま
す。一つ目のグループは、小さくて疎水性が高い分子で、標的細胞の細胞膜を
透過できるグループです。これらの物質は、細胞内に入ると細胞内タンパク質
を直接活性化するか、細胞内受容体タンパク質と結合します。もう一つのグ
ループは、大型で親水性が高い分子で、標的細胞の細胞膜を通過できないグ
ループです。細胞膜上にある受容体(細胞表面受容体)に結合して情報を伝え
ます。
細胞内受容体
疎水性低分子は細胞膜を透過し、細胞内酵素を活性化したり、細胞内受容体
タンパク質に結合します。ステロイドホルモン、甲状腺ホルモンは細胞膜を透
局所的化学伝達物質ホルモン 神経伝達物質
軸索
シナプス
血液
シグナル伝達物質の種類
細胞接触情報伝達物質と受容体 ギャップ結合
細胞間シグナル伝達の方法
78
過し、細胞質あるいは核にある受容体タンパク質と結合します。ホルモンが
結合した受容体は活性化し、核内で転写調節因子として働き、遺伝子の発現
制御を行います。
細胞表面受容体
細胞表面の膜貫通型受容体は、シグナル伝達物質(リガンド)と結合する
と立体構造が変化し、情報を細胞内に伝えることができるようになります。
細胞表面の受容体は大きく 3 つのタイプに分けられます。
① G タンパク質共役型受容体(GPCR)
このタイプは受容体がリガンドを結合すると、細胞内の G タンパク質を活
性化して、その後の反応を引き起こします。G タンパク質にはアデニル酸シ
クラーゼを活性化する Gs タンパク質、不活性化する Gi タンパク質、そして
ホスホリパーゼ C を活性化する Gq タンパク質などがあります。
② 酵素共役型受容体
このタイプは、細胞内ドメインに酵素活性がある受容体です。酵素活性を
もつ別のアダプタータンパク質が結合している場合もあります。受容体がシ
グナル伝達物質を受け取ると酵素部分が活性化して細胞内に情報が伝達され
ます。
③ イオンチャネル共役型受容体
細胞外リガンドが結合すると、チャネルを開放あるいは閉鎖します。神経
系や筋肉細胞などの電気的に興奮する細胞にみられます。
細胞表面受容体に結合する物質は、受容体の活性を阻害したり、促進した
りできるので、細胞表面受容体は創薬の重要な標的です。製薬業界は、特定
の細胞表面受容体に結合し、設定した効果だけを発揮できる低分子物質を探
しています。
いきものコラム 「巨大な神経が研究に役立っているイカとアメフラシ」
軟体動物であるイカやアメフラシは巨大な神経細胞を持っており、神経の活動を記録する実験を簡単に行うことができます。
そのため、神経系の基礎研究で、半世紀以上にわたり、研究材料として使われています。イカの神経細胞は特に軸索が大きく、
アメフラシの神経細胞は細胞体が大きいという特徴があります。
1963 年には、イギリスのアラン・ホジキン教授とアンドリュー・ハクスレー教授が、イカの神経軸索に金属製の電極を用
いて膜電位とその変化を記録して解析した功績によって、ノーベル医学生理学賞を受賞しています。
2000 年には、コロンビア大学のカンデル教授が、アメフラシを用いて脳の高次機能のメカニズムを探る研究を行い、ノー
ベル医学生理学賞を受賞しています。
◁ ホジキンらが実験に用いた
大西洋イカ
◁ アメフラシの一種
アメフラシの名前の由来は、アメ
フラシが海水中で紫色の液をだす
と、それが雨雲がたちこめたよう
に広がるからと言われます。
79
Pick Up from MBL
抗 GPCR 抗体
MBL では、免疫組織染色(IHC)に
使用できる 800 種類以上の GPCR
に対する抗体を販売しています。
詳しくは MBL ライフサイエンスサ
イト(http://ruo.mbl.
co.jp/product/gpcr/)
をご覧ください。
サイトには各抗体の推奨使用濃度や
GPCR についての詳しい解説も掲載
しております。
7-2.外からもらった情報を伝える仕組み
「細胞内の情報伝達」
シグナル伝達物質が、特定の細胞の特定の受容体に特異的に結合すると、細
胞内の他の分子へ次々と伝達されて、最終の標的となる分子に到達します。そ
の結果、標的である酵素が活性化や標的となる遺伝子の発現が誘導が起きま
す。
G タンパク共役型受容体 (GPCR) を介した細胞内シグナル伝達
GPCR は、細胞表面受容体の最大ファミリーでヒトでは 900 種類以上ある
といわれています。また、光、におい、ホルモン、神経伝達物質、局所化学伝
達物質など膨大なシグナルに対する細胞の応答を仲介します。光受容体、嗅覚
受容体、味覚受容体(一部)なども GPCR です。非常に多くの細胞機能に関わっ
ているので、創薬標的になっており、また実際に既存の薬品の多くが GPCR
を介して作用しています。
GPCR は、1 本のポリペプチド鎖が細胞膜を 7 回貫通する構造をしています。
細胞外シグナルが GPCR に結合・作用すると、タンパク質構造が変化し、細
胞質側にある G タンパク質を活性化します。G タンパク質は、α、β、γ の 3
種類のサブユニットからなり、活性化された α サブユニットは結合していた
GDP を GTP と交換します。活性化された G タンパク質はイオンチャネルを
活性化したり、膜に結合している酵素を活性化します。最も多く G タンパク
質の標的となる膜結合タンパク質は、アデニル酸シクラーゼとホスホリパーゼ
GTP GDP
GDP
α βγGTP
α
シグナル分子
GPCR
ホスホリパーゼ C
ホスファチジルイノシトール -4,5- 二リン酸
ジアシルグリセロール(DAG)
小胞体
イノシトール三リン酸
Ca2+チャネル
Ca2+
G タンパク
IP3
IP3
PKC
カルモジュリン
カルモジュリン依存性キナーゼ
GTP GDP
GDP
α βγGTP
α
シグナル分子
GPCR
Gタンパク
転写調節因子 遺伝子発現の活性化
平滑筋の収縮
核
核膜
細胞膜
グリコーゲンの分解
ATP cAMP
アデニル酸シクラーゼ
P
Pホスホリラーゼキナーゼ
ATP ADP
P
グリコゲンホスホリラーゼ
NF-κB
NF-κB
Raf
MEK
MAPK
P
P
P
MAPKP
ERKP
FosP
細胞質
プロテインキナーゼ A
プロテインキナーゼA
プロテインキナーゼC
GPCRを介した細胞内シグナル伝達
80
C で、それぞれが細胞内シグナル分子(二次メッセンジャー)を産生し、シグ
ナルを増幅します。アデニル酸シクラーゼとホスホリパーゼ C はそれぞれ別
の G タンパク質で活性化されます。
アデニル酸シクラーゼのかかわる細胞内シグナル伝達経路
G タンパク質が結合し、活性化したアデニル酸シクラーゼは、二次メッセ
ンジャー分子である環状 AMP(cAMP) を産生します。次に、cAMP は、プロ
テインキナーゼ A(PKA) に結合して活性化し、活性化された PKA は標的タ
ンパク質表面のセリンまたはトレオニン残基を特異的にリン酸化し、そのタン
パク質を活性化させます。また、活性化された PKA は核内に入り、転写調節
因子をリン酸化して標的タンパク質を発現させます。
アデニル酸シクラーゼのかかわる生理機能の例
シグナル分子 生理機能
アドレナリン心拍数増加(心臓 )、グリコーゲン分解(骨格筋)、脂肪の分解
副腎皮質刺激ホルモン コルチゾール分泌(副腎)
ホスホリパーゼ C のかかわる細胞内シグナル伝達経路
G タンパク質が結合し、活性化されたホスホリパーゼ C は、細胞膜中のイ
ノシトールリン脂質から、2 種類の二次メッセンジャー分子、1,4,5- イノシ
トール 3 リン酸(IP3) とジアシルグリセロール(DAG) を作ります。水溶性
の IP3 は、細胞質に拡散し、小胞体の Ca2+ チャネルを開口させ、小胞体内に
貯蔵されていた Ca2+ を細胞内に流出させます。細胞膜に残った DAG は Ca2+
とプロテインキナーゼ C (PKC) ※ 1 を活性化します。活性化された PKC は、
細胞内の様々なタンパク質をリン酸化し、活性化させます。また、Ca2+ は
PKC の活性化だけでなく、様々な反応に関わっています。
ホスホリパーゼ C のかかわる生理機能の例
シグナル分子 生理機能
アセチルコリン アミラーゼ分泌(膵臓 )、平滑筋の収縮
バソプレシン グリコーゲン分解(肝臓)
酵素共役型受容体を介した細胞内シグナル伝達
酵素共役型受容体は、膜貫通タンパク質で、シグナル分子結合部分は細胞膜
の外側にあり、細胞質内ドメインはそれ自身が酵素として働きます。酵素共
役型受容体は、細胞の成長、増殖を調整するシグナル分子に応答するものが
多いので、この受容体を介するシグナル伝達の異常が、がんの発症原因になっ
ています。
※ 1 PKC も PKA と同様セリン残基やトレオ
ニン残基をリン酸化するキナーゼです。
81
酵素共役型受容体のうち最も多いのは、細胞内ドメインが標的タンパク質
のチロシンをリン酸化するチロシンキナーゼとなっているもので、受容体型
チロシンキナーゼ(RTK)といいます。RTK の膜貫通部分は、1 回だけ膜を
貫通しています。シグナル分子が結合すると、受容体が 2 個一緒になってそ
れぞれ相手をリン酸化します。RTK の種類が異なるとシグナルを伝達する細
胞内のタンパク質も異なりますが、ほとんどの RTK によって活性化されるタ
ンパク質に Ras と呼ばれる GTP 結合タンパク質があります。Ras は最後には
MAP キナーゼを活性化し、様々な細胞質内のタンパク質と核内の転写調節因
子を活性化します。
EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor; 上皮成長因子受容体)
EGFR は、細胞の増殖や成長を制御する EGF を認識する、チロシンキナー
ゼ型受容体です。EGFR がリガンドと結合して活性化されると、細胞膜上を移
動し、他の受容体と二量体を形成して活性化し、それぞれがチロシンキナーゼ
として、受容体の細胞内領域にあるチロシン残基をリン酸化します。EGFR の
チロシン残基がリン酸化されると、下流の様々なタンパク質が次々と活性化さ
れてゆき(シグナル伝達)、活性化された MAP キナーゼは、核内に入って転
写因子を活性化し、増殖に関わるタンパク質やアポトーシス※ 1 に抵抗性を与
えるためのタンパク質の合成を促進します。
ATP
EGF
Grb2Sos
EGF 受容体
細胞膜PPPP
PPPP
RasRasGTPGDP
RafP
MEK
MAPK
P
P
遺伝子発現の活性化
ATP ADP
P
転写調節因子
核
核膜細胞質
MAPKP
酵素共役型受容体を介した細胞内シグナル伝達
Pick Up from MBL
がん細胞増殖に関わるシグナル伝達受容体 EGFR 関連診断薬
MEBGEN™ RASKET キット
大腸がん治療における抗体医薬とし
て抗 EGFR 抗体薬が使われていま
す。しかし、シグナル伝達の下流に
ある Ras に変異があり、つねに活
性化した状態になっていると、抗
EGFR 抗体でリガンドである EGF
ファミリーと EGFR の結合を阻害
しても増殖のシグナルを止めること
ができず、薬の効果が期待できませ
ん。患者さんにとって抗 EGFR 抗体
医薬による治療が有効であるかを前
もって確認する診断薬 MEBGEN™
RASKET キットを MBL では開発・
販売しています。国内初のKRAS 及
びNRAS 遺伝子変異を検出するマ
ルチプレックス診断薬です。詳細
は MBL 臨床検査薬サイト(http://
ivd.mbl.co.jp/search/
detail/GS-D0451.html)
をご覧下さい。
※ 1 アポトーシスについては後ほど説明します。(参照;8-1.プログラムされた死「アポトーシス」p.87)
82
7-3.細胞間の物質輸送「膜を介した物質輸送」
イオンチャネル
イオンチャネルは、イオン選択性があり、特定のイオンしか通しません。特
定の刺激によって、構造を変化させ、開閉を切り替えています。チャネルが開
くと、イオンは電気化学的勾配にしたがって、一過的に膜を通過します。チャ
ネルの開閉は、固有のリガンドの結合、機械刺激、膜内外の電位差(膜電位)
によって制御されています。
① 膜電位依存性イオンチャネル
膜電位は、特定のイオンに対する膜の透過性によって、調節されています。
動物細胞では、Na+/K+ ポンプの働きで、細胞内は細胞外に比べて Na+ 濃度が
低く、K+ 濃度が高い状態に保たれ、細胞内が負の膜電位が形成されています。
神経細胞が刺激を受け、膜電位が変化すると、膜電位依存性 Na+ チャネルが
開くため、Na+ が流入して細胞内の膜電位が上がっていきます。遅れて膜電
位依存性 K+ チャネルが活性化し、K+ が流出して急激に細胞内の電位が下がり
ます。神経の興奮によって変化した膜電位は、再び Na+/K+ ポンプの働きで元
の静止状態にもどります。この活動電位の変化により、次々に Na+ チャネル、
K+ チャネルが開いて、電気シグナルを伝達させています。軸索中に活動電位
が伝わると、神経末端で電位依存性 Ca2+ チャネルが一時的に開き、神経伝達
物質がシナプス間隙に放出されます。神経伝達物質はシナプス後細胞のリガン
ド依存性イオンチャネルを開口させ、Na+ の細胞内への流入と K+ の細胞外へ
の流出で活動電位を発生させます。
樹状突起
シナプス間隙
軸索末端
電気シグナル
Na+チャネル -K+チャネルの連続的な開閉により電気シグナルが伝達する
シナプス前神経細胞
シナプス後神経細胞
神経伝達物質を放出して化学的刺激を伝達
膜電位変化によりNa+チャネル -K+チャネルの連続的な開閉が起こり電気シグナルが伝達する
1
2
3
膜電位依存性イオンチャネル
軸索
83
② リガンド依存性イオンチャネル
神経細胞には興奮性と抑制性があります。各々の細胞は軸索末端から興奮性
または抑制性神経物質を放出し、シナプス後細胞を刺激します。神経伝達物質
がシナプス後細胞にあるリガンド依存性チャネルに結合することで、活動電位
の発生または抑制が起こります。
③ 機械刺激依存性イオンチャネル
機械刺激によるイオンチャネルの開閉は、内耳の聴覚有毛細胞でみられま
す。音の振動により基底膜が上下に動くとそれに伴い、付近の有毛細胞の不動
毛にある機械刺激依存イオンチャネルが開きます。正荷電をもったイオンが流
入すると、有毛細胞が活性化し、その下にある聴神経線維を刺激して、シグナ
ルを脳に送ります。
水チャネル
水は単純拡散だけでも生体膜を通過しますが、水の透過性の高い細胞膜には
水分子を選択的に通す水チャネル(アクアポリン)があります。水チャネルは
水の移動が必要なときには開き、移動が必要でなくなれば閉じる仕組みになっ
ています。水チャネルが開く場合には、チャネルがリン酸化され、水分子が通
過できる構造へと変化します。一方、リン酸基が取り除かれると、チャネルが
閉じて水が通過できなくなります。水チャネルは腎臓に多くみられ、水の再吸
収に役立っています。
Ca2+ チャネルが開きCa2+ が細胞内に流入
シナプス小胞が神経細胞膜と融合し神経伝達物質を放出
神経伝達物質がリガンド依存性イオンチャネルに結合
イオンチャネルが開きイオンが流入することにより膜電位が変化
前シナプス細胞の軸索を活動電位が伝わる
Ca2+
シナプス小胞
シナプス間隙
神経伝達物質
シナプス後細胞イオン
イオンイオン
電位依存Ca2+ チャネル
Ca2+
リガンド依存性イオンチャネル
リガンド依存性イオンチャネル
84
SLC (Solute carrier) トランスポーター
2015 年 6 月現在、SLC トランスポーター遺伝子はその機能によって 52
ファミリーに分類され、約 418 種類が Bioparadigms.org(http://www.
bioparadigms.org/slc/intro.htm)に登録されています。SLC トランスポーター
は、全身の組織に発現していますが、特に、腎臓、肝臓、胃腸などの泌尿器系・
消化器系、そして脳神経系で高発現しています。たとえば、小腸からグルコー
スを取り込むためには、2 種類の SLC トランスポーターが関与しています。
まず、腸管から小腸上皮細胞への取り込みには Na+- 共益型グルコース共役型
輸送体(SGLT1/SLC5A1) が、そして小腸上皮細胞から細胞外液への輸送に
は受動的グルコース輸送体 (GLUT/SLC2 ファミリー)が働いています。細胞
内にグルコースと共に取り込まれた Na+ は Na+/K+ ポンプで ATP の加水分解
で生じるエネルギーを使って能動的にくみ出されます。細胞外液に漏れ出たグ
ルコースは血管によって、他の組織へ運ばれて消費されます。また、SLC ト
ランスポーターファミリーの半分は、腎臓で特異的に発現しており、SLC ト
ランスポーターの異常(変異)は、各種の腎疾患(尿細管性アシドーシス、シ
スチン尿症、遺伝性腎性糖尿など)の発症に関係していることが報告されてい
ます。
ABC トランスポーター
ABC トランスポーターは、ATP を利用して、ペプチド、タンパク質、薬剤、
脂質など様々な物質を細胞外から細胞内へ、また細胞内から細胞外へ輸送しま
す。 現在、49 種類の ABC トランスポーターが知られていて、細胞膜以外にも、
小胞体やゴルジ体、リソソーム、ミトコンドリアなどの細胞内小器官に存在す
Pick Up from MBL
SLC トランスポーター
MBL は、疾患への関連が示唆され
ている SLC トランスポーターを中
心に抗体開発を行っています。高品
質な研究用ツールを市場に提供する
ことでトランスポーター関連疾患の
早期原因究明と治療ターゲットの開
発に貢献したいと考えています。
関連疾患の一部
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・発達障害、小頭症、低血圧
・家族性腎性糖尿
・甲状腺ホルモン異常
・癇癪発作、統合失調症
・ うつ病、起立不耐症、拒食症、心
循環器疾患
・ パーキンソニズム、トゥーレット
症候群、注意欠陥(ADHD)など
抗 GLUT1/SLC5A1 抗体の染色像
MBL ライフサイエンスサイト
(http://ruo.mbl.co.jp/product/
transporter/slc.html)に SLC と疾患
についての情報を掲載しています。
P
リン酸化による構造変化Na+が放出
P
ATP ADP
ポンプのリン酸化
Na+
Na+の結合
細胞外部
細胞質
Na+/K+ ポンプ
P
K+の結合P
P
ポンプの脱リン酸化K+
脱リン酸化による構造変化K+が放出
Na+
Na+
K+
K+
Na+/K+ポンプ
ヒト小腸 ヒト腎臓
グルコース輸送
グルコース取り込み
細胞外液
グルコース放出
小腸上皮
Na+
Na+
K+
K+
Na+
グルコース
グルコース
グルコース
腸管
Na+/K+ ポンプ
受動的グルコース輸送体GLUT/SLC2ファミリー
グルコース共輸送体SGLT1/SLC5A1
85
ることがわかっています。ABC トランスポーターは多くのがん細胞で発現し
ており、抗がん剤の排出輸送を行うことから、がん細胞の多剤耐性に関係して
いると考えられています。また、脂質輸送への関与から、ABC トランスポーター
の機能異常が様々な疾患を引き起こすことが知られています。
イオンポンプ
イオンポンプは、ATP のエネルギーを利用して、細胞や細胞小器官でイオ
ンの取り込み・排出をおこなっています。Na+/K+ ポンプは、通常、動物細胞
の全エネルギー(ATP)の 30% 以上を消費して、 Na+ を細胞外に排出し、 K+
を細胞内に取り込んでいます。このポンプの働きによって、細胞質内の Na+
濃度は細胞外液の 1/10 − 1/30 に、K+ 濃度は 10 − 30 倍に保たれています。
細胞内の 3 個の Na+ がポンプの結合ポケットに結合すると、ポンプが ATP で
自己リン酸化されて構造が変化します。構造変化によって、Na+ が細胞外に放
出されると、細胞外の 2 個の K+ が結合ポケットに結合します。続いてポンプ
のリン酸化が外れてポンプ構造が元に戻ると K+ が細胞内に遊離されます。
7-4.神経細胞が損傷される疾患「神経変性疾患」
神経変性疾患とは、脳や脊髄にある神経細胞のなかで、ある特定の神経細胞
群が徐々に損傷を受け、脱落してしまう疾患です。主として運動機能が障害さ
れるパーキンソン病や、知的機能が障害されるアルツハイマー病などがありま
す。近年、神経変性疾患の発症に、神経免疫システムの異常が関わることが明
らかになってきました。
通常、脳内には白血球が入らないようになっており、白血球の代わりに、脳
内の免疫防御を担っているのがグリア細胞※ 1 の一種であるミクログリアです。
ミクログリアは中枢神経系の約 10%を占め、脳マクロファージとも呼ばれる
ように、通常は抗炎症性サイトカインの産生や異物除去を行います。ミクロ
グリアが働きすぎると、正常なニューロンを損傷してしまうことがあるため、
通常はミクログリアが働きすぎないように制御する機構が働いています。しか
し、アルツハイマー病老人斑の主成分であるアミロイド β などによってミク
ログリアが異常に活性化される※ 2 と、神経組織に損傷を与えるようになりま
す。アルツハイマー病の発症リスクに糖尿病がありますが、糖尿病でも、組織
マクロファージが炎症性サイトカインを産生するようになることから、神経疾
患は、免疫システムの異常としての視点からも研究がされています。
Pick Up from MBL
神経変性疾患関連製品
MBL では、神経変性疾患に関連す
る抗体・キットを多数取り揃えてお
ります。ここでは一部の製品をご紹
介いたします。
抗アミロイド β 抗体
MBL では、アルツハイマー病患者
の脳切片において、老人斑を検出で
きるアミロイド β に対する抗体を販
売しています。
UCHL1 ELISA Kit
UCHL1 は、中枢神経系に豊富に存
在することから、パーキンソン病、
アルツハイマー病、脳損傷および虚
血性脳卒中のバイオマーカー候補と
して現在、とても注目を集めていま
す。
sRAGE ELISA Kit
アルツハイマー病では脳血管性認
知症や対照患者と比較して、血清
sRAGE の有意な低下が観察されま
した。
※ 1 脳の細胞には大きく分けてニューロン細胞とグリア細胞の 2 種類があります。
※ 2 ミクログリアが炎症性サイトカインやフリーラジカルを持続的に産生するようになります。
86











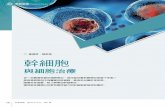











![特集 再生医療・ 幹細胞がん研究 エピジェネティクス ゲノム編集 神経科学 細胞生物学 汎用品 代謝 [特集]再生医療・幹細胞 特集再生医療・幹細胞](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/612382ab29b5760990514550/ce-coecf-cef-oecc-fff-ffce.jpg)





