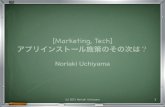1.50年後のGrand Design - MLITコミュニティ <イメージ> 【施策6】 総合的な住み替え施策の推進 世代別のライフスタイルに応じた住居 の住み替え、転居を誘発する住宅施策
5-1 理念、課題や強み、施策の方向性の ... 3-2 siryou1-2_s.pdf · a...
Transcript of 5-1 理念、課題や強み、施策の方向性の ... 3-2 siryou1-2_s.pdf · a...

A 「理念」の検討 B 「解決すべき課題」や「活かす強み」の整理 C「施策の方向性」や「施策案」の検討
子どもの学び
子どもの学び (現在案)※会議委員及び事務局の考え (現在案)※会議委員及び事務局の考え
「目指す子どもの姿」の実現に向け、項目ごとの基本的方向性を検討
5-1 理念、課題や強み、施策の方向性の整理 ○ 取組み方策である「施策の方向性」や「施策案」のまとめに向け、理想の姿や現状を合わせて整理
1 子どもの学びのあり方
(公教育としての前提)
○ 人それぞれの学びのペースや、興味・関心、
合った学び方、合った教材、心地のよい学習
空間は異なる
○ すべての子どもが安心して他者と学び合える
その為の人間関係をよくする基本を修得する
(個性の尊重、自律と協調など)
○ 個性を育む教育
○ 緩やかな協同性に支えられた個の学びの実現
○ 異年齢集団の中で、学力や社会性を高める
○ 学びの「個別化、協同化、プロジェクト化」融合
○ 探究型の学びを推進、追求したい事を学ぶ
○「教える」と「考えさせる」の両輪
○ 学校内外に多様な学びの場所をつくる
○ 生命の尊厳への理解を深める学びを推進
○ 義務教育学校に関する方向性を検討
目指す子どもの姿
(育みたい資質・能力)
○ 自由の相互承認の感度を高める
○ 自己肯定感、自己承認感を高める
○ 命や仲間を大切にする個人、集団の育成
○ 自分の存在も他者の存在も大切にする
○ 自分で決める力
○ 学ぶ場所や内容を自ら選択し、決定する力
○ 自ら考え、能力を開発し、幸せを築いていく力
○ 自ら学び続けることができる力
○ 協調性とともに、個の力・個性を育む
○ 失敗できる環境で新しいチャレンジをしていく力
(生命の尊厳や人間関係形成に関する学びの充実が必要)
○ 命の大切さや生きる意義など、人間の本質を学ぶ機会が十分にはない
大人も子どもたちに、その大切さを十分には語り伝えられていない
○ 学校で、生き物と触れ合う機会が減少していたり、命に触れる活動が弱い
○ ソーシャルスキルが自然と身に付く時代ではない。習得には訓練が必要
○ いじめ事案も含め、子どもの生き辛さの原因を深掘りし、課題を明らかにする
○ 自己承認感を高める取組み、人間関係を良くする基本を身に付ける取組みが必要
(学びの内容や水準、評価が各校でバラバラ)
○「道徳」を中心に、様々な教科・活動で生命や人間関係に関する学びを実施
○ モデル校での取組みが全校へ普及・展開していない。各校への支援体制が弱い
○ 子どもの実態や学校風土等を評価するアセスメントが各校でバラバラ
○ 白川郷学園や岐阜大学教育学部付属小中学校では、独自の教科や活動を設定し学習
(時代認識、教育改革、市の教育大綱 など)
○ 技術革新や、他者との関係性の多様化
○ 社会の変化を踏まえた教育改革の必要性
○ 150年間変わっていない教育システムの改革
○ すべての子どもたちの自由と安心を保障する
○ 一部の子を置いてきぼりにしない(SDGsの理念)
○ ケアの心に満ちた信頼と承認の温かい空間を作る
○ 教育大綱の実質化、関係者間での真の共有が必要
(小中一貫教育の実績を踏まえた展開の加速が必要)
○ 約10年、小中一貫教育を実施し、今後、小中一貫校のモデル実施へ(R2年度~)
○ 異年齢の学び合い等、子どもへのプラスは多いが、学校運営面で課題や工夫が必要
○ 小中一貫校は、固定化された人間関係をリセットできないデメリットがある
○ 校区エリアの活性や、まちづくりとの関わり・相乗効果を踏まえた検討が必要
(現状の学びの機会や内容を整理)
○ 学校・家庭・地域での生命の尊厳や人間関係形成に関する学びの機会を見える化し、
より多くの人に多くの機会提供をしていくことを検討
(学びのプログラムとアセスメントツールの統一 “独自の教科化など”)
○「生命の尊厳、人との関わり」を全ての子ども・教員が学ぶ「共通プログラム」の検討
(市独自の共通の活動や教科化の検討 など)
○ 子どもの実態や学校風土を多角的に評価できる共通アセスメントの全校導入を検討
(教職員の育成)
○ 教員の学ぶ時間(研修等)の確保、充実が必要
(中長期的な展望も含めて検討へ)
○ 具体的な効果や課題の更なる検討
○ 県内先進事例と連携した調査・研究の更なる推進(岐大教育学部との連携 など)
○ 校舎建替え計画や統廃合に関する方針等の検討の際、義務教育学校化も踏まえて検討
○ モデル校を指定した試行実践の検討(施設一体型の義務教育学校)
探究(プロジェクト型の学び)
(次代に必要な学力、資質能力の育成が必要)
○ 学校での学びの内容や学び方が、時代の変化に対応していない
○ 社会で必要な協調性や異年齢での関わり合い、自分で決める力の育成が不十分
○ 知識習得に向けた取組みに比べ、個性を育む取組みが十分ではない
○ 地域の多種多様な大人や、培ってきた文化に子どもが触れ、学ぶ機会が少ない
○ 探究する力は、学力の本質であることを関係者が共通理解して取組む必要がある
○ 社会ではトライが重要。学校でも失敗を肯定的に捉え、新しい挑戦を促す必要がある
○ 探究型の学び、自分が追求したいことを学ぶ活動を増やしていくことが必要
(教職員の育成が必要)
○ 探究に関する教員の理解、納得、推進スキルの向上が必要
(探究推進の下地はある)
○ 学校:「総合」を中心に、様々な教科・活動において探究学習を位置付け、推進
○ 学校外:社会教育施設等が行う事業で「探究」に重点を置いた様々な施策を推進
(「探究」を市の教育の理念に)
○ 探究を市や教育委員会が掲げる理念・方針に位置付けることの検討
○ 探究の意義等を子ども、教職員、保護者、地域等が共通認識できる取組みの検討
(「探究」を核としたカリキュラム編成)
○ 内容:子どもの主体性を重視した内容やプロセスの再検討
学びの「個別化」「協同化」と一体的に推進するスキームの検討
○ 時間:ICTを活用した知識習得時間の効率化と、探究時間の増加・内容の充実を検討
○ 場所:学校内外で自ら学ぶ場所や内容を選択でき、挑戦と失敗ができる学び方の検討
まち全体を子どもの探究フィールドとして再構築することの検討
○ 評価:教員や地域が子どものバリューを多角的に評価しフィードバックする仕組みを検討
(子どもの「探究」を支える人材の育成)
○ 教員が子どもの探究を支援、伴走(共同探究)できるスキルの向上(教員研修など)
○ 子どもと教員の探究を支えるコンシェルジュ的機能(コーディネーター)の配置検討
探究(プロジェクト型の学び)
生命の尊厳・人間関係形成
生命の尊厳・人間関係形成
義務教育学校
義務教育学校
理想の姿
現状
取組み方策
教育委員会の機能整理・強化
教育委員会の機能整理・強化
○ 探究型の学びの推進に向け、教員研修の充実や、教員支援の体制強化が必要 ○ 市教委・県教委・大学等が連携した教員の探究を進めるプラットフォーム構築を検討
○ 市教委組織の見直しや人的強化を検討。教育政策のシンクタンク機能の強化を検討
12

A 「理念」の検討 B 「解決すべき課題」や「活かす強み」の整理 C「施策の方向性」や「施策案」の検討
5-2 理念、課題や強み、施策の方向性の整理
2 学校組織・教職員のあり方
(教職員の資質能力の更なる向上)
○ 教職員が子どもと向き合う時間を確保する
○ 子どもとの意義ある向き合い方の検討
○ 教員が人間関係をよくする基本を修得する
○ 教員が指導に加え、支援する力を修得する
○ 子どものSOSを見逃さない仕組みや、
教職員の資質能力(感度)の向上
○ 教員が専門性を発揮できる環境づくり
○ 今必要な資質能力を備えた教職員の育成
(学校組織、教育委員会のアップデート)
○ 市・教育委員会と、学校現場の教職員、保
護者、地域がビジョンを共有
○ 教育施策や学校の業務、活動の精選
○ 学校、教育委員会のマンパワーの強化
○ 教育委員会による学校支援体制の強化
3 子どもや学校と地域との関わり
(学校の外を育て、学校とともに子どもを育む)
○ 地域と子どもとの関わりの機会を増やす
○ ボランティアや善意任せではない関与
○ 地域活動を切り口に保護者と地域と学校が
子どもの教育について情報共有する
○ 地域に子どもと向き合う許容性を育む
○ 保護者が人間関係をよくする基本の修得
○ コミュニティ・スクールを活かした子どもの学びの充実
学校組織・教職員
学校組織・教職員
地域との関わり
地域との関わり
○ 学校教育に関して保護者が学ぶ機会が少ない。親が時代の変化に対応できていない
○ 地域での交流が減少。孤立した家庭が多い。ガラス張りの付き合いが困難な状況
○ 子ども、保護者、地域が市の教育について共に学び合う機会の拡充を検討
○ コミュニティ・スクールやPTA活動で、子どもの声が入っていなかったり、活かされていない
○ 小中一貫教育の成果として、地域で子どもを育むコミュニティ・スクールとの相乗効果がある
○ 学校と地域が連携し、子どもや教員の学びを育み、地域の魅力を高める仕組みの検討
(現在案)※会議委員及び事務局の考え (現在案)※会議委員及び事務局の考え
(現在案)※会議委員及び事務局の考え (現在案)※会議委員及び事務局の考え
理想の姿
現状
取組み方策
○ 取組み方策である「施策の方向性」や「施策案」のまとめに向け、理想の姿や現状を合わせて整理
13
学校の業務実態の可視化、整理、分析、改善、共有
(学校・教職員の実態把握が必要)
○ 学校や教員のコア業務が曖昧。見える化、定義付けが必要
○ 多忙の内訳がわかるデータがない。タイムカードの分析も十分ではない
○ 多くの教員が仕事にやりがいを感じる一方で、多忙で疲弊しそうな状況にある
○ 現場の教職員(管理職、若手、養護教諭、事務職員など)の悩みや課題の深掘りが必要
○ 学校のマンパワー不足を解消する必要がある
○ いじめ事案も含め学校のチームワークやコミュニケーションがうまくいっていない
○ 市の強みであるコミュニティ・スクールやスーパーシニアの力を学校に取り込み、教員の負担軽減へ
ただし、ボランティアや善意の方へのお任せでは、地域や家庭の力の減退になる
○ 研修校・実習校は看過できない労働実態。ただ、他校の勤務実態も過酷
○ 土曜日等の教育活動(土曜授業)は効果も課題もある。休止も含め見つめ直す
○ 白川郷学園では教職員マネジメントのために職員室の席替えをして効果があった
学校の業務実態の可視化、整理、分析、改善、共有
(業務実態の可視化・改善サイクルの導入)
○ 学校のコア業務を整理し、コアの効率化と、コア以外を学校から切り離すことを検討
○ 学校ごとに多忙や多忙感を可視化・分析し、関係者による対話に基づくPDCAの実行
○ 実態共有や改善状況のチェック機能として、校区住民など関係者と勤務実態を共有
○ 業務改善に関するモデル校での取組みを全校展開していくための方策の検討
○ 土曜日等の教育活動の目的や効果の検証を踏まえ、休止も含め検討する
(学校業務スリム化に伴う地域等の受け皿の検討)
○ 学校にコーディネーターの配置を検討(スクールサポートスタッフ、コミスク・コーディネーター、地域学校協働推進員等)
○ 子ども、保護者、地域が市の教育について共に学び合う機会の拡充を検討
(学校の職場環境の改善)
○ 民間のオフィス改革等を参考とし、業務効率化を目指した学校の業務環境改善の検討
13
学校運営・授業スタイルの変革
(若手教員の育成や、授業準備の時間確保が課題)
○ ここ10数年で教員の年齢構成比が大きく変わり、若手を支え育てられる状況にない
○ 教員の一番の悩みは、授業準備の時間が足りないこと
○ 市はICT環境整備が進んでいる。国の施策も活用し更に効率的な学習スタイルを検討する
学校運営・授業スタイルの変革
(チーム担任制(全員担任制)、オンライン授業の検討)
○ 学校運営や若手育成等の観点踏まえ、固定担任制からチーム担任制への移行を検討へ
○ 既存のICT環境、国のGIGAスクール構想を活用したオンライン授業の検討へ
○ 教員それぞれの専門性やオリジナリティの発揮・活用の方策についても検討
教職員の人材開発・組織開発
(教職員の資質能力の更なる向上が必要)
○ 子どもに育むべき思考力などを、教員自身が高められていない
○ 教員研修が、今必要な教育や学校のあり方を踏まえた内容かどうか検証が必要
教職員の人材開発・組織開発
(「目指す教職員の姿」の明示、教員研修の見直し)
○「目指す子どもの姿」を実体化するために必要な教職員の姿を明確化することを検討
○ 教員研修の計画・設計にあたり、外部の専門家(人材開発等)の知見活用を検討へ
○ 教職員が相談できる場が少ない。悩みを聴きアドバイスするWeb上のツール等を検討
教育委員会の機能整理・強化
(教育行政と学校現場の疎通に課題、教育委員会の多忙解消が必要)
○ 市や教育委員会が掲げる理念が、教職員や保護者、地域と共有できていない
○ 市の教育施策の多くを担う部署(学校指導課)が多忙過ぎる状況にある
教育委員会の機能整理・強化
(教育委員会の組織再編、学校事務のあり方検討)
○ 学校支援に注力できるよう、教育委員会業務のスリム化、組織の再編を検討
○ 外部人材の調達・供給の集約化、学校事務の集約化・共通処理の検討