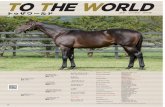タンタルコンデンサ ケース Pケース ASケース ALケース D22 パッシブデバイス タンタルコンデンサ 下面電極タイプ(大容量) : TCTシリーズ
鹿児島伊佐市「支援を支えるケース会議」
-
Upload
kou-kunishige -
Category
Health & Medicine
-
view
156 -
download
1
Transcript of 鹿児島伊佐市「支援を支えるケース会議」

支援を支えるケース会議―うまく進めるための魔法の言葉はあるのか―
2016 年 12 月 7 日(水)鹿児島県伊佐市

ケース会議
• 事例検討会• 関係者会議(スタッフ会議)• ケース・カンファレンス• 関係機関との連携 ・ 多職種連携• ネットワーク・ミーティング
• 勉強目的→現在の実質的な支援• 対象(組織内→他組織→他業種→当事者)

目的
【ケース会議】• 解決すべき問題や課題のある事例を個別に深く
検討することによって、その状況の理解を深め、対応策を決定する。
【多職種連携】• 質の高いケアを提供するために、異なった専門
的背景をもつ専門職が、共有した目標に向けて共に働くこと( http://truecolorsjapan.jp/for-helpers/ipe/ )。
• 「その状況の理解を深めること」によって、より適切な「対応策」を得ることができる、はずだが…

多職種連携に求められる能力
• 基盤となる 2 つの能力– クライエント・家族・コミュニティを中心とした
ケア– 職種間のコミュニケーション
• 多職種連携を目標として相互に統合される 4 つの能力– 各職種の役割の明確化– チーム機能の理解– 相互に連携したリーダーシップ– 職種間に生じた葛藤解決

生じる 2 つの葛藤
• 多職種連携が難しいのは、そこにしばしば二重のすれ違い(葛藤)が立ちはだかるからです。一つは職種の違い、もう一つが個人の気質による違いです。
• 専門職間の葛藤– 職種間の地位や力の格差は、多職種連携の障壁となります。さら
に知識や価値観など専門職文化の差異も、葛藤を生じる要因となります。加えて、多職種連携の方法や葛藤解決についての知識やスキルの不足も課題です。
• 個性の違い– 職種や立場とは別に、一人ひとりの気質の違いがあります。職
種の違いをどう理解し、どのように葛藤を解決するのかという方法にも、個性の違いが現われます。
– http://truecolorsjapan.jp/for-helpers/ipe/

なぜ難しいのか?
• そもそも開催することすら難しい• ケース会議をして、何か有益なことが得られると
は感じられない• ケース会議をする方法がわからない• 共通する理解に到達することもままならない• ましてや「共有した目標」など遠いところとなっ
てしまう。• それぞれが多忙の中で、新たな対応策に十分な時
間を割くことができない。対応策そのものが大変なものとなることもある。

ケース会議の隠された思惑
• 自分の理解していることを相手にも理解してもらいたい
• 誰か特定の人やグループを説得、あるは教育したい
• ある人が何か特定のことをするように持っていきたい
• など…

ケース会議にまつわる経験
• ケース会議のような場での経験を教えてください。
• あまり良い場とならなかったのは、何が作用していたと思いますか?
• 良い場となったと感じたときには、何があったのでしょうか? 何が違っていたのでしょうか?
• (共有する時間をとる)

連携(ネットワーク)
• 現代社会において、さまざまなサービスは細分化され、分断化される傾向にある。支援とは、適切なサービスにつなげることを意味することさえある。
• そのサービス単体では包括的な支援ができないため、さまざまなサービスが「連携」し、できるだけ包括的な支援が提供できるようにする必要が出てきた。
• しかし、本当に必要とされる支援は、どのサービスも提供していない場合がある。つまり、本当に必要とされているものは、さまざまなサービスの間(谷間)にあることもある。

アセスメント(理解様式)と取り組み
• アセスメント: 当事者がどのような人なのか、どのようなどのような家庭状況にいるのか、どのような経過をもっているのか、どのような人間関係にあるのか、あるいは、診断名はなにか
• 取り組み: アセスメントを得られたからといって、どのように取り組むかが見えてくるわけではない。

解けない〈問題〉
その〈問題〉が解けないのは解き方のせいなのだろうか? それとも、そもそも、問題の立て方が間違っていることはないだろうか?

「クヨクヨする」という問題
• クヨクヨとは「気に病んでも仕方のないことに心を悩ますさま(広辞苑)」• 「私、ちょっとしたことで、クヨクヨしてしまうんです」

反社会学の不埒な研究報告
パオロ・マッツァリーノ

リチャード・カールソンの「小さいことにくよくよするな!―しょせん、すべては小さなこと」が 1999 年に翻訳が出版される

「カールソンさんは、自分はくよくよしている人たちを救っているつもりなのでしょうが、現実は逆なのです。くよくよしないための百のヒントとは、裏を返せば、くよくよするためのシチュエーションを百個紹介してしまっているのと同じことです…この本のキャッチフレーズが 「しょせん、すべては小さなこと」って、 だったら黙っててくれればいいのに」

「不登校」という問題
• 学校が誕生してから、なくなったことがない現象(鹿児島の「山学校」)
• ニュージーランドにも学校に来ない人はたくさんいるが、「不登校問題」はない。
• 「不登校」問題を一瞬に解決する魔法• 「不登校」という舞台

「学力」という問題
• 平均値に取り組む罠(平均値を求める時点で必ず生じる両端)
• 永遠と続くモグラたたき• 細部を見れば「問題解決」がありそう
だが、全体を見れば決して問題は消滅しないとわかるはず・・・

「統合失調症」という問題
• 「不治の病」としての統合失調症• 「薬を一生涯にわたって飲み続けなけ
ればならない」• バイオマーカー(ある特定の疾病の指
標となるような、計測可能な特質)の欠如
• 歴史的変遷から見ると( Mad In America)

「チームワーク」という問題
• 仲良しクラブとしてのチーム• 「チームワーク」は、集団の目
的になりうるのか?• 目的志向型集団としてのチーム

自身の存在を真実だと告げる「問題」
• 不登校、発達障害、精神病、うつなど、それに実態があり、その存在のあり方が本当であると告げるような「問題」が提示される時、私たちは、すぐさま「その問題を解決すること」に囚われてしまう。
• その解決努力そのものが、その問題を維持させるための力の行使であるなどとは、思っても見ないことなのである。
• 例えば、「うつ」にまつわる否定的な考えが広まれば広まるほど、似たような症状を持っている人をも巻き込み、その勢力が広がっていく。

ロバート・ウィタカー心の病の「流行」と精神科治療薬の真実• (米国において) 1955 年には、州立あるいは郡立精神病院
にいる患者数は 558,922 であった。その内、 355,000 人だけが精神科疾患を患っていた。他の 200,000名は、認知症、末期の梅毒、アルコール依存、精神遅滞、そして、さまざまな神経学的症候群を患っていた( Source: Silverman, C. The Epidemiology of Depression (1968): 139 )。
• つまり、 1955 年には 468 人中 1名のアメリカ人が、精神科疾患のために入院していたことになる。
• 1987 年には、 125万人の人々が SSI または SSDI に対する支払いを受けている。それは、 184名中 1名のアメリカ人が精神科疾患によって障害があると認められているからである。

ミシェル・アレクサンダー新ジム・クロウ法 色盲時代における大量投獄−
https://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States

米国で蔓延する「オピオイド系鎮痛剤の中毒」
• 米国では、慢性痛の治療に使われるオピオイド系の鎮痛剤が乱用されており、中毒状態になっている者は 190万人。死亡者は 1999 年から2014 年までで 16万 5,000 人に上るとされる。
• オピオイド系と呼ばれる鎮痛剤には驚くほどの常習性がある。米国では鎮痛剤の使用および乱用が蔓延状態であり、米国政府の試算によれば、 2013 年にはおよそ 190万人の米国人がこうした鎮痛剤の依存症だったという。
• http://wired.jp/2016/04/23/americans-addicted-prescription-opiates/

震災後 PTSD になった女子高生、月経前症候群も重く
• 東日本大震災で心的外傷後ストレス障害( PTSD )になったとみられる女子高生は、月経前にイライラしたり手足がむくんだりする月経前症候群も重くなっていることが、近畿大の武田卓・東洋医学研究所長らの調査でわかった。月経前症候群と自然災害の PTSD の関連を明らかにしたのは初めて。札幌市であった日本産科婦人科学会学術講演会で発表した。
• 震災から 9 カ月後の 2011 年 12 月、仙台市中心部にある二つの高校の女子生徒1180 人について、月経前の不快な症状や PTSD の症状に関する 36 の問いの回答を点数化して分析した。 PTSD が強く疑われたのは 10%。一般にみられる 0.4%より著しく高かった。うち PTSD ではない生徒は月経前症候群が 1 割。一方、 PTSD疑い例では 4 割に中程度より重い月経前症候群がみられた。
http://www.asahi.com/special/news/articles/TKY201305140184.html

気仙沼・南三陸の状況
• 質問用紙による調査が実態を反映しないのはなぜか?
• スケーリングの質問用紙の点数で「障害」判定すること
• 「 PTSD 」というエコー• ファーストハンドトーク&セカンドハンドトーク

「ポストはどこにあるの?」
• 2007 年に、親しい友人で、カナダの優れた HIV とエイズ疫学者であるエド・ミルズ医師に、彼の数え切れない活動のひとつであるウガンダのカンパラとマベレ、そしてさらに北にある強制退去者のキャンプを訪れる旅に、私は招待されました。この旅行期間中、心的外傷として知られる北アメリカの心理学的概念の話題について、数えきれないほどの議論(そして、しばしばすべての「西洋からの援助者」に向けた穏やかな嘲笑)に遭遇しました。現地での返事は、常に「あなたが話している『(郵便)ポスト』は、どこにあるのですか?」というものです。これが、ウガンダにおいて理解されていることであり、西洋ではまったく誤解されていることなのです。
• スティーヴン・マディガン「ナラティヴ・セラピストになる」

イタリア「 180号法」(バザーリア法) 1978 年
• 「クライシス」、つまり精神的な危機に陥っている患者は、自傷しようとしていたり、稀に精神保健センターでは対応できな いレベルの他害行為が起ころうとしていたり(その場合の対処システムもあります)、激しい混乱を示していたり、感情を爆発させていたりします。「薬を飲ん でもらって鎮静してもらって症状を消す」「迷惑なので病院に閉じ込める」が日本での普通の対処でしょう。
• しかしイタリアでは、バザーリア改革以来、「クライシス」は乗り越えるべき危機であり、何かを見直すきっかけであり、乗り越えて成長する チャンスと捉えられています。だから、そういう場面でこそ、日常の場や日常の人間関係から切り離すことなく、日常の家族や隣人や仲間たちと一緒に、必要な らば日常の地域の中にある精神保健センターで客人として「おもてなし」を受けながら過ごしたりして、コミュニティで「共に」乗り越えるというアプローチが 取られています。本人への提案や働きかけはされますが、基本的に「強制」はありません。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/miwayoshiko/20151107-00051198/

オープン・ダイアログ
• 根拠に基づく実践のライブラリーは、ひとつの方法による研究しか相手にしていない。それとは別のアプローチによる知識は全くないがしろにされている。あきれたものである。
• 精神医学の専門誌には、実験的なセッティングで行われた研究しか掲載されない。
• 普遍的因果関係を見つけ出そうとすれば、地域的な要因は関心外になる。
• ここで問題となるのは、研究は比較されうるが、実際の実践はずっと複雑で比較できるものではない、ということである。
• 平均値は個別のケースについては何ひとつ物語らない。

その〈問題〉を作り上げ、維持し、拡大しているものに焦点をあてるべきということ。そのサイクル(再生産)からどのように離れることができるのだろうかと問うことが求められる。

専門家がつくり上げる境界

システムとシステムの間にインターフェイスがあります。システムの中にいるものは、そのシステム内のことに専念します。そして、そのシステム内の規律に縛られます。システムの利用者は、多くの場合、複数のシステムを同時利用する必要があります。そして、そのシステムごとに、利用するための管理上の手続きを要求されるのです。その煩わしさを、通常システム内にとどまっている人は、うまく把握できません。複数のシステムにまたがって利用する人が、社会的な弱者であったり、精神的な衰弱や苦痛がある人である場合、「複数」を利用することの難しさは、想像以上のものがあります。

このシステムとシステム間の調整をする必要性は、システムの構造上無視されます。つまり、それは、システムの外にあるものだからです。望まれているところは、システム内にいる人が、少しだけその外に足を踏み出して、活動することです。すべてのシステム内にいる人々が、一歩踏み出してくれるようになるといろいろなことが、利用者にとってたいへんありがたいものとなります。

そのためには、皮肉なことに、システム内の規律を「ちょっとだけ」拡大解釈するような英断が求められるのです。システム内では、このような存在を決してターゲットにして弾弓してはいけないのです。そのような存在は、たいへん貴重な存在になるはずです。自分が所属しているシステムの外側で起こっていることについて、意識して求めていく必要性があるのでしょう。システムとシステムの間にインターフェイスの重要性について気づくべきなのだと思います。

自分が所属しているシステムへの報身・従順さは、システム内で決して間違っていないことをしているという安心を提供してくれます。しかし、残念なことに、それが利用者の満足につながることを請け負ってはくれません。システムに対する苦情を聞く時、それは、システム自体に対する苦情なのか、システムをちょっとだけ超えたところが不在であることに対する苦情なのかを区別することも必要になります。

ミーティングの実情

「ゴミ箱カテゴリー」
• ドナルド・ショーンは、専門家は自分たちの厳密な技法では分類できない現象に対して「ゴミ箱カテゴリー」をつくりだすと言う。「多様な問題を抱えたクライエント/家族」という語は、「たくさんのゴミ箱カテゴリー」と言い換えられるかもしれない。だが、これはまさしく専門家システム側の混乱なのだ。クライエントの問題が細分化されたシステムのカテゴリーに合致しない時、システムはその仕事をどこにどう割り振るのかを互いに繰り返し交渉せねばならななくなる。「多様な問題を抱えた」ケースに遭遇するたびに交渉せねばならないのだ。こうした「境界間の交渉」は、たやすいものではない。しばしば言い合い、押し付け合いになってしまう。
• 「オープン・ダイアローグ」( 29頁)

「皆のクライエント」
• たとえば、「 ADHD 」と名づけたからといって、何かがわかったわけではない。その状態に名前をつけてカテゴリー化すると、それに適した専門家システムのもとに振り分けられる。カテゴリー化が別になると、また別のシステムが問題を引き受け、責任を負うことになるだろう。
• (フィンランドの)最近の研究では、「皆のクライエント」は「誰も背負わないクライエント」になりがちだということがわかった。(中略)「皆で責任をもつということ」は、「誰も責任をもたない」ことと同じである。
• 「オープン・ダイアローグ」( 43頁)

ネットワークミーティングで目指すところ

「未来語りのダイアローグ」
• その目的は、一方ではこれまでと同じパターンを繰り返さないやり方を見つけることであり、もう一方ではクライエントの関係を壊してしまわない程度ではあるが、これまでとは違ったやり方を見つけることにあった。つまり、「希望的予測」を使うことによって、適度に異なるやり方を見つけるのである。
• 「オープン・ダイアローグ」( 16頁)

お互いのものの見方
• めざしているのは、問題解決のために皆が一緒の理解をすることではない。むしろ各人が問題に対して独自の見方を持つことが出発点なのである。お互いのものの見方を理解しようとすることが重要なのである。そこでは参加者たちそれぞれの境界に新たな理解が生まれるのであり、誰かの理解が唯一正しいものとなることはない。
• 「オープン・ダイアローグ」( 43頁)

ちっぽけで、ありふれたもの
「相手がこうすべきだ」という提案をしている限りは、参加者自身が率先して行うという気持ちを持たないままに、大がかりなことを提案するものである。彼らは問題や解決から隔たっている。別の言い方をすれば、「外側にいる」のである。だが、自分が個人的に行き詰まって抜き差しならなくなれば、自分自身でよりよい解決策を見出そうとする。自分自身の行き詰まり感が、解決を要する問題となるのである。その時、人は傍観者であることをやめる。行き詰まりを解決しなければならない問題の真っただ中にいることになったのだから。そのようなときの解決は、コミットしていない傍観者が行う提案よりもちっぽけで、ありふれたものになることが多い。(ヤーコ・セイックラ&トム・エーリク・アーンキル , p.46 )

ケース会議の基盤となるもの
「場」の設定「グラウンドルール」「ファシリテーター」「立ち位置」「目指すところの違い」

「場」の設定
• どのような雰囲気の「場」としたいのか?
• 逆にどのような「場」としたくないのか?
• どのような要素がその「場」を好ましいものとすることができるだろうか?

「グラウンドルール」
• その場の在り方を左右するベース• グランドルールとは会議、ミーティング、自助グループなどを行う際に設定することがあるルール。会議をスムーズに進行するため、ファシリテーターが会議前に設定する場合や、ある程度、大枠を決め、参加者の案も混ぜて、共に作っていく場合もある。「グランドルールを作らない」というグランドルールになるケースもある。 (Wikipediaより)

• 地位や役職などのポジションパワーは使わない。• 誰かの意見を否定しない。• 意見が異なる場合は代替案を出す。• 積極的に「話す」「聴く」• 全員がまんべんなく意見を出せるようにする。• 1人が 2 分以上続けて話さない。• 意見を出す人に偏りを出さない。• 会議の延長はせず、必ず成果を出す。• 話すべき議題が終わったら、時間前も終了にする。• 携帯電話はマナーモードにしておく。• グランドルールを破ったら、グランドルールを指指
す。• 予定以外の議題は持ち出さない。• 隣の人と小声で話さない。

「ファシリテーター」
• 所属している部署、組織に影響を受けないで、その場の在り方に貢献できる人の確保
• 解決ではなく、会話の促進を目指す• 小さな声もくみ取っていくことを目指す

「立ち位置」
• 私たちは、自分たちの立ち位置によって何を語れるのかに大きな影響を受ける。
• 何かを代表して発言することの難しさ。
• 立ち位置の変更を促すことによって、さまざまな意見がでてくる

「目指すところの違い」
• 多様性の確保• 多面的な理解の確保• 関わっている担当者たちの理解• それぞれの立場から見えるものの違
い• 「問題」が不在である場面の発見

再生産
• 〈問題〉が問題であると認める語りを繰り返すことによって、〈問題〉が維持される
• 〈問題〉に対応することは、〈問題〉の不在だけが焦点化されがちになる。
• 〈問題〉が問題でなるなるのは、〈問題〉をどのように扱えるときなのだろうか? 焦点化されるところはどこなのか?

伊佐市のケース会議指針の作成
• さて、伊佐市では、どのような指針を作成する価値があるだろうか? みんなで、グランドルール、目的、ファシリテータの活用について考え、草案を作成してみよう。

支援共同体に向けて
• いくつかの組織や個人からなる、支援共同体を維持、機能させるために必要なことはなんだろうか?–継続すること–それぞれの組織の役割を超えたところにつな
がりが生まれるということ• それぞれの立場が尊重されながらも、そ
の役割を超えた所に対して、どのように取り組んでいけるのだろうか?

Next Step
• クライエントは自分たちの問題をどう扱ったらよいのか、専門家よりも言うべきことをたくさん持っているのだ。
• クライエントのプライベート・ネットワークと専門家ネットワークとのあいだで対話を行うことで、「皆で分かち合う実践知」というべきものが生まれる。これは、従来の専門知とは質的に異なったものだ。

• 従来の専門知とは特殊な専門的知識によって現象をコントロールしようとする。しかし、分かち合う実践知では、専門家だけが問題解決のカギを握っているのではないし、他の誰かがそれを持ってるわけではない。素人の人たちもまた、実践知を作り出すことに参加するのである。(ヤーコ・セイックラ&トム・エーリク・アーンキル , p.200 )

参考図書