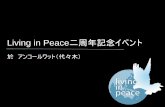50 周年を迎えたマイクロ波研究会での記念事業実施報告 ...13 4. 50...
Transcript of 50 周年を迎えたマイクロ波研究会での記念事業実施報告 ...13 4. 50...

12
【報告】
50 周年を迎えたマイクロ波研究会での記念事業実施報告 (マイクロ波研究専門委員会 前副委員長)
中津川 征士(日本電信電話株式会社)
マイクロ波研究専門委員会の活動の原点は、国際電波連
合(URSI)からの学術的検討の要請に応えるため 1955 年
に「マイクロ波伝送研究専門委員会」が設置されたことに
由来します。2015 年は、同専門委員会が設置されてから
60 年、名称を改め「マイクロ波研究専門委員会」となっ
てから 50 年の節目の年です[1][2]。表 1 に歴代の委員長名
を示します。マイクロ波の教科書で拝見するような各専門
でご活躍の方々のお名前が並んでおり、マイクロ波研究専
門委員会の歴史の重さを感じます。一方、研究専門委員会
が開催する会議名としては運営組織名から「マイクロ波伝
送研究会」、「マイクロ波研究会(MW 研)」と名称を変え
実施してきました。MW 研では、50 周年を記念し、50 年
間における MW 研の活動を振り返りつつ今後の展望を共
に語るため、2015 年 4 月から 2016 年 1 月に亘り記念事業
を実施しました[3][4]。これについて、日頃 MW 研の活動
にご協力いただいているエレクトロニクスソサイエティ
の皆様にも、この場をお借りしご報告いたします。
1. 研究会プログラム情報のデータベース化
MW 研の活動成果を誰でも参照可能とするために研究
会プログラム情報のデータベース化に取り組み、MW 研
ホームページに掲載しました[5]。発表の題目からは、導
波管から伝送線路へ、真空管から固体素子へ等、技術が発
展していく模様を読み取ることもできます。
2. マイクロ波関連施設・博物館の見学会
マイクロ波関連施設・博物館(電気通信大学 UEC コミ
ュニケーションミュージアム[6]、東芝未来科学館[7]、東
北大学電気通信研究所[8]、JAXA 相模原キャンパス施設[9])
にて見学会を実施しました。歴史を作った偉大な成果や最
新の研究内容を目の当たりにし、将来に向けた技術の流れ
を感じることができました。
3. 50 周年記念学生マイクロ波回路設計試作コンテスト
将来のマイクロ波分野を担う学生諸君に「ものづくり」
を体験してもらうことを目的に、学生マイクロ波回路設計
試作コンテストを 2011 年から実施しています。第 5 回と
なる 2015 年(試作課題:マイクロ波フィルタ)には 50
周年を記念した 50dB 減衰部門を設定し、記念すべき年を
記憶に留めるとともに、高い技術目標に向かったチャレン
ジをしてもらいました。本部門は帯域通過フィルタの減衰
域の減衰量を限りなく 50.0dB に近づけるというもので、
その結果、最優秀賞は、低域側が 49.4dB、高域側が 49.9dB
という好成績で埼玉大修士 1 年の加藤駿祈氏が見事獲得
しました。また、他の参加者からも非常に完成度が高い作
品が持ち込まれレベルの高いコンテストとなりました。
表 1 マイクロ波研究専門委員会歴代委員長 代 任 期 氏 名
初代 1966 - 68 年度 岡村 総吾
2 1969 - 70 年度 小口 文一
3 1971 - 72 年度 末武 国弘
4 1973 - 74 年度 牧本 利夫
5 1975 - 76 年度 野田 健一
6 1977 - 78 年度 西田 茂穂
7 1979 - 80 年度 熊谷 信昭
8 1981 - 82 年度 宮内 一洋
9 1983 - 84 年度 大越 孝敬
10 1985 - 86 年度 山下 栄吉
11 1987 - 88 年度 内藤 善之
12 1989 - 90 年度 米山 務
13 1991 - 92 年度 赤池 正巳
14 1993 - 94 年度 小林 禧夫
15 1995 - 96 年度 相川 正義
16 1997 - 98 年度 粟井 郁雄
17 1999 - 00 年度 水野 皓司
18 2001 - 02 年度 許 瑞邦
19 2003 - 04 年度 高山 洋一郎
20 2005 - 06 年度 荒木 純道
21 2007 - 08 年度 橋本 修
22 2009 - 10 年度 本城 和彦
23 2011 - 12 年度 大平 孝
24 2013 - 14 年度 黒木 太司
25 2015 - 16 年度 石川 容平

13
4. 50 周年記念講演会および記念式典
2016 年 1 月 15 日には、50 周年を記念した講演会と式典
をメルパルク東京で開催しました。50 周年記念講演会に
は 63 名にご参加いただき、マイクロ波研究専門委員会委
員長経験者である熊谷氏、小林氏、水野氏、荒木氏、大平
氏、石川氏から、マイクロ波から光波への研究の広がり、
当時のマイクロ波研究に関する様々な学会活動の紹介、
「マイクロ波」という言葉についての考察、マイクロ波技
術の回路的視点での考究、ワイヤレス第 3 の矢としての電
力伝送への期待、マイクロ波分野の将来展望などの視点で
ご講演を賜りました[10]-[15]。さらに、MWE の歴史展示
とも連携を図り、貴重な歴史的な資料のスライド投影で
50 年間の歴史を感じながら、50 周年を記念するイベント
として式典を実施いたしました。記念式典には 38 名にご
参加いただき、ご参加いただいた歴代のマイクロ波研究専
門委員会委員長、APMC 国内委員会委員長、APMC 実行
委員長、MWE 実行委員長、関連の深い研究専門委員会の
代表者はじめ多くの皆様より、お祝いの言葉を賜り盛況の
うちに終えることができました(写真 1)。
MW 研 50 周年という節目の年にあたり記念行事を通じ
て 50 年間の活動を振り返る機会を得ました。技術革新の
観点では、真空管が、個別部品のトランジスタを経て、集
積化されたり、半導体材料もゲルマニウムから、シリコン、
化合物へと発展したりと、各時代においてブレークスルー
が現れて、ますます発展してきた様子が見て取れます。こ
の様な技術革新は、大学・企業における研究成果の賜物に
他ならず、これらの成果を競い発表し、議論することが、
一層の研究の進展に寄与していると思われます。MW 研の
写真 1 記念式典参加者集合写真
活動を支えてきたのは、まさに多くの会員の貢献によると
ころが大きいと思います。今後も、多くの研究者が集まり、
共に語り、切磋琢磨しつつ新たな世界を創造する推進力た
る活動の場として MW 研が役割を果たしていけることを
祈念いたします。
文 献
[1] 黒木太司、信学 News Letter Vol.153, p15, July 2013.
[2] 石川容平、信学 News Letter Vol.161, p9, July 2015.
[3] 黒木太司、信学 News Letter Vol.159, p21, Jan. 2015.
[4] 石川容平 他、信学技報 Vol.115, no.391, MW2015-166,
pp.37-40, Jan. 2016.
[5] http://www.ieice.org/~mw/program/program.html.
[6] http://www.museum.uec.ac.jp/.
[7] http://toshiba-mirai-kagakukan.jp/
[8] http://www.riec.tohoku.ac.jp/.
[9] http://www.jaxa.jp/about/centers/sagamihara/index_j.html.
[10] 熊谷信昭、信学技報 Vol.115, no.391, MW2015-167,
pp.41-46, Jan. 2016.
[11] 小林禧夫、信学技報 Vol.115, no.391, MW2015-168,
pp.47-48, Jan. 2016.
[12] 水野皓司、信学技報 Vol.115, no.391, MW2015-169,
pp.49-51, Jan. 2016.
[13] 荒木純道、信学技報 Vol.115, no.391, MW2015-170,
pp.53-54, Jan. 2016.
[14] 大平 孝、信学技報 Vol.115, no.391, MW2015-171,
pp.55-58, Jan. 2016.
[15] 石川容平、信学技報 Vol.115, no.391, MW2015-172,
pp.59-62, Jan. 2016.
著者略歴:
1987 年早大・理工・電子通信卒。1989 年同大大学院・理工・
電気(通信)修士課程了。1999 年カリフォルニア工科大・工学及
び応用科学・電気修士課程了。1989 年 NTT 入社。以来、マイク
ロ波回路、ソフトウェア無線、位置情報システム、広域無線アク
セスシステム等の研究開発に従事。1998 年カリフォルニア工科大
研究助手、 2010 年 NTT 技術企画部門電波室長、2012 年 NTT ア
クセスサービスシステム研究所プロジェクトマネージャ。1996
本会学術奨励賞受賞、2002 YRP アワード受賞。IEEE 及び応用物
理学会会員。

14
【報告】
「電磁界理論研究会の活動について」 (電磁界理論研究専門委員会 委員長)
佐藤 源之(東北大学)
「電磁気学」を履修しなくても卒業できる電気・情報系
の学科があるという。最近の学部の授業では電磁気学以外
に学ばなければならない科目が増えており、何も難しそう
な電磁気学をとる必要は無いと学生が考えるのも仕方が
無いのか。しかし電気を利用した仕事をする上で電磁気学
の基本を理解しないことでどれだけ損をするかは経験し
なければわからない。一教師としては、学生にできるだけ
早くそのことを気がつかせることが重要であると考える
ようになっている。
電磁界理論研究専門委員会は他の委員会同様、総合大
会、ソサイエティ大会でのシンポジウム、セッションと年
数回の研究会を開催しているが、そのうち毎年 7 月には
(光・電波ワークショップ)として、また 1 月には(光関
係合同研究会)として、専門性の近い分野の研究専門委員
会と合同の研究会としている。加えて秋には電磁界理論研
究専門委員会の最も重要なイベントである「電磁界シンポ
ジウム」を開いている。44 回目の電磁界シンポジウムは
2015 年 10 月 29~31 日宮崎県日南海岸、名勝青島を見下
ろすホテルに泊まり込みで開催した。一般講演 46 件に加
え特別講演として「New frontiers for Maxwell's equations:
Electromagnetic modeling of lasers as open resonators with
active regions」をウクライナ科学アカデミー Alexander I.
Nosich 博士、また地元宮崎県立西都原考古博物館から東
憲章氏が「宮崎県、西都原古墳群における地中レーダー探
査の実践と GIS を利用した地下マップ制作」がお話され
た。
また数年に一度開催する日本と韓国の合同研究会 KJJC
を 2015 年 11 月に仙台国際センターで開催した。本研究会
は電磁界理論、環境電磁工学、電磁界生体影響にかかわる
分野の研究者が集い、一般の国際会議より意図的に規模を
小さくして専門性の高い研究会とすることを目指してい
る。一般講演 75 件、特別講演 2 件に韓国から 68 名に国内
参加者を加え総計 105 名の参加者があった。懇親会は松島
湾を巡る遊覧船の上で行われ、日韓研究者の親交を深めた。
KJJC を含む電磁界理論に関係する国際会議(URSI,
APSAR, PIERS)などでの発表をよりまとまった形の論文
として発行するため、本研究専門委員会では電子情報通信
学会 英文誌 特集号 "Recent Progress in Electromagnetic
Theory and Its Application" を毎年発行している。
本研究専門委員会の委員会活動は原則として、電気学
会・電磁界理論技術委員会と電磁界理論研究専門委員会が
共催で行っている。この点に関して数年来両委員会で検討
を重ねた結果、会員サービス、情報提供の観点から本年よ
り、電磁界理論研究専門委員会・技術研究報告(信学技報)
としても研究会資料を印刷・発行を行うこととしたが初年
度はスムースに新しい制度に移行できたと考えている。
最近の研究会では、電磁波の解析、散乱応用問題、アン
テナ、光導波路、光デバイスに関する解析など伝統的な問
題に加え、メタマテリアル、効率的な数値解析を行うため
の手法提案や電磁気以外の物理法則と連携した数値解析
など新しい挑戦も紹介される。一方で電磁気学の基本法則
をどのように解釈するかなどの議論も行われている。物理
の基礎から最先端の応用まで網羅する幅の広い活動を特
徴としている。
また他の研究専門委員会やURSI国内委員会との連携な
ど、活動の幅を広げる工夫を続けている。
著者略歴:
1980 年東北大・工・通信卒。1985 年同大大学院工学研究科博
士課程了。同大工学部助手、助教授を経て現在、同大東北アジア
研究センター教授。2008~2011 年東北大学ディスティングイッ
シュト プロフェッサー。1988~1989 年ドイツ連邦地球科学資源
研究所客員研究員。電磁波応用計測、人道的対人地雷検知除去の
研究などに従事。工博。2014 Frank Frischknecht Leadership Award
(SEG) 受賞。2015 電磁界理論研究専門委員会委員長。電子情報
通信学会正員、IEEE Fellow、電気学会 会員。

15
【報告】
「マイクロ波・ミリ波フォトニクス技術の新しい展開に向けて」 (マイクロ波・ミリ波フォトニクス研究専門委員会 委員長)
門 勇一(京都工芸繊維大学)
マイクロ波・ミリ波フォトニクス(MWP)研究会は、
無線通信を中心として研究開発が進められてきたマイク
ロ波・ミリ波技術と、光ファイバ通信を中核とするフォト
ニクス技術とを有機的に結合し、従来技術の枠を超える新
技術領域を開拓するため、議論の場を提供することを目的
とする研究会です。現在、委員長、副委員長及び幹事団を
含めて総勢 37 名の専門委員で構成されています。幹事団
には、「光と無線の融合や連携」を通信システム、電子航
法、及び電力システムやパワーエレクトロニクス等に応用
する研究を推進するメンバーがおります。これらのメンバ
ーが中核となり、関連する他の研究会と連携しながら、研
究会の開催、ソサイエティ大会、全国大会等におけるセッ
ションの企画、及び MWP シンポジウムの企画・開催に取
り組んでいます。本稿では今年度の活動実績と今後の活動
予定を紹介します。
研究会の開催状況については、先ず 2016 年 4 月 21 日に
テラヘルツに関連するテーマを主体に機械振興会館で開
催しました(招待講演 2 件、一般講演 6 件)。ミリ波帯・
テラヘルツ帯の標準に関する研究開発動向と光技術によ
る kHz~THz オーダーに渡る広帯域な電磁界ばく露評価
技術に関する招待講演の後、テラヘルツ波帯の信号発生と
導波に関連する技術や光技術を用いた電磁界可視化や信
号品質評価技術について議論をしました。
7 月 21~22 日には網走オホーツク・文化交流センター
にて、EMT 研、MW 研、OPE 研、EST 研との共催及び
IEE-EMT 研との連催で「光・電波ワークショップ」を開
催しました。MWP 研からは招待講演 3 件、一般講演 7 件
で貢献し、光ファイバ給電型の光ファイバ無線伝送技術や
マイクロ波無線設備、光ファイバ接続型広帯域 FMCW ミ
リ波レーダ技術、光ビート法を用いたマイクロ波・ミリ波
発生技術、コヒーレント光送受信技術等の招待講演で好評
を博し、一般講演で MWP 技術分野の最新成果を議論しま
した。
次に MWP 研の主催で予定している研究会とシンポジ
ウムについて紹介します。11 月 14 日(月)に機械振興会
館にて、「光技術を用いた無線技術」を主題にして研究会
を開催します(招待講演 3 件、一般講演 8 件)。「共鳴トン
ネルダイオード発振器を用いたテラヘルツ無線通信技術
の進展」、「バースト対応光増幅器を活用した将来光アクセ
スシステム」、及び「量子鍵配送とその高速化及び安定化
技術」に関する 3 件の招待講演、加えてテラヘルツ波の発
生から Radio-over-Fiber 技術、テラヘルツによる分光技術
と計測技術等に関する 8 件の一般講演を予定しています。
MWP 技術の新たな展開分野を開拓する目的で 12 月 9
日(金)に早稲田大学グリーン・コンピューティング・シ
ステム研究開発センターにて、「Symposium on Smart
Applications of Photonics To New Generation Power
Electronics」を、海外からの招待講演者を招いて開催予定
(招待講演 6 件、2 種研として開催)です。本シンポジウ
ムは一般社団法人・NPERC-J(1)との共催とし、主に議論
する技術領域を図 1 に示します。
図 1 MWP 技術の新しい応用展開を開拓
地球温暖化防止やエネルギーの自給自足化に向けて、発
電から送電、蓄電、消費に至る様々なレベルで電気エネル

16
ギーの柔軟で効率的利用が焦眉の課題になっています。高
性能パワー素子を用いた電力変換器、遮断器、電力ルータ
等で構成される電力ネットワークは自然再生エネルギー
源の大量導入、電力消費のピークカット、柔軟なエネルギ
ー融通、及び社会インフラとしてのリジリエンス向上等を
実現するポテンシャルを有しています。一方、高性能パワ
ー素子を用いた電源、電力変換器等は強い電磁ノイズを発
生するため、周辺装置や環境に対する影響や最新パワー素
子のゲート駆動回路そのものへの影響を低減する対策が
強く求められています。フォトニクス技術はパワー素子や
モジュールが発生する電磁ノイズの空間分布や周波数分
布を可視化する可能性、及び電磁ノイズに強く、電気的に
絶縁されたゲート駆動回路を構成する可能性を有してい
ます。本シンポジウムでは新世代パワーエレクトロ二クス
の分野で期待されるフォトニクスの応用技術のインパク
トについて、招待講演者らの講演内容を踏まえて議論致し
ます。幅広い分野からの多くの方々の参加をお待ちしてい
ます。
合同開催では年を越して、2017 年 1 月 19 日(木)~ 1 月
20 日(金)には、OPE 研、EST 研、LQE 研、EMT 研、PN
研との共催、IEE-EMT 研との連催で鳥羽商工会議所にて
フォトニクス技術を広く包含したテーマでの合同研究会
を開催予定です。
今後も 2050 年における社会的ニーズを見据えて、MWP
技術の新たな応用分野を開拓すべく、従来の細分化された
技術領域にとどまることなく、異分野の研究者を交えた魅
力のある研究発表・議論の場となるよう、引き続き活動を
行ってまいります。MWP 研究会にご興味のある方は、本
研専のホームページをご覧いただければ幸いです(2)。
(1) http://www.nperc-j.or.jp/
(2) http://www.ieice.org/~mwp/index.html
著者略歴:
1983 年東北大学大学院修士課程修了、同年日本電信電話公社
(現 NTT)厚木電気通信研究所入所、2010 年京都工芸繊維大学
大学院工芸科学研究科 電気電子工学系 教授、工博
(社)新世代パワーエレクトロクス・システム研究コンソーシア
ム(NPERC-J)理事、1990 年篠原記念学術奨励賞、2009 年日経
BP 技術賞、電波功績賞、2010 年電気通信普及財団賞、放送文化
基金賞。

17
【報告】
「ポリマーと光による革新的光部品・技術の創造」に向けて (ポリマー光部品時限研究専門委員会 委員長)
各務 学(豊田中央研究所)
ポリマー光部品(POC)時限研究専門委員会は、ポリマ
ー光回路の実用化に向けた研究開発の促進を目的とし、平
成 14 年に戒能俊邦教授(東北大)を初代委員長として発
足しました。一貫して、材料~デバイス~システム研究者
間の“フォトニクス&ポリマー“を核とした有機的交流の
場として、また分野横断での連携環境を整備する場として、
積極的に活動を続けています。
平成 26 年度より POC 研究会のスコープを「ポリマーと
光(の相互作用)による革新的光部品・技術の創造」と掲
げ、POC 研究会では、高次機能を求めているシステム/
デバイス側と、逆に、無機/半導体デバイスの限界をブレ
ークスルーするための機能付与の応用先を探す材料側の
橋渡しをすることで、革新を生むきっかけ作りを使命とし
ます。研究分野の詳細は、下記の通りとなります。
(A)産業界の求める革新ポリマー光部品・材料技術
医療用材料技術:成型加工や透明・着色制御技術
光通信用材料技術:透明、耐熱、屈折率制御技術(ポ
リマーの高次構造設計等)
太陽光発電用材料技術:太陽電池用ポリマー材料、
太陽電池エンハンストポリマー材料技術
光接続用材料技術:ファイバ接続用ポリマー材料、
自己形成ポリマー材料技術
(B)産業界に貢献する革新ポリマー技術
デバイス応用に適した革新ポリマー材料技術と、設
計・合成技術
経済性に優れたポリマー光部品実装技術
(C)光部品・サブシステム化技術
シリコンフォトニクスを始めとする異種材料との融
合可視化技術
POC 研究会はこれまで 35 回を数え、概ね年 3 回の頻度
で主催研究会を開催しております。「ポリマー光部品」と
いう比較的限定された分野がミッションですが、これ以外
の研究分野も適切に選択し、材料からアプリケーションま
でを網羅したテーマ設定を行っております。この 1 年間の
活動をまとめると次のようになります。
第 33 回 2015 年 11 月 19 日、テーマ「通信技術の歴史と
最新光通信からポリマー光デバイスまで」、NTT 武蔵野研
究開発センタ(東京)、講演数 4 件、技術資料館見学。
第 34 回 2016 年 3 月 9 日、テーマ「光インターコネクシ
ョンとポリマー材料」、産業技術総合研究所臨海副都心セ
ンター(東京)、講演数 5 件。
第 35 回 2016 年 6 月 27 日、テーマ「IoT 時代に飛躍する
『ベンチャー特集』”センサとネットワーク技術で輝きを
放て!”」、回路会館(東京)、講演数 5 件。
また、今年度は 2017 年電子情報通信学会総合大会(3/22-25、
名城大学)にて企画セッション「有機薄膜がシリコンデバ
イスの性能を飛躍的に伸ばす!」の主催を予定しておりま
す。表題にも記しました POC のスコープに沿った企画を
実践します。プログラムで日程確認のうえ、ぜひご参加く
ださい。
当時限研究会は分野横断の横串的研究とシステム応用
を扱うことが多いため、企業からの参加者が多いといった
特徴を有しています。そのため、異分野間のシナジーとな
る情報交換や、事業連携、産学連携のきっかけとなること
を強く念じております。今期(第 7 期)より本委員会の委
員長として運営に携わらせて頂きますが、これらの特徴を
活かした活動方針を基に、時代の要請も斟酌して、他研究
専門委員会や他学会との協賛などを積極的に行なう所存
です。電子情報通信学会の会員の皆様からのご提案もいた
だきながら、ポリマー光部品の発展に貢献したいと思いま
す。皆様からの忌憚のないご意見をお待ちしております。
http://www.ieice.org/~poc/jpn/welcome.html
著者略歴:
1984 年豊橋技術科学大学大学院工学研究科情報工学系修士課
程修了。三菱レイヨン株式会社勤務を経て、現在、株式会社豊田
中央研究所・主席研究員。豊田工業大学大学院連携客員教授兼務。
ポリマー通信デバイス、車載光センサ、車載ネットワークの研究
開発および国際標準化(IEC, ISO, IEEE)に従事。2008 年本会論
文賞。2016 年光通信分科会会長(自動車技術会)。

18
【報告】
「電子部品・材料研究専門委員会の活動」 (電子部品・材料研究専門委員会 委員長)
野毛 悟(沼津工業高等専門学校)
2015 年度より電子部品・材料研究専門委員会 (CPM:
Component Parts and Materials) の委員長を拝命しておりま
す野毛と申します。紙面をお借りして当研専の活動につい
てご報告したいと思います。
CPM の研究会の歴史は古く、情報通信産業の根幹を支
える電子デバイスとその材料探索を広くテーマとして抱
えております。絶縁体、半導体、磁性体に関わる部品や材
料の基礎研究から応用研究までを網羅し、多くの研究機関
や企業でそれぞれの分野に活躍されている方やその分野
に足を踏み入れた若い方々が境界を意識せずに議論でき
るユニークな研究会です。技術の進歩には異分野の複合や
融合は欠かせませんが、CPM 研究会はそのトリガーとな
る研究会を実施しております。
2015 年度にも 9 回の研究会が開催されました。先にも
述べましたが研究会が抱える範囲が広いこと、境界技術の
相互乗り入れは新しい多くの技術進歩に寄与すると期待
されるところです。とは言え、研究会での話題が広くなり
すぎると議論が薄くなってしまいます。CPM 研究会では、
研究会ごとにテーマの大枠を設定し、研究発表を募集する
ことにしております。以下、これらの研究会について簡単
にご紹介致します。
5 月:結晶成長、評価及びデバイス(化合物、Si、SiGe、
電子・光材料)およびその他
6 月:材料デバイスサマーミーティング
8 月:電子部品・材料
8 月:光部品・電子デバイス実装技術、信頼性
9 月:光記録技術、電子材料
10 月:薄膜プロセス・材料
11 月:機能性材料(半導体、磁性体、誘電体、透明導電
体・半導体、等)薄膜プロセス、材料、デバイス
11 月:デザインガイア
2 月:電池技術
上記の研究会においては、各回に主だったテーマはありま
すが、これ以外にも広く研究発表を募集しております。
本研究会ではテーマの見直しも行なっており、従来 2 月
に開催してきた電池技術については一定の方向性がみら
れたことから、新たなテーマを企画いたしました。この時
期には、大学院生などの研究もある程度のめどが立ち、研
究の振返りと次年度の研究への加速を図ってもらうため、
若手ミーティングを開催することにいたしました。「若手」
とは年齢的なくくりではなく、新規にこの分野に参画した
研究者の方々、学際領域で研究を発展させようと試行錯誤
されている方など、新たにという意味もございます。また、
一方で、諸先輩の自伝、技術や技法の「コツ」など、将来
に渡って伝承されるべき技術や研究のノウハウなども披
露して頂けるような機会にもしたいと考えております。
学会においては、研究会の活性化ということから、3 領
域の委員会が編成されました。CPM は回路・デバイス・
境界技術領域委員会の一構成委員会として今後も活動す
ることになります。これまでも多くの研究専門委員会の皆
様と共催しながら研究会を実施しておりますが、今後より
活発に共催や合同研究会ができ、多方面から多くの議論が
交わされることは大変喜ばしいことです。
異分野の研究の現場、それぞれの現場で何を問題として
いるかを知ることは極めて重要です。普段気づかない(何
となく常識と思っていたようなことがらに対して)いろい
ろな発見があり、基盤技術をどのようにブラッシュアップ
していくのがよいのかという示唆を得ることもあります。
あるいは全く新たな研究の種につながることさえありま
す。日頃、我々の研究専門委員会をベースに研究をご発表
頂いているメンバーにとっては、より刺激的な研究会活動
となるように、CPM 幹事団が知恵を絞りながら領域委員
会の活動に協力し、研究会の一層の活性化を目指したいと
思います。
最後に、CPM 研究会は研究分野の古き良き伝統を継続
しつつも、時代の変化に柔軟に対応できる研究会でなけれ
ばなりません。今後とも分野を問わず広く皆様のご指導ご
協力を頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
著者略歴:
1989 年長岡技術科学大学大学院修士課程修了、同年、神奈川工
科大学電気電子工学科助手。講師を経て、2007 年沼津高専電気電
子工学科に転出、2014 年より教授。博士(工学)。2013 年度より
CPM 副委員長、2015 年度より CPM 委員長。電子情報通信学会・
応用物理学会・電気学会・IEEE 会員。

19
【報告】
「機構デバイス研究会の紹介」 (機構デバイス研究専門委員会 委員長)
阿部 宜輝(日本電信電話株式会社)
機構デバイス(EMD:Electro-Mechanical Devices)研究
会 は 、 1962 年 に 設 立 さ れ た 機 構 部 品 ( EMC :
Electro-Mechanical Components)研究会を前身としており、
半世紀以上に亘って活動しています。発足当時は、一対の
電極の物理的接触の有無で通電を制御する電気接点を使
用したクロスバ交換機における、電気接点の信頼性が重要
な研究課題であったため、電気接点における接触・放電現
象がスコープでした。その後、通信設備における交換機は
機械式から半導体へ、伝送路も同軸ケーブルから光ファイ
バへ移行していく中で、コネクタやスイッチなどの機構デ
バイスに対する要求は多様化しており、現在の EMD 研究
会では、接触・放電現象に関する理論から材料やデバイス、
環境・信頼性、さらには微細加工技術までをスコープとし
て活動しています。特に、近年の電子機器は、デジタル化、
小型化、高速化などの点で目覚ましい発展を遂げています
が、EMD 研究会がスコープとしている電気・光信号の接
触・接続技術の着実な進歩も大きく貢献しています。更に、
最近では,MEMS などのマイクロエレクトロニクスから
ナノスケールエレクトロニクスへの技術の進展に伴う超
小型機構デバイスでの接触現象が重要な研究課題になる
一方で、自動車のエレクトロニクス化の進展や直流給電技
術の実用化への対応が求められるなど、新しい局面での基
礎研究や技術開発も活発となっており、EMD 研究会の活
動の重要性は増しています。
EMD 研究会は、毎年 10 回(4 月と 9 月は休会)開催し
ています。EMD 研究会では、信学会内の他研究会との共
催に積極的に取り組んでおり、6 月は CPM/OME、7 月は
EMCJ、8 月は LQE/OPE/CPM/R、2 月は R との共催となっ
ております。特色ある EMD 研究会としては、11 月の国際
セッションと 3 月の卒論・修論特集が挙げられます。11
月に開催する研究会は、技報の作成から発表・質疑応答を
英語で実施する国際セッション IS-EMD(International
Session on EMD)として開催しており、学生や若手研究者
が英語で発表することができる経験の場となっています。
IS-EMD は、2001 年から毎年開催しており、これまでに海
外開催を 2 度実施しており、中国などのアジア諸国や欧米
からの発表・参加もあり、国際会議の雰囲気で開催する第
1 種研究会となっています。また、3 月の研究会は、学生
の研究活動に対する活性化を図る目的で卒論・修論発表会
として開催しており、学生の皆さんに学会発表を経験して
もらう貴重な場となっております。
5 月 一般研究会(北海道・東北地区で開催)
6 月 エレソ材料デバイスミーティング(機械振興会館)
7 月 放電・EMC 特集(機械振興会館)
8 月 光部品・電子デバイス実装技術・信頼性
(北海道・東北地区)
10 月 一般研究会(関東地区)
11 月 国際セッション
12 月 一般研究会(機械振興会館)
1 月 一般研究会(関東地区)
2 月 信頼性特集(東海・関西地区で開催)
3 月 卒論・修論特集
EMD 研究会は、長い活動歴史の中において、対象とな
る研究分野を拡大しながら発展してきました。今後も、
EMD 研究会が多様な研究課題を活発な議論できる場とな
るように、研専の専門委員の皆様と協力しながら、尽力す
る所存です。
著者略歴:
1998 年九州大学大学院システム情報科学研究科修士課程修了、
同年日本電信電話(株)入社。以来、光接続技術の研究開発に従
事。現在、同社アクセスサービスシステム研究所主任研究員。博
士(工学)。電子情報通信学会会員。

20
【報告】
「IoT 時代のマテリアルサイエンスからデバイス技術の発展に向けて」 (シリコン材料・デバイス研究専門委員会 委員長)
國清 辰也(ルネサス エレクトロニクス)
今年度より、シリコン材料・デバイス(SDM)研究専
門委員会の委員長を務めることになりました國清辰也と
申します。一昨年、当時研専委員長の兵庫県立大学・奈良
安雄先生の御指名で副委員長をおおせつかり、3 年目の本
年度より委員長を務めることになった次第です。
就任当初はとまどうことが多かったですが、幹事の先生
や専門委員の皆様に助けられて、ご迷惑をおかけしながら
ここまでなんとかやってきました。SDM に関わって 3 年
目に入り、ようやく少し視野が広くなった感がございます。
当研専がカバーする各分野の発展に尽力できれば幸いで
す。
はじめは、研究会の名称からシリコンテクノロジーに特
化した専門委員会と感じていました。今年の 7 月に開催さ
れた AWAD2016 (Asia-Pacific Workshop on Fundamentals
and Applications of Advanced Semiconductor Devices、SDM、
ED 研専合同)の co-chair を任され、実際に学会を組織し
てプログラムを見てみると、シリコンに限らず、化合物半
導体からダイヤモンドまで幅広い材料・デバイスが取り上
げられ、デバイスはもちろんのこと、さまざまな物質の基
礎物性に関する研究発表があり、研専がカバーする領域の
広さを実感しました。
現在、IoT(Internet of Things, もののインターネット)
が引き起こすパラダイムシフトが予測されています。材料
科学の研究を基礎に置き、これを活かせるデバイス・プロ
セス・回路技術が発展することで、既存デバイスのさらな
る高性能化から新機能デバイスの実現につながり、最終的
には、IoT によるイノベーションに資するものと考えてお
ります。
SDM では、このような時代要請に合致する研究会を開
催しております。今年度は、4 月に「薄膜(Si、化合物、
有機、フレキシブル)機能デバイス・バイオテクノロジー・
材料・評価技術および一般」(OME と共催)、5 月には「結
晶成長、評価及びデバイス(化合物、Si、SiGe、電子・光
材料)およびその他」(CPM、ED と共催)、6 月には「MOS
デバイス・メモリ高性能化―材料・プロセス技術」(応用
物理学会 シリコンテクノロジー分科会と共同開催)をテ
ーマとする研究会を開催してきました。
また、7 月には 4 日~6 日に ED 研と合同で AWAD2016
が函館で開催されました。1993 年から日本と韓国で交互
に開催されている先端デバイスと材料を議論する学会で
今年で24回目になります。論文数の内訳はプレナリ3件、
招待講演 20 件、オーラル 55 件、ポスター 43 件で、計 121
件でした。国別内訳は韓国(64)、日本(49)、台湾(4)、
ベトナム(2)、シンガポール(1)、ドイツ(1)でした。
さらに、8 月には「アナログ、アナデジ混載、RF 及び
センサインタフェース回路、低電圧/低消費電力技術、新
デバイス・回路とその応用」(ICD と共催、ITE-IST と連
催)をテーマとする研究会が開催されました。
以上のような活動を通して、シリコン材料・デバイス分
野のさらなる発展に貢献したいと思っています。是非これ
らの研究会にご参加いただき、活発な議論がなされること
を期待しております。ご支援賜りますようお願い申し上げ
ます。
最後になりましたが、専門委員の方々、特に前研専委員
長の筑波大学・大野先生、副委員長の東北大・品田先生、
幹事の東北大・黒田先生、ルネサス エレクトロニクス・
山口様、副幹事の静岡大・池田先生には研専の運営に大変
ご尽力いただいております。この場を借りて御礼申し上げ
ます。
著者略歴:
1988 年 3 月 東京大学工学部電子工学科卒業、1988 年 4 月 三
菱電機株式会社に入社、2003 年 4 月 株式会社 ルネサス テクノ
ロジに承継転籍。2010 年 4 月からルネサス エレクトロニクス株
式会社に勤務。応用物理学会会員。IEEE EDS Senior member。専
門は半導体プロセス・デバイスのモデリングとシミュレーション。