3C Etudes - Résultats baromètre politique Tunisie, 7è vague - juillet 2012
4 + ïb* 7È0Ç í/õ Ib - 木KeyPoint · 2011. 10. 27. · Æ7c 7È (2008) fúfùf¸ 7È/Õ fÜ%&...
Transcript of 4 + ïb* 7È0Ç í/õ Ib - 木KeyPoint · 2011. 10. 27. · Æ7c 7È (2008) fúfùf¸ 7È/Õ fÜ%&...

12
木造住宅の耐震診断・補強の実務木造住宅の耐震診断・補強の実務木造住宅の耐震診断・補強の実務木造住宅の耐震診断・補強の実務
講演日 平成 23 年 2 月 16 日
場 所 (協)東濃地域木材流通センター 木 Keypoint
講 師 辻川設計事務所 辻川 誠
(スライド1)
耐震診断とは、調査と計算とございますが、
本日は診断の考え方についてご説明したいと
思います。
(スライド 2)
耐震診断とはどういうものなの、どこを耐
震診断調査するのか、報告書作成時の注意事
項、補強計画と補強方法という流れで進めま
す。実際の耐震診断では、昭和 56 年以前の建
物はほとんど補強が必要という結論にことに
なりますが、平成 12 年に木造住宅の耐震計画
の細かい規定が整備されていますので、昭和
56 年から平成 12 年までがグレーゾーンで、
私の地域で診断をすると、昭和 56 年以降の新耐震となった建物であっても診断をすると、
その多くで十分な強度が認められないのですが、国の方で急ぎたいのは、昭和 56 年以前に
建てられた建物となります。ということでは、ほとんどの建物で補強が必要ということに
なりますので、その考え方についてお話します。
(スライド 3)
近年の地震被害ということですが、兵庫県南部地震、中越沖の地震が 2 回ほどありまし
た。写真は中越沖地震の際の柏崎の商店街の写真です。店舗は、道路に対して壁が少なく、
建物全体で考えると壁の配置バランスがよくありません。またこちらは、ちょっと奥まっ
たところの住宅地ですが、玄関と南側の大きな開口、それから駐車場とで壁が全くない外
壁面が存在する建物は、何らかの影響を受けているということで、昔から大きな地震に対
2011/02/16 1
木造住宅の耐震診断・補強の実務
辻川設計事務所
木造住宅・建築物等の整備推進に関する技術基盤強化を行う事業木造住宅・建築物等の整備推進に関する技術基盤強化を行う事業木造住宅・建築物等の整備推進に関する技術基盤強化を行う事業木造住宅・建築物等の整備推進に関する技術基盤強化を行う事業
構造設計一級建築士構造設計一級建築士構造設計一級建築士構造設計一級建築士 辻川辻川辻川辻川 誠誠誠誠構造計算適合性判定員構造計算適合性判定員構造計算適合性判定員構造計算適合性判定員
平成23年2月16日平成23年2月16日平成23年2月16日平成23年2月16日 木造住宅の耐震診断法解説研修会木造住宅の耐震診断法解説研修会木造住宅の耐震診断法解説研修会木造住宅の耐震診断法解説研修会
2011/02/16 2
目次
・耐震診断とは
・耐震診断調査に関すること
・報告書作成時の注意事項
・補強計画と補強方法

13
して似た様な状態で木造住宅が倒壊してい
るという実態があります。150
0
(スライド 4)
診断は何に基づいて行なっているのかと
いうことですが、今日は基本的なことからお
話していきます。診断指針は「木造住宅の耐
震診断と補強方法」、「木造住宅の耐震診断と
補強方法の実務」という 2 冊の本があります。
これがメインになります。この指針について
の細かいQ&Aは日本建築防災協会のHPか
らダウンロードできるようになっています。
「木造住宅の耐震診断と補強方法の実務」は補強中心になっており、全国で講習会もやっ
ております。私も長野県で講師(木造住宅の耐震補強のポイントと実務講習会)をいたしまし
た。耐震診断を行なう方は、必ずこの本を手元に置いておく必要があります。
(スライド 5、6)
それから、「一般診断法による診断の実務」
は 8000 円と高価ですが、診断のプログラム
も入っているので、初めて診断をされる方は、
ここから入るとよいと思います。一般診断で
したら手計算でも可能です。ですが、補強計
画を立てるときには、いろいろな所に壁を配
置してどのくらいに耐震性が上がるかとい
うことを繰り返し検討していきます。それが
手計算だと、ちょっと壁の位置を変えただけ
で計算やり直しとなりますので、実務では 8
割以上、精密診断ではほぼ 100%の方が診断
プログラムを使用していると思います。この
本についているプログラムも含めて使われ
ていますので、ご紹介いたしました。「住宅
の普及・虫害の診断マニュアル」は、劣化に
関することが書かれていますので参考にな
2011/02/16 3
・兵庫県南部地震(1995)・新潟県中越地震(2005)・新潟県中越沖地震(2007)・岩手・宮城内陸地震(2008)
など、地震被害が相次いでいる。→耐震診断・補強の必要性
近年の地震被害
中越沖地震
中越沖地震
2011/02/16 4
・診断指針等
・木造住宅の耐震診断と補強方法((財)日本建築防災協会発行)
・木造住宅の耐震補強の実務((財)日本建築防災協会発行)
・木造住宅の耐震診断と補強方法の質問回答集((財)日本建築防災協会発行)→HPからダウンロード
2011/02/16 5
・木造住宅の耐震診断と補強方法((財)日本建築防災協会発行)
・木造住宅の耐震補強の実務((財)日本建築防災協会発行)
水色本水色本水色本水色本 茶色本茶色本茶色本茶色本
2011/02/16 6
・一般診断法による診断の実務((財)日本建築防災協会発行)
・住宅の腐朽・虫害の診断マニュアル((社)日本木材保存協会発行)

14
ると思います。1800
(スライド 7)
「木造住宅の耐震診断と補強方法」の Q&
A はこのアドレスからダウンロードできま
す。実際に実務を進めていくと、先ほどの指
針には載っていない事がたくさんあります
が、その中の多くがここに書かれていますか
ら、まず一通りこちらに目を通してから診断
をやっていただきたいと思います。
(スライド 8)
耐震診断の種類ですが、「誰にでもできる
わが家の耐震診断」は、ユーザーの方が自分
で自分の家は補強が必要なのか、診断が必要
なのかががわかるように作られたものです
から、安全ですという結論が導かれるもので
はありません。耐震診断、改修を進めていく
きっかけのひとつとして作られたものです。
そのほかに一般診断法、精密診断法とありま
して、精密診断法には精密診断法 1、精密診
断法 2 と 2 つに別れ、精密診断法 2 の中でも細かく分かれています。限界耐力計算といっ
た、関西を中心に伝統構法用で使われているものもありますが、本日は基本的なことから
ですので、一般診断法と精密診断法 1 の保有耐力診断法というところの話になります。1932
(スライド 9)
補強方法の適用範囲ということですが、在
来軸組構法、これが数多くありますが、その
他に伝統構法、それから枠組壁工法がありま
す。階数は 3 階までを扱います。混構造につ
いては、立面的な混構造に限り適用し、平面
的な混構造は適用範囲外になります。これは、
鉄骨の建物の上に木造の平屋や 2 階建てに
なって、合計 3 階になっているものは診断の
対象になりますが、平面的に鉄骨造の 2 階建
ての建物の横に木造の 2 階建ての建物が建っているような平面的に複数の構造のものが並
んでいるようなものはこの診断基準では検討できません。それはそれで、部位ごとに検討
して、ここの指針には載っていないような検討をしないといけません。20:40
2011/02/16 7
ダウンロードのアドレス
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/qaindex.html
水色本の水色本の水色本の水色本のQ&&&&A
2011/02/16 8
耐震診断の種類
• 誰でもできるわが家の耐震診断• 一般診断法• 精密診断法
精密診断法1 -保有耐力診断法精密診断法2 -保有水平耐力による方法〃 -限界耐力計算による方法〃 -時刻歴応答計算による方法
2011/02/16 9
木造住宅の耐震診断と補強方法の適用範囲
• 在来軸組構法• 伝統構法• 枠組壁工法
階数は3階までを扱う
混構造については立面的な混構造に限り適用。平面的な混構造は適用範囲外。
伝統構法伝統構法伝統構法伝統構法

15
(スライド 10)
診断法についてですが、今日お話しするこ
とは、ここに全てが集約されています。耐震
診断とは大地震動の倒壊の可能性があるか
どうかを検討するものです。中地震が来て損
傷があるかというものではありません。大き
な地震が来たら潰れてしまうだろうか、それ
だけを判断するものです。ですから壁の耐力
も、最大の大きな地震が来たときに、倒壊を
防ぐために、どの位の抵抗ができるかという
ことで決められています。建物が保有する耐力は、ここに書かれているような要素で決め
られています。耐力要素、これは在来軸組みであれば耐力壁のことですが、壁がどのよう
な接合状態になっているのか、特に古い建物では接合状態が十分でないことがほとんどで
すので、その辺を含めて考えていきます。また古い建物だと、シロアリや木材腐朽菌にや
られていることが出てきますので、劣化も考慮します。それから配置です。壁量計算は福
井地震以降ありましたが、壁の配置の規定というのが全く決められていませんでした。バ
ランスよく配置しましょうといった方向性は示されていましたが、明確なところはなかっ
たのですが、平成 12 年に、配置に関しての規定が定められましたので、そこら辺が充分で
ないことが予想されるので、それらを低減係数という形で、本来ある壁の量から出てくる
建物の耐力から低減していきます。2300
(スライド 11)
次に建物にどの位の力がかかるのかを決
めないといけません。建物の重さによって、
建物に入る地震力の大きさは変わってきま
すので、建物の仕様によって判断します。必
要耐力の決め方は、簡易必要耐力表による比
較的簡易なものと建築基準法施行令による
ものとあります。後者は建築構造設計をされ
る方が詳細に建物にかかる地震力を求める
際に使用するものです。このいずれかで計算
します。一般診断の方は比較的簡易な方法なので、面積あたりの係数をかけることで、建
物にかかる力を求めることができます。それから建物の耐震性は、上部構造の評点で表さ
れます。これは建物がどの位の耐震性があるかを示しています。(保有している耐力)と(実
際にかかる力)の割り算で、1 を上回れば安全です、1 を下回れば、保有する耐力が足りな
い、地震の方が大きく、倒壊の危険性があるという判断になります。当然その場合には補
強が必要となります。以上の「耐震診断とは 1、2」に耐震診断でやることがほとんど全て
書かれています。2500
2011/02/16 10
耐震診断とは-1
• 大地震動での倒壊の可能性について検討する。
耐力要素 接合部 劣化 ×× × 配置
何れも低減係数
【建物が持つ耐力=保有する耐力】
2011/02/16 11
耐震診断とは-2
保有する耐力 必要耐力/
【建物の耐震性=上部構造評点】
【建物に加わる地震力=必要耐力】
簡易必要耐力表による建築基準法施行令による
→→→→一般診断法、精密診断法1
→→→→精密診断法1
上部構造評点≧1.0 の場合 → 比較的耐震性がある
上部構造評点<1.0 の場合 → 補強が必要

16
(スライド 12)
次に、診断はどのようにするのかというこ
とですが、今日は一般診断法を中心に進めて、
精密診断法については一般診断法と何が違
うのかということをご説明します。まず一般
診断法ですが、耐震補強の必要性の有無を判
定するために行なわれるものです。調査の段
階ですので、建物をあまり壊すわけにはいか
ないので、基本的には非破壊調査が想定され
ています。非破壊調査の簡易な方法ですが、補強設計にこの一般診断を採用することも可
能だとしています。
(スライド 13)
必要耐力の算定方法ですが、これは通常や
っている新築の時に行なう壁量計算とほぼ
同じ流れで計算していきます。床面積あたり
どのくらいの壁が必要でしょうか、どの位の
力が加わるでしょうか、ということですから、
このように例えば平屋建てであって重い建
物であれば、0.4 という係数が定められてお
り、それに対して地域係数 Z、日本全国の地
震の起きやすさ・頻度に応じて定められた係
数です。ほとんどの地域で 1.0 です。東京も岐阜も 1.0 です。南に行くにしたがって下がっ
てゆき、0.8 や 0.7 になればその分地震力を割り引いていいということですが、通常は 1.0
です。この例ですと、係数0.4に 1.0と床面積 100㎡をかけて建物にかかる力が出てきます。
その他に各階の床面積を考慮した必要耐力の算出方法とありますが、これは精密診断法
の必要耐力の算出方法で、このように精密に出した場合も一般診断法で使うことができま
すが、標準的な計算は前者です。また下屋がある建物の場合は、後者でやった方が、地震
力が詳細に検討する分小さめに出るので、必要な補強も少なくなります。総 2 階の場合は、
どちらもさほど変わりません。
(スライド 14)
建物の仕様ですが、「軽い建物」「重い建物」
「非常に重い建物」と大体この 3 種類です。
それぞれ建物にかかる地震力を算定する係
数が変わってきて、重い建物の方が同じ面積
でも大きい地震力がかかるようになります。
従来は屋根の重さだけで決めていたのです
が、今の判断基準は屋根だけにとらわれず、
2011/02/16 12
一般診断法
• 耐震補強の必要性の有無を判定するために行われるもので、非破壊調査にて診断が可能
• 一般診断法により補強設計を行うことも可能
2011/02/16 13
必要耐力の算定方法
• 床面積あたりの必要耐力による方法簡易な方法であり総2階や平屋向き
例) 平屋建て 重い建物 床面積=100㎡地域係数Z=1.0必要耐力Qr=0.40×1.0×100=40.0kN
• 各階の床面積を考慮した必要耐力の算出法(精算法)
2011/02/16 14
建物の仕様• 軽い建物 石綿スレート、鉄板葺き
• 重い建物 桟瓦葺き
• 非常に重い建物 土葺瓦屋根
屋根の種類だけにとらわれず、壁を含めた建物全体として判断することが重要

17
壁を含めた建物全体で判断することになりました。壁が重いのであれば、屋根が軽くても
重い建物として検討する方が安全だということです。2915
(スライド 15)
必要耐力の算定における注意事項に関し
て、軟弱地盤の話ですが、地盤が軟らかいと
建物が余分にゆすられるということで、必要
耐力を 1.5 倍に割り増しします。ではどこの
地域が軟弱地盤かということですが、特定行
政庁等が指定することになっているのです
が、聞いてみますと全国で 1.5 倍に指定して
いる所は 1 箇所もないということです。です
から、法律上 1.5 倍しなければいけないとい
う地域は 1 箇所もないのですが、ただ実際に建物を診断する人は、その建物が建っている
場所が宅地造成地であったとか、昔沼であったとか、川下の海辺であるといった情報から、
個別に判断するしかないと思います。
それから、2 階建ての 1 階、3 階建ての 1、2 階については、短編長さが 4.0m 未満の場
合はその階の必要耐力を 1.13 倍するとあります。これは建物の幅が狭かったり、床面積が
小さかったりすると床面積に対して、壁の影響が大きくなってきます。また軒の出の影響
も小さな建物だと影響が大きくなりますので、その分の割り増しをしましょうということ
で決められています。3120
(スライド 16)
保有する耐力ですが、これは建物の耐力を
表しています。P は強さ、壁の強度の集計で
どの位の壁量があるのかということとほぼ
同じです。E は耐力要素の配置等による低減
ですが、壁の配置のことです。1/4 分割法を
利用してどのくらいバランスがよいか検討
しています。偏心率をちゃんと計算して判断
することもできますが、一般診断の場合は
1/4 分割法を利用することもできます。D は
劣化度による低減係数で、古い建物ですから、劣化しているでしょうというものです。3225
(スライド 17)
今あった P 建物の強さをどう算出するのかということですが、壁の耐力の合計になりま
す。C 壁強さ倍率は壁倍率と同じようなものです。1m あたりの壁耐力です。壁倍率と何が
違うのかというと、壁倍率は床面積あたりの壁率用として決められていますが、C 壁強さ倍
率は実際の強度です。1m であれば 1m の壁を押した時に、どの位の強度があるのかという
実際の強度そのものを表しています。それから建物が倒壊する時の式だけで決められてい
2011/02/16 15
• 地盤が著しく軟弱と思われる敷地の場合は、必要耐力Qrを1.5倍する
• 2階建ての1階、3階建ての1、2階については、短辺長さが4.0m未満の場合は、その階の必要耐力を1.13倍する
必要耐力の算定における注意事項
2011/02/16 16
保有する耐力
• Pd=P×E×D• Pd : 保有する耐力• P : 強さ
• E : 耐力要素の配置等による低減
係数(1/4分割、偏心率)• D : 劣化度による低減係数

18
るという点が違います。壁倍率を決めるため
に 4 つの式がありますが、その中で一番小さ
いのが壁倍率です。耐震診断では、建物が倒
壊する時の倍率で計算します。一般診断の場
合は 9.8kN/m を超える場合は 9.8kN/m とし
て頭打ちになります。ですので、どんなに壁
を補強しても 9.8kN/m 以上では計算できま
せん。lは壁の長さです。壁の長さ倍率に、
壁の長さをかけて、それから接合部による低
減をします。最近ではホールダウンなどの認定金物が出ていますので、その場合には低減
しませんが、昔は かすがい だけなどの弱い仕様でしたので、その場合には足元が抜けた
時点で壁の耐力を失ってしまいますので、低減係数をかけます。こうして Pw 壁の耐力を集
計します。その他に Pe です。これは無開口以外のたれ壁や腰壁など、計算には含めてない
けれども、地震が来たら多少は抵抗するのでしょうというのを、必要耐力の 1/4 くらいで足
しているものです。これで耐力がでます。3515
(スライド 18)
伝統構法も同じような方法で診断ができ
るようになっていますが、伝統工法は柱が太
いので、たれ壁との間でラーメン工法のよう
に抵抗できるだろうということです。柱が折
れるまでは抵抗するであろうということで
算入していますが、あまり細い柱だと折れて
しまうので、150 以上の断面であれば、耐力
に算入していいですよ、ということになって
います。3623
(スライド 19)
壁強さ倍率 C は壁の仕様ごとに決められ
ています。mあたりで何 kN まで押して耐え
られるのかということです。筋交いは、端部
の金物の有無で倍率変わってきます。金物が
なければ低めの倍率が設定されています。古
い建物では釘打ちです。右の写真は釘打ちで
すが、平成 2 年築です。新しく補強する場合
には、左の写真のように金物を入れます。
(スライド 20)
壁強さ倍率を一覧表にまとめました。これは一部です。例えば土塗り壁 塗厚 50mm
2011/02/16 17
強さ P• P=Pw+Pe• Pw : 壁の耐力Pw=Σ(C・?・f)• C : 壁強さ倍率(1m当たりの壁耐力)9.8kN/mを越える場合は9.8kN/mとする
• ? : 壁長(m)• f : 柱接合部による低減係数
fは壁強さ倍率C、基礎の仕様、壁端柱の柱頭・柱脚接合部の種類によって決まる
• Pe : その他の耐力要素Pe = 0.25Qr (Qrは必要耐力)
2011/02/16 19
• 壁の仕様ごとに決められている。単位 : kN/m
• 筋交いは端部金物の有無で倍率がことなる(15×90を除く)
• 胴縁仕様の耐力も別途定められている。• 基準法と異なり、非耐力壁も評価の対象
壁強さ倍率 C
筋かい金物有り 釘打ち筋かい
2011/02/16 18
伝統構法の場合(主要な柱の径が140
mm以上建物)
• 垂れ壁付き独立柱をPeとして柱ごとに評価(欄間は不可)
• 150mm未満の径の柱は耐力に算入しない
L

19
未満 だと 1.7kN/m、筋かい木材 30×90
端部金物あり だと 2.4kN/m、木ずりを釘打
ちした壁 だと 1.1kN/mn となっています。
3753
(スライド 21)
それから壁の接合部が金物で留められて
いるかによって、いくつか種類があります。
接合部Ⅰは告示で決められているもので、現
在の新築の基準とほぼ同じ仕様です。これだ
と低減はなく、壁の耐力がフルに使えます。
接合部ⅡやⅢとなると低減されていきます。
Ⅱは山形プレートを使った程度のもので、Ⅲ
は通し柱と通し柱の間にあるもので、ある程
度拘束力があります。Ⅳはかすがいでとめら
れたようなもので、耐震診断をするような建物は、ほとんどこのⅣになります。Ⅳだとも
のすごく低減が大きいです。接合部低減係数は 1.0~0.2 で、場所によって変わってきます
が、必ずこの接合部低減係数がかかります。
接合部の低減は、接合部だけではなく、基礎の状態によっても影響されます。基礎Ⅰと
いうのは健全な鉄筋コンクリートです。基礎Ⅱは無筋コンクリートの布基礎で、古い建物
のほとんどはこれになります。基礎Ⅲは玉石で足固めもないようなものです。昭和 20 年代
だと出てきます。玉石基礎だけで地震の際ずれてしまうという状態です。基礎はⅠが有利
でⅢになると低減が大きくなります。なぜかというと、鉄筋があると壁が持ち上がろうと
した時に基礎梁が抵抗できるからです。鉄筋がないと基礎梁が折れてしまいます。4030
(スライド 22)
耐力要素の配置等による低減係数ですが、
昔の基準では、壁量の規定はあったが、配置
の基準はなかった。冒頭の写真のように、も
しかしたら壁量はそこそこあるかもしれな
いが、一部の側に壁が足りなかったというよ
うな、極端に壁配置のバランスが悪いと倒壊
しやすいです。このように 1/4 に分割するこ
とで、左側の図ですと、X 方向に地震が来た
2011/02/16 20
壁強さ倍率とは
• 大地震時の倒壊の危険性を判断する• 終局耐力及び靱性から求まる短期許容せん断耐力を「壁強さ倍率」として用いる
工法の種類 壁強さ倍率
土塗り壁 塗厚50mm未満 1.7 kN/m
土塗り壁 塗り厚50mm以上~70mm未満 2.2 kN/m
土塗り壁 塗り厚70mm以上~90mm未満 3.5 kN/m
土塗り壁 塗厚90mm以上 3.9 kN/m
筋かい木材30×90 端部金物あり 2.4 kN/m
筋かい木材30×90 端部金物なし 1.9 kN/m
木ずりを釘打ちした壁 1.1 kN/m
壁強さ倍率の抜粋
2011/02/16 21
柱頭・柱脚接合部による壁の耐力低減係数種類 金物
接合部Ⅰ 平成12建国1460号に適合する仕様
接合部Ⅱ 羽子板ボルト、山形プレートVP、かど金物CP-T、CP-Lなど
接合部Ⅲ ほぞ差し、釘打ち、かすがい等(構面の両端が通し柱の場合)
接合部Ⅳ ほぞ差し、釘打ち、かすがい等
基礎Ⅰ:健全な鉄筋コンクリート布基礎又はベタ基礎基礎Ⅱ:ひび割れのある鉄筋コンクリートの布基礎又
はベタ基礎、無筋コンクリートの布基礎無筋コンクリートの布基礎無筋コンクリートの布基礎無筋コンクリートの布基礎、柱脚に足固めを設けた玉石基礎
基礎Ⅲ:その他の基礎
(接合部低減係数 1.00~0.20)
2011/02/16 22
• 両端1/4内の必要耐力に対する保有する耐力の充足率と床仕様により低減率を
求める。
耐力要素の配置等による低減係数(1/4分割の応用)
(一般診断法の低減係数 1.00~0.30)
1/4 1/41/2
1/4
1/4
1/2
X方向1/4分割 Y方向1/4分割
a範囲(北側) a範囲(西側)
b範囲(南側) b範囲(東側)

20
時の、上側と下側の比較をして、バランスがよいかどうかを判断します。同じように Y 方
向もバランスがよいかを判断します。これも低減係数が 1.0~0.3 まであります。バランス
がよければ、低減なしで壁耐力をフルに使え有利ですが、バランスが悪いと 0.3 まで低減さ
れます。4145
(スライド 23)
床構面の仕様ですが、壁と壁の間は床が力
を伝達します。床があまり弱いと、隣にある
壁まで力を伝達できないことになります。建
物の壁のバランスが悪い場合も、ねじれに対
して抵抗できないということで、床が非常に
大事になります。合板が貼られた床はⅠです
が、通常の診断ではⅡかⅢになります。その
他の規定としてまた吹抜けは不利になりま
す。その部分の力を伝達できないということ
で、その場合は床構面の仕様を 1 段階下げようという規定があります。4230
(スライド 24)
劣化による低減係数ということですが、屋
根葺き材、樋、外壁仕上げ、露出した躯体、
バルコニー、内壁、床について、対象の部位
が存在するか、その中で劣化があるかを集計
します。その比率を計算し低減していきます。
調査をしていると 0.63 や 0.6 になってしま
うこともあるのですが、0.7 以下にはしなく
てよいことになっています。築 10 年未満の
建物は存在点数と劣化点数の対象範囲が少
なくなるのですが、調査をするような建物はほとんど 10 年以上の建物ですので全ての項目
を調査します。4345
(スライド 25)
以上の全てが終わり、建物の壁の耐力がわ
かり、接合部の低減をし、劣化の低減をし、
配置の低減をして、最後の集計結果が出てく
るのが、上部構造評点で、耐震性能を評価す
る評点です。建物が持っている耐力と必要な
耐力との割り算です。
2011/02/16 23
一般診断に於ける床仕様(床倍率)• 床仕様Ⅰ 合板 1.0
• 床仕様Ⅱ 火打ち+荒床 0.63
• 床仕様Ⅲ 荒床 0.39
• 1辺の長さが4m以上の吹き抜けが有る場合、床構面の仕様を1段階下げる。
床構面の仕様(床仕様)
2011/02/16 24
• (1-劣化点数/存在点数)• 0.7未満となった場合は0.7とする• 築10年未満の建物は存在点数と劣化点数の対象範囲が少なくなる。但し、劣化が
認められる場合は10年以上の建物と同
等の対象範囲となる。
劣化による低減係数 D
屋根葺き材、樋、外壁仕上げ、露出した躯体、バルコニー、内壁、床について部位の存在及び劣化の有無を集計する
2011/02/16 25
� 上部構造評点=Pd/Qr
� Pd : 保有する耐力
� Qr : 必要耐力
上部構造評点上部構造評点上部構造評点上部構造評点

21
(スライド 26)
これが 1.0以上あれば一応倒壊しないと書
かけます。倒壊しないと言ってもどんな地震
が来るかわからないですから、想定外の地震
もありますから、絶対倒壊しないとは言えま
せんが、何とか 1.0 以上にしましょうという
のがひとつの目標になります。0.7~1.0 とい
うのは、明らかに壁の量、耐力が足りないと
いう状況です。0.7 未満になりますと、倒壊
の可能性が高いという表現になります。地域
によっては、1.0 以上または 0.7 以上と 2 種類に別れている場合があります。本来ならば 1.0
以上だけども、0.7 以上にすることを目標とした改修にも補助金をだすという所もあります。
(スライド 27)
いよいよ精密診断法です。これも計算の仕
方、考え方は同じですが、より細かくチェッ
クをしているという点が違うだけです。でも
これは、仕上げをはがしてやるので、現実的
ではないです。実際に精密診断をやっている
方に聞くと、本当に全部はがしてやっている
方はいなくて、一般診断法と同じような方法
でやっているようです。最終的に改修する時
に、壁をはがして劣化の状況を再チェックし、
診断内容を確認しているようです。こちらも同じように、大地震動での倒壊の可能性につ
いて検討するのは同じですが、剛性率や偏心率をきちっと計算することが違います。補強
計画の立案・補強後の耐力の検証として推奨されていますが、実際に壁がはがせないのに
精密診断でよいのか、という考え方もあるので、一般診断で補強することも可となってお
り、その方法で進める方もいます。大地震動とは、建築基準法に定める「きわめて稀に発
生する地震」のことです。4750
(スライド 28)
必要耐力についてです。建物にかかる力で、
こちらは一般診断と同じです。建築基準法に
準じて、屋根や壁や積載などの建物の荷重を
全部拾って、地震力をちゃんと出すという方
法です。2 番目は略算による必要耐力表を用
いる方法ものです。下屋がある場合は、その
影響を2階と1階との面積比率によって補正
をします。精密診断の場合は、この方法で求
2011/02/16 26
� 地盤・基礎、上部構造に分けて評価する。
� 上部構造の評点1.5以上 : 倒壊しない
1.0以上~1.5未満 : 一応倒壊しない
0.7以上~1.0未満 : 倒壊する可能性がある
0.7未満 : 倒壊する可能性が高い
総合評価総合評価総合評価総合評価
2011/02/16 28
必要耐力必要耐力必要耐力必要耐力 QrQrQrQr
� 建築基準法施行令に準じて求める方法Qi=Ci×ΣWi
Ci=Z×Rt×Ai×Co
� 略算による必要耐力表を用いる方法
� 著しく軟弱な地盤はQr×1.5
2011/02/16 27
精密診断法精密診断法精密診断法精密診断法
� 原則として、仕上げを剥がしての調査となる。
� 大地震動での倒壊の可能性について実施する。
� 剛性率による低減率がある。
� 補強計画の立案・補強後の耐力の検証に使用できる
� 大地震動とは、建築基準法に定める「きわめて稀に発生する地震」

22
めます。それから著しく軟弱な地盤は 1.5 倍します。私がやった中ではあまり 1.5 倍するケ
ースはありませんが、あまり軟弱な場合は 1.5 倍しましょうということです。4900
(スライド 29)
略算による必要耐力表を用いる方法です。
いずれかの階の短辺の長さが 6.0m 未満の場
合とあります。一般診断法では、総 2 階を想
定したものですが、これは下屋の影響を考慮
して、1 階と 2 階の床面積の違いの補正をし
た場合の値で、細かく規定されています。建
物の短辺の長さが狭いということは、壁の影
響やひさしの影響が大きくなるということ
で、狭くなればなるほど割り増しの値が大き
くなります。6.0m 以上あれば割り増ししなくてよいことになっています。必要な耐力が割
り増しということは、より厳しい診断になるということです。これはあくまで床面積あた
りの係数による略算による場合なので、ちゃんと荷重を拾って、基準法施行令に準じて計
算すれば、割り増ししなくてよいことになります。略算式でやる場合の誤差を考慮したも
のです。混構造の場合は、木造部分が振られる傾向にあるので、1.2 倍に割り増しします。
これは木造部分についてのことです。5055
(スライド 30)
保有する耐力 Qd です。これは耐力壁構造
と伝統構法などの場合の 2 種類あります。一
般診断の場合は、無開口の耐力壁だけが耐力
壁として扱われましたが、精密診断の場合は、
窓がついたたれ壁も計算して足し算をしてい
きます。一般診断の場合は 1/4 くらいの必要
耐力分だけ足しましょうというざっくりとし
たものでしたが、今度は全部足し算してちゃ
んと計算していきます。剛性率や偏心率など
と床の仕様がどうなっているのかも合わせて低減していきます。かなり詳細な検討をして
いきますので、補強壁がちょっと変わっただけで全部計算がやり直しとなると大変ですか
ら、実務ではコンピューターを使う人が多いです。伝統工法の場合も同じようにたれ壁付
の耐力壁を考慮できます。一般診断の場合は柱径が 150mm 以上ないといけませんでしたが、
精密診断では 120mm 以上であれば算入することができます。5245
(スライド 31、32)
壁の耐力は、Pw0という壁の耐力、壁強さ倍率のようなものに、壁の長さをかけて、それ
に低減の係数をかけるという、一般診断と基本的には同じです。ただ、接合部低減と壁劣
化低減のより厳しい方で耐力を出しましょうということになっています。壁一枚ごとに劣
2011/02/16 29
略算による必要耐力表を用いる方法略算による必要耐力表を用いる方法略算による必要耐力表を用いる方法略算による必要耐力表を用いる方法
� いずれかの階の短辺の長さが6.0m未満の場合は、その階をのぞく、下の全ての階の必要耐力を下表の割り増し係数を乗じた値とする
� 混構造の場合は木造部分の必要耐力を1.2倍する
1.01.151.3割増係数
6.0m以上4.0m以上6.0m未満4.0m未満
2011/02/16 30
保有する耐力保有する耐力保有する耐力保有する耐力 QdQdQdQd
� 方法1(耐力壁構造)無開口耐力壁と有開口耐力壁の耐力に剛性率による低減係数と偏心率と床仕様による低減係数を考慮する
� 方法2(伝統構法など)無開口耐力壁と垂れ壁付き独立柱(柱径120mm以上)の耐力に剛性率による低減係数と偏心率と床仕様による低減係数を考慮する

23
化を判断しなければならないので、壁を全て
はがしてみないといけないということになり
ます。開口部があいている場合には、開口部
低減係数をかけるということで、基本的には
同じような式を用います。5430
(スライド 33)
先ほどの Pw0壁基準耐力ですが、壁は中心
に軸組みがあり、その両側に面材が張られて
いるということが多く、軸組みの耐力とその
両側の面材の耐力の合算で出します。14kN/m
を超えてはならないというのが、一般診断と
の違いです。一般診断では 9.8 kN/m という
数字が出ていましたが、精密診断ではより多
くの補強した壁が、有効な壁として算入でき
るということです。
筋かいについても、一般診断では端部に金物があるかどうかで、壁の耐力自体が変わっ
ていましたが、精密診断の場合は筋かいの耐力はひとつしかなくて、それに端部の金物が
あるかどうかで低減の係数をかけてやります。5615
(スライド 34)
釘の種類や間隔が診断基準と違うことがあ
るので、それを考慮して計算することができ
ます。釘 N50 で間隔が@150 を基準とすると
@100 だともっと耐力が上がります。逆に@
200 だと耐力を低減します。釘の種類も N50
で打つところを違う種類であると低減しない
といけません。釘の種類や間隔まで調べてい
2011/02/16 31
壁の耐力と剛性壁の耐力と剛性壁の耐力と剛性壁の耐力と剛性
� 壁の耐力
Qwn=Σ(Pwo×?×min(Cf,Cdw )
Cf : 接合部低減係数Cdw : 壁劣化低減係数
有開口の場合は開口低減を考慮
Qwn=Σ(Pwo×?×Ko×min(Cf,Cdw )
Ko : 開口低減係数
2011/02/16 32
壁の剛性壁の剛性壁の剛性壁の剛性
� 壁の剛性
Swn=Σ(Swo×?×min(Cf,Cdw )
Cf : 接合部低減係数Cdw : 壁劣化低減係数
有開口の場合は開口低減を考慮
Qwn=Σ(Swo×?×Ko×min(Cf,Cdw )
Ko : 開口低減係数
2011/02/16 33
壁基準耐力壁基準耐力壁基準耐力壁基準耐力
� 壁基準耐力 Pwo 外周壁 : Pwo = Ewf + Ewo + Ewi内周壁 : Pwo = Ewf + Ewi + Ewi
Ewf : 軸組等の要素基準耐力Ewo : 外壁面の要素基準耐力Ewi : 内壁面の要素基準耐力
壁基準耐力Pwoは、14kN/mを越えてはならない木製筋かいの接合部仕様による低減係数を考慮する
(基準剛性Swoも上式にならい、耐力を剛性と読み替える)
2011/02/16 34
面材張り耐力壁の耐力修正面材張り耐力壁の耐力修正面材張り耐力壁の耐力修正面材張り耐力壁の耐力修正
� 面材張り耐力壁の耐力を修正する場合の釘間隔は実際の釘間隔が100mm以下であっても100mmより小さい間隔としてはならない。
� 面材張り耐力壁の表にない釘で打たれたものは以下とする。修正耐力=元の耐力×(実際に打たれている釘の直径/所定の釘の直径)2乗
釘の種類または間隔が診断指針の耐力表のものと異なる場合の修正

24
くには、壁全部はがさないとわからないので、実際には精密診断は容易にできないのです。
(スライド 35、36)
開口部のある壁は、開口の程度によって低
減係数がありますが、窓枠の開口なのか、掃
きだしの開口なのかによっても変わってきま
す。また開口の幅は、3m を超える場合は 3m
とします。0
(スライド 37)
一般診断と同じように、壁の接合部がどう
なっているかというのも考えないといけませ
ん。壁の耐力と比較して、柱頭柱脚の接合部
の耐力が十分かどうか。ほとんどの場合は金
物が入っておらず、補強時に施工します。
(スライド 38)
一般診断は、劣化している箇所が全体の比
率で求めましたが、精密診断の場合は、壁一
枚ごとにどこに劣化があるかという場所も特
定しないといけません。また横架材に劣化が
認められる場合は、劣化部から 455mm 以内
に含まれる部材によって構成される壁の耐力
を低減しなければなりませんが、アンカーボ
ルトがあれば、その先を低減しなくてもよい
とする特別ルールがあります。10015
2011/02/16 35
有開口耐力壁2有開口耐力壁2有開口耐力壁2有開口耐力壁2
� 開口には窓開口と掃きだし開口とがある。
� 窓開口→垂れ壁・腰壁がある開口で、開口高さが概ね600~1200mm程度のもの。
� 掃き出し開口→垂れ壁がある開口で垂れ壁高さが360mm以上のもの
(水色本P-60)
0.10.150.2掃き出し開口
0.20.30.4窓型開口
2m超(ただし、3m超は3mと見なす)
1m超2m以下1m以下開口の幅(m)
単位長さあたりの強度の比率
表4.11 開口低減係数 Ko
2011/02/16 36
開口幅開口幅開口幅開口幅
中央に柱がある場合でも連続した開口とみなす
開口幅
3mを越える場合は3mとする
垂れ壁
無開口壁
柱
2011/02/16 38
壁の劣化低減係数壁の劣化低減係数壁の劣化低減係数壁の劣化低減係数 Cdw� 横架材に劣化が認められる場合は劣化部から
455mm以内に含まれる部材によって構成される壁の耐力を低減。
� 壁一枚ごとに低減係数をかける。
を低減する範囲部材、接合部の耐力
455mm劣化部分
低滅しない
アンカ-ボルト等
土台等横架材に劣化が認められた場合の接合部、
独立柱の耐力低減範囲
2011/02/16 37
柱接合部による壁の低減係数柱接合部による壁の低減係数柱接合部による壁の低減係数柱接合部による壁の低減係数 Cf� 壁の耐力に比較して柱頭・柱脚接合部の耐力が十分か、そうでないかによって耐力を低減する。1階については基礎の仕様も考慮に入れる。
接合金物なし 接合金物あり

25
(スライド 39)
雨漏りなどの劣化があるときは、そこから
45 度で斜線を引いて、過半が含まれる壁の耐
力は低減します。部材に劣化がある場合は、
その部材につながってくる壁は、劣化してい
ると考えて壁の耐力を低減します。10115
(スライド 40)
垂れ壁付き独立柱についてですが、柱の樹
種によって耐力が異なります。それから、断
面が一般診断に比べると細い断面でも検討で
きます。
(スライド 41)
剛性率・偏心率の低減ですが、床の仕様に
応じて低減値が決まっています。皆さんもソ
フトを使うと思いますが、これは手計算では
大変です。
(スライド 42)
最終的には建物の持つ耐力と、建物にかか
る力の割り算で診断値を決めましょうという
のは、一般診断と全く同じことです。精密診
断では細かく精密に拾ったということです。
10240
2011/02/16 39
劣化の影響範囲劣化の影響範囲劣化の影響範囲劣化の影響範囲
� 劣化部を含む耐力要素
� 雨漏りが原因の劣化の場合は45°の影響線内に過半が含まれる部分の耐力要素
45°の斜線45°の斜線
耐力を低減する耐力要素
劣化部
耐力を低減する耐力要素
劣化部劣化部
2011/02/16 40
垂れ壁付き独立柱垂れ壁付き独立柱垂れ壁付き独立柱垂れ壁付き独立柱(伝統構法伝統構法伝統構法伝統構法)
� 欄間は耐力として評価しない
� 柱の樹種により耐力が異なる
� 一般診断とは耐力として算入する柱の小径が異なる。→120mm以上を評価
L
2011/02/16 41
剛性率による低減剛性率による低減剛性率による低減剛性率による低減 Fs� Fs=1.0/(2.0-Rs/0.6) (Rs≦0.6)� Fs=1.0 ( 0.6≦Rs)
偏心率と床仕様による低減偏心率と床仕様による低減偏心率と床仕様による低減偏心率と床仕様による低減 Fe� Fe = Fep × Fef
Fe : 偏心率と床仕様による低減係数
Fep : 偏心率による低減係数Fef : 床仕様による低減係数
2011/02/16 42
建物耐力の評点建物耐力の評点建物耐力の評点建物耐力の評点
� 耐力の評点=保有する耐力Qd/必要耐力Qr
評点は、階毎、方向毎に求める

26
(スライド 43)
精密診断には、コメントを書きましょうと
いうルールがあります。その中で基礎が無筋
コンクリートでは、アンカーボルトの部分に
クラックが入っていることがあります。それ
から水平構面の損傷に関する問題点の警告に
ついてですが、2 階の直下に壁がない外周壁
が 2 面以上ある、下屋があり部分 2 階建てで
2 階の直下部分に壁がないというような場合
です。10320
(スライド 44)
柱が折れる可能性があるということですが、
伝統工法の柱について、水色の本に載ってい
ますが、柱がある程度長いのに径が細いと、
折れやすいとコメントすることになっていま
す。該当するかどうかは、本に載っています
ので、コメントをしなければいけないという
ことを覚えていてください。また横架材接合
部の外れについてですが、12 畳以上の大きな
部屋があると、柱と梁のジョイント部分が外
れやすくなります。また下屋が多いと不利になります。10445
(スライド 45-52)
今度は計算のための調査の仕方についてで
す。押入れの天袋から目視で調査します。筋
交いや火打ちを見たり、木ずりや土塗り壁が
出ているかどうかを確認します。内装材がベ
ニヤでぺらぺらでは耐力は取れないのですが、
そういったことも確認します。目視調査が基
本になります。虫に食われているか、雨漏り
の劣化、筋交いの有無、内装材、接合部、羽
子板があるか等諸々の点を調査します。
2011/02/16 43
その他・各部の検討その他・各部の検討その他・各部の検討その他・各部の検討
基礎� 無筋コンクリートはアンカーボルトのところで割れやすい。
水平構面の損傷に関する問題点の警告� 2階の直下に壁がない外周壁が2面以上ある
� 部分2階建てで、2階の直下部分に壁が少ない。
2011/02/16 44
その他・各部の検討その他・各部の検討その他・各部の検討その他・各部の検討
柱の折損(垂れ壁付き独立柱)� 水色本 P-82の表4-29で網掛け部分に該当する柱が有る場合は曲げ破壊が生じる可能性がある
横架材接合部の外れ� 12畳以上の大きな部屋がある
� 母屋部分より、下屋部分に壁が多い
L
2011/02/16 45
・耐震診断調査に関すること
2011/02/16 46天袋からの目視調査天袋からの目視調査天袋からの目視調査天袋からの目視調査(小屋組み・小屋組み・小屋組み・小屋組み・2階床階床階床階床下下下下)

27
(スライド 53-58)
2 階の床下も同じように、押入れの天袋か
ら覗きます。羽子板などの金物や筋交い、木
ズリ、内装材、水平構面、床組みの状態など
を確認します。ユニットバスの上からも覗く
事ができます。また面材の厚さを調査します。
コンセントボックスで、仕上げの厚さを確認
できます。そうやって内装面材の調査をしま
す。土塗り壁の場合は、ちり寸法などから逆
算します。10740
2011/02/16 50
・小屋裏の調査
・小屋組み等の状態(雨漏りや劣化の有無)・水平構面の状態(火打ち梁の有無と量)・耐力要素の確認筋交いの有無と取り付け状態木ズリ等の確認内装材の仕上げ厚さ確認柱梁接合部の確認(羽子板ボルトの有無)
2011/02/16 51天袋からの目視調査天袋からの目視調査天袋からの目視調査天袋からの目視調査(2階床下階床下階床下階床下)
2011/02/16 52羽子板ボルトの確認羽子板ボルトの確認羽子板ボルトの確認羽子板ボルトの確認(2階床下階床下階床下階床下)
2011/02/16 47天袋からの目視調査天袋からの目視調査天袋からの目視調査天袋からの目視調査(小屋組み小屋組み小屋組み小屋組み)
2011/02/16 48下屋部分下屋部分下屋部分下屋部分(小屋組み小屋組み小屋組み小屋組み)
2011/02/16 49垂木の食害垂木の食害垂木の食害垂木の食害
2011/02/16 53
・2階床下調査
・床組み等の状態(劣化の有無)・水平構面の状態(火打ち梁の有無と量)・耐力要素の確認筋交いの有無と取り付け状態木ズリ等の確認内装材の仕上げ厚さ確認柱梁接合部の確認(羽子板ボルトの有無)

28
(スライド 59-67)
それから柱の傾斜を測定します。そして間
取りなど図面との整合性をチェックします。
増改築が繰り返されていて、新築時の図面は
そのまま使えません。次に外壁や基礎のクラ
ックを調査します。鉄筋探査機による調査も
します。基礎掘削は、底盤があるかどうか、
そして深さを調査しています。不動沈下をし
ていると十分な底盤がない場合が予想されま
す。外壁に浮きがないかも調べます。1 階床
下の目視調査をします。根がらみがあるか筋
かいがあるかどうかもわかる場合があります。
2011/02/16 59柱傾斜測定柱傾斜測定柱傾斜測定柱傾斜測定
2011/02/16 57面材の目視調査面材の目視調査面材の目視調査面材の目視調査
2011/02/16 58
・内装面材の調査
・ラスボードの厚さの確認(9mm未満は耐力算入不可)・化粧合板の厚さの確認(5.5mm未満は耐力算入不可)・土塗り壁の厚さの確認(ちり寸法などから逆算)
2011/02/16 54ユニットバス点検口からの目視調査ユニットバス点検口からの目視調査ユニットバス点検口からの目視調査ユニットバス点検口からの目視調査
2011/02/16 55面材の目視調査面材の目視調査面材の目視調査面材の目視調査
2011/02/16 56

29
2011/02/16 64外壁のひび割れ及び浮き調査外壁のひび割れ及び浮き調査外壁のひび割れ及び浮き調査外壁のひび割れ及び浮き調査
2011/02/16 651階床下の目視調査1階床下の目視調査1階床下の目視調査1階床下の目視調査
2011/02/16 661階床下の状況1階床下の状況1階床下の状況1階床下の状況
2011/02/16 671階床下の状況1階床下の状況1階床下の状況1階床下の状況
2011/02/16 60建物と図面との整合性のチェック建物と図面との整合性のチェック建物と図面との整合性のチェック建物と図面との整合性のチェック
2011/02/16 61クラックスケールによる基礎ひび割れ調査クラックスケールによる基礎ひび割れ調査クラックスケールによる基礎ひび割れ調査クラックスケールによる基礎ひび割れ調査
2011/02/16 62鉄筋探査機による調査鉄筋探査機による調査鉄筋探査機による調査鉄筋探査機による調査
2011/02/16 63基礎掘削調査基礎掘削調査基礎掘削調査基礎掘削調査




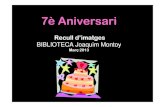




![` Û / ! /+Ë* 7È/õ I d ¦ 0¿0£ W `0Y ( 0¿0£ ¦ » d 7Á ¼0¿ …...` Û / ! /+Ë* 7È/õ I d 0¿0£ W 7Á ¼0¿ "I0 Ù ] i>&>/>' 16 (>+ `0Y ( 0¿0£ » d 8 W >ÿ>ï>í>ø>ñ](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5edeee62ad6a402d666a4aaa/-7-i-d-00-w-0y-00-d-7-0-.jpg)









