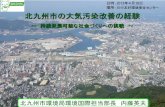新型インフルエンザ等対策ガイドライン6 オ)死亡・重症患者の状況の把握 新型インフルエンザによる全ての死亡者・重症患者の把握を、一定数に
3学修成果の把握とその活用 - 河合塾の大学 ...Kawaijuku Guideline 2014 特別号 39...
Transcript of 3学修成果の把握とその活用 - 河合塾の大学 ...Kawaijuku Guideline 2014 特別号 39...

37Kawaijuku Guideline 2014 特別号
Part.3 学修成果の把握とその活用
学生が受講した授業について評価したり、学生の意見を聞いたりすること。アンケート調査の形式で行われることが多い。大学では、結果を教員にフィードバックして教員個人や組織としての授業改善に役立てたりしている。また、「この授業を通して、どのような力を養うこと
ができたか」などの質問項目を設けることによって、学修成果の把握に活用できる点も注目されている。最近では、卒業生への授業評価アンケートを実施する大学も増えている。大学教育が社会に出てからどのように役立ったのかを知り、大学教育の改善に生かす狙いがある。
授業評価
Part.3学修成果の把握とその活用
キーワード
CONTENTS
◆キーワード…………………………………… P.37◆大学選びのポイント………………………… P.39◆大学の取り組み学習院大学文学部 …………………………… P.40京都工芸繊維大学 …………………………… P.42國學院大學経済学部 ………………………… P.44京都光華女子大学 …………………………… P.46立命館大学 …………………………………… P.48龍谷大学文学部 ……………………………… P.50金沢工業大学 ………………………………… P.53東北大学工学部 ……………………………… P.56
大学教育における学修成果の把握といえば、以前は、
卒業論文・卒業研究が代表的なものであった。しかし、
現在は、大学教育を通じて育成するものは、卒業論文・
卒業研究に代表される専門的な知識・能力だけでなく、
「知識・理解」「汎用的技能」「態度・志向性」「総合的な
学習経験と創造的思考力」などから成る「学士力」も必
要であるという考え方が打ち出されている。こういった
能力がきちんと修得できているかを把握し、成績評価や
卒業認定の基準に含め、厳密に評価することで、大学教
育の質を保証することが、いま大学には求められている。
▼授業評価の具体例 東洋大学 入学時と卒業時に、全学で統一した授業評価アンケートを実施。入学時には大学生活の目標、学びたいこと、身につけたい能力など、卒業時にはその入学時の目標が
どれぐらい達成できたか、どんな能力を身につけることができたか、あるいは目標が達成できなかったことは何かなどを確認し、学生の学修成果の把握に努めている。
大学における学びは、授業の受講だけではなく、学生の自主的、主体的な学びも重要になる。そこで、学生の学修時間や学修に対する関わり方をアンケート調査した
り、ポートフォリオなどの学修記録などを活用したりすることによって、学修状況を把握する試みも行われている。
学修状況調査
▼学修状況調査の具体例 島根大学教育学部 学生の成長を把握するための「プロファイルシステム」を採用。①自分のGPAを、学年の平均得点との比較によって、自己点検を実施。②学部が設定した教師力の育ちに関わる項目(学校理解、子ども理解、授業評
価力、授業企画力など)の学生による自己評価。これらが学年ごとにどう推移していったか、また項目のどこが強いか(弱いか)などの把握。③地域の学校や諸施設における各学生の体験学修の時間集計や、その内容の把握、の3つで構成されている。

38 Kawaijuku Guideline 2014 特別号
卒業論文・卒業研究は、主に最終学年の1年間程度を使って、研究成果を論文などにまとめるものである。大学での学修成果を集大成する機能を果たしている。その
学生の学修や、教員の教育実践などについて、学修(授業)計画表や、レポート、作品、成績表など、学びの状況を記録・蓄積したもの。学生自身が自分の学修成果を振り返ることができるようにするとともに、教員や
審査においては、一定の水準を満たしているかどうかをチェックするために、複数の教員による査読や、口頭試問などを課している場合が多い。
職員と共有し、学生への履修指導、就職・進学支援などで活用するほか、組織的な教育改善に役立てる大学・学部もある。また、ウェブ上で記録できる大学もある。
卒業論文・卒業研究
ポートフォリオ
▼卒業論文・卒業研究の具体例 大谷大学 卒業要件として、卒業論文の提出と口述試問
▼ポートフォリオの具体例 長浜バイオ大学 学生・教員が双方向に使用している「バイオ学習ワンダーランド」では、授業プリントがツール内より取得でき、また日々の授業の出席状況や単位修得状況が把握できるようになっている。日々の大学生活の中で学生
を全学科で課している。口述試問では、指導教員が主査、専門分野の教員が副査となり、卒業論文の内容を掘り下げている。
自らが自分を取り巻く学習状況を把握できる工夫を凝らしている。さらにポートフォリオには自らの学習状況を確認して振り返りを記入。ポートフォリオを確認しアドバイスを行う担当者であるスーパーバイザーからのコメントが学生生活の励みになっている。
学内にある多様な教育情報を一元的に収集し、分析することで、大学としての計画の立案や意思決定などを速やかに行うことができるようにする組織を作る大学が増えている。学内にある客観的なデータを集め、それに基
目標に準拠した評価のための基準づくりに関する方法論であり、学習者が何を学修するかを示す評価規準と、学習者が到達しているレベルを示す具体的な評価規準を、マ
づいた意思決定を行う動きだが、まだ過渡期にあり、IRを担当する部門・人材、具体的に取り組む内容、収集・分析したデータをどのように活用するかについて、模索が続いている。
トリックス形式で表示したもの。事前に明示した目標に準拠した観点について、何ができればどの段階にあるのか、具体的に記述されているところに特徴がある。
IR(Institutional Research=機関調査)
ルーブリック
▼ルーブリックの具体例 大正大学 2013年度よりルーブリック評価を1年生の基礎ゼミ科目(それに準ずる科目)に対し導入した。事前に
FD活動によりルーブリックの研修会を実施し、基礎ゼミ科目以外でも教員の判断によりルーブリック評価を導入している。
トテスト(学生をその学力や能力・スキルに応じてクラス等に分けるための試験)を実施し、学習状況(GPA値)との相関を見ることで、学修成果の把握に役立てている。
▼IRの具体例 神戸親和女子大学 学生の個人データ(入試状況、学習状況、プレイスメントテスト結果、属性など)をシステムで管理し、分析している。例えば、学年はじめにプレイスメン

39Kawaijuku Guideline 2014 特別号
Part.3 学修成果の把握とその活用
2008年12月に公表された、中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」では、大学卒業までに身につけるべき能力として、新たに「学士力」という考え方が打ち出され、注目を集めた。さらに「学士力」をきちんと修得
できているかどうかを、成績評価や卒業認定の基準に含め、厳密に評価することによって、卒業生の質を保証することが提言されている。この背景には、大学進学率が上昇
して、多様な学習歴の学生が入学するという高等教育が「ユニバーサル化」した状況がある。これまで、大学を卒業すれば、ど
の大学であっても、「学士」として一定水準以上の能力を有していることが保証されていると考えられてきたが、「ユニバーサル化」した状況では、大学に対して質の保証を求めなければ、日本の「学士」に対する世
界的な評価を得るのは困難と考えられるようになってきた。そのため、大学ではGPAを利用し
た成績評価や卒業基準の厳格化が進んでいるが、学生にとって納得できる評価の在り方が確立されているとは言えない状況である。そこで、現在、多くの大学で取り
組んでいるのが、学生の学修成果の把握である。それも、学期末の試験やレポート、卒業時の卒業論文・卒業研究の内容や水準など、1回の試験や1度の提出物で学修成果を測定するのではなく、学生の自学自習を含めて、日々の学びを総合的に見て、学修成果を把握しようという取り組みである。例えば、アンケート調査を実施し
たり、ポートフォリオを導入して学修状況を記録させ、それを教員が情報共有して指導に役立てたりといった内容だ。そうして収集した情報を
分析して、客観的な視点で教育改善につなげるIRの部局を設置して、組織的に取り組む大学も増えつつある。また、教員もルーブリックなどを活用して、評価基準を定め、共有化する試みも増えている。とはいえ、学生の学修成果の把握は、まだ始まったばかりだ。大学の取り組みと、それが大学の教育改善に生かされているのかをチェックすることが重要になる。そして、学修成果の把握の前提となっているのが、教育課程を体系的に編成してそれを明示しているかである。さらに学生に充実した大学教育を行い、教育の質を保証しようとしているか、それに伴って、留年・中退者が増える可能性があるが、基準を満たしていない学生を支援する仕組みを備えているかどうかが、大学選びのポイントの1つとなるだろう。
学生が納得できる質の保証となっているか
大学選びのポイント
学生の成績評価方法の1つ。アメリカやヨーロッパの大学・高校では以前から用いられている。一般的な仕組みは、学生の成績を5段階で評価し、それぞれに4~0のグレードポイントを与えるというもの。A=4(点数でいうと100 ~ 90)、B=3(89 ~ 80)、C=2(79 ~
70)、D=1(69 ~ 60)、E=0(59以下)で換算する。その平均値がGPAである。進級判定や卒業判定、退学勧告の基準として用いている大学はそれほど多くなく、多くの大学では、学生に対する個別の学修指導や、奨学金や授業料免除対象者の選定基準として活用されている。
GPA(Grade Point Average)
▼GPAの具体例 千葉大学 2004年度からGPA制度を導入している。普遍教育では、2007年度から普遍教育科目の成績評価の状況(人数、割合)およびクラス平均(GPCA)を一覧にまとめ、委員会等を通じて教員間で情報共有や現況確認を行うことを通じて、成績評価の適正化に努めている。 青森公立大学 開学時からGPA制度を導入。この制度
は、「教育に責任を持ち、社会に対して教育の質を保証する」という本学の教育理念に基づき実施している。一定の学力水準(GPA2.00)に満たない者を成績不振者として注意喚起や面談を行っている。4学期(2年間)連続してGPA2.00未満の状況が続き、かつ累積GPA(これまでに履修した科目全てのGPA)2.00未満となった学生には、「退学勧告」を行っている。
(各大学の具体例は、2012 年度・2013 年度の「ひらく 日本の大学」調査への回答に基づく)

40 Kawaijuku Guideline 2014 特別号
学習院大学文学部複数の教員が査読する卒業論文のほか日本語日本文学科では卒業試験も課す
学習院大学文学部では、全学科で卒業論文に相当するものを必修とし、査読や口頭試問も2~3名で実施するなど、充実した指導を実施している。特に、日本語日本文学科では卒業論文のほか、学科の卒業生なら当然身につけておくべき知識の修得を確認するために、他の文学部ではあまり見られない卒業試験も古くから課している。
日本語日本文学科では卒業試験を実施合格しないと再試験や課題を課す
学習院大学文学部日本語日本文学科では、古くから卒業試験が行われている。いつから行われているかは正確には不明だが、日本語日本文学科の伝統になっている。実施されるのは、例年1月中旬~下旬のうち1日で、
日本語日本文学系の学生は7科目(そのうち4科目選択)、日本語教育系の学生には4科目が課される<図表1>。試験時間は90分で、その時間内で全科目の問題を解く。問題作成や採点は同学科の教員が担当している。出題内容は、例えば「日本語学」では「比較言語学と
対照言語学の違いについて簡単に説明しなさい」といった問題が5題出される。「変体仮名」ならば、江戸時代の版本を見て、その一部を読みくだす。また、漢字の書き取りも課される。同学科では、学生全員に『新選総合漢字問題集』(川鍋義一・小秋元段編、おうふう)を配布しており、1~2年次に年2回、必修科目の「基礎演習」の授業の中で、出題範囲を設定して試験を実施している。卒業試験はその総復習の場になっている。いずれの科目も、大学で学ぶ日本語・日本文学の基
本的な知識が中心だが、科目ごとに基準点が設けられており、それに合格しなければ再試験を受けることが義務づけられている。数年前までは、全員が全科目を合格するまで何回も試験が実施されていたが、何回も不合格を繰り返す学生もいたことから、現在は再試験までとなっている。再試験に不合格になった場合は課題が与えられ、レポートを提出する。甘くなったようではあるが、その課題は卒業論文を仕上げるのと同じくらいハードな内容
で、しっかり取り組まなければ卒業を認めない仕組みになっている。そのため、日本語日本文学科の学生たちの間では、12月下旬に卒業論文を提出した後も、卒業試験に向けた準備に入るのが当然といった雰囲気が醸成されているそうだ。日本語日本文学科では、その授業は単純に知識を伝授する場ではなく、日本の多様な文化現象を取り上げ、その構造やシステムなどについて自分なりの考察を加える場である。そうした自分独自の理論、見解の集大成が卒業論文であり、4年間の学修成果を問う最大の評価軸になっている。その一方で、日本語日本文学科の卒業生なら当然身につけておくべき知識がしっかり修得できているかを確認するために卒業試験を取り入れているのだ。そして、学生は、卒業試験対策の学修をすることで、大学院入試でも強みを発揮していると言う。
<図表1>日本語日本文学科卒業試験の内容
日本語日本文学系
漢字書き取り古文解釈変体仮名日本語学言語学文学史(古典)文学史(近代)
<文学史の区分>古典=上代~近世近代=近代~
日本語教育系
漢字書き取り日本語学言語学日本語教育学

41Kawaijuku Guideline 2014 特別号
Part.3 学修成果の把握とその活用
教員全員で口頭試問を行う学科もあり重圧を跳ね返せるだけの深い考察が求められる卒業論文
学習院大学文学部では卒業論文も重視し、充実した指導体制がとられている<図表2>。指導教員1人に加えて、2~3名(学科によって人数は異なる)の教員が査読し、口頭試問を実施する。史学科のように、学科の教員全員で口頭試問を行う学科もある。ずらりと並んだ教員の前で、さまざまな角度からの質問に対応しなければならないため、学生には相当な重圧がかかる。それを跳ね返せるだけの深い考察が要求されているわけだ。なお、卒業論文の指導教員は原則として学生が選ぶこ
とができるが、査読する教員は、テーマを見てそれに適した教員を大学で決める。指導教員は1年間、オフィスアワーのように相談時間を設定し、その時間は研究室にいることが義務づけられている。卒業論文では、学生が袋小路に迷い込んで、次の方向性が見出せなくなることもあり、適宜相談に応じて適切なアドバイスを送ることによって、それを防いでいる。また、卒業論文の評価は100点満点で点数化され、50
点以上が合格となる。相当厳格な評価が行われており、日本語日本文学科を例にとると、「優」の成績の学生は3割程度だという。学科で共通の評価基準は特に定めず、査読する教員の裁量に任されている。独創性を重視する教員もいれば、関連する研究書を読み込んで、じっく
り実証するスタイルの論文を高く評価する教員もいるが、それでも優れた論文は、どの教員が読んでも高く評価されるもので、最終的な点数が大幅に違うということはほとんどないということだ。
積極的に議論に参画するパワーが薄れており今後は授業方法の工夫も必要に
文学部においては、他学部以上に卒業論文が重要になる。文学部で学ぶ学問は、他学部のように体系的に積み上げていくのが困難だ。教員個人の個性が色濃く、教員の数だけ方法論と学問体系があるといっても過言ではない。そうした学問の特性の中で、学生は4年間の学びで何を身につけるべきなのか。世の中の動きに付和雷同することなく、一歩立ち止まって自分なりの理論、見解を打ち立て、それをもとに周囲の人々と議論できる力を養うことを最終目標とするならば、卒業論文はその力を高める場でもある。このように、充実した卒業論文の指導体制になっているが、自分なりの理論や見解を打ち立てるのに有効だと考えられる演習形式の授業が豊富であるにもかかわらず、学生が積極的に議論に参画しようとする意欲や自己主張が薄れている点が課題である。学生にもっと積極的に発言する姿勢を身につけてもらうために、授業方法の改善も必要になると考えられる。
(2013 年度 大学履修要覧より)
<図表2>学習院大学文学部「卒業論文規定」
(1) 学生は最終年次において卒業論文(フランス語圏文化学科にあっては卒業翻訳を含む)(12単位)を提出しなければならない。
(2) 各学科とも、卒業論文(フランス語圏文化学科にあっては卒業翻訳を含む)の題名届は、指導教授を定め研究室を通して6月30日(日曜日の場合には7月1日、土曜日の場合は7月2日)までに学生センター教務課に届け出なければならない。
(3) 卒業論文(フランス語圏文化学科にあっては卒業翻訳を含む)は12月20日(日曜日の場合には12月21日、土曜日の場合は12月22日)午後4時までに学生センター教務課に提出しなければならない。期限に遅れた場合はいかなる理由があっても受理されない。
(4) ドイツ語圏文化学科にあっては卒業研究(4単位)と卒業研究指導演習(8単位)をもって、フランス語圏文化学科にあっては卒業演習(12単位)をもって卒業論文にかえることができる。
(5) 英語英米文化学科にあっては卒業研究(4単位)と卒業研究演習(8単位)をもって卒業論文にかえることができる。

42 Kawaijuku Guideline 2014 特別号
京都工芸繊維大学専門技術者が備えておくべきリテラシーの習熟度を評価する「KITスタンダード検定」を実施
京都工芸繊維大学は、京都高等工芸学校および京都蚕業講習所に端を発する110年あまりの歴史を持つ、工芸科学部1学部の工科系大学である。バイオ、材料、電子、情報、機械、環境などの先端科学技術分野から建築・デザインまでの幅広い分野において、ものづくりを基盤とした「実学」をめざした教育研究を行っている。
大学の独自性を踏まえてリテラシーを抽出
京都工芸繊維大学では、2009年度から21世紀知識基盤社会を担う専門技術者が備えるべき知識・技能を「KITスタンダード」として体系的に整理し、その内容を修得する教育プログラムをスタートさせている。大学卒業後、学生たちが働く社会では、大学で専攻し
た分野だけでなく、幅広い分野の知識が要求される。そのため、社会のニーズに対応できる能力を養成した上で、卒業させることが大学の責務となる。そこで、卒業生が数多く就職している企業などに、今どのような分野の知識が必要とされているのか、アンケート調査を実施するとともに、学域構成の特色を加味して、「遺伝子」「環境科学」「ものづくり」「造形感覚」「知的財産」の5つのリテラシーと、基礎科目の「英語」「数学」を21世紀理工系学生が備えるべきリテラシー(事象を理解・整理し、活用する能力)として抽出し、学生が卒業までに備えておくべき「KITスタンダード」として設定した。カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーに、在学
中にどのようなリテラシーの養成をめざすのかを明示している大学は多い。だが、特徴的なのは、学生個々の各リテラシーの習熟度を計数的に評価するために、「KITスタンダード検定」という独自の検定制度を導入していることである。それによって、学生一人ひとりの能力を外部に向けて客観的に示すことが可能になっている。履修の流れは、前期科目の「KIT入門」でKITスタン
ダードや検定について理解を深めた後、受検を希望する学生は、後期科目で「KITスタンダード」を登録する。過去問に取り組みながら各リテラシーの基礎を学ぶとともに、リテラシーを高めるためにはどのような関連科目の受講が有効なのかという履修指導の役割も兼ねている。
ICT技術を駆使した受検システムを確立
「KITスタンダード検定」は、年1回(12 ~1月)の実施で、1つのリテラシーから20問出題され、12問以上正解で合格になる。3つのリテラシーで合格すれば1単位、5つすべてに合格した場合は2単位が付与される。3つのリテラシーを16問以上正解すれば「S」、14~15問正解は「A+」、それ以外は「A」評価になる。1年次配当の科目だが他学年の受講も可能で、在学中に何度でも挑戦でき、最も高い得点を成績とすることができる。また、この検定試験は教職員が協力して推進している点も注目だ。問題を作成するのは教員で、すでに各リテラシー 160~310題が蓄積されている。検定当日の運営を担当するのは事務職員で、ICT技術を用いた新しい試みである。例えば受検申し込みは携帯電話で行い、当日は代理受検を防止するための本人確認として、着席後本人しか知り得ない情報をランダムに質問して携帯電話を用いて回答させる。出題はパワーポイントの問題をスクリーンに映写し、クリッカー(無線型小型回答機)で回答。受検者からの回答はデータ集計機を通じてデータベースに蓄積されるため、採点業務も省力化されている。
検定に向けた自学自習環境を整備英語版の過去問集も作成
もう1つ、特筆すべき点は、学生に自主的な学修を促すため、検定試験に向けた自学自習環境が整えられていることである。附属図書館には「KITスタンダードコーナー」が開設され、5つのリテラシーへの理解・関心を深めるための書籍が備えられている。また、過去問に挑戦し、自己採点できる「自学自習Webシステム」も構

43Kawaijuku Guideline 2014 特別号
Part.3 学修成果の把握とその活用
築されている。Web上で公開されている過去問は、日本語版だけでなく、英語版もある。外国人留学生に対しても、英語版により自学自習シス
テムの活用を試行的に行っている。また、英語版の過去問は日本人学生にとっても大きな意義がある。国際的高度専門技術者には英語力が不可欠であり、日本語と英語の問題を見比べながら勉強することによって、英語力の向上につなげ、将来的には英語版の検定試験を課しても十分に対応できることが理想だという。さらに、検定合格のための対策セミナーも実施されて
いる。実は、検定がスタートした当初、リテラシー間の問題の難易差が大きく、合格率に差が生じていた。そこで、問題の標準化を図るとともに、特に合格率が低かった「ものづくり」「知的財産」に関しては、企業の第一線の技術者などの外部講師を招いたセミナーを開講している。学生の参加意欲も旺盛だ。なお、5つのリテラシーについては検定が実施されて
いるが、「英語」「数学」の2つの基礎科目に関してはそれとは別の教育プログラムが用意されている。まず「英語」は、学生が個別にパソコンを利用したオンライン英語学習システムの導入や、英国・豪州への短期英語研修、英語教員によるオフィスアワーなど、学生の継続的な自学自習を体系的に支援している。TOEIC、TOEFL、IELTS(注)による到達目標も示されており、学生のスコアに応じて単位が与えられる。「数学」は、「線形代数」「微分積分」「数学演習」など、授業科目ごとに、最低限解けるようになってほしい問題を網羅した「KIT数学ガイド」が入学時に配布される。各数学科目の全体像や、学修の到達目標などを把握することができる冊子である。
学生はこのガイドに基づいて自学自習を進めていくが、高校までの数学と大学で学ぶ数学の接続がうまくいかない学生も見受けられる。そんな学生のために設置されたのが「数学サポートセンター」である。大学院生と、数学の成績が優秀な3年次以上の学部生から「数学サポーター」を募り、一定時間帯に質問の受付や、数学の学習法のアドバイスを行う。学生にも好評で、延べ利用者数は、大幅に増加している。
検定により学生の学修意欲が高まる受検率のアップを図ることが今後の課題
では、「KITスタンダード検定」が、学生の学修成果の評価の上でどのように有効に機能しているのか。この検定だけで学生の卒業時の質を保証できるわけではなく、特に理工系では、演習・実習を通して高められる能力も重要である。例えば、フォトモザイクやロストワックスなどの制作を通じて、科学的なアプローチと芸術的なアプローチを同時に体験する「科学と芸術の出会い」、藍染などの京都の伝統工芸を実体験する実習など、特色ある大学教育支援プログラム(特色GP)にも採択された実践的なプログラムが豊富に用意されている。それらを含めたカリキュラム全体で、総合的な力をアップさせることが重要となる。その成果の一例として、2010年11月に米国マサチューセッツ工科大学で開催されたiGEM(国際遺伝子改変マシーンコンテスト)世界大会において、「大腸菌でアートを描く」というユニークなテーマで臨んだ京都工芸繊維大学チームが、130チーム中最も高い評価を得たチームのみに授与されるベストポスター賞を受賞している。このように、学生が「KITスタンダード検定」を意識することによって、学修意欲が高まる効果が見られており、質保証の1つの手段になると考えられている。実際、「自学自習Webシステム」へのアクセス数は飛躍的に増加しており、リテラシー修得のための学習に自主的に取り組む学生が増えている。しかし、課題も残されている。「KITスタンダード検定」は必修ではないこともあって、受検者数が伸び悩んでいる。また、いったん単位を取得してしまうと、より高い成績評価にするためにという目的で再受検する学生はあまり多くないのが実情である。検定の成績上位者を表彰するなど、受検率をアップさせるための戦略を立案することが今後の課題になるだろう。
<写真>KITスタンダード検定受検の様子。教室前方スク
リーンでも問題が表示されており、学生の回答状況もわかる。
(注)IELTS(アイエルツ)…International English Language Testing System

44 Kawaijuku Guideline 2014 特別号
國學院大學経済学部初年次必修科目「基礎演習」の授業アンケートに学修成果に関する項目を設け その結果をFD活動に活用
2012年11月に創立130周年を迎えた國學院大學は、東京・渋谷と横浜市郊外のたまプラーザにキャンパスがある大学である。皇典講究所以来の歴史があり、現在は、文学部、経済学部、法学部、神道文化学部、人間開発学部の5学部からなる。経済学部では初年次教育とFDに力を入れた教育改革を推進。特に学生アンケートの活用や、優れた授業方法の教員間の共有などを通して、学生の学修成果の向上に成果を上げている。
学生の現状とニーズを把握し共通認識を持った上で初年次教育を展開
経済学部では、2005年度頃から意識的にFD(注1)活動を推進し、2009年度のカリキュラム改訂に伴って教育目標の明確化を図るなど、積極的な教育改革を進めている。特に重点を置いているのが初年次教育で、2006年度から、1年次の学部共通必修科目「基礎演習」において、独自の授業アンケートを実施している。導入の背景には、学生の多様化に伴って、必ずしも
大学教育に対するレディネス(準備・心構え)が十分ではない学生が増えていることがある。そうした中、全ての学生に、いかに学修に主体的に取り組ませるかが、初年次教育の重要な課題であると認識されるようになった。そこで経済学部では初年次教育の核として「基礎演習」を位置づけた。「基礎演習」は1クラス約20名の少人数編成で、経済学部の専任教員ほぼ全員が担当している。以前は、授業設計が各教員の裁量に任されており、授業内容や教育目標について教員間で違いがあった。これを改めるため、「基礎演習」独自の授業アンケートを実施し、学生の現状とニーズを把握し、それに基づいて教員間で共通認識を持った上で初年次教育を展開することにしたのである。現在「基礎演習」は、1年次前期の必修科目「基礎演
習A」と、1年次後期の義務履修科目(注2)「基礎演習B」に分かれている。基礎演習の目的は4年間の学修を有意義にするため、スキルや問題意識を固めることだけでなく、自分の居場所を実感してもらうこと、1年次から将来の仕事を意識してもらうことなどである。経済学部では2008年の教授会合意として、次の3つが
「基礎演習に盛り込むべき内容」として定められた。① 初年次研修→大学で学ぶ意識の醸成、國學院大學についての理解、履修の仕方や進路選択を含む大学生活のガイダンス(居場所の理解となじむこと)。② 学ぶための基本的スキルの学習→プレゼンテーション・レジュメ作成、ディスカッション、レポート作成、情報リテラシー、日本語表現。③ 専門教育への導入・問題意識の養成→文献講読(テキスト理解)、プレゼンテーション、レジュメ作成、ディスカッション。また、全学部のほとんどの科目で授業アンケートを実施している。質問項目は「この授業にどの程度出席しましたか」「予習・復習をするなど授業に意欲的に取り組みましたか」など、授業態度に関するもの(9項目)が中心で、学修内容にまでは踏み込んでいない。それに対して、「基礎演習」の授業アンケートは、教授会合意の「盛り込むべき内容」に沿って、「論述試験答案の書き方」「情報リテラシー」「専門書の読み方」など、大学ならではの学びのスキルを身につける上で、授業がどの程度役立ったかを、6段階で答えさせている。これまでの「基礎演習」の授業アンケート結果を見ると、年度を追うごとに、学生の満足度、学修の到達度の評価は確実に高まっている。これは学生からの評価がよい刺激になり、授業改善につなげている教員が増えてきたからだと考えられる。さらに経済学部では、毎年7月と12月に行われる教授会懇談会で、授業アンケートの集計結果を公表するとともに、評価が高かった教員が自らの取り組みを紹介する機会を設けている。具体的には、以前は学生に書かせたままだったレポートを、何回も添削指導するようにした事例、教員が手本となるレジュメ
(注1)FD…ファカルティ・ディベロップメント (注2)義務履修科目…進級・卒業要件には含まれないが、全員が自動的に履修科目として登録される科目。

45Kawaijuku Guideline 2014 特別号
Part.3 学修成果の把握とその活用
を作成して、学生に自分のレジュメと比較させて、どの部分を修正する必要があるのか気づかせるようにした事例などがある。そうした工夫が、他の教員の参考になり、自主的な授業改善につながっているのだ。
「できる式アンケート」と「教員アンケート」を追加導入
2011年度から、学部独自のFDアンケートに、2つの調査が追加された。その1つが「できる式アンケート」である。「基礎演習」で学んだことが、その後の学修にどのように生かされたのか、どんなことが「できる」ようになったのかを卒業時点まで追跡調査し、3年次以降のコース選択、ゼミへの参加や、就職活動への準備につながったかどうかを検証する試みである。「できる式アンケート」は、1年次前期・後期、2年修了時、卒業時の4回実施し、「大学になじむ」「スキルの養成」「専門研究への関心の醸成」の3つの観点から、19項目について、自分の学修成果を答えさせる<図表>。「できる式アンケート」は導入後3年のため、詳しい分析には至っていないが、高学年になるにつれて、多くの項目の達成度が高まるのが理想だ。また、継続して同じ項目のアンケートを実施することで、学生が大学で修得すべき項目を自覚し、4年間を通じて意識的に高めるようになることや、節目ごとに自己評価するための振り返りのツールとして活用されることが期待されている。もう1つの調査は、「基礎演習」の教員アンケートで、
学生アンケートのような定型的な質問項目は設けられておらず、自由記述である。教員は授業を進める上でどんな点に悩んでいるのか、それを解決するためにどのような工夫を凝らし、その結果どのような成果が得られたのかなどを記述する。これにより教員同士が互いに同じようなことで悩んでいることがわかるほか、自分とは違う取り組みを、自己紹介の仕方から、グループ・ワークの仕方や本の輪読の仕方などまで、知ることができるのだ。例えば、学生には、「しっかりと勉強するように」と言うのではなくて、レジュメを作る時は何時間、レポートを書く時は何時間と、具体的に指示した方が取り組みやすいという意見が他の教員の参考になったこともある。教員同士の取り組みを共有することが、FDにおいても重要であることがわかった。
個別指導への活用が課題
経済学部では、初年次教育としては「基礎演習」の他に、情報リテラシーを鍛える「コンピュータと情報」、経済学の最も基礎的・初歩的な内容を網羅し、自分が関心のある分野を見つけて、3年次からのコース選択にも役立つ「日本の経済」を1年次の必修科目としており、この3科目を初年次教育の3本柱と位置づけている。そして、これらの科目でもさまざまな改革が進行している。例えば、「日本の経済」は4~5名の教員が担当しており、以前は授業内容に若干の違いがあった。そこで、2007年度から2年間、教員が得意な分野の授業をビデオ撮影し、それぞれの教員が実際にどのように授業を進めているのか、どこに重点を置いて説明しているのか、映像を見ながら意見交換する場を設けた。各教員の専門分野を映像化したため、他の教員により参考になることもポイントである。さらに、現在は、テキストを担当教員で作成し、共通の試験も行っている。経済学部で今後の課題として認識しているのは、学生の主観的なデータを、教員アンケートや学生の成績状況などと合わせてみることによって、より多角的に分析する仕組みを検討することである。また、現在の授業アンケートは、学生が個人を特定されることを敬遠するため無記名が原則である。そのため、学生の学修成果を測定した後、ゼミや授業において学生への個別指導などに活用することが困難であることも課題である。そこで、学生が学修の経過を振り返ることができる、いわば「履修カルテ」を導入することも検討されている。
<図表> 基礎演習「できる式」アンケート結果 (2012年度)学部全体の状況
(n=451 複数回答 単位:%)注 ☆は基礎演習を通じて1年次修了までに身につけてほしい項目。
☆友だちとおしゃべり☆ネットで検索☆短いレポート☆レジュメ作成
☆みんなの前で自己紹介☆みんなの前で説明や発表
☆教員と話☆新聞
☆本の要約☆新書
☆みんなで議論データベース
あるテーマの論文をまとめる☆新聞雑誌の文章を要約
統計データ専門書調査
長いレポート注の付いた論文
無回答
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

46 Kawaijuku Guideline 2014 特別号
京都光華女子大学教育と生活面の支援を統合した総合的支援「京都光華のエンロールメント」を推進
京都光華女子大学は、「仏教精神に基づく女子教育の場の実現」をめざして1940(昭和15)年に開学した光華高等女学校を前身とする女子大学である。2014年度からはキャリア形成学部、健康科学部の2学部に再編、2015年にはこども教育学部を新設予定である。学生支援としては、2007年から教育、キャリア、情報システム、ファイナンシャルエイド、生活サポートの5つの側面から学生を支援する「京都光華のエンロールメント」を実施している。
学生の総合的・多角的なアセスメントを実施し学生ポータルサイト「光華navi」に情報を集約
2007年度、京都光華女子大学では「京都光華のエンロールメント」を開始した。これは「入学前から卒業後まで一貫して、あらゆる場面で教職員が連携し、全力で学生をサポートするシステム」である。この教育システム導入の背景には、大学のユニバーサ
ル化が進行する中、学習能力、意欲、入学目的などが多様な学生が入学するようになることが予想されたことがある。そうした中、学生一人ひとりの満足度を高めるためには、これまでの経済面や学生生活面を中心とした学生支援だけでなく、教育面も含めた総合的な学生支援が必要であると考え、総合的な学生支援を「教育改革」と位置づけて取り組むことにしたのである。2008年度には、「学生個人を大切にした総合的支援の推進」が、文部科学省の「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」に選定され、本格的な取り組みがスタートした。まず実施されたのが、IR(注1)の概念に基づく 「学生の
総合的アセスメント」である。京都光華女子大学では、IRをエビデンス(データ)に基づく戦略・施策の計画、実施、評価、修正(PDCA)、およびそのためのデータ収集・分析と位置づけた。学生を総合的に支援するためには、まず、学生の現状を体系的に把握することが不可欠である。そこで以前から把握していた学生の出席状況、成績、単位取得状況などに加え、個人面談情報、生活実態、経済状況、意識、態度、将来への希望などを含めた、総合的・多角的なアセスメントを実施することにした。また、調査結果が分散していたのでは学生を総合的に把
握することはできないため、学生ポータルサイト「光華navi」にすべての情報を集約するシステムを構築。これによって成績だけでなく、広範な学生評価情報を体系的に測定して包括的に把握することが可能となり、学生支援を支える客観的な資料として有効に活用できるようになったのである。
学生の意識・意欲を中心に調査・記録する「光華ライフアルバム」
総合的アセスメントの内容は、成績、出席状況のほか、プレイスメントテスト(入学時点で実施する国語、英語の基礎学力調査)、授業アンケート、卒業時満足度調査、面談記録、就職活動記録、経済状況記録、自己発見レポート(注2)、キャリアアプローチ(注3)など多岐に渡る。その中で、独自の取り組みとして注目されるのが「光華ライフアルバム」である。学生の意識・意欲を中心とした調査で、毎年6月に実施される。学習意欲・関心、大学適応度、人格特性、学習、生活サイクル、日常生活行動、キャリア形成などの項目があり、項目ごとの約10の質問に「光華navi」上で、5段階評価で回答していく。学生全体の平均値も表示されるので、学生は自分のスコアと比較して、その後の学生生活の在り方を見直す資料として活用できる。また、質問項目は学年によって異なるが、4年間を通じて同じ項目もある。卒業時には、1年次と4年次でその伸長度を測定する「Development 目標」として掲げている学習、社会人基礎力、資格・体験についても評価し、学生はそれらの推移を見て、自分の成長を実感することもできる<図表1>。
(注1)IR…Institutional Research (注2)1年次10月に実施。基礎学力、社会的能力などの意識・態度について調査。

47Kawaijuku Guideline 2014 特別号
Part.3 学修成果の把握とその活用
授業アンケートなどの結果を踏まえて教員が学生に授業改善策をウェブ上で公開
学生の同意を得た情報は、「光華navi」で教員も閲覧できる。それによって、特別な配慮が必要な学生が支援を求めるのを受動的に「待つ」のではなく、教員から能動的に手を「差しのべる」動きが活発化している。それが学生にとって「自分にやさしい大学」という意識を生み、充実した学生生活につながっている。また、総合的アセスメント結果を教育改革につなげ
る役割を担うのが、2012年4月に発足したEM・IR部(注
4)である。多岐にわたる改革を別々の委員会で議論していたのでは改革はなかなか進まない。そこで総合的な学生支援に関してはEM・IR部が一手に担う体制にしたのである。具体的には、さまざまなデータの傾向を分析し、授業内容・方法の改善、学生支援策、学生募集・広報戦略などの基本方針を策定し、提案している。すでにEM・IR部では、授業形態、受講人数、授業方
法・内容などの授業属性と、学生の意欲や授業評価との関係など、多様な角度から傾向分析を実施。学修意欲の向上につながる授業やカリキュラムについて検討を進めている。その分析結果に基づいて、学科や教員に改善点を指摘しており、それを受けて、学科内、および全学的な「FD委員会」で議論が活発化している。注目されるのは「授業アンケート」と「光華ライフ
アルバム」「出席率」「GP(各授業の成績)」を比較した2011年度の分析結果である<図表2>。「授業アンケート」は、「この授業の予習・復習を1週間のうちどの程度したか」「この授業を受けて役に立ったか」「授業内容はわかりやすいか」「課題量は適切か」など、8項目
について5段階で評価する。「授業アンケート」の評価と「出席率」ではそれほど有意な相関関係は見られないが、「光華ライフアルバム」の得点が高い(つまり、意欲・関心が高い)学生、および「GP」が高い学生の方が、授業への満足度も高いという結果が出ている。これは、授業の満足度を高めることが、学生の意欲・関心や成績向上に直結することを意味している。そこで、この結果を受けて教員には、学生の授業評価をもとに担当授業についてのリフレクション(内省)を行い、授業改善策と、学生の要望への対応策をまとめた 「リフレクションペーパー」を「光華navi」上で学生に公表することを義務づけた。授業評価の結果が良好だった教員にも現状に甘んじず、さらなる改善策を立案するよう促している。また、教員評価の40%を教育分野で、その半分以上を授業アンケートの評価(得点)で行うようにしたこともあり、教員も授業改善に真剣に取り組んでいる。学生にとっても、授業アンケートの自分の声がしっかりと教員に届き、授業改善に反映されているという実感が得られることは、授業への参加意欲や学修意欲の向上につながる。そしてこの取り組みを効果的に実施していくために、データ(事実)に基づく施策立案を行うべく、データ収集→分析→施策立案・実施のPDCAの流れの確立を急いでいる。同時に客観的な達成目標の設定と、その評価方法の確立に向けた取り組みも進行中である。一連の取り組みで最も大切なことは、エンロールメントマネジメントの重要性について教員・学生の共通認識を高めることであり、そのため、教員、学生双方への広報も重視している。エンロールマネジメントが大学にとって必要であることを、教員が認識し、学生もメリットを実感することによって、学内が一体となった活動に進化させていく予定だ。さらに、現在は在学生を中心に行っているアセスメントを、今後は保護者、高校生、卒業生、企業といった大学のすべてのステークホルダーに広げていく構想もある。それによって、より多面的な視点からの学生支援が可能になることが期待できる。
<図表1>光華ライフアルバム 卒業時の項目例 <図表2>授業アンケートの 評価と出席、成績、意欲・関心の関係
光華ライフアルバム:Development目標 (回答必須)5件法[身についている-やや身についている-どちらでもない-やや身についていない-身についていない]◆以下の各項目について、現在どの程度身についていますか。1.学習面(入学時と同項目) 1 一般的な教養 2 専攻分野や学科の知識 など7項目2.社会人基礎力(キャリア形成)(入学時と同項目) 1 物事に進んで取り組む力 2 他人に働きかけ巻き込む力 など14項目
光華ライフアルバム:資格・体験2件法[取得した-取得していない]3.以下の資格や体験を大学生活で取得しましたか。(入学時と同項目) 1 教員免許や司書など、大学の単位の取得で可能な免許・資格 2 管理栄養士やコンピュータ関係など、試験合格で取得できる受
験資格 など5項目
4.14.03.93.83.73.63.5
GP区分別
出席率区分別
意欲・関心別
高 中 低
(注3) 3年次10月に実施。就職活動に向けてのレディネスを調査。(注4)EM はエンロールメントマネジメントの略。

48 Kawaijuku Guideline 2014 特別号
立命館大学教育改革総合指標(TERI)の導入で組織としての教育改革能力を向上
立命館大学は、1869(明治2)年に、西園寺公望が新しい時代を担う若者を育成するために設立した私塾「立命館」を前身とする、日本で最も伝統のある私立大学の1つである。現在、学士課程は、京都の衣笠キャンパスと滋賀県のびわこ・くさつキャンパス合わせて13の学部で構成されている。立命館大学では時代の要請に応えるさまざまな教育改革を行っており、2007年からは、教育改革総合指標(TERI)を作成し、教育改革を推進している。
FDを教職員、学生が一丸となり教育目標を達成するための活動と定義
立命館大学では、学内に教育開発推進機構を設置し、大学や学部・研究科・教学機関が掲げた人材育成像と教育目標を実現するために、全学に関わる教育内容の改善に向けた提案および研究を行っている。教育開発推進機構には、FD(ファカルティ・ディベロップメント)を推進するために「教育開発支援センター」と「接続教育支援センター」の2つのセンターが設置され、教学部と連携して、各学部の自発的なFDを支援している。 立命館大学では、FDを「建学の精神と教学理念を踏まえ、学部・研究科・他教学機関が掲げる理念と教育目標を実現するために、カリキュラムや個々の授業についての配置・内容・方法・教材・評価等の適切性に関して、教員が職員と協働し、学生の参画を得て、組織的な研究・研修を推進するとともに、それらの取り組みの妥当性、有効性について継続的に検証を行い、さらなる改善に活かしていく活動」と定義している。 これは、FDは教育目標を達成するための全ての活動を含むもので、教員だけでなく職員や学生も一丸となって、PDCA(Plan〔計画〕、Do〔実行〕、Check〔点検・評価〕、Action〔改善〕)サイクルを回していく取り組みであることを意味している。 そして、PDCAサイクルを回してFDを円滑に・より有効にするための仕組みが、2007年に開発された教育改革総合指標「TERI」(Total Education Reform Indicator)である。
TERIは、卒業生調査や授業アンケート、学生調査などの定量的評価や情報をエビデンス(証拠)として蓄積するとともに、組織を成熟度<図表>により評価し、成熟度レベルを向上させるための基準を併せ持ったシステムである。特筆すべき点は、「組織の成熟度」という視点での評価指標が含まれていることだ。組織の成熟度はもともと、民間企業用に開発されたものだが、大学という組織に導入し、組織として達成すべき方向性や組織としてのヴィジョンを示したという点で、画期的なものである。 PDCAサイクルを回すためには、「Plan」において、第一に「何を実現したいか」という達成目標、第二に達成目標に対して組織として「何をするか」という共通認識・具体的項目、第三に「目標達成をどのようにして達成するか」という評価指標、第四に評価基準を決定する必要がある。PDCAサイクルを回すということは、この4項目を決定した後、Planに従って実行し、その結果を評価指標と基準で評価し、結果が不十分であれば改善するということであり、TERIのもう一つの役目はこれらのプロセスや結果を記録し、エビデンスとして残すことである。 しかし、目標の入力、データの蓄積は行ったものの、PDCAサイクルの理解が十分ではなかったために、データをどのように収集して活用するかといった点が不十分ではないかという課題が生じた。そこで、2011年から運用面の支援や研修を充実させて、「新TERI」として再スタートを切ったのである。

49Kawaijuku Guideline 2014 特別号
Part.3 学修成果の把握とその活用
TERIの運用を通し卒業時の質保証を担保
では、現在、新TERIは実際にはどのように運用されているのだろうか。 まず、新TERIには、各学部で定めた人材育成目標や教育目標を達成するための手段、各目標の達成度を測る指標や基準を定め(Plan)、入力する。その成果(達成度)が出た場合、その都度、学部や個々の教職員がプロセスを含めて結果を入力する。 具体的には、学部ごとに、「専門の基礎知識を修得する」「幅広い教養を身につける」「コミュニケーション能力を身につける」といった教育目標や、目標を達成するための具体的な取り組み、達成度を測る指標が定められ、新TERIに入力される。教育目標の達成度は、学生に対する「学びの実態調査」など各種調査や内部評価で得られた数値、機関別認証評価などの際に収集したデータなどを活用している。例えば、卒業時の質保証の1つを「卒業論文」としている学部では、適切な引用の注記がなされているか、先行研究を踏まえているか、問題設定は適切か、論理的な考察がなされているかといった内容を指標として設定している。 なお、「学びの実態調査」は、教育開発推進機構が、学生に対する質問項目を学部とともに作成したもので、新入生に対しては全学部で、在校生に対しては12学部で行っている。質問項目の約8割は全学共通、残りが学部独自のもので構成される。
TERIを効果的に運用するため研修も充実
新TERIを効果的に運用するために、教学部が主導して、新TERI導入以降、教員に対して教育目標や評価指標の立て方などに関する研修を2011~2013年の間に約30回実施した。また、FD懇談会を年4回実施しているが、ある学部から、5つの指標のうち2つ程度、評価が低い指標があったが、翌年度から教育方法を変更すると評価が改善されたなど、具体的な成果も報告されている。また、同じ授業を担当している教員間で集まり、目標を共有化する動きも活発化している。 このほか、教育開発支援センターでは、PDCAサイクルの考え方やロジックの組み立て方などの支援を中心
に、各学部から要望があれば、その都度、新TERIへの入力方法を説明、新TERIに入力されたデータの点検など、さまざまな支援を行っている。教学部と教育開発支援センターでは、今後も教員に対する支援を充実させていく考えだ。 また、TERIをきっかけに、「manaba+R」というe-learningの仕組みを作って、学生が予習・復習を行ったり、教員が講義を補足したり、学生が課題を提出して教員がそれに対してコメントをつけたり、授業アンケートを実施して到達目標に対する達成度をその場で確認したりといった動きも見られるという。 しかし、立命館大学では、TERIの一番の成果は、大学という組織に、組織としての成熟度という指標とその基準を導入したことにあると考えている。この指標と基準の導入により、組織が「漠然と変わった」「良くなった」というのではなく「この指標と基準に基づいて組織のレベルがこれだけ向上した」と学内外に提示できるとともに自組織の変容を促進できることである。ちなみに、指標は4が最高で、3あれば組織の成熟度が高いといわれている。なお、教育開発推進機構の成熟度はTERIの指標の2.5の段階である。 一般的に、企業組織のレベルを1段階向上させるのに2年必要だと言われているが、全ての学部のレベルが3以上になれば、かなりの教員が常に教育目標を念頭に置いて行動するようになっているということであり、教育成果は画期的に向上すると期待している。 立命館大学では、このように新TERIを活用して、大学全体として卒業時の質の担保をするとともに、さらに、教員が同じ教育の方向性を持ち、自らの教育内容・方法を改善することをめざしている。
<図表>立命館大学における 教育改革総合指標の成熟度評価基準
評価1 形式的な検討であったり、検討が行われていないレベル
評価2 具体的な検討が行われたが、学部教員全体の合意が得られていないレベル
評価3 実効性が検討され、合意が得られ、周知されているレベル
評価4 社会のニーズの変化に対して機敏に対応するための継続的、組織的な体制が整っているレベル

50 Kawaijuku Guideline 2014 特別号
龍谷大学文学部アカデミック・リテラシーや卒業論文のルーブリックを作成し、学修成果を検証
龍谷大学は1639(寛永16)年に西本願寺に設けられた「学寮」にはじまる歴史のある大学で、2015年度新設予定の農学部を加え、9学部からなる総合大学である。文学部は、1949年の新制大学への移行と同時に開設された伝統のある学部である。文学部では、「卒業論文」を4年間の集大成として位置づけ、これを目標に4年間の学修を見直し、大学で身につけるべき力を総合的に育成する取り組みを行っている。
学内の「GP」に採択された卒業論文を目標とする取り組み
龍谷大学では、2011年度から、各学部・研究科が独自に推進する優れた教育プログラムを、学内で採択し、予算などの支援を行う「龍谷GP(Ryukoku Good Practice)」がスタートした。採択されたプログラムの1つが、文学部の「ラーニング・アウトカムを具現する『卒業論文』の質保証~継続的なアカデミック・リテラシー教育の再構築~」である。文学部では以前から卒業論文を4年間の学修の集大
成と位置づけ、複数教員による口述試問を実施するなど、学生が卒業時に身につけておくべき能力を厳正に評価してきた。それによって、学生、教職員の間で、卒業論文こそが最重要の目標という共通認識が醸成されている。しかし、卒業論文の具体的な到達目標や評価基準が学部内で統一されていないこと、各年次の取り組みがどのように卒業時の質保証へとつながるのか4年間の学修の体系性・系統性が具体的に明示されていないこと等の課題も残されていた。そこで、卒業論文を目標に初年次と卒業年次に力点を置きつつ4年間の学修全般を見直し、「学びの文学部スタイル」を確立することになったのである。
ルーブリックを用いてアカデミック・リテラシーと卒業論文を評価する
取り組みの最大の特色は、アカデミック・リテラシーと卒業論文について、日本の大学ではまだ例が少ないル
ーブリックを作成していることだ。文学部では、「読む力」「書く力・発信する力」「調べる力」「考える力」「議論する力」を総称して、アカデミック・リテラシーと呼んでいる。課題の探究→発見→追究→解決といった大学ならではの学びを実現するための基本となる能力である。文学部の学位授与方針(ディプロマポリシー)とも連動しており、学生が卒業までに身につけることを期待している。ルーブリックではそれぞれの「力」の達成基準を「相当の努力を要する」「やや努力を要する」「十分満足できる」「期待している以上である」の4段階に分けて、レベルごとに具体的に記述している。2013年4月から、アカデミック・リテラシーのルーブリックを「履修要項」に掲載している<図表1>。ルーブリックとして、学生に求められる能力を項目に分けて、項目ごとにレベルを具体的に文章化することによって、学生は現時点での自分の到達度を把握することができる。つまり、学生に対してあらかじめ目的や到達目標を示すことにより、教育効果を高める狙いがある。また多くの学生の到達度が低い項目は、カリキュラムを検討するなど、学内での改革の資料として役立てることもできる。また、教員にとっても授業を設計する上で大いに参考になるはずだ。もちろん、各教員が1科目でアカデミック・リテラシーのすべてをバランスよく高めることはできない。しかし、学部として、4年間で学ぶ科目全体を通して、こうした能力をトータルに養成するのだということを明示することによって、各授業でどの力をどれくらい高めていくべきか、またそのための授業内容・方法をどうするのかといった検討と改善の動きが、

51Kawaijuku Guideline 2014 特別号
Part.3 学修成果の把握とその活用
自発的に教員の間で生まれることにつながると期待されている。
早い時期から卒業論文への意識を高めるために卒業論文ルーブリックを「スタディーガイド」に掲載
卒業論文ルーブリックについては、2012年度は、数名の教員が試行的に活用した。学生からの要望などを踏まえた上で、2013年度からすべての学生に公表・明示し、利用を推奨している。ルーブリックの項目は、「先行研究を調べる」「問題
を設定する」「考察する」「きちんとした文章で表現する」「論文としての体裁を整える(典拠・参考文献の明
記など)」といった論文を作成する上でのスキルが中心で、口述試問でよく質問される内容がほぼ網羅されている。5段階のレベルを設定し、基準項目ごとに求められることを文章で示している<図表2>。卒業論文ルーブリックを試行的に活用した教員によると、学生からは作成中の卒業論文がどの段階にあるのか、客観視するのに役立ったと好評であったという。その教員は学生に夏休みに草稿を作成させ、9月にそれをもとに個人面談を行っているが、その際にルーブリックを活用して、項目ごとに学生に自己評価をさせ、教員も草稿を読んで、教員の立場から評価した。学生は自分と教員の評価の違いを比べ、自分では十分だと考えていたのに教員の評価が低い項目がある場合はそこに意識を向けて
<図表1>文学部アカデミック・リテラシー・ルーブリック*1 このアカデミックスキル・ルーブリックは学生の皆さんが、龍谷大学の文学部生として求められるスキルを、どの程度達成できてい
るかを確認するためのものです。*2 おりにふれて、このルーブリックで自分の学修状況を振り返り、自身の学修に足りないものを確認し、各自の学修を深めるツールと
して利用してください。
学位授与の方針 相当の努力を要する やや努力を要する 十分満足できる 期待している以上である
知識・理解
人間社会の根本を見つめるために、「言語(ことば)」の持つ力を深く理解することができる。
「言語(ことば)」の持つ力をまったく理解できていない。
学科・専攻の教育理念に基づき、「言語(ことば)」の持つ力が必ずしも理解できていない。
学科・専攻の教育理念に基づき、「言語(ことば)」の持つ力が一定程度理解できている。
学科・専攻の教育理念に基づき、「言語(ことば)」の持つ力が深く理解できている。
テキストの正確な読解に基づいた、人文学の幅広い教養を身につけている。
テキストの読解ができず、教養の学修も進んでいない。
学科・専攻の教育理念に基づき、テキストが正確に読解できず、教養の学修も不十分である。
学科・専攻の教育理念に基づき、一定程度テキストの読解ができ、幅広い教養を学んでいる。
学科・専攻の教育理念に基づき、テキストの正確な読解ができ、幅広い教養が身についている。
幅広い学問領域について基礎的な知識を持ち、それぞれの領域が持つ見方について説明することができる。
多様な領域からの見解をまったく理解できていない。
学科・専攻の教育理念に基づき、多様な領域からの見解をあまり深く理解できていない。
学科・専攻の教育理念に基づき、多様な領域からの見解を一定程度理解できている。
学科・専攻の教育理念に基づき、多様な領域からの見解を深く理解できている。
思考・判断
人間や社会の諸問題について主体的・積極的に判断し、対応できる。
現代社会の諸問題についてまったく取り組めていない。
学科・専攻の教育理念に基づき、現代社会の諸問題について必ずしも積極的に取り組めていない。
学科・専攻の教育理念に基づき、現代社会の諸問題について一定程度取り組んでいる。
学科・専攻の教育理念に基づき、現代社会の諸問題について積極的に取り組んでいる。
課題の探求、発見、追究、解決という一連のプロセスを達成する能力を身につけている。
課題の探求から解決にむけた能力がまったく身についていない。
学科・専攻の教育理念に基づき、課題の探求から解決にむけた能力が必ずしも身についていない。
学科・専攻の教育理念に基づき、課題の探求から解決にむけた能力がある程度身についている。
学科・専攻の教育理念に基づき、課題の探求から解決にむけた能力が十分身についている。
幅広い分野の知識・理解をもとにして、問題に対して多角的な思考、判断を行うことができる。
多様な思考力・判断力がまったく身についていない。
学科・専攻の教育理念に基づき、多様な思考力・判断力が必ずしも身についていない。
学科・専攻の教育理念に基づき、多様な思考力・判断力が一定程度身についている。
学科・専攻の教育理念に基づき、多様な思考力・判断力が身についている。
(項目の一部を抜粋して作成)

52 Kawaijuku Guideline 2014 特別号
1 2 3 4 5
先行研究 国内の先行研究を把握できていない。
国内の先行研究を把握しているが、整理して説明できない。
国内の先行研究を把握し、整理して説明できる。
国外の先行研究も把握しているが、整理して説明することができない。
国内外の先行研究を把握し、整理して説明できる。
問題設定 問題の設定が曖昧である。
ある程度明確な問題を設定しているが、適切な問題であるとはいえない。
ある程度、明確で適切な問題を設定している。
適切で明確な問題を設定しているが、独創性はない。
適切で明確な問題を設定しており、独創性がある。
考 察資料の分析に基づいておらず、論理的整合性にも欠ける。
概ね資料の分析に基づいているが、論理的整合性に欠ける。
概ね資料の分析に基づき、ほぼ論理的整合性をもった考察を加えている。
資料の分析に基づき、ほぼ論理的整合性をもった考察を加えている。
資料の分析に基づき、論理的整合性をもった考察を加えている。
(項目の一部を抜粋して作成)
<図表2>卒業論文ルーブリック※ 卒業論文にかかわる学修進度の目安です。あくまで一例ですから、詳細は各学科・専攻の教員の指導に従ってください。※ 成績評価は、「演習Ⅱ」「論文評点」「口述評点」の総合評価によります。
取り組むというように、その後の研究に活かすことができたという。また、卒業論文提出後に、学修成果を振り返り、実感するための道具としても有効である。活用した学生からは、ルーブリックの文章をもっと具
体的にしてほしいといった要望も出された。例えば「ほぼ」と記述されていても、どこまでやっていればいいのか曖昧で、具体例で示すなどの工夫を望む学生が少なくない。この点は今後の課題と言えよう。なお、卒業論文ルーブリックは、2013年4月から、学
科・専攻ごとに独自に作成している「スタディーガイド」に掲載し、入学直後に実施される1泊2日の「フレッシャーズキャンプ」で配布している。アカデミック・リテラシー・ルーブリックが全学科・
専攻共通の「履修要項」に掲載されるのに対し、卒業論文ルーブリックが「スタディーガイド」に掲載されるのは、学科・専攻によって求められる力の具体的内容やレベルが異なる場合があるからである。例えば、「先行研究を調べる」場合でも、英語英米文学科や歴史学科東洋史学専攻の学生なら、国外の先行研究にも目配りする必要があるが、必ずしもそこまでの作業を問われない学科・専攻もある。学生自身の自己点検・評価にきちんと活用してもらうには、専門分野に応じた配慮も重要なため、学科・専攻ごとに最適化された卒業論文ルーブリックを各「スタディーガイド」に掲載する方が学生にとって利便性が高いのである。ただし、卒業論文ルーブリックを作り、卒業生の質を
保証するといっても、卒業論文の指導だけに力を入れれ
ばいいというわけではない。カリキュラム全体が有機的に連携しながら、卒業論文へと収斂する教育を進めることが重要である。学生に入学直後に卒業論文ルーブリックを配布するのは、将来、卒業論文を仕上げる際にどんなことが求められるのかを早い段階で意識して、それに基づいて、4年間の学びのスタイルを設計してもらいたいという狙いによるものである。
主体的、能動的な学修姿勢の醸成をサポートするアクティブ・ラーニング・コーナー
このように、ルーブリックは学生が自らの現状を振り返り、学びを改善するためのツールとして活用されることが前提である。本当の意味での活用が進行するためには、学生自身の主体的、能動的な学修姿勢が不可欠になる。それをサポートするために、2012年度、深草キャンパスの図書館内に設置されたのが「アクティブ・ラーニング・コーナー」である。ここには平日の一定時間に、大学院生のチューター(登録12名、毎回2名で担当)が配置されており、1・2年生を主な対象に、チューターがレポートの書き方や課題の見つけ方などの相談に応じている。そしてここが、自学自習の態度を促す場として機能することが期待されている。

53Kawaijuku Guideline 2014 特別号
Part.3 学修成果の把握とその活用
金沢工業大学目的に応じて9種類のポートフォリオを活用教員からの綿密なフィードバックが特色
「全科目で双方向型のアクティブ・ラーニングを導入」「学生主体の課外プロジェクト活動を推進」など、画期的な教育を実践していることで知られる金沢工業大学。ポートフォリオも2004年度からと、早い時期から導入している。しかも、目的に応じて9種類ものポートフォリオがあり、その大半において教員から学生への綿密なフィードバックが行われており、学生、教員が一体となった学びの環境の構築に生かされている。
1週間の行動履歴を記録学生にPDCAを意識させないことが重要
ポートフォリオというと、一般的には、レポートや作品、成績表など、学びの成果を蓄積しておき、振り返りに役立てるツールとされている。だが、金沢工業大学では、目的、クラスサイズ(教員がどこまで関与できるか)、記録する内容などの諸条件によって、当然、ポートフォリオの有り様も変わってくるはずで、そもそもどの大学にも通用する一律の形態は存在しないと考えている。そこで、金沢工業大学では現在、目的に応じて9種類ものポートフォリオを活用している<図表>。 2004年度、最初に導入されたのが「修学ポートフォリオ」と「キャリアデザインポートフォリオ」だ。 「修学ポートフォリオ」は、1年次の必修科目「修学基礎」で1年間を通した課題として課される。「修学基礎」は大学における学びの基礎を作る科目と位置づけられている。文章作成法、グループ討議法、プレゼンテーション法などを講義と演習を通して身につけるとともに、教員やゲストスピーカーによる講話からヒントを得て、自分なりのキャリア設計を考えさせていく科目である。 「修学ポートフォリオ」には1週間の行動履歴を記録する。まず、その週に特に力を入れる目標を3つ記載する。漠然とした抽象的な目標ではなく、「この科目のテスト対策をする」「ドローイングの練習をする」「資格の勉強をする」など、できるだけ身近で実現可能な具体的な目標にするよう促している。目標を達成して成功体験を積み重ねることが重要だからである。1週間後にどれだけ達成できたか、◎、○、△、×で自己評価する。 また、毎日の行動履歴を書き込む欄もあり、授業の遅
刻・欠席理由、正課授業以外に勉強した内容、利用した学内外の教育施設、アルバイト、食事、睡眠、運動など、修学生活に関するさまざまな情報を記載する。最後に「1週間で努力したこと、困ったこと」を記して、翌週に「修学基礎」の授業を担当するクラス担任の教員に提出。教員はそれにコメントを加えて、必ず手渡しで返却している。 導入された2004年度頃は、大学の大衆化に伴って、目的意識が薄いままに入学してくる学生の増加が問題になりつつあった。金沢工業大学では、その状況にいち早く対応するために、いわば手帳代わりにスケジュール管理ができるツールを作り、日々の目標を持って大学生活が送ることができるようにとの思いで「修学ポートフォリオ」を導入した。 「1週間で努力したこと、困ったこと」の欄には、入学当初は「よく頑張った」「つらかった」など、一言しか書けない学生も少なくない。けれども、教員から必ずコメントが寄せられ、「何がどのようにつらかったのか」「どう対処して解決を図ったのか」といった適切な質問が投げかけられる。学生がそれに一つひとつ答えることで、自らを振り返る習慣が身につき、新たな課題に気づく意義は大きい。それによって、毎日の身近な目標が生まれ、主体的に学ぼうとする意欲も喚起される。コメントを書く教員の負担は相当なものだが、受け入れた学生を責任持って教育していくという強い覚悟が感じられる。 こうして1週間単位の行動履歴を記録し、それが学期単位、学年単位で蓄積されていけば、PDCAサイクルが構築される。もちろん、それを大きな狙いにしているが、学生にはPDCAを意識させないことも重要と考えている。自分がいま行っていることが、PDCAのどの段階に相当

54 Kawaijuku Guideline 2014 特別号
するのかを考えさせるような仕組みにしたのでは、むしろ学生の伸び伸びとした行動を阻害してしまう。自然な流れの中で、結果としてPDCAサイクルが回っていくようなシステムにすることが理想だという。
できるだけ文章で記述させることで自己分析力、自己アピール力が高まる
1~3年次には「キャリアデザインポートフォリオ」の作成も義務である。1年次は「修学基礎A・B」、2年次は「技術者と社会」、3年次は「技術マネジメント」という必修科目の中で「キャリアデザインポートフォリオ」を活用している。これは、キャリアデザインを他の授業と切り離し特化して学ぶのではなく、工学系の学生として不可欠な素養を身につける中で、その1つとしてキャリアデザインがあるという考え方によるものである。 まず1年次は、小学校から高校までの自分史を作り、それを踏まえて、大学卒業後の進路や、そのために在学中に何をすべきかを考える。2年次は社会情勢を踏まえて、3年次では自己の特徴を生かして、将来像を考える。いずれも具体的な設問が与えられ、文章で記述させる点が特色だ。 例えば、1年次では「高校時代までを振り返り、学校の授業以外で得意だったことは何ですか」「興味ある職業に必要な能力を得るためには、在学中に何をすることがよいと考えますか。理由も含めて述べてください」、2年次では「政治、経済、社会、産業・技術の中から1つ選び、これから10年後の世界や日本の情勢について、どのように変化しているか予想し、1,000字以内で具体
的に記述せよ」、3年次では「10年後の自分のありたい姿について、どんな組織に所属し、どんな人たちに囲まれていたいか、自分を取り囲む人たちにどのような貢献、価値提供をしたいかを踏まえて、300字程度で記述せよ」といった設問が用意されている。○×方式や、選択肢から選ぶ方式ではなく、学生に書くことを課すことで、自分を深く見つめ直すようになる。自己分析力、自己アピール力が高まり、就職活動の際の強みにもなっているようだ。 そのほかのポートフォリオでも、文章で記述させる欄が数多く設けられている。 「達成度評価ポートフォリオ」は、1~3年次の学年末に作成・提出が義務づけられている。今年度の目標と、それがどの程度達成できたかを文章で記述する。金沢工業大学では「自律と自立」「リーダーシップ」「コミュニケーション能力」「プレゼンテーション能力」「コラボレーション能力」の5つを、“KIT人間力”として重視しており、これらの能力がどのような努力によってどの程度成長したか、こちらも文章で記述する。最後に翌年度の目標と、それを達成するための行動予定を記入する。進級すると「達成度評価ポートフォリオ」をもとに、新学年の修学アドバイザー教員により、全学生に対する面談が行われる。3年間継続することで、自分の成長を経年変化で実感することができるし、教員も過去の状況を踏まえて適切なアドバイスをすることが可能になる。 金沢工業大学では、学生の様子を保護者に伝えるため、約50会場で保護者会を実施している。保護者との個別面談もあるが、そこでも「達成度評価ポートフォリオ」が活用されている。学生がどのような努力をしているか、
<図表>KITポートフォリオシステム
プロジェクトデザインポートフォリオ
達成度評価ポートフォリオ
修学ポートフォリオ自己評価レポートポートフォリオ
1~3年次各学年末に作成今年度の目標と達成度自己評価、希望進路とその実現に向けて実際にとった行動・成果・展望、次年度の目標とこれを達成するための行動予定など
修学アドバイザーと新年度個人面談
修学基礎科目・専門科目および課外活動における自己評価
「1週間の行動履歴」と「各期の達成度自己評価」を登録
目標を達成させるための活動プロセスや成果の記録
変えるAction
つくるPlan
プロジェクト活動から自分自身を自己点検評価する
行動・記録する(蓄積)Do
気づくCheck
蓄積した記録を基に自己評価することで目標への達成度を評価
プロジェクトデザインⅠ・Ⅱにおける成果物と自己評価プロジェクトデザインⅢにおける活動記録と指導記録
学生自身による目標の設定
次の改善を図る活動計画を作成し、実行 修学・進路・学内活動に関する自己診断、行動履歴
プロジェクトデザイン成果物と達成度の自己評価
キャリアデザインポートフォリオ
▶高校までの自分史▶大学卒業後のキャリア像▶在学中の取り組み▶自分の特性と目標
自分史や卒業後、在学中の取り組みなどを登録

55Kawaijuku Guideline 2014 特別号
Part.3 学修成果の把握とその活用
将来にどんな夢を抱いているか、具体的な資料をもとに説明できる効果は絶大だ。個人情報のため、保護者にも「達成度評価ポートフォリオ」を渡すことはないが、この面談を契機として、学生と保護者が将来について話し合う機会が増えることも少なくないという。 2013年度から新たに導入されたのが「新聞ポートフォリオ」。毎日の新聞記事で気になったものを100字程度にまとめる。1年次の「修学基礎A・B」、2年次の「技術者と社会」、3年次の「技術マネジメント」で活用されている。ものづくりの世界でも、社会の動きに敏感になることが求められるが、最近は新聞を読まない学生が増えているため、導入されたポートフォリオだ。その効果で、全国の新聞が揃えられているライブラリーセンター(図書館)の新聞コーナーを訪れる学生が大幅に増加している。 「自己評価レポートポートフォリオ」は、人文社会科学・体育系科目の全開講科目で実施されている。学習支援計画書(シラバス)に明示されている行動目標(最大6項目)がどの程度達成できたか、パーセントでの自己評価とその理由を記述させるものだ。教員にとっては授業改善の貴重な資料になっている。 「プロジェクトデザインⅠ・Ⅱポートフォリオ」は、金沢工業大学の特色の1つである1・2年次必修の「プロジェクトデザインⅠ・Ⅱ」の科目で活用されている。学生によるグループを編成し、自分たちで設定したテーマについて調査・研究し、問題解決を図る授業だ。その成果物であるポスター、設計報告書、口頭発表スライドなどを蓄積する。同時に、第1週、第8週、第16週の3つの時期に、「図・グラフ・イラストなどを効果的に使用して発表することができる」「他の人の発表に対して、適切な質問をすることができる」といった能力について、5段階で自己評価する。最初は自分の能力に自信を持っていても、周囲のグループのレベルの高さを見て、自己評価が下がることもある。そんな場合は、教員がそのグループと面談してフォローしている。 「プロジェクトデザインⅢポートフォリオ」は、卒業研究を進める学生の、いわば日報、月報である。授業や学会などで多忙な教員は必ずしも毎日、卒業研究の学生に接することはできない。そんなときでも、このポートフォリオの提出と、教員のコメント返却で、スムーズに研究を進めることができる。活動した時間を記入する欄もあり、単位の実質化にもつながっている。 「就業力ポートフォリオ」は、学内でアルバイトをす
る学生スタッフが対象である。現在、1,000名以上の学生がスタッフの登録をしており、本格的なインターンシップの役割を果たしている。24項目のジェネリックスキルについて、学生スタッフを経験する前、半年後、1年後にどう変化したのか自己評価し、担当の職員がコメントし、不足している能力についてはアクションプランを立てて、改善を図る仕組みになっている。 「オナーズプログラムポートフォリオ」は、特別奨学生が対象だ。成績基準以外に、何らかの課外研究活動、クラブ活動に参加することが義務づけられており、その活動目標、実績を文章で記述する。
学修成果のエビデンスとして就職面接などで有効に活用
こうした多彩なポートフォリオは、さまざまな成果をもたらしている。何よりも大きいのが、大学で学んだ成果をエビデンスとして示せることだ。すべてのポートフォリオをクリアファイルシートにまとめて、就職の面接などで提示する学生もいる。学修成果の「見える化」が図られ、就職の面接での言葉にも説得力が生まれるため、面接官が身を乗り出してくることもあるそうだ。そうした活用をさらに促進するために、さまざまなポートフォリオを統合化させたシステムの構築も進めている。 学生にとって各種ポートフォリオに記入することは決して楽ではないはずだが、学生の評価を見ると「行動履歴」や「達成度評価」の作成は有益だと感じている割合は、最近5年間では91 ~ 95%で推移しており、高い満足度となっている。 また、教員からのフィードバックがあることで、教員と学生の距離が縮まる効果も大きい。さらに、特に頑張った学生を教員が推薦して表彰する「学長褒賞」に該当する学生は、ポートフォリオを導入してから3倍に増加。多くの大学で2年次に見られるGPAの中だるみが、金沢工業大学ではほとんど見られない。常に自分の学びの状況を振り返る習慣が身についている効果と考えられる。 そのほか、予想外の効果も出てきた。その1つが上級生による下級生のサポートで、下級生の学習の面倒を見る「勉強会」や、多様な相談に応じる「?相談コーナー」などが自主的に発足している。保護者会でも、自分のポートフォリオのデータを披露し、ミニ講演を行う学生も出てきている。自らの学びの成果に自信を持っていることの表れといえる。

56 Kawaijuku Guideline 2014 特別号
東北大学工学部「ポートフォリオ」(学習等達成度記録簿)を用いて個々の学生の能力や個性に応じた指導を実施
教育の達成度を把握し、個々の学生の学習履歴に応じた学修効果を見るために、東北大学工学部では2003年度から「ポートフォリオ」(学習等達成度記録簿)を用いている。2010年度からはウェブ形式のポートフォリオを導入し、内容や記入スペースを拡充するとともに、履修や成績に関する情報も含め、学生と教員が随時見ることができるようにした。さらに、ポートフォリオを用いて、セメスターごとに面談を実施し、学修成果の把握に役立てている。
設定した目標を達成した「結果」だけでなくそれに至る「プロセス」も重視
大学における教育面の評価は、教育の達成度(アウトカムズ)を評価軸にするのが世界的な潮流になっている。しかし、教育の達成度を定量的に評価するのは簡単なことではない。定量的な評価としては、例えば、国家資格・資格試験の合格者数や、TOEICなどのスコア、卒業生へのアンケート調査などが指標になる。しかし、これらはいずれも学修目標が達成されたかどうかの「結果」を見るためのもので、多様な個性を持つ個々の学生の学習履歴に応じた学修効果を見ることはできない。そうした課題を解決するために、東北大学工学部では、
2003年度から「ポートフォリオ」を導入した。導入当初、使用されていたのは紙面ポートフォリオ
(A4用紙2枚表裏4ページ)である。4年間およびセメスターごとの学習目標、その達成状況の自己評価、取得資格などが記載できる。学内ではポートフォリオを「学習等達成度記録簿」と呼んでいるが、「学習等」としているのは、大学での経験は、学習だけでなくサークルやアルバイトなどさまざまな活動があるからだ。そのため、目標達成に役立った学習以外の活動を書き込む項目も設けている。学生は各セメスター終了時に、この紙面ポートフォリ
オをもとにアドバイザー教員の面談を受ける。アドバイザー教員を務めるのは教授全員で、教員1人当たり約20名の学生を担当する。この面談で教員からアドバイスされたことも紙面ポートフォリオに記入する。ポートフォ
リオの導入によって、学生は達成目標を自覚して自己鍛錬を積むことができるようになり、教員も個々の学生の課題を迅速に把握できるようになった。
単位取得や成績と連動させた指導を行うために「ウェブポートフォリオ」に移行
だが、その一方で、2006年度末にこのシステムについて学生・教員にアンケート調査を実施したところ、いくつかの問題点も明らかになった。例えば、紙面では記入スペースが限定されており、面談で啓発されたことを十分に書くことができないという声が聞かれた。また、紙面ポートフォリオには高度な個人情報が含まれているため、大学の事務局が管理しており、学生や教員が常時見直すことは困難だった。さらに、教員からは学生の履修や成績と連動していないことが問題だという指摘もあった。単位の取得状況や成績を見ながら助言したいという要望があったのだ。そこでこれらの問題点を解消するために、2008年度からUSBメモリーを使ったエクセル形式の電子ポートフォリオに移行し、さらに、文部科学省「質の高い大学教育推進プログラム」(教育GP)に採択されたことを契機に、2010年度からはウェブ形式のポートフォリオを導入した。電子化したことで内容や記入スペースを拡充できたとともに、履修や成績に関する情報も含めることができ、学生と教員が随時ポートフォリオを見ることができるようになった。

57Kawaijuku Guideline 2014 特別号
Part.3 学修成果の把握とその活用
目標とする能力項目と履修科目を関連づける「マトリックス」を作成
では、現在のウェブポートフォリオはどのように用いられているのかを紹介しよう。まず、学生は1年次の必修科目「情報基礎B」の中
で、活用法を学ぶ。ポートフォリオ等の記入の方法のほか、個人認証など情報セキュリティーに関しては、とりわけ綿密に指導される。次いで、履修登録が完了した時点で、ウェブポートフォリオに必要事項を記入して第1回目の面談に臨む。その後各セメスターに1回、面談が
実施される。記入する項目は、4年間およびセメスターごとの「勉学目標」と「勉学以外の分野での目標」、および大学側があらかじめ設定した16項目の目標(課題を発見できる能力、人前での発表能力、英語・その他の外国語による表現力など)で構成されている<図表1>。前者は記述式、後者は100点満点で自己採点を行う。16項目の目標はUSBメモリーからウェブに移行した際に見直し、各項目を授業科目と関連づけた。それが、<図表2>の「マトリックス」で、どの科目でどのような能力が涵養されるのか、明確にわかるようになっている。
こうして自己採点されたウェブポートフォリオをもとに行われる個人面談では、達成度や習熟度を確認しあうとともに、学生が現在直面している課題などについて適切なアドバイスが受けられる。学生の自己採点では客観的な評価にならないという意見もあるが、学生同士を比較することにはあまり重点を置いていない。一人ひとりの学生に着目すると「英語の勉強を頑張ってTOEICのスコアが伸びた」「PBL形式の授業で問題解決能力が身についた」などの理由から点数が大幅に上がるときがある。他者との比較ではなく、学生個々の目標達成度が時系列で見られるところに、ポートフォリオの大きな意義があるのだ。また、ウェブ形式になったことで、学生はいつでも自分のポートフォリオを見ることができ、常に目標を確認しながら学修を進められるようになった。さらに、学生ができるだけ頻繁にポートフォリオをチェックするように、同じポータルサイトに、休講情報など、学生が必ずアクセスする情報も載せるなど工夫をしている。将来的には、学生の自己採点と大学入試の得点や卒業時の成績との相関関係も調査し、入試改革、カリキュラム改善に役立てる予定だ。このようにさまざまな成果があがっていることから、2013年9月からは大学全体の「学務情報システム」の中に履修登録、休講情報、ポートフォリオなどをポータルサイトにまとめて表示するようになった。今後、全学での活用が期待されている。
<図表1>東北大学工学部のウェブポートフォリオ
<図表2>東北大学工学部電気系のマトリックス
項 目 電気系
課題を発見できる能力基礎ゼミ、創造工学研修、プログラミング演習、実験系の科目、卒業研修など
実験計画などを設定できる能力情報処理演習、創造工学研修、プログラミング演習、実験系の科目、卒業研修など
人前での発表能力基礎ゼミ、情報処理演習、創造工学研修、プログラミング演習、実験系の科目、卒業研修など
人と話し合ったり、議論する能力 基礎ゼミ、創造工学研修、実験系の科目、卒業研修などチームの一員として取り組める(チームワーク)能力
創造工学研修、実験系の科目、卒業研修など
読書、講演会への参加、英会話や情報処理学習など大学以外での学習による自己啓発・生涯学習能力
学外見学、インターンシップなど
自ら着想する能力・創造する能力 創造工学研修、卒業研修など(項目の一部を抜粋して作成)