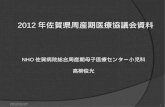松戸市議会放射能対策協議会 会議記録 - Matsudo · 松戸市議会放射能対策協議会 会議記録 1 日 時 平成24年7月23日(月)午後1時30分開議.
平成28年度 日本医師会医療情報システム協議会 -...
Transcript of 平成28年度 日本医師会医療情報システム協議会 -...

広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認
平成28年度 日本医師会医療情報システム協議会
と き 平成 年 月 日㈯ 午後 時~ 月 日㈰ 午前 時 分~ところ 日本医師会館 大講堂
広島県医師会常任理事 牛尾 剛士
日医IT化宣言 ~さらなる医療IT基盤をつくる~
平成 年度日本医師会医療情報システム協議会が「日医IT化宣言 ~さらなる医療IT基盤をつくる~」をメインテーマとして、平成 年 月 日㈯、 日㈰の 日間にわたり日本医師会館大講堂において開催され、当会から水野常任理事、大谷常任理事、志田原常任理事らが出席した。今年度は長崎県医師会が開催担当県であった。 日目は祝日ということで、開始時刻が例年より早く、地域医療連携システムの事例報告として、日医認証局・日レセを利用した事例が 題、地域での取り組み事例が 題の合計 題と、例年よりも多く発表された。というのも、地域医療連携システムは、平成 年頃から国の補助金を活用して全国各地で構築され始め、早いところでは初めてのシステムリプレイスの時期を迎える頃であり、 つの区切りを迎える時期となる。そういう意味でも、今回は各地の地域医療連携システムの成果について、多くの事例が報告された。 また、シンポジウムでは、医療分野専用ネットワーク構想について説明が行われ、レセプトオンライン請求や地域医療連携システムへの接続のために、医療機関は複数のVPNを切り替えて接続をしている状況から、そのネットワークを統合する医療分野専用ネットワークの構築が考えられている。高いセキュリティを担保しつつ、かつ使い勝手が良く、安価なネットワークを構築する方向で進んでいる。その概要について説明があった。 最後に、来年度は北海道医師会が当番県で開催されることが発表され閉幕した。 日間の参加者は総数 名(講師等関係者含む)であった。
【 日目】 月 日㈯
開会挨拶日本医師会長 横倉 義武
昨年 月の診療報酬改定で、検査・画像情報提供加算および電子的診療情報評価料が新設された。これは、ITに対する診療報酬上の評価がされたということだが、日進月歩で変貌している医療IT化に時期を逃さず適切に対応することが求められる中で、日本医師会が本協議会で活動してきた成果であ
ると考えている。 加算を算定するには、技術的に保護されたセキュアなネットワークが不可欠であり、日本医
師会は医療分野のIT化の新たな指針「日医IT化宣言 」を公表し、安全なネットワークを構築することを宣言した。この新たな宣言は、従来の「ORCAプロジェクト」の推進のみの内容にとどまることなく、医療分野のIT政策全体を包括する内容となっている。 同宣言をもとに、医療等IDやHPKIの普及に向けて、すべての医療機関が接続できる、公的な全国ネットワークとして「医療等分野専用ネットワーク構想」を提唱している。本ネットワークは、厳格な機関認証を受けた医療機関や接続要件を満たした事業者のみが接続可能で、全国の医療機関などをカバーする公益性を担保する一方で、コスト効果に優れた全国的に最適化されたネットワークになるよう検討している。 さらに、内閣官房の次世代医療ICT基盤協議
代 読松原 謙二日本医師会副会長

昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)
会においては、改正個人情報保護法施行後に、病歴情報など配慮が必要な個人情報は本人の許可なく第三者に提供ができなくなるため、第三者などの研究に必要な情報を提供できる「医療情報匿名加工・提供機関(仮称)」に関し、積極的に関与していく所存である。 今後も日本医師会はこれまで以上に力を入れて患者の医療情報を厳格なセキュリティで守りつつ、医療分野のIT化に取り組んでいく。 最後に、この協議会が、先生方にとって有意義なものとなることを祈念する。
況 況 況
日本医師会は医療IT委員会で地域医療連携のための新たな日本医師会IT化戦略と他職種連携のあり方について検討を進め、「日医IT化宣言 」を発表した。これを受け、今回の協議会は「日医IT化宣言 さらなく医療IT基盤をつくる」をテーマとして開催する。現在、地域包括ケアシステムの構築が進められている中で、か
かりつけ医を中心とした多職種連携を行うためにはICTによる地域連携システムが欠かすことのできないものとなっている。各地で医療におけるICTの活用がされている。一方で、政府はマイナンバー法を施行して以降、日本医師会としては、当初から医療情報とマイナンバーが直接結び付かない仕組みの構築が必要であるとし、医療分野専用のIDの導入を提案しており、具体的な検討が行われているところである。 地域連携システムを進めていく上で、安心・安全な医療IT基盤を作っていくことが大変大切なことである。各地でネットワークが構築されているが、これからは地域を超えて行われていく。そのためには、高度なセキュリティが保たれ、共通して利用できる広域ネットワークが求められている。現在、日本医師会は情報安全に安心して連携させるための医療等分野専用ネットワーク構想を提唱している。その件に関しても本協議会の中で詳しくご説明があると思うが、先生方にご議論いただきたい。日本医師会を中心として、医療IT基盤を作っていただけたらと願っている。 今回の協議会のプログラムはどれも興味深いものばかりであり、最後までご清聴いただき活発なご議論を期待している。最後に本協議会が実り多いものとなり、これからの医療情報シス
テムの発展に寄与することを祈念する。
Ⅰ.日医IT戦略セッション 座長/運営委員(川出 靖彦、富田 雄二)
日本医師会のIT戦略について 【日医IT化宣言 】
日本医師会常任理事 石川 広己 従来以上に急激な変化を見せ始めている医療分野のIT化を取り巻く環境に鑑み、日本医師会では平成 年 月に「日医IT化宣言 」を公表した。 日医IT化宣言 (概略)
・安全なネットワークを構築し、プライバシーを守る
・医療の質向上と安全の確保をITで支える・国民皆保険をITで支える・地域医療連携・多職種連携をITで支える・電子化された医療情報を電子認証技術で守る
新たな宣言は、従来の「ORCAプロジェクト」の推進のみの内容にとどまることなく、医 療分野のIT政策基盤の構築(医療・介護分野における個人情報保護の整理、HPKI認証局、 HISPRO、医療・介護分野のビッグデータ構築と利活用(医療情報匿名加工・提供機関(仮称))、ORCA事業の継続、医療等分野専用ネットワークの形成などについて報告があった。
日本医師会ORCA管理機構㈱の今後について日本医師会ORCA管理機構㈱代表取締役社長
上野 智明 昨年設立した日本医師会ORCA管理機構㈱では、日医総研で推進してきたORCAプロジェクトを引き継ぎ、誰もが安全で安心して活用できる医療介護情報の基盤づくりに向け、利用者へのサービス向上はもちろん、時代の潮流にあわせた地域医療・介護の戦略的開発を行っている。 ORCAプロジェクトは 年に発足し、日医標準レセプトソフトのユーザ数は約 , 医療機関で、レセコン市場で国内第 位のシェアとなった。オープンソースの手法によって、レセコンの価格を引き下げてきた実績があり、今後は電子カルテなどを含めた医療情報システムのコストダウンを図っていく。また、診療報酬で評価されることになった「電子的診療情報評価
蒔本 恭日本医師会
医療情報システム協議会運営委員会委員長
長崎県医師会長

広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認
料」への対応ソフトなど医療介護分野における周辺ソフトの充実を図っている。 つ目の柱としては、日本医師会の「次世代医療ICT基盤」関連事業にも取り組みを始めた。今後は、高いレベルでの個人情報の取り扱いが必要な医療・介護において、国民が安心できる質の高いITの更なる発展に寄与していく。そのために、医療・介護分野のビッグデータの利活用における「医療情報匿名加工・提供機関(仮称)」についても、積極的に係わっていく予定である。
日本医師会文書交換システム (MEDPost)について
日本医師会ORCA管理機構㈱開発部部長西川 好信
平成 年度診療報酬改定において、診療情報提供書などの電子化の評価として「検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料」が新設された。平成 年 月現在の届出状況は、全国あわせて「 , 施設(広島県は、愛知、北海道に続いて全国第 位の 施設)」にとどまっている。 加算を算定するためには、医師資格証を用いての電子署名と安全な回線を用いての送受が必要となるため、これらの制約のために申請したくても申請できない場合がある。 そこで、日本医師会が企画した文書交換サービス「MEDPost(メドポスト)」は、前述の加算を算定するための施設基準を満たしており、セキュアで安全な通信環境を皆さまに提供できるものとなっている。 施設要件としての、HPKIによる電子的署名を施すことは、医師資格証と「MI_CAN」でできる。「MI_CAN」で検査結果や画像の入ったPDF形式の電子紹介状を作成し、医師資格証を用いてそれに電子署名を施す。さらに、電子的なネットワークを施すことは、この「MEDPost」でできるようになる。結果的に医師資格証は必須となる。 医療系の文書は、患者のクリティカルな個人情報の塊であり、取り扱いには十分な配慮が必要である。「MEDPost」は、地域包括ケアの推進における情報連携ツールとして気軽に他職種連携を実現するための仕組みである。 月 日より申込受付開始で、サービスは平成年 月 日より利用開始する。
なぜHPKIをやったのか、医師資格証の今後について
日本医師会電子認証センターシステム開発研究部門長
矢野 一博 医師資格証の申請数は、 年 月末時点で, 枚、広島県は 年 月末時点で 枚であり、枚数としては全国第 位だが、広島県内の医師 , 名に対する割合としては、僅か. %に過ぎない。 ただ、 年 月の診療報酬改定で電子化された診療情報提供書などの算定要件にHPKI(Healthcare Public Key Infrastructure)が明記されたことに加えて、「検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料」が新設されたことと、同時に日本医師会会員に対しては、初回発行手数料を無料にし、年間利用料を廃止してからは、著しく申請数が増えている。 ただ、 , 枚は、日本医師会会員 万人での割合は僅か .%、非会員も含めた 万人の医師での割合は僅か .%あまりである。 そのため、医師資格証を利用する機会を増やすために、医師会の講習会などにおける出欠および単位管理ができる仕組みの構築や、航空会社との連携による事前登録制度の構築を進めた。 今後は、医師資格証をお持ちの医師が、自宅で受講履歴のリアルタイム検索が可能なサービスの提供や、医師資格証の発行申請時にマイナンバーカードのキー情報を用いることで、電子申請を可能とし、住民票の写しなどの申請書類を一部省略できるよう準備を進めている。
Ⅱ.事例報告セッション①座長/運営委員(牟田 幹久、小室 保尚、
服部 徳昭、吉田 貴)
【日医認証局・日レセを利用した事例】 「セキュリティをコントロールする ~「ゆけむり医療ネット」におけるコンテキスト・スイッチの応用~」
別府市医師会会長 矢田 公裕別府市医師会ICT・地域医療連携室 室長
田能村祐一 「ゆけむり医療ネット」は、別府市医師会を中心とした医療・保健・福祉を連携し、二次医療圏で完結する医療連携を中心に、基幹病院と病院・診療所を閉鎖されたネットワークで結び、患者の同意の上診療情報を参照するシステムで

昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)
ある。 年目を迎え、利用者の意見として「ID・パスワードなどに関する煩わしさ」を解消するため、コンテキスト・スイッチ技術を利用したログインの仕組みの実証実験を実施した。
あじさいネットにおける検査・画像情報提供加算の実際
長崎県医師会常任理事・あじさいネット理事 牟田 幹久
平成 年 月の診療報酬改定で、「検査・画像情報提供加算並びに電子的診療情報評価料」が新たな項目として加わった。この つの項目を算定するには厳しいハードルが課せられ、実際に算定している会員はほとんどいないのが現状である。その最大の理由が、実際に算定するための 回 回の手順が多過ぎることである。例えば、電子認証は地域医療ネットワークのVPNに接続中は実施できないため、いちいち接続を切り替える必要がある。また、紙の診療情報提供書であれば事務員が郵送してくれるが、電子データは医師が自分でパソコン上で操作しなければ送信できない。セキュリティを高め過ぎると手間が増え、結果、使い勝手が悪くなる。そして誰も使わなくなる。日本医師会には、ぜひそのバランスの良いものを求めたい。
日本医師会文書交換ソフトを利用した医療連携の模索碧南市医師会顧問・碧南市健康を守る会会長
山中 寛紀 碧南市は、人口約 , 人の比較的小さな市で、市民病院以外に民間病院 つと 医療機関で構成されている。会員は、平成 年 月時点で名である。 これまで約 年間ICTを利用したネットワークづくりが検討されてきたがいまだ確立されなかったが、 年ほど前から地域包括ケアプランの観点から介護現場における多職種連携の必要性が高まり、平成 年度から「電子連絡帳」と称したICTによる連携が始まる。 医師会内で種々模索する中で日本医師会の文書交換ソフトが本格稼働することを知り、これを利用した医療連携について本格的に検討している。
ORCA連携自動健診システム 「健診オートボーイ」
医療法人光省会 福田外科病院院長福田 俊郎
数年来、健診の自動化をコンセプトに、健康診断をいかに自動化し省力化が可能か試行錯誤しながら健診システムを開発した。すべての検査機器、測定機器からの数値データを自動で取り込み、中継機器を通してネットワークで健診サーバへ登録。データに基づき異常判定、病名、所見を自動出力する。 データの自動入力により、人手をかけることなく多人数に対応が可能で、病名、所見も自動で出力されるため見落としや入力ミスもなくなった。 今後は、がん検診をはじめ、各種健診が自動で短時間にできることが望まれ、さらに健診業務では電子媒体でのファイリング、報告、請求が欠かせなくなっている。
「まめネット」における日医認証局活用事例報告
島根県医師会常任理事 児玉 和夫 平成 年 月に電子紹介状に日医認証局を利用した電子署名付加を導入。これにはまめネット独自の紹介状システムに電子署名を付加する以外に「日レセ+MICAN」、さらに任意の電子紹介状でもPDF変換されれば正式な電子署名として付与可能にするなど、今まで慣れ親しんだ紹介状ソフトが利用できるのも一つの特徴といえる。 今後、電子署名は電子処方箋、主治医意見書などにも活用されますます便利になる予定である。
日医標準レセプトソフト(ORCA)を利用した点眼薬の表示システムの試作
坂出市医師会 広報・情報担当理事久保 賢倫
眼科へ来られる患者は、視力の悪い方が多く、文字を見ることが難しく、点眼薬をキャップの色や瓶の形で判断しているため、思い込みなどにより使用目的や回数を間違えることがある。そのため点眼薬をテレビ画面に大きく表示できれば、間違いが減るのではないかと検討した。 そこで、ORCAを動かすOSもアンドロイドのOSも共にLinaxであるため、タブレットからORCAを見に行くシステムを試作したところ、高齢者には大変好評で、テレビ画面を指指しな

広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認
がら、適切な服薬指導ができるようになった。 ORCAのOSはLinaxであるためORCAのデータベース内をすべて利用することができ、レセプト業務のためだけに使うのではなく、診療所のICT化のコアとして役に立つのではないかと思われた。
いばらき安心ネット-医師資格証を用いた運用及びORCAの役割-
茨城県医師会副会長 松﨑 信夫 いばらき安心ネット(ibaraki medical association Safety Network:iSN)は、茨城県医師会が地域医療再生特例臨時交付金で整備した医療情報共有システムである。iSNでは、医療機関同士が、それぞれ電子署名された診療情報提供書を交換し、標準規格「SSMIX」で提供された患者情報(①患者氏名等基本情報②診断名③投薬内容④アレルギー情報⑤血液検査結果⑥入退院履歴)を共有することが可能である。 平成 年 月から実運用しているiSNについて、医師資格証を用いてどのように運用しているかや、利用状況や運営上の課題、今後の目標について報告があった。
Ⅱ.事例報告セッション② 【地域での取り組み事例】 患者・家族参加型システム「Note4U」の運用と課題
鶴岡地区医師会理事 三原 一郎 年以上にわたり地域電子カルテ「NetU」の運用を継続し、とくに在宅医療の分野で多くの実績をあげてきた。一方で、在宅医療においては、家族支援という視点も重要なことから、医療・介護などのサービス提供側の連携のみならず、主体者である本人あるいは家族などのネットワークへの参加が望まれることから、年に患者・家族支援ツールとして「Note
U」を開発した。 「NoteU」は、「NetU」と連動することで、「NetU」の検査結果や処方内容など患者情報が閲覧でき、また、患者側からはバイタルなど医療側へ伝えたい情報を「連絡ノート」として伝えている。「連絡ノート」は、患者・家族にとって、安心して在宅医療を継続できる信頼感にもつながっている。運用事例はまだ少ないが、今後蓄積されるものと思われる。
診療支援ツールの新たな展開 ICT化糖尿病連携手帳による地域包括ケア体制構築と広域運用への課題
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター医長
幸原 晴彦 電子カルテの診療支援ツールとして、チーム医療で作成した糖尿病サマリーシートは、必要な医療情報が 画面上にすべて一括表示される。俯瞰できる形としたことで、外来診察時の診断速度と理解度を大幅に向上した。患者にはその情報を多様な様式で分かりやすく紙媒体で渡している。ネットワークを使わず患者中心の地域連携が成り立っている。
⑽ Aケアカードシステム浪速区での挑戦浪速区医師会副会長 久保田泰弘
平成 年 月よりブルーカード(患者急変時対応カード)システムを実施しており、現在では、近隣の 病院が連携病院である。 そして、新たな取り組みとして、医療・介護連携として、多職種による情報共有、共通認識について検討し、Aケアカード(多職種連携カード)システムを構築した。 これは、多職種の立場から、患者の基本情報をシステムに入力することで情報が付加されていく仕組みである。パソコンが苦手な先生方のために、事務方の代行入力サービスを行い、紙カルテの先生方の参加を促している。われわれは、医師会員全員参加が可能なシステムでありアナログ部分を残し、ICTをより使いやすくするシステムを目指している。
⑾ かかりつけ医における外来診療要約 -「年刊サマリー」の様式考案と実践-
医療法人明輪会 荒川医院 副理事長荒川 迪生
診療情報は単なる自動収録ではなく、医師が能動的に要約収録すること、とりわけ外来診療の全経過概括の作成が重要視される。かかりつけ医の包括的診療には利点と課題とがあり、診療の質を高め、課題を克服するためには「外来診療要約」が必要である。 外来通院患者を対象に、初診時からの診 療の全経過を網羅し、 年に 回程度外来診 療要約(以下、「年刊サマリー」)した。 年月からは正式に全長期受診患者の「年間サマリー」を開始し、アプリケーションソフトにはMicrosoft Office Excel を用い、 年か

昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)
らは電子カルテにDoctor’s Desktop(日医標準レセプトソフト対応電子カルテシステム)を用いた。「年刊サマリー」は労力と時間のかかる作業ではあるが、かかりつけ医は自⾝の診療補強や修正ができ、診療の質が向上した。
⑿ 医師会プライベートネットワークと画像公開システム
岡崎市医師会システム担当理事・日名南おおはまクリニック院長
大浜 仁也 会員施設および医師会の各施設間にはプライベートネットワークが構築されており、医師会から会員への情報発信や依頼診療予約、検査のオーダリングなどさまざまなシステムが稼働している。今回その仕組みに健診画像の閲覧機能(DICOM ビューワ)を追加した。 これまで人間ドック・健診で撮影された画像を医療機関に提供する場合、フィルムもしくはCDに複製し対応していたが、今回のシステムでは、施設内の本体PACSに原本運用・保存された健診画像を最終結果報告が確定されるタイミングで公開用画像サーバに圧縮画像(参照用画像)として転送する。 受診者がかかりつけ医を受診するにあたり、持参する報告書内に印字されたバーコードを読み取ることで受診者情報を特定し、画像を閲覧することで受診者やかかりつけ医の利便性を向上させた。
⒀ うすき石仏ねっとでもっと地域を元気に!臼杵市医師会医療福祉統合センター長
舛友 一洋 うすき石仏ねっとには、病院、医科診療所、歯科診療所、調剤薬局、訪問看護ステーションなどの医療機関だけでなく、居宅事業所、介護老人施設、介護福祉施設などの介護系機関、地域包括支援センター、臼杵消防署、臼杵市役所などの公的機関も参加している。 平成 年 月からは念願であった健診データの共有も始まった。
⒁ なごや地域における医療連携ネットワークの活用事例
名古屋市医師会理事 若松 建一 近年、中核病院の診療情報を診療所に居ながらにして閲覧可能とした 対Nの地域医療連携ネットワークが名古屋市内の各中核病院によって展開された。
しかし、診療所は各中核病院が運用する 対Nの地域医療連携ネットワーク毎に異なるVPN接続が求められ、中核病院は 対N地域医療連携ネットワークを利用するすべての診療所に対しVPN設定を行う必要があった。 これらを解消するため、各中核病院が運用する 対N地域医療連携ネットワークを紡ぐ広域的なネットワーク「なごや病診連携ネット」を年に運用開始した。診療所はどこか つの中
核病院が展開するVPNに接続することでポータルサイトに接続し、シングルサインオンにより他の中核病院が運用する 対N地域医療連携ネットワークへ接続可能となった。
【 日目】 月 日㈰
会長挨拶 昨日は 名を超す参加があったということで、日本医師会のIT戦略セッションならびに事例報告セッションが行われた。ご参加の先生方におかれましては、日本医師会のIT戦略、ならびに各地域のITを利用した医療連携についての動きを耳にされたことと思う。
日本医師会は、昨年日医IT化宣言 を公表した。これは昨日も石川常任理事から説明があったと思うが、われわれは医療の専門家集団として、日本医師会自ら先頭に立って医療現場のIT化を推進する土台となるネットワークづくりのイニシアティブをとる、その決意を宣言したのがこれまでのIT化宣言であったが、それを、医療分野のIT化をとりまく環境が急速に変化する現在に対応するためのアップデートを行ったものである。 また、大きな被害をもたらした東日本大震災から 年が経過したが、昨年は熊本でも大きな地震があった。このような大規模な自然災害の経験から、日常診療に対して患者の医療・介護情報をどのように取り扱っていくのかが大切になってくる。そのためには医療や介護情報連携とIT化の共通基盤の構築が重要で、電子化された情報を安全で安心して交換できる仕組みを作っていく必要があり、そのネットワークの構築整備が急務であろうと思われる。その中では当然、個人情報保護への取り組みが重要であるのはいうまでもない。 本日は、「医療等分野専用ネットワーク構想について」と題して、さまざまな視点から、医
横倉 義武日本医師会会 長

広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認
師会としての視点から、各学会の先生方の視点から、行政などの視点からということでご報告いただく予定となっている。 日本医師会では、日医IT化宣言 の宣言をもとに、患者が安心して医療にかかることができる環境をITの世界でも構築できるよう、今後さまざまな提案、議論を行う所存である。先生方も各地で実際にお取り組みいただいているが、その中での課題、問題がこの協議会で解決していただける場となれば幸いである。
Ⅲ.シンポジウム「医療等分野専用ネットワーク構想について」座長/運営委員
(藤原 秀俊、目々澤 肇、若林 久男)
「医療等分野専用ネットワーク」の実現に向けて
日本医師会電子認証センターシステム開発研究部門長
矢野 一博 昨年の日医協は、IT時代における地域医療連携のあり方をメインテーマに、サブテーマとして「医療等IDについて」を掲げていた。 日目のシンポジウムⅢで日本医師会の医療分野等ID導入に関する検討委員会からも検討の途中経過が報告された。その後、 年 月に検討委員会の報告書が取りまとめられ、現在、政府において医療等IDの運用に向けた検討がされている。 報告書でも触れられているが、医療等IDは、単にIDを作るのみならず、IDを付与した医療や介護の情報の連携や流通を実現するものであること、また、検討の途上で出てきた診療報酬の改定や電子処方箋のガイドラインなどにおいて、それらの情報を流通させるためには「安全なネットワークを利用すること」とされており、医療等IDの検討は単にIDのあり方だけの検討ではなく、IDも含めた情報の連携や流通をいかに安全に行うかという点にまで検討の範囲が広がってきた。 これらを受けて、現在、日本医師会ではそれらの情報を安全に連携、流通させるためのネットワーク、すなわち「医療等分野専用のネットワーク」の実現に向け検討を開始している。 「医療等分野専用ネットワーク」は、厳格な機関認証を必要とし、接続条件を満たした機関のみが接続できるネットワークである。医療等IDや、医師資格証を扱うため、高度なセキュリ
ティに守られた公益性の高いネットワークとなる。事業主体は公益性を担保するため、公的組織を事業主体と考えている。
医療用IX、HPKI、JPKIを用いた医療等分野専用ネットワークの構築について
東京工業大学科学技術創成研究院社会情報流通基盤研究センター教授
大山 永昭 現在、地域医療連携やレセプトオンライン請求用のネットワーク、さらにはHPKIやJPKI等が実稼働している。これらのインフラを活用して医療等分野の情報化をさらに推進するには、これらのネットワークを相互に接続し、全国レベルの安全な医療等分野専用のネットワークの構築が必要である。この目的を達成するための現実的なソリューションとなるIX(Inter-network eXchange)と、医師および患者の確実な本人確認を可能とするHPKIとJPKIの連携およびそれらの利用例として、転居などによる地域を跨る医療機関間での情報提供を取り上げ、保険資格確認にJPKIのPINなし認証を用いれば、医療機関を識別することで、同一人物でも接続先医療機関が異なることで違う接続として認識でき、誰がどの医療機関のサービスを受けたかのエビデンスとなる。
医療等ネットワークのあるべき姿一般財団法人医療情報システム
開発センター 理事長山本 隆一
医療や介護のような社会保障基盤に専用のネットワークを整備している国はエストニアのような小国を除くとほとんどない。基盤として整備しているわが国と比較し得る規模の国としては英国がほとんど唯一であろう。英国は年から英国保健省とNHSのプロジェクトとしてNPfIT-CfHの名のもとに大規模な医療IT基盤の整備を進めてきた。 一定の成果はあるものの、相当厳しい非難を受け、 年にプロジェクトは消滅した。冷静に評価すれば少なくとも一部は成果をあげており、現在でも活用されている。しかし昨年に新たなプロジェクトの模索が始まるまで、数年間は医療ITにかなり否定的な風潮があったことも事実である。 わが国で、医療等ネットワークのような、単なる誘導ではなく、公的支援による基盤の整備を進めるにあたっては英国を他山の石として、社会的

昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)
コンセンサスや、はるかに重要なことであるが、医療現場のコンセンサスを得つつ、一方では少子高齢化社会が間近に迫っていることを考えると、大胆且つ慎重に進める必要がある。「これ(ネットワーク)があるからできる」ではなく、「これが必要だからネットワークで実現する」という視点でネットワークを構築する必要がある。
医療等分野のICTに関する取組について厚生労働省 政策統括官付情報化担当参事官
佐々木裕介 厚生労働省においては、日本再興戦略 等に基づき、医療データのデジタル化・標準化、患者・現場をつなぐネットワーク化、イノベーションを生み出すビッグデータ化を推進することとしている。 特に、ネットワーク化(医療情報の共有・連携)に関しては、オンライン資格確認のインフラを活用した医療等IDの導入に向けた検討を進めるとともに、医療等分野における複数のネットワークの相互接続について、技術面、運用面等に関する調査研究を今年度実施している。さらに、「保健医療分野のICT活用推進懇談会」の提言(年 月)などを踏まえ、健康・医療・介護の公的データベースを連結し、ビッグデータとして活用するプラットフォームの構築に向けて、今後、検討を進めていくこととしている。
日本のIT戦略の中での医療等ITの取組について
内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室社会保障改革担当室内閣参事官
上村 昌博 年、『高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)』が制定され、内閣総理大臣を本部長とする、IT総合戦略本部が設置されるとともに、わが国のIT戦略が策定された。その後、IT本部に内閣情報通信政策監(政府CIO)を置き、府省横断的な「横串」、重複排除、連携強化を図るとともに、IT投資の全体最適化、見える化、PDCAの徹底、地方公共団体、民間との連携などの体制強化、IT戦略も数次の改定を経て来ている。 近年、スマートフォンやIoTの普及により、さまざまなデータがビッグデータとして蓄積されつつあり、その流通を促進し「データ」の積極活用を社会全体に拡げることで、社会課題の解決が図られる可能性が高まっている。また、今後、社会基盤として活用が期待されるAIの推
進にあたり、AIに投入する「データ」を質・量ともに向上・増大させて流通させることが必要である。さらに、超少子高齢社会を迎えさまざまな課題を抱えるわが国では、勘と経験ではなく、さまざまな「データ」に基づく政策を進めることが必要である。このような「データ」の重要性の高まりを踏まえ、「官民データ活用推進基本法」が制定された。
閉会式 次期担当県挨拶
昨日と本日と本当に有意義な会であった。 年の超高齢社会を迎え、地域包括ケアシステムを構築するにあたり、いまやICTは不可欠となっており、本会の会議は今後ますます重要なものとなってくる。
日間にわたっての会議の担当であった蒔本長崎県医師会長はじめ長崎県医師会の方々、日本医師会運営委員、日本医師会事務局の皆さま方のご苦労に心から敬意を表する。 来年は北海道の担当で、開催場所を北海道にさせていただきたかったが、日本医師会会館での開催ということで、皆さま方を北海道にお招きできないことは残念だが、別の機会に北海道にお越しいただきたいと思っている。来年度の協議会が皆さまにとって有意義なものになるよう努力してまいりたいと思っておりますので、皆さまにも引き続きご指導いただきたい。
閉会挨拶 あじさいネットに携わって 年が経過し、あじさいネットの活動を通じ全国各地の方々と携わってきた。どの地域のシステムが良いとか、成功しているとか評価するのはおかしい、それぞれの地域にはそれぞれの事情や特性があり、その中で自分たちがどういう地域
医療をやりたいのか、またやれるのかを地域の中で議論しそれにITをどう活用していくのか、ということが大事であると思っている。 あじさいネットはITを用いた地域ネットワークの成功例、フロントランナーといわれているが決してそうではないと思っている。南の地方でしか咲かない花を北で咲かせることはできない。咲かせるためには品種改良が必要なように、
長瀬 清北海道医師会長
牟田 幹久運営委員会委員・長崎県医師会常任理事

広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認
全国各地の医療ネットワークの取り組みを知り、真似でも構わないので、手を加えて自分たちの地域に合ったネットワークにすることが大切だと思っている。今回の担当を引き受けるにあたり、ぜひ全国各地の取り組みを一堂に会して紹介できる機会があればと思い実践した。 まだまだ知りたいことはたくさんあるとは思うが、またの機会にご容赦いただきたい。全国各地でITを用いた医療ネットワークが行われているが、これはITが医療に利活用できると分かっただけに過ぎない。強いていえば、今はまだやっと土地を耕したに過ぎず、これからやっと畑に何の種をまき、どんな芽をならせるのか、われわれの手腕が試される時だと思っている。超高齢化社会を迎えるにあたり、地域の人々が安全・安心に暮らせるために、われわれが頑張っていかなければならないと思っている。 結びに、ご後援をいただいた先生方、本協議会を企画し運営に尽力いただいた日本医師会関係者ならびに協議会運営委員の方に心よりお礼申し上げるとともに、ここにご参集いただいた皆さま方のますますのご活躍を祈念する。
担当理事コメント 今年度の日医協は、日医IT化宣言 をテーマとして開催された。 特に、今年度の日医協で関心のあったテーマは以下の つである。 まず つ目は、電子紹介状のやりとりに係る加算の算定要件が、ORCAの関連アプリケーションで完結できるようになったことである。 加算を算定するためには、医師資格証を用いて電子署名を行い、さらにその文書をセキュアで安全な回線を用いて送受することが条件とな
るが、前者の電子署名はこれまでも医師資格証と「MI_CAN」で行うことが出来ていた。後者のセキュアで安全な回線での送受については、これまではHMネットのような地域医療連携ネットワークのVPN回線を使わなければいけなかった。つまり、後者を実施するために、地域医療ネットワークに参加する必要があった。 しかし、「MEDPost」を使うことで、地域医療ネットワークに参加していない医療機関でも、セキュアな環境での送受を行うことができるようになる。これは、算定要件を満たすためのハードルを下げるものと言える。ただ、電子署名を付加出来る唯一の手段である医師資格証の発行枚数は、年間利用料が無料になった今もなお、日本医師会会員の %にも満たない状況ではあるが、これらのことを受けて、今後発行枚数も増えるのではないかと思われる。 つ目は、「医療等分野専用ネットワーク」の構築である。ネットワークの構築という文字から、日本医師会は膨大な費用を掛けて新たなネットワーク基盤を作るものかと思われたが、そうではなく、われわれがいま既存で利用しているレセプトオンライン請求用のVPNや、地域医療連携ネットワークにおけるVPNなど、異なるセキュアなネットワークを相互接続出来るIX(Inter-network eXchange)を構築し、異なるネットワーク間の橋渡しを行うというものであった。そうすることで、われわれは目的別にいくつも契約せざるを得なかった回線を つだけ契約すれば良いということになる。 以前より、地域医療連携ネットワークで、どの県でも問題となっていた高額な月額利用料の負担を解消するために、全国で利用できる共通のセキュアネットワークの構築を具現化したものであり、今後のさらなる発展に期待したい。
e-広報室に下記を追加いたしました。
ビデオライブラリー●平成 年度日医認定健康スポーツ医再研修会
通達文書●自動体外式除細動器(AED)設置登録情報の適切な更新登録について●厚生労働省「年金制度」及び「臨時福祉給付金(経済対策分)」に係る リーフレット・ポスターの設置及び掲示等について●認知症に係る運転免許更新等における診断書提出に関する情報提供について
新着のお知ら新着のお知らせせ新着のお知ら新着のお知らせせ