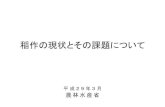平成28年度 平成28年8月出水に対する常呂川の 各種 … Matsuda, Yukinaga Komizo,...
Transcript of 平成28年度 平成28年8月出水に対する常呂川の 各種 … Matsuda, Yukinaga Komizo,...

Masahiro Matsuda, Yukinaga Komizo, Sadamu Ootami
平成28年度
平成28年8月出水に対する常呂川の
各種検討について ―雨量・流量の検証及び被災箇所の各種調査・検討―
網走開発建設部 治水課 ○松田 聖彦
古溝 幸永
大田見 定
8月17日から1週間に3つの台風が連続して北海道に上陸し、常呂川流域では累計雨量が観測史
上第1位を記録した。この降雨により、常呂川では2箇所の水位観測所で計画高水位を超過し、
越水による堤防決壊や河岸侵食、漏水等の被害が発生した。
本報告は、今回出水の雨量や流量についての検討結果及び、被災箇所の本復旧に向けて実施
した各種調査や今後の対策工における検討結果の報告を行うものである。
キーワード:自然災害 災害復旧
1. はじめに
平成28年8月~9月にかけて台風(7号,9号,11号,10号)
が連続して北海道に接近・上陸し、この影響で網走開発
建設部が管理している網走川、常呂川、湧別川、渚滑川
のすべての河川で、記録的な水位を観測し、うち湧別川
を除く3つの河川で計画高水位を上回るなど、オホーツ
ク地方の各地に被害をもたらす記録的な大雨となった。
なかでも常呂川では、8月中旬から下旬までの間に3つの
台風が連続して接近・上陸するかつてない気象状況によ
り堤防からの越水が多数発生し、常呂川水系の2支川
(柴山沢川:2条7号区間、東亜川:北海道管理河川)で堤
防が決壊するなどの外水氾濫が発生し、河川管理施設の
ほか、沿川の農地にも甚大な被害をもたらした。
本報告は、今期の洪水の特徴及び被害の状況について
紹介するとともに、被災箇所の本復旧に向け実施した各
種調査及び今後の対策工における検討結果について報告
を行うものである。
2. 常呂川の洪水概要
(1)雨量
図-2は気象庁北見観測所の年間降雨量とH28.8~9月
洪水の総雨量(H28年8月16日~9月10日)の比較を示し
たもので、平均年降雨量約800mmに対し約400 mmと、平
均年降雨量の50%に相当する雨量が当該期間に観測され
た。
また、表-1は常呂川流域内の水位・流量観測所地点
における流域平均雨量を洪水毎に整理したものである。
1回目の台風7号(8月17日~18日)と2回目の台風9号(8
月20日~22日)に伴う線状降水帯の影響で、流域平均雨
量100mmを越える強雨が2度にわたって流域全体に降り、
これによって常呂川の水位が上昇を繰り返し、記録的な
降雨状況となった。
東亜川
柴山沢川
台風11号8/21上陸
台風7号8/17上陸
台風9号8/23上陸
台風10号8/30上陸
382
0
200
400
600
800
1,000
1,200
S53
S54
S55
S56
S57
S58
S59
S60
S61
S62
S63 H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
雨量
(mm
)
年降雨量
H28.8.16~H28.9.10総雨量
平均約800mm平均約800mm
382mm
図-1 常呂川流域図
図-2 気象庁北見観測所の年間降水量とH28.8~9月洪水の総雨量

Masahiro Matsuda, Yukinaga Komizo, Sadamu Ootami
表-1 水位流量観測所地点における洪水毎の流域平均雨量
(2)水位
図-3に示す常呂川の水位縦断図は、下流部の被害箇
所の痕跡水位を示したもので、KP8.4~29.4の21kmにわ
たり計画高水位を超過し、さらにはKP18.4~25.6の区間
においては多くの箇所で現況堤防高を超過し越水が起こ
っていたことが推察される。
また、図-4に示すグラフは、被害の著しかった区間
に最も近傍な太茶苗水位観測所の水位グラフであるが、
台風7号の影響により1度目の水位上昇が有り、平常の水
位に下降する前に台風9号が上陸したことから、基底の
水位が通常水位よりも2mも高い位置からの2度目の水位
上昇となった。その影響により約32時間にわたり計画高
水位を超過する状況となり、越水の発生や、堤防決壊及
び漏水等の被害が発生した。
(3)流量
検証手法は、各地点の実測観測流量を用い貯留関数に
よる流出計算によって流量再現を行うこととした。
河道追跡計算の河道データは河川整備計画検討時の断
面を用い、鹿ノ子ダムは今回の洪水の実績放流量を与え
流出計算を行った。
被害地区に近い太茶苗地点の1回目と2回目の水位上昇
における各観測所地点の流量実績値と計算値のピーク流
量結果は、図-5となり、概ね流量波形が一致すること
が確認できた。今後は、河道断面の最新データや氾濫状
況を勘案して、氾濫戻しも含め、流出量の精査及び水位
検証を行っていく。
なお、河川整備計画目標流量は図-6に示すとおりで
あるが、今回の流出計算結果から今期の洪水流量は、基
準観測点となる北見観測所で整備計画目標流量を上回る
結果となり、記録的な洪水であったことがわかる。
無加川
置戸 上常呂 北見 忠志 太茶苗 上川沿 北光社
台風 7号(H28.8.17) 122 112 108 102 94 93 112
台風 9号(H28.8.20-21) 149 150 140 138 136 136 132
台風11号(H28.8.22-23) 61 57 57 56 53 53 60
台風10号(H28.8.29-31) 93 69 60 56 47 46 63
台風12号(H28.9.8-9) 66 75 70 72 71 71 59
常呂川
常呂川流域
観測所名事 象 名
5K 6K 7K 8K 9K 10K 11K 12K13K 14K 15K 16K 17K 18K 19K 20K 21K 22K 23K 24K 25K 26K27K 28K 29K 30K 31K 32K 33K 34K 35K
仁頃川
共立橋
太幌橋
栄福橋
日吉橋
忠志橋
常呂川水系 常呂川 水位縦断図(5.0km~35.0km)
計画堤防高 計画高水位
痕跡水位 左岸 痕跡水位 右岸
平均河床高 最深河床高
堤防越水区間
HWL超過区間
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
雨量(
mm/hr)
計画高水位 12.38m
はん濫注意水位 10.10m
水防団待機水位 9.30m
平常時水位 6.80m
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3
観測水位(m)
日時
雨量
観測水位
計画高水位
はん濫注意水位
水防団待機水位
平常時水位
計画高水位超過時間
・8月18日 6:10 ~ 8月18日11:40(累計 4:30)
・8月20日20:50 ~ 8月22日 5:30(累計32:40)
※9月 9日21:30 ~ 9月10日 3:50(累計 6:20)
2m程度高い
約32時間にわたり計画高水位を超過
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130 150
標高
(m)
距離 (m)
太茶苗地点(KP18.9)の横断形状
14.22m(H28.8.21 0:40)越水が発生
計画高水位 12.38m 1.84m
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0
100 200 300 400 500 600 700 800 900
1,000
08/1
6
08/1
7
08/1
8
08/1
9
08/2
0
08/2
1
08/2
2
08/2
3
08/2
4
降雨
(mm
)
流量
(m3/
s)
置戸
降雨実績流量計算流量高水流観
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
08/1
6
08/1
7
08/1
8
08/1
9
08/2
0
08/2
1
08/2
2
08/2
3
08/2
4
降雨
(mm
)
流量
(m3/
s)
北見
降雨
実績流量(標準法)計算流量
高水流観
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
08/1
6
08/1
7
08/1
8
08/1
9
08/2
0
08/2
1
08/2
2
08/2
3
08/2
4
降雨
(mm
)
流量
(m3/
s)
太茶苗
降雨
実績流量
計算流量
高水流観
1,500
オホーツク海
■北見
無加川
1,300
●河口
仁頃川
700
図-6 整備計画目標流量配分
図-5 主な観測所における実績値と計算値のピーク流量
ピーク水位
14.24m
図-3 ピーク時の痕跡水位縦断図
図-4 太茶苗観測所における水位グラフと断面図
■:基準地点
●:主要地点
単位:m3/sec

Masahiro Matsuda, Yukinaga Komizo, Sadamu Ootami
3. 被害の概要
(1)越水が発生した地区における河道特性
越水は、主に北見市常呂自治区において山間部の狭窄
部を蛇行して流れる地域(写-1参照)に位置する日
吉・福山地区で発生した。特に常呂川の柴山沢川合流点
付近の低水路幅は、図-7に示すとおり上下流に比べて
概ね100~200mほど狭くなっており、かつ高水敷におい
て樹木が繁茂していることも流下阻害の要因となり、当
該区間は水位が上昇しやすく水位が高い状態が比較的長
く続く区間であったといえる。
また、山と堤防に挟まれた河川周辺の地形においては、
概ね農地として土地利用されており、一度洪水氾濫が生
じれば、氾濫水が溜まりやすい貯留型氾濫原の特徴を有
する地区である。
(2)被害の状況
日吉・福山地区の被害は、2箇所で堤防決壊(うち1箇
所は北海道管理河川)、6箇所で堤防越水が発生し、河
岸侵食、基盤漏水など13箇所にもおよぶ河川管理施設の
被害が発生した。内外水の氾濫によって河川沿いでは多
くの農地が冠水し、たまねぎの生産量が全国一位を誇る
北見市において、今回の洪水でのたまねぎ畑を含めた農
地の被害は極めて甚大なものとなった。(写-2・3参照)
また、河川管理施設の被害では、次々来襲する降雨に
よって河川の水位が高い状況が長時間続くことによる被
害が特徴的であった。
ここでは、今回の洪水における河川管理施設の被害と
して代表的なものとなる「常呂川水系柴山沢川における
堤防決壊と、常呂川本川において越水したにもかかわら
ず決壊に至らなかった要因分析」、「基盤漏水による堤
内側の噴砂のメカニズム」について検証した。
なお、被害の要因等については、現在も堤防調査委員
会などにより、調査検討を進めている段階であることを
申し添える。
a)堤防決壊の要因分析
これまで柴山沢川の堤防決壊については、①越水によ
るもの②洪水流による侵食によるもの③堤防浸透や堤防
基盤における漏水によるものが要因として考えられるこ
とから、検証を行ってきている。
先にも記したとおり、今回決壊した柴山沢川の合流点
上下流付近は、著しく水位上昇しやすい区間であり、同
地区においても越水が発生していたことが明らかとなっ
ている。(図-8・9参照)
4
KP14
KP16
KP18KP20
KP22
KP24
KP26
KP15
KP17KP19
KP21
KP23
KP25
KP27柴山沢川
越水範囲凡例 越水箇所
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
川幅(m)
高水敷
低水路
柴山沢川合流点
平均川幅470m 平均川幅
280m
平均川幅430m
農地被害状況越水状況
0
10
20
30
40
50
10
11
12
13
14
15
16
17
8/19 0:00 8/20 0:00 8/21 0:00 8/22 0:00 8/23 0:00 8/24 0:00 8/25 0:00
柴山
沢川
流量
(m3 /
s)
常呂
川水
位(m
)
常呂川水位(m)
柴山沢川流量(m3/s)常呂川ピーク 8/21 5:00
柴山沢川ピーク 8/2016:00 (14m3/s)
(8/20 22:20避難指示)地先の方からの聞き取りにより避難した時点では決壊は発生していない。
ピーク が
13時間差
常呂川合流点
SP0.00
KP20.6+118.42m
柴山橋
SP1089.36
2条7号区間終点
SP1089.36
破堤区間(L=100m)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0 200 400 600 800 1000 1200
標高
(m)
計画築堤高計画高水位現況堤防高(左岸)痕跡水位(柴山沢川)痕跡水位(常呂川)計算水位(柴山沢川ピーク時)計算水位(本川ピーク時)平均河床高(現況)
KP1.0-40m KP1.1-40m
本川ピーク時において越水が発生
柴山沢川ピーク時では越水していない
図-9 柴山沢川の水位縦断図
図-7 日吉・福山地区の河道特性(川幅)
写-1 日吉・福山地区の河道特性
写-3 日吉・福山地区の浸水状況
図-8 常呂川の水位と柴山沢川の流出ハイドロ
SP 写-2 日吉・福山地区の被害状況

Masahiro Matsuda, Yukinaga Komizo, Sadamu Ootami
洪水流による侵食は、写-4に示すとおり河道部が直
線であり上流から下流方向を見ても低水路部の侵食は見
られず、現地の堤内側の土砂堆積状況から、流向は下流
から上流に向かっていたことが分かる。
また、堤防浸透によるすべり破壊及びパイピング破壊
に対する安全性については、図-10に示すとおりいずれ
も基準値を満足する結果となり、現地踏査でも決壊した
箇所以外での堤防の法すべりや噴砂などの現象は確認で
きなかった。
こうしたことから、長時間にわたり河道の水位が高い
状態が続き、また、降雨等によって堤防の湿潤化はあっ
たものの、決壊の主要因としては、常呂川の背水により
越水し、堤防が徐々に侵食され決壊に至ったものである
と確認できた。
次に、常呂川本川で越水が確認された日吉30号樋門付
近箇所では決壊には至らなかった要因について、現時点
での調査結果をもとにした分析について報告する。
柴山沢川の決壊箇所や各越水地点の堤防は計画堤防
高・断面を満足しており、堤防形状に大きな差はない状
況であった。
こうした状況のもと、柴山沢川と日吉30号樋門につい
て「土質状況」「植生状況」「越水時の内水状況」の比
較分析を行った。
ボーリング調査による土質の違いについては、柴山沢
川、日吉30号樋門ともに、堤体土質は主としてシルト砂
質土であり、極端な土質の差はないことが分かったが、
このことについては、今後堤体復旧に併せて土質サンプ
リングを行うなど土質試験による詳細な違いを分析し堤
体侵食への影響を検討していきたいと考えている。
一方、植生の違いは明らかとなった。日吉30号樋門付
近越水箇所の植生は、決壊した柴山沢川に比べ平均根毛
量が多く(写-5、図-11参照)、越流水に対する侵食
への耐力は比較的大きかったものと考えられる。
また、越水時の内水状況の違いについては、日吉30号
樋門付近越水箇所では、流入する支川の影響により、越
水時には既に一定程度内水が湛水していたことが分かっ
ており(図-12参照)、本川からの越流水は湛水した内
水によって減勢され、比較的堤体の侵食が生じにくい状
況にあったと考えられる。
なお、日吉30号樋門付近越水箇所のほか、5箇所の越
水箇所のうち3箇所は堤防取付道路の坂路部分で、上下
流の堤防高より若干低い箇所において越流が発生したが、
その越流水は緩勾配の坂路を流下したことにより、堤防
侵食は生じたものの決壊には至らなかったと考えられ、
他の越流箇所は、樋門や観測機器設置箇所などコンクリ
ート製の階段や構造物基礎により侵食が進みにくく、部
分的な侵食が見られたものの堤防本体への大きな影響は
なかった。
b)堤内側の噴砂のメカニズム
次に、今回の出水被害のもう一つの特徴として、一部
の区間(KP24.6~27.2)の堤内側で数多くの噴砂痕(写
-6参照)が見られた。これは長時間にわたる高い水位
の影響を受け、基盤破壊が発生し、堤内側に噴砂が生じ
る基盤漏水と考えられたことから、そのメカニズムを解
明すべく、基礎地盤と噴砂の粒度や周辺の変状状況の調
査・検討を行った。
柴山沢川
被災区間
土砂堆積が下流から上流へ伸びている
Fs=1.444 > 1.32(OK)裏法すべり破壊に対する計算結果
局所動水勾配(水平)0.137 < 0.5(OK)
局所動水勾配(鉛直)0.291 < 0.5(OK)
パイピング破壊に対する計算結果外水位 EL15.800m
内水位 EL13.500m
<柴山沢川>
表層0-1㎝
表層2-3㎝
表層0-1㎝
表層2-3㎝
根茎 根毛
根茎 根毛
根茎 根毛
根茎 根毛
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
深さ
(㎝)
σ0(gf/vm3)<柴山沢川>
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
深さ
(㎝)
σ0(gf/cm3)<日吉30号>
最大内水位 EL=15.19越水前22:30内水位 EL13.90
横断距離(m)
10.0
12.0
14.0
堤内側18.0
16.0堤外側
EL(m
)
GL=13.60m
写-5 根毛量の違い
図-12 内水位の状況
図-10 柴山沢川の浸透流解析結果
<日吉30号>
図-11 堤体法面の深さ毎の平均根毛量 写-4 現地の堤内側の土砂堆積状況
<日吉30号> <柴山沢川>

Masahiro Matsuda, Yukinaga Komizo, Sadamu Ootami
写-6 常呂川本川の噴砂状況
基盤破壊の可能性を探るため、ボ-リング調査、試掘
調査を実施し、今回洪水の実績観測雨量及び水位を与え、
浸透に対する安全性の評価を行った。その結果、図-13
に示すとおり基準値を超過し、基礎地盤において浸透破
壊が生じ噴砂が発生したと推定された。
今回の常呂川における噴砂は、法尻部だけでなく法尻
から30m以上離れたところからも噴砂痕が多数見られた
ため、その基盤破壊のメカニズムをより詳細に把握する
ため試掘調査を実施した。結果、明確なパイピングホー
ルや水みちは確認できなかったが、堤内側は農地であり
粘性が高い地盤が表面に分布しているもののその層厚は
一様でなく、法尻より離れた位置であっても地質的な弱
部があれば噴砂が発生し、特に表土の被覆層が薄いとこ
ろで発生していることが確認できた。そのため、堤内側
の農地条件として、試掘調査をもとに表土の粘性が高い
地盤をモデルに組み込み解析を実施した結果、図-13に
示すとおり、基準値を超過する結果となり、離れた地点
においても噴砂することが解明された。
図-13 浸透流解析結果
このことについては、図-14に示すとおり北見工業大
学による表面波探査及びコーン貫入試験の結果1)からみ
ても、そのメカニズムは、ほぼ一致する考察結果となっ
た。
図-14 北見工大による検討結果1)
また、試掘調査等において網状に砂を噛んだクラック
が無数に存在し、噴砂直下は地盤層が緩く崩れやすい状
況であることが判明した。試掘の状況と緩み箇所は、コ
ーン貫入試験や表面波探査との整合がとれていることか
ら、河川流水の高い水位による地盤内の水の圧力伝播に
よって3次元的に網状で水が流れ、表土の薄い箇所など
の弱部から水があふれ出すといったメカニズムであるこ
とが分かった。(図-15参照)
図-15 噴砂のメカニズムの検討結果
4. 再度災害防止の対策 (1)対策の必要性
前項で述べてきた被災箇所の対策については、早急な
復旧工事が必要であるが、災害復旧事業だけでは現況復
旧のみとなることから、今回と同規模の洪水が発生した
場合には、再度災害が発生する可能性が高い。そのため、
再度災害を防止するためには、河川水位の低減が必要不
可欠である。
■照査結果図
局所動水勾配(鉛直):0.70>0.5 NG(水平):0.87>0.5 NG
堤内側は農地であり、粘性が高い地盤が表面に分布している。⇒モデルに反映すると、法尻より離れた位置でも基準値を満足しない(噴砂の可能性)
表層の粘性土シルト砂質土
砂質土
れき質土
砂れき質土
▽H.W.L 18.22▽D.H.W.L
横断方向のS波速度分布
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
-0.0
-1.0
-2.0
深
度
(m)
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0
距離程 (m)
表面波探査解析結果
(m/s)
S波速度
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
270
290
縮尺=1/114
表層の低速度領域(シルト層)が薄い
サウンディングによるNd値の分布
堤体側
噴砂領域 Nd = 0 ~3程度緩い領域
Nd = 10以上硬い領域
Nd = 5~10程度比較的硬い
圧力は選択流的に伝播??
深さ2mまで簡易動的コーン貫入試験を実施
北見工業大学工学部 社会環境工学科より資料提供
パイピング
地形、地質的な弱部で発生
明確なパイピングホール等は存在せず、弱部箇所へ 3次元的(網状)に水が流れる
噴砂
【噴砂のメカニズム】
○KP26.8における浸透流解析結果
○堤内側の表土を組み込んだ解析結果
パイピング

Masahiro Matsuda, Yukinaga Komizo, Sadamu Ootami
(2)対策概要
(1)の状況を踏まえ、現況復旧のほか、河川水位の低
減を図るための河道掘削を緊急的かつ集中的に実施する。
その具体的な内容について図-16に示すとおり、計画
高水位を超過した区間を対象に河道掘削を行うことで、
河道内水位を今回出水規模程度においても計画高水位程
度にまで低減させ、洪水氾濫を未然に防ぐことを目指す。
河道の掘削断面については、現在詳細な検討を行って
いるところであるが、現況河道を出来るだけ活かし、上
下流区間の流下能力を勘案し下流への負担が極力生じな
いような掘削断面の設定を行うとともに、その掘削敷高
は平水位を基本に掘削を実施することで、自然環境へも
配慮することを検討している。
なお、今期の度重なる台風の影響による道内各地での
甚大な被害を受け、北海道開発局及び北海道では、被害
の著しい河川を対象に「北海道緊急治水対策プロジェク
ト」を策定し、河川管理施設だけでなく被害のあった農
地にも視野を広げ、緊急的かつ集中的な総合復旧事業を
行い、地域社会基盤の早期復旧を目指すこととしている。
(3)対策の効果
図-17は、越水した太茶苗地点の横断図で、今回洪水
の流量が流下した実績の水位と河道掘削実施後の水位を
示したものである。
掘削区間の上下流バランスを考慮し設定した断面によ
り、約1.0mの水位低減を図ることができ、計画堤防高
以下の水位となることから、越水による外水氾濫を防ぎ、
復旧工事と併せて事業を行うことによって、洪水氾濫を
未然に防ぐ効果が期待できる。
(4)掘削土の有効活用
本事業では、河道掘削土が約120万m3発生し、その残
土処理が課題となる。一方で、図-16に浸水範囲を示し
ているが、堤内側の農地が低くなっており、外水氾濫の
ほか、内水氾濫も発生していることから、河道掘削土を
活用した農地の嵩上げ等について、現在関係機関と鋭意
協議を進めているところである。(図-18参照)
こうして河川と農業が連携した整備を行うことで、安
全・安心な地域社会が形成されることが期待される。
5.あとがき
本稿では、現段階での出水時雨量・流量の検証結果及
び被災箇所の本復旧に向け実施した各種調査や対策工に
おける検討結果を取りまとめてきた。今後も検証を進め、
これ以降の河川整備へ反映していきたい。
6. 謝辞
今回の各種報告については、国土技術政策総合研究所、
土木研究所、寒地土木研究所、北見工業大学及び土木学
会常呂川現地調査団など各研究機関の調査協力等によっ
て可能となったものである。調査に携わった関係者皆様
に対し謝意を表するとともに、引き続き、今後の関連調
査や河川整備に向けた各種検討における調査についての
協力を要請させていただき、本稿の時点報告を終える。
7. 参考文献
1)川尻峻三、川口貴之、山下聡、渡邊康玄、早川博、
宮森保紀:土木学会地盤工学委員会堤防研究小委員会、
第4回河川堤防技術シンポジウム2016.11.29発表資料
河道掘削
20.8k
河道掘削
12.7k
42.0k
北見市
河岸侵食
柴山沢川 堤防流出
低水護岸流出
低水護岸流出
高水敷洗屈
低水護岸流出
低水護岸流出
低水護岸流出
漏水(堤防・基盤)
漏水(堤防・基盤)
堤防一部流出
低水護岸流出河岸侵食
低水護岸流出
20.8k
河川災害復旧等関連緊急事業区間L=8,100m
「河川災害関連緊急事業」区間L=21,200m
平面図
標準断面図
H.W.LH28.8洪水痕跡水位
× 災害復旧申請箇所
浸水範囲
河道掘削
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130 150
標高
(m)
距離 (m)
実績水位14.22m▽ (H28.8.21 0:40)
越水が発生
計画高水位12.38m
1m程度の低減
▽ 計画高水位 12.38m
▽ 掘削後は1m程度の水位低減
掘削予定箇所
(KP18.9)
河道掘削 運搬
置土
敷均し
日本の「食料庫」である 農地の早期復旧のため、 河道掘削土を有効活用 できるように関係機関と調整
福山右岸地区の農地被害 端野地区の農地被害福山右岸地区の農地被害
図-16 河道掘削範囲と掘削概略断面図
図-17 太茶苗地点の現況河道における掘削実施後の水位
図-18 農地復旧との連携