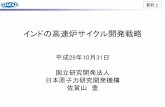鉛フリー対応高速リフロー炉の開発古河電工時報第115号(平成17年1月)52 特集:サーマル・ソリューション/応用技術 鉛フリー対応高速リフロー炉の開発
平成26年度 研究開発・評価報告書 評価課題「高速増殖炉/高速炉...
Transcript of 平成26年度 研究開発・評価報告書 評価課題「高速増殖炉/高速炉...
-
日本原子力研究開発機構
September 2015
Japan Atomic Energy Agency
JAEA-Evaluation
2015-005
平成26年度 研究開発・評価報告書
評価課題「高速増殖炉/高速炉サイクル技術の研究開発」及び
「「もんじゅ」における研究開発及びこれに関連する研究開発」
(事後評価)
Assessment Report of Research and Development Activities in FY2014
Activities : “R&D Programs on FBR/FR Cycle Technologies” and
“R&D Programs on Prototype Fast Breeder Reactor Monju and its Related Activities”
(Post-Review Report)
高速炉研究開発部門
Sector of Fast Reactor Research and Development
DOI:10.11484/jaea-evaluation-2015-005
-
本レポートは国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が不定期に発行する成果報告書です。
本レポートの入手並びに著作権利用に関するお問い合わせは、下記あてにお問い合わせ下さい。
なお、本レポートの全文は日本原子力研究開発機構ホームページ(http://www.jaea.go.jp)より発信されています。
This report is issued irregularly by Japan Atomic Energy Agency.Inquiries about availability and/or copyright of this report should be addressed toInstitutional Repository Section,Intellectual Resources Management and R&D Collaboration Department,Japan Atomic Energy Agency.2-4 Shirakata, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken 319-1195 JapanTel +81-29-282-6387, Fax +81-29-282-5920, E-mail:[email protected]
© Japan Atomic Energy Agency, 2015
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究連携成果展開部 研究成果管理課
〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方 2 番地4電話 029-282-6387, Fax 029-282-5920, E-mail:[email protected]
-
JAEA-Evaluation 2015-005
平成 年度 研究開発・評価報告書
評価課題「高速増殖炉 高速炉サイクル技術の研究開発」及び
「「もんじゅ」における研究開発及びこれに関連する研究開発」(事後評価)
日本原子力研究開発機構
高速炉研究開発部門
( 年 月 日受理)
独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という)は、「国の研究開
発評価に関する大綱的指針」(平成 年 月 日内閣総理大臣決定)及びこの大綱的指
針を受けて作成された「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成 年
月 日文部科学大臣決定)、並びに原子力機構の「研究開発課題評価実施規程」(平成
年 月 日制定、平成 年 月 日改正、平成 年 月 日改正)等に基づき、「高
速増殖炉 高速炉サイクル技術の研究開発」及び「「もんじゅ」における研究開発及びこれに
関連する研究開発」に関する事後評価を高速炉サイクル研究開発・評価委員会に諮問し
た。
これを受けて、高速炉サイクル研究開発・評価委員会は、本委員会で定められた評価方
法に従い、原子力機構から提出された第2期中期目標期間(平成 年度~平成 年度)
における研究開発の実績について評価した。
本報告書は、高速炉サイクル研究開発・評価委員会より提出された事後評価の「評価結
果(答申書)」等をまとめたものである。
本報告書は、研究開発評価委員会(高速炉サイクル研究開発・評価委員会)が「国の研究開発評価
に関する大綱的指針」等に基づき実施した外部評価の結果を取りまとめたものである。
日本原子力研究開発機構 高速炉研究開発部門(事務局)
大洗研究開発センター(駐在):〒 茨城県東茨城郡大洗町成田町 番地
i
-
JAEA-Evaluation 2015-005
Assessment Report of Research and Development Activities in FY2014 Activities : “R&D Programs on FBR/FR Cycle Technologies” and
“R&D Programs on Prototype Fast Breeder Reactor Monju and its Related Activities”
(Post-Review Report)
Sector of Fast Reactor Research and Development Japan Atomic Energy Agency
Oarai-machi, Higashiibaraki-gun, Ibaraki-ken
(Received June 11, 2015)
Japan Atomic Energy Agency (JAEA) asked the advisory committee “Evaluation Committee of Research and Development Activities for Fast Reactor Cycle” (the Committee) to assess “R&D Programs on FBR/FR Cycle Technologies” and “R&D Programs on Prototype Fast Breeder Reactor Monju and its Related Activities” during the period between FY2010 and FY2014, in accordance with “General Guideline for the Evaluation of Government R&D Activities” by Cabinet Office, Government of Japan, “Guideline Evaluation of R&D in Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology” and “Regulation on Conduct for Evaluation R&D Activities” by JAEA.
This report summarizes results of the assessment by the Committee.
Keywords : Evaluation Committee, FBR, FR, FBR Cycle, FR Cycle, Monju,
Prototype Fast Breeder Reactor Monju This work has been performed based on “General Guideline for Evaluation of Government R&D Activities” by Cabinet Office, Government of Japan, etc.
ii
-
目次
概要
高速炉サイクル研究開発・評価委員会の構成
審議経過
評価方法
評価結果
評価結果(答申書)「高速増殖炉 高速炉サイクル技術の研究開発」
評価結果(答申書)「「もんじゅ」における研究開発及びこれに関連
する研究開発」
付録(日本原子力研究開発機構資料)
付録
Contents1. Summary .................................................................................................... 1
2. The evaluation committee for FR Cycle technologies ............................. 2
3. Evaluation Committee of Research and Development activities ............. 3
4. Procedure of assessment ............................................................................ 4
5. Results of assessment ................................................................................ 7
5.1 Results of assessment(Committee Report) “R&D Programs on
FBR/FR Cycle Technologies” .............................................................. 7
5.2 Results of assessment(Committee Report) “R&D of Programs on
Prototype Fast Breeder Reactor Monju and its Related Activities”
........................................................................................................... 32
Appendix(documented by Japan Atomic Energy Agency) .......................... 57
Appendix CD-ROM
iii
JAEA-Evaluation 2015-005
-
This is a blank page.
-
.概要
独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という)は、「国の研究開
発評価に関する大綱的指針」(平成 年 月 日内閣総理大臣決定)及びこの大綱的指
針を受けて作成された「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成 年
月 日文部科学大臣決定)、並びに原子力機構の「研究開発課題評価実施規程」(平成
年 月 日制定、平成 年 月 日改正、平成 年 月 日改正)等に基づき、「高
速増殖炉 高速炉サイクル技術の研究開発」及び「「もんじゅ」における研究開発及びこれに
関連する研究開発」に関する事後評価を高速炉サイクル研究開発・評価委員会に諮問し
た。
これを受けて、高速炉サイクル研究開発・評価委員会は、原子力機構の第2期中期目標
期間(平成 年度~平成 年度)における「高速増殖炉 高速炉サイクル技術の研究開
発」及び「「もんじゅ」における研究開発及びこれに関連する研究開発」について、それぞれ
の実績を評価した。
本報告書は、高速炉サイクル研究開発・評価委員会より提出されたそれぞれの事後評価
の「評価結果(答申書)」等をまとめたものである。
- 1 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
高速炉サイクル研究開発・評価委員会の構成
本委員会は平成 年 月 日に設置され、関連分野の専門家を中心として、社会科学
の専門家を含む 名の委員から構成されている。
委員長 森山 裕丈 京都大学 原子炉実験所 所長
委員長代理 越塚 誠一 東京大学 大学院工学系研究科 教授
委 員 植田 伸幸 電力中央研究所 原子力技術研究所 所長・研究参事
五十音順 宇埜 正美 福井大学附属国際原子力工学研究所 副所長・教授
木倉 宏成 東京工業大学 原子炉工学研究所 准教授
黒崎 健 大阪大学 大学院工学研究科 准教授
竹下 健二 東京工業大学 原子炉工学研究所 教授
堂崎 浩二 日本原子力発電株式会社 開発計画室 室長代理
中村 裕行 日本原燃株式会社 理事 再処理事業部再処理計画部長
村上 朋子 日本エネルギー経済研究所 戦略研究ユニット
原子力グループマネージャー
山本 章夫 名古屋大学 大学院工学研究科 教授
- 2 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
審議経過
( )第1回委員会開催(事後評価):平成 年 月 日(金)
・高速増殖炉 高速炉サイクル技術の研究開発に関する事後評価
・第2期中期計画における進捗(炉システムの研究開発、核燃料サイクルシステムの研
究開発、研究開発の運営等に関する事項(国際協力)、自己評価結果)
・上記説明に関する質疑応答
( )第2回委員会開催(事後評価):平成 年 月 日(金)
・「もんじゅ」における研究開発及びこれに関連する研究開発に関する事後評価
・第2期中期計画における進捗(自立した運営管理体制の確立、発電プラントとしての
信頼性の実証、運転経験を通じたナトリウム取扱い技術の確立、研究開発の運営等
に関する事項、自己評価結果)
・上記説明に関する質疑応答
( )第3回委員会開催(事後評価の総合評価):平成 年 月 日(金)
・第 回及び第2回委員会における事後評価の総合評価
・委員会としての事後評価のまとめ(事後評価における総合評価の自己評価、委員会
としての総合評価の討論)
( )第4回委員会開催(事前評価):平成 年 月 日(金)
・高速炉サイクル研究開発に関する事前評価
・第3期中長期計画(高速増殖原型炉「もんじゅ」における研究開発、高速炉の実証技
術の確立に向けた研究開発、使用済燃料の再処理、燃料製造に関する技術開発及
び放射性廃棄物の減容化・有害度低減の研究開発)
・上記説明に関する質疑応答
- 3 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
評価方法
第 回委員会(平成 年 月 日開催)、第2回委員会(平成 年 月 日
開催)及び第3回委員会(平成 年 月 日開催)において、原子力機構から提示
した第2期中期目標期間(平成 年 月~平成 年 月)における高速炉サイクル研
究開発を説明し、質疑応答で内容を確認して、評価対象ごとに本委員会所定の評価項
目に従って、事後評価を実施した。
評価対象
「高速増殖炉 高速炉サイクル技術の研究開発」及び「「もんじゅ」における研究開発
及びこれに関連する研究開発」のそれぞれを評価した。
評価項目
評価項目は「国の研究開発評価に関する大綱的指針」及び「文部科学省における研
究及び開発に関する評価指針」に示されている評価の観点(必要性、有効性、効率性)
等を参考に意見を取りまとめた。
<必要性の観点>
① 国費を用いた研究開発としての意義
② 研究開発計画の妥当性
<有効性の観点>
③ 研究開発の達成度
④ 新たな課題への反映の検討
⑤ 効果・効用(アウトカム)
⑥ 人材育成の貢献の程度
<効率性の観点>
⑦ 実施体制の妥当性
⑧ 内外他機関との連携の妥当性
⑨ 目標・達成管理の妥当性
評価対象期間
平成 年 月より平成 年 月まで
- 4 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
事後評価スケジュール
平成 年 月 日(金)
~ 部門長挨拶 ( 分)
~ 評価委員の自己紹介 ( 分)
~ 諮問事項について ( 分)
~ 評価方法とスケジュールについて 説明 分、質疑 分
~ 炉システムの研究開発について 説明 分、質疑 分
~ 休憩
~ 核燃料サイクルシステムの研究開発について 説明 分、質疑 分
~ 研究開発の運営等に関する事項(国際協力)について
説明 分、質疑 分
~ 自己評価結果について 説明 分、質疑 分
平成 年 月 日(金)
~ 前回宿題対応について ( 分)
~ 「もんじゅ」における研究開発及びこれに関連する研究開発
①自立した運営・管理体制の確立 説明 分、質疑 分
~ ②発電プラントとしての信頼性の実証 説明 分、質疑 分
~ 休憩
~ ③運転経験を通じたナトリウム取扱技術の確立
説明 分、質疑 分
~ 研究開発の運営等に関する事項について
説明 分、質疑 分
~ 自己評価結果について 説明 分、質疑 分
- 5 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
平成 年 月 日(金)
~ 前回宿題対応について 分
~ 研究開発・評価委員会の今後の進め方について
説明 分、質疑 分)
~ 事後評価における総合評価の自己評価について
(高速増殖炉/高速炉サイクル技術の研究開発)
説明 分、質疑 分
~ 事後評価における総合評価の自己評価について
(高速増殖炉/高速炉サイクル技術の研究開発)
説明 分、質疑 分
~ 休憩 分
~ 委員会としての総合評価の討論 分
~ 事後評価のまとめ 分
~ その他 分
- 6 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
評価結果
評価結果(答申書)「高速増殖炉 高速炉サイクル技術の研究開発」
平成27年2月18日
独立行政法人 日本原子力研究開発機構
理事長 松浦 祥次郎 殿
研究開発・評価委員会
(高速炉サイクル研究開発・評価委員会)
委員長 森山 裕丈
研究開発課題の評価結果について(答申)
当委員会に諮問 26原機(炉)001 のあった下記の研究開発課題の事後評価
について、その評価結果を別紙のとおり答申します。
記
研究開発課題「高速増殖炉 高速炉サイクル技術の研究開発」
以上
- 7 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
高速炉サイクル研究開発・評価委員会報告書
「高速増殖炉 高速炉サイクル技術の研究開発」の評価結果(事後評価)
(答申書)
独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)は、高速増殖炉
サイクル技術の実用化を目指して国の政策に基づき「高速増殖炉サイクル実用化研究開発
( プロジェクト)」を実施してきており、「高速炉サイクル研究開発・評価委員会」(以下、
「当研究開発・評価委員会」という。)の前身である「次世代原子力システム/核燃料サイク
ル研究開発・評価委員会」では、 プロジェクトの開始時( 年度)及び中間とりまとめ
時( 年度)に研究開発計画、研究開発実施体制、進捗状況等について確認してきた。
今般、当研究開発・評価委員会は、原子力機構からの諮問を受け、第2期中期目標期間
(平成 年度~平成 年度)中における「高速増殖炉 高速炉サイクル技術の研究開発」
の業務実績(研究開発成果)に関する事後評価を実施した。当研究開発・評価委員会として
は、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成 年 月 日内閣総理大臣決定)
及び「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成 年 月 日 最終改
定 平成 年 月 日 文部科学大臣決定)等に基づき、指針に示されている評価の観点
(必要性、有効性、効率性)から重要と考えられる評価項目を設定し、各委員による4段階の
評定及び評価理由・意見を総合的に勘案した上で評価結果を取りまとめた。
以下に評価結果を示す。
Ⅰ.総合評価
(総合所見)
第2期中期目標期間では、平成 年 月 日に発生した東日本大震災に伴う東京電力
株式会社福島第一原子力発電所(以下、「1F」という。)事故以降、我が国のエネルギー・原
子力政策が見直されることとなり、 フェーズⅡへの移行が見送られている。国からの予
算(運営費交付金)も大幅に削減されることになり、エネルギー・原子力政策が定まるまでの
間は、技術基盤の維持と国際標準化への貢献のために必要な取組に限定されている。第2
期中期目標期間の最終年度に「もんじゅ研究計画」(平成 年 月、文部科学省「もんじゅ
研究計画作業部会」)が反映された「エネルギー基本計画」(平成 年 月閣議決定)が策
定され、研究開発の再開が可能になったところである。
このように非常に厳しい環境下ではあるが、 フェーズⅠの成果を取りまとめており、
この成果は今後の日本の高速炉サイクル開発の重要な基盤構築に繋がるものとして評価で
きる。また、実用化に向けた研究開発の凍結下においても、高速炉サイクルの研究開発に
必要な試験施設・設備や解析コードの機能を維持・管理するとともに、外部資金による研究
開発を通じて試験技術や評価能力に係る技術基盤を維持しつつ、各種データの取得やデ
(別紙)
- 8 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
ータベースの拡充を図るなど、研究成果の最大化に努めている。特に国際標準化に関して
は、我が国主導で安全設計クライテリアを構築して第 世代原子力システム国際フォーラム
( )の承認を受け、国際原子力機関( )や高速炉開発各国の規制側との議論を進め
るなど、大きな進展があったことは優れた業績と評価できる。
「もんじゅ研究計画」の策定に当たっては、「もんじゅ」等を用いた研究開発の技術的観点
からの整理に貢献しており、その計画が反映された「エネルギー基本計画」の策定後は、高
速炉の安全設計ガイドラインの具体案を作成するとともに安全性強化に係る技術基盤の構
築・強化を実施し、廃棄物減容・有害度低減を目指した研究開発では、次期中長期目標期
間での本格展開につながる成果を得ている。
以上を踏まえ、1F事故後の厳しい状況下で第2期中期計画の変更はあったものの、国の
方針に沿った取組を進め、国際的にも認められる成果も得ており、第2期中期目標期間中
の原子力機構の取組みは総合的に妥当であると評価する。
なお、今回の事後評価の中で今後の研究開発について参考とすべき意見があったので、
主な意見を次に示す。原子力機構においては、これらの意見を次期中長期目標期間での
研究開発活動に適切に反映することを期待する。
○ 技術基盤の維持は最重要課題の一つであり、原子炉システムと核燃料サイクル共に十
分に技術維持を行っていただきたい。ただし、技術そのものが古くなる場合もあるので、
新しい技術開発への挑戦も行って欲しい。
○ 核燃料サイクルシステムは、廃棄物減容・有害度低減を目指した研究開発において重
要であり、炉システムに対して遅れが生じないよう留意する必要がある。ただし、廃棄物
減容及び 取扱いについては、「研究のための研究」という視野狭窄状態に陥らない
ことを望みたい。
○ 予算が限られている中で、効率良く研究・開発が進むようフランス等と国際協力の下、
研究開発を推進すべきである。炉型や燃料形態で共通に協力できる事項や、国際標準
となり得る研究開発について継続的に検討されることを期待する。
○ 大学等研究機関との連携による基礎基盤研究は優秀な人材確保の意味からも重要で
あり、今後も推進をお願いしたい。
○ 研究開発結果を積み重ねていくことが将来のためにも重要であり、成功・不成功、また
公開・非公開を問わず、データベース化を図るなど体系的に整理しておく必要がある。
以下に主な評価のポイントを示す。
(研究開発としての意義)
研究開発としての意義については、「エネルギー基本計画」(平成 年 月閣議決定)に
も示されているように、我が国は高レベル放射性廃棄物減容化・有害度低減や資源の有効
利用等に資する核燃料サイクルの推進を基本方針としており、それを実現するために重要
な選択肢である高速炉サイクル技術に係るものであり、その意義は大きい。
- 9 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
(研究開発計画の妥当性)
研究開発計画の妥当性については、東日本大震災に伴う1F事故から「エネルギー基本
計画」の策定に至るまで、第2期中期目標期間中に研究開発計画を2回変更せざるを得な
い状況にあったことを考慮する必要がある。震災前においては国の方針に沿って プロ
ジェクトを進め、震災後の国の政策が定まるまでの間は原子力委員会決定等を踏まえて「技
術基盤の維持」と「国際標準化への貢献」に取組み、「エネルギー基本計画」策定後は、「も
んじゅ研究計画」を踏まえ「高速増殖炉/高速炉の安全性強化」と「廃棄物減容・有害度低
減」に重点を置いた研究開発を行っている。いずれの期間の取組みも国の方針に沿って実
施しているものであり、研究開発計画は妥当と判断できる。
(研究開発の達成度)
それぞれの期間の取組みの達成度については、以下の通りである。
フェーズⅠの成果(革新技術の採否可能性判断)については、国の評価委員会に
おいても評価が行われていたが、炉システムが先行しており、開発リスクが認められる革新
技術については代替技術を合わせて検討していることなど、当研究開発・評価委員会として
も概ね妥当と判断した。なお、核燃料サイクルに係る革新技術の採否可能性判断は検討継
続となった技術が多く、必ずしも達成度が十分とは言えない面もあるとの指摘もあった。
震災後の国の政策が定まるまでの間は、予算が大幅に削減された厳しい状況下ではあっ
たが、試験施設・設備や解析コード機能を維持・管理するとともに、外部資金による研究開
発を通じて試験技術や評価能力に係る技術基盤(実証施設の基本設計や革新要素技術の
工学規模実証を開始できるレベル)を維持しつつ、各種データの取得やデータベースの拡
充を進めた。特に、国際標準化に関しては、1F事故を教訓として国際的な高速炉の安全性
向上に係る取組に重点を移し、我が国主導で安全設計クライテリアを構築して で承認を
受け、 や高速炉開発各国の規制側との議論を進めるなど、大きな進展があった。
「エネルギー基本計画」策定後においては、高速炉の安全設計ガイドラインの具体案を作
成するとともに安全性強化に係る技術基盤の構築・強化を実施し、廃棄物減容・有害度低
減を目指した研究開発では、次期中長期計画期間での本格展開につながる成果が得られ
ている。また、国際協力として仏国の実証炉 (
)計画協力に対する体制を構築して具体的な研究協力
を進めている。
このようにそれぞれの期間で、中期計画に沿った成果が得られており、中期計画期間を
通して達成度は妥当と判断できる。
(新たな課題への反映の検討)
原子力政策を含むエネルギー政策の見直しの中で、文科省の「もんじゅ研究計画作業部
会」において、高速増殖炉サイクルを含む核燃料サイクルに係る研究開発の一翼を担う「も
- 10 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
んじゅ」等の具体的な研究計画が議論され、その際、原子力機構は「もんじゅ等を用いた研
究開発」の技術的な観点からの再整理に貢献した。その結果として、「もんじゅ研究計画」が
取りまとめられ、「エネルギー基本計画」に反映された。なお、「もんじゅ研究計画」で示され
た廃棄物減容・有害度低減及び安全性強化を目指した研究開発は、元来高速炉サイクル
研究の中で重点的に位置付けられるものであり、新たな課題とは言い難いとの意見もあっ
た。
国レベルの政策への反映は研究開発の再開に繋がるものであり、新たな課題への反映
の検討の観点からも原子力機構の一連の取組は適切であったと評価する。
(効果・効用(アウトカム))
フェーズⅠの成果(革新技術の採否可能性判断)である安全性・信頼性・経済性に
優れた高速炉サイクルシステムを構成する革新技術の妥当性の総合的評価は、日本のみ
ならず世界の高速炉開発における重要な基盤と成り得る。我が国主導で構築した安全設計
クライテリアの国際標準化は、世界で開発される高速炉の安全確保に貢献するとともに、我
が国が国際組織の中で中心的役割を果たしながら国際協力を進めるうえでも大きな効果が
期待でき高く評価できる。日仏 協力は、シビアアクシデント・燃料・原子炉技術の分
野における日仏の相互補完的効果が見られ、我が国の高速炉実証技術の確立への寄与が
期待できる。技術基盤の維持の一環で取組んだ燃料デブリの基礎特性評価や汚染水の除
染に係る検討は、1Fの廃止措置に向けた取組にも貢献するものと考えられる。なお、1F事
故関連の研究は原子力全体の問題であり、高速炉核燃料サイクルシステムの成果とするの
は疑問との意見もあった。
これらの取組みは今後の高速炉サイクル研究開発の発展に繋がり、また国際的にも認め
られるものであることから、効果・効用(アウトカム)の観点でも着実な成果が得られていると
認められる。
(その他)
予算と人員に制限がある中、原子力機構内外への人材育成の取り組み、実施体制の整備、
国際プロジェクトの活用、国内機関との連携、外部資金の獲得、成果発信、広聴・広報活動
も行われてきており、これらの活動を含めて、研究開発の管理運営は妥当であったと判断で
きる。
- 11 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
Ⅱ.評価の観点に基づく評価
事後評価は国の評価指針等に基づき、次に示す評価の観点から重要と考えられる評価
項目を設定して評価を行った。評価項目は次の(1)~(9)を設定した。
<必要性の観点>
(1)国費を用いた研究開発としての意義
(2)研究開発計画の妥当性
<有効性の観点>
(3)研究開発の達成度
(4)新たな課題への反映の検討
(5)効果・効用(アウトカム)
(6)人材育成の貢献の程度
<効率性の観点>
(7)実施体制の妥当性
(8)内外他機関との連携の妥当性
(9)目標・達成管理の妥当性
ここで、第2期中期目標期間中の研究開発の内容が大きく3つの期間(①革新技術の採
否判断、②技術基盤の維持、安全設計要求の国際標準化、③廃棄物減容・有害度低減及
び安全性強化を目指した研究開発)に区分されることから、(2)研究開発計画の妥当性及
び(3)研究開発の達成度については、それぞれの期間毎に評価した。また、「(8)内外他機
関との連携の妥当性」については、国外と国内とに分けて評価した。
以下には、評価項目ごとの「 」「 」「 」「 」の評定結果とそれに対応する意見が分かるよ
うにまとめた。また、「( )総合評価」にはそれぞれの委員の評価を示した。
(1)国費を用いた研究開発としての意義(国や社会のニーズへの適合性)
( :高く評価できる :評価できる 妥当である :概ね評価できる 概ね妥当である :
実績等が不十分である)
〔評価結果 名〕
年に策定された「エネルギー基本計画」にあるように、そもそも、高速炉サイクル技術開発を進めることは我が国のエネルギー政策に合致するものである。また、高速
炉サイクル開発研究を高いレベルで総合的に実施できる機関は の当該部門し
か国内には存在しない。以上二点より、当該部門における研究開発に国費を投入す
ることの意義は極めて大きいと考える。(ただし、安全性を十分に確保することは前提
であるが。)
エネルギー資源の乏しい我が国にとって、サイクルの技術開発は必須であり、高く評
- 12 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
価できる。
〔評価結果 : 名〕
「エネルギー基本計画」( 年 月閣議決定)に至る一連の政策によるものであり、妥当である。
現在、1F事故の処理が第一の急務ではあるものの、日本および世界の長期エネルギー事情を鑑みると、国費を用いてでも高速炉および核燃料サイクルの開発は必須
と考えられる。昨今の経済状況を考えると、以前に比べて十分な予算が確保されてい
るとは思われないが、高速炉および核燃料サイクルを積極的に推進している旧西側
先進国はフランスと日本のみであるので、少ない予算で効率良く研究・開発が進むよ
うフランス等と国際協力の下、研究開発を推進すべきである。
高速炉に関する研究開発および技術の維持は、世界から見ても重要課題であり、国費を投じて推進することは十分意義がある。また、1F事故後の高速炉に関する研究
開発の凍結後は、いかに技術維持を行い国際協力に尽力してきたかは評価に値す
る。しかしながら、国や社会への説明内容や説明方法には工夫が必要であり、国民
に分かりやすく丁寧に説明する手段を考えて欲しい。
高速炉サイクルの実用化は将来の我国のエネルギー供給の安定化のためのひとつの重要な選択肢であり、かつ放射性廃棄物の環境負荷低減の意味から大変重要で
ある。国費を投じる意義は大きいと考える。
高速炉サイクルの研究開発は国の原子力政策に沿うものであり、国費を投入する意義については自己評価のとおりで適切である。
政策の方向性に合致しており問題は見当たらない。 研究開発は、国の政策に従って適正に立案され、進められている。
(2)研究開発計画の妥当性
①革新技術の採否判断の期間( 年度)
( :高く評価できる :評価できる 妥当である :概ね評価できる 概ね妥当である :
実績等が不十分である)
〔評価結果 名全員〕
「エネルギー基本計画」( 年 月閣議決定)に至る一連の政策の方針に合致するものであり、基本的に妥当である。
年までの ・フェーズⅠまでの計画は、当時の状況では十分妥当であるし、現在の本来の計画が遂行出来ない状況を考えると、なおさら当時の計画が妥当であ
ったと言わざるをえない。
年度までは プロジェクトを中心に実施されてきたものの、実施に係るもので国の示す方針とも整合しているため、計画として妥当なものと判断した。
- 13 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
プロジェクトにおいて取り組まれた研究開発は、計画から得られた成果に至るまで、妥当なものだと考える。実際、外部有識者から構成される プロジェクトの評
価委員会において フェーズⅠにおける の取り組みが検証され、妥当なも
のであったと判断されている。評価者もその判断に賛同している。
計画として進められてきた研究計画であり、研究計画は妥当なものである。 評価とした。
国の方針に基づき開始された プロジェクトの実施に係る 年度までの研究開発計画は妥当である。
政策の方向性に合致しており問題は見当たらない。 1F事故前の状況において、 プロジェクトおよび関連した研究開発計画は適切に策定されていたと判断できる。ただし、 プロジェクトのあり方については、今後、
外的状況の変化を踏まえた見直しが不可欠である。
②技術基盤の維持の期間( 年度~ 年度)
( :高く評価できる :評価できる 妥当である :概ね評価できる 概ね妥当である :
実績等が不十分である)
〔評価結果 : 名〕
「エネルギー基本計画」( 年 月閣議決定)に至る一連の政策の方針に合致するものであり、基本的に妥当である。なお、「平成 年度原子力関係経費の見積りに関
する基本方針」( 年 月、原子力委員会決定)における「技術基盤の維持」や「国
際標準化への貢献」について、それぞれの定義(と内容)を確認する必要がある。
1F事故後は、1F事故対応を最優先課題とせざる得ない中でも、1F事故の経験を生かしたより安全な原子力システムの開発や1F事故対応の収束後の高速炉、サイクル
技術の開発の再開につながる計画であり、十分妥当と考えられる。
1F事故後は、 フェーズⅡが見送りとなったものの技術基盤の維持や国際標準化への貢献に注力したところは評価に値する。中でも第4世代原子力システム国際フ
ォーラム( )における我が国の主導による安全設計要求の構築とその国際標準化
に向けた取組みに関する計画は、後の活動に大きく影響を与えたとして評価できる。
なお、マイナーアクチニド分離技術などの研究開発や炉システム、核燃料サイクル技
術に関する研究開発における技術基盤の維持は重要であるものの研究技術が古い
物もあり、新しい技術開発への挑戦も行って欲しい。
1F事故を受けて、 フェーズⅡへの移行を見送り、代わりに、原子力委員会によって示された方針に従って、技術基盤の維持や国際標準化への対応に関する研究
開発に舵をきったことは、妥当な判断であるといえる。
1F事故後の技術基盤の維持、安全設計要求の国際標準化など期待された通りの研究開発を進めており、「 」評価とした。
- 14 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
1F事故後は、状況の変化を踏まえて国が示した方針に従い、技術基盤の維持や国際標準化への貢献を具体化した計画の見直しを行っており、妥当である。
1F事故後の状況変化に応じて計画を見直したことは適切な対応と評価する。特に開発の中で安全設計基準の構築に取り組むとしたことは高く評価できる。
1F事故後の研究計画は、国の方針に従って適切に設定されていたと判断する。〔評価結果 : 名〕
“技術基盤の維持”と“国際標準化への貢献”の具体的内容が明確でなく、 %妥当とする材料が不足である。
③廃棄物減容・有害度低減及び安全性強化を目指した研究開発( 年度)
( :高く評価できる :評価できる 妥当である :概ね評価できる 概ね妥当である :
実績等が不十分である)
〔評価結果 : 名〕
「エネルギー基本計画」( 年 月閣議決定)に至る一連の政策の方針に合致するものであり、基本的に妥当である。
廃棄物減容・有害度低減は、1F事故以前より掲げられていた目標であり、それは1F事故後も変わらない。むしろ1F事故を受けた「エネルギー基本計画」では、高速炉の
安全性強化とともにより強く支持されており、それに沿った計画は妥当である。
1F事故後は、 フェーズⅡが見送りとなったものの技術基盤の維持や国際標準化への貢献に注力したところは評価に値する。中でも第4世代原子力システム国際フ
ォーラム( )における我が国の主導による安全設計要求の構築とその国際標準化
に向けた取組みに関する計画は、後の活動に大きく影響を与えたとして評価できる。
なお、マイナーアクチニド分離技術などの研究開発や炉システム、核燃料サイクル技
術に関する研究開発における技術基盤の維持は重要であるものの研究技術が古い
物もあり、新しい技術開発への挑戦も行って欲しい。
主に、炉システムに関する研究開発として「安全性の強化」を、核燃料サイクルシステムに関する研究開発として「放射性廃棄物減容・有害度低減」に取り組んだことは、
妥当であるといえる。
高速炉の安全性強化に関しては十分研究を進めていると判断できる。マイナーアクチニド( )の分離核変換に関しては限られた予算で、十分な研究環境でなかった
ことを考慮すれば、総合的には「 」と評価できる。
「もんじゅ」については、 年 月に閣議決定された「エネルギー基本計画」に沿って、安全性強化、放射性廃棄物減容・有害度低減とこれらに必要な技術基盤の維持
を目指した計画の見直しを行っており、妥当である。
「エネルギー基本計画」に沿って開発の方向性を定めたことは妥当と考える。なお、高速炉サイクルが全面的に採用されるのは、 年程度先のことと考えられ、その間
- 15 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
の と の共存期間に必要とされる技術の開発に取り組むことも必要と考えられ
る。
「エネルギー基本計画」および「もんじゅ研究計画」の策定を受けての研究計画 高速炉の安全性向上、廃棄物減容・有害度低減、基盤技術強化 の設定は適切である。
〔評価結果 : 名〕
「もんじゅ研究計画」では、安全性強化や廃棄物減容・有害度低減に加え「これまでの高速炉研究開発成果のとりまとめ(実証)」が柱と位置付けられたはずである。
(3)研究開発の達成度
①革新技術の採否判断の期間( 年度)
( :高く評価できる :評価できる 妥当である :概ね評価できる 概ね妥当である :
実績等が不十分である)
〔評価結果 : 名〕
プロジェクトにおける革新技術の採否判断は、当時想定されていた達成目標に適合した形で行われており、妥当なものであったと判断する。
〔評価結果 : 名〕
それぞれの期間で目標とした研究開発は実施されているので基本的に妥当である。進捗状況は項目によるが、安全設計要件の国際標準化について特に進展が見られ
る。項目ごとの達成度については、炉システムの研究開発が先行しており、開発リスク
が認められる革新技術については、代替技術を合わせて検討していることなどが評
価される。(実用技術については性能の保証、特に今後は確率論的安全評価( :
)などのバックデータが求められる。)
妥当と判断する。本来であれば、「検討継続」とされた技術について、研究計画の策定と一部実施内容が含まれるべきであるが、震災以降中断されている現状を鑑み、
実施内容は妥当と判断する。
原子炉システムおよび核燃料サイクルシステム 再処理技術と燃料製造技術 の研究開発について、課題ごとに革新技術の採否可能性判断を行っている。原子炉システ
ムに関しては、「設計成立性」「製作性」「運転・保守性」「経済性」の4つの視点に基
づき採否判断を示しているのに対し、核燃料サイクルシステムでは、「技術的成立性」
と「性能目標への貢献度」の視点から採否判断されているため、双方に統一的な視
点もあっても良いと思われる。また、どれも重要課題ではあるものの思い切った判断も
必要ではないかと思われる。なお、 フェーズ の成果については、原子炉と核
燃料サイクルの双方についての評価委員会から十分な評価が得られている。
プロジェクトにおいて取り組まれた研究開発は、計画から得られた成果に至るま
- 16 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
で、妥当なものだと考える。実際、外部有識者から構成される プロジェクトの評
価委員会において フェーズⅠにおける の取り組みが検証され、妥当なも
のであったと判断されている。評価者もその判断に賛同している。
ナトリウム冷却炉については 種類の革新技術の採否が代替技術も含めて検討されており、原子力委員会の性能目標を概ね達成していることを確認している。核燃料
サイクル技術は の革新技術の採否判断がなされているが、約半数は検討継続課
題であるものの、ナトリウム冷却炉の革新技術と同様原子力委員会の性能目標を概
ね達成している。 フェーズ の研究開発の達成度は「 」評価とする。
革新技術の採否可能性判断については、炉システム、核燃料サイクルともに開発目標、性能目標を踏まえ、メーカ、電力と協力し適切に評価を行い判断しており、目的
を達成している。
〔評価結果 : 名〕
ナトリウム冷却炉技術では、照射試験の伴う高燃焼度炉心燃料技術でまだ判断結果が出ていないもののその他については採否の判断がなされている。一方核燃料サイ
クル技術については、 年度まで検討継続となった技術が多く、現在の状況を考
えると 年度までに判断することも困難と考えられるため、達成度は十分とは言え
ない。
データを取得しつつ、また、関係者と議論を続けながら革新技術の採否を検討したことは評価できる。また、代替技術の検討を進めた点も評価できる。なお、個人的には、
革新技術として開発が進められている技術要素は、遠隔メンテナンスを前提とした技
術が多く、実運用時の稼働率が懸念される。メンテナンスフリーの思想を開発に織り
込むことを期待したい。
②技術基盤の維持の期間( 年度~ 年度)
( :高く評価できる :評価できる 妥当である :概ね評価できる 概ね妥当である :
実績等が不十分である)
〔評価結果 : 名〕
技術基盤の維持は、最重要課題の一つであり、原子炉システムおよび核燃料サイクル関係において、十分に技術維持を行っていただきたい。なお、実証炉の概念設計
は行えなかったものの、設計基準を超える想定事象の進展防止のための設計方策を
適切に摘出し、国際標準を目指した安全設計クライテリアの構築を行い、各国の規制
側組織や の場で議論を進めて国際的な認識を深められたのは高く評価した
い。
安全設計要件の国際標準化では多国間国際協力を活用して我が国が主導的な役割を果たして要件を具体化し国際理解を得ることができた、という成果は卓越しており、
- 17 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
②③の時期の研究開発の達成度は「 」と評価されるべきである。
技術基盤の維持については、限られた研究資源を効率的に活用し、必要なデータの取得、解析及び試験の実施を通じて目的を達成した。特に、 において示したリー
ダーシップと成果としての安全設計クライテリアの構築は高く評価できる。さらに国際
的な安全基準高度化に関する議論の場、及び国内における学会活動等を通じて、
規制当局を含む関係者に における成果を共有するとともに、技術開発と安全基
準は車の両輪であって最も重要であるとの理解を促進する活動を期待する。
(安全設計要件の国際標準化)開発の中に安全基準構築を織り込み、国際的な認識を深めた点は高く評価できる。サイクル分野でも同様の取り組みを進めてもらいたい。
このために、事故時の核種挙動のデータ取得、サイクル施設の 手法の開発など
にも取り組んでもらいたい。
〔評価結果 : 名〕
それぞれの期間で目標とした研究開発は実施されているので基本的に妥当である。進捗状況は項目によるが、安全設計要件の国際標準化について特に進展が見られ
る。項目ごとの達成度については、炉システムの研究開発が先行しており、開発リスク
が認められる革新技術については、代替技術を合わせて検討していることなどが評
価される。(実用技術については性能の保証、特に今後は などのバックデータが
求められる。)
妥当と判断する。予算が削減されている状況で、外部資金などを有効活用して、継続課題の解決に取り組むとともに基盤技術を維持する内容を妥当と判断す
る。
技術基盤の維持および安全設計要求の国際基準化に関しては、福島対応に関係する部分もあり、これまでの機構の持つ研究資産の活用も含まれるものの短期間で十分
な成果をあげている。これらは、福島対応終了後、再度高速炉および核燃料サイクル
開発が再開された時に重要となる技術であるので、さらなる継続を期待する。
技術基盤の維持や国際標準化対応に関する成果が着実に挙げられている。 フェーズⅡに移行せずに大きく研究計画が変更されたこと、極めて限られた予算であっ
たこと、社会情勢等を鑑みると、ここで得られた成果(研究開発の達成度)は、質・量と
もに高いと評価できる。
炉システムについては高速増殖炉の解析・評価能力等に関わる技術基盤の維持と安全設計要求の国際標準化を進めている。核燃料サイクルについては再処理技術
基盤、燃料製造技術基盤の維持、福島対応技術の推進を達成しており、技術基盤の
維持に努めたと判断できる。以上の結果から「 」評価とする。
安全設計クライテリア( )の国際標準化が“我が国主導のもと”で の承認を得て、“各国規制側との議論を深めた”のが客観的事実であれば、評価は「 」ではなく
- 18 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
「 」となるべきである。
技術基盤の維持として実施した の構築作業は、ナトリウム高速炉の安全性のあり方 を見直す大変良い試みであり、高く評価できる。また、この成果を国際的に発信
し、国際標準にしようとするとする取り組みは、国際協力のあり方として一つのロール
モデルになり得るものである。引き続き、同様の取り組みをお願いしたい。
〔評価結果 : 名 評価と重複記載 〕
(技術基盤の維持)少ない予算の中で基礎的なデータの取得を進めたことは評価できる。グッドデータだけでなく、技術の限界を示すバッドデータの取得にも心がけても
らいたい。
③廃棄物減容・有害度低減及び安全性強化を目指した研究開発( 年度)
( :高く評価できる :評価できる 妥当である :概ね評価できる 概ね妥当である :
実績等が不十分である)
〔評価結果 : 名〕
進捗状況は項目によるが、安全設計要件の国際標準化について特に進展が見られる。項目ごとの達成度については、炉システムの研究開発が先行しており、開発リスク
が認められる革新技術については、代替技術を合わせて検討していることなどが評
価される。(実用技術については性能の保証、特に今後は などのバックデータが
求められる。)
安全設計要件の国際標準化では多国間国際協力を活用して我が国が主導的な役割を果たして要件を具体化し国際理解を得ることができた、という成果は卓越しており、
②③の時期の研究開発の達成度は「 」と評価されるべきである。
(安全設計要件の国際標準化)開発の中に安全基準構築を織り込み、国際的な認識を深めた点は高く評価できる。サイクル分野でも同様の取り組みを進めてもらいたい。
このために、事故時の核種挙動のデータ取得、サイクル施設の 手法の開発など
にも取り組んでもらいたい。
〔評価結果 : 名〕
妥当と判断する。なお、 を中心とする国際協力を進めるにあたって、冷却系機器開発試験施設( ) シビアアクシデント( )装置を用いた実験内容など、
日仏で共有できる内容、かつ、過去の研究と整合のある内容(シビアアクシデントシナ
リオの検証につながること)の精査が必要と考える。
廃棄物減容・有害度低減はこれまでも機構が継続して取り組んできた課題であり、シビアアクシデント対策など安全性強化に関する部分が加わって、1F事故を受けて加
速された。既に機構が持っていた資産や能力をフルに発揮したこともあり、短期間で
- 19 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
十分な成果をあげていると考えられる。
技術基盤の維持は、最重要課題の一つであり、原子炉システムおよび核燃料サイクル関係において、十分に技術維持を行っていただきたい。なお、実証炉の概念設計
は行えなかったものの、設計基準を超える想定事象の進展防止のための設計方策を
適切に摘出し、国際標準を目指した安全設計クライテリアの構築を行い、各国の規制
側組織や の場で議論を進めて国際的な認識を深められたのは高く評価した
い。
炉システムにおける「安全性の強化」、核燃料サイクルシステムにおける「放射性廃棄物減容・有害度低減」、いずれにおいても、短期間ではあるがそれぞれにおいて重要
な成果が挙げられている。特に、放射性廃棄物減容・有害度低減に関する研究成果
として、 含有燃料の基礎物性という極めて重要かつ貴重なデータが取得され始め
ており、今後の発展が大いに期待できる。
炉システムについては、安全設計ガイドラインの作成、シビアアクシデン対策試験計画及び炉心損傷時の影響緩和策等の安全性強化に係る技術基盤を構築、
計画への協力(日仏協力)を進めた。核燃料サイクルについては 含有燃料製造
技術として、抽出クロマトグラフィの基礎データ所得、 含有燃料製造や基礎的な
燃料特性の測定、解析、評価、シミュレーション技術を開発している。これらの成果か
ら「 」評価とする。
安全性強化を目指した研究開発では、安全アプローチガイドラインの具体化、SA対策や熱流動、高温構造設計手法の高度化等を推進するとともに、日仏協力を活用し
た安全性強化の取り組みも開始した。また、放射性廃棄物減容・有害度低減に関し
て 燃焼のための分離技術、燃料製造技術の開発に取り組んだ。これらにより、安
全性強化に関する目的を達成している。
安全性強化・廃棄物減容・ 取り扱いに関しては、まだこれらの活動が始まったばかりであることから、定量的な評価は困難であるが、計画策定時に想定されていた成
果は達成されたものと判断する。なお、廃棄物減容および 取り扱いについては、
「研究のための研究」という視野狭窄状態に陥らないことを望みたい。
(4)新たな課題への反映の検討
( :高く評価できる :評価できる 妥当である :概ね評価できる 概ね妥当である :
実績等が不十分である)
〔評価結果 : 名〕
エネルギー政策、特に、高速増殖炉サイクルを含む核燃料サイクル政策の検討に資するものであり、妥当。なお、廃棄物減容・有害度低減を目指した研究開発において
は、炉システムと同様、核燃料サイクルシステムの研究開発が重要であり、遅れが生
じないよう、留意する必要がある。
- 20 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
これも原子力専門研究機関である機構の持つ能力の高さの結果であり、新たな課題への反映も迅速に検討されている。
「もんじゅ研究開発作業部会」における「もんじゅ研究計画」策定は、放射性廃棄物減容・有害度低減や、高速増殖炉 高速炉の安全性強化を目指した研究に取り組むべ
きである事がまとめられており、「もんじゅ」独自の技術や、「海外炉」との共通技術な
どの整理を含めた国際的観点からも十分評価できる。
文部科学省「もんじゅ研究計画作業部会」において策定された研究計画に矛盾しない課題が、今後取り組むべきものとして適切に選定されている。
高速増殖炉 高速炉の安全性強化や廃棄物減容・有害度低減など新たな課題を明確にできたことから、「 」評価とする。
状況の変化に適切に対応し、国による審議会の活動を助勢し、当面の重要課題の抽出につなげた。
含有燃料の試験、炉心損傷後の再臨界可能性に関する安全研究などが提案されていることを確認した。後者は安全性向上に向けた重要な取り組みと評価する。
(所感)研究自体は妥当と思うが、廃棄物減容( 燃焼等)や安全性強化は1F事故がなかったとしても高速炉研究で重点的に位置づけられるべきものであり、“新たな課
題”であるとは考えられない。本来これは(2)研究計画の妥当性に含むべき項目かと
考える。
〔評価結果 : 名〕
一部、不十分と判断する。「もんじゅ」が計画通りに再稼働することを前提として策定されているが、性能試験の中断により約 年遅れていること、設計変更による試験手
順書の見直しが必要と予想されるため、研究実施前の作業が相当量生ずると予想す
る。
「もんじゅ研究計画作業部会」における の貢献は重要なものであったと認識するが、高速炉開発のリーダーシップを取る機関として、高速炉の固有安全など、より本
質的な課題に関する顕著な貢献をみることが出来なかった印象がある。
(5)効果・効用(アウトカム)
( :高く評価できる :評価できる 妥当である :概ね評価できる 概ね妥当である :
実績等が不十分である)
〔評価結果 : 名〕
プロジェクトにおいて実施した革新技術の採否判断・妥当性評価を通じて、我が国の高速炉開発の基盤構築に大きく貢献した。
高速炉の国際的な安全設計クライテリアを我が国主導で構築したことは、高速炉研究に関する国際協力・連携を加速させるものである。
- 21 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
燃料デブリの特性評価や汚染水除染の検討といった研究開発を通じて、1Fの廃止措置に向けた取り組みに貢献するだけでなく、関連する技術基盤の維持にも努め
た。
取り扱いの極めて困難なマイナーアクチニド元素を含有する高速炉燃料や高速炉材料に関する貴重な基礎物性データが取得されている。これらのデータは、我が国に
おいて高速炉開発を進める上で今後必ず有益なものになるだろう。
〔評価結果 : 名〕
それぞれの期間で目標とした研究開発は実施され、それぞれの効果が得られているので、基本的に妥当である。なお、1Fの廃止措置に向けた取組については、研究開
発計画(技術基盤の維持)の観点からの補足説明が必要である。
現在高速炉や核燃料サイクルを積極的に開発している旧西側先進国は日本とフランスだけであり、その成果の世界への貢献度は高い。また、1F事故およびその対応の
経験も大変貴重である。 はそれについて十分自負と責任を持って取り組むこと
を期待する。
革新技術の採否判断において、高速炉の安全性・信頼性・経済性の総合評価は世界の高速炉開発における重要な基盤となり評価できる。
安全設計クライテリアの構築は、高速炉研究の専門家及び学識経験者による学術的検討をもとに取りまとめられ、これを国際組織の中で中心的役割を果たしながら国際
協力および国際標準化に貢献していることは高く評価できる。
日仏 協力は、シビアアクシデント・燃料・原子炉技術の分野における日仏の相互補完的効果が見られ、我が国の高速炉実証技術確立に寄与しているものと評価
できる。
高速炉燃料測定技術などを応用し、燃料デブリの取出し、保管、処理処分に寄与するテーマの検討、設備整備、模擬デブリの基礎データの取得、汚染水の除染に係る
検討等を行い、1Fの廃止措置に向けた取組に寄与しているが、高速炉研究におけ
る従来の核燃料サイクル技術や再処理技術をさらに応用した廃止措置に向けた新た
な取り組みも期待したい。
日本原子力研究開発機構は 年 月に東海の再処理施設を廃止するとの方針を明らかにしたが、廃止に伴い中期計画に明示されている高速炉の核燃料サイクルの
技術基盤の維持に不安が生じることになった。また、高速炉の基盤技術が維持され
なければ、廃棄物減容・有害度低減を目指した研究開発についても実現が危ぶまれ
ることになる。自己点検内容の文書にこの件を言及すべきである。
高速炉開発に重要な基盤の構築、安全設計クライテリアの国際標準化の推進、協力(日仏協力)による安全性向上技術の開発、福島除染技術開発など、多
くの効果・効用が認められる。 評価とする。
- 22 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
効果・効用に関する自己評価は適切である。特に国際的な安全設計クライテリアの確立に主導的役割を発揮して貢献したことは高く評価できる。
非常に良い取り組みであるとともに、高い成果も出ていると評価する。今後は、他国の規制機関が関与しているのと同様、我が国の規制機関が関与できる枠組みの構築を
期待する。また、サイクル分野でも同様の取り組みに期待する。予算の制約のある中、
国際協力を進めるとしたこと、技術基盤維持の一環として、1F事故収束のためのデ
ータ取得をしたことも評価できる。基礎データの充実は非常に大切と評価する。なお、
バッドデータも貴重な知見として残していくことが重要である。
革新技術については、当時の情勢に基づき、適正な採否判断が出来たと判断する。 設計クライテリアについては、国際標準になり得るものを作成することが出来、極めて高い効果があったものと考えられる。
燃料デブリの取り出しについては、高速炉開発と直接関連しないとの見方も可能であろうが、基盤技術の維持・発展の観点からこのようなチャレンジングな課題に取り組む
ことは価値がある。なお、1Fに関連する研究成果 高速炉分野に直接関連しないもの
も含む に関しては、高速炉開発にどのように活用できるか、統一的に検討しても良い
のではないかと考える。
含有燃料物性の基礎特性把握は、その技術的成立性を確認するために重要である。一方で、得られた基礎基盤技術をどのような形で実用化技術につなげていくか
の見通しを検討しておくことは同様に必要である。現段階では、この道筋はまだ明確
になっておらず、今後の継続的な検討が望まれる。
〔評価結果 : 名〕
(評価「 」とした主な根拠)今後、ロシア・中国・インドで建設される高速炉に現 が適用されるかは不確実性が大きい。更に、 を“これまで”我が国主導で構築し、ま
た プロジェクトに協力していくことが“今後とも”我が国の安全技術の進歩、国
際化、技術実証に大きく貢献できるかどうかは、その見通しがある、とはいえるが断定
はできない。特に はフランスのプロジェクトであり、中国もロシアも注目してい
る中、我が国の貢献度評価にあたってはより客観的に見る必要がある。
(その他所感)一連の1F事故関連の研究は、高速炉サイクルというより原子力全体
に関わる問題である。新たな課題への対応として適切であったとは言えるが、高速炉
核燃料サイクルシステムの成果とするのは疑問がある。
(6)人材育成の貢献の程度
( :高く評価できる :評価できる 妥当である :概ね評価できる 概ね妥当である :
実績等が不十分である)
〔評価結果 : 名〕
- 23 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
原子力分野での人材育成では大学も厳しい状況下にあり、その中で機構は独自の人材育成を行っているだけでなく、大学との連携にしっかり関与し、大学間の連携に
おいても中心的役割を担うなど貢献度は大きい。
次の世代を考えた人材育成は重要であり、「もんじゅ」が停止している中、新しいプラントの 開発に人材を投入して行くことは評価したい。また、リタイアしたベテラ
ンの経験を若手に伝える努力は十分評価できる。
〔評価結果 : 名〕
人員と予算に制限があるなか、機構内外への人材育成の取組みが行われており、妥当である。
妥当と判断する。 年を 世代とするとき、 世代分停止状態にあることから、今後も、技術継承のための人材確保と教育・訓練を継続されることを強く希望する。
機構内部はもちろん、機構外部に対しても積極的な人材育成を様々な手段で行っている。この手のことは、成果が現れるのに時間はかかるが、話を聞く限り、効果的な活
動がなされているように思われる。これを継続することが重要と考える。博士の採用や
社会人ドクター制度に対しても高い理解を示していたことは、当該部門が我が国を代
表する(あるいは我が国唯一の)高速炉研究機関であることを考えると、評価者として
は好印象であった。
原子力技術は技術伝承が一般に難しく、特に「もんじゅ」は長期にわたり本格稼働ができない状況にあり、人材育成と技術伝承が難しい状況にある。座学とシミュレータを
利用しての可能な限りの努力をされていると評価できる。本項は「 」評価とするが、将
来の本格運転に向けてさらなる人材育成・技術伝承への努力を期待する。
「もんじゅ」の保守管理の問題で集中改革を実施する中で、人材育成の視点を持ち続け、機構内外においてやり方を工夫し、人材の育成に貢献したと評価できる。
インターンシップなどにより、次世代の人材育成に取り組んでいることは評価できる。
(7)実施体制の妥当性
( :高く評価できる :評価できる 妥当である :概ね評価できる 概ね妥当である :
実績等が不十分である)
〔評価結果 : 名〕
原子力機構全体の組織体制と業務を抜本的に見直す状況の中、機動的な事業運営のための実施体制の整備が行われてきており、妥当である。
予算が限定された状況での活動として妥当と判断する。 東日本大震災による東海・大洗施設への被害や1F事故対応の影響のあるその体制は十分妥当であったと言える。
限られた人員と予算の中での組織体制の整備は高く評価できる。
- 24 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
実施体制が妥当なものであるかどうかについて、今回の説明を聞くだけでは判断できなかった。実際、体制が優れたものであるかどうか、つまり体制の妥当性を評価する
ためには、ある程度の時間が必要と考える。とはいえ、震災等の外部要因に対して、
柔軟かつ速やかに体制を変更したことは高く評価できる。
研究開発体制の大幅な組織改革により柔軟な実施体制がとられていることは評価できる。高速炉計画の推進は重要であり、その円滑な推進のためにもプラントの維持管
理や保守管理をしっかりできる体制構築をお願いしたい。
状況、環境の変化に柔軟に対応し、実施体制を整備したと評価できる。 震災などの大きな状況変化に応じて、機構全体として、大きく組織・運営を見直して対応した点については、適切な対応であったと評価できる。
プロジェクトについては、外的条件が大きく変わる中、実施体制を適正に変更・対応させてきている。
(8) 1 国外他機関との連携の妥当性
( :高く評価できる :評価できる 妥当である :概ね評価できる 概ね妥当である :
実績等が不十分である)
〔評価結果 : 名〕
安全設計要件の国際標準化では多国間国際協力を活用して我が国が主導的な役割を果たして要件を具体化し国際理解を得ることができた、という成果は卓越しており、
研究開発の達成度は「 」と評価されるべきである。
〔評価結果 : 名〕
人員と予算に制限があるなか、国際プロジェクトの活用が行われており、基本的に妥当である。
妥当と判断する。ただし、炉型(ループ型/プール型)や燃料形態(一部の海外は非酸化物燃料を検討)の状況下において、共通に協力できる事項や、国際標準となりう
る内容について継続的に検討されることを期待する。
以前より高速炉および核燃料サイクル開発における国際協力は必須である。ましてや1F事故以降はなおさら重要と考えられる。ぜひ、 には、この分野の国際協力
において、日本がイニシアティブをとることを期待する。
国際協力の中でも において世界をリードする姿勢が見られ評価に値する。特に、国内における学術的検討のもと、安全設計クライテリアや安全設計ガイドラインの構
築は、世界の基準・規則の具体化に大きく貢献できると期待できる。また、多国間の
国際協力の推進により、国際的な信頼を得ているものと考える。
日仏間、日米仏間を中心として、着実な国際協力・連携が進められている。これらの連携は妥当なものであるといえる。また、高速炉の国際的な安全設計クライテリアを我
- 25 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
が国主導で定めたことは、高く評価できる。
日米仏三国間協力、日仏二国間協力により炉システム、核燃料サイクルの技術開発、の革新的原子炉及び燃料サイクル国際プロジェクト( :
)への参加、日米二国間協力の日米民生用原子力
研究開発協力のワーキンググループ( : )に
よる高速炉・核燃料サイクルの技術基盤の高度化など活発な国際協力により研究開
発の効率的推進やリスク低減、国際的基準・規則の作成を行っている。「 」評価とす
る。
1F事故後の我が国の原子力及び高速炉の研究開発を取り巻く環境が厳しい中で、多様な国際協力を活用し、広い視野を持ちながら連携を深め、研究開発や国際基準
等の作成を効率的に行ってきた。
予算の制約の中、国際協力を進めた点は評価できる。 適正に国際的な連携が図られていると判断する。
〔評価結果 : 名〕
自己評価を見る限り、手がけたどの分野においても我が国が一番ではあるが、そのほかに手掛けるべき分野はないのか。これまで手をつけてこなかった分野でも日本の技
術のプレゼンスをアピールし、国際貢献していく方向で何か成果を出せたら、より印
象が良くなる。
(8) 2 国内他機関との連携の妥当性
( :高く評価できる :評価できる 妥当である :概ね評価できる 概ね妥当である :
実績等が不十分である)
〔評価結果 : 名〕
予算削減の中で、海外との連携協力を積極的に進めたことは高く評価できる。また、五者協といった国、メーカ、ユーザからなる協議会を立ち上げ、ステイクホルダーから
の意見も踏まえて開発を進めた点も高く評価できる。
〔評価結果 : 名〕
人員と予算に制限があるなか、国際プロジェクトの活用、国内機関との連携が行われており、基本的に妥当である。
妥当と判断する。現状、産業界は少なくとも短期的には軽水炉へリソースを集中しているため、リソース維持のインセンティブを示すことのできる活動を継続的に進められ
ることを期待する。
大学としては、十分連携してもらっていると認識している。 国内及び国際的な連携は高く評価できる。
- 26 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
国内機関と強固で有機的なネットワークを構築していることは、ポジティブに評価できる。大学等とも連携を図ることで、人材育成にも貢献できている。
高速炉サイクルの開発に対して政策的に不透明な状況においては技術基盤の維持が重要課題である。五者体制の維持と国際協力( 協力)を進めていることは
評価できる。ただ、予算は限られているのは承知しているが、大学等研究機関との連
携による基礎基盤研究の推進を今後もお願いしたい。これは優秀な人材確保の意味
からも重要である。
国際協力及び国内機関との協力関係を有効に活用し、高速炉の研究機関としての国際的な連携、及び国内の五者体制、大学等との連携を良好に維持したと評価でき
る。
国内機関との連携は概ね適正にはかられている。五者体制については、その活動がよく見えない印象がある。
(9)目標・達成管理の妥当性
( :高く評価できる :評価できる 妥当である :概ね評価できる 概ね妥当である :
実績等が不十分である)
〔評価結果 : 名〕
原子力機構内外の状況が大きく変化するなか、予算及び人員を含めて、研究開発の管理運営が行われてきており、基本的に妥当である。なお、研究開発においては、そ
の結果を積み重ねていくことが重要であり、成功・不成功、また公開・非公開を問わず、
その結果を体系的に整理しておく必要がある。
予算と人員が限定されている状況での活動として妥当と判断する。 社会状況が大きく変わり、予算や人員が減少する中、その目標および研究管理は十分になされたと思われる。
組織のマネジメント力(特にトップ層の)については、今回の説明だけでは判断できなかった。ただ、限られた予算、人員の中で、最大限の成果を得るように柔軟な対応を
とっていたことは高く評価できる。(重要な開発項目に人員を割いたり、外部資金を獲
得したりしている。)広報については、専門家はもちろん専門家以外の人たちに対し
ても積極的に行われているようである。これについても、人材育成同様、効果が表れ
るのに時間は随分かかると思われる。根気強く継続することが重要であろう。あとは概
ね特段問題となるようなことは見いだせなかった。
研究計画管理の体制は評価できる。ただ、研究評価については、新規性や面白さだけで判断すると研究課題の選定が総花的なものになりがちである。技術開発の継続
性を考慮した計画的・効率的なものであって欲しい。研究全体を俯瞰して見ることが
できる研究管理体制が必要である。予算については研究に使える予算が限られてい
ることから、外部資金獲得の努力は評価できる。研究論文、外部発表など成果の発
- 27 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
信にも十分に取り組まれている。研究開発成果のデータベース化による知識共有へ
の取り組みは、将来のための重要な仕事であり、しっかり進めていただきたい。
組織としての研究開発プロジェクトの管理とラインや個人の業務管理についてを回すとともに品質保証活動を展開し、必要な予算と人員の確保、成果の発信、広
報活動を的確に行ったと評価できる。
問題発生の都度、適宜計画を見直すなど適切に対応してきたことが確認できた。保守管理の問題については、本当に十分な人員・予算が投入されてきたか、品質保証
が機能していたのかどうか、疑問が残る。情報発信・外部資金の活用等については、
適切に実施していることが確認できた。
外部資金の獲得(海外も含む)は当初計画では想定外だったはずで、「 」ではないか。広報・広聴活動は実施しただけでは不十分で、本来ならば成果のエビデンスが
望ましい。
研究計画管理の は概ね適正に回されている。
( )総合評価
( :高く評価できる :評価できる 妥当である :概ね評価できる 概ね妥当である :
実績等が不十分である)
〔評価結果 : 名〕
平成 年度以降の研究開発としては、当初の計画からの変更があるが、エネルギー基本計画(平成 年 月閣議決定)に至る一連の政策を受けて継続的に実施されて
きており、妥当である。
炉システムの研究開発が先行しており、開発リスクが認められる革新技術については代替技術を合わせて検討していることや、安全設計要件の国際標準化について主導
的な取組を進めていることなどが評価される。なお、核燃料サイクルシステムについて
は、研究資源の制約のなか検討課題も少なくないが、廃棄物減容・有害度低減を目
指した研究開発においては、炉システムと同様に重要であり、遅れが生じないよう、留
意する必要がある。
中期計画初期から外部情勢の変化(資金及び政策)に応じて研究開発の内容を再構築して実施されており妥当と判断する。
海外協力として挙げられている仏国「 」との研究内容については、共有できること、我が国の高速炉システム開発において優先順位が高い内容であることを確認し
て進められたい。
1F事故等社会情勢が大きく変わるなか、その時々に応じて課せられた課題に迅速に対応しており、日本で唯一の国立の原子力研究機関としての責務を十分果たしてい
ると言える。
高速炉に関する研究開発および技術の維持は、世界から見ても重要課題であり、十
- 28 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
分評価に値する。また、1F事故後の高速炉研究の凍結後は、いかに技術維持を行
い国際協力に尽力してきたか高く評価したい。ただし、国や社会への説明内容や説
明方法には工夫が必要であり、国民に分かりやすく丁寧に説明する手段を考えて欲
しい。
1F事故前までの研究開発( フェーズⅠ)に関しては「 」に近い「 」、1F事故後の研究開発に関しては概ね「 」、全体を総合的にみて「 」と判断する。
高速炉の安全性に関わる取組により安全設計クライテリアが国際的に評価され、国際標準化に向けて進展していることは特に評価できる。核燃料サイクル技術に関しては
1F事故により 計画の凍結で十分に研究開発できなかった点はあるものの、少
ない予算の中で可能な仕事を進めた点は評価できる。第2期中期計画の達成がほぼ
見込めることから、「 」評価とする。
第2期中期目標期間中の1F事故とそれに伴う原子力政策の変更等、環境の変化に応じて高速炉サイクルの研究開発計画を適切に変更して対応してきた。特に、安全
設計クライテリア及び安全設計ガイドラインの構築については、国際的な貢献度も高
く、サイクルについても限られたリソースの中でできる限りの工夫を施し成果を生み出
したことから、総合的に妥当と評価できる。
以前の活動は、計画に沿って適切に遂行されていたと評価する。 以降の環境の激変に関しては、 に対応した大きな組織目標の変更を自主的に行った上で、
最小限の経営資源の中で目標を見直し対応しており、適切に開発を進めてきたと評
価する。
厳しい環境変化のもと、特に国際プロジェクトに大きく貢献した点が評価できる。体制や予算を言い訳にすることのないよう、現実的な目標管理を今後も期待する。
総体として期待される成果を上げたものと判断される。
- 29 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
Ⅲ.個別評価のまとめ
1)評価シート提出委員:計 名
2)評価項目等と評価基準
(1)国費を用いた研究開発としての意義
(2)研究開発計画の妥当性
(3)研究開発の達成度
(4)新たな課題への反映の検討
(5)効果・効用(アウトカム)
(6)人材育成の貢献の程度
(7)実施体制の妥当性
(8)国内外他機関との連携の妥当性
(9)目標・達成管理の妥当性
( )総合評価
- 30 -
JAEA-Evaluation 2015-005
-
( :高く評価できる :評価できる 妥当である :概ね評価できる 概ね妥当である :実
績等が不十分である)
①革新技術の採否
判断( 年度)
②技術基�



![連続亜鉛めっき - Hitachi428 日立評論 VOL.57 No.5(1975-5) ペイオフリール シヤー 酸化炉 人側ループカー めっき槽 選元炉] しヱ+ 出側ループカー](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/60c3af1a6e370a4d5840a91f/ecoee-hitachi-428-cee-vol57-no51975-5-fffff.jpg)