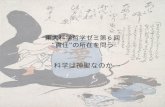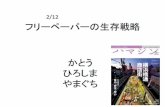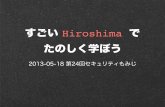第5章 青山学院大学 教育人間科学部 竹下ゼミ・法学部 熊谷ゼミcd/pdp/pdf/chapter5.pdf · 51 第5章 青山学院大学 教育人間科学部 竹下ゼミ・法学部
2018年度...
Transcript of 2018年度...
1
目次
1 はじめに
2 基本情報
2 - 1 ほぼ日手帳とは
2 - 2 ほぼ日手帳の沿革
2 - 3 ほぼ日刊イトイ新聞とは
3 本研究のKH Coder分析で用いた『ほぼ日手帳公式ガイドブック』該当箇所一覧
4 KH Coderを用いた計量テキスト分析
5 おわりに
6 参考文献
2
1 はじめに
「ほぼ日手帳」という手帳がある。手帳といってもスケジュールを書き込むことができ、スケジュー
ルを書き込めるといっても自由帳のように好きなものを切り貼りすることができる。スケジュール帳
でもなければ日記でもメモ帳でもない、「ほぼ日手帳」というひとつのコンテンツである。
この不思議な手帳は株式会社ほぼ日が制作・販売している。「ほぼ日」の中心コンテンツである「ほ
ぼ日手帳」を取り巻く世界観、哲学は、一見すると制作側とユーザーで密に共有され、共同してコン
テンツを作り上げているように見える。
それが本当ならば、テキストマイニングを行った際には似通った語句が抽出されるのではないか。そ
して、ユーザーを年々増やし続けるほぼ日手帳の魅力を、テキストの中から見つけ出せるのではない
だろうか。
分析の対象を「糸井重里」「カバー制作者」「ユーザー」に分割することで比較が明確に行えると考
え、それぞれの記述を「セクション」としてグループ化してKH Coderで分析を行ってみる。
分析結果が似通っていた際は、どういった言葉によってその世界観が共有されているのかをさらに考
察する。もし結果に相違があるのであれば、どこに相違があるのか、なぜ相違があるのか、そしてそ
の相違によってどのようなことが考えられるかを分析し結果を考察する。
また、自分の将来のためにKH coderを用いたテキストマイニングの方法を習得することも目的の一つ
として研究を進める。
3
2 基本情報
2 - 1 ほぼ日手帳とは
株式会社ほぼ日が2002年より制作・販売している手帳。2018年時点での発行部数は780,000部、2019
年1月現在で世界に78万人のユーザーがいる。特徴は主に ⑴1日1ページ仕様 ⑵「ほぼ日刊イトイ
新聞」内のコンテンツから引用した読み物「日々の言葉」 ⑶薄くて丈夫な紙「トモエリバー」を使
用 ⑶180度開く手帳本体 ⑷毎年約80種類の新作が出る手帳カバー ⑸ペンを2本差すことができる
バタフライストッパーなど。基本の手帳本体は6種類あり、2002年から続く文庫本サイズ「オリジナ
ル」、A5サイズ「カズン」、週間手帳「WEEKS」、英語版「Hobonichi Planner」、中国限定販売「簡
体字版」、5年版「ほぼ日5年手帳」。また「オリジナル」と「カズン」には分冊版の「avec」、「WE
EKS」にはメモページが3倍の「WEEKS MEGA」がある。通常のほぼ日手帳は1月始まりだが、4月始まり
の「spring」が2006年から作られている。
【表1】ほぼ日刊イトイ新聞「ほぼ日手帳、これまでの歩み」より作成
4
2 - 2 ほぼ日手帳の沿革
2002年 ほぼ日手帳の誕生
2003年 バタフライストッパーが登場
2004年 カバーが選べるようになる
2005年 全国のロフトで販売スタート
2006年 公式ガイドブック発行開始
2007年 フェイクファブリックカバーの登場
2008年 ツートンカバー登場
2009年 A5サイズのほぼ日手帳『カズン』誕生、本体リニューアル
2010年 54種類のカバーが誕生
2011年 週間のほぼ日手帳『WEEKS』誕生
2012年 東日本大震災の被災者に手帳を無償提供
2013年 ほぼ日手帳の英語版『Hobonichi Planner』誕生
2014年 ほぼ日手帳コピー大賞開催
2015年 ほぼ日手帳分冊版『avec』誕生
2016年 ユーザー参加型イベント「ほぼ日手帳使ってます!60人ミーティング」開催
2017年 全国各地でユーザーと手帳の話をする「ほぼ日手帳ミーティングキャラバン」開始
2018年 『ほぼ日5年手帳』誕生
2 - 3 ほぼ日刊イトイ新聞とは
ほぼ日刊イトイ新聞(通称:「ほぼ日」ほぼにちと読む)は糸井重里が主宰する1998年6月6日創刊の
ウェブサイトである。コピーライターだった糸井氏が毎日更新するエッセイ「今日のダーリン」やイ
ンタビュー、コラムなどの無料コンテンツを多数掲載。「ほぼ日手帳」をはじめ、腹巻きやタオル、
カレーなどの生活関連商品を開発し、サイト内の「ほぼ日ストア」で販売している。運営は株式会社
ほぼ日(創業:1979年12月24日 代表取締役社長:糸井重里 証券コード:3560)。
参考
株式会社ほぼ日(ほぼ日)
1998年に創刊したウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」を運営。主力商品である「ほぼ日手帳」をはじめとするオリジナルの
文具、日用雑貨などの企画販売や店舗・ギャラリーイベントスペースの「TOBOCHI」、犬猫の写真を投稿するSNSアプリ「ドコ
ノコ」、さまざまなアーティスト、ブランド、企業などと一緒につくる買いものを中心としたイベント「生活のたのしみ展」、
古典をテーマとする「ほぼ日の学校」など、人々が集う「場」を創造、「いい時間」を提供するコンテンツを企画、編集、制
作、販売する。2017年3月、東証ジャスダック市場に上場。糸井重里が代表取締役社長を務める。(『すいません、ほぼ日の
経営。』日経BP社 より抜粋)
5
3 本研究のKH Coder分析で用いた『ほぼ日手帳公式ガイドブック』該当箇所一覧
※ ユーザーインタビュー該当部分は斜体
2009 「あなたといっしょに、手帳が育つ。」
「静かな改良」こそが、大事な仕事だと思った。 糸井重里インタビュー p.08
リズムを整えるという仕事。 グラフィックデザイナー佐藤卓さんインタビュー p.13
こんなことにもなり得る手帳。47人の自由な使いかた
(平原綾香さん p.42/青野慶久さん p.46/たかしまてつをさん p.50)
2010 「手帳といっしょに、あなたが育つ。」
たのしいほうがいいに決まってる、と思います。 ほぼ日刊イトイ新聞 糸井重里 p.06
カバーキーパーソンに聞く
(佐藤卓さん、日下部昌子さん p.18/牧野隆司さん p.19/森蔭大介さん p.20/平武朗さん p.
21)
結論の微調整、3.7ミリ方眼。ほぼ日手帳2010の方眼の大きさはこうして決まった。
(デザインとは世の中に隠れている数式を発見すること。 糸井重里 佐藤卓 対談 p.40)
使っている人の数だけ使いかたがある手帳。43通りの自由な使いかた
(千秋さん p.46/クハラカズユキさん p.48/高田聖子さん p.50/荻野目洋子さん p.52)
2011 「いっしょにいて、たのしい手帳と。」
思いっきりたのしんでください。 ほぼ日刊イトイ新聞 糸井重里 p.06
たのしさがあるから、自由に使える手帳。ー23の自由で勝手な使いかた
(坂本美雨さん p.14/清水ミチコさん p.18/梶原しげるさん p.20/秋山具義さん p.22)
ほぼ日手帳2011ーさらに自由なコラボレーション(アンリ・べグラン/皆川明/GEORGE) p.100
2012 「どの日も、どの日も、大切な日。」
「なんでもない日、おめでとう。」という実感。 ほぼ日刊イトイ新聞 糸井重里 p.06
書いたり描いたり貼ったり読んだり。38人の自由で、楽しい使いかた。
(小久保裕紀さん p.14/あずまきよひこさん p.26)
その瞬間、誤解によってデザインが生まれた。佐藤卓さんに聞く、〈ほぼ日手帳WEEKS〉 p.106
ほぼ日手帳2012 個性派カバーピックアップ(アンリ・べグラン/皆川明) p.110
2013 「ほぼ日手帳と、その世界。」
ほぼ日手帳と、その世界。(ソニアパーク×佐藤卓×糸井重里 p.06/三國万里子 p.14/LOCHCARR
ON p.18/mina perhonen p.20/世界の伝統柄シリーズで旅をする。 p.24/HENRY CUIR p.28)
ほぼ日手帳と、その世界。ー30人の使いかた。ー(菊池亜希子さん p.44/村主章枝さん p.48/川
相昌弘さん p.52)
名づけようのないものをすくい上げるいちばん目の粗い網として、〈ほぼ日手帳〉はあります。 糸
井重里 p.122
2014 「このしのわたしは、たのしい。」
ほぼ日手帳を一緒に作ってくれた人。(荒井良二さん p.10/ひびのこづえさん p.11/平野暁臣さ
ん p.12/アンリ・べグランさん p.13)
33人のたのしい手帳と70の使いかたテクニック。(道端ジェシカさん p.62/福岡晃子さん p.66)
「ほぼ日手帳一座」なんです。 糸井重里 p.138
6
2015 「LIFEのBOOK」
Pick Up Cover(ミナペルホネン p.12/荒井良二さん p.14/中川翔子さん p.16/MOTHER2 p.18)
「新しい提案」ができるかどうか。ほぼ日手帳は、どのように変わっていくのか? 糸井重里インタ
ビュー p.22
31人のLIFEのBOOK ほぼ日手帳の使い方。(松井玲奈さん p.80/祖父江慎さん p.90/浅生鴨さん
p.96)
2016 「This is my LIFE」
ほぼ日手帳2016 TOPICKS(CACUMA p.14/ミナペルホネン p.16/MOTHER2 p.18)
ほぼ日手帳2016インタビュー(祖父江慎さん p.20/ミロコマチコさん p.21/佐藤卓さん p.22/
大江健さん p.23)
25人のLIFEのBOOK ほぼ日手帳の使い方。
(鈴木保奈美さん p.82/佐藤卓さんと日下部昌子さん p.86/夢眠ねむさん p.90)
ほぼ日手帳は、公園。つくろうと思っても、つくれない。 糸井重里インタビュー p.154
2017 「This is my LIFE.」
ことしの注目はこちら!Cover News 2017(増田セバスチャン p.12/Snow Peak p.14/ミナペルホ
ネン p.16/『MOTHER2』 p.18/junaida p.20/平林奈緒美 p.21/CACUMA p.22/POTTENBURNTO
HKII p.23)
39人のLIFEのBOOK(鈴木杏さん p.84/横峰沙弥香さん p.92)
ほぼ日手帳の航海は、これからが本番です。 糸井重里インタビュー p.154
2018 「LIFEのBOOK」
ほぼ日手帳、使ってます!(石田ゆり子さん p.08/布巻峻介さん p.12/坂本真綾さん p.14/や
ついいちろうさん p.16/前田知洋さん p.18)
ほぼ日手帳はいつも、ニュースをもたらすものでありたい。 糸井重里インタビュー p.94
Pick Up! ことしの注目カバー。(鹿児島睦 p.146/『さよならペンギン』 p.147/『MOTHER2』
p.148/星野道夫 p.149/A VERY MERRY EVERY DAY to you p.150/ザ・ビートルズ p.151/シュ
タイフ p.155)
2019 「LIFEのBOOK」
ほぼ日手帳は、人生だ! THIS IS MY LIFE.(加賀楓さん p.13/中村悠一さん p.16/エステル・
モリナさん p.20)
5年手帳の1年目。 高田明×糸井重里 対談再録 p.78
コンパスの針をおろす場所に、ほぼ日手帳がある。 糸井重里インタビュー p.150
*対象選定基準
糸井重里インタビュー、糸井重里署名あり文章、カバー制作対談、カバー制作者インタビュー、本体制作対談、一般ユーザー
を除く著名な(と著者が認定した)ユーザーインタビュー。
※新作カバーの紹介においては、制作者(またはそれに関わる人物)個人の意見・意図を含まない「説明書き」は省く。
※該当者なしの場合もしくはサンプル数が少なかった場合は、インタビュー冒頭3名分。複数名合同もしくは組織へのインタ
ビュー(回答者が複数いるなど)は対象外。
7
4 KH Coderを用いた計量テキスト分析
強制抽出語について
ほぼ日/ほぼ日手帳/1日ページ/一日ページ/カズン/ことば/たのしい/うれしい/わかる/わ
たし/きもち/よく/つよく/つくる/おもしろい/じぶん/友だち/友達/ともだち/自由/ほし
い/なぜ/驚き/おどろき/自信/思いだす/思い出す/豊か/基本/表現/人間/テーマ/めんど
くさい
*強制抽出語選定の基準…ほぼ日手帳公式ガイドブックまたは糸井重里氏の文章の傾向として、平仮
名にひらいた言葉が多いため、テキストデータを作成する過程で重要だと判別したキーワードを強制
抽出語として選定。その他にも、ほぼ日手帳の世界観を示すだろうと推測したキーワードも選定。
【表2】単純集計の結果
項目 語数 単純集計
総抽出語数 異なり語数 文 段落
総データ 71,325 5,290 2,703 112
*総抽出語数‥‥分析対象ファイルに含まれているすべての語の延べ数
*異なり語数‥‥何種類の語が含まれていたかを示す数
8
【表3】頻出語上位30語の比較
糸井重里 制作 ユーザー
抽出語
出現
回数 抽出語
出現
回数 抽出語
出現
回数 抽出語
出現
回数 抽出語
出現
回数 抽出語
出現
回数
手帳 168 うれしい 12 手帳 380 書く 54 手帳 302 見る 39
ほぼ日 121 じぶん 12 思う 206 いま 49 書く 243 人 37
人 89 言葉 12 ほぼ日 192 よく 44 使う 159 多い 37
思う 64 お客 11 人 186 持つ 44 ほぼ日 136 ページ 36
使う 51 たくさん 11 カバー 175 時間 42 思う 101 感じ 34
書く 28 意見 11 使う 170 笑 42 笑 87 言葉 34
言う 26 新しい 11 デザイン 114 卓 40 自分 70 作る 32
考える 26 知る 11 作る 104 違う 37 スケジュ
ール 60 あと 29
よく 21 話 11 見る 69 革 37 描く 54 毎日 25
作る 21 いま 10 考える 69 今回 37 仕事 49 カバー 24
時間 21 感じる 10 自分 64 選ぶ 37 日記 49 管理 23
見る 19 気持ち 10 色 62 世界 36 メモ 48 持つ 23
仕事 15 今年 10 描く 61 出る 34 言う 42 最近 22
言える 14 出す 10 言う 59 感じる 33 絵 41 前 22
自分 14 卓 10 生地 55 新しい 32 いま 39 感じる 20
【表4】特徴語10語の比較
糸井重里 制作 ユーザー
ほぼ日 0.152 カバー 0.113 手帳 0.195
手帳 0.149 思う 0.099 書く 0.195
人 0.124 デザイン 0.077 使う 0.12
思う 0.085 人 0.071 ほぼ日 0.107
言う 0.045 作る 0.056 笑 0.085
考える 0.044 色 0.043 自分 0.057
時間 0.04 描く 0.039 スケジュール 0.055
よく 0.039 見る 0.038 メモ 0.046
見る 0.034 生地 0.037 日記 0.045
言える 0.031 考える 0.034 仕事 0.044
9
まず、【表3】を見てみると、頻出語の上位それぞれ5位くらいまでは、順位は前後するものの然程違
いが見られないということがわかる。しかしそれ以降の順位において、セクション「糸井重里」「制
作側」「ユーザー」で特徴的な語句が確認できる。
糸井重里‥‥「言う」「考える」など、糸井重里本人の頭の中が言語化されているような語句が特徴
的。「よく」「時間」などの頻出度が他よりも高い
制作‥‥「デザイン」「作る」「色」「描く」などデザインに関係する語句が多いが、その中でも
「見る」「考える」「自分」「言う」など、主語が一人称である可能性が高い語句が多い。
ユーザー‥‥ユーザーとしての一般的な語句である「スケジュール」「日記」「メモ」などが見られ
る点に特徴はないが、「自分」主体であることが伺えたり、「いま」というライブ感を連想させる語
句の頻出度が他よりも高い
頻出上位の語句に相違が見られないという点では特徴が見られなかった。しかし外部変数をセクショ
ン設定して対応分析を行ったところ、以下の結果が得られた。
【表5】対応分析>外部変数「セクション(糸井重里/制作/ユーザー)」>バブルプロット
10
原点に対してセクション「糸井重里」「制作」「ユーザー」の3つが離れてプロットされている。KH
Coderの対応分析は原点から離れている語ほど特徴的であるため、【表3,4】からだけでは読み取るこ
とができなかった特徴語を【表5】から読み取ることができる。
ここで、原点から最も離れた位置にプロットされているセクション「糸井重里」の特徴語について考
えてみる。
セクション「糸井重里」の特徴語は「時間」「人」「ほぼ日」「新しい」あたりだと考えられる。そ
こで糸井重里氏の単独インタビューもしくは本人の書いた文章のみに分析データを絞り、関連語検索
「時間」で結果を抽出した。
【表6】セクション「糸井重里」>KWICコンコーダンス:抽出語「時間」
糸井重里氏の文中に「時間」という語句は21回登場している。これはセクション「糸井重里」におけ
る頻出語リストでは11番目に位置する。しかし動詞や形容詞ではなく名詞としては「手帳「ほぼ日」
「人」に次ぐ4番目だ。セクション「糸井重里」において「時間」という語句が重要であることがみ
て取れる。
さらに「時間」の前後の語句を見ると、「孤独な」「名前もつかないような」「名づけようのない」
「なんだかよくわからない」という言葉が目立つ。特にこの「名前のつかない」という意味合いで
「時間」と言う語句が用いられたのは2013年のガイドブックである。
「名づけようのないものをすくい上げるいちばん目の粗い網として、〈ほぼ日手帳〉はあります。」 ぼくは、むかしからひとりでいるところが想像できない人とは友だちになれないかもしれない、と思っていた。ひとりでいる
ときに、なにを考えているのか。その孤独な時間を、なにに使っているのか。その人のほんとうのところは、ひとりでいると
きにどうしているか、ではないかと思う。‥‥(中略)‥‥人が、ひとりでいるときには、もっとこう、ぼんやりした、なん
でもない、名前もつかないような時間があるものだ。‥‥(中略)‥‥そういう、名づけようのない時間を、名づけようのな
い気持ちを持っているということが、その人をつくる大きな要素だと思うんです。そして、ある日、そういう中に、ぽこん、
と泡みたいに、ことばとして生まれちゃうものがある。そのことばを書き留められるものとして〈ほぼ日手帳〉が役に立った
らいいなぁ、と思う。‥‥(中略)‥‥「言える形のもの」だけで人の時間がすべて埋まってしまったら、つまらないなぁと
ぼくは思うんです。なんというか、それは、全人類の総財産をちっとも増やさないと思う。だから、これからは、「なんだか
よくわからない時間」というものがますます大事になってくる。‥‥(中略)‥‥その名づけようのない時間の中で、思った
り、感じたり考えたりしたことを、拾える網みたいなものに、〈ほぼ日手帳〉が使われたらいいですよね。‥‥(後略)
『ほぼ日手帳公式ガイドブック2013 ほぼ日手帳と、その世界。』糸井重里 p.122
ほぼ日手帳の活用方法としては「同じことをするなら、たのしいほうがいい、というのが〈ほぼ日手
帳〉に込められているメッセージだと思っています。」と2011年の記述で明文化されているが、2009
11
年から2019年まで毎年、冒頭または結びの言葉として書かれている糸井重里氏の文章において「ほぼ
日手帳の存在目的」について明確に語られているのは2013年だけである。
この「名づけようのない時間」という語句がセクション「糸井重里」における最も特徴的な言葉であ
り、さらにほぼ日手帳の世界観にも通じる語句だと考えて、他との差異、特にユーザーとの差異を考
えていく。
ほぼ日側は「ほぼ日手帳の使い方は自由」と銘打っているものの、糸井重里氏が言及している「名づ
けようのない時間」は、ほぼ日手帳の存在目的であり「使い方の枠組み」として重要な要素である。
そこで次に気になるのが、ほぼ日手帳のユーザーは「名づけようのない時間」に対してどのような使
い方をしているのかという点だ。
頻出具合が高かった「書く」という語句で共起ネットワークを作成してみると以下の結果が得られた。
【表7】セクション「ユーザー」>関連語検索「書く」>共起ネット
上記の結果から、セクション「糸井重里」の特徴語から推測した「名づけようのない時間」に関係す
るセクション「ユーザー」の該当箇所は、共起ネットワークのサブグラフ「04」の赤で色付けられた
部分だと考えられる。理由としては、セクション「糸井重里」における頻出語【表3】と【表7】サブ
グラフの「04」では共通する語句が多く、また2013年のほぼ日手帳公式ガイドブックにおける糸井重
里氏の文章の内容とも関連する語句が多いと判断できるからである。
そこで、赤色の「04」部分に注目して語の繋がりをKWICとともに辿っていくと、ユーザーは「ふだん」
から「よく」書いたものを「見返す」ことを通して「考えたり」「思い出」したりでき、印象的な言
葉やエピソードの「キーワード」に「気づく」ことで「次」に向かうことができている、ということ
が推測できる。
12
ここで得られる考察としては、ほぼ日手帳の特徴は「入力」「ブラックボックス」「出力」という3
つの要素に分類できるのではないか、ということである。
ほぼ日手帳以外の手帳は「入力」が主な目的である。スケジュールを記入して、その記入されたスケ
ジュールを忘れないようにするための記憶保持の補助といった役割がある。例として挙げられるのは
能率手帳や高橋手帳などのビジネス手帳などである。
しかしほぼ日手帳は「入力」した内容を後に読み返すことで発見が得られることが多々起こる(実際
に【表7】を見ても「見返す」「思い出せる」という意味の語句が複数見られる)。その発見は「成
長」という形で「次」に繋がったり、記しておいた「キーワード」を後に深く考えてみるきっかけが
できたりと様々な形で「出力」される。しかしその入出力の間に存在するのは「名づけようのない時
間」であり、言い換えれば「ブラックボックス」である。記入した内容がどのような作用をもたらす
かその時には判定できないが、後に何かの形で作用することが大いにあり得るからである。
ほぼ日手帳の使い方はあくまでユーザーの自由だが、糸井重里氏が意図するところの「名づけようの
ない時間」や「ぽこん、と泡みたいに、ことばとして生まれちゃうもの」は、その時点では存在目的
がわからないかもしれない。しかし、「『言える形のもの』だけで人の時間がすべて埋まってしまっ
たら、つまらないなぁとぼくは思うんです。」という糸井重里氏の言葉のように、ブラックボックス
的なものの存在がほぼ日手帳の良さであり、その得体の知れないものに対する興味が多くのユーザー
を惹きつける理由なのだろう。
13
5 おわりに
私は2013年から自分の手帳を保管している。書き込めるスペースの大きい月間カレンダーを主に選ん
でずっと使ってきた。
この研究を機に、それぞれの年を振り返ってみた。日付は、4月4日に適当に定めてみた。
2013年4月4日(木) 「対面式と合同で1日リハ」
2014年4月4日(金) 「泊まり」「シルク・ド・ソレイユ 12:30〜」
2015年4月4日(土) 「御殿場オリエンテーション・キャンプ 東山荘(とうざんそう)」
2016年4月4日(月) 「上北沢自動車学校 8:50〜9:40 技能⑥」「美容院13:00〜」
2017年4月4日(火) 「自分というコンテンツが、誰かにとって価値や影響力をもてたら嬉しい」
2018年4月4日(水) 「日経BPバイト」「よごさわ歯科矯正 9:30〜11:00」
お分かりいただけるだろうか。2017年だけ、ほぼ日手帳を使っていたのである。なぜ2017年だけほぼ
日手帳を選んだのかはもう覚えていないが、1日ページを日記のように使っていた。実際の4月4日の
ページには、コンテンツにまつわる自分の考えがびっしりと書き留めてあった。
確かに、手帳の内容を振り返るという行為だけで、たとえその内容が「御殿場オリエンテーション・
キャンプ 東山荘(とうざんそう)」だけだったとしても、ある程度の思い出や記憶は蘇ってくる。
しかし自らの感情や決意を簡潔に記しておくだけで、後に見返したときに頭の中を巡る内容はこうも
違うのかということを研究を終わらせた今、自らで実感できている。「就活のことなんて考えていな
かったけど、この頃からコンテンツに興味持っていたんだなあ」とか、「結局就活でも同じこと考え
てたなあ」とか、「でも”自分”に対象を絞って考えていることは、今はしていないなあ」とかであ
る。2017年4月4日は友人と花見をした日だったので、月間カレンダーの普通の手帳に「花見」とだけ
書いていたら「花見に行った」ということしか思い出せなかっただろう。
私は、言語化できていない思考は絶対に深まることはないと考えている。普通の手帳には「思考の記
録」という役割はない。しかしほぼ日手帳には思考を書き留めてみようという気持ちが自然と湧き上
がってくる。きっとそれは、組織のトップが「言葉のプロ」のコピーライターであり、自分が彼に対
して憧れの念を持っている部分があることも大いに関係している。しかしきっと多くのユーザーがそ
ういう気持ちで使っていることと思う。「読み返したら面白いだろうな」「その時何を思うんだろう
な」というモチベーションで活用されているほぼ日手帳の「ブラックボックス」の謎はまだ深い。機
会があれば、次はもっと深い研究をしたい。
14
6 参考文献
株式会社ほぼ日 会社概要
https://www.hobonichi.co.jp/company/about.html
ほぼ日刊イトイ新聞について
https://www.1101.com/help/
ほぼ日手帳とは?
https://www.1101.com/store/techo/ja/2019/pc/about/about.html
ほぼ日手帳、これまでの歩み
https://www.1101.com/store/techo/ja/2019/pc/about/history.html
ほぼ日手帳公式ガイドブック
2009 「あなたといっしょに、手帳が育つ。」
2010 「手帳といっしょに、あなたが育つ。」
2011 「いっしょにいて、たのしい手帳と。」
2012 「どの日も、どの日も、大切な日。」
2013 「ほぼ日手帳と、その世界。」
2014 「このしのわたしは、たのしい。」
2015 「LIFEのBOOK」
2016 「This is my LIFE」
2017 「This is my LIFE.」
2018 「LIFEのBOOK」
2019 「LIFEのBOOK」
「すいません、ほぼ日の経営。」聞き手:川島蓉子/語り手:糸井重里(日経BP社 2018)
本研究のKH Coderの活用において参考にした文献は以下
『KH Coder 3 チュートリアル 漱石「こころ」を題材に【スライド版】(樋口耕一作成)』
『KH Coder 3 リファレンス・マニュアル 2018 年10 月30 日(樋口耕一作成)』
『Text Mining Maniax フリーソフトで始める日本語計量テキスト分析(後藤和智著/後藤和智事務
所 OffLine)