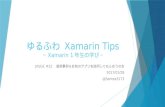ふわりんクルージョン2017年01月
-
Upload
tomokazu-takashima -
Category
Government & Nonprofit
-
view
159 -
download
0
Transcript of ふわりんクルージョン2017年01月
<難病の子どもと家族を支えるプログラムのご紹介①プログラム背景>
難病の子どもと家族の課題に取り組み、「みんなの命」を考える
▼人工呼吸器、胃婁、内部障害のある子ども• 先天性心疾患
• 内科的、外科的治療の飛躍的進歩により予後は改善。
• 酸素ボンベが必要。
• 子どもから大人に成長する中での生活困難
平成27年度小児等在宅移行研修事業 多職種合同研修(東京都助成、はるたか会) 資料より
▼予後不良の染色体異常の子ども• 染色体異常(例:18トリソミー)
• 50%は1週間以内に、1歳超えての生存は、5~10%
• 日本では積極的な治療により、長期生存例(成人例)も。
▼がんの子ども(End Of Life Care)• 患児の生命予後が限られている。小児緩和ケア。
• 人生全体の時間の中で、困難な状態の割合が大きい。
• 不条理感、受容の困難さが大きい。
• 希望を持ち続けるためのサポート(訪問看護、リハビリ、訪問学級)
家
周産期母子医療センタ(NICU)
小児総合医療施設・子ども病院
小児がん拠点病院
二次医療圏小児対応病院
幼稚園・保育園
小学校・中学校
高校・大学
就職・就労
家医療機関
福祉施設
リハビリ施設
家族支援
病院
家
<退院・地域生活のスタート>ケア十分の病院から離れる不安
<病院・家の往復>子どもと離れた環境
家族の心理的・経済的負担
<子どもが成長する日々>成長の期待とともに広がる生活空間への不安
新生児・入院児
退院する子ども・家族
地域(自宅)で暮らす子ども
子どもと家族の社会的孤立を防ぐ、みんながみんなを支える取組みを推進
<難病の子どもと家族を支えるプログラムのご紹介①プログラム背景 -難病の子どもと家族の実情>
生活環境の変化に伴う不安、成長する期待・喜びを感じる日々
難病の子どもと家族を支えるプログラム 28事業(22団体)
在宅生活を支える 入院生活を支える キャンプ・旅行を支える
建物関連整備 5事業 - 1事業 ※
モデルづくり 1事業 5事業 ※ 6事業 ※
人材育成 4事業
調査 2事業
ソーシャルムーブメント(啓発) 4事業 ※
4
2016年度
※
助成・支援団体ネットワーク会議開催(2016年5月25日)
5
ワークショップ①
自然災害への備え
ワークショップ②
みんなで考える社会的インパクト
• 投入(INPUT:リソース)
• 活動(ACTIVITY:達成されたアクション)
• 結果(OUTPUT:活動結果)
• 成果(OUTCOME:短期と長期目標)
• 波及効果(IMPACT:長期的目標)
2016年度
助成・支援団体ネットワーク会議開催(2016年11月16日)
6
アイスブレーク
みんなで日本地図をつくろう
情報共有①
2016年4月開設拠点の動向
• うりずん(栃木県)
• もみじの家(東京都)
• あおぞら共和国(山梨県)
• TSURUMIこどもホスピス(大阪府)
情報共有②
施策動向(医療的ケアが必要な障害児に
対する支援について)
アイディアソン①
団体間の連携の可能性
アイディアソン②
スポーツ x 支援活動の可能性
2016年度
7
様々な専門家がつながり、支えあう地域
療養通所介護事業所
訪問診療医
児童発達支援事業所
訪問看護ステーション
放課後等ディサービス
相談支援センター 居宅訪問型保育事業所
医療型特定短期入所事業所
特別支援学校
中学校
小学校
就労支援事業所
保育園
子育て支援センター
病院内学級
看護師が教える
ピアノ教室
日本財団 国内災害支援実績
1995 阪神・淡路大震災 兵庫県
1997 ロシア船籍タンカー重油流出事故
1998
北関東・南東北豪雨 福島県・栃木県
高知豪雨災害 高知県
神戸新湊川水害 兵庫県神戸市
1999広島呉水害・神戸新湊川水害 広島県呉市、兵庫県神戸市
岩手県軽米水害 岩手県軽米町
2000
有珠山噴火 北海道伊達市
東海豪雨 愛知県名古屋市
鳥取県西部地震 鳥取県
2001芸予地震 広島県、愛媛県、山口県
高知県西部豪雨 高知県
2003 宮城県北部連続地震 宮城県
2004
新潟水害 新潟県
福井水害 福井県
高松高潮水害 香川県高松市
三重水害 三重県
台風23号水害 兵庫県豊岡市
新潟県中越地震 新潟県
2005 台風14号水害 宮崎県宮崎市
2006 平成18年7月豪雨 長野県岡谷市、下諏訪町
2007能登半島地震 石川県
中越沖地震 新潟県
2008岩手・宮城内陸地震 宮城県栗原市
平成20年8月末豪雨 愛知県名古屋市、岡崎市
2009山口県豪雨 山口県
台風9号水害 兵庫県佐用町
2010台風9号豪雨水害 静岡県小山町
鹿児島県奄美地方における大雨災害 鹿児島県奄美市
2011
霧島山新燃岳の噴火 宮崎県
東日本大震災 岩手県、宮城県、福島県、他
紀伊半島豪雨水害 和歌山県、奈良県
2012九州北部豪雨水害 大分県、熊本県、福岡県
京都府南部豪雨水害 京都府宇治市
2013
静岡県西伊豆町豪雨水害 静岡県西伊豆町
岩手県一関市豪雨水害 岩手県一関市
山口県豪雨水害 山口県阿東市、萩市
秋田・岩手水害 岩手県雫石市
山口島根豪雨 島根県江津市、浜田市
台風18号水害 福井県若桜町
2014
平成26年雪害 山梨県甲府市
山形台風8号豪雨水害 山形県南陽市
長野台風8号豪雨水害 長野県南木曽市
台風11号、12号被害 徳島県南陽市、阿南市
丹波豪雨災害 兵庫県丹波市
広島土砂災害 広島県広島市
長野県北部地震 長野県白馬村、小谷村
2015 平成27年9月関東・東北豪雨 栃木県、茨城県、福島県、宮城県
2016
平成28年熊本地震 熊本県、大分県
平成28年6月豪雨 広島県福山市、熊本県
台風10号水害 北海道、岩手県
台風16号土砂災害 鹿児島県垂水市
鳥取県中部地震 鳥取県倉吉市他
●1995年~
● 2000年~
● 2006年~
●2010年~
●2016年~
東灘区森南町3丁目2(1995年1月18日)
写真提供:神戸市(http://kobe117shinsai.jp/)
東灘区田中町1丁目周辺(1995年1月20日)
長田区御屋敷通2丁目(1995年1月19日) 東灘区深江南町付近(1995年1月18日)
長田区海運町と日吉町の間(1995年1月17日)
灘区神前町周辺(1995年1月17日)
長田区_二葉5・6大正筋(1月)
写真提供:神戸市(http://kobe117shinsai.jp/)
大石東町6-2-1 西郷小学校(1995年2月9日)魚崎南町6丁目「東灘体育館」(1995年1月20日)
中央区避難所学校体育館内部(1995年1月17日) 「神戸市立蓮池小学校」(1995年1月19日) 「神戸市立蓮池小学校」(1995年1月19日)
松町6丁目3 若松公園(1995年2月26日)
五番町2・3丁目「室内商店街付近」(1995年1月21日)
長田区真野小学校(1995年4月6日) 六甲ライナー代替バスのりば(1995年7月16日)
写真提供:神戸市(http://kobe117shinsai.jp/)
日本財団 国内災害支援実績
1995 阪神・淡路大震災 兵庫県
1997 ロシア船籍タンカー重油流出事故
1998
北関東・南東北豪雨 福島県・栃木県
高知豪雨災害 高知県
神戸新湊川水害 兵庫県神戸市
1999広島呉水害・神戸新湊川水害 広島県呉市、兵庫県神戸市
岩手県軽米水害 岩手県軽米町
2000
有珠山噴火 北海道伊達市
東海豪雨 愛知県名古屋市
鳥取県西部地震 鳥取県
2001芸予地震 広島県、愛媛県、山口県
高知県西部豪雨 高知県
2003 宮城県北部連続地震 宮城県
2004
新潟水害 新潟県
福井水害 福井県
高松高潮水害 香川県高松市
三重水害 三重県
台風23号水害 兵庫県豊岡市
新潟県中越地震 新潟県
2005 台風14号水害 宮崎県宮崎市
2006 平成18年7月豪雨 長野県岡谷市、下諏訪町
2007能登半島地震 石川県
中越沖地震 新潟県
2008岩手・宮城内陸地震 宮城県栗原市
平成20年8月末豪雨 愛知県名古屋市、岡崎市
2009山口県豪雨 山口県
台風9号水害 兵庫県佐用町
2010台風9号豪雨水害 静岡県小山町
鹿児島県奄美地方における大雨災害 鹿児島県奄美市
2011
霧島山新燃岳の噴火 宮崎県
東日本大震災 岩手県、宮城県、福島県、他
紀伊半島豪雨水害 和歌山県、奈良県
2012九州北部豪雨水害 大分県、熊本県、福岡県
京都府南部豪雨水害 京都府宇治市
2013
静岡県西伊豆町豪雨水害 静岡県西伊豆町
岩手県一関市豪雨水害 岩手県一関市
山口県豪雨水害 山口県阿東市、萩市
秋田・岩手水害 岩手県雫石市
山口島根豪雨 島根県江津市、浜田市
台風18号水害 福井県若桜町
2014
平成26年雪害 山梨県甲府市
山形台風8号豪雨水害 山形県南陽市
長野台風8号豪雨水害 長野県南木曽市
台風11号、12号被害 徳島県南陽市、阿南市
丹波豪雨災害 兵庫県丹波市
広島土砂災害 広島県広島市
長野県北部地震 長野県白馬村、小谷村
2015 平成27年9月関東・東北豪雨 栃木県、茨城県、福島県、宮城県
2016
平成28年熊本地震 熊本県、大分県
平成28年6月豪雨 広島県福山市、熊本県
台風10号水害 北海道、岩手県
台風16号土砂災害 鹿児島県垂水市
鳥取県中部地震 鳥取県倉吉市他
●1995年~
● 2000年~
● 2006年~
●2010年~
●2016年~
37
12
2 1 10
5
10
15
20
25
30
35
40
45
日本財団における熊本地震に対する初動
2016年4月14日(木)地震 マグニチュード (Mj) 6.5
2016年4月15日(金)先遣隊 派遣
2016年4月16日(土)地震 マグニチュード (Mj) 7.3
2016年4月17日(日)支援に関する検討会議
2016年4月18日(月)助成実績団体への被害状況確認開始
2016年4月19日(火)第一弾支援策発表
① 緊急対策支援(3億円)
② 100万円を上限としたNPO、ボランティア活動支援(10億円)
③ 家屋損壊(全半壊)等に対する見舞金の支給(20億円)
④ 事業再建資金のための融資制度の創設(30億円)
⑤ 熊本城再建のための支援(30億円)
2016年4月26日(火)日本財団災害復興支援センター 熊本本部 開設
実施主体 事業費 事業内容 主な活動地域
(特)災害医療ACT研究所 137,300,000円医師や保健師等の医療専門職のチームが避難所の評価を行い、仮設トイレの使用が困難な要援護者が多い避難
所・福祉施設に無水無臭のラップ式トイレを設置(400個/126箇所)。熊本県
熊本小児在宅ケア・人工呼吸療法研究会 31,360,000円医療ケアが必要な子どもと家族の避難生活支援、自宅復帰生活支援の実施。相談、医療ケア(付添)、親の
ストレス解放、訪問診療、看護、介護など。熊本県
(一財)全日本ろうあ連盟 6,900,000円 聴覚障害者に対し、手話通訳者などの専門家を配置・派遣することによる、生活支援・相談支援の実施。 熊本県
(特)日本相談支援専門員協会 58,980,000円 生活支援が必要と思われる障害者世帯へ、ITを通じたニーズ把握、調整の実施。 熊本県、益城町
(特)み・らいず 18,650,000円在宅避難をしている障害者の方を中心とした戸別訪問や、施設に福祉専門職員を派遣し、障害者や高齢者
のケアの実施。熊本県御船町
(福)熊本市社会福祉協議会 9,990,000円 熊本市災害ボランティアセンター設置運営。資機材(土嚢袋、ヘルメット、一輪車、防塵ゴーグル)などの購入。 熊本県熊本市
(福)南阿蘇村社会福祉協議会 9,960,000円南阿蘇村災害ボランティアセンター支所の運営スタッフの配置および備品購入などの環境整備。移送支援、付
き添い支援などの実施。熊本県南阿蘇村
(福)西原村社会福祉協議会 8,360,000円西原村災害ボランティアセンター設置運営。ボランティアニーズ調査の実施。ボランティア募集、受け入れ。被
災家屋の片付けや避難所の支援。生活支援や農業復興支援に関する活動の実施など。熊本県西原村
益城災害FMボランティア連絡会 7,160,000円臨時災害放送局による益城町被災者への情報提供。地震情報、生活再建に繋がる情報、警報・注意報などの気象情報などをラジオおよびインターネットで提供。
熊本県益城町
(特)静岡県ボランティア協会 4,700,000円 ボランティアセンターの立ち上げ・運営支援およびボランティア派遣の実施。 熊本県嘉島町、西原村
(一社)危機管理教育研究所 18,000,000円 被災地における車中泊者の状況調査およびトレーラーハウスを利用して車中泊者のケアの実施。 熊本県益城町
熊本県復興リハビリテーションセンター 13,500,000円 避難所および仮設住宅における高齢者のためのリハビリテーションプログラムの実施。 熊本県
日本財団自主事業 51,149,200円長期化する避難生活における災害関連死等の被害拡大防止を目的とした、避難所および在宅避難者の状況
調査、および被災者支援拠点としての避難所運営支援の実施。熊本県益城町
緊急対策支援事業一覧(13事業) ※2016年7月28日現在
■「難病の子どもと家族を支えるプログラム」における緊急支援について
① 4月20日 緊急支援に関するニーズ調査開始
② 4月25日 「小児在宅に関するケア体制」 「周産期医療体制」に関するニーズ確認。
③ 4月30日、5月1日 熊本訪問
④ 5月6日 「医療的ケアの必要な子ども・家族の支援(専門職派遣)事業」を発表
緊急対策支援(医療ケアが必要な子ども関連)
■期間:
・3ヶ月
■予算(概算)
3,136万円
・人件費 1,800万円
・移動経費 850万円
・拠点経費 486万円
■体制
熊本小児在宅ケア・人口呼吸研究会
緒方氏(開業医)、杉野氏(開業医)、近藤氏/川瀬氏/
鍬田氏(市民病院)、島津氏(再春荘病院・ネクステッ
プ)、小篠氏・岩田氏(熊大病院)、戸枝氏(むそう)
■対象児(重複・もれあり)
・医療ケアの必要な子ども(127人、うち超重症は47
人)
・市民病院の患者(酸素60人、人工呼吸器9人、複数合併
47人)
・熊本大学病院入院(62人)
・障害者手帳受給児、手帳の範囲に入らない子ども
■支援概要
• 人口呼吸器、たんの吸引など医療ケアが必要な子ども等が、県内外の病院や療育センターに
一時的に避難している。また、避難所、車中泊の家族も財団先遣チームで確認されている。
• 医療的ケアが常時必要なため、自宅損壊確認や、自宅復帰作業が困難な状況となっている。
• 熊本小児在宅ケア・人工呼吸研究会を中心に、①子どもをケアするチーム、②親をサポート
するチームの体制を整え、自宅復帰支援を行う。
• 医療、介護、保育職が、親の代わりに医療ケア、子どもの療育を行い、同時に看護、介護職
が親とともに自宅復帰準備を行う。
• 3ヶ月をメドに、医療、看護、介護、保育の専門職の派遣を行う。
①医療ケア、内部障害等で困っている方々の相談支援
②入院中の子ども、避難している子どもの医療ケア(付添い)支援と
帰宅に向けた家族支援
③子どもの療育支援と親のレスパイト(一時的休息)支援
④在宅生活を支える訪問診療、看護、介護の実施
医療的ケアの必要な子ども・家族の支援(専門職派遣) 3,136万円<概算>
緊急対策支援(日本財団自主事業)
• 長期化する避難生活における災害関連死等の被害拡大防止を目的とした、避難所および在宅
避難者の状況調査、および被災者支援拠点としての避難所運営支援の実施。
① 2016年5月5日~8日 益城町の調査(1回目)
避難所中心とした避難所のハードと被災者の状況のアセスメント
② 2016年5月14日~29日 益城町の調査(2回目)
在宅避難者の状況のアセスメント
③ 2016年7月29日~8月5日 益城の調査(3回目)
仮設住宅が完成される中の、住宅移行の意向調査
調査の目的
長期化する避難生活で被害拡大防止を目的とした支援を実施するための情報収集
調査日時
2016年5月5日~8日
調査内容と対象
(1) 避難世帯の状況調査
避難所を利用する225世帯(647人)に家屋の被災状況や避難所の環境等を調査。
(2) 避難所の環境アセスメント
避難者数の多い避難所7カ所(避難者総数約3,000人)を訪問し、施設・設備・備品の整備状況や、避難者支援の状況を調査。
○調査結果
・避難所(車中泊を含む)からの「退去予定がない」世帯が全体の83%
・単身または2人世帯が全避難世帯の半数を占める
・食事について避難所利用者の20%が必要十分を満たしていないと回答
○分析結果
・避難生活の長期化:「退去予定がない」世帯だけでも2,000人以上*が避難生活を継続
・要支援世帯の増加:避難世帯に占める単身・非就労・高齢世帯割合が増加する
・健康状態の悪化:栄養不足や動きのない生活で体力が落ち、感染症リスクも増大する
避難所および在宅避難者の状況調査①
調査の目的
調査1(5月5日~8日実施)の対象外だった在宅避難世帯へ必要な支援を実施するための情報収集。
調査日時
2016年5月14日~29日
調査内容と対象
(1) 在宅避難世帯の状況調査
被害の大きい地区で自宅の敷地内などで生活する1,243世帯(3,195人)に家屋の被災
状況や避難生活の環境を調査。
(2) 併せて、高齢者、障害者等の社会的弱者の支援ニーズの実態調査も実施。
○調査結果
・調査対象1,243世帯のうち、応急危険度判定で「要注意」以上が全体の54%
・「要注意」以上世帯の44%が必ずしも安全でない自宅内で生活を継続している
・「要注意」以上世帯の56%が二次災害リスクが高い場所で生活
・「要注意」以上世帯のうち、65歳以上の高齢者が1人以上いる世帯が57%
○分析結果
・益城町全体で1,000人以上が安全ではない場所で避難生活を送っていると見込まれる。
・浸水や土砂崩れ等、余震及び梅雨や台風時期の大雨等による二次災害発生リスクが高い地域においては、要援護者
(高齢者など)が更に危機的状況に陥る可能性大。
避難所および在宅避難者の状況調査②
調査の目的
仮設住宅へ生活拠点を移行した後の被災者の生活支援の為の実態を把握すること。
調査日時
2016年7月29日~8月5日
調査内容と対象
益城町内12カ所の避難所の利用者で、8月以降も避難所を継続的に利用することを予定している364世帯、915人。(調査実施率:99.2%)
○調査結果
・避難所を利用している364世帯の内、152世帯(41.8%)は高齢者のみ、91世帯(25.0%)に高齢者が同居している。
・仮設住宅への移行を予定している183世帯の内、77世帯(42.1%)が高齢者のみ。
・住居見通しが立っていない39の高齢者のみ世帯の内、23世帯(59.0%)は仮設住宅を希望。
・避難所を利用している915名の内、99名(10.8%)が要援護者(認定、手帳交付等)。
○分析結果
・益城町内の仮設住宅団地では、26.8%の住宅が高齢者のみ世帯と推定。
・益城町全体の高齢者のみ世帯割合9.9%(平成22年国勢調査結果*)を大きく上回る。
*「益城町の高齢者に関する現状」https://www.town.mashiki.lg.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=58&id=639&sub_id=2&flid=1881「5 高齢者がいる世帯の状況」より
避難所および在宅避難者の状況調査③
避難所アセスメント結果①入り口付近と居住スペースの様子
評価項目
エ
ミ
ナ
ー
ス
グ
ラ
ン
メ
ッ
セ
熊
本
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
広
安
小
広
安
西
小
中
央
小
総
合
体
育
館
(
1
F
)
1 入口付近 受付担当者が配備されている ○ × ○ ○ × ○ ○
2 入口付近 外部者に向けて情報開示ができている × × × - × ○ △
3 入口付近 入口から居住スペースまで充分な距離(5m)がある ○ ○ × ○ ○ ○ ○
4 居住スペース 世帯毎の間仕切りがある × - × ○ ○ × ×
5 居住スペース 間仕切りの高さは充分ある(座って見えない高さ) × - × × ○ × ×
6 居住スペース 一人あたりのスペースが畳2畳分以上ある ○ - × × × ○ ×
7 居住スペース 居住スペースは土足でない × - ○ ○ ○ ○ ○
8 居住スペース 通路の幅が80cm以上ある ○ - ○ ○ ○ × ○
9 居住スペース 居住スペースにゴミ箱がある ○ × ○ ○ ○ × ×
10 居住スペース 居住スペースと食事をする場所が区分けされている ○ - × × × × ×
○居住スペースが狭く、充分な間仕切りがない避難所が多くみられる2016.5.8現在
入り口付近と居住スペースの様子
避難所アセスメント結果②共用スペースの様子
評価項目エ
ミ
ナ
ー
ス
グ
ラ
ン
メ
ッ
セ
熊
本
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
広
安
小
広
安
西
小
中
央
小
総
合
体
育
館
(
1
F
)
11 共用スペース 清潔な水が使える調理スペースがある × × × × × ○ ×
12 共用スペース 余暇を過ごすための交流スペースがある ○ ○ ○ × △ × ○
13 共用スペース 医療スペースがある ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
14 共用スペース 母子スペースがある × ○ × ○ × × △
15 共用スペース 児童・子供用スペースがある × ○ × ○ ○ ○ △
16 共用スペース 男女別の更衣室がある × × ○ × ○ ○ ○
17 共用スペース 誰でも使える更衣室がある × × ○ × × × △
18 共用スペース 必要に応じて個室として使用できるスペースがある × × × × × × ×
19 共用スペース 女性用個室・男性用個室がある × × × × × × ×
20 共用スペース 喫煙スペースが設置されている ○ ○ ○ ○ ○ × ○
21 共用スペース ペットに配慮されたスペースがある × × ○ × ○ × ×
22 共用スペース 外部(支援)者との面談用スペースがある × - × × × ○ ×
○着替えや相談ができる個室、調理ができるスペースがない 2016.5.8現在
共用スペースの様子
共用スペース?
配慮スペース?
避難所アセスメント結果③トイレ・衛生環境、生活ルールの様子
評価項目エ
ミ
ナ
ー
ス
グ
ラ
ン
メ
ッ
セ
熊
本
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
広
安
小
広
安
西
小
中
央
小
総
合
体
育
館
(
1
F
)
23 トイレ・衛生環境 バリアフリートイレが必要数ある × × ○ × ○ ○ ×
24 トイレ・衛生環境 ポータブルトイレが必要数ある × × × × ○ × ×
25 トイレ・衛生環境 手洗場所がトイレ付近にある ○ ○ ○ × △ ○ ×
26 トイレ・衛生環境 石鹸または消毒液が設置されている ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
27 トイレ・衛生環境 うがい薬が設置されている × × × × × × ×
28 トイレ・衛生環境 風呂またはシャワーが使用可 ○ × ○ × × × ○
29 トイレ・衛生環境 洗濯場所が確保されている × × × × ○ × ×
30 トイレ・衛生環境 物干し場所が確保されている × × × × ○ × ×
31 生活ルール 清掃ルールが決まっている × × × × ○ ○ ×
32 生活ルール ゴミ分別ルールが決まっている ○ ○ ○ - ○ ○ ○
33 生活ルール 外部からのゴミ収集日が決まっている ○ ○ ○ - ○ ○ ○
34 生活ルール 要援護者への分配ルールがある × × ○ × △ × ○
○トイレの数、洗濯や風呂に改善の余地が見られる2016.5.8現在
トイレ・衛生環境、生活ルールの様子
避難所アセスメント結果④情報共有・告知等の様子
評価項目エ
ミ
ナ
ー
ス
グ
ラ
ン
メ
ッ
セ
熊
本
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
広
安
小
広
安
西
小
中
央
小
総
合
体
育
館
(
1
F
)
35 情報共有・告知等 分別・清掃ルールが分かりやすく掲示されている ○ △ △ × ○ ○ ×
36 情報共有・告知等 避難所内のルールが集約されて掲示されている × × × × × × ×
37 情報共有・告知等 情報の定期更新のルールがある × × × × ○ × ×
38 情報共有・告知等 トイレ等重要箇所にピクトグラム(絵記号)を用いた情報掲示がなされている ○ × × × × × ○
39 情報共有・告知等 必要に応じて多言語(または優しい日本語)の情報掲示がなされている × × × × × ○ ×
40 情報共有・告知等 各種相談窓口が配置されている ○ × ○ × × × △
41 情報・通信 共用テレビ(字幕対応)がある × × × × ○ - ○
42 情報・通信 共用の電話・FAXがある × ○ △ × ○ - ○
43 情報・通信 共用PC(送受信可)がある × × × × × - ×
○ルールや情報の掲示、PCの設置による情報収集や共有の工夫が必要2016.5.8現在
情報共有・告知等の様子
グループに分かれ、避難所でのトラブル防止の具体策を発表する参加者たち トラブルの事例についてグループごとに原因と対策を討議
新宿区では初めての「被災者支援拠点」の運営訓練 3グループに分かれて訓練について話し合う参加者
緊急対策支援(日本財団自主事業)
• 長期化する避難生活における災害関連死等の被害拡大防止を目的とした、避難所および在宅避難者
の状況調査、および被災者支援拠点としての避難所運営支援の実施。
避難所とは行政による「救助」である
災害救助法は、第3条において「都道府県知事は、救助の万全を期する」と定め、第4条で「救助の種類」として仮設応急住宅、
食品、飲料水、衣料、医療等が列挙され、その1番はじめに(第1項)に記されているのが「避難所」です。
「救助」の対象は全ての被災者である
「救助」の対象は、第2条で「災害の発生した市町村の区域内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者」と
されていますので、避難所に避難した被災者に限定されてはいません。
避難所の運営は地域住民で自主的に
一方で、避難所を誰がどのように運営するのかは定めがありません。 第3条には「救助」の為に「必要な計画の樹立、強力な救
助組織の確立、並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努め」るとしか定められていないので、行政は避難所を整備すれ
ば良いとも解釈ができます。
被災者支援拠点について①
つまり避難所とは…
(1)地域全体のニーズに対応できる設備や備品を備え
(2)災害で自宅を失う等した被災者を収容しつつ、多様なニーズをもつ地域の全ての被災者の被害拡大を防ぎ
(3)地域住民による自治によって運営され
(4)そして、外部からの支援との接点となる場所
災害の直接的な被害から生き延びた全ての被災者が、
長期化する避難生活の中で命を落とすことがないような対応と支援(受援)を実現するための施設
→ 『被災者支援拠点』
被災者支援拠点について②
緊急対策支援(日本財団自主事業)• 長期化する避難生活における災害関連死等の被害拡大防止を目的とした、避難所および在宅避難者
の状況調査、および被災者支援拠点としての避難所運営支援の実施。
グループに分かれ、避難所でのトラブル防止の具体策を発表する参加者たち トラブルの事例についてグループごとに原因と対策を討議
新宿区では初めての「被災者支援拠点」の運営訓練 3グループに分かれて訓練について話し合う参加者