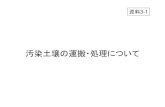汚染土壌の運搬・処理について - env4汚染土壌処理施設で処理した土壌の再処理について 汚染土壌処理施設 ※分別等処理施設から搬出される土壌につ
2016年3月1日平成 27年度東京都環境保全型農業フォーラム...
Transcript of 2016年3月1日平成 27年度東京都環境保全型農業フォーラム...

平成25年3月7日(木) 第二回クマムシの会 (於:南知多町総合体育館2階会議室) 話題提供2016年3月1日 平成27年度東京都環境保全型農業フォーラム
「有機物の連用と土壌機能」有機物 連用 壌機能」
豊田剛己(東京農工大学)1
発表内容発表内容
• 食糧生産をとりまく現状食
• 土壌管理の必要性
• 土壌肥沃度、地力、土壌の機能とは
• 有機物連用土壌vs土壌機能• 有機物連用土壌vs土壌機能
• 今後の環境保全型農業のあり方今後の環境保全型農業のあり方
2
巷は食料であふれている食
3
世界の穀物生産量・需要量の将来予測世界の穀物生産量 需要量の将来予測Tsujii(2000):穀物生産の上昇率=年0.5%、穀物消費の上昇率=年2.8%
人口増加食生活の向上
耕地面積・収量増加> 2050年までに現状の
90
)
食生活の向上 収量増加 2050年までに現状の穀物生産を2.5倍に
60
トン
/年
)物
量(億
ト穀物生産量
30
穀物 穀物需要量
0
1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 20601990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
4

食生活の変化:各国の肉類消費量食生活の変化:各国の肉類消費量
(kg/年/人) ミャンマー 中国 日本 米国
牛肉 2 4 10 44産 穀物牛肉 2 4 10 44
豚肉 2 20 18 32
1kg生産に穀物11kg
1kg生産に穀物7kg豚肉
鶏肉 4 10 15 48
g 産 穀物 g
1kg生産に穀物4kg
穀物換算量 52 224 296 900
生活向上と食生活の変化
より多くの穀物が必要
中国 日本 人 億人 億ト 世界の メ生産 億ト中国→日本 1人70kg→15億人=1億トン。世界のコメ生産4.8億トン
5
穀物生産量を増やすには穀物生産量を増やすには
• 農耕地面積を増やす
• 単位面積当たりの収量を増やす
• 単位面積当たりの栽培回数を増やす
6
1 農耕地面積は将来増やせるのか?1.農耕地面積は将来増やせるのか?
「増えてはいくが不十分」7
2 将来収量は増えるのか?
トウモロコシ
2.将来収量は増えるのか?
トウモロコシ
トウモロコシ
コメ
コムギ
:必要収量
:予測収量
コメ
ギ
ダイズ
:予測収量
コムギ
ダイズダイズ
“4作物とも、必要収量作物 も、必要収量を満たせない”
図.主要穀物の収量予測と需要を満たすための必要収量 Ray et al. (2013)
「増えてはいくが不十分」8

3 栽培回数を増やせるのか?3.栽培回数を増やせるのか?
年間平均収穫回数
「確かに増やせる余地はある」9
面積当たりの収量を高め 収穫回数を面積当たりの収量を高め、収穫回数を増やすとどうなるか?
表.四大文明の過去と現在エジプト文明
いずれも大河
の流域=沖積
エジプトはナイルの賜物
コムギ
砂漠化・塩類化のの流域 沖積
土地帯。大き
な川が上流か
砂漠化 塩類化のため不毛の地へ
メソポタミア文明
肥沃な三日月地帯
コムギ
な川が上流か
ら多量の土砂
を運搬して、肥
文明 月地帯
インダス文明
氾濫農耕 コムギを運搬して、肥
沃な土壌を形
成。
明
黄河・長江 稲作の発祥 水稲 今なお稲作を継続成。黄河・長江流域の文明
稲作の発祥地
水稲 今なお稲作を継続
「適切な土壌管理の必要性」「適切な土壌管理の必要性」
10
土壌管理の必要性作物の収穫= 耕地土壌からの養分の収奪
土壌管理の必要性
“作物:光合成により炭素(体の骨格)は作れるが、その他の養分は土壌から吸収”
10 当たり500k の玄米収量
イネの収穫を考
窒素 5.0kgリン 1.5kg
10a当たり500kgの玄米収量
考えてみるリン gカリウム 1.2kg
土壌1kg当たり窒素
10a当たりの土壌に含まれる養分量
窒素 500kg 土壌1kg当たり窒素2.5g、リン1.4g、カリウム8.9g 、深さ20cm、仮比重(土壌1cm3当
窒素 500kgリン 280kgカリウム 1780kg
新たな投入がないと窒素100年 リン200年で土壌養分が
たりの重さ=1g)として推定
新たな投入がないと窒素100年、リン200年で土壌養分がすべてなくなってしまう。→ 適切な土壌管理が必須 11
我が国における水稲単収の推移我が国における水稲単収の推移
数 持続 単数百年にわたり持続的な単収(100~150kg/10a)
西尾(2005)より12

玄米収量150kg/10aが数百年続いた意義玄米収量150kg/10aが数百年続いた意義西尾(2005)
玄米150kg/10aの収量を上げた時の水稲の部位別
作物残渣として土壌の還元される窒素量
長期連用水田における無機態窒素放出量
水稲の窒素供給量
の水稲の部位別窒素吸収量
玄米 1 49kg籾殻 0.16kgわら 1.02kg
籾殻 0.15kgわら 0.94kg
3.3kg玄米 1.49kg籾殻 0.16kgわら 1.02kg根 0 54k
わら 1.02kg根 0.54kg
水田で天然に
わら 0.94kg根 0.50kg雨・灌漑水3.0kg窒素固定 2 0kg
154kg/10aの玄米生産量
相当根 0.54kg
合計 3.21kg
水田で天然に供給される窒素量雨 灌漑水 k
窒素固定 2.0kg
合計 6.6kg
に相当
雨・灌漑水3kg窒素固定2kg
N N N水田では、150kg/10aの収量は
窒素栄養の面で持続的
NN
13N N
持続的な作物生産システム持続的な作物生産システム
○<>
収量150kg/10a ○
水田 150kg/10a ×(収奪的)> 150kg/10a ×(収奪的)
畑 収量に関わらず ×(収奪的)畑 収量に関わらず ×(収奪的)
何らかのインプット何らかのインプット
14
食品成分表を見てみよう食品成分表を見てみよう
100g当たりの含有量(mg) 10a当たりの収量と養分収奪量(kg)窒素 P K 鉄 亜鉛
コマツナ 240 45 500 2 8 0 2
100g当たりの含有量(mg) 10a当たりの収量と養分収奪量(kg)収量 窒素 P K 鉄 亜鉛
1600 3 9 0 7 8 1 0 046 0 003コマツナ 240 45 500 2.8 0.2
ダイコン皮付き
80 18 230 0.2 0.2
1600 3.9 0.7 8.1 0.046 0.0034400 3.5 0.8 10.1 0.009 0.009
ニンジン皮付き
96 25 280 0.2 0.2 3400 3.3 0.9 9.5 0.007 0.007
トマト 112 26 210 0.2 0.1
梨 48 11 140 0 0.1
玄米
5900 6.6 1.5 12.3 0.012 0.0062200 1.1 0.2 3.1 0.000 0.002
玄米 1088 290 230 2.1 1.8 522 5.7 1.5 1.2 0.011 0.009H20全国平均
“野菜もコメと同様、各種養分を土壌から収奪する”
15
耕作に伴う土壌有機物含量(肥沃度の指標)の変化耕作に伴う土壌有機物含量(肥沃度の指標)の変化(Brady and Weil, 1996)
a)含
量(t/ha 耕作開始
作物残渣
耕作により土壌
有機
物含
易分解性有機物耕作により土壌有機物含量が減少
土壌
有
全有機物含量
難分解性有機物
耕作開始後の年数16

持続的な土壌利用で特に重要なこと
養分バラ養分バランス多量要素:N,P,K,Ca,Mg,S,Fe微量要素:Zn,Cu,Mn,B,Co,Mo・・・
土壌有機物レベル(炭素含量)
17
土壌肥沃度(=地力)の定義・
土壌肥沃度(=地力)の定義
土壌肥沃度
・
土壌肥沃度とは土壌の化学性のうち植物生育に強くかかわる
性質、すなわち植物の生育に必要な土壌養分の供給力(=土壌有機物・性質、すなわち植物の生育に必要な土壌養分の供給力( 土壌有機物
含量)を土壌の自然肥沃度と養分の豊否から総合的に判断したもの(最
・
新土壌学:久馬、1997) 。
地力は作物を生産しうる土壌の能力すなわち土壌の化学的・
物理的・生物的諸性質の総合 (最新土壌学 久馬 1997)物理的・生物的諸性質の総合 (最新土壌学:久馬、1997) 。
地力窒素地力窒素は作物が土壌から吸収する肥料以外の窒素。
土壌有機物が微生物により分解され生成する無機態窒素のこと。土壌有機物が微生物により分解され生成する無機態窒素の と。
18
トマトの養液土耕栽培に伴う地力窒素の変化トマトの養液土耕栽培に伴う地力窒素の変化(愛知農総試、加藤)より
窒素
好適窒素肥料施用量
吸収量量
地力窒素
19
1作 2作 3作 4作 5作 6作
土壌肥沃度(養分供給能・地力窒素)の由来土壌肥沃度(養分供給能・地力窒素)の由来
作物
土壌残渣
土壌動物
無機N・堆
肥
根から吸収肥
・土壌壌有機 “土壌微生物・動物が多い
土壌微生物菌体
機物
土壌微生物 動物が多いほど地力窒素は高くなる”物菌体
20

土壌機能のすごさ:養分供給能土壌機能のすごさ:養分供給能
“肥料由来の養分 → 実は半分以下”肥料由来の養分 → 実は半分以下
水稲(緩効性肥料)
肥料由来 土壌窒素由来地力窒素由来
水稲(速効性肥料)
肥料由来 土壌窒素由来地力窒素由来
トウモロコシ
0% 20% 40% 60% 80% 100%
トウモロコシ
0% 20% 40% 60% 80% 100%
図.作物体が吸収した窒素の由来
水稲は藤原(1996)、トウモロコシはBrady & Weil (2008)を元に作図21
トマトの累積養分吸収量と窒素施肥トマトの累積養分吸収量と窒素施肥(愛知農総試、加藤)より
養液土耕の例
地力窒素の大きい圃場 地力窒素の小さい圃場
“地力の高い土壌では施肥Nを10kg減らせる”
22
耕地の生産力と土壌との関係耕地の生産力と土壌との関係松中(2003)松中(2003)
養分供給 気象条件地形水分の
保持・供給根の
生育環境
地形施肥管理栽培技術
土壌の機能栽培技術作物種類や品種
などの要因などの要因
耕地の生産力
23
養分供給能(地力)を高めるには?養分供給能(地力)を高めるには?
→微生物・動物量を増やす →堆肥(有機物)or緑肥→微生物・動物量を増やす
1986年開始 沖縄県農業研究センター:
→堆肥(有機物)or緑肥
1986年開始 沖縄県農業研究センタ :
化学肥料区、 緑肥区(セスバニア2.5 t/10a)、 堆肥区(牛ふん堆肥2. 5t/10a)
250
300
350CFGMCC
b bb b
化肥区
緑肥区
堆肥区/kg
土壌
)
150
200
250b
b
a aa
a
b b bb b
b堆肥区
オマ
ス(m
g/
50
100
150 a a a a
物バ
イオ
化肥
区
緑肥
区
堆肥
肥区
宮丸(2012) 0
50
2006 2007 2008 2009 2010
微生 化 緑 堆 区
図.緑肥や堆肥の施用が土壌微生物バイオマスに及ぼす影響24

堆肥の施用効果(山根 1981)堆肥の施用効果(山根、1981)
堆肥の働き 働きの詳細畑 水田
堆肥の働き 働きの詳細腐植少 腐植多 腐植少 腐植多
三要素肥料として ○ ○ ○ ○
養分として 微量要素肥料として ○ ○ × ×
緩効性肥料として ○ ○ ○ ○緩効性肥料として ○ ○ ○ ○
物理性の改造者として ○ × ○ ×
陽イオンの保持者として ○ × ○ ×安定腐植として
陽イオンの保持者として ○ × ○ ×
有害物の阻止者として ○ × ○ ×
微量 素 溶解者微量要素の溶解者として ○ × ○ ×
緩衝物質として ○ × ○ ×
生物の給源として
微生物、地中動物の給源として
○ × × ×
○:効果有り、×:効果なし、腐植の多少の判定基準:2~5%程度25
堆肥による土壌物理性改善:団粒構造堆肥による土壌物理性改善:団粒構造
粒子と粒子がバラバラ=さらさら
団粒構造発達孔隙率
粒子同士が
→孔隙率
図.単粒構造と団粒構造
孔隙率 26% 45% 73%
(川口、1974)
粒子同士がくっつく
団粒を発達させる因子は?
図.単粒構造と団粒構造
・糸状菌菌糸が無機粒子をつなぐ
・微生物の生産する高分子粘着物が土壌粒子を接着する
“微生物バイオマスが高いと団粒が発達する”
団粒の役割は?
・良好な透水性 通気性 保水性・良好な透水性、通気性、保水性
・土壌侵食防止 26
堆肥連用土壌では団粒化が促進堆肥連用土壌では団粒化が促進
化学肥料連用土壌化学肥料連用土壌
堆肥連用土壌 27
微生物ではどうにもならない=土壌硬度3000
度
微生物ではどうにもならない=土壌硬度
2500 生育不良のサ灰色低地土
壌硬
度
2000
生育不良のサトウキビ圃場
灰色低地土
土
1500
1000 都農試:下層まで柔らか
い黒ボク土500
い黒ボク土
0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
土壌深度(cm)
28