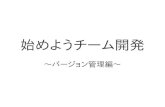2015年度ソフトウェア工学分野の先導的研究支援事業に 関する ... ·...
Transcript of 2015年度ソフトウェア工学分野の先導的研究支援事業に 関する ... ·...
「2015年度ソフトウェア工学分野の先導的研究支援事業に
関する委託契約」に係る企画競争 公募要領
別冊資料
「2011年~2014年SPES事例研究(経験報告)の一覧および概要」
2014年12月1日
独立行政法人情報処理推進機構
目 次
1. SPES事例研究(経験報告)一覧
2014年 (12件 ) ··························································· 1
2013年 (14件 ) ··························································· 1
2012年 (15件 ) ··························································· 2
2011年 (13件 ) ··························································· 3
2. SPES事例研究(経験報告)概要
2014年 ··································································· 4
2013年 ··································································· 6
2012年 ··································································· 10
2011年 ··································································· 17
当資料は、一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)が毎年開催している技術シンポ
ジウムSPESについて、JISAのWebページで公開している内容をもとに取りまとめたもの
です。なお、一覧の「分類」は各事例研究(経験報告)の概要をもとに独立行政法人情報
処理推進機構が付与したものです。
1
1. SPES事 例 研 究 (経 験 報 告 )一 覧
2014年
№ 分類 コード タイトル 企業名
1 要求工学 S1a ドメイン特化型要求抽出の取り組み~交差点における運転行動による環境変化を考慮した要求抽出~
㈱ デ ン ソ ー ア イ テ ィ ー ラボラトリ
2 テ ス ト 駆 動 開発
S1b 受け入れテスト駆動開発によるウェブサービス構築の実践事例( theta360を支える技術と開発手法)
リ コ ー ITソ リ ュ ー シ ョ ンズ㈱
3 プ ロ ジ ェ ク ト管理
S1c 実践知識の発掘と共有 ~現場技術者がソフトウェア開発で実践している工夫点~
NECソ リ ュ ー シ ョ ン イ ノベータ㈱
4 テ ス ト 駆 動 開発
S2a ユーザーエクスペリエンス品質設計プロセス導入による大規模システム開発プロジェクトにおける失敗の削減
NECソ リ ュ ー シ ョ ン イ ノベータ㈱
5 テ ス ト 駆 動 開発
S2b 受け入れテスト駆動開発のベスト・プラクティスに関する考察
㈱オージス総研
6 プ ロ ジ ェ ク ト管理
S2c 多様なプロジェクト管理の課題に対するツールの適用~Redmineの活用事例~
AVCテクノロジー㈱
7 要求工学 S3a REBOK(要求工学知識体系)に基づくトレーニングの実施~見えてきた課題~
パナソニック㈱
8 テスト S3b 「再利用」「自動化」によるテスト工程生産性向上の取組み
TIS㈱
9 標準化 S3c 適用率 100%達成の標準適用プロセス事例報告
NECネ ク サ ソ リ ュ ー シ ョンズ㈱
10 要求工学 S4a 要求仕様書の品質向上に向けた活動報告~一貫性検証の形式知化および自動化~
東芝ソリューション㈱
11 アジャイル S4b スクラムマスター奮闘記 waterfallな若手SEのアジャイルチームビルディング
富士通エフ・アイ・ピー㈱
12 人材育成 S4c 目的思考に導く「成長モデル」を基盤とした仕組み~手段思考からの脱却を目指して~
㈱デンソークリエイト
2013年
№ 分類 コード タイトル 企業名
1 その他 S1a ソフトウェア開発における電子掲示板を用いた非同期コミュニケーション改善の試み
㈱東芝
2 その他 S1b 開発文書の品質向上への取り組み~開発文書品質とプロジェクト実績との相関~
アヴァシス㈱
3 要求工学 S1c NDS要求開発活動のご紹介 ㈱ ニ ッ ポ ン ダ イ ナ ミ ッ クシステムズ
4 プロセス改善 S1d 自律改善継続実現要因の考察-現場自らが「次も改善を回そう!」と行動するために必要な要因は何か?~ SPINA3CH自律改善メソッド実証実験から得られた知見
㈱HBA
5 人材育成 S2a トップガン研修構築の考え方と実践-課題解決力、リーダーシップ力の向上を目指して-
㈱デンソー技研センター
6 アジャイル S2b 高品質を重視した NECアジャイル~ソフトウェア品質会計のエッセンスをアジャイル開発に適用~
日本電気㈱
7 開発手法 S2c デジタル複写機のネットワーク開発へのXDDP適用事例
リ コ ー I T ソ リ ュ ー シ ョンズ㈱
8 プロセス改善 S2d 「改善をやめた」組織でのプロセス改善~プロセス改善はやり直せるのか~
ヤマハ㈱
2
9 その他 S2f 高品質なコア資産開発のためのレガシー資産活用の取組み-コードクローン検出ツール CCFinderXを用いたレガシーソースコードの分析事例-
東芝ソリューション㈱
10 人材育成 S3a ピア・レビューと履行検証に着目した若手技術者の育成~業務の中で自然に学ぶ方式~
㈱デンソークリエイト
11 ソ フ ト ウ ェ ア品質管理
S3b ソフトウエア開発における QCD指標を活用した品質向上への取組み~ユーザ部門における品質管理の実践的手法の確立~
KDDI㈱
12 形式手法 S3c 情報システムにおける形式手法活用への取り組み
㈱日立製作所
13 ソ フ ト ウ ェ ア開発手法
S3d リコーにおけるソフトウェアプロダクトライン導入に向けた課題特定の取り組み事例
㈱リコー
14 テ ス ト 駆 動 開発
S3f 受け入れテスト駆動開発による実行可能な仕様に関する検証結果
㈱オージス総研
2012年
№ 分類 コード タイトル 企業名
1 要求工学 F3a 早期の要求獲得・問題解決を実現する仕組みづくり
㈱デンソークリエイト
2 オフショア F3b オフショア開発における単体テストの生産性向上策~入力支援ツールによる言語の壁の克服~
富士通エフ・アイ・ピー㈱
3 プロセス改善 F3c 継続的な価値提供のための改善プロセス リ コ ー ITソ リ ュ ー シ ョ ンズ㈱
4 要求工学 F4a 要求仕様から利用品質~ソフトウェア品質特性へのリバース結果に基づく要求仕様レビュー~利用者に喜ばれる・役立つシステムの構築に向けて
㈱HBA
5 アジャイル F4b オフショア開発におけるアジャイル開発の取り組みと評価
㈱オージス総研
6 アジャイル F4c “チーム力”で派生開発を成功させる為の“仕掛け作り”- XDDPとSCRUMの併用で派生開発を極める-
ソ ニ ー イ ー エ ム シ ー エ ス㈱
7 要求工学 S1a 要求獲得プロセスの可視化と検証の自動化
東芝ソリューション㈱
8 運用 S1b 業務運用の品質向上に向けた取り組み~メンバ全員(17名)参加による継続的な改善活動への挑戦 ~
富士通エフ・アイ・ピー㈱
9 プロセス改善 S1c TOC思考プロセスによる改善施策の合意形成-テストプロセス改善における事例-
㈱日立製作所
10 要求工学 S2a 要求開発手法「 HyThology○R 」~ REBOK実践の取り組み
㈱日立ソリューションズ
11 標準化 S2b 社内システム開発標準の開発におけるテンプレート開発作業の効率化と高品質化
東芝ソリューション㈱
12 プロセス改善 S2c 画面設計の開発プロセスの改善への取り組み-プロトタイプを用いた画面イメージの認識統一の事例-
㈱日立製作所
13 要求工学 S3a 第 3者レビューによる要件定義書の品質向上の取り組み
㈱NTTデータ
14 ソ フ ト ウ ェ アメトリクス
S3b COSMIC概算法による概算規模測定の測定コスト削減の検討結果
㈱オージス総研
3
15 ユ ー ザ ビ リ ティ
S3c NRIの社内業務システムにおける RIA化の取り組み~RIA化におけるポイント・課題に関する考察~
㈱野村総合研究所
2011年
№ 分類 コード タイトル 企業名
1 ユ ー ザ ビ リ ティ
F3a 業務システムのユーザビリティ評価と品質向上に関する取り組み
㈱三菱総合研究所
2 保守 F3b チームによる保守業務改善の取組み~保守業務の『見える化』~
富士通エフ・アイ・ピー㈱
3 保守 F4b 仮想化技術を活用したシステム保守効率化施策の検討
㈱日立製作所
4 その他 S1a 簡易な調達先アセスメント方法の提案-共に成長する改善を目指して
ヤマハ㈱
5 要求工学 S1b 人間科学と工学のアプローチによる要求獲得の質を上げるためのインタビュー手法の開発
富士通㈱
6 開発手法 S1c 人が作るソフト~経験的な開発手法の実践事例~
リ コ ー ITソ リ ュ ー シ ョ ンズ㈱
7 ソ フ ト ウ ェ ア品質
S1d プロジェクト環境を考慮した設計品質評価手法についての考察
三 菱 電 機 イ ン フ ォ メ ー ションシステムズ㈱
8 ソ フ ト ウ ェ ア品質
S1f 知的技術の形式化による、SI開発業務の品質改善について
NECシ ス テ ム テ ク ノ ロ ジー㈱
9 ソ フ ト ウ ェ ア品質
S2b 派生開発における要求仕様書の品質向上活動
アヴァシス㈱
10 ソ フ ト ウ ェ アメトリクス
S2c COSMIC 法 に 基 づ く Force.com 開 発 プ ロジェクトの生産性分析結果
㈱オージス総研
11 プロセス改善 S3a トレーニング指向アプローチによるプロセス改善-現場のキーパーソンを育てる「現場SQA」方式-
㈱デンソークリエイト
12 要求工学 S3b 要件定義の生産性を向上させるための最適化への取り組み
東芝ソリューション㈱
13 アジャイル S3c オフショア開発におけるアジャイル開発のプラクティス
㈱オージス総研
4
2. SPES事 例 研 究 (経 験 報 告 )概 要
2014年
№ 分類 コード タイトル 概要 1 要 求 工
学 S1a ド メ イ ン 特
化 型 要 求 抽出 の 取 り 組み ~ 交 差 点 にお け る 運 転行 動 に よ る環 境 変 化 を考 慮 し た 要求抽出~
交 差 点 では、運 転 に影 響 を与 える外 的 要 因 やドライバの内 的 要 因 が非 常に多 く、運 転 における認 知 ・判 断 ・操 作 の各 段 階 において満 たすべき状 態 が変 化 するため、事 故 防 止 のための要 求 をすべて抽 出 することが困 難 である。そのため、要 求 抽 出 には深 いドメイン知 識 が必 要 であり、開 発 者 同 士 が共通 理 解 を得 るのが困 難 であった。本 案 では、このような交 差 点 における安 全のための要 求 抽 出 に特 化 した手 法 を提 案 する。 ま ず 、 従 来 手 法 と し て 、 ゴ ー ル 指 向 要 求 分 析 の 一 手 法 で あ るKAOS(Knowledge Acquisit ion in autOmated Speci f icat ion)について触 れ、その問 題 点 を指 摘 する。次 に、ゴールモデルをベースに、場 の概 念 モデルとシナリオ分 析 を組 み合 わせることで要 求 を可 視 化 する手 法 を提 案 する。そして提 案 手 法 の評 価 のために、実 データ用 いて要 求 抽 出 する。さらに、提 案手 法 の有 効 性 評 価 のために、現 行 システムの対 応 範 囲 を可 視 化 する。最 後に、それら適 用 結 果 について考 察 する。
2 テ ス ト駆 動 開発
S1b 受 け 入 れ テス ト 駆 動 開発 に よ る ウェ ブ サ ー ビス 構 築 の 実践 事 例( theta360を 支 え る 技術 と 開 発 手法)
THETA360で高 品 質 かつ洗 練 されたユーザー体 験 を提 供 するべく、Webシステム構 築 への取 組 みを実 施 した。 ・リーンスタートアップ、アジャイル開 発 をベースとした開 発 手 法 で、MVPを早期 に完 成 させ、本 質 的 な価 値 の徹 底 的 検 証 を実 施 ・開 発 サイクルに受 け入 れテスト駆 動 開 発 によるアプローチを採 用 し、実 際 のものづくりから品 質 保 証 に至 るまで一 貫 した対 応 を実 施 ・テスティングフレームワークを用 い、受 け入 れテストの自 動 化 への試 み これらの取 組 み及 びその結 果 を示 し、いかに短 納 期 かつ高 品 質 なアウトプットに繋 げられたのかを述 べる。
3 プ ロ ジェ ク ト管理
S1c 実 践 知 識 の発掘と共有 ~ 現 場 技 術者 が ソ フ トウ ェ ア 開 発で 実 践 し てい る 工 夫 点~
ソフトウェア製 品 開 発 において成 功 したプロジェクトを分 析 すると,ベテラン技術 者 が過 去 の経 験 から得 た知 識 を活 用 して成 功 に導 いていることがわかった.そのため,ベテラン技 術 者 の持 つ知 識 を企 業 資 産 としてプロジェクトに活用 することは,事 業 を発 展 させるために非 常 に重 要 である. しかし,ベテラン技 術 者 の知 識 は暗 黙 知 となっていることが多 く,企 業 資産 として共 有 し有 効 活 用 することは簡 単 ではない.本 活 動 では,ベテラン技術 者 の暗 黙 知 を形 式 知 として獲 得 する手 法 を提 案 し,手 法 を実 プロジェクトに適 用 した結 果 を発 表 する.
4 テ ス ト駆 動 開発
S2a ユ ー ザ ー エク ス ペ リ エン ス 品 質 設計 プ ロ セ ス導 入 に よ る大 規 模 シ ステ ム 開 発 プロ ジ ェ ク トに お け る 失敗の削減
顧 客 要 求 の高 度 化 に伴 い、システムは複 雑 になり、使 いやすくわかりやすい操 作 が求 められています。具 体 的 には、SaaSなどのクラウド利 用 に伴 う業 務システムのサービス化 や、スマートデバイスなどのコンシューマ製 品 ・サービスの業 務 への浸 透 がそれに当 たります。 このようなニーズに対 応 するためには、システムやサービスを人 の視 点 にたっ て ユ ー ザ ー の 体 験 価 値 を 高 め る 「 ユ ー ザ ー エ ク ス ペ リ エ ン ス ( User eXperience: UX)」の考 え方 と、われわれのようなSI/ソフトウェア開 発 を遂 行する企 業 における大 規 模 なプロジェクトへ適 用 させるための新 しい手 法 が必要 となります。 なお、ここで定 義 している「大 規 模 」プロジェクトとは、2年 以 上 継 続 して実施 され、開 発 者 数 が述 べ100人 を超 えたプロジェクトを示 します。開 発 には、NECグループだけでなく、様 々な関 係 会 社 も関 わっており、オフショアとして中 国 企 業 も利 用 しています。 今 回 は、製 造 業 務 系 の生 産 管 理 システムと、基 幹 業 務 系 の営 業 管 理 システムの、2つの大 規 模 プロジェクトに対 し、UX設 計 プロセスを適 用 したので、その結 果 を報 告 します。
5 テ ス ト駆 動 開発
S2b 受 け 入 れ テス ト 駆 動 開発 の ベ スト ・ プ ラ クテ ィ ス に 関する考察
アジャイル開 発 の普 及 に伴 い、受 け入 れテスト駆 動 開 発 (A-TDD)はテスト駆 動 開 発 や継 続 的 インテグレーションなどと同 様 に、品 質 保 証 するための重要 な技 術 プラクティスのひとつとして注 目 されている。しかし、A-TDDの適 用の難 しさ、及 び導 入 、開 発 、メインテナンスのための高 いコストはA-TDD普 及の障 害 となっている。 本 研 究 では2件 の実 プロジェクトにおいてA-TDDを適 用 し、その結 果 の測定 と考 察 を行 った。本 論 では、この概 要 を述 べると共 に、A-TDDの難 しさやコストの低 減 に貢 献 するプラクティスをまとめる。
5
6 プ ロ ジェ ク ト管理
S2c 多 様 な プ ロジ ェ ク ト 管理 の 課 題 に対 す る ツ ールの適用 ~ Redmineの 活 用 事 例~
ソフトウェア開 発 管 理 は、プロジェクトの目 的 や成 果 物 によってプロセスや管 理 手 法 が変 化 します。 プロジェクト管 理 のツールは数 多 く存 在 しますが、それぞれのツール独 自 のプロセスが定 義 されていることが多 く、違 う環 境 や違う目 的 のプロジェクトに適 用 する場 合 、結 果 的 に開 発 メンバーにとって使 いにくいツールになってしまい、十 分 に活 用 されないことも少 なくありません。 Redmineは、BTS(Bug Tracking System)として開 発 されたオープンソフトのアプリケーションですが、障 害 管 理 だけでなく、タスク(作 業 )管 理 、情 報共 有 も行 える汎 用 性 の高 いツールです。弊 社 においては、その柔 軟 性 を活用 し、不 具 合 管 理 やプロジェクトの進 捗 管 理 など様 々なプロジェクトに対 応 してまいりました。それらの事 例 を紹 介 いたします。
7 要 求 工学
S3a REBOK( 要求 工 学 知 識体 系 ) に 基づ く ト レ ーニ ン グ の 実施 ~ 見 え て きた課題~
2011年 に発 行 されたREBOK®(要 求 工 学 知 識 体 系 )に基 づき研 修 教 材 を開 発 し、自 社 内 と社 外 (JISA様 主 催 )の2回 、研 修 を開 催 した。 教 材 は、もともと新 入 社 員 向 けに実 践 で使 用 できることを前 提 にケーススタディに基 づき、ロールプレイング形 式 で実 施 されていたものを改 訂 して開 発した。 実 際 に、研 修 を実 施 した結 果 とアンケート結 果 を分 析 した結 果 、下 記 の2つの課 題 が明 らかになった。(1)受 講 生 は顧 客 のRFP(提 案 依 頼 書 )を追 認する傾 向 が強 く、演 習 途 中 で出 現 する矛 盾 に手 詰 まり感 を感 じていた、(2)REBOK®のプラクティス(28個 )と、演 習 との対 応 が理 解 しづらい。 今 後 の課 題 として、(1)受 講 者 が研 修 の早 い段 階 で顧 客 の真 の要 求 に気付 きかせる。(2)演 習 を進 める中 でREBOK®の枠 組 み・構 成 を学 ぶ。(3)1日研 修 の開 発 。の3項 目 の解 決 を目 指 す。
8 テスト S3b 「 再 利 用 」「 自 動 化 」に よ る テ スト 工 程 生 産性 向 上 の 取組み
システム開 発 期 間 の短 期 化 、システム投 資 の削 減 といった顧 客 ニーズに応えるため、当 社 では「再 利 用 」「自 動 化 」に着 目 した、テスト工 程 の生 産 性 向上 に取 り組 んだ。 テストにおける「再 利 用 」「自 動 化 」というと、テスト実 行 /検 証 自 動 化 の知 名 度 が高 い。しかし、開 発 者 によるテストコード実 装 等 の準備 コストが問 題 となり、受 託 開 発 では適 用 が難 しい場 合 が多 い。また保 守 フェーズに渡 って、持 続 的 に生 産 性 向 上 効 果 を享 受 するためには、テスト自動 化 対 象 の選 別 や、効 率 的 な自 動 化 方 式 の設 計 など、高 度 なノウハウとテスト戦 略 が必 要 となる点 も適 用 を難 しくさせている。 弊 社 では、受 託 開 発プロジェクトにおける導 入 ・活 用 の容 易 性 と即 効 性 を重 視 し、テスト仕 様 書 と打 鍵 ・ 目 視 確 認 で 行 う テ ス トにお け る 生 産 性 を 高 め る テス ト 管 理 ツー ル をOSSをベースに開 発 し、社 内 展 開 を進 めた。 本 稿 では、受 託 開 発 プロジェクトにおけるテスト管 理 ツールの活 用 実 態 および、テスト設 計 および実 行 、テスト工 程 管 理 における生 産 性 向 上 効 果 について紹 介 する。
9 標準化 S3c 適 用 率100 % 達 成の 標 準 適 用プ ロ セ ス 事例報告
ソフトウェア開 発 において、生 産 性 や品 質 向 上 のための標 準 化 の取 り組 みは、各 方 面 で様 々な取 り組 みが行 われている。その一 方 で、標 準 の策 定 /適用 /定 着 の作 業 に膨 大 な工 数 が割 かれているにも関 わらず、納 得 できる効果 が少 ないのが現 状 ではないかと思 われる。弊 社 では、標 準 の策 定 と適 用の統 制 とともに広 く標 準 を周 知 させる仕 組 みを構 築 することで、適 用 率 100%を達 成 している。 適 用 率 の高 い標 準 の策 定 にあたって弊 社 では大 きく3つの視 点 で取 り組んでいる。第 一 にトラブルの未 然 防 止 の視 点 を標 準 策 定 に取 り組 み、標 準を適 用 する側 に能 動 的 な姿 勢 を促 すこと。次 に標 準 の陳 腐 化 を回 避 するために技 術 動 向 を標 準 に取 り込 んでいること。三 つ目 として標 準 の展 開 にあたり、組 織 のトップとの間 で、適 用 状 況 のフィードバックと標 準 適 用 の課 題 共 有の仕 組 みを構 築 し、組 織 内 での適 用 を促 していることである。 こうした3つの視 点 での取 り組 みにより高 い標 準 適 用 率 を維 持 している事例 について紹 介 する。
10 要 求 工学
S4a 要 求 仕 様 書の 品 質 向 上に 向 け た 活動報告 ~ 一 貫 性 検証 の 形 式 知化 お よ び 自動化~
高 品 質 な要 求 仕 様 書 の作 成 にはステークホルダ間 での要 求 の検 証 が重要 である。要 求 工 学 知 識 体 系 REBOKでは、要 求 の検 証 の観 点 として、完 全性 、トレーサビリティ、一 貫 性 などの品 質 特 性 が定 義 されている。これらの特性 のうち、要 求 間 に矛 盾 がないことを示 す一 貫 性 の検 証 は、弊 社 では技 術者 や分 析 者 に依 存 した属 人 的 な方 法 で実 施 されており、その結 果 、検 証 の品 質 にバラつき発 生 するという問 題 が発 生 している。 そこで、要 求 の一 貫 性 検 証 を均 質 に実 施 するために、我 々は、ベテラン技 術 者 の検 証 ノウハウを形 式 知 化 し、要 求 仕 様 書 の品 質 を検 証 する手 法 を提 案 する。また、一 貫 性 の検 証 は、膨 大 な量 の仕 様 書 を人 手 で行 うにはコストを要 するため、自 動 化 した。今 回 、検 証 する対 象 として、要 求 の種 類 のうちアクターに着 目 した。アクター間 の矛 盾 は仕 様 書 全 体 の品 質 に影 響 するため、優 先 して評 価 実 験 を行 った。実 際 の要 求 仕 様 書 を対 象 に本 提 案 手 法を適 用 した結 果 、アクター間 の一 貫 性 に不 整 合 がある箇 所 を特 定 できた。さらに検 証 を自 動 化 したことにより、効 率 良 く不 整 合 を発 見 することができ、仕様 書 の品 質 検 証 に有 効 な手 法 であることを確 認 した。
6
11 ア ジ ャイル
S4b ス ク ラ ム マス タ ー 奮 闘記 waterfall な若手SEのアジ ャ イ ル チー ム ビ ル ディング
ソフトウェア開 発 において今 や主 流 の1つであるスクラムによるアジャイル開発 。エンタープライズの世 界 にもその流 れは押 し寄 せつつある。Waterfal lを法 律 のように絶 対 的 手 法 として開 発 を行 ってきた弊 社 が初 めてスクラムによるシステム開 発 を行 った。さらに開 発 チームのほとんどが若 手 SEという状 況で、開 発 チームに起 こった多 くの失 敗 スクラムを紹 介 、分 析 する。 そんな中 、スクラムマスターとしてチームに参 画 していた著 者 がこのチームに対 して3つの改 善 策 を実 施 した。 コマンド&コントロールな雰 囲 気 の打 破 、教 育 的 リーダーシップの発 揮 、小 さな成 功 の提 供 である。 本 論 では、発 表 形 式 という事 を利 用 して数 値 には表 れてこない「うまくいっていないスクラムの状 態 」を共 有 し、さらにスクラムチームのチームビルディングのコツを成 功 事 例 として紹 介 する。
12 人 材 育成
S4c 目 的 思 考 に導 く 「 成 長モ デ ル 」 を基 盤 と し た仕組み ~ 手 段 思 考か ら の 脱 却を 目 指 し て~
品 質 問 題 や絶 え間 なく続 く高 負 荷 な状 況 から脱 するため、プロセス改 善 を始 めとしたレビューの強 化 等 の様 々な取 り組 みをしてきた。それらを定 着 させると共 に、有 効 に実 践 できる人 材 を育 成 するために、プロセス遵 守 の監 査 や定 量 的 な目 標 管 理 、教 育 を行 ってきた。その中 で、現 場 ではプロセス定 義に書 かれていることや教 育 で知 ったやり方 をこなすことや、目 標 値 をクリアするためにデータを作 ることに囚 われ、本 来 の目 的 を見 失 ってしまうことが多 々あった。それは、”何 を実 施 する”のかが基 盤 の「手 段 思 考 」になっており、本来 あるべき姿 である”何 を達 成 する”のかが基 盤 の「目 的 思 考 」になっていないのではないかと気 付 き、「目 的 思 考 」に導 く仕 組 みが必 要 と考 えた。 そこで、定 着 させたい大 切 な活 動 について、その活 動 の目 的 を明 らかにし、手 段 を与 えるのではなく、目 的 を見 据 えて”考 える”ことを表 現 する「成 長モデル」を考 案 した。そして、活 動 を定 着 させるための「トレーニング」と「診断 」の仕 組 みを「成 長 モデル」を基 盤 として構 築 、実 施 することで、「目 的 思考 」に導 くことに取 り組 んだ。
2013年
№ 分類 コード タイトル 概要 1 その他 S1a ソフトウェ
ア開発における電子掲示板を用いた非同期コミュニケーション改善の試み
ソフトウェアの開発では、システムイメージの共通理解の確立や、仕様などの意思決定のために、多くの質問や議論を必要とすることが多い。それぞれの話題は、並列的に進められ、1つの話題が終結するまで数日から数週間以上かかるようなケースは少なくない。
一方で、弊社では分散した部門や拠点の開発者が協調的に開発を進めることが多いことから、電子ネットワークを利用した非同期コミュニケーションが積極的に活用されることが多く、そのツールとしては、一般的な電子メールシステムが利用されることが多い。
上記のようなソフトウェア開発特有の状況の中で、一般的な電子メールシステムを利用する場合、どの話題が終結していてどの話題が終結していないかの見分けや、どのメッセージが直近のメッセージかの見分けが難しいなど、利用効率面での課題があった。弊社では、これらのような一般的な電子メールでの課題を改善するため、開発プロジェクトでの利用を主目的とした電子掲示板を開発し、ソフトウェア開発へ展開する活動を行っている。
本発表では、弊社の非同期コミュニケーションの課題を紹介し、弊社で独自に開発した電子掲示板による改善の工夫点と改善した点と判明した問題点について紹介する。
2 その他 S1b 開発文書の品質向上への取り組み ~開発文書品質とプロジェクト実績との相関~
当社での要求仕様書レビューにおける指摘事項を分類してみると、「書いている意味がわからない」といった「あいまい表現」に対する指摘が多いことが分かった。そのため、SPES2011事例研究 「派生開発における要求仕様書の品質向上活動」では、要求仕様書のレビュー前にあいまい表現を指摘するツールを使って文書品質を向上する方法を提案した。しかしその後に調査した結果、この方法だけでは十分な効果は得られなかった。
そこで、要求仕様書を始めとする日本語で書かれた、開発文書に対する記述方法を教育する必要が生じたが、日本語の開発文書に特化した文書の記述方法を教育するセミナーは存在しないため、自社で教育を行うこととなった。 教育では、自社のプロジェクトから例文を抽出して、教育コンテンツとし、受講者に課題を書いてもらう実習を取り入れた。
その後、教育の受講者が携わった開発プロジェクトを調査した結果、要求仕様書や設計書の「あいまい比率」がプロジェクトの生産性や不具合率に影響を与えていることが判明した。このことから、開発文書に対する記述方法の教育は効果があり、開発文書における「あいまい表現」の比率は、プロジェクト品質の1つの指標となり得
7
ることが分かった。
3 要 求 工学
S1c NDS 要 求 開発活動のご紹介
弊社では、主にソフトウェアの受託開発を行っている。大手メーカーやSIerより開発業務を受託することが多いのだが、長引く不況や海外企業(特にアジア圏)の台頭により、業績は悪化する。
そこで、社会情勢や委託元企業の状況に左右されないような、強い事業基盤を持つ為の施策が必要となった。 そのような時、要求開発と出会う。ただ言われるままに、言われた仕様を実現するだけのシステム開発ではなく、ユーザの想いや戦略の部分に踏み込んで、真にビジネス価値の高い情報システムを構築することを目指す要求開発活動は、我々の目指す方向性と一致した。
この方法論を社内事業の随所に用いて、要求開発と言う強みを持った企業を目指すことになった。
発表では、要求開発方法論とはそもそもどう言ったものなのか?また、導入する際の留意点や実際に得られた効果、そして要求開発活動を今後も続けて行く為の課題などについて、弊社の活動事例を通じて紹介する。
4 プ ロ セス改善
S1d 自律改善継続実現要因の考察-現場 自 ら が「次も改善を 回 そう!」と行動するために必要な要因は何か? ~ SPINA3CH自律改善メソッド実証実験から得られた知見
情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター(IPA/SEC)プロセス改善ワーキンググループが2011.7.7に初公開し、2013.3.26改訂(*1)した「SPINA3CH自律改善メソッド」の効果を確認する実証実験一事例(複数件実施のうちの一事例)の結果とその考察を報告する。
現場で日々実務を行うメンバーや管理者が“自律”して改善を継続実践するために必要な要因は何か、その要因を有効なものにするポイントやコツ、注意事項などを、実証実験の具体的な進行過程と現場メンバーの気持ちの変化などと共に共有し、今後のよりよい改善実践や継続改善につなげるための情報源になることを目指す。
“自分が変れば周囲が変わる”とはどのようなことなのか、それを実現するために一時的に必要な“心を動かす支援対応”とは何か、などをこの小さな実験結果から探る。
5 人 材 育成
S2a トップガン研修構築の考え方と実践 -課題解決力、リーダーシップ力の向上を目指して-
デンソーでは、経営戦略に必要な人材を育成するためにハイタレント研修を実施している。ソフトウェア工学のハイタレント研修は、開講時より開発プロセスに沿った講義と課題発表で構成していたが、課題発表では講義内容が十分活用できず、課題解決の考え方も不十分であった。
そこで、目指す人材像を「開発現場の課題を解決し、デンソーを引っ張っていける技術者(トップガン)」、必要な能力を課題解決力とリーダーシップ力と定義し、カリキュラムの再構築を行った。
まず、課題解決力の向上を図るために、研修に論文作成と最新技術の講義(特論)を導入した。さらに、課題形成に必要な知識・技術、工学的アプローチを修得するコースを新設すると同時に、受講者一人一人の課題形成、解決の支援を開始した。また、リーダーとしての自覚、課題解決へ立ち向かうマインドセットを形成するため、技術者としての理念、哲学を学ぶ講義を特論に加えた。
以上の取り組みにより、課題解決力を示す受講生の論文は、社外発表が数件出るレベルまで向上した。リーダーシップ力については、講義での質問の増加や、目の色の変化など、受講生が課題解決により積極的に取り組むようになった。
6 ア ジ ャイル
S2b 高品質を重視 し た NECアジャイル ~ソフトウェア品質会計のエッセンスをアジャイル開発に適用~
変化に強く俊敏なソフトウェア開発の実現のためアジャイル開発に対してNECでは依然より注目していた。しかしながらその取り組みは、社内の一部組織におけるものに限定されており、本格的な取り組みにはなっていなかった。
その主な理由として、アジャイル開発では弊社が長年にわたり培ってきたソフトウェア品質会計(品質会計)のように、十分な品質を確保するための手法が確立されていない点が挙げられる。
品質会計とは品質が作りこまれたことを確かな根拠をもって客観的に説明可能にするソフトウェア品質管理手法である。NECではアジャイル開発の持つ俊敏性を生かしながら品質状況を客観的に確認できるようにするために、品質会計のエッセンスをアジャイル開発で実現するための手法を構築した。 本手法を実際のプロジェクトへ適用した結果、アジャイル開発の長所である俊敏性や柔軟性を確保しつつ、確かな根拠をもって品質状
8
況を説明できることを確認した。 本発表では、アジャイル開発で品質を説明するために確立した手
法と、実際のプロジェクトにて実証した結果を報告する。
7 開 発 手法
S2c デジタル複写機のネットワーク開発 へ の XDDP適用事例
私の所属する組織では、デジタル複写機のネットワーク制御機能の開発を行なっている。開発の内容は、主に一定期間ごとに前身機に対する既存機能の変更や新機能の追加を行い、新製品に搭載するというものである。また、一方で市場で稼働している製品で発生する問題の対応も合わせて行なっている。
これらの開発業務を限られた人的資源で、同時並行で進める必要があり、出荷する製品の品質と決められた期間の中で確実に開発が行える生産性が重要課題である。この重要課題の克服を目的として、XDDPの取り組みを始めた。
XDDPをプロジェクトへ導入するために行った準備と、試行で得られた結果を定量的なデータで紹介する。
また試行により新たにわかった問題点とそれに対する工夫をあわせて紹介する。
8 プ ロ セス改善
S2d 「改善をやめた」組織でのプロセス改善 ~プロセス改善はやり直せるのか~
弊社では事業部門ごとに、それぞれの部門の事情に合わせてソフトウェア開発のプロセス改善を行っている。SEPG としてある事業部門に異動してみると、そこは「プロセス改善をやめた」組織だった。専任者を含むプロセス改善のためのグループが存在していたこともあったが、異動時にはグループがなくなり組織的な改善が行われなくなって 5 年がたっていた。
このような状況で専任者としてプロセス改善に取り組むことになったが、改善を再開するにあたり以下のような不安があった。 ・一からの改善実施の場合と同じ方法は使えるのか? ・再改善特有の事情はあるのか?ある場合は、どのように対応する
か? また、再開してみるとソフトの品質が悪化傾向であることが分か
り、悪化防止、品質改善を急ぐ必要があった。 組織内の状況を確認していくと、過去の改善活動の成果が「遺産」
として残っていることが分かった。そこで一般的な改善手法をベースに、「遺産」を活用しながら効率よく改善を進めることとなった。
本発表では、改善グループがなくなったことで起こったこと、再開したプロセス改善と通常のプロセス改善の違い、「遺産」の活用法など、再開から 1 年間の改善活動の内容と、そこで得た知見について報告する。
9 その他 S2f 高品質なコア資産開発のためのレガシー資産活用の取組み -コードクローン検出ツ ー ルCCFinderXを用いたレガシーソース コ ー ドの分析事例-
近年、ソフトウェアプロダクトライン(SPL)の取組みに代表される、再利用を前提としたソフトウェア開発が注目を集めている。弊社ではSPLの取組みにおいて、レガシーシステムの成果物を活用することで再利用資産であるコア資産を効率よく開発することに取り組んでいる。しかし本取り組みの中で著者らは次のような問題に直面した。
問題1:品質の良くないレガシーシステムの成果物をそのままコア資産に組み入れてしまうとコア資産全体の品質を低下させてしまう。例えば、冗長・複雑なソースコードをコア資産に組み入れるとソースコードの保守性を低下させてしまう。
問題2:大規模なレガシーシステムの成果物を分析するのはコストが多大である。
そこで、著者らはレガシーシステムの成果物がコア資産としてふさわしいものなのか、効率よく、客観的に診断する手法として、コードクローン検出ツールCCFinderX[1]に基づいた診断手法を考案した。
考案した手法を事例に適用した結果、問題1に対しては、流用・再利用によって発生した複雑・冗長なソースコードを適切に特定できるという進歩があったが、これらのソースコードがどれだけ品質へ影響があるかを導くことは今後の課題となった。問題2に対しては、手法を用いることで専門知識を持たない分析担当者でも分析を効率的に実施することができ、大規模なシステムにも対応できることを示すことができた。
モジュール間の依存度やソフトウェアメトリクスの計測など、より多くの視点から品質を診断することが今後の課題として挙げられる。
10 人 材 育成
S3a ピア・レビューと履行検証に着目
2006年頃より「人が育つ」ことを第一義としたトレーニング指向アプローチの下、プロセス改善に取り組んできたが、その理念に反し「若手技術者が思うように育っていない」という声を耳にするよ
9
した若手技術者の育成~業務の中で自然に学ぶ方式~
うになってきた。その要因は、特別な学習・教育を受けていないということではなく、普段の業務の中で技術力を自然に身に付け学ぶことができていないことにあると考えた。
そこで、業務の中で学ぶ機会として、上司・識者の技術に直接触れる機会であるピア・レビューと、エンジニアリングプロセスの履行を自己で確認する活動(EP自己履行検証)に着目した。EP自己履行検証は若手技術者にとっては余分で面倒なやらされ感いっぱいの活動に陥っていたが、それをピア・レビューの準備と位置づけることでマイナスなイメージを払拭し、効果的な活動への転換をはかり、EP自己履行検証とピア・レビューの両輪で若手技術者のスキル向上を支える仕組みを考案・展開した。
本発表では、ピア・レビューおよびEP自己履行検証がスキル向上に繋がるメカニズム、EP自己履行検証がピア・レビューの準備となる両者の親和性の考察と、これらの活動を現場で定着させるための仕組み・取り組みについて紹介する。
11 ソ フ トウ ェ ア品 質 管理
S3b ソフトウエア開発におけ る QCD 指標を活用した品質向上への取組み ~ユーザ部門における品質管理の実践的手法の確立~
プラットフォーム開発本部では、通信サービスに係る多種多様のシステム開発を実施しており、2008年頃当時は標準的品質管理手順もなく開発担当者の知識経験に依存していたため、開発プロジェクト管理項目の漏れや、開発案件毎のQCD(Quality, Cost, Delivery)のばらつきの大きさ、開発担当者異動時の品質劣化の懸念等に対する問題解決が求められていた。
ソフトウエア開発業務における品質管理は、それに係る開発担当者の負荷、統計分析結果の精度・適用性、開発担当者への有効性の理解浸透等の課題から、その実現・定着化が難しい状況にあったが、「品質向上への実践的手法の確立」に向けてPDCA活動を繰り返し取り組んできた。
本稿では、この取組みにおいて採用した「ソフトウエア開発プロセ ス の 標 準 化 」 及 び 「 ソ フ ト ウ エ ア 開 発 の QCD( Quality, Cost, Delivery)指標管理による定量的〝見える化“」の実施内容を事例紹介する。
具体的には、問題解決のために導入した「標準的ソフトウエア開発プロセスの雛型作成」、「開発規模測定へのFP(ファンクションポイント)適用」、「最適なQCD指標の適用」、「QCD分析手法の標準化」の4つの観点から、当社開発案件で実際に適用した具体的手法・実施結果、QCD指標適用時の留意点等を紹介する。
12 形 式 手法
S3c 情報システムにおける形式手法活用への取り組み
情報システムの重要性が高まるのに従い、品質や信頼性が高いソフトウェアを開発するための手法として形式手法が注目されています。しかしながら、形式手法は仕様の形式化(記号化)や論理的な証明などに対して高度な数学的知識を必要とするため、情報システムの開発現場にとって敷居の高いものとなっています。
現在、形式手法のガイド化やツール化を行い、情報システムの開発現場で形式手法を利用可能にするための取り組みを進めています。ガイド化については、DSFなどでの活動成果として「形式手法活用ガイド」を整備し、これを参照しながらEvent-Bを用いてプロジェクトの設計書に対する形式検証を推進しようとしています。また、ツール化については、決定表作成支援・検証ツールを開発し、決定表の作成工数削減および品質向上を実現しました。そして、開発作業において適用評価を行い、決定表作成の容易化や仕様漏れの発見などを行いました。
13 ソ フ トウ ェ ア開 発 手法
S3d リコーにおけるソフトウェアプロダクトライン導入に向けた課題特定の取り組み事例
ソフトウェアプロダクトライン(SPL)は、体系的なソフトウェアの再利用で、シリーズ機種を効率的に開発する方法である。SPLを導入した結果、開発期間の短縮、品質改善の効果が様々な報告で確認されている。リコーの主要製品は、既存のプロダクトに対し機能追加、性能を改善する派生開発がほとんどであり、年々規模と複雑さが増大し、品質と納期に問題を抱えている。したがって、SPLの導入は、品質、コストおよび開発効率を向上させるかどうかのキーとなっている。
14 テ ス ト駆 動 開発
S3f 受け入れテスト駆動開発による実行可能な仕様に関する検証結果
多くの企業が変化する市場、顧客のニーズに柔軟に対応するためにアジャイル開発を導入し始めているる。そこで、当社は短い反復開発で確実に顧客のニーズに応えるために、あらかじめ顧客の観点で個々の要求をテストケースとして作成し、これを自動化するという受け入れテスト駆動開発のアプローチを試み、その実用性について検証した。
今回のプロジェクトでは、主に以下 2 項目を実施した。
10
1. 受け入れテスト駆動開発をサポートするツールの選定。 2. 上記 1 で選定したツールを利用した web アプリケーションの受
入れテスト駆動開発の実用性によって、受入れ駆動テスト開発の効果を検証する。
本稿では、受け入れテスト駆動開発を説明し、上記の選定・検証に当社が採用した手法と開発プロセスを紹介する。また、検証の結果について、受け入れテスト駆動開発の実用性、導入時の前提条件や留意点及びコストについて紹介する。
2012年
№ 分類 コード タイトル 概要 1 要 求 工
学 F3a 早期の要求
獲得・問題解決を実現する仕組みづくり
講 演 概 要 デンソークリエイトは組 み込 みソフトウェアの請 負 開 発 を主 な事業 としているが、長 期 間 に渡 り常 に開 発 に追 われメンバーが疲 弊 する、という状 況 を繰 り返 していた。その状 況 から抜 け出 すには”素 早 く”動 くことが有 効であると気 づき、組 織 の素 早 さを引 き出 す仕 組 みを築 いてきた。本 稿 では、”素 早 さ”を持 つ組 織 になるための仕 組 みと、その効 果 ・事 例 について発 表 する。 【1】背 景 ・問 題
組 み込 みソフトウェア開 発 は年 々大 規 模 化 している。製 品 評 価 のフェーズでは仕 様 変 更 や不 具 合 対 応 が多 発 し、開 発 終 盤 に特 に負 荷 が集 中 する。その結 果 、次 の開 発 の立 ち上 げを始 めることができない場 合 が多 い。また、開 発 の初 期 段 階 では、仕 様 の曖 昧 さが多 い。更 に顧 客 側 での動 き様 が見えないことも加 わり、プロジェクトの立 ち上 がりの遅 れを助 長 する。
このように立 ち上 がりの遅 れが常 態 化 し、結 果 的 に開 発 終 盤 に負 荷 が集中 するという悪 循 環 に陥 っていた。そのような状 況 に対 し、現 場 は「仕 様 が決まらない・変 わる」「無 理 な要 求 を強 いられる」等 の不 平 ・不 満 を常 に抱 き、被害 者 意 識 でいっぱいのまま、悪 循 環 から抜 け出 すことができずにいた。 【2】課 題
現 場 は他 責 ・被 害 者 意 識 が強 く、悪 循 環 を断 つために顧 客 をはじめとした周 り(他 人 )に変 わってほしいと望 んでいた。 しかし、他 人 のことを変 えるには限 界 があり、変 わらないことにより一 層 不 平 ・不 満 が強 くなっていた。そこで、発 想 を変 え、仕 様 が曖 昧 ・変 わる等 の周 りが大 きく関 係 することに対 し、”そういうものだ”と受 け入 れ、自 分 たちが出 来 ることをやって、問 題 の状 況 を軽 減 するアプローチを考 えた(変 えられないことを前 提 とした)。そして、曖 昧 なもの・変 わるものに対 し我 々が出 来 ることは「早 く始 めることである」と気 づき、”素 早 さ”を持 つ組 織 になることが課 題 であると考えた。 【3】”素 早 さ”を持 つ組 織 を作 る仕 組 み
まず、”素 早 い”組 織 となるための要 件 として(1)「攻 めの気 持 ち」を持 ち、行 動 するための(2)「機 会 を持 つ」、そして、それらの定 着 を支 える(3)「モニタリング」の3つを掲 げた。 (1)「攻 めの気 持 ち」:標 準 プロセスで「上 位 活 動 への参 画 」を明 示 し、顧 客活 動 に入 り込 む覚 悟 を決 めさせた。そして活 動 の中 心 となるPM層 と、PM層を支 える若 手 メンバーのそれぞれに対 し、意 識 付 けのトレーニングを行 った。 (2)「機 会 を持 つ」:いくらプロセスがあり意 識 付 けをしただけではうまくいかない。コミュニケーションが元 々苦 手 な人 が多 いため尚 更 である。そこで、強 制的 に機 会 を持 たせる「Catch Bal l Meeting(CBM)」の仕 組 みを導 入 した。 (3)「モニタリング」:気 持 ちや機 会 があっても、元 々苦 手 な活 動 であるため、人 の弱 さが出 てしまい、やらなくなる・できなくなる可 能 性 がある。そのため活動 状 況 を定 期 的 に確 認 できる「モニタリング」の仕 組 みを構 築 し、人 の弱 さに歯 止 めをかける仕 組 みとした。また、周 りは変 えられないことを前 提 として築 いた仕 組 みだったが、自 分 たちが”素 早 く”行 動 することにより、周 りをも動 かすことができることにも気 づいた。(副 次 効 果 ) 【4】効 果 の確 認 (1)仕 組 みが機 能 しているか:活 動 状 況 で判 断 以 下 の状 況 から仕 組 みが機 能 しており、”素 早 さ”を持 つ組 織 となる仕 組 みが構 築 できたと判 断 している。 ・CBMの実 施 状 況 :活 動 開 始 から3年 間 実 施 率 は90%以 上 を維 持 し、年 間の実 施 回 数 も全 プロジェクト合 わせて1000回 を超 えるようになった。 ・上 位 活 動 への参 画 : PM自 身 の自 己 診 断 と第 三 者 によるアセスメントの診断 結 果 ともに1年 から1年 半 で満 点 近 くに向 上 し、活 動 の定 着 が見 られた。 (2)問 題 が解 決 しているか:仕 組 みを取 り入 れたプロジェクトの結 果 (事 例 )で判 断 仕 組 みを取 り入 れた実 際 のプロジェクトで効 果 が確 認 されたため、”素早 さ”を持 つ組 織 がとなることが問 題 解 決 につながると評 価 している。
11
・初 期 から「上 位 活 動 への参 画 」を積 極 的 に行 い、活 動 量 は過 去 の同 規 模のプロジェクトより格 段 に多 い。 ・「上 位 活 動 への参 画 」を基 盤 とし、過 去 の同 規 模 プロジェクトの約 4倍 の課 題 ・リスクを活 動 初 期 から素 早 く抽 出 し、素 早 く解 消 し、終 盤 の混 乱を抑 制 した。・結 果 的 に、顧 客 評 価 での不 具 合 は過 去 の同 規 模 プロジェクトの約 1/3に削 減 できた、品 質 も向 上 した。
2 オ フ ショア
F3b オフショア開発における単体テストの生産性向上策 ~入力支援ツールによる言語の壁の克服~
近 年 、IT業 界 ではコスト削 減 や要 員 確 保 を目 的 としたオフショア開 発 が広がりつつある。当 社 も中 国 でのオフショア開 発 を推 進 しており、その中 で様 々な課 題 に直 面 し、克 服 してきた。本 論 文 ではオフショア開 発 の中 でもドキュメントの日 本 語 化 という課 題 について当 社 の取 り組 みを説 明 する。
中 国 オフショア開 発 においてもドキュメンテーションは日 本 語 で行 われることが通 常 である。日 本 後 スキルに優 れた要 員 を揃 えることが理 想 であるが、日 本 ごスキルが低 い要 員 が開 発 チームに加 わることもある。すなわち、ドキュメントの翻 訳 という作 業 が避 けられない。ドキュメントの翻 訳 方 法 については様 々な方 法 があるが、検 討 の結 果 、今 回 は翻 訳 ソフトの活 用 による翻 訳 を試 行 した。
翻 訳 ソフトは安 価 かつ高 速 に翻 訳 することが可 能 であるが、翻 訳 精 度 が課 題 となる。事 前 の検 証 結 果 でもシステム用 語 や文 章 については特 に翻 訳精 度 が芳 しくなかった。そこで、翻 訳 ソフトを活 用 するために、(1)システム用語 や設 計 項 目 などの用 語 を翻 訳 辞 書 に登 録 する(約 3000項 目 )、(2)長 文ではなく短 文 の翻 訳 に限 定 するといった対 策 を講 じた。これらの対 策 の結果 、単 体 テスト仕 様 書 の翻 訳 については、日 本 語 として問 題 のないレベルで訳 せることができた。課 題 となるのは、翻 訳 辞 書 に登 録 されている単 語 のみを利 用 させることである。日 本 側 で用 意 した単 語 を利 用 してもらわない限 り、翻 訳 の精 度 は向 上 しない。そこで、「入 力 支 援 ツール」というドキュメント作 成の補 助 ツールを開 発 し、これを使 用 してもらうことで翻 訳 精 度 を確 保 した。
「入 力 支 援 ツール」はExcelのアドインであり、Excel上 で文 章 を作 成 する際 の補 助 ツールとして活 用 する。主 な機 能 はあらかじめ登 録 した語 句 をリストより選 択 し、セルに入 力 するというものである。単 体 テスト仕 様 書 は定 型 的 な文 章 で記 入 することが可 能 である。すなわち、定 型 文 章 、単 体 テスト頻 出 単語 、定 義 情 報 (画 面 項 目 定 義 、テーブル定 義 など)を入 力 すれば単 体 テスト仕 様 書 が出 来 上 がる。今 回 は「入 力 支 援 ツール」の入 力 用 辞 書 に上 記 の3つを中 国 語 ・日 本 語 の両 方 で追 加 した。その上 で、日 本 語 があまり得 意 でない要 員 1名 に「入 力 支 援 ツール」を使 って単 体 テスト仕 様 書 を中 国 語 作 成 してもらった。すなわち、単 体 テスト仕 様 書 作 成 フローは以 下 の通 りとなる。 (1)中 国 で「入 力 支 援 ツール」で単 体 テスト仕 様 書 を中 国 語 で作 成 する、(2)翻 訳 ソフトを使 い単 体 テスト仕 様 書 を中 国 語 から日 本 語 に翻 訳 する、(3)日本 語 に翻 訳 された仕 様 書 を日 本 の要 員 がレビューする。 成 果 としては以 下 の3つが挙 げられる。 (1)ツールに対 する慣 れが必 要 であったが、最 終 的 には日 本 語 スキルがある要 員 と同 等 の生 産 性 で単 体 テスト仕 様 書 を作 成 することができた。すなわち、日 本 語 スキルが低 い要 員 が日 本 語 の仕 様 書 を作 成 するより大 幅 に生 産性 は向 上 した。 (2)作 成 された中 国 語 仕 様 書 を翻 訳 ソフトで翻 訳 した結 果 、ほぼ問 題 なく日本 語 に翻 訳 できた。 (3)仕 様 書 の表 現 が統 一 され、読 みやすくなった。
今 後 は辞 書 の作 成 など事 前 準 備 の効 率 化 に取 り組 むと共 に、一 層 使 いやすいツールへと改 良 を加 えていく予 定 である。
3 プ ロ セス改善
F3c 継続的な価値提供のための改善プロセス
ソフトウェア開 発 チームのリーダーという立 場 で、基 幹 系 個 別 開 発 ソフトからコンシューマ向 けサービス開 発 へ転 向 したという経 験 から後 者 の開 発 を行うに当 たり、両 開 発 のプロセスや目 的 の違 いを対 比 しつつ直 面 した問 題 やその解 決 のための活 動 を通 して「目 的 を共 有 する」ことと「継 続 して改 善 し続 ける」ことの大 切 さとその成 果 について述 べる。
基 幹 系 個 別 開 発 でははじめにやることをすべて決 めなければいけないという難 しさがある反 面 、目 指 す効 用 や価 値 はある程 度 決 まっている事 が多 い。
しかしコンシューマ向 けサービスでは状 況 の変 化 が大 きく、また一 般 的 な解 もない、もしくは定 義 出 来 ない場 合 が多 い。
そのような領 域 の開 発 を行 うにあたり、理 想 的 な姿 を定 義 するがその実 現には多 くの障 害 がある。
理 想 的 な姿 に近 づくために、自 分 たちの現 場 である開 発 チームで取 り組んできた内 容 や価 値 観 、手 段 を使 いどのようにチームを育 て、理 想 に近 づけていったかという事 例 を共 有 する。
4 要 求 工学
F4a 要求仕様から利用品質 ~ソフトウ
システム開 発 の上 流 工 程 では要 求 分 析 に基 づき「要 求 仕 様 書 」が作 成 され、レビューによりその適 切 性 を確 認 することが多 い。しかし、多 くの場 合 「要求 仕 様 書 」には要 求 分 析 結 果 である”システム仕 様 ”だけが記 載 されていた
12
ェア品質特性へのリバース結果に基づく要求仕様レビュー ~ 利 用 者 に
喜ばれる・役
立 つ シ ス テ
ム の 構 築 に
向けて
り、システムにより解 決 すべき事 項 や解 決 後 の状 態 (システムゴールやユーザゴール)が不 明 確 なまま、分 析 ・検 討 過 程 が何 も表 現 されていないなど、レビューによる適 切 性 判 断 (主 に、妥 当 性 確 認 )が難 しい状 態 であることが多 いと推 察 している。
当 初 からこれらの事 項 を明 確 化 したうえで要 求 仕 様 書 に記 載 することが理 想 ではあるが、実 務 ではそうできない理 由 や背 景 にあふれており、今 後 も上 記 のような結 果 だけを示 した要 求 仕 様 がまかり通 る可 能 性 が高 い。
そこで、実 務 の現 場 で提 示 された「要 求 仕 様 書 」の内 容 から、利 用 時 の品 質 (利 用 者 像 ・利 用 時 コンテキストを含 む)やソフトウェア品 質 特 性 をリバースした情 報 をもとに「要 求 仕 様 書 」レビューを実 施 し、的 確 なフィードバックを提 供 する方 法 を提 案 する。
もともとはテスト設 計 方 法 論 を検 討 する過 程 で生 まれたものであるが、システム導 入 により解 決 する課 題 や、求 められるソフトウェア品 質 特 性 などを階 層的 に整 理 ・明 確 化 することで、要 求 仕 様 の適 切 性 を判 断 する根 拠 が明 確 となるだけでなく、システムに対 する非 機 能 要 求 事 項 の明 確 化 、利 用 者 の課題 に対 するITシステムと人 間 の適 切 な役 割 分 担 の採 用 、過 剰 な機 能 付 与 ・機 能 不 足 の防 止 、システム稼 働 終 了 までのライフサイクルを意 識 したシステム開 発 の促 進 、などの効 果 が期 待 できる。
5 ア ジ ャイル
F4b オフショア開発におけるアジャイル開発の取り組みと評価
本 発 表 は、オフショア開 発 へのアジャイル開 発 導 入 に関 する取 り組 みを説明 し、アジャイル開 発 プロジェクトを評 価 するためのメトリクスを選 定 し、定 量的 な結 果 を示 し、定 性 的 な効 果 を紹 介 する。
アジャイル開 発 は、欧 米 のソフトウェア開 発 の現 場 で広 く適 用 されている(※2)。日 本 のソフトウェア開 発 業 界 では、WEBサイト開 発 やゲーム開 発 など、ビジネスや技 術 の変 化 へのすばやい対 応 が要 求 されている領 域 でのアジャイル開 発 への移 行 が進 んでいる一 方 、SIerの領 域 では、組 織 の体 質 や多 階 層 の請 負 契 約 による開 発 体 制 といった業 界 の慣 行 に、アジャイル開 発が前 提 とする開 発 のやり方 がなじみにくく、その事 例 は依 然 として小 規 模 案件 にとどまる傾 向 がある。当 社 は、90年 代 から大 規 模 反 復 の開 発 を実 践 して き た 。 2011 年 か ら は 開 発 方 法 、 測 定 や 契 約 を 含 む 体 系 で あ る 「 OGIS Scalable Agile Method(OSAM)」を社 内 の開 発 プロジェクトに適 用 ・推 進 している。(※3)
オ フ シ ョ ア 開 発 に つ い て は 、 「 グ ロ ー バ ル デ リ バ リ 」 の 動 き 下 で 、 当 社 は2007年 10月 に、日 中 合 弁 の形 で上 海 欧 計 斯 軟 件 有 限 公 司 (SOT)を設 立し、グローバル事 業 展 開 の一 環 として上 海 にオフショア開 発 拠 点 を持 つに至った。設 立 以 来 の数 年 間 で、オフショア開 発 プロセスの整 備 や、開 発 経 験 の蓄 積 によって、当 社 同 様 にコスト削 減 の効 果 を上 げている(※1)。しかし、国内 のパートナー企 業 との協 力 と比 べ、仕 様 に関 する説 明 、合 意 の形 成 、詳細 な仕 様 書 の作 成 、現 地 出 張 の費 用 、品 質 管 理 /トラブルの対 応 、進 捗 管理 /遅 延 の対 応 コストなどは、依 然 大 きな課 題 のままである。これらのコスト増加 の要 因 の低 減 を目 的 として、当 社 はオフショア開 発 へのアジャイル開 発 の導 入 を試 みた。
要 求 の主 導 権 の観 点 から分 類 すると、SOTでは、以 下 2種 類 の受 託 開 発を行 っている。 1.当 社 の要 求 を満 たすための開 発 2.当 社 の顧 客 の要 求 を満 たすための開 発
上 記 2の開 発 に関 しては、日 本 で上 流 設 計 を行 い、中 国 に詳 細 設 計 ~結 合 テストの工 程 を発 注 、日 本 で成 果 物 を受 け入 れ、システムテストを実 施するという典 型 的 なオフショア開 発 である。上 記 1の開 発 に関 しては、当 社 の社 内 システムの開 発 やパッケージ開 発 になるが、当 社 が推 進 しているOSAMの一 部 を導 入 した。具 体 的 に開 発 手 法 はScrumを導 入 し、技 術 的 なプラクティスとアジャイル開 発 をサポートするツールを開 発 に導 入 した。
アジャイル開 発 の導 入 結 果 に関 し、定 量 的 なプロジェクトのデータを収 集した。また、現 地 で関 係 者 が一 堂 に会 してのプロジェクト振 り返 りを経 て、開発 関 係 者 の定 性 的 な意 見 を収 集 した。定 量 的 なデータの分 析 と定 性 的 な感 想 から、アジャイル開 発 の導 入 によって、オフショア側 のチームの一 体 感及 び、人 員 の定 着 率 が向 上 し、生 産 性 と品 質 の安 定 化 などの効 果 がもたらされた。また、課 題 についても顕 在 化 してきた。
今 後 の取 り 組 み とし て、 1)オフショア 開 発 とア ジャイ ル 開 発 のプロ セス をSOTの開 発 標 準 に盛 り込 み、また、2)当 社 の要 求 を満 たすための開 発 以 外に、当 社 の顧 客 の要 求 を満 たすための開 発 へのアジャイル開 発 の導 入 を予定 している。
6 ア ジ ャイル
F4c “ チ ー ム力”で派生開発を成功させる為の
(1) 背 景 昨 今 の組 み込 みデバイスは、製 品 競 争 の激 化 により、高 機 能 、高 品 質 、
短 納 期 、低 コストへの要 求 が強 く、これらの課 題 解 決 が急 務 となっている。しかしながら、長 きに渡 る景 気 低 迷 によりヒト・モノ・カネといったリソースが潤 沢
13
“仕掛け作り” - XDDP とSCRUM の併用で派生開発を極める
に割 かれるわけではない。派 生 開 発 においては、新 規 開 発 に比 べて更 に強い傾 向 にある。では、どうすれば迅 速 かつ最 適 の人 員 で、高 品 質 なソフトウェアを開 発 することができるのか。個 々の力 では、限 りがあるので、技 術 手 法 とチーム力 で解 決 していきたいと考 える。 (2) 課 題 ・派 生 開 発 において、迅 速 かつ最 適 の人 員 で、高 品 質 なソフトウェアを開 発したい ・派 生 開 発 におけるQCDの同 時 達 成 を目 指 したい ・様 々な変 化 に対 応 できる下 地 を作 りたい ・少 しでも現 場 を良 くしたい (3) 実 施 方 法 [技 術 的 なアプローチ] 派 生 開 発 に特 化 した手 法 であるXDDPを適 用 した。 [チームによる継 続 的 改 善 アプローチ] アジャイル開 発 手 法 の一 つであるSCRUMを適 用 した。 [開 発 フェーズの分 割 ] 開 発 フェーズを2つに分 けた。 前 半 フェーズ:基 本 構 造 に関 する(H/Wに影 響 のある)変 更 要 求 をXDDPを適 用 して品 質 を固 める後 半 フェーズ:新 規 機 能 追 加 部 分 をIteration開 発 で進 める (4) 結 果 (Q)QA 検 査 不 具 合 指 摘 件 数 : 軽 微 な内 容 の不 具 合 数 件 の み○ (D)納 期 遅 延 0日 :現 時 点 で計 画 通 りである ○ (C)予 算 超 過 無 し:現 時 点 で予 算 内 である ○ メンバの充 実 感 :プロジェクト終 了 後 のアンケートからも充 実 していると思 われる。○ 派 生 開 発 プロジェクトにおいて、派 生 開 発 に特 化 した手 法 (XDDP)を適 用 することは、品 質 面 、納 期 面 、開 発 コスト面 において効 果 があった。また、アジャイル開 発 手 法 の一 つであるSCRUMを適 用 することで、チーム内 に一 定 のリズムが生 まれ、チーム全 体 で改 善 意 識 を最 後 まで保 つことができた。理 に適 った手 法 を適 用 し、チームメンバが自 律 して改 善 を繰 り返 しながら開 発 を進 めて行 くことで、迅 速 かつ最 適 の人 員 で、高 品 質 なソフトウェアを開 発 することができると言 える。
7 要 求 工学
S1a 要求獲得プロセスの可視化と検証の自動化
要 求 工 学 知 識 体 系 REBOKの要 求 工 学 プロセスは,要 求 獲 得 ,要 求 分析 ,要 求 仕 様 化 ,要 求 の検 証 ・妥 当 性 確 認 ・評 価 から構 成 される[1].著 者の所 属 している組 織 では,要 求 分 析 、要 求 の検 証 ・妥 当 性 確 認 ・評 価 の支援 技 術 を開 発 している.要 求 分 析 の支 援 には,要 求 として定 義 すべき項 目をメタモデルとして定 義 し,要 求 の定 義 漏 れの防 止 や均 等 化 に取 組 んでいる[2].要 求 の検 証 ・妥 当 性 確 認 ・評 価 に対 しては,要 求 品 質 チェックシートと呼 ぶチェックシートを用 いて要 求 仕 様 書 の定 義 網 羅 性 を確 認 している.しかしながら,要 求 の検 証 ・妥 当 性 確 認 ・評 価 にあたり,次 のような課 題 に直面 した. 課 題 1:要 求 獲 得 プロセスの品 質 評 価 のやり方 が属 人 的 課 題 2:簡 単 に利 用 できなければ要 求 獲 得 プロセスの品 質 評 価 が定 着 しない 課 題 1に対 する解 決 策 として,メタモデルを用 いて成 功 事 例 の要 求 仕 様 書 を分 析 し「理 想 的 な要 求 獲 得 プロセス」(以 降 ,理 想 モデル)を定 義 する.理想 モデルと対 象 プロジェクトの要 求 の定 義 過 程 を比 較 することで品 質 評 価 をする手 法 として定 義 する.課 題 2に対 する解 決 策 として,要 求 品 質 チェックシートを利 用 した評 価 ツールを作 成 する.
上 述 した解 決 策 を実 事 例 に適 用 し,課 題 1,2を解 決 できるか確 認 した.確 認 の結 果 ,理 想 モデルと異 なる要 求 の定 義 過 程 となっている場 合 、要 求仕 様 書 に不 整 合 があることが発 見 できた.要 求 仕 様 書 の不 整 合 が発 見 できたことで,要 求 獲 得 プロセス検 証 手 法 は要 求 獲 得 プロセスの評 価 に効 果 があることが確 認 できた.作 成 した要 求 品 質 チェックシートを利 用 した評 価 ツールにより、要 求 獲 得 プロセスの品 質 評 価 のやり方 を統 一 することが可 能 であり,課 題 1に対 して有 用 である.
既 存 の取 組 みである要 求 品 質 チェックシートを利 用 することにより,低 コストで要 求 獲 得 プロセスの検 証 を実 現 した.プロジェクトに高 い負 荷 をかけることなく要 求 獲 得 プロセスの品 質 評 価 が可 能 になり,課 題 2を解 決 することが出 来 る.今 後 は,複 数 のプロジェクトへの適 用 を通 して,本 手 法 を継 続 的 に改 善 していく.
8 運用 S1b 業務運用の品質向上に向けた取り
講 演 概 要 富 士 通 エフ・アイ・ピーではアウトソーシングサービスの一 つとしてBPOサービスを提 供 している。本 稿 では、BPO業 務 運 用 の現 場 で発 生 する様 々な課 題 (「属 人 化 」「手 順 の陳 腐 化 」「運 用 ルールの変 更 」など)を通
14
組み~メンバ全員( 17名)参加による継続的な改善活動への挑戦~
し、課 題 解 決 のための改 善 手 法 に焦 点 をあて、現 場 主 導 で実 施 可 能 なその方 法 と効 果 について発 表 する。 1.背 景
お客 様 (社 員 :約 2,200名 )の管 理 部 門 業 務 の一 部 を2009年 10月 から当社 がサービス提 供 している。当 社 初 の本 格 的 な管 理 部 門 の業 務 BPOであったが、2009年 9月 までは他 社 (A社 )に委 託 されていた為 、お客 様 は委 託 先変 更 の意 識 がなく、短 納 期 でかつこれまでと同 様 の安 定 した運 用 を期 待 された。当 社 は,、品 質 確 保 の為 、旧 委 託 先 (A社 )の業 務 システム・運 用 手 順をそのまま移 行 (As-Is To AsIs方 式 )を実 施 。その結 果 、立 ち上 げから半 年間 は、安 定 運 用 によりお客 様 から高 評 価 を頂 いた。 2.課 題
本 稼 働 後 、半 年 間 は安 定 稼 働 していたがその後 お客 様 によるチェックのエラー検 出 数 が増 大 。2009年 度 は32件 であったが、2010年 度 では112件 にのぼった。お客 様 から得 た信 頼 を喪 失 しかねない状 況 にあった。更 に、メンバのモチベーションも低 下 傾 向 にあった。 3.課 題 解 決 に向 けた取 り組 み
これらを解 決 するために本 プロジェクトに「Lean(※1)活 動 」を適 用 した。 (※1)Leanとは、価 値 を生 み出 し、ムダを排 除 して継 続 的 改 善 の文 化 を構築 するという働 き方 具 体 的 には、以 下 サイクルを展 開 した。(※2)以 下 括 弧 内 は活 動 ポイント (1) メンバが運 用 中 に気 付 いた点 を付 箋 紙 に書 き、壁 に添 付 (問 題 の可 視化 ) (2)(1)の内 容 についてメンバ全 員 でアイディアを出 し、壁 に添 付 (否 定 はしない) (3)改 善 担 当 者 が(1)と(2)の内 容 を取 り纏 め、一 覧 表 を作 成 (既 存 運 用 への負 荷 軽 減 ) (4)メンバ全 員 で一 覧 表 を元 に改 善 内 容 を決 定 し、合 意 (メンバ主 体 の運 用へ) (5)本 番 運 用 (6)改 善 担 当 者 が改 善 成 果 の計 測 (KPIの測 定 )
9 プ ロ セス改善
S1c TOC思考プロセスによる改善施策の合意形成 -テストプロセス改善における事例-
ソフトウェア開 発 プロセス改 善 など,関 係 者 の多 い改 善 活 動 を行 う際 には,関 係 者 の合 意 形 成 が非 常 に重 要 である.この合 意 形 成 が不 十 分 だと,改 善 施 策 の意 図 を歪 曲 したり,勝 手 な解 釈 をしたりし,改 善 が十 分 な効 果 を上 げることができなくなる.しかし,このような合 意 形 成 は重 要 であるものの困難 なことが多 い.複 数 の関 係 者 が関 わる場 合 ,改 善 対 象 となる問 題 点 は複数 存 在 することがあり,関 係 者 の立 場 によって,それら問 題 点 の重 要 度 が異なってくる.また,それら問 題 点 は相 互 関 係 を持 つことも多 く,ある関 係 者 一方 の立 場 で重 要 と考 えられる問 題 点 を解 決 しようとすると,別 の関 係 者 が重要 と思 っている問 題 点 に悪 影 響 を及 ぼすようなことが起 こる.このように複 数の問 題 が相 互 関 係 を持 ち,関 係 者 がそれらについて異 なる重 要 度 を持 っていることが,関 係 者 の多 い改 善 活 動 における改 善 施 策 の合 意 形 成 を困 難 にしていると考 えられる.
本 報 告 では,このようなソフト開 発 プロセス改 善 における改 善 施 策 の合 意形 成 に 対 し て , TOC 思 考 プ ロ セ ス の 現 状 構 造 ツ リ ー の 導 入 を 提 案 す る .TOC思 考 プロセスは,制 約 条 件 の理 論 (Theory of Constraints)の手 法 の一つであり,目 的 を阻 害 している中 核 の問 題 を発 見 ・解 決 することで最 小 の労力 で最 大 の改 善 効 果 を得 る,体 系 的 な問 題 解 決 手 法 である.このTOC思考 プロセスの中 の現 状 構 造 ツリーは,改 善 対 象 の問 題 の因 果 関 係 を構 造化 したもので,このツリーを用 いて,中 核 の問 題 を1つか2つに絞 り込 んでいく.この現 状 構 造 ツリーは,上 述 のように立 場 によって重 要 度 の異 なる複 数の問 題 が存 在 している場 合 であっても,それらの因 果 関 係 を見 える化 することができ,集 中 して改 善 すべき中 核 問 題 を明 確 にできる.このように現 状 構造 ツリーは,改 善 施 策 の合 意 形 成 を困 難 にしている要 因 を排 除 できるため,複 数 の関 係 者 が関 わる改 善 活 動 において非 常 に有 効 な道 具 であるといえる.
本 報 告 では,日 立 グループのある組 込 みソフトにおけるテストプロセス改 善に対 して,TOC思 考 プロセスの現 状 構 造 ツリーを用 いた事 例 を報 告 する.改善 対 象 組 織 では,テストが不 十 分 になり,不 具 合 の抜 け漏 れが発 生 しているという問 題 があり,ソフト設 計 者 と品 質 保 証 部 の担 当 者 等 で構 成 したワーキンググループ(全 16名 )を組 織 して,この改 善 に取 り組 んだ.報 告 者 は,このワーキンググループによる改 善 施 策 の検 討 に現 状 構 造 ツリーを用 いた.結 果 ,集 中 すべき中 核 問 題 は,全 てのテスト結 果 の客 観 的 証 拠 を保 存 しなければならないという方 針 であることを明 確 にした.この中 核 問 題 を明 確 にすることで,不 具 合 摘 出 のためのテストを定 義 し,そのテストのためにテスト観 点 レビューという改 善 施 策 を,ワーキンググループメンバー全 員 が納 得 する形 で導
15
出 することができた.本 改 善 施 策 は,実 際 に試 行 ・評 価 し,多 くの不 具 合 を摘 出 できることも確 認 した.
10 要 求 工学
S2a 要求開発手法「 HyThology○R 」 ~ REBOK実践の取り組み
日 立 ソリューションズでは、2007年 より「超 上 流 プロセス対 応 力 の強 化 活動 」として、企 画 ・要 件 定 義 工 程 で適 用 する技 術 とプロセスの整 備 、それを活 用 する人 財 育 成 を推 進 してきた。今 年 4月 には、活 動 成 果 の一 つとして、要 求 開 発 手 法 「HyThologyTM」を社 内 外 に発 表 し、実 務 での適 用 を進 めている。
本 稿 では、HyThologyTM開 発 において技 術 体 系 化 のベースとした要 求工 学 知 識 体 系 (REBOK)の活 用 を中 心 に、当 社 の取 り組 みを紹 介 する。 (1)取 り組 みの背 景 と課 題
IT活 用 によるビジネスでの価 値 創 造 とプロジェクト成 功 のためには、超 上流 工 程 が重 要 である。しかし、適 用 する手 法 や方 法 論 には、コンサルティング・メソドロジからモデリング手 法 まで、多 種 多 様 な技 術 が紹 介 されており、取り組 むべき全 体 像 が把 握 しきれない状 況 が続 いている。現 場 で実 践 する為にプロセス・作 業 と手 法 を標 準 化 する事 が必 要 である。併 せて、超 上 流 工 程の専 門 家 たる高 度 IT人 財 (超 上 流 人 財 )を広 く育 成 し、超 上 流 工 程 の円 滑な遂 行 と要 求 品 質 の確 保 を図 る事 が重 要 である。 (2)プロセスと技 術 の体 系 化
顧 客 企 業 側 の体 制 やプロジェクトの特 性 により作 業 プロセスは様 々に変化 する。共 通 フレーム(SLCP)をもとに、作 業 プロセスをモデル化 し、このプロセスを遂 行 する為 の技 術 を、REBOKでの要 求 工 学 プロセスに対 応 付 けてHyThologyTMとして規 定 した。 (3)人 財 育 成
ITスキル標 準 (ITSS)の考 え方 に沿 って、遂 行 する業 務 ・タスクや必 要 なスキルを、超 上 流 人 財 モデルとして可 視 化 した。検 討 にあたってはREBOKの共 通 知 識 領 域 (REBOK Core)の内 容 を利 用 した。さらにキャリア開 発 のために、スキル習 得 の為 の選 抜 者 研 修 を開 発 し、HyThologyTMとその技 術 ・手法 、REBOKの活 用 法 等 を現 場 のSE・営 業 担 当 者 に提 供 している。 4)効 果
一 年 間 の試 行 期 間 を経 て、現 場 からは『従 来 は経 験 的 に獲 得 してきたスキルが、HyThologyTMとして、SLCP・REBOK等 の標 準 的 な体 系 で整 理 されたことにより、ノウハウの充 実 や後 進 の育 成 に有 益 』との評 価 を得 ている。顧客 企 業 からも説 明 の依 頼 を受 けており、顧 客 とベンダーが同 じ言 葉 ・考 え方で超 上 流 工 程 に取 り組 むためにも、有 効 な技 術 として適 用 を推 進 して行 きたい。
11 標準化 S2b 社内システム開発標準の開発におけるテンプレート開発作業の効率化と高品質化
ソフトウェア開 発 ベンダーにおいて、システム開 発 標 準 により、システム構築 の手 順 や作 法 を標 準 化 することは一 般 的 である。最 近 では、REBOKやBABOK、IPAの機 能 要 件 の合 意 形 成 ガイド、非 機 能 要 求 グレードなど、上流 にフォーカスした各 種 標 準 が提 供 されるなど、システム開 発 標 準 は充 実 してきている。
著 者 の所 属 する組 織 においては、プロセス、テンプレート、ガイドから構 成されるシステム開 発 標 準 を定 義 している。これらは、会 社 の戦 略 、組 織 、技術 の変 化 に伴 い、継 続 的 改 善 が必 要 である。今 回 、リリースされた各 種 標 準や、社 内 ノウハウを加 味 して開 発 標 準 の改 善 に取 り組 み、特 に開 発 成 果 物を定 義 するためのテンプレートを開 発 ・改 善 した。
しかしながら、テンプレートの開 発 ・改 善 において、次 のような課 題 に直 面した。 (1)テンプレートの開 発 手 順 が非 効 率 で遅 れが発 生 。 (2)テンプレートに記 述 する項 目 の定 義 漏 れが発 生 し、テンプレートの品 質 が低 下 。そこで、上 記 課 題 の解 決 のために、(1)の課 題 の解 決 策 として、テンプレートのフォーマット定 義 とグループ化 によりテンプレート開 発 の作 業 を共 通化 することとした。(2)の課 題 の解 決 策 としては、メタモデル(※1)を軸 として、既 存 のシステム開 発 標 準 テンプレートや、仕 様 書 作 成 支 援 ツールの仕 様 データで定 義 された項 目 と対 応 関 係 を取 ることとした。(1)、(2)の解 決 策 に基 づき、テンプレート開 発 の効 率 化 と高 品 質 化 を目 指 した。
上 述 した解 決 策 をテンプレート開 発 ・改 善 に適 用 した。本 解 決 策 の適 用後 、1テンプレートあたりの開 発 の生 産 性 が3.2倍 に向 上 した。また、開 発 した1テンプレートあたりの指 摘 件 数 も約 6割 減 少 した。
このことから、考 案 した手 法 はテンプレート開 発 の効 率 化 と高 品 質 化 に有効 であると考 えられる。この手 法 は、テンプレートの説 明 コメントや事 例 作 成作 業 に対 しても適 用 できると考 えられ、継 続 的 に改 善 していく。 (※1)「メタモデル」とは、要 件 定 義 書 や基 本 設 計 書 などの仕 様 書 をモデルとビューに分 け、モデルの構 造 を一 般 化 したものである。
12 プ ロ セス改善
S2c 画面設計の開発プロセ
本 プロジェクトでは、設 計 書 の管 理 ・情 報 の共 有 を目 的 とした基 盤 を開 発しており、社 内 のSEが顧 客 プロジェクトのために活 用 している。開 発 の過 程 に
16
スの改善への取り組み -プロトタイプを用いた画面イメージの認識統一の事例
おいて、完 成 したシステムが設 計 の段 階 で想 定 したイメージと異 なり、フィードバックを取 り込 みきれないことがあった。そのため、設 計 の段 階 で画 面 イメージの認 識 統 一 を行 うべく、プロトタイピング手 法 を採 用 した。その結 果 、効 果を得 ることができた。
しかし、これまでの開 発 では、システムの完 成 後 のイメージが伝 わるレベルでプロトタイプを作 成 していたため、作 成 コストが大 きく画 面 設 計 の開 発 効 率が悪 いという問 題 があった。また、プロトタイプの精 度 が高 くなることで画 面 の細 かいレイアウトに注 意 が向 き、重 要 度 の高 いユースケースが十 分 に議 論 されないことも起 きていた。これらの問 題 を解 決 し、画 面 設 計 の開 発 プロセスを改 善 する必 要 があると考 えた。
そこで、画 面 設 計 の開 発 プロセスの見 直 しを行 い、次 の2点 の改 善 に取 り組 んだ。 (1)ペーパープロトタイピングと実 際 に動 くプロトタイプを組 み合 わせ、段 階 的に行 うプロセスに改 善 (2)上 記 で改 善 したプロセスに従 った、画 面 設 計 作 業 とレビュー観 点 の整 理
上 記 の取 り組 みにより、次 の効 果 を得 ることができた。 (1)予 定 外 の再 レビューの削 減 (2)ユースケースの画 面 設 計 前 半 での認 識 統 一 (3)画 面 設 計 の仕 様 漏 れによる手 戻 り件 数 の削 減
結 果 、画 面 設 計 の開 発 プロセスを改 善 することができた。本 発 表 では、改善 を通 して得 られた、画 面 イメージの認 識 統 一 の事 例 とその効 果 について紹 介 する。
13 要 求 工学
S3a 第 3 者 レ ビューによる要件定義書の品質向上の取り組み
要 件 定 義 書 はシステム開 発 のプロジェクトを成 功 に導 くために重 要 なドキュメントである.顧 客 とベンダは開 発 するシステムの仕 様 を要 件 定 義 書 に記述 し,記 述 内 容 について合 意 する.さらにベンダは要 件 定 義 書 をもとに開 発の見 積 もり,開 発 計 画 を作 成 する.
要 件 定 義 書 に記 述 漏 れや曖 昧 な記 述 があると,後 工 程 で手 戻 りや追 加作 業 などの問 題 が発 生 すると考 えられる.例 えば,設 計 の担 当 者 が要 件 定義 書 の曖 昧 な記 述 を誤 解 したまま作 業 を進 めると,誤 りに気 づいたときに大きな修 正 作 業 が必 要 になる.
そこで筆 者 らは要 件 定 義 書 に起 因 するプロジェクトの問 題 を防 止 するために、要 件 定 義 書 の品 質 を第 3者 が定 量 的 に評 価 し、評 価 結 果 と改 善 提 案をプロジェクトにフィードバックする取 り組 み(要 件 定 義 書 の第 3者 レビューの取 り組 み)を開 発 し、当 社 内 の開 発 プロジェクトへの適 用 を進 めている.
要 件 定 義 書 において記 述 すべき内 容 が記 述 されているか,曖 昧 でない書き方 で記 述 されているかといった観 点 で要 件 定 義 書 の品 質 を定 量 的 に評 価し,品 質 をスコアの形 式 で表 現 する.スコアが低 いプロジェクトには要 件 定 義書 の改 善 提 案 もおこなう。これにより、プロジェクトは要 件 定 義 書 に起 因 する問 題 を予 防 するための対 策 を取 ることができる.
本 報 告 では、当 社 の要 件 定 義 書 の第 3者 レビューの取 り組 みの概 要 を紹介 する。取 り組 みでは適 用 プロジェクトへの追 跡 調 査 をおこない、第 3者 レビューの適 用 効 果 に関 するデータを収 集 した。そこで、要 件 定 義 書 の品 質 の可 視 化 ・改 善 がプロジェクトの後 工 程 での工 数 削 減 に有 用 との実 証 結 果 も併 せて報 告 する。
14 ソ フ トウ ェ アメ ト リクス
S3b COSMIC 概算法による概算規模測定の測定コスト削減の検討結果
COSMIC機 能 規 模 測 定 法 はソフトウェアの機 能 規 模 を測 定 する手 法 である。COSMIC機 能 規 模 測 定 法 で測 定 した機 能 規 模 は、労 力 や欠 陥 数 など他 の測 定 データと組 み合 わせて開 発 生 産 性 や欠 陥 密 度 を求 めることができる。これらの値 を他 のプロジェクトと比 較 して、開 発 プラクティスの良 い点 や改善 点 を明 らかにすることで、よりよい開 発 を目 指 すことができると考 えられる。
機 能 規 模 の測 定 を現 場 で展 開 するには、機 能 規 模 の測 定 コストを削 減する必 要 がある。測 定 コストを削 減 すれば、これまで測 定 コストが妨 げとなって機 能 規 模 の測 定 が難 しかった大 規 模 プロジェクトの測 定 も可 能 になる。そこで、 著 者 ら は、COSMIC 機 能 規 模 測 定 法 の概 算 法 の適 用 を検 討 し た。COSMIC概 算 法 は、COSMIC機 能 規 模 測 定 法 に基 づいて概 算 で機 能 規 模を測 定 する方 法 であり、測 定 コストの削 減 が期 待 できる。COSMIC概 算 法 を適 用 する場 合 は、COSMIC測 定 マニュアル応 用 編 に記 載 されている概 算 法の例 を元 に、個 別 に調 整 する必 要 がある。著 者 らは概 算 法 の例 の中 から、平 均 機 能 プロセス数 法 を元 に概 算 法 を定 めることにした。
まず、平 均 機 能 プロセス数 法 の具 体 的 な手 順 を決 定 して「サンプリング測定 法 」を定 め、さらに平 均 機 能 プロセス数 法 を簡 略 化 した測 定 方 法 である「過 去 データ参 照 法 」を考 案 した。サンプリング測 定 法 は、測 定 対 象 の一 部の機 能 だけをCOSMIC法 に基 づいて精 密 に測 定 し、測 定 した結 果 を元 に概算 規 模 を求 める方 法 である。過 去 データ参 照 法 は、COSMIC法 に基 づく測定 は行 わずに、基 本 設 計 書 から得 られるテーブル数 と過 去 の測 定 データを元 に概 算 規 模 を求 める方 法 である。いずれも通 常 のCOSMIC法 に基 づく測
17
定 に比 べて、簡 易 な方 法 である。サンプリング測 定 法 と過 去 データ参 照 法 は実 際 のプロジェクトに適 用 して概 算 規 模 を測 定 し、測 定 した概 算 規 模 の妥当 性 と測 定 コストの削 減 率 を検 証 した。
サンプリング測 定 法 と過 去 データ参 照 法 をプロジェクトに適 用 した結 果 、測 定 した概 算 規 模 は妥 当 であった。サンプリング測 定 法 の測 定 コストは通 常のCOSMIC機 能 規 模 測 定 法 で測 定 した場 合 より、80%程 度 削 減 でき、過 去データ参 照 法 の測 定 コストはサンプリング測 定 法 よりさらに50%程 度 削 減 できた。二 つの概 算 法 は、測 定 に求 める確 度 や、確 保 できる測 定 コストによって使 い分 けることを考 えている。
今 後 は、さらにCOSMIC概 算 法 による測 定 件 数 を増 やし、測 定 結 果 の検証 を行 う予 定 である。
15 ユ ー ザビ リ ティ
S3c NRI の 社 内業務システムにおけるRIA 化 の 取り組み ~ RIA 化 におけるポイント・課題に関する考察~
野 村 総 合 研 究 所 の 社 内 シ ス テ ム ( 業 務 プ ロ セ ス 管 理 シ ス テ ム(ProArk/BPM))の改 善 の中 で実 施 された計 画 策 定 サブシステムのRIA化 を通 し、NRI自 身 における業 務 システムRIA化 の取 り組 みの紹 介 と実 践 におけるポイント・注 意 点 を説 明 。 ・業 務 プロセス管 理 システムの紹 介 今 回 カイゼンの対 象 となったNRI社 内 業 務 システムについて、予 備 知 識 としてご紹 介 ・RIA化 の経 緯 従 来 の会 計 システムがExcelでフロント部 分 を開 発 していたため、操 作 性 を考 慮 して当 初 はExcelで開 発 したが、Java(Web系 )のシステム機 能 との業 務 的 な分 断 が課 題 となり、全 社 での利 用 開 始 を機 にRIA化 を実施 することとなった。 ・RIA化 の方 式 説 明 及 び設 計 ・開 発 時 のポイント Flexを利 用 してRIA化 を行ったため、Flexをどのように既 存 システムと連 携 させているかという技 術 的 背景 の説 明 設 計 時 点 にユーザエクスペリエンスを向 上 させるために、業 務 的 な機 能 については最 初 から見 えるようにするなど考 慮 してUIを再 作 成 した。開発 時 点 (実 装 )では、工 数 を増 加 させない・品 質 を維 持 するといった観 点 からJava側 機 能 と組 み合 わせてさくせいした。
2011年
№ 分類 コード タイトル 概要 1 ユ ー ザ
ビ リ ティ
F3a 業務シス テムのユー ザビリティ 評価と品質 向上に関す る取組み
インターネットサービスでは、システムのユーザビリティが来 訪 者 数 や売 り上げに直 結 することが広 く認 知 され、ユーザビリティテストやユーザビリティチェックシート等 が開 発 されている。近 年 では使 いやすさだけでなく使 ったときの印象 全 体 を考 慮 する「ユーザエクスペリエンス」という概 念 も重 視 されつつ在 る。一 方 、業 務 システムのユーザビリティはこれまで軽 視 されてきた。その要 因 は情 報 システム部 、システムインテグレータ、エンドユーザそれぞれに由 来 する。しかし、業 務 システムで適 切 にユーザビリティに配 慮 すると作 業 効 率 が上 がりコスト削 減 につながる事 例 や、逆 にユーザビリティが悪 かったために大 きな事故 となってしまった事 例 は多 く、筆 者 らは業 務 システムに対 してもユーザビリティを配 慮 すべきと考 えている。
このような背 景 のもと、筆 者 らは業 務 システム向 けのユーザビリティチェックシート「UxDux」を開 発 したのでその概 要 を報 告 する。業 務 システムを対 象 としたユーザビリティ評 価 手 法 の研 究 はこれまであまり行 われていない。本 手 法では業 務 システムのユーザビリティを7つのカテゴリに分 け、評 価 対 象 システムの成 績 を「見 える化 」することができる。また、採 点 結 果 に応 じて改 善 方 法 の案 を提 示 することもできる。
本 手 法 を実 システムに適 用 した事 例 として、3事 例 を紹 介 する。設 計 段 階のシステムに適 用 した事 例 では、本 手 法 がユーザビリティ改 善 に有 効 であった。電 子 申 請 システムに適 用 した事 例 では、評 価 者 やカテゴリごとの評 価 結果 のばらつきを評 価 した。3つめの事 例 では、本 手 法 を用 いずにシステム改善 を行 ったシステムに対 し、改 善 前 後 に対 して本 手 法 でユーザビリティチェックを行 った。評 価 者 数 が少 なかったため統 計 的 に有 意 とはならなかったが、改 善 後 のシステムの方 が良 い評 価 となることが確 認 された。
現 在 は本 手 法 の有 効 性 を定 量 的 に示 すため、これまでよりも多 くの評 価者 によって評 価 を実 施 し、評 価 のばらつきに対 する対 応 策 を検 討 している。また、コスト削 減 や事 故 件 数 の減 少 など、ユーザビリティ改 善 効 果 の分 析 を進 める予 定 である。
2 保守 F3b チームに よる保守業 務改善の取 組み ~保守業 務
電 子 カルテや医 事 会 計 などの病 院 システムの保 守 業 務 において、これまでは各 顧 客 担 当 SEによる属 人 的 な対 応 が多 かったため、 (1)SE間 の作 業 負 荷 の偏 り、 (2)保 守 作 業 の品 質 ・進 捗 のバラつき、 (3)情 報 共 有 不 足 による保 守 サービスの品 質 低 下 ・作 業 効 率 低 下 などの問題 が起 きていた。
18
の『見え る化』~
これらの改 善 策 として保 守 業 務 の体 制 ・方 法 を根 本 的 に見 直 し、属 人 的対 応 からチーム対 応 への転 換 を図 った。その一 つの手 段 として、リモート接続 を最 大 限 に活 用 することとした。
このリモート保 守 改 善 の取 組 みにおいて3つの成 果 を得 ることができた。1点 目 はリモート保 守 による顧 客 システム監 視 を継 続 実 施 することが、予 防 保守 の1手 法 として確 立 できた。2点 目 はリモート接 続 記 録 ツールを新 たに開発 導 入 したことにより、作 業 状 況 の収 集 ・分 析 が容 易 になり、状 況 をデータとして可 視 化 (『見 える化 』)することが可 能 となった。3点 目 はプロジェクトウェブを活 用 した保 守 情 報 の共 有 化 により作 業 の標 準 化 ・効 率 化 を図 ることができた。
今 後 は、保 守 作 業 を通 じて得 られた情 報 を分 析 し、予 防 保 守 対 策 ・保 守実 績 報 告 等 を顧 客 に提 示 することで顧 客 満 足 度 の向 上 や保 守 契 約 交 渉に活 用 していく。
これらの取 組 みは、パッケージの種 類 や業 種 ・部 門 を問 わず、リモート保守 サービス全 般 の品 質 向 上 と作 業 効 率 化 に対 し役 立 つと考 える。
3 保守 F4b 仮想化技 術を活用し たシステム 保守効率化 施策の検討
現 在 、弊 社 にて運 用 しているAシステムは、日 立 グループ内 のシステム開発 をサポートする基 幹 システムである。年 々ユーザが増 加 しており、毎 月 1000を大 きく超 えるプロジェクトで適 用 され、毎 日 数 千 人 が利 用 している。この利 用 増 に対 応 するため、随 時 WEB/APサーバの増 設 を進 めており、現 在 、9台 のWEB/APサーバにて運 用 している。
本 システム運 用 においては、システム保 守 作 業 の実 施 を目 的 として、月 に1回 日 曜 日 を計 画 停 止 日 としている。この日 は、システムが全 面 停 止 するため、全 ユーザが利 用 停 止 となる。運 用 者 はこの1日 の中 で稼 動 中 に実 施 できない保 守 作 業 を実 施 する。
こうした中 で、多 くのユーザからは月 に1回 のシステム全 面 停 止 についても短 縮 できないかという要 望 が多 く寄 せられている。また、運 用 者 の中 でも休 日作 業 が必 須 となる状 況 が負 担 となっている。
そこで、システム保 守 の効 率 化 について検 討 を行 った。 最 近 では、仮 想 化 技 術 を本 番 環 境 に適 用 した事 例 を見 かける機 会 も多 く
なってきた。現 在 運 用 しているシステムにおいても、テスト環 境 作 成 においてはサーバ仮 想 化 によるメリットを享 受 しているが、本 番 環 境 においてはまだ有効 な活 用 手 段 を見 いだせていないのが現 状 であった。今 回 、仮 想 化 技 術 を用 いて、ユーザ視 点 、運 用 者 視 点 双 方 でメリットが見 込 めるように、保 守 作業 を効 率 化 する方 式 をまとめたので、紹 介 する。
4 その他 S1a 簡易な調 達先アセス メント方法 の提案 -共に成 長する改善 を目指して
リーマンショック以 降 、弊 社 ではコスト削 減 の観 点 から、開 発 に占 める外 部調 達 の割 合 が増 えている。このことは、調 達 先 の開 発 プロセスが製 品 の品 質へ及 ぼす影 響 が増 していることを意 味 している。近 年 、調 達 に関 する問 題 が散 見 され、製 品 の品 質 を維 持 するためにも、調 達 先 の開 発 プロセスの成 熟度 を把 握 すること、更 には調 達 先 の成 熟 度 を高 めていくことが重 要 になっている。
調 達 先 の開 発 プロセスを知 るには、プロセスのアセスメントをすることになるが、本 格 的 なアセスメントは準 備 から完 了 までにかかる期 間 も長 く、アセスメントする側 、される側 ともに大 きな負 荷 がかかる。
そこで、負 荷 を抑 えた、簡 易 に実 施 できるアセスメント方 法 を検 討 し、試 行した。アセスメントは、負 荷 を抑 えるため、調 査 項 目 の数 を絞 り、各 調 査 項 目も簡 単 なものにした。また、調 達 先 へのアンケートに1週 間 、現 地 ヒアリングに2時 間 、結 果 報 告 作 成 に1週 間 、その他 準 備 、日 程 調 整 を含 めて3週 間 ~1ヶ月 程 度 で完 了 できるような工 程 にした。
調 達 先 はソフト開 発 、ハード開 発 、ソフトウェアテストと多 岐 にわたることから、異 なる業 務 内 容 の調 達 先 に対 して、同 じ方 法 を用 いてアセスメントを実施 。試 行 の結 果 、以 下 のことが確 認 できた。 -調 達 先 のアセスメント結 果 と調 達 業 務 の質 を比 較 したところ、関 連 があるこ
とが分 かった、これにより、アセスメントにより調 達 先 のプロセスの評 価 が出来 ていることが確 認 できた
-期 間 は短 いもので1ヶ月 弱 、実 際 にかかった工 数 は15時 間 程 度 アセスメントにかかる負 荷 を最 小 限 に抑 えることができた
-ソフト、ハードを問 わず、同 じ方 法 でアセスメントを実 施 し、評 価 できることが分 かった 今 後 は、アセスメント方 法 の改 善 、結 果 の利 用 方 法 の検 討 を進 め、調 達
先 の開 発 プロセスと自 社 の調 達 プロセスを改 善 し、ひいては製 品 品 質 の向上 につなげて行 きたい。
5 要 求 工学
S1b 人間科学と工学のアプローチによる要求獲得
システム開 発 プロジェクトにおける「要 求 獲 得 の成 否 」は、後 続 の開 発 工程 に重 要 な影 響 を与 える。要 求 獲 得 段 階 において、現 場 の業 務 を的 確 に把 握 すること、現 場 の人 起 点 での行 動 や意 識 を理 解 することの重 要 性 が問われている。要 求 獲 得 は、「業 務 遂 行 の目 的 を達 成 するために、システムや
19
の質を上げるためのインタビュー手法の開発
それを使 う人 が現 状 どのように行 っているか、どうあるべきかのニーズの把 握 」と考 えられる。要 求 を獲 得 するためには、情 報 を受 け取 る側 も伝 える側 も明確 に”理 解 できるように表 現 される”必 要 がある。そのため、弊 社 のようなITベンダーでは、要 求 を「いかにして顧 客 視 点 で聞 き出 すか」が必 要 である。しかし、聞 くことは属 人 的 なスキルに依 存 しがちであり、聞 くことから得 られる情 報の精 度 、粒 度 や内 容 の厚 さに差 が出 てしまう(A Wolvin 1996)。そこで、本研 究 は誰 でも、インタビューからできるだけ質 の高 い顧 客 の現 状 や問 題 意 識など要 求 を獲 得 できるよう開 発 した「インタビュー・分 析 手 法 」を提 案 し、現 場での適 用 例 から、手 法 の効 果 を検 証 していく。 【開 発 したインタビュー・分 析 手 法 】
本 手 法 は、社 会 学 や人 類 学 において、自 身 とは異 なる文 化 背 景 における生 活 、慣 習 、文 化 をありのままに把 握 する「エスノグラフィー」と、「人 」を情 報処 理 の側 面 から、認 知 活 動 (知 覚 や記 憶 など)を予 測 し、解 析 する認 知 心理 学 の理 論 を組 み合 わせて、インタビューを体 系 化 したものである(エスノ・コグニティブインタビュー)。できるだけ語 る相 手 の観 点 や言 葉 を用 いて、人 、時 間 、空 間 など多 面 的 な切 り口 で現 状 行 動 や問 題 意 識 について、相 手 の業 務 などに精 通 していない人 でも、要 求 を獲 得 できるようにツールを準 備 することで、スムーズに聞 き出 しができる。1対 1のインタビューで、1名 あたり最 大1.5時 間 で1回 あたりのインタビューを完 結 できる。さらに、複 数 人 のインタビュー結 果 を体 系 的 に整 理 、分 析 し、要 求 の網 羅 性 と集 中 度 合 い、ストーリー性 等 を確 認 ・検 証 できるツールを提 案 する。 【本 手 法 の特 徴 】
本 インタビューの特 徴 として、 ・顧 客 の現 状 や要 求 を獲 得 し、分 析 できることを前 提 としたツール類 (聴 き方の作 法 、エスノコグニティブインタビューの考 えを埋 め込 んだ質 問 実 施 時 に使 う質 問 ワークシート、など)を整 備 し、インタビューを体 系 化 したこと ・できるだけ語 る人 には短 時 間 に記 憶 を想 起 しながら話 してもらえる、人 間 関係 軸 、空 間 軸 、時 間 軸 要 求 獲 得 に必 要 な仮 説 生 成 や検 証 が可 能 であることなどがあげられる。 【結 果 と考 察 】
本 インタビューで獲 得 した内 容 を現 場 での適 用 例 から抽 出 したノウハウをベースに、話 の時 制 と業 務 プロセス、ステークホルダーなどの視 点 で検 証 した。その結 果 聞 き漏 れや解 釈 のずれを防 止 するだけではなく、予 め質 問 文 を提 示 するインタビューでは獲 得 できなかった、要 求 の背 景 やエピソードまで聞き出 せることがわかった。
6 開 発 手法
S1c 人が作る ソフト ~経験的 な開発手法 の実践事例~
ソフトウェア開 発 は本 質 的 に不 確 定 な状 況 を制 御 しながら顧 客 満 足 の度合 いを高 めてゆくという側 面 を持 つ。アジャイルと呼 ばれる開 発 手 法 群 には、ソフトウェア開 発 における経 験 的 なアプローチを支 援 するものが多 く含 まれるが、実 際 のプロジェクトに適 用 する手 順 が存 在 するわけではない。
本 論 文 では、コンシューマ向 けのWebシステム(オンラインストレージサービス)を開 発 した事 例 の紹 介 を通 して、経 験 的 アプローチでプロジェクトを推 進する際 に重 要 となる点 について述 べる。
7 ソ フ トウ ェ ア品質
S1d プロジェ クト環境を 考慮した設 計品質評価 手法につい ての考察
下 流 工 程 (テスト段 階 )の品 質 評 価 方 法 は,過 去 の実 績 と経 験 から評 価 手法 としてプロセスが確 立 されつつある.しかし,低 コストでより良 い品 質 のシステムを提 供 するためには,より上 流 工 程 からの品 質 確 保 が必 要 である.しかし,下 流 工 程 のテストによる検 出 障 害 をベースとした品 質 評 価 手 法 を単 純 に上 流 工 程 に適 用 しても,お客 様 との関 係 やメンバのスキルなどプロジェクトの環 境 に左 右 される要 因 が下 流 工 程 に比 べ大 きく,データの確 度 に懸 念 があり適 切 な品 質 評 価 を行 うことが難 しい.本 稿 ではプロジェクトの環 境 や特 性に着 目 した設 計 品 質 の評 価 方 法 について,プロジェクトの環 境 条 件 を定 量化 した評 価 手 法 について提 言 し,適 用 結 果 について考 察 する. 【目 次 】 1. 問 題 提 起 (はじめに) 2. 品 質 評 価 の現 状 -レビューとテストの違 い -フェーズと要 求 の安 定 度 の関 係 -プロジェクト成 果 物 に影 響 を及 ぼす要 因 3. 設 計 品 質 評 価 のプロセスと課 題 4. プロジェクト環 境 を考 慮 した設 計 品 質 評 価 の提 案 5. 設 計 品 質 評 価 手 法 の確 立 アプローチ -アプローチの概 要 -設 計 品 質 評 価 手 法 の確 立 6. 設 計 品 質 評 価 手 法 の評 価 -第 一 次 評 価 (完 了 プロジェクトでの適 用 ) -第 二 次 評 価 (進 行 プロジェクトでの適 用 )
20
7. 今 後 の課 題 (おわりに)
8 ソ フ トウ ェ ア品質
S1f 知的技術 の形式化に よる、 SI開発業務の品 質改善につ いて
1.背 景 NECシステムテクノロジーは、首 都 圏 及 び関 西 圏 を中 心 としたSI開 発 事
業 と製 品 開 発 事 業 があり、私 が所 属 する組 織 はSI開 発 事 業 を担 当 している。その中 で、私 は30名 のグループに在 籍 し、Javaを主 要 言 語 としたお客様 システムの開 発 業 務 を担 当 している。本 稿 は、SI開 発 事 業 を通 じ、開 発業 務 での品 質 改 善 に向 けた取 組 みと成 果 について発 表 する。 2.課 題
当 グループは、複 数 のお客 様 システムを同 時 期 に、別 々の地 域 にて開 発しているが、いづれも低 価 格 ・短 納 期 ・高 品 質 のシステム開 発 を行 わなければならない。しかし、生 産 性 /品 質 面 に於 いて、開 発 者 によりバラ付 きが発生 し、特 に品 質 面 では、結 合 /総 合 テスト工 程 にて「単 体 テストにて改 修 されるべきバグ」が発 生 し、予 定 原 価 を超 過 する状 況 であった。
このような状 況 下 、「人 の課 題 」は、開 発 者 の生 産 性 と品 質 面 での底 上 げと新 規 参 入 メンバのスムースな立 上 げであり、「物 の課 題 」は、開 発 を支 援 するツールを使 いたがらないメンバが存 在 していた。しかし、優 秀 な開 発 者 ほど、独 自 にOSS等 を調 査 し、日 々改 善 し、ツール活 用 が当 たり前 と考 えていた。「金 の課 題 」は、開 発 予 算 がいづれも厳 しく、開 発 を支 援 するツールを購入 することは難 しい状 況 であり、「情 報 の課 題 」でもあるが、OSS/技 術 情 報等 はインターネット上 に乱 立 され、知 らない情 報 は多 数 あり、同 一 のお客 様システム開 発 者 間 の共 有 は行 えても、他 のシステム開 発 メンバとの地 域 を跨がった共 有 の難 しさがあった。 3.対 策 と施 策
投 資 費 用 を抑 制 し、効 率 的 に要 員 育 成 を行 う対 策 として、優 秀 な開 発 者の開 発 プロセスや活 用 ツール、技 術 情 報 等 を形 式 化 し、グループの標 準 開発 基 盤 を整 備 ・徹 底 活 用 とした。
「物 の課 題 に対 する施 策 」として、OSSの活 用 方 法 や活 用 シーン等 を整備 し、経 験 の浅 い開 発 者 でも活 用 できるようにガイド整 備 と勉 強 会 を開 催し、要 員 育 成 と活 用 徹 底 を図 った。
「情 報 の課 題 に対 する施 策 」として、優 秀 な開 発 者 が日 々アクセスしているサイトやOSS/トラブル情 報 等 が掲 載 されているサイト情 報 を整 理 し、グループ共 有 技 術 サイトを構 築 した。 4.成 果 と適 用 効 果
Java開 発 に於 ける品 質 改 善 とSI開 発 業 務 毎 の費 用 負 担 ゼロを狙 い、OSS/内 製 にて構 成 した開 発 支 援 ツール群 (機 能 数 :10)を整 備 し、200プロジェクトに展 開 した。適 用 効 果 は適 用 プロジェクト平 均 、以 下 の品 質 改 善が図 れ、予 定 原 価 を超 過 するケースは低 減 した。
(1)単 体 テスト後 の移 行 判 定 バグ数 が、KL当 たり0.4件 改 善 (2)システムダウンに繋 がるバグを単 体 テスト完 了 時 点 にて10件 以 上 摘 出(3)開 発 環 境 がなくても品 質 状 況 が確 認 でき、管 理 者 視 点 でのチェック
が、いつでも可 能 。 5.まとめ
開 発 者 個 々の頭 にある技 術 を形 式 化 し、徹 底 活 用 することにより、各 SI開 発 案 件 の 品 質 改 善 が 図 れ た こ と は 大 き な 成 果 である が、 そ れ 以 上 に、『個 々の技 術 を結 集 し、開 発 プロセスを強 化 し続 けることが重 要 』と共 通 認識 でき、開 発 者 の意 識 改 革 が行 えたことが成 果 である。
今 後 、OSS継 続 調 査 と既 存 環 境 への組 込 、他 開 発 工 程 /他 言 語 への展 開 が重 要 と考 える。
9 ソ フ トウ ェ ア品質
S2b 派生開発 における要 求仕様書の 品質向上活動
当 社 では、20年 近 く組 込 みソフトウェア開 発 を行 ってきているが、かなりの部 分 が派 生 開 発 といって良 い。派 生 開 発 での要 求 開 発 は、2000年 の前 半に導 入 したUSDMという要 求 仕 様 の書 き方 をベースにしているが、10年 が経過 した現 在 でも当 社 の派 生 開 発 プロジェクトでは、未 だに品 質 やコスト超 過の問 題 を起 こしている。このため、派 生 開 発 プロジェクトにおいて何 が原 因 となって品 質 や生 産 性 の悪 化 につながっているのかを調 査 し始 めた。調 査 の結 果 、開 発 工 程 の上 流 で行 われる要 求 開 発 や設 計 において実 施 するレビューが思 うような効 果 を生 んでいないことが分 かってきた。これは要 求 開 発 で作 成 される要 求 仕 様 書 が、日 本 語 の文 章 として要 求 や仕 様 を記 述 しているため、レビューの方 法 やレビューアーのスキルによっては、要 求 仕 様 書 の記述 に存 在 する欠 陥 をうまく除 去 することができないためではないかと思 われた。
本 発 表 では、要 求 仕 様 書 の品 質 とは何 かを定 義 した上 で、要 求 仕 様 書の品 質 向 上 施 策 を以 下 のように決 定 し実 施 した。 1.あいまいな文 章 の排 除 の実 施
要 求 仕 様 書 に記 述 される日 本 語 のあいまい性 を排 除 するために、文 章 を
21
チェックするツールを導 入 してレビューの前 に要 求 仕 様 書 をチェックするようにした。これにより要 求 仕 様 書 のレビューでは要 求 や仕 様 の本 質 についてレビューできるようにした。 2.トレーサビリティリンクを使 った要 求 仕 様 書 レビューの実 施
派 生 開 発 の元 になっている仕 様 書 や設 計 書 などを読 んで、変 更 の仕 様が元 の仕 様 のどこに相 当 するのかを調 べる際 に、日 本 語 の文 章 の類 似 度 を使 って記 述 場 所 を検 索 できるツールを導 入 した。この検 索 した結 果 をトレーサビリティリンクとして保 存 することにより、要 求 仕 様 書 のレビューに利 用 して要 求 の漏 れ・抜 け・矛 盾 ・ダブりを効 果 的 に検 出 していくようにした。 3.要 求 管 理 の実 施
Excelの要 求 仕 様 書 は、作 成 者 によっては日 本 語 の文 章 の代 わりとして画 像 を埋 め込 んだり、要 求 番 号 を文 章 に埋 め込 んだりして要 求 仕 様 を作 成している。このため、要 求 仕 様 を文 書 として作 成 するのではなく、要 求 仕 様 の要 素 として管 理 するために、管 理 ツールを導 入 した。
これらの施 策 を実 施 した結 果 、要 求 仕 様 書 のレビューにおいて欠 陥 除 去率 が向 上 し、設 計 工 程 の生 産 性 が向 上 した。今 後 は、これらの施 策 を実 施しているプロジェクトの終 了 を待 って、プロジェクト全 体 の品 質 や生 産 性 がどう変 化 したのかを分 析 することにする。
10 ソ フ トウ ェ アメ ト リクス
S2c COSMIC 法に 基 づ くForce.com開発プロ ジェクトの 生産性分析 結果
本 発 表 では、まず、これまでの研 究 で行 ってきたCOSMIC法 に基 づくプロジェクトの生 産 性 分 析 手 法 について述 べる。この中 では、データの移 動 に基づいて機 能 規 模 を測 定 する手 法 であるCOSMIC法 の概 要 を紹 介 するとともに、プロジェクトの生 産 性 に影 響 を与 える要 因 について述 べる。さらに、そのようなプロジェクトの生 産 性 に影 響 を与 える要 因 が実 際 に生 産 性 に影 響 を与えるかどうかを確 かめるために、開 発 に要 した労 力 を機 能 部 分 と作 業 種 別 の2つの観 点 で分 類 して記 録 している点 について述 べる。つぎに、実 開 発 プロジェクトを測 定 した結 果 をもとに画 面 機 能 の生 産 性 や労 力 などの測 定 分 析値 を比 較 し、画 面 生 産 性 に影 響 を与 えた要 因 を分 析 する。
今 回 、測 定 分 析 結 果 を紹 介 するのはForce.comで開 発 を行 った2つのプロジェクトである。この2つのプロジェクトは開 発 期 間 が2.5カ月 、開 発 要 員 が2名 という短 期 間 少 人 数 開 発 であった。これらのプロジェクトの画 面 生 産 性 を、過 去 に測 定 した他 のプロジェクトの画 面 生 産 性 と比 較 し、さらに開 発 に要 した作 業 時 間 や機 能 毎 の分 析 値 の比 較 を行 って、画 面 生 産 性 に影 響 を与 えた要 因 を分 析 した。
その結 果 、Force.com開 発 プロジェクトは他 のプロジェクトより画 面 生 産 性が高 いことが分 かった。また、Force.comで開 発 した画 面 の生 産 性 は画 面 の処 理 形 式 (マスタ管 理 系 、参 照 系 、更 新 系 )によってバラつき、さらに類 似 機能 の開 発 経 験 やForce.com開 発 の習 熟 度 が生 産 性 に大 きく影 響 することが分 かった。そして、更 新 系 画 面 の生 産 性 は画 面 部 品 の連 動 や画 面 連 携 など作 り込 みの度 合 いによってバラつく事 が分 かった。
これらの測 定 分 析 結 果 から、Force.com開 発 の画 面 生 産 性 が高 い要 因は以 下 であると考 える。 ・フレームワークとサービス Force.comを利 用 した画 面 開 発 方 法 によって実 装 が効 率 化 した Force.comアーキテクチャを利 用 によって設 計 労 力 が減 少 した ・類 似 機 能 の開 発 経 験 と習 熟 度
類 似 機 能 の開 発 経 験 があったり、Force.com画 面 開 発 に慣 れることで開発 が効 率 化 したまた、以 下 の要 因 が画 面 生 産 性 に影 響 を与 えたことが分 かった。 ・画 面 の処 理 形 式 に関 わる作 り込 み度 ・類 似 機 能 の開 発 経 験 ・習 熟 度
11 プ ロ セス改善
S3a トレーニ ング指向ア プローチに よるプロセ ス改善 -現場の キーパーソ ンを 育 て る「 現 場SQA」 方 式-
デンソークリエイトでは、2006年 より「トレーニング指 向 アプローチによるプロセス改 善 」に取 り組 んできた(SPES2007~2010で発 表 )。本 稿 では、その中核 に置 いている「現 場 密 着 型 ・支 援 型 SQA」の仕 組 みと、その機 能 によって現 場 のキーマンを確 実 に育 てる「現 場 SQA」方 式 とその効 果 について発 表する。 (1)背 景 1996年 頃 よりソフトウェア業 界 の先 駆 けとなり、優 秀 なプロ集 団 となるべくしてトップダウンで始 まったプロセス改 善 は、厳 格 なプロセス定 義 とその遵 守 を強いるあまり、「やらされ感 」のもと、形 式 的 ・表 面 的 な活 動 になり、現 場 は疲 弊していた。同 じ失 敗 を繰 り返 さない思 いで活 動 する中 で、プロセス改 善 の本質 が人 を育 てることであると気 づき「トレーニング指 向 アプローチ」と名 付 けた仕 組 みを構 築 してきた。日 々の仕 事 の中 で人 を育 てるためには、現 場 目 線を持 ち、現 場 のための支 援 を行 うことがポイントと考 え、一 般 的 なSQA機 能 より幅 を広 げた現 場 密 着 型 ・支 援 型 SQAを考 案 した。
22
(2)失 敗 させないための仕 組 み 過 去 の失 敗 の大 きな要 因 の1つは、表 面 的 ・官 僚 的 なプロセス遵 守 の強 要であると考 えた。現 場 は、活 動 や改 善 推 進 チームに対 する不 信 感 や誤 解 でいっぱいになっていた。それを打 開 し、現 場 のためになり、現 場 が嬉 しい改 善活 動 にしていくために、信 頼 される改 善 推 進 チームに変 えることを考 えた。
これまでの失 敗 を踏 まえて、信 頼 される改 善 推 進 チームに必 要 な要 件 は「現 場 の本 当 の事 実 を知 り」、「現 場 と一 緒 に汗 をかき」、「高 い視 点 で足 は地 に置 いた判 断 ができる」ことであると考 えた。それを実 現 する組 織 として、それらの要 件 を満 たす三 層 構 造 から成 る「現 場 密 着 型 ・支 援 型 SQA」を構 築した。 (3)課 題
SQAの構 造 は決 まったが、三 層 構 造 の1つである、現 場 のPMに密 着 して支 援 をする機 能 (2次 SQA)に必 要 な人 材 確 保 の目 処 が立 たなかった。信 頼されるSQAとなるには、現 場 が”認 める人 ”つまり”優 秀 な人 ”である必 要 がある。しかし、適 任 となる”優 秀 な人 ”は少 なく、かつ、現 場 でも手 放 せない人 ばかりである。現 場 のためのSQAを機 能 させるためには、現 場 から”優 秀 な人 ”をSQAに持 ってくる必 要 がある。しかし、”優 秀 な人 ”を抜 いてしまうと、現 場が回 らなくなる。現 場 のためにと言 って”優 秀 な人 ”をSQAに集 めることが、逆に現 場 の不 満 となるのではないか。そのような矛 盾 が想 像 され、葛 藤 し、2次SQAの人 材 確 保 に悩 んでいた。 (4)優 秀 な人 を育 てる
”優 秀 な人 ”が少 ないからSQAの数 になるし、SQAに持 ってくるにしても対象 者 が少 ない。”優 秀 な人 ”が多 ければ解 消 するはずなので、なぜ少 ないのかを考 えてみたところ、若 い時 に”優 秀 ”として期 待 されていた人 が、期 待 通 りには育 っていないことが少 なくないことが分 かった。若 い時 の優 秀 は、技 術 的な側 面 が強 く、技 術 力 があるが故 に、担 当 範 囲 内 ではマネジメント力 もあるように見 えてしまう。しかし、PMになると技 術 的 に経 験 したことがない範 囲 も見 ることになり、技 術 的 知 識 や経 験 ではカバーしきれない本 来 のマネジメント力 の真 価 が問 われることとなり、突 然 破 綻 しやすいことが分 かってきた。また、本人 も回 りも”できる”と思 ってしまうため、自 ら学 ぶことも怠 り、周 りも指 導 しない。優 秀 な故 に、学 ぶ機 会 を逸 してしまっているのではないかと考 えた。そこで、現 場 にいながらSQAを経 験 することにより、PMとしての業 務 を疑 似 体 験し、スキルを身 につける「現 場 SQA方 式 」を考 案 した。「現 場 SQA方 式 」はPMとしての疑 似 体 験 だけでなく、視 点 の変 化 や担 当 業 務 との兼 務 という制 約 の中 で活 動 することにより、更 にマネジメント力 をのばせる有 効 な方 式 であることにも気 づいた。
「現 場 SQA方 式 」は、現 場 SQA担 当 者 にとっては優 秀 に育 ち、SQAにとっては優 秀 な人 材 が確 保 できて現 場 の支 援 ができるだけではなく、現 場 の上司 にとっても、自 分 の配 下 に置 きながら優 秀 な人 を育 てることができる、という三 者 にとって嬉 しい「一 石 三 鳥 」の仕 組 みとなった。 (5)効 果 の確 認
全 PMに対 して実 施 する内 部 アセスメントではモデルに基 づき診 断 することによりPMやプロジェクトの水 準 を定 量 化 できる。PMになる前 に現 場 SQAを経験 したメンバは、PMになった時 に、同 時 期 にPMになった他 のメンバと比 較 すると高 い水 準 を得 られた。また、本 人 も感 覚 でも有 効 性 が示 されている。また、現 場 SQA方 式 の運 用 当 初 と比 較 すると、課 題 ・問 題 を抱 えるPMの割 合が10%減 少 すると共 に優 秀 なPMは倍 増 し、全 体 の半 数 になった。
12 要 求 工学
S3b 要件定義 の生産性を 向上させる ための最適 化への取り 組み
要 件 定 義 においては,要 求 獲 得 ,要 求 記 述 ,要 求 検 証 ,要 求 管 理 のプロセスで構 成 され,さまざまな研 究 成 果 が提 供 されている[1].例 えば,変 更要 求 を意 識 した要 求 獲 得 計 画 の立 案 に対 しては,要 求 の成 熟 度 に着 目 したPRINCEモデルが提 案 され,要 求 獲 得 計 画 の立 案 に貢 献 しつつある[2].
著 者 の所 属 する組 織 においても,PRINCEモデルを用 いて,要 件 定 義 をスムーズに行 うことに取 り組 んでいる.しかしながら,発 注 者 からの要 望 を可 視化 しステークホルダ間 で合 意 を得 る要 件 確 定 プロセスにおいて,次 のような課 題 に直 面 した. (1) 要 望 の起 票 方 法 が属 人 的 であり要 望 の理 解 ・確 認 にコスト発 生 (2) 要 件 化 の方 法 が属 人 的 であり,重 要 な要 望 と、運 用 でカバーできる単 純な要 望 の区 別 なし (3) 要 件 の定 義 時 期 が特 定 時 期 に集 中 し作 業 効 率 が悪 化
そこで,上 記 課 題 の解 決 のために,PRINCEモデルが提 供 する要 求 の分類 とそれに基 づく優 先 度 決 定 ルールを用 いることで,要 件 定 義 プロセスを最適 化 する手 法 の開 発 と適 用 を試 みた.(1)の課 題 に対 しては,要 望 の仕 様記 述 基 準 を定 義 した.(2)の課 題 の解 決 には,PRINCEモデルが提 供 する要求 の分 類 に基 づき,優 先 度 ルールを定 義 した.そして,(1)と(2)の課 題 の対策 に基 づき要 件 定 義 の業 務 フローを可 視 化 し,関 係 者 に徹 底 することで(3)
23
の課 題 に対 応 することを考 案 した. 上 述 した解 決 策 を実 システム開 発 に適 用 した.本 解 決 策 の実 施 後 ,要 件
確 定 のリードタイムを平 均 1.15日 に,要 件 確 定 のコストを従 来 より80%削 減することができた.リードタイム短 縮 および要 件 確 定 コスト削 減 を実 現 できたことから,考 案 した手 法 は有 用 であることを明 らかにした.今 回 は要 求 の抽 出数 と時 期 を観 測 し,優 先 度 を決 定 するための,共 通 のものさしとして,すでに実 績 のあるPRINCEモデルを活 用 した.考 案 した手 法 は,あらゆるシステム開発 でも汎 用 的 に適 用 と考 えられ,知 識 継 承 にも貢 献 できる.今 後 は,複 数 のシステムでの観 測 を通 してデータを蓄 積 し,本 手 法 を継 続 的 に改 善 していく.
13 ア ジ ャイル
S3c オフショ ア開発にお けるアジャ イル開発の プラクティス
本 発 表 は、オフショア開 発 にアジャイル開 発 のプラクティスを導 入 する事例 について紹 介 する。
コスト削 減 を狙 い、製 造 業 の工 場 を人 件 費 の低 い地 域 に移 転 するのと同じ考 えで開 始 した日 本 のソフトウエア業 界 におけるオフショア開 発 は、すでに20年 以 上 の歴 史 がある。これを実 践 する多 くの企 業 で20%~30%のコスト削減 (※1)を実 現 している一 方 、言 葉 、文 化 、地 理 、組 織 構 造 の違 いによって、オフショア開 発 の現 場 は多 数 の課 題 を抱 えている。(※2)しかしながら、日 本 のソフトウェア業 界 は少 子 化 や高 齢 化 による人 材 不 足 に直 面 する中 、開 発 リソース確 保 のため、またグローバルな事 業 展 開 するためにも、各 ソフトウェア企 業 におけるオフショア開 発 のさらなる推 進 は不 可 避 と考 えられる。
アジャイル開 発 は90年 代 後 半 から米 国 で適 用 され始 めた。現 在 では、欧米 の多 くの企 業 のソフトウェア開 発 の現 場 で適 用 されている。(※3)アジャイル開 発 によって、反 復 開 発 による完 成 品 の市 場 投 入 の早 期 化 や仕 様 変 更への機 敏 な対 応 などがもたらされる。また、人 材 面 では、チームの自 己 管 理によって、生 産 性 や品 質 の向 上 が期 待 できる。
オフショア開 発 とアジャイル開 発 の組 み合 わせについては、米 国 -インド間 のオフショア開 発 ではすでに多 くの事 例 がある。(※4)しかし、日 本 のソフトウエア開 発 業 界 では、アジャイル開 発 の適 用 は小 規 模 案 件 とどまる傾 向 があり、大 規 模 案 件 への適 用 はまだまだ進 んでいない。これは日 本 のソフトウエア会 社 の組 織 の体 質 や多 階 層 の請 負 契 約 による開 発 体 制 といった業 界 の慣 行 に、アジャイル開 発 が前 提 とする開 発 のやり方 がなじみにくいことに原 因があると考 えられる。
オージス総 研 は2007年 10月 に、日 中 合 弁 の形 で上 海 欧 計 斯 軟 件 有 限公 司 (SOT)を設 立 し、上 海 にオフショア開 発 拠 点 を持 つに至 った。SOTでは、パッケージ開 発 と顧 客 の社 内 情 報 システム開 発 という2種 類 の受 託 開 発を行 っている。
情 報 システム開 発 に関 しては、日 本 で上 流 設 計 を行 い、中 国 に詳 細 設計 ~結 合 テストの工 程 を発 注 、日 本 で成 果 物 を受 け入 れシステムテストを実施 するという典 型 的 なオフショア開 発 である。
パッケージ開 発 に関 しては、SOTでSES契 約 、情 報 システム開 発 と同 じ一括 契 約 などのさまざまな受 託 形 態 を試 みた。しかし、いずれも日 本 側 での受け入 れ時 の検 査 で発 見 される問 題 が多 かった。しかも、日 本 側 が発 見 した問 題 に関 してSOTとの間 で責 任 の帰 属 をめぐって合 意 することが難 しいこともたびたびあり、問 題 に対 する修 正 作 業 がはかどらないこともあった。
こうした課 題 を解 決 するため、SOTが担 当 するパッケージ開 発 ではアジャイル開 発 のプラクティスの導 入 を図 った。具 体 的 には要 求 を優 先 順 位 付 きの「チケット」と呼 ばれる単 位 での管 理 、反 復 開 発 、テスト駆 動 、アジャイルテストといったプラクティスを導 入 した。また、コミュニケーションツールを複 数 活 用しながら、チームの自 主 性 を尊 重 する工 夫 することで、一 般 的 なオフショア開発 にありがちな「受 け身 の態 度 」即 ち指 示 を末 だけで、言 われたこと以 外 のことはやらない傾 向 を排 除 した。
これらのアジャイル開 発 のプラクティスの導 入 を経 て、チームの一 体 感 向上 、人 員 の定 着 率 向 上 、パッケージの品 質 向 上 などの効 果 がもたらされた。
今 後 の取 り組 みとして、1)オフショア開 発 とアジャイル開 発 の相 乗 効 果 を定 量 化 、また、2)パッケージ開 発 のみではなく、毎 回 まったく異 なる仕 様 を扱う情 報 システム開 発 へのアジャイル開 発 のプラクティスの導 入 を予 定 している。