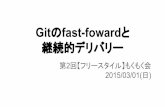先輩の知識・見識を吸収しませんか。先輩の体験を聴いてみ ... · 2020. 8. 3. · 先輩の知識・見識を吸収しませんか。先輩の体験を聴いてみませんか。先輩の失敗談を笑ってみませんか。
2015 - hiyaku.or.jp · 先ほど世代間継承の話をしました。仕事力の...
Transcript of 2015 - hiyaku.or.jp · 先ほど世代間継承の話をしました。仕事力の...

2015.3
滋賀県市町村職員研修センター 研修情報誌
「全職員必読!自治体における人材育成の意義」~一人ひとりにできること~
」「全職員必読!自治体における人材育成の意義「全職員必読!自治体における人材育成の意義」~一人ひとりにできること~
特集
「月曜日が待ち遠しい職場を作る!」~職場を変えるコミュニケーション術~
「全職員必読「全職員必読!!自治体における人材育成の自治体における人材育成の~~一人ひとりにできること~一人ひとりにできること~
特集
「月曜日が待ち遠しい職場を作る!」~職場を変えるコミュニケーション術~職場を変えるコミ ニケ シ ン術「月曜日が待ち遠しい職場を作る!」~職場を変えるコミュニケーション術~
特集

研修情報誌
2015.3 CONTENTS
全職員必読! 自治体における人材育成の意義~一人ひとりにできること~ 元東京都総務局長・東京都職員研修所長 押元 洋 1
特 集
月曜日が待ち遠しい職場を作る!~職場を変えるコミュニケーション術~ 株式会社ミュゼ 代表取締役 齋藤直美 10
特 集
紹介します、わがまちの研修 フォローアップ研修 〔愛荘町〕 8 5S活動&カイゼン研修 〔長浜市〕 9
リーダーの役割と心構え~JST講師を担って~ 湖南市人権擁護課 主幹 梶山政代 16
内部講師レポート
もし私が受講者なら、この研修に何を求めるか~公務員倫理講師を担って~ 日野町税務課 専門員 山口明一 17
原点に立ち戻ることの大切さ~新任職員(後期)研修を受講して~ 近江八幡市障がい福祉課 主事 福西翔平 18
受講者レポート
伝えることの難しさ~プレゼンテーション研修を受講して~ 豊郷町産業振興課 主事 角田成明 19
指導者養成は一挙両得!~クレーム対応指導者養成研修を受講して~ 守山市国保年金課 主査 川尻みゆき 20
チーム ガリバーの6ヶ月~政策課題研究を受講して~ 米原市伊吹自治振興課 主査 堀 正彦 21
研修講師、誕生! 22
平成27年度 おススメ研修 23

特集全職員必読! 自治体における人材育成の意義
行政を支えてきた無名の職員たちと世代間継承
今日は、皆さんがよくご存じの安土城の話から始めます。イエズス会宣教師のルイス・フロイスは、その著書「日本史」に、こう書いたそうです。「(安土城には)彼らがテンシュと呼ぶ一種の塔があり、私たちの塔より気品があり壮大な建築である」。この城を築いた織田信長に思いを馳せると「近江を制するものは、天下を制する」という言葉が実感として迫ってきますね。今「信長が城を築いた」と言いました。でも、実際に現場で汗を流したのは大工や左官、石工、絵師といった職人たちです。信長は日本史のスーパースターですが、職人たちの名前は歴史には残っていません。想像の域を出ませんが、彼らは、歴史に自分の名前が残るかどうかなどとは考えず、よい仕事を残そうという職人としての誇りをかけてひたむきに働いたのではないでしょうか。そうでなければフロイスが書き残したような壮麗な城が完成するはずはないと思います。 自治体行政に携わる職員も、この職人たちと同じではないでしょうか。職員は、名もなく、感謝もされず、ただ粛々と住民のために働いてきた。その人たちの名前は残っていません。それは、行政に匿名性という性質があるためで、職員は無名だからです。さらに言えば、行政は、資源の最適な配分をめざして永遠に続く調整です。だから行政に終わりはない。無名の公務員が、住民のために奉仕することに情熱を燃やし、よい仕事を残そうと誇りをもって、ひたすら終
わりなき調整に携わってきた。その結晶として、地域に住民福祉という花が咲き、実を結んでいる。後輩は、先輩から仕事を引き継ぎ、それに自分なりの何かを加えて、「より豊かな実りを」という願いを込めて次の世代に引き継ぐ。今、皆さんが携わっている行政は、こうした先輩たち、いわば先人の営々とした努力の積み重ねの上にあるわけです。 先輩から後輩へと仕事が引き継がれる際には、公務に関する知識やスキル、職場で経験と勘に基づいて蓄積されてきた暗黙知、公務員としての心構えなども一緒に引き継がれ、そういったものが職員を支えてきました。そして、こうした継承が繰り返されて今日に至っている。これを「世代間継承」と呼びますが、私は「人材育成とは世代間継承」であると考えています。すなわち、自治体における人材育成の意義は、世代間継承によって行政を持続可能にすることにあるのです。
世代間継承はいま
今、世代間継承はどのようになっているのでしょうか。自治体関係者から「職員が普通にできていたことが最近はできなくなった」という話をよく聞くようになりました。仕事力が落ちてきたので研修で何とかならないかと言うのです。話をまとめると、次のような実態が浮かび上がってきます。● 仕事の基本を心得ていれば間違えることはないはずの起案ミスや手続きの誤りが頻繁に見られるようになった。
全職員必読!自治体における人材育成の意義~一人ひとりにできること~
元東京都総務局長・東京都職員研修所長 押 元 洋(平成26年度OJT指導者研究会「効果的な職場研修の進め方」講師)
特集
1

特集 全職員必読! 自治体における人材育成の意義
● 資料作成を指示したが、見事にツボを外したうえに簡潔明瞭とはほど遠い仕上がりだった。
● 説明や交渉・折衝に行かせたが、かえって問題をこじらせてしまい、後始末に追われた。
● 急を要する事態なのに、職員が「指示待ち」状態で自発的に動かない。以前はどの部署にも「鬼軍曹」のような頼りになる職員がいて、こうしたことはなかった気がする。
● 現場で新たな課題が次々に生じているのに、きちんと対応できていない。筋道を立てて考えれば解決できるようなことでも、戸惑ってしまい、「どうしましょうか」と聞いてくる。
ご紹介した事例はごく一部ですが、「あるある」とうなずく方が多いのではないでしょうか。ある研修で受講者から「それは、昔はよかったという話ではないか」と切り返されましたが、そうではありません。私が出講させていただいた自治体は、ほぼ例外なくこうした問題に悩んでいました。実は、これは私自身の経験でもあるのです。おおざっぱな印象では、21世紀に入ってから次第にこういう状況が目立ってきたように思います。仕事をこなす力、いわば仕事力が
低下してきている実態が確かにあると感じています。 先ほど世代間継承の話をしました。仕事力の源泉は、先輩から後輩へ引き継がれた公務の知識やスキル、職員としての心構え、さらには文書化されていない「経験と勘に基づく職場の暗黙知」といったものです。仕事力が低下している原因は、この世代間継承がうまくいっていないことにあるのではないでしょうか。人材育成が危うくなっているということです。 世代間継承がうまく働かないのは、後輩を指導する上司や先輩の側に「後進を育てる姿勢」が薄れてきたことに原因があると思えてなりません。かつて「世代の断絶」という言葉が流行し、新人を指して「宇宙人」とか「新人類」と言った時代もありました。若い世代とコミュニケーションをとることの難しさを嘆く声は、今も絶えないようです。思うに、このコミュニケーションの困難さを言い訳にして後進に対する指導がおろそかになっている面があるのではないでしょうか。最近のことですが、「職場で新人を指導したら当人から『上から目線だ』とクレー
2

特集全職員必読! 自治体における人材育成の意義
ムをつけられたので、もう指導はやめます」という係長さんの話を聞きました。それでは人材が育たず、行政の持続可能性が危うくなります。先人が積み重ねてきた成果が失われるばかりか、現役世代の努力も泡と消えてしまう。何とか世代間継承の再生を図らなければなりません。
世代間継承を再生する
では、世代間継承を再生するにはどうしたらよいか。後進を指導する立場にある皆さんは、どのように職業人として、言い換えれば職員として成長してきたのでしょうか。採用から今日までの歩みを振り返ってみてください。 自分が職員として「一皮むけた」と感じたのは、誰の下で、何の仕事をしていた時のことですか。上司や先輩は、皆さんをどのように育ててくれましたか。皆さんも先輩や上司の指導を受けて成長してきたのではありませんか。上司や先輩の助けを借りつつ難しい仕事を成し遂げた時、自分が「一皮むけた」とか「ワンステップ成長した」などと実感したのではありませんか。 上司や先輩の立場から言うと、後輩を「育みながら面倒をみてきた」わけです。これは伝統芸能の世界などで師匠が弟子を育てるのに似ています。かつて上司や先輩が指導してくれたように、今は皆さんが部下や後輩を指導する番です。育みながら次の世代の面倒をみるのは上司や先輩の役割なのです。これは人材コンサルタントや研修請負業者にはできないことです。皆さんは、後進をしっかり育成する役目を負っていることを理解してください。それが世代間継承を再生する鍵になるのです。
仕事を通じた人材育成の大切さ
皆さんは、「経験7割、薫くん
陶とう
2割、研修1割」という言葉をご存じですか。アメリカの話ですが、経営幹部としてリーダーシップをうまく発揮できるようになった人たちに「どのような出来事が役立ったか」と聞いたところ、「70%が
経験、20%が薫陶、10%が研修」という結果が出たといいます。ここから、職業人として成長するには良質な仕事経験と上司や先輩から受ける指導や薫陶が大切であるという結論が導かれました。仕事経験と上司などから受ける薫陶が職業人としての成長に大切であるというわけです。7割、2割という数字はともかく、自分の経験に照らしても、私は的を射ている説だと思います。先ほど皆さんに自らの職員としての成長過程を振り返っていただきましたが、ご自身の歩みからも、こうした考えに共感していただけるのではないでしょうか。 上司や先輩が職員に仕事を与え、その仕事をなし遂げる過程で指導を行い、あるいは薫陶を及ぼすことによって成長を促す。これは、先ほど述べた世代間継承であり、人材育成の要です。そして、もうお気づきかもしれませんが、職場研修そのものでもあります。人材育成の基本は、仕事を通じて行う職場研修であり、その際に受ける上司や先輩からの指導や薫陶が成長に欠かすことができないのです。仕事の中身が急激に変化している時代にあっては職場研修は役に立たないという意見もあります。しかし、仕事力の低下という実態に照らすと、公務職場の仕事は基本的には変わらず、職場研修の重要性はゆるがないものと考えます。
人材育成のための基本的な姿勢
職場で人材育成を進める際の姿勢について三点お話します。 第一に、あなた自身が部下や後輩の職業人としての成長に強い関心があり、成長を強く期待しているという姿勢を日常的に示す必要があります。例えば、仕事を進める際に本人が手応えを感じられるよう声をかけるとか、一歩一歩着実に前進しているのだという気分を職員が感じられるよう前向きな評価をする。仕事の進捗に応じて「内容がだいぶよくなってきた」と感想を述べたり、褒めたりする。あるいは、行き詰
3

特集 全職員必読! 自治体における人材育成の意義
まっていたら「こういった視点を取り入れてはどうか」と助言するなどです。 第二に、職員の発達段階に応じて良質な仕事経験を与えることです。本人の実力を把握しつつ、少しずつハードルを上げ、難しい仕事をさせる。仕事を成し遂げる過程で必要な助言をし、指導を行います。 第三に、折に触れて、仕事に対するあなたの「思い」や「志」を部下や後輩に語ることです。先ほど言った「薫陶2割」の薫陶です。自分は薫陶を与えるほどの人物ではないと謙遜する人がいますが、別に偉そうなことを語れというのではなく、どういう思いで今の仕事に携わっているかを現場へ向かう途中などで話せばよいのです。上司や先輩の考えていることを部下や後輩が理解していなければ、組織目標の達成は覚束ないでしょう。この際、「上から目線」などという批判は忘れることです。ただ、相手が受け入れやすいように、言い方は工夫してください。
成長する組織風土づくり
組織のリーダーは、人材育成の土壌づくりをしなければなりません。「成長する組織」とは、職員の成長はもとより、結果として組織そのものも成長していくというイメージです。 成長する組織風土づくりにまず必要なのは、先ほども述べましたが、組織のリーダーがメンバーの人材育成に強い関心を持っており、職員としての成長を心から期待しているのだという姿勢を日常的に示すことです。要するに、「上司(リーダー)は自分の成長に強い関心を持ってくれている」と組織メンバーに感じてもらうわけです。 そして、リーダーは「アンテナを常に高く広く掲げて仕事に関する情報を熱心に集めており、その分析に余念がない」という姿を職員に見せることが大切です。庁内情報はもとより、自分が読んだ資料などのポイントや、そこから得ら
れるものの見方や考え方を折に触れて伝えていきます。リーダーが仕事に関して熱心に勉強している姿を職員に見せるわけです。逆に、リーダーがちっとも勉強しないのでは、職員からのリスペクトが得られないばかりでなく、人材育成も組織目標の達成もうまくいきません。 職員が「リーダーは、自分の成長を期待してくれているのだ」「リーダーは、よく勉強している」などと思ってくれれば、「期待に応えなくては」「自分も勉強しなくては」という気持ちが自ずとわいてくるでしょう。こうして自己啓発が促され、自ら成長しようという強い意欲が生み出されていくわけです。 職場にこういう雰囲気ができてくれば、成長する組織風土づくりがうまくいっている証拠です。成長する組織風土ができてくると組織目標の理解や共有が進み、その達成に向けて力強い歩みが始まります。職員の成長に連れて組織自体も成長していくということです。
成長する組織風土づくりを加速する
成長する組織風土づくりを加速する手立てがいくつかあります。第一に、研修から戻った職員をリーダーが継続的にフォローすることです。リーダーには、本音では研修なんて役に立たないと思っている人もいるでしょう。残念ながら、役立たない研修があることも事実ですが、リーダーのフォローが悪いために効果が発揮できていない場合が多いのです。職員が研修から戻ってきたら「ご苦労さん」とねぎらうだけではなく、「何を学んできたのか」などと研修内容に関連した質問をどんどんしてください。学んだ内容と関連する課題を見つけて掘り下げた調査や研究を指示し、結果を簡単なレポートにして提出させれば、なおよろしい。 さらに、職場で勉強会や研究会を開催し、先進事例や他の自治体の動向などを交代で職員に発表させるのも有効です。技術系の職場などでは既に実践されているところが多いと思います。
4

特集全職員必読! 自治体における人材育成の意義
職員に研修内容を報告させ、皆で情報を共有すれば、研修成果の職場還元につながります。 これ以外にも工夫のしかたは色々あると思います。皆さんも自分の持ち味を生かして、成長する組織風土づくりにチャレンジしてみてください。
職場研修で何をすればよいか
世代間継承の中心となる職場研修の話に入ります。職場研修の定義については、「職場で、上司や先輩が実務に即して知識やノウハウを意識的かつ継続的に指導、伝授して行う人材育成のための多様な取り組み」という程度に理解しておけば十分でしょう。「多様な取り組み」というのですから何をしてもよいのです。ただ、漫然と行うのではなく「意識的かつ継続的に」というところがポイントです。 職場研修は、首長の強いリーダーシップのもとに全庁的な推進体制を整備して進めるのが理想的で、最近ではそういう自治体も増えてきました。ただ、そこまでできない場合は、単独の職場で上司や先輩が行っても十分に効果をあげることができます。
職場研修にふさわしいリーダー
最近、「リーダーの役割は職員が仕事をしやすいように環境を整えることにある」とする「サーバント・リーダーシップ」という考え方が注目されています。職員に仕事をしてもらうためにリーダーが職員を支えているのだ、というのです。このリーダーシップを体現しているのがサーバント・リーダーです。神戸大学の金井壽宏教授によれば、若い世代に奉仕するという意識を持ち、若い世代を育て、彼らのために、組織や社会に何かを遺したいと考えるリーダーがサーバント・リーダーであり、そうでないと人材育成の日常活動に自然な形で従事することは難しいとされています。ここでの人材育成の日常活動というのは職場研修のことです。世代
間継承の意義を理解し、日頃の職場研修を通じて人材育成に熱心に取り組むという役割は、サーバント・リーダーでなければ務まりません。ですので、皆さんもぜひサーバント・リーダーを志していただきたいと思います。
人材育成の進行を管理する
職場研修を始める前に、個々の職員について育成の方針を立てます。ただし、あまり緻密に書き込むと身動きがとれなくなりますので、あくまで「育成メモ」程度の内容と考えて下さい。例えば、ある職員について、用紙1枚を使い、箇条書きで簡潔に、その職員の能力や性格、強みと弱み、補強する点や伸ばす点、将来のキャリア目標などを書いていきます。次に、指導者と指導の中身、その期限などを決めて書き込みます。これを四半期ごとに進行管理し、あがった成果や不足している点などを追加していきます。この「育成メモ」を見ながら、職員の育成の方向を決め、職場研修を実践していくわけです。組織のメンバーが多い場合には、育成メモの作成と進行管理を中堅クラスの職員に手分けして任せてもよいでしょう。
5

特集 全職員必読! 自治体における人材育成の意義
指導の基本
職場研修の流れですが、職員にワンランク上の目標を設定させるとか、職務拡大などを行うことによりやりがいを感じられる仕事を与える。これが基礎になります。要は、職員に少しずつ難しい仕事をやらせて、それをなし遂げる過程で指導や助言を行い、成長を図るわけです。 個別の指導では、指導者がやってみせる。次に、やり方などを説明し、職員にやらせてみる。最後に、職員が出した結果を褒める。結果が出ない場合は、どこをどうすればよいのかを指導する。これが基本です。飲み込みが早い人もいれば、そうでない人もいますから、そのあたりは臨機応変に、進めたり、戻ったりします。できるだけ職員自身に考えさせて成長を促すよう心がけることが大事です。これはコーチングと呼ばれる指導法です。職員が自由に回答できるような雰囲気のなかで「他に方法はないか?」とか「A案とB案とではどちらが正しいと思うか?」などと考えさせながら指導するのです。
職場研修の具体的な方法
次に具体的な指導の方法についてです。忙しくて職場研修などしていられない、という声をよく聞きます。しかし、持続可能な行政を目指して進めなければならないのが人材育成です。実は、忙しい職場ほど職場研修の効果はあがりやすいのです。忙しい職場に異動してくると仕事を早く覚えます。指導する側は早く戦力になってほしいから熱心に指導する、指導される側は早く一人前になりたいから一生懸命に覚える。こうして指導する側とされる側の息がぴったり合ってこそ、職場研修は最大の効果をあげるのです。 私の知り合いの課長ですが、部下が来ると3分間は帰さずにデータや考え方をいろいろ質問する。それで付いたあだ名が「3分間クッキング」です。この課長は立派に職場研修を実践し
ていると思います。「たった3分間で?」と疑問に思う人もいるでしょうが、限られた時間でも実践することが大切なのです。とはいえ、工夫も必要です。忙しい職場では、時間をやりくりし、効率的でこまめな実践を積み重ねることです。 例えば、意識して部下に資料を作成させます。最初にラフスケッチを示して作らせてみる。できたものを上司や先輩に見てもらい、盛り込む情報の取捨選択や図やグラフを使った表現の工夫などを学ばせる。こうして完成稿まで何度か修正していく過程で資料の作り方が身につきます。 職員が決裁文書を持ってきたら、できるだけその場で内容を説明させ、関連事項や今後の見通しなどを質問します。こうしたことで職員は何が重要かを学び、答えられなかった事項は後で調べておいて次の機会には答えられるようにするでしょう。 このように、職場で個々の仕事を成し遂げる過程で、助言を与え、ノウハウを伝えるわけです。 住民への説明会や交渉ごとに際しては、職員を同行し、一部始終を見聞きさせ、時には実地に体験させます。会議や説明会の司会を若手に任せるのも成長に大きな効果があります。場数を踏ませることが大切なのです。こうした場合に忘れてならないのは、職員が行き詰まったときに必ず助け舟を出すこと。そうしないと、やる気を失わせ、失敗したという消しがたいトラウマが残るばかりです。 大規模職場も職場研修がやりにくい代表とされていますが、意識してコミュニケーションの機会をつくり、なるべく多くの職員と接するよう心がけることが大切です。人事関係の意向ヒヤリングなどで面談する機会を利用して指導する。定例会議など集まる機会を増やすとともに、会議そのものは10分でも5分でもいいから早く終え、空いた時間を活用して指導する。また、仕事の実態を知る意味からも職員に同行し、現
6

特集全職員必読! 自治体における人材育成の意義
場で状況を観察しながら気がついた点を指導する。さらには業務日報やノートなどを使って情報交換しながら指導する。職員が多過ぎて一人の手に負えないときは、育成メモのところで述べたようにチームリーダーやベテラン職員に方針を伝え、指導役を任せることです。
優秀な部下や専門職に対する職場研修
職務知識が豊富でアイデアがどんどん湧いてくる、仕事もよくできる。そんな優秀な職員でも、どこか足りないところがあるものです。優秀な部下を持った上司は、対等に話ができるよう、まず謙虚な姿勢で早急に必要な知識の習得や理解に努めます。そのうえで、部下には定期的に報告させ、職場のチームワークや連携が失われないようにします。さらに、組織全体に目を向けさせ、一段レベルが高い仕事の仕方や業務改善の方法などを提案させます。「鳥の目」と「虫の目」、マクロとミクロの両方の視点に立つように指導するわけです。もう一つ、忘れてはならないのは「魚の目」です。ウオノメではなくサカナの目ですよ。魚の体側には側線という器官があり、これで水圧や水流の変化を感じ取っています。これと同じく、仕事をするときには世の中の潮流や大局を読み取る必要があることを指導します。こうした方法は、専門職に職場研修を行う場合にも応用できます。加えて、専門職には、予算当局や人事当局など庁内の他の部署や外部に説明する機会を設けることも視野を広げるよい勉強になります。
研修担当の役割
ここで研修担当の役割について一言。「経験7割、薫陶2割、研修1割」という言葉にがっくりきた研修担当の方がいるかもしれませんが、早まらないで下さい。研修担当の役割は、世代間継承が円滑に行われるよう環境を整備することにあります。具体的には、職場における成長する組織風土づくりや職場研修をバックアップ
することがそれにあたります。また、さまざまな研修を設営することにより職場研修などの効果を増大させることも大切な役割です。職場研修は、自治体の規模や予算、人員にかかわらず、工夫によって効果をあげることができる分野であり、まさに研修担当の「腕の見せどころ」だと言えるでしょう。
おわりに
最近の若い職員は、叱られることに不慣れで傷つきやすいという傾向があります。一方、上司の側は、成果を出すことを急がされる風潮から、執拗に部下の失敗を追求する例が目立ちます。こうした事情が相まって、熱心に指導したつもりなのにパワーハラスメントを受けたと言われてしまうのです。そうならないためには、職員を応援しているのだという意識を忘れないことです。職員との間で、日頃のコミュニケーションを十分にして、上司の指導を受け入れる信頼関係を築いていれば大丈夫です。 皆さんが育てた人材が活躍する頃、皆さんは職場を去っているかもしれません。しかし、皆さんが伝えたものは後輩たちの中に脈々と生き続けることでしょう。そのとき行政は持続可能となり、永遠のものとなります。皆さんのご健闘を祈っています。
7

フォローアップ研修 愛 荘 町
採用後、2・3年目の職員は、研修センターの新任職員研修受講後、4・5年後の現任職員研修まで研修の機会がありません。その間、職員はOJTにおいて先輩などから指導等を受けますが、将来を担う職員を人財(材)として磨きを掛けるには、この時期が最も大切と考え、今年度初めて本研修を実施しました。 受講者18名は4グループに分かれ、「今日までの公務員生活を振り返って」をテーマに、採用前に描いていた公務員像と現在のギャップ、また今抱えている課題について話し合いました。その後、グループごとに出た意見を分類し、ギャップの解決策や抱えている課題をまとめ、グループ発表を行い、講師がコメントを添えました。 グループワーク後は、業務に不可欠なPDCAサイクルの大切さと薄れがちな接遇のポイントについても学んでもらいました。
受講者のアンケート結果では、研修の有効性について、18人中15人が「非常に有効」、3人が「有効」と回答しました。本研修の目的を達成し、高い実施成果があったと評価しています。受講者の主な意見としては● 初心に帰ってこれまでの公務員生活を振り返る良い機会となり、愛荘町の職員としての自覚を再確認することができた。● 同じ世代の職員と少人数で話すことで、意見交換しやすく様々な悩みや課題を共有することができた。● 自分ひとりで悩むだけでなく、まわりの人に相談することで多くのことに気付けることを知った。● 住民のため、愛荘町のために、新たな気持ちで気を引き締めて日々の業務を頑張っていこうと思った。 などがありました。 当町では、採用1年足らずの職員が、中途で退職したり、長期休暇を取得したりとメンタルヘルスを抱えることが増えています。グループワークによって、お互いの悩みを話し合うことが、新たなケア対策にもなることから次年度も本研修を続けていきたいと考えています。なお、本研修は、受講者の上司でもある職員(部長級)を講師としたことで経費を掛けずに効果を上げることができました。
●実施のきっかけと、 研修の内容を教えてください!
●実施してよかったことなどを 教えてください!
紹介します、わがまちの研修▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶
紹介します、わがまちの研修
8

( )5S活動&カイゼン研修 長 浜 市
長浜市職員には、少ない人数で仕事ができるよう、仕事の見直しと職員力・組織力の向上が求められています。そこで、サブグループリーダー研修とグループリーダー研修を系統立てて実施し、仕事の効率やチーム力を高める研修を実施しました。
*サブグループリーダー研修 「職員力・組織力を高める“5S活動”」 平成25年度、サブグループリーダーは、5S活動(整理、整頓、清潔、清掃、躾)の効果(①チーム全体の“ムダ”を省いた効率の良いしくみをつくること、②より良い人間関係をつくること)と具体的な事例を学び、その内容を各グループ員に還元しました。
*グループリーダー研修 「チームでカイゼン」 平成26年度、グループリーダーは、自身の役割と、問題解決技法を活用した「カイゼン」の手法と効果(①仕事の見直し、②チーム力の向上)を学んだ後、グループ員を巻き込んで「カイゼン活動」を実践しました。
よかったことは・・・● 自主的に「カイゼン活動」に取り組んだグループは全体の約60% 「カイゼン活動」の実践は、自主性を重んじ、強制はしていません。初挑戦での実践率としては、高い数値と捉えています。● 5S活動に関する取組が約80% 5S活動の効果の理解と、新庁舎移転というタイミングのおかげで、「カイゼン活動」のテーマ選定がスムーズに進みました。● チーム力の向上 グループ員が共通のテーマで気楽に議論を重ねていくことで、チーム力が高まりました。
今後の取組と課題は・・・● 魅力あるカイゼン事例の水平展開 魅力あるカイゼン事例は、報告会の開催等により情報を発信し、他課での展開を期待します。● カイゼン活動の継続 現状把握や要因の解析、対策の検討や効果の確認等、カイゼン活動の手順は、政策・施策展開に役立つスキルです。今後も継続した取組を進める予定です。
●実施のきっかけと、 研修の内容を教えてください!
●実施してよかったことなどを 教えてください!
県内市町では独自研修を数多く実施しています。いくつかの研修について、研修担当の方からお話を伺いました!
▶▶▶▶▶▶
紹介します、わがまちの研修
9

特集 月曜日が待ち遠しい職場を作る!
あなたの職場は月曜日が待ち遠しい職場ですか?仕事へのやりがいや充実感で溢れる職場でしょうか?そのような職場にするには、職場内のコミュニケーションの充実が必要不可決です。そのコミュニケーションについて、あなたは自信がありますか?職場のメンバーとのコミュニケーションは円滑に行われているでしょうか? 弊社では定期的に「職場内コミュニケーションアンケート調査」を実施しています。先の質問は、その調査内で行われた項目の一つ。弊社の調査では63.7%の方が「自信ある」と回答しています。 また、相手のコミュニケーションの取り方を不快に感じた経験はありますか?という質問に対してなんと75.3%もの方が「ある」と回答しています。その不快なコミュニケーションの第1位は一方的、自己中心的。第2位は無愛想、不機嫌、不誠実といった態度の悪さ。そして第3位は反応、リアクションが薄い。職場内のコミュニケーションで思い当たる点があるのではないでしょうか。 ここで考えなくてはならないのは、自分はよいと思っていても、実は知らず知らずのうちに相手を不快にさせてしまっているかもしれないということです。自信がある人が63.7%いるのですから、不快に感じる人はもっと少なくてもよいはずです。しかし現実には、不快に感じている人が非常に多いという結果が出ています。気を付けなければならないのは、「自分はできている」という思い込みです。不快に感じていても相手から指摘されることはあまりありませ
ん。「指摘されない=上手く行っている」のではなく、言われないからこそ危険なのです。だからこそ自身のコミュニケーションを振り返る必要があります。
良い人間関係を築くコツ
良い人間関係を築くには「共感的態度」が欠かせません。共感的態度とは、相手が興味を持っていることに関心を示すことです。そのためには、相手を「知る」「理解する」「聴く」ことが必要です。 「知る」とは言葉や言葉以外の表情、態度などから相手の感情や考え、状態などをよく観察することです。「理解する」とは、相手の感情や考えなどに理解を示すことです。大切なのは否定をしないことです。否定をしないとは、同じ考えになる同調ではなく「あなたはそう思っているんですね、そういう考えなんですね」と相手のことを尊重することです。そして「聴く」とは、その理解を言葉や態度で示すことです。具体的には肯定的な表情、頷きや相槌、さらに相手の話を引き出すような質問や言葉がけなどをしていきます。誰しも自分のことを認められたいし、受け入れられたいものです。職場に自分の存在を受入れてくれる安心感、所属感を感じられるからこそ、仕事への意欲も湧いてくるのです。
月曜日が待ち遠しい職場を作る!~職場を変えるコミュニケーション術~
株式会社ミュゼ 代表取締役 齋 藤 直 美(平成26年度1DAYセミナー「上司力アップによる現場強化研修」講師)
特集
10

特集月曜日が待ち遠しい職場を作る!
人間の行動の原理原則
仕事へのやりがいや充実感で溢れる職場を作るためには、人間の行動の原理原則を知る必要があります。 どのような時に人は行動が前向きになり、主体的になるのでしょうか。私たちの行動は、感情の影響を受けています。私たちが抱く感情は様々なものがありますが、大きく分けると嬉しい、楽しいなどの快の感情と、辛い、苦しいなどの不快の感情の二つあります。その快・不快は脳で判断しています。脳の中の感情を判断する部分で快・不快を判断し、その情報が理性的な思考をする部分に伝達され、どういう行動をするかを決めているのです。人間は、快の感情を抱いている時には行動が積極的になり、逆に不快な感情を抱いている時は行動が消極的になります。 つまり、人は抱く感情によって行動が変わります。もし現在、職場のメンバーに積極的な行動が見られない、意欲がない場合、何かしらの不快を感じている可能性があります。どんなに正しいことを伝えても、不快を感じている限り、積極的な行動が起きないのは当然です。行動したとしても「怒られる、評価が下がる」など、不快を避けるためにイヤイヤ行動するだけで、パフォーマンスが低くなる可能性が高いです。自らやる気になり、積極的な行動を促すためには、相手の感情を快にすることがポイントです。人を動かすとは相手の感情(心)を動かすことなのです。
「ヨイ出し」し合う職場作り
快感情とは、言葉を変えると、心に喜びを感じている時です。人はどんな時、心に喜びを感じるのでしょうか。給料、待遇が良くなれば喜びを感じるのでしょうか。人の欲求は大きく分けると、苦痛や欠乏状態を避けたいという本能的な欲求と、自己実現をしたい、成長したいと
いう高レベルな欲求の二つがあります。これらの欲求にはそれぞれ特徴があり、給料、待遇などを満たしたいという前者の欲求は、不足すると大きな不満足になりますが、満たされたからといって大きな満足にはなりません。そして、達成、成長、やりがいが欲しい、という後者の欲求は、不足しても大きな不満足にはなりませんが、満たされると大きな満足を得られるのです。 つまり、給料、待遇などが充実しているからといって、人は意欲的、積極的にはならないのです。それよりも、日々の仕事の中で周りから認められ、達成感、成長や、やりがいを得ることで心に喜びを感じ、積極的に行動し出すのです。大切なのは、仕事と心の喜びを繋ぎ合わせることです。仕事をすることが自分の心の喜びに繋がっていると実感できれば、自然と意欲的になっていきます。そのために、心に喜びを感じられるコミュニケーションが必要なのです。例えば、先に説明した「共感的態度」も、心に喜びを感じられるコミュニケーションです。他にも、職場内でお互いの「ヨイ出し」し合うことをお勧めします。ヨイ出しとは、相手の良い部分を認め合う言葉がけです。
褒めているつもりが心のすれ違いを生んでいる
あなたの職場は現在、互いを認め合う、ヨイ出しし合う職場になっていますか?褒める教育のブームにより、上司側も部下を褒めようという意識が高まっています。弊社の独自調査でも、94.6%の上司は一週間に一回は部下を褒めていると回答しています。しかし、褒められる側である部下に訊くと、30%はまったく褒められていないと回答しています。残念ながら上司は褒めているつもりでも、褒められていると感じていない部下がいるのです。 褒め言葉というのは、相手の心に届いてこそ褒め言葉です。どれだけ上司が褒め言葉と思って言ったとしても、部下の心に届いていなけれ
11

特集 月曜日が待ち遠しい職場を作る!
ば、それは褒めたことにはなりません。知らず知らずに心のすれ違いが起こり、やる気を失くさせてしまう可能性があります。そのような心のすれ違いが起こる原因の一つは、上司が「褒める=結果や成果を認めること」と捉えていることが考えられます。もちろん成果を褒めることは大事ですが、逆を言えば成果がでなければ褒めないことになり、褒める機会も言葉も限られます。結果、成果が出たら褒める、期待をしていたことを相手が達成した時に褒めるという条件付きの褒め言葉は、焦りや不安、プレッシャーを相手に与えてしまい、かえって逆効果になる場合があります。また、条件付きの褒め言葉は、相手に対して評価的、上から目線になってしまうことがあるので注意が必要です。 実は、相手を認める言葉がけは条件付きではなく、無条件の言葉がけもできるのです。例えば「真剣さが伝わってくるよ!」「いつも真面目に取り組んでいるね」など、仕事をしている
姿勢を認める。また、結果は出ていなくても、「頑張っているね!」「工夫してやってくれているね」など、取り組む過程の努力も認められます。弊社の調査によると言われて嬉しい褒め言葉は、「ありがとう」です。感謝の言葉は相手の労をねぎらい、自分が貢献できているとういう実感がわく言葉です。また、「あなたがいると職場が明るくなるよ!」など成果は出ていなくても、存在そのものが職場や仲間に貢献していることを伝えるとやる気が高まります。一方、やってはいけない褒め方として、「人との比較」があります。比較をされると、焦りや不安、プレッシャーを与え逆効果になる場合があります。比較をするなら他人と比較するのではなくその人の過去と比較します。「入庁した頃よりも(前よりも、半年前よりも)よくできるようになったね!」という具合に過去と比較し、成長の視点で褒めます。
12

特集月曜日が待ち遠しい職場を作る!
相手好みの言葉がけ
心のすれ違いが起こる原因のもう一つはタイプの違いがあります。人にはそれぞれタイプがありそのタイプにより好む褒められ方が違います。成果を褒められるのが好きなタイプと、プロセスを褒められたいタイプ、ねぎらいや感謝の言葉が欲しいタイプ。また人前で褒められたいタイプと、逆に人前ではなく1対1で褒められたいタイプ、できればあまり褒められたくないタイプなど人それぞれです。大切なのは相手が心から望んでいる褒め言葉、褒め方をすることです。やってしまいがちなのは、「自分好み」で褒めてしまうことです。自分が言われて嬉しい褒め言葉や褒め方が、必ずしも相手が好むとは限りません。相手の好みは日頃の観察が必要です。相手がどんなことに価値を置き、大切にしているのか?また、どんな時やる気になるのか?相手に興味、関心を持つことが褒め上手になる第一歩です。「相手を思い通りに動かしたい」という目的で褒めても相手の心に届きません、むしろ不快にさせるだけでしょう。あくまで、相手の人間的成長を目的に褒めます。
弱みさえもヨイ出しできる
ヨイ出ししようと思っても、相手の弱みばかりに目が行ってなかなかヨイ出しできず、逆にダメ出ししてしまった、ということもあるのではないでしょうか。相手の弱みが目についてしまった時、ヨイ出しするチャンスだと思ってください。「弱み=悪いこと=改善させるべき」ではありません。弱みが強みとして生かされることもあるのです。例えば、あなたから見ると、「優柔不断で決断力がない」と感じる相手でも、他の人は「優しい、人の気持ちがわかる人」と感じていることがあります。自身の基準、価値観で判断すれば、弱みに映るかもしれませんが、まったく別の人から見ると、弱みではなく強みとして映ることがあります。あなたの基準、価値観が100%正しい判断ではありません。弱みも見る角度を変えれば、必ず生かせる強みとなります。高い成果を生み出す職場は、互いの強みを引き出し合い、生かし合う特徴があります。弱みを咎
とが
め合うのではなく、強みを認め合い、ヨイ出しし合っていきましょう。
13

特集 月曜日が待ち遠しい職場を作る!
ワンランク上のコミュニケーション──相手好みでコミュニケーション
人は大きく分けると四つのタイプに分かれます。そのタイプによりコミュニケーションの取り方、仕事の進め方、価値観など様々なことが違います。〔P14:表 1〕 そして、タイプにより好む褒め言葉や叱り方や指示の出し方が違います。〔P15:表 2〕
やってしまいがちなのは、自分のタイプ、自分の好みで褒めたり、叱ってしまうことです。しかし自分のタイプと相手のタイプが違っている場合、褒めていても相手には伝わらなかったり、逆に相手を不快にさせて人間関係を壊してしまう事さえあります。大切なのは一人一人をしっかり観察して、本当に相手が欲しがっている言葉をかけることです。 月曜日が待ち遠しい職場にするためには、や
行動型 決断力があるリーダータイプ
自分で物事を決めたく、人から指示や判断、コントロールされる事を好みません。常に目標を掲げまい進していくタイプです。また、持論が強く、自己主張も遠慮なく出来るため、時に周囲から怖がられることもありますが、裏表なく素直でさっぱりしたタイプでもあります。面倒見も良く、リーダー的存在で周囲を巻き込んでいくことも得意です。
感覚型 明るく楽観的、職場のムードメーカータイプ
明るく誰とでもすぐに仲良くなれるタイプです。いつも話題の中心で、職場のムードメーカー的存在です。プロジェクトリーダーなど、メンバーを盛り上げながら仕事を進めることも得意です。しかし、少し飽き性な所があり長期的な仕事は不向きです。物事をおおまかに捉える傾向があり、ざっくりとした報連相や指示になりがちです。また、頭の回転も速くアイデアが豊富なことも特徴です。
友好型 真面目で人との繋がりや人間関係を重視するタイプ
人を援助することが好きで、職場では縁の下の力持ち的な存在です。人との合意や協力関係を大切にするタイプです。人の感情にも敏感で、相手に合わせた受け答えができます。しかしそれ故に、相手の期待に応えすぎてしまい、本音がなかなか言えず仕事を抱え込む傾向があります。また、自分が費やした努力や好意に対して、しっかり認めて欲しいという欲求が強くあります。
分析型 何事も正確で几帳面、論理的思考のこだわりタイプ
正確にやり遂げたいという気持ちが強く、仕事を丁寧に進め、ミスや抜け・漏れは少ないタイプです。仕事に取り掛る前に、情報収集や分析、計画をしっかり行い、ノリやひらめきでは動きません。客観的に物事を捉えじっくり取り組むタイプなので、周囲の人にはマイペース、頑固な人と映ってしまうこともありますが、最後までやり遂げる努力家です。
表 1
14

特集月曜日が待ち遠しい職場を作る!
はり職場内のコミュニケーションが不可欠です。コミュニケーションを取り、信頼関係を築くことで高い成果を生み出せます。「そんな時間、余裕はない!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、信頼関係こそ効率性です。信頼関係が築けている相手だからこそ、一緒に頑張りたい、困難も一緒に乗り越えよう、助け合おうと思え、その結果、仕事は効率よく進められるのではないでしょうか。
■タイプ別の褒め方
行動型 ● プロセスよりも、結果を出したらタイミング良く褒める● コミュニケーションのスピードが速いので、短く、ズバッと褒める● リーダー的存在なので、その影響力などを言葉にして伝える
感覚型 ● 褒め言葉の内容よりも、褒める量を重視する●大げさに褒める、人前で褒める●豊富なアイデア、個性を褒める
友好型 ● 褒め言葉というより、ねぎらいや感謝の気持ちを伝える●さりげなく、小まめに褒める●人前よりも1対1で褒める
分析型 ●専門性や正確さ、プロセスを褒める●どこが良いのか具体的に褒める● こだわり部分にポイントを絞って褒める
■タイプ別の叱り方・指示の出し方
行動型 ●結論ファーストで率直に言う●細かく言わず、相手に考えさせる●プライドを傷つけない
感覚型 ● 押し付けにならないように、相手に問いかけながらアイデアを引き出す● 理詰めや細かすぎる指導や指示はNG● ある程度、自由な枠の中でのびのび仕事をさせる
友好型 ● 任せっぱなしではなくフォローの姿勢を示す● 一方的な会話にならないように、相手の話をよく聴き合意を取りながら進める● 表情、態度などが威圧的にならないようにソフトに伝える
分析型 ●具体的に、細かい情報まで伝える●理由、根拠を明確に伝える● 相手のペースを乱さず、時間を与え、じっくり取り組ませる
表 2
15

皆さんはリーダーと聞くとどんな人を思い浮かべますか。 私が講師を担当した係長級職員(1部)研修では、JST基本コースとして職場におけるリーダーの役割やマネジメントの仕方、コミュニケーションの取り方について学びます。私自身も係長級ですので、再確認を兼ねて、受講者の皆さんと一緒に考えながら進行していきました。 係長級ともなれば、係をまとめるリーダーとして、また、上司をサポートする部下として、今までとは違う立場で仕事をすることが多くなります。仕事のやり方は十人十色。それぞれ性格も違えば得手不得手もある中で、作業効率を上げながら、より良い職場環境・人間関係を築くにはどうすればよいのか、日々試行錯誤されていることでしょう。それに加えて住民からの多種多様な要望やクレーム。本当に私たちを取り巻く職場環境は年々厳しくなっていると痛感します。こんな疲弊した毎日の中では良いリーダーの存在がとても大きな力になりますね。 冒頭でお尋ねしましたが、皆さんがリーダーと聞いて思い浮かべるのはどんな人でしょうか。当初私自身が思い描いたリーダー像は、今思えば少し偏ったものでした。このことに気づいたのは、私自身が受講者としてこの研修を受講したときでした。この研修では実践に即した形でリーダーの役割を具体的に示し、多くの「気づき」を与えてくれます。また受講者のほとんどが、日頃自分と同じ悩みを抱えていることにも気づかせてくれま
す。同じ立場の者同士が悩みを共感し、解決策を見つけていくことは、この研修の大きな収穫のひとつです。ここで出会うメンバーは気持ちを共有できる仲間です。ぜひこの出会いを大切にし、困ったときは助け合ってもらいたいと思います。 正直なところ、私は自ら進んで講師になったわけではありませんでした。しかし、この経験を通じて学んだことがあります。それは、何事にもチャレンジすることの大切さです。チャレンジすれば必ず得るものはあります。今後リーダーとしての役割を担う中では、したくないことでもしなければならないときがくると思います。その時のためにもぜひ何事にもチャレンジする気持ちを持ってください。経験はきっと大きな力になります。「こんな人と一緒に働きたい」そう言われるリーダーをめざし、同じ立場の者同士共感し合い、切磋琢磨しながら前進していきましょう。
※JST=(Jinjiin Supervisory Training) 人事院式監督者研修
リーダーの役割と心構え~JST講師を担って~
湖南市人権擁護課 主幹 梶 山 政 代
内部講師レポート
内部講師レポート
16

我々公務員は一部の奉仕者でなく、全体の奉仕者として住民の命と暮らしを守るという使命を担っており、常に倫理を意識して業務にあたることが求められています。公務員倫理を含めたスキルアップを図るためには、第一に積極的に研修等に参加すること、次に指導者養成研修を受講して自身を磨き、最終的には講師として登壇することではないかと思います。 様々な業務経験を重ねていくと、その時々に「人間力」を養う数々のイベントが用意されているものだと感じることがあります。現任職員(3部)研修の講師依頼があった時、予算の時期と相まって「選択と集中」というキーワードが脳裏を過ぎりました。 人生は「選択」の連続です。その時々に様々な場面で選択を強いられますが、おのずと易しい方を選んでいるものです。この講師の依頼を受けるべきか、断るべきか。人生の中で、時として厳しい方を選択すべきとのお告げがあり、悩んだ末にチャレンジ精神で後悔しない選択をしました。 皆さんなら、公務員倫理などの職員研修に何を求めて参加しますか。研修の満足度とは、流暢な話し方だとか、テキストから脱線するユーモアだけでは決してないと思います。そんな中、私は講義の項目と項目との合間を縫うコメントに注目しました。受講者は、研修そのもの以外に、テキストからは得られない「講師固有の引出し」に期待しているのではないかと思います。 全ての項目に関して、最も伝えたい部分を、いかに表現するかをイメージしながら講師用テ
キストを組み立て、受講者の心を掴むアイスブレイクを取り揃え研修に臨みました。オープニングからエンディングまで全体の時間の流れを大切に、この講師でしか味わえない、雰囲気のある研修を目指しました。研修終了後の受講者アンケートでは、「自然と引き込まれる様な講師であった」という私の考える着地点とも言える最高の言葉を頂くことができました。 「継続は力なり」。地道な努力を続けていけば、やがて積み重ねが力となります。中学生の頃の私は友達との会話が苦手で「沈黙は金なり」と考えていました。今も本質は変わっていないのかも知れませんが、少し勇気を出して「継続は力なり」を生き方の糧としてきた結果、講師として登壇するレベルまで登ることができました。講師の「選択」を経て、コミュニケーション能力は極めて重要であると、改めて実感しています。 皆さん、研修講師として登壇する事を是非とも選択してください。この「選択」は、素晴らしい方々との出会いがあり、真の充実感と喜びが得られます。皆さんと研修会場でお会い出来ることを本当に楽しみにしています。
もし私が受講者なら、この研修に何を求めるか~公務員倫理講師を担って~
日野町税務課 専門員 山 口 明 一
内部講師レポート
内部講師レポート
17

私は現在、行政職として勤務していますが、前職は本市の障がい福祉課の発達支援員でした。発達支援員は、発達障がいを抱える方やそのご家族を対象に生活や仕事に関する相談を受けることが主たる業務です。当時は就労に関する相談が多くを占めていましたが、その他にも「日中活動する場所が欲しい」や「コミュニケーションをとることは苦手だけど、誰かと関わりたい」というニーズを聞くこともありました。そうした時は地域で利用できる施設を紹介していましたが、個々のニーズに合致しないケースもあり、十分なサービス提供ができていないと感じることも度々ありました。このような経験を重ねていくうちに、多様なニーズに対応できる支援体制の構築に取り組んでいきたいという気持ちを抱くようになり、行政職として地域の障がい福祉に携わることを目指しました。 今回の新任職員(後期)研修では、半年を振り返り、自身の仕事について客観的に見直すことができました。この半年間は「仕事に慣れる」ことに意識が向けられており、日々の業務に追われていたように思います。「仕事に慣れる」ということは、市民サービスを円滑に提供する上で重要な要素であり、私自身にとっても多くの経験を積むことができた貴重な半年間であったように思います。しかし、「忙しさのあまり、目の前にある仕事をこなすことのみに力を注いでいないだろうか」という疑問も同時に浮かぶようになりました。行政職を目指すきっかけとなった、多様なニーズに対応できる支援体制の構築という目標については、徐々に後回しになっ
ているように感じました。 この研修では、理想のまちづくりをテーマにどのような取り組みができるかアイディアを出し合う、というグループワークを行いました。グループ内には他市町の自治体職員の方々も参加されており、地域の特性や所属課に応じた様々な意見が出されました。また、理想のまちづくりを実現させるために何をどの段階で取り組み、その効果はどのようなものがあるかという観点を取り入れることで、より具体性のある構想となりました。このグループワークでは、理想のまちづくりの実現という非常に大きなテーマを扱いましたが、私の仕事に対する見方や姿勢の転換にも役立つ体験となりました。それはこれまでの半年間が、基礎を築くための準備期間であり、行政職を志した当初の目標に必ず生かすことができるという捉え方へと変化させるものでした。 今後は目標を常に意識しながら、より積極的に仕事に取り組むと同時に多くの経験を積み、市民サービスへと還元していきたいと思います。
原点に立ち戻ることの大切さ~新任職員(後期)研修を受講して~
近江八幡市障がい福祉課 主事 福 西 翔 平
受 講 者 レ ポ ート
受講者レポート
18

今年度から産業振興課に異動になり、視察等に来られた方に豊郷町の特産品や名所を発表したり、取組内容について伝える機会が増えました。私はあまり人前で話すことが得意ではなく、相手に上手に物事を伝えるということができていなかったので、自分を変えるきっかけになればと考え、今回のプレゼンテーション研修を受講しました。 研修内容としては、相手への伝え方、文章の構造等プレゼンテーションの基礎となる部分から講義が始まり、最後には何人かのグループに分かれて実際にプレゼンテーションを行いました。そして、そのプレゼンテーションについてグループ内で意見をもらい、それを踏まえて再度プレゼンテーションを行いました。 相手への伝え方では、ある図形を相手に伝えるという演習をしたのですが、なかなか相手に思うどおりに伝えられませんでした。自分の中でこう言えば伝わっているだろうと思っていても、相手はそのように受け取っていないということがあり、相手に伝えることの難しさを改めて感じました。まずは全体から細部を説明し、順を追って伝えるということ、また自分にとって常識と思っていることが相手にとって常識ではないのだということを学べました。 実際のプレゼンテーションでは、私は「皆さんに豊郷町の特産物である坊ちゃんかぼちゃを食べてほしい」というタイトルで発表しました。文章の構成に気をつけながら、坊ちゃんかぼちゃの現状、特徴、オススメの食べ方という三本の柱を軸に話を進め、具体的な主張、理由づけ、
根拠を意識しながら発表をしました。 二回目のプレゼンテーションではいただいた意見を反映し、内容を充実させつつ、目線の配り方、自然な身振り手振り等の内容以外にも気をつけて発表しました。プレゼンテーションが終わったときには、グループの人に「実際に坊ちゃんかぼちゃを食べてみたくなったわ。」と言われて、自分の思いがしっかり相手に伝わったという嬉しさとやりきったという達成感を感じることができました。 また、他の人のプレゼンテーションを聞かせていただいて、一人ひとりが工夫をされていて、吸収させていただくことが多くありました。 この研修を終えた後、何回か発表をする機会がありました。まだなかなか上手に伝えることはできませんが、「わかりやすかったです。」という言葉をかけていただいたときはこの研修が生きてきているように感じます。今後も人にどのように伝えればわかってもらえるかということを意識しながらこの研修で学んだことを職務に生かしていければと思います。
伝えることの難しさ~プレゼンテーション研修を受講して~
豊郷町産業振興課 主事 角 田 成 明
受 講 者 レ ポ ート
受講者レポート
19

クレーム対応能力は、お客様が老若男女、全住民である自治体職員には、必要不可欠なものであり、今後もますます求められる能力です。日々住民の方と接する課に所属しているため、クレーム対応について今一度学びたいと思っていたものの、今回の研修は「指導者養成」。自分に指導者など務まるのか、少し自信のないまま受講日を迎えました。 「クレーム」とはお客様がサービスに対する不満や不公平を感じた際に改善を要求する行為、意見、要望である。そのクレームを受け入れ、全身で傾聴し、適切なお詫びのあと説明し、解決策を提示し、それを今後に生かす。まずはこのことを模擬研修により学ぶとともに、研修の進め方を体験しました。 そして、これまでの研修なら、学んだことを自分が理解し、持ち帰り、実践していけばよかったのですが、今回は、私がこれを皆さんにお伝えできるようになるまでが研修です。模擬研修の後は、研修の進め方について、とにかく反復演習あるのみの三日間でした。与えられた時間内に、受講者の反応を見ながら伝えるべきことを正しく、かつ興味を持ってもらえるよう伝える。さらに本研修の場合、一方的な講義形式ではなく、発表やロールプレイもしてもらわなければならない。そして私がお伝えしたことが皆さんに伝わり、職場で実践してもらえなければ時間を割いて受講してもらう意味がない。大勢の人に研修という形でお伝えするというのは、一対一で窓口対応をするのとはまた違った能力が必要なのだと感じました。
三日間にわたる研修は大変だった分、中身の濃い、記憶に残るものとなり、クレーム対応技術と、それを大勢の人にお伝えする手法の、二つのことを一つの研修で学ぶことができました。自身にとっては初めての指導者養成研修でしたが、人に伝えようとすることで、自分のテーマへの理解がさらに深まり、また、自分の今のレベルや弱点、他自治体の皆さんの素晴らしさを知ることができました。 現時点で、私が得られたほどの学びを、講師として皆さんにお伝えできるかというと甚だ心許ないのですが、まずはこの経験を、快く研修に送り出して下さった職場へ返すことから始め、近い将来、研修講師として登壇できるよう、今後も研さんを積んでいきたいと思います。
指導者養成は一挙両得!~クレーム対応指導者養成研修を受講して~
守山市国保年金課 主査 川尻みゆき
受 講 者 レ ポ ート
受講者レポート
20

当初、研修に参加することに消極的でしたが、日々の業務を振り返るために参加を決意しました。研修を受講して、政策形成の手法と大切さについて、具体的には以下の二つのことを学ぶことができました。 一点目は、一つの課題に対する様々な考え方、地域差、視点の違いを、議論してより良い解決につなげていくことの大切さについてです。 私たちのグループは、まちの規模、職種、年齢構成も違う県内の5市町の職員で構成されています。最初は、それぞれの性格も解らない状況で、考え方も視点もそれぞれ異なっていました。 そこで、まず各市町の特徴や状況を知るために、グループ研究を、各市町の庁舎で順番に行いました。各地域の問題について共通認識を図り、またメンバー間のコミュニケーションも次第に活発になってきました。その後も、積極的に意見を出し合い、活発な議論をすることができたと思います。 このことからも、市役所内でも一つの課題に対して、一つの部署だけでなく各部署でコミュニケーションをとりながら議論を重ね、市全体として取り組むことが重要だと感じました。 二点目は、問題に対する現状の把握と分析の大切さについてです。 私たちのグループでは、「防災」をテーマに高島市南鴨、兵庫県佐用町、福井市蔵作町の被災地へ視察を行い、地元住民の方から被災時に困ったことなど生の声を聞かせていただきました。その中で、日頃の業務は、ルーチンワークになりがちであり、市民が本当に望んでいる事
は何なのかという「考える力」が欠けていると気づかされました。 改めて、日頃から市民の声を聞き、市民目線で考えることが大切であり、それをいかにより良いまちづくりのために生かしていけるかが重要であると思いました。 今回の政策課題研究で学んだこと、グループ研究での多くの経験と仲間との人脈を大切にし、今後の業務に生かし、実践していきたいと思います。日々の業務を振り返る機会をいただき本当にありがとうございました。
※政策課題研究 自治体が抱える様々な課題の解決と理想の姿をメンバー同士で調査、研究、議論し、効果的で実践的な施策を企画立案することにより、政策形成能力の向上と職場での課題に応える実践力を身につけることを目的に実施しています。平成26年度は、3グループ15名の参加があり、7月23日から1月27日までの半年にわたって実施しました。
チーム ガリバーの6ヶ月~政策課題研究を受講して~
米原市伊吹自治振興課 主査 堀 正 彦
受 講 者 レ ポ ート
受講者レポート
21

平成26年度、2つの指導者養成研修を実施し、下記の方々が修了されました。 今後、それぞれの団体で実施する研修講師として、また、当研修センターでは、JKET指導者の方々には「現任職員(1部)研修」および「現任職員(3部)研修」の公務員倫理、クレーム対応指導者の方々には「現任職員(1部)研修」のクレーム対応の指導でご活躍いただきます! ※敬称略
研修講師、誕生!
大 津 市 西寺 瑞代 栗 東 市 芝原 慶久大 津 市 正田 正道 野 洲 市 辻 昭典彦 根 市 森野 晃司 湖 南 市 伊藤 雅則長 浜 市 隼瀬 大典 湖 南 市 森井 恵長 浜 市 田中 昌幸 湖 南 市 喜多 孫和近江八幡市 武田 善雄 高 島 市 平井 亨草 津 市 廣政 孝幸 東近江市 池戸 洋臣守 山 市 畑本 政美 米 原 市 川﨑 壮登守 山 市 河本 文彦 日 野 町 山口 明一
大 津 市 髙橋 純子 栗 東 市 相宗 孝文彦 根 市 安賀 喜博 甲 賀 市 黒田 芳司彦 根 市 藤木 利昭 野 洲 市 井上 善之長 浜 市 成田 尚人 湖 南 市 市川 和美草 津 市 林 良作 高 島 市 駒井 直樹守 山 市 中吉真樹子 東近江市 中島 昌之守 山 市 川尻みゆき 米 原 市 柴田 隼人守 山 市 木村 俊雄 日 野 町 松尾 武志
※JKET=(Jinjiin Komuin Ethics Training)人事院討議式研修「公務員倫理を考える」
JKET指導者
クレーム対応指導者
研修講師、誕生!
平成26年7月 JKET指導者養成研修 平成26年8月 クレーム対応指導者養成研修
22

当研修センターでは、平成27年度も多くの研修を実施します。その中のいくつかをここでご紹介します!
平成27年度 おススメ研修
平成27年度 おススメ研修
平成24年度から実施しており、毎年、人気の高い研修です。 平成26年度の受講者アンケートでも ●簿記に触れたこともなく、決算書の見方も分からなかったが、分かるようになった ●簿記を楽しいと思えるなんて、受講するまで思いもしなかった ●法人の決算書チェック等、業務に生かすことができる などの感想をいただいております。 今後、財務書類に公会計が段階的に導入されるようになることもあり、その基礎となる複式簿記の知識はますます必要になってきます。 受講していただく方も年々増えていることから、平成27年度は、日程を2つに増やし実施します。
これまで興味はあったけれども日程の都合がつきにくかった方、簿記の知識を習得したい方はぜひ受講してください!!
複式簿記の基礎研修
平成27年度、新たに実施する研修です。 発言できない、決まらない、時間どおりに終わらない・・・そんな会議を経験したことはありませんか。 場の雰囲気作り、意見の出やすい質問の仕方、出てきた意見のまとめ方などを体感しながら学んでいただく研修です。
次のページに続きます➡
業務で会議を開催することが多い方、決まらない会議にお悩みの方はぜひ受講してください!!
会議力向上研修
平成26年度の研修風景
23

★政策形成指導者養成研修
★接遇指導者養成研修
★OJT指導者養成研修
平成27年度 おススメ研修
いずれの研修も、修了いただいた方にはそれぞれの団体で実施される研修講師としてご活躍いただくことはもちろん、当研修センターでは 政策形成指導者の方々には「現任職員(2部)研修」 接遇指導者の方々には「新任職員(後期)研修」 OJT指導者の方々には「係長級職員(2部)研修」 の指導でご活躍いただきます。
スキルアップをしたい方、研修を受けて講師に興味をもたれた方はぜひ受講ください!!
指導者養成研修
24

滋賀県市町村職員研修センターキャラクター
「HIYAKU くん」
研修情報誌
2015年(平成27年)3月発行
編集・発行 /滋賀県市町村職員研修センター住 所 〒520-0801 滋賀県大津市におの浜一丁目1番20号 ピアザ淡海4階 自治研修センター内T E L 077-527-5270F A X 077-527-5271E-mail [email protected] R L http://www.hiyaku.or.jp
2015.3

滋賀県市町村職員研修センターキャラクター
「HIYAKU くん」