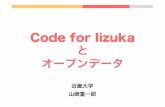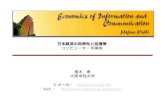オープンデータ政策の経済効果について(2014/4/22)
-
Upload
toshiya-jitsuzumi -
Category
Business
-
view
997 -
download
2
description
Transcript of オープンデータ政策の経済効果について(2014/4/22)

オープンデータ政策の経済効果についてAn Analysis on the Economic Impact of Open Data
Initiative
九州大学 実積寿也Toshiya Jitsuzumi, Kyushu University

2
オープンデータとは? 「オープンデータとは、広く開かれた利用が許可されているデータのことです。
2013 年時点では、行政機関が保有する地理空間情報、防災・減災情報、調達情報、統計情報などの公共データを、利用しやすい形で公開することを指すのが一般的です。」(小池瑠奈氏の定義 IT Pro 2013/11/12 )
2014/4/22オープンデータの経済効果を考える:何を期待し、どう推進するか?( Innovation Nippon シンポジウム 2014 年度第 1 回)
「『オープンデータ』と言えるためには、 (1) 機械判読に適したデータ形式で、 (2) 二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータである必要があります。それにより、人手を多くかけずにデータの二次利用が可能となります。」(総務省 HP http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/opendata/opendata01.html )
http://hivecolab.org/open-data-open-development/#sthash.jBqKowA1.dpbs

3
世界最先端 IT 国家創造宣言( 2013/6/14 閣議決定)
(1)オープンデータ・ビッグデータの活用の推進
行政が保有する地理空間情報( G 空間情報)、防災・減災情報、調達情報、統計情報等の公共データや、企業が保有する顧客情報、個人のライフログ情報等、社会や市場に存在する多種多量の情報、いわゆる「ビッグデータ」を相互に結び付け、活用することにより、例えば、環境、教育、交通等の多様なデータを集約・整理してその地域の状況を分かりやすく示す不動産情報提供、多種大量のデータから顧客のニーズに応じたデータを自動的に抽出するプログラム開発などの新ビジネスや官民協働の新サービスが創出され、企業活動、消費者行動や社会生活にもイノベーションが創出される社会を実現する。
このため、公共データの民間開放(オープンデータ)を推進するとともに、ビッグデータを活用した新事業・新サービスの創出を促進する上で利用価値が高いと期待されている「パーソナルデータ」の利用を促進するための環境整備等を図る。
① 公共データの民間開放(オープンデータ)の推進
2014/4/22オープンデータの経済効果を考える:何を期待し、どう推進するか?( Innovation Nippon シンポジウム 2014 年度第 1 回)

4
世界最先端 IT 国家創造宣言工程表
2014/4/22オープンデータの経済効果を考える:何を期待し、どう推進するか?( Innovation Nippon シンポジウム 2014 年度第 1 回)
政策は効率的なパッケージとなっ
ているのか?

5
オープンデータ政策の経済効果推計の概念的意義 基本的視点は「効率性」
経済学は希少資源を用いて最大の厚生を生み出す方法に関する学問
効率性と公平性の視点
利用できる情報量が多くなれば、意思決定の精度が改善される。
データ提供コストと、経済効率性改善メリットの比較から、最適な「オープンデータ提供量」が決定
もし当該水準がなんらかの制度的理由によって実現できていないのであれば、政策介入が要求される 政策介入によってどのくらいメリットが回復できるのか?
2014/4/22オープンデータの経済効果を考える:何を期待し、どう推進するか?( Innovation Nippon シンポジウム 2014 年度第 1 回)
0% オープンデータの提供量
データ提供の限界費用
経済効率改善による限界効果
最適な提供量
100%
ポイントは政策介入コストとの比較

6
オープンデータ環境が不十分であることの経済損失
2014/4/22オープンデータの経済効果を考える:何を期待し、どう推進するか?( Innovation Nippon シンポジウム 2014 年度第 1 回)
オーストラリアに関する推計( ACIL Tasman 2008 )

7
考慮すべきポイント:政策コストの多様性 オープンデータ政策のコストは、単にデータ開示のために必要な事務作業に伴うコストだけではない。 オープン化が不安である、というような漠とした心理的なもの
誤ったデータが広まって国民に誤解や混乱が起こるとか、テロリストに利用されるといった、利用とその効果に関する懸念
行政が実際には完璧なデータを持っておらず、意思決定を行う際に参照しているデータの中には公にしたくないような質の低いものがあるなど、透明化への抵抗
誤ったデータによって誰かに損害を引き起こした場合の法的責任を負いたくないといった責任問題
オープン化したデータについて受け取ることになる問い合わせに対応することの手間を懸念するといった、オープンデータのもたらす負担に関するもの
2014/4/22オープンデータの経済効果を考える:何を期待し、どう推進するか?( Innovation Nippon シンポジウム 2014 年度第 1 回)

8
考慮すべきポイント:消費における「規模の経済」 データはその絶対量と組合せ可能性によってもその有用性が左右される。
2014/4/22オープンデータの経済効果を考える:何を期待し、どう推進するか?( Innovation Nippon シンポジウム 2014 年度第 1 回)
ミクロ的にはクリティカルマスにより、需要の利用の立上がりが遅れる可能性
経済全体にとってみれば外部経済性による過少均衡がもたらされる可能性
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00ネットワーク規模
加入料金
クリティカルマス曲線
需要曲線
データ利用コスト
0% オープンデータの提供量
データ提供の限界費用
規模の経済を考慮しない限界効果
100%
規模の経済を考慮した限界効果

9
経済効果推定に何を期待すべきか? 厳密に数値を確定することは人智を超える。
あくまでも市場プレイヤーの努力を結集すべき目標 そもそも、やる価値があるか否かという問題
個別の「手堅い」領域でデータのオープン化がどの程度の効果をもたらすかについての精度の高い情報群よりも、大まかな目安としてどの程度の経済効果を意識するべきかが、積極的なオープンデータ政策を進める上では重要
政策プライオリティの順位付けに役立てばとりあえず十分? どの分野に対して、どのようなデータについてオープン化を実施した場合に、どの程度の経済
効果を得ることができるかがわかれば、それに見合った形で政府がどの程度オープンデータに注力するべきか、コストのかかる作業(データのフォーマット変換やメタデータ付与、正確なドキュメンテーション資料の作成・提供)などにどの程度力を入れることが望ましいかが見えてくる。
2014/4/22オープンデータの経済効果を考える:何を期待し、どう推進するか?( Innovation Nippon シンポジウム 2014 年度第 1 回)
オープンデータは一方では、政策決定に際してデータ主導、あるいはエビデンスに基づいた決定を可能にするという期待を集める形にもなっているが、確固とした経済効果データのみによってオープンデータ化を推進することは難しい。 データ主導の政策決定を可能にするはずの当のオープンデータ政策が必ずしもデータ主導で決まらないというのは若干皮肉な事態

10
経済効果推定の限界 経済効果全体に占めるオープンデータ貢献分の推計は難しい
オープンデータへの取り組みは極めて最近の事象であり必要なデータ蓄積が欠如
個別効果の積上げに基づく推計という代替案 理論的正当性は必ずしも保証できないが、現実的。ただし、さまざまな誤差はつきもの。
将来予測については様々なファクターにより推計値が大きく異なる。 マクロ経済の状況
産業構造変化をどの程度見込むか
補完的経営施策導入やビジネスプラン変更、制度対応の状況
データサイエンティストが十分に用意され、利用者の ICTリテラシーも向上し、ネットワーク環境や端末も普及し、既得権益者の抵抗が失敗におわり、といった理想的な条件を考えるならば…
経済推計の前提条件の確定自体が大問題 効率性改善は生産量増加と必ずしもイコールではない。
間接的な経済効果をどの程度精密に考慮するのかによって結果は大きく異なりうる。 間接的な経済波及効果を含めて経済効果を考えることは、「全産業の成長」といった現政権の目標に照らしても適切
2014/4/22オープンデータの経済効果を考える:何を期待し、どう推進するか?( Innovation Nippon シンポジウム 2014 年度第 1 回)

11
推計結果 海外の推計値を参考にすると、公共データの利用が、直接・間接の受益者を含む日本の経済全体へ与える波及効果は 2.4~ 4.7兆円程度である。オープンデータ政策の推進によって公共データが利用しやすくなれば、 1800~ 3500億円程度(総効果の 7.5%に相当)の経済効果が得られる。(国際大学 GLOCOM渡辺智暁氏による推計)
2014/4/22オープンデータの経済効果を考える:何を期待し、どう推進するか?( Innovation Nippon シンポジウム 2014 年度第 1 回)
計量可能シナリオ 実現性の高いシナリオ
推計された効果の対 GDP 比 0.51 % 0.99 %
2012 年度の経済効果 to Japan 2.4 兆円 4.7 兆円
オープンデータ政策の効果 1,800 億円 3,500 億円
ベースとしたのは ACIL Tasman (2008)
同推計はそもそも、現代的な空間情報技術が経済に与える効果を推計したものであり、オープンデータや公共データの経済効果に関する推計ではない。これを Vickery (2011) の仮定に従い公共データの価値に変換
日本とオーストラリアでは、様々な産業の規模や比率、産業間の連関が異なっている。 GDP比で見た場合に両国で概ね同じようなレベルの効果が得られるという仮定はやや根拠に乏しい

12
経済効果推定の方法
2014/4/22オープンデータの経済効果を考える:何を期待し、どう推進するか?( Innovation Nippon シンポジウム 2014 年度第 1 回)
生産要素としてのデータの定義
• 範囲の確定• 量の定義
データ活用による直接効果の推定
• 生産関数の推計
• 成長会計の利用
• 積上げ計算
データ活用による間接効果推定
• 産業連関分析
• 応用一般均衡分析
• 推計対象となるデータを明確に定義しなければ、その利用を可能にするための必要資源の量の確定もままならない
• 推計期間において利用されるデータの種類とその活用方法を事前に予見する必要がある
• 生産関数の推計や成長会計による推計は経済理論と整合的な結果をもたらすが、推計を支えるだけのデータを得ることが困難
• 与件の変化をどの程度読み込むかによって推計値は異なる
• 生産効率上昇を生産拡大と同視するケースが通常
• 伝統的な産業連関分析では産業構造の変化を見込まないのでオープンデータによる新産業創造などは考慮できない
• 応用一般均衡分析は産業構造変化を考慮できるものの、数多くの仮定に依存
• 産業統計で把握されない効果は推定できない
データ活用の経済効果
オープンデータ環境の有無により複数シナリオを設定することで、オープンデータ政策の経済効果を推定

13
ACIL Tasman ( 2008 )の例
2014/4/22オープンデータの経済効果を考える:何を期待し、どう推進するか?( Innovation Nippon シンポジウム 2014 年度第 1 回)

14
経済効果推計の精度を向上するためには?未来予測の精度を上げることの意味はともかく… オープンデータの利用の主要な事例研究や、その効果に関する研究の蓄積が有益
多様な分野の利用から得られる経済効果を調べるためには、それぞれの分野においてオープンデータが活用されてどのような効果が得られているのかについての研究の蓄積が重要
応用一般均衡モデルを用いた精緻化は魅力的な選択肢ではあるが、将来予測としてどの程度真実に迫ることができるかは未知数 革新的な産業構造転換を記述する術はない
2014/4/22オープンデータの経済効果を考える:何を期待し、どう推進するか?( Innovation Nippon シンポジウム 2014 年度第 1 回)

15
経済効果推定を利用する際の留意点 時間軸の考慮
いつの時点で実現される効果か?
どういった経路で実現される効果か?
コストとベネフィットの考慮 その効果を実現するためにはどの程度の初期投資&運営費用が必要となるか?
「勝ち組」と「負け組」の存在への配慮 負け組に対して十分なケアがないと政治的には実現できない
環境整備の視点 想定された効果を得るためにはどういった環境整備が必要か
ACIL Tasman ( 2008 )では十分な環境整備がなければ 6.3~ 7.5%ロスが生じると予測
政府介入の必要性の再検討 その効果は市場メカニズムだけでは達成できないのか?
政府介入が必須であるとしてもその形態は?
政府の失敗の可能性は常に考慮すべき
2014/4/22オープンデータの経済効果を考える:何を期待し、どう推進するか?( Innovation Nippon シンポジウム 2014 年度第 1 回)

16
結果の解釈にあたって。
2014/4/22オープンデータの経済効果を考える:何を期待し、どう推進するか?( Innovation Nippon シンポジウム 2014 年度第 1 回)
「オープンデータ政策の推進によって公共データが利用しやすくなれば、 1800 ~ 3500億円程度(総効果の 7.5 %に相当)の経済効果が得られる。」という一見して小さな推計結果はオープンデータ政策の総効果を示すものではない!!
CGE は比較静学分析なので時間軸が考慮されていない 7.5% は長期均衡が達成した後の効果
移行経路における議論は別物 勝ち組産業と負け組産業の利害調整
労働力移動、ビジネスプラクティス、業界慣行の変更の円滑化
そもそも望ましいとされる均衡に経済全体として移行するか否か、移行するにしても最適なスピードで移行するか否かは別問題 全く別の均衡が実現される可能性もありうる
ファシリテーターとして、あるいは、コーディネーターとしてのオープンデータ政策の経済価値は別に検討すべき

17
参考文献 ACIL Tasman (2008) “The value of spatial information: The impact of modern
spatial information technologies on the Australian economy,” report prepared for the CRC for Spatial Information and ANZLIC, Australia, the Spatial Information Council. Available at: http://www.crcsi.com.au/Documents/ACILTasmanReport_full.aspx
Vickery, G. (2011) “Review of recent studies on PSI re-use and related market developments.” Available at: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf//document.cfm?doc_id=1093
2014/4/22オープンデータの経済効果を考える:何を期待し、どう推進するか?( Innovation Nippon シンポジウム 2014 年度第 1 回)