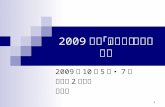平成29年度 統計年報 - city.kawasaki.jp · 川崎市上下水道局 平成29年度 統計年報 水道事業・工業用水道事業・下水道事業
2014年 平成26年 10月9日 木曜日 産学連携による人材育成と高専 …€¦ ·...
Transcript of 2014年 平成26年 10月9日 木曜日 産学連携による人材育成と高専 …€¦ ·...

産学連携による人材育成と高専教育の再発見高専教育について卒業生を交えパネル討論を行った
人材育成研究会
三菱重工業技術統括本部ものづくり技術部技監・主幹PJ統括大坂弘美氏
東京工業高等専門学校校長古屋一仁氏
高専OBOGから見た高等教育の利点と課題
パネルディスカッション
企業と高専との産学協同教育への可能性
優れた生産技術者の育成に期待
産業に適応したカリキュラム提供
高等専門学校は学校教育
法で、深く専門の学芸を教
授し職業に必要な能力を育
成する目的が定められてい
る。1962年に制度が創
設され、現在全国に
校
キャンパスの国立高専が設
置され、本科の在学生数は
4万8000人以上だ。卒
業後は就職、進学、編入学
と多様なキャリアパスがあ
り本科の昨年の求人倍率は
・4倍である。
歳からの5年一貫の技
術者教育で、高校のような
学習指導要領がないことも
あり、柔軟で産業に適応し
たカリキュラムも提供でき
る。課題解決型の実践的教
育が特徴で、何を教えるか
よりも、学生がどこまで到
達したかを重視して、目標
とする最低限の能力水準や
習得内容を明示する「モデ
ルカリキュラム」といった
ものを、今後各高専が正式
に導入していく。
また企業との産学協同教
育を重視しており、
高専
のほぼすべての学科・専攻
はインターンシップを授業
に取り入れ単位化してい
る。企業への教員インター
ンシップも、オムロンの協
力を得て始めている。特色
ある取り組みとしては、3
年次から合計
週間就業を
繰り返し企業文化に慣れて
理解を深める阿南高専
徳
島県阿南市
、地元企業の
協力を得て日常的に報酬を
得ながら実践的な体験学習
をする「企業書生制度」を
設けた長野高専
長野
市
、企業の優れた技術や
製品を一般の人に説明した
り社員と共同プロジェクト
を進める「企画広報型イン
ターンシップ」を実施する
東京高専
東京都八王子
市
などがある。
三菱重工との連携につい
ては各高専の製造実習の現
場に、生きた技術を取り入
れられる可能性に期待して
いる。ロボットコンテスト
などへのサポートや、I
E、VE
バリュー・エン
ジニアリング
についての
指導もしていただける。
また東京高専は2011
年から地域社会を教育開発
フィールドとして、例えば
地域のお年寄りや介護施設
に問題解決となるサービス
や機器を作って使ってもら
う「社会実装プロジェク
ト」に取り組んでいる。何
を創り出すべきかを学生が
考え、探し当てる。これは
自分はイノベーションを起
こせる、という自信になる
はずだ。
モノづくり日本会議は9月9日、東京・一ッ橋の如水会館で人材育成研究会「産学連携による人
材育成と高専教育の再発見」を開いた。「産学協働教育」に向けた内外の状況を報告した上で、昨
年包括提携協定を結んだ三菱重工業と国立高専機構から提携の成果や今後の方向性などを発表。さ
らに高専卒業者も交えたパネルディスカッションを通じて、産学連携のあり方や高専教育の成果な
どについて来場者に訴えかけた。
■ パネリスト
さくらインターネット 社長
田中 邦裕 氏
NTTコミュニケーションズ
クラウドサービス部
大川 水緒 氏
東京工業高等専門学校
古屋 一仁 氏
三菱重工業
大坂 弘美 氏
■ コーディネーター
日鉄住金総研
山藤 康夫 氏
田 中 氏
大 川 氏
自由な環境の中チャレンジ
山藤 今日は高専を卒業
し、起業されたり企業の最
前線で活躍されている若い
二方をお招きした。
田中 舞鶴高専在学中の
1996年に、レンタルサ
ーバ事業のさくらインター
ネットを創業し、
年に会
社設立した。当時は若い起
業と言われたが、もっと大
人になってからの方がリス
クが大きいのでは、とも考
えた。現在は大阪、東京、
北海道の3都市に5カ所の
データセンターを展開。高
専の自由な雰囲気に後押し
されたと感じている。
大川 東京高専本科の
時、チームを組んで全国高
等専門学校プログラミング
コンテスト
プロコン
に
出場。専攻科ではマイクロ
ソフト主催のITコンテス
ト「イメージカップ」世界
大会で準優勝した。大きな
思い出だ
古屋 いまは新しいサー
ビスが生まれる時代。学校
では基礎の学問を教えてい
る。その上に自分のアイデ
アを出しチャンスをものに
すれば学生時代に閉塞感も
へいそく
感じないはず。大川さんの
場合、得意分野の異なる4
人が集まり、チームワーク
を次第に身につけたことを
よく覚えている。
大坂 私
は高専にい
た5年間は
もっぱらス
ポーツ。時
代は変わっ
たと思う。
動画で拝見
した大川さ
んのプレゼンテーションは
素晴らしいもので、どこで
も高く評価されると感じ
た。
山藤 すべての学生がめ
ざましい成果を上げるとは
いかないのでしょうが。
古屋 彼らのような成果
を、普通の学生にも経験で
きるようにすることは学校
側の責任だと思う。中教審
の答申でも
主体的な学び
を
生涯学び続けることの
重要さ
と
いったこと
がうたわれ
ている。高
専はともす
ると成果を
急いできた
側面もある
かもしれな
い。カリキュラムの見直し
なども進めていきたい。
大坂 理系学生の基礎学
力の低下を心配している。
大学などにも働きかけては
いるのだが、企業側として
は入社後の若年教育が重要
となっている。
山藤 高専教育の良さと
は。
田中 自由な環境が印象
的。実は周囲には落第した
者も結構いて、自己責任で
学ばなければならないと強
く感じた。
大川 ロボットコンテス
トや組み込みマイスターへ
の挑戦といったプログラム
が用意されていて、課外活
動も含め、頑張る学生には
先生方のサポートがとても
手厚かった。
山藤 若い二人ですが学
生時代を振り返って感じる
ことは。
田中 やりたいことに没
頭できた。寝る間を惜しん
でロボコンやいろいろなこ
とに挑戦した。
大川 私が高専プロコン
に取り組み始めたのは5年
生の時から。それまでは漫
然と過ごしていた。もっと
早く面白さに気づいていれ
ばよかった。
三菱重工・高専機構包括連携協定の現状
私は佐世保高専機械工学
科の卒業生で、高専機構の
運営協議員を務めている。
また当社の技術教育改革の
統括部隊である技術統括本
部ものづくり技術部で、高
専機構との包括連携協定の
実行部隊の一員として加わ
ってきた。そうした中から
考えるのは、人間成長と教
育の関わり方として、学校
教育と企業教育が相互に補
い合う体制作りが重要だと
いうことだ。
高専機構との包括連携協
定の前提として、機構が実
践的・創造的な技術者育成
に向けて新しいカリキュラ
ムを策定するなど独自性を
持った取り組みを進めてい
ることがあった。一方で当
社は「次世代を担う人の育
成に貢献する」ことを目標
に掲げ、モノづくりの基盤
を支える技術者の育成・支
援を進めてきた。そこで昨
年3月に協定を結び、若手
人材の育成・強化を目指す
こととなった。具体的な手
段として当初国内外のイン
ターンシップ、講師の相互
派遣、共同研究などを想定
した。
昨年度はこれからの具体
的な取り組みについて協議
した上で、意見交換や高専
教育の現場の調査を行い、
当方のマレーシアの肥料プ
ラントへの海外インターン
シップも実施した。さらに
相互研鑽のメニューを考
けんさん
え、本年度は高専教員が当
社の生産技術ワークショッ
プに参加するほか、国内各
事業所へのインターンシッ
プも進めている。どうして
も現場経験や企業の最新情
報が少なくなりがちな教員
の皆さんに、企業側が経験
談を講義するなど支援して
いる。教員側にはIE
イ
ンダストリアル・エンジニ
アリング
や生産管理の授
業がほとんどないことか
ら、企業が行っている教育
の手法も提供している。
ここで製造技術と生産技
術の違いについて考えた
い。これは「技」と「術」
すべ
の違いとも言える。技は目
的を果たすための手段で、
単一解といったもの。術は
手段・手法を体系的にまと
めた「面」的なものだ。技
術者教育としては製造技術
者だけでなく、IEなどを
取り入れ目的のものを効率
よく作る生産技術者の育成
を目指さなければならな
い。こうしたモノづくりを
統括する人材の育成を高専
に大きく期待している。
企業に役立つ学生を育成
日鉄住金総研コンサルティング事業部特別研究主幹山藤康夫氏
モノづくり若手人材育成のための「産学協働教育」を考える
人材育成研究会ではこれ
まで「グローバリゼーショ
ンと人材育成」「企業にお
ける人材育成」「産学協働
教育」といったテーマにつ
いて議論してきた。そうし
た中から、例えば機械系製
造業が求めるグローバル人
材像として、「技術力」と
「創造力」の双方のスキル
を備えて新しい価値を生み
出すことなどを探ってき
た。企業は激化するグロー
バル競争を念頭に、新興国
に負けない活力を持った人
材を育成しなければならな
い。しかし一方で若手技術
系人材に対し基礎学力不足
などを懸念する声もあり、
産業界は大学の理工系教育
に対し国際水準の学力や海
外インターンシップ拡充な
どを求めている。また企業
側も求める人材の能力や学
力について明確にしなけれ
ばならないし、奨学金制度
やインターンシップを通じ
て高校・高専・大学の人材
教育に協力すべきだ。つま
り産学協働教育によって、
企業に役立つ学生を育成し
ていくという考えだ。
今回は三菱重工業と国立
高専機構の連携が1年を経
過して、どんな成果を上げ
てきたか伺おうということ
が開催の発端。同時に高専
教育という日本独自のスタ
イルの素晴らしさについて
も再認識してもらいたい。
本日登壇いただく高専卒業
生の国内外での活躍を見
て、私は心から感動した。
本研究会を今後のさらなる
産学連携の必要性を考える
機会としたい。
( ) 2014年 平成26年 10月9日 木曜日