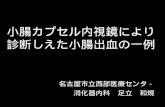1.肝動注リザーバー留置の基本技術とコツRep....
Transcript of 1.肝動注リザーバー留置の基本技術とコツRep....
-
第40回日本 IVR学会総会「技術教育セミナー」:松枝 清
1 . 肝動注リザーバー留置の基本技術とコツがん研究会有明病院 画像診断部
松枝 清
はじめに
肝動注化学療法は,肝というひとつの臓器に存在する,多くの場合多発性の腫瘍に対して,効率的に薬剤を動脈から注入して分布させることで,より高い抗腫瘍効果を得ることを目的とした治療法である。この治療法は,TACEと同様に血管造影に引き続いて行われることもあるが,連日あるいは週単位で,数ヵ月から年余に渡ってくり返し行う必要がある場合には,肝動脈に薬剤を注入するためにカテーテルを留置し,これをリザーバーに接続して皮下に埋設して施行する。これによって患者には,頻回の血管造影検査という負担なく動注化学療法を継続できる。こうしたリザーバーを用いた肝動注化学療法(肝動注リザーバー)を成立させるためには,適切な薬剤分布を得るためのカテーテル留置が不可欠であり,これには我が国で培われてきた“技術”が必要である。
リザーバーとは
カテーテルを体内に留置して行う医療行為を,患者のQOLを損なうことなく,安全かつ簡便に,繰り返し施行することを目的とした器具で,以下のような特徴がある。①体内に留置したカテーテルと接続し,長期的にシステム全体を皮下に埋没させることができる。②カテーテル内腔と交通する内室を,経皮的に穿刺することでカテーテルを介して薬剤の注入あるいは体液の回収が繰り返し行える(図1)。
③器具自体には持続注入,持続排液などのポンプ機能をもたない。
動注リザーバー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 第40回日本IVR学会総会「技術教育セミナー」‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
肝動注リザーバーを用いた治療に必要な技術
肝動注リザーバーを留置し,適切な薬剤分布を維持しながら治療を継続していくためには,表1のような事項に精通する必要がある。こうした技術のめざすところは,安全かつ確実に,そして長期にわたって,“肝”への,適切な薬剤注入ルートとして機能することであり,これは肝動脈血流を制御することである。また基本的に選択される“技術”と,症例ごとに応用される“技術”がある。けして難易度や煩雑さを, “技術”の実行性あるいは選択における言い訳にせず,複数の手技に精通し,個々の症例において, “最も適した留置法”を選択できるようにする。そしてシステムトラブルに対応するための“技術”や,薬剤分布を維持するための“技術”といったメインテナンスに関する“技術”も大切である1)。
Percutaneous Catheter Placement for Hepatic Arterial Infusion-Basic Technique and Tips-
Department of Diagnostic Imaging, Cancer Institute HospitalKiyoshi Matsueda
Redistribution, Side hole catheter, Tip-fixation methodKey words
(463)87
図1 コアレスニードルを穿刺したリザーバーの断面写真(セルサイトポート)
-
第40回日本 IVR学会総会「技術教育セミナー」:松枝 清
88(464)
技術教育セミナー / 動注リザーバー
肝動注リザーバー留置技術の目指すところ
側孔型カテーテル先端固定留置法を用い,90%を上回る技術的成功,90%を上回る治療導入可能率,そして留置後1年における肝動脈開存率が80%以上というのが,これまでの報告をふまえた数値目標である2~4)。
肝動注リザーバー留置の基本技術
表1に示す技術のなかで,本稿では,血流改変の複数肝動脈の一本化と肝外薬剤流出動脈の処理,カテーテル・ポート留置におけるカテーテル留置法について詳述する。
1.血流改変 血流改変の目的は,①留置カテーテルから注入される薬剤が肝全体に分布する,②肝以外の臓器(胃・十二指腸・膵など)に薬剤が分布しない,③カテーテル留置が確実に行え,かつ安定した留置状態が維持できる,④カテーテルが留置されるあるいは留置された肝動脈以外からの,肝への動脈性供血を遮断することである。
〈演習1〉血流改変の対象となる血管を理解するための血管模式図に,血管名をあてはめてみよう(図2)。 血流改変の対象となる血管には,転位/副右肝動脈(rep./acc. RHA),転位/副左肝動脈(rep./acc. LHA),右胃動脈(RGA),胃十二指腸動脈(GDA),副左胃動脈(acc. LGA),上十二指腸動脈(SDA),後上膵十二指腸動脈(PSDA),転位後上膵十二指腸動脈(rep. PSPDA),背膵動脈(DPA),肝鎌状間膜動脈(falciform a.),下横隔動脈(IPA),副腎動脈(Ad.A),内胸動脈(ITA),左胃動脈(LGA),胃大網動脈(GEpA)などがあるが,血管造影所見からこれらの血管解剖を瞬時にかつ確実に理解すること,そして非典型的な血行動態の存在に気づきそれを確認し対処できるといった技術も必要とされる。①複数肝動脈の一本化 原則的には,転位/副肝動脈を塞栓して,総肝動脈から分岐する肝動脈に一本化する。転位右肝動脈の場合,胃・十二指腸・膵に分岐する枝の末梢で,肝内肝動脈枝分岐の手前で塞栓する。転位左肝動脈の場合,最終胃枝分岐後で肝内動脈枝分岐の手前で塞栓する。すなわち塞栓形態は血管の幹部塞栓で,0.035 inchプッシャブルコイルによる塞栓を基本とするが,コイルアンカーの併用,フローコントロール下での塞栓などの工夫が必要であることも少なくない。もしも転位肝動脈にマイクロカテーテルしか入らない場合には,フローコントロールの併用や,Fibered IDC/GDCの使用を考慮する。 最も注意すべきなのはコイルの肝動脈分岐にかかるmigrationであり,摘出をまずは試みるが,この操作によってより致命的な血流分布障害を起こさないことに注意が必要で,放置するあるいはより末梢に押し込むといった対応のほうが事態を悪化させないことも少なくない。 複数肝動脈の一本化という血流改変によって,右下横隔動脈などからの肝外性供血を惹起あるいは増加させる可能性があることに留意する。前にはなかった肝外性供血が血流改変後に顕在化することはよくあるので,転位右肝動脈を塞栓した後には必ず右下横隔動脈を再度造影するくらいの注意を要する。 転位肝動脈への一本化を図ることの是非についてのコンセンサスはないが,肝外性供血路(側副路)の発達による不均等血流分布を招く可能性があり,転位肝動脈に留置した場合の肝動脈閉塞頻度が高いといった指摘がある。
〈演習2〉LGAから分岐する転位左肝動脈および上腸間膜動脈(SMA)から分岐する転位右肝動脈がある症例で,総肝動脈から分岐する中肝動脈(MHA)に肝動脈血流を一本化してみよう(図3)。 血流改変は難しいもの,仮に失敗した場合の影響が大きいものから行うのが原則である。この場合にはまず,①RGAの根幹部塞栓をはじめに行う。これは
血管解剖と血行動態の把握血流改変 ①複数肝動脈の一本化 ②肝外薬剤流出動脈の処理 ③肝外性供血路への対応カテーテル・ポート留置 ①動脈アクセス(経路) ②カテーテル留置法(側孔型カテーテル先端固定法)薬剤分布の評価と管理 ①薬剤分布の評価 ②システムトラブルへの対応
表1 肝動注リザーバーを用いた治療に必要な技術
図2 演習1:血流改変の対象となる血管
-
第40回日本 IVR学会総会「技術教育セミナー」:松枝 清
技術教育セミナー / 動注リザーバー
(465)89
RGA塞栓が必ずしも容易ではないこと,そしてRGA塞栓時にMHAを損傷あるいはコイルが逸脱したりした場合にはMHAへの一本化はできなくなる可能性を考えてのことである。なお肝動脈が3本から構成される場合,RGAはいわゆるMHAの根幹部から分岐することが多い。RGAの根幹部塞栓が成功したら,次はSMAから分岐する,② rep. RHAを幹部塞栓する。Rep. RHAの根幹部からは,膵・十二指腸・空腸に分布する小さな枝(↑)があることに注意し,この遠位で幹部塞栓する。そして,③ rep. LHAは,胃に分布する細かな枝(↑)のすべてを越えた部位で塞栓する。カテーテル留置および先端固定がより簡単になるように,④PSPDAを先に塞栓し,⑤GDAでの側孔型カテーテル先端固定法でカテーテルは留置する。②肝外薬剤流出動脈の処理 薬剤流出による厄の原因となる動脈分枝を多くは根
幹部で塞栓するもので,枝払いといわれることがある。代表的な対象は,RGA,GDA,acc. LGA,SDA,PSPDA,rep. PSPDA,DPA,falciform a.などである。 右胃動脈は通常固有肝動脈ないし左肝動脈から分岐することが多いが,必ず前向きに分岐し,くるっと反回して1本のまま小彎沿いに走行し,胃角付近で左胃動脈の後枝と吻合する(図4)。小彎に向かうので血管分岐と走行をイメージして探るといい。複数の幽門枝を近位から分岐することに注意して,これを塞栓部位より手前に残さないように根幹部塞栓を行う。順行性に右胃動脈を選択できない場合には,左胃動脈側との吻合を利用して右胃動脈へアプローチする方法も有用である。習熟すれば90%以上の成功率でRGA塞栓は可能であることが報告されている5)。 上十二指腸動脈はGDA,PSPDA,PHA,RGAなどから分岐し,十二指腸球部上面に分布する(図5)。こ
図4 右胃動脈の血管解剖 a : 総肝動脈造影 b : 右胃動脈走行を示す造影CT(MIP)
a b
図3演習2:血流改変複数肝動脈の一本化
a b
①②
③
④
⑤
-
第40回日本 IVR学会総会「技術教育セミナー」:松枝 清
90(466)
技術教育セミナー / 動注リザーバー
うしたマイナーな分枝への薬剤流入も,潰瘍形成の原因になることがある。 枝払いでは細い動脈の塞栓が必要なことも多く,塞栓にはマイクロコイルが用いられるが,コイルのみによる塞栓が難しい場合には液体塞栓物質NBCA(n-butyl-2-cyanoacrylate)とLipiodolの混合液を併用する。コイルと同様の近位塞栓を目的とした場合はNBCA:Lipiodol=1:1.5,肝外性供血路の塞栓など鋳型塞栓を目的とした場合にはNBCA:Lipiodol=1:8~10の混合比を目安にしている。
2.カテーテル・ポート留置①カテーテル留置法 過去のカテーテル留置法には,主にはGDAから逆行性にカテーテルを挿入する外科的(開腹留置)や,経皮的留置として投げ込み法あるいはCHAコイル法などがあったが,カテーテル先端の移動や肝動脈の中枢型閉塞が起こり長期的に安定した動注の継続に問題があった(図6)。如何に留置カテーテルが移動しにくく,肝動脈の中枢型閉塞が起こりにくいカテーテル留置が
できるか,という命題に対し編み出された方法が側孔型カテーテル先端固定留置法である(図7)。 側孔型カテーテル先端固定留置法は,カテーテルに設けた側孔を薬剤注入に適した位置に置いて,カテーテル先端を薬剤注入に影響のない血管に固定するものである。カテーテル固定に用いる血管により,胃十二指腸動脈に固定する場合はGDA coil法,脾動脈に固定する場合はSpA coil法と呼ばれる6)。いわゆる投げ込み法といわれる過去のカテーテル留置法と比較して,肝動脈開存率は1年でおよそ80%と有意に高いことが確認されている3)。 この側孔型カテーテル先端固定留置法の進化型として側孔型細径カテーテル先端固定留置法があり,細径カテーテルに側孔を設けて薬剤注入に適した位置に置き,カテーテル先端を薬剤注入に影響のない血管に固定するもので,胃十二指腸動脈(GDA coil法)のみでなく肝動脈末梢(肝動脈末梢固定法)にも用いられる
(図8)。 カテーテル留置においては,留置の確実性,留置カテーテルの安定性,留置カテーテルによる血流動態へ
図6 過去のカテーテル留置法 参考文献6)より引用
RGA
GDA
CHA
a b
図5上十二指腸動脈a : 総肝動脈造影b : 選択的上十二指腸動脈造影
a:外科的(開腹)留置 c:CHAコイル法b:投げ込み法
-
第40回日本 IVR学会総会「技術教育セミナー」:松枝 清
技術教育セミナー / 動注リザーバー
の影響,血流改変の難易度などを総合的に勘案して決定することが重要である。
〈演習3〉GDAの血流が求肝性であった場合のカテーテル留置法を考えよう(図9)。
(467)91
いろいろな留置法は考えられるが,①RGAを根幹部塞栓後,側孔がGDA近位にくるように,カテーテル先端を右胃大網動脈末梢に固定する,②RGAを根幹部塞栓後,GDAは開存させたまま,側孔は固有肝
a b
図7側孔型カテーテル先端固定留置法a : GDAコイル法b : SpAコイル法参考文献6)より引用
RGA
GDA
SPA
LGA
DPAside hole
a b
図8側孔型細径カテーテル先端固定留置法(進化型)a : GDAコイル法b : 肝動脈末梢固定法
図9 演習3:GDAの血流が求肝性であった場合 b : ①右胃大網動脈固定 c : ②肝動脈末梢固定
a b c
-
第40回日本 IVR学会総会「技術教育セミナー」:松枝 清
技術教育セミナー / 動注リザーバー
動脈において,肝動脈末梢固定法を用いて留置するといった方法がある。
〈演習4〉右肝動脈がGDAに転位している場合のカテーテル留置法を考えよう(図10)。 RGAを塞栓して総肝動脈に側孔をおいて先端をGDAに固定する方法①だと,laminar flowにより薬剤分布に不均衡が生じる可能性がある。この血管解剖は左肝動脈が総肝動脈から分岐しているともいえるが,もし不均衡分布が生じた場合,LHAを幹部塞栓して肝動脈血流を一本化することで不均衡を解消できる可能性がある②。薬剤分布の状況はflow check(DSAおよびCTA)によって定期的にチェックする必要があり,適切な血流分布を得るための血流改変は何回でも行う心構えが大切である。
その他
大腿動脈経由でカテーテルを留置した場合の穿刺部の止血には,縫合止血デバイスやコラーゲン使用吸収性局所止血材を用いるといった方法もあるが,カテーテル刺入部皮下組織結紮(シース(カテーテル)が大腿動脈を貫いている部分にできるだけ近いところで,シースを取り巻くように結紮糸をかけておき,シース抜去と同時に周りの皮下組織ごと結紮する)方法は簡便かつ有効である7)。
おわりに
肝動注リザーバーは今,再び活躍の時を待つ境遇にあるが,これまで培われてきた様々な技術は,様々なIVRの局面で活かすことができる内容を含んでいると考えられる。 なお,演習1~4に用いたスケッチは,荒井保明先生の作成された,質の高い共同研究を行うための…
経皮的肝動注カテーテル留置法マニュアル(特定研究28,29)から,許可を得て転用させていただいた。
【参考文献】1) リザーバー研究会編:リザーバー療法. 南江堂, 東京, 2003, p21 -22.
2) Yamagami T, Iida S, Kato T, et al: Using n-butyl cyanoacrylate and the fixed-catheter-tip technique in percutaneous implantation of a port-catheter system in patients undergoing repeated hepatic arterial chemotherapy. AJR Am J Roentgenol 179: 1611 -1617, 2002.
3) Seki H, Kimura M, Yoshimura N, et al: Hepatic arterial infusion chemotherapy using percutaneous catheter placement with and implantable por t: assessment of the factors affecting patency of the hepatic artery. Clin Radiol 54: 221 -227, 1999.
4) Tanaka T, Arai Y, Inaba Y, et al : Radiologic placement of side-hole catheter with tip fixation for hepatic arterial infusion chemotherapy. J Vasc Interv Radiolo 14: 63 -68, 2003.
5) Inaba Y, Arai Y, Matsueda K, et al: Right gastric artery embolization to prevent acute gastric mucosal lesions in patients undergoing repeat hepatic arterial infusion chemotherapy. J Vasc Interv Raiolo 12: 957 -963, 2001.
6) 竹内義人, 荒井保明, 稲葉吉隆, 他:肝動注リザーバー療法における側孔注入式カテーテル先端固定留置法についての検討-特に肝動脈閉塞防止効果について-. IVR会誌11:471 -476, 1996.
7) リザーバー研究会編:リザーバー療法. 南江堂, 東京, 2003, p39 -42.
92(468)
図10 演習4:右肝動脈がGDAに転位している場合
① ②
-
第40回日本 IVR学会総会「技術教育セミナー」:佐藤洋造,他
2 . 留置困難例に対する技術愛知県がんセンター中央病院 放射線診断・IVR部
佐藤洋造,山浦秀和,加藤弥菜,井上大作,稲葉吉隆
はじめに
“まずRGAとPSPDAを塞栓して,次に右胃大網動脈までガイドワイヤを挿入して,慎重に留置カテーテルに交換して…,よし,今日もイメージトレーニングもばっちり!!”と気合を入れて血管造影を行うと…,“あれ? この血管なに? どうしよう…(- -;)” ある程度の症例数を経験すると,このようにいわゆるGDAコイル法で上手くいかない症例にどこかで遭遇する。そのような時に,本稿の内容が少しでも参考になれば幸いである。
カテーテル留置困難なケース
肝動注リザーバー留置困難例として様々な要因が挙げられるが,体型や血管蛇行などの要因は今回除外し,3つの項目に分類した。①解剖学的要因に伴う技術的に留置が困難な症例,②良好な肝内血流分布の維持が困難な症例,③システム不具合に伴う再留置の症例,これらの項目について当院での症例をもとに解説する。原則は左鎖骨下動脈経由で側孔型カテーテル留置法を用いており,Celiac Aから末梢側にカテーテル細径部を留置するいわゆる“入江法”で施行している1~4)。 個人的には留置カテーテルとして,Long tapered W-spiral catheter(パイオラックス)を好んで用いている。側孔型カテーテル留置法の詳細は松枝先生の項を参照いただきたい。
動注リザーバー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 第40回日本IVR学会総会「技術教育セミナー」‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
1.技術的困難例 Replaced HAを代表とする解剖学的要因に伴うものであり,Celiac Aの狭窄・閉塞例や外科的手術に伴う血管解剖の変化も原因となりうる。また腫瘍の血管増生に伴う血流の変化なども問題となることがある。
症例1.Replaced HA例解剖:SMAよりReplaced RHA,LGAよりReplaced LHAが分岐する,いわゆる“3本バラバラ”の症例である(図1a,b)。留置法:定型的にReplaced RHA,Replaced LHAを塞栓し,MHAに一本化した後,GDAコイル法で留置した(図1c)。
症例2.Celiac A閉塞例①解剖:動脈硬化に伴うCeliac A閉塞例であり,SMAより膵頭部 arcadeを介して肝動脈が描出される。CHAの血流は遠肝性である(図2a,b)。問題点:Celiac A経由の留置は順行性アクセスは困難であり,SMAより膵頭部arcadeを介してCeliac Aより大動脈へとガイドワイヤを進め,pull-through法を用いる必要がある。SMA経由の留置では,膵頭部arcadeを介してカテーテル留置を行う必要がある。またCHAは遠肝性血流であり,側孔の位置も問題である。留置法:膵頭部arcade が比較的発達しており,SMA経由で膵頭部 arcadeを介してカテーテル先端を肝動脈の末梢側に留置し,カテーテル側孔をPHAに作成
Side-hole Catheter Placement for Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy in Technically Difficult Cases
Department of Diagnostic and Interventional Radiology, Aichi Cancer Center HospitalYozo Sato, Hidekazu Yamaura, Mina Kato, Daisaku Inoue, Yoshitaka Inaba
Side-hole Catheter Placement, Replaced hepatic artery, Arterial stenosisKey words
(469)93
略語一覧腹腔動脈:Celiac A,総肝動脈:CHA,固有肝動脈:PHA,胃十二指腸動脈:GDA,後上膵十二指腸動脈:PSPDA, 前上膵十二指腸動脈:ASPDA,上腸間膜動脈:SMA,左胃動脈:LGA,右胃動脈:RGA,右胃体網動脈:Rt GEPA, 転位右肝動脈:Replaced RHA,転位左肝動脈:Replaced LHA,中肝動脈:MHA
-
第40回日本 IVR学会総会「技術教育セミナー」:佐藤洋造,他
94(470)
技術教育セミナー / 動注リザーバー
図1 a : Celiac A造影,b : SMA造影 LGAよりReplaced LHA,SMAよりReplaced RHAが分岐する。 c : Flow check。MHAに一本化した後,GDAコイル法で留置した。
図2 a : SMA造影,b : 膵arcade造影 SMAより膵頭部arcadeを介して肝動脈が描出される。 c : Flow check。SMA経由で膵頭部arcadeを介して肝動脈末梢固定法で留置した。
図3a : SMA造影。SMAより膵頭部
arcadeを介して肝動脈が描出される。本例ではRGAが発達している(矢印)。
b : Flow check。SMA経由で膵頭部arcadeを介してカテーテル先端をRGAに留置した。
a b c
a b c
a b
-
第40回日本 IVR学会総会「技術教育セミナー」:佐藤洋造,他
技術教育セミナー / 動注リザーバー
(471)95
図4 a : SMA造影,b : Celiac A造影 術後変化などによるCeliac A狭窄例であり,CHAの血流は遠肝性である。 c : Flow check。Celiac A経由でいわゆるCHAコイル法で留置した。
図5 a : Celiac A造影。LGAよりReplaced LHA,SMAよりReplaced RHAが分岐する。 b : Flow check。カテーテル先端をASPDAに留置して,GDAコイル法で留置した。
した(図2c)。
症例3.Celiac A閉塞例②解剖:SMAより膵頭部arcadeを介して肝動脈が描出され,本例ではRGAが発達している(図3a)。留置法:SMA経由で膵頭部arcadeを介してカテーテル先端をRGAに留置し,カテーテル側孔をPHAに作成した(図3b)。RGAの塞栓も兼ねた留置法である。
症例4.Celiac A狭窄例解剖:術後変化などによるCeliac A狭窄例であり,CHAの血流は遠肝性である(図4a,4b)。問題点:通常のGDAコイル法ではCeliac A経由の血流が十分ではないため,早期肝動脈閉塞のリスクがある。肝動脈末梢固定法では,PHAが短く側孔を置く十分な距離がない。留置法:Celiac A経由でいわゆるCHAコイル法で留置した(図4c)。側孔はGDAに作成しており,膵頭部arcadeを介して十分な肝動脈血流が得られている。
症例5.胃癌術後症例解剖:Rt GEPAは切除後である(図5a)。問題点:GDAを塞栓して,肝動脈末梢固定法で側孔をPHA~CHAに留置するのが簡便であるが,膵頭部arcadeに十分ガイドワイヤを挿入することができれば,GDAコイル法も可能である。留置法:カテーテル先端をASPDAに留置して,GDAコイル法で留置した(図5b)。
症例6.食道癌術後症例解剖:Rt GEPAは再建胃管を栄養しており頭側へと走行している。LHAが実際はやや近位より分岐しており,PHAの長さは若干短い(図6a)。問題点:GDAコイル法は再建胃管の虚血のリスクがある。肝動脈末梢固定法はPHAが短めであり,laminar flowの影響で肝左葉の分布不良を来す可能性がある。留置法:LHAを塞栓した後,肝動脈末梢固定法で留置した(図6b)。Flow checkのCTAでは良好な血流分布が得られている(図6c)。
a b c
a b
-
第40回日本 IVR学会総会「技術教育セミナー」:佐藤洋造,他
96(472)
技術教育セミナー / 動注リザーバー
図6a : Celiac A造影。Rt GEPAは再建胃管を栄養しており頭側へと走行している(矢印)。
b : Flow check。LHAを塞栓した後,肝動脈末梢固定法で留置した。
c : CTA。良好な血流分布が得られている。再建胃管(矢印)。
ca b
図7a : SMA造影。SMAより膵頭部
arcadeを介して肝動脈が描出される。
b : ASPDA造影。Rt GEPAが再建胃管を栄養しており頭側へと走行している。
c : PSPDA造影。GDAから肝動脈および遠肝性血流のCHAが描出される。
d : Flow check。SMA経由でPSPDAを介してカテーテル先端をSPAに挿入し,CHAコイル法で留置した。
ca b
d
-
第40回日本 IVR学会総会「技術教育セミナー」:佐藤洋造,他
技術教育セミナー / 動注リザーバー
症例7.食道癌術後+Celiac A閉塞例解剖:動脈硬化に伴うCeliac A閉塞例であり,SMAより膵頭部arcadeを介して肝動脈が描出され(図7a),ASPDAの選択造影では,Rt GEPAが再建胃管を栄養しており頭側へと走行している(図7b)。PSPDAの選択造影では,GDAから肝動脈および遠肝性血流のCHAが描出される(図7c)。PHAの長さは短い。留置法:SMA経由でPSPDAを介してカテーテル先端をSPAに挿入し,CHAコイル法で留置した。カテーテル側孔はGDAに作成した(図7d)。
症例8.GDAの求肝性血流解剖:いわゆるcommon typeであるが,巨大肝転移巣による影響でGDAは求肝性血流となっている(図8a,b)。問題点:GDAコイル法では,GDA塞栓の際にコイルの肝動脈への逸脱のリスクを伴う。肝動脈末梢固定法はPHAが短めであり,laminar flowの影響で肝左葉の分布不良を来す可能性がある。留置法:コイルの逸脱のリスクを考慮しPSPDA,ASPDAを塞栓して,GDAを遠肝性血流に戻してからGDAコイル法で留置した(図8c,d)。ちなみに当科では血流改変において IDCなどのデタッチャブルコイルは一切使用していない。
2.肝内血流分布の維持が困難な症例 肝動注化学療法を行う際には,肝内血流分布の維持は必須項目である。肝動脈閉塞を避けるための肝動脈
(473)97
自体の血流維持も重要であるが,転位肝動脈例に対しての血流改変も一考の余地がある。
症例9.大腸癌肝転移例解剖:Celiac AよりReplaced RHA,LGAよりReplaced LHAが分岐する,いわゆる“3本バラバラ”の症例である(図9a,b)。肝右葉中心に肝転移巣を認める(図9c,d)。問題点:Replaced LHAは塞栓を行うとして,1.Re-placed RHAを塞栓して定型的にMHAに一本化を行うのか,2.MHAも塞栓して主病巣を栄養するReplaced RHAに一本化を行うのか。1.の方法で肝右葉の主病巣への血流が維持されるかであるが,経験的には胆管周囲動脈叢や右腎被膜動脈などからの側副路が発達すると思われる。留置法:胆管周囲動脈叢などの発達を防ぐためにGDAから総肝動脈までを塞栓し,Replaced RHAに一本化を行うこととした。MHAやReplaced LHAの血流は,Replaced RHAから吻合枝を介して描出される(図9e)。その後に肝動脈末梢固定法で留置した(図9f)。Flow checkのCTAでは左葉も含め良好な血流分布が得られている(図9g)。 ただし長期的な経過観察となると,Replaced RHAの血流でReplaced LHAの支配領域の分布を維持するのは困難と思われ,胃肝間膜などを介した側副路の発達があると推測される。本例では,あくまで肝右葉に主病変が存在するという条件での判断である5)。
図8a : Celiac A造影b : SMA造影巨大肝転移巣による影響でGDAは求肝性血流となっている。GDA(矢印)。c : Celiac A造影(塞栓後)d : Flow checkPSPDA,ASPDAを塞栓して,GDAを遠肝性血流に戻してからGDAコイル法で留置した。
ba c
d
-
第40回日本 IVR学会総会「技術教育セミナー」:佐藤洋造,他
技術教育セミナー / 動注リザーバー
3.再留置の症例 フィブリンシース形成やカテーテル破損・閉塞などのシステム不具合で動注継続が困難となる症例もあり,以前は原則既存の鎖骨下動脈経由のカテーテルを大腿動脈経由で抜去した後に,新たなカテーテルの再留置を行っていた。しかしLong tapered W-spiral catheterを用いたGDAコイル法で留置した症例では,既存のカテーテル牽引の際にテーパー部(側孔部)でカテーテルの断裂を来した症例も経験された。またカテーテル抜去の際に,GDAのコイル・血栓のCHA~PHA側への逸脱が危惧された症例で,抜去をせずに新たに細径リザーバーカテーテルを再留置した報告もある6)。
症例10.以前にLong tapered W-spiral catheterを用いたGDAコイル法を行った症例で(図10a),定期的なflow checkの際に,カテーテル周囲にフィブリンシースの形成が疑われた(図10b)。解剖:Celiac Aの造影でCHA~PHAに明らかな狭窄などの所見は認めなかった(図10c)。
留置法:Co-axial systemを用いて,non taper 2.7F W-spiral catheter(パイオラックス)を前区域枝に挿入し,側孔がPHAに位置するように留置した(図10d)。5Fフロスティカテーテル(テルモ・クリニカルサプライ)は腸骨動脈分岐部まで引いて,大腿部にマイクロカテーテル対応のサーディカポート(テルモ・クリニカルサプライ)を留置した(図10e,f)。CHA部には2本の2.7Fカテーテルが走行する状態であるが,経過観察中に明らかな肝動脈の閉塞所見を認めなかった。 本法はカテーテル抜去や血流改変の必要もなく,留置は非常に簡便である。以前の様な5Fカテーテルでは,このような留置法では肝動脈閉塞をきたす可能性が高いと思われる。当院では複数の症例で同じ留置法を施行しているが,現在のところ肝動脈閉塞をきたした症例は経験していない7)。
まとめ
留置困難という定義に適さない症例もあるかもしれないが,留置法に“工夫や考察を要する症例”を紹介
98(474)
図9a : Celiac A造影,b : LGA造影Celiac AよりReplaced RHA,LGAよりReplaced LHAが分岐する。c,d : 造影CT。肝右葉中心に肝転移巣を認める。e : Celiac A造影(塞栓後),f : Flow checkMHAやReplaced LHAの血流は,Replaced RHAから吻合枝を介して描出され,肝動脈末梢固定法で留置した。g : CTA。左葉も含め比較的良好な血流分布が得られている。
dg
a b ce f
-
第40回日本 IVR学会総会「技術教育セミナー」:佐藤洋造,他
技術教育セミナー / 動注リザーバー
(475)99
した。カテーテル留置自体には特殊な技術・デバイスは使用しておらず,血管解剖に適した留置法の選択を出来ることが“技術”と言えるかもしれない。いずれの場合でも重要なことは,まずは血管解剖を十分に把握することであり,近年マルチスライスCTの登場により術前に詳細な情報を得られるため,ある程度の留置プランを立てておくことが望ましい。 最後に付け加えておくが,肝動注化学療法においてカテーテル留置術を完結することが達成目標ではなく,良好な血流分布の維持によってもたらされる腫瘍縮小効果を得ることが目的であり,それにはflow checkなどの定期的なメンテナンスが必要不可欠である。
【参考文献】1) 荒井保明:肝動注化学療法, リザーバー療法, リザーバー研究会編. 南江堂, 東京, 2003, p60 -72.
2) IrieT: Intraarterial chemotherapy of liver metastases: implantation of a microcatheter-port system with use of modified fixed catheter tip technique. J Vasc Interv Radiol 12: 1215 -1218, 2001.
3) 佐藤洋造, 荒井保明, 松枝 清, 他:腹腔動脈以遠カテーテル細径部留置法(入江法)を用いたGDA-coil法についての検討, 第25回リザーバー研究会抄録集, p21, 2003.
4) Seki H, Shiina M: Placement of a long tapered side-hole catheter in the hepatic artery: technical advantages, catheter stability, and arterial patency. AJR Am J Roentgenol 187: 1312 -1320, 2006.
5) 佐藤洋造, 山浦秀和, 名嶋弥菜, 他:複数の肝動脈を有する症例に対しての, 転移右肝動脈への一本化における考案. 第34回リザーバー研究会抄録集, p53, 2009.
6) 大井博之, 関 裕史, 尾崎利郎, 他:肝動脈閉塞・カテーテル逸脱に対しカテーテルを抜去せずに別ルートから肝動注カテーテルを再留置した2例, 第31回リザーバー研究会抄録集, p35, 2007.
7) 佐藤洋造, 稲葉吉隆, 山浦秀和, 他:Long tapered W-spiral catheterを用いた細径部留置法後の肝動注リザーバー再留置~Co-axial systemを用いて~, 第33回リザーバー研究会抄録集, p89, 2008.
図10 a : Flow check(初回留置直後),b : Flow check(19ヵ月後) GDAコイル法を行った症例で,カテーテル周囲にフィブリンシースの形成が疑われた。 c : Celiac A造影。CHA~PHAに明らかな狭窄などの所見は認めなかった。 d, e, f : Flow check。Co-axial systemを用いて肝動脈末梢固定法で留置した。
da b c
e f