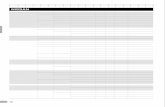00:00 (汽笛) >> テロップ 昭和 39 年(1964年)10 月5日1 【 00:00】 (汽笛) >> テロップ:昭和39年(1964年)10月5日 【 00:17 】 >> テロップ:
1927 年/ 昭和 2年 - Waseda University¹´/ 昭和2年 1・12...
Transcript of 1927 年/ 昭和 2年 - Waseda University¹´/ 昭和2年 1・12...
1927年/ 昭和 2年
1・12
横山大観および下村観山作「明暗」完成披露,1月下旬に図書館のホール突当り正面壁に掲げ
られる〈③ 240〉
1・15
安部磯雄,教授を辞任し講師となる〈③ 393,527〉
1・22
理事会,教授と政党委員長との両立は困難との見地から大山郁夫の教授解任を決議,「大山事
件」の発端となる〈③ 396〉
1・24
政治経済学部教授会,理事会の大山郁夫教授解任決議につき協議し,辞任勧告の形を採ること
を決議。また,大山留任を教授会に訴えるための学生大会開催〈③ 395,397〉
1・26
政治経済学部教授会,辞任勧告を断った大山郁夫の解職を決議〈③ 399−400〉
1・27
維持員会,大山郁夫解職を承認し,1月 26日付で発令〈③ 401〉
2・10
学生有志,大山郁夫の告別演説会開催,演説終了後,社会科学研究会を中心に学生自治同盟
結成〈③ 401−406〉
2・11
早稲田工手学校第 29回卒業式挙行,優等卒業生に徳永校長奨学賞が授与され,昭和 20年ま
で継続〈③ 645〉
2・18
2月 10日結成の学生自治同盟を無効とし,社会科学研究会会員 9人の退学処分を発表
〈③ 406〉
2・23
学生自治同盟結成に関与した社会科学研究会会員 28人の退学・停学・謹責処分を発表
〈③ 406〉
2・28
学生処分に反対する校友達,早稲田劇場で演説会開催,終了後のデモ行進で校友 5人検束
〈③ 407〉
3・24
学苑派遣留学生を対象に「外国留学生ニ関スル規程」を制定し,4月 1日より施行〈維持,
③ 744〉
6・8
「教職員任免規程」制定・施行〈③ 160−162,407〉
6・22
社会科学研究会主導下に雄弁会主催・新聞学会後援の大学擁護記念講演会が計画されたが,
実施を許可されず〈③ 410〉
6
専門部と高等師範部に配属将校が着任し,軍事教練開始〈③ 857〉
6
坪内博士記念演劇博物館設立発起人(代表渋沢栄一),募金趣意書を発表〈③ 429〉
7・11
ラグビー蹴球部,オーストラリア遠征に出発〈③ 541−542〉
9・22
ラグビー蹴球部,オーストラリア遠征より帰国〈③ 542〉
9・22
安部前野球部長記念会,戸塚球場で安部磯雄の胸像除幕ならびに安部体育奨励基金伝達式
挙行〈③ 527−528〉
10・4
専門部各科の教務主任を廃して科長を置き,政治経済科長に服部文四郎,法律科長に遊佐慶
夫,商科長に小林行昌嘱任〈学報 394・17,維持〉
10・19
護国寺の大隈重信墓所で故総長大隈侯爵記念事業報告祭挙行,大隈庭園で大隈綾子銅像除
幕式挙行〈③ 247〉
10・20
大隈庭園で招魂殿開殿式および招魂祭挙行,大隈記念講堂で創立 45周年・大隈記念講堂開
館記念式典挙行〈③ 247−248〉
10
正門筋向いに鉄筋コンクリート 3階建の早稲田大学出版部事務所竣工〈③ 499〉
11・7
社会科学研究会,学苑当局に無断で教室を使用してロシア革命記念講演会開催〈③ 412〉
11・26
中島会,前第一高等学院長中島半次郎胸像除幕式を第一高等学院玄関前で挙行〈学報 394・67〉
11・28
ロシア革命記念講演会無断開催の責任者の除籍処分に伴い社会科学研究会消滅
〈③ 412−413,『早稲田大学新聞』昭和 2年 12月 1日号〉
12・15−16
名誉教授坪内雄蔵の最終講義が大隈講堂で行われる(最終講義の嚆矢)〈③ 489−490〉
12・19
早稲田専門学校生,早稲田専門学校の専門部への校名変更を要求してストライキに突入(翌年 1月まで校名改称問題が続く)〈③ 217,『早稲田大学新聞』昭和 3年 1月 19日号〉
12
早稲田大学出版部,通信講義録『電気工学講義』創刊〈③ 501〉
この年
馬術部,体育会に加入〈③ 545〉
この年
応援部,第一応援歌「競技の使命」(五十嵐力作詞・山田耕筰作曲)発表〈③ 1139〉
1928年/ 昭和 3年
2・4
中学校・工業学校・工手学校卒業を入学資格とする夜間 2年 4学期制の早稲田高等工学校(機
械工学科,電気工学科,建築学科,土木工学科)の設置認可を東京府に申請〈『早稲田高等工
学校沿革に関する書類綴』〉
2・10
坂本三郎,早稲田専門学校長辞任し,平沼淑郎嘱任,また 4月開校予定の早稲田高等工学校
長に徳永重康嘱任〈維持〉
2・28
第二高等学院増築工事竣工〈③ 261〉
2
早稲田工手学校,入学資格を尋常小学校卒業から高等小学校卒業へ引き上げるとともに高等科
を廃止し,修業年限を 2年半にもどす〈③ 212〉
3・14
早稲田専門学校各科に教務主任を置き,政治経済科教務主任に小林新,法律科教務主任に大
浜信泉,商科教務主任に中田浩を嘱任〈維持〉
3・16
早稲田高等工学校の設置認可〈③ 221〉
4・16
早稲田高等工学校,始業式挙行〈③ 221〉
4
商学部,選択科目を新設し,第 2・3学年を第一分科(経済),第二分科(貿易),第三分科(金融),
第四分科(会計),第五分科(保険),第六分科(交通)の 6分科に分ける〈③ 672〉
5・3
卓球部,体育会に加入〈学報 400・12,③ 547〉
5・13
早稲田高等工学校,開校記念式挙行〈③ 222〉
6・30
坪内雄蔵,建築中の演劇博物館と,その建築費に充当するため牛込区余丁町の自宅との寄附を
申し出る〈③ 431〉
6
『早稲田大学新聞』,第 161号を以て休刊,新聞学会は秋に喜多壮一郎が会長を辞任したのち
後任会長不在のため消滅〈③ 421〉
7・1
10月開館予定の演劇博物館副館長に吉村(河竹)繁俊就任(館長は当分の間空席)〈『演劇博物
館五十年』140,290〉
8
第 9回オリンピック(アムステルダム大会)の三段跳で商学部生織田幹雄優勝,専門部商科生南
部忠平 4位,水泳 100メートル自由形で商学部生高石勝男 3位,水泳 800メートル・リレーで第
一高等学院生米山弘・専門部政治経済科生新井信男・明治大学生佐田徳平・高石勝男のチー
ム 2位〈③ 512−513〉
10・27
演劇博物館開館式挙行〈③ 432−433〉
10
早稲田大学出版部,通信講義録『電気工学予科講義』創刊〈③ 501〉
12・16
杉山前院長胸像設立発起人会,前第二高等学院長杉山重義胸像除幕式挙行〈学報 407・31〉
この年
早稲田高等工学校の親睦会である稲工会,『稲工会雑誌』創刊〈③ 226〉
この年
応援部,第二応援歌「早稲田応援歌」(三上於菟吉作詞・近衛秀麿作曲)および第三応援歌「天
に二つの日あるなし」(西条八十作詞・中山晋平作曲)発表〈③ 1139〉
1929年/ 昭和 4年
1・27
演劇博物館の宣伝や運営資金の獲得を目的とする演劇博物館後援会(会長市島謙吉)発足
〈③ 433,『演劇博物館五十年』291〉
3・14
中桐確太郎,高等師範部長辞任し,牧野謙次郎嘱任〈維持〉
4・22
金子馬治,演劇博物館長嘱任〈維持〉
4上旬
雄弁会員を中心とする早稲田学生新聞社,『早稲田学生新聞』創刊〈③ 421−422〉
5・10
二木保幾が前年 6月に会長を辞任したのち後任会長不在の雄弁会,継続願出期限切れのため
消滅〈③ 422〉
6・1
維持員を 25名以内から 35名以内に増員した改正校規施行〈③ 471,④ 407−413〉
10・8
維持員会,東伏見運動場接続地 770坪の購入を決議〈③ 262〉
10・20
高田早苗・坪内雄蔵・市島謙吉・浮田和民 4先生古稀祝賀会が開催され〈③ 658−659〉,高田早
苗は自身の古稀記念事業として教職員の退職金に充当するための 35万円の高田基金募集を祝
賀会に依頼〈③ 648−649,657−658〉
10
早稲田大学出版部,通信講義録『建築講義』創刊〈③ 501〉
10
内ヶ崎作三郎,講演部(編輯及講演部の後身)長を辞任し,喜多壮一郎就任〈③ 491〉
この年
拳闘部,体育会に加入〈③ 548〉
1930年/ 昭和 5年
1・28
大隈会館および大隈庭園敷地 9,055坪の土地所有権移転登記完了〈③ 181−182〉
3・17
川原田政太郎が中心となって開発中の早稲田式テレヴィジョン(機械式),東京朝日新聞社大講
堂で 5尺(1.5m)四方の画面への放映に成功〈③ 449−450〉
3
航空研究会設立〈③ 1147〉
3
三之輪−早稲田間に王子電気軌道路線(現在の都電荒川線)が全通〈④ 726〉
4
法学部,法律一辺倒の学科配当を改め,第 2・3学年で第一類(法律)・第二類(行政)・第三類
(経理)から 1類を選択必修させる〈③ 673−675〉
9・5
演劇博物館後援会解散し,国劇向上と演劇博物館充実を目的とする財団法人国劇向上会(会長
市島謙吉)設立〈③ 433,『演劇博物館五十年』147−148〉
10・3
五十嵐力,文学部長辞任し,吉江喬松嘱任〈維持〉
10・16
全学の学生委員が集まって結成した全早稲田連合学生委員会,早慶野球戦入場券の学苑側の
配布方法をめぐって学生大会を開き,入場券不買を決議,「早慶野球戦切符事件」起る
〈③ 456−458〉
10・18
不穏な学内状況を斟酌して臨時休業措置をとる。全早稲田連合学生委員会は学生大会を開き,
全早稲田連合学生委員会公認,体育会即時解散等 5項目の要求を決議〈③ 461−462〉
11・4
高田早苗・田中穂積の経営方針に不満を抱く坂本三郎,専門部長および監事の職を辞し,学苑
を去る。以後専門部長は置かれず,維持員会は埴原正直および上原鹿造を監事に互選
〈③ 473,維持〉
11・8
校友の逓信政務次官中野正剛,総長と全早稲田連合学生委員会代表者とに調停案を提示
〈③ 477−478〉
11・13
全早稲田連合学生委員会,学生大会を開いて調停案受諾を決議,「早慶野球戦切符事件」終息
〈③ 480〉
12・8
常務理事を 1名増員し,金子馬治就任,また幹事を教務幹事と庶務幹事の 2種に分け,教務幹
事に岡村千曵を,庶務幹事に難波理一郎を嘱任〈③ 677,維持〉
この年
早稲田大学出版部,通信講義録『電気工学予科講義』を『最新電気講義』と改称〈③ 501〉
この年
早稲田自動車協会(会長喜多壮一郎)創立〈③ 1143〉
1931年/ 昭和 6年
2・24
学苑の命を受けて中華民国学生の入学資格を調査した青柳篤恒,「早稲田大学及中華民国各
大学聯絡私案」を提出〈④ 637−638〉
3・5
高田早苗,高田基金募集に関わる寄附金 15万円余を第 1回分として学苑に寄附〈③ 659−660〉
3・13
各学部間の意思疎通を図るための「学部協議委員規程」廃止,また「科外教育審議会規則」を廃
止し,学生の会の新設・継続の審査・承認は 4月以降学部長会議に引き継がれる〈③ 761,維持〉
4・1
教職員の退職金に充当するための高田基金設定〈③ 660〉
4・6
青柳篤恒私案を基に,外国人留学生の初の学部・学院入学規程である「外国留学生入学ニ関ス
ル内規」制定〈④ 638〉
5・20
維持員会,旧文学部木造校舎(学苑最初の校舎)を東伏見運動場へ移築し,運動各部の合宿所
「グリーンハウス」として使用することを決議〈③ 262,1120〉
5・30
旧文学部木造校舎を取り壊した跡地に鉄筋コンクリート造の文学部校舎(現 8号館)竣工
〈③ 262,746〉
5
レスリング部設立,体育会に加入〈③ 1140〉
6・14
高田早苗,理事・総長の辞表提出〈③ 582−585〉
6・23
維持員会,高田早苗の理事・総長辞職を承認し,鈴木寅彦を理事に選出,理事会,常務理事田
中穂積を総長に互選,維持員会,田中穂積の第 4代総長就任を承認〈③ 585−586〉
6・23
校友会幹事連絡委員会,高田早苗銅像建設を決議〈③ 604〉
6・30
戸塚球場で早稲田式テレヴィジョンによる野球実況中継に成功〈③ 451〉
7・3
田中穂積総長就任式挙行〈③ 591−594〉
7・10
維持員会,高田早苗の名誉総長推薦を決議するが,高田はこれを固辞〈③ 595〉
9
早稲田工手学校の採鉱冶金科を鉱山及金属科と改称〈③ 212〉
9
空手研究会(会長大浜信泉)設立〈③ 1141〉
10・8
維持員会,大隈信常(会長)・市島謙吉・高田早苗・坪内雄蔵・渋沢栄一の維持員辞任を承認,理
事松平頼寿を維持員会長に互選,また難波理一郎の庶務幹事辞任を承認し,永井清志を嘱任,
幹事を補佐する副幹事を設ける〈③ 596−598〉
10・15
維持員会長に就任した松平頼寿の理事辞任に伴い,増田義一を理事に互選〈③ 598〉
11
史学会,『史観』創刊〈③ 167,763〉
12・10
校友会幹事ら,高田早苗銅像建設発起人会を開催し,建設資金を校友からの募金に仰ぐことを
決定〈③ 604〉
12・24
学部長・科長・教務主任会議に「学制改革綱要」提示,カリキュラムの本格的改革に着手
〈③ 681−684〉
12
文学部哲学科,『フィロソフィア』創刊〈③ 167〉
この年春
応援部(部長中村万吉),体育会に加入し,早慶野球戦の応援に初めてブラスバンドが参加,ま
た 6月 13日の早慶野球第 1回戦に第六応援歌「紺碧の空」(住治男作詞・古関裕而作曲)が初
めて演奏〈③ 530−531,1139,『稲魂♢♢早稲田大学応援部創立五十周年記念誌』21〉
この年春
創立 30周年を迎えた支那協会,日華協会と改称〈③ 769,学報 438・39〉
この年
早稲田大学出版部,通信講義録『最新電気講義』を『電気工学予備講義』と改称〈③ 501〉
この年
排球クラブ設立〈③ 1143〉
この年頃
高田馬場から早稲田を経由して東京駅に至る市営バス路線開通〈③ 271〉
1932年/ 昭和 7年
1・27
埴原正直,監事辞任し,渡辺亨就任〈維持〉
2・29
全学のカリキュラムを全面的に改革して学生の自主的研究を重視した改正学則の認可を文部大
臣に申請〈③ 734〉
3・17
大山郁夫夫妻,アメリカに向けて横浜を出航し,15年半に及ぶ亡命生活に入る〈④ 485−486〉
4・9
2月申請の学則変更,文部大臣の認可を得る。選択科目を大幅に増やしたほか,文学部哲学科
の東洋哲学専攻および社会哲学専攻を廃して代りに支那哲学専攻,印度哲学専攻,心理学専
攻,倫理学専攻,社会学専攻を新設し,文学科の支那文学専攻を廃し,史学科は専攻制度を採
用して国史専攻,東洋史専攻,西洋史専攻の 3専攻に分け,商学部の類別選択科目に第七分
科(英語)を加え,理工学部電気工学科に「電力応用」を専攻する第三分科を追加し,採鉱冶金
学科の第 3学年での採鉱専攻および冶金専攻を廃し,応用化学科の必修科目のうち工業化学
に関する科目を分別してそれを「工化第一部」というように第五部まで設け,高等師範部は 1年制
予科を廃して 3年制本科を 4年制に改める〈③ 669−738,1003−1004,記要 17・140−141〉
4
早稲田工手学校,1期から 3期までの共通科(予科)および 4期と 5期の本科(各期とも半年の合
計 2年半制)をすべて本科とし,4月から翌年 1月まで,および 11月から翌年 8月までの 10ヵ月
制の予科を新設して,修業年限を 3年 4ヵ月に延長したほか,予科の入学資格を尋常小学校卒
業,本科の入学資格を予科修了または高等小学校卒業と改める〈③ 212,837,記要 17・141〉
4
体育会長が置かれ,山本忠興嘱任〈学報 446・16〉
5・10
野球部,新人選手のリーグ戦 1年間出場停止の廃止や入場料の徴収に踏み切った東京六大学
野球連盟の方針に反対して連盟脱退を声明〈③ 1121−1122〉
5・10
速記研究会(会長稲毛金七),学生の会として公認〈③ 787〉
5・14
東京六大学野球連盟の理事・評議員連合委員会,早稲田大学野球部の脱退を承認し,東京大
学野球連盟と改称〈③ 1122〉
8
第 10回オリンピック(ロサンゼルス大会)の三段跳で校友南部忠平優勝,また走幅跳で 3位,棒
高跳で理工学部生西田修平 2位,水泳 100メートル背泳で理工学部生入江稔夫 2位〈③ 513−514〉
9・7
東京大学野球連盟の理事会,早稲田大学野球部の連盟復帰を決議し,東京六大学野球連盟の
旧称にもどる〈③ 1122〉
9下旬
大礼服姿の大隈重信銅像,校庭から大隈講堂へ移転〈③ 606〉
10・10
西村真次『半世紀の早稲田』刊行
10・17
ガウン姿の大隈重信銅像(朝倉文夫作)および高田早苗銅像(藤井浩祐作)の除幕式挙行
〈③ 606〉
10・18
創立 50周年式典挙行〈③ 607−610〉
10
学苑所在地の住居表示が東京府豊多摩郡戸塚町大字下戸塚 647番地から東京市淀橋区戸塚
町 1丁目 647番地に変更〈③ 270〉
11・9
維持員会,創立 50周年に際して皇室より下賜された恩賜金 1万円を基金として,学術奨励を目
的とする恩賜記念賞の設置を決議〈③ 622〉
この年秋
日華協会,東亜協会と改称〈③ 769〉
この年
陸上ホッケー部,スケート・ホッケー部より分離・独立〈③ 547〉
1933年/ 昭和 8年
1・14
「恩賜記念賞規程」制定,4月 1日施行〈③ 622−623〉
1・18
婦人問題研究会(会長浮田和民)設立〈③ 788〉
1・20
理事会,早稲田高等工学校および早稲田工手学校を除く学部ならびに付属学校の優等卒業生
に賞品を授与する優等賞制度を 4月 1日に発足させることを決議(「優等賞規程」は昭和 9年 5月 7日制定)〈③ 643−644〉
2・16
優等賞の賞品は銀時計と決定〈③ 644〉
3・9
イギリスの劇作家ジョージ・バーナード・ショー,演劇博物館を訪問〈③ 434−437〉
3
早稲田高等工学校,学部ならびに付属学校の優等賞制度に準じた優等賞制度を設け,4月 1日
より施行〈③ 645−646〉
3
老朽校舎改築および理工学部中央研究所設置を目的とする創立 50周年記念事業が発表され,
100万円の募金開始〈③ 620〉
3
高杉滝蔵,野球部長辞任し,寺沢信計,部長代理に就任〈③ 1125〉
4・15
本部校舎(現 3号館南側)竣工〈③ 746〉
4・30
テレヴィジョン研究室竣工〈③ 451,751−752〉
5・17
大隈重信の長女熊子死去,享年 69歳〈③ 171〉
7・10
戸塚球場の夜間照明設備完成し,開場式挙行〈③ 755,1119〉
7・
2−8 これまで講話に重点を置いてきた軍事教練,学部学生を対象に千葉県一ノ宮海岸で初めて
野外教練を課す〈③ 865,学報 462・7〉
10・4
寺尾元彦,理事就任〈維持〉
10・22
早慶野球戦リンゴ事件勃発〈③ 1123−1124〉
11・3
武道館開館式挙行〈③ 747,1120〉
11・10
寺沢信計野球部長代理,早慶野球戦リンゴ事件の責任を取って辞表を提出,18日に辞表受理
〈③ 1125〉
11・15
渡辺亨の死去(10月 13日)に伴い,名取夏司,監事就任〈維持〉
11・22
早慶野球戦リンゴ事件決着〈③ 1125〉
この年
新聞研究会(会長喜多壮一郎)再興〈③ 770〉
この年
劇芸術研究会(会長中村吉蔵)設立〈③ 780〉
この年
空手部(部長大浜信泉),体育会に加入〈③ 1141〉
この年
体操部,体育会に加入〈③ 1142〉
1934年/ 昭和 9年
1・23
「会計規程」を改正し,従来の諸基金を合併して単に基金と称する〈④ 618〉
2・2
図書館の書庫 3層・研究室 3室増築工事竣工〈③ 747〉
3・1
第一・第二高等学院生を対象とする「早稲田高等学院優等賞規程」制定・施行〈③ 646〉
3・30
「中華民国留学生入学ニ関スル内規」制定,4月 1日施行〈④ 638−639〉
4・1
宇都宮鼎,第二高等学院長辞任し,杉森孝次郎嘱任〈維持〉
4・10
理工学部各学科に工業経営分科の新設,文部大臣の認可を得る(実際の設置は翌昭和 10年 4月)〈③ 995〉
4・15
政・法教室(現 3号館北側)竣工〈③ 747〉
4
ゴルフ倶楽部設立〈③ 1145,学報 481・77〉
4頃
南門から演劇博物館までの間,図書館と本部校舎との間,本部校舎と政・法教室との間の通路の
舗装完成〈③ 755〉
6
第 3次『早稲田文学』創刊〈④ 691〉
6
現在の馬場下交差点と地下鉄早稲田駅交差点との間の道路拡幅工事完了〈④ 731〉
7・4
経済史学会設立〈学報 477・41−42〉
10・29
金子馬治,演劇博物館長辞任し,吉村(河竹)繁俊嘱任〈維持〉
12
航空研究会内にグライダー倶楽部創立〈③ 1148〉
この年
職員の満 60歳(副課長・副主事以上は 65歳)停年制実施〈③ 989〉
この年
早稲田自動車協会(昭和 5年創立)と早稲田モーター研究会(昭和 7年創立)とが合併して自動
車部となり,体育会に加入〈③ 1143〉
この年
排球部,体育会に加入〈③ 1143〉
この年
早慶野球戦リンゴ事件を契機に応援部解散〈③ 1139〉
1935年/ 昭和 10年
2・7
恩賜記念賞審査委員長が推薦した学生の優秀な研究に対して授与する教職員賞制定(昭和 18年まで継続)〈③ 627〉
2・7
理事会,『早稲田大学新聞』の復刊を許可〈③ 771〉
2・28
名誉教授坪内雄蔵死去,享年 75歳〈③ 661−662〉
3・14
大学部商科および商学部出身者,商学部校舎改築促進会の発起人会を開催し,30万円の募金
を開始〈③ 751,学報 482・63〉
3・15
退職金を補充するために「教職員積立金規程」制定,4月 1日施行〈③ 656〉
3・15
平沼淑郎,早稲田専門学校長辞任し,中村万吉嘱任〈維持〉
4・24
『早稲田大学新聞』復刊〈③ 771〉
4
商学部,7分科制を廃止して選択科目 2部制を採用し,第 2・3学年で第一部から 2科目,第二
部から 1科目を選択させる〈③ 991〉
4
理工学部,各学科に工業経営分科を増設,電気工学科は合計 4分科となる〈③ 995−998,1004〉
4
早稲田高等工学校,修業年限を半年延長して 2年半とし,これを 5期に分ける〈③ 1021〉
4
経済学偏重の政治経済攻究会に不満を持つ政治経済学部政治学科の学生,政治学会(会長浮
田和民)創立〈③ 762〉
6・10
専門部・高等師範部校舎(現 1号館)竣工〈③ 747〉
9末
専門部・高等師範部校舎の北側空地に鳩の家完成〈③ 756〉
9末−10
正門が今日の位置に移築され,門柱および門扉撤去〈③ 755〉
11・15
上原鹿造の死去(11月 4日)に伴い,早川徳次,監事就任〈維持〉
11・20
西村真次『小野梓伝』,冨山房より刊行
11・21
冨山房主坂本嘉治馬より寄附された 1万円を基金として小野奨学基金設定〈③ 638〉
11・23
大隈庭園内で小野梓胸像(本山白雲作)除幕式挙行〈③ 639−640,⑤ 168〉
12・6
満州国留日早稲田大学学生会発足〈④ 640−641〉
1936年/ 昭和 11年
1・16
理事会,3大節(紀元節,天長節,明治節)奉祝行事を本年より実施することを決定〈理事〉
2・11
教職員および学生,宮城前広場に参列して紀元節奉祝式を挙行。以後,毎年の紀元節に奉祝
式が行われる〈『早稲田大学新聞』昭和 11年 2月 5日号,学報 462・9〉
2・26
2・26事件勃発〈③ 879−880〉
2
第 4回冬季オリンピック(ガルミッシュ・パルテンキルヘン大会)で,専門部生石原省三,スピード・
スケート 500メートルに 4位(日本初の入賞)〈③ 516〉
4・20
教育に関する勅語(教育勅語)謄本の下付を文部大臣に申請〈④ 295〉
4・27
文部省,天皇機関説問題と絡む教員思想調査の一環として憲法の担当教員および講義内容に
関する報告書の提出を指令,5月 20日に回答〈③ 835,『昭和十一年四月起 文部省関係書
類』〉
4・29
天長節奉祝式を戸塚球場で挙行し,田中穂積総長が教育勅語を奉読。以後,毎年の天長節に
勅語が奉読される〈④ 295〉
4
早稲田工手学校,予科の修業年限を 2ヵ月延長して 1年とし,2年半制の本科の開始期が 4月
および 10月になるとともに,電工科を電気科と改称〈③ 1020−1021〉
5・5
西村真次(編)『小野梓全集』全 2巻,冨山房より刊行
5・15
西武鉄道東伏見駅前に競泳用プール竣工〈③ 1120〉
6・1
第一・第二高等学院,襟章を学院別・学年別・クラス別を示すものに改める〈学報 496・9〉
7・23− 8・1
中等学校教員を対象とする夏期講習会開催〈③ 1115−1117〉
7・30
西武鉄道東伏見駅前に飛込用プール竣工〈③ 1120〉
8・
1−8 第 3回日米学生会議,学苑で開催〈④ 659−660,『開戦前夜のディスカッション♢♢日米学生
交流五十年の記録♢♢』204−205〉
8
第 11回オリンピック(ベルリン大会)で,校友西田修平,棒高跳に 2位,商学部生牧野正蔵,水泳
400メートル自由形に 3位入賞〈③ 516〉
9・10
理工学部応用化学実験室(現 6号館北側)竣工〈③ 747〉
9・17
理事会,御真影の奉戴を決議〈③ 864〉
10・5
御真影の下賜願書を文部大臣に提出〈『自昭和十一年十月至昭和二十年十二月御真影拝戴に
関する一件書類』〉
11・3
教職員および学生,明治神宮参拝。以後,毎年の明治節に参拝が行われる〈学報 501・8〉
この年
専門部の学生委員,週番委員を設けて風紀維持に当る〈③ 881〉
1937年/ 昭和 12年
2・15
保谷村の土地 7,158坪を西武鉄道より買収することを決定〈③ 754〉
4・1
牧野謙次郎死去(3月 24日)に伴い,原田実,高等師範部長嘱任〈学報 506・29〉
4・29
天長節祝賀式と併せて,教職員および学生代表委員,恩賜記念館貴賓室に奉安の御真影を初
めて遥拝〈『早稲田大学新聞』昭和 12年 4月 28日号〉
4・29
ヘレン・ケラー,大隈講堂で講演〈④ 667〉
4
文学部,学生の減少により文学科の露西亜文学専攻を廃止するとともに,カリキュラムを,哲学
科・文学科・史学科 3学科共通の基礎学科目と,哲学科・文学科の専攻共通科目と,各専攻の科
目とに 3層構造化する(史学科の専攻共通科目は昭和 13年 4月より発足)〈③ 991−993〉
4
隣接地に校地拡張を目的とする皇紀 2600年奉祝創立 60周年記念事業の資金 100万円募金開
始〈③ 622,846〉
5
高等学院だけでなく学部・専門部・高等師範部でも体格検査実施〈③ 881〉
5
健康相談所にレントゲン設置〈③ 881〉
6・15
金子馬治死去(6月 1日)に伴い,吉江喬松,理事就任〈学報 509・7〉
7・7
北京郊外の蘆溝橋で日中両軍が衝突(日中戦争(「支那事変」と呼称)勃発)〈③ 811〉
7・15
維持員会,各務幸一郎の寄附金 30万円で鋳物研究所を建築すること,および,建築費 30万円のうち 20万円を限度として学苑が立て替えて商学部校舎を建築することを決議〈③ 748,751〉
7・25−31
中等学校教員を対象とする 2回目で最後の夏期講習会開催〈③ 1117〉
7・27
木村鬼雄,華北南苑で戦死(校友最初の戦争犠牲者)〈④ 158,203〉
8・24
内閣,「国民精神総動員実施要綱」決定〈③ 814−815〉
9・9
理事会,応召教職員に関する「昭和 12年支那事変応召者取扱内規」を定めるとともに,学生・生
徒の応召者は休学扱いとすることを決定〈③ 818〉
9・9
理事会,職員で組織する特設防護団の設置を決定〈④ 120,152〉
9・10
理工学部実験室(現 6号館南側)竣工〈③ 748〉
9・14−21
田中穂積総長,各学部・付属学校ごとに 8回に亘り「非常時局に直面して学徒に告ぐ」と題して訓
示〈③ 820−821,882−883〉
9・15−19
特設防護団,初めて防空演習実施〈学報 512・18〉
9・23
早稲田工手学校,軍用機献納金 920円を東京朝日新聞社に委託〈③ 826〉
9・24
田中穂積総長,学界を代表して東京中央放送局より「国民精神総動員について」を放送〈③ 820〉
9・25
調査課員岡崎確,北支で戦死(教職員最初の戦争犠牲者)〈③ 818,④ 157,182〉
9
教職員・学生・校友会,恤兵金 6,052円を陸軍省および海軍省に献納〈③ 826〉
10・2
田中穂積総長,キング・レコードに「非常時局ニ直面シテ」を録音〈③ 820〉
10・2
文学部生小森忠夫,山西省朔県で戦死(在学生最初の戦争犠牲者)〈③ 817,④ 162〉
10・19
田中穂積総長,『ジャパン・アドヴァタイザー』に声明書 ”JapanStands for Justice (正義の日
本)” 寄稿〈③ 820〉
11・3
正門を入って左側の植込みに国旗掲揚場と建学之碑が完成し,国旗掲揚式並建学之碑除幕式
挙行〈③ 629−630,755〉
12・14
戸塚球場で南京陥落祝賀式挙行〈③ 820,823,885〉
1938年/ 昭和 13年
3・26
早稲田実業学校長天野為之死去,享年 77歳〈③ 666〉
3・30
戸塚町所在相馬邸土地 8,861坪(甘泉園)の移転登記完了〈③ 637,753,754〉
4・1
石川登喜治,10月開所予定の鋳物研究所の所長に嘱任〈③ 912−913〉
4・1
「国家総動員法」公布,5月 5日施行〈③ 816〉
4・18
石川登喜治,理工学部応用金属学科教務主任嘱任〈理事〉
4・18
徳永重康,早稲田高等工学校長辞任し,内藤多仲,嘱任〈理事〉
4・18
前年春に衆議院議員となった喜多壮一郎,科外講演部長辞任し,出井盛之,嘱任〈③ 1104,理
事〉
4・25−12・24
「東亜の文化開発に雄飛すべき青年学徒を養成」するための特設東亜専攻科(夜学)を設置し,4月 27日に開講式を挙行〈③ 824,838〉
4
文学部哲学科に芸術学専攻増設〈③ 993〉
4
理工学部に応用金属学科増設〈③ 837〉
6・1
中村万吉死去(5月 24日)に伴い,高井忠夫,早稲田専門学校長に嘱任〈維持,学報 520・11〉
6・1
教員の満 70歳停年制が採用され,昭和 18年 4月 1日より実施〈③ 990〉
6・2
教練を行う体操教員に軍服着用を義務づける〈③ 865〉
7・5
東亜経済資料室,10月竣工予定の商学部校舎内に設けられることとなり,関係諸機関および校
友会支部に資料寄贈と協力を依頼〈③ 932−933〉
7・14
維持員会,「鋳物研究所規程」を承認,4月 1日に遡って適用〈③ 912〉
7・14
維持員会,西武鉄道東伏見駅前のプール所在地 2,000坪の買収を決定〈③ 753,754〉
7
戸塚町に鋳物研究所竣工〈③ 748,912〉
10・1
理事・商学部長平沼淑郎の死去(8月 14日)に伴い,北沢新次郎,商学部長に嘱任(理事は補
充せず)〈③ 1059〉
10・8
商学部校舎(現 11号館)竣工〈③ 748〉
10・21
鋳物研究所開所式挙行〈③ 909,912〉
10・25
故大隈総長生誕 100年記念祭挙行〈③ 631−636〉
10・28
戸塚球場で漢口陥落祝賀式挙行〈③ 820,894〉
12・3
名誉学長高田早苗死去,享年 78歳〈③ 664〉
12・5
高田早苗の大学葬挙行〈③ 664−665〉
12
各学部・付属学校各科より教員 1名合計 12名をそれぞれ 4週間前後,中国大陸視察に派遣
〈③ 745,838〉
1939年/ 昭和 14年
1・14
維持員会,女子の学部入学を認めるための学則改正を決議,2月 15日に文部大臣の認可を得
る。女子高等師範学校本科または女子専門学校本科の卒業者あるいは修業年限 3年以上の官
立教員養成所の女子修了者を学部入学資格者に包含する〈③ 802〉
1・24
専門部に工科(機械工学科,電気工学科,建築学科,土木工学科)新設が文部大臣の認可を得
る〈③ 1012〉
1・27
米式蹴球部(部長中島太郎)およびヨット部(部長杉山謙治),体育会に加入〈③ 1144,1145,『早稲田大学新聞』昭和 14年 2月 1日号〉
2・1
内藤多仲,4月開設予定の専門部工科長に嘱任,また各科に主任を置き,機械工学科主任に山
ノ内弘,電気工学科主任に川原田政太郎,建築学科主任に吉田享二,土木工学科主任に内藤
多仲を嘱任〈③ 1013〉
4・1
専門部に工科開設〈③ 1012〉
4・1
専門部各科の教務主任を 1名ずつ増員して 2名ずつとする〈理事〉
4・21−25
第 3回日比学生会議,学苑で開催〈④ 660,『早稲田大学新聞』昭和 14年 4月 26日号〉
4
文学部哲学科の支那哲学専攻を支那学専攻と,西洋哲学専攻を哲学専攻と改称したほか,印度
哲学専攻を廃止〈③ 993〉
4
早稲田高等工学校の修業年限を半年延長して 3年とし,入学時期を年 1回 4月に改め,5期に
分けられていた科目制が 1年 2学期の学年制となる〈③ 1021〉
4
軍事教練,学部の必修科目となる〈③ 858,865〉
4
女子 4人が初めて学部に入学〈③ 804−805〉
5・1
特設東亜専攻科,2回目の入学式挙行(翌年度は聴講生募集を停止するので,特設東亜専攻科
は 2年間のみ存在)〈学報 532・13〉
5・30
「陸軍現役将校学校配属令」制定 15周年記念の閲兵分列式が 5月 22日に挙行された際に天皇
が下賜した「青少年学徒ニ賜ハリタル勅語」の奉読式が戸塚球場で挙行〈③ 895−896〉
6・27
支那事変勃発 2周年記念勅語奉読式並興亜青年勤労報国隊壮行会,大隈講堂で開催
〈③ 1042〉
8・30
興亜青年勤労報国隊に参加した学生 64人,満州および北支より帰国〈③ 897〉
9・1
ドイツ,ポーランドに侵攻(第二次世界大戦勃発)
9・20
興亜青年勤労報国隊に参加した指導教官および隊員による報告講演会を科外講義として開催
〈③ 1042〉
10・4
徳永重康,平沼淑郎死去後 1名欠員であった理事に就任,名取夏司の死去(3月 11日)により 1名欠員の監事に磯部愉一郎就任〈学報 536・16〉
11・1
内藤多仲,早稲田高等工学校長を辞任し,吉田享二,嘱任〈理事〉
11・10
銃後国民育成の強化徹底を図るため「国民精神総動員早稲田大学実行委員会規程」施行
〈③ 830−831〉
11・16
玉井勝則(火野葦平),大隈講堂で「戦線より帰りて」と題する科外講演を開催
〈③ 898−899,1111〉
12・24
津田左右吉の学説を攻撃する『原理日本』臨時増刊号刊行〈③ 1068〉
1940年/ 昭和 15年
1・9
文部省,津田左右吉の解職を要求〈③ 1073−1074〉
1・11
文学部教授会,津田左右吉の辞任を承認し,田中穂積総長,津田の解職を文部省に報告
〈③ 1074−1075〉
1・25
早稲田大学出版部からの寄附金を基に,教職員退職基金を補う「出版部基金」設定,4月 1日実
施〈③ 656−657〉
2・9
理事・早稲田工手学校長徳永重康の死去(2月 8日)に伴い,山ノ内弘,早稲田工手学校長嘱任
〈理事〉
2・10
内務省,津田左右吉著『神代史の研究』『古事記及日本書紀の研究』の発禁,『日本上代史研
究』『上代日本の社会及び思想』の一部削除の処分を行う〈③ 1062,1075−1076〉
3・9
津田左右吉および岩波書店主岩波茂雄,出版法違反により起訴〈③ 1076〉
3・15
徳永重康の後任として,杉森孝次郎,理事就任〈学報 542・12〉
3・15
理工学部研究所(創立 50周年記念事業の一環であった理工学部中央研究所新設構想を変更し
たもの)を設立するため,喜久井町の土地 1,918坪および建物 524坪の買収を決定
〈③ 920−921〉
4・12
理事・文学部長吉江喬松の死去(3月 26日)に伴い,日高只一,文学部長嘱任〈理事〉
4・12
西村真次著『大和時代』『日本古代社会』『日本文化史概論』絶版勧告を受けてこれに従ったこと
を文部省に報告〈③ 835,1062,『昭和十五年三月 文部省関係書類』〉
4
理工学部採鉱冶金学科は第一分科(採鉱)・第二分科(冶金)・工業経営分科の 3分科制を採用
〈記要 17・148〉
4
青年学校義務制(昭和 14年 4月 26日公布・施行「青年学校令」に基づく)により予科志望者の激
減を予測した早稲田工手学校は,予科の生徒募集を停止し,本科生のみを募集〈③ 1021〉
4
早稲田高等工学校に応用化学科(教務主任小栗捨蔵)増設〈③ 1021〉
5・15
吉江喬松の後任として,北沢新次郎,理事就任〈学報 544・8〉
5・15
理工学部研究所用地隣接地 25坪弱の購入を決定〈③ 921〉
6・25
興亜学生勤労報国隊(興亜青年勤労報国隊の後身)壮行会挙行〈③ 901,1042〉
7・11
野々村戒三,第一高等学院長辞任し,高等師範部長原田実を嘱任,高等師範部長には勝俣銓
吉郎を嘱任〈理事〉
9・14
田中穂積総長,教職員を大隈講堂に集め,学生・生徒の体位向上を重視する教育方針を宣明
〈③ 901−902〉
9・21
興亜経済研究所設立準備委員会,定款および理事長北沢新次郎をはじめとする人事を決定
〈③ 934−936〉
9・27
理事会,学徒錬成部道場建設と忠魂碑建立を決議〈③ 832−833〉
9・27
法学部および商学部の教務主任を 1名ずつ増員して各 2名を置く〈理事〉
9・28
興亜経済研究所,第 1回理事会を開催し,第 1年度の事業計画および予算を審議〈学報 550・4〉
10・7
学徒錬成部の新設を決定し,田中穂積を学徒錬成部長に嘱任〈③ 832〉
11・1
興亜経済研究所開所式挙行〈③ 839,936〉
11・5
紀元 2600年奉祝創立 60周年記念式典挙行(予定していた忠魂碑除幕式は中止)
〈③ 840,843−845,849〉
11
音楽関係の各種学生の会を鳩合して音楽協会(会長西条八十)結成〈③ 776−777〉
12・
2−6 第 1回体力章検定実施〈③ 957−958〉
12・14
甘泉園に接続する相馬家所有地 6,125坪の買収を決定〈③ 753,754〉
12・21
報国碑(忠魂碑を変更)除幕式,恩賜記念館前で挙行〈③ 849−850〉
この年春
体育会,応援技術部設立〈③ 1140,『早稲田大学新聞』昭和 15年 4月 24日号〉
この年夏
創立 50周年記念事業の理工学部研究所(当初の構想では理工学部中央研究所)を喜久井町に
設立〈③ 750,918−925〉
この年秋
法学部に東亜法制研究所設置〈③ 942〉
1941年/ 昭和 16年
2・5
島田賢平,「俳句事件」に連座して検挙〈③ 1064〉
2・17
第 1回体力章伝達式挙行〈③ 958〉
3・11
京口元吉,講義内容が自由主義的であると警視庁より指弾されて文学部教授会に辞表を提出し,
27日の理事会で辞職承認〈③ 1060〉
4・1
教務部長・庶務部長・経理部長を置いて幹事に分担させることとし,教務部長に岡村千曵,庶務
部長に大島正一,経理部長に永井清志を嘱任〈理事〉
4・15
高井忠夫,早稲田専門学校長辞任し,上坂酉蔵(酉三)嘱任〈理事〉
4・24
理事会,久留米に勤労耕作用畑地約 1町歩の買収を決定〈③ 952〉
4・29
興亜経済研究所,『興亜政治経済研究』第 1輯刊行〈③ 933−934〉
4
文学部哲学科の支那学専攻を廃止して東洋哲学専攻を復活し,哲学専攻を西洋哲学専攻の旧
称に復し,教育学専攻を新設〈③ 993〉
4
4分科に分れていた理工学部電気工学科は,動力及通信専攻の第二分科を電気通信専攻に改
めるとともに,動力及電機製作専攻の第一分科と電力応用専攻の第三分科とを合併して電気工
学専攻の第一分科とする〈③ 1004〉
4
第一・第二高等学院は,「学校教練の強化,体錬,錬成,勤労作業」を学徒錬成部で行う錬成科
と,従来の学友会に替えて「科学,語学,芸術,国防,武道,競技」から選択必修させる特修科と
を設置し,午前の国民科・自然科学科・外国語科,午後の錬成科・特修科の 5体系に学科配当を
編成(錬成科は実現せず)〈③ 993,1149〉
4
軍事教練,高等学院・専門部・高等師範部の必修科目となる〈③ 858〉
4
早稲田工手学校は「青年学校令」に準拠して学科課程を改正し,予科を廃止して入学資格を高
等小学校卒業またはこれと同等以上へと引き上げ,修業年限を半年延長し 3年に改めてこれを 6期に分けたほか,鉱山及金属科を採鉱冶金科と改称〈③ 1021〉
4
専門部工科の木造校舎,第二高等学院北側のテニス・コート跡地に竣工〈③ 752〉
4
小平錬成道場を久留米道場,東伏見体錬道場を東伏見道場,戸塚球場を戸塚道場,第一高等
学院運動場を戸山道場と改称〈③ 952−953〉
5・31
早稲田工手学校,4月 1日に遡って青年学校と同等以上の学校として認定するよう東京府知事に
申請(10月 30日に認定)〈③ 1021〉
5
久留米道場が一部竣工(完工は 9月)し,学徒錬成部の事業開始〈③ 752,952〉
6・3
学部長・付属学校長会議,学生の礼は挙手で行うと定める〈③ 834,904〉
6・27
興亜学生勤労報国隊壮行会挙行〈学報 557・12〉
7・5
学徒錬成部開所式挙行〈③ 952〉
8・1
学部,専門部,高等師範部,第一・第二高等学院の学生・生徒が勤労動員を組織的に行うための
早稲田大学報国隊(当初は義勇団と呼称),発会式を挙行〈③ 1047−1050〉
8・
3−12 早稲田大学報国隊,第二高等学院生 300人を東京兵器補給廠に派遣(最初の学徒勤労
動員)〈③ 1050〉
9・15
東亜法制研究所,『新立法の動向』第 1輯刊行〈③ 944〉
9・27
学徒錬成部久留米道場,教職員に完成披露〈③ 952〉
10・3
早稲田専門学校,早稲田高等工学校,早稲田工手学校の生徒をも加えた早稲田大学報国隊,
結成式を挙行〈③ 833〉
10・16
「大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ臨時短縮ニ関スル件」(勅令第 924号) により,在学・
修業年限は 6ヵ月以内を限度として臨時に短縮可能とされるとともに,同日の「大学学部等ノ在学
年限又ハ修業年限ノ昭和 16年度臨時短縮ニ関スル件」(文部省令第 79号) により,本年度は 3ヵ月短縮となる〈③ 971〉
10・16
「兵役法中改正法律中改正」(勅令第 923号)および「在学徴集延期期間ノ短縮ニ関スル件」(陸
軍・文部省令第 2号)により,学生の徴兵猶予年齢が 25歳まで低下するとともに,最高学年在籍
者については年齢に関わりなく卒業期日から 8ヵ月遡った時点で徴集延期期間が終了したものと
看做される〈③ 972−973〉
11・1
津田左右吉出版法違反事件の公判,東京地方裁判所で開始(翌年 1月 15日に終了)
〈③ 1077−1081〉
11・6−10
第 2回体力章検定実施(第 3回以降も実施されたかどうかは不明)〈③ 958,学報 561・10〉
11・8
音楽協会,学徒錬成部に吸収されて学徒錬成部音楽隊結成式挙行〈③ 777,960〉
12・8
対米英宣戦布告(太平洋戦争(「大東亜戦争」と呼称)に拡大)〈③ 905−906,969,979〉
12・8
燈火管制開始〈③ 906〉
12・20
鋳物研究所,『早稲田大学鋳研報告』第 1号刊行〈③ 915〉
12・25
学部・専門部・高等師範部・早稲田専門学校で最初の繰上げ卒業式(修業年限 3ヵ月短縮)を挙
行し〈③ 1024,1030−1031〉,最後の恩賜記念賞が授与される〈③ 625〉
12・27
早稲田高等工学校,最初の繰上げ卒業式(修業年限 3ヵ月短縮)挙行〈『早稲田高等工学校教
務に関する書類』〉
この年秋
広告研究会,宣伝文化研究会と改称〈③ 784〉
1942年/ 昭和 17年
1
前月の専門部卒業者のうち学部への進学を希望する者を対象に,3月まで授業料無料の臨時補
習科を設ける〈記要 17・153〉
2・18
シンガポール陥落を記念して,大東亜戦捷第 1次祝賀式並祝賀行進を戸塚道場で挙行〈学報
565・10〉
3・30
津田左右吉出版法違反事件に関連して,田中穂積総長,教職員の指導監督不行届の理由で文
部大臣より戒告処分を受ける〈③ 836〉
4・1
体育会の学徒錬成部への統合開始〈③ 962,1150〉
4・18
アメリカ軍,初めて日本本土を空襲〈③ 1033〉
4
商学部,選択科目制を廃止したほか,従来随意科目であった外国語を選択必修とする〈③ 990,記要 17・153〉
4
理工学部電気工学科の第二分科が分離独立して電気通信学科(教務主任黒川兼三郎)となる。
これに伴い第一分科の呼称も消滅し,電気工学科の分科は工業経営分科のみとなる〈③ 1004,記要 17・153〉
4
理工学部応用化学科の工業化学必修科目 5部制が 7部制となる〈記要 17・153〉
4
高等学校・大学予科の修業年限 6ヵ月短縮が実現すると 1年半になってしまうことを懸念した 2年
制の第二高等学院は 3年制課程を併設し,定員の半分を 3年制課程に入学させる〈③ 993−994〉
4
高等師範部に国民体錬科(教務主任今田竹千代)設置〈③ 966−968,994〉
5・11
理事会,金属類特別回収の国策に呼応して,戸塚道場の照明塔を取り壊し献納することを決定
〈③ 1119〉
5・20
早稲田女子学生会(会長杉森孝次郎)結成〈③ 809,『早稲田大学新聞』昭和 17年 5月 27日号〉
5・21
津田左右吉に禁固 3ヵ月,岩波茂雄に同 1ヵ月(ともに執行猶予 2年)の判決が下るが,検事局・
両被告とも 23日に控訴〈③ 1083〉
7・13
学生・生徒の日常生活指針を定めた「学徒十戒」制定〈④ 103−104,理事〉
7・13
理事・法学部長寺尾元彦死去(6月 28日)に伴い,法学部長に専門部法律科長遊佐慶夫を,専
門部法律科長に中村宗雄を嘱任〈理事〉
9・10
理事会,学徒錬成部久留米道場隣接地 13,031坪の買収を決定〈③ 952〉
9・27
学部・専門部・高等師範部・早稲田専門学校,2回目の繰上げ卒業式(修業年限 6ヵ月短縮)挙
行〈③ 1033−1034〉
9・30
第一・第二高等学院,最初の繰上げ修了式(修業年限 6ヵ月短縮)挙行〈記要 17・154〉
9・30
早稲田高等工学校,2回目の繰上げ卒業式(修業年限 6ヵ月短縮)挙行〈『早稲田高等工学校教
務に関する書類』〉
9
「俳句事件」に連座した島田賢平,講師辞任〈③ 1065〉
10・1
最初の繰上げ修了高等学院生を迎えて学部入学式挙行〈学報 572・23〉
10・1
理工学部応用化学科に石油分科増設〈③ 752,1006〉
10・4
塩沢昌貞,政治経済学部長辞任し,中野登美雄嘱任〈理事〉
10・5
寺尾元彦の後任として,内藤多仲,理事就任〈維持〉
10・22
体育会の学徒錬成部への統合が完了し,体育会解散式挙行〈③ 963,1150〉
10
7月頃科外講演部長を辞任した出井盛之の後任として,川原篤嘱任〈学報 569・10,572・25〉
11・5
東亜法制研究所,『新立法の動向』第 2輯刊行,以後出版活動途絶〈③ 944−945〉
12・11
満 70歳停年制導入に伴う最初の停年教員 17名の送別会開催〈③ 990〉
12・25
鋳物研究所,『早稲田大学鋳研報告』第 2号刊行,以後休刊〈③ 915〉
この年
端艇部,漕艇部と改称〈③ 1132〉
この年
送球部,体育会に加入〈③ 1145〉
この年
米式蹴球部,廃止〈③ 1144〉
1943年/ 昭和 18年
1・15
早川徳次死去(昭和 17年 11月 29日)に伴い,大橋誠一,監事就任〈維持〉
1・15
諸研究所を学部付属でなく大学直轄とする「付属研究所規程」制定,4月 1日施行
〈③ 913,927−928〉
1・15
維持員会,理工学部石油工学科(10月開設予定)用地として早稲田奉仕園の土地 2,365坪およ
び建物 4棟 913坪(日本バプテスト伝道社団所有)の買収を決定〈③ 752−753,1008−1009〉
1・20
田中穂積総長,大学院を官立大学に集中させる文部省構想に反対する意見書「学制改革と大学
院問題」を発表し,文部省ほか関係方面に配付〈③ 981−983〉
1・21
高等学校および大学予科の修業年限を 2年に短縮する「高等学校令中改正」(勅令第 38号)お
よび「大学令中改正」(勅令第 40号)公布,4月 1日施行〈③ 994,1032〉
1・27
勝俣銓吉郎,任期満了により高等師範部長辞任,当分の間後任を置かず〈理事〉
1
専門部(工科を除く)および早稲田専門学校の 2年生は第 3学年に,高等師範部の 3年生は第 4学年に進級し,修業年限が 3ヵ月短縮〈記要 17・154〉
4・1
理工学部研究所,「付属研究所規程」に基づき理工学研究所と改称〈③ 928〉
4・6
文部省,東京六大学野球連盟に解散を命じる〈③ 1129〉
4・10
学徒錬成部を紹介する『学徒錬成』刊行
4・14
3月 29日付文部省通牒「戦時学徒体育訓練実施要綱」に基づき「戦時学徒体育基本要綱」を発
表し,体育の目標を戦力増強に集中させる〈③ 963−964〉
4・15
『早稲田学報』第 578号発行,以後不定期刊行となる〈④ 533−534,777〉
4・25
春季校友大会開催,今回を以て校友大会は中断〈学報 579・26〉
4
第一・第二高等学院の修業年限をともに 2年に変更・短縮〈③ 994,1031−1033,④ 53〉
4
高等師範部英語科,生徒募集一時停止〈③ 994,④ 52〉
4
早稲田専門学校,第 1・2学年の選択科目制を廃止し,第 3学年の選択科目を 2類に分けて各 1科目を選択させる〈記要 17・155−156〉。また商科を第一部と第二部とに分け,第一部には実業学
校教員志望者を,第二部にはそれ以外の者を入学させる〈③ 994〉
5
山本忠興,理工学研究所長嘱任〈③ 928〉
6・14
田中穂積,学徒錬成部長辞任し,杉山謙治嘱任〈③ 964,理事〉
6
戸塚道場の照明塔撤去〈③ 1119〉
8・19
文部省からの照会により,大学院特別研究生候補者 17人を文部大臣に推薦〈③ 986〉
9・21
内閣,学生に対する徴兵延期の特典を停止する「在学徴集延期臨時特例」決定〈③ 973,1087〉
9・26
学部・専門部・高等師範部・早稲田専門学校,3回目の繰上げ卒業式(修業年限 6ヵ月短縮)挙
行〈③ 1034〉
9・29
7帝国大学と 3官立大学と私立では早慶両大学のみを対象とする「大学院又ハ研究科ノ特別研
究生ニ関スル件」(文部省令第 74号)公布,10月 1日実施〈③ 975,984〉
9・30
第一・第二高等学院,2回目の繰上げ修了式(修業年限 6ヵ月短縮)挙行〈学報 580・12〉
9・30
特設防護団を校内防空と校外防空とに分けて警戒警報発令時の配備を決め,約 200人が校内
防空初訓練に参加〈④ 120−121〉
10・1
大学院特別研究生制度発足〈③ 986〉
10・1
2回目の繰上げ修了高等学院生を迎えて学部入学式挙行〈学報 580・12〉
10・1
理工学部応用化学科の石油分科が分離独立して石油工学科(教務主任山本研一)が発足し,土
木工学科(教務主任草間偉)が新設され,機械工学科・電気工学科・建築学科・応用化学科の 4学科に置かれていた工業経営分科が分離独立(採鉱冶金学科の工業経営分科は廃止)・合併し
て工業経営学科(教務主任上田輝雄)が発足,工業経営学科は第一分科(機械工学)・第二分科
(電気工学)・第三分科(建設工学)・第四分科(応用化学)に分かれる
〈③ 998−999,1006−1010〉。なお,石油工学科は石油分科在籍者をも編入〈記要 17・156−157〉
10・1
文学部長日高只一,高等師範部長兼任嘱任〈理事〉
10・2
「在学徴集延期臨時特例」(勅令第 755号)が公布され,文部次官,「在学徴集延期停止ニ関スル
件」を通牒して,徴集延期中の学生・生徒は全員 10月 25日から 11月 5日までの間に各自の本
籍地で徴兵検査を受けるよう指示〈③ 973,1036,④ 162−163〉
10・7
理事会,学徒出陣により 12月 1日入営予定の学生・生徒に鍛錬実施を決定し,10月 11日から
11月 21日にかけて学徒錬成部で実施〈④ 104〉
10・7
理事会,昭和 19年度に農学部開設を決定(文部省に申請するに至らず)〈④ 93−94〉
10・12
内閣,文科系軽視・理科系重視の「教育ニ関スル戦時非常措置方策」決定,学校・大学の統廃合
を進める〈③ 975−978〉
10・15
出陣学徒壮行会,戸塚道場で開催〈③ 1088−1091〉
10・16
早慶壮行野球試合,戸塚道場で開催〈③ 1091−1094〉
10・16−17
漕艇班の出陣学徒9人,東京湾縦断敢行〈③ 1094-1095〉
10・18
特設防護団に学生・生徒を編入し,校内防空のほかに校外防空をも割り当てる〈④ 121〉
10・18
財団法人大日本育英会(会長永井柳太郎)創立,翌昭和 19年 4月より特殊法人となる〈『日本育
英会十年誌』7,④ 1136〉
10・20
「昭和 18年度陸軍特別志願兵臨時採用規則」(陸軍省令第 48号)により,在学中の外地人に陸
軍への志願を要請〈④ 651−652〉
10・21
文部省学校報国団主催の出陣学徒壮行会,明治神宮外苑競技場で開催〈③ 1095−1097〉
10・30
文部次官,陸軍特別志願兵制度を推進するための「朝鮮人台湾人学生生徒ニ関スル件」を通牒
〈④ 652〉
10・31
学生が激減するため,約 140名の非常勤講師解任〈③ 989〉
10
宣伝文化研究会解散〈③ 784〉
11・13
「修学継続ノ為ノ入営延期等ニ関スル件」(陸軍省令第 54号)および陸軍省告示第 54号により,
大学院特別研究生と理工学部・第一高等学院理科・専門部工科の学生・生徒は入営を延期され
る〈③ 973,記要 17・157〉
12・1
文科系学生・生徒約 6,000人,一斉に入営〈④ 3〉
12・3
文部省専門教育局長,「朝鮮人,台湾人特別志願兵制度ニヨリ志願セザリシ学生生徒ノ取扱ニ関
スル件」を通牒し,陸軍特別志願兵に志願しない外地出身学生・生徒は自発的に休学または退
学させること,従わない場合は休学措置を採ることを指示〈④ 652−653〉
12・9
理事会,商学部の経営学部改称案を審議〈③ 987,④ 49〉
12・24
「徴兵適齢臨時特例」(勅令第 939号)が公布・施行され,徴兵年齢が 19歳に引き下げられる
〈④ 163〉
12・29
専門部農科の昭和 19年度新設の認可を文部大臣に申請(実現せず)〈④ 93−94〉
12
篭球部,活動休止〈③ 1136〉
この年
学生を留年させないよう科目本位制を学年制に切り換える〈③ 738〉
1944年/ 昭和 19年
1・8
内閣,「緊急学徒勤労動員方策要綱」決定し,「勤労即教育」を本旨として勤労動員が休暇中だけ
でなく年間を通じて行われる〈④ 107〉
1・14
理事会,4月より専門部・高等師範部・早稲田専門学校の学生を生徒と呼称するとともに,制帽を
角帽から丸帽に改めることを決定(遵守されず)〈④ 30,34〉
1・15
『早稲田学報』第 581号発行,これを以て休刊〈④ 534〉
1・17
陸軍特別志願兵として入営する外地出身学生・生徒の出陣壮行会,大隈講堂で挙行
〈③ 1099−1100,④ 653〉
1・24
早稲田専門学校生中の希望者で組織する学徒増産挺身隊第 1部隊,結成式挙行。午前 7時よ
り午後 3時半まで石川島造船所に勤務し,午後 6時より早稲田専門学校で授業を受ける
〈④ 128〉
1
第一高等学院文科および第二高等学院,理工学部進学希望者のために文科第二部を創設し,9月までの 9ヵ月間補習教育を実施〈③ 1037,④ 24,53〉
2・19
職員中心であった特設防護団に残留学生をも組み入れて結団式挙行〈④ 96,153〉
2・22
特設防護団(団長は総長兼務)を学徒錬成部管掌下に置き,報国隊員の全学生を防空要員に充
当〈④ 121〉
2・25
内閣,「決戦非常措置要綱」決定し,中等学校以上の学生・生徒全員を常時勤労に動員
〈④ 107−108〉
3・7
山本忠興,理工学部長辞任し,専門部工科長の内藤多仲を嘱任,専門部工科長には堤秀夫を
嘱任〈③ 928,④ 31,理事〉
3・10
『早稲田大学理工学研究所報告』第 1輯発行,以後中断〈③ 928〉
3・22
増田義一,理事辞任し名誉理事となり,後任に中野登美雄就任し常務理事となる〈④ 4,維持,理
事〉
3・22
興亜経済研究所と東亜法制研究所とを統合して興亜人文科学研究所(所長は総長兼務)設立
〈④ 100−101〉
3・31
比較的高給を支給されていた古参の課長 3名と主事 8名,職制縮小に伴い退職〈④ 95〉
4・1
専門部および早稲田専門学校の商科,経営科と改称〈③ 987,④ 49〉
4・1
専門部工科に航空機科,電気通信科,鉱山地質科を増設したほか,既存の機械工学科を機械
科,電気工学科を電気科,建築学科を建築科,土木工学科を土木科と改称〈④ 25−30〉
4・1
高等師範部の修業年限を 1年短縮して 3年に改めたほか,国民体錬科に 1年制の専攻科設置
(専攻科は 1度も機能せず)〈④ 52〉
4・1
早稲田高等工学校に航空機科,電気通信科,木材工業科を増設したほか,既存の機械工学科
を機械科,電気工学科を電気科,建築学科を建築科,土木工学科を土木科,応用化学科を化学
工業科と改称〈④ 33〉
4・1
職制縮小のため本部の文書課・学生課・人事課を廃止し,庶務部に厚生課・秘書課を,教務部に
教練課を新設するとともに,政・法・文・商各部および高等師範部の事務所を廃止する代りに法文
系事務所(連合事務所)を新設〈④ 95〉,また,学生・生徒の激減により機能が低下した学徒錬成
部に勤労動員関係および報国隊関係の事務を移管〈④ 104,110〉
4・20
山本忠興,理事・理工学研究所長辞任し,理工学部長内藤多仲に理工学研究所長を嘱任,杉森
孝次郎,第二高等学院長辞任し,赤松保羅嘱任〈③ 928,理事〉
5・20
留日学生協会(会長小松芳喬),発会式挙行〈④ 657−658〉
5・20
新聞研究会,『早稲田大学新聞』第 324号発行,これを以て廃刊〈③ 772,④ 590,777〉
6・14
専門部経営科長小林行昌死去(6月 2日)に伴い,末高信嘱任〈理事〉
6・14
陸軍現役配属将校,陸軍軍事教官と改称〈③ 874〉
7・22
興亜人文科学研究所(所長田中穂積),開所式挙行〈④ 102〉
7・24
服部文四郎,専門部政治経済科長辞任し,中村佐一嘱任〈理事〉
8・21
学生・生徒が勤労動員で出校不能のため,特設防護団を教職員主体の組織に再編して結成式
挙行〈④ 153−154〉
8・22
総長田中穂積死去,享年 68歳〈④ 5,102〉
8・28
田中穂積の大学葬挙行〈④ 5〉
9・13
科外講演部長川原篤応召(6月)につき,吉村正,部長代行嘱任〈理事〉
9・13
理事会,第一高等学院校舎の東京師団経理部への賃貸および戸塚道場のスタンド鉄骨・照明塔
の一部供出を決定〈④ 96−97〉
9・16
日高只一・林癸未夫,理事就任,中野登美雄,第 5代総長に就任〈④ 5〉
9・16
維持員会長松平頼寿死去(9月 13日)に伴い,小山松寿就任〈維持〉
9・24
学部・専門部・高等師範部・早稲田専門学校,4回目(学部は今回が最後)の繰上げ卒業式(修
業年限 6ヵ月短縮)挙行〈記要 17・160〉
9・25
前年の学徒出陣で応召中の最高学年在学生(戦死者を含む)に卒業証書授与〈③ 1102,④ 181〉
9・30
第一・第二高等学院,3回目(今回が最後)の繰上げ修了式(修業年限 6ヵ月短縮)挙行〈記要
17・160〉
10・5
杉森孝次郎,理事辞任〈④ 14〉
10・5
中野登美雄,政治経済学部長辞任し,林癸未夫嘱任〈理事〉
10・5
理事会,東伏見道場の中島飛行機株式会社への貸与を決定し,14日に貸与〈④ 97,105〉
10・10
中野登美雄総長就任式挙行〈④ 5,16−18,111〉
10・18
「兵役法施行規則改正」により,11月 1日から 17歳以上を兵役に編入〈記要 17・160〉
10・25
教務部より『早稲田学園彙報』創刊〈④ 535〉
10
「決戦非常措置要綱ニ基ク大学教育ニ関スル措置要綱」(6月 14日通牒)に基づいて法文系各
学部は科目制を廃止し,学年制を採用,文学部は各学科の専攻別を廃止〈④ 44−45〉
11・4
津田左右吉,時効成立により出版法違反免訴〈③ 1084〉
12・11
留学生をまとめて教育する臨時留日学生部,開設式挙行〈④ 657〉
12・18
法学部長遊佐慶夫死去(11月 17日)に伴い,専門部法律科長中村宗雄を嘱任〈理事〉
12・29
内閣,「留日学生教育非常措置要綱」決定し,翌年 3月 1日付で留学生を地方の大学等に分散・
集合させたので,学苑における留学生教育は中断〈④ 658−659〉
1945年/ 昭和 20年
1・11
中村宗雄,専門部法律科長辞任し,大浜信泉嘱任〈理事〉
1・11
理事会,屋外の幾つかの銅像を取り外して屋内に保管し,銀牌を全部供出すると決定〈④ 97〉
1・20
早稲田高等工学校を「専門学校令」に基づく学校に昇格させて早稲田工業専門学校を 4月より
開校したいと文部省に認可を申請(認可されず)〈④ 34〉
2・1
商学部を 4月より産業経営学部と改称することを文部省に申請(実現せず)〈③ 987,④ 51〉
2・8
理事会,早稲田工手学校を工業学校に昇格させることを決定(実現せず)〈④ 34〉
3・1
理事林癸未夫,常務理事に就任〈④ 94〉
3・1
理事会,理工学部実験室屋上のアンテナや戸塚道場の照明塔の撤去を決定〈③ 758,④ 96〉
3・5
理工学部 1年生と専門部工科 1年生とで成る学徒消防隊が結成式を挙行,各消防署へ配属
〈④ 96,121,164−165〉
3・10
学徒消防隊の学苑生 7人,東京大空襲で焼死〈④ 121,164−165〉
3・18
内閣,「決戦教育措置要綱」決定,国民学校初等科を除く学校における授業を 4月 1日より向う 1年間停止〈④ 44,108〉
3・20
研究および教育施設の新設・拡充ならびに田中穂積前総長記念事業等に要する資金の調達を
目的とする臨時資金部設置〈④ 527〉
3・29
幹事・副幹事制を廃止〈④ 95〉
3
教場での一斉入学試験を中止し,内申書に基づく人物・知力の総合考査により合否を判定
〈④ 98〉
4・1
専門部工科に生産技術科増設〈④ 31−33〉
4・2
最初の 2年制第一・第二高等学院修了生を迎えて学部入学式挙行〈『早稲田学園彙報』昭和 20年 5月 1日号〉
4・27
文学部教室と武道館,東部軍が使用〈④ 97〉
4
学徒錬成部廃止に伴い,同音楽隊は音楽協会に復旧〈④ 586〉
5・1
本部事務組織を教務部(教務課・学生課)・経理部(会計課・調度課・施設課)・庶務部(庶務課・
人事課)の 3部 7課制に改組し,学徒錬成部を廃止してその管掌事務を学生課に吸収したほか,
法文系事務所(連合事務所)を廃止〈④ 95−96,105,131〉
5・10
空襲による被害拡大を予防するため,第二高等学院に近接する木造建物 4棟の取り壊し決定
〈④ 96〉
5・20
教務部,『早稲田学園彙報』〔第 5号〕刊行,これを以て廃刊〈④ 535〉
5・22
「戦時教育令」(勅令第 320号)公布され,報国隊を廃止,また 6月下旬までに学徒隊結成を義務
づける〈④ 109,132〉
5・25
空襲により,第一高等学院校舎,理工学研究所,大隈会館,恩賜記念館,電気・機械実験室,製
図教室,専門部工科校舎等全焼,演劇博物館,文学部・高等師範部校舎,商学部校舎,理工学
部研究室等半焼〈④ 140−152〉
6・29
食糧増産,軍需生産,防空防衛等に教職員・学生生徒を動員するための学徒隊,結成式挙行
〈④ 132〉
7・12
大隈会館焼け跡の一部と戸塚道場の一部を農耕地として憲兵司令部へ貸与を決定〈④ 97〉
7・17
御真影,軽井沢の旧野球部合宿所に疎開〈④ 143〉
7−8
図書館・演劇博物館・本部の図書・書類・器具の一部を疎開〈④ 99〉
8・7
豊川海軍工廠への空襲により,勤労動員中の学苑生 15人死亡〈④ 127,134−147〉
8・15
終戦の詔書放送(第二次世界大戦終結)
8・16
学徒勤労動員解除〈④ 133〉
8・23
陸軍軍事教官退任〈③ 874〉
8・28
文部省,9月中旬より授業再開を指令〈④ 315−316〉
8・30
特設防護団解散〈④ 295〉
9・6
優等賞廃止〈③ 647〉
9・8
御真影,軽井沢より復校〈④ 143〉
9・8
第一・第二高等学院,授業再開〈記要 17・162〉
9・11
学部・専門部・高等師範部の最高学年を除く各学年,授業再開〈④ 316〉
9・15
日高只一,高等師範部長辞任,原田実,第一高等学院長辞任し,第二高等学院長赤松保羅を
高等師範部長に嘱任,岡村千曵を第一・第二高等学院長兼務に嘱任〈④ 318,理事〉
9・20
小野梓賞廃止〈③ 639〉
9・30
学部・専門部・高等師範部・早稲田専門学校,卒業式(後 3者は 5回目かつ最後の繰上げ卒業
(修業年限 6ヵ月短縮))挙行〈記要 17・162−163〉
10・1
学部第 2・3学年,授業再開〈④ 316〉
10・3
千葉県印旛郡佐倉町所在の元東部第 64部隊兵舎へ高等学院を移転するとともに農学部をも新
設する計画を立て,その一時借用を申請〈④ 296,525〉
10・4
理事塩沢昌貞死去(7月 7日)および杉森孝次郎辞任(昭和 19年 10月 5日)に伴い,堤秀夫お
よび磯部諭一郎,理事に就任,また磯部に代って黒田善太郎,監事に就任〈維持〉
10・4
林癸未夫,政治経済学部長辞任し,久保田明光嘱任,中村宗雄,法学部長辞任し,大浜信泉嘱
任,北沢新次郎,商学部長辞任し,伊地知純正嘱任,大浜信泉,専門部法律科長辞任し,中村
弥三次嘱任〈理事〉
10・6
「戦時教育令」廃止〈④ 294〉
10・11
専門部・高等師範部・早稲田専門学校の制帽を丸帽から角帽にもどす〈④ 295〉
10・28
神宮球場で六大学OBの紅白野球試合開催〈④ 169,564〉
11・15
陸海軍諸学校の生徒を転入学させる〈④ 318〉
11・18
神宮球場でOB・現役一体のオール早慶野球戦が戦後最初の早慶戦として挙行〈④ 564−565〉
11・22
「体育会規程」制定され,体育会復活〈④ 562−563〉
11・23
ラグビー蹴球部のOBおよび学生,早慶戦挙行〈④ 567〉
11・26
第二高等学院生,学生大会を開き,陸士海兵からの優先転学反対を決議(戦後学生運動の嚆
矢)〈④ 453〉
11・29
中島正信,科外講演部長嘱任,伊地知純正,体育会長嘱任〈④ 562,理事〉
11上旬
疎開させていた図書・書類・器具の復校完了〈④ 295〉
12・1
学友会復活〈④ 453〉
12・6
臨時佐倉設営部(部長内藤多仲)設置〈④ 296〉
12・7
「学生ノ会ニ関スル規則」を廃止し,「学生団体規程」制定〈④ 453,578〉
12・8
バスケットボール部,復活第 1回早慶戦挙行〈④ 569〉
12・10
全学学生大会開催され,学生共済会設立を決議〈④ 450〉
12・13
GHQその他外部機関との折衝に当る連絡部(部長伊地知純正)設置〈④ 437,理事〉
12・15
臨時資金部,戦災復興計画の遂行をも担って再発足〈④ 527〉
12・21
政治経済学部教授会,アメリカ亡命中の大山郁夫の教授復帰を決議〈④ 499〉
12・26
東伏見学生寮(約 280人収容可能)修復〈④ 447〉
12・27
御真影を文部省に奉還〈④ 295〉
12・31
理工学部の石油工学科を燃料化学科と改称し,機械工学科の航空力学および航空機の 2科目
を廃止し,専門部工科航空機科を運輸機械科と改称したほか,早稲田高等工学校航空機科を廃
止し,その 2年生は機械科または電気科の第 2学年に,1年生は本人の希望する他科の第 1学
年に転科させる〈④ 344−348,記要 17・163〉
12上旬
早大職員消費組合結成〈④ 478〉
この年秋
社会主義・共産主義の研究を目指す社会科学研究会結成〈④ 585〉
この年秋
学生雄弁会および弁論部結成〈④ 587−588〉
1946年/ 昭和 21年
1・10
理事会,『早稲田大学新聞』の復刊を許可し,年額 2万円の補助金支給を決定〈④ 591〉
1・15
学部・付属学校の学生委員,連合学生委員会結成〈④ 454〉
1・18
文化会幹事会結成〈④ 454〉
1・22
体育会幹事会結成〈④ 454〉
1・25
中野登美雄,総長辞任〈④ 19,306〉
1・26
連合学生委員会・文化会幹事会・体育会幹事会が一体となった学生自治委員会,学生大会を開
催し,学生自治会の承認と私学の復興と戦災校舎の復旧を決議〈④ 454〉
1・29
千葉県印旛郡佐倉町所在の元東部第 64部隊兵舎の一時借用につき許可を得るが,高等学院
の佐倉移転および農学部の新設計画は実現せず〈④ 296,525〉
1・31
理事会,校規を改正して総長決定方法を改めることを決議し,これが実現するまで総長欠員のま
まとし,常務理事林癸未夫を総長事務代行とする〈理事〉
1・31
理事会,学苑周辺の都市計画を立案するための早稲田文教地区計画委員会の設置を決議〈理
事〉
2・1
京口元吉,文学部講師に復職〈④ 306,518〉
2・8
職員会(委員長吉田初雄),「早稲田大学職員会規約」施行〈④ 476−478〉
2・12
維持員会,校規改正案起草委員会(委員長黒田善太郎)設置を決議〈④ 404−405〉
2・14
興亜人文科学研究所,人文科学研究所(所長北沢新次郎)と改称〈④ 1144〉
2・25
新聞会,『早稲田大学新聞』(当初は『早大新聞』)再刊〈④ 591−592〉
2
排球部,戦後第 1回部員総会を開催し,活動再開〈④ 573〉
2頃
学生自治委員会の有志による大山郁夫帰校促進準備会発足〈④ 501〉
3・7
第二高等学院教員組合(代表委員長竹野長次)結成〈④ 471−474〉
3・14−4・18
「高等学校規程中改正」(昭和 21年 5月 4日付文部省令第 18号)により高等学校・大学予科の
修業年限が 3年に延長される結果,昭和 21年度より第一・第二高等学院の修業年限が 3年に復
旧するため,今回は高等学院修了者が皆無となるので,一般より入学志願者を公募して学部編入
試験実施〈④ 348−349,『早大新聞』昭和 21年 2月 25日号〉
4・1
「大学院特別研究生規程」施行,文部大臣の認可承認を得ていた特別研究生関係事項が総長の
処理に委ねられる〈④ 24−25,349〉
4・15
維持員会,校規改正案起草委員会の答申を承けて,校規および維持員会規程・評議員会規程
の改正ならびに総長選挙規程の新設を決議,19日に改正校規認可願を文部大臣に申請し,5月
10日に認可を得,5月 15日より発効〈④ 407−419〉
4
各学部とも選択科目を大幅に復活させて学年制を加味した科目制に改めるとともに,文学部は各
学科の専攻を復活させた上で芸術学専攻を哲学科から文学科へ移し,哲学科の倫理学専攻を
廃止し,文学科の露文学専攻を復活させ,史学科に人文地理学専攻を新設〈④ 356,358−392〉
4
高等学校および大学予科の修業年限が 3年に復旧したのに伴い,第一・第二高等学院も 3年制
となる〈④ 348−349〉。また,昭和 16年度に設置された特修科を廃止〈記要 20・212−213〉
4
専門部および早稲田専門学校の経営科,旧称の商科に改める〈④ 356〉
4
高等師範部は 4年制に復旧して女子の入学を認めると同時に,英語科の生徒募集を再開し,国
民体錬科を体育科と改称するとともに専攻科を廃止し,社会教育科を新設
〈④ 342−344,348,350,356−357〉
4
早稲田工手学校の生徒募集を停止し,夜間 4年制の早稲田工業学校(校長山ノ内弘)を開校,
早稲田工手学校在籍者を早稲田工業学校の第 1または第 2学年へ移行〈④ 1029〉
4
早稲田文教地区計画委員会,早稲田文教地区案を完成(実現せず)〈④ 314〉
4
フェンシング部(部長滝口宏),体育会に加入〈④ 574〉
5・1
学生共済会,事業開始〈④ 450−451〉
5・27
学生雄弁会と弁論部,合併して雄弁会(会長中谷博)となる〈④ 588〉
5・31
理事会,学生自治会の設立を承認〈④ 454,457〉
6・7
評議員会(会長新井章治),新校規による維持員 35名を選出〈④ 429〉
6・10
総長選挙人会(総数 90名)が招集されて津田左右吉を総長に選出,津田は総長就任を固辞
〈④ 424−426〉
6・14
大山郁夫帰校促進準備会,大山招聘の決議文採択し,大山郁夫帰校促進会と改称
〈④ 501−502〉
6・15
維持員会,小汀利得を維持員会長に選出し,大隈信常を新校規に基づく名誉総長に推挙
〈④ 429−430〉
6・15
工芸美術研究所付属技術員養成所(所長今和次郎),東伏見運動場の旧体育部校舎で開校,
本科 1年・専攻科 2年のうち本科の授業を開始〈④ 357−358,記要 17・168〉
6・23
ア式蹴球部,部員総会を開き活動再開〈④ 568〉
6・29
総長選挙人会が再度招集されて島田孝一を第 6代総長に選出〈④ 427−428〉
6下旬
「好ましからざる教育者」を追放するための「早稲田大学学部教員適格審査委員会規程」制定さ
れ,大規模な審査開始〈④ 306,480〉
6頃
自動車部,活動再開〈④ 573〉
7・5
維持員会,新校規による理事および監事を選出し,総長島田孝一のほかに赤松保羅・伊原貞敏・
大浜信泉・反町茂作・上坂酉蔵(酉三)・吉村正が理事に,黒田善太郎・板谷宮吉が監事に就任
〈④ 430〉
7・15
維持員会,上坂酉蔵(酉三)・伊原貞敏・吉村正の常務理事就任を承認〈④ 430〉
8
早稲田大学出版部,戦争末期に中断した通信講義録『中学講義』と『女学講義』の刊行再開
〈④ 556〉
9・16
各学部長,付属学校長,付属機関長で構成される部科長会設置〈④ 434−435〉
9・16
本部事務組織の 3部 7課制を廃止し,秘書課・庶務課・教務課・学生課・就職課・調査課・教育普
及課・会計課・営繕課の 9課制に改めたほか,連絡部を渉外部と改称〈④ 436−437〉
9・17
島田孝一総長就任式挙行〈④ 428,431〉
9・26
理事会,千葉県印旛郡佐倉町所在の元東部第 64部隊兵舎借用を断念,臨時佐倉設営部を廃
止,30日の維持員会はこれを承認〈④ 296〉
9・30
人文科学研究所,機関誌『人文科学研究』第 1号発刊〈④ 1145〉
9
上坂酉蔵(酉三),早稲田専門学校長辞任し,安部民雄,校長事務取扱嘱任〈理事〉
10・1
政治経済学部に新聞学科を増設し,同学部 1年生および在学生中より希望者 50人を編入して
発足〈④ 351−353〉
10・1
日高只一,文学部長辞任し,谷崎精二嘱任,内藤多仲,理工学部長辞任し,山本研一嘱任,岡
村千曵,第一・第二高等学院長辞任し,第一高等学院長に渡鶴一嘱任,第二高等学院長に竹
野長次嘱任,中村佐一,専門部政治経済科長辞任し,時子山常三郎嘱任,中村弥三次,専門部
法律科長辞任し,外岡茂十郎嘱任,安部民雄,早稲田専門学校長嘱任〈理事〉
10・8
文部省,教育勅語奉読の廃止を通達〈④ 295〉
10・24−26
「日本国憲法」(11月 3日公布,昭和 22年 5月 3日発効) 啓蒙のため新憲法講座を大隈講堂
で開催,一般に公開〈④ 302〉
10
佐野学,商学部講師に復帰〈④ 517−518〉
10
石川登喜治,鋳物研究所長辞任〈理事〉
11・12−16
津田左右吉,大隈講堂で特別講演会開催〈④ 426〉
11・13
新憲法公布の式典を大隈講堂で挙行〈④ 302〉
11・14
中島正信,科外講演部長辞任〈理事〉
11・17−12・5
文部省の委嘱による公民文化講座を 5回に亘り大隈講堂で開催〈④ 309−310〉
11・21
中谷博,科外講演部長嘱任〈理事〉
12・5
企画委員会(委員長吉村正)設置,早稲田大学のあり方を多角的に審議〈④ 439,917−918〉
12・10
教育制度研究委員会(委員長島田孝一)発足,新制早稲田大学の基本構想を検討
〈④ 918−921〉
1947年/ 昭和 22年
1・11
名誉総長大隈信常死去,以後名誉総長を置かず〈④ 430〉
1・15
付属機関長を選挙で選ぶことを謳った「図書館規程」「坪内博士記念演劇博物館規程」「理工学
研究所規程」「鋳物研究所規程」制定・施行(選挙制は永続せず)〈④ 435,1142〉
1・22
企画委員会,入試制度刷新などを総長に建議〈④ 439〉
2・15
維持員会,各付属機関において選出された候補者を長に嘱任し,図書館長は林癸未夫から岡村
千曵に交替,鋳物研究所長は飯高一郎となる(演劇博物館長吉村繁俊と理工学研究所長内藤
多仲は重任)〈④ 1143,維持〉
2・15
臨時資金部廃止〈④ 527−528〉
3・1
理事会の諮問機関として教職員の採用・解任を審議する人事委員会設置〈④ 310,437〉
3・31
「教育基本法」および「学校教育法」公布〈④ 913−916〉
3
軟式庭球部(部長末高信),体育会に加入〈④ 576〉
4・10
「早稲田大学学生自治会規程」施行〈④ 458−462〉
4・25
教育普及課(のち早稲田大学彙報編輯室)より『早稲田大学彙報』創刊〈④ 540,777〉
4
早稲田工業学校に新制中学校を併設,3年生のみを収容し,早稲田工業学校が次年度に早稲
田工業高等学校に昇格するとともに廃校となる〈④ 356,926,1029−1030〉
5・7
「学生団体規程」に代えて「学生の会に関する規程」制定・施行〈④ 578−580〉
5・22
各学生の会の代表者から成る文化会設立準備委員会,第 1回会合開催〈④ 580〉
5・29
大隈精神昂揚講演会,6月 20日まで 3回に亘り大隈講堂で開催〈④ 439−440〉
5・30
GHQより公職追放の指令を受けた石橋湛山,維持員および評議員の辞任願を提出
〈④ 311−312〉
6・12
教職員と学生との意思疎通を図るための「教職員学生協議会規程」制定・施行〈④ 463−465〉
6・23
「早稲田大学学生自治会規程」に基づく第 1回自治議会が 26日まで開催され,人事委員会廃止
をはじめ 17項目から成る決議文を総長に提出〈④ 465−467〉
6・27
上坂酉蔵(酉三),理事(常務理事)辞任し,池原義見,理事(常務理事)就任〈④ 430〉
7・8
大学基準協会創立,会員校の資格審査の基準となる「大学基準」決定〈④ 916,『大学基準協会
十年史』96−97〉
7末
早稲田大学復興会発足,復興費 2,000万円(のち 1億円に修正)の募金を開始,併せて地方校
友会の再建に努める〈④ 528−529,621〉
9・16
教育制度研究委員会,答申書「学制改革に関連して本大学の採るべき方策について」を総長に
提出〈④ 918−924〉
9・19
文化団体連合会(文化会設立準備委員会の後身)の常任委員会,文化団体連合会規約草案を
決定し,翌 20日に学苑当局に承認を求める〈④ 580〉
9・28
学部卒業式挙行(9月挙行の卒業式は今回で最後)〈記要 17・170〉
9・29
英語の勉学を希望する在学生および校友を対象とする 3ヵ月課程の特設英語講座,開講式挙行
(翌昭和 23年 9月より 12月までの第 4回を以て廃止)〈記要 17・170−171〉
10・10
教育制度改革委員会(委員長大浜信泉)発足,新制早稲田大学の構想を更に検討〈④ 924〉
10・15
維持員会,教旨検討委員会(委員長大浜信泉)の設置を決定〈④ 439,1068〉
10・23
大山郁夫,亡命先のアメリカより帰国〈④ 504−507〉
10・28
大学・学生自治会共催による大山郁夫先生歓迎大会,大隈講堂で開催〈④ 510−511〉
10・29
維持員会長小汀利得,GHQより公職追放の指令を受ける〈④ 312〉
10
会計課を経理課と,学生課を学生生活課と改称したほか,資材課を新設〈④ 437〉
12・15
小汀利得,維持員会長辞任し,原安三郎就任〈④ 312−313〉
この年
軟式野球部(部長毛利亮),体育会に加入〈④ 575〉
1948年/ 昭和 23年
1・15
文部省,大学設置委員会を設置し,大学基準協会の採択した「大学
1
早稲田大学出版部,戦争末期に中断した通信講義録『商業講義』の刊行再開〈④ 558〉
1
津田左右吉,昭和 21年 11月に大隈講堂で行った特別講演会の速記に手を入れて『学問の本
質と現代の思想』を出版し,その印税を津田奨学資金として寄贈〈④ 426〉
2・12
吉村正,理事(常務理事)辞任〈④ 430〉
2・18
本部事務組織に部制が復活し,総務部(秘書課,庶務課,経理課,就職課),教務部(教務課,
学生生活課,調査課,教育普及課),施設部(営繕課),渉外部の 4部 9課となる〈④ 437−438,維持〉
3・16
教育制度改革委員会,『学制改革要綱(案)』を答申〈④ 924,930−932〉
3・26
日本私立大学協会結成〈④ 1057−1058〉
3
早稲田工業学校廃校〈④ 1029−1030〉
4・1
大山郁夫,政治経済学部および専門部政治経済科教授に復職〈④ 480,515−516〉
4・1
年金制度の整備に伴い「教職員積立金規程」廃止〈④ 1167〉
4・29
戦時中に中断した春季校友大会,5年ぶりに開催〈④ 544−545〉
4
専門部政治経済科に自治行政専攻を設置〈④ 354−356〉
4
高等師範部体育科は生徒募集を停止するとともに,在籍する 2・33年生の修業年限を 3年に短
縮〈④ 344〉
4
新制の夜間 4年制の早稲田工業高等学校(機械科,電気科(第一分科,第二分科),金属工業
科,建築科,土木科)が発足し,早稲田工業学校の生徒を第 1・2学年に移行させて 4月 24日に
開校式(校長山ノ内弘)を挙行〈④ 356,819,1029−1030〉
4
工芸美術研究所付属技術員養成所,生徒募集を停止〈④ 358〉
5・10
本部事務組織が統廃合され,調査課と教育普及課を廃止し,秘書課を秘書役と,庶務課を総務
課と改称し,施設部に臨時建設課と総務部に資材課を新設〈④ 438〉
5・14
久保田明光,理事就任〈④ 430−431,維持〉
7・14
「人文科学研究所規程」制定,翌 15日施行され,人文科学研究所は大学直属の付属機関となる
〈④ 1144−1145〉
7・20
『早稲田大学彙報』第 2巻第 7・8号刊行,これを以て廃刊〈④ 545〉
7・30
新制早稲田大学の設置認可を文部大臣に申請〈④ 932〉
9・15
第一・第二高等学院,専門部,高等師範部,早稲田専門学校に学部教授会と同等の教授会を設
け,かつこれらの付属学校長を教授会の選挙に委ねる〈④ 434〉
9・18
全日本学生自治会総連合(全学連)結成大会,20日までの 3日間に亘り学苑および東京商科大
学で開催〈④ 468〉
9・20
校友会,『早稲田学報』復刊第 1号刊行〈④ 546−547,777−778〉
10・3
早稲田工手学校,最後の卒業式を挙行し,11月 1日付で廃校〈④ 1029〉
この年春
伊地知純正,体育会長辞任し,堤秀夫就任〈理事〉
この年
東洋美術陳列室,図書館 2階の小部屋に開設〈④ 1146〉
1949年/ 昭和 24年
1・20
早稲田大学奨学基金を設定し,大日本育英会の奨学金を貸与されていない学生に授業料相当
額を給与〈④ 441−442,理事〉
2・1
文化団体連合会,大学より公認〈④ 580−584〉
3・26
第一・第二高等学院,最後の修了式を挙行,修了生は 4月開校の新制学部の第 3学年に進学し,
第 1・2学年修了生はそれぞれ新制学部の第 1・2学年に移行〈記要 17・172〉
3・26
野球部および稲門クラブ,安部磯雄(2月 10日死去)追悼式を戸塚球場で挙行,戸塚球場を安
部球場と,合宿所を安部寮と改称〈④ 565〉
3・31
第一・第二高等学院廃校〈④ 1036〉
4・1
久保田明光,第一政治経済学部長(政治経済学部長兼務)嘱任,大浜信泉,第一法学部長(法
学部長兼務)嘱任,谷崎精二,第一文学部長(文学部長兼務)嘱任,赤松保羅,教育学部長(高
等師範部長兼務)嘱任,伊地知純正,第一商学部長(商学部長兼務)嘱任,山本研一,第一理工
学部長(理工学部長兼務)嘱任,時子山常三郎,第二政治経済学部長(専門部政治経済科長兼
務)嘱任,外岡茂十郎,第二法学部長(専門部法律科長兼務)嘱任,佐藤輝夫,第二文学部長嘱
任,末高信,第二商学部長(専門部商科長兼務)嘱任,堤秀夫,第二理工学部長(専門部工科長
兼務)嘱任,竹野長次,早稲田高等学院長嘱任〈④ 936,1038,維持〉
4・1
体育部(部長事務取扱佐々木八郎)新設され,新制学部全学生を対象に保健体育科目の授業を
担当〈④ 946〉
4・1
早稲田奉仕園の土地・建物(昭和 18年 1月取得)の基督教新生社団(日本バプテスト伝道社団
の後身)への返還契約締結〈④ 1120−1121〉
4・15
時子山常三郎,専門部政治経済科長辞任し,久保田明光嘱任(政治経済学部長・第一政治経済
学部長兼務),外岡茂十郎,専門部法律科長辞任し,大浜信泉嘱任(法学部長・第一法学部長
兼務),末高信,専門部商科長辞任し,伊地知純正嘱任(商学部長・第一商学部長兼務),安部
民雄,専門学校長辞任し,時子山常三郎嘱任〈維持〉
4・16−18
新制早稲田大学各学部,第 1回入学式挙行〈学報 3巻 4号・4〉
4・21
新制早稲田大学の設立,文部大臣の認可を得る。第一政治経済学部(政治学科,経済学科,新
聞学科,自治行政学科),第一法学部,第一文学部(哲学科〈東洋哲学専修,西洋哲学専修,心
理学専修,社会学専修,教育学専修〉,文学科〈国文学専修,英文学専修,仏文学専修,独文学
専修,露文学専修,芸術学専修〉,史学科〈国史専修,東洋史専修,西洋史専修〉),教育学部
(教育学科,国語国文学科,英語英文学科,社会科),第一商学部,第一理工学部(機械工学科,
電気工学科,鉱山学科,建築学科,応用化学科,金属工学科,電気通信学科,工業経営学科,
土木工学科,応用物理学科,数学科),第二政治経済学部(政治学科,経済学科),第二法学部,
第二文学部(哲学専修,心理学専修,社会学専修,教育学専修,日本文学専修,外国文学専修,
芸術学専修,史学専修),第二商学部,第二理工学部(機械工学科,電気工学科,建築学科,土
木工学科)を置き,新制高等学校卒業を入学資格とし,修業年限は 4年となる〈④ 932〉
4・22
教旨検討委員会の建議に基づき教旨を改訂し,「立憲帝国の忠良なる臣民として」の語句を削除
〈④ 439,1069〉
4・23
早稲田高等学院(新制中学卒業を入学資格とし,修業年限 3年),第 1回入学式挙行〈④ 1038〉
4・24
新制大学開設記念式典,安部球場で挙行〈④ 932〉
4
学部(旧制)・専門部・高等師範部・早稲田専門学校・高等工学校,学生・生徒募集を停止〈記要
17・173〉
4
早稲田大学出版部,従来の通信講義録『中学講義』『女学講義』『商業講義』を『中学科講義』『商
業高等科講義』に全面的に改めたほか,『新制高等学校講義』を発刊〈④ 942〉
4
劇研究会と学生劇場とが合併して演劇研究会結成〈④ 590〉
5・6−13
第 1回大隈記念祭開催〈④ 441,519,1099−1100〉
5・25
新制早稲田大学の内容に添った改正校規が文部大臣の認可を得,施行〈④ 1075〉
5
戸山町の早稲田高等学院および早稲田工業高等学校の校舎新築第 1期工事竣工
〈④ 1120,1121〉
6・10
坪内雄蔵の旧宅「双柿舎」(在熱海)が国劇向上会より譲渡される〈④ 1122〉
6・10
維持員会,学徒錬成部跡地の一部 3,188坪の売却決定〈⑤ 158〉
6・15
大隈信幸より大隈重信関係文書が寄贈される〈③ 175−176,④ 1148,学報 3巻 8号・3〉
6・28
総長選挙人会,島田孝一を総長に再選〈④ 1096〉
6
部科長会を学部長会議と改称〈④ 1133〉
7・1
高田馬場−早大正門間にスクールバス開通〈学報 3巻 7号・1〉
7・4− 8・6
夏季学期開催〈④ 940,理事〉
7・5
赤松保羅・伊原貞敏・久保田明光,理事辞任し,伊地知純正・山本研一・吉村繁俊・吉村正就任
〈維持〉
7・5
久保田明光,政治経済学部長・第一政治経済学部長・専門部政治経済科長辞任し,中村佐一嘱
任〈維持〉
7・25
本部事務組織を改め,秘書役を総務部より独立させて秘書室とし,学生厚生部を新設して総務部
より就職課を,教務部より学生生活課をこれに移し,第二学部関係の事務連絡を統轄する第二事
務部と、校外教育を担当する教育普及部を新設,また教務部に調査課復活〈④ 1156〉
7
古川晴風ら 4名,第 1回ガリオア基金留学生に選抜〈学報 3巻 8号・1,④ 1185〉
10・1
外岡茂十郎,第二法学部長辞任し,和田小次郎嘱任,山本研一,第一理工学部長辞任し,堤秀
夫嘱任(理工学部長・専門部工科長兼務),堤秀夫,第二理工学部長辞任し,帆足竹治嘱任,師
岡秀麿,体育部長嘱任〈維持〉
10・6
科外講演部廃止〈④ 1156〉
11・1−15
早稲田祭(準公認第 1回)開催〈⑤ 822〉
11・3
津田左右吉,文化勲章受章〈⑤ 942−943〉
11・17
「副手規程」制定〈④ 1135〉
12・1
面影橋−高田馬場駅間に都電開通〈④ 726,『早稲田大学新聞』昭和 24年 11月下旬号,⑤ 845〉
12・15
「私立学校法」公布,翌昭和 25年 3月 15日施行〈④ 1059,1071〉
12・22
寄附生命保険を朝日生命保険相互会社と契約〈④ 1127〉
1950年/ 昭和 25年
1・21
維持員会,昭和 20年 12月修復の東伏見学生寮 3棟の富士産業株式会社よりの買収を決定〈④
1122〉
2・15
理事会,大隈研究室設置を決定し,4月,図書館内に発足〈④ 1148〉
2
大学院設置準備委員会設置〈④ 1006〉
3・1
教員個人に対する研究助成を行う「特殊研究助成費規程」制定,4月 1日より施行
〈④ 1154−1155〉
3・1
双柿舎を運営する双柿会発足し,双柿舎を一般に公開〈④ 1179〉
3・31
工芸美術研究所付属技術員養成所廃止〈④ 358,⑤ 36〉
4・10
高等学院ならびに早稲田工業高等学校校舎新築第 2期工事竣工〈④ 1120,1121〉
4・12
国会稲門会結成〈学報 600・29〉
4・22
教員が 1年間講義を担当せず人文科学研究所で研究に専念するための学内派遣研究員制度
(国内研究員制度の前身)発足〈④ 1149,1153〉
5・2
大学院設置準備委員会,報告書を総長に提出〈④ 1006〉
5・20
健康相談所を廃止し,現 1号館地下に設けられた診療所(所長日影董)開所式挙行
〈④ 1170−1172〉
6・11
戸塚警察署,5月 30日の「人民大会事件」に関連して学生自治会事務所および共産党細胞事務
所を捜索〈⑤ 327−328〉
6・15
大浜信泉,理事辞任し,吉村正の後任と併せて,小林八百吉および外岡茂十郎,理事就任〈維
持〉
6・28
大隈会館の復旧工事竣工し,翌 29日に開館式挙行〈④ 1120,1122〉
8・9−25
教育普及部と校友会の共催により北海道および東北地方で第 1回社会教育講座を開催〈学報
603・28,⑤ 626−627〉
9・28
学生自治会,レッド・パージ反対を掲げて学生大会を開催強行,大会後のデモで警官隊と小ぜり
合い〈⑤ 328−329〉
10・17
学生自治会,レッド・パージ反対および平和と大学擁護を訴える集会を開いたのち構内をデモ行
進し本部 2階会議室に乱入,これを占拠したので,学苑当局は戸塚警察署に警官隊の出動を要
請,警官隊は 143人(うち学外者 40人)を検挙〈⑤ 331−332〉
10・18
9月 28日事件およびその後の試験ボイコットに関与した学生 26人を除籍等処分〈⑤ 333〉
10・27
10月 17日事件で検挙された学生のうち 86人を除籍処分〈⑤ 333〉
10
診療所に歯科およびレントゲン科増設〈④ 1172〉
11・3
正宗忠夫(白鳥),文化勲章受章〈⑤ 942〉
12・15
維持員会,「私立学校法」に基づく学校法人早稲田大学校規を承認〈④ 1080−1089〉
12・15
教員の海外留学を再開するための「留学生規則」制定〈④ 1150−1152,1182〉
12・20
付属早稲田高等学院を早稲田大学高等学院と,付属早稲田工業高等学校を早稲田大学工業高
等学校と改称〈④ 1030,1038〉
1951年/ 昭和 26年
2・15
学校法人早稲田大学校規,文部大臣の認可を得る〈④ 1089〉
3・1
新校規を登記,財団法人時代の維持員(維持員)会は評議員(評議員)会,評議員(評議員)会は
商議員(商議員)会と改称〈④ 1089〉
3・25
旧制学部最後の卒業式と新制学部最初の卒業式挙行〈記要 19・93〉
3・26
初の「年金規則」制定,4月 1日より施行〈④ 1164〉
3
工業高等学校の卒業生若干名を第二理工学部へ推薦入学許可〈⑤ 302〉
4・1
第一文学部文学科の芸術学専修を廃止し,演劇専修および美術専修を新設〈④ 941〉
4・1
新制大学院の修士課程発足,5日に文部大臣の認可を得る。政治学研究科(政治学専攻),経
済学研究科(経済学専攻),法学研究科(民事法専攻,公法学専攻,基礎法学専攻),文学研究
科(東洋哲学専攻,西洋哲学専攻,心理学専攻,社会学専攻,教育学専攻,日本文学専攻,英
文学専攻,仏蘭西文学専攻,独逸文学専攻,露西亜文学専攻,芸術学専攻),商学研究科(経
営学専攻,商学専攻),工学研究科(機械工学専攻,電気工学専攻,建設工学専攻,鉱山及金
属工学専攻,応用化学専攻)を設置〈④ 1005〉
4・1
工業高等学校の金属工業科,生徒募集を停止〈④ 1031,⑤ 301〉
4・25
喜久井町の理工学研究所の復旧工事竣工〈④ 1120,1122−1123,1147〉
5・11
新制大学院,第 1回入学式挙行〈学報 612・32〉
5・15
総務部より経理部を分離・独立させるとともに,総務部を庶務部と改称〈④ 1156−1157〉
5・31
高等師範部および早稲田専門学校廃校〈④ 950,⑤ 36−38〉
5・31
体育部および体育会のあり方を検討する体育制度委員会(委員長大浜信泉)設置〈理事,
⑤ 791−792〉
5
大隈研究室,『大隈研究』第 1輯刊行〈④ 1149〉
6・22
日本私立大学連盟結成〈④ 1060−1062〉
7・1
健康保険組合,厚生大臣より設立認可を得る〈④ 1173〉
7・31
早稲田大学復興会廃止〈④ 1129〉
9・15
寄附金を扱う常設機関として資金部設置〈④ 1129〉
9・22
総長選挙人会,島田孝一を総長に三選〈④ 1097〉
10・15
「部科長会規程」を廃止し(ただし部科長会は昭和 24年 6月に学部長会議と改称),「学部長会
規程」制定,翌昭和 27年 1月 16日施行〈④ 1132−1133〉
10・16
学生共済会解散し,早稲田大学消費生活協同組合結成〈⑤ 781−782〉
10・21
空襲で焼失した恩賜記念館の跡地に法文系大学院校舎(現 7号館)と,その西側に理工系大学
院校舎(現 12号館)とが竣工し〈④ 1120,1123−1124〉,大隈講堂で新制大学院開設式を挙行〈学
報 616・28〉
10・31
専門部および高等工学校廃校〈④ 356,950,1036,⑤ 38〉
1952年/ 昭和 27年
4・1
教育学部の教育学科を教育学課程と教育行政課程と社会教育課程の 3課程に,社会科を地理
歴史課程と社会科学課程の 2課程に分ける〈④ 1055〉
4・1
大学院文学研究科に史学専攻(修士課程)設置〈④ 1008,記要 19・97〉
4・22
運動各部の選手育成だけでなく体育部で正課体育の指導をも担当していた体育会と,各学部の
保健体育教育を担当する体育部とを廃止し,両者を統合した体育局(局長大浜信泉)設置
〈④ 947,⑤ 791−792〉。運動各部の部員は正課の体育実技を免除〈記要 19・97〉
4・22
校規改正案起草委員会が設置され,法人役員の任期延長および増員を検討〈④ 1091−1092〉。
校規改正は見送られる
5・8
5月 1日の「血のメーデー事件」に関係した学苑生を調査中の神楽坂警察署員が構内で学生の
吊るし上げに遭い,救出のため警官隊が突入して多数学生が負傷(「5月 8日早大事件」)
〈⑤ 341−348〉
5・21
「5月 8日早大事件」に関し校友国会議員の調停により大学と警察との和解成立〈⑤ 354−355〉
5
大学院博士課程設置研究委員会設置〈④ 1006〉
7・1
第二事務部と渉外部を廃止し,学生厚生部を学生部,教育普及部を社会教育部とそれぞれ改称
し,教務部より調査課を分離・独立させて調査部とし,庶務部に厚生課を新設〈④ 1157〉
9
小倉房蔵寄贈の完之荘の大隈庭園内への移築完成〈④ 1122〉
10・18
大学院博士課程設置研究委員会,博士課程に関する成案を総長に提出〈④ 1006〉
10・18
共通教室校舎(21号館♢♢現 10号館)竣工〈④ 1120,1124〉
10・21
創立 70周年記念式典挙行〈④ 1106−1112〉
12・5
教員互助会発足〈④ 1167−1168〉
1953年/ 昭和 28年
1・26
山岳部,アコンカグア登頂〈④ 1188〉
4・1
文学研究科史学専攻および法学研究科基礎法学専攻を除く大学院各研究科で博士課程発足,
また商学研究科の経営学専攻を廃止〈④ 1007−1008,1055,記要 19・99〉
4・1
教員互助会を廃止して教職員厚生会発足〈④ 1168〉
4
音楽協会より管弦楽団およびグリー・クラブが分離・独立〈⑤ 829,831〉
7・15
総長および理事の任期を 3年から 4年に延長,監事の任期を 3年から 2年に短縮し,理事を 7名以内から 9名以内に,評議員を 45名から 57名にそれぞれ増員するとともに,常務理事の呼称
を常任理事に改める改正校規が評議員会で承認される。9月 24日に文部大臣の認可を得,法人
役員全員改選の翌昭和 29年 9月 1日より施行〈④ 1094〉
7
平田冨太郎・一又正雄・飯島小平,戦後最初の学苑派遣海外留学生として欧米に出発
〈④ 1182,1187〉
8・23
大日本育英会,日本育英会と改称〈『日本育英会十五年史』195,④ 1136〉
10・15
勤続 30年に達した専任教職員を対象とする永年勤続教職員表彰制度を制定し,10月 21日の
創立記念日に表彰〈④ 1162〉
11・3
小川健作(未明),文化功労者受章〈⑤ 944〉
12・10
人事委員会廃止〈④ 1131〉
12・17
学苑の教育制度全般について再検討するため学制研究委員会(委員長大浜信泉)設置
〈④ 1158,⑤ 257〉
12・17
野球部,台湾遠征に出発,翌年 1月帰国〈④ 1182,1189−1190〉
この年
教員の海外留学が困難なため,国内の他大学や企業に 1年間派遣する国内留学制度発足
〈④ 1186〉
この年
健康保険組合,逗子の民家を初の保養所として購入〈④ 1178〉
1954年/ 昭和 29年
1・30
応用化学科教室(9号館――現 6号館)第 1期増築工事竣工し,応用化学科は早稲田奉仕園よ
りここに移る〈④ 1120,1121,1124−1125〉
3・31
早稲田奉仕園の土地・建物をすべて旧所有者の基督教新生社団に返還〈④ 1120,1121〉
4・1
大学院文学研究科史学専攻に博士課程設置,工学研究科に応用物理学専攻(修士課程)設置
〈④ 1008,1056,記要 19・101−102〉
4・1
工業高等学校の土木科,生徒募集を停止〈⑤ 301〉
5・15
早稲田大学出版部より土地を借用して南門筋向いに学生会館竣工〈④ 1120,1125〉
5
練馬区上石神井所在の智山学園の土地・校舎および周辺土地を購入〈⑤ 155〉
9・1
前年に改正された校規施行〈④ 1094〉
9・22
総長選挙人会,大浜信泉を総長に選出〈④ 1137−1139〉
10・1
任期満了により,島田孝一,総長退任
10・2
大浜信泉,第 7代総長に就任
10・19
大浜信泉総長就任式挙行〈⑤ 50−51〉
11・3
山田三良,文化功労者受賞〈⑤ 944〉
11・20−24
大学側の意向を無視して早稲田祭挙行(のちにこれを第 1回と数える)〈⑤ 823〉
この年
東洋美術陳列室,学生会館に隣接する早稲田大学出版部元倉庫に移転〈④ 1146−1147〉
この年
健康保険組合,水上町湯檜曾に奥利根荘を,東京都西多摩郡桧原村に山の家を開設〈④ 1178〉
1955年/ 昭和 30年
1・17
資金部と社会教育部と調査部を廃止し,校友部と調度部と就職部と科外講演部を新設し,教務部
に調査係を置く〈④ 1158−1161〉
2・1
外国人留学生の受入枠を確保するための外国学生特別選考制度発足〈⑤ 100−101〉
2
図書館南側の増築工事竣工〈④ 1125−1126〉
3
早稲田大学奨学基金を廃止して大隈奨学基金を設定し,奨学生を一般奨学生と新入生対象の
特別奨学生との 2種に分ける〈⑤ 218〉
4・1
大隈研究室と人文科学研究所とを合併して大隈記念社会科学研究所に改組〈④ 1149,⑤ 125−126〉
4
アメリカ合衆国国務省国際協力局(ICA),大学間の研究者交換プログラムへの協力を学苑に打
診〈⑤ 71−72〉
5・16
株式会社館山製作所所有の千葉県館山市所在土地・建物を購入〈記要 14・134〉
5
学制研究委員会,夜間学部のあり方を検討する第二学部専門委員会(委員長上坂酉蔵)設置を
決定〈⑤ 257−258〉
6
ICAの提案を受けて理工学部とジョージア工科大学との提携を理工学部教授会に諮るも,否決さ
れる〈⑤ 73−75〉
7・11
館山寮開寮式挙行,正課体育および体育局各部の合宿所として使用〈学報 653・36〉
10
大浜信泉総長,ミシガン大学を訪問し,生産性向上の研究を目的とする教員交換協定の内容を
打ち合わせる〈⑤ 75−76〉
11・3
校友会が学苑創立 70周年を記念して募金した資金により,大隈庭園内に校友会館が竣工し,落
成式挙行〈④ 1115,1126〉
11・18
小野梓先生〔没後〕70年記念祭挙行〈⑤ 872−874〉
12・8
中華人民共和国科学院院長郭沫若来校〈⑤ 706,707〉
12
管弦楽団,交響楽団と改称〈⑤ 829〉
この年春
第一学部と第二学部の格差解消を目指す「単一学部制」実施要求運動が学生の間で高まる
〈⑤ 255−256〉
1956年/ 昭和 31年
1・19
ミシガン大学総長ハーラン・ハッチャー一行来校し,教員交換協定内容を煮詰める〈⑤ 77〉
2・1
ミシガン協定の受皿として生産研究所(所長大浜信泉)が開所式挙行〈⑤ 77〉
4・1
教育学部教育学科教育行政課程,学生募集を停止〈⑤ 285−286〉
4・1
重要事項を教職員に伝えるため庶務部より『早稲田大学広報』発刊〈④ 1161〉
4・5
理事会,産業の生産性向上を目的として研究者を交換することを謳ったミシガン大学との協定書
に調印〈⑤ 78−79〉
4・11
校友会と共催で第 1回全国支部長会を開催〈⑤ 929〉
5・9
ミシガン大学,学苑との研究者交換協定書に調印し,ミシガン協定が発効〈⑤ 79−80〉
5・17
理工学研究所,文部省輸入機械購入補助金で購入したボーイング社製アナログ型電子計算機
の公開実験を開催〈⑤ 139,広報昭和 31年 5月 26日号〉
5・23
アメリカ合衆国の血清学者A・ウィーナー来校〈⑤ 706〉
8・11
高等学院,戸山町キャンパスより練馬区上石神井へ移転し,9月 8日に移転祝賀会を開催〈広報
昭和 31年 9月 7日号〉
8・22
練馬区上石神井の高等学院,旧智山学園校舎の改築・増築工事竣工〈⑤ 155−157〉
8
ミシガン協定最初の学苑側派遣教員として,青木茂男出発〈⑤ 128〉
9・1
高等学院および工業高等学校の専任教員(会)を教諭(会)と改める〈広報昭和 31年 9月 12日
号〉
9・12
ミシガン協定を学問の独立に対する脅威と看做した学生,第 1回交換教授チャールズ・ゴーディ
来日予定の羽田空港と大隈銅像前とで集会を開催〈⑤ 84〉
9・24
ハワイに足止めされていたミシガン大学側第 1回派遣教授ゴーディ,来日〈⑤ 86〉
10・22
文部省,大学基準協会が決定する「大学基準」に代る「大学設置基準」を省令(第 28号)で制定・
施行〈⑤ 59,293,525〉
10・30
理工学研究所に放射性同位元素研究室が竣工し,11月 15日に開室〈⑤ 131,広報昭和 31年
11月 12日号〉
この年
早稲田大学出版部,通信講義録の購読者募集停止〈④ 942〉
1957年/ 昭和 32年
1・14
語学教育研究委員会(委員長渡鶴一)発足〈⑤ 136〉
1・23
前年 12月 23日に校友初の内閣総理大臣となった石橋湛山の総理大臣就任祝賀会を大隈庭園
で開催〈⑤ 940−941〉
1・25
創立 75周年記念事業実行委員会(委員長阿部賢一)設置〈⑤ 164−165〉
1
学部組織研究委員会(委員長大浜信泉)設置〈⑤ 259〉
3・15
名誉博士号贈呈制度制定〈⑤ 165−166,210〉
4・4
式服および学位章に関する規程が制定・施行され,肩にかける学位章は取得学位により色分けさ
れる〈⑤ 166,214〉
6・23
水泳部,中華人民共和国遠征に出発〈⑤ 700−701〉
9・5
診療所,現 1号館地下より早稲田大学出版部建物内に移転〈広報昭和 32年 9月 11日号,
⑤ 228〉
10・1
日本政府,オーストリアと留学生交換協定を締結〈⑤ 122〉
10・7
インド首相パンディット・ジャワハルラル・ネールに名誉博士号贈呈〈⑤ 211〉
10・19
理工学研究所に内藤多仲博士記念耐震構造研究館竣工〈⑤ 131−132〉
10・20
内閣総理大臣石橋湛山に名誉博士号贈呈〈⑤ 211〉
10・20
創立 75周年を記念して戸山町キャンパスに記念会堂竣工〈⑤ 194− 195〉
10・21
創立 75周年記念式典を記念会堂で挙行〈⑤ 172〉
11・5
ソヴィエト社会主義共和国連邦の生化学者A.オパーリン来学〈⑤ 706〉
11・25
フランスの哲学者ガブリエル・マルセル来学〈⑤ 706〉
11・30
創立 75周年を記念して法文系大学院校舎増築工事完成,大隈記念室および小野記念講堂を
設置〈④ 1123,⑤ 167−168〉
この年
健康保険組合,熱海所在建物を購入し保養所「熱海寮」を開設〈⑤ 230〉
1958年/ 昭和 33年
3・3
語学教育研究委員会,総長に報告書を提出〈⑤ 136〉
3
早稲田大学出版部,通信講義録全廃〈④ 942−943〉
4・1
第二理工学部電気工学科を,強電部門を主とする電気工学専修とエレクトロニクスを主とする電
気通信学専修との 2専修に分ける〈広報昭和 32年 2月 27日号,記要 19・108〉
4・1
高等学校教諭 1級免許を付与するため,修業年限 1年の専攻科(国語国文学専攻科,英語英文
学専攻科)設置〈⑤ 286−287〉
4・1
大隈奨学基金を大隈記念奨学基金と改め,奨学生を大学院奨学生と一般奨学生との 2種に分け
る〈⑤ 218−219〉
4・1
法学部に比較法研究所(所長中村宗雄)設立〈⑤ 134−136〉
5・15
顕著な研究業績を挙げた教員を対象とする大隈記念学術褒賞制度発足〈⑤ 215−216〉
5・15
学術,文芸,スポーツ等に抜群の成果を挙げた学生を対象とする小野梓記念賞制度発足
〈⑤ 217〉
8・1
「大学年金規則」制定・施行され,年金制度発足〈⑤ 225−226〉
9・12
ドイツ連邦共和国の歴史哲学者カール・レヴィット来校〈⑤ 706〉
9・20
総長選挙人会,大浜信泉を総長に再選〈⑤ 52〉
11・3
窪田通治(空穂),文化功労者受章〈⑤ 944〉
1959年/ 昭和 34年
2・20
政治経済学部使用の 1号館と 3号館の連結工事竣工〈⑤ 195〉
3・17
理工学部使用の 14号館南北両端の連結工事竣工〈⑤ 195−196〉
4
早稲田精神昂揚会(当初は早稲田精神研究会と称する)発足〈⑤ 833−834〉
6・16
インドネシア大統領アハマド・スカルノ来校〈⑤ 706〉
6・19
早稲田大学消費生活協同組合,総会を開いて法人化および早稲田大学生活協同組合への名称
変更を決議〈⑤ 783〉
7・1
教務部に語学教育研究室(室長川本茂雄)設置〈⑤ 137〉
9・10
トルコおよびイランから地震研究の留学生を招くための名誉教授内藤多仲博士奨学金制度発足
〈⑤ 121〉
10・8
電子計算室(室長難波正人),診療所内に開室〈⑤ 140〉
10・8
調度部調度課に印刷所設置〈広報昭和 34年 10月 22日号〉
11・25
創立 80周年記念事業委員会(委員長安念精一),第 1回会合開催〈⑤ 177〉
この年
学生部が主催し診療所が担当する学生の定期健康診断開始〈⑤ 228〉
1960年/ 昭和 35年
3・31
旧制早稲田大学(大学院,学部)廃止〈④ 950,1007,⑤ 38〉
3・31
ドイツ連邦共和国首相コンラート・アデナウアーに名誉博士号贈呈〈⑤ 211〉
4・1
ボン大学との研究者交換開始〈⑤ 89〉
4
学術出版補助費制度発足〈⑤ 153〉
5・
8−10 市島春城先生生誕 100年記念祭挙行〈⑤ 875−876〉
5・16
創立 80周年記念事業委員会,評議員会に答申を提出し,評議員会は答申通り記念事業計画を
決定〈⑤ 178〉
5・22
坪内逍遥生誕 100年記念式典挙行〈⑤ 874−875〉
5・25
応用化学科教室(9号館――現 6号館)第 2期工事竣工〈④ 1120,1125〉
6・15
創立 80周年記念事業募金事務局を設置し,20億円の募金に着手〈⑤ 182−183〉
6・15
教員給与の所管箇所を庶務部より教務課に移すとともに,人事部を新設して職員人事・給与の管
掌事務を庶務部より移す〈⑤ 746〉
6・15
日米安全保障条約改定阻止を標榜する全学連が国会突入を企てて警官隊と衝突,東京大学学
生 1人が死亡〈⑤ 371〉
9
ミシガン協定による最後の学苑側派遣教員として,名取順一出発(12月帰国)〈⑤ 130〉
11・14−16
高田早苗先生生誕 100年記念祭挙行〈⑤ 876−877〉
11・15
評議員会,長野県菅平の土地 12,504坪および建物 88坪の購入を決定,運動部合宿所として
使用〈⑤ 163〉
12・1
理事会,パリ大学との研究員交換協定承認〈⑤ 89〉
12
「創立 80周年記念事業資金募集趣意書」発表〈⑤ 196〉
1961年/ 昭和 36年
1・16
評議員会,西大久保の国有地 11,233坪の購入を決議〈⑤ 203〉
1
図書館内に校史資料係設置〈⑤ 747〉
2・17
久野奨学基金を設定し〈⑤ 221〉,4月 1日より支給
4・1
第二理工学部の学生募集を停止して第一理工学部の学生定員をほぼ倍増し〈⑤ 260〉,第一理
工学部の鉱山学科を資源工学科と改称〈⑤ 291〉
4・1
大学院工学研究科を理工学研究科と改称し,応用物理学専攻に博士課程を開設するとともに,
数学専攻(修士課程・博士課程)を増設〈⑤ 291−292〉
4・1
工業高等学校が戸山町キャンパスより本部キャンパス 15号館へ移転するとともに,産業技術専修
コースを開設〈⑤ 303〉
4・1
インドネシア賠償留学生受入制度に基づく受入開始〈⑤ 122−123〉
5・10
ア式蹴球部,大韓民国遠征に出発,18日帰国〈⑤ 701−702〉
5・15
評議員会,長野県菅平グラウンド隣接地 8,760坪の購入を決定〈⑤ 163〉
5
本庄市長・市議会議長,本庄地区への早稲田大学誘致の陳情書を届ける〈⑤ 160〉
6・3
創立 80周年記念の建設事業を推進するため,臨時建設局設置〈⑤ 183〉
7・1
教員組合結成〈⑤ 235−236〉
7・4
文部省,大学設置認可基準大幅緩和の方針を発表〈『大学設置基準の研究』130−131,⑤ 60〉
7・12
ソヴィエト社会主義共和国連邦科学アカデミーとの学術交流として,増田冨寿出発(翌 8月 10日
にヴィクトル・ヴラーソフ来校)〈⑤ 93〉
7・15
職員組合結成〈⑤ 240−241〉
7・20
体育局の建物が戸山町キャンパスに竣工〈⑤ 196〉
7・26
大久保山一帯を学苑校地に予定する旨の覚書を本庄市・児玉町・美里町と交換,翌昭和 37年よ
り用地買収に着手〈⑤ 160〉
8・14
高等学院の講堂竣工〈⑤ 157〉
8
スタンフォード大学の在外教育計画による大学生 17人を第一文学部委託学生として受け入れる
〈⑤ 109〉
9・6
大隈会館敷地内の学生ホールに 3階を増築して第二共通教室とする〈⑤ 198〉
11・11
スペインの歴史哲学者ディエス・デル・コラール来校〈⑤ 706〉
11・15−17
天野為之先生生誕 100年記念祭挙行〈⑤ 877〉
12・14
駐日アメリカ合衆国大使エドウィン・ライシャワー来校〈⑤ 706〉
12・15
アルゼンチン共和国大統領アウトゥロ・フロンディシに名誉博士号贈呈〈⑤ 211〉
1962年/ 昭和 37年
2・6
アメリカ合衆国司法長官ロバート・ケネディ来校〈⑤ 707−709〉
2
第二学部検討委員会(第 1次)(委員長戸川行男)設置〈⑤ 261〉
3
学苑教授暉峻康隆,『婦人公論』に「女子学生世にはばかる」発表,また 4月には慶応義塾大学
教授池田弥三郎が同誌に「大学女禍論」を発表し,女子の大学への大量入学現象を批判〈⑤ 44〉
4・1
教育学部教育学科の教育行政課程を廃止するとともに「課程」をすべて「専修」と改称し,教育学
科に教育心理学専修を増設〈⑤ 288−289〉
4・1
教職員・学生の海外留学・出張手続や外国人教員・学生に関する事項を扱う外事課を教務部内
に設置〈⑤ 123−124,747〉
4・3
高等学院および工業高等学校が移転した跡の戸山町キャンパスに文学部校舎が竣工し,5日に
落成式挙行〈⑤ 201〉
4・6
第一・第二文学部が戸山町キャンパスに移転した跡の本部キャンパス 4号館に,教育学部が移
転〈⑤ 198,202〉
5・23
ソヴィエト社会主義共和国連邦の人類初の宇宙飛行士ユーリー・ガガーリン来校〈⑤ 709−711〉
6・25
早稲田キャンパス新聞会,『早稲田キャンパス』発刊〈⑤ 840〉
7・1
客員教授の制度が設けられ,9月 1日に教育学部のバートン・E・マーティン,10月 18日に第一・
第二文学部の除村吉太郎を嘱任〈⑤ 214−215,広報昭和 37年 11月 14日号〉
7・6
第二学部検討委員会(第 1次),第二学部縮小・第一学部拡大を骨子とする答申書を総長に提
出〈⑤ 263〉
9・1
理事 2名増員・評議員 1名増員を骨子とする改正校規施行〈⑤ 245〉
9・1
特別功労者および特別縁故者を名誉評議員とする制度を施行し,12日,石橋湛山と松村謙三に
委嘱〈⑤ 246,広報昭和 37年 10月 16日号〉
9・20
総長選挙人会,大浜信泉を総長に三選〈⑤ 55〉
10・1
語学教育研究室を教務部から独立させて語学教育研究所(所長川本茂雄)を設置〈⑤ 138−139〉
10・14
応援歌「燃ゆる太陽」(佐伯孝夫作詞・吉田正作曲)発表〈⑤ 186−187〉
10・20
ミシガン大学総長ハーラン・ヘンソーン・ハッチャー,校友・衆議院議員松村謙三,校友佐伯好郎
に名誉博士号を贈呈〈⑤ 211〉
10・21−22
創立 80周年記念式典挙行〈⑤ 190−192〉
11・3
内藤多仲,文化功労者受章〈⑤ 944〉
11・17−18
早稲田精神昂揚会・自動車部・早稲田キャンパス新聞会の共催で本庄−早稲田間の第 1回 100キロ・ハイク開催〈⑤ 837〉
12・1
アーラム大学およびアンティオック大学と,在外教育計画に基づく大学生受入協定書に調印
〈⑤ 112〉
12・5
第二学部検討委員会(第 2次)(委員長時子山常三郎)設置〈⑤ 263〉
1963年/ 昭和 38年
3・18
早稲田精神昂揚会の 5人,サンフランシスコを発ってアメリカ大陸徒歩横断に出発(11月 13日に
ニューヨーク着)〈⑤ 834−835〉
4・1
アメリカ合衆国の大学の在外教育計画による委託学生を受け入れて 1年間英語で講義を行う国
際部(部長小松芳喬)を各種学校として設置し,9月 16日に開講〈⑤ 113〉
4・1
ロバート・ケネディ奨学基金設定され,大学院学生に支給開始〈⑤ 221〉
4・13
甘泉園の一部 3,462坪と交換して入手した水稲荷神社所有地 2,064坪の登記完了〈⑤ 200〉
5・1
学生部,『新鐘』発刊〈⑤ 747〉
5・8
理事会,ワシントン大学(セントルイス)との交換教授協定承認〈⑤ 91〉
5・15
評議員会,学徒錬成部跡地の残余の土地 18,690坪の売却を決定〈⑤ 158−159〉
5
職員会が解散し,職員共済会発足〈⑤ 228〉
6・15
西大久保の理工学部建築用地に隣接する国有地 2,111坪と甘泉園の一部 2,963坪との交換決
定〈⑤ 203〉
7・15
大隈記念社会科学研究所を社会科学研究所に改組し,大隈重信の事蹟研究を研究所の目的か
ら削除〈⑤ 126〉
9・30
西大久保キャンパスに理工学部の第 1期工事竣工〈⑤ 203〉
10・15
長野県菅平の建物増築工事竣工し,菅平寮と命名,12月より学生の体育訓練と教職員・一般学
生の厚生施設として使用〈⑤ 230,広報昭和 39年 1月 29日号〉
10・17
早稲田精神昂揚会のアメリカ大陸横断隊,ワシントンで司法長官ロバート・ケネディと会見
〈⑤ 835−836〉
10・21
大隈重信生誕 125年祭を 11月 12日まで開催〈⑤ 879−880〉
11・10
名誉教授の窪田通治と内藤多仲に名誉博士号贈呈〈⑤ 211−212〉
11・28
全国早稲田大学学生会連盟結成〈⑤ 826−827〉
12・9
校友会,大隈重信生誕 125年記念祭を開催〈⑤ 880−881〉
12・17
早稲田実業学校,学苑の系属校となる〈⑤ 300〉
12
図書館内にあった校史資料係を教務部所管の校史資料室と改め,大隈重信の事蹟研究をも社
会科学研究所から引き継ぐ〈⑤ 747−750〉
1964年/ 昭和 39年
1・18
ロバート・ケネディ,再度来校〈⑤ 836−837〉
3・3
上石神井の高等学院の第 1期増築工事として 3階建校舎竣工〈⑤ 157〉
4・1
教育学部教育学科に体育学専修を増設,また理学科(数学専修・生物学専修・地学専修)を新設
〈⑤ 289−290〉,加えて,従来教育学部卒業生にはすべて文学士の称号が与えられてきたが,教
育学科卒業生には教育学士,理学科卒業生には理学士の称号付与を昭和 39年度入学者より適
用〈記要 19・120−121〉
4・1
従来,大学院学生は入学時点で修士課程を経ずに博士課程を選択することもでき,2本立てと
なっていたが,この方式が廃止され,博士課程進学者は修士課程修了者に限定〈⑤ 294−295〉
4・1
工業高等学校,生徒募集を停止〈⑤ 303〉
4・1
夜間の各種学校として産業技術専修学校(校長木村幸一郎)開校,高等学校卒業以上を入学資
格とする 2年制本科(機械工作科,電気科,建築科,産業経営科)および本科卒業を入学資格と
する 6ヵ月制専修科を設置〈⑤ 303−304〉
4・1
津田つねの寄附金を基に設定された津田奨学基金,支給を開始〈⑤ 221〉
4・1
学生健康保険組合設立〈⑤ 770〉
4
文化団体連合会に反発する 76サークルがサークル連合を結成〈⑤ 821〉
5・25
ソヴィエト社会主義共和国連邦第一副首相アナスタス・ミコヤン来校〈⑤ 706〉
6・18
給与や労働条件をめぐる職員の苦情を処理するため,苦情処理委員会設置〈広報昭和 39年 6月 27日号〉
7・6
第二学部検討委員会(第 2次),第二学部の廃止と新夜間学部の設立を骨子とする答申書を総
長に提出〈⑤ 263−265〉
7・14
職域稲門会代表者会(職域校友代表者会の前身)発足〈⑤ 930〉
7・20
カリフォルニア州立大学連盟(CSC)と学生交流計画協定調印〈⑤ 118〉
8・24
国際部,五大湖私立大学連盟(GLCA)との第 1回交換教員を派遣〈⑤ 117〉
9・1
国際部,日本人学生を聴講生として受入開始〈⑤ 117〉
9・15
評議員会,第二学部廃止・新夜間学部設立を決定〈⑤ 265−266〉
10・9
上石神井の高等学院に体育館を新築するため解体した木造校舎の東伏見運動場への移築が完
了し,合宿所「稲西寮」として使用〈⑤ 158〉
10・10−24
第 18回オリンピック(東京大会)が開催され,記念会堂がフェンシング競技の会場となる〈⑤ 195〉
11・3
尾崎士郎,文化功労者受章〈⑤ 944〉
11・12
「名誉教職員規程」を改正し,名誉教授の資格要件として教授在職 20年以上と定める〈⑤ 215〉
12・15
山吹町および鶴巻町の学苑所有地と交換して正門前の土地 221坪を取得〈⑤ 206−207〉
12・15
評議員会,学徒錬成部跡地の売却代金で東伏見運動場の東南の土地 3,615坪の購入を決定
〈⑤ 158−159〉
1965年/ 昭和 40年
2・1
総長室を新設して,秘書室を秘書課と改めてこれに編入し,校友部校友課を総長室に移管した
上で校友部を廃止し,更に企画調査係と旧称の校史資料係にもどした校史資料室とを総長室に
置くほか,教務部の調査係を廃止し,厚生課を庶務部から人事部へ移管し,庶務部に文書課を
新設〈⑤ 747−750〉
2・3
漢陽大学校と研究員交換協定調印〈⑤ 95−97〉
3
西大久保キャンパスの理工学部の第 2期工事竣工〈⑤ 203〉
4・1
第二法学部および第二商学部,学生募集を停止し,第一法学部および第一商学部の学生定員
を増員〈⑤ 266〉
4・1
理工学部に物理学科を設置〈⑤ 292〉
4・1
国際部,「学校教育法」に基づく「留学生別科」となる〈⑤ 114〉
4・1
特殊研究助成費を廃止し,教員図書購入費制度発足〈⑤ 150−151〉
4・1
大学院理工学研究科建築学専攻の大学院学生を対象とする十代田奨学基金,機械工学専攻の
大学院学生および学部学生を対象とする山内奨学基金,支給開始〈⑤ 221〉
4・1
ハワイ大学東西文化センターからの委託学生受入協定実施〈⑤ 117〉
4
社会科学部設置委員会(委員長芳野武雄)設置〈⑤ 272〉
6・18
日本商工会議所会頭足立正,学苑評議員・日本化薬社長原安三郎,松下電器産業会長松下幸
之助に名誉博士号を贈呈〈⑤ 212〉
6・18
創立 80周年記念事業のための募金活動業務が終結し,各種委員会解散〈⑤ 184〉
6・30
校史資料係,『早稲田大学史記要』発刊
7・9
学部長会,第二文学部の存続を了承〈⑤ 279−281〉
8・
1−31 全国早稲田大学学生会連盟,欧州学生交歓見学団派遣〈⑤ 827〉
9・7
コロンビア大学総長グレイソン・ルイス・カークに名誉博士号を贈呈〈⑤ 212〉
9・11
上石神井の高等学院,第 2期工事の体育館新築工事ほか竣工〈⑤ 158〉
9
応援部,「コンバット・マーチ」(作曲三木佑二郎・編曲牛島芳)を応援歌に採用〈⑤ 812〉
10・15
評議員会,第一政治経済学部の自治行政学科および新聞学科の廃止を決定〈⑤ 295−296〉
12・6
正門前に竣工間近の第二学生会館の管理運営に関し,大学案を公表〈⑤ 381−382〉
12・11
大学側の第二学生会館管理運営案に反発して本部前に坐り込んだ学生と学苑当局との交渉が
決裂して理事らが監禁状態となったため警官隊の出動を要請し,構内に突入した警官隊が共闘
会議議長大口昭彦を検挙〈⑤ 379〉
12・14
共闘会議議長大口昭彦釈放〈⑤ 379〉
12・20
評議員会,学費値上げ(文科系 6割増,理工系 5割増)を決定〈⑤ 387〉
12・27
正門前に第二学生会館竣工〈⑤ 207,376〉
12
尾久の艇庫を売却〈記要 15・202〉
1966年/ 昭和 41年
1・18
第一法学部および教育学部の学生,学費値上げに抗議してストライキに入り(20日には第一政治
経済学部・第一商学部・第一文学部,21日には理工学部が続く),「学費・学館紛争」勃発
〈⑤ 389〉
2・4
学生 12,000人が集まった記念会堂で大浜信泉総長の学費値上げ理由説明会開催,学生は納
得せずストライキ続行〈⑤ 401−404〉
2・21−22
入学試験実施のため警官隊に構内から学生を排除するよう出動を要請し,学生 203人が検挙さ
れる〈⑤ 410−412〉
2・24−3・6
ロックアウト体制の下で入学試験実施〈④ 412−413〉
3・7
ロックアウトが解除され,共闘会議派の学生は 25日の卒業式を大学当局弾劾の集会にすると発
表〈⑤ 415〉
3・16
営団地下鉄東西線,中野−竹橋間で営業開始〈⑤ 846〉
3・19
学部長会,全学同時の卒業式の中止を決定〈⑤ 417〉
3・20
総長室校友課,大学の実情を学生の父兄にも伝える目的で『早稲田』(『早稲田ウィークリー』の前
身)発刊〈⑤ 750〉
3・25
大隈講堂で卒業式を挙行した商学部以外の学部は,事務所で学生証と引き換えに卒業証書を
卒業生に渡す〈⑤ 417〉
4・1
第二政治経済学部,学生募集を停止〈⑤ 266−267〉
4・1
第二政治経済学部・第二法学部・第二商学部に代る夜間 4年制の社会科学部(社会科学科――
学部長芳野武雄)開設,卒業生には社会科学士の学士号を授与〈⑤ 274〉
4・1
存続が決定した第二文学部は,外国文学専修のうち仏文学専修・露文学専修・独文学専修を廃
止するとともに,従来の 8専修制をⅠ類(東洋文化専攻,西洋文化専攻,社会専攻)・Ⅱ類(日本
文学専攻,英文学専攻,美術専攻,演劇専攻)の 2類 7専攻制に改める〈⑤ 282−283〉
4・1
第一文学部は従来の 3学科 15専修制をⅠ類(哲学専攻,東洋哲学専攻,心理学専攻,社会学
専攻,教育学専攻,日本史学専攻,東洋史学専攻,西洋史学専攻,美術史学専攻,人文専攻)・
Ⅱ類(日本文学専攻,中国文学専攻,英文学専攻,フランス文学専攻,ドイツ文学専攻,ロシア文
学専攻,演劇専攻,文芸専攻)の 2類 18専攻制に改める〈⑤ 281−283〉
4・1
第一政治経済学部の自治行政学科および新聞学科,学生募集を停止〈⑤ 295−298〉
4・1
建築学専攻学生を対象とする村野奨学基金,商学部 1年生を対象とする商学部奨学基金,支給
を開始〈⑤ 221−222〉
4・8,11
理工学部の学生,学年末試験受験可否の投票を行い,受験賛成が多数を占める〈⑤ 420〉
4・9,11,12
商学部の学生,学年末試験受験可否の投票を行い,受験賛成が多数を占める〈⑤ 420〉
4・13
商学部の学生,バリケードを解除(理工学部は 14日解除)〈⑤ 420〉
4・18
理工学部と商学部で学年末試験実施〈⑤ 420〉
4・21
教育学部,新 4年生のみを対象に早稲田実業学校で学年末試験を実施〈⑤ 420〉
4・23
総長大浜信泉,学部長会で辞意を表明〈⑤ 420〉
4・24
全理事,総長大浜信泉に辞表を提出〈⑤ 420〉
5・1
学部入学式挙行〈⑤ 421〉
5・10
評議員会,大浜信泉の総長辞任を承認,阿部賢一,総長代行に就任〈⑤ 446〉
5・16
阿部賢一総長代行,学費のうち施設費の 2万円引下げを評議員会に提案し,7月 15日の評議
員会はこれを決定〈⑤ 425〉
5・20
尾久の艇庫に代る戸田艇庫完成〈記要 15・203〉
5・21
第一商学部の学生,ストライキ続行可否の投票を実施して中止を決め,また第二政治経済学部の
新 2・3年生,学年末試験受験可否の投票を実施し受験と決定〈⑤ 428〉
5・23
第一商学部および理工学部ならびに第一政治経済学部・第一法学部・第二文学部の一部で授
業再開〈⑤ 428〉
6・4
第一政治経済学部の学生,ストライキ中止を決定(5−7日には第二文学部,14日には第一法学
部・教育学部(民青系)・第二政治経済学部,15日には教育学部(革マル系)が続く)〈⑤ 428〉
6・22
第一文学部の学生がストライキ中止を決定し,155日間に及んだ「学費・学館紛争」の幕を閉じる
〈⑤ 429〉
7・7
早稲田大学一般奨学金,支給開始〈⑤ 222−223〉
9・17
総長選挙人会,阿部賢一を総長に選出〈⑤ 453〉
9・22
阿部賢一,第 8代総長に就任〈広報昭和 41年 9月 22日号〉
9・27
古代エジプト調査隊(隊長川村喜一)出航〈学報 765・53,⑤ 654〉
9
国際部を通じて五大湖私立大学連盟(GLCA)加盟大学への学生の留学開始〈⑤ 696〉
10・5
阿部賢一総長就任式挙行〈⑤ 453〉
10・14
学生会館問題委員会が設置され,翌昭和 42年 5月 6日まで学生との協議が続くが,結論を出せ
ずに解散〈⑤ 436〉
11・3
井伏満寿二(鱒二),文化勲章受章〈⑤ 942〉
11・5
15号館新築・4号館増築工事竣工〈⑤ 199−200〉
1967年/ 昭和 42年
1・26
昭和 38年より機能を停止していた給与委員会に関する規程を廃止〈⑤ 237,広報昭和 42年 2月
18日号〉
1下旬−3下旬
古代エジプト調査隊(隊長川村喜一),現地にて予備調査を行う〈⑤ 654,学報 773・34〉
2・15
16号館(教育学部)竣工〈⑤ 199〉
3・13
モスクワ大学との研究員交換協定に基づきユリ・N.ラヴォトノイが来学し,約 1ヵ月滞在〈⑤ 94,学
報 770・57−58〉
3・15
創立 80周年記念事業募金事務局と総長室校友課を廃止し,総長室に資金課および広報課を新
設〈⑤ 750〉
4・1
従来の「留学生規則」に代る「在外研究員等規則」施行〈⑤ 148−149,広報昭和 42年 3月 3日
号〉
4・27
理事会,教育研究委員会および大学機構研究委員会の設置を決定し,6月 1日付で委員を嘱任
〈⑤ 538〉
4
教育学部,4号館より 16号館へ移転〈⑤ 200〉
4
第一・第二理工学部,本部キャンパスより西大久保キャンパスへの全面移転完了〈学報 770・57〉
4
生産研究所,19号館(法文系大学院)より西大久保キャンパスへ移転〈広報昭和 42年 4月 28日
号〉
5・11
学生会館問題委員会,「学生会館規程(案)」および「学生会館運営委員会規程(案)」を発表
〈『早稲田』昭和 42年 5月 17日号〉
5・15
事務主任の職名を事務長と改めるとともに,教務部の学籍係を学籍課に昇格〈⑤ 751〉
6・15
建築学奨学基金および沖奨学基金設定〈⑤ 778−779,広報昭和 42年 6月 21日号〉
9・22
伊原奨学基金設定〈⑤ 779,広報昭和 42年 9月 30日号〉
9
社会科学部が 8号館より 14号館へ,社会科学研究所が診療所建物から 20号館へ移転〈広報昭
和 42年 9月 20日号,9月 25日号,学報 775・54〉
10・16
佐藤栄作首相のアジア訪問に反対する 3派系全学連が 10月 8日に警官隊と衝突した事件(第 1次羽田事件)に関連して,文学部自治会室が捜査される〈学報 777・40−41,広報昭和 42年 10月
23日号〉
10・24
戸山町キャンパス内の記念会堂と文学部校舎との間に記念会堂と接続する形で第二体育館が,
体育局校舎南側に体育測定室・心理学実験室棟が竣工〈⑤ 658〉
10・25
佐賀市水ヶ江大隈公園内に昭和 41年 11月に竣工した大隈記念館(設計今井兼次),開館式挙
行〈学報 777・55−56〉
10−12
創立 85周年を記念して,10月 21日の大隈侯銅像献花式をはじめ歴史展や講演会などが行わ
れる〈学報 776・56,広報昭和 42年 10月 17日号〉
11・12
昭和 43年 3月に廃校となる早稲田大学工業高等学校を記念するため,同校卒業生で組織され
る稲友会と同校生徒会とから庭石 1基が寄贈され,阿部賢一総長により稲友石と命名されて大隈
庭園内に設置〈学報 778・52〉
11・15
「弔慰金贈呈規則」施行に伴い,昭和 26年以来の「生命保険による遺族慰藉」制度廃止
〈④ 1166−1167〉
11・20
西大久保キャンパスに理工学部の第 3期工事竣工〈⑤ 203〉
11・21
政治経済学部教授会,政治経済研究所の設置を決議し,翌 22日に設置申請書を理事会に提出
〈⑤ 650〉
12下旬
8号館(旧理工学部製図教室)の取り壊し開始〈学報 778・52〉
1968年/ 昭和 43年
1・29
東京大学医学部学生自治会,インターン制度に代る登録医師制度に反対して無期限ストに突入
(東大紛争の発端)〈⑤ 437−438〉
3・25
生活協同組合,10号館(現 13号館)1・2階で営業開始,のち 4号館(現 8号館)地階より全面移
転〈『早大生協三十年のあゆみ』157,⑤ 783〉
3・31
第二理工学部廃止,早稲田大学工業高等学校廃校〈⑤ 261,303〉
4・1
大学院経済学研究科,理論経済学・経済史専攻および応用経済学専攻の 2専攻に分れる
〈⑤ 616〉
4・1
第一理工学部,理工学部と改称〈⑤ 261〉
4・1
教員図書購入費を廃止し,教員研究費制度発足〈⑤ 151,広報昭和 43年 11月 20日〉
4・1
学生相談センター(所長川合幸晴)開設〈⑤ 771−772〉
4・1
高等学院奨学基金設定〈広報昭和 43年 6月 19日号〉
4・15
阿部賢一総長,評議員会で辞意を表明し,了承される〈⑤ 485〉
4・15
国税庁が日本大学の経理に 20億円の使途不明金があると発表,これに端を発して 5月 27日に
日大全共闘が結成される〈⑤ 438〉
5・3
岩手県下閉伊郡田野畑村で思惟の森植樹祭と青鹿寮地鎮祭挙行〈⑤ 678,839〉
5・27
学生の妨害により実施不可能となった総長選挙を郵便投票に変更〈⑤ 494〉
6・15
東京大学医学部の学生が安田講堂を占拠,17日に機動隊を導入してこれを排除したことに反発
して,20日には全学部がストに突入,7月 2日安田講堂を再占拠
6・20
時子山常三郎,第 9代総長に選出され,阿部賢一,総長辞任〈⑤ 496,広報昭和 43年 6月 22日
号〉
6・23
事務システム研究会発足〈⑤ 753〉
7・13− 8・11
船上大学研究会(会長中島正信),第 1回早稲田船上大学挙行〈⑤ 704−705〉
7・17
教育研究委員会,検討結果を総長に報告〈⑤ 538〉
9・17
前国際復興開発銀行総裁ユージン・ロバート・ブラックに名誉博士号贈呈〈⑤ 212〉
9・24
大学機構研究委員会,検討結果を総長に報告〈⑤ 538〉
9・27
経理を客観的な立場から明らかにするため,公認会計士に監査を依頼することを決定〈学報 785・
55,786・35,⑤ 744〉
10・21
反日共系学生,国際反戦デーとなったこの日に新宿駅を占拠・放火〈⑤ 441〉
11・6
佐賀市水ヶ江で大隈重信生家復元工事落成式挙行〈学報 786・57,787・56〉
12・13
学部長会大学院委員長会合同会,大学問題研究会設置についての総長提案を承認し,準備委
員会の設置を決定〈⑤ 502〉
12・16
韓国赤十字社総裁・大韓民国前国務総理崔斗善に名誉博士号贈呈〈⑤ 212〉
12・29
文部省,翌昭和 44年の東京大学の入学試験を中止と決定〈⑤ 501〉
この年
ワシントン大学(セントルイス)との研究員交換計画終了〈⑤ 683〉
この年
国際部協定校ワシントン大学(セントルイス)への学苑学生派遣開始〈⑤ 696〉
この年
国際部協定校カリフォルニア州立大学連盟(CSC)加盟校へ学苑学生派遣(本年限り)〈⑤ 696〉
1969年/ 昭和 44年
1・17
在学生が国際部協定大学に留学する場合,留学先で履修した科目につき最高 12単位を早稲田
大学の単位として認定〈⑤ 698〉
1・18−19
東京大学で安田講堂を占拠していた学生が機動隊により排除され,375人が逮捕〈⑤ 440〉
2・18
日本大学,機動隊を導入して全学封鎖を解除〈⑤ 438〉
2・19
大学問題研究会設置準備委員会,第 1回会合開催〈⑤ 502〉
3・26
8号館(現 4号館――政治経済学部教員研究室,学生部室,学生ラウンジ)改築工事竣工
〈⑤ 659〉
4・1
大学暦を変更。1週間短縮した夏季休暇の開始を 2週間遅らせ,前期の授業および試験を夏季
休暇前にすべて終らせるとともに,冬季休暇を 1週間延長〈広報昭和 43年 11月 8日号〉
4・1
寄附金を以て外国人留学生教育助成基金を設定〈広報昭和 44年 5月 13日号〉
4・4
早大全共闘を名乗る学生が自主管理と称して第二学生会館を占拠〈広報昭和 44年 5月 21日
号〉
4・17
明 18日の学生会館に関する説明討論集会の開催に反対する早大全共闘の学生が 1号館本部
を占拠〈『早稲田』昭和 44年 4月 21日号外〉
4・18
学友会,学部自治会,文化団体連合会,サークル連合その他の要求に応じ,学生会館問題委員
会が学生会館に関する説明討論集会を正門広場で開催〈『早稲田』昭和 44年 4月 23日号〉
4・25
理事会,学内の秩序保持に関する基本方針を宣明した「宣言」(「学内平和宣言」)を発表
〈⑤ 581〉
4・26
4・28沖縄デーを控えて学生政治集団の流血事件が懸念されたので,警察隊の導入により本部
占拠の学生を排除し,この日から 5月 6日午前 7時まで休業・学内立入禁止の措置を採る〈『早
稲田』昭和 44年 5月 10日号〉
4・28
沖縄デーで反日共系学生らが銀座一帯の道路を占拠。この日,早大全共闘の学生が本部を再
占拠〈学報 791・50〉
4・30
中央教育審議会,「当面する大学教育の課題に対応するための方策」を文部大臣に答申
〈⑤ 457−458〉
4
法学部,2号館(現 1号館)より 4号館(現 8号館)へ移転〈⑤ 200〉
5・4
法商研究室棟落成〈⑤ 201〉
5・9
大隈重信銅像と高田早苗銅像にカラー・スプレーが吹きつけられ,「反大学/早大解体」と大書さ
れた看板が立てかけられているのが発見される〈『早稲田』昭和 44年 5月 19日号外〉
5・23
本部封鎖を解除〈学報 792・54〉
5・24
紛争処理に対する文部大臣の権限を強化するための「大学の運営に関する臨時措置法案」,国
会に上程〈⑤ 458〉
5下旬
学生政治集団の暴力事件(内ゲバ)が相次ぐ〈『早稲田』昭和 44年 8月 10日号〉
5
第一学生会館内の東洋美術陳列室閉鎖〈④ 1147〉
6・1
総長室の校史資料係を独立させて大学史編集所とし,企画調査係を企画調査課に昇格させ,更
に,法文系大学院事務所を廃止して各研究科に事務所を置き,外事課で扱っていた国際部の事
務を国際部事務所に移管し,記念事業臨時建設局を廃止〈⑤ 208−209,751,広報昭和 44年 6月 4日号〉
6・1
学生に対する凶器準備集合罪などの容疑で文学部が警察の捜査を受ける〈『早稲田』昭和 44年
8月 10日号〉
6・5
第一文学部および第二文学部の学生,「大学の運営に関する臨時措置法案」などに反対してスト
ライキに突入,以後,他学部もストライキに入る〈『早稲田』昭和 44年 8月 10日号〉
6・6
理事会,「大学の運営に関する臨時措置法案」反対の意思を表明〈学報 792・54〉
6・16
評議員会,校規および同付属規則改正案起草委員会の設置を決定〈⑤ 541〉
6・23
学部長会大学院委員長会合同会の大学問題研究会設置準備委員会,最終案「大学問題研究会
設置要綱」をまとめる〈⑤ 502〉
6・24
インド首相インディラ・ガンジーに名誉博士号贈呈〈⑤ 212〉
7・11
校規および同付属規則改正案起草委員会,第 1回委員会を開催して総長選挙規則改正案の先
議を決定〈⑤ 542−543〉
7・12
全学スト共闘(革マル系)が大隈講堂を占拠〈学報 794・57〉
7・18
大学問題研究会,第 1回運営委員会開催〈⑤ 502〉
7・24
東京教育大学評議会,筑波学園都市への移転と新大学構想を決定
8・3
自由民主党の強行採決により「大学の運営に関する臨時措置法」(法律第 70号)が可決され,17日より施行〈⑤ 458〉
8・5
時子山常三郎総長,「大学の運営に関する臨時措置法」の強行採決に遺憾の意を表明〈『早稲
田』昭和 44年 8月 10日号〉
8・14
追分セミナーハウス竣工〈⑤ 675〉
9・3
警察に出動を要請して,第二学生会館および大隈講堂を占拠していた学生を排除〈『早稲田』昭
和 44年 9月 29日号〉
9下旬−10上旬
各学部でストライキ解除を求める学生の動きが活発化〈『早稲田』昭和 44年 10月 21日号〉
10・16
各学部のストライキ解除決議ののち,警察に出動を要請して全学の封鎖を解除し,27日まで学内
立入を禁止する〈学報 796・6−7〉
10・27
授業再開〈学報 796・8−9〉
10下旬
本部各事務所が 1号館から 2号館へ移転開始〈⑤ 200,752〉
11・21
筑波研究学園都市新大学創設準備調査会設置〈⑤ 474〉
11・28
理事会,昭和 10年完成以来門柱と扉のなかった正門に,鉄柵状の門扉を新設することを決定
〈理事,⑤ 865〉
12・29
長期の学生ストライキに伴う年間授業日数不足を解消するため,大学暦では 12月 15日より翌年
1月 10日までの予定であった冬季休業を 12月 29日より翌年 1月 3日までと短縮〈広報昭和 44年 10月 14日号〉
12
国際部協定校に留学中の履修単位を早稲田大学の単位として認定する限度枠を撤廃し,認定を
各学部教授会に一任〈⑤ 698〉
この年
学生会館問題委員会,「学生会館管理運営大綱案」を作成して学生側に提示し交渉を続けるが,
決着に至らず,第二学生会館は昭和 55年まで閉鎖〈⑤ 436−437〉
この年
モスクワ大学との研究員交換協定終了〈⑤ 95〉
この年
国際部協定校オレゴン州立大学への学苑学生派遣開始〈⑤ 696−697〉
1970年/ 昭和 45年
1・11
OECD教育調査団来日,11月 19日に報告書発表
1・12
早稲田大学印刷所が 5号館地下室から早稲田大学出版部隣の工場 2階へ移転〈広報昭和 45年 1月 27日号〉
1・15
本庄校舎(平成 5年に本庄セミナーハウスと改称)竣工〈⑤ 669〉
3・13
1年間授業を担当せずに研究に専従する国内研究員に関する規程を定めて制度化〈⑤ 153,広報昭和 45年 3月 26日号〉
3・31
赤軍派学生,日航機よど号をハイジャックし,4月 3日に北朝鮮へ亡命〈⑤ 441〉
4・1
大学院文学研究科の西洋哲学専攻を哲学専攻と改称〈⑤ 616〉
4・1
第二文学部,Ⅰ類・Ⅱ類の類別編成を廃止するとともに文芸専攻を増設〈⑤ 612〉
4・1
科外講演部,本部事務組織から付属機関に分離・独立〈⑤ 751〉
4・1
教務部内に電算化準備室を設置〈⑤ 753〉
4
図書館,19号館(現 7号館)2階に学習図書室を開設〈『早稲田大学図書館史』102−103〉
5・18
漢陽大学校と「経営講座」に関する講師派遣協定締結〈⑤ 685〉
5・21
総長室企画調査課の管理下に大学問題研究資料室が 2号館 4階に開室〈⑤ 506〉
5・31
漢陽大学校との人物交流計画終了〈⑤ 684〉
6
図書館,マイクロ資料室を開設〈『早稲田大学図書館史』103〉
7・1
小野梓記念賞の文芸賞を芸術賞に改める〈⑤ 217〉
7・1
日本私学振興財団が発足し,人件費を含む私立大学経常費補助金が国庫より支出される
〈⑤ 743〉
7・24
校規および同付属規則改正案起草委員会,評議員会に提出するための総長選挙規則改正案を
まとめる〈⑤ 556〉
7・30
「総長選挙規則」が評議員会で可決,即日施行され,教職員のほぼ全員と学外評議員全員により
先ず総長候補者を選挙し,その候補者について学生による信認投票を経たのち,学外商議員全
員を含めた総勢 1,000名近い選挙人による決定選挙を行うという 3段階方式に改められる
〈⑤ 556−561〉
7−8
教育学部,夏季学期実施,夏季学期はこれを以てすべて廃止〈⑤ 611〉
8・25
校規を改正し,任期満了以前に後任総長が決まらない時には後任総長が就任するまで前任総長
の任期を伸長〈⑤ 561〉
8・28
総長候補者選挙が行われ,候補者となる要件を満たした 4名が決まるが,うち 2名は辞退
〈⑤ 569−570〉
8・31
大学問題研究会,最終報告書を総長に提出〈⑤ 505〉
8・31
「大学設置基準」が一部改正され,一般教育科目の運用について弾力化が図られる〈⑤ 527〉
9・1
建物・校舎の号館表示変更〈⑤ 660,752〉
9・10−12
総長候補者 2名に対する学生の信認投票が行われるが,一部学生の妨害に遭って成立せず〈⑤
571−572〉
9・17
学生の妨害を懸念した選挙管理委員会,総長決定選挙を郵便投票によって行うことを決定
〈⑤ 576〉
10・4
総長決定選挙の郵便投票開票の結果,村井資長が第 10代総長に就任し,時子山常三郎,総長
退任〈⑤ 578〉
11・2
第 1回ホーム・カミング・デー開催〈⑤ 931−932〉
11・11
総長選挙規則改正案をまとめて暫く休会していた校規および同付属規則改正案起草委員会,校
規改正案の作成に着手〈⑤ 585〉
1971年/ 昭和 46年
1・25
29号館が竣工し,生協食堂,理髪所,教・職員組合事務所などが入る〈⑤ 662〉
3・3
理事会,早稲田大学一般奨学金の新規募集を昭和 48年度より停止する代りに早稲田大学貸与
奨学金を 47年度より発足させることを決定(後者の規則制定は昭和 48年 10月 26日)〈⑤ 778,理事〉
3・3
昭和 46年度末に予想される財政不足額 6億円のうち 3億円を学生の父兄からの寄附に仰ぐた
め,教育振興協力金を翌年 2月 29日までの予定で募集する〈⑤ 738,広報昭和 46年 5月 11日
号〉
4・1
大学院理工学研究科,修士課程の学生定員を 340人から 1,560人へ,博士課程のそれを 135人から 624人へ増加〈⑤ 616〉
4・1
第一文学部,Ⅰ類・Ⅱ類の類別編成を廃止〈⑤ 612〉
4・1
教員研究費を個人研究費と改め,個人で行う研究に対して支給〈⑤ 151〉
4・1
「在学中に海外留学する者の取扱いに関する規程」を施行し,早稲田大学の許可を得て外国の
大学へ留学する在学生について,留学期間は長期欠席扱いとして在学年数に算入せず,留学
前後の早稲田大学で の学習期間を通算して単位を取得できるよう計らう〈⑤ 697〉
4・19
図書館,新聞閲覧室を 7号館 1階へ移転〈広報昭和 46年 5月 11日号〉
4
古代エジプト調査委員会(委員長平田寛)設置〈⑤ 655〉
5・9
岩手県の思惟の森で青鹿寮落成式挙行〈⑤ 678−679〉
6・11
中央教育審議会,「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的政策について」
を文部大臣に答申〈⑤ 472−473〉
6・21−23
塩沢昌貞博士生誕 100年記念講演会および展示会開催〈⑤ 885−886〉
7・19
小委員会,「校規改正要綱案」を校規および同付属規則改正案起草委員会へ提出,以後,1年
10ヵ月に亘って休会〈⑤ 586−595〉
7
事務システム研究会,『事務システム研究会報告』をまとめて解散〈⑤ 753〉
10・8
企画調査課を総長室より独立させて企画調整部とし,人事部人事課を人事一課および人事二課
に二分する〈⑤ 751−752〉
10・28
文学部学生読書室(32号館内)増改修工事竣工〈⑤ 664〉
11・15
評議員会,昭和 48年度の学費の値上げを決定,以後翌年にかけて各学部で学生大会が開かれ,
ストライキに突入〈学報 819・54〉
11
第 1次古代エジプト調査隊派遣〈⑤ 655〉
12・18
警視総監自宅に配達された小包み爆弾が爆発〈⑤ 441〉
12・24
新宿伊勢丹前の派出所脇でクリスマス・ツリーに仕掛けられた爆弾が爆発〈⑤ 441〉
1972年/ 昭和 47年
1・14
法学部教授会,学年末試験延期を発表,以後他の学部も同様の措置を採る〈学報 819・54〉
2・4
理事会,2様に歌われてきた早稲田大学校歌 3番第 1節の歌詩「あれみよあしこの」を「あれみよ
かしこの」に統一することを決定〈② 249,理事,広報昭和 47年 3月 17日号〉
2・28
公費助成の拡大に伴い制定された「学校法人会計基準」に従って会計処理を行うため,「会計規
程」を廃して「会計規則」を制定・施行〈⑤ 744,広報昭和 47年 3月 6日号〉
4・1
大学院理工学研究科の鉱山及金属工学専攻を資源及金属工学専攻と,理工学部の電気通信学
科を電子通信学科と改称〈⑤ 616,612〉
5・10−31
愛知県犬山市の博物館明治村で大隈重信展開催〈学報 822・56〉
6・
8−15 大学史編集所,大隈重信侯没後 50年祭記念講演会および展示会を開催〈学報 823・57〉
9・6
アーラム大学総長ランドラム・ライマー・ボーリングに名誉博士号贈呈〈⑤ 212〉
9・18
体育局研究室増築工事竣工〈⑤ 664〉
9・26−11・5
創立 90周年記念行事として学宝展,演奏会,講演会,映画会などを日本橋三越や大隈講堂で
開催〈学報 825・57,828・53〉
10・7
高知県宿毛市で小野梓墓碑建立除幕式挙行〈学報 827・24−28〉
11・8
第一文学部 2年生川口大三郎,革マル派の暴行を受け死亡〈⑤ 437,学報 827・53〉
11・28
第一文学部および社会科学部で学生大会が開かれ,革マル派自治会執行部をリコールし,臨時
執行部を選出,以後翌年にかけて全学で自治会のあり方をめぐる学生間の対立・抗争が激化し,
学年末試験も延期される〈学報 829・57−58,831・58〉
この年
漢陽大学校との「経営講座」に関する講師派遣協定終了〈⑤ 685〉
1973年/ 昭和 48年
3・19
韓国の高麗大学校との学術研究交流協定が調印され,6月 1日発効〈⑤ 685−686〉
3・30
モスクワ大学との学術研究交流協定が調印され,4月 1日発効〈⑤ 686−687,『早稲田』昭和 48年 5月 16日号〉
4・1
在籍学生のいなくなった第二政治経済学部・第二法学部・第二商学部を廃止し,第一政治経済
学部を政治経済学部と,第一法学部を法学部と,第一商学部を商学部と改称〈⑤ 613〉
4・1
理工学部に化学科を増設〈⑤ 612−613〉
4・1
大学院理工学研究科の応用物理学専攻を物理学及応用物理学専攻と改称するほか,文学研究
科に中国文学専攻(修士課程)を増設〈⑤ 616〉
4・2
学部入学式の最中に百数十人の学生が乱入したため入学式を中止,翌 3日挙行予定の大学院
および専攻科の入学式も中止〈学報 831・55〉
4・11
革マル派の集会およびデモが予定され,反革マル派がこれを糾弾する集会を計画したので,暴
力事件予防のため西門および東門を閉鎖〈学報 832・56〉
4・12
校友会,終身維持費制度の採用を決定〈学報 831・33〉
5・7
校規および同付属規則改正案起草委員会小委員会,「校規改正要綱案」に関し各方面から提出
された意見書の説明を聞く機会を設けるために会議を再開〈⑤ 595−596〉
5・8
覆面姿の学生数十人が講義中の村井資長総長を拉致し,5月 17日に団体交渉を行う旨の確約
書に署名させる〈学報 832・56〉
5・10
語学教育研究所 LL教室増築工事竣工〈⑤ 664〉
5・16
学生政治集団間の抗争が激しく,人命に関わる事態が起りかねないと判断して,翌 17日に約束
させられた全学集会を取り止める旨掲示する〈学報 832・56〉
5・25
『早稲田フォーラム――大学問題論叢――』創刊〈⑤ 528〉
7・2
高等学院の美術教室竣工〈⑤ 664〉
10・1
筑波大学開校〈⑤ 474〉
10・22
文学部図書室増築工事竣工〈⑤ 664〉
11・7
小委員会,校規改正最終案を校規および同付属規則改正案起草委員会総会に提出〈⑤ 599〉
11・8
川口大三郎一周忌に当り混乱を予防するため全学休講措置を採る。革マル派および反革マル派
は学外で「川口君追悼集会」を開催〈学報 837・52〉
11・19
黒ヘルメット姿の武装学生集団が「総長団交」を要求して図書館を占拠したので,排除のため機
動隊に出動を要請〈学報 838・59〉
12・14
文化勲章受章者の村野藤吾に名誉博士号贈呈〈⑤ 212〉
この年
第一文学部で推薦入学実施〈⑤ 614〉
この年
大学間協定に基づき,シカゴ大学および高麗大学校から留学生を受け入れるとともに両大学へ
学苑学生を派遣〈⑤ 697〉
1974年/ 昭和 49年
1・16
評議員会,校規および同付属規則改正案起草委員会より提出された校規改正案を審議し,採択
〈⑤ 599〉
1・19
前年 11月の石油危機を契機に物価が異常に騰貴したため,総長名で経費節減を教職員に訴え
る〈広報昭和 49年 1月 24日号〉
1中旬
第 3次古代エジプト調査隊,第 18王朝期の彩色階段を発掘〈⑤ 655−656〉
4・1
総長の 3選禁止,理事定員 1名増,評議員定員 9名増などを骨子とする改正校規施行
〈⑤ 599−607〉
4・1
研究所長会設置〈⑤ 643−644〉
4・12
校友会,商議員の校友会選出割当数の算定基準を支部の登録会員数から維持費納入会員数に
改める〈⑤ 927,学報 841・1〉
4・15
生産研究所をシステム科学研究所と改称〈⑤ 647,広報昭和 49年 5月 8日号〉
5・1
商議員の定数を学内 227名以内・学外 400名以内とする改正「商議員会規則」施行〈⑤ 607〉
6・20
文部省,「大学院設置基準」および「学位規則」を省令で公布,昭和 50年 4月 1日施行〈⑤ 621〉
7・15
評議員会,産業経営研究所の設置を承認〈⑤ 649〉
8末
校友会館の 3階増築工事竣工〈⑤ 927〉
9・20
総長候補者選挙が実施され,村井資長と滝口宏が選出されたが,滝口は候補者となることを辞退
〈⑤ 583〉
9・22
学徒出陣のため卒業式に出席できなかった昭和 19年 3月卒業者に対し,大隈講堂で卒業証書
授与式を挙行〈③ 1102−1103〉
10・1
産業経営研究所,法商研究室棟 3階で業務開始〈⑤ 649〉
10・6
学生の信認投票の結果,村井資長,総長と決定〈⑤ 583,広報昭和 49年 10月 8日号〉
10・15
賛助商議員の制度発足〈広報昭和 49年 11月 7日号〉
11・5
村井資長,総長再任〈広報昭和 49年 11月 7日号〉
12・2
昭和 50年度および 51年度の学費の改定を学生に公表〈広報昭和 49年 12月 16日号〉
12・5
社会科学部で学生大会が開かれ,学費値上げに反対して 5日から 3日間のストライキに入る〈学
報 849・45〉
この年
商学部で推薦入学実施,また,外国の大学で学位を取得した者に学士入学(第 3学年編入)の
受験資格を付与〈⑤ 614,学報 838・57〉
1975年/ 昭和 50年
1・14
法学部と社会科学部で学生大会が開かれ,学費値上げ白紙撤回を要求してストライキに入る。以
後,他の学部もストライキに入り,学年末試験が延期またはリポート提出に切り換えられる〈学報
849・45〉
4・1
大学院文学研究科中国文学専攻に博士課程設置〈⑤ 616〉
4・25
故佐藤武夫教授遺族の寄附金を基金として,大学院理工学研究科建設工学専攻修士課程在籍
者であって建築計画や都市計画建設史を主題とする修士論文が優秀な者に褒章を授与する佐
藤武夫記念賞発足〈広報昭和 50年 5月 12日号〉
4
従来からの教育振興協力金募金に加えて,目標額 5億円の早稲田大学債募集〈『早稲田ウィーク
リー』昭和 50年 4月 24日号,学報 853・広告〉
4
フィリピンのラ・サール大学よりアウレリオ・カルデロン来学し,同大学との学術研究交流開始
〈⑤ 686〉
6・1
住居表示変更に伴い学校法人早稲田大学の所在地が新宿区戸塚町 1丁目 647番地から新宿
区西早稲田 1丁目 6番 1号となる〈⑤ 608〉
6・13
石黒和平および故笹井省三遺族の寄附金を基に,商学研究科学生読書室図書購入費その他に
充てるための商学研究科研究基金を設定,4月 1日より適用〈広報昭和 50年 7月 31日号〉
6・30
鋳物研究所 2号館増築工事竣工〈⑤ 664−665〉
12・19
長期計画懇談会発足,創立 100周年記念事業構想の成文化に着手〈⑤ 976〉
この年
国際部を窓口とする学苑学生派遣先がオレゴン州立大学連盟加盟校へと拡大〈⑤ 696〉
1976年/ 昭和 51年
1・16
学費値上げ白紙撤回を要求する学生の声が高まり,不穏な情勢になったので,第一文学部は 1月 26日より実施予定の学年末試験中止の掲示を出す。以後,学生がストライキに入った他の学
部でも試験延期またはリポート提出への切り換え措置を採る〈学報 859・55−56〉
4・1
昭和 49年 6月公布の「大学院設置基準」および「学位規則」に基づき「大学院学則」および「学位
規則」を改正〈⑤ 622−623〉
4・1
本庄校地文化財調査室を教務部に設置,12月 18日に埋蔵文化財の発掘調査を完了〈⑤ 671〉
4・1
学苑創立 100周年を記念して,校友その他の寄附金を基に,森林資源の維持培養を図るための
学術調査および研究などを目的とする大隈記念育林基金設定〈広報昭和 51年 4月 14日号〉
5・15
静岡県引佐町で分収造林契約を結び,大隈記念育林基金に基づく育林活動開始〈学報 921・
40−41〉
6・15
大学院委員会を大学院研究科委員長会に改組,4月 1日に遡って適用〈⑤ 609〉
6・15−17
大学史編集所,田中穂積先生生誕 100年記念講演会および展示会開催〈⑤ 886〉
7・2
理事会,長期計画懇談会がまとめた「長期計画構想」の骨子を承認〈⑤ 976〉
7・15
教育関係の校友の会を糾合した稲門教育会発足〈学報 864・53〉
10・22
国際交流に関する事業を助成するため早稲田大学国際交流基金設定〈⑤ 688〉
10・29
「紺碧の空」記念碑除幕式,大隈庭園内で挙行〈学報 867・36〉
12・8
高等学院のセンター棟竣工〈⑤ 665−666〉
12・25
古代エジプト学術調査の拠点となるワセダ・ハウスの開所式,エジプトのルクソールで挙行
〈⑤ 680〉
1977年/ 昭和 52年
2・15
理事会,『長期構想について』を作成〈⑤ 976−977〉
3・15
評議員会,総長選挙規則検討小委員会の設置を決定〈⑤ 562〉
4・1
古代エジプト調査室,文学部校舎内に設置〈⑤ 656〉
4・1
創立 100周年記念事業準備室,総長室の所管として企画調整部内に設置〈⑤ 752,977〉
4・18
評議員会,創立 100周年記念事業計画委員会の設置を決定,5月 27日に第 1回委員会を開催
〈⑤ 977〉
6・24
研究器材購入費や学生指導費を補助するため,篤志家の寄附金を基に理工学部研究・教育基
金を設定,4月 1日に遡って適用〈広報昭和 52年 7月 22日号〉
7・11
創立 100周年記念事業計画委員会小委員会発足〈⑤ 979〉
7・22
故海老崎ツル遺贈の寄附金を基に,学部学生を対象とする海老崎奨学基金設定,昭和 53年度
より運用〈⑤ 779,広報昭和 52年 10月 3日号〉
7・22
これまで使用してきた「停年」の表記を「定年」に改める〈広報昭和 52年 10月 3日号〉
12・2
昭和 53年度および 54年度の改定学費を公表〈広報昭和 52年 12月 16日号〉
12・20
記念会堂横第二体育館の屋上一部を使う形で,文学部および大学院文学研究科学生用ラウンジ
ならびに大学院研究読書室の増築工事竣工〈⑤ 667〉
1978年/ 昭和 53年
1・13
法学部で学生大会が開かれ,学費値上げ撤回を要求して翌 14日にストライキに入る。法学部は
学年末試験を延期。以後,他の学部もストライキに入る〈学報 879・49−50〉
4・1
第一・第二文学部,教養課程・専門課程 2・2年制を 1・3年制に改める〈⑤ 612〉
4・1
産業技術専修学校廃校,早稲田大学専門学校(産業技術専門課程——校長三田洋二)開校
〈⑤ 625〉
4・1
現代政治経済研究所(所長正田健一郎)設置〈⑤ 652〉
4・15
総長選挙規則検討小委員会,検討結果を評議員会に答申〈⑤ 563−565〉
4・15
創立 100周年記念事業計画委員会,「記念事業の候補」と「募金計画案」を盛り込んだ『創立 100周年記念事業計画委員会小委員会中間報告』を作成,これを公表して意見や提案を求める〈⑤
979−981〉
4・28
理事会,保存図書館を本庄校地に設けるため保存図書館設置検討委員会を設置〈理事〉
5・26
評議員会,総長候補者の略歴・業績書に候補者以外の者が執筆した推薦文を添付してよいとす
る改正「総長選挙規則」を可決,即日施行〈⑤ 565〉
7・1
理工学部の住居表示が新宿区西大久保 4丁目 170番地から新宿区大久保 3丁目 4番 1号に変
更〈⑤ 203〉
9・20
フライブルク大学教授ハンス−ハインリッヒ・イェシェックに名誉博士号贈呈〈⑤ 212〉
10・27
篤志家からの寄附金を基に機械工学学術賞基金を設定し,機械工学に関し卓抜な成績を挙げた
学生を褒賞〈広報昭和 53年 11月 29日号〉
11・4
村井資長,総長退任〈⑤ 969〉
11・5
清水司,第 11代総長就任〈⑤ 972〉
1979年/ 昭和 54年
1・19
社会科学部,学生大会を開催,学費値上げに反対して翌 20日より 3月 1日までストライキに入る。
以後,他の学部もストライキに入り,学年末試験はリポート提出等の方法で行われる〈学報 889・56〉
1・25
早稲田中学・高等学校,契約書に調印して 4月 1日より学苑の系属校となる〈⑤ 632〉
1
創立 100周年記念事業計画委員会,清水司総長の下で活動再開〈⑤ 981〉
1
理事会,本庄校地に高等学校を新設することについて検討するために高等学校設置検討委員会
(委員長正田健一郎)設置を決定〈⑤ 633〉
2・23
エクステンション事業準備室(室長宇野政雄)設置〈⑤ 628〉
2
早稲田実業学校,一般の受験生と同一の入学試験を経た上で帰国子弟を受け入れる〈学報
887・58〉
3・15
評議員会,松代校地(新潟県)購入を決定〈⑤ 677〉
3・31
理工学部の化学系棟(65号館)竣工〈⑤ 666〉
4・1
早稲田大学専門学校,産業経営専門課程増設〈⑤ 626〉
4・27
大学からの繰入金と篤志家の指定寄附金を基に研究助成基金を設定〈広報昭和 54年 6月 13日号〉
7・16
教育学部または体育局で実技を担当する教員の定年を満 65歳に延長〈広報昭和 54年 11月 7日号〉
7
高等学校設置検討委員会の答申に基づき,本庄高等学院(仮称)設置専門委員会(委員長戸谷
高明)設置〈⑤ 634〉
9・17
創立 100周年記念事業計画委員会,答申「創立 100周年記念事業の基本計画について」をまと
める〈⑤ 982〉
10・3
ソニー株式会社取締役名誉会長井深大に名誉博士号贈呈〈⑤ 212〉
10・13
ベルリン・フィルハーモニー交響楽団終身常任指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤンに名誉博士号
贈呈〈⑤ 213〉
10・15
評議員会,創立 100周年記念事業計画委員会の答申に基づき,総合学術情報センター建設と,
新キャンパスでの人間科学系学部および体育・スポーツ科学系学部ならびに総合医科学研究セ
ンター新設と,国際交流センターおよび早稲田大学会館ならびに大学本部棟建設を骨子とし,募
金目標額を 200億円と定めた記念事業計画を決定〈⑤ 982−984〉
11・1
創立 100周年記念事業準備室を廃止し,創立 100周年記念事業推進連絡本部と記念事業事務
部門と記念行事事務部門と創立 100周年記念事業募金事務局を設置〈⑤ 984−985〉
11・5
エクステンション事業準備室,福岡国際ホールでエクステンション開講記念講演会開催〈⑤ 630〉
12・1
環境保全センター(所長村上博智)設置〈⑤ 645〉
12・14
主事会を廃止し,部長会および課長・事務長会を設置〈広報昭和 55年 1月 8日号,1月 12日
号〉
この年
南カリフォルニア大学と研究員交換協定を締結,昭和 55年度より交換開始〈⑤ 683〉
1980年/ 昭和 55年
1・16
第 1回創立 100周年記念事業委員会開催〈⑤ 985〉
1・18
第 1回創立 100周年記念事業募金委員会開催〈⑤ 985〉
1・18
理事会,「創立 100周年記念事業募金趣意書」を決定し〈理事〉,6月下旬に発送開始〈⑤ 989〉
1・18
理事会,安部球場周辺再開発事業委員会設置〈理事〉
2・24
商学部の入学試験問題漏洩,発覚〈広報昭和 55年 4月 17日号〉
3・27
新キャンパス用地取得対策連絡会発足〈⑤ 989〉
5・2
学部長会,入試制度検討連絡委員会設置〈⑤ 615〉
6・6
特定課題研究助成費および学術出版等補助費に関する規程を施行し,4月 1日に遡って適用
〈広報昭和 55年 7月 17日号〉
6・22
高等学院にプールおよび付属屋竣工〈⑤ 666〉
6
本庄高等学院(仮称)設置専門委員会,答申を提出〈⑤ 634−635〉
7・4
在学生が国際部協定大学に留学する場合,留学先で履修した科目の早稲田大学認定単位が最
高 30単位となる〈⑤ 698〉
7・15
評議員会,本庄高等学院の昭和 57年 4月開校を決定〈⑤ 635−636〉
8・1
本庄高等学院開設準備室(室長神沢惣一郎)発足〈⑤ 636〉
8・18
エクステンション事業準備室,第 1回創立 100周年記念地方講演会を富山県農協会館で開催
〈⑤ 993−994〉
9・19
理事会,創立 100周年記念事業実行委員会に 10専門委員会の設置を決定(うち 2専門委員会
は発足せず)〈⑤ 989〉
9
国際部設置科目を他学部の学生が受講する場合,それを正規の単位として認定〈⑤ 695〉
11・21
評議員会,所沢市三ヶ島地区を新キャンパス候補地として検討することを決定〈⑤ 987−988〉
11・21
第二学生会館改修工事竣工,25日開館〈⑤ 669〉
11・25
新キャンパス用地取得対策連絡会解散〈⑤ 990〉
12・8
新キャンパス用地取得対策委員会発足〈⑤ 990〉
12・18
現キャンパス総合整備計画委員会発足〈⑤ 990〉
この年
大学間協定に基づきラ・サール大学からの留学生受入と同大学への学苑学生派遣開始〈⑤ 697〉
1981年/ 昭和 56年
1
西門近くに相撲部の道場が完成し,11日道場開き挙行〈⑤ 800,学報 909・50〉
3・6
理事会,創立 100周年記念行事実行委員会の設置を決定し,11日に発足〈⑤ 993〉
4・1
エクステンション事業準備室を廃止し,エクステンション・センター(所長西沢脩)開設〈⑤ 630〉
5・7
商学部教授会,昭和 46年度以来入学試験問題漏洩および成績原簿改竄が行われていたことを
公表〈学報 911・32,広報昭和 56年 6月 12日号〉
5・8
評議員会,新キャンパス用地を所沢市三ヶ島地区と決定〈⑤ 990〉
5・25
森繁久弥主演によるミュージカル「屋根の上のヴァイオリン弾き」,創立 100周年記念行事の 1つ
として大隈講堂で上演〈⑤ 994〉
5・29
新キャンパス用地取得対策委員会を廃止し,新校地開発推進委員会設置〈⑤ 752,990〉
6・1
第一・第二文学部および体育局の住居表示が新宿区戸山町 42番地から新宿区戸山 1丁目 24番 1号に変更〈⑤ 196〉
7・3
学部長会,外国学生特別選考制度の受入基準緩和を承認,昭和 57年度より帰国子女募集を開
始〈⑤ 698−699〉
7
企画調整部,『早稲田大学大学問題研究会最終報告書(抜粋)』再版〈⑤ 506〉
7
大学と住民とから成る西早稲田地区市街地再開発協議会が発足し,安部球場周辺の地域社会
の文化的環境を向上させるための検討に着手〈学報 936・56〉
10・1
学外の情報処理施設およびデータ・バンクを共同利用するためのリモート・データ・ステーションを
理工学部構内に開設〈広報昭和 56年 12月 9日号〉
10・15
教務事務電算化委員会設置〈⑤ 753〉
10・20
武道館の跡地に体育厚生施設(17号館)竣工,体育施設だけでなく,学生生活協同組合も 13号館から移転して開業〈⑤ 668,783〉
10・30
戸山キャンパスの文学部木造校舎跡地に鉄筋コンクリート造校舎(34号館)竣工〈⑤ 667〉
この年秋
正門から鉄柵状の門扉を撤去し,アコーディオン式開閉ドアを設置〈⑤ 865〉
1982年/ 昭和 57年
2・25
理事会,100周年総合計画審議会の設置を決定〈⑤ 991,広報昭和 57年 7月 30日号〉
2・28
本庄高等学院第 1期工事竣工〈⑤ 672〉
2
2代目校旗完成〈学報 925・32−33〉
3・10
英仏遠征中のラグビー蹴球部,日本の単独チームとしては初めてケンブリッジ大学チームに勝利
〈⑤ 801,1006−1007〉
3・31
大学史編集所,学苑創立 100周年記念出版『小野梓全集』(全 5巻)刊行
4・1
本庄高等学院(学院長神沢惣一郎)開校,4月 6日開校式挙行〈⑤ 638−639〉
4・1
津田奨学基金を廃止して津田左右吉記念基金を設定し,津田奨学金,津田博士記念室設置お
よび管理,津田墳墓管理に充当〈広報昭和 57年 1月 22日号〉
4・1
十代田奨学基金と建築学奨学基金を廃止し,新たな建築学奨学基金設定,大学院理工学研究
科の建築学専攻学生で成績優秀者に奨学金を支給〈広報昭和 56年 12月 18日号〉
4・1
篤志家からの寄附金を基に鋳物研究所研究奨励基金を設定〈広報昭和 57年 3月 8日号〉
4・15
教務事務システム開発準備室設置〈⑤ 753〉
4・15
フランス共和国大統領フランソワ・モーリス・ミッテランに名誉博士号贈呈〈⑤ 213〉
4・23
教務事務電算化委員会,答申を総長に提出〈広報昭和 57年 6月 23日号〉
4・28
100周年総合計画審議会が発足し,清水司総長,「現キャンパスにおける教育研究条件の整備
充実計画を考慮した 100周年記念事業の内容について」を諮問〈⑤ 991,1008〉
5・28
学苑の事業を援助した者に賛助員の名称を贈る制度を設ける〈広報昭和 57年 7月 12日号〉
6・15−16
総長候補者選挙が行われ,西原春夫と本明寛が候補者となる〈⑤ 1008〉
6・21
元アメリカ合衆国上院議員ジェームズ・ウィリアム・フルブライトに名誉博士号贈呈〈⑤ 213〉
6
北京大学と学術研究交流の協定書を交換し,昭和 58年 4月より研究者の交流開始〈⑤ 683〉
7・22
総長決定選挙が行われ,西原春夫が当選〈⑤ 1008−1009〉
9・22
参議院議員河野謙三に名誉博士号贈呈〈⑤ 213〉
9・30
中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会副委員長・日中友好協会会長廖承志に名誉博
士号贈呈〈⑤ 213〉
10・1
スポーツ振興に顕著な功績を挙げた 70歳以上の校友を表彰するための「スポーツ功労者表彰規
程」施行〈広報昭和 57年 11月 26日号〉
10・4
学生能楽連盟 7団体および校友能楽師・狂言師による創立 100周年記念祝賀能,大隈講堂で
上演〈⑤ 1005−1006〉
10・20
ボン大学前総長ハンス−ヤコプ・クリュンメル,パリ大学区総長ピエール・タバトニ,モスクワ大学総
長アナトリー・アレクセーエヴィッチ・ログノフ,高麗大学校前総長・大韓民国国務総理金相浹,マ
ラヤ大学副学長ウンクウ・アブドル・アジズに名誉博士号贈呈〈⑤ 213〉
10・21
創立 100周年記念式典,記念会堂で挙行〈⑤ 995−999〉
10・22−23
国際シンポジウム「21世紀をめざす世界と日本」,大隈小講堂および小野講堂で開催,また「世界
の大学」および「ロボット・生命・人間」をテーマとする創立 100周年記念講演,大隈講堂で開催
〈⑤ 1000−1004〉
10・24
創立 100周年記念クラシック演奏会,記念会堂で開催〈⑤ 1006〉
10・30
創立 100周年記念歌舞伎「勧進帳」鑑賞会,大隈講堂で開催〈⑤ 1006〉
11・4
清水司,総長退任〈⑤ 1009〉
11・5
西原春夫,第 12代総長就任〈⑤ 1009〉
12・13
織田幹雄,スポーツ功労者(第 1号)として表彰〈広報昭和 58年 1月 19日号〉
12
教育学部教育学科体育学専修,優秀な高校スポーツ選手を対象とする特別選抜入試を実施〈学
報 913・2〉
この年秋
入試制度検討連絡委員会,答申をまとめる〈⑤ 615〉
この年
初の帰国子女入学試験実施〈⑤ 699〉
この年
理工学部,推薦入学実施〈学報 913・2〉
1983年/ 昭和 58年
1・17
西原春夫総長,100周年総合計画審議会に「総合学術情報センターの内容の具体化」と「新キャ
ンパスに設置する教育・研究施設」を諮問〈⑤ 1009〉
3・15
事務機械化推進本部(本部長新井隆一)設置〈⑤ 753〉
3・18
100周年総合計画審議会,1月 17日の総長諮問の了承を答申〈⑤ 1009〉
3・26
創立 100周年記念地方講演会(最終回)を徳島県建設センターにて開催〈⑤ 994〉
4
システム科学研究所,社会人を対象とする 1年制の全日制研修教育機関「早稲田ビジネススクー
ル(WBS)」 開校〈『定時商議員会報告書』昭和 59年・109〉
5・31
創立 100周年記念行事実行委員会,任務を完了して『早稲田 1982年――記念行事記録――』
を 6月に刊行〈広報昭和 58年 6月 30日号〉
6・1
創立 100周年記念事業推進連絡本部および新校地開発事業室を廃止し,創立 100周年記念事
業整備建設本部を発足させるとともに,創立 100周年記念事業募金事務局を本部事務組織に組
み込む〈⑤ 752〉
6・15
総長が 100周年総合計画審議会に対し,第 1次実施計画として(1)総合学術情報センターの設
置,(2)総合人間科学系学部および総合人間科学研究センターならびに運動施設の設置・建設
について諮問し,審議会は各小委員会を設置〈⑤ 1009−1010〉
7・15
教務事務システム開発準備室を廃止し,事務システム開発室設置〈⑤ 753〉
8・20
基本計画を策定した西早稲田地区市街地再開発協議会が解散して,西早稲田地区市街地再開
発準備組合が設立総会を開催〈学報 936・56〉
9・16
安部球場周辺再開発事業委員会を廃止し,西早稲田地区市街地再開発事業対策委員会設置
〈広報昭和 58年 10月 12日号〉
10・15
電子計算室を廃止し,情報科学研究教育センター(教務部直轄)設置〈広報昭和 58年 12月 6日
号〉
1984年/ 昭和 59年
2・15
100周年総合計画審議会,小委員会の報告に基づき,昨年 6月の総長諮問(1)総合学術情報セ
ンター設置につき約 60億円の予算で実施することを総長に答申〈⑤ 1028〉
3・2
100周年総合計画審議会の答申を受けて,総合学術情報センター実施計画委員会を設置
〈⑤ 1028−1029,広報昭和 59年 5月 2日号〉
4・1
第一文学部に学科制が復活するとともに,史学科に考古学専修設置(この時,第一・第二文学部
の「専攻」は「専修」に改められる)〈『定時商議員会報告書』昭和 59年・39〉
4・6
総合学術情報センター実施計画委員会設置に伴い,創立 100周年記念事業実行委員会の 8専
門委員会廃止〈⑤ 1029〉
7・13
100周年総合計画審議会,総合人間科学系学部および総合人間科学研究センターならびに運
動施設の設置・建設について総長に答申〈⑤ 1011〉
9・14
所沢キャンパス実施計画委員会設置〈⑤ 1011〉
9・17
『早稲田大学学術年鑑』創刊〈⑤ 523〉
10・31
総合学術情報センター実施計画委員会,「総合学術情報センター基本計画書」を承認
〈⑤ 1029−1030〉
11・9
新学部設立準備委員会設置〈⑤ 1011〉
11・15
評議員会,創立 100周年記念事業第 1次実施計画を決定,また所沢校地開発計画粗成工事起
工式挙行〈⑤ 1011〉
1985年/ 昭和 60年
1・1
創立 100周年記念事業整備建設本部を廃止し,建設本部設置〈広報昭和 59年 12月 28日号〉
5・29
評議員会,人間総合科学部の設立計画を議決〈⑤ 1011〉
6・1
高等学院の住居表示が練馬区上石神井 1丁目 216番地から練馬区上石神井 3丁目 31番 1号に変更〈⑤ 155〉
7・31
人間総合科学部設置認可申請書を文部大臣に提出〈⑤ 1012〉
9・25
所沢キャンパスに新設予定の人間総合研究センターの 1研究テーマとなるストレス研究のために,
財団法人パブリックヘルス・リサーチセンターと事業提携の覚書を交換〈⑤ 1026〉
11・3
タイル募金およびスポーツ募金の募集開始〈⑤ 1037〉
11・15
エクステンション・センター棟竣工,25日に竣工式挙行〈広報昭和 60年 11月 28日号〉
12・1
新学部設立準備委員会を廃止し,人間総合科学部開設準備室設置〈⑤ 1012〉
12・9
100周年総合計画審議会,総合学術情報センター施設計画と人間総合研究センター設立構想と
予算額の一部修正についての総長の報告を了承して解散〈⑤ 1010〉
1986年/ 昭和 61年
2・2
所沢新キャンパス建築工事地鎮祭挙行〈⑤ 1012〉
2・18
総合学術情報センター実施計画委員会,施設計画図改定案を承認〈⑤ 1031〉
4・1
人間総合研究センター開設準備委員会設置〈⑤ 1027〉
5・29
評議員会,人間総合科学部の人間科学部への名称変更を決議〈⑤ 1012〉,これに伴い,人間総
合科学部開設準備室を人間科学部開設準備室と改称〈広報昭和 61年 6月 10日号〉
6・30
あらためて人間科学部設置認可申請書を文部大臣に提出〈⑤ 1012〉
10・30
松代セミナーハウス竣工〈広報昭和 61年 11月 26日号〉
11・5
西原春夫,総長重任〈広報昭和 61年 11月 20日号〉
12・23
文部大臣,人間科学部の設置を認可〈⑤ 1012〉
1987年/ 昭和 62年
4・1
教育学部教育学科体育学専修,学生募集を停止〈⑤ 1023〉
4・1
理工学部の金属工学科を材料工学科と改称〈広報昭和 61年 5月 13日号〉
4・1
所沢キャンパスに人間科学部(人間基礎科学科,人間健康科学科,スポーツ科学科――学部長
浅井邦二)開設,卒業生には社会学士を授与〈⑤ 1014〉
4・1
所沢図書館開館〈⑤ 1037〉
4・15
人間総合研究センター(所長牛山積)設置〈⑤ 1027〉
4・21
野球部関係者と大学との間で,安部球場の用地転用に関する協議が整う〈⑤ 1032〉
5・1
松代セミナーハウス開設〈広報昭和 62年 3月 13日号〉
5・17
所沢キャンパスで所沢校地開発計画(第 1期工事)竣工式・落成式および人間科学部開校式挙
行〈⑤ 1014〉
5・28
所沢キャンパスにカール・ミレスの彫刻「人とペガサス」設置〈学報 976・54〉
5・29
理事会,総合学術情報センター基本設計書を承認〈⑤ 1034〉
6・12
現キャンパス総合整備計画委員会を廃止し,将来計画審議会(第 1次)を設置〈広報昭和 62年 8月 19日号〉
7・15
所沢キャンパス自然環境保全委員会および所沢キャンパス自然環境調査室設置〈⑤ 1028〉
10・15
統合情報ネットワーク運営委員会(「WINS委員会」,教務部所管)設置〈広報昭和 62年 11月 24日号〉
11・6
東伏見体育施設竣工〈広報昭和 63年 1月 26日号〉
11・22
安部球場で最後の全早慶野球戦開催,このあと安部球場が取り壊され,翌 12月に野球部の練習
場は東伏見に移転〈⑤ 1034〉
1988年/ 昭和 63年
3
西早稲田地区市街地再開発準備組合,基本計画を策定〈学報 986・39〉
4・1
大学院理工学研究科の資源及金属工学専攻を資源及材料工学専攻と改称〈広報昭和 62年 9月 21日号〉
4・1
語学教育研究所より日本語研究教育センターが分離・独立〈広報昭和 63年 5月 19日号〉
4
エクステンション・センター,合計 76単位を履修すると修了証を授与する「オープンカレッジ」開設,
4月 9日に開講記念講演会開催〈学報 980・44−46〉
5・27
情報科学研究教育センターを教務部所管から独立の研究所に改組〈広報昭和 63年 7月 15日
号〉
10・21
鋳物研究所を各務記念材料技術研究所と改称〈広報昭和 63年 8月 15日号〉
11・18