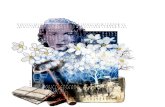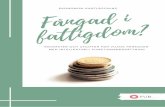156 ̈ .docx) vw 71P]gmnopq]`x jJyz( ! ¤w^8 >qG . ] ¥ - BC >q 8 ] ! "# $ D¨' 8 ] ©Kro ª../ . ]...
Transcript of 156 ̈ .docx) vw 71P]gmnopq]`x jJyz( ! ¤w^8 >qG . ] ¥ - BC >q 8 ] ! "# $ D¨' 8 ] ©Kro ª../ . ]...
◇ 学年 第6学年 ◇ 単元名 相手のコートに打ち返せ!プレルボール(E ボール運動 イ ネット型) ◇ 本時の目標 相手のアタックを防ぐためには,どのように守ると良いのかがわか り,ポジションや役割を考えることができるようにする。 ◇ 学習の流れ(6時間目/全8時間) 学習活動 指導上の留意事項(◇) ((((◆「努力を要する」状況と判断した◆「努力を要する」状況と判断した◆「努力を要する」状況と判断した◆「努力を要する」状況と判断した児童児童児童児童への指導の手立てへの指導の手立てへの指導の手立てへの指導の手立て)))) 評価規準〔観点〕 (評価方法) 1 準備・準備運動・挨拶 2 課題意識をもたせる。 3 本時のめあてを確認する。 4 ゲーム1(ペアチームで)10 分 ・ペアチームで「人と人の間」や「コートの端」等をねらって強いボールを打ち合うゲームを行う。 守りを組織化する必要性に気付く 5 チームタイム(ペアチームで) (作戦会議&コート練習)10 分 ・グリッドコートを利用して,守り方 の作戦を考える。 ・考えた作戦(動き)をペアチームと協力してコート内でやってみる。 6 ゲーム2(チーム対抗で)15 分 ・グリッドコートで対抗戦を行う。 ・前・後半各 5 分のゲーム A・B ペア対 C・D ペア E・F ペア対 G・H ペア 7 本時を振り返り,次時につなげる。 8 整理運動・片付け・挨拶
◇5時間目まで「攻め」中心の学習を展開し,各チームの攻撃が上達している。そこで「チームがゲームに勝つためにはどうしたら良いのか」を問いかけ,相手のアタックを防ぐ必要性に気付かせる。 ◇既習事項を確認できるよう,資料や図を掲示する。 【子供たちが見付けた攻撃のポイント】 「強いボール」を打つ。「人と人との間」,「コートの端」, 「相手の足下」をねらうと得点につながりやすい。 【これまでのポジションの変化】 (1・2 時間目) ○ ○ ○ ○ (3 時間目) ○ ○ ○ ○ (4・5 時間目) ○ ○ ○ ○ 役割分担が未分化 後衛1人守備 後衛2人守備 ◇前半と後半でプレーヤーとアドバイザーを交代するよう指示し,考えた作戦(動き)を相互評価できるようにする。(前半:A プレーヤー,B アドバイザー/後半:B プレーヤー,A アドバイザー) ◇「攻め」も「守り」も上達することで,最終的には「相手の守りに対応し,攻め方を組み立てるゲーム」に発展することを示唆する。
・自分のチームの特徴に応じた「守り」の作戦を立てている。 〔思考・判断〕 (発言・行動観察・学習カード)
体育体育体育体育科科科科の事例の事例の事例の事例 ○○○○ 攻守の切り替えに合わせてポジショニングを変更できる攻守の切り替えに合わせてポジショニングを変更できる攻守の切り替えに合わせてポジショニングを変更できる攻守の切り替えに合わせてポジショニングを変更できる。。。。
本単元を通して育てたい力
【守りの作戦例】 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ◆ポジションや役割に応じた動きが困難な児童には,グリッドコート内で一緒にやってみる。
【習得している知識・技能等】 ・ボールをコントロールして返球するために必要な組み立ての方法+ある程度のボール操作技能
★4の学習活動で明らかにした課題を基に,ペアチームで守りの作戦を考え,試行しながら練習に取り組むことで,対抗戦での活用につなげることができます。
話合いの視点を明確にするとともに,考えたことを試してみる場を設定しましょう。
児童のまとめ例 ・ 「一人一人が守るべきエリア」や「人と人の間にアタックされたときの約束」を決めたり,お互いに声 をかけ合いながらポジションを確認したりすることで,レシーブのフォローができ,攻めにつなげること ができました。
《本《本《本《本時時時時での活用とは》での活用とは》での活用とは》での活用とは》 相手の攻撃相手の攻撃相手の攻撃相手の攻撃のののの上達上達上達上達とともにとともにとともにとともに,守りを,守りを,守りを,守りを組織化して点を取られないようにし組織化して点を取られないようにし組織化して点を取られないようにし組織化して点を取られないようにしないと試合に勝てなくなるので,守ないと試合に勝てなくなるので,守ないと試合に勝てなくなるので,守ないと試合に勝てなくなるので,守りのポジションや役割に視点を当てりのポジションや役割に視点を当てりのポジションや役割に視点を当てりのポジションや役割に視点を当てた作戦が必要となるた作戦が必要となるた作戦が必要となるた作戦が必要となることことことこと チームでの守り方の作戦を考えよう。(そして,攻めにつなげよう。)
○相手はコートの端を狙ってくるからなるべくコートの端を守るようにする。 ○足下にアタックされたらできるだけ高く上げて他の人がフォローする。 ○間も狙われるので矢印のエリアも守る。
◇ 学年 第3学年 ◇ 単元名 体つくり運動「体力を高める運動」 ◇ 本時の目標 自己の健康や体力に応じて強度,時間,回数,頻度を 設定し,運動の計画を立てることができるようにする。 ◇ 学習の流れ(5時間目/全7時間) 学習活動 指導上の留意事項(◇) ((((◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導の手立て◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導の手立て◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導の手立て◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導の手立て)))) 評価規準〔観点〕 (評価方法) 1 課題意識をもたせる。 2 本時のめあてを確認する。 3 トリオ学習1(体ほぐしの運動) ・緊張を解いて脱力できる運動を選択し,組み合わせて行う。 4 運動後に,感じたことを共有する。 5 トリオ学習2(運動の実践及び計画の修正) ・Bくんは作成した運動計画を説明する。 ・Bくん作成の運動計画を3人で実施する。 ・運動計画を見直し,修正する。 ・改善した運動を1種目実施する。 6 本時のまとめを行う。 7 本時を振り返り,次時につなげる。
◇新体力テストの結果から,自己の体力の優れている要素と課題と思われる要素を確認するとともに,習得している知識・技能を活用して,自己の健康や体力に合った運動を計画するよう,生徒へ助言する。 ◇ねらいに合った運動例を選択できるよう,運動例を書いた学習資料を掲示する。 ◇緊張を解いて脱力できるよう,音楽をかけるなど工夫する。 ◇「汗をかいたあとは,すっきりした気分になるね」,「体の調子が整うとストレスが軽減できるね」など, 感じたことを共有化できるようにする。 ◇工夫したことやサポートしてほしいところなどを,他 の2人に伝えるよう指導する。 ◇互いにサポートしながら,運動の行い方が正しく,安全に実施できるよう支援する。 ◆「健康に生活するための体力を高めるには,この運動は負荷が強すぎるので○○の運動は,1セット○回,週○回くらいがいいと思うよ」等,アドバイスの例を紹介し,それらを参考にしながらアドバイスができるよう指導する。 【観察する視点】 ①ねらいに合った運動であるか ②偏りがなく,Bくんに合っているか ③運動の強度,時間,回数,頻度は適しているか ④実生活の中でできる運動であるか ◇他の2人から 受けた指摘の中から,改善するとよい点を見付け,実生活の中で継続して取り組める運動計画への修正を繰り返し行うよう指導する。 ◇振り返りの視点を明確に提示し,振り返りを深めるようにする。
運動の種類 強度 量・回数 頻度 なわとび ふつう 15~20 分 月・水・金 竹ふみ 強 5分 毎日
運動の種類 強度 量・回数 頻度 なわとび ふつう 5~10 分 火・木 竹ふみ ふつう 5分 毎日
・ねらいや体力の程度に応じて強度,時間,回数,頻度を設定している。〔思考・判断〕 (学習カード・行動観察)
保健体育科の事例保健体育科の事例保健体育科の事例保健体育科の事例 ○○○○ 各自が健康や体力に応じて「健康に生活するための体力を各自が健康や体力に応じて「健康に生活するための体力を各自が健康や体力に応じて「健康に生活するための体力を各自が健康や体力に応じて「健康に生活するための体力を高める」と「運動を行うための体力を高める」のどちらかを高める」と「運動を行うための体力を高める」のどちらかを高める」と「運動を行うための体力を高める」のどちらかを高める」と「運動を行うための体力を高める」のどちらかを選択し,日常生活の中で継続して取り組める運動の計画を立選択し,日常生活の中で継続して取り組める運動の計画を立選択し,日常生活の中で継続して取り組める運動の計画を立選択し,日常生活の中で継続して取り組める運動の計画を立て,体力の向上を図ることができる。て,体力の向上を図ることができる。て,体力の向上を図ることができる。て,体力の向上を図ることができる。 本時の学習を通して育てたい力 【習得している知識・技能等】 ・体ほぐしの運動及び体力を高める運動の運動例 ・運動を継続する意義,体の構造,運動の原則の 理解
★観察の視点を明確にすることで,適切な自己評価・相互評価をしながら,運動計画を実践することができ,修正につながります。 観察の視点を明確にする学習カードを工夫し,グループで観察し合う活動を仕組みましょう。
生徒のまとめ例 ・私は,「健康に生活するための体力を高める」ための運動を計画し実施しました。しかし,友達からのアドバイスにより,少し過重な計画だったと気付きました。今後は,日常生活で継続して取り組めるよう,自分の健康や体力に適した運動の強度,時間,回数,頻度を計画するよう,修正していきたいです。
自己の健康や体力に応じて強度,時間,回数,頻度を設定し,運動の計画を立て実践してみよう。 ★教師の発問を工夫することで,ねらいに合った運動になっているか考えさせ,適切な運動を選択することにつなげていきます。
発問を工夫し,ねらいに合った運動を選ばせましょう。
◇ 学年 第2学年 ◇ 単元名 体育理論 運動やスポーツの効果的な学習の仕方「運動やスポーツの活動時の健康 ・安全の確保の仕方」 ◇ 本時の目標 これまでの健康・安全に関する学習の知識を基に,運動やスポーツ を行う際に,気象条件の変化などの様々な危険を予見したり,回避 する方法について説明することができるようにする。 ◇ 学習の流れ(6時間目/全6時間) 学習活動 指導上の留意事項(◇) ((((◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導の手立て◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導の手立て◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導の手立て◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導の手立て)))) 評価規準〔観点〕 (評価方法) 1 課題意識をもたせる。 2 本時のめあてを確認する。 3 自然に関わるスポーツを挙げる。 4 自然に関わるアウトドアスポーツの事故の記事を読んで,事故発生の原因を考える。 5 グループワーク ○ 次の場面の健康・安全面の危険性と対応策についてグループで話し合う。 ・台風接近時のサーフィン ・台風接近時のキャンプ ・雷雨時の屋外スポーツ ・考査終了後のスポーツ ○ 全体に発表し,交流する。 6 本時のまとめを行う。 ○ グループの発表を基に,個人で振り返りを行い,ワークシートに記入する。 7 本時を振り返り,卒業後につなげる。
◇運動やスポーツを行う際の危険性を理解することが,生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続することにつながることに気付かせる。 ◇ 思い付いたことを発言させる。 ◇ワークシートに記入させる。 ◇アウトドアスポーツを実施する人の年齢,性別,経 験や気象,環境の状況,計画の仕方などについて考慮するよう助言する。 ◇自然の中では環境の変化への配慮が必要であるこ とを理解できるようにする。 ◇今までの生活の経験や本時に学習した内容を関連付けて意見を出すようにさせる。 【話し合う視点】 ① 予測される環境の変化 ② スポーツの実施者の状況 ◆話合いが上手くいかないグループには,「7月の期末考査後の運動部練習の時の様子」などをイメージさせ,話合いを行うように助言する。 ◇グループの発表を基に,個人でまとめる。 ◇危険を予見し,回避できるようになることは,生涯スポーツを継続するために必要なことである。この単元で学習したことを生かしてほしいと伝える。
・運動やスポーツを行う際の気象条件の変化などの様々な危険性を予見したり,回避する方法について説明できる。〔思考・判断〕 (ワークシート・行動観察)
保健体育科保健体育科保健体育科保健体育科((((体育体育体育体育))))の事例の事例の事例の事例 高等学校高等学校高等学校高等学校
○○○○ 卒業後のスポーツ活動を想定して,気象条件の変化など卒業後のスポーツ活動を想定して,気象条件の変化など卒業後のスポーツ活動を想定して,気象条件の変化など卒業後のスポーツ活動を想定して,気象条件の変化など様々な危険を予見し回避する意識と能力様々な危険を予見し回避する意識と能力様々な危険を予見し回避する意識と能力様々な危険を予見し回避する意識と能力 本時の学習を通して育てたい力 【習得している知識・技能等】 ・中学校の「安全な運動やスポーツの行い方」についての知識 ・運動・スポーツによるけがや健康面への影響,事故についての知識
★1つの事例から学んだことの活用が,卒業後のスポーツ活動の危険を予見し回避する意識と能力を付けることにつながります。 「4の学習活動」で学んだことを違う場面にも活用させましょう。
生徒のまとめ例 ・運動やスポーツを行う際には,行う人の性別,年齢,技術や体力を考慮して計画する必要がある。また,ゲリラ豪雨などの気象の変化を予測して,スポーツを中断したり,避難しないといけないと思った。
《本時での活用とは》《本時での活用とは》《本時での活用とは》《本時での活用とは》 「持っている知識を使「持っている知識を使「持っている知識を使「持っている知識を使って他人に説明する」とって他人に説明する」とって他人に説明する」とって他人に説明する」という行為を通して,新しいう行為を通して,新しいう行為を通して,新しいう行為を通して,新しい学習内容について理い学習内容について理い学習内容について理い学習内容について理解するということ。解するということ。解するということ。解するということ。 これまでの健康・安全に関する学習の知識を基に,運動やスポーツを行う 際に,気象条件の変化など様々な危険を予見したり,回避することができるようになろう。 【例】スキー,登山,キャンプ,海水浴など
![Page 1: 156 ̈ .docx) vw 71P]gmnopq]`x jJyz( ! ¤w^8 >qG . ] ¥ - BC >q 8 ] ! "# $ D¨' 8 ] ©Kro ª../ . ] V J]^ « G ¬ ª]^ Q R2 ,0 8 M® Kro ª.¯ ' ...](https://reader042.fdocument.pub/reader042/viewer/2022022619/5bac4fda09d3f2cb568b66df/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: 156 ̈ .docx) vw 71P]gmnopq]`x jJyz( ! ¤w^8 >qG . ] ¥ - BC >q 8 ] ! "# $ D¨' 8 ] ©Kro ª../ . ] V J]^ « G ¬ ª]^ Q R2 ,0 8 M® Kro ª.¯ ' ...](https://reader042.fdocument.pub/reader042/viewer/2022022619/5bac4fda09d3f2cb568b66df/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: 156 ̈ .docx) vw 71P]gmnopq]`x jJyz( ! ¤w^8 >qG . ] ¥ - BC >q 8 ] ! "# $ D¨' 8 ] ©Kro ª../ . ] V J]^ « G ¬ ª]^ Q R2 ,0 8 M® Kro ª.¯ ' ...](https://reader042.fdocument.pub/reader042/viewer/2022022619/5bac4fda09d3f2cb568b66df/html5/thumbnails/3.jpg)