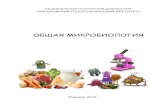Ô ì»Êùx R ﵀ rO lhTcdgakkai.ws.hosei.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2016/11/gb201601.p… ·...
Transcript of Ô ì»Êùx R ﵀ rO lhTcdgakkai.ws.hosei.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2016/11/gb201601.p… ·...

日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか
――70年代序盤における日教組の政治的機会構造――
法政大学キャリアデザイン学部 教授 筒井 美紀日本大学人文科学研究所 研究員 長嶺 宏作
日本大学文理学部 准教授 末冨 芳
1 問題の所在と本論の目的 日本教職員組合(日教組)の教育・労働運動が大きな転換を余儀なくされたのは、1974年の4.11全一日ストに対する大弾圧である、と指摘されている。否定されたはずの公務員のストに対する刑事罰が復活し、大量の行政処分が発令され、他方で共産党の「教師聖職論」が日教組運動の分断を深めたからだ、と。たしかにそのとおりで、1974年の4.11は決定的なピークであるとして、多くの言及がある。ストの通称からも明らかなように、73年は半日ストを構えたので、74年はいよいよ全一日だ、との目標を日教組は掲げた。こうしたストへの傾斜は、なぜこのタイミングで、どのように生じたのか。日教組は、73年の半日ストをどのように闘い、何がもたらされたのか。本論は、これらの問いを解明する(1)。74年のピークの迎え方を、より深く理解すべく、プレリュードの部分を詳らかにする。 先行研究を紐解くと、この解明は必ずしも充分ではない。たしかに、日教組が高めてきた対決的姿勢や戦闘性は、GHQのゼネスト中止勧告による政令201号への反発、そこに発するスト権奪還への強烈な意欲、55年体制と教育政治がもつイデオロギーの磁力に求められる(Duke�1973)。この大きな図柄に加えるべきなのは、政治過程を細かく追うことで確認される、さまざまなアクターの行為、そしてそれらの関係である。
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 61

ところが労働運動史の分野では、日教組が対象とされるのは、主要単産の生成と展開の全体像をつかむという視点(岡崎ほか1971)や、春闘や政治選挙といったイベントにおける各単産の行為とその影響という視点(水野2002a)に基づくことが多く、日教組の分析は一定レベルに留まる(筒井2014)。他方、労働政治学・教育政治学の分野では、Thurston(1973)による、日教組の創設以来を対象にした総合的研究がある。ただし対象期間は1971年までであり、日教組とその外部環境との関係は、行政(文部省・教育委員会)とILOと社会党とが対象とされ、総評・公務員共闘・公労協などとの関係には踏み込んでいない。だが、日教組の態度や戦略は、当時の労働界での位置や他労組の在り方・動向のなかで形成されてきたのだから、これを等閑視することはできない
(筒井2014)。 本論も(2)、「集団にとって外部にある資源を強調する」政治的機会構造論に依拠する(Tarrow�1998=2006,�p.49)。政治的機会構造論は、人びとは機会に基づいて行為するというトクヴィルの命題に着想を得た考え方で、ストライキといった集合行為(collective�action)の一般説明法則ではなく、「それがいつ生じるかを知るための手がかりとして理解されるべき」ものである(Tarrow�1998=2006,�p.49)。政治的機会構造とは、集合行為の誘因を与えるもののことであり、そのほとんどは流動的な性質をもつ(同書、第5章)。以下では、日教組の政治的機会構造がいかに状況依存的であったか――日教組のストライキという集合行為が、当時の総評における位置によって、いかに左右されたか――が明らかにされる。 そのために行なった作業は次のとおりである。まず、各労組・労働団体の年史や労働運動の当事者・関係者の著作内に散在する、大小さまざまな出来事を整理する。続いて、「出来事AとBのあいだには何があったのか」「水面下でC氏に話をつけたのは誰だったのか」といった問いを設定し、日教組や総評の大会や委員会の議事録(速記録)の読み込みと、当事者からの聴き取りによって、これらの「見えない糸」を結んでいく。 1973年は、日教組(と公務員共闘)が春闘に初めて本格的に参加した年である。それまで、日教組がその牽引車となってきた公務員共闘の運動は、8月の人事院勧告と12月の予算審議に焦点を当ててきた。ただし、「政府は人事院の
62 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

勧告をまたずに賃金回答すべき義務と責任がある」(日本教職員組合1977:351)として、1972年は春闘後段(5.19)にストを構え、その準備として初めて春段階(3月)に臨時大会を開催するなど、徐々に本格化を進めてきた。ここで1973年が「本格的」参加の年だというのは、半日ストを、最高の山場である4月下旬(4.27)に設定したからである。前年7月に自民党文教部会が人確法の骨子をまとめたことを踏まえて、日教組は73春闘で、「五段階賃金阻止、賃金大幅引上げ」「処分阻止、スト権奪還」を二大要求とした(日本教職員組合1977:352)。 日教組が、1970年代初頭に春闘への本格的参加を決意したのは、1970年代に入って総評が「本格的な階級闘争」、つまり賃金闘争のみならずスト権奪還闘争に注力するようになり、それゆえ総評・春闘共闘委員会と首相や官房(副)長官など政府のトップ層との交渉の場に、日教組も臨む必要があったからである。文部大臣・文部省との不毛な協議・交渉に長いあいだ業を煮やしていた日教組にとっては(槇枝1976)、これは合理的な行為であっただろう。ただしそのためには、国労や動労、全逓や全電通に負けないようなストの力量を示し、日教組要求を総評内で聞き入れてもらう必要がある。当時の総評では、スト権はストライキの行使によってこそ奪還できるという運動理論が優勢であったから、他労組との比較に基づくこうした理屈が日教組内で唱えられていた(筒井2014)。 実際に73春闘では大規模なストが構えられ、総評・春闘共闘委員会は、「七項目合意」という一定の成果を得る。「一定の」とは、総評・春闘共闘委員会として必ずしも満足のいく結果ではなかったと同時に、日教組にとっては大きな不満が残る結果であった、という意味である。しかも文部省は、「七項目合意」を蔑ろにし続けた(図表1に関連年表)。 以上を踏まえると、先述した解明課題は、より具体的に次の4つに設定できる。第1に、1958年の勤評闘争以来、多数の救援対象者を抱えて財政的に苦しく、ストに必ずしも積極的ではない組合員が多数おり、また主流左派/主流右派/反主流派に分かれるなか、日教組としては大規模な半日ストの方針決定はいかにしてなされたのか。(第3節)。第2に、「日教組と公務員共闘は総評のドル箱」と言われていたものの、公務員共闘および総評における日教組の位置
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 63

づけは、実際はどの程度だったのだろうか(第4節)。第3に、日教組は「七項目合意」の何が不満で、総評内でそれをどのように訴えたのだろうか(第5節)。第4に、「七項目合意」を無視し続けた文部省に対し、日教組はいかなる交渉を試み、その結果はどうだったのだろうか(第6節)。これら4つの問いの解明によって、日教組が1974年の闘争のピークへと向かっていく状況を、より深く理解することができよう(第7節)(3)。
2 データと方法 本論で主に活用するデータは次の5つである。(1)各労組・労働団体の年史
(『日教組三十年史』『総評四十年史』『公労協スト権奪還闘争史』『公務員共闘三十年のあゆみ』)、(2)当事者(槇枝元文、大木正吾、安養寺俊親など)の著述。(3)日教組中央委員会と大会の議事録(速記録)、『議案資料集』や『大会決定事項集』、規約・細則。(4)総評大会と総評拡大評議員会の議事録(速記録)、総評「73年春闘経過報告」。(5)日教組弾圧対策部長(1972〜1989年)を務めた髙山三雄氏の聴き取り(2013年8月29日、2014年12月22・23日実施)。 データ(5)について3点、補足説明をしておく。第1に、日教組本部の弾圧対策部(長)について。その職務は、昇給延伸などによる救援適用者の審査、処分撤回をめぐる文部省との交渉、各県教委との交渉や裁判闘争を行なう各県教組への指導・助言などである。組織内部では三役(委員長、副委員長、書記長)、法政部長、組織部長、財政部長など、組織外部では日政連議員や弁護団と緊密に連絡を取り合う。それゆえ、18年間この要職にあった髙山氏への聴き取りは、「見えない糸」を結んでいく作業の鍵の1つとなる。 第2に、聴き取りデータの利用方法について。以下の分析では、対象者の語りのうち、誰がいつ・どこで・何を行なったか・発言したかという行為レベルでの出来事を中心に利用し、対象者がなす「あのときはこのように思っていた」といった過去の感情や思考の回顧については「客観的事実」としては捉えていない。それには偏りがあるからであり(御厨2011)、本論の主眼は行為レベルでの「客観的事実」を確認することにあるからである。 第3に、聴き取りでは記憶の喚起に工夫を凝らした。事前の史資料調査から得られた出来事の場所・日時、関係人物、予算の推移などを年表やグラフにし
64 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

図表1 日教組73春闘半日スト関連年表日教組関係 政府、総評、公務員共闘
’69 4.2 最高裁都教組無罪判決11.13 11.13スト。12万人という空前の行政処分。
’70 3.10-11 #80中央委員会。組織機構整備特別委員会・藤山幸男委員長より、救援資金月額119円から450円への値上げ提案。
6.2-4 #38定期大会(徳島市)。上記値上げ承認。8.13 人事院勧告、初の5月実施。9.24-25 #81中央委員会。闘争資金ベースアップ1か月分
拠出の提案。108対69票で承認。’71 8.10 佐賀地裁、佐賀県教組事件の行政処分無効確認
請求に勝訴判決。’72 6.19-22 #41定期大会(秋田)
7.7 田中角栄内閣発足7.13 公務員共闘、7.13スト中止。春闘参加をめぐり、槇枝/
安養寺(自治労)で意見の相違。8.7-11 総評#44定期大会8.15 人事院勧告、初の4月実施。10.18-19 #86中央委員会。73春闘半日ストを決定。また、
全農林警職法の反動判決の可能性について情報キャッチ。
’73 2.13 公務員共闘賃専総会、教員給与10%上昇問題(差別的賃金体系)を調整できず。
2.20 政府、人確法を閣議決定2.26-27 総評#45臨時大会。日教組、闘争方針への教育問題を盛
り込みを提案、反応薄。3.1-2 #42臨時大会。73春闘半日スト決定。藤山幸男委
員長より、一人平均6000円の闘争資金臨時徴収の提案、了承。
4.26 公労協スト。4.27 日教組、公務員共闘とともに午前半日スト 国労72時間スト、私鉄総連48時間スト。
5:30am�山下官房副長官と大木事務局長との間で「七項目合意」と「五項目念書」。
5.1 政府側、「念書は存在しない、組合側の宣伝だ」と否定5.15 文部省、人事主管課長会議。各県の人事課長に、4.27ス
ト強行処分を指導、七項目合意は文部省には無関係の旨、伝達。
5.18 中小路書記長、岩間初中局長らに5.15人事主管課長会議について質す。後日正式回答する、と発言。
5.19 #5総評拡大評議員会。中小路書記長、日教組の窮状への対処を訴える。
5.28 岩間初中局長、「過去の処分については引き続き協議する」について曖昧な回答。
6.22 #6総評拡大評議員会。日教組代議員欠席するも、公労協系代議員より処分問題への対処の訴え。
7.16 槇枝-奥野文部大臣会談。議論は平行線。7.30-8.3 総評#45臨時大会。大会後の大量処分という背信行為へ
の対処をめぐり激論。8〜9月 国労・動労で14万人の処分。8.27 福岡県教委、4.27ストで18,773人処分。9.3 第三次公制審答申。
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 65

て提示し、また、髙山氏と親しい関係にあった平沢保人氏(元日教組情宣部長、主流右派)にも同席していただき、ともに質問した。聴き取りは全てICレコーダに録音し、反訳を作成した。
3 半日ストに向けての日教組内部の議論3-1 70年代初頭における日教組の状況 日教組は、1958年の勤評闘争以来、半日以上のストを構えてはおらず、勤務時間内への5〜10分食い込み、早朝29分、午前2時間、といった規模のストがせいぜいであった。その理由としては、1966.10.21ストへの弾圧(戒告以上の処分者6万人超)と、1969.11.13人勧完全実施要求ストへの弾圧(同・約12万人)が大きい。したがって、第86回中央委員会(1972.10.19)と、それに続く第42回臨時大会(1973.3.1-2)での、73春闘で半日ストを構えることという決定は、大きな決断であった。その経緯を確認していこう。 70年代初頭、日教組本部は、大規模ストを構えないと埒が空かないと考えていた。だからたとえば、橋本章夫副委員長は「ストライキをやや弱めて一息つく。そうしたことを何年か繰り返してよい情勢であろうか」と問いかけ(第81回中央委員会、1970.9.24-25)(4)、槇枝元文書記長(当時)は「公労協や民間がことしは24時間スト、48時間ストライキというのを組んでおる中で、30分ストライキをかまえて、政府出てこい、佐藤総理出てこいといっても、とてもじゃないけれども」無理だと指摘した(第84回中央委員会、1971.6.2)(5)。 ただし、大規模なストを構えるのには大金がかかる。ビラ・パンフレットの印刷や動員者の移動手段の手配(闘争基金特別会計)のみならず、処分による賃金・賞与カットや昇給延伸などの補償金や裁判費用(救援基金特別会計)が発生するからだ。これらの費用は組合員から毎月徴収していたが、闘争基金は臨時徴収もしばしばなされていた。
3-2 救援資金の大幅値上げ――119円から450円へ 1969.11.13ストへの行政処分は、日教組の資金繰りを根本的に変えてしまう。1960年の第一次賃金闘争以来九次までの合計を超える、12万人の処分が発令されたのだ。同スト後の第80回中央委員会(1970.3.10-11)における槇枝書記長
66 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

の説明によれば、これまでは、闘争資金の臨時徴収2000円、救援月額119円でやってきた。だが、「そうすると来年に送る金が一銭もない。しかも…闘争資金というものも追加せずにくずしてきている。こういう過程の中で来年度一挙に救援資金を増額しなければならないという事態に立ち至った」(6)。 この処分への対処には30億円かかるので、月額119円の救援資金は450円に値上げせざるを得ない。そう報告したのは、組織機構整備特別委員会の藤山幸男委員長(都教組委員長)である(7)。これに対する各県代議員からの質疑・意見は、主流左派/主流右派/反主流派とに整理される。要点を述べると、主流左派(岩手など)は、迫力のある闘争を遂行するため値上げは当然、主流右派
(神奈川や三重や兵庫)は、値上げには賛成だが展望を見せよ、また一般組合員の納得のいく下部討議のスケジュールと資料作成とをしっかりやれ、反主流派(長野など)は、値上げに反対はしないがストをやらない・やれない県教組の現状も認めてほしい、というものである。発言を逐語的に少し見てみよう。 岩手の代議員曰く、「救援の銭がないからそれをまかなうんだという考え方ではなくて、少なくとも七〇年代の闘いの展望に立った場合には救援体制の確立というよりも、むしろ闘争資金を備蓄というか、積み立ての強化をしていくのだという観点で、今後の指導をすべきではないか」(8)。他方で神奈川の代議員は、「なんといってもこの問題は11.13を闘ったあと大きく出てきた問題なんです。それだけに組合員には理解と納得のいく説明をしなければいけない…こまかいデータと親切な説明書をつけて…十分議論をしてよし日教組のためにやろうじゃないかという気構えを起こさせなければならない」と主張した(9)。 しかるに長野県の代議員は、率直に「ずいぶん一方的な角度から申し上げますと、長野県というのはずいぶんお人よしというようなことになりかねません」と述べた(ここで野次)(10)。長野の経験は時間外職場集会くらいでストは一度もないが、組織率は99%以上だ。ストとその拠出に反対する多くの組合員を支部役員が説得に回り、これまでの臨時闘争資金も全員が拠出してきた。その理由は、「結局組織を割らないということを一番大切に考えてきたから」であり、だから「侮辱的な野次も甘んじて受けているわけであります」。だが、今回の大幅値上げには「非常に困難な道であるという感じを持つわけであります」。
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 67

このように、119円から450円への救援資金の値上げに最も消極的なのは反主流派だが、決して強硬な反対を示していたわけではなかったのだ。かくして、第80回中央委員会で提案されたこの救援資金の値上げは、下部討議に付され、同年6月の第38回大会(徳島)にて承認される。だが、これで財政問題が片づいたわけではない。なぜなら、この値上げによって賄われるのは、過去の処分者への補償だからである。給与のベースアップが毎年あるから、そのぶん昇給間差は広がり、処分者数が同じなら、救援資金額は毎年上がる。
3-3 闘争資金――ベースアップ1ヵ月分拠出をめぐる議論 したがって、半日という大規模ストに備えるには、ずっと大がかりな金銭的備蓄が不可欠である。そこで、第38回大会(徳島)のあとに実施された第81回中央委員会(1970.9.24-25)では、第1号議案として、ベースアップ1ヵ月分を闘争資金として拠出、という本部提案がなされた。橋本副委員長が「…鋭い闘いを反復組織しうるような体制を確立し…闘いを…成功させるためには…苛酷な処分をはね返して闘いを継続、発展させうるような救援資金体制の確立を図ることが絶対に必要かつ不可欠なものであると思います」と述べると、議場がざわつき、議長が静粛を促した。「救援資金についてまず備蓄をしないで、言わば素手で…ストライキに突入する」(11)ようでは駄目であり、仮に全組合員が平均8千円出せば30数億円、1万円出せば40億円が積み上げられると指摘した。そのうえで、これを職場討議に付し、次回、次々回の中央委員会で集約していきたい、と括った。 槇枝書記長も、次のような説明を述べて補強する。「大会決定にある、数年後には、半日あるいは一日単位のストライキをもって七〇年代の課題を実現しよう。そのための資金としてまずこれだけは拠出をしておこうではないかということです…これはちょうど全逓なり[全]電通なり国労などが毎年その年の賃金引き上げの一ヶ月分差額を蓄積していくということを恒常化しておる、このことも一つの教訓としたわけです」(12)。 ところが、長野など反主流派はこの提案に反対し、主流右派の兵庫と神奈川も反対に回る。長野の代議員曰く「備蓄の必要を認めながらも、組合員の多くに理解できない点がある…闘争資金と救援資金は別なのか一緒なのか…本県の
68 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

実情として非常に組合員に混乱を招く危険性があり、ひいては組織問題ということも考えざるを得ない事態に追い込まれる」(13)。さらに兵庫の代議員は、この提案の「方向は、救援資金ないし闘争資金の拠出の思想を一変するもので、それだけに、さらに慎重な過程を積んだ提案がほしかった…積極的に闘争資金を備蓄する必要は認めます。しかし…現場の組合員が手の届くやり方で、積極的に闘争資金を準備するといった方向を期したい」と述べた(14)。 上記の発言からは、反対されているのは、ベースアップ1ヵ月分の拠出自体ではなく、それを熟議を経ずに提案した拙速さだということがわかる。大がかりな備蓄そのものには反対ではないのである。かくして、長野・神奈川・兵庫は、1ヵ月分拠出という文言を削除せよという修正案を出す。採決の結果は、108対69で否決となった。修正案賛成は4割、つまり日教組本部は危ない橋を渡ったのだが、そのあと結果的には、1971年7月の第39回定期大会(佐賀嬉野)では、ベースアップ1ヵ月分拠出は承認される。
3-4 主流左派/主流右派/反主流派のスタンス 通説的な日教組理解では、社会主義協会を理論的支柱とする主流左派が、ストの行使をとおしたスト権奪還を主張したのに対して、現実主義の主流右派と、教師聖職論の反主流派とがこれに反対した、とされている。だが以上から明らかなように、救援問題は、1970〜71年の時点では、これら三派のあいだで、実は争点と言うほどの争点にはなっていなかったのである。これは別稿で論じたいが、財政面とイデオロギー面から、救援問題とスト戦術がクリティカルに争点化していったのは、1974年の4.11全一日ストなのであった。 当時、弾圧対策部長であり、主流右派のリーダー格であった髙山三雄氏は、
「救援資金の急激な値上げで、組織に亀裂が入ったのではないか」という私たちの質問に否と答えた。「反主流は…『俺らはストライキは参加できないけども、処分をされたら救援資金や闘争資金は目一杯出すよ』と言っていた」。「俺は、あの頃、もう救援資金が底をつくので値上げしなければならないということで…。宇野やん[同じ法政部の宇野弘・滋賀]が内野[日教組本部]にはいたんだけども、外野[各都道府県教組]では埼玉高の山下[楠一]…。それと、大阪の…篠浦[一朗]」らと話をすると、「救援資金の値上げにはほとんど反対
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 69

しなかったんだ」。 64春闘が盛り上がる最中の4月8日、共産党は突如として「スト反対」の声明を出したことがあった。これがすぐさま7月に自己批判されると、日教組の反主流派も「賃金闘争の必要性を強調、1965年の日教組大会で『賃金でスト』の方針がだされると全面的に賛成し」、さらには「『人事院勧告の完全実施といった低い要求ではなく、大幅賃上げを要求して強力にたたかえ』と主張していた」(立川1981,�pp.87-88)。つまり反主流派は、1964年7月から、1973年の春闘半日スト中に都教組が「保護要員」を置くころまで、ないし、1974年4月17日付『赤旗』に「教師=聖職論をめぐって」が掲載されるころまでは、(消極的であったにせよ)ストに賛成であったのだ。 主流左派・右派ではどうだったのか。前項に挙げた、中央委員会での代議員の発言には、ストに対する温度差が感じられる。そこで、髙山氏に「むしろ主流派の中の左右で大きな意見の違いがあったんですか」と質問すると、「あった。それはあった。あったけども、決定的な反対はしなかったんだな。それはしょうがないもの」と答えた。「決定的な反対はしなかった」というのは、主流右派は、救援・闘争資金の大幅値上げを充分に議論しないプロセスを批判はしたものの、スト権奪還には大規模ストが必要、それには大がかりな備蓄が不可欠だという原理原則には反対ではなかった、と理解できる。 では、「それはしょうがないもの」というのは、主流右派は、嫌々ながらストに賛成していた、という意味なのか。髙山氏曰く「1971年辺りから、僕は、ストライキ権はストライキを積み重ねることによって奪還できるんだという考えだったんだ、この頃はね」。これは「俺なんかはストライキ推進派だった」という髙山氏個人の考え方だったのだろうか。そこで「右も左も、『スト権奪還』という建て前で、ストライキをやろうというのが声としては大きかった時代ですか?」と訊いてみると、「ああ。イケイケだったね。いま考えると、いかに教条的だったか」(15)。つまり、「それはしょうがないもの」が意味しているのは、ストを通じたスト権奪還は、やるからにはやるという積極的な構えであったと考えられる。
70 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

3-5 ストと通じたスト権奪還への誘因 集合行為に誘因を与えるもの、すなわち政治的機会構造は、Tarrow�
(1998=2006,�第5章)によれば、①制度的アクセスの開放、②政治的提携の変動、③エリートの分裂、④影響力のある同盟者、⑤国家の抑圧能力、に整理できる(16)。日教組の73春闘半日ストへの傾斜に関しては、①④⑤がとりわけ重要である。 まず①は、総評・春闘共闘委による中央政府交渉であり、文部省・文部大臣との不毛な交渉に苛立っていた日教組にとっては非常に重要な、政府への制度的アクセスであった。次に④は、①とも重なるが、スト権奪還路線で中央政府交渉を進めていた総評・公労協・公務員共闘であり(これについては第4節で詳述)、その後ろ盾となっていたILOである。 ⑤は、日教組にとってプラスとマイナスの要素とがある。プラスの要素は、1971〜72年にかけて裁判所が、勤評を初めとした事件に、立て続けに勝訴判決を下したことである(17)。髙山氏も「佐教組の事件。行政処分無効確認[等]等請求[事件]の勝利判決は期待をもったね。これはもう行政処分はないだろうと思いましたね」と述べている。 しかるにマイナスの要素とは、1972年7月7日に田中角栄内閣が発足したこと、政府・自民党が「和解は望ましくない」と、頑として強硬姿勢を変えなかったことである。日教組の弱体化に心血を注いだ田中総理大臣は、同年12月の第二次内閣で「日教組を目の仇にした」(槇枝2008,�p.191)奥野誠亮を文部大臣に起用する。なお日教組は、1972年秋の時点で、反動判決の可能性を掴んでいた。1972.10.18の第86回中央委員会で中小路清雄書記長は、「いま日教組の顧問弁護団その他等からの情勢として集約しますと、4.2都教組判決を支持するグループは現在十五名中の裁判官五名…反対する思われる裁判官は七名、未知数が三名…全農林警職法事件…等…最高裁の動向に対しては、私どもの緊急の行動が要請される状況にあります」(18)と述べている。 以上をまとめると、日教組は、1971年までに、闘争・救援資金の増額問題は差し当たりクリアするなかで、ストを通じたスト権奪還闘争にプラスとマイナスの出来事が錯綜する、将来の見通しが不透明な状況のもと、73春闘半日ストへと突入していく。Eisinger(1973,�p.15)を援用すれば、ストライキなどの「抗
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 71

議は政治的機会の開放的要素と閉鎖的要素との混合を特徴とするシステムにおいて」最もよく起こりやすい、ということである。勝ち負けいずれの見込みも立ちにくいからこそ、闘争行為へと誘われたと考えられよう。かくして、第42回臨時大会(1973.3.1-2)では、組織機構整備特別委員会が、73春闘では50億円かかる見込みなので、一人平均6000円の臨時徴収によって闘争資金の不足を補うことを提案し、これが了承される。 本節の最後に、ストライキを促すであろう、より根本的な要因があることを述べておきたい。それは、損失に対する脅威である。その究極は生命・生存に他ならない(Tarrow�1998=2006,�p.155)。日教組の場合は、ストを止めるとその非を認めたことになり、組合および組合員の社会的生存が否定されるということだ(19)。またストを止めることで、スト自体の非合理性を認めてしまい裁判闘争と処分撤回闘争でも負けてしまうことになる。これらは何としても避けたい・避けねばなない事態だったのではなかろうか。
4 公務員共闘における日教組の位置4-1 労働戦線の統一における官公労の位置づけ 本節では、労働運動における公務員共闘の位置づけを明らかにしてから、公務員共闘における日教組の位置づけを明らかにすることで、73春闘に向かう日教組の政治的機会構造を確認したい。 1973年の半日ストで民間労組とともに官公労も参加し(第1節)、74年には国民春闘として生活闘争、政治闘争へと運動が広がった。しかし、その拡大の背後には労働運動の行き詰まりの打開という面があった。1973年の第一次オイルショックを契機に高度経済成長が終息し、今までのような賃金要求型の運動が徐々に支持されなくなっていた。そこで再度、労働運動の再編が課題として浮上した。すでに1970年から労働運動の再編の議論がはじまり、合化労連の太田薫と鉄鋼労連の宮田義二を中心として民間組合が先行して同盟と総評の組合を結集した新しい労働戦線の統一(労戦統一)が目指された(20)。そのため労働戦線の統一が、同盟などと総評民間単産が主導権を取って行なわれる右派的な流れに対して、官公労を中心として対抗する動きがあった。 図表2にあるように、総評は432万規模の団体で、労働運動の中心にいるが、
72 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

同盟が228万人の規模で存在し、春闘などで闘うときには同盟との共闘がなければ、労働者側の要求が通りづらくなっていた。そこで図表2にあるように労働戦線の統一の主導権をどこが取り、統一の中心を、縦の棒線で示した位置の右側に置くのか、左側に置くのかで、綱引きがあった。 当時、春闘の賃金相場を決める有力な組合(パターンセッター)は、宮田の鉄鋼労連や太田の合化労連などの基盤産業のストにあり、それが労働運動の発言力や交渉力にも影響を与えていた。たとえば、73年春闘において、5月までストを行なった民間(金属、化学、交通などの中小組合、炭労、全鉱)は15,159円(20.1%)を獲得、72時間ストを行った公労協(国労、動労、全逓)は14,167円(17.5%)を獲得、半日ストの公務員共闘は14,000円(14.8%)を獲得している(21)。そこで官公労の組合が労戦戦線の統一の主導権を取るうえでも、より優位な交渉を取るうえでも「スト権を回復して民間並みになろう」というスローガンのもとに民間並みにストを打てる組合となることが目指された
(22)。 そこで次に、官公労の中の2つの有力な共闘組織である公務員共闘と公労協の関係について考えたい。
図表2 1973年の労働運動の状況参照:労働省1977『資料労働運動史 昭和48年』労務行政研究所より筆者作成
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 73

4-2 公務員共闘と公労協 1948年に人事院が発足し、公共企業体労等働関係法が成立したことで、官公労は次第に、三公社五現業を中心とした公労協と、国公と日教組と自治労の非現業を中心とした公務員共闘とに分かれることになる。これは最終的な労働交渉の調停の場が、公労協は公労委(公共企業体等労働委員会)、公務員共闘が人事院に分かれたためでもある。 したがって、官公労のなかでも人事院に対して交渉する公務員共闘と、労働協約締結権が認められ、公労委による裁定で交渉する公労協では条件が違うとともに、ストライキなどの実力行使による交渉の実現性が異なっていた。とくに、公労協は国労や全逓のように基盤産業ではないが、交通や郵便のインフラを止める交通ストを行なうことで民間単産に代わりうるパターンセッターとなっていた。そのため官公労のなかでも公労協に続くべきだと考えられていた。 図表2に戻ると1973年時点で、公務員共闘は約198万人の組合員がおり、その中で最大規模の単産が自治労(約107万人)であり、二番手が日教組(約59万人)であり、両者あわせて約166万人をしめ、日教組は公務員共闘の両翼の一方であった。しかも、それだけでなく組合員数の規模でいえば、公労協は約85万人であり、総評全体では約432万人であった(23)。公務員共闘は総評の構成員の半数近くをもしめるにも関わらず、労働運動を牽引できていないという問題があった。 73春闘直前の総評第45回臨時大会(2.26-27)で自治労の丸山康雄が「昨年の公労協の仲間が激しい七十二時間の闘いをかまえ、交通ゼネストという体制の中で、政府の干渉をはねのけながら闘った昨年の春闘の経験を目のあたりにみ、私どもはいまや春闘の単なるおつきあいではない、あるいはぶらさがりではないという心境に立ちながら、私どもは七三春闘に取り組んでいます」(24)と述べるように、ストを打てる産別組合となることは労働運動の全体の立場において、発言権を左右させる重要な問題であった。 先述したように労戦統一の話が進むなかで、民間と官公労のあいだの綱引きがあり、1972年の春闘を解説する特集号の中で、公労協が春闘の先頭に立って賃金相場の主導権を握ろうとすることに対して、総評の太田薫元議長(1958〜1970年)は次のように述べている。
74 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

「公労協のストライキは民間と違って一発大勝負の傾向を持っている。当然、政府を巻き込んで有利な条件をつくっておかなければならなくなる。だから、公労協単独で先行すると政府が容認できる範囲の賃上げにしかならない。民間の前にそんな賃金が出されるのは危険だ、ガイドポストにつながらないという保証があるのか」(25)。
太田は、あくまで民間が先頭にならなければ、公務員の賃金については政府交渉が必要となるために政府が考えているもの以上に要求が通らないのではないかと、民間先行で公労協が続いた方がよいと主張した。この競合関係のなかで公労協はイニシアチブを取るうえで、交通ストを切り札にして強いストを打ち、さらに公務員共闘との結合により、官公労が労働運動の全体の主導権を握ろうと考えていた。 公務員共闘は、官公労の一員として民間との春闘の一角をしめる。そして、官公労のなかでも公労協とともに労戦統一の右派的な展開に対抗して、総評のなかにおける主導権をとることが求められた。そこで次に人事院交渉を行なってきた公務員共闘について考えたい。
4-3 公務員共闘の到達 1966年から1975年まで労働省秘書官であった石井甲二は人事院勧告の完全実施を行なうことの意義について、次のように述べている。
「(1967年8月)現在の労働運動の流れをみて経済の成長=国民生活の安定に即応して、民間労組は著しく健全化の方向を辿っており、むしろ総評系労組は危機にさらされている。しかし、官公労組は依然として左翼的な姿勢を崩しておらず、公務員が政府批判の先頭に立つという特殊な形態をとっている。日本の労働運動の健全化の方向を支える経済的、社会的基盤が大きく前進しているにも拘らず、総評を中心とする日本の労働運動の姿勢が現実の労働者意識と遊離した形で低迷している基本的原因の一つはこの官公労組合のあり方である。そして、それに口実を与えている重要な要素の一つが長い間人事院勧告の完全実施を無視した政府の態度にあったことは否定し得ない」(26)。
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 75

労働省の秘書官として政府側に近い立場からも、人事院勧告の完全実施に積極的であったが、官公労の労働組合のあり方には制限を加えるべきであり、また、労働運動の再編する必要性があると考えていた。 ここには公務員共闘が抱えた、もう1つの問題があった。それは石井が指摘したように、人勧の完全実施は裏を返せば運動目標を失うことを意味していた。1970年に人勧の完全実施が実現され、1972年には実施時期が5月から4月となり、いよいよ人勧の問題はクリアにされ、次の運動目標への展開が必要であった。当時、公務員共闘の事務局次長であった山本興一(自治労)は交渉を述懐して「その時総裁(人事院総裁・佐藤達夫)が『山ちゃん、4月完全実施後は公務員共闘の運動目標がなくなるぜ』といわれたことが今でも耳にこびりついて離れない」と述べているように(27)、次の目標はスト権や団交権を認めるという根本的な目標、つまり、人勧体制の打破にならざるを得なかった。 自治労の書記長である安養寺俊親は、「最後に実施時期の四月という問題まで切ってしまえば、もう切るものがなくなってきたわけです。政府の側も切り離すものがなくなるわけですから、これからは必至で力で抵抗するしかないと思うのです。だから、これからは先はいよいよぎりぎりいっぱいの闘いになると思います」と述べている(28)。 しかしながら、スト権の問題は政治的な体制が変わらない限り、実現が困難な問題であった(29)。それを実現するためには公務員共闘は春闘の体制のなかでストライキを打ち、実力で訴えて政府側の譲歩を引き出していく必要があった。
4-4 公務員共闘の弱さ 一方で、春闘の一環のなかで政府交渉を行なうことの問題も指摘されていた。図表3にあるように、人事院との交渉は1960年の公務員共闘結成から本格的に行なわれるようになったが、人事院等へ動員をかけて交渉するだけで、1965年になるまでストライキを構えていなかった。この時は、人事院勧告が出された後に、予算が確定する時期にあわせて対政府交渉を行なうという戦術をとっていた。このことは公務員共闘の当初の戦術は、あくまで人事院の枠組みのなかでの交渉であったということである。
76 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

この戦術で1965年〜1969年にかけて人事院勧告の完全実施を求め、実施時期を10月から6月まで少しずつ早めさせ、1969年には人事院勧告前と勧告後にストライキを構えることで、いよいよ5月実施まで確約させることになった。 最後に4月実施を目指し、1971年を契機に運動を一歩進めて春闘の一環のなかで交渉することになる。ただし、公務員共闘内において自治労の安養寺と日教組の槇枝のあいだで、1970年の公務員共闘の会議で春闘のなかで闘うのか、秋闘で独自に闘うのかについて議論となった。結果的には、双方の意見をとり、過渡的に春闘と今まで公務員共闘が闘ってきた秋闘の両方でストなどの動員をかけることになった。 1972年の7月13日のスト中止を受けての座談会において、1970年の議論を踏まえて自治労の安養寺は、次のように述べた。
「今度、春闘にもっていたとしても、なんといっても公労協などが二四時間くらい汽車を止めたりする。そして民間のほうも三日間でもやるという状態のときに、一時間か二時間、仮に半日であっても、公務員の闘争の影は薄くなるわけですね。…やはり一歩遅れて公労協もやった、民間もだいたいすんだ、ではいったいわれわれ公務員を政府はどうしてくれるのかという迫り方のほうが弱いなりに実感があるのではないか」(30)。
安養寺は、春闘で統一した闘いをすることの意義を認めながらも、人事院体制を打破するというならば、①人事院に依存しない体制、②春闘での立場の確立、③地方公務員の個別交渉に力をつける必要がある、と指摘した。 一方で日教組の槇枝は、春闘に期待を寄せて「政府のお膝元の公務員だけは政府が何も回答せんがためにやりますよということになれば、これは仮に二時間以上であっても、ぜんぜん見る気もしないということにならないのではないか」と述べ(31)、春闘で共同行動を起こせば政府が出てこざるを得ない状況を作り出すとしていた。 春闘の一環のなかで闘うことが政府への圧力となるのか、あるいは力量がないなかで行なうことは埋没していってしまうのかについての逡巡があった。人事院交渉をしないということは、公務員共闘が民間や公労協と同じように闘っ
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 77

て交渉することを意味し、いままで良くも悪くも人事院の枠組みのなかで交渉することで守られていた部分がなくなる可能性があることも意味していた。 それでも日教組の中小路は、その意義を1973年の春闘直前の総評臨時大会で次のように述べている。
「前提として政府の態度が変更される、こういうことがない限り、私どもとしてはやはり七三春闘の中で、四月決戦段階に向けてのストライキ行動を配置した中で政府を引きずり出してくる、こういう闘いの基本路線が明確でなければ、単に政府との接触、あるいは交渉ということについて、この問題は解決しない、このように思うわけです。…この四月決戦段階というところに向けて、最大の闘いを集中をし、そこをヤマ場にして田中[角栄]を引きずり出してきて、みずから回答をさせる。スト権の問題についても、賃金引
図表3 人事院勧告の変遷と公務員共闘統一要求・戦術配置
年次人事院勧告の概要
実施時期 国会での主な決定内容
公務員共闘統一要求 戦術配置
勧告月日 平均基準内給与
平均アップ率・額
1960年 8月8日 ¥21,740 12.4%¥2,682 10月 勧告通り 一律� ¥3,000
1965年 8月13日 ¥36,640 7.2%¥2,651 9月 勧告通り 一律� ¥3,000
最賃� ¥12,000 10.22(中止)
1970年 8月14日 ¥62,500 12.67%¥8,022 5月 勧告通り
¥10,000以上最低� ¥8,000最賃� ¥30,000
7.10(中止)
1971年 8月13日 ¥71,915 11.74%¥8,578 5月 勧告通り
¥15,000以上最低� ¥10,000最賃� ¥37,000
5.207.15
1972年 8月15日 ¥82,045 10.68%¥8,907 4月 勧告通り
¥20,000以上最低� ¥14,000最賃� ¥45,000
5.197.13(中止)
1973年 8月9日 ¥92,290 15.39%¥14,493 4月 勧告通り ¥20,000以上
最賃� ¥50,0004.27(半日スト)12.4(中止)
1974年 7月26日 ¥120,165 18.62%¥21,385 4月 勧告通り ¥30,000以上
最賃� ¥70,0003.26(一時間スト)4.11(一日スト)
1975年 8月13日 ¥144,830 10.85%¥15,117 4月 勧告通り
¥30,000以上最賃日額� ¥2,800
5.9(中止)5.10(中止)
参照:�日本公務員労働組合共闘会議1990『公務員共闘30年の歩み』日本公務員労働組合共闘会議、「人事院勧告の変遷」より一部抜粋。
78 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

上げの問題についても回答をさせる、こういう闘いの構想を、この総評大会の中で明確にする必要があるのではないか」(32)。
中小路の指摘は、賃金問題とスト権の問題を解決するには、政治的な決着が必要であり、人事院でいくら交渉したとしても、結局のところ政府の了承がなければ問題は解決しないので、政治的な譲歩を引き出すような闘いが必要であるというものである。 春闘に参加することに慎重であった自治労の安養寺も、スト前には春闘への参加を容認していくことになる。というのも、第三次公務員制度審議会の委員として、労働権の問題を審議し、政府側との妥協を模索していたが、結局のところ公政審の議論も労働側の期待するところとはならなかった。さらに官公労は、どの単産もスト権の問題の裏に処分問題を抱えており、スト権の解決は、違法ストによって処分されていた組合員の実損回復の闘いであり、累積された実損を取り戻す必要があったからである。 安養寺は、1973年春闘の終わった後の11月には次のように述べている。
「政府の政経分離、公制審まちという方針を打破して、交渉の場に引き出し、多くの問題を持ちながらも合意文章を交換することに追い込んだのであって、一定の前進をかちとったものであるといえます。このたたかいは、初めて春闘に結集した公務員共闘に確信を与え、企業側の一発回答を大きく破り長期ストを覚悟してたたかった民間部門のたたかいなど、多くの無形の成果をかちとるうえで貢献しました。…[それでも処分者が出たことにふれ]…長期的にみれば労働者側に、結局は力関係による以外には、権利闘争前進のみちがないことを教訓として残したのです」(33)。
公務員共闘は春闘のなかで公務員共闘が埋没する恐れがあったとしても中央交渉を進めるうえで、春闘のなかで闘うことを選んでいく。それは公制審をはじめとする政府側との交渉において展望が開けなかったことで、労働運動の盛り上がりにより力関係を変えること、つまり、ストによる実力行使へと戦術が傾いていった。
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 79

4-5 分断と統合 しかしながら、当時の日教組の立場は公務員共闘のなかで難しい立場にも立たされていた。74年に成立することになる人確法によって教員の給料は10%上昇し、他の公務員との差別的な給与体系となり、日教組を公務員共闘のなかで浮かせることになった。公務員共闘賃専総会において、職種によらない統一の賃金体系を求めために調整を図ったが、「調整がむずしいのでわりきって双方を認めあうことにした」と曖昧なかたちで決着した(34)。 そこで、むしろ10%を引き上げは人勧体制を無視した賃金政策であるとして、批判した。総務長官との交渉において、政府は、賃金要求は人事院で解決する問題であると逃げるのに対して、「ではなぜ、組合側が要求もしないのに、政府は教員賃金を10%増も自らいいだしたのだ。また、それに基づいて人事院が配分しようとしているのは何なのか。政府がいくら人事院を云々しても、実際には、公務員賃金について、昨年、一昨年とも政府(総務長官)から回答を引き出している」と迫り、人事院への要求から政府への直接交渉へと重点を移していった(35)。統一的な賃金体系で官公労はまとまるつもりが、日教組自身が破り、統一した闘いという前提を揺るがしかねないために、政府との直接交渉で一挙に解決するという主張であったが、最終的な交渉の展望について運動の流れに依存し、どれだけの見通しがあったかは疑わしいものでもあった。 もちろん、公務員共闘は人事院体制を打破するために中央交渉が失敗しても、革新市政などの各地方自治体や担当官庁への直接交渉と合意を取りつけることで、勧告を放棄させて、民間の労働組合と同じような団体交渉権の確立を目指すという展望ももっていた。 しかし、この論理は単産ごとに創意あふれる交渉か、分断かで評価が分かれるものであり、公務員共闘内における統一した交渉に水をさすものであったといえる。日教組の交渉相手である文部省に比べ、自治労の交渉相手である自治省では、経済闘争以外での問題は多くなく、単独交渉の可能性が高かった。たとえば、自治労は自治大臣と定期的な会談を行なっており、対立するが一定の交渉を行なっていた。しかるに、日教組の場合、単独交渉の可能性が低く、単組ごとの地方教育委員会や地方人事委員会との交渉は、単組の狙い撃ちの危険性をともなっていた。
80 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

スト権奪還は、人事院と公労委に分かれた公務員共闘と公労協が同じ土俵に立ち、ストライキを使った労使交渉ができることを意味し、もし、それが成功すれば、民間が先行する労働運動全体の主導権が取れ展望が開けることを意味していた。当然、政府側は、分断工作を行ない、公務員共闘と公労協のあいだでは非現業と現業に分ける、そして、公務員共闘内では人確法による職種の給与体系を変えることによって日教組と自治労を分断しようとした。 スト権奪還としての権利問題は官公労を統合し、統一した労働運動を展開できる一方で、最終的な妥結する面においては、権利問題として最後まで闘い抜くのか、どこかの場面で妥結していき、賃上げと処分の緩和で譲歩していくのかの見通しがなければ、政治的な交渉で一挙に解決するのではなく、個別に切り崩されながら妥結するという問題をはらんでいたといえる。 日教組は、公務員共闘の最有力の単産として公務員共闘内での牽引役であり、そして、労戦統一問題を背後に公労協とともに官公労が統一して、春闘の一環のなかでの立場として闘うことが求められた。さらに、官公労の各単産はスト権などの労働基本権の確立が人事院や公制審で解決されないとなると、実力行使による解決しかないとスト権ストへ突き進んでいく。以上が、日教組が73春闘半日ストへと向かう政治的機会のありようである。 一方で、スト権の問題とは、つまるところ処分問題と表裏をなしており、最終的な交渉において、どのように統一した妥結をしていくのかの見通しがあったわけでなかった。そこで、次節で総評指導部と政府側との交渉をめぐっての合意と日教組の対応について検討する。
5 73春闘における総評の政府交渉と日教組の対応 5-1 総評運動における73春闘の概要 1973年における総評全体のイシューは、労働戦線統一と春闘であった。スト権ストは公務員系組合にとっては重要な課題であったものの、「スト権ストが、公労協のたたかいであっても、かならずしも総評全体のたたかいではなかった」(36)という指摘に明らかなように、日教組が対政府交渉の切り札と考えていた、スト権奪還・労働基本権の確立は民間労組を含めた総評全体の関心を集める要求とはいえなかったことは、総評内の公務員系組合である日教組の位置づ
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 81

けを検証する上でも重要な前提である。 またスト権ストは、日教組の加盟する公務員共闘ではなく、現業系組合である公労協(公共企業体等労働組合協議会、国労、全逓、全電通、全林野、動労、全専売、全印刷、全造幣、アル専)が主導してきた経緯がある。 とくに1973年から1974年にかけて田中内閣が弱体化し、三木内閣が発足したことにより、「公社・現業自体の労使関係と政治状況の両面から短期決戦的にスト権問題を決着させようという意向が公労協から強く示されるようになっていた」(37)。公労協主導のスト権奪還・労働基本権確立闘争の強化という状況のなかで、73春闘に先だって、1973年2月10日に最初のスト権ストが開始され、国労、全電通、全逓が拠点半日ストを行なうなど現業系の公労協の大胆なストライキ戦術が展開された。これに対し日教組を含む公務員共闘は30分前後のストや職場集会など影響の限定されたストライキにすぎなかった(38)。 このような状況のなかで、1973年4月末のスト権ストが構えられ、ストを中止させるために政府と総評が取り交わした合意文書が「七項目合意」である。具体的には1973年4月27日に、総評の市川議長、大木事務局長等と内閣官房副長官、労働大臣等政府との直接交渉によって労働基本権問題、処分問題等について明文化した合意文書である。 その内容は「①労働基本権問題については公制審においてすみやかなる結論が出されることを期待し、答申が出た場合はこれを尊重する、②政府は労使関係の正常化に努力する、③ILOの勧告、結社の自由委の報告等に対しては理解し、慎重に対処する、④処分については公正慎重に行う、⑤過去の処分にともなう昇給延伸の回復問題については引き続き協議する、⑥労働、厚生、総務等関係大臣との間の協議の結果については当然尊重する、⑦以上の合意を機にストはただちに中止する」というものであった(39)。この文書の実行を前提に、ストは中止された。 しかし、「七項目合意」のうち「④処分については公正慎重に行う」については、8月にすでに国鉄による処分が下され、実現されなかった。国労・動労処分に対し、大木事務局長は「大会中四回にわたって山下官房副長官と会談し、「七項目合意」にもとづき処分の一ヶ月の延期について話し合ったが不調に終わった」(40)。
82 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

大木自身も「七項目合意」については、総評幹事会総括の文言を引用し次のような位置づけを行なっている。「七項目合意事項は、内容的に不満な点が多いし、継続交渉となった部分もある。…七項目合意事項はあくまで四月末時点のものである。むしろわれわれが重視すべきことは、この大統一ストを背景としてきりひらいた政府との交渉の場を足場として、七項目を実際に実行させることをはじめ、今後いかに要求実現をはかっていくかにある」(大木1976,�p.104)。 スト権・労働基本権奪還問題については「①労働基本権問題については公制審においてすみやかなる結論が出されることを期待し、答申が出た場合はこれを尊重する」とされており、実質的には公制審に責任が転嫁されたが、公制審は1973年9月の「官公労働関係の基本に関する事項」の最終報告の中で、3公社5現業職員のスト権については①全面・一律禁止、②国民生活への影響の少ない分野での部分的承認、③全部門への条件付き付与の三論が併記されるにとどまっていた(41)。 このように73春闘の総評対政府交渉の成果としての「七項目合意」については、その実効性に限界があったということが把握できる。
5-2 73春闘における日教組要求 さて73春闘において日教組はどのような対政府交渉の要求を行なっていたのであろうか。またその要求は総評の73春闘の全体要求のなかでいかなる位置づけにあったのだろうか。 日教組が、73春闘に関して具体的な要求を行なったのは総評第45回臨時大会
(1973.2.26-27)である。中小路書記長は、スト権奪還闘争について、次のような主張を行なっている。教員を対象とした人材確保法案が「教員給与10%引き上げなどというのは、教員に対してはこんりんざいストライキ権を与えないという攻撃にほかならないわけです」との見解のもとで、「73春闘で突破口を切り開いて、74春闘で決着をつける」ために、政府交渉をより確実に行う必要性を中小路は主張している(42)。とくに、処分政策、賃上げ、スト権について
「四月決戦段階というところに向けて、最大の闘いを集中しそこをヤマ場にして田中を引きずり出してきて、自ら回答をさせる。スト権の問題についても、
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 83

賃金引上げの問題についても回答をさせる、こういう闘いの構想を、この総評大会の中では明確にする必要があるのではないか」と主張している(43)。 その背景には、「この春闘に参加する公務員共闘、特に日教組としましても何回もまだストライキを打つ力量、こういうものをまだたくわえておりません」という日教組の闘争力の弱さがある(44)。ストライキに関して、国労や動労と比較して、それほど積極的な姿勢を持たない日教組がスト参加するためには、総評の対政府交渉の戦術をより明確にしてもらい、それで都道府県の単組や組合員の説得材料にする必要があったためと考えられる。 これらの日教組の主張に対して、大木事務局長はスト権問題については、他の代議員からの質問も含め回答を行なっている。公務員制度審議会での対応を含め「おそらく本年の後半から来年にかけて公制審の答申を受けた立場からすれば、法改正問題についてわれわれの闘争を一段とエスカレートさせる、そのような段階を迎えると考えておりまするから、いろいろ意見がございましょうけれども、私たちといたしましては、現実的に扱っている立場からすれば、むしろ本年の春闘の後段の段階から本年の秋、あるいは来年の国会、このような問題の中で結果的には、スト権奪還の関係法案の問題が、相当大きな論争を呼ぶ段階を迎えるのではないかと考えております」と見通しが述べられている(45)。 ただしこれは立法戦術としての闘争方針が述べられているのであって、中小路書記長からの質問にあった春闘中での政府交渉に関する戦術ではない。政府交渉戦術については、大木事務局長は長時間ストこそが政府交渉の足がかりをつくるという立場を表明している。「国労や動労の方や、公労協、官公労全体が公務員共闘の方にもきびしいことを申し上げているのですが、朝から1時間か2時間のストライキではとても政府は出てきません。もし4月の下旬に決着をつけたいということならば、なぜ四月の中旬に同じ半日のストライキということにお願いできないのでしょうかと私はきびしくお願いしているのです」と熱弁している(46)。 本論の課題である総評における日教組の位置づけでいえば、1時間、2時間単位のストライキでは問題にならないレベルということで、ストライキという意味での闘争力でいえば相当に低い評価しか与えられていないことが明確になる。
84 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

また具体的な対政府交渉については、4月中旬の民間スト、4月下旬に「公労協の諸君は48時間のストライキをぶつ、私鉄の諸君がまさしく公労協でいったんのストライキをぶつ、公務員共闘の諸君もそのときに具体的な金額がどのように出るかというような問題等について、私たちはたいへんなげたを預けるわけでありますけれども、最大限の本年春闘の戦術を行使していただく。そういった中でこそ、私はまさしく対政府交渉の展開も可能だと思う」と述べている(47)。ただしどの時点で政府側の誰と交渉するなどの具体的な総評大会においてはされておらず、中小路書記長が要求した田中総理大臣あるいは人確法に関しての文部大臣等との交渉についても言及されていない。 つまり73春闘における総評内での日教組は、ストライキ戦術に弱い組合として相対的に低い位置づけしか与えられておらず、また対政府交渉に関しても、教育要求等含め一通りの位置づけは与えられたものの、交渉相手としての文部省をどのように位置づけるかという問題については公式の場での回答が得られていない状況にあったといえる。
5-3 73春闘後の総評の中での日教組要求の位置づけ さて73春闘後の日教組は国労や動労に先行し文部省が厳重処分の方針を打ち出すなど、他労組と比較しても厳しい結果となった。処分問題に関する総評への日教組の要求は、総評拡大評議員会、同第46回定期大会で確認できる。 73春闘後最初となる第5回拡大評議員会では、中小路日教組書記長は処分問題について、早くも「七項目合意」の課題を指摘している。「文部省が、各県の人事主管課長会議を招集をしまして、その席上で日教組の4・27半日ストライキに対して、いままでにかってないほどの高姿勢で、厳重な処分をすべきである、こういう指示を具体的に始めているわけです」(48)。つまり、国労や動労への処分よりも先に、日教組への処分方針が文部省より明確化されているという問題が存在した。この文部省の姿勢が73春闘スト中止における総評との合意に対する「政府の違背事項という形で、徹底的に追及をする行動を強化していかなければならないのではないか」と総評の見解を質している(49)。 また政府に対する処分問題の追求について、73春闘のスト中止のさいに交わされた非公式の合意文書(いわゆる「念書」)(50)を材料にすべきではないか、
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 85

と中小路日教組書記長が大木総評事務局長に迫っている。「いわゆる念書等の問題についても、これを国民の前に明らかにする、こういう私たちの基本的な姿勢をもって政府に対してそういう状況を起こさせないということを私は徹底的に追及をしていくことが必要ではないか」(51)。 これに対し大木総評事務局長は、73春闘における「七項目合意」について
「不十分だ」ということを認めたものの、非公式文書(いわゆる「念書」)を材料に政府交渉を強化すべきではないかという中小路の主張については「みなさんの口からは念書ということばができる。私の口からこれについては一切ノーコメント」と(52)、中小路が要求した念書の公表や、政府への追及などについては直接の回答を行っておらず、日教組の置かれた状況に対しては相当に物足りない内容であったといえよう。 また1973年7月30日〜8月3日の総評第46回大会で、中小路日教組書記長は、総評との合意を履行しなかった政府に対して、総評から経緯を明らかにするように求めている。 くわえてスト権についても「日教組などに対しては、使用者側委員のいろいろな公務員制度審議会における討論の中、意見の中でも二重も三重もしぼりをかけて、絶対スト権は与えない、こういうことを相手側は策動をしております。この前文部大臣と交渉いたしましたが、その点についてはもう明確です」と日教組の立場の特殊性を強調している(53)。 そのために、スト権における現業と非現業との分断政策について「どう総評が意思統一をするかという問題」が「一点の弱点」として、スト権の分断政策をどのように処理するのかの姿勢を質している(54)。 これに対し大木事務局長は、「中小路さんのおっしゃった問題についてなのです。私自身公制審が官公労働者についてスト権を許可するかどうか、たいへんにむずかしい局面だと率直に思います。…全体の労働者の問題として、幹事会側としますれば、官公労働者全部のスト権の問題の解決を目指して、公制審答申の、あるいは見解表明等があった場合にも対処してまいりましょう」(55)と回答を行なうにとどめている。 ただし第1節で述べたようにスト戦術のなかで闘争力が高く、またスト権の確立が比較的実現しやすい現業部門に73および74春闘でのプライオリティが置
86 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

かれていたことも確かである。中小路日教組書記長に対する大木総評事務局長の回答は、総評としての全体姿勢を説明したものにすぎず、文部大臣交渉などへの言及はない。あえてシンプルにまとめるならば、ストライキに強い現業系の公労協中心の73春闘のなかで、ストライキに弱い日教組の位置づけは低いものであったという見取り図を描くことが可能であろう。
6 文部省に対する日教組の交渉:公式ルートと非公式ルート6-1 「七項目合意」を無視した文部省の行動 第5節で確認したように、「七項目合意」および(いわゆる)「念書」の、総評による取り扱い方、また対政府交渉の仕方に対して、日教組は大きな不満を抱いていた。なぜなら、「七項目合意」は、労働基本権問題の具体的解決については第三次公制審に譲っており」(自治労運動史編集員会1979,�p.642)、「五項目念書」には「過去の処分について恣意的差別を行なわない」という日教組にとっては重要な文言が入っていたのに、これを盾に交渉はしていかないと大木事務局長は述べたからである。とはいえ、合意の第⑤項目すなわち、過去の処分問題については引き続き協議することについては、総評と政府代表は合意したと解釈して、日教組は文部省との交渉に臨んでいった。 だが、日教組はすでに、大いなる不信感を抱いていた。というのも、1972年11月の、ILOのジェンクス事務総長の提案に従って、12月から翌年2月にかけて断続的に行なわれた政府代表と総評との協議において、「文部省は依然として処分問題の話し合いを拒否しているではないか」と総評代表が問い詰めたとき、文部省側は「事務局レベルでは交渉している」と述べたのだが、この「交渉」は日教組にとっては、曖昧な言い逃れにしか思えなかったからである(56)。 日教組にすれば案の定というべきか、文部省は73春闘後、「七項目合意」を無視した行動を繰り返していく。5月15日開催の人事主管課長会議において文部省は、各県の人事課長に、「七項目合意」は文部省には無関係であるから、4.27スト強行処分を行なうよう指導する(57)。3日後の5月18日、日教組闘争本部は岩間初中局長と鈴木地方課長らを質す。「この合意七項目は文部省に完全に関係がない、こういう主張を当初はしておりましたけれども、私たちの正当な追及の前にだんだんと後退し、最終的には、もう一ぺん大臣との協議、ある
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 87

いは政府部内における協議を行なわなければ、日教組との対立している見解について回答することができない、こういうことを回答するに至りました。そして後日、日教組に対して、回答を正式に行ないたいということが、岩間初中局長より提起されました」(58)。 その回答は、5月28日になされる。中小路書記長によれば、岩間初中局長は、「合意は尊重する、ただし…(第)五項目、すなわち過去の処分については、今後引き続き協議するという項目でありますけれども、この『引き続き協議する』という内容は、直ちに県教委と県教組との協議を義務づけるものではないというふうに述べるにとどまった…わけであります」(59)。どういう意味かと日教組が迫ると、鈴木地方課長がジュネーブに出張中なのでこれ以上言えない、とのことだった。日教組にとっては時間稼ぎとしか思えないが、鈴木地方課長が帰国してから、さらに追及するという手段を取らざるを得ない。 日教組は、初中局長と地方課長レベルの交渉と並行して、槇枝委員長と奥野文部大臣とのトップ会談をも企図していた。6月に申し入れたこの会談は、7月16日に実現したが、議論に妥協の余地は見出されずに終わる。実は9月10日にも第2回会談が行なわれたが、議論は平行線をたどるのみであった。奥野文部大臣は、過去の処分問題について日教組と協議する正当性も必要性も認めていない。中小路書記長によれば、奥野文部大臣は、スト続行中の4.27午前零時に開かれた関係閣僚会議で、第五項目は、公立の教員など地方公務員は関係がないということで了解をとりつけた、と周囲に述べていた(60)。 トップの文部大臣がかようなスタンスであったことを背景に、8月28日には、福岡県教委が4.27ストで大量処分を発令する(61)。停職11、減給181、戒告18,581で、計18,773にも上った。たしかに、8〜9月に発令された国労・動労の14万人と比べれば僅かといえるかもしれないが、国労・動労のそれはほとんどが訓告などで、実害のある処分は少なかったのである。したがって日教組は、これは狙い撃ちだと認識しよう。しかも、春闘共闘委と政府との口頭確認
(大木・山下会談)のなかで、9月3日の第三次公制審解散までは処分をしない、と言われたのだと了解している日教組に、対政府不信の火が燃え盛って当然であろう(62)。この火に油を注ぐかのように、8月30日の全国都道府県教育委員長・教育長会議で、奥野文部大臣は「スト参加者を処分した福岡県教委を
88 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

独りぽっちにするな」と発言した(63)。
6-2 対文部省交渉の非公式ルート 以上のように、文部大臣、初中局長、地方課長といった公式ルートによる対文部省交渉は、一向に埒が空かなかった。だがこのままでは、1966.10.21ストや1969.11.13ストなどの大規模処分に、73春闘半日ストによる大量処分がさらに積み重なっていく。そこで日教組は、交渉の非公式ルートを模索した。前出の髙山三雄・弾圧対策部長は次のように述べる。
「文部大臣と直接交渉はできないけども、裏口で随分斡旋してくれたんだよ。で、初中局とは随分話をした覚えがある。そのときに文部省は、『救援資金の関係で絶対に和解をしてはいけない』ということだったんだけども、表向きは反対をしながら、裏に回って応援してくれたことがある…各県[教委]は和解をしたいんだけども、文部省が反対だということでみんな遠慮していたんだよ。それを裏へ回ってOKをしてくれたのは、初中局の岩間さんなんかだったな。その頃、それで随分と和解が成り立ったんだよ。…その大きな原動力は、やっぱり田中ピンさん[田中一郎、当時総務部長]だ。田中ピンさんが国会対策委員長[委員長という職はなく、国会担当]で…随分と骨を折って、文部省の岩間さんなんかを説得して、表向きは反対だけども、各県が和解をし始めた頃にはほとんど知らん顔をしてくれたんだよ。だから、それでずっと和解が進んだんだ」
田中一郎国会担当は、国会で一番出入りしていた山口鶴雄衆議院議員(群馬出身の日政連議員、社会党内では江田三郎派)と小野明参議院議員(福岡出身の日政連議員、社会党内では十日会派)に依頼して、岩間初中局長にはたらきかけてもらったのである。岩間初中局長は、「最初はほとんど会うてくれなかったけどね。日教組とはもう交渉もしなければ、話もしないと。『交渉は要らないから、話だけ聞いてくれ』ということで、山鶴さんと小野さんなんかを通してやってもらったから、裏で話をしたってことだな」。「山鶴さんは、頼みの綱だったんだよ。で、また、山鶴さんはよくやってくれたし、力もあった」。
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 89

このような、髙山三雄→田中一郎→山口鶴雄・小野明→岩間英太郎というルートによって交渉の場を確保した後は、髙山氏は、岩間初中局長と鈴木地方課長と、1対2で会って話し合うようになる。当時問題だったのは、文部省が日教組対策として各県に付与していた、使途自由の交付金である。「『日教組と和解をしたら、交付金は出せません』という攻撃を、初中局はやったんだ…だから、僕は、岩間さんとそれを話をしたときに、そのことで何回も交渉をしたんだよ」。つまり、交付金を餌に日教組との和解を阻止するのはやめてほしい、ということである。 結果として岩間初中局長は、この要求を受け入れる。「『面と向かって、文部省は、OKするわけにはいかない。だけど、止めません』という話で、最終的に岩間さんと話をしたことがある。だから、[各県教委が]伺いを立てたらば、文部省は……『自由にやんなさい』と」いうニュアンスを漂わせた。各県教委が文部省に伺いを立てると、「岩間さんがほとんど無視した[=問題視していないような気配を見せた]んだね。聞かないような格好で、それでもう和解が進んでいったというような気がしますね」。
6-3 非公式ルートによる交渉の各県への効果 Thurston(1973)が指摘するように、中央レベルでは熱く闘われるイデオロギー闘争は、地域レベルでは薄まって、より実質的な課題をめぐる交渉が、県教委と県教組とのあいだでなされる傾向がある。髙山氏の「各県[教委]は和解をしたいんだけども、文部省が反対だということでみんな遠慮していた」という言明は、これに対応する。つまり、いつまでも強硬処分を出し続け、昇給延伸が長引いて、非平和的状態が続いていくのは、地域の教育行政・教育実践にとってマイナスである。地公法に基づく一般行政処分が永久に続くというのも、行政法の理論面から考えても不当であろう。 ただし、イデオロギー闘争は地域レベルでは薄まるというのは、一般的な傾向にすぎないことに、注意しなければならない。「それでもう和解が進んでいった」といっても、そうなったのは少数の県であり、進まない県の方が多かったのである(64)。つまり、初中局が各県での和解交渉を黙認したとしても、その成否は、各県教委と各県教組との関係性に左右された。この関係性に影響
90 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

を及ぼしていたのは、ひとつには県教組のイデオロギーないし態度、いまひとつには自民党強硬派のイデオロギーないし態度である。 第3節で述べたように、1969.11.13ストへの行政処分は、日教組の資金繰りを根本的に変えてしまった。そこで日教組にとっては、昇給延伸を止めることが、それまでにも増して重要になった。それには、裁判闘争で処分撤回を勝ち取る(「非があるのは県教委側だ」)など真正面から対峙する方法だけでは不充分だ。県教委と県教組が互いの言い分とを認めて譲り合う「和解」もまた、必要である。しかしながら、この和解に抵抗感を示す県教組が一定数存在した。槇枝書記長は第81回中央委員会(1970.9.24-25)で、「精神主義的になり、処分されたことに満足感を持っておるということであってはならない」と戒めている(65)。この傾向は、1970年代序盤を通じてなかなか変化せず、それを裏付けることに、髙山三雄氏は、「裁判闘争を通して、あくまでも公務員のストライキ権を奪還をするというところに重点を置いて」いたため、「この頃は『和解』とか『実損回復』とかいう言葉は、日教組内部ではかなり禁句だったね」と述べている。和解の実績を上げた県が幾つかあったにもかかわらず、それは必ずしも日教組全体の方向性としては定着しなかった。 他方で自民党強硬派は、保科幹事長が各県連への通達で、和解には絶対応じるなと指導していた。それゆえ、自民党が優勢な地方議会では、たとえ県教委が柔軟姿勢を見せていたとしても、和解推進には困難が大きかった。たとえば福岡の代議員は、第80回中央委員会(1970.9.24-25)で、「団体交渉で不当処分問題が今日撤回するような甘っちょろいもんじゃないということも…みんなわかっている…教育委員長の自宅に連日五日間なり、デモなり、いろいろ抗議をしていって、やっと…交渉の場が出てくる」と指摘している(66)。 県教組および自民党強硬派のイデオロギーないし態度は、以上のように、各県教委と各県教組との関係性を左右した。したがって、初中局が各県での和解交渉を黙認したことの、県レベルでの交渉に対する効果は、一定程度に限られていた、と言えよう。
7 結論と今後の課題 日教組が、73春闘半日ストをいかに迎え闘い、その結果何がもたらされたの
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 91

か。本論はこの問いを、1970〜73年の期間において、日教組内部に加えて、公務員共闘や総評といった労働界の動向をも対象としつつ解明した。日教組のストライキという集合行為は、当時の労働界での位置や他労組の在り方・動向のなかで形成されてきた。それゆえ本論は、先行研究では手薄であった政治過程に踏み込んだ(67)。別言すれば、自民党・文部省対教育運動という図式ではなく、多元主義的な図式を用いたのである。主な知見は以下4点に整理される。 第1に、1969.11.13ストへの行政処分は、日教組の資金繰りを根本的に変えてしまい、救援資金と闘争資金の大幅値上げがなされたが、1974.4.11弾圧以前は、主流左派/主流派/反主流派のあいだでは、救援・闘争資金問題はクリティカルな争点にはなっていなかった。反主流派も値上げにはむしろ賛成であった。勝ち負けいずれの見込みも立ちにくいからこそ、日教組はストを通じたスト権奪還へと誘われたのであり、ストを止めることはその非合理性を認めたことになり、裁判闘争も処分撤回闘争にも負けてしまうからである(第3節)。 第2に、日教組は公務員共闘の最有力単産として公務員共闘内での牽引役であり、労戦統一問題を背後に公労協とともに官公労が統一して、春闘の一環のなかでの立場として闘うことが求められた。さらに、スト権の問題とは、つまるところ処分問題と表裏をなしており、官公労の各単産はスト権などの労働基本権の確立が人事院や公制審で解決されないとなると、実力行使により一挙に解決するしかないとスト権ストへ突き進んでいく(第4節)。 第3に、総評における日教組の位置は、スト戦術の弱さゆえに相対的に低く、73春闘では対政府交渉に文部省を位置づけるという総評方針を明確な要求や方針を引き出すことができていない。その一方で、文部省は日教組を、73春闘の成果とされる「七項目合意」の中で、「処分については公正慎重に行う」という条項の対象外と解釈し、都道府県教育委員会に対し人事処分について厳しい姿勢で臨む方針を通達するなど、厳しい結果となった。この理由としては、教員組合であるがゆえの要求のわかりづらさという困難を抱えていることも作用している。すなわち、日教組は教員組合という独自性に由来する要求のわかりづらさ、スト戦術の弱さという二重の要因により、73春闘での総評における位置は低かったといえるのである(第5節)。
92 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

第4に、文部省は「七項目合意」を無視し続け、和解は不可という指導を各県に対して続ける。日教組は、日政連議員を通じた非公式ルートによって、初中局長から和解推進を黙認するという態度を引き出した。だが、自民党強硬派および少なからぬ県教組の対決的姿勢によって、その効果は限られていた(第6節)。 以上をまとめよう。Tarrow(1998=2006)の政治的機会構造の概念を援用すれば、日教組の73春闘半日ストが生じるには、制度的アクセスの開放、影響力のある同盟者の存在、国家の抑圧能力の変動といった、状況依存的な要因などがはたらいた。財政的に非常に大きな無理をして、日教組としては大規模なストを構えたものの、総評・春闘共闘委は4.27の対中央政府交渉を公労協の利害を優先するかたちで行ない続けた。大木総評事務局長との交渉には、山下官房副長官という「準トップ級」が対応したことからも推察されようが、そこでの合意事項が文部省に反映されることは、少なくとも公式的にはなかったのである。 日教組が政府と交渉したテーマは、スト権や処分問題など労働基本権に関わるものと、労働条件や教員定数など教育行政に直結したものの2つに大別されようが、文部省が交渉に応じ対応する姿勢を見せたのは後者のみであった。これには、西岡武夫や藤波孝生といった自民党文教族が、人確法や主任制導入に注力していたことも関係しているだろう。いずれにせよ日教組は、両者の対応にコストを割かねばならなかった。 日教組が、その組織規模・資金力が当てにされたほどには総評内では高い位置が与えられていなかったとしても、総評が「影響力のある同盟者」であることに変わりはなく、したがって総評が、74春闘で労働基本権問題に決着をつけるべく、より大きなストを構えんとしているなかでは、日教組は歩調を合わせて、半日からさらに進んで全一日のストを目標に掲げざるを得なかったといえる。ふり返ればこの姿勢は、1973年頃に文部省とのあいだで、ある程度生じていた和解の雰囲気を吹き飛ばしてしまったのかもしれない。 73春闘半日ストのあと日教組は、なかなか進捗しない処分撤回あるいは和解
(したがって財政問題)を引き続き抱えつつ、反主流派のストにおける保護要員配置や、総評・公務員共闘における劣位といった問題に対処していかねばな
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 93

らなかった。そのプロセスでは何が進行していたのか。74春闘での全一日ストはどのように迎えられ闘われ、何を帰結したのか。別稿で論じたい。
[注](1)本論文は、平成25〜27年度・日本学術振興会科学研究費補助金研究・基
盤研究(A)・広田照幸研究代表「戦後日本における教育労働運動と社会・教育システムの変容との相互作用に関する研究」の成果の一部であり、日教組所蔵資料の利用は、同研究会と日教組のあいだで取り交わされた協定書・覚え書に基づく。
(2)筒井(2014)では、政治的機会構造論そのものを援用してはいないが、それと同様の発想に立って分析している。したがって、ここで「本論も」と表現している。
(3)本論文の分担は以下のとおりである。筒井美紀:第1,2,3,6,7節。長嶺宏作:第4節。末冨芳:第5節。
(4)日教組第81回中央委員会議事録、p.239.(5)日教組第84回中央委員会議事録、p.84.(6)日教組第80回中央委員会議事録、p.88.(7)この委員会は、1961年の第23回定期大会で設置が決定された。日教組中
執と各県教組代表者1名からなり、日教組本部・県・支部・分会の組織機構および運営、各級機関の専従役員及び組合書記の問題について検討を行なってきた。
(8)日教組第80回中央委員会議事録、p.420.(9)日教組第80回中央委員会議事録、p.211.(10)日教組第80回中央委員会議事録、p.408.�次の引用も同様。(11)日教組第81回中央委員会議事録、pp.237-238.(12)日教組第81回中央委員会議事録、p.302.(13)日教組第81回中央委員会議事録、pp.283-287.(14)日教組第81回中央委員会議事録、p.373.(15)髙山氏はまた、「僕は、こんなこと[ストの積み重ねによるスト権の奪
還]ではうまくないなというような思いをした覚えがあるな。後半[4.11以降]は、スト権奪還なんていうのは公務員制度審議会で議論すればいいことであって、スト権奪還のためにストライキをやるなんていう
94 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

のはばかばかしいことだなというように思い始めた。前半[4.11以前]はそうじゃなかったけどね」とも述べている。
(16)ここに挙げた5要素は、流動的ないし状況依存的なものであり、より正確にいえば、Tarrowは、より安定的な側面も存在する、と述べる。それらは、国家の強さ、[運動体など]挑戦者に対する戦略、抑圧と社会統制、の3つである(同書、第5章)。
(17)1971.3.23最高裁、福岡県教組事件と佐賀県教組事件に全員無罪判決、1971.8.10佐賀地裁、佐賀教組事件の行政処分無効確認請求に勝訴判決、1971.10.15東京地裁、都教組勤評事件(十割休暇闘争)の懲戒処分を取り消し、など。
(18)第83回中央委員会議事録、pp.62-63.(19)労働法学者の本多淳亮は、「昇給延伸は、一時的な減給や罰金以上の苛
酷な処分だ…それはもはやストにたいする処分というよりも、団結を攪乱し組織を破壊することをねらった不当労働行為性の強い処分」であるから「絶対に許せないのである」と指摘している(本多1974)。この指摘を踏まえれば、「損失の脅威」とは、団結権の侵害をとおした組織破壊のことを意味する。
(20)ものがたり戦後労働運動史刊行委員会編(2000).(21)もちろん公務員の給料は民間の平均賃金に準ずるため、民間の給与水
準が一定程度高くなるのは当然であるが、民間の賃金にぶら下がっているという負い目を官公労は持っていた。そのために人勧体制を打破した
「本格的な賃金闘争」を行なうことで、官公労が主導権をもった労働運動のあり方が求められていた。水野秋(2002b)p.194.
(22)同上、p.191.(23)労働省(1977)pp.758-781.(24)日本労働組合総評議会『第45回 臨時大会速記録』pp.15-16.(25)日本評論社編(1972)pp.98-101.(26)石井甲二(1998)pp.304-305.(27)日本公務員労働組合共闘会議(1990).(28)早川�征一郎�他(1972.7)p.15.(29)戸木田嘉久(2003)pp.116-121.(30)早川�征一郎�他(1972.7)pp.18-19.
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 95

(31)同上、p.20.(32)日本労働組合総評議会『第45回 臨時大会速記録』p.4.(33)安養寺俊親(1973.11)pp.29-33.(34)公務員共闘会議(1973.2.13)『公務員共闘速報』No.367.(35)公務員共闘会議(1973.3.21)『公務員共闘速報』No.368.(36)『総評40年史』第1巻、p.580.(37)『総評40年史』第1巻、p.724.(38)『総評40年史』第1巻、p.724.(39)『総評40年史』第1巻、p.557.(40)『総評40年史』第1巻、p.560.(41)『総評40年史』第1巻、p.725.(42)総評第45回臨時大会速記録・2日目、p.3.(43)総評第45回臨時大会速記録・2日目、p.5.(44)総評第45回臨時大会速記録・2日目、p.5.(45)総評第45回臨時大会速記録・2日目、p.51.(46)総評第45回臨時大会速記録・2日目、pp.57-58.(47)総評第45回臨時大会速記録・2日目、p.63.(48)総評第5回拡大評議員会議事録、p.35.(49)総評第5回拡大評議員会議事録、p.35.(50)大木総評事務局長と山下官房副長官とのあいだに交わされたメモが、
「念書」あるいは「五項目念書」と呼ばれている。これについては末冨が別稿で論じる予定である。
(51)総評第5回拡大評議員会議事録、p.36.(52)総評第5回拡大評議員会議事録、pp.49-50.(53)総評第46回定期大会速記録・第3日、p.27.(54)総評第46回定期大会速記録・第3日、pp.27-28.(55)総評第46回定期大会速記録・第3日、pp.34-35.(56)日教組第83回中央委員会議事録、pp.84-85。中小路書記長の説明。(57)日教組第83回中央委員会議事録、pp.81-82。中小路書記長の説明。(58)日教組第83回中央委員会議事録、pp.81-82。中小路書記長の説明。(59)日教組第83回中央委員会議事録、pp.81-82。中小路書記長の説明。(60)日教組第83回中央委員会議事録、pp.84-85。中小路書記長の説明。
96 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

(61)当時の福岡県知事は亀井光。1967年から83年までの4期を勤めた。内務省を経て、労働省労働基準局長、労政局長などを歴任した。福岡県知事時代は県職労や教組に対して強硬姿勢で臨んだ(福岡県教職員組合1995)。
(62)日教組第83回中央委員会議事録、p.163。中小路書記長の説明。(63)『福岡県教組40年史�第2分冊』p.653.(64)和解が進んだ県は、岩手、大分、山形、大阪などであり、中央委員会
で適宜その報告がなされている。(65)日教組第81回中央委員会議事録、p.38.(66)このような、各県連をとおした自民党の強硬姿勢は、1995年の「歴史
的和解」によって大きな変化を迎える。渡久山長輝氏(元日教組書記長、1994-1996年)は2015年2月4日のインタビューで、「自民党とか文部省は反対だったの。本当に反対だったけども、その指示は必ずしも各県までいかなかった。逆に石川県は、森さんが自民党の幹事長で和解に応じたんだから…ということは、石川とか、各県でうまくいっているところは、処分をしていくことの意味がだんだんなくなった。それよりは和解をして、教育現場にこれ以上混乱を作らないほうがいいだろうというような考え方がだんだん出てきていましたね」と語った。
(67)他労組ということでは、同盟(および民社党)の動向に関する解明も不可欠である。同盟(および民社党)は、ストは違法だから厳重処分は当然であるというスタンスであったため、政府・自民党の動きに棹をさしたからである。『同盟新聞』といった資料には、日録的な行動記録が多数記されているので、その分析を今後の課題としたい。
[引用文献]安養寺俊親1973.11「スト権奪還春闘―その課題と展望」『賃金と社会保障』労働
旬報社、No.638,�pp.29-33Duke,�Benjamin�C.�1973�Japan’s Militant Teachers: A History of the Left-wing Teachers’
Movement,�University�Press�of�Hawaii.�『日本の戦闘的教師たち:外人研究者に語られた日教組の闘争三十年』市川博訳、1976 教育開発研究所。
Eisinger,�Peter.�K.�1973�“The�Conditions�of�Protest�Behavior�in�American�Cites,”�American Political Science Review�67,�pp.11-28.
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 97

福岡県教職員組合1995『福岡県教組40年史�第二分冊』葦書房早川�征一郎�他1972.7「《座談会》人勧体制と公務員労働組合」『賃金と社会保障』
(労働旬報社)No.605,�pp.6-36本多淳亮1974「団結権と職場の権利闘争」片岡昇・青木宗也・籾井常喜・中山和
久・本多淳亮著『スト権奪還の理論』労働旬報社石井甲二1998『労働省ものがたり:昭和四十年代初頭』労働基準調査会、pp.304-
305.公共企業体等労働組合協議会1978『公労協スト権奪還闘争史』イワキ出版戸木田嘉久2003『労働運動の理論発展史:戦後日本の歴史的教訓』新日本出版槇枝元文1976『官公労働運動――労働運動の再構築と賃金・スト権闘争』労働旬
報社槇枝元文2008『槇枝元文回想録――教育・労働運動に生きて』アドバンテージ
サーバー御厨貴2011『オーラル・ヒストリー :現代史のための口述記録』中央公論新社水野秋2002a『太田薫とその時代:「総評」労働運動の栄光と敗退(上)』同盟出
版サービス水野秋2002b『太田薫とその時代:「総評」労働運動の栄光と敗退(下)』同盟出
版サービスものがたり戦後労働運動史刊行委員会編2000『ものがたり 戦後労働運動史Ⅷ:
労働戦線統一のはじまりからスト権ストへ』第一書林中小路清雄1989「教育労働運動35年—総括の視点<9> 日教組と賃金闘争(1)」
『月刊�国際労働』No.220 pp.88-95,�75(編集の都合上、ページがとんでいるもの)
日本評論社編1972「交通・公労協・公務員共闘」『月刊 労働運動 72春闘読本』3月臨時増刊、pp.98-101
日本公務員労働組合共闘会議1973.2.13『公務員共闘速報』No.367日本公務員労働組合共闘会議1973.3.21『公務員共闘速報』No.368日本公務員労働組合共闘会議1990「公務員共闘と私:’73〜’74山本興一」『公務員
共闘30年の歩み』日本公務員労働組合共闘会議日本教職員組合編1977『日教組三十年史』労働教育センター日本労働組合総評議会1973.2.26-27『第45回 臨時大会速記録』日本労働組合総評議会1974『総評二十年史(下巻)』労働旬報社
98 法政大学キャリアデザイン学部紀要第13号

日本労働組合総評議会1993『総評40年史�第1巻』第一書林岡崎三郎執筆代表1971『日本の産業別組合―その生成と運動の展開』総合労働研
究所大木正吾1976『三千万人の春闘論-生活闘争から国民春闘へ―』総合労働研究所労働省1977『資料労働運動史 昭和48年』労務行政研究所立川洋1981『いまなぜ日教組か』三一書房田沼肇1971「日教組」岡崎三郎ほか前掲書pp.273-294Tarrow,�Sydney�1998�Power in Movement, 2 nd Edition,�Cambridge�University�Press.�
大畑裕嗣監訳『社会運動の力――集合行為の比較社会学』彩流社Thurston,�Donald�R.� 1973�Teachers and Politics in Japan,�Princeton�University�
Press.筒井美紀2014「日教組における批准投票制度の確立過程――1960年代前半におけ
るストライキ拡充の模索――」『日本労働社会学年報』第25号、pp.126-149.
日本教職員組合は73春闘半日ストをどう闘ったか 99

ABSTRACT
How Japan Teachers Union (JTU) Went on “Half-Day Strike” for 1973 Shunto: the Political Opportunity Structure of the JTU in the Early 1970s
Miki TSUTSUIKosaku NAGAMINE
Kaoru SUETOMI
This�paper�clarifies�the�process�and�the�result�of�the�“Half-Day�Strike”�for�1973�Shunto�by�the�JTU.��The�authors�examine�not�only�the�internal�process�of� the�JTU�but�also� the�external�one�such�as�Komuin-kyoto�and�Sohyo,�by�using�the�theory�of�Political�Opportunity�Structure�(Tarrow,�1996).���Because�its�strike,�collective�action,�was�formed�through�the�position�of�the�JTU�in�the�labor,�where�were�many�other�unions,�this�paper�looks�into�the�wider�political�process.� � In�other�words,� it�employs�the�multi-dimensional�scheme,�not� the�scheme�of� the�LDP�&�Ministry�of�Education�versus�Education�Movement.��Four�main�findings�are�below: 1)�the�administrative�punishment�to�“1969.11.13�strike”�changed�the�finance�of� the�JTU�fundamentally� to�cause�the�steep�raising�of�relief�and�struggle�fees,� but� the� finance�was� not� problematic� among� the� left� and� right�mainstreams�and� the�anti-mainstream�before� “1974.4.11�oppression.”� �The�JTU�could� not� help� going� on� strike� because� it�was� beyond� calculation�whether�the�JTU�would� lose�or�win�and�because�stopping� its�strike�meant�they�were�illegal�and�lose�cases. 2)�because�the�JTU�was�the�most�powerful�and�leading�union�in�Komuin-kyoto,� it�was�required�to�strike�with�the�other�public�sector�unions�against�
100

the�restructuring�of�the�labor�side�led�by�right-wing�private�sector�unions.��In�addition,� since� the� right� to� strike�was� inseparable� to� dealing�with� the�administrative�punishment�and�since� these�problems�were�unlikely� to�be�solved�through�Jinji-in�and�Koseishin,� the�public�sector�unions� thought� that�the�only�way�was�to�go�on�strike.� 3)�the�position�of�the�JTU�in�Sohyo�was�relatively�low�because�they�were�weak� in� strike�and�because� they� failed� to�make� its� requests�accepted�by�Sohyo�for�the�negotiation�with�the�government.� �Furthermore,�the�Ministry�of�Education� ignored�“the�Seven�Agreements”�and�never�stopped�punishing�the�JTU.�Also,�the�fact�that�the�requests�of�teachers�union�were�difficult�for�other�unions� to�understand� lowered� the�positon�of� the� JTU�as� for� 1973�Shunto�in�Sohyo.� 4)�the�JTU�managed�to�obtain�cooperation�of�the�Director�of�the�Primary�and�Secondary�Education�Bureau�through�the�informal�route�mediated�by�the�Nisseiren�congressmen.��However,�the�influence�was�limited�because�of�pro-war�attitudes�of�the�LPD�hawkish�and�some�prefecture�unions�of�the�JTU. In�summary,�some�of�the�causes�of�“Half-Day�Strike”�for�1973�Shunto�of�the�JTU�are�“increases� in� institutional�access”,� “influential�ally”,�and�“change� in�state�capacity� for� repression,”� all� of�which�are� situational� (Tarrow,�1996).��Now�that�Sohyo,� influential�ally,� intended�a�much� larger�strike� to�win� the�basic�legal�rights�to�labor�in�1974�Shunto,�the�JTU�could�not�but�go�on�“All-Day�Strike.”� �The�authors� think� that� some�atmosphere� for� reconciliation�between� the� JTU�and� the�Ministry� of�Education�might� vanish� by� this�attitude.
101




![RELEASE TRIMESTRAL 4T16 - grupocopobras.com.br€¦ · í õ ô x ô í ô î ï ð x î î ô î ì ì x ì ì ì î ñ ì x ì ì ì _ À ] > _ µ ] r ñ ì x ì ì ì í ì ì](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5ba2a4ee09d3f2d14d8c57c0/release-trimestral-4t16-i-o-o-x-o-i-o-i-i-d-x-i-i-o-i-i-i-x.jpg)











![AG Automne 2018 - ACVL · ^ ] ] µ } À ] } ] î ì í ô { ô õ ô v î ì í ó{ ô ñ õ v î ì í ò](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5fefe43a0713e6253f34918b/ag-automne-2018-acvl-v-.jpg)