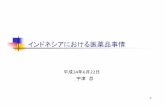インドネシア共和国 下水道運営に係る 基準(案) …open_jicareport.jica.go.jp/pdf/252902.pdfインドネシア共和国 公共事業省 インドネシア共和国
インドネシア共和国 アサハンアルミニウム精錬開...
Transcript of インドネシア共和国 アサハンアルミニウム精錬開...
インドネシア共和国
アサハンアルミニウム精錬開発関連施設整備事業
及び
ヨウ素坑井試掘試験事業
投融資審査等調査報告書
2002年 12月
鉱 開 計
CR(5)
02-04
国 際 協 力 事 業 団
No.
序 文
インドネシア共和国における「アサハンアルミニウム精錬開発関連施設整備事業」は、アサハ
ン川の豊富な水資源を利用した水力発電開発と、その電力を使ったアルミ精錬をパッケージにし
た日本・インドネシア共和国共同のナショナル・プロジェクトです。国際協力事業団はこの事業
の関連施設整備に対し、1976~1985年にかけて資金の貸付を行いました。
一方、「ヨウ素坑井試掘試験事業」はスラバヤ州パサランにおいて、ヨウ素生産に向けて試掘
を行い、生産井戸開発のための様々な試験を実施しようというものです。期間は2002年から3年
間の予定で、国際協力事業団は2001年8月に、この事業についての融資承諾を行っています。
前者については、以前として多額の累積損失を負っていることが報告され、債権保全の観点か
らの調査が必要となりました。また、後者についても、2002年5月の第1回貸付金が適正に使用
されたかどうかを審査し、事業の実施状況を調査する必要がありました。
本報告書は、上記の目的で2002年12月に派遣された調査団の調査結果を取りまとめたものです。
今後の事業の進展の一助となれば幸いです。
2002年12月
国際協力事業団
鉱工業開発協力部
部長 中 島 行 男
目 次
序 文
目 次
地 図
写 真
第1部 アサハンアルミニウム精錬開発関連施設整備事業
第1章 調査の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
1-1 調査の経緯・目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
1-2 調査内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
1-3 事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
1-4 調査日程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
1-5 調査団の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
1-6 主要面談者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第2章 調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
2-1 概要(団長所感)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
2-2 個別事項の調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第2部 ヨウ素坑井試掘試験事業
第1章 調査の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
1-1 調査の経緯・目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
1-2 調査内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
1-3 事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
1-4 調査日程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
1-5 調査団の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
1-6 主要面談者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第2章 調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
2-1 概要(団長所感)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
2-2 個別事項の調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
2-3 貸付金に係る国内経理審査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
2-4 今後の事業スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
付属資料
1.アサハンアルミニウム精錬開発事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
1-1 P.T.INALUM社年度別返済金額予定表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
1-2 第28期中間決算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
1-3 日本アサハンアルミニウム(株)所有のP.T.INALUM社の評価減の実施について・・・・・・・・・・・ 31
1-4 アサハンプロジェクトについて 2002年11月 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
2.ヨウ素坑井試掘事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
2-1 プロジェクト資金入金・支払状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
2-2 三井物産(株)社内資料・伝票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
① 第1回貸付金入金伝票 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
② 第1回目送金(5月31日)リクエストレター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
③ 第1回目現地送金(5月31日)伝票 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
④ 第1回目送金分受領済みレター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
⑤ 第1回目送金分現地銀行入金スリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
⑥ 利払い金伝票(9月30日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
⑦ 第2回目送金リクエストレター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
⑧ 第2回目送金日本側承認レター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
⑨ 第2回目現地送金(11月20日)伝票 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
⑩ 第2回目送金分受領済みレター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
⑪ 第2回目送金分現地銀行入金スリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
2-3 1本目の試掘井掘削用資金額明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
2-4 事業遅延の原因となった事業サイト確保のための土地取得資金の
追加依頼レター(三井物産(株)側は、追加提供を拒否) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62
本報告書の記載内容の公開に関しては、あらかじめ、国際協力事業団 鉱工業開発協力部 計画・投融資課(TEL:03-5352-5175)までご照会ください。
-3-
第1章 調査の概要
1-1 調査の経緯・目的
今回の調査は、インドネシア共和国(以下、「インドネシア」と記す)において1976~1985年
にかけて貸付を行ったアサハンアルミニウム精練開発関連施設整備事業に関し、今後の債権保
全の観点から、事業の現状及び今後の見通しについて調査・確認するものである。特に、2002
年3月末現在の決算関係書類からは、1996年に実施された固定資産の評価替えによって債務超
過を回避しているように読みとれるため、決算内容の事実確認作業を行う。また、貸付の対象
となった関連施設の稼働状況を確認しつつ、今後の事業及び資金見通しについても調査を行う。
1-2 調査内容
主に以下の3点について、現状を調査するとともに、企業の業況調査を行う。
(1) 財務書類確認と事実確認
(2) 融資案件対象施設の現状調査
(3) 現地企業の業況及び今後の進捗等に関する調査
詳細な個別調査事項は、主に以下のとおりである。
1)日本アサハンアルミニウム(株)
① 国際協力事業団(JICA)からの借入金を含めた全借入金の年度別返済予定。
② P.T.INALUM社への貸付金の回収状況。
③ 2001年3月期の子会社株式評価損(50%減)の算定方法・基準。
2)インドネシア・アサハンアルミニウム(株)(P.T.INALUM社)
① 今後の中期的な生産、販売見通し。
② 販売先別見通し(インドネシア側の引取増は今後望めないのか)。
③ 今後2~3年の損益見通し。
④ 2002年度、為替レートの変動による為替損益は、どれくらいになると試算されるか。
⑤ 1996年8月13日付け大蔵省令に従った資産の再評価(2002年3月末決算書p9部分)
は、どのような内容か。これまで財務上の影響(メリット)はみられたか。
⑥ 1998年6月19日付けで財務会計基準委員会に承認された“Impairment of Asset
Value”(2002年3月末決算書p10部分)はどのような内容か。その後、この承認によ
り何か影響は発生しているか。
⑦ 老朽化した関連施設、生産施設の状況と今後の事業への影響。また、地域社会的環境
を含めた周辺環境に影響は生じていないか、今後も発生しないか。
⑧ メガワティ政権への交代や地方自治の進展などの政治的要因から事業運営に影響を及
-4-
ぼすような問題は発生していないか。
⑨ 事業サイト周辺の最近の治安状況。
1-3 事業の概要
(1) 事業の内容
アサハン川の豊富な水資源を利用した水力発電開発と、その電力を使ったアルミ製錬を
パッケージにした我が国とインドネシア政府によるナショナル・プロジェクト。
1)資本構成
インドネシア政府 41.1%(3億7,850万ドル)
日本側 58.9%(5億4,190万ドル:約650億円)
注:日本側出資金は、国際協力銀行と民間企業(アルミ製錬5社と関係商社7社)が
各々50%出資。
2)資金調達(借入額)
ダム建設を含む発電施設及びアルミ製錬所の建設資金は、その全額を我が国から融資。
円借款:615億円 主にダム及び発電所建設資金に使用。
日本輸出入銀行:1,741億円 主にアルミ製錬所の建設資金に使用。なお、融資額には
市中銀行協調融資分を含む。
JICAほか:153億円 主に水力発電所サイト及び製錬所サイトにおける道路、学校、病
院、電話施設、教会、集会所などのインフラ施設の建設資金に使用。なお、
融資額には市中銀行協調融資分(45億8,000万円)を含む。
(2) 貸付の概要
本事業に対し、1976~1985年にかけて、道路、学校、病院などの関連施設整備に必要な資
金を当事業団が、本邦の投資会社である日本アサハンアルミニウム(株)に貸し付けた。
1)貸付総額: 約107億円
2)未返済残高: 約35億円(2002年11月末現在)
3)最終返済期日:2014年6月25日
(3) 事業の動向
1)構造的環境
① 近年、電力とアルミニウムの生産、販売は安定してきており、黒字経営が見込まれる
ところであるが、引き続き累積損失を負っている。トバ湖への有効流入量の増減や売価
変動、また、借入金が円建てであることから為替変動の影響を大きく受け、為替予約に
よるリスクヘッジを実施するとともに、追加出資、金利引き下げ、返済期間延長などの
再建策も実施している。
-5-
② ルヌン河の流水系を変更し、水をトバ湖に導く発電所プロジェクトは、1983~1984年
のルヌン水力発電開発計画を踏まえ、1991年に円借款が認められた。当初1999年完成予
定としていたが、工事が難航していることから、2005年の完成予定となる方向である。
なお、同発電所が完成すれば、発電量、アルミ生産量の増加が期待できる。
③ 本プロジェクトで建設された発電所、製錬所などの施設は、稼働後30年にあたる2013年
にインドネシア側に譲渡される(当初の基本契約事項)。
2)最近の動向
① 現在、日本アサハンアルミニウム(株)の累積損失は、約10億ドルに達している。
② 操業25年が経ち、円借による発電施設が老朽化し、2000年には重大事故が起き、様々
なリハビリが必要となっている。
③ 当事業団の貸付により建設された施設も老朽化し、一部修復を行っているところであ
るが、既にインドネシア側へ譲渡した施設についてもリハビリが求められている。
④ 同事業の水力発電に利用するトバ湖近郊では、森林伐採による環境問題が深刻化して
おり、植林プロジェクトが求められている。さらに、降雨量の減少によるトバ湖水位低
下も周辺住民に与える影響があるとして問題となっている。
⑤ 同事業のダムでは土砂の堆積が進んでおり、その要因調査が求められている。
⑥ 日本アサハンアルミニウム(株)損益状況
1999年3月末 2000年3月末 2001年3月末 2002年3月末
営業収益 6,293 5,599 3,669 3,174
経常損益* 0 0 0 0
特別損益
子会社株式評価損** 0 0 △49,935 0
当期利益 0 0 △49,935 0
累積損益 0 0 △49,935 △49,935
* 本邦内借入先への元金・利息支払い額及び管理費の合計額と同額をインドネシア現地法人から利息等収入として受け取っているため経常損益は計上していない。
** 2001年期にインドネシア現地法人の株式債権を50%減価処理。
⑦ インドネシア・アサハンアルミニウム(株)(P.T.INALUM社)販売・損益状況
1999年 2000年 2001年 2002年(f)
地金販売量(1,000t) 121 195 173 184
売上高 (100万ドル) 178 300 244 255
経常損益( 〃 ) △55 △21 △11 △39
当期損益( 〃 ) △216 200 79 △66
累積損益( 〃 ) △1,292 △1,030 △985 △1,072
期中平均為替レート 111.60 110.58 125.14 125.00
-6-
1-4 調査日程
日順 月 日 曜 行 程 業務内容 宿泊地
1 12月9日 月 東京→ジャカルタ 移動:JL725(11:25→17:10) ジャカルタ
8:30 JICAインドネシア事務所打合せ
PMアサハンアルミニウム(株)製錬開発事業調査
2 12月10日 火 ジャカルタ市内
P.T.INALUM社ヒアリング
ジャカルタ
ジャカルタ→スラバヤ 移動:GA312(12:00→13:15)
PM ヨウ素坑井試掘試験事業調査3 12月11日 水・関係者ヒアリング・事業地調査事前打合せ
スラバヤ
ホテル→事業地 陸路移動:8:30→9:30
事業地→WatudakonAMPM
ヨウ素坑井試掘試験事業調査・事業地・P.T.Kimia Farma社Watudakon工場
スラバヤ4 12月12日 木
Watudakon→ホテル 陸路移動:17:00→18:00
スラバヤ→ジャカルタ 移動:GA313(12:00→13:15)
在インドネシア日本国大使館表敬
16:30 JICAインドネシア事務所報告5 12月13日 金
ジャカルタ→ 移動:JL726(22:30→ 機中泊
6 12月14日 土 →東京 →7:25着)
1-5 調査団の構成
担 当 氏 名 所 属
団長/総括・事業管理 岩崎 政典国際協力事業団 鉱工業開発協力部計画・投融資課課長代理
債権管理 助川 正文 国際協力事業団 投融資技術相談員
1-6 主要面談者
(1) 国内事前調査側関係者
日本アサハンアルミニウム(株) 12月4日(水)
藤岡 聡 経理部長
(2) 現地調査側関係者
1)P.T.INALUM社
梶原 義彦 取締役(企画、経理部門担当)
2)在インドネシア日本国大使館
高橋 正和(一時帰国中) 一等書記官
-8-
第2章 調査結果
2-1 概要(団長所感)
今回の調査では、主に1996年3月末から2002年3月末の決算内容、最近の生産・販売実績と
今後の見通しについて調査を行ったが、当初予定した内容をおおむね調査することができた。
当事業は、10億ドルを超える累積損失が会社運営に大きな重荷となっているが、直ちにこれを
解消することは困難である。今後もトバ湖の水量、アルミニウムのLME(London Metal
Exchange)価格及び為替リスクという見通しの立てにくい3点について、常時注視し続けた
うえで、短期的な目標を達成すべく業績を伸ばしていくことが必要である。なお、当初、調査
を予定していた「融資案件対象施設の現状調査」については、10月末、現地事業サイト周辺で
隣州ナングル・アチェ・ダルサラム州を本拠地とするGAM(自由アチェ運動)の武装ゲリラ
と軍・警察側との間で銃撃戦が発生したため、今回は現地サイトでの調査は見合わせ、ジャカ
ルタ現地法人での聞き取り調査のみを実施した。
2-2 個別事項の調査結果
12月4日、現地調査に先立ち、本邦側の投資会社である日本アサハンアルミニウム(株)に以
下の個別事項について調査を行った。
(1) 日本アサハンアルミニウム(株)
1)当事業団からの借入金を含めた全借入金の年度別返済予定
P.T.INALUM社から日本アサハンアルミニウム(株)への年度別返済金額予定を入手し
た(付属資料1-1参照)。日本アサハンアルミニウム(株)から各借入先に対する返済金
額も基本的に同額である。
2)P.T.INALUM社からの貸付金の回収状況
2002年9月30日現在、日本アサハンアルミニウム(株)の借入金は、約1,113億円であり、
そのうちJICAからの借入金は、約34億円である(付属資料1-2参照)。借入金返済の原
資は、すべてP.T.INALUM社からの貸付金の返済金である。P.T.INALUM社からの返済
は、予定通り行われており、貸付金の回収に問題は生じていない。2013年には、借入金の
返済が完了する計画である。
3)2001年3月期の子会社株式評価損(50%減)は、どのような算定方法・基準等により行っ
たのか。
① 2001年3月期に子会社株式評価損(50%減)499億円を計上している。子会社株式は、
P.T.INALUM社に対する出資金額である998億円である。P.T.INALUM社は、借入金に
かかわる多額の為替差損により、ドルベースの純資産が減少しており、2000年3月期決
-9-
算に資本金9億2,047万6,000ドルに対して純資産が7,835万9,000ドルとなっていた。金
融商品にかかわる会計基準により、財政状態が悪化した子会社に対して評価減をする必
要が生じ、2001年3月期に子会社株式評価損を計上した(付属資料1-3参照)。
② 当プロジェクトは、2013年に終了し、インドネシア側に売却される契約であり、2013年
時点の評価額で評価減を行った。今後の為替変動の影響を勘案し、2000年3月時点の評
価減の実施幅は、50%減とした(付属資料1-4参照)。
現地法人P.T.INALUM社からの調査結果は以下のとおりである。
(2) インドネシア・アサハンアルミニウム(株)(P.T.INALUM社)
1)今後の中期的な生産、販売見通し
① すべてがトバ湖の水量及びアルミニウムのLME価格次第である。年間生産量20万t、
アルミニウム価格1t=1,400ドルで推移すれば採算ベースである。
② 2002年12月9日現在、水位904.08m、LME価格1,340~1,350ドルとなっているため、
338炉稼働の増産体制に入っている。
③ 2003年は400炉稼働の年産19万t体制としたい。
2)販売先別見通し(インドネシア側の引取増は今後望めないのか?)
① インドネシア側の4割の引取義務は、国内の需要低迷のため、最近まで一部日本側が
引き取り、第三国へ輸出していた。販売先は、2002年12月までに2万4,000tをマレイ
シア、シンガポールなど様々である。
② インドネシアでは、国内の景気が徐々に回復傾向にあるため、需要増となりつつある。
このため2003年は、インドネシア側の4割の引取義務も十分達成可能である。
3)今後2~3年の損益見通し
① 全額円建て借入のため、ドルベースの売上金から円ベースへの換算率に大きく左右さ
れる。そのため見通しが立てにくい。
② 為替レート、LME価格などある程度リスクヘッジの可能な分野もあるが、トバ湖の
水位が業績を大きく左右するため、中長期の損益見通しが立てにくい。
4)2002年度、為替レートの変動による為替損益は、どれくらいになると試算されるか。
① 2001年度段階で1米ドル=133円を想定したが、2002年度初期に1米ドル=130円で
あったため、2002年度は3,500万ドルの差損を計上している。
② 2003年3月期末に1米ドル=125円となった場合、約6,900万ドルの差損となる。
5)1996年8月13日付け大蔵省令に従った資産の再評価(2002年3月末決算書p9部分)は、
どのような内容か。これまで財務上の影響(メリット)はみられたか。
① インドネシア政府が、国際会計基準にある時価会計を企業会計に導入することとなっ
たため、その方針に整合的な処理を行った。
-10-
② 以前は、「インドネシア法人の累積損益が資産の3分の2を下回った場合は、同法人
を解散させなければならない」という法律が存在した。
③ 1997年に時価会計による評価替えを実施した結果、資産価値が大幅に増加し、同時に
会計上の減価償却期間が評価替えを行った年から開始されるため、スメルター設備30年、
山林50年に延長された。
④ 資産価値の増加及び償却期間の延長によって結果的に債務超過を免れたように映る。
⑤ 当事業を2013年にインドネシア側へ譲渡する際、日本側が受け取る株式譲渡益が減少
するため、不利な内容でもある。
6)1998年6月19日付けで財務会計規準委員会に承認された“Impairment of Asset Value”
(2002年3月末決算書p10部分)はどのような内容か。その後、この承認によって何か影
響は発生しているか。
① 国際的な企業会計規準の導入による資産の洗い替え、(1997年を起算年とする)償却
期間の再設定に関する内容である。
② 国際的な会計規準の導入については、インドネシア国内に反対ないし検討するための
機関、人材が存在しないためスムーズに導入された(アジア通貨危機後のIMFスタンド
バイクレジットのコンディショナリティにも存在)。
③ ただし、期末損益はともかく償却前のマイナス計上は考え難い(約7,000万ドルが対
象)。
ほかに「米国アンダーセン系列の監査法人を今後も使うつもりか」の問いに対して、
「替えるつもりである。5年以上同じ監査人を使うことを禁じる規則もある」とのこと。
7)老朽化した関連施設、生産施設の状況と今後の事業への影響。また、地域社会的環境を
含めた周辺環境に影響は発生していないか、今後も発生しないか。
① JICAの関連施設整備事業で建設した病院、道路及び橋などは、技術レベルの低下又
は老朽化が見られるが、地元自治体による補修工事などにより維持されており、周辺地
域の人々の利用度も高い。
② 具体的には、1か所の橋を除いてすべて稼働している。
③ 地域社会への環境影響は発生していない。むしろ地域社会へは、2001年35万ドル、2002年
80万ドル(金額は対外秘)の植林などを目的に寄附行為を実施している。
8)メガワティ政権への交代、又は地方自治の進展などの政治的要因から事業運営に影響を
及ぼすような問題は発生していないか。
① 中央政府の大臣と地方政府との権限争い的なものがある(例:本来地方政府に入るこ
とが自然なannual fee見合いの地方配分がない)。
② 公共事業による改修が適当なものまで企業側に負担を求めてくることがある。
-11-
9)事業サイト周辺の最近の治安状況
① 10月下旬に捜索していた4名の不審者については、その後の動向は不明である。最近
は落ち着いている。
② 在インドネシア日本国大使館からの警備強化の要請に基づき、ラクサマラ国営企業省
大臣から警備強化の指示書が出されており、軍・警察20名以上で常時警備している。現
体制は、1月中旬まで継続予定である。
③ 近辺で過去に環境影響などで問題があったインドネシアレーヨン工場の事業再開が、
政府ベースで強行されようとしているため、周辺住民が「大企業は同列」的な発想で攻
撃されるのが心配である。
-15-
第1章 調査の概要
1-1 調査の経緯・目的
本事業は、スラバヤ州パサラン地区において、三井物産(株)、関東天然瓦斯(株)、合同資源
産業(株)の3社が工業・農業用、医療用などの原料に使用される「ヨウ素(Iodine)」を含む「カ
ン水」の滞留層を試掘し、生産井戸を開発するための試験事業を実施するものとして2001年
8月にJICAの融資承諾を得ている。その後、企業側は、米国で発生した同時多発テロによる
世界情勢及び治安等の変化を考慮し、事業遂行を控えていた。今般、現地情勢などを確認した
結果、当該試験事業を再開することとした。2002年10月からは、事業サイトにおいて、JICA
から派遣した開発協力専門家の協力を得つつ、試掘作業を開始している。
今回の調査では、2002年5月の第1回資金貸付分について資金の適正使用及び事業の実施状
況を確認・審査する観点から、開始された試掘作業の状況を現地で調査する。同時に開発協力
専門家の活動状況の調査も行う。
1-2 調査内容
主に以下の4点について、現状を調査する。
1)試掘作業の状況
2)生産テスト結果のヒアリング
3)開発協力専門家の活動状況
4)今後の進捗に関する見通し
(1) 詳細な個別調査事項
1)試掘井戸の状況
2)掘削機械をはじめとする設備機器の稼働状況
3)試掘の作業体制、内容
4)派遣専門家、本邦出張作業員及び現地作業員の労働状況
5)試掘サイトと周辺住民との関係(専門家が活動中に気づいた点を含む)
6)試掘作業が環境に及ぼす影響の有無
7)生産テストの評価結果と今後の見通し(事業化の見込みがどの程度あるか。ヨウ素の含
有成分率が70~100ppmあるか)
8)今後の事業化にあたっての留意点
(2) 開発協力専門家への調査事項
1)現地法人P.T.Kimia Farma社側の知識、技術レベル(事業化に向けて、十分な知識、
技術力をもっているか。今後、技術支援を実施するとしたら何が必要か。)
-16-
2)JICA専門家派遣制度についての要望
3)JICA事務所の受入体制(インドネシア到着後、適切なタイミングで事務所からコン
タクトがあったか。安全ブリーフィングは十分、かつ分かりやすいものだったか)
1-3 事業の概要
(1) 事業の内容
今回予定されている試験事業は、当該地区の鉱区内試掘井戸深度1,000m前後において十
分なヨウ素の含有、賦存状況を調査するために以下の試験を実施するものである。試験期間
は2002年度から3年間である。
1)地下の水流層や異常高圧層の特性把握及び泥水管理方法や異常高圧層の監視技術の確立
(日本国内におけるヨウ素坑井の掘削とは、ヨウ素を含有する「カン水」いわゆる塩水流
層の地層が異なるため)
2)塩水流層内に混在する成分等のチェック
3)混入物質の混在防止方法の検討
4)地層圧力分布や岩質の把握によるケーシング、ビットなど技術改良の検討
5)ヨウ素原料開発に対応するための、環境影響評価を踏まえた試験工程の検討
今後、本邦企業3社は、本試験事業の結果を踏まえ、商業生産ベースの本格事業化が確
認された場合、現地民営化企業P.T.Kimia Farma社と共同でヨウ素生産開発プロジェク
トを開始する予定である。
(2) 貸付の概要
2001年8月の融資承諾では、3年間の試験事業のために資金総額3億円を内諾している。
このうち2002年5月に試掘用資金の一部として第1回目の貸付を実行した。
1)貸付の相手方:三井物産(株)
2)貸付額:7,980万円
3)次回貸付実行予定:生産テスト終了後(2002年12月下旬予定)に約3,600万円。
(3) 事業の動向
当初、2002年7月15日開始予定であった掘削作業スケジュールは、約3か月の遅れ10月23日
から開始された。主な動向は以下のとおりである。
1)10月23日の掘削開始のセレモニーは予想以上に盛大で、警察署長などの地元有力者が出
席した。
2)11月3日までに、コンダクターパイプ(掘削坑の地上近辺の坑井外枠部分)244mをセ
メント注入固定した。
3)11月4日までに深度296mまで掘削したが、今後使用予定のコアリングリグビット(先端
-17-
部)と回転部をつなぐロッキングカップリングが準備されていないことが判明した。した
がって、当該部品をカナダから取り寄せるまで掘削作業を5日間(11月8日まで)中断し
た。
4)試掘作業のため第2次人員(合同資源産業(株)2名、関東天然瓦斯開発(株)1名)が
11月17日に出発した。
5)11月20日深度約688~692mまで掘削。
6)11月24日までに深度約900mまで掘削した。この時点で泥流の噴出が激しく、1日に20~
30m程度しか掘削できない状況だったが、12月3日の予定深度1,000mまでの掘削は十分
達成可能な見通しである。
7)11月27日深度約930mまで掘削し、最終的に1,100mまで掘削予定である。その後、12月
13日より生産テストを10日間程度実施した。
1-4 調査日程
第1部第1章1-4(p6)に同じ。
1-5 調査団の構成
第1部第1章1-5(p6)に同じ。
1-6 主要面談者
(1) 国内事前調査側関係者
1)合同資源産業(株) 千葉事業所 11月22日(金)
遠藤 信哉 取締役所長(兼)鉱業部長
砂川 茂 取締役副所長(兼)ヨード部長
市東 直紀 本社 企画部副部長(兼)企画課長
2)関東天然瓦斯開発(株) 茂原鉱業所 11月22日(金)
山崎 英夫 開発部課長(開発担当)
早津 晋
3)三井物産(株) 11月28日(木)
御代 靖之 無機製品部化成品室長
吉武 直子 無機製品部化成品室
(2) 現地調査側関係者
1)P.T.Kimia Farma (Persero) Tbk. Watudakon工場
Drs. Abdullah Basuki 工場長
-18-
Ir. Mardiasto 副工場長
Mulya Sukmana
Ir. Suprayitno
2)テクノアース(株)(JICA派遣短期専門家:10月16日~12月19日)
柏倉 一弥 さく井部長
3)(株)新和調査設計(JICA派遣短期専門家:10月16日~12月19日)
川口 通世 ISO管理・企画室長
4)関東天然瓦斯開発(株)(出張作業員)
樋口 朋之 茂原鉱業所開発部課長
鈴木 克美 茂原鉱業所開発部課長代理
国末 彰司 茂原鉱業所開発部係長
5)合同資源産業(株)(出張作業員)
樋口 康則 千葉事業所鉱業部課長
大庭 慶一 千葉事業所鉱業部
6)インドネシア三井物産(株)スラバヤ事務所
堀尾 常夫 所 長
7)在インドネシア日本国大使館
高橋 正和(一時帰国中) 一等書記官
8)JICAインドネシア事務所
大竹 祐二 次 長
真野 修平 所 員
-19-
第2章 調査結果
2-1 概要(団長所感)
今回の調査は、2002年5月7日に当事業団から貸付を行った資金の適正使用の観点から、
現地サイトで開始された1本目の試掘井戸の掘削作業の状況を調査した。また、当事業団か
ら2か月間の短期派遣を行っている2名の開発協力専門家の活動状況についても調査を行っ
た。
試掘作業については、若干の掘削スケジュールの遅延がみられたが、おおむね順調に進捗し
ていた。作業内容も関東天然瓦斯開発(株)、合同資源産業(株)及び三井物産(株)に派遣専門家
を含めた日本側と現地共同実施者のP.T.Kimia Farma社及びコントラクター会社P.T.
Mutiara Biru Perkasa社との間で十分連携がとられ、当初決められた内容及び発生する状況
へ適切に対応しているように見受けられた。各深度で採取する分析用試料についても、日本側
及びP.T.Kimia Farma社と適量分割し、相互に分析・評価する体制をとっており、今後の事
業化に向けて公平、効率かつ協力的に進捗するよう工夫していた。当初予定から約2週間遅れ
て12月20~25日に開始される予定の生産テストについては、これまでの分析結果から事業化に
向けて期待がもてるものとなっていることから、今後、詳細なデータが整理される見込みであ
る。
また、当事業団からの派遣専門家2名についても、特段大きな問題もなく活動していた。今
後、12月18日の現地出発間際まで生産テストに向けたデータ分析・評価を継続する意向とのこ
とであった。公用旅券のビザの関係上、テストの最終段階まで立ち会うことはできないが、当
初、当事業団が想定した「本事業の技術的調整と地質の検証、ヨウ素鉱床の存在状況の確認」
の派遣目的は達成可能と思われる。
今後、本事業については、採取した分析用試料の分析・評価結果を含めた総合的な評価によ
り商業化生産に妥当な数量が確保されることが確認されれば、次の2本目の試掘井掘削の試験
事業に進むこととなる。
2-2 個別事項の調査結果
(1) 国内のヨウ素事業調査
今回の現地調査に先立ち、11月22日にヨウ素事業の現況を把握する観点から、本件関係企
業である合同資源産業(株)(千葉県茂原市)のヨウ素工場を訪問した。主な調査結果は以下
のとおりである。
1)世界のヨウ素生産の37%が日本で、うち87%が千葉、10%が新潟で生産されている。
2)千葉では現在9社が操業中である。そのなかでヨウ素生産事業に関しては、合同資源産
業㈱が、最大手、かつパイオニアである(1934年創業)。
3)三井グループのガス事業縮小化以降、1994年ごろから同業の関東天然瓦斯開発(株)と株
-20-
式をもち合い、人員、事業面において相互協力・補完関係を維持している。1997年からは
関東天然瓦斯開発(株)分のヨウ素も受託加工生産している。販売面でも三井グループがサ
ポートしており、業界内での競争力を維持している。
4)今後のヨウ素事業の見通し
① 製品需要は、多種の汎用品(医薬品、フィルム材料、肥料など)へ広がっているが、
量的に急激な市場拡大は望めない。
② 日本では、資源量、事業コストの面から増産は望めない。
③ 最大生産国チリも生産方法(燃焼法)、事業コストの面から増産は難しいと思われる
(よって、今回のインドネシアヨウ素試験事業に大いに期待している)。
5)インドネシアヨウ素試験事業に際しての留意点
① 環境面:使用済みカン水の処理方法及び塩害発生を防ぐための放水、又は地中還元な
どの検討が必要である。
② 生産面:同時に採取される天然ガスの処理方法及び商業生産段階での国内販売、輸出
等の使途を明確にする必要がある。
③ 社会面:商業生産段階での複数(50~100本)掘削の際、近隣住民の合意取り付けは、
事業の最大配慮事項である(千葉県で主に坑井掘削事業を営む関東天然瓦斯開発(株)担
当課長談)。
6)インドネシアヨウ素試験事業での関係企業の協力体制
合同資源産業(株)がヨウ素生産技術、関東天然瓦斯開発(株)が坑井開発技術、三井物産
(株)が製品販売等のコマーシャル部分をそれぞれ担当している。
(2) インドネシア現地での調査結果
1)試掘作業の状況調査
① 試掘井戸の状況
a)コアリング(掘削先端部分)は、12月5日に1,105mに到達し、その後抗井を広げ
る作業を行い、12月10日にほぼ当初予定の大きさを達成した。
b)天然ガスの濃度が千葉に比べ高く、掘削後、138mでブローアウト(異常噴出)が
発生したが、適切に対応した。
② 掘削機械をはじめとする設備機器の稼働状況
特に不具合、大きなトラブルは発生していない。使用設備機器は、日本のものと異な
るが、設備によっては日本より良いものを使っているものもあった。
③ 試掘の作業体制、内容
a)特に、現地側と日本人側の分担は決めていない。お互いに「同じチームメンバー」
-21-
という認識で友好かつ協力的に活動していた(実際の契約では、現地パートナーであ
るP.T.Kimia Farma社とフルターン契約を締結しているコントラクター会社P.T.
Mutiara Biru Perkasa社が工事の全責任を負っている)。
b)日本側の作業体制は、JICA派遣専門家2名を含めた総勢7名を3つのグループに
分け、2交代制で毎日ホテルを午前8時又は午後5時に出発している。
c)現地側は、総勢45名を1グループ15名ずつ3グループに分け、2交代制である。た
だし、グループのシフトは、2グループで朝6時から夕方6時まで2週間作業を続け
たあと、1グループは1週間の休みをとっている。
d)現地側の作業内容は、掘削用の土台の上で掘削機械を操作する人員が4~5名、泥
水処理機械周辺で3~5名、その他周辺設備機器、監督者等で5名であった。
④ 派遣専門家、本邦出張作業員及び現地作業員の労働状況
a)炎天下での作業が体力的に最も厳しい条件であるが、海に近いこともあり、多少の
風がある。日本の最悪状況下での作業よりは良い。通常10月後半には雨期に入るが、
2002年は11月中旬ごろとなり、雨の回数、量も少ない。
b)水は、サイト内のコンテナハウス(冷房完備)に常備されており、いつでも摂取可
能である。食事はホテル準備のランチボックス、又は現地側作業員の宿舎を兼ねてい
る近くのレストラン(サイトから約500m)の利用が可能である。
⑤ 試掘サイトと周辺住民との関係(専門家が活動中に気づいた点を含む)
工事開始のセレモニーの際に関係近隣者が出席したが、その後特に交流はなく、時折
工事を遠目に見学していることもある。一番近くの民家はサイトから約200m程度のと
ころにある。
⑥ 試掘作業による環境影響の有無
これまで掘削作業に対する苦情はなかった。掘削モーター(ディーゼル製)の音、排
気ガスについても影響はない。塩分を含んだ余分な水もサイト内のため池に一時的に貯
留し、必要であれば地中(約350m)にポンプで強制循環させていた。
2)生産テストの結果ヒアリング
① 生産テストの評価結果と今後の見通し
a)生産テストは、坑内のガス圧力が高いため11月下旬以降慎重に掘り進めた結果、当
初予定より約2週間遅れ、12月20日~25日の間で開始し、年末年始にかけて作業を完
了させる予定である。
b)これまで4回の分析用試料を採取したが、深度330m近辺が最も良い数値であった。
350~400m近辺での生産を想定した場合、良い結果が期待できる(サイトから40kmの
現地パートナーP.T.Kimia Farma社Watudakon工場の生産用井戸の深度も300~350m
-22-
であった)。
深度別のヨウ素濃度は300m→80ppm、336m→81.7ppm、338m→71ppm、339m→60ppm、
500m→30ppm、526m→16ppmであった。
3)開発協力専門家の活動状況の調査・確認
① 現地法人P.T.Kimia Farma社側の知識、技術レベル
a)今回のコントラクターであるP.T.Mutiara Biru Perkasa社の知識レベルは高く、
大学のmaster degreeをもっている者も幾人かおり、50歳代の熟練工でも相当程度の
知識を確認できた(以上、地質学分野専門の川口専門家)。
b)また、技術レベルについては、プルタミナなど国内の原油・天然ガス掘削事業を経
験していると思われ、自前のリグも18基所有している(日本でも掘削会社自体がリグ
を所有することはまれであり、通常はリグなどの機材はリースである)。日本側から
の知識・技術の指導はほとんど必要なかったが、何か突発的な事象が生じた場合の適
切な対応を提言・助言することは何度かあった(以上、掘削技術分野専門の柏倉専門
家)。
c)今回の事業では、P.T.Mutiara Biru Perkasa社が泥水など抗井全体のデータを測
定する別会社をもっていた。
② JICA専門家派遣制度についての要望
a)地中のガス圧が高かったために作業全体が遅延し、2か月の派遣期間中に生産テス
トに立ち会うことが結果的にできなかった。
b)今回は、貸付の相手方の三井物産(株)のスラバヤ事務所がサポートしているため、
特に負担とはならなかったが、サポートがなかった場合、交通費なしの日当のみの支
給では滞在費を賄いきれない。
c)所属先補填が低すぎる。JICAの所属先補填額の算出方法は、基本給+いくつかの
手当てを対象としているが、最近、日本国内の給与体系が変化しており、基本給を押
さえ、高額の各種手当てによって年収を増やしているコンサルタント事務所などのよ
うな給与体系に対応できていない。
d)掘削作業が、24時間体制に移行した際、専門家2名を含む少数の日本人作業員を2
グループ、2交代制とした結果、休暇が全く取得できない状況となった。唯一、今回
は、ラマダン明けのリバラン祭と工期が重なったため、2日だけ全作業が休みとなっ
た。前述のインドネシア側の2週間ごとに1週間の休みとは大きな差異がある。
e)当初、JICA専門家という身分的なものもあり、事業にどのように貢献したらよい
か不明であったため、休みを入れたスケジュールを設定できなかった。
f)薬の調達、スラバヤ市内の食事場所、病院など、専門家に対する主に通常生活面で
のバックアップがなかった。結局、三井物産(株)スラバヤ事務所に依存することとな
-23-
り、負担をかけた(これは、JICAインドネシア事務所がスラバヤにないことも起因
しているが、今回の派遣が短期専門家でもあることからJICAジャカルタ事務所から
のサポートにもおのずと限界がある)。
③ JICAインドネシア事務所の受入体制
入国時は問題なく行われた。ただし、その後特に連絡は取り合わなかった。入国時に
キャンセルとなったスラバヤ領事館との面談について、帰国前の再設定が行われていな
かったためJICAジャカルタ事務所真野調整員及び三井物産(株)スラバヤ事務所堀尾氏
に調整を依頼。その後、12月17日午後に総領事との面談がセットされた。
4)今後の進捗等に関する見通し調査
今後の事業化にあたっての留意点
a)これまでの評価結果から2本目の試掘井戸は、当初予定地点から若干変更を要する可
能性がある。
b)2本目の試掘の際も今回と同様、専門家派遣を必要とする可能性がある。
c)天然ガスの処理方法が最大の留意点で、天然ガスの鉱業権は別途ラピンドプラタスカ
が所有している。数百メートル近辺にガスパイプラインが通っているので送ガスするの
も一案である。
d)技術的には、異常プレッシャーが高いのでこれを押さえつつ、いかに対応していくか
が問題である。
e)不要カン水の処理方法(海に流す、地下に戻すなど)。
f)地域への貢献方法。最新式のプラントを導入すると大きな雇用創出は期待できない。
g)電力、輸送路などの基礎インフラは問題ない。
2-3 貸付金に係る国内経理審査
本事業は、現時点で現地法人を設立せず、本邦三井物産(株)ら3社の現地直接事業として実
施している。2002年4月25日付け限度貸付契約書も三井物産(株)のみを債務者として契約して
いる(現地法人記載なし)。このため2002年5月7日付けで行った坑井試掘用資金の第1回貸
付金7,980万円に係る経理審査を11月28日(木)14時から三井物産(株)本社にて以下の3点を
中心に実施した。
(1) 2002年5月のJICA貸付金の資金使途の分かる関係書類(現地企業への送金書類、送金先
からの領収書など)の確認
(2) 現地企業への第1回目の送金以降、第2回目の送金(11月20日)まで及び現時点での貸付
金の所持状況の分かる書類の確認
(3) 今後の資金借入申請の見通し
-24-
[審査結果]
JICAの当試験事業に関する経理資料は、三井物産(株)化学品グループ無機製品部化成品室
で管理、保存されていた。今回の経理審査において、以下のとおり資金の適正使用の観点から
問題となる事項は特に見受けられなかった。入手資料は付属資料2-2のとおりである。
1)2002年5月7日にJICAから貸し付けた7,980万円は、三井物産(株)化学品グループ経理部
が管理する銀行口座に入金され、記帳されたことを確認した。
2)4者間(インドネシア側:P.T.Kimia Farma社、日本側:三井物産(株)、関東天然瓦斯
開発(株)及び合同資源産業(株))の基本契約に基づき、2002年5月31日に32万ドルがインド
ネシア側に送金された。受取人は、インドネシア法人のP.T.Kimia Farma社であり、Bank
MADIRIのジャカルタ支店の口座に振り込まれた。為替レートは、1米ドル=123.45円であ
り、円貨換算で3,950万4,000円であった。P.T.Kimia Farma社は、三井物産(株)宛に2002
年6月11日に32万ドルを受領した旨のレターを発出している(付属資料2-2④参照)。
3)2002年11月20日に、4者間の基本契約に基づき、28万ドルがインドネシア側に送金された。
為替レートは、1米ドル=122.4円であり、円貨換算で3,427万2,000円であった。インドネ
シア側からの受領レターは、11月29日付けで発出(付属資料2-2⑩参照)。
4)JICAからの貸付金額のうち、調査時点で602万4,000円の未使用金額が発生していた。こ
れは、最近の円高傾向から換算率の関係上生じたものである(貸付当初は1米ドル=133円
で換算)。当該未使用金は、本件事業以外に流用されておらず、4者間の基本契約に基づく
今後の送金用に三井物産(株)化学品グループ経理部が管理する銀行口座において管理されて
いた。
5)今後の支払予定は、4者間の基本契約に基づき、12月中に28万9,727ドル、その後5万ドル
の合計33万9,727ドルである。1米ドル=122円で換算とすると、円貨換算で約4,144万6,694
円である。上記3)の未使用金額602万4,000円は、これらの送金の一部に充当され、不足資
金約3,542万2,694円を第2回目の借入金額としてJICA宛に申請予定とのことであった。
6)当初7月15日開始予定であった掘削スケジュールが約3か月遅延した(結果的に現地送金
も遅延)理由は、インドネシア側が事業サイトとなる土地の取得又は賃貸借契約の完了遅延
によるものである。この点について、インドネシア側から日本側関係企業に宛てた資金の追
加要請レター(付属資料2-4参照)を入手し、事実を確認した(この要請は、最終的に日
本側が拒否)。
2-4 今後の事業スケジュール
国内事前調査及び現地調査の結果、本事業の今後のスケジュールは以下のとおりとなること
を確認した。
2002年12月20~25日 生産テスト開始
-25-
2003年1月初め 生産テスト終了
2003年2月中 採取済み分析用試料の分析・評価終了
2003年5月下旬 2本目掘削工程開始(1本目の評価結果により実施を決定)
2003年9月初旬 2本目試掘井掘削開始
2003年10月下旬 2本目掘削終了
2004年以降 日本側3社及びP.T.Kimia Farma社との間で1本目、2本目の
分析評価結果を基に事業化を含めた検討を行い、3本目の試掘井
戸の掘削の必要性を判断
付 属 資 料
1.アサハンアルミニウム精錬開発事業
1-1 P.T.INALUM社年度別返済金額予定表
1-2 第28期中間決算の概要
1-3 日本アサハンアルミニウム(株)所有のP.T.INALUM社の評価減の実施について
1-4 アサハンプロジェクトについて 2002年11月
2.ヨウ素坑井試掘事業
2-1 プロジェクト資金入金・支払状況
2-2 三井物産(株)社内資料・伝票
① 第1回貸付金入金伝票
② 第1回目送金(5月31日)リクエストレター
③ 第1回目現地送金(5月31日)伝票
④ 第1回目送金分受領済みレター
⑤ 第1回目送金分現地銀行入金スリップ
⑥ 利払い金伝票(9月30日)
⑦ 第2回目送金リクエストレター
⑧ 第2回目送金日本側承認レター
⑨ 第2回目現地送金(11月20日)伝票
⑩ 第2回目送金分受領済みレター
⑪ 第2回目送金分現地銀行入金スリップ
2-3 1本目の試掘井掘削用資金額明細
2-4 事業遅延の原因となった事業サイト確保のための土地取得資金の
追加依頼レター(三井物産(株)側は、追加提供を拒否)