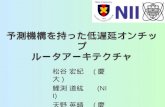蛍光顕微鏡の使い方 Olympus IX70とMetaMorphを用 …‚’終了...
Transcript of 蛍光顕微鏡の使い方 Olympus IX70とMetaMorphを用 …‚’終了...

蛍光顕微鏡の使い方:Olympus IX70とMetaMorphを用いた撮像
生体有機ではOlympusの倒立型蛍光顕微鏡IX70 (すでに販売終了した古いモデル)が使用可能です。ここでは、蛍光顕微鏡画像を自分で取れるようになることを到達目的として、基本的な操作方法や基本事項を説明します。
IX70蛍光顕微鏡は、いわゆる通常の「蛍光顕微鏡」であり「共焦点レーザー顕微鏡」ではありません。そのため、共焦点顕微鏡に比べれば焦点面前後の蛍光の影響が大きく、画像がぼやけやすくなります。また共焦点顕微鏡はほとんどの操作をソフトウェア上で行い、あまり接眼レンズを除く機会がありませんが、IX70はフィルターの切り替えやシャッターの開閉なども手動です。焦点の合わせ具合などをしっかりできないと良い画像は撮れないなど、不便なところはありますが、顕微鏡のトレーニングとしては良い顕微鏡とも言えます。最低限の使い方に加えて、NDフィルターや補正環、露光時間・ダイナミックレンジ、フィル
ターの選択などの基本事項を理解した上で使えるようになれば、焦点顕微鏡画像ほどではないにしろ、良い画像は撮れるようになるはずです。
1
2017.5.19 大金

操作の流れ
2
スタートアップ・観察1. 電源ON (PC、水銀ランプ、顕微鏡、CCDカメラ)2. MetaMorphを起動3. サンプルをステージにセット4. 対物レンズを選択5. 明視野でピントを合わせる6. フィルターを選択し、明視野照明をOFF、励起光の
シャッターを開ける7. 観察する
シャットダウン1. MetaMorphを終了2. データを取り出す (USBメモリ)3. PCの電源をOFF4. レンズの掃除5. 低倍率レンズに替え、低い位置にする6. CCDカメラ・顕微鏡本体・水銀ランプの電源OFF7. 顕微鏡にカバーをかける
撮像・保存1. MetaMorphのメニューバー > Acquire2. Exposure timeや保存先・ファイル名など
を設定3. 励起光シャッターを開ける (退色を防ぐた
め必要な時間だけ開ける)4. 光路をCCDに切り替え、Show Liveでピン
トを微調整し、Acquire5. あるいは、光路は接眼レンズのまま目で見
てピントを合わせ、光路をCCDに切り替えてAcquire(慣れてきたらこちらの方が早い)
6. Save

蛍光顕微鏡の基本的な原理
3
n 蛍光顕微鏡のおおまかな原理水銀ランプからは複数の波長の光が発生する。そのうち必要な波長の光をexcitation filterで取り出し、サンプルにあてる。サンプルから出る光のうち励起光そのものはemission filterで吸収され、蛍光のみがCCDカメラへ届く。励起光の強さは、NDフィルターにより調節されている。
ND (neutral density) filter減光フィルター。波長に関わらず透過量を調節するフィルターで、励起光の強さを調節するのに使用。
Excitation/Emission filter特定の波長の光を通すフィルター。
Dichroic mirror特定の波長の光は反射し、それ以外の波長の光は透過させるフィルター。例: 485nmの励起光は反射し、500nm以上の蛍光は通過させる。
水銀ランプ
NDフィルター
フィルター・ミラーユニット
サンプル
対物レンズ
明視野照明
CCDカメラ or 接眼レンズ
Emission filter
Excitation filterDichroic mirror
水銀ランプ
NDフィルター
CCDカメラ
明視野照明サンプルステージ
対物レンズ
接眼レンズ

顕微鏡と周辺機器の起動
4
n 電源をON (PC、CCDカメラ電源、顕微鏡、水銀ランプ)
CCDカメラと水銀ランプは安定するまでに10分程度は時間がかかる。水銀ランプは一度つけたら15分は消さないこと。また、一度消したら10分はつけないこと。水銀ランプは寿命があるので消し忘れに注意。
n ログインAdministrator、パスワードなし。
n MetaMorphを起動CCDカメラが起動されてないないと、警告が出る。解析だけで撮像しないのであればCCDカメラの電源はつける必要はない。
n デスクトップの個人フォルダ内にフォルダを作成しておく
データ管理方法の一例:「日付_実験名 (e.g., 20130510_NPC1-GFP-ExpressionCheck)」フォルダ内にサンプルごとにフォルダを作成し、その中に同じサンプル由来の画像を保存 (個々のファイル名は手動では入力しない)。
PC本体
CCDカメラとその電源
IX70顕微鏡
水銀ランプ
p 顕微鏡の電源は本体右裏側p CCDカメラの電源は後ろの黒いbox

サンプルをステージにセット
5
n サンプルに合わせたステージ台・アダプターを選び、サンプルをセット
3.5cm dish / IWAKI Glass-bottom dish「広穴金属ステージ + 3.5cm dishアダプター」あるいは、「金属ステージなしで3.5cm dishアダプター」を使用する。狭穴金属ステージを用いても良いが、対物レンズを変える際などにレンズが金属ステージと当たりやすいことに注意。
96-well plate (glass-bottom EzView etc.)「狭穴金属ステージ」を使用する。金属ステージなしや広穴金属ステージを用いた場合、96-well plateの端のwellを見る際、プレートの端がステージに乗らず安定しない。
Other dishes (10cm dish / screw cap flask)狭穴金属ステージのみを使用。撮像位置を動かすのに手でdishを動かすことになるので、細かい位置調整は難しい。
Slide glass (with cover glass)チャンバースライド (スライドガラスに取り外し可能なwellが固定されたもので、カバーガラスをのせて使用するもの)やカバーガラス上で細胞培養した場合 (スライドガラスにのせて使用)。狭穴・広穴金属ステージとスライドガラス用のアダプターを使用。
狭穴金属ステージ
広穴金属ステージ
3.5cm dishアダプター

明視野 (位相差) 観察
6
n まずは低倍率 (x4やx10)でピントを合わせる高倍率になればなるほどピントは合わせにくいので、低倍率で合わせてから高倍率レンズに変える。
n 明視野照明は左手前のスライダー・スイッチで調節・ON/OFF可能スライダーで光量0から最大まで調節可能。蛍光撮影時など、一時的に照明を落としたい場合は、スライダーの上のLight OFFスイッチを押すと消せる。もう一度押すと付く。このスイッチを使うと、照明の明るさを変えずにON/OFFできる。OFFではスイッチが点灯する (暗い蛍光観察時にもみえるように)。

対物レンズと位相差観察用リングスリットの選択
7
n 細胞を明視野で見るのに、位相差観察を行う場合が多い。その際、対物レンズに合わせて位相差観察用のリングスリットを選択する必要がある。
細胞は薄く透明なので、光の吸収ではコントラストがつきにくい。そこで、屈折率の違う物体を通過する際に光の位相がずれる現象を利用した位相差観察が用いられる。この方法では、位相のズレをコントラストに変
換するため、照明側と対物レンズ側で対応したレンズスリットを用いる必要がある。対物レンズごとに指定されたリングスリットを用いる (たいてい、もっとも綺麗にコントラストがつくものが指定されたリングスリットである)。
対物レンズ 倍率 開口数 Phase Contrast Immersion 底面の厚さ UV励起UPlanFl 4x 0.13 PhL 可UlanFl 10x 0.3 Ph1 可LCPlanFl 20x 0.4 Ph1 不可LCPlanFl 40x 0.6 Ph2 1.1±0.5 不可LUCPlanFL N 60x 0.7 Ph2 0.1-1.3 可PlanApo 100x 1.4 Ph2 Oil 0.17 可
リングスリット
BF / PhL / Ph1 / Ph2
# BF: リングスリットなし

対物レンズの補正環の調整
8
n 補正環がついている対物レンズでは、サンプル (プラスチックシャーレかカバーガラスか)に応じて、補正環を調整する。
高倍率・高開口数のレンズほど、サンプルとの間のガラス・プラスチックの厚さの影響が大きく、画質が劣化しやすい (ぼやける)。レンズによっては、この厚さの影響を補正する補正環がついている。この補正環の調整を行うかどうかで、画質は大きく変わる。調整はおよその目盛りでサンプルに合わせておおまかに調節し、サン
プルを観察しながら微調整する。なお、通常のカバーガラスやガラスボトムディッシュでは0.17mmの
厚みであり、プラスチックシャーレ (IWAKI培養用)の場合、96-wellプレートで1.5mm、24-wellで1.3mm、6-well/12-wellで1.2mmである。
対物レンズ 倍率 開口数 Phase Contrast Immersion 底面の厚さ UV励起UPlanFl 4x 0.13 PhL 可UlanFl 10x 0.3 Ph1 可LCPlanFl 20x 0.4 Ph1 不可LCPlanFl 40x 0.6 Ph2 1.1±0.5 不可LUCPlanFL N 60x 0.7 Ph2 0.1-1.3 可PlanApo 100x 1.4 Ph2 Oil 0.17 可
プラスチック・ガラス両方OK
プラスチックのみプラスチック・ガラスガラスのみ

光路の切り替え (CCDカメラ / 目 / フィルムカメラ)
9
n 対物レンズから入った光をCCDカメラ側で検出するか、目(接眼レンズ)で見るか、フィルムカメラ側で検出するかを手動で切り替える必要がある。
1. 目で見る場合は、接眼レンズ側の光路を使用。2. 撮影する場合は、CCD側の光路へ切り替える。3. 接眼レンズとフィルムカメラ側の光路は現在使用していない。
右側面の光路切り替えスイッチ
CCDカメラ
接眼レンズ
接眼レンズとフィルムカメラ

接眼レンズの調整 (目の幅と視度調整)
10
n 接眼レンズの間の距離を自分の目の幅に合わせて調整
目の幅は人によって異なるので、接眼レンズの幅も自分の目に合わせて調整する。接眼レンズを覗きながら、見やすい幅に調整すればOK。目の幅があっていないと、両目で覗いても片方の
目の視野が欠けるなど、見にくくなるし疲れる。
n 接眼レンズの右片方についている視度調整環で左右の目の視度差を補正する
左目でまずサンプルにピントを合わせ、次に右目で視度調整環を回してピントを合わせる。これで両目で「楽に」見える。視度差があっていなくても人間の目はそれに対応してピントを合わせることはできるが、疲れる。
視度調整環
接眼レンズ間の距離を調整可能

フィルターセットの選択と蛍光観察
11
n 励起光のON/OFFは、シャッターで制御ステージ下の右側に励起光シャッターがある。観察するときのみ、シャッターを開ける (レバーを手前に引く)。退色を抑えるため、シャッターを開けるのは観察中・撮影中の最小限の時間のみにとどめる。
n 検出する蛍光波長の切り替えは、フィルターターレットで行う。
励起光シャッターの下にフィルターを切り替えるためのターレットがある。現在4種類のフィルターセットが使用可能。Blue励起Green検出のNIBA、Green励起Red検出のWIG、UV励起Blue検出のNUA、そしてbroad UV励起でBlueより超波長を広く検出するWU。
NIBA WIG NUA WUExcitation 470-490nm 520-550nm 360-370nm 330-385nm
band pass filter band pass band pass band passEmission 515-550nm 580nm < 420-460nm 420nm <
band pass long pass band pass long pass多重染色 可 可 可 不可Examples FITC (fluorescein) TRITC DAPI DAPI
GFP rhodamine Hoechst HoechstPI filipin
Open
Close

NDフィルター
12
n 励起光の強度は、NDフィルターで調節。水銀ランプ由来の励起光は、ND(neutral density)フィルターで強度を調節する。サンプルの蛍光が見える範囲で、なるべく弱めの励起光を用いる方が良い。Alexa系の蛍光色素は比較的退色に強いが、フルオレセイン系蛍光団やGFPも強すぎる励起光を使うと観察中に退色する。DansylやNBDなどの蛍光団は一層退色が早く、Show Liveでピントを合わせているうちにみるみる退色する。慣れてきたらShow Liveは使用せず、目でピントを合わせてすぐにCCDカメラに切り替えて撮像するのがよい。
n スライド式のNDフィルターホルダーを抜き差しすることで、NDフィルターあり・フィルターなし・完全シャットアウトの三段階で変更可能。
ホルダーには、左からNDフィルター・フィルターなし・シャットアウトの3段階。「ND25」は励起光を25%にカットするフィルター。他に、ND50やND10、ND5などがある。
n 異なる透過率のNDフィルターを使用する場合は、フィルターホルダーに入っているNDフィルターを交換する。
NDフィルターはフィルターホルダーにのせているだけなので、必要があれば交換する。
NDフィルターホルダー(裏側ランプハウスの手前にある)
NDフィルターフィルターなし
フィルターホルダーを左に引き出した場合
NDフィルターの例(ND25)

油浸レンズとレンズの掃除
13
n 油浸レンズ (100x) を使用する場合は、専用のimmersion oilをレンズの上に一滴のせてからサンプルをのせる。
高倍率レンズには油浸レンズが多い。レンズとサンプルとの間の空間をガラスとほぼ同じ屈折率を持つオイルで満たして光の屈折を抑え、高い開口数 (レンズの集光能力・明るさ)と解像度が得られる。油浸レンズでない通常のレンズの方が扱いは楽 (オイル不要で掃除も不要)ではあるが、同じ倍率であれば、油浸レンズの方が感度よく撮像できる。低自家蛍光イマージョンオイル (Olympus)を使用している。油浸レンズかどうかはレンズに書いてある (油浸であればoilと記載)。当
然のことながら、油浸でないレンズにimmersion oilを使うとうまく撮像できない。
n 油浸レンズ使用後は、かならず専用のレンズクリーナーとレンズクリーニングティッシュでオイルを落とす。
キムワイプはレンズに傷をつけるので絶対に使用しないこと (ステージなどレンズ以外を拭くのはOK)。レンズクリーニングティッシュとしてはWhatman 105、クリーナとしてはHyper Clean 6310を使用している。クリーニングティッシュは、一度オイルがつくいた部分では他の部分は拭かない (汚れが広がる)。クリーナーは無水アルコールやそのエーテル混合液などでも代用は可能であるが、キシレンを含むものや曇り止めを含むメガネ用のものは使わないこと (表面コーティングや部材に悪影響)。

MetaMorphの撮影時の設定
14
n Exposure Time露光時間。目で見て明るいサンプルであれば、100ms-200ms程度から調整。目で見て暗いレベルでは1000-3000msから。Saturationさせない範囲で十分な露光時間を選択する。なお、AutoExposeは遅いのでお勧めしない。
n Show LiveLiveでCCDカメラの画像をモニターできる。ピントや視野の微調整に使用する。
n Binning / Live BinBinningとは、CCDカメラの各ピクセルに相当する検出器 (1392 x 1040 pixels)を複数まとめて一つの検出器のように扱うようなイメージ (正確ではないが)。Binning 2x2では、2x2の4ピクセル分を1ピクセルとして扱い、解像度は下がるがS/N比が上がり、速く撮像できる (ようなイメージで操作上は十分)。撮影時にbinningは基本1のまま。Live Binは
露光時間が長い場合に、2-3程度に設定することで、Show Live画面の更新を速くできる(>500ms以上の露光時間で有用)。

MetaMorphのAutoscale表示について
15
n DisplayタブのAutoscaleにチェックが入っている場合、表示される画像は最大値から最小値までを白から黒として表示されている。
Show Live中にもAcquire後の画像にも適用される。これはデータ自体はスケーリングされておらず、画面の表示上のスケーリング。
Autoscaleされた画像では、シグナルが弱いとバックグラウンドにランダムノイズが見える (蛍光強度が弱いサンプルは、ランダムノイズが相対的に大きく見える)。なお、明視野撮影時にShow Live画面が
真っ黒な場合(ランダムノイズも見えない)は、照明が強すぎる場合である。
Lo%とHi%で蛍光の弱い部分と強い部分をどの程度saturationさせて表示させるかを指定可能。これも表示のみの設定で生データには影響しない。

撮影と手動での保存 (16-bit tiff保存)
16
n Image:の画像名をクリックし、Specified (…..)をクリック。
n Specify Image Nameウィンドウでファイル名を入力
Acquireした画像にとりあえずつく名前。
n Acquire入力したファイル名で画像が撮影される (未保存)。2枚目以降は、「-2」や「-3」が後ろについた名前となる。「acquired-2.tif」や「acquired-11.tif」などの名前になる。欠点は、ファイル名でこれらのファイルを並べ替えると、番号順にならないこと (acquired-1 > acquired-10 > acquired-11 > acquired-2 > acquired-3 …といった順番になる)。
n Save保存先を聞かれるので選択して保存。ファイル名も変更可能。保存先は前回保存した場所になっている。同じサンプルを撮影している場合は変更不要。
(1)(2)
(3)
(4)(5)

MetaMorphで定型ファイル名での保存 (16-bit tiff)
17
n Save w/Sequenceにチェックこれにチェックを入れることで、「Save …..」の動作が変わる。保存先やファイル名は聞かれずに、次のSet Saveで設定した保存先とファイル名の規則に従って保存されるようになる。
n Set Save…から保存先とファイル名の形式を指定
保存先は、例えばC:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/(個人フォルダ)/(日付_実験名)/(サンプル)など。ファイル名を「Image001」とした場合、1枚目はImage001.tifとして指定したフォルダに保存され、2枚目はImage002.tifとして保存される。
n Acquireし、SaveSaveでは最後にAcquireした画像のみが保存される。Acquireした直後の画像は画像名についている「*」マークは、まだ保存されていないことを示している。ここでもう一度Acquireすると上書きされる。一枚AcquireするごとにSaveする。
(1)
「Image001」と入力Image001.tifImage002.tifImage003.tif …と保存
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)(7)

16-bit TIFFと8-bit TIFF16-bit TIFFは蛍光強度を0-65535までの65536段階の階調で記録できる。一方で、8-bit TIFFは0-255までの256階調しか記録できない。また、ファイルサイズが16-bitでは8-bitの倍のサイズになるIX70に付属のCCDカメラは12-bitカメラで
あり、16-bitで保存した場合は、使用可能な階調のうち1/16しか使っていないことになる。そうすると、MacのPreviewなどの一般的な画像表示ソフトウェアでは真っ黒にみえる (コントラストを調整すれば一応見える)。Image Jなどのソフトウェアでは自動で表示するrangeを調整してくれるので、問題なく見れる。これはファイルをブラウジングする際には不
便である。定量的な解析をする予定がなく、パターンだけ見れればいいという程度であれば、8-bitにスケーリングするとブラウジングが楽になり、ファイルサイズも小さくできる。ただし、元データの最小値から最大値までを256階調に圧縮していることには留意すべき。
8-bit TIFFにスケーリングして保存する場合
18
n 撮影した画像(保存されてないもの)を選択n Display > Scale Imageで8-bitにCopyRangeはImage Min/Maxとし、AutoScaleにチェックを入れておく。画像間で同じスケーリングをしたい場合はチェックせずにマニュアルで値を入力する。
n 元の画像を閉じ、新たにできた画像を保存。