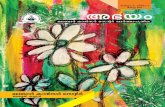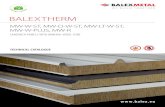mw-mcc.kerala.gov.in/NewsLetter/Abhayam_March2017.pdf · mw- ... a
² æ ³ - m-repo.lib.meiji.ac.jp...C 2 ÞÃçtmMoßo æO{C 2 ÞÃçxzÀ t mw ü ¨qz'Àwå ѱ...
Transcript of ² æ ³ - m-repo.lib.meiji.ac.jp...C 2 ÞÃçtmMoßo æO{C 2 ÞÃçxzÀ t mw ü ¨qz'Àwå ѱ...

【論文】
中小企業管理会計の発展段階モデル
Management Accounting Models based on Life Cycle Stages of SMEs
本 橋 正 美
Masami MOTOHASHI
【キーワード】中小企業の発展段階、株式会社エコムの事例、中小企業の比較尺度、中小企業と中堅企業との区別の必要性、中小企業に適用すべき管理会計技法、管理会計技法による類型化、発展段階による類型化、中小企業管理会計の発展段階モデル
目 次
1.は じ め に2.中小企業の発展段階(1)中小企業の発展段階と株式会社エコムの事例(2)エコムの業績管理
①予算管理システム②原価管理システム
3.中小企業と中堅企業との区別の必要性(1)中小企業の比較尺度(2)中小企業と中堅企業との区別4.中小企業に適用すべき管理会計技法5.中小企業管理会計の発展段階モデル6.む す び
1.は じ め に
本稿で取り上げる「中小企業管理会計の発展段階モデル」については、既に前稿〔14〕で筆者が考察を行っている。また、中小企業の発展段階との関係で「中小企業の業績管理システム」の事例研究として株式会社エコムを取り上げて考察を行った〔15〕。本稿の目的は、筆者が2019年8月28日
中小企業管理会計の発展段階モデル- 73 -

に「中小企業管理会計の発展段階モデル」の論題で日本管理会計学会2019年度年次全国大会において報告した内容を踏まえ、さらに検討を行うものである〔16〕。「中小企業管理会計の発展段階モデル」についての筆者の考え方は、前稿の内容と基本的な部分では変更はない。そのため本稿では、前稿において説明が不十分であった点について、その後の研究成果を追加し考察するものである。そして、本稿では次に、中小企業と中堅企業との区別の必要性について、中小企業の比較尺度、中小企業と中堅企業との区別について考察する。さらに、中小企業に適用すべき管理会計技法について検討し、その場合、管理会計技法による類型化も可能であるが、特に戦略管理会計技法の中小企業への適用については限界があることを明らかにする。それらの考察を踏まえて、中小企業管理会計の発展段階モデルについて考察を行う。発展段階モデルは、業種による2つの分類と、企業のライフサイクルすなわち創業期、成長期、成熟期、衰退期、再生期の5つの発展段階とを組み合わせた10個のモデルに分類する。
2.中小企業の発展段階
(1)中小企業の発展段階と株式会社エコムの事例
中小企業の発展段階の1つの事例として取り上げる株式会社エコム(ECOM:静岡県浜松市北区新都田4-5-6:浜松テクノポリス内:以下、エコムと略称する)〔19〕は、髙梨允氏(創業者)が1985年8月1日に湖南工業団地(浜松市馬郡町)に「株式会社正英バンズ」を設立したのが始まりである。現在のエコムは、業種は先端熱技術総合エンジニアリング、資本金は1億円、従業員数は65名である。現在の代表取締役である髙梨智志氏(2代目)が事業承継を行ったのが2009年であり、会社創業から24年目である。企業のライフサイクルが20年~30年であることから考えても、経営者が2代目へ受け継がれたタイミングは適切な時期であったと考えられる。
他方、エコムでは、管理会計システムすなわち予算管理システムと原価管理システムを導入したのは2016年であり、創業から31年目、2代目の就任から7年目である。管理会計システムの導入時期が決して早い訳ではないが、2代目になってから管理会計システム導入の必要性を強く認識したものと思われる。いわば企業のライフサイクルの2巡目で管理会計システムが導入されたことになる。エコムの管理会計システムとりわけ業績管理は、要約すれば①予算管理システム、②原価管理システムから構成されており、極めてシンプルな管理会計システムであるということができる。なお、図表-2のエコムの売上推移から明らかなように、年間の売上高は20億円程度であり、本社と工場がある浜松を拠点に札幌と関西に支店を開設しているが、未だ ERP の導入は行われていない。この点については、中小企業と中堅企業との区別の基準として年間売上高が30億円~50億円を境にそこから上か下かによって区別することができるが、それに関しては後述する。
会計論叢第15号 - 74 -

(2)エコムの業績管理
エコムの管理会計システムとしては、月次の予算管理システム、および受注製品ごとの原価管理システムが導入されている。受注製品は、一品一様(注文製品ごとに異なる仕様の製品)であるため、受注品は、それぞれ注文製品ごとに個別の原価計算・原価管理システムによって管理されている。以下では、エコムの管理会計システムとしての予算管理システムおよび受注製品ごとの原価管理システムについて明らかにする。
①予算管理システム
エコムの予算管理システムでは、部門別の月次→四半期→半期→年次のそれぞれの期間で管理が行われ、そして、予算管理システムは、短期利益計画(期別の経営計画)および中期経営計画と連
中小企業管理会計の発展段階モデル- 75 -
図表-1 エコムの会社の沿革(抜粋)
出所:www.ecom-jp.co.jp(注)「2016年に予算管理システム、原価管理システムを導入」の箇所は聞取調査から筆者が加筆している。
1985 2004 20 2009 2 2015 30 2016 8,800 1 2016 2017 2018
図表-2 エコムの売上の推移
出所:www.ecom-jp.co.jp

携させている。その業績管理においては、月次および四半期での事業分野別の PDCA サイクルが行われ、経営方針の数値目標については、リアルタイムで数値の管理が行われている。予算編成に際しては、各部門長が部門の計画を立案し、会社全体の予算との調整は役員会で決裁する。また、短期利益計画の損益分岐点分析に関しては、直接原価率というエコムの1つの KPI を用いて、その数値を月次で追っている。直接原価率とは、P/L の製造原価の中の材料費、部品購入費、外注費などで外部に支払われる金額である。換言すれば、直接原価率とは売上高対仕入外注比率であり、直接原価率の目標は対売上高で55%以下を目指している。直接原価率は別の観点から見れば、付加価値概念のうち控除法(中小企業庁方式)における付加価値率で説明することができる。すなわち、外注加工費の割合を可能な限り下げることができれば、結果として付加価値率は高くなるのである。
エコムでは、少ない人数でオペレーションしている一方で、可能な限り内製率を上げれば、その分粗利益が増加するので、内製率を上げることに全社で取り組んでいる。設計・購買・製造側からは1%のコストダウンにより1,000万円強の粗利益の改善が得られ、営業側からは1%の高い価格での契約や受注増により1,000万円強の粗利益の改善が得られることになる。こうした製造や販売などの部門のわずか1%の努力で粗利益が2,000万円増加するため、全社の KPI とすることで粗利益改善を目指しているのである。直接原価率という KPI は、管理会計では一般的には使われていないが、非常に分かり易い指標であり、全社員にこの KPI の目標値を達成するように情報共有ができていることは優れた管理指標であるということができる。
エコムは、熱処理関係の装置の製造を行ういわば設備業という側面上、月次での予算数値のバラツキは致し方ないところもあるため、四半期での差異分析を重視している。環境変化への対応については、例えば、材料費の値上がり(高騰)などの大きな環境変化が期中にあれば、諸経費等の値上げ交渉することはあるが、あまり実施したことはない。期中に変更するのは、予算の目標値に関して半期で業績と照らし合わせて再編成することがある。
注文の引受可否の意思決定は、営業部門主導の商談の先行管理を参考にして、6か月先ぐらいまでの引合いについて部門長会議で話合いが行われる。最終の意思決定は売上責任のある営業部門が決定するが、製造側の工場負荷状況と利益率を鑑みて最終決定が行われている。これは、毎週開かれている営業・設計・製造などの各部門長会議で話し合われている。各部門の設備投資計画は、各部門長からの予算申請をもって、役員会で決議し、全社的な計画は社長を筆頭とした役員会ですべて合議により決定されている。
販売費・一般管理費については、可能な限り無駄なものは使わない方針で、売上総利益を上げて、それとの対比で、その分販管費も増やすことを意識している。それは、やはり従業員の給与や待遇を上げたいからである。基本的には、販管費を上げた分は粗利益でカバーする考えである。粗利益40%以上、対売上高で販管費20%以上ぐらいが当面の目標であるとされる。
②原価管理システム
エコムにおける受注製品は、一品一様(注文製品ごとに異なる仕様の製品)であるため、受注品は、それぞれ注文製品ごとに個別の原価計算・原価管理が行われている。具体的には株式会社テクノアの TECHS-S(テックス・エス)という個別受注型の受注システムで原価管理を行っている。TECHS-S とは、テクノア社により個別受注型の機械・装置業向けに開発された中小中堅企業のための生産管理システムである。TECHS-S の導入効果についてテクノア社によれば、 進捗・納期管理の強化と原価低減効果、利益体質(会社の品質)への改善と継続効果、OA(オフィス・オート
会計論叢第15号 - 76 -

メーション)効果があるとされている。すなわち、TECHS-S の導入により PDCA や QCD が可能となり、① OA 効果による事務改善、②原価管理、納期管理、負荷調整による現場改善、③利益体質改善、営業力強化、社員のやる気向上などに役立つと思われる。エコムでは、TECHS-S を用いた受注製品の試算は設計部が行い、受注したら材料費・外注費・設計費・組立費などの予算書を作成して、リアルタイムで予算書と照らし合わせた原価把握ができるシステムとなっている。
エコムにおける原価管理は、トータルでの原価管理が中心である。そして、個別受注型の製品製造であるため、部品や製作の標準化を進めていて、誰が設計しても同じ部品、同じ設計になることで最終的な原価低減を目指している。標準化することにより原価改善を推進し、購買部門の業務における交渉努力もある。リードタイムの管理については、営業部門の先行管理を参考にして工場の技術管理課が行っている。限られた工場スペースで効率的な受注活動と工程管理を目指しており、現在は Excel ベースでの工程管理を行っているが、将来は TECHS-S と連携できるシステムを導入予定である。また、製品価格決定のために直接原価率により事業別に管理している(製品は60%、メンテナンス工事は40%など)。当然のことながら、直接原価率の低い案件を優先して受注を行っている。
3.中小企業と中堅企業との区別の必要性
(1)中小企業の比較尺度
長寿企業(老舗企業)の比較尺度に関しては、神田良氏によれば長寿企業(老舗企業)の比較は、以下の5つの尺度で行うべきであると考えている〔2〕。
①年齢(創業からの年数)②継承(何代目)③資本金(金額)④従業員数⑤売上高他方、安田武彦氏によれば企業のライフサイクルの比較は、以下の4つの尺度で行うべきである
と考えている〔17〕。①付加価値(額)②業績状況(収支状況)③売上高成長率④従業者数成長(増加)率
長寿企業(老舗企業)の比較尺度に関する上記の何れの見解も、確かに現実的かつ実務的な比較尺度であると思われる。創業からの経過年数、資本金額や売上高などの財務業績や従業員数などの数値を用いれば、中小企業の発展段階を4~5つ程度の尺度で簡便に比較できると思われる。さらに、業種・業態や経営者の属性(いくつかの項目に絞って)、あるいは経営分析の主要項目などを追加すれば、より詳細な比較・分析が可能となる。上記の長寿企業(老舗企業)の比較尺度を参考にして、中小企業の比較尺度をあげれば、以下のような項目にまとめることができる〔13〕。
①業種・業態
中小企業管理会計の発展段階モデル- 77 -

②事業規模・業績:売上高(あるいは資本金、付加価値額、従業員数など)③発展段階:ライフサイクル(創業からの経過年数:成長率)
(2)中小企業と中堅企業との区別
財務省の「法人企業統計調査年報」では、資本金の金額により企業を分類している。すなわち、資本金「10億円以上」の企業を大企業、「1億円以上10億円未満」の企業を中堅企業、「1,000万円以上1億円未満」の企業を中小企業、「1,000万円未満」の企業を個人企業(零細企業)として分類している〔5〕。
これに対して、日本銀行の「企業短期経済観測調査(短観)」では、以下のように企業を従業員数によって大企業、中堅企業、中小企業に分類している〔9〕。
図表-3 日本銀行における企業の分類
出所:日本銀行の「企業短期経済観測調査」から筆者が作成。
1,000 1,000 1,000 300 999 100 999 50 999 50 299 20 99 20 49
一方で、大企業、中堅企業、中小企業の分類に関して、会社法第2条第6号では、大会社を「資本金5億円以上または負債200億円以上」と定めているので、「資本金5億円未満かつ負債200億円未満」が中小会社となる。また、法人税法(租税特別措置法関係通達第42条の7第5項)では「資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人」が大規模法人となっており、それ以外は中小法人となる。
そして、中小企業基本法では、中小企業を業種分類によって以下の定義に分けられている。すなわち「中小企業基本法」(1963年制定:昭和三十八年七月二十日法律第百五十四号、最終改正:平成二八年六月三日法律第五八号)における中小企業の定義は、図表-4のように業種、資本金または従業員数によって分類されている〔6〕。業種は、製造業その他、卸売業、サービス業、小売業に分類されている。資本金または従業員数は、製造業その他が3億円以下、300人以下、卸売業が1億円以下、100人以下、サービス業が5,000万円以下、100人以下、小売業が5,000万円以下、50人以下となっている。また、中小企業のうち小規模事業者は、従業員数のみによる分類であり、製造業その他が20人以下、卸売業、サービス業、小売業が5人以下となっている〔6〕。
会計論叢第15号 - 78 -
図表-4 「中小企業基本法」における中小企業の定義
出所:『中小企業白書 2019年版』www.chusho.meti.go.jp
3 300 20 1 100 5
5,000 100 5 5,000 50 5

他方、近畿経済産業局の『平成25年度 関西地域における中堅製造企業の実態調査(報告書)』によれば、年間売上高100億円以上1,000億円未満を中堅企業と定義している。同様に大阪市経済局による報告書『大阪の中堅企業の現状とポテンシャル:中堅企業実態調査結果より』では、中堅企業を年間売上高で「50億円以上100億円未満」、「100億円以上300億円未満」、「300億円以上500億円未満」の3つに分類している〔3〕。
林總氏は、中小企業と中堅企業とを区別する年間売上高を30億円とされている。すなわち、年間売上高が30億円以上の企業を中堅企業とし、30億円未満の企業を中小企業として分類するのである。林總氏の見解は、これまで国内外の企業約200社に対して原価計算システム・管理会計システムの設計導入、ERP システムの導入、ビジネス・コンサルティングを行ってきた経験から導かれたものである。
さらに、ノークリサーチ社による「中堅・中小向け ERP のシェア動向」に関する調査では、中小企業を年間売上高により4つの範疇すなわち「5億円未満」、「5億円以上~10億円未満」、「10億円以上~20億円未満」、「20億円以上~50億円未満」に分類している。また、中堅企業を年間売上高により3つの範疇すなわち「50億円以上~100億円未満」、「100億円以上~300億円未満」、「300億円以上~500億円未満」に分類している〔10〕。ノークリサーチ社による中小企業と中堅企業との分類は、ERP を導入する必要があるか否かの基準を年間売上高50億円としていると見ることができるのである。
上記のように、中小企業、中堅企業、大企業を分類する基準ないし尺度には資本金の金額、従業員数、売上高規模などがあるけれども、とりわけ中小企業と中堅企業との区別について筆者は売上高基準を採用し、管理会計システムが情報システムであること、また管理会計システムが ERP と密接に関係していることを考えて、年間売上高50億円を中小企業と中堅企業との区別の基準とすることにする。もちろん、年間売上高20億円~40億円ぐらいの中小企業で、業種・業態、あるいは事業の展開の仕方によっては ERP を用いて業務管理を統合化する必要がある可能性は十分にあるといえる。
筆者が売上高基準を採用する理由は、資本金の金額は創業当初あるいは、事業を拡大していく中で資本金の増額(増資)を行うことになるが、そのことが必ずしも売上高ないし事業規模に比例しているとはいえないからである。また、従業員数による企業の分類も従業員数すなわち社員数は業種によってばらつきがあることと、また、当該企業の業務量に対して正社員と派遣社員あるいはパートタイマーやアルバイトの人数との比率によって、やはり従業員数の多寡が必ずしも売上高ないし事業規模に比例しているとはいえないからである〔14〕。
中小企業管理会計の発展段階モデル- 79 -
図表-5 中小企業の企業数と従業者数の現状
出所:『中小企業白書 2019年版』www.chusho.meti.go.jp この資料は総務省「平成28年経済センサス-基礎調査」が再編加工されたものである。
1.1 0.3 1,459358 99.7 3,22053 14.8 2,176305 85.2 1,044

中小企業の企業数と従業者数の現状については図表-5のとおりである。上記の数値は2016年(最新)の数値であり、その2年前の2014年と比較すると中小企業は23万者減少している。そして、CRD データによる中小企業の売上高の分布(2016年度:最新)を見ると、売上高3~4千万円の企業が最も多く、売上高1億円以下の企業が全体の50%強、売上高10億円超の企業が全体の9%弱となっている〔1〕。
4.中小企業に適用すべき管理会計技法(管理会計技法による類型化)
わが国で一般的に利用されている原価計算および管理会計技法について整理すれば図表-6の原価計算・管理会計技法のとおりである。原価計算には、実際原価計算(個別原価計算・総合原価計算)、標準原価計算、直接原価計算があり、一方、管理会計には、経営分析、経営計画(長期経営計画・中期経営計画・短期利益計画)、予算管理、原価管理、資金管理、ABC・ABM、BSC、ライフサイクル・コスティング、品質原価計算、差額原価収益分析、投資計画の経済性計算がある。これらの原価計算・管理会計技法のうちどの技法を利用するかは、中小企業の経営者には任意のことであり、必要であれば利用することは可能である〔14〕。後述する中小企業管理会計構築のための基礎要件のところで説明するが、筆者は図表-6の原価計算・管理会計技法の中でとりわけ利益計画(長期・中期・短期)の策定・実行、予算管理・直接原価計算(部門別・セグメント別)の実施、原価管理(特に固定費管理)の実施が重要であると考えている〔11〕。
図表-6 原価計算・管理会計技法
出所:筆者が作成。
ABC ABM BSC
なお、図表-6の原価計算・管理会計技法における戦略管理会計の技法、すなわち⑨ ABC・ABM、⑩ BSC、⑪ライフサイクル・コスティング、⑫品質原価計算の中小企業への適用については限界があると思われる。その理由は、管理会計技法を実際に利用するためには情報システムすなわちソフトウェアを導入し、自社で運用するかシステム・インテグレータに運用を委託することになる。あるいはクラウド型の月額利用料を支払うサブスクリプション方式を利用することになる。何れの方
会計論叢第15号 - 80 -

法を利用するにしてもコスト・ベネフィットに見合った利用目的や導入効果が得られなければ意味がないといわざるを得ないのである〔14〕。
図表-7 戦略管理会計技法の主目的
出所:筆者が作成。
ABC ABM BSC
中小企業に適用すべき管理会計技法については、管理会計技法による類型化ができない訳ではないが、中小企業庁が公表している「中小企業実態基本調査<業種分類表・国地域分類表>」下記の図表-8「日本標準産業分類一覧における産業大分類および産業中分類」を見ても、極めて多種多様であり、管理会計技法を業種・業態別に分類し、適用の可否を論じることはかなり難しいと思われる。
中小企業庁では、この「中小企業実態基本調査<業種分類表・国地域分類表>」について中小企業基本法第10条における「政府は、中小企業の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない」との規定に基づき、平成16年度から毎年、中小企業実態基本調査を実施している。最新の調査報告書は、中小企業の平成29年度決算等に関する回答を集計し、まとめられたたものである〔7〕。この調査は、中小企業の更なる発展に寄与する基礎資料とすることを目的として、わが国の中小企業の財務面や経営面の基礎的データを産業別・規模別に把握していて、政府は、中小企業政策を的確に企画・立案・実行するために活用しているとされる。中小企業施策の企画・立案などを行う各地方公共団体では、わが国の中小企業の実態の把握や財務分析などに、また、産業界や各企業においては、財務分析や経営判断をする際に、本調査を活用することが有用であるとする。そして、この調査は、日本標準産業分類(平成25年10月改定、平成26年4月1日施行)のうち、以下の産業大分類および産業中分類を対象に実施しているとする。業種分類は、図表-8の日本標準産業分類一覧における産業大分類および産業中分類のとおりである。産業大分類のアルファベットは、D、E、G、H、I、K、L、M、N、R の10個である。また、産業中分類には、06から92までの2桁の数値が割り当てられ、その数値は分類ごとに連続番号が付されているが、分類が異なれば番号が続いている訳ではない。そして、分類における従業者の規模別分類は、法人企業
(常用雇用者数5人以下、6~20人、21~50人、51人以上の4区分)と個人企業に区分されている〔7〕。
中小企業管理会計の発展段階モデル- 81 -

さて、次に論点を中小企業管理会計構築のための基礎要件を取り上げる。この点に関して筆者は、少なくとも以下の4つの点が重要であると考えている〔11〕。
①経営者自身が管理会計の基礎知識とりわけ原価・利益概念の知識を持つこと(税理士任せにしない)。
②利益計画(長期・中期・短期)の策定・実行。③予算管理・直接原価計算(部門別・セグメント別)の実施。④原価管理(特に固定費管理)の実施。
上記①の点は、経営者自身が原価・利益概念すなわち管理会計の基礎知識を持ち、税理士任せにしてはいけないということである。中小企業経営者が経理業務を税理士に依頼してはいけないということではなく、任せっ切りにしてはいけないということであって、経営者自身が管理会計の知識を持って自社の現状を計数により詳細に把握することである。②の利益計画(長期・中期・短期)の策定・実行は必ず行わなければならない必須事項であるといえる。長期・中期・短期の利益計画
会計論叢第15号 - 82 -
図表-8 日本標準産業分類一覧における産業大分類および産業中分類
出所:日本標準産業分類一覧から筆者が作成。
D 60 07 ( ) 08
E
09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 ( ) 19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32
G 37 38 39 40 41
H 43 44 45 47 48 49
I
50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61
K 68 69 70
L 72 ( ) 73 74 ( )
M 75 76 77
N 78 79 80
R ( ) 88 89 90 ( )91 92

を持たなければ、時系列的な目標管理ができていない、あるいは目指すべき利益目標が定まっていないことになってしまう。利益計画(長期・中期・短期)の策定・実行は、必要不可欠で極めて重要な作業である。③の予算管理・直接原価計算(部門別・セグメント別)は可能な限り行うべきである。また、中小企業が優れた管理会計システムを構築するためには、上記③の点に関していえば、予算管理と共に直接原価計算による原価・利益計算が必要である〔11〕。
5.中小企業管理会計の発展段階モデル(発展段階による類型化)〔14〕
中小企業の発展段階に関する諸説すなわち中小企業も含めた企業のライフサイクルに基づき中小企業管理会計の発展段階モデルについて考察する。わが国の「中小企業基本法」における中小企業の定義では、中小企業(小規模事業者も含む)を業種によって資本金や従業員数で分類しているけれども、筆者は「Ⓐ製造業」と「Ⓑ卸売業・サービス業・小売業」の2つに分類する。その理由は、いうまでもなく、「製造業」には製品の製造という生産管理のプロセスがあり、その情報を測定するには原価計算システムが必要であるからである。もう1つの「卸売業・サービス業・小売業」では、原価計算を行う部分もあるが、「製造業」における原価計算と比較すれば、データの複雑性や詳細度、情報量の点から見れば製造業ほどではないといえる。
図表-9 中小企業管理会計の発展段階モデル
出所:筆者が作成。
図表-9の中小企業管理会計の発展段階モデルにおいて、筆者は、管理会計を中小企業の発展段階と企業のライフサイクルに従って分類する。そこでの管理会計システム(実績の測定である財務会計と業績の診断・評価である経営分析も含む)は、主として業績管理会計の技法を取り上げることにする。管理会計技法の一方の意思決定会計の技法については、原価の固変分解を行い、直接原価計算手法による利益計画での損益分岐点分析や事業別・セグメント別管理システムを実現すれば、差額原価収益分析や投資計画の経済性計算まで実施することは可能である。以下で各期において導入すべき管理会計技法や管理会計システムについて説明する。なお、①創業期以降、②成長期、③成熟期、④衰退期、⑤再生期への移行について、その移行があったかどうかの判断基準のようなものはないと理解している。考えられる判断基準としては、売上高や利益額が増加ないし減少している、あるいは、それらの金額が頭打ちになっているなどの状態で判断できると思われるのである。
以下の各期において、既述の図表-6に示した原価計算・管理会計技法のどの技法を利用するかは、中小企業経営者にとっては、まったく任意であり、必要であれば利用することが望ましいことはいうまでもない。①創業期
実績の正確な測定・管理(経営分析も含む)→財務会計システム・原価計算システムの導入②成長期
予算管理・原価管理の実施→予算管理システム・原価管理システムの導入事業別・セグメント別管理→直接原価計算による事業別・セグメント別管理システムの導入
中小企業管理会計の発展段階モデル- 83 -

③成熟期必要に応じて ERP・BSC などの導入④衰退期
この時期は、当該企業の最初のライフサイクル(20~30年程度)を経て、事業承継や、これまでの経営体制・経営基盤の再確認と整備に注力する必要があるので、管理会計システムの再構築を無理に行う必要はないと考える。その理由は、中小企業は大企業に比べて利用できる経営資源すなわち人、金、物、情報(情報システム)に制約があり、管理会計システムの導入・運用についても制約があるからである。特にこの衰退期に管理会計システムの再構築を行うことには限界があるであろう。むしろ、上述の中小企業管理会計の再構築のため中小企業経営者は、まず製品やサービスの品質あるいは経営品質を高めるための努力を行うべきである。そして、取引先との交渉力(価格、品質、納期)や顧客満足、あるいは従業員満足を高める努力が必要である。さらに5S や5ゲン主義、カイゼン活動、TQC、TQM などの経営管理・現場管理の基礎的な条件整備に積極的に取り組む必要がある〔11〕。⑤再生期
上記の④衰退期を脱することができれば、それまでにできなかった、あるいは不十分であった管理会計システムの導入に取り組むべきである。すなわち、この再生期に改めて以下の点に注力すべきである。
実績の正確な測定・管理(経営分析も含む)→財務会計システム・原価計算システムの再構築予算管理・原価管理の実施→予算管理システム・原価管理システムの再構築事業別・セグメント別管理→直接原価計算による事業別・セグメント別管理システムの再構築必要に応じて ERP・BSC などの再構築なお、上記の5つの発展段階は、必ずこの5つの段階があるとは限らず、創業後、成長期、成熟
期に至らずに市場から撤退してしまう企業もあるであろうし、また、衰退期が必ずあるともいえない。さらに衰退期の後に必ず再生期があるとは限らないのである。中小企業経営者は自社が将来、優良企業・長寿企業になるべく存続・成長・発展を目指して経営を行うべきである。
筆者は、上記のような中小企業管理会計の発展段階モデルを、まず「Ⓐ製造業」と「Ⓑ卸売業・サービス業・小売業」の2つに分類し、そして、その分類を①創業期、②成長期、③成熟期、④衰退期、⑤再生期の各時期と組み合わせてⒶ①~⑤の5つとⒷ①~⑤の5つで、合わせて10個のモデルに分類することにする。⑤再生期の後のことは図表-9の中小企業管理会計の発展段階モデルでは示していないが、中小企業経営者は、当該企業が将来、優良企業・長寿企業になるべく存続・成長・発展を目指して経営を行うことは重要なことである。実際には、中小企業が時代の流れの中で環境変化に適合できずに倒産してしまうこともあるであろうし、また、再生を図ることが口でいうほど簡単なことではないと思われるけれども、困難を克服し、継続して努力することが肝要であると思われる。
上記のように筆者は、①創業期においては、実績の正確な測定・管理(経営分析も含む)を行うために、財務会計システムを、また、製造業ではそれに加えて原価計算システムを導入し、実績の測定を正確に行うことに注力すべきであると考える。次の発展段階である②成長期においては、予算管理システムと原価管理システムの導入、および可能であれば事業別・セグメント別管理を、すなわち直接原価計算による事業別・セグメント別管理システムの導入に力を入れるべきであると考
会計論叢第15号 - 84 -

えるのである。この段階で、いわば本格的な管理会計システムの導入を行うことになる。さらに、③成熟期においては、必要であれば ERP や BSC などの導入を実行することになる。ERP それ自体は管理会計そのものという訳ではないが、業務管理を統合し、管理会計情報を用いてリアルタイムで当該企業の経営管理・業務管理を行うには不可欠な情報システムであるといえる。
なお、図表-9の中小企業管理会計の発展段階モデルにおいて筆者は、①創業期、②成長期、③成熟期、④衰退期、⑤再生期の5つの発展段階(時期)を示している。『中小企業白書 2019年版』で、わが国の中小企業における開廃業率の推移を見ると、2017年度の
データであるが開業率は全業種平均で5.6%、また、廃業率は全業種平均で3.5%となっており、この数値は中小企業のライフサイクルと生産性に関係があるといえる。このような、わが国の中小企業における開廃業率の数値は、筆者が提案する中小企業管理会計の発展段階モデルについても多少なりとも関係があると思われる。しかしながら、筆者が提案する中小企業管理会計の発展段階モデルは、いわば理論モデルであるので、上述のように5つの発展段階が実情とは異なることがあることはやむを得ないと考えるのである。また、物事を分類する場合、複雑かつ難解な分類を行うよりも、なるべくシンプルで明快な方が望ましいことから、上記のような合計で10個のモデルに分類したのである。そして、上記の各期に示した管理会計システムは、実際には情報システムであるので、そのシステム導入にはパッケージ・ソフトウェアを利用する方法やクラウド型の情報サービスを利用する方法などを選択することになる。
6.む す び
本稿においては、まず中小企業の発展段階に関連して「中小企業の業績管理システム」の事例研究として株式会社エコムを取り上げて考察を行った。そして本稿では、筆者が「中小企業管理会計の発展段階モデル」の論題で学会発表を行った内容を踏まえ、さらに検討を行った。次いで、中小企業と中堅企業との区別の必要性について、中小企業の比較尺度、中小企業と中堅企業との区別について考察した。さらに、中小企業に適用すべき管理会計技法について検討を行い、その際、管理会計技法による類型化も可能であるが、特に戦略管理会計技法の中小企業への適用については限界があることを明らかにした。それらの考察を踏まえて、中小企業管理会計の発展段階モデルについて考察を行った。発展段階モデルは、業種による2つの分類と、企業のライフサイクルすなわち創業期、成長期、成熟期、衰退期、再生期の5つの発展段階とを組み合わせた10個のモデルに分類した。筆者が考える中小企業管理会計の発展段階モデルは、「Ⓐ製造業」と「Ⓑ卸売業・サービス業・小売業」の2つに分類し、そして、その分類を①創業期、②成長期、③成熟期、④衰退期、⑤再生期の各時期と組み合わせてⒶ①~⑤の5つとⒷ①~⑤の5つで、合わせて10個のモデルに分類した。このような中小企業管理会計の発展段階モデルは理論モデルであるため、この発展段階モデルの中小企業管理会計実務への適用には一層の検討が必要であり、その検討については今後の課題とする。
(参考文献・HP アドレス)〔1〕一般社団法人 CRD 協会『平成30年度財務情報に基づく中小企業の実態調査に係る委託事業』
2019年3月。なお、CRD 協会は、わが国の財産である CRD(Credit Risk Database)について中小企業庁から委託を受け、中小企業の成長可能性を評価する「成長期待値評価モデル」に関する報告書を作成し、また、モデル搭載ツール(Growth Four)を開発している。これらの資
中小企業管理会計の発展段階モデル- 85 -

料は、経済産業省の HP に公開されている。〔2〕神田良・清水聰・北出芳久・岩崎尚人・西野正浩・黒川光博『企業不老長寿の秘訣:老舗に
学ぶ』白桃書房、2000年。〔3〕近畿経済産業局『平成25年度 関西地域における中堅製造企業の実態調査(報告書)』2014年。
www.kansai.meti.go.jp〔4〕古畑友三『5ゲン主義入門』日科技連出版社、1996年。〔5〕財務省『法人企業統計調査』www.mof.go.jp〔6〕中小企業庁『中小企業白書 2019年版』www.chusho.meti.go.jp〔7〕中小企業庁『平成30年中小企業実態基本調査』2019年。www.chusho.meti.go.jp, www.e-stat.
go.jp〔8〕中部産業連盟編『新まるごと5S 展開大事典』日刊工業新聞社、2016年。〔9〕日本銀行『企業短期経済観測調査』www.boj.or.jp〔10〕(株)ノークリサーチ「2018年中堅・中小向け ERP のシェア動向とユーザ企業が抱く課題:
ニーズの関連」2018年10月。www.norkresearch.co.jp〔11〕本橋正美「中小企業管理会計の特質と課題」『会計論叢』(明治大学)第10号、2015年2月、
51-69頁。〔12〕本橋正美「中小企業管理会計の事例研究アプローチ」『会計論叢』第12号、2017年3月、29-
47頁。〔13〕本橋正美「中小企業の発展段階と管理会計システム」『会計論叢』第13号、2018年3月、75-
93頁。〔14〕本橋正美「中小企業管理会計システムの類型」『会計論叢』第14号、2019年3月、87-110頁。〔15〕本橋正美「第8章 中小企業の業績管理システム:株式会社エコムの事例」(水野一郎編著『中
小企業管理会計の理論と実践:メルコ学術振興財団研究叢書11』中央経済社、2019年、129-139頁所収。)
〔16〕本橋正美「中小企業管理会計の発展段階モデル」日本管理会計学会2019年度年次全国大会(専修大学)、2019年8月28日。
〔17〕安田武彦「『企業の一生の経済学』とその課題」『中小企業のライフサイクル:日本中小企業学会論集㉖』2007年8月、30-41頁。
〔18〕山形陽一『大阪の中堅企業の現状とポテンシャル:中堅企業実態調査結果より』大阪市経済局、2010年5月。www.pref.osaka.lg.jp
〔19〕www.ecom-jp.co.jp 2019年11月22日アクセス。
会計論叢第15号 - 86 -