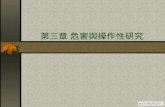Qualitative Research 質性研究 / 定性研究 中央大學. 資訊管理系 范錚強 mailto: [email protected] 2010.05 12.
監修 - ibd-nandarou.jp · 25.1 25.2 38.3 7.8 3.6 厚生労働科学研究費補助金...
Transcript of 監修 - ibd-nandarou.jp · 25.1 25.2 38.3 7.8 3.6 厚生労働科学研究費補助金...
25.1
25.2
38.3
7.8
3.6
厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等政策研究事業 「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」(鈴木班) 一目でわかるIBD 炎症性腸疾患を診察されている先生方へ 第二版 より作図
不明
20
(%)
10
00〜4
5〜9
10〜14
15〜19
20〜24
25〜29
30〜34
35〜39
40〜44
45〜49
50〜54
55〜59
60〜64
65〜69
70〜74
75〜79
80〜
潰瘍性大腸炎の推定発症年齢
難病情報センターホームページ(2018年7月現在)から引用
1615
特定医療費 (指定難病 )受給者証所持者数
167,872人
厚生労働省 衛生行政報告例 特定疾患(難病)医療受給者証所持者数、登録者証所持者数より作図* 2010年度のデータには、東日本大震災の影響により、宮城県及び福島県が含まれていません
*
潰瘍性大腸炎の患者数を厚生労働省特定疾患医療受給者証所持者数でみると、平成28年度で167,872人でした。2015年以降に減少した理由は、2015年より一部の軽症者が同医療受給者証の発行対象から外れたためです。世界的にみると欧米諸国を中心に患者数が多く、北欧やアメリカの白人、ユダヤ人に特に多いといわれています。
持続性または反復性の粘血便、血便が主で、下痢、腹痛、発熱、体重減少、嘔気・嘔吐、貧血などを伴います。 症状が強い活動期と、症状がほとんどない寛解期があります。長い期間の経過には、症状の移りかわりのタイプから、下表のように区別されます。 下表の病型のうち、再燃寛解型が最も多くなっています。
〈目 的〉 病変の部位、分布、炎症の状態などを知るために行います。
〈方 法〉 バリウムと空気を肛門より注入して大腸のX線撮影を行います。下剤を服用いただく時の患者さんへの注意も忘れずに(トイレが頻繁になる等)。
〈目 的〉 大腸の病変を観察するために行います。
〈方 法〉 肛門より内視鏡を腸内に挿入して観察します。
〈注意点〉・ 患者さんの緊張をほぐし、安心して検査を受けられる環境を作ります。・下剤を服用いただく時の患者さんへの注意も忘れずに(トイレが頻繁になる等)・抗凝固剤、鉄剤、抗アレルギー剤など服用の有無を確認し、服用の中止を指示して下さい。
1) 5-アミノサリチル酸製剤
症状により、下記のような薬剤が選択されます。
2) 副腎皮質ホルモン剤(ステロイド)
3) 免疫調節剤
4) 生物学的製剤
分 類
5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA製剤)
サラゾスルファピリジン(経口・坐剤)メサラジン(経口・坐剤・注腸・顆粒)
プレドニゾロン(経口)
ブデソニド(注腸フォーム)
シクロスポリン(点滴)*
メルカプトプリン(経口)*
インフリキシマブ(点滴)アダリムマブ(皮下注)
ゴリムマブ(皮下注)
タクロリムス(経口)
アザチオプリン(経口)
ベタメタゾン(坐剤)**
リン酸ベタメタゾンナトリウム(注腸)
プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム(注腸)
プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(点滴)
副腎皮質ホルモン剤(ステロイド)
免疫調節剤
生物学的製剤
薬剤 (投与方法) 軽 症 中等症 重 症 劇 症
* : 保険適用外 ** : 直腸炎型のみ ▲ : 難治例その他、 整腸薬、 抗生物質、 漢方薬なども用いられています。
厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等政策研究事業 「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」(鈴木班)平成29年度総括・分担研究報告書 平成30年3月 より引用改変
治療回数:一連の治療につき10回まで(劇症の方は11回まで)保険適用
指定難病医療費助成の認定をされている患者さんは、顆粒球吸着療法を受けることによる、特別な自己負担は発生しません。
顆粒球吸着療法は、血液を一旦、体外に連続的に取り出し、白血球の中の特に炎症に関与している顆粒球・単球を選択的に除去する医療機器(顆粒球吸着器)に通し、その後血液を体内に戻すものです。
(注)このイラストはイメージです。
潰瘍性大腸炎は「難病の患者に対する医療等の法律」において指定難病に定められています。申請手続きを行い認定されると、薬物療法や顆粒球吸着療法などの治療に対して公費による助成が受けられます。なお、認定基準につきましては、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所等)で確認して下さい。患者さんが加入している医療保険上の世帯の収入に応じて、医療費の自己負担限度額
(下記表)が設定されています。
*1 高額かつ長期とは月ごとの医療費総額が50,000円を超える月が年間6回以上ある方です(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が10,000円を超える月が年間6回以上)。
*2 人工呼吸器等装着者とは人工呼吸器又は体外式補助人工心臓を装着している方で、厚生労働省が定めた基準を満たす方です。
※1指定難病の医療費の助成を受けることができるのは、都道府県からの指定を受けた指定医療機関で行われ た医療に限られます(病院、薬局、訪問看護ステーションいずれも同様)。
※2臨床調査個人票をもとに審査した結果、申請した疾病の診断基準は満たすが重症度分類(症状の程度)は満たさなかった方で、申請した月以前の12ヶ月間(発症1年未満の場合には発症月から申請月の間)において、申請した疾病にかかった医療費等の総額(10割分)が33,330円を超える月が3ヶ月以上ある方は軽症かつ高額の対象となります。
自己負担限度額 (月額) (単位:円)
月額自己負担限度額 (外来+入院+薬代+訪問看護の費用)
患者負担割合:2割
入院時の食費 全額自己負担
階層区分の基準
〔( )内の数字は、夫婦2人世帯の場合における年収の目安〕
市町村民税課税以上約7. 1万円未満
(約160万円~約370万円)市町村民税
7. 1万円以上 25. 1万円未満(約370万円~約810万円)
市町村民税非課税(世帯)
本人年収~80万円
本人年収80万円超~
階層区分
生活保護
低所得Ⅰ
低所得Ⅱ
一般所得Ⅰ
一般所得Ⅱ
上位所得
0̶
2,500
一般 高額かつ長期*1
人工呼吸器等装着者*2
5,000
10,000
20,000
30,000
0
2,500
5,000
5,000 1,000
10,000
20,000
0
市町村民税25.1万円以上(約810万円~)
難病の患者に対する医療等に関する法律 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/より
申請手続きは、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所等)で行います。*申請から受給者証交付まで3~4ヶ月程度かかります。*申請されてから受給者証が交付されるまでの間に指定医療機関においてかかった医療費については、受給者証が届いてから払い戻し請求をすることができます(指定医療機関でない医療機関でかかった医療費は、払い戻しの請求をすることができません)。詳しくは、都道府県の各担当窓口で確認して下さい。*受給者証には有効期限がありますので、継続する場合には、更新手続きが必要です。
申請に必要な主な書類1)申請書:指定難病医療費支給認定申請書2)診断書:指定医が作成した臨床調査個人票3)住民票:世帯全員の住民票の写し4)医療保険上の世帯の所得を確認できる書類:市区町村民税課税状況確認書類5)保険証:申請者を含む医療保険上の世帯全員の被保険者証のコピー6)同意書:医療保険の所得区分確認
注)医療保険上の世帯は、自己負担限度額を算定する際に基準となる世帯のことをいい、住民票上の世帯とは異なります。患者さんの加入する医療保険の種類によって医療保険上の世帯が異なります。
* 申請に必要な書類は都道府県により異なる場合がありますので、 詳しくは各担当窓口で確認して下さい。
〈特定医療費 (指定難病) 受給者証の申請の流れ〉
申請 審査 承認・受給者証の交付
医療情報サービス Minds(マインズ)https://minds.jcqhc.or.jp
医療法人 恵仁会 松島クリニック 福島恒男東京山手メディカルセンター 内科 ・ 炎症性腸疾患センター 髙添正和
平成14年5月初版平成30年9月改訂