2004 年全国攻读硕士学位研究生入学考试英语试题data.kaoyany.top/2019/07/201907302026_3888.pdf · 2004年全国攻读硕士学位研究生入学考试英语试题
湘 南 考古学専攻 Course歴史学科 考古学専攻 Course of Archaeology, Department of...
Transcript of 湘 南 考古学専攻 Course歴史学科 考古学専攻 Course of Archaeology, Department of...

SHONANCampus
2 017学 科 案 内湘 南
Cou
rse of Archaeology, D
epartment of H
istoryS
chool of L
etters
歴 史 学 科考 古 学 専 攻
東海大学 文学部

歴 史 学 科 考 古 学 専 攻
Course of Archaeology,Department of HistorySchool of Letters
東海大学では建学の精神に基づき、「自ら考え、集い、挑み、成し遂げる」これら4つの力を身につけ、時代に即応できる人材を育成します。
文学部歴史学科考古学専攻では次のように教育目標を定めています。 歴史学科考古学専攻では、考古学を通じて①人間とは何か、己とは何者かを発見し、新しい世界を切り開ける人間を育てる。②論理的思考を養う。③忍耐力と社会性を育む。ここの3つの目標を掲げています。具体的には①として常にどこに在っても、時間や空間を越えた存在としての人間を理解しようとする広い視野を持ち、そのうえで自己の位置を把握し、確固たる1人として生きられる人材育成を目指しています。②の技術や③の能力の養成は、それを実現するためのものです。 この教育目標を理解し、その目標を達成するために自ら学ぶ意欲を持った人を求めます。
本学全体及び各入学試験のアドミッション・ポリシーは、東海大学オフィシャルサイトにてご確認ください。
■ 歴 史 学 科 考 古 学 専 攻02 Course of Archaeology, Department of History ■ 03
これが文学部の研究室ですか?ほかとは随分雰囲気が違いますね。なんだか「もの」であふれている。 そう、これが土器。口の内側にお焦げの
ような炭が付いていることもある。肉や野
草を入れて煮炊きしたんだろうね。この黒く
てきらきら輝く石のかけらが黒曜石という
石で作られた石器。この付近では採れない
ので、遠くからはるばる運ばれて来たもの
なんだ。その隣にあるのは昔の人が食べた
動物の骨。よく見てごらん。動物を解体した
時に付いた石器の切り痕がみえるでしょう?
この袋に入っているのはただの土なんでしょう? この土は中に含まれている植物花粉を調
べるために採集したサンプルだよ。これによ
って周囲にどんな植物が生えていたかがわ
かるんです。その当時の気候を判断する有
力な手がかりになる。
みんなただのガラクタ類ではないんですね。でもこれらと先生の研究とはどんな関係があるのですか?
これらすべてが大事な研究資料なのです
よ。土器も石器も昔の人が使った道具です
よね。動物の骨は昔の人の大事な食糧資源、
植物の種子とか花粉はその当時の環境を知
る上で必要になります。考古学ではこれら
の資料を「遺物」と呼んでいます。人間自
身の骨も立派な遺物になります。どこで、ど
のような環境条件の下で、どんな人たちが、
いつ、何のために、どのような技術を使って、
何をしたか、ということを、これらの「もの」
を使って研究します。墓や住居などの「構造
物」も「遺構」という名前で一括される考古
学資料です。
また、これらの「もの」が存在していた場
所、つまり「遺跡」のなかで、「もの」がどの
ようなあり方を示しているのか、あるいは
「もの」と「もの」の関係を通して、そこで行
われた人間行動を復元し、その背後にある
社会の構造や決まり、あるいは当時の人々
のもっていた宗教観、世界観といったものま
で追究していくことになるのです。
「もの」の形の変化から時代の前後関係を
知ったり、作り方の癖からそれを作った「集
団」の特徴を探ったりすることにかけては日
本の考古学研究は世界の最先端をいってい
るのですよ。
それでは「考古学」とは「もの」を使って人間の歴史を探る学問であると考えてよいわけですね。そしてその点でほかの歴史学科との違いがあるのですね?
そうです。考古学が人間の「歴史」にかか
わる以上、われわれの専攻が「歴史学科」
にあることは当然ですね。でも普通「歴史」
というと「文字」によって書かれた「文献」
を資料に使うものと考えられています。
でも文字は人類の歴史のなかでつい最近
発明されたもので、それも世界の一部の地
域だけのことでした。それ以前の長い長い
時間を知ったり、文字をもたなかった世界を
知るには土器や石器、食料の残り、住居や
墓といった人間の生活にともなった「もの」
を資料とするしか方法がないのです。「もの」
は人がそこにいたら必ず残ると考えられま
すので、考古学は時間的にも空間的にも人
類の歴史を知る唯一の学問と言えるので
すよ。
考古学は「文献」のたくさんあるつい最近の時代も研究していると聞きましたが? 「もの」から歴史を研究するのですから時
代を選びません。「文献」がある時代でもそ
こに記されるテーマには日常の当たり前の
ことは残されないのが普通です。たとえば
落語にでてくる江戸時代の長屋の八つあん、
熊さんの日常生活も考古学の発掘でやっと
具体的に分かるようになりました。
ほんと、考古学って面白そうですね。いろいろな分野の学問と関連があるし、自分の興味のもち方でいろいろな研究ができそう。
そう、私たちと一緒に勉強しましょう。そ
れに少人数の家庭的雰囲気の研究室だから
一生の親友もすぐできますよ。学外で行う
考古学実習も良い思い出になりますよ。
それにしてももう少し「もの」を整理してスッキリした研究室にできないのですか? さっき訪ねた別の研究室には観葉植物と応接セットがありました。
そのようにできれば、もっと良いアイデア
が生まれて研究論文もたくさん書けるかも
しれませんね。でもこれも意外なところで
考古学の教育に役立っているのですよ。そ
の積み上がっている書類の束、上の方ほど
新しく、下へ行くほど古くなる、まさに考古
学の「層位学的研究」を実践するフィールド
とは考えられませんか? どうです、この部屋
を発掘してみては。何か宝物でも見つかる
かもしれませんよ。
発掘はしてみたいけど、本当の野外の遺跡でお願いしま一す! それではまた遊びに来ます。今日はありがとうございました。
考古学研究室へようこそ。さあ、ドアを開けて中へお入りください。どうです? すこし驚いたでしょう?
考古学は人類の過去の文化を取り扱う学問です。ただし、考古学でいう文化とは、人類が遺跡のなかに物的証拠
として刻みつけ、あるいは廃棄したすべてのものから再現され復元される過去の人間の活動全体を含みます。
あるものは日常的な生活の痕跡かもしれませんし、またあるものは偶発的に起こった事件の痕跡かもしれませ
ん。とある個人が繰り返し行った行為の累積かもしれませんし、組織だった祭式などの集積かもしれません。
それらを遠い過去から現在までの時間軸に沿って整理し、一定のまとまりが見えたとき、そのまとまりを考古学
では「文化」と呼びます。
つまり人間の営みにかかわるすべての物事を、遺跡に残された物的証拠を通じて的確に再現し、復元する方法
を考古学専攻では学びます。
・ 考 古 学 専 攻 で 学 ぶ こ と ・

歴 史 学 科 考 古 学 専 攻
Course of Archaeology,Department of HistorySchool of Letters
東海大学では建学の精神に基づき、「自ら考え、集い、挑み、成し遂げる」これら4つの力を身につけ、時代に即応できる人材を育成します。
文学部歴史学科考古学専攻では次のように教育目標を定めています。 歴史学科考古学専攻では、考古学を通じて①人間とは何か、己とは何者かを発見し、新しい世界を切り開ける人間を育てる。②論理的思考を養う。③忍耐力と社会性を育む。ここの3つの目標を掲げています。具体的には①として常にどこに在っても、時間や空間を越えた存在としての人間を理解しようとする広い視野を持ち、そのうえで自己の位置を把握し、確固たる1人として生きられる人材育成を目指しています。②の技術や③の能力の養成は、それを実現するためのものです。 この教育目標を理解し、その目標を達成するために自ら学ぶ意欲を持った人を求めます。
本学全体及び各入学試験のアドミッション・ポリシーは、東海大学オフィシャルサイトにてご確認ください。
■ 歴 史 学 科 考 古 学 専 攻02 Course of Archaeology, Department of History ■ 03
これが文学部の研究室ですか?ほかとは随分雰囲気が違いますね。なんだか「もの」であふれている。 そう、これが土器。口の内側にお焦げの
ような炭が付いていることもある。肉や野
草を入れて煮炊きしたんだろうね。この黒く
てきらきら輝く石のかけらが黒曜石という
石で作られた石器。この付近では採れない
ので、遠くからはるばる運ばれて来たもの
なんだ。その隣にあるのは昔の人が食べた
動物の骨。よく見てごらん。動物を解体した
時に付いた石器の切り痕がみえるでしょう?
この袋に入っているのはただの土なんでしょう? この土は中に含まれている植物花粉を調
べるために採集したサンプルだよ。これによ
って周囲にどんな植物が生えていたかがわ
かるんです。その当時の気候を判断する有
力な手がかりになる。
みんなただのガラクタ類ではないんですね。でもこれらと先生の研究とはどんな関係があるのですか?
これらすべてが大事な研究資料なのです
よ。土器も石器も昔の人が使った道具です
よね。動物の骨は昔の人の大事な食糧資源、
植物の種子とか花粉はその当時の環境を知
る上で必要になります。考古学ではこれら
の資料を「遺物」と呼んでいます。人間自
身の骨も立派な遺物になります。どこで、ど
のような環境条件の下で、どんな人たちが、
いつ、何のために、どのような技術を使って、
何をしたか、ということを、これらの「もの」
を使って研究します。墓や住居などの「構造
物」も「遺構」という名前で一括される考古
学資料です。
また、これらの「もの」が存在していた場
所、つまり「遺跡」のなかで、「もの」がどの
ようなあり方を示しているのか、あるいは
「もの」と「もの」の関係を通して、そこで行
われた人間行動を復元し、その背後にある
社会の構造や決まり、あるいは当時の人々
のもっていた宗教観、世界観といったものま
で追究していくことになるのです。
「もの」の形の変化から時代の前後関係を
知ったり、作り方の癖からそれを作った「集
団」の特徴を探ったりすることにかけては日
本の考古学研究は世界の最先端をいってい
るのですよ。
それでは「考古学」とは「もの」を使って人間の歴史を探る学問であると考えてよいわけですね。そしてその点でほかの歴史学科との違いがあるのですね?
そうです。考古学が人間の「歴史」にかか
わる以上、われわれの専攻が「歴史学科」
にあることは当然ですね。でも普通「歴史」
というと「文字」によって書かれた「文献」
を資料に使うものと考えられています。
でも文字は人類の歴史のなかでつい最近
発明されたもので、それも世界の一部の地
域だけのことでした。それ以前の長い長い
時間を知ったり、文字をもたなかった世界を
知るには土器や石器、食料の残り、住居や
墓といった人間の生活にともなった「もの」
を資料とするしか方法がないのです。「もの」
は人がそこにいたら必ず残ると考えられま
すので、考古学は時間的にも空間的にも人
類の歴史を知る唯一の学問と言えるので
すよ。
考古学は「文献」のたくさんあるつい最近の時代も研究していると聞きましたが? 「もの」から歴史を研究するのですから時
代を選びません。「文献」がある時代でもそ
こに記されるテーマには日常の当たり前の
ことは残されないのが普通です。たとえば
落語にでてくる江戸時代の長屋の八つあん、
熊さんの日常生活も考古学の発掘でやっと
具体的に分かるようになりました。
ほんと、考古学って面白そうですね。いろいろな分野の学問と関連があるし、自分の興味のもち方でいろいろな研究ができそう。
そう、私たちと一緒に勉強しましょう。そ
れに少人数の家庭的雰囲気の研究室だから
一生の親友もすぐできますよ。学外で行う
考古学実習も良い思い出になりますよ。
それにしてももう少し「もの」を整理してスッキリした研究室にできないのですか? さっき訪ねた別の研究室には観葉植物と応接セットがありました。
そのようにできれば、もっと良いアイデア
が生まれて研究論文もたくさん書けるかも
しれませんね。でもこれも意外なところで
考古学の教育に役立っているのですよ。そ
の積み上がっている書類の束、上の方ほど
新しく、下へ行くほど古くなる、まさに考古
学の「層位学的研究」を実践するフィールド
とは考えられませんか? どうです、この部屋
を発掘してみては。何か宝物でも見つかる
かもしれませんよ。
発掘はしてみたいけど、本当の野外の遺跡でお願いしま一す! それではまた遊びに来ます。今日はありがとうございました。
考古学研究室へようこそ。さあ、ドアを開けて中へお入りください。どうです? すこし驚いたでしょう?
考古学は人類の過去の文化を取り扱う学問です。ただし、考古学でいう文化とは、人類が遺跡のなかに物的証拠
として刻みつけ、あるいは廃棄したすべてのものから再現され復元される過去の人間の活動全体を含みます。
あるものは日常的な生活の痕跡かもしれませんし、またあるものは偶発的に起こった事件の痕跡かもしれませ
ん。とある個人が繰り返し行った行為の累積かもしれませんし、組織だった祭式などの集積かもしれません。
それらを遠い過去から現在までの時間軸に沿って整理し、一定のまとまりが見えたとき、そのまとまりを考古学
では「文化」と呼びます。
つまり人間の営みにかかわるすべての物事を、遺跡に残された物的証拠を通じて的確に再現し、復元する方法
を考古学専攻では学びます。
・ 考 古 学 専 攻 で 学 ぶ こ と ・

BKカリキュラムの特徴 考古学専攻で学べる専門科目一覧
主専攻科目
考古学専攻は日本考古学、外国考古学、応用考古学の3つの柱で人類の過去を総合的に探求します。
■専門基礎科目の必修化と基礎的教養の重視 歴史研究の一分野である考古学は、ほかの史学に比べると関連する広い分野をもっており、これらの基礎的理解がまず必要となります。そのため歴史学基礎科目として、1年次には「日本史概説」「東洋史概説」「西洋史概説」が、2年次には「歴史の見方」「歴史総合講座」が開講されています。 また、考古学に直結した専門科目として、「考古学研究入門」「日本考古学概説」「外国考古学概説」を必ず受講していただき、考古学研究の基礎と概要を学びます。
■世界的視野での専門領域の学習 考古資料は世界のあらゆる地域に存在します。これらを広く世界史的、あるいは人類史的観点から研究することも考古学専攻の特色の一つです。 主専攻科目として〈日本考古学〉のほかに、東アジア・北アジア・南アジア・西アジア・ヨーロッパなどの国外諸地域の考古学についても広い視野からの学習が可能となるように〈外国考古学〉という学科目の下に、各種の授業科目が開設されています。
■関連学問を通して知の世界を広げる 考古学の研究では、理化学的な知識や考古学への応用の実際を学ぶために〈応用考古学〉が開設されています。〈応用考古学〉に属する講義・演習で取り扱われるテーマには、地質学・第四紀学・環境考古学・植物考古学・実験考古学などがあります。
■野外調査の実践 考古学研究の基礎はフィールド調査にあります。遺跡に立つことから課題やテーマが生まれ、発掘調査を通して解答が求められます。そのため考古学の研究では何よりも実地、実際における調査技術と資料分析法の修得が不可欠です。これらを訓練し、修得させる実習授業として、「野外考古学演習」「資料分析法演習」「考古学実習」が開設されています。
■問題解決能力の育成 すべての授業科目は4年次第8セメスターで作成・提出される卒業論文に向かって組み立てられています。考古学専攻ではとりわけ卒業論文を重視します。それは、自らの力で問題を発見し、問題を解決するまたとない機会だからです。卒業論文の作成を通じて初めて、考古学を学ぶことの意味を再確認することになり、気力と忍耐力も培われていきます。
考古学研究入門日本考古学概説外国考古学概説応用考古学概説
先土器時代講義縄文時代講義弥生時代講義古墳時代講義歴史時代講義南アジア考古学講義西アジア考古学講義外国考古学地域研究講義応用考古学講義野外考古学演習資料分析法演習考古学実習
先土器時代演習縄文時代演習弥生時代演習古墳時代演習歴史時代演習南アジア考古学演習西アジア考古学演習外国考古学地域研究演習応用考古学演習考古学研究法卒業論文基礎1
卒業論文基礎2卒業論文
1年次 2年次 3年次 4年次 考古学研究の基礎を学ぶ 〔1年次(1・2セメスター)〕 考古学基礎
考古学を学ぶ最初の入門的授業 遺跡見学や本学所蔵の考古資料を観察することで、遺跡・遺物とはどのようなものであるのかを学びます。さらに考古学に関連する著作を読むことで、文章を読み取る基礎訓練を行います。
考古学研究入門
人類300万年の歩みを検証する 考古学は「型式学」「層位学」といった独自の方法により、文字を持たなかった時代の社会の復元を可能にします。授業では世界史的な視野から考古学がとる基礎的方法について学びます。
外国考古学概説
テーマ別に広がる考古学の世界を学ぶ 応用考古学には動物考古学、植物考古学、岩石考古学などのほか、形質人類学や地球化学、文化人類学、民俗学などを応用した研究もあります。個々の研究方法と考古学で語ることのできる世界の広さを紹介します。
応用考古学概説
考古学研究の基礎的な知識や研究方法を学ぶ 明治期以降の日本の考古学研究の歴史を学ぶなかで、現在の研究を多面的に理解できるように授業を展開します。
日本考古学概説
主専攻科目一覧必修選択 単位数授 業 科 目 名学 科 目 必修選択 単位数授 業 科 目 名学 科 目
日本史概説東洋史概説西洋史概説歴史の見方歴史総合講座考古学研究入門日本考古学概説A日本考古学概説B外国考古学概説A外国考古学概説B応用考古学概説人類学概説A・B考古学研究法先土器時代講義A・B縄文時代講義A・B弥生時代講義A・B古墳時代講義A・B歴史時代講義A・B先土器時代演習A・B縄文時代演習A・B弥生時代演習A・B古墳時代演習A・B歴史時代演習A・B南アジア考古学講義A・B西アジア考古学講義A・B
外国考古学地域研究講義A外国考古学地域研究講義B外国考古学地域研究講義C南アジア考古学演習A・B西アジア考古学演習A・B外国考古学地域研究演習A外国考古学地域研究演習B外国考古学地域研究演習C応用考古学講義A応用考古学講義B応用考古学講義C応用考古学演習A応用考古学演習B応用考古学演習C野外考古学演習資料分析法演習考古学実習考古学特別講義考古学特別演習卒業論文基礎1卒業論文基礎2卒業論文ことばの世界知のフロンティア基礎情報処理Ⅰ
選択選択選択選択選択必修必修選択必修選択選択選択必修選択選択選択選択選択選択選択選択選択選択選択選択
選択選択選択選択選択選択選択選択選択選択選択選択選択選択必修必修必修選択選択必修必修必修選択選択選択
4442222222224222222222222
2222222222222244222226222
■ 歴史学基礎
■ 考古学基礎
■ 日本考古学
■ 外国考古学
■ 外国考古学
■ 応用考古学
■ 考古学基幹科目
■ 文学部共通科目
卒業単位数一覧修得すべき単位数構 成 授 業 科 目科 目 区 分
現代文明論1現代文明論2文理共通科目体育科目英語コミュニケーション科目必修科目選択科目
22628
303242
124
Ⅰ 現代文明論
Ⅱ 現代教養科目
Ⅲ 英語コミュニケーション科目Ⅳ 主専攻科目
Ⅴ 自己形成科目 合 計
※ほかにも教職科目があります。
■ 歴 史 学 科 考 古 学 専 攻04 Course of Archaeology, Department of History ■ 05

BKカリキュラムの特徴 考古学専攻で学べる専門科目一覧
主専攻科目
考古学専攻は日本考古学、外国考古学、応用考古学の3つの柱で人類の過去を総合的に探求します。
■専門基礎科目の必修化と基礎的教養の重視 歴史研究の一分野である考古学は、ほかの史学に比べると関連する広い分野をもっており、これらの基礎的理解がまず必要となります。そのため歴史学基礎科目として、1年次には「日本史概説」「東洋史概説」「西洋史概説」が、2年次には「歴史の見方」「歴史総合講座」が開講されています。 また、考古学に直結した専門科目として、「考古学研究入門」「日本考古学概説」「外国考古学概説」を必ず受講していただき、考古学研究の基礎と概要を学びます。
■世界的視野での専門領域の学習 考古資料は世界のあらゆる地域に存在します。これらを広く世界史的、あるいは人類史的観点から研究することも考古学専攻の特色の一つです。 主専攻科目として〈日本考古学〉のほかに、東アジア・北アジア・南アジア・西アジア・ヨーロッパなどの国外諸地域の考古学についても広い視野からの学習が可能となるように〈外国考古学〉という学科目の下に、各種の授業科目が開設されています。
■関連学問を通して知の世界を広げる 考古学の研究では、理化学的な知識や考古学への応用の実際を学ぶために〈応用考古学〉が開設されています。〈応用考古学〉に属する講義・演習で取り扱われるテーマには、地質学・第四紀学・環境考古学・植物考古学・実験考古学などがあります。
■野外調査の実践 考古学研究の基礎はフィールド調査にあります。遺跡に立つことから課題やテーマが生まれ、発掘調査を通して解答が求められます。そのため考古学の研究では何よりも実地、実際における調査技術と資料分析法の修得が不可欠です。これらを訓練し、修得させる実習授業として、「野外考古学演習」「資料分析法演習」「考古学実習」が開設されています。
■問題解決能力の育成 すべての授業科目は4年次第8セメスターで作成・提出される卒業論文に向かって組み立てられています。考古学専攻ではとりわけ卒業論文を重視します。それは、自らの力で問題を発見し、問題を解決するまたとない機会だからです。卒業論文の作成を通じて初めて、考古学を学ぶことの意味を再確認することになり、気力と忍耐力も培われていきます。
考古学研究入門日本考古学概説外国考古学概説応用考古学概説
先土器時代講義縄文時代講義弥生時代講義古墳時代講義歴史時代講義南アジア考古学講義西アジア考古学講義外国考古学地域研究講義応用考古学講義野外考古学演習資料分析法演習考古学実習
先土器時代演習縄文時代演習弥生時代演習古墳時代演習歴史時代演習南アジア考古学演習西アジア考古学演習外国考古学地域研究演習応用考古学演習考古学研究法卒業論文基礎1
卒業論文基礎2卒業論文
1年次 2年次 3年次 4年次 考古学研究の基礎を学ぶ 〔1年次(1・2セメスター)〕 考古学基礎
考古学を学ぶ最初の入門的授業 遺跡見学や本学所蔵の考古資料を観察することで、遺跡・遺物とはどのようなものであるのかを学びます。さらに考古学に関連する著作を読むことで、文章を読み取る基礎訓練を行います。
考古学研究入門
人類300万年の歩みを検証する 考古学は「型式学」「層位学」といった独自の方法により、文字を持たなかった時代の社会の復元を可能にします。授業では世界史的な視野から考古学がとる基礎的方法について学びます。
外国考古学概説
テーマ別に広がる考古学の世界を学ぶ 応用考古学には動物考古学、植物考古学、岩石考古学などのほか、形質人類学や地球化学、文化人類学、民俗学などを応用した研究もあります。個々の研究方法と考古学で語ることのできる世界の広さを紹介します。
応用考古学概説
考古学研究の基礎的な知識や研究方法を学ぶ 明治期以降の日本の考古学研究の歴史を学ぶなかで、現在の研究を多面的に理解できるように授業を展開します。
日本考古学概説
主専攻科目一覧必修選択 単位数授 業 科 目 名学 科 目 必修選択 単位数授 業 科 目 名学 科 目
日本史概説東洋史概説西洋史概説歴史の見方歴史総合講座考古学研究入門日本考古学概説A日本考古学概説B外国考古学概説A外国考古学概説B応用考古学概説人類学概説A・B考古学研究法先土器時代講義A・B縄文時代講義A・B弥生時代講義A・B古墳時代講義A・B歴史時代講義A・B先土器時代演習A・B縄文時代演習A・B弥生時代演習A・B古墳時代演習A・B歴史時代演習A・B南アジア考古学講義A・B西アジア考古学講義A・B
外国考古学地域研究講義A外国考古学地域研究講義B外国考古学地域研究講義C南アジア考古学演習A・B西アジア考古学演習A・B外国考古学地域研究演習A外国考古学地域研究演習B外国考古学地域研究演習C応用考古学講義A応用考古学講義B応用考古学講義C応用考古学演習A応用考古学演習B応用考古学演習C野外考古学演習資料分析法演習考古学実習考古学特別講義考古学特別演習卒業論文基礎1卒業論文基礎2卒業論文ことばの世界知のフロンティア基礎情報処理Ⅰ
選択選択選択選択選択必修必修選択必修選択選択選択必修選択選択選択選択選択選択選択選択選択選択選択選択
選択選択選択選択選択選択選択選択選択選択選択選択選択選択必修必修必修選択選択必修必修必修選択選択選択
4442222222224222222222222
2222222222222244222226222
■ 歴史学基礎
■ 考古学基礎
■ 日本考古学
■ 外国考古学
■ 外国考古学
■ 応用考古学
■ 考古学基幹科目
■ 文学部共通科目
卒業単位数一覧修得すべき単位数構 成 授 業 科 目科 目 区 分
現代文明論1現代文明論2文理共通科目体育科目英語コミュニケーション科目必修科目選択科目
22628
303242
124
Ⅰ 現代文明論
Ⅱ 現代教養科目
Ⅲ 英語コミュニケーション科目Ⅳ 主専攻科目
Ⅴ 自己形成科目 合 計
※ほかにも教職科目があります。
■ 歴 史 学 科 考 古 学 専 攻04 Course of Archaeology, Department of History ■ 05

BK主 専 攻 科 目
あらゆる時代を探求する 〔2・3年次(3~6セメスター)〕 日本考古学
世界の地域を深く知る 〔2・3年次(3~6セメスター)〕 外国考古学
学際的な知識を修得する 〔2・3年次(3~6セメスター)〕 応用考古学
さまざまな調査・研究方法を学ぶ 〔2・3年次(3~5セメスター)〕 考古学基幹科目
卒業論文を作成する〔3・4年次(6~8セメスター)〕
■ 歴 史 学 科 考 古 学 専 攻06 Course of Archaeology, Department of History ■ 07
日本列島の先土器(旧石器)時代について学ぶ 人類が言語を獲得し、道具を使用しはじめたのは先土器時代のことです。そのため、人類の歴史を遺物=道具から研究する考古学にあって、先土器時代の研究はもっとも基礎的な研究領域となります。
先土器時代講義
土器を通して縄文時代を理解する 縄文土器により時代の範囲が規定され、土器様相の変化や変異によって時期や地域が認識されます。「土器型式」と「土器型式論」について、研究の歴史と近年の研究を解説しながら縄文時代の理解を深めてもらいます。
縄文時代講義
弥生時代という社会の転換期について学ぶ 弥生時代は本格的な稲作の導入や金属器の使用、そして階級社会やクニの始まり、クニ同士の抗争など、大きな変化が読み取れる時代です。授業では物質資料を扱う考古学が明らかにした弥生時代について論じます。
弥生時代講義
前方後円墳研究の基礎を学び古墳時代の新たな解釈を知る 日本各地に築かれた前方後円墳には、それぞれの地域的特色や個性が認められ、従来の解釈には大幅な修正が求められています。授業では前方後円墳研究における諸問題を取り上げながら今後の課題について論じます。
古墳時代講義
文献史料が登場している歴史時代の考古学 歴史時代のうちでも、律令国家の形成期から平安時代末期までを対象とし、この時代の食器である土師器と須恵器を取り上げ、その特質や相互関係について解説し、古代土器研究の動向について学びます。
歴史時代講義
インド・パキスタン、ネパール、スリランカの考古学 この広大な地域は、さまざまな古代文明・文化が展開している地域でもあります。本講義では、南アジア考古学研究の歴史を具体的にたどり、特に最古の古代文明であるインダス文明を中心に講義を進めていきます。
南アジア考古学講義
農耕・牧畜の発祥の地で文明の起源をさぐる 西アジアという歴史的世界を特徴づけることになった環境の問題から出発し、この地域に展開された考古学的調査・研究の歴史、メソポタミアを中心とする新石器時代以降の文化について講じます。
西アジア考古学講義
フィリピンを中心とした東南アジア先史時代の文化を概観する ベトナムや台湾、フィリピン、タイ、マレーシアといった南シナ海を囲む広い地域での流通や交易(土器・玉製品)の研究成果を紹介しながら、東南アジアにおける先史時代の枠組みや考え方について論じます。
外国考古学地域研究講義A
中国考古学の概要を学び、最新の研究現状を知る 中国の旧石器時代から近現代まで幅広く取り上げ、東アジア世界やユーラシア大陸における共通性と多様性についても考えます。考古学資料からどのような方法で解釈し、研究が進められているのかを理解します。
外国考古学地域研究講義B
古代エジプト・中近東の考古学資料を理解する 3000年以上にわたる古代エジプトの社会で、土器や陶器・ファイアンス・ガラス・金属がどのような用途で使われ、そしてその製作方法と窯業の技術のかかわりを全体で見ていきます。
外国考古学地域研究講義C
人類紀または氷河時代と呼ばれる第四紀から地球規模で人類を考える 46億年の地球史のなかで、現在を含むわずか258万年間を第四紀と呼びます。第四紀とはどのような時代なのかを概観し、第四紀学と考古学それぞれの研究方法の原理と限界、現在までの到達点と問題点を論じます。
応用考古学講義A
過去の人々の生活を復元するための岩石学 地球科学の立場に立った岩石の基礎的な分類基準と岩石を判定する場合の特徴について、具体的な例を示しながら解説します。石器や石製品を使用した人々の生活を復元することに有効な岩石学を目指します。
応用考古学講義B
土器の原料を構成している土について学びます 土器の観察と各地で採取された粘土の鉱物分析を行い、土器の胎土分析研究の基礎を学びます。また、石器についても石材の化学成分から何を語ることができるのかについても講義します。
応用考古学講義C
測量技術の基礎を修得する実践的授業 遺跡の立地を理解するためには周辺地形を読み取ることが必要です。そのため、測量機材を用いた実践的活動を授業のなかで行い、測量技術の修得を目指します。授業は週2コマを使い、野外で実施します。
野外考古学演習
実際に遺跡を調査する実習授業 考古学全教員の指導のもと、発掘調査あるいは測量調査、分布調査などを実施します。各種調査機材を用いての技術の修得に加え、地域社会のなかでの考古学調査のあり方とその実際についても理解を深めてもらいます。
考古学実習
資料の記録化について基礎的技術を修得する 考古学資料の基礎的技術に、遺跡や遺物の特徴を適切に把握し、記録化する方法があります。この記録化に必要な遺物の観察法と実測法、写真撮影などの基礎技術を学びます。
資料分析法演習
考古学研究のさまざまな方法、学史について学びます ヨーロッパで確立された近代考古学は、日本でも100年にわたり研究が進められてきました。授業では複数の教員により、長きにわたる考古学研究の足跡をたどりながら、今日ある研究の諸課題について講義します。
考古学研究法
卒業論文は、自ら「テーマ」を設定し、それについて「研究史の追跡」「研究現状の把握」「資料収集」「資料分析」そして「まとめ」を行う一連の流れで作成されます。本授業は、こうした作業をいかにして行うかを教示し、来るべき卒業論文作成の基礎能力を養成することを目的にしています。
卒業論文基礎1・2
すべての授業は4年次の8セメスターで作成・提出される卒業論文に向かって組み立てられています。 考古学はとりわけ卒業論文を重視します。それは、各人が設定した「テーマ」に従い、自らの力で問題を発見し、これらの問題を解決するまたとない機会となるからです。
卒業論文幅広い学問領域をカバーするカリキュラム
通常の講義・演習に加え、サマーセッション、ウインターセッション期間に開講される「考古学特別講義」「考古学特別演習」では、学外から考古学の第一線で活躍する講師を招き、動物考古学、植物考古学など幅広い分野にわたって授業を展開します。

BK主 専 攻 科 目
あらゆる時代を探求する 〔2・3年次(3~6セメスター)〕 日本考古学
世界の地域を深く知る 〔2・3年次(3~6セメスター)〕 外国考古学
学際的な知識を修得する 〔2・3年次(3~6セメスター)〕 応用考古学
さまざまな調査・研究方法を学ぶ 〔2・3年次(3~5セメスター)〕 考古学基幹科目
卒業論文を作成する〔3・4年次(6~8セメスター)〕
■ 歴 史 学 科 考 古 学 専 攻06 Course of Archaeology, Department of History ■ 07
日本列島の先土器(旧石器)時代について学ぶ 人類が言語を獲得し、道具を使用しはじめたのは先土器時代のことです。そのため、人類の歴史を遺物=道具から研究する考古学にあって、先土器時代の研究はもっとも基礎的な研究領域となります。
先土器時代講義
土器を通して縄文時代を理解する 縄文土器により時代の範囲が規定され、土器様相の変化や変異によって時期や地域が認識されます。「土器型式」と「土器型式論」について、研究の歴史と近年の研究を解説しながら縄文時代の理解を深めてもらいます。
縄文時代講義
弥生時代という社会の転換期について学ぶ 弥生時代は本格的な稲作の導入や金属器の使用、そして階級社会やクニの始まり、クニ同士の抗争など、大きな変化が読み取れる時代です。授業では物質資料を扱う考古学が明らかにした弥生時代について論じます。
弥生時代講義
前方後円墳研究の基礎を学び古墳時代の新たな解釈を知る 日本各地に築かれた前方後円墳には、それぞれの地域的特色や個性が認められ、従来の解釈には大幅な修正が求められています。授業では前方後円墳研究における諸問題を取り上げながら今後の課題について論じます。
古墳時代講義
文献史料が登場している歴史時代の考古学 歴史時代のうちでも、律令国家の形成期から平安時代末期までを対象とし、この時代の食器である土師器と須恵器を取り上げ、その特質や相互関係について解説し、古代土器研究の動向について学びます。
歴史時代講義
インド・パキスタン、ネパール、スリランカの考古学 この広大な地域は、さまざまな古代文明・文化が展開している地域でもあります。本講義では、南アジア考古学研究の歴史を具体的にたどり、特に最古の古代文明であるインダス文明を中心に講義を進めていきます。
南アジア考古学講義
農耕・牧畜の発祥の地で文明の起源をさぐる 西アジアという歴史的世界を特徴づけることになった環境の問題から出発し、この地域に展開された考古学的調査・研究の歴史、メソポタミアを中心とする新石器時代以降の文化について講じます。
西アジア考古学講義
フィリピンを中心とした東南アジア先史時代の文化を概観する ベトナムや台湾、フィリピン、タイ、マレーシアといった南シナ海を囲む広い地域での流通や交易(土器・玉製品)の研究成果を紹介しながら、東南アジアにおける先史時代の枠組みや考え方について論じます。
外国考古学地域研究講義A
中国考古学の概要を学び、最新の研究現状を知る 中国の旧石器時代から近現代まで幅広く取り上げ、東アジア世界やユーラシア大陸における共通性と多様性についても考えます。考古学資料からどのような方法で解釈し、研究が進められているのかを理解します。
外国考古学地域研究講義B
古代エジプト・中近東の考古学資料を理解する 3000年以上にわたる古代エジプトの社会で、土器や陶器・ファイアンス・ガラス・金属がどのような用途で使われ、そしてその製作方法と窯業の技術のかかわりを全体で見ていきます。
外国考古学地域研究講義C
人類紀または氷河時代と呼ばれる第四紀から地球規模で人類を考える 46億年の地球史のなかで、現在を含むわずか258万年間を第四紀と呼びます。第四紀とはどのような時代なのかを概観し、第四紀学と考古学それぞれの研究方法の原理と限界、現在までの到達点と問題点を論じます。
応用考古学講義A
過去の人々の生活を復元するための岩石学 地球科学の立場に立った岩石の基礎的な分類基準と岩石を判定する場合の特徴について、具体的な例を示しながら解説します。石器や石製品を使用した人々の生活を復元することに有効な岩石学を目指します。
応用考古学講義B
土器の原料を構成している土について学びます 土器の観察と各地で採取された粘土の鉱物分析を行い、土器の胎土分析研究の基礎を学びます。また、石器についても石材の化学成分から何を語ることができるのかについても講義します。
応用考古学講義C
測量技術の基礎を修得する実践的授業 遺跡の立地を理解するためには周辺地形を読み取ることが必要です。そのため、測量機材を用いた実践的活動を授業のなかで行い、測量技術の修得を目指します。授業は週2コマを使い、野外で実施します。
野外考古学演習
実際に遺跡を調査する実習授業 考古学全教員の指導のもと、発掘調査あるいは測量調査、分布調査などを実施します。各種調査機材を用いての技術の修得に加え、地域社会のなかでの考古学調査のあり方とその実際についても理解を深めてもらいます。
考古学実習
資料の記録化について基礎的技術を修得する 考古学資料の基礎的技術に、遺跡や遺物の特徴を適切に把握し、記録化する方法があります。この記録化に必要な遺物の観察法と実測法、写真撮影などの基礎技術を学びます。
資料分析法演習
考古学研究のさまざまな方法、学史について学びます ヨーロッパで確立された近代考古学は、日本でも100年にわたり研究が進められてきました。授業では複数の教員により、長きにわたる考古学研究の足跡をたどりながら、今日ある研究の諸課題について講義します。
考古学研究法
卒業論文は、自ら「テーマ」を設定し、それについて「研究史の追跡」「研究現状の把握」「資料収集」「資料分析」そして「まとめ」を行う一連の流れで作成されます。本授業は、こうした作業をいかにして行うかを教示し、来るべき卒業論文作成の基礎能力を養成することを目的にしています。
卒業論文基礎1・2
すべての授業は4年次の8セメスターで作成・提出される卒業論文に向かって組み立てられています。 考古学はとりわけ卒業論文を重視します。それは、各人が設定した「テーマ」に従い、自らの力で問題を発見し、これらの問題を解決するまたとない機会となるからです。
卒業論文幅広い学問領域をカバーするカリキュラム
通常の講義・演習に加え、サマーセッション、ウインターセッション期間に開講される「考古学特別講義」「考古学特別演習」では、学外から考古学の第一線で活躍する講師を招き、動物考古学、植物考古学など幅広い分野にわたって授業を展開します。

Course of Archaeology,Department of HistorySchool of Letters
Course of Archaeology,Department of HistorySchool of Letters
BK教 員 紹 介Course of Archaeology,Department of History
School of Letters
講師・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
非常勤講師・・・・・・・・・・・
1人8人
教授・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
准教授・・・・・・・・・・・・・・・・・
2人3人
DATA5
Course of Archaeology, Department of History ■ 09■ 歴 史 学 科 考 古 学 専 攻08
・研究テーマ・
・専門分野・
北條 芳隆 教授Y.Hojo大阪大学大学院文学研究科
・研究テーマ・
・専門分野・
松本 建速 教授T.Matsumoto筑波大学大学院歴史・人類学研究科
・研究テーマ・
・専門分野・
秋田 かな子 准教授K.Akita東海大学文学部史学科 (現:歴史学科)
・研究テーマ・
・専門分野・
宮原 俊一 講師S.Miyahara東海大学大学院文学研究科
第四紀の地磁気に関し、特に考古地磁気層序(房総半島)、火山灰中の磁性鉱物の熱磁気特性を中心に研究しています。ともに土層に含まれる鉱物から得る情報で、第四紀の環境復元の資料を提供しています。●受験生へのメッセージ:日ごろからいろいろなことに興味・関心を持つように心掛けてほしいと思います。
石器石材の岩種鑑定結果を用い、石材選択の問題や使用石材から見た地域性と石材移動を追究し、また肉眼による岩種鑑定を研究しています。さらに石材と古環境の復元にも関心を寄せています。●受験生へのメッセージ:真実に迫るにはいろいろな切り口から見る必要があります。石材からみる考古学、新しい切り口です。
人類がまだ遊動生活を送っていた時代、先土器時代について研究しています。特に、南関東地方の遺跡の分析を通じて、人類がどのように生活しどのような生産活動をしていたかに関心を持っています。●受験生へのメッセージ:人類がどんな方法で生きてきたかを知ることで、あなたの生き方を学んでください。
日本の弥生時代は、人々がダイナミックに活動し、文物と情報が行き交う激動の時代です。そして、各地域でクニというまとまりが誕生していきます。その過程を、遺跡の分析を通して明らかにしたいと考えています。●受験生へのメッセージ:執着心と粘着性、通説にとらわれない発想が明日を拓く。
・研究テーマ・
・専門分野・
會田 信行 非常勤講師N.Aida北海道大学大学院理学研究科
・研究テーマ・
・専門分野・
柴田 徹 非常勤講師T.Shibata東京教育大学理学部地学科
・研究テーマ・
・専門分野・
田尾 誠敏 非常勤講師M.Tao東海大学文学部史学科 (現:歴史学科)
日本考古学のうち文献史料が登場してからの歴史時代について、相模地域を中心に研究を行っています。特に土器を通して当時の社会をどのように読み解くことができるかに興味をもっています。●受験生へのメッセージ:発掘調査から得た資料を扱い解釈するために経験と知識を培ってください。
古代エジプトのファイアンス(やきもの)やガラスなどの研究と、日本の最先端の科学技術を考古学に応用した考古科学の研究を行っています。原材料や製品の動きを追うことで、古代の交易や経済のシステムが見えてきます。●受験生へのメッセージ:古代エジプト文明の謎を一緒に解き明かしましょう。
・研究テーマ・
・専門分野・
伊藤 健 非常勤講師T.Ito國學院大學大学院文学研究科
・研究テーマ・
・専門分野・
立花 実 非常勤講師M.Tachibana東海大学文学部史学科 (現:歴史学科)
古墳時代、墳丘墓、前方後円墳、腕輪形石製品
日本考古学
縄文時代、土器型式論、住居構造
日本考古学
縄文時代~中世、蝦夷、胎土分析、鉄生産
日本考古学
縄文時代、土器、古代技術
日本考古学
第四紀、考古磁気、環境磁気学、磁性鉱物
第四紀学
石器時代、石材、実証性、複数の視点
応用岩石学
弥生時代、地域社会、階級性、情報ネットワーク
日本考古学
歴史時代、土器、交易、地域社会
日本考古学
特に長江流域の新石器文化について研究を進めています。集落の構造・墓の構造や埋葬の仕方・農耕技術などから当時の社会を復元し、現在の私たちの生活にどのように影響してきたのかを調べています。 ほかに日本考古学史について、近代日本の成長を通して研究しています。●受験生へのメッセージ:則天去私。
・研究テーマ・
・専門分野・
小柳 美樹 非常勤講師Y.Koyanagi東海大学大学院文学研究科
中国考古学、新石器文化、長江、飲食文化
中国考古学
先土器時代、南関東地方、石器形態、人類の領域
日本考古学
バルカン半島で食糧生産経済が導入されてから、いかにして青銅器時代が始まったのか、その過程について研究しています。土器などの分析をもとに、当時の文化と社会のあり方について考えています。●受験生へのメッセージ:経験の数と直感でモノの見方を豊かにしてください。
インド北西部に所在するインダス文明遺跡の考古学的調査に従事し、インダス文明の社会構造や古代都市のあり方について、思考実験を繰り返しています。インド留学や毎年のインド調査を経て、現地にもすっかり慣れてしまい、インドカレーもおいしく作れるようになりました。●受験生へのメッセージ:考古学とは人間を成長させる学問です。毎日のように思考実験を繰り返しながら、元気に明るく、考古学を楽しんでみてください。
・研究テーマ・
・専門分野・
千本 真生 非常勤講師M.Semmoto東海大学大学院文学研究科
・研究テーマ・
・専門分野・
小茄子川 歩 非常勤講師A.Konasukawaデカン大学院大学考古学科
バルカン半島、新石器時代~青銅器時代、環黒海、原印欧語族
南東ヨーロッパ考古学
インダス文明、古代都市、南アジア型発展径路
南アジア考古学
縄文時代以来の日本列島、主に東日本に住んでいた人々について研究しています。多面的に人間を見るためにさまざまな方法でアプローチしています。特に、人間の自然への働きかけ方の変化に注目しています。●受験生へのメッセージ:土に残されたメッセージ、皆さんと読み解ける日を楽しみにしています。
縄文時代の型式のあり方や変化のしかたについて考えています。また縄文時代の住居について、その構造や地域性に興味があります。これらを総合し縄文時代の社会構造の解明を目指しています。●受験生へのメッセージ:いつでも研究室、そして整理作業室に見学に来てください。
日本の古墳時代、特に前方後円墳の出現過程に焦点をあて墳丘の存在理由、墓の構築に注ぎ続けたエネルギーとは何かを調べています。また沖縄県西表島の調査にともない「日本文化」の正体に迫っています。●受験生へのメッセージ:「もの」にこだわってナンボの粘着質の世界で、しかも体力勝負、それが考古学です。
主に縄文時代から弥生時代の文化や社会について研究しています。土器や石器をはじめとするさまざまな考古資料から、古代の人々の暮らしぶりを明らかにしていきたいと考えています。●受験生へのメッセージ:関心、疑問、挑戦、持続、体力。5つのキーワードが大学生活をより豊かなものにします。
・研究テーマ・
・専門分野・
山花 京子 准教授(兼担)K.Yamahanaシカゴ大学文学部大学院
アジア文明学科
古代エジプト、ファイアンス、ガラス、考古科学
エジプト学・考古科学
人類は、約1万年前の氷河期が終わったころに、農耕や牧畜という新たなライフスタイルを始めました。農耕や牧畜は世界のいくつかの中心地で始まりました。その一つが中東(西アジア)です。私は、大昔の人々が、いつ、どのように、農耕や牧畜を始めたのか、その起源とプロセスを探るために中東やコーカサス地方で発掘調査を行っています。●受験生へのメッセージ:若いときにしかできないことがあります。考古学では、貴重な経験ができます。
・研究テーマ・
・専門分野・
有村 誠 准教授M.Arimuraリヨン第2大学大学院
コーカサス、農耕の起源、新石器化、文化遺産の保護と活用、石器
西アジア考古学

Course of Archaeology,Department of HistorySchool of Letters
Course of Archaeology,Department of HistorySchool of Letters
BK教 員 紹 介Course of Archaeology,Department of History
School of Letters
講師・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
非常勤講師・・・・・・・・・・・
1人8人
教授・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
准教授・・・・・・・・・・・・・・・・・
2人3人
DATA5
Course of Archaeology, Department of History ■ 09■ 歴 史 学 科 考 古 学 専 攻08
・研究テーマ・
・専門分野・
北條 芳隆 教授Y.Hojo大阪大学大学院文学研究科
・研究テーマ・
・専門分野・
松本 建速 教授T.Matsumoto筑波大学大学院歴史・人類学研究科
・研究テーマ・
・専門分野・
秋田 かな子 准教授K.Akita東海大学文学部史学科 (現:歴史学科)
・研究テーマ・
・専門分野・
宮原 俊一 講師S.Miyahara東海大学大学院文学研究科
第四紀の地磁気に関し、特に考古地磁気層序(房総半島)、火山灰中の磁性鉱物の熱磁気特性を中心に研究しています。ともに土層に含まれる鉱物から得る情報で、第四紀の環境復元の資料を提供しています。●受験生へのメッセージ:日ごろからいろいろなことに興味・関心を持つように心掛けてほしいと思います。
石器石材の岩種鑑定結果を用い、石材選択の問題や使用石材から見た地域性と石材移動を追究し、また肉眼による岩種鑑定を研究しています。さらに石材と古環境の復元にも関心を寄せています。●受験生へのメッセージ:真実に迫るにはいろいろな切り口から見る必要があります。石材からみる考古学、新しい切り口です。
人類がまだ遊動生活を送っていた時代、先土器時代について研究しています。特に、南関東地方の遺跡の分析を通じて、人類がどのように生活しどのような生産活動をしていたかに関心を持っています。●受験生へのメッセージ:人類がどんな方法で生きてきたかを知ることで、あなたの生き方を学んでください。
日本の弥生時代は、人々がダイナミックに活動し、文物と情報が行き交う激動の時代です。そして、各地域でクニというまとまりが誕生していきます。その過程を、遺跡の分析を通して明らかにしたいと考えています。●受験生へのメッセージ:執着心と粘着性、通説にとらわれない発想が明日を拓く。
・研究テーマ・
・専門分野・
會田 信行 非常勤講師N.Aida北海道大学大学院理学研究科
・研究テーマ・
・専門分野・
柴田 徹 非常勤講師T.Shibata東京教育大学理学部地学科
・研究テーマ・
・専門分野・
田尾 誠敏 非常勤講師M.Tao東海大学文学部史学科 (現:歴史学科)
日本考古学のうち文献史料が登場してからの歴史時代について、相模地域を中心に研究を行っています。特に土器を通して当時の社会をどのように読み解くことができるかに興味をもっています。●受験生へのメッセージ:発掘調査から得た資料を扱い解釈するために経験と知識を培ってください。
古代エジプトのファイアンス(やきもの)やガラスなどの研究と、日本の最先端の科学技術を考古学に応用した考古科学の研究を行っています。原材料や製品の動きを追うことで、古代の交易や経済のシステムが見えてきます。●受験生へのメッセージ:古代エジプト文明の謎を一緒に解き明かしましょう。
・研究テーマ・
・専門分野・
伊藤 健 非常勤講師T.Ito國學院大學大学院文学研究科
・研究テーマ・
・専門分野・
立花 実 非常勤講師M.Tachibana東海大学文学部史学科 (現:歴史学科)
古墳時代、墳丘墓、前方後円墳、腕輪形石製品
日本考古学
縄文時代、土器型式論、住居構造
日本考古学
縄文時代~中世、蝦夷、胎土分析、鉄生産
日本考古学
縄文時代、土器、古代技術
日本考古学
第四紀、考古磁気、環境磁気学、磁性鉱物
第四紀学
石器時代、石材、実証性、複数の視点
応用岩石学
弥生時代、地域社会、階級性、情報ネットワーク
日本考古学
歴史時代、土器、交易、地域社会
日本考古学
特に長江流域の新石器文化について研究を進めています。集落の構造・墓の構造や埋葬の仕方・農耕技術などから当時の社会を復元し、現在の私たちの生活にどのように影響してきたのかを調べています。 ほかに日本考古学史について、近代日本の成長を通して研究しています。●受験生へのメッセージ:則天去私。
・研究テーマ・
・専門分野・
小柳 美樹 非常勤講師Y.Koyanagi東海大学大学院文学研究科
中国考古学、新石器文化、長江、飲食文化
中国考古学
先土器時代、南関東地方、石器形態、人類の領域
日本考古学
バルカン半島で食糧生産経済が導入されてから、いかにして青銅器時代が始まったのか、その過程について研究しています。土器などの分析をもとに、当時の文化と社会のあり方について考えています。●受験生へのメッセージ:経験の数と直感でモノの見方を豊かにしてください。
インド北西部に所在するインダス文明遺跡の考古学的調査に従事し、インダス文明の社会構造や古代都市のあり方について、思考実験を繰り返しています。インド留学や毎年のインド調査を経て、現地にもすっかり慣れてしまい、インドカレーもおいしく作れるようになりました。●受験生へのメッセージ:考古学とは人間を成長させる学問です。毎日のように思考実験を繰り返しながら、元気に明るく、考古学を楽しんでみてください。
・研究テーマ・
・専門分野・
千本 真生 非常勤講師M.Semmoto東海大学大学院文学研究科
・研究テーマ・
・専門分野・
小茄子川 歩 非常勤講師A.Konasukawaデカン大学院大学考古学科
バルカン半島、新石器時代~青銅器時代、環黒海、原印欧語族
南東ヨーロッパ考古学
インダス文明、古代都市、南アジア型発展径路
南アジア考古学
縄文時代以来の日本列島、主に東日本に住んでいた人々について研究しています。多面的に人間を見るためにさまざまな方法でアプローチしています。特に、人間の自然への働きかけ方の変化に注目しています。●受験生へのメッセージ:土に残されたメッセージ、皆さんと読み解ける日を楽しみにしています。
縄文時代の型式のあり方や変化のしかたについて考えています。また縄文時代の住居について、その構造や地域性に興味があります。これらを総合し縄文時代の社会構造の解明を目指しています。●受験生へのメッセージ:いつでも研究室、そして整理作業室に見学に来てください。
日本の古墳時代、特に前方後円墳の出現過程に焦点をあて墳丘の存在理由、墓の構築に注ぎ続けたエネルギーとは何かを調べています。また沖縄県西表島の調査にともない「日本文化」の正体に迫っています。●受験生へのメッセージ:「もの」にこだわってナンボの粘着質の世界で、しかも体力勝負、それが考古学です。
主に縄文時代から弥生時代の文化や社会について研究しています。土器や石器をはじめとするさまざまな考古資料から、古代の人々の暮らしぶりを明らかにしていきたいと考えています。●受験生へのメッセージ:関心、疑問、挑戦、持続、体力。5つのキーワードが大学生活をより豊かなものにします。
・研究テーマ・
・専門分野・
山花 京子 准教授(兼担)K.Yamahanaシカゴ大学文学部大学院
アジア文明学科
古代エジプト、ファイアンス、ガラス、考古科学
エジプト学・考古科学
人類は、約1万年前の氷河期が終わったころに、農耕や牧畜という新たなライフスタイルを始めました。農耕や牧畜は世界のいくつかの中心地で始まりました。その一つが中東(西アジア)です。私は、大昔の人々が、いつ、どのように、農耕や牧畜を始めたのか、その起源とプロセスを探るために中東やコーカサス地方で発掘調査を行っています。●受験生へのメッセージ:若いときにしかできないことがあります。考古学では、貴重な経験ができます。
・研究テーマ・
・専門分野・
有村 誠 准教授M.Arimuraリヨン第2大学大学院
コーカサス、農耕の起源、新石器化、文化遺産の保護と活用、石器
西アジア考古学

古墳に学ぶ
■北條 芳隆 [教授]
ClipBoard
私の研究室では、前方後円墳の出現期に焦点をあてて古墳の研究を主に進めてきました。しかし現在は沖縄県西表島の初期農耕集落と、北海道旭川にあるアイヌ文化期のチャシ跡遺跡の調査も古墳の調査と並行して進めているところです。 前方後円墳の出現場所が本州の中心にある大和だとすると、西表島は日本列島の南端、旭川は北端になります。これら3地域で展開した過去を掘り下げながら、「日本史」や「日本文化」を捉えなおそうと考えています。写真は長野県伊那谷での古墳調査時のものです。
C l i p B o a r d #1
C l i p B o a r d #3
C l i p B o a r d #2
研究室を離れて時空を超えて人間を知る
土器を読む
回す!
■宮原 俊一 [講師]
■秋田 かな子[准教授]
■松本 建速 [教授]
ClipBoard
ClipBoard
ClipBoard
日本列島上の縄文時代以来の人々がどんな言葉を話していたのかを考古学的に考える研究に取り組んでいます。関連するすべての学問を総動員し、ありとあらゆるデータを使って考える「総合考古学」です。日本列島上の東側には、後にアイヌ語となった言葉を話す人々が住んでいました。遮光器土偶をともなうことで有名な亀ヶ岡式土器を使う人々は、おそらくその系統の言葉を話していました。同時代の日本列島西側の人々とは言葉が違っていたのでしょう。現在の日本語となるやまと言葉は、いつから話されるようになったのでしょう。 土を掘り過去への旅をするためのガイドブックは、現在の世界です。北海道のアイヌ語と日本語の地名の残り方の研究も始めました。考古学は、歴史学というだけでなく、時間も空間も超えた人類学です。
縄文時代の土器や石器、人々が暮らしていた遺跡や住居のことなどにいろいろと想いを巡らせていますが、とりわけ縄文土器が好きです。理由は、土器は器であるだけではなく、人々の間を取り結ぶはたらきを持つツールだと思っているからです。ちょっと難しく言うと、「土器にはコミュニケーションを媒介する機能があって、文様・装飾・造形には地域間のネットワークの結び方とその仕組みが表われているのだ」と表現することができます。 写真は、そんな縄文土器のなかでもコミュニケーションを媒介する機能に特化した、「注口土器」と呼ばれる土器の注ぎ口と把手の部分を集めたものです。ふふふ、ちょっとマニアックですね。でも、遠い過去の人々が遺したこれらの土器が、私と彼らの間を取り結んでいることは確かですよ。
ある人は回転台と呼び、またある人はロクロと呼んでいるものを回しています。足で下の円盤を回し、これに連結する上の円盤に回転を与えているのです。上の円盤には粘土が置かれ、回転する力を利用しながら土器を作ろうとしているのです。このように、“かつて使われていた道具”をいろいろ復元し、これを実際に使ってみることで、道具の動きや扱い方を頭で考え、身体で試しているのです。 普段は縄文時代の研究をしていますが、その方法の一つとして、技術史的な側面から過去の生活や文化を見つめなおす作業を行っています。ただ考えるだけでなく、身体を動かすことによって生まれてくる多くの発見や謎もあるのです。
㈰
C l i p B o a r d #4
■ 歴 史 学 科 考 古 学 専 攻10 Course of Archaeology, Department of History ■ 11
研 究 紹 介・フィー ルド 便 り考 古 学 カ レ ン ダ ー
入学から卒業までの4年間、考古学専攻生は大学での授業に加え、夏と春の長期休暇を利用して国内外で実施される発掘調査に積極的に参加しています。また、サークル活動やアルバイト、就職活動や卒業論文など、盛りだくさんのメニューをこなしながら充実した4年間を送っています。
たかはし いちこ(2008年度卒業) Copyright(c) Ichiko Takahashi.
All rights reserved

古墳に学ぶ
■北條 芳隆 [教授]
ClipBoard
私の研究室では、前方後円墳の出現期に焦点をあてて古墳の研究を主に進めてきました。しかし現在は沖縄県西表島の初期農耕集落と、北海道旭川にあるアイヌ文化期のチャシ跡遺跡の調査も古墳の調査と並行して進めているところです。 前方後円墳の出現場所が本州の中心にある大和だとすると、西表島は日本列島の南端、旭川は北端になります。これら3地域で展開した過去を掘り下げながら、「日本史」や「日本文化」を捉えなおそうと考えています。写真は長野県伊那谷での古墳調査時のものです。
C l i p B o a r d #1
C l i p B o a r d #3
C l i p B o a r d #2
研究室を離れて時空を超えて人間を知る
土器を読む
回す!
■宮原 俊一 [講師]
■秋田 かな子[准教授]
■松本 建速 [教授]
ClipBoard
ClipBoard
ClipBoard
日本列島上の縄文時代以来の人々がどんな言葉を話していたのかを考古学的に考える研究に取り組んでいます。関連するすべての学問を総動員し、ありとあらゆるデータを使って考える「総合考古学」です。日本列島上の東側には、後にアイヌ語となった言葉を話す人々が住んでいました。遮光器土偶をともなうことで有名な亀ヶ岡式土器を使う人々は、おそらくその系統の言葉を話していました。同時代の日本列島西側の人々とは言葉が違っていたのでしょう。現在の日本語となるやまと言葉は、いつから話されるようになったのでしょう。 土を掘り過去への旅をするためのガイドブックは、現在の世界です。北海道のアイヌ語と日本語の地名の残り方の研究も始めました。考古学は、歴史学というだけでなく、時間も空間も超えた人類学です。
縄文時代の土器や石器、人々が暮らしていた遺跡や住居のことなどにいろいろと想いを巡らせていますが、とりわけ縄文土器が好きです。理由は、土器は器であるだけではなく、人々の間を取り結ぶはたらきを持つツールだと思っているからです。ちょっと難しく言うと、「土器にはコミュニケーションを媒介する機能があって、文様・装飾・造形には地域間のネットワークの結び方とその仕組みが表われているのだ」と表現することができます。 写真は、そんな縄文土器のなかでもコミュニケーションを媒介する機能に特化した、「注口土器」と呼ばれる土器の注ぎ口と把手の部分を集めたものです。ふふふ、ちょっとマニアックですね。でも、遠い過去の人々が遺したこれらの土器が、私と彼らの間を取り結んでいることは確かですよ。
ある人は回転台と呼び、またある人はロクロと呼んでいるものを回しています。足で下の円盤を回し、これに連結する上の円盤に回転を与えているのです。上の円盤には粘土が置かれ、回転する力を利用しながら土器を作ろうとしているのです。このように、“かつて使われていた道具”をいろいろ復元し、これを実際に使ってみることで、道具の動きや扱い方を頭で考え、身体で試しているのです。 普段は縄文時代の研究をしていますが、その方法の一つとして、技術史的な側面から過去の生活や文化を見つめなおす作業を行っています。ただ考えるだけでなく、身体を動かすことによって生まれてくる多くの発見や謎もあるのです。
㈰
C l i p B o a r d #4
■ 歴 史 学 科 考 古 学 専 攻10 Course of Archaeology, Department of History ■ 11
研 究 紹 介・フィー ルド 便 り考 古 学 カ レ ン ダ ー
入学から卒業までの4年間、考古学専攻生は大学での授業に加え、夏と春の長期休暇を利用して国内外で実施される発掘調査に積極的に参加しています。また、サークル活動やアルバイト、就職活動や卒業論文など、盛りだくさんのメニューをこなしながら充実した4年間を送っています。
たかはし いちこ(2008年度卒業) Copyright(c) Ichiko Takahashi.
All rights reserved

BK卒 業 後 の 進 路在学生・卒業生からのメッセージ
考古学専攻の学生の就職先は大きく2つに分かれます。一般企業に就職する学生と、
考古学の専門性を活かした職業に就く学生です。一般企業に就職した学生も考古学
を学んで得た貴重な体験を職場で活かしています。
• 岩手県文化振興事業団• 山形県埋蔵文化財センター• 群馬県立自然史博物館• 埼玉県埋蔵文化財調査事業団
就 職(2014年度)
一 般 企 業 公 官 庁
専門性を活かした職業
進 学(2013~ 2015年度)
そのほか大学院進学者も増えています。大学院では考古学あるいは関連する周辺分野の学問をより専門的に研究します。近年では右のような例があります。考古学研究の幅広さが現れています。
• 東海大学大学院
• 鹿児島大学大学院
• 筑波大学大学院
• 鳴門教育大学大学院
• 兵庫教育大学大学院
• 國學院大学大学院
• 奈良大学大学院
大 学 院
進 路
土屋 了介 さん ■2006年度卒業 神奈川県小田原市文化財課世界の成り立ちを探求する
• ウチダテクノ• 佐賀鉄工所• プロシーズ• ヒガシトゥエンティワン• 小田急商事• ツルヤ• ビックカメラ• コープみらい• やまと• 石橋楽器店• ノジマ• LEOC• ステラコーポレーション
学 校
■ 歴 史 学 科 考 古 学 専 攻12 Course of Archaeology, Department of History ■ 13
後藤 功介 さん ■3年次 私立東海大学付属菅生高等学校(東京都)出身好奇心が大事
宮本 由子 さん ■3年次 県立厚木高等学校(神奈川県)出身
皆さんは「考古学」と聞いて、どのようなイメージをもちますか? 私のイメージは、「古いお宝を探したり、古代の文字を解明したりするトレジャーハンターのようなもの」でした。学部・学科を選ぶ際も、このようなイメージと好奇心から、特に深い知識ももたずにこの専攻に入ることを決めたのです。 入学後、長期休暇期間には学外の発掘調査に初めて参加しました。最初のうちは調査責任者や先輩たちに教えてもらうことばかりでしたが、だんだんに慣れてきて、いよいよ自分で遺物を掘り出した瞬間は、やはりお宝を発見した気持ちでした。発掘調査の現場では、ほかの大学の学生との交流もあったため、トレジャーハント以外の「考古学」にも触れることができ、とても有意義な時間でした。 皆さんも、「考古学」を選ぶ理由がただの好奇心だったとしても、その気持ちを忘れないでください。それが大事だと思うのです。皆さんと一緒に学べる日を楽しみにしています。
独特な歴史学を学ぼう 私は昔から「もの」を観察することが好きでした。「もの」の形の意味を考えたり、それが作られなければいけなかった背景を知ったりすることに、とてもワクワクします。考古学専攻で学べる科目は、そのような好奇心を満たしてくれるものばかりです。 入学してから、考古学にはほかの歴史学とは全く違う勉強が必要であると知りました。ほとんどの授業で文字史料は使いません。資料となるのは土器の実測図や地形図などです。それらをどう見れば歴史を探れるのか、授業では考古学独特の方法について段階を踏んで教わっています。また、発掘現場では、地形から土地の利用方法を予測したり、遺物の出土状況から過去にそこで何が起きたのか考えたりします。これらにはさまざまな知識が求められるため、勉強の幅がおのずと広がりました。入学以前と比べて、ありきたりな日常風景に向ける目も変わってきたと感じています。 私にとって考古学は、自分の今置かれている社会や環境にあらためて興味をもたせてくれるキッカケになっています。
※過去の実績を含む
皆さんは自分自身のことをよく知っているでしょうか。 現代の日本で暮らす私たちの多くは、米を食べ、鍋などで加熱調理をし、日本語で読み書きをし、考え、判断をする、といったことを自然に行っています。しかしながら、以上のような行動は、歴史的な出来事の積み重ねの結果、はじめて私たちの生活の一部となったものなのです。 現在の米を主食とする食生活は、弥生時代に日本列島の広い範囲で水稲耕作が根づき、その後、稲の生産性を向上させることで成り立ちました。ただし、そうなるまでには紆余曲折があり、過去の人々の試行錯誤や努力の積み重ねのおかげで現在にいたったといえるのです。それは箸や匙などの食具や、日常生活を支えるその他の道具・工具類についても当てはまりますし、家を建てる際の地鎮祭のような、精神的な活動や風習についても同様に考えることができます。 考古学を学ぶうちに、皆さんは自分の日常生活を形作る諸要素の成り立ちを、実物(遺物)から実証的に探求することになります。日常生活にとどまらず、世界の成り立ちについて考えてみませんか?
さじ
• 文化庁• 新潟県庁• 宮城県教育委員会• 山梨県教育委員会• 大和市教育委員会
• 東海大学付属小学校〔現:東海大学付属静岡翔洋小学校〕• 神奈川県公立高等学校

BK卒 業 後 の 進 路在学生・卒業生からのメッセージ
考古学専攻の学生の就職先は大きく2つに分かれます。一般企業に就職する学生と、
考古学の専門性を活かした職業に就く学生です。一般企業に就職した学生も考古学
を学んで得た貴重な体験を職場で活かしています。
• 岩手県文化振興事業団• 山形県埋蔵文化財センター• 群馬県立自然史博物館• 埼玉県埋蔵文化財調査事業団
就 職(2014年度)
一 般 企 業 公 官 庁
専門性を活かした職業
進 学(2013~ 2015年度)
そのほか大学院進学者も増えています。大学院では考古学あるいは関連する周辺分野の学問をより専門的に研究します。近年では右のような例があります。考古学研究の幅広さが現れています。
• 東海大学大学院
• 鹿児島大学大学院
• 筑波大学大学院
• 鳴門教育大学大学院
• 兵庫教育大学大学院
• 國學院大学大学院
• 奈良大学大学院
大 学 院
進 路
土屋 了介 さん ■2006年度卒業 神奈川県小田原市文化財課世界の成り立ちを探求する
• ウチダテクノ• 佐賀鉄工所• プロシーズ• ヒガシトゥエンティワン• 小田急商事• ツルヤ• ビックカメラ• コープみらい• やまと• 石橋楽器店• ノジマ• LEOC• ステラコーポレーション
学 校
■ 歴 史 学 科 考 古 学 専 攻12 Course of Archaeology, Department of History ■ 13
後藤 功介 さん ■3年次 私立東海大学付属菅生高等学校(東京都)出身好奇心が大事
宮本 由子 さん ■3年次 県立厚木高等学校(神奈川県)出身
皆さんは「考古学」と聞いて、どのようなイメージをもちますか? 私のイメージは、「古いお宝を探したり、古代の文字を解明したりするトレジャーハンターのようなもの」でした。学部・学科を選ぶ際も、このようなイメージと好奇心から、特に深い知識ももたずにこの専攻に入ることを決めたのです。 入学後、長期休暇期間には学外の発掘調査に初めて参加しました。最初のうちは調査責任者や先輩たちに教えてもらうことばかりでしたが、だんだんに慣れてきて、いよいよ自分で遺物を掘り出した瞬間は、やはりお宝を発見した気持ちでした。発掘調査の現場では、ほかの大学の学生との交流もあったため、トレジャーハント以外の「考古学」にも触れることができ、とても有意義な時間でした。 皆さんも、「考古学」を選ぶ理由がただの好奇心だったとしても、その気持ちを忘れないでください。それが大事だと思うのです。皆さんと一緒に学べる日を楽しみにしています。
独特な歴史学を学ぼう 私は昔から「もの」を観察することが好きでした。「もの」の形の意味を考えたり、それが作られなければいけなかった背景を知ったりすることに、とてもワクワクします。考古学専攻で学べる科目は、そのような好奇心を満たしてくれるものばかりです。 入学してから、考古学にはほかの歴史学とは全く違う勉強が必要であると知りました。ほとんどの授業で文字史料は使いません。資料となるのは土器の実測図や地形図などです。それらをどう見れば歴史を探れるのか、授業では考古学独特の方法について段階を踏んで教わっています。また、発掘現場では、地形から土地の利用方法を予測したり、遺物の出土状況から過去にそこで何が起きたのか考えたりします。これらにはさまざまな知識が求められるため、勉強の幅がおのずと広がりました。入学以前と比べて、ありきたりな日常風景に向ける目も変わってきたと感じています。 私にとって考古学は、自分の今置かれている社会や環境にあらためて興味をもたせてくれるキッカケになっています。
※過去の実績を含む
皆さんは自分自身のことをよく知っているでしょうか。 現代の日本で暮らす私たちの多くは、米を食べ、鍋などで加熱調理をし、日本語で読み書きをし、考え、判断をする、といったことを自然に行っています。しかしながら、以上のような行動は、歴史的な出来事の積み重ねの結果、はじめて私たちの生活の一部となったものなのです。 現在の米を主食とする食生活は、弥生時代に日本列島の広い範囲で水稲耕作が根づき、その後、稲の生産性を向上させることで成り立ちました。ただし、そうなるまでには紆余曲折があり、過去の人々の試行錯誤や努力の積み重ねのおかげで現在にいたったといえるのです。それは箸や匙などの食具や、日常生活を支えるその他の道具・工具類についても当てはまりますし、家を建てる際の地鎮祭のような、精神的な活動や風習についても同様に考えることができます。 考古学を学ぶうちに、皆さんは自分の日常生活を形作る諸要素の成り立ちを、実物(遺物)から実証的に探求することになります。日常生活にとどまらず、世界の成り立ちについて考えてみませんか?
さじ
• 文化庁• 新潟県庁• 宮城県教育委員会• 山梨県教育委員会• 大和市教育委員会
• 東海大学付属小学校〔現:東海大学付属静岡翔洋小学校〕• 神奈川県公立高等学校

SC HOOLOFLETTERS
http://www.u-tokai.ac. jp/academics/undergraduate/ letters/
Cou
rse of A
rchaeo
logy,
Dep
artmen
t of H
istory
Scho
ol o
f Letters
文学部のアドミッションポリシーについては、本学ホームページに掲載しておりますのでそちらをご覧ください。http://www.u-tokai.ac.jp/about/philosophy_history/concept/admission_policy.html
現代は激動の時代。東海大学文学部は、そのなかを生き抜くための「自分の座標軸」を獲得する場所です。文学部の14学科・専攻では、授業から課外活動にいたるあらゆる領域で、そのための環境づくりに取り組んでいます。
先輩たちは、今、何をしているの?――14学科・専攻在学生へのインタビューから――
世界をより的確に知るために、英語力を鍛えようと思っています!
――文学部では、【TOEIC®テスト団体受験】の機会を提供。1・2年次は無料で受験できるほか、さまざまな受験優遇策を用意しています。
海外研修旅行に行きます。直接世界を体験して、学んだ言葉を活かしたい!
――文学部には、アジア、ヨーロッパ、北欧、アメリカ大陸へ出かける【海外研修授業】があります。またアラビア語、ギリシア語など【多様なアジア・ヨーロッパの言語の入門科目】も用意されています。
まずは日本語の表現力、コミュニケーション力を磨くことを考えています!
――文学部では、すべての授業で【読む(Read)・書く(Write)・話す(Speak)3つの力を養う目標】をシラバス(授業計画)に掲げ、全教
員が工夫して授業に臨んでいます。オムニバス形式の文学部共通授業【ことばの世界】も開講されています。
情報発信の力をつけたい。メッセージを広く社会に届ける活動をしています!
――文学部には【キャンパススタジオ】があり、学生たちが主体となって放送番組(テレビ、ラジオ、ネット放送)を制作し、社会的にも高い評価を受けています。
先生方と一緒に、大学での研究や学びを地域の皆さんと共有するイベントを開いています!
――文学部には、専用の小さな博物館【文学部展示室】(3号館4階)があります。また【知のコスモス】の名のもとに、教員の研究を紹介する番組や、講演会・イベントなども頻繁に開かれ、地域の皆さんと学びあう場が生まれています。
「人間とは何か」「世界の多様性」について、幅広い視点を身につけたい!
――文学部には、【知のフロンティア】など学科・専攻の枠を超えたオムニバス授業や、教育研究プロジェクトがいくつもあります。【副専攻制度】も充実。交流することから学びも広がります。
文学部[学科構成]文 明 系●文明学科 ●アジア文明学科 ●ヨーロッパ文明学科 ●アメリカ文明学科 ●北欧学科
歴 史 系●歴史学科 日本史専攻 ●歴史学科 東洋史専攻 ●歴史学科 西洋史専攻 ●歴史学科 考古学専攻
言語文学系●日本文学科 ●文芸創作学科 ●英語文化コミュニケーション学科
現代社会系●広報メディア学科 ●心理・社会学科
文学部は、皆さんの資格取得を応援し、レベルアップの場を提供します。
資 格
◆高等学校教諭一種免許状・・・教科:地理歴史◆中学校教諭一種免許状・・・・・教科:社会
【教職課程】 学科・専攻・課程に設置され、特定の免許教科について、高等学校及び中学校の教員免許状を取得するために学修します。本学科の卒業者で、卒業までに教職に必要な所定の科目(教職に関する科目、教科に関する科目など)を修得すれば、下記の免許教科についての免許状を取得することができます。
【学芸員課程】 博物館学芸員の資格を取得するために必要な知識と技術を学修します。博物館・美術館・水族館・動物園・資料館など、歴史・芸術・自然科学などに関する資料を収集、展示する機関で働く学芸員は、専門職としての資格が必要です。学芸員に必要な所定の科目を修得し、本学科を卒業することで、資格を取得できます。
【司書・司書教諭課程】 司書・司書教諭の資格を取得するために必要な基礎知識と技術を学修します。 生涯学習が盛んとなってきている現代社会において、図書館の文献・資料は、独自の学習・研究で早急に諸情報を収集する場合だけでなく、多種多様な知的関心を充足させるのに欠かせないものとなっています。 図書館の利用者に的確な情報を提供することは司書の役目であり、大量の情報が集約された文献・資料、あるいはデータベース化された記録媒体などから情報を提供するための知識と技術が求められています。 司書に必要な所定の科目を修得し、本学科を卒業することで、資格を取得できます。 なお、司書教諭とは、学校図書館の教育・専門的職務に従事する教員をいい、教職課程を履修し、本学科所定の科目を修得すれば取得できます。
【社会教育主事】 21世紀は生涯教育の時代といわれています。こうした時代に力を発揮するのが社会教育主事の資格です。社会教育を行う方に指導と助言をすることのできる資格です。所定の科目を修得し、1年以上の社会教育主事補の職を経験し、試験に合格すれば、資格を取得できます。
・当・該・学・科・で・取・得・で・き・る・免・許・
●教員試験講座 教員採用試験に出題される科目のうち、一般教養・教職教養・面接対策・論作文に的を絞り、指導経験豊富な講師陣によって行われる実践的な特別講座です。
●公務員講座 各種の公務員試験に出題される教養・専門科目のなかでも出題数の大半を占める主要科目を中心に、問題演習などを含めて実際の試験に即した授業を行います。
●そのほかにも、金融セミナーや、マスコミ講座・日商簿記(2級・3級)・秘書検定(1級・準1級・2級)などの講座・勉強会を実施しています。
各種講座について(含有料)
●JOB-LEAGUEは東海大学のインターンシップ(企業での就業体験)制度です。 他大学より早く、2年次の春期休暇中に実施しています。先輩の体験談もあるガイダンスが秋に開催されます。
東海大学JOB-LEAGUE
LEVEL UP!
Course of Archaeology, Department of History ■ 15■ 歴 史 学 科 考 古 学 専 攻14

SC HOOLOFLETTERS
http://www.u-tokai.ac. jp/academics/undergraduate/ letters/
Cou
rse of A
rchaeo
logy,
Dep
artmen
t of H
istory
Scho
ol o
f Letters
文学部のアドミッションポリシーについては、本学ホームページに掲載しておりますのでそちらをご覧ください。http://www.u-tokai.ac.jp/about/philosophy_history/concept/admission_policy.html
現代は激動の時代。東海大学文学部は、そのなかを生き抜くための「自分の座標軸」を獲得する場所です。文学部の14学科・専攻では、授業から課外活動にいたるあらゆる領域で、そのための環境づくりに取り組んでいます。
先輩たちは、今、何をしているの?――14学科・専攻在学生へのインタビューから――
世界をより的確に知るために、英語力を鍛えようと思っています!
――文学部では、【TOEIC®テスト団体受験】の機会を提供。1・2年次は無料で受験できるほか、さまざまな受験優遇策を用意しています。
海外研修旅行に行きます。直接世界を体験して、学んだ言葉を活かしたい!
――文学部には、アジア、ヨーロッパ、北欧、アメリカ大陸へ出かける【海外研修授業】があります。またアラビア語、ギリシア語など【多様なアジア・ヨーロッパの言語の入門科目】も用意されています。
まずは日本語の表現力、コミュニケーション力を磨くことを考えています!
――文学部では、すべての授業で【読む(Read)・書く(Write)・話す(Speak)3つの力を養う目標】をシラバス(授業計画)に掲げ、全教
員が工夫して授業に臨んでいます。オムニバス形式の文学部共通授業【ことばの世界】も開講されています。
情報発信の力をつけたい。メッセージを広く社会に届ける活動をしています!
――文学部には【キャンパススタジオ】があり、学生たちが主体となって放送番組(テレビ、ラジオ、ネット放送)を制作し、社会的にも高い評価を受けています。
先生方と一緒に、大学での研究や学びを地域の皆さんと共有するイベントを開いています!
――文学部には、専用の小さな博物館【文学部展示室】(3号館4階)があります。また【知のコスモス】の名のもとに、教員の研究を紹介する番組や、講演会・イベントなども頻繁に開かれ、地域の皆さんと学びあう場が生まれています。
「人間とは何か」「世界の多様性」について、幅広い視点を身につけたい!
――文学部には、【知のフロンティア】など学科・専攻の枠を超えたオムニバス授業や、教育研究プロジェクトがいくつもあります。【副専攻制度】も充実。交流することから学びも広がります。
文学部[学科構成]文 明 系●文明学科 ●アジア文明学科 ●ヨーロッパ文明学科 ●アメリカ文明学科 ●北欧学科
歴 史 系●歴史学科 日本史専攻 ●歴史学科 東洋史専攻 ●歴史学科 西洋史専攻 ●歴史学科 考古学専攻
言語文学系●日本文学科 ●文芸創作学科 ●英語文化コミュニケーション学科
現代社会系●広報メディア学科 ●心理・社会学科
文学部は、皆さんの資格取得を応援し、レベルアップの場を提供します。
資 格
◆高等学校教諭一種免許状・・・教科:地理歴史◆中学校教諭一種免許状・・・・・教科:社会
【教職課程】 学科・専攻・課程に設置され、特定の免許教科について、高等学校及び中学校の教員免許状を取得するために学修します。本学科の卒業者で、卒業までに教職に必要な所定の科目(教職に関する科目、教科に関する科目など)を修得すれば、下記の免許教科についての免許状を取得することができます。
【学芸員課程】 博物館学芸員の資格を取得するために必要な知識と技術を学修します。博物館・美術館・水族館・動物園・資料館など、歴史・芸術・自然科学などに関する資料を収集、展示する機関で働く学芸員は、専門職としての資格が必要です。学芸員に必要な所定の科目を修得し、本学科を卒業することで、資格を取得できます。
【司書・司書教諭課程】 司書・司書教諭の資格を取得するために必要な基礎知識と技術を学修します。 生涯学習が盛んとなってきている現代社会において、図書館の文献・資料は、独自の学習・研究で早急に諸情報を収集する場合だけでなく、多種多様な知的関心を充足させるのに欠かせないものとなっています。 図書館の利用者に的確な情報を提供することは司書の役目であり、大量の情報が集約された文献・資料、あるいはデータベース化された記録媒体などから情報を提供するための知識と技術が求められています。 司書に必要な所定の科目を修得し、本学科を卒業することで、資格を取得できます。 なお、司書教諭とは、学校図書館の教育・専門的職務に従事する教員をいい、教職課程を履修し、本学科所定の科目を修得すれば取得できます。
【社会教育主事】 21世紀は生涯教育の時代といわれています。こうした時代に力を発揮するのが社会教育主事の資格です。社会教育を行う方に指導と助言をすることのできる資格です。所定の科目を修得し、1年以上の社会教育主事補の職を経験し、試験に合格すれば、資格を取得できます。
・当・該・学・科・で・取・得・で・き・る・免・許・
●教員試験講座 教員採用試験に出題される科目のうち、一般教養・教職教養・面接対策・論作文に的を絞り、指導経験豊富な講師陣によって行われる実践的な特別講座です。
●公務員講座 各種の公務員試験に出題される教養・専門科目のなかでも出題数の大半を占める主要科目を中心に、問題演習などを含めて実際の試験に即した授業を行います。
●そのほかにも、金融セミナーや、マスコミ講座・日商簿記(2級・3級)・秘書検定(1級・準1級・2級)などの講座・勉強会を実施しています。
各種講座について(含有料)
●JOB-LEAGUEは東海大学のインターンシップ(企業での就業体験)制度です。 他大学より早く、2年次の春期休暇中に実施しています。先輩の体験談もあるガイダンスが秋に開催されます。
東海大学JOB-LEAGUE
LEVEL UP!
Course of Archaeology, Department of History ■ 15■ 歴 史 学 科 考 古 学 専 攻14

Course of Archaeology, Department of HistorySchool of Letters
2016.4 BK14◎本案内は、特に記載がない限り2016年4月現在の内容を掲載しています。
常に未来を見据え自らが取り組むべき課題を探求する力
多様な人々の力を結集する力
困難かつ大きな課題に勇気をもって挑戦する力
失敗や挫折を乗り越えて目標を実現していく力
成し遂げ力挑み力
集い力自ら考える力
「4つの力」のイメージキャラクターリッキー
「明日の歴史を担う強い使命感と豊かな人間性をもった人材」に育つよう、全学を挙げて取り組んでいます。
東 海 大 学 は 4 つの力を育 成します。
〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1Tel:0463-58-6422(直通) Fax:0463-50-2186
入試広報課


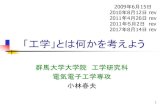
















![工学専攻[A日程] this page2018(平成30)年度10月入学(工学専攻) 1 平成30年度10月入学 信州大学大学院総合理工学研究科(修士課程) 工学専攻](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5aa093fb7f8b9a6c178e429d/a-translate-this-page20183010.jpg)