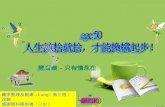捨て犬・捨て猫問題にどのように立ち向かうか...捨て犬・捨て猫問題にどのように立ち向かうか 55 いえる。図2では環境破壊の大きな原因を作った人間が加害者でもあり,また土壌汚染や生態系破壊
た に 説 侖 と 對 は 立 に 法 捨 比 二 こ 然 さ 正 五 …...選 擇 の 文 に...
Transcript of た に 説 侖 と 對 は 立 に 法 捨 比 二 こ 然 さ 正 五 …...選 擇 の 文 に...

五
種
正
行
論
-
特
に
『選擇集』第
二章
を中心としてー
・
藤
堂
恭
俊
一
雜行の捨
・抛と異類
の助業
への止揚
二
正助二業
の勝劣、專傍と廢立、助正の二義
三
助業論と五種正行階梯論
一
雑行
の捨
・抛
と異類
の助
業
への止揚
、
法然は
『選擇集』第二章のなかで五種正行についてとりくんでいる。しかもその論述は正雜
二行封比
の形式のも
とにこころみている。法然はこの章において善導の正雜二行、助正二業の説を引用し、これを中心として
「善導和
侖
立二正雜比行一。捨二雜行二歸
一正行己
(第二章の標章)ということを論じている。この善導の正雜二行、助正二業の
説
は、
『觀經疏』卷第四散善義にお
いて深心を解釋するなかの就行立信の内容として論じたものである・先づ正行
に對比される雜行について考えてみようと思う。善導は就行立信を論ずるなかで、法然が第二章の標章として示し
た
「捨二雜行一」というような、あるいは同じく第二章私釋段で正雜二行の得失をめぐる五番の相對において示した
五
種
正
行
論
一〇三

一〇四
「西方行者。須下捨二雜行一、
修中正行上也」というような、
さらに第十六章私釋段のなかで示した畧選擇の文にみら
れる
「抛二諸雜行
一」というような、選捨の意志表示を行
つていな
いのである。善導はわずかに
「若行二後雜行一。師
心常聞斷。雖二廻向得ブ生。衆名二疎雜之行一也」ヒいうように、雜行の失を指摘するにとどまつているのである。偏
依善導
一甑を標榜する法然にして、なぜあえて善導が指摘しなかつたところの捨、抛どいうこどを言
い切つたので
あ
ろうか。またなにを根據とすることによつて、そのような斷言をなし得たのであろうか。
この問
いかけにたいして法然は
『逆修説法』のなかで、
「彌時機下。當世行者。
雜行往生云事。
思可レ繦事也」
(第六七日の読法)というように、時と機の觀點にたつて雜行
の捨てらるべきこヒを指摘している。こ
のことは雜行往
生
といつていることから知られるように、
雜行は往生行でないから
「思可レ繦」と示したのではな
い。
法然は善導
と同じように
「往生行雖レ多。
大分爲レニ。
一者正行。二者雜行」(『選擇集』第二章私釋段)といつているように、
雜
行もまた正行とならんで、まぎれもなく往生行であることには相違ないという建前にたつているのである。それに
・
も
かかわらず時機不相應蓄
う觀點にたつて、
恵
可レ紹」と斷言しているのである。
はたしてこのよ.つに、
時と
讐
いう觀點から捨、ということを斷定しうるのであろうか。なぜな
らば、正法時、像法時と?つさ
つな末法時に
比してよりよい時期において、あるいは下品下生といつた最下の機根に比して、よりよい素質能力をもつ上中品に
た
いして、雜行に往生行としての効果を認あなければならないからである。從
つて時と機を觀點とする斷定は相對
的
であり・眞の斷定でなく、ただ限られた時機のなかだけの斷言におわつてしξ
つであそ
つ。しかれば捨、抛をな
りたたしめる根源的な理由とばいつたいなんであろうか。なにに基準をおいて捨、抛を決断するのであ弓つか。
願生者にとつて信仰の對象
(所歸)とその目的
(所求)は、阿彌陀佛とその淨土に往生することであ
るが、いうとこ
ろ
の阿彌陀佛は、聖人をもふくめてあらゆる凡夫を漏れなく救
いとろうとする意志、すなわち本願
の聖意をもつて

晝
に對向している人格身であり、その淨土はそうした本勢
聖意を實現する救いの鬢
して蒔
彌陀怫の、意志を
はなれて在り得ない世界である。從
つてそのような淨土に往生を願うのであるから、その往生行
(去行)は、迎いと
ろうとする阿彌陀佛
の意志に基準をおいて取捨選擇がなさるべきであり、あま
つさえ阿彌陀佛の意志によつて往生
行
が既に用意され、仕度されていることを知るならば、願生者はこれを等閑覗することはできないわけである。法
然は
『三心義』
のなかで、
「正行といふは阿彌陀佛におきてした
(親)しき行なり。雜行といふは阿彌陀佛におきて
うど
(疎)き行なり」といつている。この法然による往生行にたいする親
。疎の分到は、かならずや阿彌陀佛の本願
の聖意に基準をおいてなされたことであろうと思われる。從
って法然が雜行にたいして捨
、抛を決
斷したのは、雜
行
がかかる本願の聖意にたいして疎であればこそであり、まさにここにその根源的な理由があると言
いうるであろ
う。先に指摘したように、正雜二行を分到した善導の遺文の上、明確な取捨選擇の意志表示を見出
し得ないのであ
るが、偏依善導
一師を標榜する法然があえて雜行の選捨を決斷したことは、はたして法然の獨斷であると言
いうる
であろうか。あるいはたとい善導の遺文のなかに捨、抛というような意志表示を見出せないとしても、法然をして
そのような決斷をあえて行わしあるような内容が、既に善導によつて用意されていたのであろうか。この問
いかけ
にたいして善導は、いかなる解答をよせてくれるであろうか。
善導は
『散善義』のなかで、雜行を
「若行一一後雜行一。翫心常問斷。
雖レ可二廻向得ワ生。
衆名二疎雜之行一也」と規
定している。この逡文をとおして、正雜二行分到
の創唱者である善導が、雜行
の雜をいかなる意味
において使用し
たかということの大體を知ることができる。この遺文のなか
「心常間斷」
という
のは、願生者がその信仰の對象で
あ
る阿彌陀佛にかかわる問題であり、
「可二廻向得7生」というのは、願生者
の信仰の目的である往
生にかかわる問
題
である。いうならぼこれは、阿彌陀佛とその淨土
への往生にたいして、この雜行がいかにかかわ
つているかを示
五
種
正
行
論
一〇五

一〇六
したものである。このような内容をもつ遺文を中心として雜行の雜たる所以を考えてみようと思う。先に指摘した
ように、願生者は阿彌陀佛とその淨土、および往生行の三者に
一貫する本願
の聖意にたいして、ねんごろな配慮を
なす
べきであるにも拘らず、雜行を行ずるということはその配慮を行
つていないなによ
りの證據である。このよう
に本願の聖意にもとつかない行を往生行として行ずることは、本願の聖意によつて所求、所歸、去行
の三者を
一貫
す
ることができないことを意味する。所求、所歸、去行の三者が阿彌陀佛の聖意によつて
一貫し得
てこそ、その信
仰
は純粹であるが、本願の聖意にもとつかない去行を行ずるということは、所求、所歸、去行三者
の
一貫性を破る
ことであり、信仰の純粹性をみだすことであるから不純
(A)といわなけれぼならない。また本願
の聖意に
もとつか
な
い去行を行ずるということは、いうならば、本願の聖意によつて
一貫
せしめられている所求、所歸
のなかに、異
質
な去行をまじえる
(B)ことでもある。
一は願生者における信仰の純粹性にかかわる問題であり、
一は信仰の封象
である阿彌陀佛の意志にかかわる問題である。さらに去行自身
の上からいうならぼ、本願の聖意にもとつかない雜
行
には種々の行を豫想することができる。
從つて本願
の聖意にもとつく
一筋
の行でない雜行には、
多種多樣の行
(C)があるといわなければならない。このA
・B
・C三者のなか、Aは
「心常間斷」という句にかかわりがあり、
Bは
「可二廻向得7生」という旬にかかわりをもつものである。すなわち、・先づAについていうならば、所求、所歸、
去行の三者を本願の聖意でつらぬくことができないということは、雜行を去行として行ずるからである。このこと
は往生行までも用意、仕度してすべてのものを救濟しようとする阿彌陀佛という人格身の意志にそわないこと~い
なぞおうとしないことであるから、阿彌陀佛と願生者とを直接的に結びつけ、佛凡の人格的なふれあいをな
りたた
し
める去行を行じないということである。從つて雜行を行ずるということは、佛凡の人格的な樹應
の道を閉
し、佛
凡
の間を斷繦せしめることになる。
「心常間斷」とはこの邊の滄息を物語ものである。次にBについていうならば、

雜行が本願
の聖意にもとつかない行、本願の聖意にもとつく行にたいして異質
の行であるということは、往生行と
して直接なものでないこと、本來的なものでないことを意味している。なぜなれば
「可二廻向得ワ生」といわれてい
るように、方向がえという屈折を得なければ、往生行としての効果をもたらすことができないからである。さらに
善導はこのように往生行として種々の難點をも
つ雜行を、疎雜之行とも名づけている。この
「疎雜之行」
の疎の字
には、もともと親しくな
い、おろそか、うとんずる、遠ざけるという意味がもたれている。これによると雜行は、
本願の聖意にたいして親しくないぼかりでなく、むしろそれをおろそかにし、遠ざけるというような違背
の傾向を
も持
つ行であることが知られるであろう。法然は
『選擇集』第二章において善導
の散善義
の文を引用し、これにた
いして私釋をこころみたあとに、善導の
『往生禮讃』の文を引用している。その
『往生禮讃』
の文
によると、雜行
の失を十三の多きにわたつて指摘している。このなか特に
「與二佛本願一不二相應一故。與
レ教相違故。不レ順二佛語一」
と指摘される三點は、雜行が阿彌陀佛の本願の聖意のみならず、釋迦、六方諸佛の意志にたいして違背するもので
あることを雄辨に物語
つている。
このように雜行に關する善導の遺文を理解するとき、法然が雜行を捨、抛した所以がおのずから知ることができ
るであろう。すなわち、佛凡の人格的樹應をなりたたしめないような行を、また廻向というような方向がえをここ
ろみなけれぼ往生行とならない行を、善導はすでに雜行と名づけ、疎雜之行と命名し、その難點を指摘しているの
である。善導はこのような雜行について捨、抛するという意志表示をしていないが、そのような決斷をなすべきこ
とを他人にゆだねているとも考えられるのである。このように考えるならば、法然が雜行にたいし
てこころみた捨、
抛
という決斷は、決して獨斷ではなく、そのように決斷をなさしめたのは、むしろ善導の遺文の行間にあふれる善
導
の意志であるといつても過言ではあるまい。法然が
『選擇集』の第二章を標章して
「善導和尚立二正雜
二行一。捨二
五
種
正
行
論
一〇七

一〇八
,..
雜
行
一歸
二正
行
一之文
」
ど
い
つた
の
は、
な
に
よ
り
も
こ
の
こ
と
を證
す
る
も
の
であ
る。
こ
の
よう
に捨
、
抛
さ
る
べき雜
行
を往
生
行
と
し
て、
正塙
と
併説
し
た
こと
は
ど
う
いう
意味
を
も
つて
いる
ので
あ
ろ
う
か。この問題について特に法然
の意圖するところを探叙
つてみようと思う。法然によるならば雜行とは具體的に菩
提心、三學、六波羅蜜等を指している。總じていうならばそれらは聖道門の行であるから、阿彌陀佛の本願
の聖意
にもとつく淨土門の行とはおのずから異質のものといわざるを得ない。從つて淨土門の立場にたつかぎり、聖道門
の行を内容とする雜行を捨、抛するのは至極當然のことであり、それは
『選擇集』第
一章においてこころみられた
「捨二聖道一正歸二淨土」
(第
一章の標章)と同意趣にもとつくものであるということができる。それにも拘らず、異質
覗される雜行を正行とならべて往生行と規定することは、雜行と名づけられる聖道門の行を、淨土門における往生
行
と對立する聖道門
の行としておわらさないためである。このことは淨土門の立場から、聖道門の行にたいして往生
行
としての任務、役割を與えることであり、聖道門の行を往生行の
一種として淨土門の實踐體系のなかに組み入れ
る
ことを意味する。このように聖道門
の行をして、淨土門の實踐體系のなかにその所を得しあると
いつても、もと
もと聖道門
の行であるから、それをして往生行としての効用を發揮せしめるべく廻向どいう方向がえが強要される
わけである。かくして
『選擇集』第
一章において
一端、捨聖歸淨として捨てられた聖道門を、いな聖道門をして聖
道門たらしめる具體的實踐である菩提心、三學、六波羅蜜等を、第二章にお
いて拾
いあげて、さとりのための行と
は別途な往生行として生かされた行が、
正行にたいする雜行である。
琺然は畧選擇において
「夫
速欲レ離二生死一。
に
二種勝法中。且閣二聖道門一。選入二淨土門一」と言
い、そのなか特に
「且」という字を「閣」にたいしておいているの
は、實はこの邊の滔息を豫想してのことである。いいかえれば、法然は第
一章においてさとりの教行證としての聖
道門を、淨土門に對立するものとして認めることによつてこれを捨てたのであるが、第三
早にお
いてさとりをひ、b

く
ための行を笙
行としてとりあげることによつて.塰
阻の實靉
系
のなか組
み・」んだのである、かく署
門
の行を塗
門における笙
行の
一警
してとりあげたからには、聖道門の寔
たいし百
的・(所求)の變更芳
向が
え
(廻向)とを
強
要
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つた
ので
あ
る
。
さ
ら
に畧
選擇
に
は
こ
の文
に續
いて
「正
雜
二行
中
。
且
抛
二諸
雜
行
一。
選
應
レ歸
ゴ正
行
一」
と
い
つて
いる。
こ
こに
も
ま
た
亘
Lの字を
「抛」にたいしておいているが、その
宜
Lはいかなることを雜行
の上に慧
しての。しとであ弓
つか。
こ
のことは本願の聖意にもとつく行でな
いものとして捨、抛したところの雜行を拾
いあげて、正定業
の能助として
の任務・役割を與えることである。
いいかえれば、雜行を異類
の助業
に止揚し、正定業にたいしてよりかかわりの
深
い行とし星
かすことである。このことについて法然は、
『選擇集』第四章私釋段
のなかで、助正
の義をあき
り
かにして
「爲助
二成念佛㌔
説二此諸行
。此亦有三
童
。
一以商
響
根莇
二成念塵
。二以二異響
根勣
歳
念佛こ
と
いつている・このなか異類の善磐
は旦體
的纂
かなる善根を指しているのであろ・つか。法然は異類
の善根を規
定
して
『無量壽經』所説の上輩にかぎ
つてい・つならば
「捨家棄欲。而作沙門。鑾
、提、奪
者。是助行也。亦是能助
也」と指摘している。このように雜行を異類の助業として、同類
の助業とならべて正定業
の能助とせしめるのは、
捨、抛が行われる領域
にお
いてでないことはたしかである。しからば雜行が異類
の助業として正定業
の能助となり
う
るのは、
いかなる領域にお
いてであろうか。
.
紛
法然は禪勝房の問いにたいして答えた
「或時遠江國蓮花寺住僣禪勝房參ご上人一奉レ問二種々之事
一上人
一々答レ之」
の第三の問答において、「我身乘二佛本願一之後。決定往生信起之上。結二縁他善
一事。全不レ可レ爲二雜行↓可レ成二往生
助業一也。善導釋申。已隨二(喜)他善根一。以二自他善根殉廻一一向淨土↓云云以二此釋
一可レ知也」といつている。このよう
に阿彌陀佛の本願の聖意にもとつく正定業を行ずることによつて、願生者に決定往生の信が確立して以後において、
五
種
正
行
論
一〇九

一一〇
雜行は始めて異類
の助業として正定業
の能助たりうるのである。ここにおいて注意しなけれぼならな
いことは、異
類
の助業が同類の助栗とならんで正定業を助成するということである。同類の助業はのちに論ずるごとく
「非本願
選擇之行」
でありながら、
なおかつ正定業とならんで
「阿彌陀佛におきてしたしき行」
とされるものである。こ
のような同類の助菓と肩をなら
べられて、異類の助莱が諡かれるということに首肯しがたい點がな
いであろうか。
同類
の助業は始めから助業として正定業を助成する行業であり、それを行ずるものをして正定業
へ方向づける行業
であるのに反し、異類
の助業は始めから異類
の助業でなく、むしろ雜行として、捨、抛さるべき行
であ
つたが、願
生者に決定往生の信が確立することによつて、正定業を助成する行業にまでたかめられた行業であ
る。從
つて前者
は最初から往生の行業として正定業
の上に止揚さるべきものであり、しかも正定業とのかかわりが直接的であるか
ら、
ことあたらしく廻向を必要としない行業であるのにたいして、後者は雜行と規定されたその領域において廻向
を待たなけれぼ往生行としての効用を發揮し得ない行である。このような讃誦等の助業と雜行との相違は・雜行が
異類
の助業にたかめられることによつてなくなるのであろうか。禪勝房の問いにたいする法然の解答によるかぎり・
爾
者の相違はながく繼續してなくならないのである。なぜなれば、法然の解答には、善導の廻向發願心釋に説
く廻
向
ということを銘記しているからである。かく廻向を必要とする異類の助業とそれを必要としない同類
の助業は同
格硯することができな
い。
このように廻向を必要とするといつても、異類の助業は既に正定業によ
つて決定往生の信を確立した人に
よつて
行
じられるのたいして、雜行はそのような決定往生の信を確立していない人によ
つて行ぜられるのであるから・そ
こにおのずから兩者の間に相違がなけれぼならないであろう。善導は廻向發願心を釋して、
「以
二此自他所修善根↓
悉皆眞實深信、串
廻向。願シ生覆
國こといつている。これによると廻向が行われる心的場は眞實深心であるこ
とが

知
られる.このことがら考えるならば、雜行を行ずる人はそれを往生行としての効果をもたらす
ために、先づみず
からの内に眞實深心を確立しなければ、所詮廻向のしようすらないのにたいして、異類の助業を行ずる人は、廻向
がなされる心的場である眞實深心が既にみずからの内に確立しているのであるから、異類の行業を
その眞實深心の
なかに廻向すればよいのである。
ここにおいて留意すべきことは、
たとい雜行が正行とならんで往生行と規定さ
れ
ても、廻向を必要とするかぎり、それをしなければ往生行として効用をもたらすことができな
いわけである。雜
行が往生行として効用を發揮するにはどうしても、廻向が行われる心的場としての眞實深心が、雜行を行ずる人の
心
のなかに確立しなければならない。しかるに雜行を行ずることよつては、みずからの心のなかに眞實深心を確立
し得ないのである。なぜなれば、先に指摘したように雜行を行ずることは、彌陀、釋迦、六方諸佛
の意志に違背す
る
のであるから、雜行によつて信法という深心の側面を確立することができないのである。さら
に
『選擇集』第二
章
に引用された
『往生禮讃』
の文
のなかに、
雜行を行ずる人の失
の
一として
「無レ有二慚愧懺悔之
心一故」といつて
いるが、これは深心がもつ他
の側面である信機をなりたたしめるような素地を、雜行によつて形成
し得ないことを
指
摘したものである。このように雜行を行ずることによつて眞實深心の内容をなす信機、信法を確立し得ないとい
う
ことは、雜行が正行とならんで往生行であると規定されても、實際的には雜行に往生行として効用を期待するこ
とができないことを意味する。かかる雜行にたいして往生行としての効用を發揮せしめるのは、眞實深心をみずか
ら
の心のなかに確立した人においてである。そこにおいては雜行はもはや雜行でなくなり、異類
の助業と改名され、
正定業にたいして能助というはたらきをとおして、ふかいつながりをもつにいたるわけである。
1
『大胡太郎實秀へつかはす御返事』のなかに、
「善導和尚をふかく信じて、淨土宗にいらん人は、
一向に正行を修すべしと
申
す
事
に
て
こ
そ候
へ。
そ
の
う
へは善
導
のを
し
へを
そむ
き
て、
餘行
をく
は
へん
と
思
は
ん
人
は、
を
のー
な
ら
ひ
た
る樣
とも
こ
そ候
五
種
正
行
論
一一一

一=
一
らめ。それをよしあしとはいか
丶申候
へき。善導
の御心
にてす
丶め給
へる行どもををきなからす
~め給は
ぬ行
をす
こし
にても
くは
ふへき樣
なしと申事にてこそ候
へ。す
丶め給
へる正行ばかりだにも
なを物うき身にて、
いまだす
~め給は
ぬ雜行
を加
へん
ことはま事
しから
ぬかたも候そかし」
(『黒谷上人語燈録』卷第十三所收)とい
つている。これは法然が善導
の遣文をとをして雜
行
の捨、抛す
べきことを信者に教示した
一例
であ
る。
『選擇集』第
二章の標章
と言
い、こ
の滄
息の文
といい、その文底
に法然
が善導をも
つて彌陀
の化身
と仰ぎ、
その遺文を彌陀
の直説としてうけと
つた態度を感じとることが
できる。
な
お鎌
倉のこ位
の禪尼
へ進ぜられた書
である『淨土宗略抄』
(『黒谷上人語燈録』L卷第十
二所收)
にも、『大胡太郎秀實
へつかは
す御返事』
と同意
趣の内容をみることができる。
2
この問題に
ついて香月乘光敏授
は
「法然教學における行
の體系」(日本佛教學會年報第三十號所收、昭和四十年三月刊)のな
かでふれている。
3
特
に
「且」
の字
に
ついての理解は同右竭載
の香月数授
の論文參照。
4
醍醐本
『法然上人傳記』
のなかに收
めら
れている。これの外
に異本として
『西方指南抄』下末所收本
に
『或人念佛不審聖人
奉問次答』があり、『黒谷上人語燈録』卷第十四所收本
に
『十二問答』がある。『醍醐本』と
『西方指南抄』に収めら
れいるも
のはす
べて十
一問答
であ
る。
問者
について
『十二問答』
の卷末に
「この問答
の問いをば、進行集には、禪勝房
の問と
い
へり。あ
る文には、隆寛律師
の問
とい
へり。たつ
ぬべし」とあり、また長祿四年
(一四六〇)書寫になる
『往
生要義』(西本願寺所藏)に合綴されている書寫本
には
「進行集十
二問
答隆寛律師問上人答」
とあり、
『西方指南抄』本は問者
に
ついて特定
の人物
の名
を記していない。
二
正
助
二
業
の
勝
劣
、
專
傍
と
廃
立
、
助
正
の
二
義
法
然
は正
助
の
二業
に
つ
い
て
『無
量
壽經
釋
』
のな
か
で助
業
を
も
つ
て劣
と
な
し、
正
定
業
を
も
つて勝
とな
し、
ま
た
『選
擇
集
』
の畧
選
擇
にお
い
て助
業
を
傍
と
し
、
正定
業
を專
と
し、
到
然
と
二業
に區
別
を
た
て
て
いる
の
であ
る。
しか
る
に善
導
は
光だ
正
定業
を
も
つ
て
「順
二彼
佛
願
一故
」
と
な
し、
禮
誦
等
の四種
の正
行
を
も
つて
「名
爲
二助業
こ
と言
い、
そ
こ
に勝
劣
、

專傍の區別を明示していないのである。ここにおいて法然はいかなる觀點にたつことによつて勝
劣、專傍というこ
とを言
い切
つたのであろうか。またそれはなにを根據とすることによつて斷言し得たのであろうか。そういつた問
いかけにたいして考えてみたいと思う。既に前篩において指摘したように法然は、
『三心義』において正行を
「阿
彌
陀佛
におきてしたしき行」
というように、
言
いかえを行
つている。
この點からすれば五種正行の
一々はすべて
「阿彌陀佛におきてしたしき行」として、なんら相違するところがないように思われる。しかるに法然は善導の正
助
二業読を繼承して、讀誦、觀察、禮拜、讃歎、供養
の行をもつて助業となし、第四の稱名行にかぎ
つて正定業と
し
ているのである。このように
「阿彌陀佛におきてしたしき行」としての正行を正助二業に分到することは、その
行
がもつ阿彌陀佛自身における親しさの濃度差にもとつくのであろうか。あるいはそれ以外のなにものかに基準を
おくことによつて二業を分到したのであろうか。
この問
いかけにたいして法然は
『無量壽經釋』のなかで、次
のようにこたえている。
問日・何故五種之中獨以二稱名念佛一爲二正定業
一乎。答日。
順二彼佛願
一故。
意云。
稱名念佛是彼佛本願行也。
故
修レ之者乘二彼佛願一必得二往生一。由二願不ツ虚故以二念佛一爲二正定之業一。本願義至レ下應レ辨。但正定者法藏菩薩於二
二百
一十億諸佛誓願海中
一。選二定念佛往生之願一。故云レ定也。選擇之義亦如レ前。依二此等意一故
以二念佛一名爲二正
定之業一也。讀誦等行邸非二本願選擇之行一。故名爲レ助。念佛亦是正申之正。禮誦等是正中之助
。正助雖レ異同在一、
彌陀一。故雖レ爲レ正然非レ無一一勝劣之義一。
このように法然は、五種正行のなかの第四稱名正行が正定業である所以を指摘して
「本願選擇之行」とし、また
禮
誦等を助業となす所以を非本願選擇之行に求
め、さらにこれらの兩者
の間に勝劣
の別あることを認めて、前者を
も
つて勝
とし、後者をもつて劣としているのである。このことは阿彌陀佛自身が本願
の聖意によ
つて選定した徃牛
五
種
正
行
論
二
三

一一四
行
であるか、しからざるかという點に基準をおいて正助二業を分勃し、さらにそれにたいして勝劣の相違を剣定し
たことを意味する。このように助業をもつて非本願選擇之行と規定することは、正助二業を分到
せしめるものは阿
彌陀佛自身における親しさの濃度差、
つまり阿彌陀佛みずからの意志によ
って選定された行であるか、
いなかにあ
る。從
つて助業は既.に考察したような點で雜行となんら相違しない行ではないかという疑問をいだかしめるのであ
る。しかるに法然は助業を
「非本願選擇之行」と規定しながらも他面、正定業の
「正中之正」なるのにたいして
「正
中之助」と規定し、さらに正定業とならんで
「阿彌陀佛におきてしたしき行」である所以に關説
して、「正助雖レ異。
同二在彌陀一」といつているのである。このことは、正定業は阿彌陀佛
の本願
の聖意が徃生行として稱名の
一行を選
擇し、選定したのにたいして、助業はそのような
「本願選擇之業」でないけれども、なんらかの點
において阿彌陀
佛
の本願の聖意にかかわりのある行であることを示している。從
つて助業を
「非本願選擇之行」
であるという點で
雜行と同質覗するようなことがあつても、雜行が本願
の聖意にたいして違背する傾向をも
つのに反して、助業は本
願
の聖意に適合する傾向をもつ點で、この兩者を到然と區別する必要があるわけである。
しかれぼ助業において期待されるところの本願の聖意に適合する傾向とは、いつたいいかなる點を指していうの
であろうか。この問
いかけは、助業が正定業とならんで
「阿彌陀佛におきてしたしき行」であるとされる所以を、
あきらかにしようとすることでもある。このことに.ついて善導は
「若修二前正助二行一。心常親近。
憶念不レ斷。
名
爲
二無間
一也」と言
い、法然はこの善導の説を布衍して親縁、近縁、無間、不廻向、純
の五義をも
つてこたえている。
これによると、助業は正定業とならんで佛凡間に親近性をなりたたしめる行であることが知られるであろう。この
佛凡間に感じられ親近こそ、法然をして助業を正定業とならべて
「阿彌陀佛におきてしたしき行」
と規定せしめ、
あるいは
「正助雖レ異。同在二彌陀一」ど指摘せしめているのである。このように助業が
「阿彌陀佛におきてしたしき

行」である所以をあきらかにするにあたつて、善導も法然もともに正助
二業を同格碗しながら論を進めているよう
に思われる。しかし正定業ヒ助業とはあくまでも區別さるべきであるから、、助業が「阿彌陀佛におきてしたしき行」
であるとか、
「正助雖レ異。
同在二彌陀
匚
といわれる所以を正確に理解するために、助業を嚴密
に規定する必要は
な
いであろうか。なぜなれば助業という場合、助業が助業としての任務をはたしおわつた場合と、助業が助業とし
ての任務、役割を途行中の場合との二種にわけることができるからである。この場合、前者のよう
に助業が助業と
しての任務、役割をはたしおわつたのでは、もはや助業でなくな
つてしまうから、これを助業と呼ぶことは不適格
であると考えられるであろう。しかしその場合の助業は、高次なる正定業の上に止揚され、生かされているのであ
つて、決して死んでしまつたわけでもなければ、捨てられたわけでもな
いのであるから、助業
とし
ての輝かしい因
用
を認めておく必要がある。ともかく助業がその任務、役割を果途しようと、途行中であろうと、
いかなる點を指
し
て
「阿彌陀佛におきてしたしき行」であるとか、「正助雖レ異。同在二彌陀
一」とかいわれるかに
ついて考えてみた
いと思う。具體的にいうならば前者は、たとえば、讀誦の行をとおして正定業である稱名の
一行
に徹しうるように
なれば、讀誦という助業が正定業である稱名行
の上に止揚され、生かされることになるから、讀誦
はもはや助業で
なくなり、阿彌陀佛とどのようなかかわりをもつにいたるのであろうか。また讀誦を行ずるという場合、その助業
が任務、役割を途行中において、阿彌陀佛とどのようなかかわり逢もつにいたるのであろうか。善導や法然が指摘
した佛凡間
の親近性は前者においてなりたつであろう。しからば後者の場合はどうであろうか。後者の場合は前者
と同Uく阿彌陀佛とかかわりをもつといつても、兩者の間にはおのずから相違をきたすことであ
ろう。なぜなれば、
前
者の場合はもはや讀誦が助業としての任務、役割をはたしおわつて、高次な正定業である稱名行
の上に止揚され、
生かされているのであるから、まつたく
「本願選擇之行」となりきつているのである。このよう
に考えると後者は、
五
種
正
行
論
一一五

一一六
助業としてその任務、役割を途行中であるから、正定業の上に止揚されていないが、淨土の三部經
を讀誦し、阿爾
陀佛
の依正二報を觀察し、阿彌陀
一佛を禮拜し、讃歎、供養するその
一々の行が、なんらかの方法
で直接、間接に
阿彌陀佛にかかわりをもつのである。このこことは任務、役割を途行中の助業が
「非本願之行」
と規定されながら
も、なをかつ
「正助雖レ異。
同在一一彌陀一」とされる所以であり、
この點においてこそ雜行と
一線
を劃しうるのであ
る。このように考えるならば、
「阿彌陀佛におきてしたしき行」を正助二業に分到することは、
その行がもつ阿彌
陀佛自身における親しさの濃度差にもとついてなされたということができるであろう。ここにいう親しさの濃度差
と
いうのは、阿彌陀佛みずからの意志によつて選ばれた行という意味での親しさと、阿彌陀佛みず
からの意志によ
るものではないが、阿彌陀佛
の意志にかかわつてくるところの行という意味での親しさの相違を
いうのである。
今までの考察によつて知られるように、
助業は
「非本願選擇之行」
と規定される點で雜行と同質覗され、
他面
「阿彌陀佛におきてしたしき行」と規定される點で正定業と同質覗される。このことは助業が
「非本願選擇之行」
と
いう性格と
「阿彌陀佛におきてしたしき行」という性格、
いうなれば異質的な二つの性格をかねそなえているこ
とを示すとともに、助業が正定業でも、雜行でもない所以を物語
つているといえるであろう。
法然はさらに畧選擇において
「正助
二業中。獪傍一一於助業一。選應レ專二正定一。正定之業者。部是稱二佛名一。稱レ名
必得レ生。依二佛本願一故」といつている。このなかにおいて示されている專傍という分到は勝劣の場合とおなじく、
善導
のこころみなかつたところである。ここに專傍というのは、勝劣のごとく正助二業そのものに關係することで
なく、この二業を行ずる人の實踐的態度を示すものである。このなか專というのは、正定業である稱名の
一行にか
ぎ
つて、これをもつぱら行ぜよという
ことである。そのかぎりにおいて法然が
『選擇集』第四章私釋段にお
いて示
も光廢立の義に通ずるわけであるが、今
の場合はあくまでも傍にたいする專であるから、多分に相對的であると言

い得よう。これにたいして傍というのは、讀誦等の助業をかたわら行ぜよというのであるから、第
二次的であると
言
い得よう。
從
つてこの專傍の分到は、
法然が
『無量壽經釋』
においてこころみた勝劣という行業自身にたいす
る分刋をふまえてのことである。總Uてこれを
いうなれば、生死を出ずるたあの行業の主人格は專であり、これに
た
いする隨俘格が傍である。主人は隨俘者を同道しても、しなくても主人であるのにた
いして、隨俘者は主人あ
つ
て
の隨俘者であり、主人なくして隨俘者たり得ないという點で、專傍は廢立という實踐態度
へ移行する必然性を内
に藏している。このことは單に實踐態度
の領域だけにかぎつたことではな
い。正助二業が行業自身
として勝劣の相
違をもつという觀點にたてぼ、劣である助業を廢し、勝である正定業を立てることの當然なることが知ちれるであ
ろう。かく考えるならば、廢されても當然とみなされる助業を始めから設ける必要性がないはずであるのに、なぜ
正助二業を併説しなければならないのであろうか。特
にこの問題は行業自體
の問題にとどまるも
のでなく、むしろ
誰
れが、
いかなる素質、能力をもつた人が、その行業を行ずるかという實際問題にかかわつている。すなわち往生
行
はそれを行ずることによつて始めて往生行になりうるのであるから當然、往生行を行ずる人の素質、能力を問題
覗
しなければならな
いわけである。
具體的にいうならば、
助業を傍に行じなければ正定業を行じ得ない人、
助業
を行Uなくとも正定業を專ら行じうる人というように大別される。正定業
のみを行ずることが本來的であり、理想
的態度であるにも拘らず、正助二業が併説される所以は往生行を行ずる人の機根に起因するといわなければならな
い。のちに節をあらためて論ずるように、助業は實踐上からただ助業だけににどまるものでなく、正定業
の上に止
揚
されるのであるから、正助二業を併行したとしても究竟には正定業の
一行に移行することを忘れ
てはならない。
從
つて助業を傍にするとは、助業が助業としての任務を途行中であることを示すものである。
法然は
『津戸三郎
へつかはす御返事』という十月十八日付の書翰のなかで、
「正助二業の中には、正業のす
、め
五
種
正
行
論
二
七

二
八
によりて、ふた心なくただ第四の稱名念佛をすべし」と教示している。このことはひとえに正定業
をとりあげて、
助業をかえりみない廃立の態度を示したものである。いうところの廢立の義について法然は
『選擇集』第四章にお
いて、「謂諸行爲レ廢而説。念佛爲レ立而説」といつている。
ここに
「爲レ廢而読」といわれる諸行
のなかに、雜行を
始め助業をふくめているこどは助正の義に
「爲レ助二成念佛一誂二此諸行一者。此亦有三一意一。
一以二同類善根一助二成念
佛
一。
二以二異類善根一助二成念佛一」というのによつて知られるところである。
同類の助業とは正定業にたいして助
業
といわれる禮誦等
の行業であり、異類の助業とはしぼらく捨、抛された雜行を決定往生の確信
の上に助業として
復活せしめた行業である。そのことはともかく、かく廢立の義にお
いて雜行はおろか助業までも廢するということ
は、阿彌陀佛の意志にもとついた正定業である稱名の
一行のみを行ずるということであるから、劣と規定される助
業
を廢することであり、また實踐的には助業の助成なくして稱名の
一行を行ずることである。從
つて助業を傍にし
ながら稱名を行じなくても、稱名の
一行に徹しうるようになつた場合もふくまれるわけである。こ
のような廢立の
,-
.
義
は、法然が
『念佛問答集』において指摘した
「本願の念佛には、ひとりだちをせさせて助をささ
ぬなり」という
念佛のひとりだちとして、往生を行ずる實踐的態度
の理想を示したものであり、
「本願選擇之行」
としての正定業
の本來の面目もここにあるわけである。
これを要するに、
『選擇集』第
二章における法然
の正雜
二行、正助
二業
の説を
一貫しているものは、阿彌陀佛の
本
願の聖意にもとつく稱名
一行を唯
一の往生行として説きあかさんとする方向にあつたと言
いうるであろう。それ
は
「助をささぬ」ところの
「念佛
のひとりだち」を意味し、このひとりだちは廢立義として第四章
にお
いて始めて
明確に指示するにいたつた。このことは第三章においてこころみられたような、阿彌陀佛の本願の聖意を徹底的に
追究し、開顯することによつて始めてなりた
つわけである。このような
「助をささぬ」ところの
「念佛のひとりだ

ち」をなりたたすためには、雜行にたいして捨、抛をおこない、助業にたいしてもその劣、傍を指摘し、究極的に
助業が願生者をして稱名の
一行に方向づけるはたらきを持
つことを明示しなければならなかつた。
しかるにひとた
び、稱名行にもとついて決定往生の信が確立した上において、かつて捨、抛したところの雜行を異類
の助業として、
稱名行の能助という役割、任務を付與するにいたつている。このことは助正義として第四章においてあかすところ
であるが、聖道門
の行を雜行としてとりあげ、これに往生行としての任務
・役割を付與した第二章
の精神に、その
實を結ぼしめることである。ここにおいて第
一章において捨、閣された聖道門は、實際的に往生行
にかかわるもの
として、淨土門の上に生かされ、その分相應の所を得しめられたことを意味する。
ここにおいて留意すべきことは、決定往生の信
の確立を頂點とし、これを境としてその前後にお
いて行にたいす
る扱いに大きな變化
のあることである。すなわち決定往生の信を確立するまでは、雜行を捨・抛し
て
一途に正行を
行ずるという排他的な態度をどる。これは行について決定往生の信を確立せんがためであつて・そ
のためには雜行
を行ずるこどを障碍として排斥するわけである。しかるにひとたび決定往生の信が確立するか
らには・排斥した雜
行
を往生行のために異類の助業としてとりあげ、それに役割、任務を與えて生かすようにできるのである。このよ
う
に決定往生の信に生かされる行は、ただ雜行にかぎられているわけではない。法然はさらに助業
の範圍をひろげ
て.衣食住の三は念佛
の助業也。よくー
たしなむべし。妻を儲くる事、自身助られて念佛申さん爲也・念佛の妨に
なりぬべからんには、ゆめー
持
つべからず。從類眷屬も如
レ是。所知所領を儲けん事も、惣じて念佛の助業なれ
ば大切也。妨に成
べくぼゆめく
持
べからず。すべて是をいは望、自身安穩にて・念佛往生とげ
んがためには可イ
事もみな念佛
の助業なり。
五
種
正
行
論
一一九

一二α
靴
いうように、生活全體を念佛
のための助業とみなしているのである。法然はこの文章の前段にお
いて、その内容
を總括するかのような教示を、
「問奉て云。後生をば彌陀如來の本願をたのみ奉て候
へば、往生疑なく候。現世を
ば
いかやうにおもひ存
べく候らん」という問
いにた
いして與えている。すなわちそれによると、
「上臥答給はく。
現世を過
べきやうは・
念佛の申されん方によりてすぐべし」と指示し、
また
『常に仰せ、bれける御詞』として、
「縱餘事を
いとなんとも、念佛を申しー
これをするおもひをなせ。餘事をしし念佛すとは思べか、bず」と語
つて
いる・このように往生行をして日常的な一行爲、營みに關係芒
める基礎は決定往生の信にあり、また逆姿
」れを基
礎
とすることによ
つて・今まで排斥されていた雜行旨
常的行爲をよみがえ、bせ箜
」とができるのである。
ω
『念佛問答集』は現存
しないが、
『黒谷上人語燈録』卷第+
五所収
の
,藷
人傳読
の詞Lのなかに引用されている。
ω
『九簿
』卷第四下所収・
これと同じも
のが
『諸人傳説
の詞』
のなかに引用さ
れてい・。
『九卷傳』所収のも
のは
『諸人傳
詭』
の詞
に比
して布衍
したあとが看取される。
㈹
『四+八卷傳』卷第二土
所収。
『;・芳談』卷中にも引凋されている。
三
助業
論
と
五種
正業
階梯
論
正定業
にたいして禮誦等
の四種
の正行は助業と名
つけられ、しかも正定業を助成するという任務、役割をもつも
のである。この正定業を助成するためには、助業がいかなる點において正定業である稱名正行に直接的に、廻向と
いう方向がえを經ずに結びつくのであろうか。あるいは、法然は觀察を行ずることを極力排斥しているのに拘らず、
なぜそれを助業
の
一として採用する五種正行をもつて、往生行としてとりあげているのであろうか。法然はなぜ觀
察
することを排斥しなければならなかつたのであろうか。このように觀察を排斥するならば、事實上五種正行とい

善
驥
萎
くずすことになるであうつ、しがし法然は襲
を排斥しながらも五種正行を往生行も
て認めている
のであるから・觀察をどのようにうけとつていたかということが問題覗されるであろう。さらに助業は良忠が指摘
し
て
いる
よ
に
・
念
佛
に怠
り
のあ
る
時
に
こ
れ
を
行
・つと
いう
よ
う
な織
的
な面
し
か持
つて
いな
いの
で
あ
弓
つか。
そ
つし
た
滄
極
的
な
面
を
ふ
く
め
て、
助
業
に
は
も
つと積
極
的
に
正定
業
に
か
か
わ
る意
圖
耄
って
いな
い
ので
あ
う
つか。
.」の
よ。つ
な點について考えてみたいと思う。
、
先づ助業を行ずることがいかにそのまま稱名正行にかかわるのであそ
つかと℃つ問
いかけにたいして、盖口導はい
かなる解答をよせてくれるであろうか。かの
『散善義』の就行立信
のところで
一心專譚諞此韆
彌陀經無量壽經等二
心專注思憩
觀三察憶・念彼國二報莊嚴薯
禮鏨
、心專禮二彼塑
(中略)
若讃歎供養師
一心專讃歎供養。
と
いつている・これによると阿彌陀佛のことを轟
繞
く塗
の三部經を讃誦し、阿彌陀佛
の芒
ます塗
の依正
二報の莊嚴患
想し・觀察し、憶念し、阿彌堕
佛にかぎつて・」れを禮拜し、讃歎し、供養すると
℃つ以外、。しれ
ら
の助業がいかなる點にお
いて、稱名行にた℃
て直接的繕
びつくかとい・つ・」とについて、なにも指示するζ
」
ろが毒
のである・
これにた℃
て法然は
蕪
量蘿
釋』のなかでわずかに
「正助雖・異。
同在二彌陀己
と指摘す
る
に
とど
ま
つて
いる
先づ法然は轜
について
「轜
せんには、彌陀經等の三部讐
轜
して、餘の轜
をまuえざれ」
(窶
藷
苧
第三の問答)と規定し、善導
の説をそのまま繼承しながら、淨土の三部經以外の經典を讀誦することを禁じているの
である・しからば淨土の三部讐
いか議
誦すれば助業となりうるのであう
つか。
『蜑
壽経』に
ついて法然は
此讐
無量蘿
読二念佛往生支
套
一七種
。
一菜
願文。二者願成就文。三者圭
中
高
專念文。四者中輩虫
二二
五
種
正
行
論

ニ
ニ
向專念文。五者下輩
両
專念文。奢
無上功徳文。七者特留此經文也。又此七處文合爲
レ三・
著
本願・此攝レ
ニ。謂黎
願願成就也。二者三輩。此攝匕二。謂圭
塞
下輩也。又就
二此下輩
有三
類
㌔
三者流逋・此攝レニ・
謂無上功徳特留此經也。
本願在二彌墮
三薔
下釋迦自説也。其隨二彌陀本壓
而説也。三萋
中各勸三
向專念
給・流通文申讃
二無上功
.r5i °特留此讐
給。源隨二順讙
本壓
給故也.然者云惷
佛往生
事。
本願爲二根杢
也・
所詮此讐
レ始至レ絡・
可レ意三得説二彌陀本願一也。雙卷經大意略如レ斯矣。
と
『逆修読法』
(五七日の説法)のなかでいつているように、この經典の根本意藻
阿彌
陀佛の本願
の聖意に隨順す
る念佛を、往生行として読くのである鬘
けとるべきことを指摘してい
る。また
『觀無量壽經』に
ついて法然は
流通有二多文段
。取・要釋・之。經云。佛告阿難汝好持是語云々。
釋レ之有三
意二
者先依二善
導㌔
廢二定散諸
行
一。但
歸
二念
佛
一門
一。
二者於
二經
中
諸
文
一。
畧
輔
二助
此義
一。
辰
二善導廢
二定散諸行
歸二念佛
雨
暑
。善毒
二佛告阿難等文去
。從
二讐
阿難汝好持是語邑
下・正明下付二
屬彌陀名號一流中通於遐代上。上來雖レ説二定散兩門之盆一。望二佛本願一意在
下衆生
一向專稱中彌陀佛名上(中略)二以二諸
文一輔助者。此經意説二定散善根叩雖レ明二諸行往生つ論二其正意一。正有二念佛往生
一。其文雖レ多略引一一三五一。以輔二
其義一。
一第九觀光明遍照文。
二第十二觀無量壽佛化身無數等文。
三下品上生智者復教
三合掌叉手稱二南無阿彌陀
佛支
。四同下・盟
生化佛稱讃汝稱二佛多
故諸霑
滅文。五下品中生聽聞彌陀功徳往生文・六下品下生+念往生
文。七若念佛者當レ知此人乃至生二諸佛家一文
と
『觀無量壽經釋』のなかでいつているように、定散二善の行を廢して
「一向專稱彌陀佛名」せ
しめることがこの
經典の根本意趣であると受けとる
べきことを指示し、さらに
『阿彌陀經』について

阿彌陀經者。初説ゴ極樂世界依正二報一。
次説下修二一日七日念佛一之往生上。
後説下六方諸佛於二念佛
一行一證誠護
念之旨上。則此經不レ説一一餘行一而選説二念佛
一行一。
文云。説二不可以少善根輻徳因縁得生彼國一。読下聞レ読二阿彌陀佛一執二持名號。若
一日乃至七日
一心不亂其人臨二
命終時一。阿彌陀佛與二諸聖衆
一現在二其前
一。是人絡時心不二顛倒一郎得中往生上。
爰知餘善少善根也。
念佛多善根也。
修二彼少善根餘行一不レ可レ得二往生一。修二多善根念佛一可レ得二往生一。
是故善導和尚釋二此文一云。
極樂無爲涅槃界。
隨縁雜善恐難生。故使如來選要法教念彌陀專復專云々。阿彌陀經大意略如レ斯。
凡念佛往生是彌陀如來本願行也。教主釋尊選要法也。六方諸佛證誠説也。
餘行不レ然。
其旨具二經文及諸師釋一
也。佛經功徳存レ略如レ斯。
と
いうように
『逆修読法』
(初七日の説法)のなかでいつている。法然は釋尊が選び、六方の諸佛が證誠する
「彌陀
如來本願行」としての念佛を読くのが、この經典の根本意趣であると受けとるべきことを指摘し
ている。
これを要するに、讀誦が正定業である稱名の助業となりうるのは、讀誦するそのことにあるのでなく、讀誦する
ことをとおして淨土の三部經が知らしめるところの根本意趣を素直にうけとることを第
一要件し、その當然
の歸結
として讀誦者を稱名の
一行にむかわしめ、徹せしめることを豫想し、期待してのことである。いうなれば讀誦とい
う形式が助業どなるので癒く、讀誦される經典の内容が讀誦者に稱名の最勝行である所以を知らしめ、讀誦者をし
て稱名の
一行に方向づけを行う點を指して、讀誦を正定業
の助業というのである。從
つて讀誦される經典が淨土の
三部經にかぎられていればそれでよいというのではない。肝要なことはそれをいかなる意地にもとづき、いかに讃
みとる方という點にある。興味本位や研究
の目的のために讀むのではなく、その意地は出離生死という
一大事にあ
るわけである。法餐
『三部經狸
のなかで「淨土の
一門に?らんとお毛はん人は、道鑾
、導
の釋
耄
て所琢の三部
五
種
正
行
論
一二三

=一四
經を習うべきなり」といつているが、これは經典をいかに讀みとるべきかといことに關連してのことである。この
法然の指示はただ單に傳習を重靦してのことというよりも、それをとおして阿彌陀佛本願の聖意、釋尊出世の本懐、
諸佛の證誠をいかに的確に讃みとるかということに重點がおかれているのである。かの隆寛が傳えた法燃の詞
の
一
つに
「源空も念佛のほかに、毎日に阿彌陀經を三卷よみ候ひき。
一卷は唐、
一卷は呉、
一卷は訓なり。しか渇庵こ
ロハ
の經に詮ずるところ、ただ念佛申せとこそとかれて候
へば、
いまは
一卷もよみ候はず。
一向念佛を申候也」という
のがある。この詞は經典
の内容、とくに根本意趣を讀みとることが讀誦者に稱名の最勝行たる所以を知らしめ、稱
名
の
一行に徹するよう方向づけることを、法燃自身
の體驗をとをして語
つたものである。しかも讀誦の行業は讀誦
者をしてひとたび稱名の
一行に徹
せししめるというみずからの任務、役割をはたすことによつて、みずからが讀誦
行業であることを否定し稱名の
一行のなかにみずからを肯定するのである。このように讃誦の行業は最終的に稱名
行
の上に止揚さるべき性格をもつことを、この法然の詞はよく物語
つている。
次に觀察について法燃は
「憶念觀察せむには、かの病
二報莊嚴等を觀察して、餘の觀察をまじえざれ」
(『要義
問答』)と・
善
導
の説
を
繼承
し
て
いる。
法
然
は
『一期
物
駈躑
のな
か
で
「以
二我吩
際
一觀
二佛
相
好
一。
更
非
二如
レ詭
觀
一。
深
に
憑
二本
願
一。
口唱
二名
號
一。
唯
是
一事
」
と11111い、
ま
た
『つね
に仰
せら
れ
け
る御
詞
』
のな
か
にも
近
來
の行
人
觀
法
を
な
す
こと
な
か
れ。
佛
像
を觀
ず
と
も、
運
慶
康
慶
が
つく
り
た
る佛
ほど
だ
にも
、
觀
じ
あ
ら
は
す
べか
らず
。
極
樂
を觀
ず
と
も、
櫻
梅
桃
李
の花
果
ほ
ど
も觀
じ
あら
はさ
ん
こ
と
か
たか
る
べし
。
ただ
彼
佛
今
現
在
レ世
成
佛
。
當
レ
知
本
誓
重願
不
レ虚
。
衆
生稱
念
必
得
二往
生
一の釋
を
信
じ
て、
ふ
かく
本
願
を
た
の
み
て
一向
に名
號
を
とな
ふれ
ば
三
心
お
の
つ
か
ら具
足
す
る
な
り
と言
い、
観察
す
べき
で
な
い
こと
を強
く教
示
す
るば
か
り
で
なく
、
觀
察
を
しり
ぞけ
て稱
名
の
一行
を
勸
め
て
いる
ので
あ
る
゜

ざらにまた乘願房
の傅読
の言葉のなかに
乘願上人のいはく。ある人問ていはく、色相觀は觀經の詭也、たとひ稱名の行人なりといふとも、これを觀ず
べく候か。
いかん。上人答ての給はく。源空もはじめはさるいたづら事をしたりき。いまはしからず。但信の稱
名也。
ωとあるよう、法然はみずからの體驗にもとついて觀察を
「さるいたづら事」と斷言し、もつぱら稱名の
一行に勵ん
で
いることを語つている。從つて先にかかげた法然の詞はすべて法然自身
の體驗にうらづけられた教示であること
が知られるであろう。
この觀察をめぐ
つて
「さるいたづら事」と言い、
「非二如レ説觀一」という法然の詞の間には、
意志表示の基準を異にしていることを忘れてはならない。前者は稱名に對比して本願
の聖意にもとつかない行とし
ての觀察をいたつたのであろうし、後者は實踐者の素質、能力という點から經典の所説どおりの觀察ができないこ
とをいつたものであろう。從
って法然ほどの人にしてなぜ觀察をさけねばならないのかということ
は、兩方にかか
るわけである。法然にとつては前者が本來的であり、後者は第ご義的であつたであろうと思う。法然はさらに、さ
㈲
き
に示した觀察にたいする教示、體驗をふまえながら次のようなことをいつている。すなわち
『要義問答』
のなか
で
「問。念佛と申候は、佛の色相を念じ候か」というのにたいして、
「佛
の色相光明を念ずるは觀佛三昧なり。報
身
を念じ、同體の佛性を觀ずるは、智あさく、心すくなき、われらは境界にあらず」と言
い、さら
に續
いて心の散
亂する者は觀察に代
つて稱名を行ぜよという
『往生禮讃』の文、および第十八願文を釋する
『觀念法門』の文を竭げ、
「どくー
安樂淨土に、往生させおはしまして、彌陀觀音を師として、法華の眞如實相卒等の妙理、般若の第
一義
空、
眞
言
S,
心
成
佛
、
一切
の聖
教
、
心
のま
ま
にさ
とら
せお
はし
ま
す
べし
」
と
結
ん
で
いる
。
こめ
こと
ば
か
ら類
推
す
る
なら
ば
、往
生
の
のち
淨
土
にお
いて觀
察
す
べし
と受
け
と
る
こと
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
のよ
う
に
理解
し
た
な
ら
ば
、
五
種
正
行
論
=
一五

一二六
も
はや觀察は往生行の助業としての資格を失うことになるであろう。
ともかく觀察をしりぞけるというこどは、ただ法然にかぎつてのことであろうか。觀察をふくめた五種正行を往
生淨土行として創設した善導ですら、
「問日。何故不レ令レ作レ觀。
直遣三專穩二名字一者有二何意一也。答日。
乃由三衆
生障重境細心驫識賜神飛難二成就一也」と
『往生禮讃』前序にいつている程である。これによると觀察がしりぞけら
れるのは、觀察に堪えな
いという行者自身
の機に起因することが知られる。もしこのような考えに基づくのであれ
ば、觀察をしりぞけるということは、五種正行をも
つて稱名爲正としないことを意味するであろう。なぜなれば觀
察爲正であればこそ、觀察に堪えないものにたいして稱名が諡かれるわけであり、稱名は單なる觀察の代行にしか
すぎないことになるかちである。このような觀察爲正の立場にたてば、觀察はもはや觀察に堪えう
る人という特定
の機根にたいして設けられたことになるであろう。從
つて觀察に堪え得ない下機
のものにとつて觀察は、ただ觀察
と
いう名目だけにおわ
つてしまつて、五種正行において意圖される助業
のはたらきを觀察に期待し得なくなるであ
ろう。もしこのように觀察が、それに堪えうる特定の機根に樹するものであるならば、特に稱名を必要としないこ
とにもなるであろう。このように觀察を中心として五種正行を考えるならば、下機をふくめたすべての人が、行じ
う
るという五種正行設定の意義がなくなると考えざるを得ないのである。
法然が善導
の五種正行
の諡を繼承し、正助
二業を分到しながらも、そのなかの觀察という助業を事實上否定した
と
いうことは、五種正行という往生淨土の實踐體系をくずし、こわすことを意味しな
いであろうか。もしそうでな
いというのであれば法然は、稱名という正定業
のために助業となり、しかもすべての人が機根の上下にかかわらず
㈲
行
じうるどいう觀點から、觀察を
いかに解し、説き示したであろうか。法然は
『三心料簡』のなか
で
「五種正行中
觀察門事。非二十三定善殉散心念佛行者。極
樂有樣相像欣慕心也」どいっている。この文はあきら
かに散心の行者が

むこなう觀察を規定しているひすなわちここにいう觀察は、普通
1般におこなわれる常規の定善行どしてのそれで
なく、あくまでも心の散亂動搖する行者が、淨土の三部經に説示され、あるいは繪謁、彫刻に表現されている淨土の
有樣、所謂勝相をとおして、阿彌陀佛の淨土の有樣を相(相
の字は想に通ず)像することによつて、欣慕
の心情をた
かめることを
いうのである。法然は念佛行者の行う觀察、勿論稱名の助業
ということをふくめての觀察を
「極樂有
樣相像欣慕心」と規定したのである。しかしこのような法然の觀察についての説
は獨斷でなかろうか。善導は
『散
善義』において觀察正行を規定してコ
心專注思二想觀三察憶四念彼國二報莊嚴一」といつている。善導
はこのように觀
察
の前後に思想ど憶念とをおいている。これはおそらく善導のいう觀察の始終を示したものであろうが、このなか
思想というのば、思は對象にむかつて心
・心所を發動せしめる心の作用を言
い、想とは封象のすがた
(像)を心の上
にとり込んで取像する心所の精神作用のことであるから、極樂の勝相
にむかつて心をはたらかせて、それをとらえ
て思いはからい、心の上に取像することをいうので、まさしく
「極樂有樣相像」することである。
そうした極樂
の
勝相
にたいする當然の結果として、極樂を欣慕するという心情がかりたてられることになるわけである.
いうなれ
ば
「極樂有樣相像」するということは思想し、觀察し、憶念するという善導が規定した觀察
の枠を逸脱しないので
あ
る。しかしこのような觀察にたいする法然の規定は、今日現存する遺文
のなかに數多く見出すことのできるもの
でなく、稀れな遺文に屬するものである。このように他
に類例をみない法然
のことばであるという點から、これを
法然の考えでないと否定することは輕率に屬するであろう。たとえ他に類例を求めることができなくとも、それは
そ
の法然の遺文を編纂する時點
における聞題として、ともかく觀察を稱名行
の助業として採用して
いるという立場
にたつ時、そのこと丶矛盾しなけれぼ法然
のことばとして綵用して然るべきであろう。善導
の觀察
にたいする規定
には、思想、觀察、憶念というようにふくみが多いわけであるから、法然がそのなかの思想だけをとりあげたとして
五
種
正
行
論
=一七

一二八
も、決して善導
の説に違反するわけではない。このように觀察をもつて「極樂有樣相像」するという法然
の見解に從
う
ならば、觀察はいかなる點で稱名正行の助業となり得るのであろうか。極樂の勝相に心をはたら
かせて、それを
とら
えて思
いはからうと同時に、それを取像するという心、心所
のはたらきは、極樂の勝相にたいして欣慕という
宗教情操をかりたて、その心情のおもむくところ淨土に往生を願うという所求および、その淨土の主である阿彌陀
佛
に歸依し、歸命するという所歸とを確固不動ならしめるに役立
つことであろう。かく所求、所歸
ということが確
立すれば、その勢
いのおもむくところその淨土にたいして願生という切なる思
いをかりたて、去行
としての稱名
一
行
に歸することになるであろう。このように法然の指摘したように觀察を
「極樂有樣相像欣慕」す
ると規定するな
らば、觀察は稱名
一行
の助業となり、し殄も五種正行という實踐體系をくずさずに正行の
一として、す
べての人が
ア
行
じ得るであろう。これに續く禮拜、讃歎秘供養
の行がいかなる點で、稱名
一行
の助業となりうるかということに
ついて、法然は遺憾ながら讀誦や觀察の場合のような手がかりを、なにも遺していないのである。
そうした點で、
禮
拜等
の行が炉かなる點で正定業である稱名
の助業となり得るかについては、讀誦や觀察の場合に準じて理解する
より外に方法はなわけである。從
つて禮拜、讃歎、供養という行を行ずること自體に目的があるのではなく、それ
ら
の行を行ずることが究極的に稱名の
一行にむかわしめ、徹せしめるのでなければならない。
これを要するに助業は、正定業である稱名の
一行に徹しきれない願生者をして、稱名
の
一行に徹
せしめるために
設けられたものであり、助業はその任務、役割をはたしおわつてのちなお、正定業にたいし助業としてとどまらず、
果
途の上は正定業のなかにみつからを否定し、正定業というより高い立場の上にみつからを生かす
のである。そう
いう意味にお
いて助業は究極的には正定業の上に止揚さるべきものであるのに反し、正定業は助業
に比してより高
い立場にあるものとして、助業をみつからの上に止揚するものであるとψうことができるであろう。このことは往

生淨土
の實踐體系から
いうなれば、助業はあくまでも第
二義的なものであり、決して本來的なものでなことを示し
て
いる。法然は本來的な正定業と第二義的な助業との關係を、
『十二箇條問答』のなかで、
「人のみちをゆくに、
主人
一人につきて多くの眷屬の行くがごとし。徃生業の中に念佛は主人也。餘の善は眷屬也。しかれば餘善きらふ
まではあるべからず」といつている。
この詞は念佛と餘善の關係をのべたものであるが、正助二業
の關係を考える
上
に示唆を與えている。すなわち正定業は主人公であり、助業は眷屬者とみなされるが、このなか、主人公は眷屬
者をしたがえなけれぼ主人公であり得な
いと
いうことがないように、
「本願選擇之行」である正定業は
「非本願選
擇之行」をまつまでもなく、唯
一の往生行であるわけである。また主人公は眷屬者を隨俘せしめることをこぼむも
のでな
いのである。たとい眷屬者の數が多くても、眷屬者はあくまでも
一人の主人公の意趣に從い、主人公のため
にすべてを捧げてみつからを顧みないのである。そのように助業は正定業のために助成することはあ
つても、正定
業
ではない。しかし正定業を助成するという任務、役割をはたしおわることによ
つて、助業はそれみつからである
ことを正定莱のなかに否定することによつて、みつからの生命をいかすのである。ここに助業に課
せられた任務、
役割をとおして、それが設けられた意義を知ることができるのである。
正助
二業を實際に行ずる場合、その行じ方に三つある。すなわち、第
一には先づ助業を行じたならば、その當然
の結果として正定業を行ずるようになる。第二には先ず正助二業を併行すれば、最終的に正定業に徹しうるように
なる。第三には最初から正定業の
一行を行じながら、ときとして助業を行じて正定業に徹するよう
になる。これら
三者のなかいずれの行じ方が本來的であるのであろうか。この閊
いかけにたいして法然はなんらふれるところがな
い。しかしこの問題はそれを行ずる人によつて相違するのであるから、
一概に規定し得な
いわけである。從
つて法
五
種
正
行
論
一二九

一三〇
然
がこれについて教示するところのない分は、正助二業を行ずる縁が無量であることを、語らずし
て語つていると
思
われる。
しかるに良忠は
『選擇傳弘決疑鈔』のなかで、
・「念佛者。
心念口稱。
常能勇猛。
唯修
二念佛一。不二必
兼7助。若有三行人一。其性懶惰。數怠一一念佛一。則於一一其時一。
修レ助勵レ正」と言
い、
また
『決答疑問鈔』においても
「若行二念佛一。有二懈惰心之時
一。以二餘四行
一。
可レ助二念佛行二
と異口同調に、
念佛におこたりのある時にかぎつ
て助業を行ぜよと指摘している。この良忠の指摘は、出離生死の要路を正定業である稱名の
一行
の上に決斷しなが
ら
も、なおそれに徹しきれない人を豫想してのことである。しかし良忠は
「助正之義。
隨レ機不定。
或有下正業難二
成辯一者。更修二助業殉大事方成上」というように、正定業に先だ
つて助業を行ずることを認めている
のである。とも
かく
いずれにしても、正定業である稱名の
一行に徹しうるようにさえなれぼ、助業はその任務、役
割をはたすわけ
であり、またそうした意圖をも
つのが五種正行である。もしかりに良忠が指摘したように助業は、念佛におこたり
のある時にこれを行ずるならば、
稱名
の
一行に徹する上に役立つというのであれば、
出離生死の要路を稱名の
一
行
に決斷していな
い人はいつたいどうなるであろうか。五種正行はそのよう蠹人にたいして無縁であるのであろう
か。阿彌陀佛の本願の聖意から
いうならば、出離生死の要を稱名の
一行に決斷していない人をもふくめて、稱名
の
一行に向わしめるような實踐體系を五種正行に求めるべきでなかろうか。このことは、助業はただ念佛者だけのも
のでなく、それ以前の人のものでもあることに着眼すべきでなかろうかという問いかけである。さらにまた五種正
行
は稱名正行を主軸として、前三後
一に助業を配列しているが、その讀誦、觀察、禮拜、さらに讃
歎、供養という
順序によ
つて配列することが、稱名の
一行に方向
つけることにたいしてどのような役割をもち、ど
のように効果的
であるのであろうか。すなわち、助業がそのような次第順序によ
つて配列されているということは、四種、ないし
は五種の助業に階梯のあることを示したものでなかろうか、という問
いがけである。これら二つの問いかけにたい

し
てv兩者の接點を求めながら考えてみたいと思う。
五種正行のなか、助業の第
一になぜ讀誦を配列しなければなちなかつたのであろうか。觀察よりも、禮拜よりも、
讀誦をまず第
一に配列するこどが、實踐體系として最もこのましいからであろう。さきに指摘したように讀誦は淨
土
の三部經にかぎ
つてこれを讀誦するのであるが、その目的とするところは經典が知らしめようとする内容を素直
にうけとるこどにあ
つて、單に經曲ハを讀誦するという形式にあるのではない。淨土の三部經には淨土宗
の信仰の三
大支柱である所求、所歸、去行の三者について詳述されている。すなわち經典の知らしめるところ
の所求とは淨土
に往生(淨土建立の意趣と淨土の勝相、當爲としての往生と往生相)することであり、所歸とは阿彌陀佛同(人格身としての本願
の聖意)であり、[去行とは稱名行
(正定業-選擇本願念佛)である。
このように信仰にどつて不可歓な信仰の目的と對
象、および目的達成
の方法を、まず第
一に知らしめる意味にお
いて讀誦を五種正行の第
一に配列し
たのでなかろう
か。このように信仰
の三大支柱を知らしめたのであるから、次はその
一一を1
往生する淨土の勝相と信仰の對象
である阿彌陀佛、さらに往生淨土の實踐としての稱名を、第二觀察、第三禮拜、第四稱名という順序にお
いて配冽
したことが知られる。さらに第五の讃歎ど供養はそうした信仰
のもりあがりにお
いておこなわれる行爲であるから、
これを最後に配列されたわけである。かくして五種正行は信仰
の三大支柱を中心として構成されて
いることが知ら
れ
るとともに、讃誦、觀察、禮拜の三正行はいわば願往生の心をたかめ、
つのらせる任務、役割をもつものであり、
稱名正行は前三行を前提
とすることによつて形成された願往生の目的を達成せしめることを任務とし、役割とする
も
のであり、讃歎、供養
の正行は稱名正行を中心として讀誦、觀察、禮拜をふくめた四種正行を行ずることによつ
て、おのずからもりあがつた信仰の歡喜、感謝、あるいは歸命、欣慕
の心惰が、信仰の對象にたいして示すあらわ
れである、ということができるであろう。このように五種正行の配列順序を考えるならば、それは信仰の階梯にも
五
種
正
行
論
;二

一三二
とついていると言い得るわけである。しかし實際的
には五種正行を行ずる人の素質、能力は千差萬別であるから、
それを行ずるにあたつてかならずしも、配列の次第順序を經るとはかぎらないわけである。從
つて
一概に五種正行
をもつて信仰の階梯に準じたものであると言
いきれない面
のあることを忘れてはならない。
讀誦を第
一におくような配列順序をもつて構成されている五種正行は、かならず、それを行ずる人を豫想してい
る
であろうから、次にそれを行ずる人のいかなる能力に封應せしめているかを問わなければならな
い。そこには傳
統的に人間精神
の三樣相、あるいは三能力と考えられている知、情、意を豫想することができる。第
一の讀誦は淨
土
の三部經が詭き示し、知らしめんとする所求、所歸、去行の三者を、行者が素直にうけとることであるから、人
間
にそなわる知にもとついて行われるわけである。素直にうけとるのであるから、こざかしい分別をはたらかす必
要
はなく、むしろさけなければならな
いのである。このように信仰の世界のなんたるかが經典をとおして理解する
と
いうことは、ただ單なる解のために行われるのでなく、行
への動機づけを豫想してのことである。第二の觀察、
第三の禮拜、第四の稱名は、そうした解の展開としての行と言わなければならない。まず觀察は救濟の場であり、
佛凡對面の場でもある淨土の勝相を取像することによつて、欣慕の情をたかめるということであり、それは人間に
そなわる倩にもとついて行われるわけである。淨土の勝相にたいする欣慕の情は
一面、淨土が此岸
の世界
でなく彼
岸
の世界であるという此彼二岸の隔繦の情と、現實の世界である此岸にたいして厭離の惰を俘う。かかる隔繦、厭
離
の情はさらに淨土
への欣慕の倩をたかめる。また他面、淨土を欣慕する情は淨土の主である阿彌
陀佛にたいして
親縁
、近縁という佛凡の關係をなりたたしめようとする心情を誘發する傾向がみられる。次に阿彌陀
一佛にたいし
て行われる禮拜、その尊容を仰ぎ、かつ尊容の前に膝まずき低頭、接足作禮するそこには、觀察の行において豫想
きれるような情と異
つたものが豫想される。すなわち、柯彌陀佛のす
べてにお
ψて側滿であり、最勝であるのに此

して、わが身の無常、苦、不淨なることに氣つかしめられる。さらに禮拜にはそうした人間
の身體的なあり方から
自
己の内にむかつて、
「外現二賢善精進之相一。内懷二虚假こ
といつた自己の不實なること、
「自身
現是罪悪生死凡
夫
。曠劫已來常沒常流轉。無有出離之縁」というような、ぬぐ
いようのない自己の罪悪性というように、佛の前に
立
つた自己をこよなく深く内省せしめ、慚愧懺悔の情を誘發する傾向がみられる。自己の内に根強く形成された自
我、我執を氣つかしめるのも禮拜である。また他面、禮拜の行は行者をして
一層たかく阿彌陀佛を仰がしめるとと
も
に、憑依の情をつのらせる。
このように佛凡の關係をとおしてなりた
つ心惰において、觀察は佛に近づこうとする心倩が強
い點で求心的であ
り・
禮拜は佛に遠ざかる心惰が強
い點で遠・心的である蓄
うことができるであ弓つ。
いつれにしても淨哨
依正
二報を欣慕し、阿彌陀佛を禮拜することは、實際的にいつてそれぞれ單
一の行ではなく、かならず心念口稱を件つ
ている點
で複行
である。觀察と禮拜
の兩者は心念口稱によつて貫ぬかれていることを忘れてはならない。このこと
は觀察、禮拜の二行が單獨行としてなりたたないことを意味するとともに、求心と遠心とを内容とする感惰は稱名
を行ずることを決斷せしめるものであると言えるであろう。そうした點で讀誦、觀察、禮拜は稱名
へ方向づけるも
のとして・助業としての性格を少しも改めていないのである。特に觀察、禮拜の兩者は心念口稱に
つら
ぬかれてこ
そ觀察・禮拜の行たり得るのである。そういつた意味において、さきに指摘した觀察、禮拜をとおして懷かれた感
惰
は、心念口稱
の上になりたつといつても過言でないのである。次に稱名は救い主を阿彌陀
一佛に見出し、その本
願
のはたらきによつて願往生の目的を逹成しようとする意志による決斷を待
つて行われる。この決斷は先に指摘し
たような觀察、禮拜の二行をとおして、みずからの内にもりあがつた阿彌陀佛にたいする求心的、遠心的な感倩
の
上
になされる。稱名はただ阿彌陀佛の佛號をとなえるのでなく、阿彌陀佛にたいする繦對憑依であ
る歸命の意味を
五
種
正
行
論
一三三

一三四
も
つ南無に佛號を連續せしめた六字の名號をとなえることである。このような稱名
であればこそ、阿彌陀佛に全身
全靈をささげて歸命し、救われたいと願う凡夫
の意志とすべてのものを漏れなく救
いとろうとする阿彌陀佛
の意志
とがあい呼應し、佛凡を結ばしめる直線道であり得るのである。
「心常親近」して佛凡の問斷がなく、無間である
と言われる所以はここに存するわけである。さきに觀察や禮拜
の行の上に見出した欣慕、親近、懺悔、憑依
の惰は、
佛凡間の無間のアスペクトとして稱名行の上になりたつと言
い得るであろう。最後に讃歎と供養
の行は阿彌陀佛の
す
べてを讃歎し、阿彌陀佛に供養することであるが、阿彌陀佛にたいする欣慕、親近、懺悔、憑依
の心情
のあらわ
れ
であるから、稱名によつてつらぬかれているわけである。この讃歎と供養
の行ば究極的には稱名行の上に止揚さ
れるのであるから、稱名することがこの上ない讃歎であり、供養でありうるわけである。
このように五種正行の配列順序は人間にそなわる知情意とい屮つ能力に對應せしめて設定されていることを見極め
る
ことができたのである。このことは五種正行を往生行として設定した善導やそれを繼承する法然
によつて指摘さ
れた正助
二業
の分到をくずすことなく、五種正行がいかなる人にたいしても往生行であり得ることを示すものであ
る。從
つて助業が念佛に怠りある者
のために設けられたというような狹
い枠をはずして、いなそれをもふくめて、
五種正行が萬人
のための往生行でありうるということは、すべてのものを漏れなく救
いとろうとする阿彌陀佛の聖
意
にかなうわけでもある。
.
なお五種正行については正行を行ずることにお
いて佛凡問のかかわりを行者がいかに實感するか、稱名をめぐる
念聲の問題、さらには正定業である選擇本願念佛等について言及しなければならないのであるが、紙數の關係で別
の機會にゆずりたいと思う。

ω
隆寛傳説
の詞
『諸人傳説
の詞』所収
(『黒谷上人語燈録卷第十五所収)。また
『明義進行集』
卷第
二の隆寛
の項
にも同趣
の詞
が載
せら
れている。
ω
醍
醐本
『法然上人傳記』所収
『一期物語』、
および信空傳説の詞
とし
て
『諸人傳説
の詞』
のなかに収
められ
ている。
㈹
『四十八卷傳』
卷第二十
一所収、また
『西方指南抄』
卷申本所収
の
『十七條御法語』に出ず。
ω
『諸
人傳詭
の詞』、『決答授手印疑問鈔』
に出ず。
㈲
『要義問答』(『黒谷上人語燈録』卷第十三所收)。なお
『西方指南抄』卷下末所収本
は、
『語燈録』本
の
「境にあらず」
まで
を問としている。
㈲
醍醐本
『法然上人傳記』所収。法然が使用した
「欣慕」という表現
は、おそらく善導
の
『散善義』
の深
心釋中
の
「又決定深
信。釋迦佛説二此觀經三幅九品定散
二善一。證
二讃彼佛依正
二報一。使二人欣慕一」という文
によ
つた
のであろう
と思われる。
ω
讃歎が稱名
の
一行に徹すること
について良忠
は、辨長
のことば
を引用し
て
「先師云。
口稱二南無阿彌陀佛
一。不レ可レ有二過レ此
之讃嘆二
(『往
生論註記』
卷第
四
稱彼如來名釋)
と言
い、また聖冏
は
『決疑鈔直牒』卷第四に輿いて
「讃嘆門至極在二稱名↓
仍以レ説二南無阿彌陀佛一。爲二讃嘆門
一」と指摘
している。
㈹
『黒谷上人語燈録』卷第十四所収。
㈲
念聲是
一にた
つての心念口稱
である。
昭和四十年
三月稿
・同四十
六年
一月改
稿。
广
五
種
正
行
論
一三五