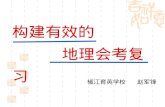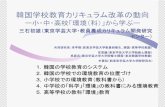学校における飲酒防止教育 - mhlw...学校における飲酒防止教育 スポーツ・青尐年局 学校健康教育課 健康教育調査官 北垣邦彦 学校における飲酒防止教育
人権academic3.plala.or.jp/mikura-s/R011218P.pdf校長 松田 隆...
Transcript of 人権academic3.plala.or.jp/mikura-s/R011218P.pdf校長 松田 隆...

平成 30・31 年度 東京都教育委員会人権尊重教育推進校
研究主題
「『 歳の旅立ち』に向けて、広い視野から
自他の人権を考えることのできる児童・生徒の育成」
挨拶 御蔵島村立御蔵島小学校
御蔵島村立御蔵島中学校 校長 松田 隆
本校は、平成30・31年度東京都教育委員会人権尊重教育推進校として、研究主題を「『15歳の旅立
ち』に向けて、広い視野から自他の人権を考えることのできる児童・生徒の育成」として取組を進めてき
ました。
小中併設校であることを生かし、小学校・中学校の教職員が共に一つの研究に取り組むことで、本校児
童・生徒に身に付けさせたい資質・能力を明らかにし、知識的側面、価値的・態度的側面、技能的側面の
3つの側面から、具体的な手だてを追究することを目指しました。
ここに、2年間の成果を報告させていただきます。未だ研究の途上ではありますが、御高覧の上、御指
導・御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、本校の研究推進にあたり、御指導いただいた講師の先生方、東京都教育委員会、東京都教育庁
三宅出張所、御蔵島村教育委員会の皆様に心より感謝申し上げます。
御蔵島村立御蔵島小学校
御蔵島村立御蔵島中学校
〒100-1301 東京都御蔵島村
電話 04994-8-2211・2231 ファクシミリ 04994-8-2143

■ 学校概要 本校は、伊豆諸島の御蔵島にある唯一の学校であり、小学生と中学生が同じ校舎で生活を送る併設校と
なっている。島民は約 300人で、みな顔見知りであり、子供たちは幼い頃から家族同然に大事にされ育っ
てきた。島の大部分は原生林に覆われ、海は青く澄んでおり、沿岸には約 150頭ものイルカが生息してい
る。豊かで厳しい自然の中、たくさんの愛情にふれながら暮らしている本校の児童・生徒であるが、島内
には高等学校がないため、高校進学を機に島を離れることになる。
それが「15歳の旅立ち」であり、島を離れて新しい生活を送る子供たちが主体的に人生を切り拓くこ
とができるよう、9年間の教育活動を組織的・計画的に推進していくことが求められている。
■ 令和元年度 研究構想図
学校教育目標
・自主 自分から進んで努力する子供(生徒)
・協和 決まりを守り互いを助け合い協力す
る子供(生徒)
・健康 明朗で心身ともに健康な子供(生徒)
社会的要請
・ 問題発見・解決能力、言
語能力、情報活用能力
等の資質・能力等の育
成が求められている。
児童・生徒の実態 ・ 少人数のため、友達同士の
会話の幅が限定的である。
・ 高校進学時には島を離れる
ことになるので、早い時期
での自立が求められる。
研 究 主 題
「『15歳の旅立ち』に向けて、広い視野から自他の人権を
考えることのできる児童・生徒の育成」
目指す児童・生徒像
『15歳の旅立ち』に向けて、
広い視野から自他の人権を考えることのできる児童・生徒
平成 30年度の成果と課題
成果
・ 様々な人権課題に対する児童・生徒の実態を捉え、効果
的な題材設定をしたことや体験的な活動を取り入れたこ
とで学習意欲が高まった。
・ 互いの考えを尊重しながら話し合おうとする様子が見ら
れた。
課題
・ 伝え合う力、思考力や想像力を高めるため、話合い活動を
重点に行っているが、さらに異学年合同の構成の工夫や、
地域の人材の活用を計画的に行うことが必要である。
本校において、人権教育を通じて育てたい資質・能力を3つの側面(知識的側面、価値的・態度的側面、技能的側面)
から考え児童・生徒の現在の課題を明らかにし、3側面の分科会で年間を通して授業に取り組むことで、児童・生徒の人
権に関する資質・能力を身に付けさせることができるであろう。
研 究 仮 説
価値的・態度的側面分科会 知識的側面分科会 技能的側面分科会
分 科 会
児童・生徒の実態調査
研 究 の 内 容
人権教育として効果的な授業の編成を検討する。
人権課題の選択
研究授業の実践

■ 研究経過
平成30年度
●校内研修会「人権教育の進め方について」
講 師 東京都教育庁三宅出張所指導主事 半野田 聡 先生
●実践研修会 中1~中3 特別の教科 道徳 人権課題「子供」に関わる取組
授業者 技能的側面分科会 後藤 彩夏 教諭
講 師 東京都教育庁指導部指導企画課統括指導主事 志村 安 先生
東京都教育庁指導部指導企画課指導主事 辻 慎二 先生
●島しょ教育研修会 小1~小2 特別活動 人権課題「外国人」に関わる取組
授業者 価値的・態度的側面分科会 小林 裕 主任教諭
講 師 東京都教職員研修センター研修部専門教育向上課指導主事 國長 泰彦 先生
●実践研修会 小5~小6 外国語科 人権課題「外国人」に関わる取組
授業者 知識的側面分科会 栗本 春香 教諭
講 師 東京都教育庁三宅出張所指導主事 半野田 聡 先生
●島しょ教育研修会 中1~中3 特別の教科 道徳 人権課題「障害者」
授業者 価値的・態度的側面分科会 野中 将人 教諭
講 師 東京都教職員研修センター研修部教育経営課統括指導主事 隅田 登志意 先生
●島しょ教育研修会 特別支援教室 自立活動
授業者 知識的側面分科会 生井 一公 主任教諭
講 師 東京都教職員研修センター研修部専門教育向上課指導主事 柴田 貴志 先生
●東京都道徳教育推進拠点校研修会 中1~中3 特別の教科 道徳 人権課題「HIV 感染者・ハンセン病患者等」
授業者 知識的側面分科会 古堅 靖教 教諭
講 師 東京都文京区立明化小学校副校長 齋藤 道子 先生
●人権教育推進協議会 小3~小4 体育科 人権教育を通じて育てたい資質・能力「自己の課題を見付け、その解決に向けて思考し判断する力」
授業者 技能的側面分科会 太田 雅子 教諭
講 師 東京都人権啓発センター専門員 林 勝一 先生
●教職員向けアンケート 授業で取り扱った人権課題の項目と回数を集計(年度末)
●児童・生徒向けアンケート 人権に関する意識調査の実施(年度始)
平成31年度
●校内研究授業 中1~中3 技術科 人権課題「インターネットによる人権侵害」
授業者 知識的側面分科会 川手 一翔 教諭
講 師 東京都教育庁三宅出張所指導主事 小林 正士 先生
●島しょ教育研修会 小4 総合的な学習の時間 人権課題「高齢者」
授業者 技能的側面分科会 亀井 久士 主幹教諭
講 師 東京都教職員研修センター研修部教育開発課指導主事 吉本 一也 先生
●校内研究授業 中1~中3 美術科 人権教育を通じて育てたい資質・能力「豊かな情操」
授業者 価値的・態度的側面分科会 小林 奈央 教諭
講 師 東京都教育庁三宅出張所指導主事 小林 正士 先生
●校内研究授業 小5・6 学級活動 人権課題「災害に伴う人権問題」
授業者 知識的側面分科会 栗本 春香 教諭
講 師 八王子市立弐分方小学校校長 小川 賀世子 先生
●校内研究授業 中 1~中3 音楽科 人権教育を通じて育てたい資質・能力「豊かな情操」
授業者 技能的側面分科会 木村 有紀 教諭
講 師 東京都教育庁三宅出張所指導主事 小林 正士 先生
●島しょ教育研修会 特別支援教室 自立活動
授業者 技能的側面分科会 生井 一公 主任教諭
講 師 東京都教職員研修センター研修部専門教育向上課指導主事 須長 輝夫 先生
●校内研究授業 小1~小2 体育科 人権教育を通じて育てたい資質・能力「協力や公正の態度」
授業者 価値的・態度的側面分科会 太田 雅子 教諭
講 師 東京都教育庁三宅出張所指導主事 小林 正士 先生
●人権教育推進協議会 中 1~中 3 特別の教科 道徳 人権課題「子供」
授業者 知識的側面分科会 佐々木 潤 主任教諭
講 師 東京都人権啓発センター専門員 田村 鮎美 先生
●教職員向けアンケート 授業で取り扱った人権課題の項目と回数を集計(2学期中)
●児童・生徒向けアンケート 人権に関する意識調査の実施(年度始・2学期中)

■ 人権感覚を磨くための取組
人権コラム 毎月発行の学校だよりに、教職員による「人権コラム」を掲載して
いる。それぞれが授業の中で取り上げた人権課題や授業による児童・
生徒の変容の様子を中心に紹介している。また、取り上げる事例も
普遍的な視点からの取組や個別的な視点からの取組などの他、多岐に
渡っている。
御蔵島では、全ての村民に学校だよりが配布される。児童・生徒が
学んでいることを村全体に知っていただくことで、子供たちへの言葉掛けとしてフィードバックされ、人権
に対する意識が高まっている。
人権掲示板 児童や生徒が行き来することの多い廊下や階段に「人権掲示板」を設置し、
人権に関するポスターや新聞記事等を掲示している。
設置当初は児童・生徒の実態に合わせ、「人権ってなんだろう?」という特
集を組むことから始めた。また、社会的な関心の高まりに合わせ、「LGBT」
や「ハンセン病」の特集を組むなど、常に児童・生徒が人権課題についての
正しい知識に触れることで、人権感覚を磨くことができるようにしている。
奉仕日 御蔵島には、昭和4年から受け継がれている「奉仕日」と呼ばれる
自主的な清掃活動がある。毎月5のつく日(5日・15日・25日)の朝6
時半に子供たちがほうきやちりとりを持って集まり、村の中を清掃す
る。現在では保健美化委員会の児童・生徒が中心となって参加を呼び
掛けたり、清掃場所を決めたりしている。
村民の方々からは「子供たちのおかげで村がきれいになって、嬉し
い。」といった声が寄せられており、この取組を通して、人のために
頑張ろうとする心や、問題を他人事にしない態度などが育っている。
人権の花 毎年、低学年児童が「人権の花」の種を植え、大切に育てている。
「人権の花に水をあげよう。」「人権の花の芽が出たよ。」――児童
が「人権」という言葉を繰り返し使うことで、心の中に残るようにし、
人権教育への意識を高めている。

■ 知識的側面分科会の実践 ○各教科等の目標 ☆人権教育の視点
普遍的な視点からの取組
小学校第5・6学年 外国語科 「ニッポン、ここが大変!」 人権課題『外国人』に関わる取組 ○ 困っている外国人に対して自分ができることは何かを考え、道案内やお土産の紹介など、言語を使って
積極的にコミュニケーションを図る。
☆ 外国人観光客が日本で感じた困りごとについて考える学習を通して、生活習慣や文化の違いなど共生に
向けて大切なことを理解させる。
指導の工夫と成果
・ 英語によるインタビュー動画のリスニングや「中国で飲食店に入っ
た日本人観光客」の疑似体験を行った。また、児童が日頃よく利用
する村内の飲食店に許可を取り、実際に使用されているメニューを
中国語に翻訳したものを作成した。これらにより、言葉が通じない
ことに対する外国人観光客の困り感を実感し、「これからは困ってい
る外国人のために行動したい。」という気持ちを高めさせることがで
きた。
課題と今後の指導
・ 東京都が人権課題として挙げている「在日外国人が受ける差別や不利益」等に関する知識やそれに対して
正しく行動しようとする態度を育てるためには、この授業をきっかけとして、個別的な視点からの取組に
つなげていく必要がある。後日、小学校6年生は社会科の学習の中で、在日外国人の抱える人権課題につ
いて触れた。「相手が外国人でも日本人でも、自分たちの接し方は変わらないし、変わってはいけない。」
という意見が児童から挙がった。
個別的な視点からの取組
中学校第1~3学年 特別の教科 道徳 「ライアン・ホワイトから学ぶ」C 公正、公平、社会正義 人権課題 『HIV 感染者・ハンセン病患者等』 ○ HIV感染者の伝記を通して、偏見や差別のない社会の実現のために必要なことは何かを考える。
☆ HIV 感染者への偏見や差別と、その原因となる考え方について知ることを通して、偏見や差別を解消しよ
うとする心情や態度を育てる。
指導の工夫と成果
・ 養護教諭と連携し、HIV 感染症について事前の保健学習を行った。
偏見や差別の心をもたないためには、正しい知識を身に付けること
が大切であることを実感させることができた。
課題と今後の指導
・ 差別の原因が正しい知識の理解不足によるものだけではないことを
指導するためにも、価値的・態度的側面や技能的側面と関連させた
指導を充実させる必要がある。偏見や差別が起こる他の要因につい
ては、授業後に掲示物に追記することや、他の事例についての授業
実践の中で扱うことで、生徒が考える機会をつくった。
分科会の提案する手だて
知識を高める手作り掲示
・ 人権への関心を喚起するために、分科会
の掲示コーナーを作り、年間を通して情
報を発信した。
・ 作成にあたり、グラフや数値などの客観
的なデータを意図的に用いることで、知
識を高めることをねらった。
HIV 感染症についての黒板掲示 人権課題「インターネットによる
人権侵害」についての階段掲示

■ 価値的・態度的側面分科会の実践 ○各教科等の目標 ☆人権教育の視点
普遍的な視点からの取組
中学校第1~3学年 美術科 「形・色・心の分析」 人権教育を通じて育てたい資質・能力 『豊かな情操』 ○ 造形的な見方・考え方を働かせて作品を比較・分析し、感じ取ったことを言葉で表現し合う。
☆ 絵画作品の分析を通して、自己の見方・感じた方を肯定的に捉えさせるとともに、他者の見方・感じ方
も認め、多様性に対し寛容な態度とともに豊かな情操を育む。
指導の工夫と成果
・ 明るさや鮮やかさ、色数、曲線的/直線的、写実的/抽象的など、
色や形についての視点を数多く示したうえで絵画作品の分析に取り
組ませた。視点は根拠となり、生徒は絵から感じ取ったことに根拠
をもって伝え合うことができた。たとえ自分とは感じ方が異なって
いたとしても、その根拠を知ることで他人の意見を否定せずに受け
止めることができるような意見交流の場につなげることができた。
課題と今後の指導
・ 自分の考えを豊かな表現で伝えられるようになることは、互いを理解し尊重し合う態度を高めることに
つながる。そのためにも、美術科に関わる語彙を増やしていく手だても必要である。今年度、音楽科の教
員が「音楽をあらわす言葉」として約50パターンの言葉を掲示していることから、児童・生徒が日頃か
らその言葉を活用する様子を紹介した。それを参考に、各学年・各教科の実態に応じた取組を始めた。
個別的な視点からの取組
中学校第1~3学年 特別の教科 道徳 「広い心で」B 思いやり、感謝 人権課題 『障害者』 ○ 自分とは異なる他者に対して差別的になるのではなく長所に目を向けたり、生活上の困難について考え
たりする。
☆ 視覚障害者の感じる困難について知ることを通して、障害者に対する偏見や差別の背景には、障害への
理解不足があることに気付かせ、互いの人権を尊重しながら共に生きていこうとする態度を育む。
指導の工夫と成果
・ 障害者スポーツでもあるサウンドテーブルテニスを体験する活動を
取り入れた。視覚障害者の感じる「困難」への気付きが、競技だけ
でなく障害者の生活全体へと広がった。障害者への偏見や差別を認
めない態度や合理的配慮への理解を高めることができた。
課題と今後の指導
・ 「障害を理由とする差別」を認めない態度を育てる大切さは疑う余
地はないが、その方法として障害を「一つの個性」として捉えさ
せることについては、指導の在り方について意見が分かれた。教職員がどのように捉えるべきか、また
それを児童・生徒にどのように示していくべきか、今後も検討していく。
分科会の提案する手だて
話合いルールの見直し
・ 従来、小学校で使われていた「話合いの
ルール」を人権的な価値観や態度を養う
視点から見直した。
・ 小・中学校の全ての学級に周知・配布し、
活用することで児童・生徒の望ましい話合
いの態度や技能を育んだ。
はなしあい 5つのやくそく
行事に向けて、異学年合同で
話し合う機会が多い

■ 技能的側面分科会の実践 ○各教科等の目標 ☆人権教育の視点
普遍的な視点からの取組
小学校第3・4学年 体育科(保健) 「けんこうな生活」 人権教育を通じて育てたい資質・能力 『他の人と対等で豊かな関係を築くことのできる社会的技能』 ○ 健康を保持増進するには、生活の仕方や体を清潔に保つこと、生活環境を整えることが必要であること
を理解し、整理整頓や教室の明るさ、うがい・手洗いなど健康のためにできることを考える。
☆ 健康等について自分たちの生活環境を振り返ることを通して、友達と対等で豊かな関係を築くことので
きる社会的技能を育む。
指導の工夫と成果
・ 整理整頓ができていない教室の写真を図書室のスクリーンに映し、
「どのようにしたら、みんなが気持ちよく生活できるだろう。」と考
えさせた。教室に戻ると、写真の様子が再現されていることに気付
き、児童は意欲的に環境を整え始めた。落ちているものを拾ったり、
灯りをつけたりするたびに教師がその理由を問うことで、「みんなが
気持ちよく生活するために」という意識を高めることができた。
課題と今後の指導
・ みんなのために教室環境を整え、「生活見直し宣言」もしたが、
今後の生活に継続的に生かすことができるかが重要である。そのため、授業後に教室環境についての写真
資料を校内に掲示した。それを見ることで、気持ちのよい環境を整えることができているか、必然的に振
り返るだろうと考えた。また、保健目標や生活目標についての講話の中で、小学校3・4年生の「生活見
直し宣言」に触れるなどすることで、意識の継続化を図った。
個別的な視点からの取組
小学校第4学年 総合的な学習の時間 「住みやすい島をめざして」 人権課題 『高齢者』 ○ 高齢者にとって住みやすい御蔵島の姿とはどのようなものか、インタビューや施設訪問などを繰り返す
ことで探究し、「将来の御蔵島」と「今の私にできること」を見付ける。
☆ 高齢者が直面している困難さについて調べる活動を通して、高齢者等に対する適切な自己表現等を可能
にするコミュニケーション技能を育む。
指導の工夫と成果
・ 相手を大切にする技能を高めるために、課題の探究の対象となる人
と直接話したり関わったりする機会を6回設定した。回を重ねるご
とに、話の聞き方や言葉の掛け方が上達し、会話が広がるようにな
った。また、ロールプレイを通して(人権を侵害する事例の)被害
者である高齢者の気持ちへの共感的理解を図ることができた。
課題と今後の指導
・ 高齢者を思いやる気持ちを実際に行動で表すことを、授業内で完結
させるのは難しく、そのため学校外での活動が主となる。そこで、児童が書いた「今の自分にできるこ
と」という提言を学級通信で紹介することで家庭に周知し、実践につながるようにした。
分科会の提案する手だて
振り返りカード「おもいやり名人」
・ 行事や授業の振り返りをする際に、「言
われてうれしかった言葉」や「されてう
れしかったこと」という視点を示した。
・ カードを読み、どんなことで友達がうれ
しく思うのかを知り、取り入れることで
実践力が向上していくことをねらった。
掲示された振り返りカード 振り返りカードにも書かれた
野菜の皮むきを教える上級生の姿

■ 研究の成果と課題
■ おわりに 小学校副校長 廣瀬 京子
■ 研究に携わった教職員 ◎研究推進委員長 ○研究推進委員
成 果 ● 多くの実践の中で体験的な活動を取り入れた。児童・生徒は、自ら体験することで人権について実感
を伴って理解し、問題を解消するためには自分に何ができるのか考えるようになった。
● ICT 機器を活用して資料を効果的に示したり、互いの意見を視覚的に示したりした。このことが、ス
ムーズに課題を把握させたり、考える時間を十分に確保させることにつながり、相手の意見を一層尊
重しながら発言する態度を育てることができた。
● 児童・生徒対象のアンケートにおいて「相手の言動から相手の気持ちを考え、自分がどのように行動
していくべきか判断できますか。」の問いに対し、「できる」または「どちらかといえばできる」と
肯定的な回答をした割合が 76%→78%にやや増加した。その中でも「できる」と回答した割合が
32%→37%と、5ポイント増加していることから、自己肯定感を高めることができた。
● 新聞の切り抜きやパンフレット、分科会の手作り掲示物を年間通して更新し、さまざまな人権課題を
テーマにして授業を行ったことにより、児童・生徒・教職員の人権感覚が磨かれ、偏見や差別を解消
しようとする意識が高まった。
● 児童・生徒の自己や他者を大切に思う気持ちが高まり、人のために力を発揮しようとする姿が多く見
られるようになった。
課 題 ● 児童・生徒が少人数のため、「多様な意見を受け止めた上で、自分の考えを見つめ直し、深める」と
いう展開が難しかった。異学年合同授業、児童・生徒役として教員が参加する授業、村民の方々に参
加していただく授業など、その単元に効果的な集団の在り方を検討していく。
● 人権感覚をさらに磨くため、今後も掲示物や授業を通して啓発を図っていく。
● 「15歳の旅立ち」以降も自他の人権を大切にした生き方ができているかが、今回の研究の結果とな
る。引き続き、村民の方々の協力のもと、長期的視野に立って児童・生徒を見守り、成長を後押しし
ていく。
この2年間の研究を通して、私たち教職員は様々な取組を行って参りました。昨年度は、まず人権につい
ての基礎知識を得るところから始めました。今年度も引き続き3つの分科会を中心に校内研究を進め、日常
的な実践を取り入れながら児童・生徒の人権感覚の涵養に努めて参りました。今後は、研究の成果と課題を
生かし、児童・生徒及び教職員の人権意識をさらに高めていきたいと考えております。
本校の研究について御指導・御助言を賜りました講師の先生方をはじめ、東京都教育委員会、各関係機関
の皆様に心から御礼を申し上げるとともに、今後とも一層の御指導・御助言を賜りますようお願い申し上げ
ます。
● 平成31年度
校長 松田 隆 小学校副校長 廣瀬 京子 中学校副校長 坂下 惣栄
小1 太田 雅子 小2 ○栗本 直子 大西 敏夫 小3 大曽根 茂
小4 ◎亀井 久士 小5 ○栗本 春香 小6 小林 裕
中1 佐々木 潤 野中 将人 後藤 彩夏
中2 吉野 久美子 ○川手 一翔 小林 奈央
中3 ○野田 美鈴 ○佐藤 航平 木村 有紀 大橋 拓郎
しいのき 生井 一公 養護 七戸 藍 栄養士 池上 球美
事務 大川 伸一 調理員 廣瀬 幸介 調理補助員 堀川 由佳里
● 平成30年度
(副校長) 菊間 路人 ◎栗本 直子 栗本 和恵 影山 聡美 小野寺 恵太 古堅 靖教